解説記事2020年06月08日 論考 外国籍パートナーシップ持分のクロス・ボーダー現物出資と課税(2020年6月8日号・№837) -塩野義製薬事件東京地裁判決の検討-
論考
外国籍パートナーシップ持分のクロス・ボーダー現物出資と課税
-塩野義製薬事件東京地裁判決の検討-
岩田合同法律事務所 弁護士・東京大学客員教授 佐藤修二
弁護士・公認会計士 浜崎祐紀
弁護士 野口大資
東京地方裁判所は、先般、塩野義製薬が外資系製薬会社とのジョイント・ベンチャー事業の再編に伴って行ったクロス・ボーダーの現物出資が適格現物出資に該当するか否かが争われた事案において、納税者勝訴の判決を下した(東京地判令和2年3月11日裁判所ウェブサイト掲載)。
グローバル企業において、外国籍パートナーシップ等のハイブリッド・エンティティを利用したり、クロス・ボーダーの現物出資を行ったりすることは稀ではなく、本判決が実務に与える影響は小さくないと思われる。本稿では、判決の概要をご紹介し、若干の検討を試みる。
1 事案の概要
内国法人である原告は、英国領ケイマン諸島籍の特例有限責任パートナーシップ(Cayman Islands exempted Limited Partnership。以下「CILP」という。)の出資持分を有していたところ、その出資持分の全て(49.99%。以下「本件CILP持分」という。)を、原告の英国完全子会社に対し、現物出資(以下「本件現物出資」という。)により移転した。
原告は、本件現物出資は適格現物出資(法人税法2条12号の14)に該当し、同法62条の4第1項の規定によりその譲渡益の計上が繰り延べられるとして、法人税等を確定申告した。ところが、原告は、東税務署長から、本件現物出資が適格現物出資には該当しないとして更正処分を受けたため、その取消しを求めて提訴した。
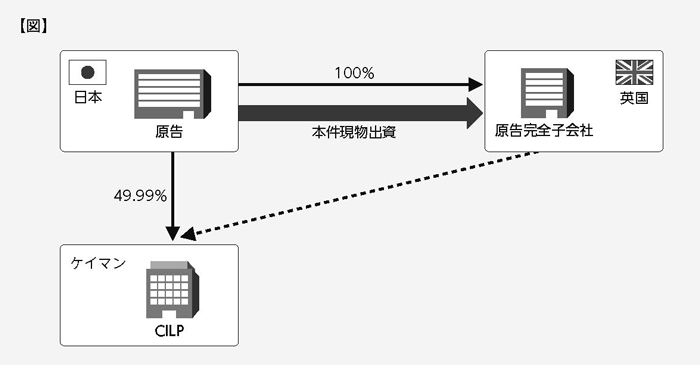
2 争 点
争点は、本件現物出資が適格現物出資に該当するか否かであり、具体的には、本件現物出資の対象資産が「国内にある事業所に属する資産」(当時の法人税法施行令4条の3第9項。現在の同条第10項)に該当するか否か、という点であった。すなわち、現物出資先が外国法人である場合において、現物出資の対象資産が「国内にある事業所に属する資産」であるときは、対象資産の含み益が日本で課税を受けないまま国外に流出してしまうことを避けるため、適格現物出資には該当しないものとされている(法人税法2条12号の14、同法施行令4条の3第10項)。本件では、現物出資の対象資産が、「国内にある事業所に属する資産」であったかどうかが争われた。
3 判決の概要
裁判所は、以下のように判断し、本件CILP持分は「国内にある事業所に属する資産」ではないとして、課税処分を取り消した。
(1)「国内にある事業所に属する資産」の判断基準について
裁判所は、「国内にある事業所に属する資産」の判断基準について、法人税基本通達1-4-12が示す判断基準(「国内にある事業所に属する資産」に該当するか否かは、原則として、当該資産が国内にある事業所又は国外にある事業所のいずれの事業所の帳簿に記帳されているかにより判定するが、実質的に国内にある事業所において経常的な管理が行われていたと認められる資産については、国内にある事業所に属する資産に該当することになる、とするもの)に言及し、この通達の示す判断基準は、「まず、その資産の経常的な管理がどの事業所において行われていたかを判定し、その判定に当たっては当該資産が当該事業所の帳簿に記帳されていたか否かを重要な考慮要素とし、次いで、その判定の結果当該資産の経常的な管理が行われていたと認められる事業所が国内にある事業所に当たるか否かを判定し、それが肯定された場合に『国内にある事業所に属する資産』に該当すると認める旨をいう趣旨に理解することが可能である」とした上で、そのように理解される判断基準に沿って検討するのが相当であるものとした。
(2)現物出資の対象資産について
次いで、裁判所は、上記判断基準に従った判断の前提問題としての現物出資の対象財産の捉え方について、ケイマンにおける特例有限責任パートナーシップ法の定めにおいてパートナーシップ持分は譲渡可能な資産として位置づけられていること、本件現物出資に係る契約の規定上、本件CILP持分が現物出資の対象資産とされていたこと等から、現物出資の対象資産は本件CILP持分であったと解するのが相当であるとした。もっとも、CILPは、日本の組合に類似した事業体であり、ケイマンにおける特例有限責任パートナーシップ法及び本件のパートナーシップ契約においても、CILPの事業用資産の共有持分と切り離されたパートナーとしての契約上の地位のみが他に移転することは想定されていないものと解される(この点が、株式の移転とは根本的に異なる)ため、本件CILP持分の内実は、CILPの事業用財産の共有持分とLPとしての契約上の地位とが不可分に結合されたものと捉えられなければならない、とした。
(3)現物出資の対象資産の経常的な管理が行われていた事業所について
裁判所は、本件CILP持分は、上記のとおり事業用財産の共有持分とLPとしての契約上の地位とが不可分に結合された資産であるから、これを経常的な管理の対象として捉える場合においても、個々の事業用財産の持分やパートナーシップ契約上の個々の権利等に分解してそれぞれを管理する事業所を個別に検討するのは相当ではなく、これらが全て結合された1個の資産とみてその管理が行われていた事業所を特定するのが相当であるとした。
その上で、パートナーがCILPの事業に参加する目的は、その出資に由来する事業用資産の運用により利益を得ることであり、パートナーとしての契約上の地位は、その運用のための手段と位置付けられるものであるから、CILPのパートナーシップ持分の価値の源泉はCILPの事業用財産の共有持分にあるということができ、また、CILPの事業用財産の共有持分とパートナーとしての契約上の地位との関係は、前者を主とする主物と従たる権利義務との関係に類似する関係にあるものと捉えることが可能であるとし、それゆえ、本件CILP持分の経常的な管理が行われていた事務所は、CILPの事業用財産、中でもその主要なものの経常的な管理が行われていた事業所とみるのが相当である、とした。
以上を踏まえ、本件では、CILPの事業用資産は、①現金、②知的財産のライセンス、③治験データ等の無形資産、及び④出資資産等で構成されているところ、その主要なものの経常的な管理は、日本以外の地域にある事務所において行われていたといえることから、本件CILP持分は「国内にある事業所に属する資産」には該当しないと判断した。
4 若干の検討
これまで、わが国の民法上の組合や外国籍パートナーシップに関する租税裁判例は、パス・スルー課税となるか否か、すなわち当該事業体が租税法上の法人に該当するか否かの点が論点となるものが多かった(脚注1)。その意味で、持分の法的性質にフォーカスされた本判決は、目新しいものであるといえよう。
本判決の特徴的な点は、本件現物出資の対象資産を本件CILP持分としつつも、その属する事業所の判定においては、本件CILP持分は、事業用財産の共有持分とリミテッド・パートナーとしての契約上の地位が不可分に結合したものであり、かつ、両者は事業用財産の共有持分を主とする主物と従たる権利義務との関係に類似する関係にあるとして、CILPの事業用資産を構成する資産の管理状況に着目したところにある。従来、民法上の議論等においても、組合の持分について、本判決のように、財産の共有持分と契約上の地位との関係が主物と従たる権利義務との関係に類似するとの整理はされてこなかったように思われ、本判決の判断は興味深い。
本件の訴訟過程においては、組合の持分の法的性質を、とりわけ本件のように持分の譲渡がなされた文脈においてどのように捉えるかについて、原告による詳細な主張が行われたようであり(脚注2)、本判決の判断は、こうした訴訟上の議論を踏まえたものと思われる。わが国の民法上の組合(本判決は、CILPも、わが国の民法上の組合に類似するものとしている)は、株式会社等と異なり、それ自体として法人格を有するものではないという法的性質に照らせば、組合の持分の財産的価値の実体は、組合財産にあるというべきであろう。その意味で、組合の持分の実体について、組合財産を中心として捉えた本判決の判断は、組合の私法的な性質に照らしても妥当なものと思われる。
本件の更正処分は2014年になされており、今回の第一審判決までに5年半ほどの時間を要している。判決を読むと、原告代理人によって、事実面・法律面で充実した主張がなされ、裁判所も、国側の主張も含めて慎重な検討の上、本判決に至ったことが想像される。判決は、結論的に、外国籍リミテッド・パートナーシップの持分について、外国に所在する資産と判断するものであり、ビジネス界の通念にも合致するものといえよう(脚注3)。
なお、本件では、現物出資を行う前に、原告が大阪国税局調査第一部調査総括課長に宛てて事前照会を行い、適格現物出資に該当するとの口頭での回答を得ていたようである。このような経緯から、後になって適格現物出資ではないとして課税処分を行うことは、信義則違反であるとの主張もなされた。本判決では、そもそも適格現物出資に該当すると判断されたことから、この論点に対する判断は示されていない。しかし、納税者の予測可能性の観点からすれば、課税当局の然るべき役職者による事前照会回答を得ていながら課税処分を受けたという経緯は看過できず(脚注4)、裁判所は、結論の落ち着きという観点からは、こうした経緯も考慮した可能性はあるように推察される。
全体として、本判決は、理論的に精緻であるとともに、結論の座りも良い。国側は控訴しているようであるが、控訴審においても判断の方向性が維持されることを期待したい。
脚注
1 近時の代表例としては、米国デラウェア州のリミテッド・パートナーシップに関する最判平成27年7月17日民集69巻5号1253頁がある。
2 本件の訴訟代理人の手になる、太田洋「組合に係る課税関係についての若干の考察」金子宏=中里実編『租税法と民法』(有斐閣、2018)402-407頁を参照。
3 なお、本事案の裁判長である古田孝夫判事は、資本剰余金を原資とする配当の税務処理が争われた事案の裁判長として、法人税法施行令の規定が違法・無効であるとする注目すべき判断を示したこともある(東京地判平成29年12月6日裁判所ウェブサイト掲載)。この判決については、佐藤修二「法人税法施行令を違法・無効とした判決の衝撃」税務弘報2018年9月号所収を参照。
4 課税処分当時の報道は、事前照会を行ったにもかかわらず課税されたという点にフォーカスしていた(日本経済新聞2014年9月14日朝刊)。
佐藤修二
1997年東京大学法学部卒業、2005年ハーバード・ロースクール卒業(LL.M.,Tax Concentration)。2011年~14年、東京国税不服審判所国税審判官。2019年~東京大学法科大学院客員教授。著作に、『実務に活かす!税務リーガルマインド』(編著、日本加除出版、2016)、『税理士のための会社法ハンドブック〔2019年版〕』(編著、第一法規、2019)など。
浜崎祐紀
2004年東京大学経済学部卒業、2010年早稲田大学大学院法務研究科修了。2003年~06年、監査法人トーマツ勤務。2013年~15年、PwC税理士法人勤務。著作に、『実務に活かす!税務リーガルマインド』(共著、日本加除出版、2016)、『税理士のための会社法ハンドブック〔2019年版〕』(共著、第一法規、2019)など。
野口大資
2016年大阪大学法学部卒業、2018年東京大学法科大学院修了。岩田合同法律事務所において、租税訴訟案件等に従事。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















