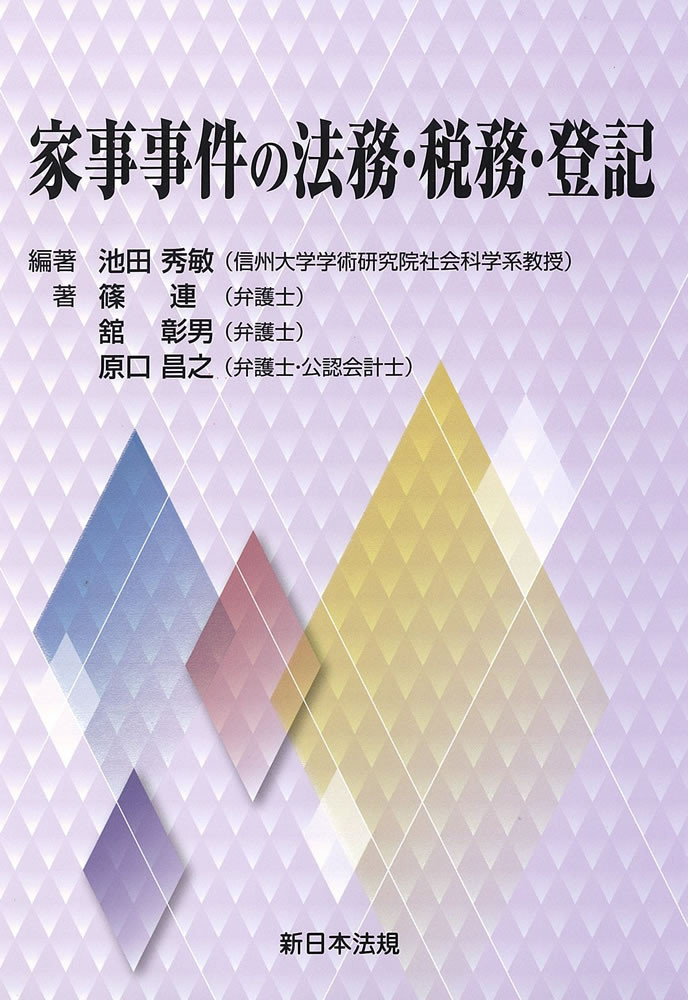民事2014年09月12日 負担付贈与という選択肢 執筆者:池田秀敏
親の面倒をみてきた自分の貢献度に相応した遺産が相続できるよう、親に遺言書を書いてもらった。ところが、そのことを知った他の兄弟姉妹が親に働きかけ、新たな遺言をさせようとしている。相続紛争を未然に防ぐために書かれた遺言が、かえって相続開始前の紛争を引き起こし、遺言合戦のようなことになってしまった・・・そんな事例も少なくないかと思われます。
このような事態となってしまうのは、遺言というものが自由に撤回でき(民1022)、また、新たな遺言がなされると、それと矛盾する古い遺言は撤回されたものとみなされてしまうためでもあります(民1023)。そこで、そのような撤回権の行使が制約される負担付死因贈与について検討したいと思います。
死因贈与は、贈与者の死亡によって贈与の効力が生じる契約ですが、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用するとされており(民554)、遺贈と同様にいつでも撤回ができるのが原則です(最判昭47・5・25民集26・4・805)。これは、死因贈与においても、贈与者の最終意思が尊重されるべきだとする考え方によるものです。
しかし、契約時に受贈者に負担を課した負担付死因贈与契約の場合には、負担の履行をした受贈者側の利益も無視できなくなります。そのため、判例によれば、負担の履行があった場合において贈与者による一方的な撤回が認められるのは、「やむをえないと認められる特段の事情」がある場合に限定されています(最判昭57・4・30民集36・4・763)。つまり、負担付死因贈与においては、贈与者による撤回が制限される場合があり、冒頭に書いたような紛争を回避できる余地があるということです。
しかも、不動産を目的とした死因贈与の場合には、仮登記による順位保全が可能です。贈与者が死因贈与の効力が発生する前に当該不動産を第三者に譲渡してしまったとしても、後に本登記をすれば、その第三者に対して死因贈与を主張することができます。また、公正証書で負担付死因贈与契約書を作成し、その際に死因贈与執行者を指定しておけば、執行者の権限によって本登記が可能となります。
死因贈与は、相続させる遺言のような方法に比べると、不動産取得税が課税され、登録免許税が割高になるデメリットもありますが、負担付死因贈与には、以上のような効果を獲得できるメリットがあります。
ただ、贈与者が負担付死因贈与を撤回した場合や、新たな遺言をしてしまい、後々、他の相続人との紛争が生じて訴訟にまで発展したような場合には、「負担」の内容とその「履行」状況が問題とされるでしょう。ちなみに、撤回権の制限について判示した最高裁判例の事案(上記最判昭57・4・30)では、受贈者が贈与者に対し、毎月一定額のほかに年2回賞与の半額を送金することになっていました。明快な負担が認定できた事案であったことに留意すべきでしょう。親の面倒をみるといった扶養も、一応「負担」の内容となり得ると考えられますが、その軽重の度合いは家族の状況によって様々ですから、実際になされた負担が贈与財産の価値と釣り合うものかが問われるはずです。
結局のところ、贈与者である親がその「履行」に不満をもち、その結果として撤回に至ってしまうと、相続紛争を回避できないことになります。多少の不満が生じるのは致し方ないとしても、それが大事には至らないような日頃のコミュニケーションが、紛争予防において最も重要なことなのかも知れません。
(2014年8月執筆)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.