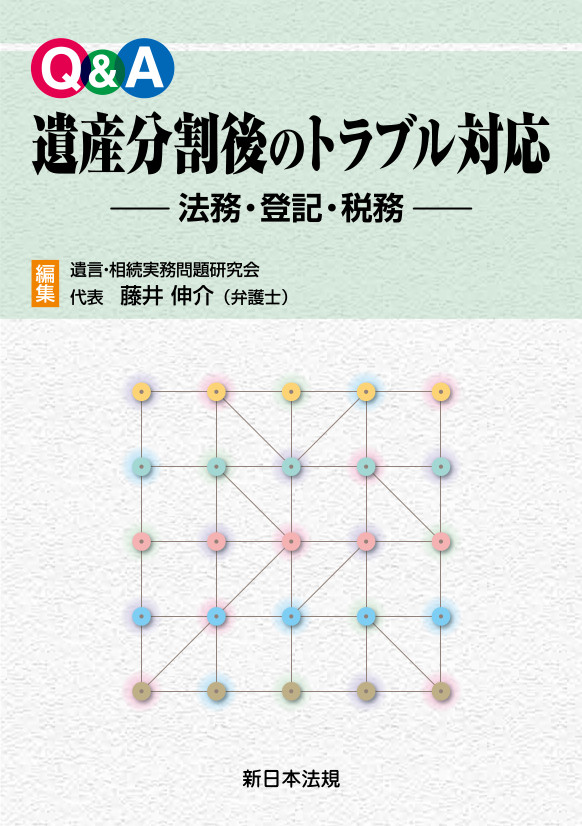相続・遺言2014年04月21日 信託銀行による遺言信託の【落とし穴】 執筆者:藤井伸介
平成26年4月5日付日本経済新聞夕刊1面(大阪版)に【「争続」公文書で防ぐ】と題する記事が掲載された。平成25年の公正証書遺言作成件数が前年より9%増え、10年前の1・5倍である9万6,020通になったとのことである。
このうち何件が信託銀行の遺言信託によるものか不明であるが、平成25年1月12日の日本経済新聞電子版の記事によれば、平成24年9月末の信託銀行が取り扱う遺言信託による遺言書保管件数が7万2,761件となり、3年前に比べて約1万件増えたとのことであるから、昨年は、更に遺言書保管件数も増えているだろう。
ところで、遺言信託の多くの事例では、遺言信託契約をした信託銀行を遺言執行者に指定し、しかも、「相続させる遺言」ではなく「遺贈」とすることがかなり多い。
しかしながら、ここに大きな【落とし穴】がある。
遺言執行に関して受遺者・相続人間に紛争が発生した場合、信託銀行は、遺言執行者への就職を辞退することになるから、せっかく高額の遺言信託手数料を支払って公正証書遺言を作成しても、いとも簡単に【無効扱い】されてしまうのである。
いやそんな筈はない、そう簡単に辞退しない、と思いたいだろうが、信託銀行が報酬を得て紛争事例を扱うことになれば、弁護士法72条に抵触する可能性が出てくるから、信託銀行としては紛争事例については就職を辞退せざるを得なくなるのである。現に、信託銀行のHPなどには、さりげなく、【遺言執行が著しく困難な場合には、遺言執行者への就職を辞退させていただくことがあります。】と記載されている。
では、遺言書に指定された遺言執行者が就職を拒絶するとどうなるか?
昭和62年4月23日最高裁判例によれば、遺言執行者の指定された遺言に反する相続人の行為は民法1013条に反し無効であるとされているが、昭和62年の最高裁判例解説の279頁には、『相続人の処分行為の有効を主張する側において被指定者が就職を拒絶した事実の主張立証責任を負担するとの考え方に立っているものと推測されようか。』と記載されている。つまり、遺言執行者に指定された者が就職を拒絶した時は、民法1013条が適用されず、相続人も処分行為をなし得るということになる。となると、受遺者以外の相続人としては、勢い、受遺者たる相続人に強く働きかけて、遺贈を放棄させて遺産分割協議書に署名押印させるということになりかねない。
もっとも、【相続させる旨の遺言】については、平成3年4月19日最高裁判例により直ちに権利移転の効果が生じるとされており、物権的効力を生ずると解されるから、判例理論からすれば、【相続させる旨の遺言】に反する遺産分割協議はできない筈だが、民法907条及び908条からすると、遺言に反する遺産分割協議も可能と考えるのもむべなるかな、である。
しかしながら、【受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる】という民法986条の規定は、【特定遺贈】にのみ適用され、【包括遺贈】には適用されず、包括遺贈には、相続放棄申述に関する規定が適用されるのである。
そして、もっと問題なのは、【特定遺贈】と【包括遺贈】の区別を理解せず、【包括遺贈】であるにも拘わらず、【特定遺贈】だと誤解されることがしばしばあることである。
包括遺贈については、家庭裁判所において相続放棄申述申立が受理されない限り、放棄できないにも拘わらず、受遺者に圧力を加えて【遺贈を放棄します】と言わせて、遺産分割協議書などに署名押印させてしまう強引な協議が行われることになりかねないのである。
遺言執行者が就職してしっかり対応すれば上記の如き不都合は発生しない筈だが、いとも簡単に遺言執行者への就職を辞退されたら、遺言者の真意は実現されないのである。
そして、信託銀行と遺言信託契約を締結する遺言者は、このようなことを全く知らない。
遺言と異なる遺産分割についてどう考えるか大変難しい問題であるが、遺言信託では、そのような事項については説明されないから、遺言者は【落とし穴】に嵌るのである。
(2014年4月執筆)
人気記事
人気商品
関連商品
関連カテゴリから探す
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.