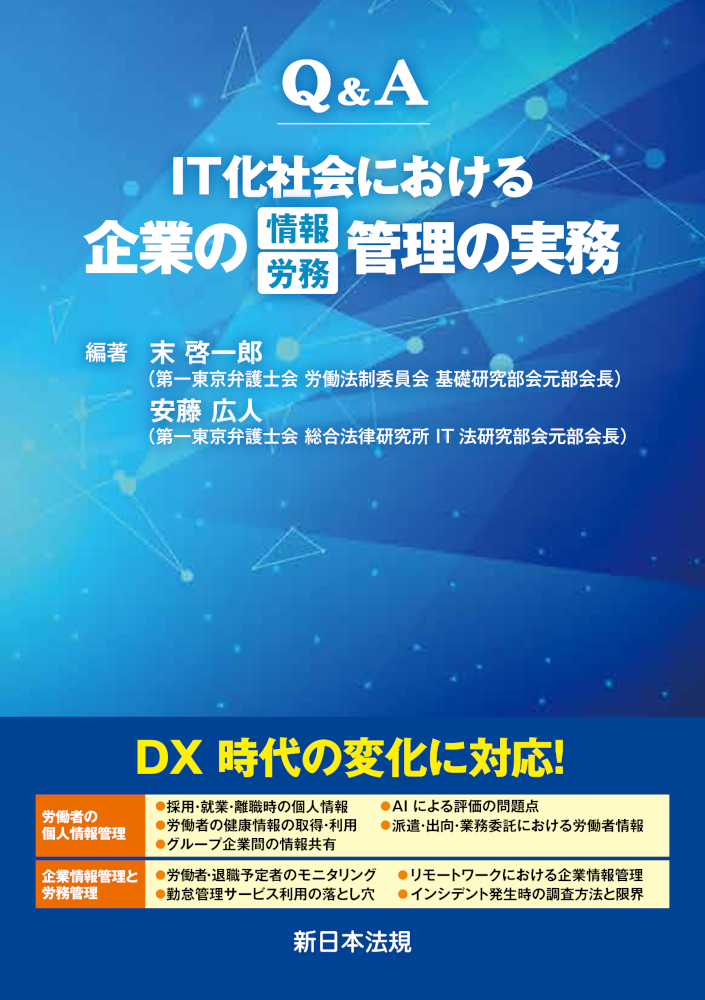一般2025年09月12日 人間関係の悩みを「AIブッダ」に相談すると、どんな答えが返ってくるのか? AI活用最前線【人生相談・医療・農業編】 提供:共同通信社

人工知能(AI)の活用が身の回りのさまざまな分野で進んでいる。歴史上の人物AIに恋愛相談をしたり、健康診断のデータから将来かかる恐れがある病気まで予測したりしてくれる。
企業や自治体の中には、長時間にわたる単純な仕事や、膨大な量の書類を扱う作業をAIに代替させようとする取り組みが多く見られる。一方で人間でなければ対応できないケースや、AIでなければ気づくことができなかった発見を得られた例もある。使い方を間違えれば差別とも誤解されかねない取り組みもあり、十分な配慮が必要だ。「人間でなければできない仕事」と「AIに任せていい仕事」を明確にしていくことが導入の鍵となる。(共同通信=沢野林太郎)
【人生相談】AIブッダ、ソクラテスに恋愛相談(京大・名古屋大)
ブッダやソクラテスら歴史上の偉人の経典や哲学を学習して回答する人工知能(AI)を、京都大と名古屋大の研究者が開発した。
「付き合っていた人と別れました。理想の相手を見つけるにはどうしたらいいですか」。京都大4年の男子学生はブッダの教えを学習したAI「ブッダボットプラス」に恋愛相談をした。パソコンのキーボードをたたいて質問を入力すると、ブッダAIは「自らが正しい行いをすれば良い人が自然と寄ってくる」と回答を画面に表示した。
男子学生は「正しい行いはしているはず」と質問を続ける。すると「執着し過ぎると心が縛られてしまう。執着を手放すと理想の相手に出会う機会が訪れる」と諭す。男子学生は「本当に求めているのはどのような人なのか、見つめ直しなさい、ということかな」とつぶやいた。
ブッダAIを開発したのは京都大の熊谷誠慈(くまがい・せいじ)教授(仏教学)。「仏教と縁がなかった人にもブッダの教えに触れてほしい」と思い、新たなブッダAIを2023年7月に開発した。企業が従業員のカウンセリングに導入することを想定する。
名古屋大の岩田直也(いわた・なおや)准教授(古代哲学)などの研究チームは、古代ギリシャのソクラテスやプラトンなど計22人分の哲学を学んだAI「ヒューマニテクスト」を2024年5月に発表した。
名古屋大大学院2年の女子学生はソクラテスを選んで「どのようにしたら妻と良好な関係を保つことができますか」と尋ねた。回答は「対話を通じてお互いの立場や考えを理解し、真実を探求する姿勢が大切だ」。岩田准教授はソクラテスが相手に質問を投げかける「問答法」と呼ばれる手法により、真理を探究したと解説したが、女子学生は「妻に多くの質問をすると嫌われてしまいそう」と話した。
元人工知能学会会長の松原仁(まつばら・ひとし)・京都橘大教授は「例えばヒトラーの考えを学習させた、AIヒトラーの開発も可能だ。AIも他の技術と同じで、人間を幸せにする面と負の側面を持つ。使う人の倫理が問われている」と話している。
【医療】発症リスクをAI予測(熊本県荒尾市)
人工知能(AI)を使って血液のタンパク質や健康診断の結果を解析し、脳卒中やがんなどの発症リスクを予測するサービスを医療ITが提供している。生活習慣の改善点を示し、健康な生活を送ってもらうのに役立つと期待。有料で保険は適用されないが、費用を負担する自治体もある。
NECグループのフォーネスライフ(東京)は2021年、提携病院で発症リスクのAI予測サービスの一般提供を始めた。病院で数ミリリットルの血液を採血し、東京の施設に運んで約7千種類の血中タンパク質の量を割り出す。
AIは病気にかかった人のタンパク質の種類や量の特徴を学習。採血した血液中のタンパク質に同じような傾向があると発症リスクが高いと判断する。
保健師の資格を持つ担当スタッフが「20年以内の認知症発症リスク53%」「4年以内の心筋梗塞・脳卒中27%」などとAIの予測結果を説明し、生活習慣の改善方法を助言する。費用は1回当たり5万4780円だ。
荒尾市は費用を負担し、住民の希望者に2024年3月から本格的に提供している。単年度で約2億円の予算を確保し、この年の3月以降2025年1月までに延べ350人が利用した。市のスマートシティ推進室の宮本賢一(みやもと・けんいち)室長は「住民が健康に暮らすことで、自治体が負担する医療費の削減につながる」と語る。
予測サービスを監修した国際医療福祉大大学院の下川宏明(しもかわ・ひろあき)教授は「健康的な生活に切り替え発症リスクを減らすことが期待できる」と説明した。
メディカル・データ・ビジョン(東京)はソニーの子会社と共同でAIが血圧や肝機能といった健康診断の結果に基づき、34の疾患の発症リスクを予測するサービスを2024年10月に始めた。
メディカル社が医療機関から本人の承諾を得て集めた全国約5千万人分の匿名化された診療データをAIに学習させた。健康診断の結果をスマートフォンのアプリに入力すると、3年以内の発症リスクの予測を示す。料金は月550円だ。
AIが人の病気を予測できるようになれば、健康寿命が延びるかもしれない。しかしAIの判断は予測であるため、うのみせずに健康診断や医師による診療を受ける必要がある。
【農業編】AIが農作物の病害虫予測(JA豊橋)
AIが農作物の病害虫の発生を予測したり、診断したりするスマートフォンのアプリをIT企業ミライ菜園(名古屋市)が開発した。過去の約100万件の発生記録や、気象データを学習して予測。日本農薬(東京)とNTTデータCCS(同)はスマホで農作物の写真を撮ると病害の種類を特定し、防除に適した農薬を提案する。
病害虫の発生予測により、農薬をタイミング良く散布することで、収穫量の拡大や農薬の使用量削減が期待できる。「温暖化の影響で気温の低下が例年より遅い」など、農家が判断に迷う際の助けになりそうだ。
ミライ菜園のアプリは、ブロッコリーやイチゴ、トマトなど計10種類の作物に対応する。病害虫が発生した農家がアプリに情報を送ると、近隣の農家が発生を知ることができる機能も盛り込んだ。JA豊橋が利用するほかJA全農ぐんまなどが試験導入した。畠山友史社長によると、キャベツの産地で比較的気温が低い群馬県嬬恋村では、温暖な地域でみられた病害が発生している。「AIを使うことで気候変動に対応した栽培ができる」と強調する。
日本農薬とNTTデータCCSは、病害虫や雑草の種類をスマホで撮影した写真で判別するAIアプリを提供する。計25の作物で、1100以上の病害虫や雑草を診断。無料で利用でき、ダウンロード数は約25万となった。NTTデータCCSの担当者は「経験を積んだ農家や農業指導員の知見を共有できる」と語った。
アプリを利用している愛知県豊橋市の農家は、どの病害虫なのか結果がすぐに分かる点を評価している。これまでは人に聞いたり自分で調べたりして結果が分かるまで数日かかっていたが、その間に病気が広がってしまうことがあった。アプリ導入後は、病気の発生を抑えることができ、収量も増えたという。
別の農家は、ブロッコリーだけで1万3千本も育てている。一本一本すべてを見て回ることはできないため、農薬散布などの畑全体の作業方針を決める際にアプリを活用している。
これらアプリは、農業に特化した「集合知」のようなAIだ。熟練者のノウハウだけでなく、現在の周囲の状況も教えてくれる。新規就農者には役立つだろう。
(2025/09/12)
(本記事の内容に関する個別のお問い合わせにはお答えすることはできません。)
人気記事
人気商品
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -