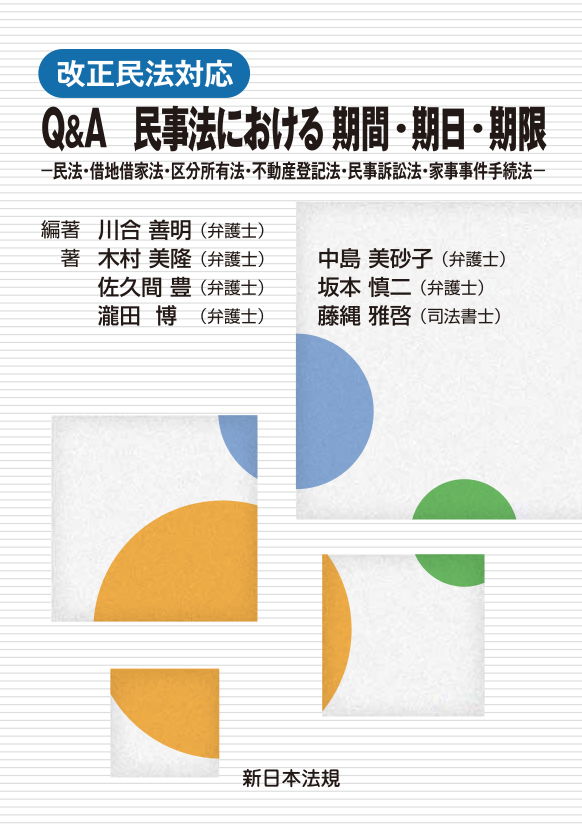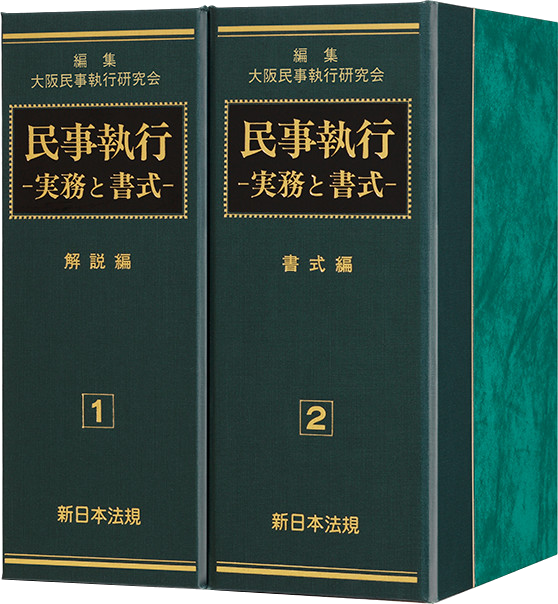PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
民法の一部改正(令和4年12月16日法律第102号〔第1条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年4月26日(政令第173号)において令和6年4月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月16日
- 施行日 令和6年04月01日
法務省
明治29年法律第89号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月16日
- 施行日 令和6年04月01日
法務省
明治29年法律第89号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇民法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一七三号)(法務省)
民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一〇二号)の施行期日は、令和六年四月一日とすることとした。
◇民法等の一部を改正する法律(法律第一〇二号)(法務省)
一 民法の一部改正関係
1 再婚禁止期間の撤廃等
再婚禁止期間に関する規定について所要の見直しを行うこととした。(第七三三条、第七四六条及び第七七三条関係)
2 嫡出の推定
㈠ 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定することとし、女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とすることとした。(第七七二条第一項関係)
㈡ ㈠の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定することとした。(第七七二条第三項関係)
3 嫡出の否認
㈠ 父、子又は母は、子が嫡出であることを否認することができることとした。(第七七四条第一項及び同条第三項関係)
㈡ 子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができることとした。(第七七四条第四項関係)
4 嫡出否認の訴え
父、子、母及び前夫の否認権は、それぞれ所定の者に対する嫡出否認の訴えによって行うこととした。(第七七五条第一項関係)
5 嫡出否認の訴えの出訴期間
㈠ 父、子、母及び前夫の否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ所定の時期から三年以内に提起しなければならないこととした。(第七七七条関係)
㈡ 子は、その父と継続して同居した期間が三年を下回るときは、二一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができることとした。(第七七八条の二第二項関係)
6 認知の無効の訴え
㈠ 子若しくはその法定代理人、認知をした者又は子の母は、それぞれ所定の時期から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができることとした。(第七八六条第一項関係)
㈡ 子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間が三年を下回るときは、二一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができることとした。(第七八六条第二項関係)
7 子の人格の尊重等
親権を行う者は、監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこととするとともに、懲戒に関する規定を削除することとした。(第八二一条及び第八二二条関係)
二 児童福祉法の一部改正関係
児童相談所長等は、一時保護が行われた児童等で親権を行う者等のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができることとし、この場合において、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこととした。(第三三条の二第二項及び第四七条第三項関係)
三 国籍法の一部改正関係
認知された子の国籍の取得に関する規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しないこととした。(第三条第三項関係)
四 児童虐待の防止等に関する法律の一部改正関係
児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこととした。(第一四条第一項関係)
五 人事訴訟法の一部改正関係
1 嫡出否認の訴えの当事者
父が子の出生前に死亡したとき又は所定の期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族は、父の死亡の日から一年以内に限り、嫡出否認の訴えを提起することができることとした。(第四一条第一項関係)
2 認知の無効の訴えの当事者
㈠ 認知の無効の訴えについても、1と同様の規律を設けることとした。(第四三条第一項関係)
㈡ 子が所定の期間内に認知の無効の訴えを提起しないで死亡したときは、子の直系卑属又はその法定代理人は、認知の無効の訴えを提起することができることとし、この場合においては、子の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならないこととした。(第四三条第二項関係)
六 家事事件手続法の一部改正関係
裁判所は、嫡出否認についての合意に相当する審判が確定したときは、前夫に対し、当該合意に相当する審判の内容を通知することとした。(第二八三条の二関係)
七 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の一部改正関係
妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫、子又は妻は、その子が嫡出であることを否認することができないこととした。(第一〇条関係)
八 その他
この法律の制定に伴い、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二条~第六条関係)
九 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一〇二号)の施行期日は、令和六年四月一日とすることとした。
◇民法等の一部を改正する法律(法律第一〇二号)(法務省)
一 民法の一部改正関係
1 再婚禁止期間の撤廃等
再婚禁止期間に関する規定について所要の見直しを行うこととした。(第七三三条、第七四六条及び第七七三条関係)
2 嫡出の推定
㈠ 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定することとし、女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とすることとした。(第七七二条第一項関係)
㈡ ㈠の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定することとした。(第七七二条第三項関係)
3 嫡出の否認
㈠ 父、子又は母は、子が嫡出であることを否認することができることとした。(第七七四条第一項及び同条第三項関係)
㈡ 子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができることとした。(第七七四条第四項関係)
4 嫡出否認の訴え
父、子、母及び前夫の否認権は、それぞれ所定の者に対する嫡出否認の訴えによって行うこととした。(第七七五条第一項関係)
5 嫡出否認の訴えの出訴期間
㈠ 父、子、母及び前夫の否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ所定の時期から三年以内に提起しなければならないこととした。(第七七七条関係)
㈡ 子は、その父と継続して同居した期間が三年を下回るときは、二一歳に達するまでの間、嫡出否認の訴えを提起することができることとした。(第七七八条の二第二項関係)
6 認知の無効の訴え
㈠ 子若しくはその法定代理人、認知をした者又は子の母は、それぞれ所定の時期から七年以内に限り、認知について反対の事実があることを理由として、認知の無効の訴えを提起することができることとした。(第七八六条第一項関係)
㈡ 子は、その子を認知した者と認知後に継続して同居した期間が三年を下回るときは、二一歳に達するまでの間、認知の無効の訴えを提起することができることとした。(第七八六条第二項関係)
7 子の人格の尊重等
親権を行う者は、監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこととするとともに、懲戒に関する規定を削除することとした。(第八二一条及び第八二二条関係)
二 児童福祉法の一部改正関係
児童相談所長等は、一時保護が行われた児童等で親権を行う者等のあるものについても、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができることとし、この場合において、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこととした。(第三三条の二第二項及び第四七条第三項関係)
三 国籍法の一部改正関係
認知された子の国籍の取得に関する規定は、認知について反対の事実があるときは、適用しないこととした。(第三条第三項関係)
四 児童虐待の防止等に関する法律の一部改正関係
児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、児童の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の児童の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないこととした。(第一四条第一項関係)
五 人事訴訟法の一部改正関係
1 嫡出否認の訴えの当事者
父が子の出生前に死亡したとき又は所定の期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族は、父の死亡の日から一年以内に限り、嫡出否認の訴えを提起することができることとした。(第四一条第一項関係)
2 認知の無効の訴えの当事者
㈠ 認知の無効の訴えについても、1と同様の規律を設けることとした。(第四三条第一項関係)
㈡ 子が所定の期間内に認知の無効の訴えを提起しないで死亡したときは、子の直系卑属又はその法定代理人は、認知の無効の訴えを提起することができることとし、この場合においては、子の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならないこととした。(第四三条第二項関係)
六 家事事件手続法の一部改正関係
裁判所は、嫡出否認についての合意に相当する審判が確定したときは、前夫に対し、当該合意に相当する審判の内容を通知することとした。(第二八三条の二関係)
七 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律の一部改正関係
妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫、子又は妻は、その子が嫡出であることを否認することができないこととした。(第一〇条関係)
八 その他
この法律の制定に伴い、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二条~第六条関係)
九 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
関連商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.