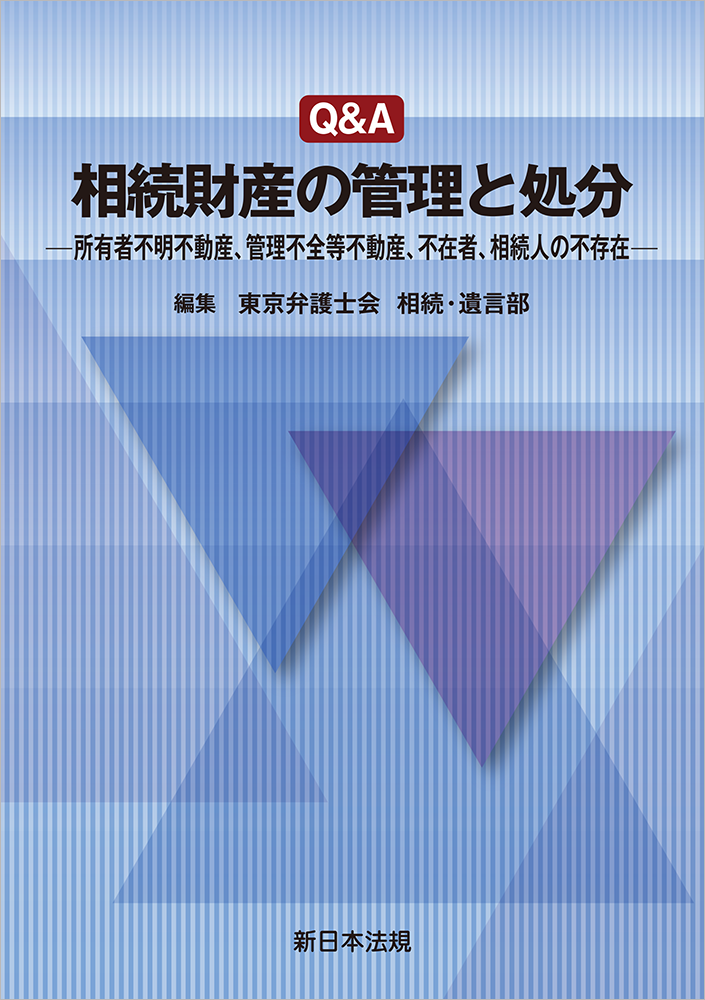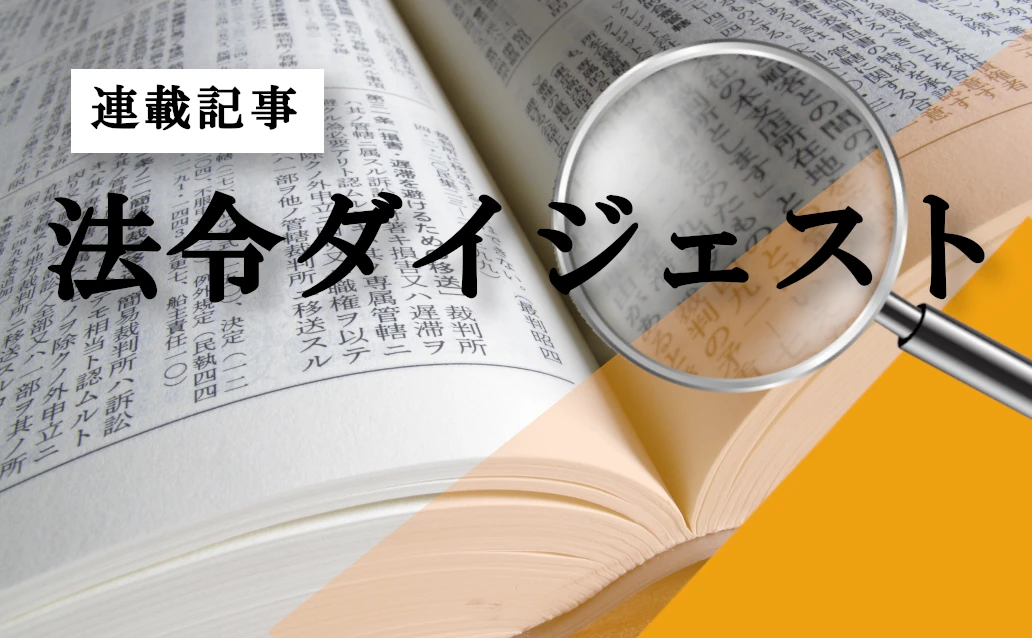資料2002年06月24日 【税務通達】 所得税基本通達 法第9条《非課税所得》関係
法第9条《非課税所得》関係
〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
9-1 労働基準法第8章《災害補償》の規定により受ける補償のうち、同法第79条《遺族補償》及び第80条《葬祭料》の規定により受ける遺族補償(同法第82条《分割補償》に規定する分割補償のうち遺族補償に係る部分を含む。)及び葬祭料は、令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》に規定する非課税所得に該当する。
(非課税とされる年金の範囲)
9-2 法第9条第1項第3号ロに掲げる年金には、次に掲げるものが含まれる。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1)死亡した者の勤務に基づき、使用者であった者から当該死亡した者の遺族に支給される年金
(2)死亡した者がその勤務に直接関連して加入した社会保険又は共済に関する制度、退職年金制度等に基づき、当該死亡した者の遺族に支給される年金で、当該死亡した者が生存中に支給を受けたとすれば法第35条第3項《雑所得》の規定によりその者の公的年金等とされるもの
〔旅費(第4号関係)〕
(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)
9-4 法第9条第1項第4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(1)給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するためにした旅行 給与所得
(2)給与所得を有する者が転任に伴う転居のためにした旅行 給与所得
(3)就職をした者がその就職に伴う転居のためにした旅行 雑所得
(4)退職をした者がその退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得
(5)死亡による退職をした者の遺族がその死亡による退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得(法第9条第1項第15号の規定により非課税とされる。)
(非常勤役員等の出勤のための費用)
9-5 給与所得を有する者で常には出勤を要しない次に掲げるようなものに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。
(1)国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与
(2)会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与
(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当)
9-6 災害対策基本法第31条《職員の派遣義務》の規定により災害地に派遣された職員に対し、その派遣を受けた都道府県又は市町村から同法第32条《派遣職員の身分取扱い》の規定により支給される災害派遣手当については、その職員が本来の勤務地を離れて災害地に滞在するために必要な宿泊等の費用を弁償するものであると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。
〔通勤手当(第5号関係)〕
(交通用具を使用する者に係る通勤手当の非課税限度額の計算)
9-6の2 令第20条の2第2号ハ《非課税とされる通勤手当》に規定する「その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等」の額は、その者が現に通勤のため交通機関を利用した場合に負担することとなる運賃等の額によるべきであるが、その者が通勤のために利用する交通機関がないなどにより、当該運賃等の額により難い場合には、その者の交通用具を使用する通勤距離に相当する距離につき旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項《会社の目的及び事業》に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項《指針の公表等》に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)の鉄道を利用した場合に負担することとなる各旅客会社等の旅客営業規則に定める地方交通線の通用期間1か月の通勤定期旅客運賃の額によって差し支えないものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭63直法6-7、直所3-8改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)
(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)
9-6の3 令第20条の2 に規定する「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとする。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142追加) (注) 「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」の中には、令第167 条の3 第1 項第1 号に規定する「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。
〔現物給与(第6号関係)〕
(船員法第80条の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料)
9-7 船員法第80条《食料の支給》の規定の適用がない漁船の乗組員に対しその乗船中に支給される食料については、その乗組員の勤務がその漁船の操業区域において操業する他の同条の規定の適用がある漁船の乗組員の勤務に類すると認められる場合に支給されるものに限り、令第21条第1号《非課税とされる職務上必要な給付》に掲げる食料に準じて課税しなくて差し支えない。
(制服に準ずる事務服、作業服等)
9-8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。
(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)
9-9 令第21条第4号に規定する「職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するため」に貸与を受ける家屋には、次に掲げるようなものが該当する。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)
(1)船舶乗組員に対し提供した船室
(2)常時交替制により昼夜作業を継続する事業場において、その作業に従事するため常時早朝又は深夜に出退勤をする使用人に対し、その作業に従事させる必要上提供した家屋又は部屋
(3)通常の勤務時間外においても勤務を要することを常例とする看護師、守衛等その職務の遂行上勤務場所を離れて居住することが困難な使用人に対し、その職務に従事させる必要上提供した家屋又は部屋
(4)次に掲げる家屋又は部屋
イ早朝又は深夜に勤務することを常例とするホテル、旅館、牛乳販売店等の住み込みの使用人に対し提供した部屋
ロ季節的労働に従事する期間その勤務場所に住み込む使用人に対し提供した部屋
ハ鉱山の掘採場(これに隣接して設置されている選鉱場、製錬場その他の附属設備を含む。)に勤務する使用人に対し提供した家屋又は部屋
ニ 工場寄宿舎その他の寄宿舎で事業所等の構内又はこれに隣接する場所に設置されているものの部屋
(公邸)
9-10 国家公務員宿舎法第10条《公邸》の規定により無料で公邸の貸与を受けることによる利益については、令第21条第4号に掲げる利益に準じて課税しなくて差し支えない。
〔外国公務員等の給与等(第8号関係)〕
(人的非課税)
9-11 国内に居住する外国の大使、公使及び外交官である大公使館員並びにこれらの配偶者に対しては、課税しないものとする。
(外国政府等に勤務する者の給与)
9-12 法第9条第1項第8号の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(昭50直所3-4、平5課法8-2、課所4-6改正)
(1)その勤務先は、外国政府若しくは外国の地方公共団体又は昭和47年12月8日付大蔵省告示第152号に定める国際機関(以下この項においてこれらを「外国政府等」という。)に限られるのであるから、外国政府等に該当しない法人から受ける給与は、たとえその法人が外国政府等の全額出資に係るものであっても、非課税とならないこと。
(注)上記の告示に定める国際機関以外の国際機関からその職員が受ける給与についても、条約(例えば、国際連合の特権及び免除に関する条約第5条第18項(b)《課税の免除》、専門機関の特権及び免除に関する条約第6条第19項(b)《課税の免除》、アジア開発銀行を設立する協定第56条第2項《課税の免除》等)により非課税とされる場合があることに留意する。
(2)外国政府等に勤務する者で令第24条《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件》に規定する要件に該当するものが、その勤務により受けるものであっても、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与は、非課税とならないこと。
(注)これらの給与についても、租税条約により非課税とされる場合があることに留意する。
(3)その勤務が外国政府又は外国の地方公共団体のために行われるものであっても、例えば、その外国政府又は外国の地方公共団体が舞踊、サーカス、オペラ等の芸能の提供を行っている場合のその業務のように、我が国若しくは我が国の地方公共団体の行う業務以外の業務又は収益を目的とする業務に従事したことにより受ける給与は、非課税とならないこと。
〔強制換価等による譲渡(第10号関係〕
(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)
9-12の2 法第9条第1項第10号及び令第26条《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(非課税とされる山林の伐採又は譲渡による所得)
9-12の3 法第9条第1項第10号の規定により非課税とされる所得は、資産の譲渡による所得のうち棚卸資産(令第81条各号《譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産》に掲げる資産を含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得以外の所得に限られるから、山林の伐採又は譲渡による所得であっても、営利を目的として継続的に行われる山林の伐採又は譲渡による所得については、法第9条第1項第10号の規定は適用されない。(昭50直資3-11、直所3-19追加)
(譲渡対価が債務の弁済に充てられたかどうかの判定)
9-12の4 令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」かどうかは、同条に規定する資産の譲渡の対価(当該資産の譲渡に要した費用がある場合には、当該費用に相当する部分を除く。)の全部が当該譲渡の時において有する債務の弁済に充てられたかどうかにより判定する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(代物弁済)
9-12の5 次に掲げる代物弁済による資産の譲渡に係る所得は、令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたもの」に該当する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(1)債権者から清算金を取得しない代物弁済
(2)債権者から清算金を取得する代物弁済で当該清算金の全部を当該代物弁済に係る債務以外の債務の弁済に充てたもの
(注)清算金とは、代物弁済に係る資産の価額が当該代物弁済に係る債務の額を超える場合におけるその超える金額に相当する金額として債権者から債務者に対し交付される金銭その他の資産をいう。
〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係〕
(収益調整金の意義)
9-13 令第27条《オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの》に規定する収益調整金とは、オープン型の証券投資信託の追加信託が行われる際に、黒字の収益調整金として経理された金額をいう。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注)オープン型の証券投資信託の経理処理においては、元本固定方式がとられているため、場合によっては赤字の収益調整金を生ずることもあるが、赤字の収益調整金は、実際に信託された金額が元本額及び黒字の収益調整金として経理した金額の合計額に対して不足していること、すなわち、実際には信託されなかった金額があることを示すものである。
〔学資金(第14号関係)〕
(使用人等に学資金等として支給される金品)
9-14 使用者から役員又は使用人に対してこれらの者の修学のため、又はこれらの者の子弟の修学のための学資金等として支給される金品(その子弟に対して直接支給されるものを含む。)は、原則として、法第9条第1項第14号かっこ内に規定する給与に該当するのであるから、当該役員又は使用人に対する給与等(法第28条第1項《給与所得》に規定する給与等をいう。以下9-17において同じ。)として課税することに留意する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
9-15 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(使用人に対し学資に充てるために支給する金品)
9-16 使用者が使用人に対しその者の学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)における修学のための費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、9-15の取扱いに準じ、課税しなくて差し支えないものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
〔相続等により取得するもの(第15号関係)〕
(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
9-17 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注)上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の支給期については、36-9、36-10及び36-14の(1)に定めるところによる。
(年金の総額に代えて支払われる一時金)
9-18 死亡を年金給付事由とする令第183条第3項《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》に規定する生命保険契約等の給付事由が発生した場合で当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金がその死亡をした者によって負担されたものであるときにおいて、当該生命保険契約等に基づく年金の受給資格者が当該年金の受給開始日以前に年金給付の総額に代えて一時金の支払を受けたときは、当該一時金については課税しないものとする。(昭49直所2-23追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
〔保険金、損害賠償金等(第16号関係)〕
(必要経費に算入される金額を補てんするための金額の範囲)
9-19 令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に算入される金額を補てんするための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用を補てんするものとして計算された金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項《資産損失の必要経費算入》の規定によりこれらの項に規定する損失の金額の計算上控除される保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、これに含まれない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
9-20 令第30条第1号の規定により非課税とされる「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注)いわゆる死亡保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」には該当しないのであるから留意する。
(高度障害保険金等)
9-21 疾病により重度障害の状態になったことなどにより、生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受けるいわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等(一時金として受け取るもののほか、年金として受け取るものを含む。)は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(所得補償保険金)
9-22 被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補てんとして損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注)業務を営む者が自己を被保険者として支払う当該保険金に係る保険料は、当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであるから留意する。
(葬祭料、香典等)
9-23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金の非課税)
9-24 次に掲げる給付については、課税しないものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平10課法8-2、課所4-5改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)
(1)国家公務員退職手当法第10条《失業者の退職手当》の規定による退職手当
(2)次に掲げる休業手当金で、組合員、その配偶者又は被扶養者の傷病、葬祭又はこれらの者に係る災害により受けるもの
イ国家公務員共済組合法第68条《休業手当金》の規定による休業手当金
ロ地方公務員等共済組合法第70条《休業手当金》の規定による休業手当金
ハ私立学校教職員共済法第25条《国家公務員共済組合法の準用》の規定によるイに準ずる休業手当金
(3)労働基準法第76条第1項《休業補償》に定める割合を超えて休業補償を行った場合の当該休業補償
〔傷病者の恩給等(第3号関係)〕
(労働基準法による遺族補償及び葬祭料)
9-1 労働基準法第8章《災害補償》の規定により受ける補償のうち、同法第79条《遺族補償》及び第80条《葬祭料》の規定により受ける遺族補償(同法第82条《分割補償》に規定する分割補償のうち遺族補償に係る部分を含む。)及び葬祭料は、令第30条《非課税とされる保険金、損害賠償金等》に規定する非課税所得に該当する。
(非課税とされる年金の範囲)
9-2 法第9条第1項第3号ロに掲げる年金には、次に掲げるものが含まれる。(昭63直法6-1、直所3-1改正)
(1)死亡した者の勤務に基づき、使用者であった者から当該死亡した者の遺族に支給される年金
(2)死亡した者がその勤務に直接関連して加入した社会保険又は共済に関する制度、退職年金制度等に基づき、当該死亡した者の遺族に支給される年金で、当該死亡した者が生存中に支給を受けたとすれば法第35条第3項《雑所得》の規定によりその者の公的年金等とされるもの
〔旅費(第4号関係)〕
(非課税とされる旅費の範囲)
9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。
(非課税とされる旅費の範囲を超えるものの所得区分)
9-4 法第9条第1項第4号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な支出に充てるものとして支給される金品の額が、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲の金額を超える場合には、その超える部分の金額は、その超える部分の金額を生じた旅行の区分に応じ、それぞれ次に掲げる所得の収入金額又は総収入金額に算入する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(1)給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するためにした旅行 給与所得
(2)給与所得を有する者が転任に伴う転居のためにした旅行 給与所得
(3)就職をした者がその就職に伴う転居のためにした旅行 雑所得
(4)退職をした者がその退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得
(5)死亡による退職をした者の遺族がその死亡による退職に伴う転居のためにした旅行 退職所得(法第9条第1項第15号の規定により非課税とされる。)
(非常勤役員等の出勤のための費用)
9-5 給与所得を有する者で常には出勤を要しない次に掲げるようなものに対し、その勤務する場所に出勤するために行う旅行に必要な運賃、宿泊料等の支出に充てるものとして支給される金品で、社会通念上合理的な理由があると認められる場合に支給されるものについては、その支給される金品のうちその出勤のために直接必要であると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。
(1)国、地方公共団体の議員、委員、顧問又は参与
(2)会社その他の団体の役員、顧問、相談役又は参与
(災害地に派遣された職員に支給される災害派遣手当)
9-6 災害対策基本法第31条《職員の派遣義務》の規定により災害地に派遣された職員に対し、その派遣を受けた都道府県又は市町村から同法第32条《派遣職員の身分取扱い》の規定により支給される災害派遣手当については、その職員が本来の勤務地を離れて災害地に滞在するために必要な宿泊等の費用を弁償するものであると認められる部分に限り、法第9条第1項第4号に掲げる金品に準じて課税しなくて差し支えない。
〔通勤手当(第5号関係)〕
(交通用具を使用する者に係る通勤手当の非課税限度額の計算)
9-6の2 令第20条の2第2号ハ《非課税とされる通勤手当》に規定する「その者が通勤のため交通機関を利用したとしたならば負担することとなるべき運賃等」の額は、その者が現に通勤のため交通機関を利用した場合に負担することとなる運賃等の額によるべきであるが、その者が通勤のために利用する交通機関がないなどにより、当該運賃等の額により難い場合には、その者の交通用具を使用する通勤距離に相当する距離につき旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第1条第1項《会社の目的及び事業》に規定する旅客会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項《指針の公表等》に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)の鉄道を利用した場合に負担することとなる各旅客会社等の旅客営業規則に定める地方交通線の通用期間1か月の通勤定期旅客運賃の額によって差し支えないものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、昭63直法6-7、直所3-8改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)
(新幹線通勤の場合の非課税とされる通勤手当)
9-6の3 令第20条の2 に規定する「その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」には、新幹線鉄道を利用した場合の運賃等の額も含まれるものとする。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142追加) (注) 「最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額」の中には、令第167 条の3 第1 項第1 号に規定する「特別車両料金等」は含まれないことに留意する。
〔現物給与(第6号関係)〕
(船員法第80条の規定の適用がない漁船の乗組員に支給される食料)
9-7 船員法第80条《食料の支給》の規定の適用がない漁船の乗組員に対しその乗船中に支給される食料については、その乗組員の勤務がその漁船の操業区域において操業する他の同条の規定の適用がある漁船の乗組員の勤務に類すると認められる場合に支給されるものに限り、令第21条第1号《非課税とされる職務上必要な給付》に掲げる食料に準じて課税しなくて差し支えない。
(制服に準ずる事務服、作業服等)
9-8 専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、令第21条第2号及び第3号に規定する制服に準じて取り扱って差し支えない。
(職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等)
9-9 令第21条第4号に規定する「職務の遂行上やむを得ない必要に基づき使用者から指定された場所に居住すべきものがその指定する場所に居住するため」に貸与を受ける家屋には、次に掲げるようなものが該当する。(平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)
(1)船舶乗組員に対し提供した船室
(2)常時交替制により昼夜作業を継続する事業場において、その作業に従事するため常時早朝又は深夜に出退勤をする使用人に対し、その作業に従事させる必要上提供した家屋又は部屋
(3)通常の勤務時間外においても勤務を要することを常例とする看護師、守衛等その職務の遂行上勤務場所を離れて居住することが困難な使用人に対し、その職務に従事させる必要上提供した家屋又は部屋
(4)次に掲げる家屋又は部屋
イ早朝又は深夜に勤務することを常例とするホテル、旅館、牛乳販売店等の住み込みの使用人に対し提供した部屋
ロ季節的労働に従事する期間その勤務場所に住み込む使用人に対し提供した部屋
ハ鉱山の掘採場(これに隣接して設置されている選鉱場、製錬場その他の附属設備を含む。)に勤務する使用人に対し提供した家屋又は部屋
ニ 工場寄宿舎その他の寄宿舎で事業所等の構内又はこれに隣接する場所に設置されているものの部屋
(公邸)
9-10 国家公務員宿舎法第10条《公邸》の規定により無料で公邸の貸与を受けることによる利益については、令第21条第4号に掲げる利益に準じて課税しなくて差し支えない。
〔外国公務員等の給与等(第8号関係)〕
(人的非課税)
9-11 国内に居住する外国の大使、公使及び外交官である大公使館員並びにこれらの配偶者に対しては、課税しないものとする。
(外国政府等に勤務する者の給与)
9-12 法第9条第1項第8号の規定の適用に当たっては、次のことに留意する。(昭50直所3-4、平5課法8-2、課所4-6改正)
(1)その勤務先は、外国政府若しくは外国の地方公共団体又は昭和47年12月8日付大蔵省告示第152号に定める国際機関(以下この項においてこれらを「外国政府等」という。)に限られるのであるから、外国政府等に該当しない法人から受ける給与は、たとえその法人が外国政府等の全額出資に係るものであっても、非課税とならないこと。
(注)上記の告示に定める国際機関以外の国際機関からその職員が受ける給与についても、条約(例えば、国際連合の特権及び免除に関する条約第5条第18項(b)《課税の免除》、専門機関の特権及び免除に関する条約第6条第19項(b)《課税の免除》、アジア開発銀行を設立する協定第56条第2項《課税の免除》等)により非課税とされる場合があることに留意する。
(2)外国政府等に勤務する者で令第24条《給与が非課税とされる外国政府職員等の要件》に規定する要件に該当するものが、その勤務により受けるものであっても、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与は、非課税とならないこと。
(注)これらの給与についても、租税条約により非課税とされる場合があることに留意する。
(3)その勤務が外国政府又は外国の地方公共団体のために行われるものであっても、例えば、その外国政府又は外国の地方公共団体が舞踊、サーカス、オペラ等の芸能の提供を行っている場合のその業務のように、我が国若しくは我が国の地方公共団体の行う業務以外の業務又は収益を目的とする業務に従事したことにより受ける給与は、非課税とならないこと。
〔強制換価等による譲渡(第10号関係〕
(「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義)
9-12の2 法第9条第1項第10号及び令第26条《非課税とされる資力喪失による譲渡所得》に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、債務者の債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達することができないと認められる場合をいい、これに該当するかどうかは、これらの規定に規定する資産を譲渡した時の現況により判定する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(非課税とされる山林の伐採又は譲渡による所得)
9-12の3 法第9条第1項第10号の規定により非課税とされる所得は、資産の譲渡による所得のうち棚卸資産(令第81条各号《譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産》に掲げる資産を含む。)の譲渡その他営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡による所得以外の所得に限られるから、山林の伐採又は譲渡による所得であっても、営利を目的として継続的に行われる山林の伐採又は譲渡による所得については、法第9条第1項第10号の規定は適用されない。(昭50直資3-11、直所3-19追加)
(譲渡対価が債務の弁済に充てられたかどうかの判定)
9-12の4 令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられた」かどうかは、同条に規定する資産の譲渡の対価(当該資産の譲渡に要した費用がある場合には、当該費用に相当する部分を除く。)の全部が当該譲渡の時において有する債務の弁済に充てられたかどうかにより判定する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(代物弁済)
9-12の5 次に掲げる代物弁済による資産の譲渡に係る所得は、令第26条に規定する「その譲渡に係る対価が当該債務の弁済に充てられたもの」に該当する。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(1)債権者から清算金を取得しない代物弁済
(2)債権者から清算金を取得する代物弁済で当該清算金の全部を当該代物弁済に係る債務以外の債務の弁済に充てたもの
(注)清算金とは、代物弁済に係る資産の価額が当該代物弁済に係る債務の額を超える場合におけるその超える金額に相当する金額として債権者から債務者に対し交付される金銭その他の資産をいう。
〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係〕
(収益調整金の意義)
9-13 令第27条《オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち非課税とされるもの》に規定する収益調整金とは、オープン型の証券投資信託の追加信託が行われる際に、黒字の収益調整金として経理された金額をいう。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注)オープン型の証券投資信託の経理処理においては、元本固定方式がとられているため、場合によっては赤字の収益調整金を生ずることもあるが、赤字の収益調整金は、実際に信託された金額が元本額及び黒字の収益調整金として経理した金額の合計額に対して不足していること、すなわち、実際には信託されなかった金額があることを示すものである。
〔学資金(第14号関係)〕
(使用人等に学資金等として支給される金品)
9-14 使用者から役員又は使用人に対してこれらの者の修学のため、又はこれらの者の子弟の修学のための学資金等として支給される金品(その子弟に対して直接支給されるものを含む。)は、原則として、法第9条第1項第14号かっこ内に規定する給与に該当するのであるから、当該役員又は使用人に対する給与等(法第28条第1項《給与所得》に規定する給与等をいう。以下9-17において同じ。)として課税することに留意する。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(使用人等に対し技術の習得等をさせるために支給する金品)
9-15 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(使用人に対し学資に充てるために支給する金品)
9-16 使用者が使用人に対しその者の学校教育法第1条《学校の範囲》に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)における修学のための費用に充てるものとして支給する金品で、その修学のための費用として適正なものについては、役員又は使用者である個人の親族のみをその対象とする場合を除き、9-15の取扱いに準じ、課税しなくて差し支えないものとする。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
〔相続等により取得するもの(第15号関係)〕
(相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等)
9-17 死亡した者に係る給与等、公的年金等及び退職手当等(法第30条第1項《退職所得》に規定する退職手当等をいう。)で、その死亡後に支給期の到来するもののうち相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、課税しないものとする。(昭63直所3-3、直法6-2、直資3-2、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注)上記の給与等、公的年金等及び退職手当等の支給期については、36-9、36-10及び36-14の(1)に定めるところによる。
(年金の総額に代えて支払われる一時金)
9-18 死亡を年金給付事由とする令第183条第3項《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》に規定する生命保険契約等の給付事由が発生した場合で当該生命保険契約等に係る保険料又は掛金がその死亡をした者によって負担されたものであるときにおいて、当該生命保険契約等に基づく年金の受給資格者が当該年金の受給開始日以前に年金給付の総額に代えて一時金の支払を受けたときは、当該一時金については課税しないものとする。(昭49直所2-23追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
〔保険金、損害賠償金等(第16号関係)〕
(必要経費に算入される金額を補てんするための金額の範囲)
9-19 令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に算入される金額を補てんするための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用を補てんするものとして計算された金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項《資産損失の必要経費算入》の規定によりこれらの項に規定する損失の金額の計算上控除される保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、これに含まれない。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(身体に損害を受けた者以外の者が支払を受ける傷害保険金等)
9-20 令第30条第1号の規定により非課税とされる「損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約に基づく給付金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの」は、自己の身体の傷害に基因して支払を受けるものをいうのであるが、その支払を受ける者と身体に傷害を受けた者とが異なる場合であっても、その支払を受ける者がその身体に傷害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、当該保険金又は給付金についても同号の規定の適用があるものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注)いわゆる死亡保険金は、「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」には該当しないのであるから留意する。
(高度障害保険金等)
9-21 疾病により重度障害の状態になったことなどにより、生命保険契約又は損害保険契約に基づき支払を受けるいわゆる高度障害保険金、高度障害給付金、入院費給付金等(一時金として受け取るもののほか、年金として受け取るものを含む。)は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8、昭57直所3-8、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(所得補償保険金)
9-22 被保険者の傷害又は疾病により当該被保険者が勤務又は業務に従事することができなかったことによるその期間の給与又は収益の補てんとして損害保険契約に基づき当該被保険者が支払を受ける保険金は、令第30条第1号に掲げる「身体の傷害に基因して支払を受けるもの」に該当するものとする。(昭55直所3-19、直法6-8追加、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(注)業務を営む者が自己を被保険者として支払う当該保険金に係る保険料は、当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入することができないのであるから留意する。
(葬祭料、香典等)
9-23 葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、令第30条の規定により課税しないものとする。(平元直所3-14、直法6-9、直資3-8改正)
(失業保険金に相当する退職手当、休業手当金の非課税)
9-24 次に掲げる給付については、課税しないものとする。(昭60直所3-21、直資3-5、平元直所3-14、直法6-9、直資3-8、平10課法8-2、課所4-5改正、平14課法8-5、課個2-7、課審3-142改正)
(1)国家公務員退職手当法第10条《失業者の退職手当》の規定による退職手当
(2)次に掲げる休業手当金で、組合員、その配偶者又は被扶養者の傷病、葬祭又はこれらの者に係る災害により受けるもの
イ国家公務員共済組合法第68条《休業手当金》の規定による休業手当金
ロ地方公務員等共済組合法第70条《休業手当金》の規定による休業手当金
ハ私立学校教職員共済法第25条《国家公務員共済組合法の準用》の規定によるイに準ずる休業手当金
(3)労働基準法第76条第1項《休業補償》に定める割合を超えて休業補償を行った場合の当該休業補償
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.