解説記事2003年01月13日 【税務・会計解説】 自己株式の会計と税務の基本をマスターしよう 第1回(2003年1月13日号・№2)
自己株式の会計と税務の基本をマスターしよう 第1回
自己株式(金庫株)の取得・保有・譲渡の解禁を受けて、会計上・税務上の取扱いが整備されてきました。非公開会社が自己株式を取得した場合の会計上・税務上の取扱いを今回で、消却・譲渡した場合の取扱いを次回以降にて解説します。
平成13年6月の商法改正において、自己株式(金庫株)の取得が解禁されました。また、平成14年4月1日からは、自己株式の処分(譲渡)が認められることになりました。商法上の自己株式の取得・保有・譲渡に対する制限が、原則的になくなったことから、会計及び税法は、自己株式の取扱いを新しく定めました。自己株式の取得・保有・譲渡の解禁は、多くの会社で実際に行われており、会計人はその会計処理・税務処理に迫られます。これまで明らかとなった自己株式の会計上と税務上の取扱いについて事例を中心に解説します。
I 自己株式を取得した場合
【1】 買い受け会社(A株式会社)での取扱い
設例のA株式会社(非公開会社)が自己の発行するA社株式を相対取引で取得した場合の会計上・税務上の取扱いを検討してみましょう。
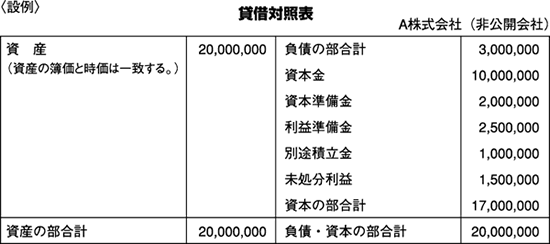
A株式会社の発行済株式数 200株
A株式会社はA社株式(自己株式)2株を対価170,000円(適正な時価)で取得しました。
(1)会計上の取扱い
企業会計基準委員会が公表した「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」では、「取得した自己株式は、取得原価をもって資本の部から控除する(第19項)。」とされています。したがって、「自己株式2株を170,000円で取得した」場合の会計上の仕訳は、次のようになります。
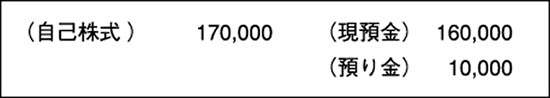
自己株式の取得原価は、170,000円となりますが、税務上の計算でみなし配当金(利益積立金相当額50,000円)が計上されることになるため、A株式会社は、みなし配当金に対する源泉徴収義務を負い、源泉所得税相当額(50,000円×20%=10,000円)の預り金を計上します。
A株式会社が自己株式を取得した会計期間での当期利益を200,000円とすると、当該会計期間末におけるA株式会社貸借対照表の資本の部の表示は次のようになります(会計期間の終了時まで自己株式を保有しつづけている場合)。
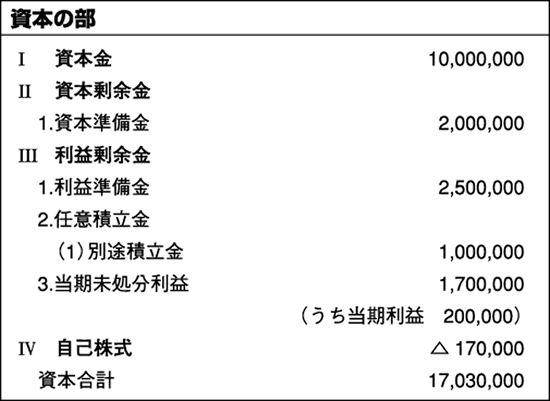
(2)税務上の取扱い
法人税法は、自己の株式の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得を除く。)について、株主に交付した金銭等の額が当該株式に対応する取得時の資本等の額を超える場合には、その超える金額を利益積立金額から控除することを規定しています(法法2条十八カ)。上記の自己株式の取得で、当該自己株式の資本等の金額を120,000円とすると、税務上の仕訳は、次のようになります。
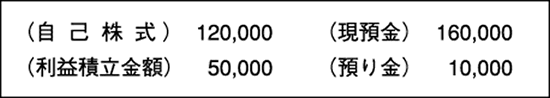
会計上で取得原価とされたものであっても、法人税法では、みなし配当(法法24条1五)となる部分の金額(50,000円)を利益積立金額から控除することが規定されています。これは、利益積立金額の計算に関する明細書(別表五(一))で調整されることになります。
一方、法人税法上は、所得の金額に関する明細書(別表四)での取扱いが規定されていません。所得金額の総額は変わりませんが、みなし配当として取り扱われる金額は、別表四上で社外流出したものとして処理され、同額の自己株式認定損(減算・留保)の計上により、別表四と利益積立金額の関係が維持されます(下記記載例のほか、みなし配当金額を別表四当期利益の社外流出・配当欄に記載する方法によっても同様の結果を導出します。)。
この結果、自己株式を取得したA株式会社の法人税別表の記載は、次のようになります。
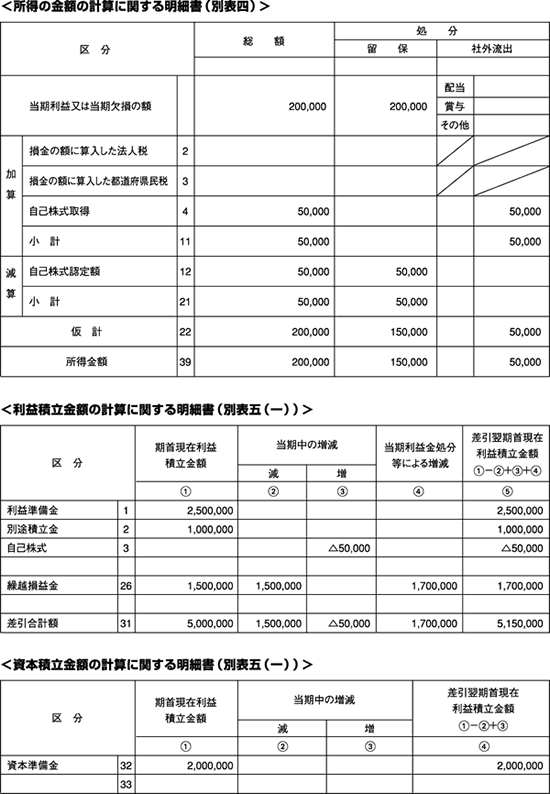
【2】 譲渡した個人株主Xの取扱い
上記の設例で、個人株主X(A社株式の取得価額10万円)がA社株式を譲渡したものとして、個人株主Xの課税上の取扱いを検討してみましょう。
個人株主Xは、次の仕訳のように考えているでしょう。
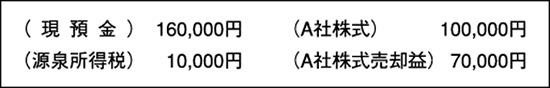
個人株主Xが、A社株式売却益を一本で認識しているとしても、税務上は、個人株主Xは、次のように配当所得と譲渡所得を区分して認識することになります(所法25条<1>五、所令61<2>五、措法37条の10<4>五)。A社株式売却益(70,000円)のうち、みなし配当とされる部分の金額(50,000円)を除いた金額(70,000円-50,000円=20,000円)が譲渡所得の対象として取り扱われることになります。
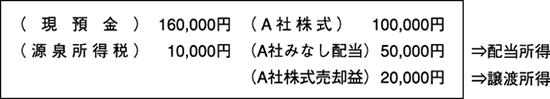
【3】 譲渡した法人株主Yの取扱い
上記の設例で、法人株主Y(A社株式の取得価額15万円)がA社株式を譲渡したものとして、法人株主Yの譲渡時の会計上・税務上の取扱いを検討してみましょう。
法人株主Yの会計仕訳は次のようになります。
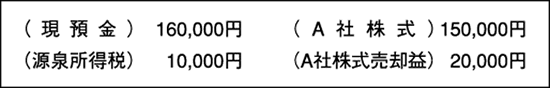
個人株主Xと同様に、法人株主Yは、税務上次のように、キャピタル・ロス及びみなし配当を認識することになります(法法24条<1>五、法令23<1>五、法法61条の2<1>)。A社株式売却益(20,000円)のうち、みなし配当とされる部分の金額(50,000円)を除いた金額(20,000円-50,000円=△30,000円)がキャピタル・ロスとなります。
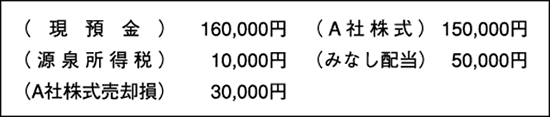
法人株主Yでは、税務上みなし配当に計上した金額(50,000円)について、受取配当等の益金不算入額計算の対象とすることができます(別表八の「配当等の収入金額の明細」に、通常の配当と別行で記入します。)。
みなし配当に係る源泉所得税(10,000円)は、所得税額控除の対象になります。みなし配当に係る源泉所得税は、所有期間あん分を要しません(別表六(一)の「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」に記入します。)。
自己株式(金庫株)の取得・保有・譲渡の解禁を受けて、会計上・税務上の取扱いが整備されてきました。非公開会社が自己株式を取得した場合の会計上・税務上の取扱いを今回で、消却・譲渡した場合の取扱いを次回以降にて解説します。
平成13年6月の商法改正において、自己株式(金庫株)の取得が解禁されました。また、平成14年4月1日からは、自己株式の処分(譲渡)が認められることになりました。商法上の自己株式の取得・保有・譲渡に対する制限が、原則的になくなったことから、会計及び税法は、自己株式の取扱いを新しく定めました。自己株式の取得・保有・譲渡の解禁は、多くの会社で実際に行われており、会計人はその会計処理・税務処理に迫られます。これまで明らかとなった自己株式の会計上と税務上の取扱いについて事例を中心に解説します。
I 自己株式を取得した場合
【1】 買い受け会社(A株式会社)での取扱い
設例のA株式会社(非公開会社)が自己の発行するA社株式を相対取引で取得した場合の会計上・税務上の取扱いを検討してみましょう。
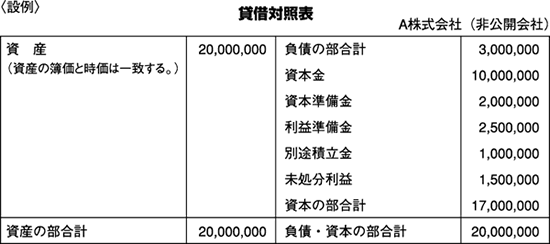
A株式会社の発行済株式数 200株
A株式会社はA社株式(自己株式)2株を対価170,000円(適正な時価)で取得しました。
(1)会計上の取扱い
企業会計基準委員会が公表した「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」では、「取得した自己株式は、取得原価をもって資本の部から控除する(第19項)。」とされています。したがって、「自己株式2株を170,000円で取得した」場合の会計上の仕訳は、次のようになります。
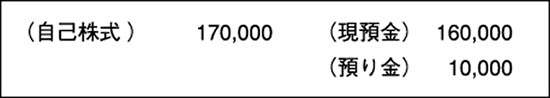
自己株式の取得原価は、170,000円となりますが、税務上の計算でみなし配当金(利益積立金相当額50,000円)が計上されることになるため、A株式会社は、みなし配当金に対する源泉徴収義務を負い、源泉所得税相当額(50,000円×20%=10,000円)の預り金を計上します。
A株式会社が自己株式を取得した会計期間での当期利益を200,000円とすると、当該会計期間末におけるA株式会社貸借対照表の資本の部の表示は次のようになります(会計期間の終了時まで自己株式を保有しつづけている場合)。
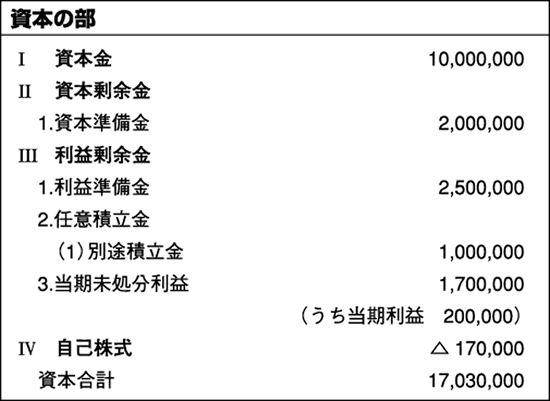
(2)税務上の取扱い
法人税法は、自己の株式の取得(証券取引所の開設する市場における購入による取得その他の政令で定める取得を除く。)について、株主に交付した金銭等の額が当該株式に対応する取得時の資本等の額を超える場合には、その超える金額を利益積立金額から控除することを規定しています(法法2条十八カ)。上記の自己株式の取得で、当該自己株式の資本等の金額を120,000円とすると、税務上の仕訳は、次のようになります。
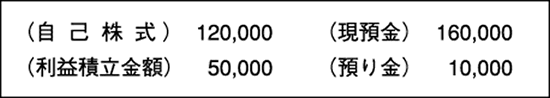
会計上で取得原価とされたものであっても、法人税法では、みなし配当(法法24条1五)となる部分の金額(50,000円)を利益積立金額から控除することが規定されています。これは、利益積立金額の計算に関する明細書(別表五(一))で調整されることになります。
一方、法人税法上は、所得の金額に関する明細書(別表四)での取扱いが規定されていません。所得金額の総額は変わりませんが、みなし配当として取り扱われる金額は、別表四上で社外流出したものとして処理され、同額の自己株式認定損(減算・留保)の計上により、別表四と利益積立金額の関係が維持されます(下記記載例のほか、みなし配当金額を別表四当期利益の社外流出・配当欄に記載する方法によっても同様の結果を導出します。)。
この結果、自己株式を取得したA株式会社の法人税別表の記載は、次のようになります。
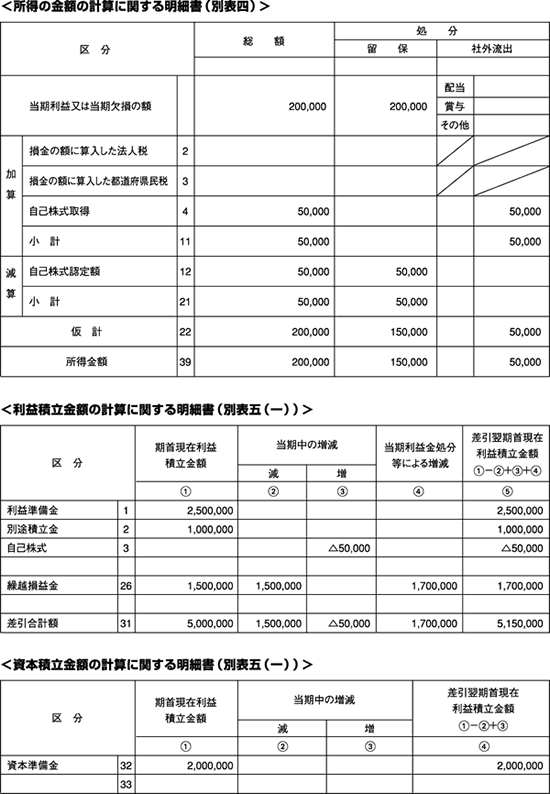
【2】 譲渡した個人株主Xの取扱い
上記の設例で、個人株主X(A社株式の取得価額10万円)がA社株式を譲渡したものとして、個人株主Xの課税上の取扱いを検討してみましょう。
個人株主Xは、次の仕訳のように考えているでしょう。
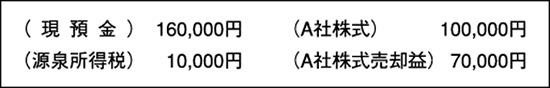
個人株主Xが、A社株式売却益を一本で認識しているとしても、税務上は、個人株主Xは、次のように配当所得と譲渡所得を区分して認識することになります(所法25条<1>五、所令61<2>五、措法37条の10<4>五)。A社株式売却益(70,000円)のうち、みなし配当とされる部分の金額(50,000円)を除いた金額(70,000円-50,000円=20,000円)が譲渡所得の対象として取り扱われることになります。
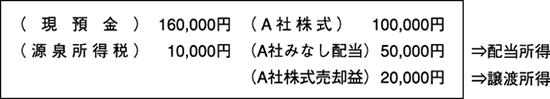
【3】 譲渡した法人株主Yの取扱い
上記の設例で、法人株主Y(A社株式の取得価額15万円)がA社株式を譲渡したものとして、法人株主Yの譲渡時の会計上・税務上の取扱いを検討してみましょう。
法人株主Yの会計仕訳は次のようになります。
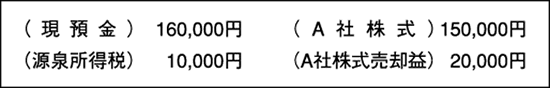
個人株主Xと同様に、法人株主Yは、税務上次のように、キャピタル・ロス及びみなし配当を認識することになります(法法24条<1>五、法令23<1>五、法法61条の2<1>)。A社株式売却益(20,000円)のうち、みなし配当とされる部分の金額(50,000円)を除いた金額(20,000円-50,000円=△30,000円)がキャピタル・ロスとなります。
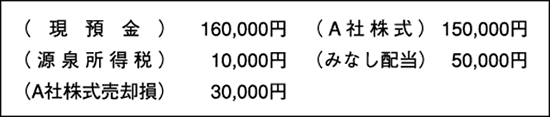
法人株主Yでは、税務上みなし配当に計上した金額(50,000円)について、受取配当等の益金不算入額計算の対象とすることができます(別表八の「配当等の収入金額の明細」に、通常の配当と別行で記入します。)。
みなし配当に係る源泉所得税(10,000円)は、所得税額控除の対象になります。みなし配当に係る源泉所得税は、所有期間あん分を要しません(別表六(一)の「その他に係る控除を受ける所得税額の明細」に記入します。)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















