解説記事2003年01月27日 【ニュース特集】 商法改正は10年間で10回以上!!ビジュアル会社法今昔比較 機関編(2003年1月27日号・№4)
商法改正は10年間で10回以上!!
ビジュアル会社法今昔比較
機関編
商法改正は平成5年改正(社外監査役や監査役会が導入された改正)から数えると、なんと10回以上の改正を経ています。改正は資金調達・企業再編のニーズへの対応やコーポレート・ガバナンス(企業統治)の徹底、IT対応等の観点から必要なものでしたが、度重なる改正で商法、特に会社法ならびに商法特例法は大きく変貌を遂げています。
そこで、T&Amasterでは「ビジュアル会社法今昔比較」をシリーズ化し、今回は「会社の機関」に絞って、10年前との比較をしてみることとしました。改めて、その変貌ぶりに驚かれることでしょう(なお、便宜上資本金5億円以上のいわゆる大会社を想定しています)。
昔 1993.4.1
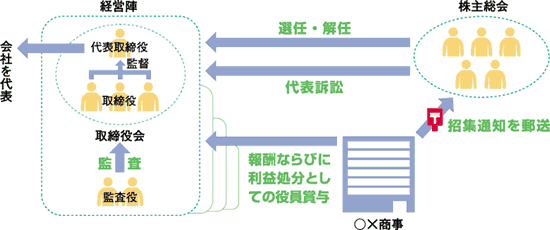
経営陣:取締役が取締役会を構成し、その取締役会が会社の重要事項を決定したり、代表取締役の代表権の行使をチェックします。取締役の報酬は原則として確定額ベース。
監査役は、大会社では2人以上(任期は2年)。社外監査役は義務付けられていませんでした。また、監査役会という制度も存在しませんでした。
取締役の責任:青天井。大和銀行事件第一審判決では総額約830億円の損害賠償判決が出され、話題になりました。
代表訴訟:賠償額に比例した提訴費用がかかりました。会社が訴えを提起すべきかどうか判断する期間(熟慮期間)は、株主の請求を受けた時から30日以内でした。会社が被告の取締役側に補助参加(いわば助太刀)できるか否かは争いがありました。
株主総会:招集通知は郵送で株主に送付されます。株主は株主総会に出席し、議決権行使を行います(もっとも委任状または書面投票制度は当時もありました)。
今 2003.4.1
従来型の企業統治制度(次ページ参照)に加えて、大会社及びみなし大会社は定款で定めることにより、委員会等設置会社制度を採用できます(14年改正:なお、「等」とは執行役を指します)。
経営陣:委員会等設置会社では、取締役会の中に指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設けます。各委員会はそれぞれ3人以上の取締役から構成され、かつ、その過半数が社外取締役かつ執行役でない者である必要があります。業務執行自体は執行役が行い、取締役会は監督に専念します。すなわち、執行と監督とを分離するアメリカ型の統治制度といえます。なお、監査委員会があるため、従来の監査役会・監査役制度を並存することができません。
委員会等設置会社の場合、取締役は執行役を兼ねることができますが、監査委員会の取締役(監査委員)は兼務できません。取締役・執行役の報酬は報酬委員会が決定します。そこで、株主総会においての利益処分の一環としての役員への金銭分配(役員賞与)ができなくなりました。その代わり、取締役の報酬は、例えば利益に一定率を乗じるといった業績連動型の報酬や金銭以外の報酬(自社製品、車、住宅等)もOKとなりました(14年改正)。
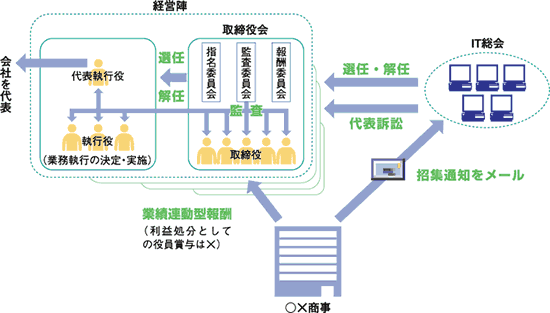
取締役の責任:取締役・執行役の法令又は定款に違反する行為(犯罪や重過失を除く)により会社が損害を受けても定款記載による取締役会決議または株主総会による決議により、責任を軽減することが可能となりました(13年改正)。責任は報酬4年分(代表取締役・代表執行役は6年分、社外取締役は2年分)を基礎とした額にまで軽減可能です。
代表訴訟:提訴費用は一律8,200円(5年改正)。熟慮期間は、株主の請求を受けた時から60日以内と伸長されました(13年改正)。監査役全員の同意があれば会社は被告取締役側に補助参加できると明文化し、手続面の立法的解決を図りました(13年改正)。
株主総会:株主の承諾があれば、電磁的方法(メール等)により、招集通知を送れるようになりました。電磁的方法による議決権行使も可能です。株主全員が電磁的方法により議案に賛成したのであれば株主総会自体省略可能です(以上、13年改正)。また、株主総会の特別決議の定足数を定款により「3分の1」まで緩和することも可能となりました(14年改正)。
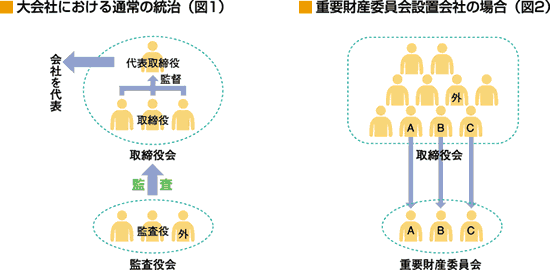
委員会等設置会社を採用予定の会社はまだ多くはありません。多くの会社が図1のような従来からの統治形態を取っています。なお、社外取締役は任意です。監査役は3人以上(任期は4年)で、監査役会を構成します。そのうち、1人以上は社外監査役です(*1)。また、委員会等設置会社以外でも業績連動型報酬や金銭以外の報酬は可能です(14年改正)。
重要財産委員会は、商法特例法上の大会社又はみなし大会社であれば、取締役会決議により採用することができる制度で、取締役3人以上で組織されます(14年改正)。ただし、取締役の数が10人以上であり、そのうちの1人以上が社外取締役であること、委員会等設置会社でないことが要件となっています。重要財産委員会設置会社では、今まで取締役会の専属的決議事項とされていた重要財産の処分及び譲受、多額の借財について、同委員会に決定させることができ、迅速かつ、機動的な経営が可能となります。
大会社以外だとどうなる?
それでは、大会社以外の場合、各制度はどのようになるのでしょうか。一覧にしてみました。
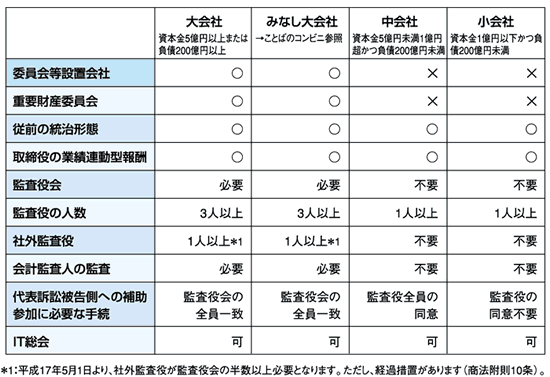
ビジュアル会社法今昔比較
機関編
商法改正は平成5年改正(社外監査役や監査役会が導入された改正)から数えると、なんと10回以上の改正を経ています。改正は資金調達・企業再編のニーズへの対応やコーポレート・ガバナンス(企業統治)の徹底、IT対応等の観点から必要なものでしたが、度重なる改正で商法、特に会社法ならびに商法特例法は大きく変貌を遂げています。
そこで、T&Amasterでは「ビジュアル会社法今昔比較」をシリーズ化し、今回は「会社の機関」に絞って、10年前との比較をしてみることとしました。改めて、その変貌ぶりに驚かれることでしょう(なお、便宜上資本金5億円以上のいわゆる大会社を想定しています)。
昔 1993.4.1
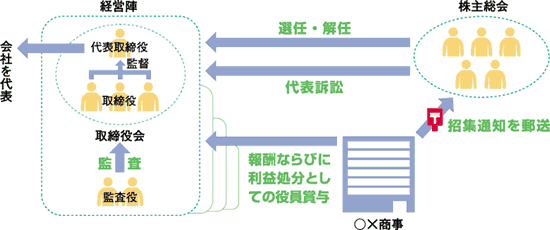
経営陣:取締役が取締役会を構成し、その取締役会が会社の重要事項を決定したり、代表取締役の代表権の行使をチェックします。取締役の報酬は原則として確定額ベース。
監査役は、大会社では2人以上(任期は2年)。社外監査役は義務付けられていませんでした。また、監査役会という制度も存在しませんでした。
取締役の責任:青天井。大和銀行事件第一審判決では総額約830億円の損害賠償判決が出され、話題になりました。
代表訴訟:賠償額に比例した提訴費用がかかりました。会社が訴えを提起すべきかどうか判断する期間(熟慮期間)は、株主の請求を受けた時から30日以内でした。会社が被告の取締役側に補助参加(いわば助太刀)できるか否かは争いがありました。
株主総会:招集通知は郵送で株主に送付されます。株主は株主総会に出席し、議決権行使を行います(もっとも委任状または書面投票制度は当時もありました)。
今 2003.4.1
従来型の企業統治制度(次ページ参照)に加えて、大会社及びみなし大会社は定款で定めることにより、委員会等設置会社制度を採用できます(14年改正:なお、「等」とは執行役を指します)。
経営陣:委員会等設置会社では、取締役会の中に指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設けます。各委員会はそれぞれ3人以上の取締役から構成され、かつ、その過半数が社外取締役かつ執行役でない者である必要があります。業務執行自体は執行役が行い、取締役会は監督に専念します。すなわち、執行と監督とを分離するアメリカ型の統治制度といえます。なお、監査委員会があるため、従来の監査役会・監査役制度を並存することができません。
委員会等設置会社の場合、取締役は執行役を兼ねることができますが、監査委員会の取締役(監査委員)は兼務できません。取締役・執行役の報酬は報酬委員会が決定します。そこで、株主総会においての利益処分の一環としての役員への金銭分配(役員賞与)ができなくなりました。その代わり、取締役の報酬は、例えば利益に一定率を乗じるといった業績連動型の報酬や金銭以外の報酬(自社製品、車、住宅等)もOKとなりました(14年改正)。
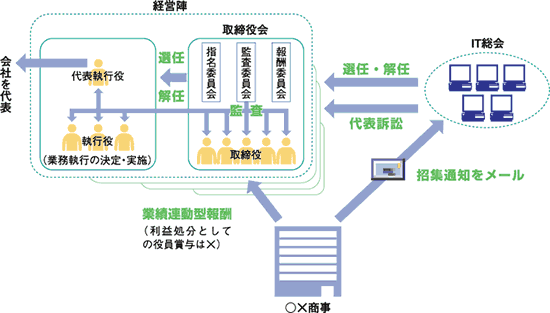
取締役の責任:取締役・執行役の法令又は定款に違反する行為(犯罪や重過失を除く)により会社が損害を受けても定款記載による取締役会決議または株主総会による決議により、責任を軽減することが可能となりました(13年改正)。責任は報酬4年分(代表取締役・代表執行役は6年分、社外取締役は2年分)を基礎とした額にまで軽減可能です。
代表訴訟:提訴費用は一律8,200円(5年改正)。熟慮期間は、株主の請求を受けた時から60日以内と伸長されました(13年改正)。監査役全員の同意があれば会社は被告取締役側に補助参加できると明文化し、手続面の立法的解決を図りました(13年改正)。
株主総会:株主の承諾があれば、電磁的方法(メール等)により、招集通知を送れるようになりました。電磁的方法による議決権行使も可能です。株主全員が電磁的方法により議案に賛成したのであれば株主総会自体省略可能です(以上、13年改正)。また、株主総会の特別決議の定足数を定款により「3分の1」まで緩和することも可能となりました(14年改正)。
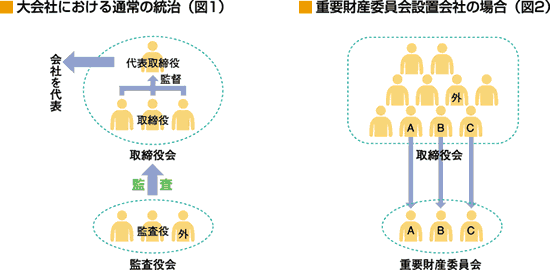
委員会等設置会社を採用予定の会社はまだ多くはありません。多くの会社が図1のような従来からの統治形態を取っています。なお、社外取締役は任意です。監査役は3人以上(任期は4年)で、監査役会を構成します。そのうち、1人以上は社外監査役です(*1)。また、委員会等設置会社以外でも業績連動型報酬や金銭以外の報酬は可能です(14年改正)。
重要財産委員会は、商法特例法上の大会社又はみなし大会社であれば、取締役会決議により採用することができる制度で、取締役3人以上で組織されます(14年改正)。ただし、取締役の数が10人以上であり、そのうちの1人以上が社外取締役であること、委員会等設置会社でないことが要件となっています。重要財産委員会設置会社では、今まで取締役会の専属的決議事項とされていた重要財産の処分及び譲受、多額の借財について、同委員会に決定させることができ、迅速かつ、機動的な経営が可能となります。
大会社以外だとどうなる?
それでは、大会社以外の場合、各制度はどのようになるのでしょうか。一覧にしてみました。
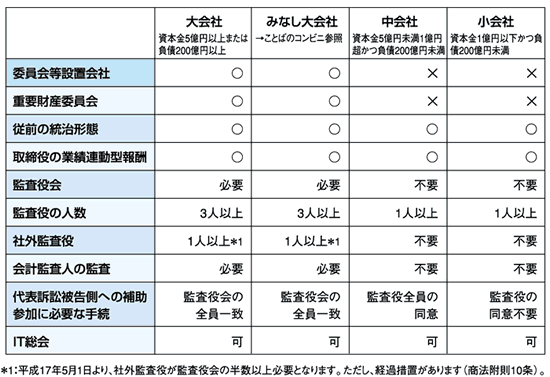
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















