解説記事2003年07月21日 【実務解説】 『経理財務版 業務マップ』の概要と活用方法について(2003年7月21日号・№028)
実務解説
『経理財務版 業務マップ』の概要と活用方法について
経済産業省商務情報政策局 サービス政策課 柿川恵介
1.はじめに
経済産業省では企業の経理財務部門の業務を網羅的・機能的に分類・整理した『経理財務版 業務マップ』を作成し、業務プロセスの見直しや組織・人員の再編成に必要な業務の適切な評価・棚卸し、業務に携わる人材の客観的スキル評価を支援する共通指標としてこのたび公表した。本稿では『業務マップ』の紹介と、その具体的な活用方法を提案したい。
2.『経理財務版 業務マップ』とは?
【企業の経理財務部門をめぐる動き】
厳しい事業環境の中で、企業の経理財務部門もより一層の効率化を迫られているが、四半期開示や連結納税、さらには導入に向けた議論が進行中の減損会計等の度重なる新制度導入に対して、各企業ともより迅速、かつ適切に対応することが求められている。
その一方で、近年では特に財務戦略の強化や管理会計の充実等、経営に直接関わるコア業務へのシフトの必要性も高まっており、その意味では経理財務部門は業務の効率化と高度化の同時達成という、非常に困難な課題に直面しているといえる。
さらに言えば、「コア業務へのシフト」と「プロセス系業務の外部化」という業務の「二極分化」がすでにかなりの程度進展しつつある、と見ることもできる。
特にプロセス系業務については、シェアードサービス化によるグループ経営の最適化、システム化や派遣人材の活用等による更なる効率化が図られており、さらに新しい動きとして、シェアードサービス会社がグループ内の顧客企業に対して提供するサービスに価格を付けてサービスメニューを作成することで、従来のコストセンターからプロフィットセンターへの転換を図ろうとする動きも見られる。
【業務棚卸しのツール】
このように、企業の経営環境や社会のニーズに応じて、経理財務部門の役割や機能の高度化、再編成を進めていくにあたっては、短期的なコスト削減のみを目的としてルーティン業務を単純に切り離すのではなく、長期的視野に立って経理財務部門が担うべき機能やミッションを明確にし、部門全般にわたる業務の適切な棚卸し・評価に基づく業務の再定義、最適な業務プロセスへの変更を図り、それに見合った新たな組織・人員の編成を行い、必要な経験・スキルを有する人材を迅速に獲得することが不可欠となる。
なお、これらの課題は必ずしも大手グループ企業のみに限定されるわけではない。中小・ベンチャー企業においても、企業規模の拡大や株式公開の準備にあたっては業務の洗い出しや戦略的な組織体制の整備が必要となってくるし、これらの業務を担う人材の獲得も重要な問題となる。また、会計制度変更に対応した業務実施体制の整備や間接コストの最小化は企業規模の大小にかかわらず共通の課題といえる。
とはいえ、自社の業務や人員を全て棚卸しし、最適な業務・組織体制を整備するということは大変な手間とコストがかかる作業であり、また、他社情報等の客観情報もなかなか入手しにくいのが現実である。
その意味で、企業間、業種間の共通指標となるものがあれば各企業における利用価値は高いと考えられる。
【人材スキル可視化のツール】
他方、上記のような組織・業務の動きは、これらの業務に従事する人材に求められる経験、スキルの高度化を促すことにも繋がる。企業が求める業務経験、スキルの獲得は、今後ますます人材の自立的努力によるところが大きくなってくると考えられるが、人材側にとっては、企業が経理財務職に求める業務経験・スキルが明らかになっていない場合も多く、自らのキャリアパス形成が困難なケースが多い。
したがって、求められるスキルを可視化する指標となるものがあれば、人材が自らの業務経験やスキルをマッピングすることが可能になり、自立的なキャリア形成、ひいては企業と人材間でのマッチング向上にも繋がることが考えられる。
本稿にてご紹介する『経理財務版 業務マップ』は、経理財務部門の業務全体を網羅的・機能的に分類整理したものであり、企業の業務プロセス変革や組織・人員体制の整備、人材スキル評価の容易化、キャリアパス形成の指標として活用することが可能である。
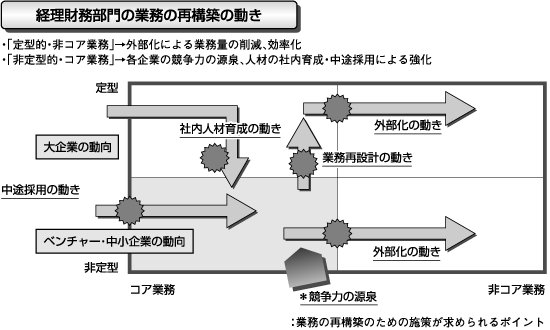
3.『業務マップ』の概要
【経理財務業務の世界地図】
『業務マップ』は、最も業務範囲が広いと想定される大手製造業の経理財務部門を想定して記述したものであり、これにより企業の同部門における業務の全体像の把握が可能な、いわば経理財務業務の「世界地図」として捉えることができる。
業務マップそのものは、全体の概略を俯瞰する「鳥瞰図」と、さらに詳細な情報を記載した「詳細図」の二本立てとしている。例えて言えば鳥瞰図で「大陸」を把握し、詳細版で「半島」や「都市名」を把握できるようになっている。
現実の企業の業務体系は企業規模、業種、さらに個々の企業によって当然異なるものではあるが、可能な限り幅広い業務をカバーすることで一定程度の汎用性を目指したものとなっている。例えば、大手企業では通常、人事部等で行われている給与計算や退職金の支払いといった業務も、中小企業では決算業務等と同様、管理部門で一括して行われているケースが多いことから、会計周辺業務と位置づけられるものについては本業務マップでカバーしている。
また、業務の体系を分かりやすくするために、業務の機能別に階層構造(大分類→中分類→グループ→モジュール)を用いて記述している。さらに、業務内容を分かりやすくするために、具体的な実務の構成要素(モジュール)に分解した記述にしている。この業務マップに特徴的なことは、モジュール単位の区切り方について、担当する人単位で区切るのではなく、業務のひとかたまりのプロセス毎に区切った点である。これにより、一人あたりの業務が細分化された大手企業にとっても、一人あたりのカバーする業務範囲が幅広い中小企業にとっても、各業務の認識が可能となるようにしている。
加えて各モジュールでのコミュニケーション相手、一般的な担当者像等の参考情報を付記することで、業務の性格、各企業における標準的な業務実施体制をイメージしやすくしている。
OperatingMap18_19.PDF
4.『業務マップ』の活用方法
この業務マップは必要に応じてカスタマイズすることで、様々な用途に活用することが可能と考えられる。以下では、このうち企業にとって特に利用価値が高いと考えられるものについて提案したい。
【活用方法1】
業務プロセスの見直し、組織・人員の整備・見直し
この業務マップを活用することで、業務プロセス見直しの効果試算の容易化を図ることができる。例えば、会計システム再構築による業務の効率化を行う際には、業務マップに基づき現行の業務量把握を行い、ワークフローの導入や上流アプリケーションとのデータ接続等による効率化効果をグループやモジュールごとに試算することが考えられる。
また、シェアードサービス化やアウトソーシング化の対象業務を検討する参考情報としても活用できる。例えば現行の投入工数、利用システム、業務の社内での分散度合い、経理財務部門内での完結性といった特性を業務マップに付加することで、シェアードサービス化に適した業務の分析が可能となる。また、業務マップに基づき事前に業務の役割分担を細かいレベルで明確にしておくことで、混乱なく業務を移行することができる。
他方、中小・ベンチャー企業が株式公開の準備段階等において業務・組織体制の確立を検討する際には、業務マップの体系を用いて業務の洗い出しや今後付加すべき組織機能の検討を行うことができる。
【活用方法2】
シェアードサービス会社等のサービスメニュー作成
シェアードサービスを提供する企業が、例えば、半期毎の契約更改時に、提供するサービスのメニューと価格、品質について業務マップを用いてユーザーに明示することにより、サービス内容に対するユーザーの理解を深め、契約更改時には、各サービスの満足度や重要度を確認してニーズに合ったサービスメニューやサービスレベルについて具体的な議論を行うことが可能となる。
また、アウトソーシング受託会社が、業務マップに基づくサービスメニューにおいて、自社で対応可能な業種、会計処理、会計システムを明確にし、サービスレベルや責任範囲も明確にすることで、引き合いから受注に至るまでの営業プロセスを効率化することができる。
【活用方法3】
社内職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)、スキル標準、目標管理制度の整備・見直し
業務マップを活用することで、職務記述書(いわゆるジョブ・ディスクリプション)の作成が容易となる。また、現在職務記述書を有している企業においても、業務マップの客観情報を基に改訂が容易になる。
また、部門内の業務目標設定と評価の具体化にも資すると考えられる。例えば、半期毎の目標設定と成果確認に業務マップを活用することで、担当者は、業務マップの体系を用いて、上司と相談しながら半期毎の到達目標を設定し、期末には、この目標設定内容に沿って成果を確認することが可能となる。上司にとっては部下の業務内容や希望が把握しやすくなり、従来よりも有効なOJTやコーチングを行うことができるようになるし、担当者にとっても目標設定が行いやすくなることで、評価への納得度や満足度も向上するものと考えられる。
さらに、職務給制度の導入を検討する企業においては、経理財務部門の職務ポイントの算出に業務マップを活用することができ、業務マップで表現された業務の体系を活用することで、ポイント算出に必要な評価軸のパラメーターを設定することができ、経理財務部門へのヒアリングの負担を軽減することができる。
【活用方法4】
人材スキルの客観評価(採用効率化、個人の自己スキル把握)
新規人材を獲得したい企業にとっては、例えば中途採用等のエントリーシートのチェック項目に業務マップを活用することができる。これにより採用候補者の有する業務経験、スキル等の把握が容易になり、面接の効率化、人材ミスマッチのリスク軽減を図ることができる。
また、社内ジョブローテーションを行う際にも、あらかじめ各社員の経験業務や保有スキルを業務マップ上で位置付けておくことにより、適材適所に応じた人材配置、計画的な社内人材育成を行うことができる。
その他、人材派遣/紹介会社の場合は、業務マップの体系を用いて登録人材の業務経験、スキルを管理することにより、企業から引き合いがあった場合に、人材ニーズを的確に把握し、人材DBを照会することで、迅速に提案・回答を行うことも考えられる。さらに、派遣社員が対応する業務の広がりや高度化の把握が容易となり、ニーズにあった人材の育成を効率的に行うことができる。ひいては、企業に対して、派遣人材を活用した業務プロセス改善の提案を行うことも考えられる。
一方、人材にとっては、自らの有する業務経験やスキルの棚卸し、自己評価を行う指標になる。これにより、例えば今後、自ら獲得していくべき業務経験やスキル、自らの市場価値を客観的に把握し、企業が求める業務経験やスキルの獲得、自立的なキャリアパスの形成を図ることができる。
また、転職の際に、業務マップを用いて自らが対応できる業務、チャレンジしたい業務を示し、自己アピールするツールにもなりうる。
最も重要なことは、企業側が求める経験・スキルと、人材が有する経験・スキルについて、共通の指標に基づき摺り合わせを行うことが可能となるという点である。
5.今後の取り組み
以上、紹介してきたように、この業務マップを活用することにより、企業の業務プロセス変革や必要な人材の獲得等を通じて、これまで管理部門の一部であった経理財務部門がその付加価値を高め、企業の競争力強化の重要なプレーヤーとしての役割を果たすことに繋がるとともに、人材が自立的なキャリア形成を達成することで企業、人材双方のベストマッチングが可能となることを期待するものである。
本来であれば、今回の業務マップ作成にあたって、さらに現実の業務のフローに沿った再編成や、業務プロセス変革の検討等に有用な業務情報、各業務遂行に必要な実務経験や知識等のスキル情報を付加したいところであったが、作成期間の関係上、残念ながらそこまで至らなかった。
そのため、このような情報を付加しつつ今後さらなるバージョンアップを図り、オープンソースとして公開することで、引き続き各社の取り組みを支援していきたいと考えている。
6.業務マップの入手方法
本稿でご紹介した『業務マップ』は以下のウェブアドレスから無料でダウンロードすることができる。
(経済産業省ホームページ)
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003982/
また、マップ本体はMSエクセル形式で作成しており、用途に応じて自由にカスタマイズが可能となっているので、是非ご活用いただければ幸甚である。
『経理財務版 業務マップ』の概要と活用方法について
経済産業省商務情報政策局 サービス政策課 柿川恵介
1.はじめに
経済産業省では企業の経理財務部門の業務を網羅的・機能的に分類・整理した『経理財務版 業務マップ』を作成し、業務プロセスの見直しや組織・人員の再編成に必要な業務の適切な評価・棚卸し、業務に携わる人材の客観的スキル評価を支援する共通指標としてこのたび公表した。本稿では『業務マップ』の紹介と、その具体的な活用方法を提案したい。
2.『経理財務版 業務マップ』とは?
【企業の経理財務部門をめぐる動き】
厳しい事業環境の中で、企業の経理財務部門もより一層の効率化を迫られているが、四半期開示や連結納税、さらには導入に向けた議論が進行中の減損会計等の度重なる新制度導入に対して、各企業ともより迅速、かつ適切に対応することが求められている。
その一方で、近年では特に財務戦略の強化や管理会計の充実等、経営に直接関わるコア業務へのシフトの必要性も高まっており、その意味では経理財務部門は業務の効率化と高度化の同時達成という、非常に困難な課題に直面しているといえる。
さらに言えば、「コア業務へのシフト」と「プロセス系業務の外部化」という業務の「二極分化」がすでにかなりの程度進展しつつある、と見ることもできる。
特にプロセス系業務については、シェアードサービス化によるグループ経営の最適化、システム化や派遣人材の活用等による更なる効率化が図られており、さらに新しい動きとして、シェアードサービス会社がグループ内の顧客企業に対して提供するサービスに価格を付けてサービスメニューを作成することで、従来のコストセンターからプロフィットセンターへの転換を図ろうとする動きも見られる。
【業務棚卸しのツール】
このように、企業の経営環境や社会のニーズに応じて、経理財務部門の役割や機能の高度化、再編成を進めていくにあたっては、短期的なコスト削減のみを目的としてルーティン業務を単純に切り離すのではなく、長期的視野に立って経理財務部門が担うべき機能やミッションを明確にし、部門全般にわたる業務の適切な棚卸し・評価に基づく業務の再定義、最適な業務プロセスへの変更を図り、それに見合った新たな組織・人員の編成を行い、必要な経験・スキルを有する人材を迅速に獲得することが不可欠となる。
なお、これらの課題は必ずしも大手グループ企業のみに限定されるわけではない。中小・ベンチャー企業においても、企業規模の拡大や株式公開の準備にあたっては業務の洗い出しや戦略的な組織体制の整備が必要となってくるし、これらの業務を担う人材の獲得も重要な問題となる。また、会計制度変更に対応した業務実施体制の整備や間接コストの最小化は企業規模の大小にかかわらず共通の課題といえる。
とはいえ、自社の業務や人員を全て棚卸しし、最適な業務・組織体制を整備するということは大変な手間とコストがかかる作業であり、また、他社情報等の客観情報もなかなか入手しにくいのが現実である。
その意味で、企業間、業種間の共通指標となるものがあれば各企業における利用価値は高いと考えられる。
【人材スキル可視化のツール】
他方、上記のような組織・業務の動きは、これらの業務に従事する人材に求められる経験、スキルの高度化を促すことにも繋がる。企業が求める業務経験、スキルの獲得は、今後ますます人材の自立的努力によるところが大きくなってくると考えられるが、人材側にとっては、企業が経理財務職に求める業務経験・スキルが明らかになっていない場合も多く、自らのキャリアパス形成が困難なケースが多い。
したがって、求められるスキルを可視化する指標となるものがあれば、人材が自らの業務経験やスキルをマッピングすることが可能になり、自立的なキャリア形成、ひいては企業と人材間でのマッチング向上にも繋がることが考えられる。
本稿にてご紹介する『経理財務版 業務マップ』は、経理財務部門の業務全体を網羅的・機能的に分類整理したものであり、企業の業務プロセス変革や組織・人員体制の整備、人材スキル評価の容易化、キャリアパス形成の指標として活用することが可能である。
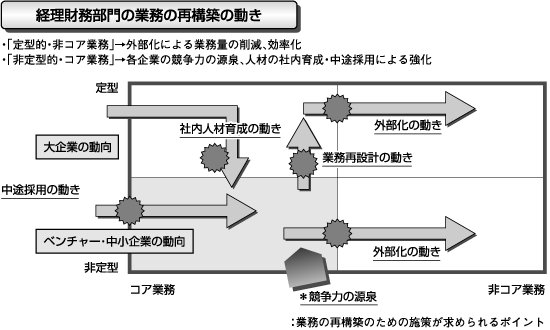
3.『業務マップ』の概要
【経理財務業務の世界地図】
『業務マップ』は、最も業務範囲が広いと想定される大手製造業の経理財務部門を想定して記述したものであり、これにより企業の同部門における業務の全体像の把握が可能な、いわば経理財務業務の「世界地図」として捉えることができる。
業務マップそのものは、全体の概略を俯瞰する「鳥瞰図」と、さらに詳細な情報を記載した「詳細図」の二本立てとしている。例えて言えば鳥瞰図で「大陸」を把握し、詳細版で「半島」や「都市名」を把握できるようになっている。
現実の企業の業務体系は企業規模、業種、さらに個々の企業によって当然異なるものではあるが、可能な限り幅広い業務をカバーすることで一定程度の汎用性を目指したものとなっている。例えば、大手企業では通常、人事部等で行われている給与計算や退職金の支払いといった業務も、中小企業では決算業務等と同様、管理部門で一括して行われているケースが多いことから、会計周辺業務と位置づけられるものについては本業務マップでカバーしている。
また、業務の体系を分かりやすくするために、業務の機能別に階層構造(大分類→中分類→グループ→モジュール)を用いて記述している。さらに、業務内容を分かりやすくするために、具体的な実務の構成要素(モジュール)に分解した記述にしている。この業務マップに特徴的なことは、モジュール単位の区切り方について、担当する人単位で区切るのではなく、業務のひとかたまりのプロセス毎に区切った点である。これにより、一人あたりの業務が細分化された大手企業にとっても、一人あたりのカバーする業務範囲が幅広い中小企業にとっても、各業務の認識が可能となるようにしている。
加えて各モジュールでのコミュニケーション相手、一般的な担当者像等の参考情報を付記することで、業務の性格、各企業における標準的な業務実施体制をイメージしやすくしている。
(業務マップの仕様)
| ||||||||||||||||||||
OperatingMap18_19.PDF
4.『業務マップ』の活用方法
この業務マップは必要に応じてカスタマイズすることで、様々な用途に活用することが可能と考えられる。以下では、このうち企業にとって特に利用価値が高いと考えられるものについて提案したい。
【活用方法1】
業務プロセスの見直し、組織・人員の整備・見直し
この業務マップを活用することで、業務プロセス見直しの効果試算の容易化を図ることができる。例えば、会計システム再構築による業務の効率化を行う際には、業務マップに基づき現行の業務量把握を行い、ワークフローの導入や上流アプリケーションとのデータ接続等による効率化効果をグループやモジュールごとに試算することが考えられる。
また、シェアードサービス化やアウトソーシング化の対象業務を検討する参考情報としても活用できる。例えば現行の投入工数、利用システム、業務の社内での分散度合い、経理財務部門内での完結性といった特性を業務マップに付加することで、シェアードサービス化に適した業務の分析が可能となる。また、業務マップに基づき事前に業務の役割分担を細かいレベルで明確にしておくことで、混乱なく業務を移行することができる。
他方、中小・ベンチャー企業が株式公開の準備段階等において業務・組織体制の確立を検討する際には、業務マップの体系を用いて業務の洗い出しや今後付加すべき組織機能の検討を行うことができる。
【活用方法2】
シェアードサービス会社等のサービスメニュー作成
シェアードサービスを提供する企業が、例えば、半期毎の契約更改時に、提供するサービスのメニューと価格、品質について業務マップを用いてユーザーに明示することにより、サービス内容に対するユーザーの理解を深め、契約更改時には、各サービスの満足度や重要度を確認してニーズに合ったサービスメニューやサービスレベルについて具体的な議論を行うことが可能となる。
また、アウトソーシング受託会社が、業務マップに基づくサービスメニューにおいて、自社で対応可能な業種、会計処理、会計システムを明確にし、サービスレベルや責任範囲も明確にすることで、引き合いから受注に至るまでの営業プロセスを効率化することができる。
【活用方法3】
社内職務記述書(ジョブ・ディスクリプション)、スキル標準、目標管理制度の整備・見直し
業務マップを活用することで、職務記述書(いわゆるジョブ・ディスクリプション)の作成が容易となる。また、現在職務記述書を有している企業においても、業務マップの客観情報を基に改訂が容易になる。
また、部門内の業務目標設定と評価の具体化にも資すると考えられる。例えば、半期毎の目標設定と成果確認に業務マップを活用することで、担当者は、業務マップの体系を用いて、上司と相談しながら半期毎の到達目標を設定し、期末には、この目標設定内容に沿って成果を確認することが可能となる。上司にとっては部下の業務内容や希望が把握しやすくなり、従来よりも有効なOJTやコーチングを行うことができるようになるし、担当者にとっても目標設定が行いやすくなることで、評価への納得度や満足度も向上するものと考えられる。
さらに、職務給制度の導入を検討する企業においては、経理財務部門の職務ポイントの算出に業務マップを活用することができ、業務マップで表現された業務の体系を活用することで、ポイント算出に必要な評価軸のパラメーターを設定することができ、経理財務部門へのヒアリングの負担を軽減することができる。
【活用方法4】
人材スキルの客観評価(採用効率化、個人の自己スキル把握)
新規人材を獲得したい企業にとっては、例えば中途採用等のエントリーシートのチェック項目に業務マップを活用することができる。これにより採用候補者の有する業務経験、スキル等の把握が容易になり、面接の効率化、人材ミスマッチのリスク軽減を図ることができる。
また、社内ジョブローテーションを行う際にも、あらかじめ各社員の経験業務や保有スキルを業務マップ上で位置付けておくことにより、適材適所に応じた人材配置、計画的な社内人材育成を行うことができる。
その他、人材派遣/紹介会社の場合は、業務マップの体系を用いて登録人材の業務経験、スキルを管理することにより、企業から引き合いがあった場合に、人材ニーズを的確に把握し、人材DBを照会することで、迅速に提案・回答を行うことも考えられる。さらに、派遣社員が対応する業務の広がりや高度化の把握が容易となり、ニーズにあった人材の育成を効率的に行うことができる。ひいては、企業に対して、派遣人材を活用した業務プロセス改善の提案を行うことも考えられる。
一方、人材にとっては、自らの有する業務経験やスキルの棚卸し、自己評価を行う指標になる。これにより、例えば今後、自ら獲得していくべき業務経験やスキル、自らの市場価値を客観的に把握し、企業が求める業務経験やスキルの獲得、自立的なキャリアパスの形成を図ることができる。
また、転職の際に、業務マップを用いて自らが対応できる業務、チャレンジしたい業務を示し、自己アピールするツールにもなりうる。
最も重要なことは、企業側が求める経験・スキルと、人材が有する経験・スキルについて、共通の指標に基づき摺り合わせを行うことが可能となるという点である。
5.今後の取り組み
以上、紹介してきたように、この業務マップを活用することにより、企業の業務プロセス変革や必要な人材の獲得等を通じて、これまで管理部門の一部であった経理財務部門がその付加価値を高め、企業の競争力強化の重要なプレーヤーとしての役割を果たすことに繋がるとともに、人材が自立的なキャリア形成を達成することで企業、人材双方のベストマッチングが可能となることを期待するものである。
本来であれば、今回の業務マップ作成にあたって、さらに現実の業務のフローに沿った再編成や、業務プロセス変革の検討等に有用な業務情報、各業務遂行に必要な実務経験や知識等のスキル情報を付加したいところであったが、作成期間の関係上、残念ながらそこまで至らなかった。
そのため、このような情報を付加しつつ今後さらなるバージョンアップを図り、オープンソースとして公開することで、引き続き各社の取り組みを支援していきたいと考えている。
6.業務マップの入手方法
本稿でご紹介した『業務マップ』は以下のウェブアドレスから無料でダウンロードすることができる。
(経済産業省ホームページ)
http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0003982/
また、マップ本体はMSエクセル形式で作成しており、用途に応じて自由にカスタマイズが可能となっているので、是非ご活用いただければ幸甚である。
| ○ 本件に関するお問い合わせ先 経済産業省商務情報政策局サービス政策課 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 TEL 03-3580-3922 FAX 03-3501-6613 kakigawa-keisuke@meti.go.jp |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















