解説記事2003年12月08日 【会計実務解説】 企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の解説(2003年12月 8日号・№046)
実務解説
企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の解説
企業会計基準委員会 研究員 山中成大
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会は、平成15年10月31日に企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「適用指針」という。)を公表した。本稿では、適用指針の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ 適用に関する留意点
減損処理は、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなったという通常の状態とは異なる事態において、例外的に経営者の見込みなどの内部的な情報に基づき、将来に損失を繰り延べないよう回収可能性を反映させるように帳簿価額を臨時的に減額する会計処理と考えられる。
このため、そもそも具体的な判断を一律に示すことは困難な場合が多いが、その中で、適用指針は、減損の兆候をはじめとして、必要と考えられる範囲において一定の目安や例示を示している。企業は、減損会計基準及び適用指針の定めに従って減損処理を行うものとされるが、これらに定めがないため状況に応じ個々の実態を考慮して適用する場合には、減損会計基準及び適用指針の趣旨を適切に斟酌する必要がある(2項)。
Ⅲ 資産のグルーピング
1 資産のグルーピングの必要性
減損処理の3つステップ([図表1])に際して、複数の資産が一体となって独立したキャッシュ・フローを生み出す場合には、資産のグルーピングを行うこととなる。
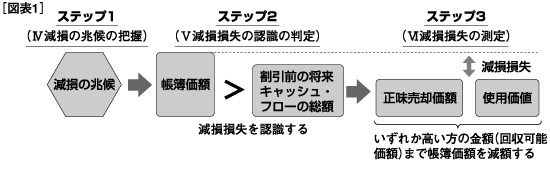
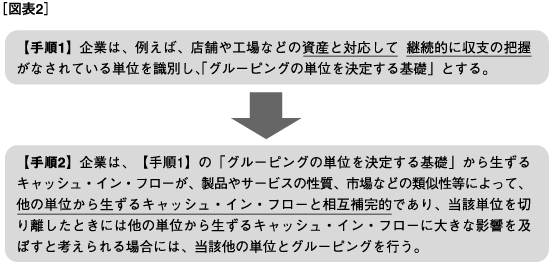
2 資産のグルーピングの手順の例示
減損会計基準において、資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行うこととされており、実務的には、管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の単位等を考慮してグルーピングの方法を定めることになると考えられている。
適用指針では、まず、[図表2]のように、資産のグルーピングを行う手順を例示することにより、実務的な指針として役立てることを考えている(7項、[設例1])。
(1)手順1
一般に、管理会計上の区分は、事業別、製品別、地域別などの区分を基礎にして行われていると考えられるが、継続的に収支の把握がなされている単位は、予算や業績評価の区分より小さい場合もある。また、ここでいう「収支」は、必ずしも企業の外部との間で直接的にキャッシュ・フローが生じている必要はなく、また、発生基準に基づく損益の把握でもよい。
次に、「資産と対応して」とあるように、減損会計は固定資産を対象とするため、原則として、これを細分化せず、例えば、店舗や工場などの物理的な1つの資産において継続的に収支の把握がなされている単位が「グルーピングの単位を決定する基礎」になる。
なお、事業の特性により、継続的な収支が事業を行っている大きさでしか把握されていないこともあると考えられる。すなわち、事業の種類や業態によっては、当該資産から生ずるキャッシュ・イン・フローが他の資産から生ずるキャッシュ・イン・フローと相互補完的であるため、管理会計上も合理的な内部振替価格を用いて収入の把握を行うことが困難な場合があり、また、当該資産に関わるキャッシュ・イン・フローに見積もり要素が極めて多いため、管理会計上、資産ごと又は複数の資産をまとめた単位では継続的な収支の把握に意義を見出せない場合がある。検討過程において、前者については例えば一部の電力事業において、後者については例えば一部の保険事業において、このようなケースに該当する場合があるとの認識が示されたが、これらの判断は企業の実態によるので、上述した業種の企業がすべて該当するわけではなく、また、他の業種の企業では該当しないということではないと考えられる。いずれにしろ、このようなケースは管理会計上の目的や効果から合理性を有するものに限られることに留意する必要がある(70項(1))。
(2)手順2
手順1で識別された「グルーピングの単位を決定する基礎」のうち、それぞれのキャッシュ・イン・フローが相互補完的であり、それぞれの単位を切り離したときには、他の単位から生ずるキャッシュ・イン・フローに大きな影響を及ぼす場合には、他の単位とグルーピングを行うことになる。
なお、稀ではあるが、法規制によって企業に製品やサービスの供給義務があり、このため、販売価格の認可制や広い安全義務、また拡張撤退が自由にできないような場合には、供給義務が課されている資産又は複数の資産は、当該資産から生ずるキャッシュ・イン・フローには相互補完的な影響があることに該当すると考えられる(70項(2))。検討の過程では、例えば一部の鉄道事業においてこのようなケースにあたる場合があるとの認識が示されたが、これらの判断についても企業の実態によるので、このような業種の企業がすべて該当するわけではなく、また、他の業種の企業では該当しないということではないと考えられる。
3 処分が決定された資産及び廃止が決定された事業に係る資産
取締役会等において、資産の処分や事業の廃止に関する意思決定を行い、その代替的な投資も予定されていない場合には、これらに係る資産を切り離しても他の資産又は資産グループの使用にほとんど影響を与えない場合があり、このようなケースに該当する資産のうち重要なものは、独立した資産グループとして取り扱うことになる(8項前段)。
4 将来の使用が見込まれていない遊休資産
遊休状態とは、企業活動にほとんど使用されていない状態であって、過去の利用実態や将来の用途の定めには関係がない現在の状態であり、このような状態にある資産が遊休資産である(72項)。「将来の使用が見込まれていない遊休資産」は、上記3と同様に、通常、当該遊休資産を切り離しても他の資産又は資産グループの使用にほとんど影響を与えないと考えられるため、重要なものについては、独立した資産グループとして取り扱う。また、企業が「将来の使用を見込んでいる遊休資産」は、その見込みに沿って、グルーピングを行うことになる(8項後段)。
Ⅳ 減損の兆候
減損の兆候とは、資産又は資産グループに減損が生じている可能性を示す事象をいい、その程度は必ずしも画一的に数値化できるものではなく、厳格に定められるものではないが、一定の目安を設けることも実務上の指針として役立つ側面もあることから、適用指針では、必要と考えられる範囲において、その目安を示している(77項)。企業は、通常の企業活動において実務的に入手可能なタイミングにおいて利用可能な情報に基づき、以下のような減損の兆候がある資産又は資産グループを識別する(11項)。
1 営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスの場合
(1)「営業活動から生じる損益」について
「営業活動から生ずる損益」には、当該資産又は資産グループの減価償却費や、本社費等の間接的に生ずる費用、損益計算書上は原価性を有しないものとして営業損益に含まれていない項目でも営業上の取引に関連して生じた損益(例えば、たな卸資産の評価損)であれば含まれる。ただし、支払利息など財務活動から生ずる損益や利益に関連する金額を課税標準とする税金については、営業活動から生ずる損益に含まれず、また、大規模な経営改善計画等により生じた一時的な損益も含まれない。実務上、営業活動から生ずる損益は、このような考え方を反映した管理会計上の損益区分に基づいて行われるものと考えられる(12項(1))。
(2)「継続してマイナス」及び「継続してマイナスとなる見込み」について
「継続してマイナス」とは、おおむね過去2期がマイナスであったことを指すが、当期の見込みが明らかにプラスとなる場合は、兆候としての意義が薄いことから、該当しないと考えられる。また、「継続してマイナスとなる見込み」とは、前期と当期以降の見込みが明らかにマイナスとなる場合を指す(12項(2))。
なお、事業の立上げ時など予め合理的な事業計画(当該計画の中で投資額以上のキャッシュ・フローを生み出すことが実行可能なもの)が策定されており、当該計画にて当初より継続してマイナスとなることが予定されている場合、実際のマイナスの額が当該計画にて予定されていたマイナスの額よりも著しく下方に乖離していないときには、減損の兆候には該当しない(12項(4))。
2 使用範囲又は方法について回収可能額を著しく低下させる変化がある場合
資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、例えば、以下の①から⑦のような当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、又は、生ずる見込みである場合には、減損の兆候となる(13項)。
なお、資産グループについては、資産グループ全体について以下の①から⑦のような変化が生じたか、又は、生ずる見込みである場合のみならず、主要な資産が使用されている範囲又は方法について、以下の①から⑦のような変化が生じたか、又は、生ずる見込みである場合も含まれる(13項なお書き)。
① 資産又は資産グループが使用されている事業を廃止又は再編成すること
② 当初の予定よりも著しく早期に資産又は資産グループを処分すること
③ 資産又は資産グループを異なる用途に転用すること
④ 資産又は資産グループが遊休状態になり、将来の用途が定まっていないこと
⑤ 資産又は資産グループの稼働率が著しく低下した状態が続いており、著しく低下した稼働率が回復する見込みがないこと
⑥ 資産又は資産グループに著しい陳腐化等の機能的減価が観察できること
⑦ 建設仮勘定に係る建設について、計画の中止又は大幅な延期が決定されたことや当初の計画に比べ著しく滞っていること
3 経営環境の著しい悪化の場合
経営環境の著しい悪化は、個々の企業において大きく異なるため、適用指針では、①市場環境の著しい悪化、②技術的環境の著しい悪化、③法律的環境の著しい悪化の例示を示すにとどめている(14項)。
4 市場価額の著しい下落の場合
「市場価格が著しく下落したこと」には、少なくとも市場価格が帳簿価額から50%程度以上下落した場合が該当する(15項)。ただし、50%程度以上下落していない場合でも、例えば、処分が予定されている資産で、市場価格の下落により、減損が生じている可能性が高いと見込まれるときのように、状況に応じ個々の企業において判断することが必要なときがある(89項ただし書き)。
また、固定資産については、市場価格が観察可能な場合は多くないため、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標が容易に入手できる場合(容易に入手できる評価額や指標を合理的に調整したものも含まれる。)には、これらを、減損の兆候を把握するための市場価格とみなして使用する(15項また書き)。
なお、資産グループについては、資産グループ全体の市場価格が把握できない場合でも、①資産グループの主要な資産の市場価格が著しく下落した場合や、②(土地が主要な資産ではなくとも)資産グループの帳簿価額のうち土地の帳簿価額が大きな割合を占め、当該土地の市場価格が著しく下落した場合も含まれる(15項なお書き)。
5 共用資産やのれんの減損の兆候
共用資産については、共用資産を含むより大きな単位について、上記1から4における事象がある場合、または、共用資産そのものについて、上記2又は4における事象がある場合、減損の兆候があることになる(16項)。
のれんについては、のれんを含むより大きな単位について、上記1から4における事象がある場合、減損の兆候があることになる(17項)。
Ⅴ 減損損失の認識の判定
減損会計基準では、減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識することとしている。この際、割引前将来キャッシュ・フローを見積る期間は、資産又は資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数と20年のいずれか短い方とされている(96項)。
1 経済的残存使用年数
資産又は資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数は、当該資産が今後、経済的に使用可能と予測される年数と考えられる。なお、経済的残存使用年数が、当該資産の減価償却計算に用いられている税法耐用年数等に基づく残存耐用年数と著しい相違がある等の不合理と認められる事情のない限り、当該残存耐用年数を経済的残存使用年数とみなすことができる(21項)。
2 主要な資産
資産グループ中の主要な資産は、資産のグルーピングを行う際に決定され、当期に主要な資産とされた資産は、原則として、翌期以降の会計期間においても当該資産グループの主要な資産となる(22項)。なお、土地等の非償却資産や建物等の経済的残存使用年数が20年を超える資産も主要な資産とすることができるが、その場合にも、当該資産が資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産であるかどうかに留意する必要がある(23項)。
また、共用資産やのれんは、原則として、主要な資産には該当しない(24項)。
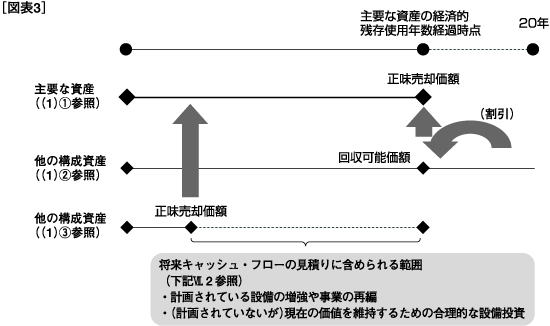
3 割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積り
(1)資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数が20年を超えない場合(97項)
この場合、以下を当該主要な資産の経済的残存使用年数までの割引前将来キャッシュ・フローに加算する(18項、[設例2](ケース1))。
① 主要な資産の経済的残存使用年数経過時点における主要な資産の正味売却価額
② 主要な資産以外の構成資産の経済的残存使用年数が、主要な資産の経済的残存使用年数を超える場合には、当該主要な資産の経済的残存使用年数経過時点における当該他の構成資産の回収可能価額(下記Ⅵ3(2)②参照)
③ 主要な資産以外の構成資産の経済的残存使用年数が、主要な資産の経済的残存使用年数を超えない場合には、当該他の構成資産の経済的残存使用年数経過時点における当該構成資産の正味売却価額
なお、これらのイメージ図は[図表3]のとおりである(横軸は経済的残存使用年数、矢印は割引前将来キャッシュ・フローに加算する金額を示す。)。
(2)資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数が20年を超える場合(98項)
この場合には、20年経過時点の回収可能価額を20年目までの割引前将来キャッシュ・フローに加算する(18項(2)、[設例2](ケース2))。資産グループ中の主要な資産以外の構成資産の経済的残存使用年数が20年を超えない場合には、当該構成資産の経済的残存使用年数経過時点における当該構成資産の正味売却価額を主要な資産の経済的残存使用年数までの割引前将来キャッシュ・フローに加算し(18項(3))、20年を超える場合、以下を21年目以降に見込まれる将来キャッシュ・フローに加算し、20年経過時点の回収可能価額に含める(18項(4))。
・当該構成資産の経済的残存使用年数が、主要な資産の経済的残存使用年数を超える場合には、当該主要な資産の経済的残存使用年数経過時点における当該構成資産の回収可能価額(下記Ⅵ3(2)②参照)
・当該構成資産の経済的残存使用年数が、主要な資産の経済的残存使用年数を超えない場合には、当該構成資産の経済的残存使用年数経過時点における当該構成資産の正味売却価額
Ⅵ 減損損失の測定
1 減損損失の測定
減損会計基準では、減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とするとしている(25項)。「回収可能価額」とは、資産又は資産グループの「正味売却価額」と「使用価値」のいずれか高い方の金額をいう。
2 正味売却価額
(1)正味売却価額の算定
売却による回収額である正味売却価額の算定において、市場価格が観察可能である場合には、原則として、市場価格に基づく価額が時価となる。また、市場価格が観察可能ではない場合には、「合理的に算定された価額」が時価となるが、市場価格に準ずるものとして、合理的な見積りに基づき、以下のような方法で算定される(28項)。
① 不動産については、「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定する。
② その他の固定資産については、コスト・アプローチやマーケット・アプローチ、インカム・アプローチによる見積方法が考えられるが、資産の特性等によりこれらのアプローチを併用又は選択して算定する。
なお、上記①及び②のいずれの場合でも、重要性が乏しい場合には、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標を、「合理的に算定された価額」とみなすことができる。
(2)将来時点の正味売却価額
正味売却価額は、現在のみならず、[図表3]のように、例えば、経済的残存使用年数経過時点のような将来時点のものも算定する場合がある。将来時点の正味売却価額は、当該時点以後の一期間の収益見込額を、その時点の収益率で割り戻した価額から、処分費用見込額の当該時点における現在価値を控除して算定することが考えられるが、適用指針では、以下のように、いくつかの簡便的な方法も示されている(29項)。
まず、このような方法によって将来時点の正味売却価額を算定することが困難な場合には、現在の正味売却価額(償却資産の場合には、現在の正味売却価額から適切な減価額を控除した金額)を用いることができる。この場合、現在の時価を容易に入手することができないときには、現在における一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標を利用して、現在の正味売却価額を算定することができる。
また、資産の減価償却計算に用いられている残存価額に重要性が乏しい場合には、当該残存価額を、当該資産の経済的残存使用年数経過時点における正味売却価額とみなすことができる。
さらに、減損損失の認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積るにあたって、主要な資産以外の構成資産が償却資産のときには、現在の当該構成資産の帳簿価額から主要な資産の経済的残存使用年数までの適切な減価額を控除した金額を用いることができる。
3 使用価値
(1)使用価値の算定
使用による回収額である使用価値の算定においては、将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクについて、将来キャッシュ・フローの見積り(分子)と割引率(分母)のいずれかに反映させる必要がある。
当該リスクは、実務上、割引率に反映させる場合が多く、この場合には、当該リスクを反映させない将来キャッシュ・フローと、以下のもの又はこれらを総合的に勘案した割引率により、使用価値を算定する(39項(1)、45項、[設例6])。
① 当該企業における当該資産又は資産グループに固有のリスクを反映した収益率
② 当該企業に要求される資本コスト
③ 当該資産又は資産グループに類似した資産又は資産グループに固有のリスクを反映した市場平均と考えられる合理的な収益率
④ 当該資産又は資産グループのみを裏付け(いわゆるノンリコース)として大部分の資金調達を行ったときに適用されると合理的に見積られる利率
資産又は資産グループに係る将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクについて、将来キャッシュ・フローの見積りに反映させた場合には、貨幣の時間価値だけを反映した無リスクの割引率(将来キャッシュ・フローが得られるまでの期間に対応した国債の利回り)を用いて使用価値を算定する(39項(2)、46項)。
(2)将来時点の使用価値
① 20年経過時点の回収可能価額
減損損失の認識の判定において、割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積るにあたり、20年経過時点の回収可能価額を算定する場合、当該時点における使用価値は、20年経過時点以降に見込まれる将来キャッシュ・フローに基づいて、当該時点の現在価値として算定される(32項)。
② 経済的残存使用年数経過時点における他の構成資産の回収可能価額
[図表3]のように、将来キャッシュ・フローを見積る期間経過時点において経済的残存使用年数が存在する他の構成資産の回収可能価額を算定する場合、それは原則として、当該時点における他の構成資産の正味売却価額となる(33項、34項)。
ただし、当該経過時点後に、将来キャッシュ・フローの見積りに用いた資産の使用に係る合理的な計画が存在している場合には、当該合理的な計画に従って算定した将来キャッシュ・フローの当該経過時点における現在価値を用いることができる(33項ただし書き、34項ただし書き、[設例3])。
また、減損損失の認識の判定において、割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積るにあたり、主要な資産以外の構成資産が償却資産のときには、現在の構成資産の帳簿価額から主要な資産の経済的残存使用年数までの適切な減価額を控除した金額を用いることができる(33項また書き)。
Ⅶ 将来キャッシュ・フロー
1 将来キャッシュ・フローを見積る際の留意点
減損会計基準では、減損損失を認識するかどうかの判定及び使用価値の算定において見積られる将来キャッシュ・フローは、企業に固有の事情を反映した合理的で説明可能な仮定及び予測に基づいて見積るとしているが、将来キャッシュ・フローを見積るにあたっては、以下のような点に留意する(36項)。
① 企業は、取締役会等の承認を得た中長期計画の前提となった数値を、企業の内外の情報と整合的に修正し、各資産又は資産グループの現在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮して、将来キャッシュ・フローを見積る。
② 中長期計画が存在しない場合、企業は、内外の情報に基づき、各資産又は資産グループの現在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮して、将来キャッシュ・フローを合理的に見積る。これには、過去の一定期間における実際のキャッシュ・フローの平均値に、これまでの趨勢を踏まえた一定又は逓減する成長率の仮定をおいて見積ることも含む。
③ 中長期計画の見積期間を超える期間の将来キャッシュ・フローを算定する場合、企業は、①の数値に、合理的な反証がない限り、それまでの計画に基づく趨勢を踏まえた一定又は逓減する成長率の仮定をおいて見積る。
2 将来キャッシュ・フローの見積りに含められる範囲
① 将来キャッシュ・フローの見積りに際しては、資産又は資産グループの現在の使用状況及び合理的な使用計画等を考慮する。このため、計画されていない将来の設備の増強や事業の再編の結果として生ずる将来キャッシュ・フローは、見積りに含めない(38項(1))。
② 資産又は資産グループの現在の使用状況及び合理的な使用計画等を考慮し、現在の価値を維持するための合理的な設備投資に関連する将来キャッシュ・フローは、見積りに含める(38項(2)、[設例2]及び[設例3])。
③ 将来の用途が定まっていない遊休資産については、現在の状況に基づき将来キャッシュ・フローを見積る。なお、資産グループについては、資産グループ全体について将来の用途が定まっていない遊休状態である場合のみならず、主要な資産が将来の用途が定まっていない遊休資産である場合にも、現在の状況に基づき将来キャッシュ・フローを見積ることとなる(38項(3))。
④ 将来キャッシュ・フローの見積りに際し控除する本社費等の間接的に生ずる支出は、現金基準に基づいて見積る方法のほか、発生基準に基づいて見積る方法(ただし、この場合でも、共用資産の減価償却費は間接的に生ずる支出には含まれないことに留意する。)によることもできる(40項)。
3 利息の受払額並びに法人税等の支払額及び還付額
利息の受払額並びに法人税等の支払額及び還付額は、通常、固定資産の使用又は処分から直接的に生ずる項目ではないため,原則として、将来キャッシュ・フローの見積りには含めない(41項及び42項)。
Ⅷ 共用資産及びのれんの取扱い
1 共用資産の取扱い
共用資産に減損の兆候がある場合、減損損失の認識の判定及び測定は、原則として、[図表4]のように、共用資産が関連する複数の資産又は資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位で行う(48項、[設例7-1])。
また、共用資産の帳簿価額を各資産又は資産グループに配分する方法を採用するにあたっては、以下の点に留意する(49項、[設例7-2])。
① 共用資産の帳簿価額を各資産又は資産グループに配分して管理会計を行っている場合や、共用資産が各資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に密接に関連し、その寄与する度合いとの間に強い相関関係を持つ合理的な配賦基準が存在する場合には、共用資産の帳簿価額を配分する方法を採用することができる。
② 当期にこの方法を採用した場合には、原則として、翌期以降の会計期間においても同じ方法を採用する必要があり、また、当該企業の類似の資産又は資産グループにおいては、同じ方法を採用する必要がある。
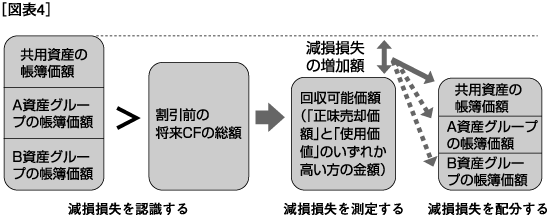
2 のれんの取扱い
分割されたのれんを含む、より大きな単位に減損の兆候がある場合、減損損失の認識の判定及び測定は、原則として、のれんが帰属する事業に関連する複数の資産グループにのれんを加えた、より大きな単位で行う。この場合、のれんを加えることによって算定される減損損失の増加額は、原則として、のれんに配分する(52項、[設例8])。
のれんの帳簿価額を各資産グループに配分する方法を採用するにあたっては、共用資産の帳簿価額を各資産又は資産グループに配分する方法を採用する場合と同様の点に留意する必要がある(53項)。
Ⅸ 減損処理後の会計処理と開示
1 減損処理後の会計処理
減損損失の戻入れは行わず、減損処理を行った資産についても、減損損失を控除した帳簿価額から残存価額を控除した金額を、企業が採用している減価償却の方法に従って、規則的、合理的に配分する(55項)。なお、遊休資産の減価償却費は、原則として、営業外費用として処理する(56項)。
2 財務諸表における表示
減損損失は、原則として、特別損失とする。貸借対照表における表示は、原則として、「直接控除形式」で表示するが、減価償却を行う有形固定資産については、「独立間接控除形式」「合算間接控除形式」で行うこともできる。この場合、減価償却累計額の表示形式と同じものである必要はない(57項)。
3 注記
重要な減損損失を認識した場合には、損益計算書(特別損失)に係る注記事項として、以下の項目を注記する。ただし、減損会計基準を初めて適用した事業年度においては、減損損失を計上していなくとも、全般的な資産のグルーピングの方針等を注記することができる(58項)。
① 減損損失を認識した資産又は資産グループの概要
② 減損損失の認識に至った経緯
③ 特別損失に計上した金額と主な固定資産の種類ごとの減損損失の内訳
④ 減損損失を認識した資産グループの概要と資産をグルーピングした方法
⑤ 回収可能価額が正味売却価額の場合には、その旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率
Ⅹ その他
1 借手側が所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている場合の取扱い
リース資産及びリース資産を含む資産グループに関する減損の兆候の把握、減損損失を認識するかどうかの判定及び減損損失の測定は、通常の資産に準じて行う(61項)。リース資産に配分された減損損失は、重要性がある場合には負債の部において「リース資産減損勘定」等適切な科目をもって計上する。当該負債は、リース契約の残存期間にわたり定額法によって取崩され、当該取崩額は、各事業年度の支払リース料と相殺する(60項、[設例9])。
2 中間会計期間において減損処理を行った資産に係る取扱い
中間会計期間において減損処理を行った場合には、年度決算までに資産又は資産グループに新たな減損の兆候があり追加的に減損損失を認識すべきであると判定される場合を除き、年度決算において、中間会計期間を含む事業年度全体を対象として改めて会計処理を行わない(63項)。
3 再評価を行った土地について減損処理を行った場合の土地再評価差額金の取扱い
「土地の再評価に関する法律」により再評価を行った土地については、再評価後の帳簿価額に基づいて減損会計を適用する。この場合、減損処理を行った部分に係る土地再評価差額金は取り崩すこととなると解されるが、法律の定めのもとで1回限りの臨時的かつ例外的に行われた土地再評価差額金は、売却した場合と同様に、剰余金修正を通して未処分利益に繰り入れる(64項、[設例10])。
ⅩⅠ 実施時期等
適用指針は、減損会計基準の実施にあわせて平成17年4月1日以後開始する事業年度から適用されることとなる(ただし平成16年3月31日以後終了する事業年度については早期適用可)。なお、減損会計基準を早期に適用した場合でも、正当な理由による会計方針の変更に該当することに留意する必要がある(65項)。
企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」の解説
企業会計基準委員会 研究員 山中成大
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会は、平成15年10月31日に企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「適用指針」という。)を公表した。本稿では、適用指針の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ 適用に関する留意点
減損処理は、収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなったという通常の状態とは異なる事態において、例外的に経営者の見込みなどの内部的な情報に基づき、将来に損失を繰り延べないよう回収可能性を反映させるように帳簿価額を臨時的に減額する会計処理と考えられる。
このため、そもそも具体的な判断を一律に示すことは困難な場合が多いが、その中で、適用指針は、減損の兆候をはじめとして、必要と考えられる範囲において一定の目安や例示を示している。企業は、減損会計基準及び適用指針の定めに従って減損処理を行うものとされるが、これらに定めがないため状況に応じ個々の実態を考慮して適用する場合には、減損会計基準及び適用指針の趣旨を適切に斟酌する必要がある(2項)。
Ⅲ 資産のグルーピング
1 資産のグルーピングの必要性
減損処理の3つステップ([図表1])に際して、複数の資産が一体となって独立したキャッシュ・フローを生み出す場合には、資産のグルーピングを行うこととなる。
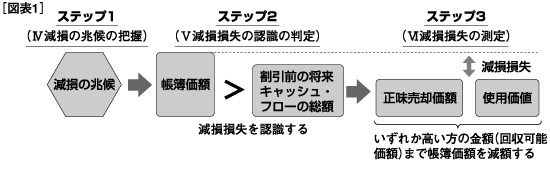
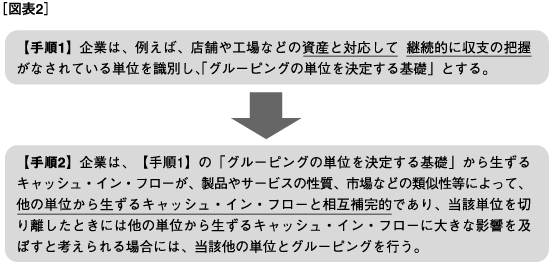
2 資産のグルーピングの手順の例示
減損会計基準において、資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行うこととされており、実務的には、管理会計上の区分や投資の意思決定を行う際の単位等を考慮してグルーピングの方法を定めることになると考えられている。
適用指針では、まず、[図表2]のように、資産のグルーピングを行う手順を例示することにより、実務的な指針として役立てることを考えている(7項、[設例1])。
(1)手順1
一般に、管理会計上の区分は、事業別、製品別、地域別などの区分を基礎にして行われていると考えられるが、継続的に収支の把握がなされている単位は、予算や業績評価の区分より小さい場合もある。また、ここでいう「収支」は、必ずしも企業の外部との間で直接的にキャッシュ・フローが生じている必要はなく、また、発生基準に基づく損益の把握でもよい。
次に、「資産と対応して」とあるように、減損会計は固定資産を対象とするため、原則として、これを細分化せず、例えば、店舗や工場などの物理的な1つの資産において継続的に収支の把握がなされている単位が「グルーピングの単位を決定する基礎」になる。
なお、事業の特性により、継続的な収支が事業を行っている大きさでしか把握されていないこともあると考えられる。すなわち、事業の種類や業態によっては、当該資産から生ずるキャッシュ・イン・フローが他の資産から生ずるキャッシュ・イン・フローと相互補完的であるため、管理会計上も合理的な内部振替価格を用いて収入の把握を行うことが困難な場合があり、また、当該資産に関わるキャッシュ・イン・フローに見積もり要素が極めて多いため、管理会計上、資産ごと又は複数の資産をまとめた単位では継続的な収支の把握に意義を見出せない場合がある。検討過程において、前者については例えば一部の電力事業において、後者については例えば一部の保険事業において、このようなケースに該当する場合があるとの認識が示されたが、これらの判断は企業の実態によるので、上述した業種の企業がすべて該当するわけではなく、また、他の業種の企業では該当しないということではないと考えられる。いずれにしろ、このようなケースは管理会計上の目的や効果から合理性を有するものに限られることに留意する必要がある(70項(1))。
(2)手順2
手順1で識別された「グルーピングの単位を決定する基礎」のうち、それぞれのキャッシュ・イン・フローが相互補完的であり、それぞれの単位を切り離したときには、他の単位から生ずるキャッシュ・イン・フローに大きな影響を及ぼす場合には、他の単位とグルーピングを行うことになる。
なお、稀ではあるが、法規制によって企業に製品やサービスの供給義務があり、このため、販売価格の認可制や広い安全義務、また拡張撤退が自由にできないような場合には、供給義務が課されている資産又は複数の資産は、当該資産から生ずるキャッシュ・イン・フローには相互補完的な影響があることに該当すると考えられる(70項(2))。検討の過程では、例えば一部の鉄道事業においてこのようなケースにあたる場合があるとの認識が示されたが、これらの判断についても企業の実態によるので、このような業種の企業がすべて該当するわけではなく、また、他の業種の企業では該当しないということではないと考えられる。
3 処分が決定された資産及び廃止が決定された事業に係る資産
取締役会等において、資産の処分や事業の廃止に関する意思決定を行い、その代替的な投資も予定されていない場合には、これらに係る資産を切り離しても他の資産又は資産グループの使用にほとんど影響を与えない場合があり、このようなケースに該当する資産のうち重要なものは、独立した資産グループとして取り扱うことになる(8項前段)。
4 将来の使用が見込まれていない遊休資産
遊休状態とは、企業活動にほとんど使用されていない状態であって、過去の利用実態や将来の用途の定めには関係がない現在の状態であり、このような状態にある資産が遊休資産である(72項)。「将来の使用が見込まれていない遊休資産」は、上記3と同様に、通常、当該遊休資産を切り離しても他の資産又は資産グループの使用にほとんど影響を与えないと考えられるため、重要なものについては、独立した資産グループとして取り扱う。また、企業が「将来の使用を見込んでいる遊休資産」は、その見込みに沿って、グルーピングを行うことになる(8項後段)。
Ⅳ 減損の兆候
減損の兆候とは、資産又は資産グループに減損が生じている可能性を示す事象をいい、その程度は必ずしも画一的に数値化できるものではなく、厳格に定められるものではないが、一定の目安を設けることも実務上の指針として役立つ側面もあることから、適用指針では、必要と考えられる範囲において、その目安を示している(77項)。企業は、通常の企業活動において実務的に入手可能なタイミングにおいて利用可能な情報に基づき、以下のような減損の兆候がある資産又は資産グループを識別する(11項)。
1 営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスの場合
(1)「営業活動から生じる損益」について
「営業活動から生ずる損益」には、当該資産又は資産グループの減価償却費や、本社費等の間接的に生ずる費用、損益計算書上は原価性を有しないものとして営業損益に含まれていない項目でも営業上の取引に関連して生じた損益(例えば、たな卸資産の評価損)であれば含まれる。ただし、支払利息など財務活動から生ずる損益や利益に関連する金額を課税標準とする税金については、営業活動から生ずる損益に含まれず、また、大規模な経営改善計画等により生じた一時的な損益も含まれない。実務上、営業活動から生ずる損益は、このような考え方を反映した管理会計上の損益区分に基づいて行われるものと考えられる(12項(1))。
(2)「継続してマイナス」及び「継続してマイナスとなる見込み」について
「継続してマイナス」とは、おおむね過去2期がマイナスであったことを指すが、当期の見込みが明らかにプラスとなる場合は、兆候としての意義が薄いことから、該当しないと考えられる。また、「継続してマイナスとなる見込み」とは、前期と当期以降の見込みが明らかにマイナスとなる場合を指す(12項(2))。
なお、事業の立上げ時など予め合理的な事業計画(当該計画の中で投資額以上のキャッシュ・フローを生み出すことが実行可能なもの)が策定されており、当該計画にて当初より継続してマイナスとなることが予定されている場合、実際のマイナスの額が当該計画にて予定されていたマイナスの額よりも著しく下方に乖離していないときには、減損の兆候には該当しない(12項(4))。
2 使用範囲又は方法について回収可能額を著しく低下させる変化がある場合
資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、例えば、以下の①から⑦のような当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、又は、生ずる見込みである場合には、減損の兆候となる(13項)。
なお、資産グループについては、資産グループ全体について以下の①から⑦のような変化が生じたか、又は、生ずる見込みである場合のみならず、主要な資産が使用されている範囲又は方法について、以下の①から⑦のような変化が生じたか、又は、生ずる見込みである場合も含まれる(13項なお書き)。
① 資産又は資産グループが使用されている事業を廃止又は再編成すること
② 当初の予定よりも著しく早期に資産又は資産グループを処分すること
③ 資産又は資産グループを異なる用途に転用すること
④ 資産又は資産グループが遊休状態になり、将来の用途が定まっていないこと
⑤ 資産又は資産グループの稼働率が著しく低下した状態が続いており、著しく低下した稼働率が回復する見込みがないこと
⑥ 資産又は資産グループに著しい陳腐化等の機能的減価が観察できること
⑦ 建設仮勘定に係る建設について、計画の中止又は大幅な延期が決定されたことや当初の計画に比べ著しく滞っていること
3 経営環境の著しい悪化の場合
経営環境の著しい悪化は、個々の企業において大きく異なるため、適用指針では、①市場環境の著しい悪化、②技術的環境の著しい悪化、③法律的環境の著しい悪化の例示を示すにとどめている(14項)。
4 市場価額の著しい下落の場合
「市場価格が著しく下落したこと」には、少なくとも市場価格が帳簿価額から50%程度以上下落した場合が該当する(15項)。ただし、50%程度以上下落していない場合でも、例えば、処分が予定されている資産で、市場価格の下落により、減損が生じている可能性が高いと見込まれるときのように、状況に応じ個々の企業において判断することが必要なときがある(89項ただし書き)。
また、固定資産については、市場価格が観察可能な場合は多くないため、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標が容易に入手できる場合(容易に入手できる評価額や指標を合理的に調整したものも含まれる。)には、これらを、減損の兆候を把握するための市場価格とみなして使用する(15項また書き)。
なお、資産グループについては、資産グループ全体の市場価格が把握できない場合でも、①資産グループの主要な資産の市場価格が著しく下落した場合や、②(土地が主要な資産ではなくとも)資産グループの帳簿価額のうち土地の帳簿価額が大きな割合を占め、当該土地の市場価格が著しく下落した場合も含まれる(15項なお書き)。
5 共用資産やのれんの減損の兆候
共用資産については、共用資産を含むより大きな単位について、上記1から4における事象がある場合、または、共用資産そのものについて、上記2又は4における事象がある場合、減損の兆候があることになる(16項)。
のれんについては、のれんを含むより大きな単位について、上記1から4における事象がある場合、減損の兆候があることになる(17項)。
Ⅴ 減損損失の認識の判定
減損会計基準では、減損の兆候がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がこれらの帳簿価額を下回る場合には、減損損失を認識することとしている。この際、割引前将来キャッシュ・フローを見積る期間は、資産又は資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数と20年のいずれか短い方とされている(96項)。
1 経済的残存使用年数
資産又は資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数は、当該資産が今後、経済的に使用可能と予測される年数と考えられる。なお、経済的残存使用年数が、当該資産の減価償却計算に用いられている税法耐用年数等に基づく残存耐用年数と著しい相違がある等の不合理と認められる事情のない限り、当該残存耐用年数を経済的残存使用年数とみなすことができる(21項)。
2 主要な資産
資産グループ中の主要な資産は、資産のグルーピングを行う際に決定され、当期に主要な資産とされた資産は、原則として、翌期以降の会計期間においても当該資産グループの主要な資産となる(22項)。なお、土地等の非償却資産や建物等の経済的残存使用年数が20年を超える資産も主要な資産とすることができるが、その場合にも、当該資産が資産グループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとって最も重要な構成資産であるかどうかに留意する必要がある(23項)。
また、共用資産やのれんは、原則として、主要な資産には該当しない(24項)。
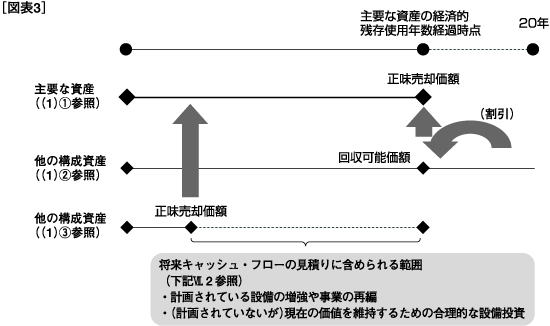
3 割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積り
(1)資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数が20年を超えない場合(97項)
この場合、以下を当該主要な資産の経済的残存使用年数までの割引前将来キャッシュ・フローに加算する(18項、[設例2](ケース1))。
① 主要な資産の経済的残存使用年数経過時点における主要な資産の正味売却価額
② 主要な資産以外の構成資産の経済的残存使用年数が、主要な資産の経済的残存使用年数を超える場合には、当該主要な資産の経済的残存使用年数経過時点における当該他の構成資産の回収可能価額(下記Ⅵ3(2)②参照)
③ 主要な資産以外の構成資産の経済的残存使用年数が、主要な資産の経済的残存使用年数を超えない場合には、当該他の構成資産の経済的残存使用年数経過時点における当該構成資産の正味売却価額
なお、これらのイメージ図は[図表3]のとおりである(横軸は経済的残存使用年数、矢印は割引前将来キャッシュ・フローに加算する金額を示す。)。
(2)資産グループ中の主要な資産の経済的残存使用年数が20年を超える場合(98項)
この場合には、20年経過時点の回収可能価額を20年目までの割引前将来キャッシュ・フローに加算する(18項(2)、[設例2](ケース2))。資産グループ中の主要な資産以外の構成資産の経済的残存使用年数が20年を超えない場合には、当該構成資産の経済的残存使用年数経過時点における当該構成資産の正味売却価額を主要な資産の経済的残存使用年数までの割引前将来キャッシュ・フローに加算し(18項(3))、20年を超える場合、以下を21年目以降に見込まれる将来キャッシュ・フローに加算し、20年経過時点の回収可能価額に含める(18項(4))。
・当該構成資産の経済的残存使用年数が、主要な資産の経済的残存使用年数を超える場合には、当該主要な資産の経済的残存使用年数経過時点における当該構成資産の回収可能価額(下記Ⅵ3(2)②参照)
・当該構成資産の経済的残存使用年数が、主要な資産の経済的残存使用年数を超えない場合には、当該構成資産の経済的残存使用年数経過時点における当該構成資産の正味売却価額
Ⅵ 減損損失の測定
1 減損損失の測定
減損会計基準では、減損損失を認識すべきであると判定された資産又は資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とするとしている(25項)。「回収可能価額」とは、資産又は資産グループの「正味売却価額」と「使用価値」のいずれか高い方の金額をいう。
2 正味売却価額
(1)正味売却価額の算定
売却による回収額である正味売却価額の算定において、市場価格が観察可能である場合には、原則として、市場価格に基づく価額が時価となる。また、市場価格が観察可能ではない場合には、「合理的に算定された価額」が時価となるが、市場価格に準ずるものとして、合理的な見積りに基づき、以下のような方法で算定される(28項)。
① 不動産については、「不動産鑑定評価基準」に基づいて算定する。
② その他の固定資産については、コスト・アプローチやマーケット・アプローチ、インカム・アプローチによる見積方法が考えられるが、資産の特性等によりこれらのアプローチを併用又は選択して算定する。
なお、上記①及び②のいずれの場合でも、重要性が乏しい場合には、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標を、「合理的に算定された価額」とみなすことができる。
(2)将来時点の正味売却価額
正味売却価額は、現在のみならず、[図表3]のように、例えば、経済的残存使用年数経過時点のような将来時点のものも算定する場合がある。将来時点の正味売却価額は、当該時点以後の一期間の収益見込額を、その時点の収益率で割り戻した価額から、処分費用見込額の当該時点における現在価値を控除して算定することが考えられるが、適用指針では、以下のように、いくつかの簡便的な方法も示されている(29項)。
まず、このような方法によって将来時点の正味売却価額を算定することが困難な場合には、現在の正味売却価額(償却資産の場合には、現在の正味売却価額から適切な減価額を控除した金額)を用いることができる。この場合、現在の時価を容易に入手することができないときには、現在における一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標を利用して、現在の正味売却価額を算定することができる。
また、資産の減価償却計算に用いられている残存価額に重要性が乏しい場合には、当該残存価額を、当該資産の経済的残存使用年数経過時点における正味売却価額とみなすことができる。
さらに、減損損失の認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積るにあたって、主要な資産以外の構成資産が償却資産のときには、現在の当該構成資産の帳簿価額から主要な資産の経済的残存使用年数までの適切な減価額を控除した金額を用いることができる。
3 使用価値
(1)使用価値の算定
使用による回収額である使用価値の算定においては、将来キャッシュ・フローが見積値から乖離するリスクについて、将来キャッシュ・フローの見積り(分子)と割引率(分母)のいずれかに反映させる必要がある。
当該リスクは、実務上、割引率に反映させる場合が多く、この場合には、当該リスクを反映させない将来キャッシュ・フローと、以下のもの又はこれらを総合的に勘案した割引率により、使用価値を算定する(39項(1)、45項、[設例6])。
① 当該企業における当該資産又は資産グループに固有のリスクを反映した収益率
② 当該企業に要求される資本コスト
③ 当該資産又は資産グループに類似した資産又は資産グループに固有のリスクを反映した市場平均と考えられる合理的な収益率
④ 当該資産又は資産グループのみを裏付け(いわゆるノンリコース)として大部分の資金調達を行ったときに適用されると合理的に見積られる利率
資産又は資産グループに係る将来キャッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクについて、将来キャッシュ・フローの見積りに反映させた場合には、貨幣の時間価値だけを反映した無リスクの割引率(将来キャッシュ・フローが得られるまでの期間に対応した国債の利回り)を用いて使用価値を算定する(39項(2)、46項)。
(2)将来時点の使用価値
① 20年経過時点の回収可能価額
減損損失の認識の判定において、割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積るにあたり、20年経過時点の回収可能価額を算定する場合、当該時点における使用価値は、20年経過時点以降に見込まれる将来キャッシュ・フローに基づいて、当該時点の現在価値として算定される(32項)。
② 経済的残存使用年数経過時点における他の構成資産の回収可能価額
[図表3]のように、将来キャッシュ・フローを見積る期間経過時点において経済的残存使用年数が存在する他の構成資産の回収可能価額を算定する場合、それは原則として、当該時点における他の構成資産の正味売却価額となる(33項、34項)。
ただし、当該経過時点後に、将来キャッシュ・フローの見積りに用いた資産の使用に係る合理的な計画が存在している場合には、当該合理的な計画に従って算定した将来キャッシュ・フローの当該経過時点における現在価値を用いることができる(33項ただし書き、34項ただし書き、[設例3])。
また、減損損失の認識の判定において、割引前将来キャッシュ・フローの総額を見積るにあたり、主要な資産以外の構成資産が償却資産のときには、現在の構成資産の帳簿価額から主要な資産の経済的残存使用年数までの適切な減価額を控除した金額を用いることができる(33項また書き)。
Ⅶ 将来キャッシュ・フロー
1 将来キャッシュ・フローを見積る際の留意点
減損会計基準では、減損損失を認識するかどうかの判定及び使用価値の算定において見積られる将来キャッシュ・フローは、企業に固有の事情を反映した合理的で説明可能な仮定及び予測に基づいて見積るとしているが、将来キャッシュ・フローを見積るにあたっては、以下のような点に留意する(36項)。
① 企業は、取締役会等の承認を得た中長期計画の前提となった数値を、企業の内外の情報と整合的に修正し、各資産又は資産グループの現在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮して、将来キャッシュ・フローを見積る。
② 中長期計画が存在しない場合、企業は、内外の情報に基づき、各資産又は資産グループの現在の使用状況や合理的な使用計画等を考慮して、将来キャッシュ・フローを合理的に見積る。これには、過去の一定期間における実際のキャッシュ・フローの平均値に、これまでの趨勢を踏まえた一定又は逓減する成長率の仮定をおいて見積ることも含む。
③ 中長期計画の見積期間を超える期間の将来キャッシュ・フローを算定する場合、企業は、①の数値に、合理的な反証がない限り、それまでの計画に基づく趨勢を踏まえた一定又は逓減する成長率の仮定をおいて見積る。
2 将来キャッシュ・フローの見積りに含められる範囲
① 将来キャッシュ・フローの見積りに際しては、資産又は資産グループの現在の使用状況及び合理的な使用計画等を考慮する。このため、計画されていない将来の設備の増強や事業の再編の結果として生ずる将来キャッシュ・フローは、見積りに含めない(38項(1))。
② 資産又は資産グループの現在の使用状況及び合理的な使用計画等を考慮し、現在の価値を維持するための合理的な設備投資に関連する将来キャッシュ・フローは、見積りに含める(38項(2)、[設例2]及び[設例3])。
③ 将来の用途が定まっていない遊休資産については、現在の状況に基づき将来キャッシュ・フローを見積る。なお、資産グループについては、資産グループ全体について将来の用途が定まっていない遊休状態である場合のみならず、主要な資産が将来の用途が定まっていない遊休資産である場合にも、現在の状況に基づき将来キャッシュ・フローを見積ることとなる(38項(3))。
④ 将来キャッシュ・フローの見積りに際し控除する本社費等の間接的に生ずる支出は、現金基準に基づいて見積る方法のほか、発生基準に基づいて見積る方法(ただし、この場合でも、共用資産の減価償却費は間接的に生ずる支出には含まれないことに留意する。)によることもできる(40項)。
3 利息の受払額並びに法人税等の支払額及び還付額
利息の受払額並びに法人税等の支払額及び還付額は、通常、固定資産の使用又は処分から直接的に生ずる項目ではないため,原則として、将来キャッシュ・フローの見積りには含めない(41項及び42項)。
Ⅷ 共用資産及びのれんの取扱い
1 共用資産の取扱い
共用資産に減損の兆候がある場合、減損損失の認識の判定及び測定は、原則として、[図表4]のように、共用資産が関連する複数の資産又は資産グループに共用資産を加えた、より大きな単位で行う(48項、[設例7-1])。
また、共用資産の帳簿価額を各資産又は資産グループに配分する方法を採用するにあたっては、以下の点に留意する(49項、[設例7-2])。
① 共用資産の帳簿価額を各資産又は資産グループに配分して管理会計を行っている場合や、共用資産が各資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に密接に関連し、その寄与する度合いとの間に強い相関関係を持つ合理的な配賦基準が存在する場合には、共用資産の帳簿価額を配分する方法を採用することができる。
② 当期にこの方法を採用した場合には、原則として、翌期以降の会計期間においても同じ方法を採用する必要があり、また、当該企業の類似の資産又は資産グループにおいては、同じ方法を採用する必要がある。
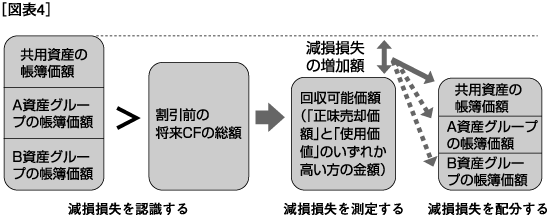
2 のれんの取扱い
分割されたのれんを含む、より大きな単位に減損の兆候がある場合、減損損失の認識の判定及び測定は、原則として、のれんが帰属する事業に関連する複数の資産グループにのれんを加えた、より大きな単位で行う。この場合、のれんを加えることによって算定される減損損失の増加額は、原則として、のれんに配分する(52項、[設例8])。
のれんの帳簿価額を各資産グループに配分する方法を採用するにあたっては、共用資産の帳簿価額を各資産又は資産グループに配分する方法を採用する場合と同様の点に留意する必要がある(53項)。
Ⅸ 減損処理後の会計処理と開示
1 減損処理後の会計処理
減損損失の戻入れは行わず、減損処理を行った資産についても、減損損失を控除した帳簿価額から残存価額を控除した金額を、企業が採用している減価償却の方法に従って、規則的、合理的に配分する(55項)。なお、遊休資産の減価償却費は、原則として、営業外費用として処理する(56項)。
2 財務諸表における表示
減損損失は、原則として、特別損失とする。貸借対照表における表示は、原則として、「直接控除形式」で表示するが、減価償却を行う有形固定資産については、「独立間接控除形式」「合算間接控除形式」で行うこともできる。この場合、減価償却累計額の表示形式と同じものである必要はない(57項)。
3 注記
重要な減損損失を認識した場合には、損益計算書(特別損失)に係る注記事項として、以下の項目を注記する。ただし、減損会計基準を初めて適用した事業年度においては、減損損失を計上していなくとも、全般的な資産のグルーピングの方針等を注記することができる(58項)。
① 減損損失を認識した資産又は資産グループの概要
② 減損損失の認識に至った経緯
③ 特別損失に計上した金額と主な固定資産の種類ごとの減損損失の内訳
④ 減損損失を認識した資産グループの概要と資産をグルーピングした方法
⑤ 回収可能価額が正味売却価額の場合には、その旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率
Ⅹ その他
1 借手側が所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っている場合の取扱い
リース資産及びリース資産を含む資産グループに関する減損の兆候の把握、減損損失を認識するかどうかの判定及び減損損失の測定は、通常の資産に準じて行う(61項)。リース資産に配分された減損損失は、重要性がある場合には負債の部において「リース資産減損勘定」等適切な科目をもって計上する。当該負債は、リース契約の残存期間にわたり定額法によって取崩され、当該取崩額は、各事業年度の支払リース料と相殺する(60項、[設例9])。
2 中間会計期間において減損処理を行った資産に係る取扱い
中間会計期間において減損処理を行った場合には、年度決算までに資産又は資産グループに新たな減損の兆候があり追加的に減損損失を認識すべきであると判定される場合を除き、年度決算において、中間会計期間を含む事業年度全体を対象として改めて会計処理を行わない(63項)。
3 再評価を行った土地について減損処理を行った場合の土地再評価差額金の取扱い
「土地の再評価に関する法律」により再評価を行った土地については、再評価後の帳簿価額に基づいて減損会計を適用する。この場合、減損処理を行った部分に係る土地再評価差額金は取り崩すこととなると解されるが、法律の定めのもとで1回限りの臨時的かつ例外的に行われた土地再評価差額金は、売却した場合と同様に、剰余金修正を通して未処分利益に繰り入れる(64項、[設例10])。
ⅩⅠ 実施時期等
適用指針は、減損会計基準の実施にあわせて平成17年4月1日以後開始する事業年度から適用されることとなる(ただし平成16年3月31日以後終了する事業年度については早期適用可)。なお、減損会計基準を早期に適用した場合でも、正当な理由による会計方針の変更に該当することに留意する必要がある(65項)。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















