資料2004年04月19日 【税務関係資料】 税理士試験に関するQ&A
試験日程・試験科目について
問1 試験日程と試験科目(出題範囲)を教えてください。
(答)
平成16年度第54回税理士試験の日程及び試験科目の出題範囲は下表のとおりです。
| 月日 | 時 間 | 科 目 | 出 題 範 囲 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 月 3 日 (火) | 9:00~11:00 | 簿 記 論 | 複式簿記の原理、その記帳・計算及び帳簿組織、商業簿記のほか工業簿記を含む。ただし、原価計算を除く。 | ||
| 12:30~14:30 | 財務諸表論 | 会計原理、企業会計原則、商法中商業帳簿及び会社の計算に関する規定、商法施行規則中総則、財産の評価、貸借対照表等の記載方法等及び純資産額から控除すべき金額に関する規定(ただし、特定の事業を行う会社についての特例を除く。)、財務諸表等の用語・様式及び作成方法に関する規則 | |||
| 15:30~17:30 | 消費税法 又は酒税法 |
| |||
| 8 月 4 日 (水) | 9:00~11:00 | 法人税法 | |||
| 12:00~14:00 | 相続税法 | ||||
| 15:00~17:00 | 所得税法 | ||||
| 8 月 5 日 (木) | 9:00~11:00 | 固定資産税 |
| ||
| 12:00~14:00 | 国税徴収法 | (1)と同じ。 | |||
| 15:00~17:00 | 住民税又は 事 業 税 | (2)と同じ。 |
受験の申込みについて
問2 受験案内や受験願書は、いつ、どこでもらえますか。
(答)
平成16年度第54回税理士試験の受験案内及び受験願書は、4月30日(金)から下表の各国税局及び沖縄国税事務所で、6月4日(金)まで交付します。
なお、受験案内及び受験願書の交付は一人一部に限らせていただきます。
|
| 申込用紙等交付場 |
|
(交通手段) |
| ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
人事第二課 | 060 | 札幌市中央区大通西10丁目札幌第二合同庁舎 | 011(231)5011 | ||
|
|
人事第二課 | 980 | 仙台市青葉区本町3丁目3番1号 仙台合同庁舎(地下鉄「勾当台公園駅」下車、北2出口から県庁方面へ徒歩5分) | 022(263)1111 | ||
|
川越市 |
人事第二課 | 330 | さいたま市中央区新都心1番地1 さいたま新都心合 同庁舎1号館 (JR埼京線「北与野駅」から徒歩7分 JR宇都宮線・高崎線・京浜東北線「さいたま新都心駅」から徒歩5分) | 048(600)3111 | ||
|
|
人事第二課 | 100 | 千代田区大手町1丁目3番3号大手町合同庁舎3号館 | 03(3216)6811 | ||
|
|
人事第二課 | 920 | 金沢市広坂2丁目2番60号金沢広坂合同庁舎 | 076(231)2131 | ||
|
|
人事第二課 | 460 | 名古屋市中区三の丸3丁目3番2号名古屋国税総合庁舎 | 052(951)3511 | ||
|
大阪府 |
人事第二課 | 540 | 大阪市中央区大手前1丁目5番63号大阪合同庁舎三号館 | 06(6941)5331 | ||
| - | 大阪市中央区大手前1丁目7番31号 (地下鉄谷町線「天満橋駅」1番出口又は京阪電鉄「天満橋駅」東出口から徒歩2分) | - | |||
|
|
人事第二課 | 730 | 広島市中区上八丁堀6番30号広島合同庁舎1号館(JR広島駅前バス乗り場Bホームで9番線から合同庁舎経由のバスに乗車。「合同庁舎前」バス停下車しすぐ) | 082(221)9211 | ||
|
|
人事第二課 | 760 | 高松市天神前2番10号高松国税総合庁舎 | 087(831)3111 | ||
|
|
人事第二課 | 812 | 福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号福岡合同庁舎 | 092(411)0031 | ||
|
|
人事第二課 | 860 | 熊本市二の丸1番2号熊本合同庁舎1号館 | 096(354)6171 | ||
|
|
人 事 課 | 900 | 那覇市旭町9番地 沖縄国税総合庁舎 | 098(867)3101 |
| (注) | ②では、郵送による申込用紙等の請求及び郵送による受験申込みは、一切受け付けておりません。 |
問3 受験案内や受験願書を、郵送してもらうことはできますか。
(答)
受験案内や受験願書は、郵便で請求することもできます。
この場合には、郵送による申込用紙の交付期間(平成16年度は4月30日から5月24日まで。当日消印有効。)に、各国税局及び沖縄国税事務所あてに、以下の点に注意して請求してください。
なお、請求先の各国税局及び沖縄国税事務所の所在地は、問2の「各国税局及び沖縄国税事務所の一覧」を参照してください。
○ 封筒の表面に「税理士請求」と赤書きすること。
○ 140円切手をはったあて先・郵便番号明記の返信用封筒(A4判大)を同封すること。これがない場合には送付しません。
○ 1人1部ずつ請求すること。
問4 受験申込みは、いつ、どこで行うのですか。
(答)
平成16年度第54回税理士試験の受験願書の受付は、以下のとおり行います。
○受付期間: 平成16年5月25日(火)から平成16年6月4日(日)まで(土曜日及び日曜日は除く。)
○受付場所: 試験を受けようとする受験地を管轄する国税局又は沖縄国税事務所(ただし、大阪府又は京都府で受験を希望する方の持参による申込受付場所は「受験案内」又は大阪国税局ホームページで確認してください。)
○受付時間: 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間は受け付けません。)
なお、一部の科目に合格している方は直近の税理士試験等結果通知書又は一部科目合格通知書のコピー、一部の科目について免除を受けている方は税理士試験等結果通知書又は一部科目免除決定通知書のコピーが必要になります(直近分の一部科目合格通知書が昭和60年度以前の場合には、合格済の全科目分のコピーが必要となります。)。
問5 郵便で受験を申込むことはできますか。
(答)
郵便で受験申込みができます。
この場合には、以下の点に注意して、受験者ごとになるべく早く申し込んでください。6月4日(金)までの消印のあるもの(料金後納又は料金別納郵便については6月4日(金)までに到着したもの)に限り受け付けます。
1 税理士試験受験願書の所定の箇所に受験手数料(問7参照)に相当する収入印紙を消印しないではること。
2 受験票の裏面には、郵便番号・あて先を明記し、返信用切手(50円)をはること。
3 申込書類は、試験を受けようとする受験地を管轄する国税局又は沖縄国税事務所あてに送付すること。
4 封筒(A4判大)の表面には、「税理士受験」と赤書きし,必ず「書留」、「簡易書留」又は「配達記録郵便」で送付すること。
問6 受験科目の選択方法を教えてください。
(答)
受験科目については、以下の点に注意して選択してください。
○ 受験科目数は、免除申請科目と併せて会計学2科目以内、所得税法又は法人税法を含めた税法3科目以内の合計5科目以内です(受験者は一度に5科目を受験する必要はなく、1科目ずつ受験してもよいことになっています。)。
○ 消費税法と酒税法は、いずれか1科目の選択に限ります。
○ 住民税と事業税は、いずれか1科目の選択に限ります。
問7 受験手数料はいくらですか。
(答)
受験手数料は、受験申込科目数に応じ、次のとおりとなっています。税理士試験受験願書の所定の箇所に受験申込科目数及び受験手数料を記入の上、受験手数料に相当する収入印紙を消印をしないではってください。現金、郵便切手、証紙等では受け付けられませんので注意してください。
| 受験申込科目数 | 1科目 | 2科目 | 3科目 | 4科目 | 5科目 |
| 受験手数料 | 3,500 円 | 4,500 円 | 5,500 円 | 6,500 円 | 7,500 円 |
問8 受験票を紛失した場合には、どうすればよいのですか。
(答)
受験票を紛失した場合は、受験を申込んだ国税局又は沖縄国税事務所の人事課税理士試験担当係で、7月12日(月)から7月30日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日等は除く。)に受験票の再交付を受けてください。
手続は、身分証明書を持参し、各国税局又は沖縄国税事務所で行ってください。
なお、試験当日に受験票を持参しないと、税理士試験は受験できません。
受験資格について
問9 受験資格にはどのようなものがありますか。
(答)
税理士試験受験資格一覧表(税理士法第5条関係抜粋)
| 受験資格(次の学識、資格、職歴、認定のいずれかに該当することが必要) | 提出書類(注1・2・3) | ||
| 学 識 | 大学又は短大を卒業した者で右欄のいずれかに該当する者 | 法律学又は経済学を主たる履修科目とする学部(法学部、経済学部、商学部、経営学部)・学校を卒業した者 | 卒業証明書 |
| 上記以外の学部(文学部、工学部など)・学校を卒業した者で、一般教育科目等において、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者 | 成績証明書 (卒業年次の記載のないものは卒業証明書も必要) | ||
| 大学3年次以上の学生で右欄のいずれかに該当する者 | 法律学又は経済学に属する科目を含め62単位以上を取得した者 | 成績証明書 (年次の記載のないものは在籍証明書も必要) | |
| 法律学又は経済学に属する科目を含め36単位以上を取得した者(ただし、外国語及び保健体育科目を除き、最低24単位の一般教育科目が必要) | |||
| 専修学校の専門課程((1)修業年限が2年以上かつ(2)課程の修了に必要な総授業数が1,700時間以上に限る。)を修了した者等で、これらの専修学校等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した者 | ・成績証明書 (卒業年次の記載のないものは卒業証明書も必要) ・課程証明書(当該専門課程が左欄の(1)及び(2)の要件を満たす課程であることについて都道府県知事等が発行した証明書を専修学校が原本証明したもの) | ||
| 司法試験第二次試験合格者 | 所管官庁の合格証明書 | ||
| 資 格 | 日本商工会議所主催簿記検定試験1級合格者 | 日本商工会議所発行の合格証明書 | |
| (社)全国経理学校協会主催簿記能力検定試験上級合格者 (昭和58年度以降の合格者に限る。) | (社)全国経理学校協会発行の合格証明書 | ||
| 会計士補 | 公認会計士協会発行の登録証明書 | ||
| 会計士補となる資格を有する者 | 公認会計士審査会会長発行の公認会計士第二次試験合格証明書又は同試験の免除科目が全科目に及ぶことを証する書面 | ||
| 職 歴 | 右欄の事務又は業務に3年以上従事した者 | 弁理士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士等の業務 | 登録証明書及び業務従事証明書(同業者2人以上の証明) |
| 法人又は事業を営む個人の会計に関する事務 | 職歴証明書 (様式等は問18を参照) | ||
| 税理士・弁護士・公認会計士等の業務の補助の事務 | |||
| 税務官公署における事務又はその他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務 | |||
| 認 定 | 国税審議会により受験資格に関して個別認定を受けた者 (注4) | 国税審議会会長発行の受験資格認定通知書のコピー | |
(注1) 卒業証書や合格証書は、受け付けられませんので、必ず証明書を添付してください。また、証明書等(受験資格認定通知書を除く。)のコピーも受け付けられません。
(注2) 証明書の氏名と現在の氏名が異なっている場合には、戸籍抄本等の証明書類が必要です(問19参照)。
(注3) A4規格でない証明書や戸籍抄本等は、A4用紙にはってください。
(注4) 次に掲げるような事由により受験しようとする場合には、あらかじめ国税審議会会長の認定を受けてください。
1 法律学又は経済学に関し、上記の「学識」に掲げる者と同等以上の学識を有すると認められること。
(例:外国の大学を卒業した者等で、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修している者)
2 上記の「職歴」に掲げる事務又は業務に類していると認められるものに、3年以上従事したこと。
(個別認定申請に必要な書類)
1 税理士試験受験資格認定申請書(様式は、問21参照)
2 住民票
3 学識、職歴、事務又は業務の内容を証明する書面
4 郵便番号及びあて先を明記し、所要額の切手(配達記録であれば330円、簡易書留であれば470円、書留であれば540円の切手)をはったA4判大の返信用封筒
問10 年齢や国籍に制限はありますか。
(答)
税理士試験の受験資格には国籍や年齢の制限はありません。
問11 大学の法学部(又は経済学部、商学部、経営学部)を卒業しましたが、受験資格はありますか。
(答)
大学又は短大を卒業した方のうち、一般教育科目等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修した方には受験資格があります。
したがって、法律学又は経済学を主たる履修科目とする学部(法学部、経済学部、商学部、経営学部)を卒業した方には、一般的には受験資格があります。
受験申込みの際に、受験資格を有することを証する書面として、卒業証明書を提出してください。
問12 大学の文学部を卒業しましたが、受験資格はありますか。
(答)
文学部や理工学部などを卒業した方も、一般教育科目等において、法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修していれば受験資格があります。
受験申込みの際に、受験資格を有することを証する書面として、成績証明書(卒業年次の記載がない場合には、卒業証明書も必要となります。)を提出してください。
法律学又は経済学に属する科目の具体的内容については、問15を参照してください。
問13 大学を3年次の中途で退学しても受験資格はありますか。
(答)
大学3年次以上に在学中又は3年次以上で中途退学した方でも、一般教育科目等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修し、かつ、次のいずれかに該当する場合には、受験資格があります。
○ 合計62単位以上を修得していること。
○ 一般教育科目、外国語科目、保健体育科目及び専門教育科目という従来の4区分制を採用している大学等において、一般教育科目のうち、外国語及び保健体育科目を除いた科目が24単位以上であって、かつ、専門教育科目等を含めて、36単位以上修得していること。
問14 専門学校を卒業しましたが、受験資格はありますか。
(答)
専修学校の専門課程(修業年限が2年以上課程の修了に必要な総授業数が1,700時間以上)を修了した方が、これらの専修学校等において法律学又は経済学に属する科目を1科目以上履修していれば、受験資格があります。
この場合、成績証明書(卒業年次の記載がない場合には、卒業証明書も必要となります。)と課程証明書(当該専門課程が上記及びの要件を満たす課程であることについて都道府県知事等が発行した証明書を専修学校が原本証明したもの)を受験願書に添付してください。
問15 「法律学に属する科目」や「経済学に属する科目」にはどのような科目が含まれますか。
(答)
「法律学に属する科目」には、法学(概論)、法律概論、憲法(概論)、民法、刑法、商法、行政法、労働法、国際法等が該当します。
「経済学に属する科目」には、(マクロ又はミクロ)経済学、経営学、経済原論、経済政策、経済学史、財政学、国際経済論、金融論、貿易論、会計学、簿記学、商品学、農業経済、工業経済等が該当します。
また、履修した科目が法律学又は経済学に該当するかどうかが科目の名称から判定しかねる場合には、授業内容が記載されている学生便覧や担当教授の所属学部等が分かるものを取り寄せた後、各国税局人事第二課(沖縄国税事務所人事課)試験担当係へ御照会ください。
問16 法人(個人)の会計事務に従事していますが、受験資格はありますか。
(答)
法人又は事業を営む個人の会計に関する事務に従事した人のうち、貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて計理する会計に関する事務に通算して3年以上従事した人には、税理士試験の受験資格が認められます。
通算する期間には、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務、仕訳帳等から各勘定への転記事務、決算手続に関する事務、財務諸表の作成事務等に主に従事していた期間が含まれます。
これに対して、電子計算機を使用して行う単純な入出力事務など簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事務に従事していた期間は含まれません。
要件に該当する受験者は法人等の代表者又は人事責任者から、職歴証明書を発行してもらい、受験資格を証する書面として受験申込みの時に受験願書に添付してください。
職歴証明書の様式(ひな形)については、問18を参照してください。
問17 銀行(信託銀行)で貸付事務に従事していますが、受験資格はありますか。
(答)
銀行、信託会社、保険会社又は日本銀行等特別の法律により設立された金融業務を営む法人において、資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関して行う貸付先又は投資先の業務及び財産に関する帳簿書類の審査事務、並びにこれら審査事務を含む資金の貸付け又は有価証券に対する投資に関する事務に、通算して3年以上従事した人は、税理士試験の受験資格が認められます。
この場合、受験者は法人等の代表者又は人事責任者から、職歴証明書を発行してもらい、受験資格を有することを証する書面として受験申込みの時に受験願書に添付してください。
なお、証券会社やリース会社は金融業務を営む法人には該当しません。
職歴証明書の様式(ひな形)については、問18を参照してください。
問18 職歴証明書の様式を教えてください。
(答)
経理事務、税理士業務補助事務等に3年以上従事したことを受験資格とする方は、受験申込みの時に受験願書に「職歴証明書」を添付してください。
職歴証明書は、A4用紙を使って次の要領で会社等の代表者又は人事責任者から証明を受けてください。
まず、「証明書」と表題を書き、続けて、受験者の住所、氏名、生年月日を書いてください。
次に、いつからいつまでの期間にどのような事務に従事していたか、所属、役職及び事務内容を詳しく書いてください。
この事務内容は、経理一般等とせずに、経理のどの様な事務に従事していたか等、具体的な内容を書いてください。
そして、この事務内容等が変わった場合は、行を変え、同じように記載してください。
最後に「上記のとおり相違ないことを証明する。」旨の文言と、証明年月日を書き、会社等の所在地、電話番号、名称をつけて会社等の代表者又は人事責任者から署名と公印の捺印をしてもらってください。
○職歴証明書の様式(ひな形)
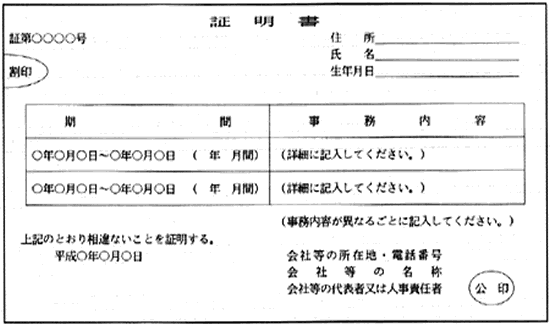
問19 受験資格を有することを証する書面に記載された氏名と現在の氏名が異なる場合には、どうすればよいのですか。
(答)
受験資格を有することを証する書面に記載されている氏名と現在の氏名が異なるときは、氏名を変更したことを証明する書類として、戸籍抄本等を添付して受験申込みをしてください。
なお、既に一部科目に合格している場合は、問38を参照して国税審議会会長あてに、改姓届を提出してください。
問20 外国の大学を卒業しましたが、受験資格はありますか。
(答)
外国の大学等で、法律学又は経済学を履修の上卒業した方は、申請により受験資格の認定が受けられる場合がありますので、次の書面を国税審議会会長あて提出してください。 提出先は、郵便番号100-8978東京都千代田区霞が関3-1-1 国税庁内 国税審議会会長あてです。
1 税理士試験受験資格認定申請書 (様式については、問21を参照してください)
2 住民票の写し(申請者本人分の抄本、外国人にあっては外国人登録済み証明書の写し)
3 卒業証明書(卒業した大学が証明したもの)
4 成績証明書(卒業した大学が証明したもの)
5 3及び4の和訳(申請者が和訳したもの)
6 大学等の紹介文(次の内容を申請者が適宜な書類に記載したもの。)
①正式名称(大学、学部、学科、専攻名)
②所在地
③設置根拠法令
④連絡先(電話番号)
⑤入学資格(入学の前提となる教育機関等)
⑥卒業要件(修業年限、必要単位数、必須科目と単位数等)
⑦卒業して得る資格(取得学位、上級学校への入学資格の有無、その他参考となる資格等)
(注1) 大学等の紹介文①~③については現地語により表記するとともに和訳し、④~⑦については和文で記載する。
(注2) 設置根拠法令とはその国において、日本国の学校教育法等に相当するものを指すが、一部の大学にあっては、個別の法令が設置根拠となっている場合があるので、その内容が分かるように和文で記載する。
(注3) 郵便番号及びあて先を明記し、所要額の切手(配達記録であれば330円、簡易書留であれば470円、書留であれば540円の切手)をはったA4判大の返信用封筒を同封する。
問21 受験資格認定申請書の様式を教えてください。
(答)
受験資格認定申請書の様式
(注) この受験資格認定申請書を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。
受験地・試験場について
問22 受験地を教えてください。
(答)
平成16年度第54回税理士試験は、札幌市、仙台市、川越市、朝霞市、東京都、金沢市、名古屋市、京都府、大阪府、広島市、高松市、福岡市、熊本市及び那覇市において行います。試験は、一つの受験地で受験してください。
なお、税理士試験受験願書受付後における受験地の変更は認めません。
問23 受験地は希望どおりになりますか。
(答)
受験地は、原則として受験者の希望を考慮しますが、受験者数等の状況に応じて近隣の受験地(例えば大阪府から京都府)に変更になる場合もあります。
問24 自分の試験場はいつ分かりますか。
(答)
試験場は、受験者に郵送(又は手渡し)する受験票に記載して通知します。
試験に使用できる文房具・計算機について
問25 試験に使用できる文房具を教えてください。
(答)
答案の作成には、必ず黒か青インキの万年筆又はボールペンを使用してください。
鉛筆や消しゴムで消せるボールペンなどの筆記具、赤インキのペン及び修正液(修正テープを含む。)は、使用できません。
なお、ホチキスの使用は認められます。
問26 試験に使用できる計算機を教えてください。
(答)
計算機は、次の4つの条件のすべてに該当する場合にのみ使用が認められます。
○
乾電池や、太陽電池で作動する電源内蔵式のものであること。試験場では、コンセントは使用できません。
○ 演算機能のみを有するものであること。紙に記録する機能、音が出る機能、プログラムの入力機能があるものは、その機能の使用のみならず、計算機全体が使用できません。(消費税の税込み、税抜き機能のみを有する電卓は使用可)
○ 数値を表示する部分がおおむね水平であるもの。表示窓が極端に横に倒れるものなどは使用できません。
○ 外形寸法がおおむね26センチメ-トル×18センチメ-トルを超えないものであること。つまり、おおむねB5判の紙からはみ出ない大きさの計算機を使用してください。
試験科目の免除について
問27 学位取得による試験科目の免除制度が改正されたと聞きましたが、改正後の制度はいつから適用されますか。
(答)
税理士法改正後の学位取得による試験科目の免除制度は、平成14年4月1日以降に大学院に進学した方について適用されます。
したがって、平成14年3月31日以前に大学院に進学した方については、税理士法改正前の制度が適用されます。
問28 平成14年4月1日以降に大学院に進学した場合の試験科目の免除制度について教えてください。
(答)
税理士法改正により、修士の学位等取得による試験科目の免除制度については、試験の分野(税法科目、会計学科目)ごとに、いずれか1科目(※注)の試験で基準点を満たした者(いわゆる一部科目合格者)が、自己の修士の学位等取得に係る研究について国税審議会の認定を受ける制度に改められました。国税審議会から認定を受けた場合には、税法科目であれば残り2科目、会計学科目であれば残り1科目にも合格したものとみなされて試験が免除されます。
(※
注) 税法科目にあっては、所得税法又は法人税法以外の科目でも構いません。また、試験合格の科目と研究の内容が同一(例えば、所得税法に合格した者が所得税法関係の研究をするなど)であっても構いません。
なお、研究等の内容や認定の基準については、「改正税理士法の『学位による試験科目免除』制度のQ&Aについて」を参照してください。
問29 平成14年3月31日以前に大学院に進学した者ですが、博士又は修士の学位取得により試験科目の免除を申請する場合の手続について教えてください。
(答)
過去に合格した科目や免除決定された科目を含めると、今回の学位取得(平成14年3月31日以前に大学院に進学)による免除申請で試験科目の全部が免除となる場合には、随時、国税審議会会長あて「全科目免除」の申請をしてください。
過去に合格した科目や免除決定された科目を含めても、今回の免除申請で試験科目の全部が免除とならない場合には、受験申込みと併せて(1科目以上の受験申込みをした上で)、「一部科目免除」の申請をしてください。
「全科目免除」の申請に必要な書面については、問30を参照してください。
「一部科目免除」の申請に必要な書面については、問31を参照してください。
問30 平成14年3月31日以前に大学院に進学した者ですが、博士又は修士の学位取得による「全科目免除」の申請に必要な書面について教えてください。
(答)
平成14年3月31日以前に大学院に進学し、博士又は修士の学位を取得した方が、「全科目免除」を申請する場合には、以下の書類を、随時、国税審議会会長あて提出してください。
提出先は、郵便番号100-8978東京都千代田区霞が関3-1-1 国税庁内 国税審議会会長あてです。
○
税理士試験免除申請書(様式及び記載方法については、問32参照)
○ 住民票(A4規格でないものはA4用紙にのりづけしてください。)
○ 学位取得証明書(A4規格でないものはA4用紙にのりづけしてください。)
○ 成績証明書(A4規格でないものはA4用紙にのりづけしてください。)
○ 学位論文の概要(A4判で12,000字~16,000字程度の分量にまとめ左とじしたものに学位論文の目次及び参考(引用)文献目録を添付する。)
○ 論文の内容についての指導教授の証明書(様式及び記載方法については問33参照)
○ 税理士試験等結果通知書又は一部科目合格(免除決定)通知書の写し(A4用紙にコピーしたもの)
○ 郵便番号・あて先明記のA4判大の返信用封筒【所要額の切手(配達記録であれば330円の切手、簡易書留であれば470円の切手、書留であれば540円の切手)をはってください。】
問31 平成14年3月31日以前に大学院に進学した者ですが、博士又は修士の学位取得による「一部科目免除」の申請に必要な書面について教えてください。
(答)
平成14年3月31日以前に大学院に進学し、博士又は修士の学位を取得した方が、「一部科目免除」の申請をする場合には、税理士試験の受験申込みと併せて(1科目以上の受験を申込みした上で、)以下の書類を提出してください。
○
学位取得証明書(A4規格でないものはA4用紙にのりづけしてください。)
○ 成績証明書(A4規格でないものはA4用紙にのりづけしてください。)
○ 学位論文の概要(A4判で12,000字~16,000字程度の分量にまとめ左とじしたものに学位論文の目次及び参考(引用)文献目録を添付する。)
○ 論文の内容についての指導教授の証明書(様式及び記載方法については問33参照)
問32 税理士試験免除申請書の様式と記載方法について教えてください。
(答)
税理士試験免除申請書の様式
(注) この税理士試験免除申請書を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。
○
「税理士法第11条第2項の規定により通知された科目」の欄には、過去の合格科目名と一部科目合格通知書番号を記入してください。
○ 「税理士法第8条の規定により受験を免除される科目」の欄には会計学の免除を申請する場合(過去に免除決定されている場合を含む。)には、「会計学に属する科目」と記入し、税法の免除を申請する場合(過去に免除決定されている場合を含む。)には、「税法に属する科目」と記入してください。
(記載例1)
・ 税法に属する科目・・・今回、学位の取得により免除を申請する
・ 会計学に属する科目・・・過去に試験により合格している
| 税理士法第11条第2項の規定により通知された科目 | 簿記論 財務諸表論 一部科目合格通知書番号 (○○○○○○) |
|---|---|
| 税理士法第8条の規定により受験を免除される科目 | 税法に属する科目 |
(記載例2)
・ 税法に属する科目・・・今回、学位の取得により免除を申請する
・ 会計学に属する科目・・・過去に学位の取得により免除されている
| 税理士法第11条第2項の規定により通知された科目 | 一部科目合格通知書番号 ( ) |
|---|---|
| 税理士法第8条の規定により受験を免除される科目 | 税法に属する科目 会計学に属する科目 |
問33 指導教授の証明書の様式と記載方法について教えてください。
(答)
指導教授の証明書の様式
(注) この指導教授の証明書を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。
○ 「学位」欄・・・「修士(法学)」、「修士(商学)」など学位取得証明書に記載してある学位名を記入する。
○ 「提出し の学位を」欄・・・同上
○ 「 学に属する」欄・・・ 「法律」、「財政」又は「商」のいずれかを記入する。(改正前の税理士法適用の場合)
○ 「 学指導教授」欄 ・・・「租税法」、「財政」、「会計」、「経営」など指導教授の専攻分野の名称を記入する
合格(免除決定)通知書の紛失について
問34 税理士試験等結果通知書又は一部科目合格(免除決定)通知書を紛失した場合には、どうすればよいのですか。
(答)
税理士試験等結果通知書、一部科目合格通知書及び一部科目免除決定通知書の再発行は行っておりません。これらの通知書を紛失された方で、税理士試験の受験申込みやその他の理由で証明が必要な方には「証明書」を発行しますので、「一部科目合格(免除)証明願」に必要事項を記入の上、住民票と80円切手をはった郵便番号・あて先明記の返信用封筒を同封して国税審議会会長あて請求してください。
「一部科目合格(免除)証明願」の様式については、問35を参照してください。
なお、税理士試験等結果通知書又は昭和61年度以降の一部科目合格通知書を所持している方は、それ以前の一部科目合格通知書を紛失していても受験の申込みや試験免除を申請する場合には不要ですので「証明願」の提出は必要ありません。
請求先は、郵便番号100-8978東京都千代田区霞が関3-1-1 国税庁内 国税審議会会長あてです。
問35 一部科目合格(免除)証明願の様式を教えてください。
(答)
一部科目合格(免除)証明願の様式 (注) この一部科目合格(免除)証明願を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。
なお、レポート用紙などのA4判の紙に以下の事項を記載して請求してもかまいません。
○ 一部科目合格(免除)証明願(表題)
○ 住所
○ 氏名とふりがな
○ 生年月日
○ 電話番号
○ 一部科目合格(免除)番号
○ 合格(免除)科目と合格(免除)年度
○ 使用目的
問36 合格証書(税理士試験免除決定通知書)を紛失した場合には、どうすればよいのですか。
(答)
合格証書(税理士試験免除決定通知書)の再発行は行っておりません。合格証書(税理士試験免除決定通知書)を紛失された方で、税理士登録等のために証明が必要な方には「証明書」を発行しますので、一部科目合格(免除)証明願(問35参照)の「一部」を「全部」に訂正し、必要事項を記入の上、住民票と80円切手をはった返信用封筒を同封して国税審議会会長あて提出してください。
請求先は、郵便番号100-8978東京都千代田区霞が関3-1-1 国税庁内 国税審議会会長あてです。
住所・氏名の変更について
問37 受験申込みをした後に住所を変更しましたが、何か手続は必要ですか。
(答)
税理士試験の受験を申込んだ後に試験結果の通知先を変える事情が生じた場合には、11月末までに国税審議会会長あてに「通知先変更届」を提出してください。また、旧住所地の郵便局へも転居届を忘れずに提出してください。
通知先変更届は次の例を参考に作成してください。
通知先変更届の提出先は、郵便番号100-8978東京都千代田区霞が関3-1-1 国税庁内 国税審議会会長あてです。
通 知 先 変 更 届
・
受験地 ○○○○
・ 受験番号 ○○○○○
(フリガナ) (○○○ ○○○)
・ 氏 名 ○○ ○○
・ 生年月日 昭和○年○月○日
・ 住所 新 〒○○○-○○○○
○○○○○○○
TEL○○○○-○○○○
旧 〒○○○-○○○○
○○○○○○○
TEL○○○○-○○○○
問38 結婚で姓が変わりましたが、何か手続は必要ですか。
(答)
姓が変わった場合は、国税審議会会長あてに「改姓届」に戸籍抄本等を添付して提出してください。
改姓届が必要な場合は、過去の試験で一部の科目に合格した方が改姓した時と、受験を申込んだ方が、その年の合格発表日までの間に改姓した時です。
改姓届の様式については、問39を参照してください。
改姓届の提出先は、郵便番号100-8978 東京都千代田区霞が関3-1-1 国税庁内 国税審議会会長あてです。
また、改姓とともに、住所も変更された方は、別途、通知先変更届(問37参照)も提出してください。
問39 改姓届の様式を教えてください。
(答)
改姓届の様式 (注) この改正届を利用する場合には、A4の用紙で提出してください。
なお、レポート用紙などのA4判の紙に以下の事項を記載して改姓届としてもかまいません。
○ 改姓届(表題)
○ 受験地(受験申込後合格発表までの間に提出する場合のみ記入)
○ 受験番号(受験申込後合格発表までの間に提出する場合のみ記入)
○ 一部科目合格(免除)通知書番号
○ 過去の合格(免除)済科目の有無
○ 新・旧両方の姓名とふりがな
○ 生年月日
○ 住所
○ 電話番号
合格発表について
問40 合格発表日はいつですか。
(答)
平成16年度第54回税理士試験の合格発表は、平成16年12月10日(金)に行います。
問41 合格者の発表方法を教えてください。
(答)
合格者の発表は、次のとおり行います。
○
合格科目が5科目に達した方・・・合格証書を郵送するとともに、合格発表の日の官報及び国税庁ホームページに氏名を掲載します。
○ 一部の科目に合格した方又は免除決定された方・・・税理士試験等結果通知書を郵送します。
○ 受験された方で、合格科目のない方・・・税理士試験結果通知書を郵送します。
なお、申込んだ科目をすべて欠席した方への試験結果の通知はありません。
問42 試験結果の通知が届かない場合には、どうすればよいのですか。
(答)
試験結果の通知書等が届かない場合には、平成16年12月17(金)以降に国税審議会事務局税理士試験担当あてに照会してください。
国税審議会事務局の電話番号は(代)03-3581-4161です。
(注)
試験結果の通知書等は、受験申込みの際に提出していただいた「宛名カード」に記載された住所地に送付しますので、通知先を変える事情が生じた場合には、国税審議会会長あてに「通知先変更届」(問37参照)を提出してください。
税理士登録について
問43 登録に必要な実務経験等や登録手続に関して教えてください。
(答)
税理士登録に必要な実務経験等、登録手続に関する質問は、日本税理士会連合会・登録課【電話03(5435)0938】にお問い合わせください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















