資料2004年03月27日 【税務通達等】 国税徴収法基本通達 第2章 国税と他の債権との調整
第2章 国税と他の債権との調整
第1節 一般的優先の原則
第8条関係 国税優先の原則
納税者の総財産
1 法第8条の「納税者の総財産」とは、納税者に帰属する財産で差押えが禁止されているものを除いたすべての財産をいうが、次に掲げる場合には、それぞれに掲げる財産に限定される。
(1) 法第24条((譲渡担保権者の物的納税責任))の規定により、譲渡担保権者を第二次納税者とみなして納税者の国税をその譲渡担保財産から徴収する場合には、その譲渡担保財産
(2) 法第36条第1号((実質課税額等の第二次納税義務))の規定により、国税の賦課の基因となった収益が生じた財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産(取得財産を含む。)
(3) 法第36条第2号((実質課税額等の第二次納税義務))の規定により、国税の賦課の基因となった資産の貸付けに係る財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産(取得財産を含む。)
(4) 法第37条((共同的な事業者の第二次納税義務))の規定により、納税者の事業の遂行に欠くことができない第二次納税義務者の重要な財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産(取得財産を含む。)
(5) 法第38条((事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務))の規定により、納税者からの事業譲渡により譲り受けた財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産(取得財産を含む。)
(6) 法第41条第1項((人格のない社団等に係る名義人の第二次納税義務))の規定により、納税者の財産で法律上第二次納税義務者に帰属するとみられる財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産
(7) 通則法第52条第1項((担保の処分))の規定により、物上保証人が提供した担保財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産
(8) 限定承認をした相続人が承継した被相続人の国税を徴収する場合には、その相続により取得した財産
別段の定め
2 法第8条の「別段の定」とは、法第2章((国税と他の債権との調整))に規定する事項のうち第9条から第11条まで((強制換価手続の費用等の優先))、第15条から第21条まで((法定納期限等以前に設定された質権の優先等))、第23条((法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等))及び第26条((国税及び地方税等と私債権との競合の調整))に規定されている事項をいう。
国税の優先徴収
(その他の債権)
3 法第8条の「その他の債権」とは、国税、地方税及び公課以外の債権で金銭の給付を目的とするものをいう。
(優先徴収)
4 法第8条の「先だって徴収する」とは、納税者の財産が強制換価手続により換価された場合に、その換価代金から国税を優先して徴収することをいう。
国税の優先徴収の例外
(法における優先徴収の例外)
5 法第59条第3項後段及び第4項((動産の前払賃料の優先配当))並びに第71条第4項((自動車等の前払賃料の優先配当等の準用規定))の規定により、これらに規定する前払借賃に相当する債権が国税(法10条の滞納処分費を除く。)に先立って配当されることがある。
(他の法律における優先徴収の例外)
6 法以外の法律の規定により、国税が地方税、公課その他の債権と同順位又は後順位になる場合として、次のものがある。
(1) 地方税法第14条の4((強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先))又は第14条の8((担保を徴した地方税の優先))の規定により、道府県たばこ税、市町村たばこ税又は軽油引取税等の地方税に後れて配当を受けることがある。
(2) 収容貨物が関税法の規定により公売又は随意契約により売却された場合には、同法第85条第1項((公売代金等の充当))の規定により、公売又は随意契約による売却に要した費用、収容に要した費用、収容課金及び関税が国税に優先する。
(注) 上記の場合においては、国税は質権又は留置権により担保される債権に先立って配当される(関税法85条2項)。
(3) 国税を徴収すべき外国貨物について、関税を徴収するための換価又は交付要求をした場合には、関税法第9条の4第1項及び第2項後段((徴収の順位))の規定により、関税が国税に優先する。
公課が徴した担保との関係
7 公課が担保を徴している場合における当該公課と国税との関係は、公課に関する法律が国税に劣後する旨の優先順位を規定しているにかかわらず、法第2章第3節から第5節まで((国税と被担保債権との調整等))に規定する私債権と国税との関係と同様に取り扱うものとする。
第9条関係 強制換価手続の費用の優先
交付要求
1 法第9条の「交付要求」とは、法第82条第1項((交付要求の手続))、第86条第1項((参加差押えの手続))、第159条第9項((保全差押えに係る交付要求))(通則法38条4項において準用する場合を含む。)、滞調法第36条の10第1項((みなし交付要求))及び通則法第39条第3項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の交付要求をいう。
配当すべき金銭
2 法第9条の「配当すべき金銭」とは、それぞれ次に掲げる金銭をいう。
(1) 滞納処分(法5章)、滞納処分の例による処分、国税滞納処分の例による処分、国税徴収の例による処分、市町村税の滞納処分の例による処分等の場合は、法第129条第1項((配当の原則))の換価代金等又はこれに準ずる金銭(第128条関係5参照)
(2) 不動産、船舶、航空機、自動車及び建設機械に係る強制執行又は担保権の実行としての競売の場合は、その売却代金(執行法86条1項1号、121条、188条、189条、192条、193条、航空法8条の4第2項、道路運送車両法97条2項、建設機械抵当法26条2項、執行規則84条、97条、98条、175条から177条まで)
なお、上記の売却代金には、次のものが含まれる。 イ 差押債権者が、競売手続の取り消されることを回避するため提供した保証(手続費用及び優先債権の見込額を超える額で差押債権者が申し出た額と最低売却価額との差額)がある場合には、その申出額から現実に売却された売却代金の額を控除した額(執行法86条1項2号、63条2項2号) 〔例〕 最低売却価額・・・・・・・・・・・・・・・・・・110万円
執行費用及び優先債権額・・・・・・・・130万円
申出額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131万円
提供した保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21万円
売却代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120万円
この場合には、売却代金120万円のほか、提供した保証21万円のうち11万円(131万円-120万円)も売却代金となる。
ロ 買受人が買受代金を納付しないことにより売却決定が取り消された場合(執行法80条参照)には、買受人が提供した保証(同法86条1項3号)
(3) 動産に係る強制執行又は担保権の実行としての競売の場合は、売得金、差押金銭又は手形等の支払金(執行法139条1項、192条)
(4) 債権及びその他の財産権に係る強制執行又は担保権の実行としての競売の場合は、次に掲げるもの(執行法166条1項、193条2項) イ 第三債務者が供託した場合(同法166条1項、2項、157条5項参照)供託金
ロ 売却命令により売却した場合売得金
ハ 動産の引渡請求権の執行としてその引渡しを受け売却した場合(同法163条2項参照)売得金
(5) 強制管理の場合は、執行法第98条第1項((債務者に対する収益等の分与))の規定による分与をした後の収益又はその換価代金から、不動産に対して課される租税その他の公課及び管理人の報酬その他の必要な費用を控除した金銭(同法106条1項)
(6) 農業用動産抵当権実行令の規定による競売の場合は、その売得金(同令1条、執行法139条1項、192条)
(7) 企業担保権の実行手続の場合は、売却代金と企業担保権の目的となる会社の金銭(管財人が費用及び報酬に充てた金銭を含む。)との合計額に相当する金銭(企業担保法52条)
(8) 鉄道抵当法第3章((強制競売及強制管理))、軌道ノ抵当ニ関スル法律又は運河法の規定による強制競売の場合は、その競落代金(鉄道抵当法68条、71条、77条ノ2、軌道ノ抵当ニ関スル法律1条、運河法13条)
(9) 鉄道抵当法第3章、軌道ノ抵当二関スル法律又は運河法の規定による強制管理の場合は、その鉄道財団、軌道財団又は運河財団の収入に係る金銭(鉄道抵当法87条等)
手続に係る費用
3 法第9条の「手続に係る費用」とは、それぞれ次に掲げるものをいう。
(1) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)の場合には、法第136条((滞納処分費の範囲))に規定する費用又はこれに準ずる費用
(注) 上記の「これに準ずる費用」としては、地方税の督促手数料がある(地方税法14条の3参照)。
(2) 強制執行の場合は、強制執行の準備費用としての執行文の付与、判決の送達、判決確定証明書の付与(裁判上の費用)、執行の申立てをするため出頭するに必要な旅費(裁判外の費用に限る。)等の費用と強制執行の開始によって生じた費用としての執行官の手数料、立替金、鑑定費用、保証供与の費用、差押財産の保存費用等(執行法42条1項参照)
(3) 担保権の実行としての競売の場合又は企業担保法による企業担保権の実行手続の場合は、(2)に準ずる費用(執行法194条及び企業担保法17条において準用する執行法42条参照)
(4) 鉄道抵当法、軌道ノ抵当二関スル法律又は運河法の規定による強制競売又は強制管理の場合は、(2)に準ずる費用(鉄道抵当法68条1項等参照)
(5) 破産手続の場合は、破産法第47条第1号((財団債権の範囲))に規定する裁判上の費用、第3号に規定する管理、換価及び配当に関する費用(破産管財人の報酬を含む。昭利45.10.30最高判)、同法第70条第1項ただし書((強制執行等の失効の特例))の規定により破産管財人が破産財団のために強制執行等の手続を続行する場合の費用(同法70条2項参照)
費用の優先権
4 法第9条の「次いで徴収する」とは、納税者の財産が強制換価手続により換価された場合に、その執行機関にした交付要求に係る国税は、その換価代金からその手続の費用に次いで徴収することをいう。したがって、その手続の費用は、交付要求に係る国税(滞納処分費を含む。)に優先して徴収する。
強制換価手続の費用が優先しない場合
(強制管理)
5 不動産の強制管理の場合には、執行法第106条第1項((配当等に充てるべき金銭等))の規定により不動産に対して課させる租税は、管理の費用に先立って弁済を受ける。
(破産)
6 破産手続の場合において破産財団が財団債権の総額を弁済するに不足することが明らかになったときは、破産法第51条第1項((財団不足の場合の弁済方法))の規定により、財団債権である破産手続上の費用(破産管財人の報酬を除く。)と財団債権である国税とは平等弁済を受ける。
第10条関係 直接の滞納処分費の優先
滞納処分による換価
1 法第10条の「滞納処分により換価」とは、公売(法94条、107条)、随意契約による売却(法109条、110条)、差押債権(法53条1項の保険金等の支払を受ける権利を含む。)又は差押有価証券若しくは差押無体財産権等に係る債権の取立て(法67条1項、57条1項、73条5項、74条)及び国税滞納処分の例による処分(通則法52条1項、53条)としての換価をいう。
滞納処分費の優先
(滞納処分に係る滞納処分費)
2 法第10条の「その滞納処分に係る滞納処分費」とは、納税者の財産につき滞納処分による換価をした場合において、その換価の目的となった財産についての滞納処分費(法136条)で、その換価の基因となった国税についての滞納処分費をいう。 〔例1〕 甲国税によりA財産とB財産とを差し押さえ、A財産についてだけ換価した場合には、A財産についての滞納処分費だけが法第10条の滞納処分費に該当し、B財産についての滞納処分費は、法第10条の滞納処分費には該当しない。
〔例2〕 甲国税によりA財産を差し押さえ、乙国税により当該差押えに対し交付要求をした場合の交付要求に係る国税の滞納処分費は、法第10条の滞納処分費には該当しない。
(前払借賃に対する滞納処分費の優先)
3 法第26条第1号((国税及び地方税等と私債権との競合の調整))、第59条第3項後段及び第4項((動産の前払賃料の優先配当))並びに第71条第4項((自動車等の前払賃料の優先配当等の準用規定))の規定においては、滞納処分がされた財産を占有していた第三者の有する前払借賃に相当する債権の配当順位が、その滞納処分に係る滞納処分費に次ぐものとして定められている。
第11条関係 強制換価の場合の消費税等の優先
消費税等
1 法第11条の「消費税等(その滞納処分費を含む。)」には、課税資産の譲渡等に係る消費税並びにその附帯税及び滞納処分費は含まれない。
優先徴収
(移出)
2 法第11条の「移出」とは、それぞれ次に掲げる場合の移出をいう。
(1) 酒税法第6条の3第1項第4号((酒類等の製造場に現存する酒類等が公売等により換価された場合のみなし移出))の規定に該当する場合
(注) 酒税法第28条第1項((未納税移出))の規定の適用を受けて酒類製造者が酒類の製造場から移出する酒類については、上記に該当することはない(同法6条の3第1項ただし書)。
(2) 揮発油税法第5条第3項((揮発油の製造場に現存する揮発油が公売等により換価された場合のみなし移出))の規定に該当する場合(地方道路税法7条1項参照)
(3) 地方道路税法第7条第1項((徴収))の規定により揮発油税に併せて徴収する地方道路税についは、その揮発油について揮発油税法第5条第3項の規定に該当する場合(地方道路税法5条1項参照)
(4) 石油ガス税法第5条第3項((石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスが公売等により換価された場合のみなし移出))の規定に該当する場合
(5) 石油税法第5条第3項((石油の採取場に現存する石油が公売等により換価された場合のみなし移出))の規定に該当する場合
(公売又は売却)
3 法第11条の「公売若しくは売却」とは、それぞれ次に掲げる場合の公売又は売却をいう(輸徴法8条1項2号、6号)。
(1) 関税法第84条第1項((収容貨物の公売))又は第3項((収容貨物の随意契約による売却))の規定により、公売又は随意契約による売却をする場合
(2) 関税法第134条第5項((領置物件又は差押物件の公売又は随意契約による売却))の規定により、公売又は随意契約による売却に係る代金を還付する場合
(換価代金)
4 法第11条の「換価代金」とは、それぞれ次に掲げるものをいう。
(1) 通則法第39条((強制換価の場合の消費税等の徴収の特例))の規定を適用する場合にあっては、同条第1項の売却代金
(2) 関税法第84条第1項((収容貨物の公売))又は第3項((収容貨物の随意契約による売却))の規定により公売又は随意契約による売却をする場合にあっては、その公売代金又は売却代金
(3) 関税法第134条第5項((領置物件又は差押物件の公売又は随意契約による売却))の規定により還付する場合にあっては、その還付に係る公売代金又は売却代金
徴収の手続
5 法第11条を適用する場合における徴収の手続については、次のことに留意する。
(1) 通則法第39条((強制換価の場合の消費税等の徴収の特例))の規定により徴収する場合には、同条第2項の規定により、執行機関及び納税者に対し、徴収すべき税額その他必要な事項を書面により通知しなければならない(国税通則法施行令(以下「通則令」という。)10条)。この通知の様式は、別に定めるところによる。
(注) 上記の通知は、強制換価手続により換価に付される物品に係る消費税等(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)の納税地を所轄する税務署長が行う(酒税法30条の2第1項等)。
(2) 輸徴法第8条第1項第2号又は第6号((公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収))の規定により徴収する場合には、通則法第36条第1項((納税の告知))の規定による納税の告知をする必要がない(輸徴法8条3項)。
第12条関係 差押先着手による国税の優先
差押先着手による優先
(交付要求)
1 法第12条第1項の「交付要求」とは、法第82条第1項((交付要求の手続))、第86条第1項((参加差押えの手続))、第159条第9項((保全差押えに係る交付要求))(通則法38条4項において準用する場合を含む。)、地方税法第68条第4項((法人等の道府県民税に係る交付要求))、第72条の68第4項((事業税に係る交付要求))等の規定による交付要求をいう。
(法第9条との関係)
2 法第12条第2項の「第9条(強制換価手続の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く」とは、強制換価手続の費用の一般的優先は、法第9条で既に規定されているので、重複して規定することを避けることを明らかにしたものである。
(劣後徴収)
3 法第12条第2項の「次いで徴収する」とは、納税者の財産が国税又は地方税により差し押さえられた場合に、その執行機関に交付要求をした国税は、その換価代金につき、その差押えに係る国税又は地方税に劣後して徴収することをいう。
差押先着手が適用されない場合
4 法第11条((強制換価の場合の消費税等の優先))、第14条((担保を徴した国税の優先))、地方税法第14条の4((強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先))、第14条の8((担保を徴した地方税の優先))の規定の適用がある場合には、法第12条の規定は適用されない。
(注) 譲渡担保財産について、譲渡担保権者の国税により差押えがされ、その差押えに対し譲渡担保の設定者の国税により交付要求がされた場合には、その設定者の国税を優先して徴収するため、当該差押えを交付要求とみなし、交付要求を差押えとみなすことになっている(国税徴収法施行令(以下「令」という。)9条1項前段)。
第13条関係 交付要求先着手による国税の優先
交付要求先着手による優先
(交付要求)
1 法第13条の「交付要求」は、第12条関係1に掲げる交付要求のほか、滞調法第36条の1O第1項((みなし交付要求))に規定する交付要求が含まれる。
(交付要求の競合)
2 納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税又は地方税の交付要求が競合した時のその優先順位は交付要求のされた時の順位による。
なお、上記の交付要求のされた時とは、滞納処分にあっては、その行政機関等に交付要求書又は参加差押書が送達された時をいい、送達時が同時である場合には、これらの交付要求に係る国税及び地方税は同順位になるものとする。
この同順位の場合における国税及び地方税に配当する金額は、債権現在額申立書に記載されている税額によりあん分計算したところによる。
交付要求先着手が適用されない場合
3 法第11条((強制換価の場合の消費税等の優先))、第14条((担保を徴した国税の優先))、地方税法第14条の4((強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先))、第14条の8((担保を徴した地方税の優先))の規定の適用がある場合には、法第13条の規定は適用されない。
(注)1 譲渡担保財産について行った譲渡担保の設定者の国税の交付要求は、譲渡担保権者の国税又は地方税の交付要求に後れていても、譲渡担保の設定者の国税を優先して徴収するため、譲渡担保の設定者の交付要求は、先にされたものとみなされる(令9条2項前段)。
2 滞調法第1O条第3項((強制執行続行の決定があった場合の交付要求))(11条の2,17条、19条、20条の8節1項、20条の1O又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(以下「滞調令」という。)12条の2等において準用する場合を含む。)の規定による交付要求に係る国税については、法第12条((差押先着手による国税の優先))の規定が適用される(滞調法10条4項、17条、19条、20条の8第1項、20条の10、滞調令12条の2等)。
第14条関係 担保を徴した国税の優先
担保財産があるとき
(担保提供に関する規定)
1 国税についての担保の提供に関する法律の規定としては、おおむね次に掲げるものがある。
(1) 納税の猶予、納期限の延長等の場合
通則法第46条第5項((納税の猶予の場合の担保の徴取))、租税特別措置法第70条の4第1項((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予))、第70条の6第1項((農地等についての相続税の納税猶予))、通則法第52条第6項((納税の猶予等の保証人についての準用))、法第32条第3項((納税の猶予等の第二次納税義務者についての準用))、第152条((換価の猶予に係る分割納付、通知等))、消費税法第51条((引取りに係る課税貨物についての納期限の延長))、酒税法第30条の6((納期限の延長))、たばこ税法第22条((納期限の延長))、揮発油税法第13条((納期限の延長))、地方道路税法第8条第1項((担保の提供))、石油ガス税法第20条((納期限の延長))、租税特別措置法第41条の8第1項((山林を現物出資した場合の納期限の延長))、所得税法第132条第1項((延払条件付譲渡に係る所得税額の延納))、相続税法第38条第4項((相続税及び贈与税の延納の場合の担保の提供))
(2) 保全担保の提供命令の場合
法第158条第1項及び第4項((保全担保の提供命令))、酒税法第31条第1項前段((保全担保の命令))、たばこ税法第23条第1項((保全担保の提供命令))、揮発油税法第18条第1項((保全担保の提供命令))、地方道路税法第8条第2項((保全担保の提供命令))、航空機燃料税法第16条第1項((保全担保の提供命令))、石油ガス税法第21条第1項((保全担保の提供命令))、石油税法第19条((保全担保の提供命令))、印紙税法第15条第1項((保全担保の提供命令))
(3) 繰上保全差押え等の場合
通則法第38条第4項((繰上保全差押えの場合の法159条4項の準用))、法第159条第4項((保全差押えの場合の担保提供))
(4) その他特殊な場合
通則法第51条第1項((増担保の提供命令等))、第105条第3項及び第5項((不服申立てをした者の担保の提供))、輸徴法第7条第6項((内国消費税の納付前に郵便物を受け取る場合の担保の提供))、第9条第2項((輸入の許可前における引取りの場合の内国消費税額に相当する担保の提供))、第10条第2項((保税工場外における保税作業の場合の内国消費税額に相当する担保の提供))、第11条第2項((保税運送等の場合の内国消費税額に相当する担保の提供))、第13条第2項((内国消費税を免除する場合の内国消費税額に相当する担保の提供))
(担保財産)
2 法第14条の「担保財産」とは、通則法第50条第1号から第5号まで((担保の種類))に掲げる財産で、国税に関する法律の規定により担保として提供された財産、法第158条第4項((保全担保))の規定により抵当権を設定したものとみなされた財産又は輸徴法第14条第2号及び第3号((担保の種類))に掲げる財産で、同法の規定(9条2項、10条2項、13条2項)により担保として提供された財産をいい、物上保証として提供された第三者の財産が含まれる。
なお、法第14条の「担保財産」には、民法第372条((他の担保物権の規定の準用))又は第350条((留置権等の規定の準用))の物上代位の規定により担保権の効力が及んだ財産が含まれる。
他の法律等との関係
(酒税法第34条との関係)
3 酒税法第31条第1項((酒類の保存))の規定により保存された酒類については、法第14条の規定が準用される(酒税法34条3項)。
(法第11条との関係)
4 担保を徴した国税は、法第11条(強制換価の場合の消費税等の優先)の規定により、強制換価の場合の消費税等(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)に劣後する。
(関税法第9条の4との関係)
5 関税が納付されていない外国貨物について滞納処分があった場合において、その外国貨物に係る関税と外国貨物を担保に徴している国税とが競合したときは、関税法第9条の4((徴収の順位))の規定により、外国貨物を担保に徴しているその国税はその関税に劣後する。
(民法等との関係)
6 法第14条又は地方税法第14条の8((担保を徴した地方税の優先))の規定の適用を受ける国税又は地方税が2以上ある場合におけるその国税又は地方税の優先順位は、それぞれの担保権の順位によるものとする(民法373条等)。
(注) 抵当権により担保される国税と他の国税との関係においては、被担保債権となる利息等の範囲を規定する民法第374条((被担保債権の範囲))の適用はないことに留意する((第82条関係3の(2)参照))。
担保を徴した国税の優先
7 法第14条の規定により、担保を徴した国税が、他の国税及び地方税に先立って徴収することができるのは、担保財産を通則法第52条((担保の処分))の規定に基づき滞納処分の例により処分した場合又は担保財産につき強制換価手続が行われた場合である。
先順位の担保権との関係
(担保財産が納税者に帰属する場合)
8 国税につき徴している納税者の担保財産(国税のための担保権の設定時において第三者に帰属していたものを除く。法17条、23条3項参照)に先順位の質権若しくは抵当権が設定されているとき又は担保のための仮登記(法23条1項に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)がされているときは、その被担保債権は、国税の法定納期限等(法15条1項参照)後に設定又は登記されたものに限り、国税に劣後する。
(担保財産が第三者に帰属する場合)
9 国税につき徴している第三者の担保財産(担保権の設定時において納税者に帰属していたものを含む。法22条参照)に先順位の質権若しくは抵当権が設定されているとき又は担保のための仮登記がされているときは、その被担保債権は、その国税に優先する。
第3節 国税と被担保債権との調整
第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先
法定納期限等
(第1号の法定納期限等)
1 法第15条第1項第1号に規定する法定納期限等については、次のことに留意する。
(1) 法定納期限以前に発せられる更正通知書若しくは決定通知書又は法定納期限以前に提出された期限後申告書又は修正申告書(例えば、法定申告期限が5月31日でその法定納期限が6月30日である石油ガス税について、6月1日に発した決定通知書又は6月15日に提出された修正申告書。石油ガス税法16条1項、18条1項参照)は、法第15条第1項第1号の更正通知書等には該当しない。
(2) 法第15条第1項第1号の「納税告知書を発した日」とは、通則法第36条第2項((納税告知書の送達等))の規定による納税告知書を発した日をいい、賦課決定通知書により確定した国税についても、その通知書を発した日ではなく、その国税に係る納税告知書を発した日が法第15条第1項第1号の法定納期限等に該当する。
(注) 法第15条第1項の「発した日」とは、更正通知書等を交付送達又は郵便による送達のため税務署から持って出た日(私設郵便差出箱に差し入れたときは、その差し入れた日)をいう。
また、公示送達による場合の「発した日」とは、通則法第14条第2項((公示送達の掲示))の規定による掲示を始めた日をいう。
(3) 賦課決定通知書と納税告知書とを発することとされている場合において、賦課決定通知書による国税の確定がその法定納期限以内であるときは、納税告知書を発した日が法定納期限後であっても、その告知に係る国税は、法第15条第1項第1号の国税には該当しない。
(注)1 法定納期限以前に賦課決定通知書により確定する国税には、揮発油税法第12条第2項((みなし移出等に係る揮発油についての揮発油税の徴収))等の規定によるものがある。
2 国税に関する法律の規定により、一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税のうち、賦課課税方式による国税(例えば、酒類、酵母、もろみの密造者、密造酒類を不法に所持し、譲渡し又は譲り受けた者、保存酒類又は検定前の酒類を処分し又は製造場から移出した者その他酒税法に違反した者に課される酒税(酒税法54条5項、56条3項))の確定は、すべて法定納期限後である。
(4) 再評価税が法定納期限後に更正又は決定により確定した場合には、更正又は決定の通知書を発した日ではなく、納税告知書を発した日が、その法定納期限等となる(資産再評価法71条4項)。
(5) 法第15条第1項第1号の「申告があった日」については、通則法第22条((郵送に係る納税申告書の提出時期))の規定により期限後申告書又は修正申告書が郵便物通信日付印により表示された日等に提出されたものとみなされる場合でも、換価代金の配当等に当たっては、これらの申告書が税務署に現に提出された日を法定納期限等として取り扱うものとする。
なお、期限後に提出された納税申告書が、通則法第22条の規定により、期限内に提出されたものとみなされた場合には、法定納期限後に納付すべき額が確定したものではないが、当該申告に係る国税の法定納期限等については、上記に準じて取り扱う。
(第2号の法定納期限等)
2 法定納期限前に通則法第38条第1項((繰上請求))の規定により繰上請求がされた国税の法定納期限等は、繰上請求書(又は納税告知書)により指定された納期限である。
(注) 法第15条第1項第3号の第二期分の所得税について繰上請求をした場合における第二期分の所得税の法定納期限等は、その繰上げに係る納期限と第一期分の所得税の納期限との、いずれか早い方の納期限である。
(第3号の法定納期限等)
3 通則法第11条((災害等による期限の延長))の規定により、第一期分の所得税の納期限の延長が認められた場合には、その延長された期限が、法第15条第1項第3号の納期限となる。
(第5号の2の法定納期限等)
4 法第15条第1項第5号の2の「その納付があった日」を法定納期限等とする国税は、同号の国税に係る附帯税及び滞納処分費に限られる。
(第6号の法定納期限等)
5 譲渡担保権者に対する告知又は法第159条第1項((保全差押え))若しくは通則法第38条第4項((保全差押えの規定の準用))の規定による差押えを受ける者に対する保全差押金額若しくは繰上保全差押金額(以下5において「保全差押金額等」という。)の通知に係る国税の法定納期限等は、次に掲げるところによる。
(1) 法第24条第2項((譲渡担保権者に対する告知等))の規定により金額の国税に係る法定納期限等は、法第24条第2項前段又は第4項後段((譲渡担保権者に対する告知等))の規定に基づく告知書を発した日である。
(2) 法第159条第3項((保全差押金額の通知))又は通則法第38条第4項((保全差押えの規定の準用))の規定により通知した金額の国税に係る法定納期限等は、これらの規定による通知書を発した日である。
(3) 保全差押金額等の納付すべき国税の額が確定していない場合でも、その保全差押金額等の国税があるものとして、法第15条第1項第6号の規定を適用するものとする。
(4) 国税の額が保全差押金額等を超えて確定した場合におけるその超える額に相当する国税の法定納期限等については、法第15条第1項第6号の規定の適用がない。
(第7号の法定納期限等)
6 法第15条第1項第7号に規定する法定納期限等については、次のことに留意する。
(1) 相続人(包括受遺者及び死因贈与(民法554条)により包括名義の贈与を受けた者を含む。以下同じ。)には、相続(包括遺贈及び包括名義の死因贈与を含む。以下同じ。)の放棄をした者は含まれない(同法939条)。
(注) 上記の「包括受遺者」とは、相続人以外の者で遺言によって遺産の全部又はその何分の一という割合によってその一部を与えられた者をいい(民法964条)、「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいい、その法律上の取扱いは、遺贈に関する規定に従う(同法554条)。
(2) 相続があった日とは、被相続人(包括遺贈者及び死因贈与により包括名義の贈与をした者を含む。以下同じ。)が死亡した日(民法882条)又は失そう宣告により死亡したとみなされた日(同法31条)をいい、包括遺贈の場合は、遺贈が無条件であれば遺言者が死亡した日、停止条件付であればその条件成就の日をいう。
(注) 上記の「死亡した日」については、民法第32条ノ2((同時死亡の推定))の規定がある。
(3) 破産宣告があった場合において、破産法第42条((相続財産破産における相続債権者の優先))、第43条((相続人の破産における相続債権者と固有債権者の順位))又は第44条((相続人の固有債権者の優先))の規定により、国税が私債権に劣後することとなるときは、法第15条第1項第7号の規定の適用はない。
(第8号の法定納期限等)
7 法第15条第1項第8号に規定する法定納期限等については、次のことに留意する。
(1) 「合併により消滅した法人」とは、吸収合併により消滅した法人及び新設合併により解散した法人をいう。
(2) 「合併後存続する法人」とは、吸収合併により他を吸収して存続する法人をいい、合併により設立した法人は含まれない。
(3) 「その合併のあった日」とは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人が、合名会社、合資会社、株式会社又は有限会社であるときは、その法人が本店所在地において変更の登記又は設立の登記をした日をいう(商法101条、102条、147条、414条1項、416条1項、有限会社法62条、63条参照)。
(4) 「合併のあった日前にその納付すべき税額が確定したもの」は、通則法第15条第3項第2号から第4号まで及び第6号((納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税))に掲げる国税については、合併のあった日前に納税告知書を発したものに限られる(法15条1項7号)。
(附帯税及び滞納処分費の法定納期限等)
8 附帯税及び滞納処分費の法定納期限等は、その附帯税及び滞納処分費の納付又は徴収の基因となった国税の法定納期限等である(法2条10号ニ、15条1項本文)。
(連帯納付義務に係る相続税等の法定納期限等)
9 相続税法第34条((連帯納付の義務))に規定する連帯納付義務に係る相続税又は贈与税の法定納期限等は、本来の納税者の相続税又は贈与税に係る法定納期限等と同じである(昭和55.7.1最高判参照)。
(通則法第5条第3項の納付責任に係る国税の法定納期限等)
10 通則法第5条第3項((相続による国税の納付義務の承継))に規定する納付責任に係る国税を相続財産から徴収する場合における当該国税の法定納期限等は、相続により承継した本来の国税の法定納期限等と同じである。
(物納の撤回に係る相続税の法定納期限等)
11 物納の撤回に係る相続税の法定納期限等は、相続税法施行令第19条の4第4項((物納の撤回の手続及び承認))に規定する書面を発した日である(同令19条の4第8項)。
質権の優先
(質権)
12 法第15条の「質権」とは、民法第342条((質権の内容))に規定する質権(根質権を含む。)をいい、動産質、不動産質及び権利質がある。
なお、上記の「質権」には、仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)がされた質権が含まれ、また、仮登記には、民事保全法(以下「保全法」という。)第53条第2項((不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行))(同法54条((不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行))において準用する場合を含む。)の限定による仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)が含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。
(質権を設定している場合)
13 法第15条第1項の「質権を設定している場合」には、納税者に対する債権について納税者の財産の上に質権を設定している場合のほか、納税者以外の者に対する債権について納税者の財産の上に質権を設定している場合(納税者が物上保証人となっている場合等)も含まれる。
(法定納期限等以前の設定)
14 法第15条第1項の「法定納期限等以前」には、その法定納期限等に当たる日を含む。したがって、その日に設定された質権も、法定納期限等以前に設定された質権となる。
(物上代位との関係)
15 質権は、その目的物が滅失等した場合の物上代位の目的物についても、優先権を行使することができる(民法350条、昭和31.11.26神戸地判参照)。ただし、このためには、物上代位の目的物が納税者に払渡し又は引渡しされる前に差し押さえることが必要である(民法304条1項ただし書、350条。法53条2項参照)。
(物上代位の目的物に対する差押えが競合する場合の優先関係)
16 質権の物上代位の目的物に対する差押えと当該目的物に対する滞納処分による差押えとが競合した場合における優先関係は、質権の設定と差押国税の法定納期限等との先後により判定する(昭和56.3.30東京高判)。
債権額の範囲
(質権の目的物の価額)
17 法第15条の「換価代金」には、質権の設定された財産のほか、従物、付加物、利息債権等質権の効力の及んでいるものの換価代金も含まれる。
(質権によって担保される債権額)
18 質権により担保される債権額の範囲は、民法第346条((被担保債権の範囲))の規定により、設定行為に別段の定めのない限り、元本のほか、利息、違約金、質権実行の費用、質物保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れたかしによって生じた損害の賠償金の一切に及ぶ。
なお、不動産質権により担保される債権額の範囲については、第16条関係6及び7と同様である(民法361条)。
登記又は登録をすることができる債権
(登記をすることができる質権)
19 法第15条第2項の「登記をすることができる質権」とは、土地、建物等を目的とする質権、地上権等を目的とする質権その他登記が第三者に対する対抗要件となっている質権をいう。
(登録をすることができる質権)
20 法第15条第2項の「登録をすることができる質権」とは、無体財産権質、電話加入権質、記名国債質、記名社債質その他登録が第三者に対する対抗要件又は効力要件となっている質権をいう。
有価証券
21 法第15条第2項の「有価証券」は、第56条関係13と同様である。
証明
(証明の必要)
22 法第15条第1項の規定の適用を受けるためには、質権者は、登記(登録を含む。以下同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その設定の事実を証明しなければならない(法15条2項)。
なお、19及び20の質権については、証明を要せず、徴収職員は、その質権の設定の事実を確認しなければならない。
(転質がある場合の証明)
23 民法第348条((転質権))の規定に基づく転質権者が、原質権につき法第15条第2項の証明をしたときは、法第15条第2項の質権者がその設定の事実を証明した場合に当たるものとする。
(証明の期限)
24 質権の証明は、次に掲げる日までにしなければならない(令4条3項)。
なお、証明の期限については、通則法第10条第2項((期限の特例))の規定の適用がない(通則令2条7号)。
(1) 債権を目的とする質権の証明その債権の第三債務者から給付を受けた金銭の配当計算書を作成する日の前日
(2) 有価証券に係る金銭債権を取り立てる場合のその有価証券を目的とする質権の証明 給付を受けた金銭の配当計算書を作成する日の前日
(3) その他の質権の証明 滞納処分に係る売却決定をする日の前日
(証明の方法)
25 滞納処分の場合における質権の証明は、次に掲げる方法によってしなければならない。
(1) 登記をすることができる質権以外の質権(有価証券を目的とする質権を除く。)の設定の事実の証明税務署長に対し、26から28までに定める証書のいずれかを提出すること又はそれらの証書を呈示するとともにその写しを提出すること(令4条2項)。
(2) 有価証券を目的とする質権(登録をすることができる質権を除く。)の設定の事実の証明 税務署長に対し、質権設定の事実を証する書面又はその事実を証するに足りる事項を記載した書面を提出すること(令4条1項)。
(公正証書)
26 法第15条第2項第1号の「公正証書」とは、公務員がその権限に基づき適法に作成した証書をいい、判決書、公証人の作成した公正証書及びこれらの謄本等がある。
(私署証書)
27 「私署証書」とは、私文書をいい、公正証書以外の文書はすべて私署証書であって、当事者の作成したものであるか、第三者の作成したものであるか、作成者の署名押印があるかどうかを問わないが、法第15条第2項第2号の「私署証書」とは、例えば、登記所又は公証人が認証し、その認証の年月日等の記載がされた契約書等をいう。 (注) 登記所は、当事者の請求に基づき私文書である「担保差入書」等に確定日付のある印章を押し(民法施行法5条2号)、確定日付簿にその旨を記入することとされている(確定日付簿及び日附印章調整規則参照)。
(内容証明を受けた証書)
28 法第15条第2項第3号の「内容証明を受けた証書」とは、郵便法第63条((内容証明))の規定により、内容証明を受けた文書をいう。
(確認)
29 質権の設定が法定納期限等以前であるかどうかについては、徴収職員が調査の上確認しなければならない。
質権設定の時期
(登記をすることができる質権)
30 登記をすることができる質権の設定の時期は、その質権の設定登記の日による。
(仮登記のある場合)
31 質権設定の仮登記又は質権設定請求権保全の仮登記がされた後において、その仮登記に基づく本登記(本登録を含む。以下同じ。)がされたときのその質権の設定の時期は、その仮登記がされた日によるものとする。
(登記をすることができる質権以外の質権)
32 登記をすることができる質権以外の質権(有価証券を目的とする質権を除く。)の設定の時期は、それぞれ次に掲げる日による(法15条3項)。ただし、その質権がその対抗要件を備えた日が次に掲げる日より遅いときは、その対抗要件を備えた日を法第15条の質権の設定の時期とする。
(1) 公正証書については、その日付の日
(2) 登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書については、その印章の日付の日
(3) 内容証明を受けた証書については、郵便局のその通信日付(郵便規則109条)の日
(有価証券を目的とする質権)
33 登録をすることができる質権以外の質権のうち、有価証券を目的とする質権の設定の時期は、質権者がその有価証券を占有した日による。
優先権行使の否認
(第4項の趣旨)
34 法第15条第4項は、国税に優先する質権者(登記をすることができる質権以外の質権を有する者に限る。)が2人以上ある場合において、先順位質権者が法第15条第2項の質権設定の証明をしなかったためその質権が国税に劣後することとなるときは、私法上の質権の優先順位にかかわらず、その劣後することとなる金額の範囲内において、国税に優先する後順位質権者に対して優先権を行使することができないことを定めたものである。 〔例1〕 第1順位 質 権・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万円
第2順位 質 権・・・・・・・・・・・・・・・・・・40万円
第3順位 国 税・・・・・・・・・・・・・・・・・・25万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100万円
上記の場合に、第1順位の質権者が質権により担保される債権50万円のうち20万円しか証明できず、第2順位の質権者が40万円につき証明したとすれば、まず第1順位の質権にその証明できた金額20万円を充て、次に第2順位の質権40万円を充て、次に第3順位の国税に25万円を充てる。そして残余金15万円は、第1順位の質権に充てる。したがって、第1順位の質権者に35万円、第2順位の質権者に40万円、第3順位の国税に25万円を配当することとなる(36,37参照)。
〔例2〕(法15条4項と法18条1項本文との関係)
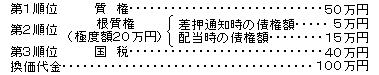
上記の場合に、第1順位の質権者が証明せず、第2順位の根質権者が証明したとすれば、まず根質権に5万円、国税に40万円を順次充て、次に、私法上の原則に従って第1順位の質権50万円を充て、残余金5万円を根質権に充てる。したがって、第1順位の質権者に50万円、第2順位の根質権者に10万円、第3順位の国税に40万円を配当することとなる(36,37参照)。
(証明をしなかった場合)
35 法第15条第4項の「証明をしなかった」場合には、証明の期限に後れて証明した場合が含まれる。
(国税に後れる金額の範囲内)
36 法第15条第4項の「国税におくれる金銭の範囲内」とは、先順位質権者が、その質権が国税に優先することを証明しなかったため、国税に後れることとなった結果、換価代金から配当を受けられなくなった金額の範囲内をいう。
(優先権を行うことができない)
37 法第15条第4項の「優先権を行うことができない」とは、先順位の質権は、後順位の質権に優先する私法上の原則にかかわらず、先順位の質権者が後順位の質権者に劣後することをいう。
第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
抵当権の優先
(抵当権)
1 法第16条の「抵当権」とは、民法第369条((抵当権の内容))、鉄道抵当法第17条((抵当権の内容))、自動車抵当法第4条((抵当権の内容))、航空機抵当法第4条((抵当権の内容))及び建設機械抵当法第6条((抵当権の内容))に規定する抵当権(民法398条ノ2、鉄道抵当法7条2項、自動車抵当法19条の2、航空機抵当法22条の2及び建設機械抵当法24条の2に規定する根抵当権を含む。)をいい、その目的物には、不動産、地上権及び永小作権(民法369条)、立木(立木二関スル法律(以下「立木法」という。)2条2項)、工場財団(工場抵当法14条2項)、鉱業財団(鉱業抵当法3条)、漁業財団(漁業財団抵当法6条)、道路交通事業財団(道路交通事業抵当法9条)、港湾運送事業財団(港湾運送事業法23条)、鉱業権(採掘権に限る。鉱業法13条)、漁業権(漁業法23条1項)、採石権(採石法4条3項)、ダム使用権(特定多目的ダム法21条)、鉄道財団(鉄道抵当法4条)、軌道財団(軌道ノ抵当二関スル法律1条)、運河財団(運河法13条)、工場財団を組成しない工場(工場抵当法2条)、船舶(商法848条)、自動車(自動車抵当法3条)、航空機(航空機抵当法3条)、建設機械(建設機械抵当法5条)、農業用動産(農業動産信用法12条)並びに観光施設財団(観光施設財団抵当法9条)がある。
なお、上記の「抵当権」には、仮登記(保全仮登記を含む。)がされた抵当権も含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。
(抵当権を設定している場合)
2 法第16条の「抵当権を設定しているとき」には、納税者に対する債権について納税者の財産の上に抵当権を設定している場合のほか、納税者以外の者に対する債権について納税者の財産の上に抵当権を設定している場合(納税者が物上保証人になっている場合等)も含まれる。
(法定納期限等以前の設定)
3 法第16条の「法定納期限等以前」には、その法定納期限等に当たる日を含む。したがって、その日に設定された抵当権も、法定納期限以前に設定された抵当権となる。
(物上代位の目的物に対する差押えが競合する場合の優先関係)
4 抵当権の物上代位の目的物に対する差押えと当該目的物に対する滞納処分による差押えとが競合した場合における優先関係は、第15条関係16と同様である。
債権額の範囲
(抵当権の目的物の価額)
5 法第16条の「換価代金」には、抵当権の設定された財産のほか、従物、付加物等抵当権の効力の及んでいるものの換価代金も含まれる。
(抵当権によって担保される債権額)
6 抵当権により担保される債権額の範囲については、次のことに留意する。
(1) 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてだけその抵当権を行うことができる。ただし、それ以前の定期金であっても、満期後特別の登記をしたときは、その登記の時からこれを行うことを妨げない(民法374条1項)。
(2) 民法第374条第1項((被担保債権の範囲))の規定は、抵当権者が債務の不履行により生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の2年分についても適用される。ただし、利息その他の定期金と併せて2年分を超えることはできない(同法374条2項)。
(根抵当権によって担保される債権額)
7 根抵当権により担保される債権額の範囲は、確定した元本、利息、損害賠償金等を併せてその極度額の範囲に限られる(民法398条ノ3第1項)。
抵当権の設定時期
8 抵当権の設定の時期は、その登記がされた日によるものとする。また、抵当権設定の仮登記又は抵当権設定請求権保全の仮登記がされた後において、その仮登記に基づく本登記がされたときのその抵当権の設定の時期は、その仮登記がされた日によるものとする。
徴収職員の調査
9 法第16条の規定の適用については、抵当権者の証明を要件とするものではない。
なお、徴収職員は、抵当権の設定の事実及びその設定の時期が国税の法定納期限等以前であるかどうかにつき調査確認しなければならない。
第17条関係 譲受け前に設定された質権又は抵当権の優先
財産の譲受け
(譲り受けたとき)
1 法第17条の「財産を譲り受けたとき」とは、納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を売買、贈与、交換、現物出資、代物弁済等により取得したときをいい、相続又は合併による承継の場合の取得は含まない。 (注)1 相続又は合併による財産の取得があった場合には、譲受人が通則法第5条((相続による国税の納付義務の承継))、第6条((法人の合併による国税の納付義務の承継))又は第7条((人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継))の規定により、それぞれ納税義務を承継することになること及びその財産上の質権又は抵当権と国税との優先関係については、法第15条第1項第7号又は第8号((法定納期限等))の規定があることに留意する。
2 納税者の財産を譲り受けた者が、第三者のため質権又は抵当権を設定した後、その譲渡が取り消された場合(詐害行為として取り消された場合を含む。)、解除された場合又は無効である場合において、それらの効果を第三者である質権者又は抵当権者に対して主張できないとき(例えば、売買が虚偽表示である場合には、善意の第三者である質権者又は抵当権者に対して、その無効を主張することはできない。民法94条2項)は、その質権又は抵当権が法第17条の譲受け前に設定されたものとして、同条を適用するものとする。
(納税者が担保財産を再取得した場合)
2 納税者が所有する財産上に質権又は抵当権を設定した後その担保財産を第三者に譲渡し、更にその納税者がその担保財産を再取得した場合には、法第17条の規定を適用することなく、法第15条((法定納期限等以前に設定された質権の優先))又は第16条((法定納期限等以前に設定された抵当権の優先))の規定を適用するものとする。
(法定納期限等との関係)
3 納税者が、質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けた場合においては、その質権又は抵当権の設定の時期がその納税者の納付すべき国税の法定納期限等の以前であると後であるとを間わず、その質権又は抵当権により担保される債権は、その国税に優先する。
証明
(証明の期限等)
4 登記をすることができる質権(第15条関係19,20)以外の質権が法第17条第1項の規定の適用を受けるための証明については、第15条関係22から28までと同様である(法17条2項、令4条、通則令2条7号)。
(譲受け前であることの確認)
5 質権の設定の時期がその質権の目的となった財産の譲受け前であるかどうかについては、譲受け前であることを判断するに足りる書類を提出させ、徴収職員が調査確認するものとする。
法第26条との関係
(先順位の質権の証明がなかった場合)
6 法第17条第2項の証明をすべき質権が2以上ある場合において、先順位の質権について第2項の証明がなく、後順位の質権について第2項の証明があったときの配当については、法第26条((国税及び地方税と私債権との競合の調整))の規定を類推適用するものとする。 〔例〕 譲渡人を設定者とする先順位の質権甲・・・・・・・・3万円
譲渡人を設定者とする後順位の質権乙・・・・・・・・4万円
譲受人の国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9万円 (注)1 納税者が、甲質権及び乙質権の設定された財産を譲り受け、その後納税者の滞納国税につき滞納処分をした。
2 甲質権については法第17条第2項の証明がなく、乙質権について第2項の証明があった。したがって、甲質権は国税に後れるが乙質権に優先し、また乙質権は甲質権に後れるが国税に優先することになる。
※配当額の計算 イ 法第26条第2号の規定に準じて、国税及び私債権に充てるべき金額の総額は、法第17条の規定により、乙質権に4万円、国税に5万円(換価代金9万円-乙質権4万円)となり、国税の総額は5万円、私債権の総額は4万円となる。
ロ 法第26条第3号の規定により、国税に5万円を充てる。
ハ 法第26条第4号の規定により、私債権に充てるべき4万円は、民法第355条((動産質権の順位))の規定により、甲質権3万円、乙質権1万円(4万円-3万円)となる。
ニ 上記の結果、配当額は次のとおりになる。
甲質権・・・・・・・・・・・・・・3万円
乙質権・・・・・・・・・・・・・・1万円
国 税・・・・・・・・・・・・・・・5万円
(納税者が担保財産を再取得した場合において第三者が設定した質権又は抵当権があるとき)
7 納税者が所有する財産上に質権又は抵当権を設定した後、その担保財産を第三者に譲渡し、その第三者がその担保財産上に質権又は抵当権を設定し、更にその後納税者がその担保財産を再取得した場合のその納税者の国税及び担保財産上の質権又は抵当権により担保される債権に対する配当については、法第26条((国税及び地方税等と私債権との競合の調整))の規定を類推適用するものとする。 〔例〕 納税者を設定者とする抵当権甲(設定登記 昭和57. 7.31)・・4万円
譲受人を設定者とする抵当権乙(設定登記 昭和57.10.11)・・6万円
差押国税(法定納期限等 昭和57. 5.31)・・・・・・・・・・・・・・・・7万円
換価代金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
(注) 乙抵当権を設定した後納税者がその財産を再取得し、その後納税者の滞納国税につき滞納処分をした。
この場合には、甲抵当権は国税に後れるが乙抵当権に優先し、また、乙抵当権は甲抵当権に後れるが、法第17条の規定により国税に優先する。
※配当額の計算 イ 法第26条第2号の規定に準じて、国税及び私債権に充てるべき金額の総額は、
(1)まず法第17条の規定により乙抵当権に6万円、(2)次いで、甲抵当権の設定登記よりも法定納期限等の古い国税4万円(換価代金1O万円-乙抵当権6万円)となり、国税の総額は4万円、私債権の総額は6万円となる。
ロ 法第26条第3号の規定により、国税に4万円を充てる。
ハ 法第26条第4号の規定により、私債権に充てるべき金額は、民法第373条第1項((抵当権の順位))の規定により、甲抵当権4万円、乙抵当権2万円(6万円-4万円)となる。
ニ 上記の結果、配当額は次のとおりになる。
国 税・・・・・・・・・・・・・・4万円
甲抵当権・・・・・・・・・・・・・4万円
乙抵当権・・・・・・・・・・・・・2万円
第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等
優先債権額の範囲
(債権額の限度)
1 法第18条第1項の「債権額を限度とする」については、法第15条から第17条まで(法定納期限等以前に設定された質権の優先等)の規定により国税に優先する質権又は抵当権により担保される債権額のうち、法第18条第1項の規定により国税に優先する元本債権額は、その質権者又は抵当権者に2又は3の通知書が送達された時の元本債権額に相当する金額を限度として取り扱う。
なお、上記の通知書が送達された時までに根抵当権の元本債権額が確定しているときは、法第18条の規定が適用されないことに留意する。
(差押えの通知を受けた時)
2 法第18条第1項の「差押の通知を受けた時」とは、質権又は抵当権の目的となっている財産を差し押えた場合において、差押えの通知書(法55条)又は差押調書の謄本(令22条1項ただし書、2項)を、その質権者又は抵当権者に送達した時をいう。
(交付要求の通知を受けた時)
3 法第18条第1項の「交付要求の通知を受けた時」とは、質権又は抵当権の目的となっている財産につき交付要求又は参加差押えをした場合において、法第82条第3項(質権者等に対する交付要求の通知)の規定による交付要求の通知書又は第86条第4項(質権者等に対する参加差押えの通知)の規定による参加差押えの通知書を、その質権者又は抵当権者に送達した時をいう。
(根抵当権の確定との関係)
4 根抵当権の元本債権額は、根抵当権者が、根抵当権の目的となった財産に対する滞納処分による差押えがあったことを知った日から2週間を経過したときに確定する(民法398条ノ20第1項4号)が、国税に優先する根抵当権の元本債権額は根抵当権者に2の通知書が送達された時の元本債権額に相当する金額が限度となる(法18条1項本文)。
なお、滞納処分による差押えがあったことを知った日から元本確定(民法398条ノ20第1項)の日までの間に増加した根抵当権の元本債権額は、その根抵当権に後れて登記した担保権には優先する(同法373条1項)ことに留意する。
(根抵当権の確定事由の消滅との関係)
5 滞納処分による差押えが解除された場合には、根抵当権の担保すべき元本は確定しなかったものとみなされる(民法398条ノ20第2項)。当該差押えに対してした参加差押えは参加差押えをした時にさかのぼって差押えの効力を生じることになるから、この差押えとの関係においては、根抵当権者が参加差押えのあったことを知った日から2週間を経過したときに、根抵当権の担保すべき元本は確定する。
なお、次に掲げる場合には、差押えを解除しても、根抵当権の担保すべき元本の確定の効果は、消滅しないことに留意する。
(1) 根抵当権者である税務署長が、当該財産を滞納処分により差し押えたとき(民法398条ノ20第1項3号)。
(2) 根抵当権の担保すべき元本が確定した後において、その根抵当権又はその根抵当権を目的とする権利を取得した者がいるとき(民法398条ノ20第2項ただし書)。
(差押え又は交付要求の競合)
6 差押え又は数個の交付要求(参加差押えを含む。)が競合して行われた場合においては、それぞれの通知を受けた時の債権額を、それぞれの差押え又は交付要求に係る国税との関係において、法第18条第1項の債権額の限度とする(法第18条1項本文)。
なお、法第18条第1項本文の規定を適用すると、いわゆる「ぐるぐる回り」が生ずる場合には、法第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)の規定を適用又は類推適用するものとする。
〔例1〕 根抵当権(設定登記 昭和57. 7.30)極度額・・・・・・・・・・・・・10万円
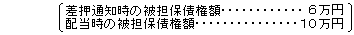
国税(法定納期限等 昭和58. 3.15)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円
※配当額の計算 イ 根抵当権の配当時における被担保債権額10万円のうち、法第18条第1項本文の規定により国税に優先するのは、差押通知時の債権額6万円である。したがって、換価代金15万円のうち6万円を根抵当権に充てる。
ロ 換価代金15万円のうち根抵当権に充てた6万円を控除した残額9万円のうち、法第18条第1項本文の規定により国税に7万円を充てる。
ハ 換価代金15万円のうち、上記イ及びロの金額を控除した残額2万円は、根抵当権がまだ4万円(配当時の被担保債権額10万円-上記のイの6万円)の配当を受ける権利があるので、これに充てる。
ニ 上記の結果、配当額は次のとおりになる。 根抵当権・・・・・・・8万円 (国税に優先する部分6万円十国税に劣後する部分2万円)
国 税・・・・・・・・7万円
〔例2〕 根抵当権(設定登記 昭和56. 7.30)極度額・・・・・・・・・・・・・11万円
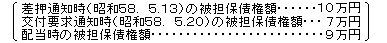
差押国税(法定納期限等 昭和58. 3.30・・・・・・・・・・・・・・・・・8万円
交付要求地方税(法定納期限等 昭和58. 1.31)・・・・・・・・・12万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20万円
※配当額の計算 イ 根抵当権の配当時における被担保債権額9万円のうち、根抵当権の交付要求通知時における被担保債権額7万円は差押通知時の被担保債権額10万円よりも小さく、この限度においては法第18条第1項本文の規定により国税及び地方税のいずれにも優先するから、換価代金20万円のうち7万円を根抵当権に充てる。
ロ 根抵当権の2万円(9万円-7万円)と国税8万円、地方税の12万円とは、次のとおり、三者間で優先順位が交錯していわゆる「ぐるぐる回り」が生ずることとなるので、法第26条の規定により配当額を定める。 (イ) 根抵当権と国税の間においては、根抵当権(2万円)は、差押通知時の被担保債権額(10万円)の範囲内であるから、法第18条第1項本文の規定により国税に優先する。
(ロ) 根抵当権と地方税の間においては、根抵当権(2万円)は、交付要求通知時の被担保債権額(7万円)の範囲外である(上記イで既に7万円の配当を受けることになっている。)から、法第18条第1項本文の規定により地方税に劣後する。
(ハ) 国税と地方税の間においては、国税は、法第12条第1項(差押先着手による国税の優先)の規定により地方税に優先する。
ハ 法第26条第2号の規定により、根抵当権の設定登記及び国税、地方税の法定納期限等の古い順に従って、換価代金13万円(20万円-7万円)を、(1)根抵当権1万円(換価代金20万円-イの金額7万円-地方税12万円=1万円)、(2)地方税12万円、(3)国税0と定める。
ニ 法第26条第3号の規定により、国税及び地方税に充てる金額は、法第12条((差押先着手による国税の優先))の規定により、差押国税8万円、交付要求地方税4万円となる。
ホ 法第26条第4号の規定により、根抵当権に1万円充てる。
ヘ 上記の結果、配当額は次のとおりになる。
根抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・8万円
差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・8万円
交付要求地方税・・・・・・・・・・・4万円
(破産手続等との関係)
7 破産手続又は企業担保権の実行手続との関係においては、法第18条第1項の規定が適用されることはない(令36条4項参照)。
第三者の担保財産に対する滞納処分等との関係
8 国税につき徴している第三者の担保財産(担保権の設定時において納税者に帰属していたものを含む。)を滞納処分の例により処分する場合には、担保権の効力として配当を受けることとなるため、法第18条第1項の規定は適用されない。また、法第22条第5項((担保権付財産が譲渡された場合の国税徴収のための交付要求))の規定により交付要求をする場合には、法第22条第1項に規定する質権者又は抵当権者が配当を受ける額から徴収するものであり、法第18条第1項の規定は適用されない。
第1項本文の規定の適用除外
(権利を害することとなるとき)
9 法第18条第1項ただし書の「権利を害することとなるとき」とは、差押え又は交付要求に係る国税に優先する先順位債権者の差押え等の通知後増加した部分の債権額は、その国税には劣後するが、その国税に優先する他の債権を有する者(以下第18条関係において「後順位債権者」という。)の債権に優先するため、先順位債権者に配当すべき当該増加した部分の債権額を法第18条第1項本文に従って国税に配当することにより、後順位債権者が配当を受けられなくなるときをいう。 〔例1〕 法第18条第1項ただし書の「権利を害することとなるとき」に該当する事例 第1順位 国税に優先する根抵当権の配当時の被担保債権甲・・10万円
差押通知書が債権者に送達された時の債権額・・・・・・・2万円
第2順位 国税に優先する抵当権の被担保債権乙・・・・・・・・・・・・4万円
第3順位 差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円
イ 法第18条第1項本文の規定によると、換価代金15万円は、(1)差押えの通知を受けた時の甲根抵当権の債権額2万円、(2)第2順位の乙抵当権4万円、(3)第3順位の国税5万円、(4)甲根抵当権4万円(15万円-(1)の2万円-(2)の4万円-(3)の5万円)にそれぞれ充てられる。
ロ しかし、第1順位の甲根抵当権は、第2順位の乙抵当権に優先するため、乙抵当権4万円は甲根抵当権に吸い上げられ、甲根抵当権10万円(イの①の2万円十イの(4)の4万円十イの(2)の乙抵当権4万円)、乙抵当権0、国税5万円という配当になる。
ハ この結果、乙抵当権者の権利は、国税が優先配当を受けることによって害されたことになる。したがって、法第18条第1項の規定は適用しないで、法第16条((法定納期限等以前に設定された抵当権の優先))の規定により配当計算をすることになるから、その優先順位どおり(1)甲根抵当権10万円、(2)乙抵当権4万円、(3)国税1万円(換価代金15万円-(1)の10万円-(2)の4万円)の配当額となる。
〔例2〕 法第18条第1項ただし書の「権利を害することとなるとき」に該当しない事例 第1順位 国税に優先する根抵当権の配当時の被担保債権甲・・・10万円
差押通知書が債権者に送達された時の債権額・・・・・・・・4万円
第2順位 国税に優先する抵当権の被担保債権乙・・・・・・・・・・・・・3万円
第3順位 差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
上記の場合においては、換価代金は10万円であり、配当時において、乙抵当権に優先する甲根抵当権の被担保債権額は1O万円であり、もともと乙抵当権者は民法その他の法律の規定(法18条1項本文の規定を除く。)によっては配当を受けることができないのであるから、乙抵当権者に配当をしないこととしても、その権利を害したことにはならない。
(他の債権を有する者)
10 法第18条第1項ただし書の「他の債権を有する者」には、先順位債権者と後順位債権者とが同一人である場合のその後順位債権者も含まれる。
(この限りでない)
11 法第18条第1項ただし書の「この限りでない」とは、同条第1項本文の規定を適用することにより後順位債権者の権利を害することとなる場合には、同条第1項本文の規定を適用しないことをいうものとする。
増額の付記登記
(根質等の増額の登記)
12 根質又は根抵当権の債権額を増加する登記には、次のような登記がある。
(1) 根質により担保される債権極度額又は元本極度額を増額する変更契約による極度額の登記
(2) 根抵当権により担保される極度額を増額する変更契約による極度額の登記
(3) 根質の債権極度額を元本極度額にする変更登記(変更登録を含む。以下同じ。)
(4) 利息若しくは遅延損害金を増加する変更登記又は利息若しくは遅延損害金に関する定めの登記がない場合にその定めを新たに登記する登記
(質権等の増額の登記)
13 質権又は抵当権の債権額を増加する登記には、次のような登記がある。
(1) 債権額の一部が被担保債権として登記されている場合においてその被担保債権額を増額する登記
(2) 利息を元本に組み入れる場合の債権額増額の登記
(3) 利息若しくは遅延損害金を増加する変更登記又は利息若しくは遅延損害金に関する定めの登記がない場合にその定めを新たに登記する登記
(付記登記)
14 債権額の増額の登記は、登記上利害関係を有する第三者の承諾書又はこれらの者に対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記登記(付記登録を含む。以下同じ。)によりすることができる(不動産登記法56条、自動車登録令2条等)。
(設定の時期)
15 付記登記により債権額を増加する登記がされた場合には、その順位は主登記(主登録を含む。以下同じ。)の順位によるが(不動産登記法7条1項、自動車登録令3条等)、法第15条から第17条まで((法定納期限等以前に設定された質権の優先等))の規定の適用については、その付記登記がされた時に、その増加した債権額につき質権又は抵当権が設定されたものとみなされる(法18条2項)。
第19条関係 不動産保存の先取特権等の優先
不動産保存の先取特権等の優先
1 法第19条第1項各号に掲げる先取特権(仮登記(保全仮登記を含む。)がされたものを含む。法133条3項、令50条4項参照)は、特定の行為により財産の価値を保存した等の場合に成立するものであり、その行為によって国税も利益を受けること及びこれらの先取特権は質権又は抵当権よりも優先する効力を有するところから、法第20条第1項に規定する先取特権とは異なり、その成立の時期が国税の法定納期限等後である場合又は差押え後である場合にも、国税に優先する。
不動産保存の先取特権
(意義)
2 法第19条第1項第1号の「不動産保存の先取特権」は、不動産自体の保存費用又は不動産に関する権利の保存、追認若しくは実行のために要した費用について、その不動産の上に存する先取特権である(民法326条)。 (注)1 不動産の保存とは、不動産の現状を維持することをいう。
2 不動産の保存費用等は、次のような費用である。
(1) 不動産の保存費用とは、不動産の滅失又はき損を防ぐために行った修理の費用等である。
(2) 権利の保存費用とは、例えば、納税者の所有不動産を第三者が占有しており、取得時効が完成しようとしている場合において、納税者の債権者がその時効を中断したときに要した費用等である。
(3) 権利の追認に要した費用とは、(2)の例で占有者に対して納税者の所有権を承認させたときに要した費用等である。
(4) 権利の実行に要した費用とは、(2)の例で占有者が納税者へ不動産を返還させたときの費用等である。
(効力の保存)
3 不動産保存の先取特権は、保存行為の完了後直ちに、その債権額を登記することによってその効力を保存するものであるから(民法337条。不動産登記法115条参照)、登記をしていない場合はもちろん、遅滞して登記をしている場合は、先取特権としての優先権を行使できない。
(優先順位)
4 不動産保存の先取特権が、共益費用を除く一般の先取特権、他の特別の先取特権、抵当権又は不動産質権と競合した場合には、その登記の時期の前後にかかわらず、不動産保存の先取特権が優先する(民法329条2項、331条1項、339条、361条)。
不動産工事の先取特権
(意義)
5 法第19条第1項第2号の「不動産工事の先取特権」は、工匠(大工、左官等)、技師又は諸負人が不動産に関してした工事の費用について、その工事によって生じた不動産の増加が現存する場合に限り、その増加額についてだけ、その不動産の上に存する先取特権である(民法327条)。法第19条第1項第2号の「不動産工事の先取特権」は、工匠(大工、左官等)、技師又は諸負人が不動産に関してした工事の費用について、その工事によって生じた不動産の増加が現存する場合に限り、その増加額についてだけ、その不動産の上に存する先取特権である(民法327条)。 (注) 不動産の工事とは、不動産の保存と対比すべきものであって、例えば、倒れかかっている家屋を修理するのは保存であり、一定の計画に従って改造するのは工事である。また、一連の工事のうち、上棟までの費用を工事費とし、その後の費用を保存費とすることは許されない(明治43.1O.18大判)。
(増価額の評価)
6 不動産工事の先取特権の目的となっている不動産を換価する場合には、税務署長は、その工事による不動産の増価額を評価しなければならない。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人に評価を委託し、その評価額を参考として増価額を定めるものとする(令5条)。 (注) 民法第338条第2項((不動産工事による増価額の評価))では、不動産の増価額は配当加入のときに裁判所において選任した鑑定人をして評価させることを要する旨規定しているが、この規定は、滞納処分による換価の場合には適用されない。
(効力の保存)
7 不動産工事の先取特権は、工事を始める前に、費用の予算額を登記することによってその効力を保存するものであるから(民法338条1項本文。不動産登記法115条参照)、登記をしていない場合はもちろん、工事を始めてから登記をしている場合には、先取特権としての優先権を行使できない。
なお、登記した予算額よりも実際の費用が超過した場合には、先取特権は登記した予算額を限度として存在し(民法338条1項ただし書)、実際の費用が予算額よりも少ない場合には、実際の費用の額を限度として先取特権が存在する。
(優先順位)
8 不動産工事の先取特権は、不動産保存の先取特権に次ぐ順位の優先権を有するから(民法331条1項)、共益費用の先取特権を除く一般の先取特権、不動産保存の先取特権を除く他の特別の先取特権、抵当権及び不動産質権に優先する(同法329条2項、331条1項、339条、361条)。
都市再開発法第107条の施行者の先取特権
(意義)
9 都市再開発法第107条((先取特権))の先取特権は、施行者が施設建築物の一部を取得した者から徴収すべき清算金について、その施設建築物の一部の上に有する先取特権である(同条1項)。
(効力の保存)
10 都市再開発法第107条((先取特権))の先取特権は、同法第101条第1項((施設建築物に関する登記))の規定による登記(施設建築物及び施設建築物に関する権利についての必要な登記)の際に、清算金の予算額を登記することによってその効力を保存するものであるが、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については、先取特権が存在しない(同法107条2項)。
(みなし不動産工事の先取特権)
11 都市再開発法第107条((先取特権))の先取特権は、不動産工事の先取特権.(民法327条)とみなされ、また、10によってした登記は、民法第338条第1項本文((不動産工事の先取特権の保存))の規定に従ってした登記とみなされるから(都市再開発法107条3項)、優先順位については、8と同様である。
都市再開発法第118条の事業代行者の先取特権
(意義)
12 都市再開発法第118条((先取特権))の先取特権は、事業代行者である都道府県知事又は市町村長(同法114条参照)が統轄する地方公共団体が、市街地再開発組合の債務について保証契約をした場合(同法116条参照)において、その保証に係る債務を弁済したときに、その求償権に関し、市街地再開発組合の取得すべき施設建築物の一部の上に有する先取特権である(同法118条1項)。
(効力の保存等)
13 都市再開発法第118条((先取特権))の先取特権の効力の保存、優先順位等は、10及び11と同様である(同条2項、3項)。
立木の先取特権
(意義)
14 法第19条第1項第3号の「立木の先取特権に関する法律第1項(立木の先取特権)の先取特権」は、他人の土地の上に立木を有する者が、土地の所有者に対して、樹木伐採の時期にその樹木の価格に対する一定割合の地代を支払うべき契約をした場合において、その土地の所有者が地代についてその立木の上に有する先取特権である(立木ノ先取特権二関スル法律1項)。
(優先順位)
15 立木の先取特権は、他の権利に対して優先の効力を有するが、民法第329条第2項ただし書((共益費用の優先))の規定の適用は妨げられない(立木ノ先取特権二関スル法律2項)。
商法第810条の救助者の先取特権
(意義)
16 法第19条第1項第4号の「商法第810条(救助者の先取特権)の先取特権」は、船舶又は積荷の全部若しくは一部が海難にあつた場合において、義務なくしてこれを救助したときに、救助者が、その救助料債権について救助した積荷の上に有する先取特権である(商法800条参照)。
(救助料債権)
17 救助料債権については、次のことに留意する。
(1) 救助者の故意又は過失によって海難を引き起こした場合等にあっては、救助料の請求ができない(商法809条)。
(2) 救助料の額は、特約のない限り、救助した物の価額を超えることができず、また先順位の先取特権(19の(1)から(4)まで参照)があるときは、救助料の額はその先取特権者の債権額を控除した残額を超えることができない(商法803条)。
(3) 救助料の請求権は、救助した時から1年を経過したときは、時効によって消滅する(商法814条)。
(優先順位等)
18 商法第810条((救助者の先取特権))の先取特権については、船舶債権者の先取特権(同法842条)に関する規定が準用されているので(同法810条2項)、優先順位及び除斥期間については、21及び22の(1)とそれぞれ同様である。
また、商法第810条の救助者の先取特権は、その目的物である積荷が第三取得者に引き渡されたときは消滅する(同法813条)。
商法第842条の船舶債権者の先取特権
(先取特権を有する債権)
19 法第19条第1項第4号の「商法第842条(船舶債権者の先取特権)の先取特権」は、次の(1)から(8)までに掲げる債権について成立する先取特権である。
(1) 船舶及びその属具の競売に関する費用並びに競売手続開始後の保存費
(2) 最後の港における船舶及びその属具の保存費 (注) 「最後の港」とは、競売をする時において船舶の存在するところをいい、航海を終わって帰来した港等をいうものではない。
(3) 航海に関して船舶に課した諸税
(4) 水先案内料及びひき(挽)船料
(5) 救助料及び船舶の負担に属する共同海損(商法788条以下参照) (注) 上記の救助料は、義務なくして海難を救助した場合の救助料(商法800条)だけでなく、契約による救助料を含む(明治45.2.17大判)。
(6) 航海継続の必要によって生じた債権(商法715条、719条参照) (注) 船籍港内で発生した修繕費等の債権は、上記の「航海継続の必要によって生じた債権」に含まれない(昭和55.5.26福岡地判)。
(7) 雇用契約によって生じた船長その他の船員の債権。
(8) 船舶がその売買又は製造の後まだ航海をしない場合において、その売買又は製造及びぎ(艤)装によって生じた債権並びに最後の航海のためにする船舶のぎ(艤)装、食料及び燃料に関する債権(大正11.9.21長崎控判参照)
(先取特権の目的となる財産)
20 商法第842条((船舶債権の先取特権))の先取特権の目的となる財産は、19に掲げる債権の発生に係る船舶(同法684条参照)及びその属具並びに先取特権が生じた航海における運送賃でまだ受け取っていないものである(同法843条)。
(優先順位)
21 商法第842条((船舶債権者の先取特権))の先取特権は、他の先取特権、船舶抵当権及び船舶質権(登記した船舶は質権の目的とすることができない。同法850条)に優先する(同法845条、849条、民法334条)。また、商法第842条の船舶債権者の先取特権が競合した場合には、次により優先順位が定まる。
(1) 航海ごとに各群をつくり、後の航海で発生したものが前の航海の発生したものに優先する(商法844条3項)。
(2) 同一航海で発生したものの間における優先順位は、19の(1)から(8)までに掲げる順序に従うが、19の(4)から(6)までの債権相互間では、後に発生したものが前に発生したものに優先する(商法844条1項)。
(3) 同一順位のものの間では、債権額の割合に応じて弁済を受けるが、19の(4)から(6)までの債権相互間では、後に発生したものが前に発生したものに優先する(商法844条2項)。
(消滅原因)
22 商法第842条((船舶債権者の先取特権))の先取特権は、次に掲げる場合には消滅する。 (注) この期間は除斥期間である。
(1) 先取特権の発生後1年を経過したとき(商法847条1項)。
(2) 19の(8)に掲げる債権の先取特権については、船舶が発航したとき(商法847条2項。大正12.5.14大判参照)。
(3) 登記できる船舶の譲渡が行われた場合において、譲渡人が船舶譲渡の登記をした後、先取特権者に対して一定期間内(1月を下ることができない。)に債権の申出をすべき旨を公告したにかかわらず、先取特権者がその期間内にその申出をしないとき(商法846条)。
(4) 登記できない船舶(商法686条2項)又は船舶の属具が第三取得者に引き渡されたとき(民法333条)及び運送賃債権が譲渡されたとき。
国際海上物品運送法第19条の船舶先取特権
(意義)
23 法第19条第1項第4号の「国際海上物品運送法第19条(船舶先取特権)の先取特権」は、船舶の全部又は一部を運送契約の目的とした場合(よう(傭)船契約した場合)で、よう(傭)船者が更に第三者と運送契約をしたとき(再運送契約をしたとき)において、運送品に関する損害で船長の職務に属する範囲内で生じたものについて、賠償を請求できる者が、その債権について船舶及びその属具の上に有する先取特権である。
(優先順位等)
24 国際海上物品運送法第19条((船舶先取特権))の先取特権については、商法第842条((船舶債権者の先取特権))の先取特権と競合する場合には同条第9号の先取特権と同一順位とされており(国際海上物品運送法19条2項)、また商法第845条((他の先取特権に対する優先))、第849条((船舶抵当権に対する優先))、第844条第3項((後の航海で発生したものの優先))、第844条第2項((同一順位の場合のあん分等))、第847条第1項((除斥期間))及び第846条((船舶の譲渡と先取特権の消滅))の規定が準用されているので(国際海上物品運送法19条3項)、優先順位及び先取特権の消滅については、21並びに22の(1)及び(3)と同様である。
なお、登記できない船舶(商法686条2項)又は船舶の属具が第三取得者に引き渡されたときは、先取特権が消滅する(民法333条)。
船舳の所有者等の責任の制限に関する法律第95条の先取特権
(意義)
25 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(以下「船主責任制限法」という。)第95条(船舶先取特権)の先取特権は、航海に関して生じた生命又は身体が害されたことによる損害及び物の滅失又は損傷による損害に基づく債権につき、その債権者が事故に係る船舶、その属具及び受領していない運送賃の上に有する先取特権である(同条1項)。
(責任制限手続の開始の効果との関係)
26 責任制限手続(船主責任制限法に基づく責任制限手続をいう。以下27において同じ。)開始決定後においては、当該開始決定の取消し又は手続の廃止の決定が確定したときを除き(同法95条4項)、船主責任制限法第95条((船舶先取特権))の先取特権を行使することはできない(同法33条後段)。
(優先順位等)
27 船主責任制限法第95条((船舶先取特権))の先取特権は、商法第842条第8号((船舶先取特権のある債権))の先取特権に次ぐ(船主責任制限法95条2項)。この先取特権については、商法の船舶債権者の先取特権に関する規定の一部が準用されており(船主責任制限法95条3項)、優先順位及び除斥期間については、21の(1)及び(3)の前段並びに22の(1)及び(3)とそれぞれ同様である。
なお、上記の先取特権が発生後1年で消滅する前に、責任制限手続の開始決定があり、その後に当該開始決定の取消し又は手続の廃止の決定が確定したときは、当該取消し又は廃止の決定の確定後1年を経過した時に消滅する(船主責任制限法95条4項)。
油濁損害賠償保障法第40条の先取特権
(意義)
28 油濁損害賠償保障法(以下「油濁保障法」という。)第40条((船舶先取特権))の先取特権は、船舶から流出した油等による油濁損害に基づく債権につき、その債権者が事故に係る船舶、その属具及び受領していない運送賃の上に有する先取特権である(同法40条1項)。
(優先順位等)
29 責任制限手続(油濁保障法に基づく責任制限手続をいう。)の開始の効果と油濁保障法第40条((船舶先取特権))の先取特権との関係については、26と同様であり(同法38条)、同条の先取特権の優先順位及び除斥期間については、27と同様である(同法40条)。
優先債権等のための動産保存の先取特権
(国税に優先する債権)
30 法第19条第1項第5号の「国税に優先する債権」とは、法第15条から第20条まで((法定納期限等以前に設定された質権の優先等))の規定によって国税に優先する質権、抵当権及び先取特権(いずれも、動産に関するものに限る。)の被担保債権をいい、留置権の被担保債権等(同法21条、59条3項参照)は含まれないものとする。
(優先債権のために動産を保存した者の先取特権)
31 法第19条第1項第5号の「国税に優先する債権のために動産を保存した者の先取特権」とは、30の担保権付債権が成立した後、その動産を保存した者がその動産上に有するその動産保存の先取特権(民法321条)をいう。
なお農業動産信用法第4条第1項第1号((農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権))の先取特権(34参照)は、上記の動産保存の先取特権と同様に取り扱う(同法11条参照)。
(国税のために動産を保存した者の先取特権)
32 法第19条第1項第5号の「国税のために動産を保存した者の先取特権」とは、国税の滞納処分による差押えの効力が生じた時若しくは交付要求(参加差押えを含む。)の効力が生じた時又は国税に係る担保権の設定時の後において、その動産を保存した者がその動産上に有する動産保存の先取特権(民法321条)をいう。
なお、農業動産信用法第4条第1項第1号((農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権))の先取特権(34参照)は、これと同様に取り扱う(同法11条参照)。
(動産保存の先取特権)
33 動産保存の先取特権は、動産の保存費用又は動産に関する権利の保存、追認若しくは実行のために要した費用について、その動産の上に存する先取特権である(民法321条)。 (注)1 動産の保存とは、動産の現状を維持することをいう。
2 動産の保存費用等は、次のような費用である。
(1) 動産の保存費用とは、動産の滅失又はき損を防ぐために行った修理の費用等である。
(2) 権利の保存費用とは、例えば、納税者の所有物を第三者が占有しており、取得時効が完成しようとしている場合において、納税者の債権者がその時効を中断したときに要した費用等である。
(3) 権利の追認に要した費用とは、(2)の例で、占有者に対して納税者の所有権を承認させたときに要した費用等である。
(4) 権利の実行に要した費用とは、(2)の例で、占有者から納税者へ動産を返還させたときの費用等である。
(農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権)
34 農業動産信用法第4条第1項第1号((農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権))の先取特権は、農業用動産又は農業生産物について、その保存又はその物に関する権利の保存、追認若しくは実行のために必要な資金の貸付けをした場合において、農業協同組合等(同法4条参照)の貸付債権につき、その農業用動産又は農業生産物の上に存する先取特権である(同法5条)。
なお、上記の先取特権は、優先権の順位について、動産保存の先取特権とみなされる(同法11条)。
(優先順位)
35 動産保存の先取特権及び農業動産信用法第4条第1項第1号((農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権))の先取特権の優先順位は、次のとおりである。
(1) 動産保存の先取特権又は農業動産信用法第4条第1項第1号の先取特権が、他の特別の先取特権、質権又は抵当権と競合した場合には、第2順位の優先権を有する(民法330条1項。以下第19条及び第20条関係において、これら第2順位の先取特権を「第2順位担保権」という。)。したがって、第1順位の優先権を有する不動産賃貸の先取特権(同法312条)、旅店宿泊の先取特権(同法317条)、運輸の先取特権(同法318条)、動産質権(同法334条)、農業用動産抵当権(農業動産信用法16条)、自動車抵当権(自動車抵当法11条)、航空機抵当権(航空機抵当法11条)及び建設機械抵当権(建設機械抵当法15条。以下第19条及び第20条関係において、これらの担保権を「第1順位担保権」という。)には劣後し、第3順位の優先権を有する動産売買の先取特権(民法322条)、種苗肥料供給の先取特権(同法323条)、農工業労役の先取特権(同法324条)及び農業動産信用法第4条第1項第2号から第6号までの先取特権(同法11条。以下第19条及び第20条関係において、これらの先取特権を「第3順位担保権」という。)には優先する。ただし、(2)及び(3)の場合においては、この限りでない。
(2) 第1順位担保権を有する者が、その債権取得の当時において、既に第2順位担保権者又は第3順位担保権者があることを知っていたときは、その第2順位担保権又は第3順位担保権が第1順位担保権に優先する(民法330条2項前段、334条、農業動産信用法16条、自動車抵当法11条、航空機抵当法11条、建設機械抵当法15条)。
(3) 第1順位担保権が成立した後、その動産を保存したときの第2順位担保権は、その第1順位担保権に優先する(民法330条2項後段、334条、農業動産信用法16条、自動車抵当法11条、航空機抵当法11条、建設機械抵当法15条)。
(4) 第2順位担保権が競合したときは、後に保存したものが、前に保存したものに優先する(民法330条1項2号後段)。
(先取特権の消滅)
36 動産に関する先取特権は、その動産が第三取得者に引き渡されたときは消滅する(民法333条)。
証明の期限と方法
37 法第19条第1項第3号(登記したものを除く。)から第5号までの先取特権が第1項の規定の適用を受けるための証明については、第15条関係24及び25の(2)と同様である(法19条2項、令4条1項、3項、通則令2条7号)。
登記事項の調査確認
38 法第19条第1項第1号から第3号(登記したものに限る。)までの先取特権については、徴収職員がその登記されている先取特権がある事実を調査確認しなければならない。
第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
不動産賃貸の先取特権等の優先
1 法第20条第1項各号に掲げる先取特権(仮登記(保全仮登記を含む。)に係るものを含む。法133条3項、令50条4項参照)は、法第19条第1項各号に規定する先取特権とは異なり、一定の条件の下に質権又は抵当権に優先し、又は同順位であるところから、先取特権の成立が国税の法定納期限等以前又は財産譲渡時以前であるときに限り、その被担保債権は、国税に優先する。
なお、法第20条第1項各号及び法第19条第1項各号((不動産保存の先取特権等の優先))の先取特権に該当しない先取特権の被担保債権は、国税に劣後することはもちろん、滞納処分手続においては劣後配当も受けられない。
法定納期限等以前からあるとき
2 法第20条第1項の「法定納期限等以前」には、その法定納期限等に当たる日を含む。したがって、その日に成立した先取特権も、法定納期限等以前にある先取特権となる。
財産譲渡との関係
(譲り受けたとき)
3 法第20条第1項の「財産を譲り受けたとき」は、第17条関係1と同様である。 (注) 先取特権のある財産が譲渡された場合における譲渡人の国税と先取特権との関係については、法第22条((担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収))の規定に相当する規定がないことに留意する。
(譲渡による先取特権の消滅)
4 法第20条第1項第1号の先取特権については、その目的となっている動産が第三取得者に引き渡されたときは消滅する(民法333条)。
不動産賃貸等の先取特権
(不動産賃貸の先取特権)
5 法第20条第1項第1号の「不動産賃貸の先取特権」は、不動産の賃貸料その他賃貸借関係から生ずる賃貸人の債権(損害賠償請求権等)について、賃借人の動産の上に成立するものであるが(民法312条)、その被担保債権及び目的財産については、次のことに留意する。
(1) 賃貸人が敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けることができない不足額についてだけ先取特権が成立する(民法316条)。また、賃借人の財産の総清算の場合(破産の場合等)には前期、当期及び次期の賃借料その他の債権並びに前期及び当期において生じた損害賠償についてだけ先取特権が成立する(同法315条)。
(2) 土地の賃貸人の先取特権の目的物は、賃借地又はその利用のためにする建物に備え付けた動産、その土地の利用に供した動産及び賃借人が占有しているその土地の果実であり(民法313条1項)、建物の賃貸人の先取特権の目的物は、賃借人がその建物に備え付けた動産である(同法313条2項)。
また、賃借権の譲渡又は転貸があった場合においては、賃借権の譲受人又は転借人の動産及び譲渡人又は転貸人の受けるべき金額(賃借権譲渡の対価等)にも、先取特権の効力が及ぶ(民法314条)。
(質権と同一順位の先取特権)
6 法第20条第1項第1号の「質権と同一の順位」の先取特権とは、不動産賃貸の先取特権のほか、旅店宿泊の先取特権(民法317条)及び運輸の先取特権(同法318条)をいい(同法330条1項、334条)、先取特権の目的財産が農業上の果実(収穫物)であるときは、農業の労役者の先取特権(同法324条)をいう(同法330条3項、334条)。
(旅店宿泊の先取特権)
7 「旅店宿泊の先取特権」は、旅客、その従者及び牛馬の宿泊料並びに飲食料の請求権について、その旅店にある債務者の手荷物の上に存する先取特権である(民法317条)。
(運輸の先取特権)
8 「運輸の先取特権」は、旅客又は荷物の運送賃及びそれに付随する費用(荷造費等)の請求権について、運送人の所持内にある荷物の上に存する先取特権である(民法318条)。
(動産保存の先取特権等)
9 「動産保存の先取特権」及び「農業動産信用法第4条第1項第1号((農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権))の先取特権」については、第19条関係33及び34と同様である。 (注) 上記の先取特権は、法第20条第1項第1号に該当する場合(14参照)のほか、法第19条第1項第5号に該当する場合(第19条関係31、32参照)と、これらいずれにも該当せず、劣後配当も受けられない場合とがある。
(動産売買の先取特権)
10 「動産売買の先取特権」は、動産の代価及びその利息について、その動産の上に存する先取特権である(民法322条)。
(種苗肥料供給の先取特権)
11 「種苗肥料供給の先取特権」は、種苗若しくは肥料の代価及びその利息又は蚕種若しくは蚕の飼養の供した桑葉の代価及びその利息について、その種苗若しくは肥料を用いた後、1年内にその用いた土地から生じた果実(収穫物)又はその蚕種若しくは桑葉から生じた物の上に存する先取特権である(民法323条)。
(農工業労役の先取特権)
12 「農工業労役の先取特権」は、農業労役者については最後の1年間、工業労役者については最後の3月間の賃金について、その労役によって生じた果実(農業収穫物)又は工業製作物の上に存する先取特権である(民法324条)。
(農業動産信用法の先取特権)
13 「農業動産信用法第4条第1項第2号から第6号まで((農業用動産の購入資金貸付けの先取特権等))の先取特権」は、貸し付けた債権の元本及び利息について、次に掲げる財産の上に存する先取特権である(同法4条1項1号の農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権については、第19条関係34参照)。
なお、優先順位については、次の(1)及び(2)の先取特権は動産売買の先取特権(10参照)と、(3)から(5)までの先取特権は種苗肥料供給の先取特権(11参照)と、それぞれみなされる(農業動産信用法11条)。
(1) 農業用動産の購入資金貸付けの先取特権については、貸付けを受けた資金をもって購入した農業用動産(農業動産信用法6条)
(2) 薪炭原木の購入資金貸付けの先取特権については、貸付けを受けた資金をもって購入した薪炭原木から生産した薪炭(農業動産信用法9条)
(3) 種苗又は肥料の購入資金貸付けの先取特権については、貸付けを受けた資金をもって購入した種苗又は肥料を用いた後1年内にその用いた土地から生じた果実、また、桑樹の肥料購入資金貸付けの先取特権についてはその果実たる桑葉より生じた物(農業動産信用法7条)
(4) 蚕種又は桑葉の購入資金貸付けの先取特権については、貸付けを受けた資金をもって購入した蚕種又は桑葉より生じた物(農業動産信用法8条)
(5) 水産養殖用種苗又は水産養殖用じ(餌)料の購入資金貸付けの先取特権については、貸付けを受けた資金をもって購入した種苗を養殖した物又は貸付けを受けた資金をもって購入したじ(餌)料を用いて養殖した物(農業動産信用法10条)
(これらに優先する先取特権)
14 法第20条第1項第1号の「これらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第1項第3号から第5号までに掲げる先取特権を除く。)」とは、次のものをいう。
(1) 第1順位担保権(第19条関係35の(1)参照)を有する者が、その債権取得の当時において、既に第2順位担保権者(第19条関係35の(1)参照)又は第3順位担保権者(第19条関係35の(1)参照)のあることを知っていた場合におけるその第2順位担保権及び第3順位担保権(民法330条前段。第19条関係35の(2)参照)
(2) 第1順位担保権成立後第2順位担保権が成立した場合におけるその第2順位担保権(民法330条2項後段。第19条関係35の(3)参照) (注) 上記に該当しない場合、すなわち、第2順位担保権又は第3順位担保権と第1順位担保権との競合がない場合、第1順位担保権が第3順位担保権よりも先に成立した場合及び第1順位担保権の成立当時に第2順位担保権者又は第3順位担保権者のあることを知らなかった場合には、法第20条第1項第1号には該当しない。
(優先順位)
15 第20条関係5から14までの先取特権の優先順位は、第19条関係35と同様である(民法330条1項、2項)。ただし、先取特権の目的財産が農業上の果実である場合の優先順位は、第1順位が農業の労役者、第2順位が種苗又は肥料の供給者、第3順位が土地の賃貸人である(同法330条3項)。
不動産売買の先取特権
(意義)
16 法第20条第1項第2号の「不動産売買の先取特権」は、不動産の代価及びその利息について、その不動産の上に存する先取特権である(民法328条)。
(効力の保存)
17 不動産売買の先取特権は、売買契約と同時に(売買による所有権移転登記とともに)、また代価又はその利息の弁済がない旨を登記することによってその効力を保存するものであるから(民法340条)、登記をしない場合はもちろん、売買契約と同時に登記していない場合にも、先取特権としての優先権を行使できない。
(優先順位)
18 不動産売買の先取特権は、不動産保存の先取特権及び不動産工事の先取特権に次ぐ優先権を有し(民法331条1項)、抵当権又は不動産質権と競合した場合には、登記の前後によって優先順位が定まる(同法341条、373条)。また、同一の不動産について逐次の売買があった場合における売主相互間の順位は、売買の時期の前のものが後のものに優先する(同法331条2項)。
借地法第13条の土地所有者等の先取特権等
(借地法第13条の先取特権) 編注9
19 法第20条第1項第3号の「借地法第13条(土地所有者等の先取特権)に規定する先取特権」の意義等は、次のとおりである。
(1) 借地法第13条の先取特権は、土地所有者又は賃貸人が、弁済期に至った最後2年分の地代又は借賃について、借地権者がその土地に所有する建物の上に有する先取特権である(同法13条1項)。
(2) 借地法第13条の先取特権は、地上権又は賃貸借の登記をすることによって効力を保存するものであるから(同法13条2項)、これらの登記をしていない場合には、先取特権としての優先権を行使できない。
(3) 借地法第13条の先取特権は、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに(2)による登記前に登記されている質権及び抵当権には劣後するが、他の権利に対しては優先の効力を有する(同法14条)。
(罹災都市借地借家臨時処理法第8条の先取特権)
20 法第20条第1項第3号の「罹災都市借地借家臨時処理法第8条(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権」の意義等は、次のとおりである。
(1) 罹災都市借地借家臨時処理法第8条の先取特権は、賃借権の設定(同法2条)又は借地権の譲渡(同法3条)があった場合において、賃貸人又は借地権の譲渡人が、借賃の全額又は借地権の譲渡の対価について、借地権者がその土地に所有する建物の上に有する先取特権である(同法8条1項)。
(2) 罹災都市借地借家臨時処理法第8条の先取特権は、借賃についてはその額及び存続期間、借賃の支払時期の定めがあるときはその旨、弁済期の到来した借賃があるときはその旨、また譲渡の対価についてはその対価の弁済されない旨を登記することによって効力を保存するものであるから(同法8条2項)、これらの登記をしていない場合には、先取特権としての優先権を行使できない。
(3) 罹災都市借地借家臨時処理法第8条の先取特権は、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに(2)による登記前に登記されている質権及び抵当権には劣後するが、他の権利に対しては優先の効力を有する(同法8条3項)。
(接収不動産に関する借地借家臨時処理法第7条の先取特権)
21 法第20条第1項第3号の「接収不動産に関する借地借家臨時処理法第7条(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権」は、賃借権の設定(接収不動産に関する借地借家臨時処理法3条)又は借地権の譲渡(同法4条)があった場合において、賃貸人又は借地権の譲渡人が、借賃の全額及び貸借権の設定の対価又は借地権の譲渡の対価について、その賃借権の設定又は借地権の譲渡を受ける者がその土地に所有する建物の上に有する先取特権である(同法7条1項)。
なお、上記の先取特権の効力の保存及び優先の効力については、20の(2)及び(3)と同様である(同法7条2項、3項)。
一般の先取特権
(種類及び意義)
22 一般の先取特権には、次のものがある。
(1) 民法の規定による先取特権 イ 共益費用の先取特権(民法306条1号)は、各債権者の共同の利益のためにした債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在するが、これが総債権者のうちの一部の者にとってだけ利益となっているときは、その者に対してだけ存在する(同法307条)。
ロ 雇人給料の先取特権(民法306条2号)は、雇人が受けるべき最後の6月間の給料について存在する(同法308条)。
ハ 葬式費用の先取特権(民法306条3号)は、債務者の身分に応じてした葬式の費用(死亡者の財産の上に先取特権が成立する。)又は債務者がその扶養すべき親族の身分に応じてした葬式の費用(葬式をした者の財産の上に先取特権が成立する。)について存在する(同法309条)。
ニ 日用品供給の先取特権(民法306条4号)は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその使用人の生活に必要な最後の6月間の飲食品及び薪炭油の供給の代価について存在する(同法310条)。
(2) 商法の規定による先取特権
商法第295条((会社使用人の先取特権))の先取特権は、身元保証金の返還を目的とする債権その他会社と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する(同法295条1項)。
(3) 有限会社法の規定による先取特権
有限会社法第46条第2項((会社使用人の先取特権))の先取特権は、有限会社と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する(同法46条2項、商法295条1項)。
(優先順位等)
23 一般の先取特権の優先順位等は、次のとおりである。
(1) 一般の先取特権は、特別の先取特権には劣後するが、共益費用の先取特権だけは、その利益を受けた総債権者に対して優先の効力を有する(民法329条2項)。
また、登記をした一般の先取特権と抵当権又は不動産質権とが競合した場合には、登記の早いものが優先する(民法341条、373条参照)。
(2) 22の(1)の先取特権(民法の規定による先取特権)が競合した場合には、その優先順位は、22の(1)のイからニまでの順序に従う(民法329条1項)。また、22の(2)及び(3)の先取特権(会社使用人の先取特権)の優先順位は、22の(1)のイの先取特権(共益費用の先取特権)に次ぐ(商法295条2項、有限会社法46条2項)。
(3) 一般の先取特権は、まず不動産以外の財産について弁済を受けることを要し、その不足額についてだけ不動産から弁済を受けることができ(民法335条1項)、また不動産からの弁済についても、まず特別担保の目的となっていないものから弁済を受けることを要するのであって(同法335条2項)、これらの順序に従わず、配当加入を怠ったときは、配当加入をすれば弁済を受けたであろう限度において、登記をした第三者に対して先取特権を行使することができない(同法335条3項)。ただし、不動産以外の財産に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産に先立って特別担保の目的不動産の代価を配当すべきときは、この限りでない(同法335条4項)。
(共益費用の先取特権とみなされる先取特権)
24 建物の区分所有等に関する法律第6条の先取特権は、建物の区分所有者(同法2条2項)が共用部分(同法2条4項)又は建物の敷地につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び専用部分(同法2条3項)を所有するための建物の敷地に関する権利を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に有する先取特権であり(同法6条1項)、その優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなされる(同法6条2項)。
証明の期限等
25 法第20条第1項第1号の先取特権が第1項の規定の適用を受けるための証明については、第15条関係24及び25の(2)と同様である(法20条2項、令4条1項、3項、通則令2条7号)。
なお、法第20条第1項第2号から第4号までの先取特権については、証明を要せず、徴収職員はその先取特権がある事実を確認しなければならず、また、法第20条第1項各号の先取特権が法定納期限等以前又は譲受け前からあるかどうかについては、徴収職員が調査確認しなければならない。 (注) 法第20条第1項第1号の先取特権は、その目的財産が第三取得者に引き渡されたときは消滅するから(民法333条)、財産の譲受けとの関係は考慮する必要がない。
第21条関係 留置権の優先
留置権
(留置権の種類)
1 法第21条の「留置権」とは、民法第295条((留置権の内容))に規定する民事留置権のほか、商事留置権である代理商の留置権(商法51条)、商人間の留置権(同法521条)、問屋の留置権(同法557条)、運送取扱人の留置権(同法562条)、運送人の留置権(同法589条)及び船舶所有者の留置権(同法753条2項)をいう。
(民事留置権)
2 民法の規定による留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合において、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる権利をいう(民法295条1項本文)。
なお、民事留置権については、次のことに留意する。
(1) 物に関して生じた債権とは、物と関連のある債権をいい、債権が物自体より発生した場合又は債権が物の返還義務と同一の法律関係若しくは事実関係より発生した場合のその債権が、これに当たる。 (注)1 債権が物自体より発生した場合の例としては、物のかしによる損害賠償請求権、物に加えた費用の償還請求権がある。
2 債権が物の返還義務と同一の法律関係より発生した場合の例としては、物の売買代金債権、物の修繕料債権がある。
(2) 他人の物とは、債権者(留置権者)以外の者の所有物をいい、債務者の物に限らず、第三者の物も含まれる。
(3) 債権が弁済期にない間は、留置権は発生しない(民法295条1項ただし書)。 (注) 債権の弁済期については、期限の利益喪失に関する民法第137条((期限の利益の喪失))及び破産法第17条((弁済期の到来))の規定があるほか、特約により期限の利益を失う場合がある。
(4) 物の占有が不法行為によって始まったときは、留置権は成立しない(民法295条2項)。
なお、留置権者が債務者に対抗できる占有の権原がなく、かつ、それを知り、又は過失により知らないで占有を始めた場合にも、留置権は成立しない(昭和30.3.11東京高判)。
(留置権と果実収取権)
3 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立ってこれを留置権により担保される債権の弁済に充てることができる(民法297条1項)。この場合において、収取した果実は債権の利息に充て、なお残余があるときは元本に充てなければならない(同法297条2項)。
(留置権と費用償還請求権)
4 留置権者は、留置物につき必要費を支出したときは、その物の所有者に対しその必要費の償還をさせることができる(民法299条1項)。また、留置権者は、留置物につき有益費を支出したときは、その価格の増加が留置物につき現存する場合に限り、その費用額又は増加額の償還をその留置物の所有者に対し請求することができるが、その所有者の請求により裁判所が期限につき相当期間の許与をした場合には、その有益費につき留置権を行使することができない(同法299条2項)。
(留置権の移転)
5 留置権の移転は、その担保される債権と目的物の占有とを、ともに移転することによって行うことができる。
(留置権の消滅)
6 留置権は、目的物の滅失、没収、収用、混同、留置権により担保される債権の消滅等によって消滅するほか、次に掲げる場合にも消滅する。
(1) 留置権者が、留置物につき善良な管理者の注意を怠り、債務者又は留置物の所有者の承諾なくして使用若しくは賃貸をし、又は担保に供したため、債務者又は留置物の所有者が、民法第298条第3項((債務者の消滅請求))の規定により留置権の消滅の請求をした場合
(2) 債務者又は留置物の所有者が、留置権者の承諾又はこれに代わるべき民法第414条第2項ただし書((履行の強制))の判決を得て相当の担保を提供して留置権の消滅を請求した場合(同法301条)
(3) 留置権者が、債務者又は留置物の所有者の承諾を得て賃貸又は質入れをした場合以外で、留置物の占有を喪失した場合(民法302条) (注) 留置権のある財産を滞納処分により差し押さえ、徴収職員がその財産を占有しても、私法上の占有関係には影響を及ぼさないことから、留置権は消滅しない。
(破産による留置権の失効等)
7 破産財団の財産上にある留置権のうち、商法の規定によるものはその破産財団に対しては特別の先取特権とみなされるが(破産法93条1項)、他の留置権は破産財団に対してはその効力を失う(同法93条2項)。また、更生会社の財産上にある商法の規定による留置権に限り、更生担保権となる(会社更生法123条1項)。
(代理商の留置権)
8 代理商の留置権とは、代理商が、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権が弁済期にあるときに、その弁済を受けるまで、本人のために占有する物又は有価証券を留置することができる権利をいう(商法51条)。
(商人間の留置権)
9 商人間の留置権とは、商人間においてその双方のために商行為である行為によって生じた債権が弁済期にあるときに、債権者が、債務の弁済を受けるまで、債務者との間の商行為によって自己の占有に帰した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる権利をいう(商法521条)。
(問屋の留置権)
10 問屋の留置権とは、問屋が自己の名をもって第三者のために物品の販売又は買入れをしたことによって生じた債権が弁済期にあるときに、その弁済を受けるまで、債権者である問屋が、債務者であるその第三者のために占有している物又は有価証券を留置することができる権利をいう(商法557条、51条)。
(運送取扱人の留置権)
11 運送取扱人の留置権とは、運送取扱人が、運送品に関して受け取るべき報酬・運送賃その他委託者のためにした立替え又は前貸しについて、債務の弁済があるまで、その運送品(報酬等を請求できる運送品に限られるが、委託者の所有物であることを要しない。)を留置することができる権利をいう(商法562条)。
なお、運送中の運送品に対する留置権の行使は、荷送人としての運送品処分権(商法582条)の行使によって行う。 (注) 運送取扱人とは、運送品発送人の計算において、自己の名をもって運送人と運送契約を締結し、その他運送に必要な手配をすることを業(取次業)とする者をいい、荷送人としての権利を有する(運送品発送人は、この荷送人には該当しない。)。
(運送人の留置権)
12 運送人の留置権とは、運送人が、運送品に関して受け取るべき報酬、運送賃その他荷送人のためにした立替え又は前貸しについて、債務者の弁済があるまで、その運送品を留置することができる権利をいう(商法589条、562条)。
なお、運送人は、運送賃その他法定の債権(例えば、通関手続の費用、倉庫保管料等)につき、運送品に対して先取特権(民法318条)をも有する。
(船舶所有者の留置権)
13 船舶所有者の留置権とは、荷受人が運送契約又は船荷証券に定められる約定等によって運送賃、付随の費用、立替金、てい泊料及び運送品の価格に応じ共同海損又は救助のために負担すべき金額を支払わないときに、船長が、これらの支払があるまで、その運送品を留置することができる権利をいう(商法735条2項)。
留置権の優先
(同一債権につき留置権と先取特権とがある場合)
14 換価に付された財産上にある留置権により担保される債権が、同時にその財産についての先取特権によって担保されている場合(例えば、荷物の運輸の場合には、運送人は、運送賃についてその荷物の上に留置権を有すると同時に、動産の先取特権をも有する。民法318条)には、留置権により担保される債権は先取特権等に優先して配当を受け、先取特権により担保される債権は留置権により担保される債権に対して配当された額の範囲において消滅する。
(留置権の成立時期と法定納期限等との関係)
15 留置権の被担保債権は、その留置権の成立の時期が国税の法定納期限等の以前であると後であるとを問わず、国税に優先し、かつ、質権、抵当権、先取特権又は担保のための仮登記により担保される債権に先立って配当を受ける。
(差押え後に成立した留置権)
16 留置権の被担保債権は、その留置権の成立の時期が差押え後であっても、法第21条の規定により、国税等に優先して配当を受けられるものとする。ただし、留置権者が、差押債権者に対抗できる占有の権原がなく、かつ、それを知り、又は過失により知らないで占有を始めたときは、その留置権の成立をもって差押債権者に対抗できないものとする(2の(4)参照)。 (注) 上記ただし書の例としては、滞納者が自動車の差押えを受け、運行の許可がされないまま保管をしていた場合(法71条5項)において、その自動車の修理を業者に依頼し、その業者がそれらのを知りながら修理をしたときの留置権がある。すなわち、この例の場合には、修理代金についての差押自動車を目的物とする留置権の成立は、差押債権者に対抗することができず、したがって、法第21条の適用はないものとする。
証明の期限等
17 法第21条の留置権が、第1項の規定の適用を受けるための証明については、第15条関係24及び25の(2)と同様である(法21条2項、令4条1項、3項、通則令2条7号)。
留置権者が配当を受けられる場合
18 留置権者は納税者の財産が滞納処分によって換価される場合においてのみ、法第21条第1項の規定により配当を受けることができる。
第22条関係 担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収
徴収できる場合
(他に国税に充てるべき十分な財産がない場合)
1 法第22条第1項の「他の国税に充てるべき十分な財産がない場合」については、次のことに留意する。
(1) 「他に」とは、法第22条第1項の譲渡した財産を除外することをいう。
(2) 十分な財産がないかどうかは、4に準じて判定する。
(3) 上記(2)の判定は、法第22条第1項の財産譲渡の時の現況により行う。
(質権又は抵当権)
2 法第22条の「質権又は抵当権」は、登記したものに限られ、登記しない質権又は抵当権については、法第22条の規定の適用がない。 (注) 通則法、法その他の国税に関する法律の規定により担保を徴した国税に係る担保権については、法第14条の規定により担保を徴した国税が他の国税又は地方税に優先するため、法第22条の規定は適用されない。
(譲渡)
3 法第22条の「譲渡」は、第17条関係1と同様である。
なお、納税者が財産を譲渡した後、その譲受人が更にその財産を譲渡した場合においても、法第22条の規定の適用がある。
(国税に不足すると認められるとき)
4 法第22条第1項の「国税に不足すると認められるとき」とは、法第22条第4項の通知を発する時の現況において、納税者に帰属する財産(国税につき徴している担保財産で、第三者に帰属しているもの及び保証人の保証を含めるものとする。)で滞納処分(交付要求及び参加差押えを含む。)により徴収できるものの価額が、納税者の国税の総額に満たないと認められることをいい、その判定は、滞納処分を現実に執行した結果に基づいてする必要はないものとする。
なお、上記の場合における財産の価額の算定については、昭和55.6.5付徴徴2-9「公売財産評価事務提要の制定について」通達に定めるところによるが、次のことに留意する。
(1) 財産について、法その他の法律の規定により納税者の国税に優先する私債権、公課、地方税又は納税者以外の者の国税がある場合には、その優先する債権額に相当する金額をその財産の処分予定価額から控除して財産の価額を算定する。
(2) 法第76条第5項((給与の差押禁止の特例))の規定により納税者の承諾がある場合に限り差押えができる給料等がある場合には、原則として、その承諾が得られないものとしてその財産の価額を算定する。
(3) 財産について、その取立てをすることとされている場合には、換価するものとしてその財産の価額を算定する。
(4) 継続収入に係る債権又は将来生ずべき債権がある場合には、換価するものとしてその債権の価額を算定する。
(5) 交付要求に係る財産がある場合には、直ちにその財産を換価したとした場合において配当を受けることができると認められる金額を基準として、その財産の価額を算定する。
(6) 滞納処分費を要すると認められる場合には、その見込額を控除して財産の価額を算定する。
(徴収できることの意味)
5 法第22条第1項の「徴収することができる」とは、質権者又は抵当権者が強制換価手続において、質権又は抵当権の被担保債権につき配当を受けるべき金額のうちから、納税者の国税を徴収できることをいい、質権者又は抵当権者はその国税についての納付義務を負うものではない。
なお、質権者又は抵当権者は、通則法第41条第1項((第三者の納付))の規定による第三者納付の場合以外は、その国税を自己の名において納付することもできない。
(抵当権付債権の譲渡等と法第22条の適用)
6 法第22条第1項の質権又は抵当権の被担保債権が第三者に譲渡された場合にも、法第22条の規定を適用することができる。
なお、法第22条1項の質権又は抵当権の被担保債権が強制換価手続により差し押さえられた場合(転付命令があった場合を含む。)において、これらの担保権の目的財産が強制換価され、その差押債権者がその執行機関から配当を受ける場合についても、同様である。
(被担保債権の弁済等と法第22条の不適用)
7 法第22条の規定により質権者又は抵当権者から納税者の国税を徴収できるのは、質権者又は抵当権者が強制換価手続において配当を受けるべき金額がある場合に限られるので、次に掲げる場合には、法第22条の規定による徴収ができない。
(1) 強制換価手続終了前に質権又は抵当権の被担保債権が弁済、免除(民法519条)、混同(同法520条)等により消滅し、配当を受けるべき金額がない場合
(2) 民法第377条((代価弁済))、第378条((てき除))等の規定により、代価弁済又はてき除により抵当権が消滅した場合(不動産質権について、同法361条((抵当権の規定の準用))の規定によりてき除等をした場合を含む。)
徴収できる金額
8 法第22条第1項の規定により納税者の滞納国税(令6条1項2号参照)を徴収することができる金額は、(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した額と納税者の滞納国税の額とのうち、いずれか少ない額である(法22条2項)。 (1) 法第22条第1項の質権又は抵当権の被担保債権が、譲渡に係る財産の換価代金から配当を受けることができる金額(次の例において「配当金額」という。)
(2) 譲渡に係る財産を納税者の財産とみなして、その財産の換価代金につき納税者の国税の交付要求があったものとした場合において、法第22条第1項の質権又は抵当権の被担保債権が配当を受けることができる金額(次の例において「仮定配当金額」という。) 〔例1〕(抵当権が1つの場合)
A 譲渡人の国税(法定納期限等昭和58. 3.15)・・・・・・・・・・8万円
B 甲抵当権の被担保債権(設定登記昭和58. 4.11)・・・・・・6万円
C 換価代金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円 イ 配当金額(Bの全額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6万円
ロ 仮定配当金額(Cの10万円-Aの8万円)・・・・・・・・・・・・2万円
ハ 徴収額の限度(イの6万円-ロの2万円)・・・・・・・・・・・・・4万円
※ 徴収できる金額(Aとハとの少額の方)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4万円
(甲抵当権者が配当を受けることができる金額6万円のうちから、4万円を徴収することができる。)
〔例2〕(抵当権が2以上ある場合)
A 譲渡人の国税(法定納期限等昭和57. 3.15)・・・・・・・・・・・6万円
B 甲抵当権の被担保債権(設定登記昭和57. 4.10)・・・・・・・3万円
C 乙抵当権の被担保債権(設定登記昭和57. 5. 1)・・・・・・・4万円
D 丙抵当権の被担保債権(設定登記昭和57. 6.21)・・・・・・・2万円
E 換価代金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円 (1) 配当金額
換価代金10万円の各抵当権に対する配当金額は、抵当権の順位により次のとおりとなる。 イ 甲抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3万円
ロ 乙抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4万円
ハ 丙抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円
(2) 仮定配当金額
換価代金10万円は、国税が交付要求をすると6万円配当され、残額の4万円は担当権の順位により次のとおりとなる。 ニ 甲抵当権(4万円の範囲内でBの全額)・・・・・・・・・・・・3万円
ホ 乙抵当権(Cは4万円あるが4万円-二の3万円)・・・・・1万円
ヘ 丙抵当権(4万円-二の3万円-ホの1万円)・・・・・・・・・・0円
(3) 徴収額の限度
各抵当権者から徴収することができる国税の金額は、(1)から(2)を控除した金額であることから、次のとおりとなる。 ト 甲抵当権(イの3万円-二の3万円)・・・・・・・・・・・・・・・・・O円
チ 乙抵当権(ロの4万円-ホの1万円)・・・・・・・・・・・・・・・3万円
リ 丙抵当権(ハの2万円-への0円)・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円
※ 徴収できる金額(トとチとリの合計額と、Aとの少額の方)・・・・5万円
(甲抵当権者が配当を受けることができる金額からは徴収できないが、乙抵当権者が配当を受けることができる金額4万円のうちから3万円 チ と丙抵当権者が配当を受けることができる金額2万円からその全額2万円 リ とを、徴収することができる。)
〔例3〕(優先抵当権と劣後抵当権とがある場合)
A 譲渡人の国税(法定納期限等昭和58. 3.15)・・・・・・・3万円
B 甲抵当権の被担保債権(設定登記昭和58. 2. 1)・・・・・・4万円
C 乙抵当権の被担保債権(設定登記昭和58. 4.10)・・・・・・5万円
D 換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円 (1) 配当金額
乙抵当権は、その設定登記の順位により甲抵当権に劣後する。そこで、乙抵当権に対する配当金額は、換価代金から甲の被担保債権を控除した残額の範囲で定まることになる。
Dの10万円-Bの4万円=6万円(ただし、乙抵当権の被担保債権は5万円であるので、5万円が配当金額となる。)・・・・・・・・・・・・5万円
(2) 仮定配当金額
法定納期限等と抵当権の設定順位に従い配当をするとすれば、国税に劣後する乙抵当権が配当を受けるべき金額は、次のとおりとなる。
Dの10万円-Bの4万円-Aの3万円・・・・・・・・・・・・・・3万円
(3) 徴収額の限度
乙抵当権者から徴収することができる国税の金額は、(1)から(2)を控除した金額であることから、次のとおりとなる。
(1)の5万円-(2)の3万円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円
※徴収できる金額(Aと(3)との少額の方)・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円
(乙抵当権者が配当を受けることができる金額5万円のうちから2万円を徴収することができるが、甲抵当権については法22条の適用がない。)
質権等の代位実行
(代 位)
9 法第22条第3項の「質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる」とは、税務署長が、質権者又は抵当権者の地位に立って、その質権又は抵当権を実行できることをいう。
なお、上記の場合において、質権又は抵当権の代位実行をするために民法第381条((てき除権者への抵当権実行の通知))の通知等の前提手続を必要とするときは、それらの手続についても代位することができる。
(他の代位権者がある場合と代位実行との関係)
10 質権者又は抵当権者に代位(民法392条、398条ノ16,499条等)してその質権又は抵当権を実行する者がいる場合には、これらの代位権者が配当を受けることができる金額からも、納税者の国税を徴収することができる(法22条1項)。
なお、上記の代位権者が質権又は抵当権の実行をしない場合には、税務署長は、その代位実行をすることができる(法22条3項)。
(実行)
11 法第22条第3項の「実行」とは、登記した質権又は抵当権が設定されている財産を執行法等の規定により売却し、その売却代金からこれらの担保権の被担保債権の弁済を受けることをいう。
なお、次に掲げる財産に対する実行は、それぞれに掲げる法令の規定により行う。
(1) 自動車抵当法の適用を受ける自動車、建設機械抵当法の適用を受ける建設機械又は航空機抵当法の適用を受ける航空機執行規則
(2) 農業動産信用法の適用を受ける農業用動産農業用動産抵当権実行令
(3) 鉄道抵当法の適用を受ける鉄道財団鉄道抵当法第3章((強制競売及強制管理))の規定のうち強制競売に関する規定
(4) 軌道ノ抵当二関スル法律の適用を受ける軌道財団又は運河法の適用を受ける運河財団軌道ノ抵当二関スル法律第1条((鉄道抵当法の準用))又は運河法第13条((運河抵当))の規定に基づき準用される鉄道抵当法第3章((強制競売及強制管理))の規定のうち強制競売に関する規定
(5) 電話加入権質に関する臨時特例法の規定により質権が登録された電話加入権執行法第193条((質権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等))の規定又は電話加入権質に関する臨時特例法第11条第1項本文((質権の実行としての特別の処分))の規定
(代位実行ができる場合)
12 法第22条第3項の規定による代位実行ができるのは、法第22条第1項の質権又は抵当権についてその実行をすることができる要件を充足した場合に限られる。この場合において、法第22条の規定により徴収することができる国税の範囲が、質権者又は抵当権者の配当を受けることができる金額の一部であるときでも、代位による実行ができる。
(原則的な実行の要件)
13 質権又は抵当権者の実行をすることができるのは、法律に特別の規定(14参照)がない限り、次に掲げる要件のすべてに該当している場合である。
(1) 登記がされている質権又は抵当権及びこれらの担保権により担保されている債権があること。
(2) 被担保債権が履行遅滞になっていること。
(3) 民法第378条((てき除))の第三取得者に対して質権又は抵当権の実行をしようとする旨の通知をし(同法381)、その通知後(第三取得者がその通知を受けた後)1月内に第三取得者から債務の弁済又はてき除の通知を受けていないこと(同法387条)。 (注) 民法第381条((てき除権者への抵当権実行の通知))の規定による抵当権実行の旨の通知については、次のことに留意する。 1 第三取得者とは、抵当不動産について所有権、地上権又は永小作権を取得した者をいい(民法378条)、抵当権者に対抗できる者に限られるから、登記をしていなければならない。しかし、これらの権利について仮登記をしている者があるときは、その者は通知を受けた後本登記をした上ででき除(同法378条)ができるので、その者に対しても、抵当権実行の旨の通知をするものとする。
2 抵当権実行の旨の通知をした後において、第三取得者から権利を承継した者が生じた場合又は新たに第三取得者が生じた場合には、それらの者には改めて通知をする必要がない(昭和4.11.20大決、昭和7.5.23大決)。
なお、上記の場合においては、第三取得者ができ除ができる期間内に限り、新たな第三取得者もでき除ができる(民法382条3項)。
3 抵当権実行の旨の通知は、登記簿記載の第三取得者の住所あてにすれば足り、その通知が到達しなかった場合において、通常到達したと認められる時から1月内に、第三取得者から債務の弁済又はてき除の通知を受けないときは、民法第387条((抵当権者の競売請求))の規定による競売の請求をすることができる(昭和6.12.11大決)。
(実行の要件の特例)
14 次に掲げる財産については、抵当権の実行ができる場合として、それぞれ次に掲げる特別の規定がある。
(1) 自動車 自動車抵当法第17条第1項及び第2項((抵当権の実行))
(2) 航空機 航空機抵当法第20条第1項及び第2項((抵当権の実行))
(3) 鉱業財団 鉱業抵当法第4条第2項及び第3項((採掘権の取消通知と抵当権の実行))並びに第5条((採掘権者の廃業通知と抵当権の実行))
(4) 漁業財団 漁業財団抵当法第4条第2項及び第3項((漁業権の取消通知と抵当権の実行))
(5) 道路交通事業財団 道路交通事業抵当法第14条第2項及び第3項((免許の取消し及び失効))
(6) 鉄道財団 鉄道抵当法第22条第1項及び第2項((免許の失効又は取消しと抵当権の実行))
(7) 軌道財団 軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条((鉄道抵当法の準用))(鉄道抵当法22条1項、2項参照)
(8) 運河財団 運河法第13条((軌道ノ抵当ニ関スル法律の準用))(鉄道抵当法22条1項、2項参照)
(9) 採掘権 鉱業法第57条第2項((採掘権の取消しと抵当権))及び第58条((採掘権の放棄と抵当権))
(10) 漁業権 漁業法第41条第2項((抵当権者の保護))
(実行の手続)
15 法第22条第3項の規定により質権者又は抵当権者に代位して実行する手続は、質権者又は抵当権者がする実行手続と同様である。この場合においては、次のことに留意する。
(1) 競売申立ての書面には、代位実行の権利を有する者であることの証明書類として、法第22条第4項((質権者への通知))の通知書の謄本と同条第1項及び第2項の規定により徴収すべき国税があることを証する書類を添付する。
(2) 競売の申立ては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(以下「法務大臣の権限法」という。)の規定により法務省の関係部局に依頼して行う。
(滞調法との関係)
16 法第22条第1項の譲渡に係る財産について強制執行又は担保権の実行としての競売(法22条に該当する質権者又は抵当権者の申立てに係るものを除く。)が開始されている場合においても、重ねて法第22条第3項の規定による実行の申立てができる(執行法47条1項、188条等)。また、譲受人の国税により当該財産について滞納処分による差押えがされている場合にも、質権者又は抵当権者に代位して質権又は抵当権の実行の申立てができる(滞調法11条の2,20条等)。 (注) 法第22条第3項の規定による実行の申立てにより執行法等による競売が開始されている場合にも、譲受人の国税を徴収するため差押えをすることができる(滞調法28条の2,35条等)。
(代位実行に係る国税等の優先)
17 法第22条第3項の規定により質権又は抵当権を代位実行した場合のその実行に係る国税は、法第12条((差押先着手による国税の優先))の規定に準じて、その実行手続につき、交付要求をした他の国税又は地方税に、優先して徴収できるものとする(法22条5項、地方税法14条の16第5項)。また、地方税法第14条の16第3項((質権等の実行))の規定により質権又は抵当権の代位実行をした場合のその実行に係る地方税は、法第22条第5項の規定により交付要求をした国税に優先して徴収できるものとする(地方税法14条の6参照)。
質権者等への通知
(徴収の通知)
18 税務署長は、法第22条第1項の規定により納税者の国税を徴収しようとするときは、令第6条第1項各号((徴収の通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により、質権者又は抵当権者に通知しなければならない(法22条4項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
なお、上記のこの書面に記載する「法第22条第1項の規定により徴収しようとする金額」については、「法第22条第2項第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額」と記載するものとする。
(通知の時期)
19 法第22条第4項の通知は、法第22条第3項の規定による質権若しくは抵当権についての代位実行の申立て又は法第22条第5項の規定による執行機関に対する交付要求をする時までに行うものとする。
(質権の処分等があった場合の通知)
20 質権若しくは抵当権の処分(民法375条、361条、398条ノ11等)又は質権付若しくは抵当権付債権の譲渡があり、その旨が付記登記されている場合の法第22条第4項の通知は、付記登記に係る質権者又は抵当権者に対してする。この場合における通知は、登記されている住所又は居所(住所又は居所が登記されている所と異なることを知っているときは、その知れている住所又は居所)あてにするものとする。
交付要求による徴収
(交付要求書)
21 法第22条第5項の規定による交付要求は、令第6条第2項((交付要求の手続))に規定する事項を記載した令第36条第1項((交付要求書の記載事項))の交付要求書(国税徴収法施行規則(以下「規則」という。)3条に規定する別紙第7号書式)により行わなければならない(令6条2項)。
(交付要求ができる時期)
22 法第22条第5項に規定する交付要求は、その相手方執行機関が配当すべき金銭を、法第22条第1項の質権者又は抵当権者に交付する時まですることができる。
(交付要求の通知)
23 法第22条第5項の規定により交付要求をしたときは、法第82条第2項及び第3項((交付要求の手続))の規定に準じて交付要求の通知をすることに取り扱う。この場合においては、次のことに留意する。
(1) 法第82条第2項に準ずる通知は、法第22条第1項の質権者又は抵当権者に対して行う。
(2) 法第22条第5項の規定による交付要求をした旨の通知は、滞納者に対してもすることに取り扱う。
(3) 法第82条第3項に準ずる通知は、強制換価手続の目的財産上の利害関係人に対してするのではなく、法第22条第1項の質権又は抵当権上の利害関係人(例えば、抵当権付債権上に質権を有する者。法55条1号、3号参照)に対して行う。
(4)(1)から(3)までの通知については、令第36条第2項及び第3項((滞納者、質権者等に対する交付要求の通知))並びに第6条第2項((交付要求))に準じて処理する。
(交付要求の解除)
24 交付要求の解除については、法第84条((交付要求の解除))の規定に準じて処理する。
この場合における法第84条第3項に準ずる通知の相手方については、23と同様に取り扱う。
(税務署長が代位実行する場合)
25 税務署長が、法第22条第3項の規定により質権者又は抵当権者に代位して、その質権又は抵当権を実行する場合には、その滞納国税を徴収するため、法第22条第5項の規定による交付要求をする必要がない。
(交付要求先着手による国税又は地方税の優先)
26 法第22条第5項の規定により先にした交付要求に係る国税は、同項の規定又は地方税法第14条の16第5項((担保権付財産が譲渡された場合の地方税の交付要求))の規定により後れてした交付要求に係る国税又は地方税に、優先して徴収できる(法13条)。また、地方税法第14条の16第5項((担保権付財産が譲渡された場合の地方税の交付要求))の規定により先にした交付要求に係る地方税は、法第22条第5項の規定により後れてした交付要求に係る国税に、優先して徴収することができる(地方税法14条の7)。
(納税者の国税と譲受人の国税との関係)
27 法第22条第1項の譲渡に係る財産の権利者の国税及び地方税と同条及び地方税法第14条の16((担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収))の規定により徴収できる国税及び地方税とは、競合関係を生じない。 (注) 納税者の国税は、法第22条の規定により譲受人の国税に優先する質権又は抵当権の被担保債権額につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することになるので、法第12条((差押先着手による国税の優先))及び第13条((交付要求先着手による国税の優先))並びに地方税法第14条の6((差押先着手による地方税の優先))及び第14条の7((交付要求先着手による地方税の優先))の規定が適用されることはない。
第4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整
第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先
担保のための仮登記の優先
(仮登記担保契約)
1 法第23条第1項の「仮登記担保契約」とは、金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記のできるものをいう(仮登記担保契約に関する法律(以下「仮登記担保法」という。)1条)。
(担保のための仮登記)
2 法第23条第1項の「担保のための仮登記」とは、仮登記担保契約で、土地又は建物の所有権又はその所有権以外の権利(先取特権、質権、抵当権及び企業担保権を除く。)の取得を目的とするものに基づく仮登記をいう(仮登記担保法1条、20条参照)。 (注) 仮登記担保契約の目的となる権利としては、土地又は建物の所有権、不動産登記法第1条(登記事項)に掲げる地上権、永小作権、地役権、賃借権及び採石権(同法2条)、立木法上の立木の所有権(同法2条)、船舶の所有権及び賃借権(商法686条、687条、船舶登記規則1条)、航空機の所有権(航空法3条の3、航空機登録令26条)、工場財団(工場抵当法14条)、鉱業財団(鉱業抵当法3条)、漁業財団(漁業財団抵当法6条)、港湾運送事業財団(港湾運送事業法26条)、道路交通事業財団(道路交通事業抵当法8条)及び観光施設財団(観光施設財団抵当法8条)の所有権、建設機械の所有権(建設機械抵当法7条、建設機械登録令9条)、ダム使用権(特定多目的ダム法20条、26条、ダム使用権登録令3条)、特許権(特許法27条、66条、98条、特許登録令2条)、実用新案権(実用新案法14条、26条、49条、実用新案登録令2条)、意匠権(意匠法20条、36条、61条、意匠登録令2条)、商標権(商標法6条、35条、71条、商標登録令2条)、漁業権(漁業法23条、50条、漁業登録令27条)及び入漁権(漁業法43条、50条、漁業登録令27条)がある。
(担保のための仮登記がされている場合)
3 法第23条第1項の「仮登記担保契約に関する法律第1条に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下「担保のための仮登記」という。)がされているとき」には、納税者に対する債権について納税者の財産の上に担保のための仮登記がされている場合のほか、納税者以外の者に対する債権について納税者の財産の上に担保のための仮登記がされている場合(納税者が物上保証人となっている場合)も含まれる。 (注) 債務不履行を停止条件とする代物弁済契約に基づく権利移転請求権保全の仮登記、代物弁済の予約に基づく権利移転請求権保全の仮登記、債務不履行を停止条件とする賃借権、地上権等の設定請求権保全の仮登記等実質的な意味で金銭債権担保の機能を果たしている仮登記は、担保のための仮登記に当たるものとする。
(法定納期限等以前にされている担保のための仮登記)
4 法第23条第1項の「法定納期限等以前」には、その法定納期限等に当たる日を含む。したがって、その日にされた担保のための仮登記も、法定納期限等以前にされた担保のための仮登記となる。
債権額の範囲
(担保のための仮登記の目的物の価額)
5 法第23条第1項の「換価代金」には、担保のための仮登記がされた財産のほか、従物、付加物等担保のための仮登記の効力の及んでいるものの換価代金も含まれる。
(担保のための仮登記によって担保される債権額)
6 担保のための仮登記によって担保される債権額の範囲については、次のことに留意する。
(1) 担保のための仮登記がされている財産につき強制換価手続が行われた場合において、その担保のための仮登記の権利者(以下「仮登記担保権者」という。)が、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ権利を行使することができる(仮登記担保法13条2項)。また、仮登記担保権者が債務の不履行により生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においても、その最後の2年分について権利を行使することができる(同法13条3項本文)。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない(同項ただし書)。
(2) 仮登記担保権者が、担保のための仮登記の実行の通知に基づき、その財産を取得する場合には、仮登記担保法第13条第2項及び第3項(20条において準用する場合を含む。)は適用されないから、利息その他の定期金は2年分に限定されない。
担保のための仮登記がある財産の差押え
(清算期間の経過前にされた本登記の効力)
7 清算期間の経過前に、仮登記担保権者のために担保のための仮登記に基づく本登記がされていても、その所有権等の移転の効力は生じない(仮登記担保法2条1項参照)から、この場合には、債務者である滞納者に代位しその本登記を抹消の上、担保のための仮登記がされている財産を差し押さえることができる。 (注) 清算期間とは、仮登記担保権者が仮登記担保契約によって財産を取得しようとする場合に行う清算金(仮登記担保法3条1項に規定する清算金をいう。)に係る見積額の通知書が、その契約の相手方である債務者又は第三者に到達した日から2月の期間をいう(同法2条1項参照)。
(清算期間の経過前にされた清算金の支払と財産の差押え)
8 清算期間を経過しなければ、担保のための仮登記がされた財産の権利移転の効力は生じない(仮登記担保法2条1項、20条)から、清算期間の経過前においては、清算金の支払がされても、その財産の差押えができる。
清算金の支払請求権に対して物上代位権の行使があった場合の優先
(清算金)
9 法第23条第2項の「清算金」とは、清算期間が経過した時における担保のための仮登記がある財産の価額から、その時の債権及び債務者又は第三者が負担すべき費用で仮登記担保権者が代わって負担したものの額(仮登記担保法2条2項参照)とを控除した額に相当する金銭をいう。
(物上代位)
10 仮登記担保法第4条第1項に規定する物上代位とは、担保のための仮登記がされている場合において、その仮登記後に登記がされた先取特権、質権又は抵当権を有する者が、債務者又は第三者の清算金の支払請求権を差し押さえることにより、先取特権等の効力をその順位に従って清算金の支払請求権に及ぼすことができることをいう。
なお、担保のための仮登記後にされた担保のための仮登記の権利者の物上代位についても同様である(仮登記担保法4条2項、3項)。
(物上代位権の行使があった場合の債権額の範囲)
11 物上代位権の行使に係る担保権によって担保される債権が弁済を受けることのできる金額の範囲は、担保のための仮登記がされた財産の換価代金から配当を受け得る場合と同様に、元本のほか最後の2年分の利息又は損害賠償債権等の金額に限られる(仮登記担保法4条3項、20条、民法374条等)。
清算金の支払請求権の差押え
(清算金の支払請求権者)
12 清算金の支払請求権を有する者は、担保のための仮登記がされた財産が譲渡された場合においても、仮登記担保契約の相手方である債務者又は第三者である(仮登記担保法3条1項、20条)。
(差し押さえることができる清算金支払請求権の範囲)
13 差し押さえることができる清算金の支払請求権(供託金の還付請求権を含む。以下14から16までにおいて同じ。)は、仮登記担保権者が行った担保のための仮登記の実行の通知に係る清算金の見積額の範囲内に限られない。したがって、通知した清算金の見積額が過少であると認められるときは、正当な清算金の額に達するまで差し押さえることができる。
(差押えをすることができる時期)
14 清算金の支払請求権に対する差押えは、仮登記担保権者が仮登記担保権の実行の通知をした後清算金の支払又は供託をするまでの間は、することができる。
(物上代位権者への差押えの通知)
15 清算金の支払請求権について差押え又は交付要求をした場合において、既に、その清算金の支払請求権に対する物上代位権の行使(仮登記担保法4条1項又は2項(物上代位)に規定する権利の行使をいう。)による差押えをした者があるときは、その者に対して書面により差押え(法55条)又は交付要求(法82条3項)の通知をするものとする。この場合の書面は、別に定めるところによる。
(受戻権の行使と清算金の支払請求権に対する滞納処分との関係)
16 清算金の支払請求権を差し押さえた場合において、仮登記担保権者が、清算期間経過後、清算金を差押債権者に支払又は供託する以前に、債務者又は第三者が、債権等の額(債権が消滅しなかったものとすれば債務者が支払うべき債権等の額をいう。)に相当する金銭(9参照)を仮登記担保権者に提供して、担保のための仮登記がされた財産の受戻権を行使したとき(仮登記担保法11条本文)は、清算金の支払請求権に対する差押えの効力は失われる。 (注) 受戻権とは、債務者又は第三者が、仮登記担保権者から清算金の支払債務の弁済を受けるまで、債権等の額に相当する金銭を仮登記担保権者に提供して、担保のための仮登記がされている財産の受戻しを請求することができる権利をいう。
根担保仮登記の効力
17 仮登記担保契約で消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記は、強制換価手続においてはその効力を有しない(法23条4項、仮登記担保法14条、20条)ので、国税の徴収との関係においては、担保のための仮登記によって担保される債権が存在しないものとして取り扱われることになる。
第24条関係 譲渡担保権者の物的納税責任
譲渡担保財産からの徴収
(譲渡担保財産)
1 法第24条の「譲渡担保財産」とは、納税者がその所有する財産を債権者又は第三者に譲渡し、その譲渡により、自己又は第三者の債務の担保の目的となっている財産をいう(昭和5.10.8大判参照)。
なお、動産、有価証券、債権、不動産、無体財産権等のほか、法律上まだ権利と認められていないものであっても、譲渡できるもの(手形を除く。法附則5条4項)は、すべて譲渡担保の目的物とすることができる。 (注)1 譲渡担保設定契約には、次のようなものがある(昭和8.4.26大判参照)。 (1) 債権の担保の目的をもって担保の目的物を債権者に譲渡し、その担保に係る債務を履行した場合には債務者がその目的物の返還を受け、不履行の場合には債権者がその財産を換価して優先弁済を受けるか又はその財産を確定的に取得することができる旨の譲渡担保設定契約
(2) 担保のための権利の移転につき売買の形式をとるもので、売主が将来対価を支払って目的物を売主に買い戻す権利を留保した売買(買戻約款付売買)の形式をとる譲渡担保設定契約又は売却した目的物につき売主が将来予約完結権を行使することによって再度売買契約が成立し、その効果としてその目的物が再び売主に戻る旨の予約(再売買の予約)の形式をとる譲渡担保設定契約
2 債務不履行の場合には、譲渡担保財産を確定的に取得することができる旨の特約があっても、債務者が債務の履行をしないときは、債権者は譲渡担保財産を換価又はこれを評価した価額から債権額を控除し、残額を債務者に支払わなければならない(昭和46.3.25最高判)。
3 債務者は、弁済期を経過しても、帰属清算型(債権者が自らその目的物の帰属主体となり、その価額を適正に評価して差額を債務者に支払うもの)の譲渡担保の場合は、債権者がその実行をしない間は、元利金を弁済して譲渡担保財産を受け戻すことができる(昭和47.11.24最高判)。また、処分清算型(債権者が目的物を第三者に処分して、その換価代金のなかから元利金を差し引いた残額を債務者に支払うもの)の譲渡担保の場合においても、債権者が譲渡担保財産を換価するまでは(対抗要件として登記を必要とするものについては、第三者への移転登記をするまでの間をいう。昭和50.11.28最高判参照)、同様である(昭和43.3.7最高判)。
(国税に不足すると認められるとき)
2 法第24条第1項の「国税に不足すると認められるとき」とは、第22条関係4と同様である。
ただし、不足するかどうかの判定は、法第24条第2項の告知書を発する時の現況によるものとする。 (注) 譲渡担保財産上に滞納者が有する法第25条第1項((譲渡担保財産の換価の特例))の買戻権の登記等に係る権利がある場合には、その権利の価額と滞納者の有する滞納処分ができる他の財産との価額の合計により、上記の不足するかどうかの判定をする。
(譲渡担保権者に対する告知)
3 税務署長が、法第24条第2項前段の規定により譲渡担保権者に対してする告知は、令第8条第1項各号((告知書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第1号書式の告知書により行う。
(徴収することができる金額)
4 譲渡担保財産から徴収することができる金額は、法第24条第1項及び第6項の規定の要件に該当することにより徴収することができる滞納国税(令8条1項2号参照)の全額であって、納税者の財産が徴収すべき滞納国税に不足すると認められる場合のその不足額に限られない。
(税務署長等に対する通知)
5 法第24条第2項後段の規定により、譲渡担保権者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)の所在地を所轄する税務署長及び納税者に対してする通知は、令第8条第2項各号((通知書に記載すべき事項))に掲げる事項を記載した書面により行う。この書面の様式は、別に定めるところによる。
譲渡担保財産に対する滞納処分
(10日を経過した日)
6 法第24条第3項の「告知書を発した日から10日を経過した日まで」とは、告知書を発した日を第1日として12日目の日までをいう(通則法10条1項1号参照)。
(注) 法第24条第3項の「発した日」については、第15条関係1の(2)の(注)と同様である。
(完納されていないとき)
7 法第24条第3項の「完納されていないとき」とは、納税者又は第三者(譲渡担保権者を含む。)の納付又は充当による完納がされていない場合のほか、免除、賦課の取消し等により徴収しようとする金額に係る納税者の国税の全額が消滅していないときをいう。
(みなし第二次納税義務者)
8 法第24条第3項の「第二次納税義務者とみなして」とは、譲渡担保財産に対する滞納処分の執行に限り、第二次納税義務者とみなすだけではなく、法の他の規定(法10章の規定を除く。)の適用についても第二次納税義務者とみなされることをいう(法24条7項参照)。
(譲渡担保財産からの徴収)
9 譲渡担保権者は、納税者の国税についての納付義務を負うものではないから、次の規定は、譲渡担保財産からの徴収については適用されない。
(1) 法第32条(3項から5項までを除く。)から第39条まで及び第41条第2項((第二次納税義務の通則等))
(2) 法第151条から第159条まで((滞納処分に関する猶予及び停止等))
(3) 通則法第4章第1節((納税の猶予))及び第55条((納付委託))
(督促の不要)
10 法第24条第2項の告知書を発した日から10日を経過した日までに告知書により告知した徴収しようとする金額が完納されていないときは、督促(納付催告書による督促を含む。)を要せず、直ちに滞納処分をすることができる。
(差押えの繰上げ)
11 通則法第38条第1項((繰上請求))の規定の準用に当たっては、同項の「納付すべき税額の確定した国税」は「法第24条第2項の告知をした徴収しようとする金額」を、また通則法第38条第1項の「納期限」は「法第24条第2項の告知書を発した日から10日を経過した日」を、それぞれいうものとする。
(納税者等が占有する譲渡担保財産に対する差押え等)
12 譲渡担保財産につき滞納処分を執行する場合において、当該譲渡担保財産を納税者又はその者の特殊関係者(令13条1項各号参照)が占有しているときは、法第58条((第三者が占有する動産等の差押手続))及び第59条((引渡命令を受けた第三者等の権利の保護))の規定(法71条4項等において準用する場合を含む。)は、適用されない(令24条4項、6項)。
(保険に付されている譲渡担保財産に対する差押えの効力)
13 譲渡担保財産を差し押さえた場合に、その財産が、譲渡担保権者を受取人とする法第53条第1項((保険に付されている財産に対する差押えの効力))の損害保険に付され又は共済の目的となっているときは、同項の規定が適用されるから、その財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知する。この通知については、第53条関係13に準じて行うものとする。 (注) 譲渡担保財産を差し押さえる前にその財産が火災その他により滅失等をし、これに基因して譲渡担保権者が保険金、共済金又は補償金を受領できる場合においては、それらに係る請求権等を譲渡担保財産として、法第24条の規定を適用することができる。
(譲渡担保財産の範囲)
14 法第24条第3項の規定により滞納処分ができる譲渡担保財産の範囲は、おおむね、次に掲げるとおりとする。
(1) 譲渡担保財産の付加物及び従物 (注) 付加物及び従物が除外される場合は、次に掲げる場合である。 1 設定行為に別段の定めがあったとき(民法370条ただし書参照)。
2 民法第424条((詐害行為取消権))の規定により、債権者が、債務者の行為を取り消すことができるとき(同法370条ただし書参照)。
3 納税者及び譲渡担保権者以外の第三者が、権原によりその財産につき付加行為をしたとき(民法242条ただし書、大正6.4.12大判)。
(2) 企業用動産等を一括して譲渡担保とした場合においては、集合物としての同一性のある限り、その譲渡担保権の設定後その集合物に加えられたもの(昭和30.12.6大阪地判)
(譲渡担保財産の譲渡の場合)
15 譲渡担保財産が譲渡担保権者から更に譲渡された場合において、その譲渡が法第24条第3項又は第4項の規定による差押え後にされたものであるときは、その差押えに係る滞納処分の続行ができる。
(第1項の要件に該当する場合)
16 法第24条第4項の「同項の要件に該当する場合」とは、次の要件を満たしている場合の納税者の国税に係る差押えをいう。
(1) 納税者が譲渡した財産で、その譲渡により担保の目的となっている財産があること。
(2) 納税者の財産につき滞納処分を執行しても、なお徴収すべき国税に不足すると認められること。
(3) 差押えに係る国税の法定納期限等が、その譲渡担保の譲渡に係る権利の移転の登記時前にあること(譲渡担保権者が法24条6項に規定する証明ができなかったときを含む。)。
(交付要求等をした場合の効力)
17 譲渡担保財産を法第24条第1項の納税者の財産としてした参加差押え又は交付要求については、次に掲げるところによる。
なお、参加差押え又は交付要求が有効である場合は、法第24条第4項後段に規定する告知及び通知をしなければならない。
(1) 参加差押え又は交付要求をした相手先の差押えが、法第24条第4項の規定に基づき、同条第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる場合には、同条の規定により譲渡担保財産から徴収することができる国税に係る参加差押え又は交付要求である場合に限り有効である。
(2) 参加差押え又は交付要求をした相手先の差押えが、法第24条第1項の要件を満たさないことにより同条第4項の規定の適用を受けないものであるときは、その差押えは取り消されるので、交付要求は効力を失うことになるが、参加差押えが法第24条第4項の規定によるものであるときは有効な差押えとなる。
(3) 法第24条第1項の要件を満たさないことにより同条の規定が適用されない国税に係る参加差押え又は交付要求は、同条第4項の規定が適用されず、取り消されるべきものである。
抵当権等との関係
(譲渡前に譲渡担保財産上に抵当権等がある場合)
18 質権、抵当権、先取特権等がある財産が譲渡され、その譲渡に係る譲渡担保財産が、強制換価手続により換価された場合の法第24条第1項の規定によりその譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税と、譲渡担保権者の国税及びその抵当権等の被担保債権との優先関係については、次に掲げるところによる。
(1) 納税者の国税と抵当権等の被担保債権との関係 イ 法第24条第1項の規定により譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税の法定納期限等は、法第15条第1項第6号((告知に係る法定納期限等))の規定により、法第24条第2項の告知書を発した日となるので、抵当権等の被担保債権は、原則としてその納税者の国税に優先する(法15条、16条、19条、20条)。
ロ 法第22条((担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収))の規定により、その登記された質権又は抵当権の被担保債権につき配当を受けるべき金額から納税者の国税を徴収できるときは、同条に規定する手続によりその国税を徴収することができる。
(2) 譲渡担保権者の国税と抵当権等の被担保債権との関係
抵当権等の被担保債権は、原則として譲渡担保権者の国税に優先する(法17条、19条、20条)。
(3) 納税者の国税と譲渡担保権者の国税との関係
法第24条第1項の規定により譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税は、譲渡担保権者の国税の法定納期限等とは関係なく、原則として、譲渡担保権者の国税に優先する(令9条)。 (注) 譲渡担保権者の国税が法第14条((担保を徴した国税の優先))の規定に該当する場合には、納税者の国税は譲渡担保権者の国税に劣後する。
(4) 納税者の国税と譲渡担保権者の国税と抵当権等の被担保債権との関係
原則として、まず第1に抵当権等の被担保債権に、第2に法第24条第1項の規定により譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税に、第3に譲渡担保権者の固有の国税に、それぞれ充てる。この場合に、第2の国税が満足を受けず、かつ、法第22条((担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収))の規定に該当するときは、上記(1)のロにより、その満足を受けない部分につき、第1の債権者が受ける金額からその国税を徴収する。
(譲渡後に譲渡担保財産に設定した抵当権等がある場合)
19 納税者の財産が担保の目的で譲渡され、その譲渡に係る譲渡担保財産に抵当権その他の担保権の設定等があった後、その財産が強制換価手続により換価された場合の法第24条第1項の規定によりその譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税と譲渡担保権者の国税と抵当権等の被担保債権との優先関係については、次による。
(1) 納税者の国税と抵当権等の被担保債権との関係
法第24条第1項の規定により譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税の法定納期限等は、法第15条第1項第6号の規定により、法第24条第2項の告知書を発した日となるので、その日と抵当権の設定等の日とを比較し、法第15条、第16条又は第18条から第20条まで((法定納期限等以前に設定された質権等の優先))の規定によりその優劣が定められる。
(2) 譲渡担保権者の国税と抵当権等の被担保債権との関係
譲渡担保権者の国税の法定納期限等と抵当権の設定等の日とを比較し、法第15条、第16条又は第18条から第20条まで((法定納期限等以前に設定された質権等の優先))の規定によりその優劣が定められる。
(3) 納税者の国税と譲渡担保権者の国税との関係
法第24条第1項の規定により譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税は、原則として譲渡担保権者の国税に優先する(令9条)。 (注) 譲渡担保権者の国税が法第14条((担保を徴した国税の優先))の規定に該当する場合には、納税者の国税は譲渡担保権者の国税に劣後する。
(4) 納税者の国税と譲渡担保権者の国税と抵当権等の被担保債権との関係
(1)から(3)までによって優先関係を定めるが、なお定まらない場合には、法第26条((国税及び地方税等と私債権との競合の調整))の規定によって優先関係を定める。
(譲渡担保財産上に譲渡前後に抵当権等がある場合の抵当権等と納税者の国税と譲渡担保権者の国税との関係)
20 譲渡が仮にないとした場合において、納税者の国税(7万円)に劣後する抵当権(甲8万円)がその譲渡担保財産上にあり、その譲渡後その財産上に納税者の国税に優先し、譲渡担保権者の国税(4万円)に劣後する抵当権(乙3万円)が設定された場合において、その譲渡担保財産を譲渡担保権者の国税で換価し、その換価代金(13万円)を配当する場合の配当額は、次のようになる。
(1) 一次的の配当金額は、法第17条((譲受前に設定された質権又は抵当権の優先))の規定により甲抵当権に8万円、法第16条((法定納期限等以前に設定された抵当権の優先))の規定により譲渡担保権者の国税に4万円、乙抵当権に1万円となる。 (注) 納税者の国税は、乙抵当権の設定がその国税の法定納期限等(法15条1項6号)以前であることから、乙抵当権には劣後する。したがって、換価代金が13万円であることから、納税者の国税には配当はない。
(2) 納税者の国税は、令第9条((譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例))の規定により譲渡担保権者の国税に先立って徴収するから、(1)による譲渡担保権者の国税の配当金額4万円は、その全額が納税者の国税に配当すべき金額となる。
(3) 納税者の国税は、(2)によっても徴収できない金額3万円(納税者の国税7万円-(2)の配当を受けた金額4万円)につき、法第22条((担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収))の規定により徴収できる範囲の金額2万円を、(1)による甲抵当権者の配当を受けるべき金額8万円から徴収できるので、納税者の国税は、更に2万円の配当を受ける。
(4)(1)から(3)までにより、甲抵当権に6万円、納税者の国税に6万円、乙抵当権に1万円の配当となる。
(第4項の規定の適用を受ける差押え)
21 法第24条第5項の「前項の規定の適用を受ける差押」とは、譲渡担保財産を納税者の財産としてした差押えであって、かつ、法第24条第1項及び第6項の要件に該当する差押えをいう。この場合には、法第24条第4項後段の規定に基づく第2項の告知及び通知をしていることは必要でない。
(その他弁済以外の理由)
22 法第24条第5項の「その他弁済以外の理由」とは、譲渡担保財産により担保される債権が消滅する場合において、譲渡担保財産が納税者に復帰しないこととなる場合のものをいう。したがって、相殺(民法505条)、免除(同法519条)、混同(同法520条)、消滅時効の完成(同法166条以下)等により、譲渡担保財産により担保される債権が消滅した場合は、これに該当しない。
(期限の経過)
23 法第24条第5項の「期限の経過」とは、それによって納税者が譲渡担保財産を自己に復帰させることを請求できないこととなる期限の経過をいう。なお、次のことに留意する。
(1) 買戻約款付売買の場合
買戻約款付売買契約において定められている買戻しができる期間は、民法第579条((買戻し特約))に規定する買戻権については次のとおりであり、その他の買戻約款付売買については契約に定められている期間による(昭和9.8.3大判、大正8.11.10東京地判、昭和8.4.26大判)。 イ 買戻しの期間は、10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは10年に短縮される(民法580条1項)。
ロ 買戻期間を定めたときは、その後この期間を伸長することができない(民法580条2項)。
ハ 買戻期間を定めないときは、5年内に限り買戻権の実行ができる(民法580条3項)。
(2) 再売買の予約の場合
再売買の予約による予約期間は、その契約の定めるところによるが、その期間の定めがない場合には、予約完結権はそれを行使できるときから20年間で消滅時効にかかる。
(契約の履行以外の理由)
24 法第24条第5項の「その他その契約の履行以外の理由」とは、納税者が譲渡担保財産を自己に復帰させることを請求できる権利が消滅することとなる理由のうち、期限の経過及びその契約の履行以外の理由をいい、買戻権又は再売買の予約の完結権の消滅時効の完成等がこれに該当する。
(第5項の適用がない場合)
25 法第24条第5項の規定により、譲渡担保財産として存続するものとみなして法第24条第3項の規定を適用できる場合であっても、法第24条第3項の差押え前に、譲渡担保財産が譲渡担保権者から更に譲渡された場合には、法第24条第5項の規定によって譲渡担保財産として存続するものとみなすことはできない(15参照)。
(譲渡担保財産が納税者に復帰した場合)
26 譲渡担保財産につき法第24条第3項の差押えをした後、その譲渡担保財産が納税者に復帰した場合には、その差押えは、納税者の財産としてした差押えとして、滞納処分の続行ができるものとする。この場合には、税務署長は、遅滞なく、譲渡担保権者及び納税者にその旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
証 明
(譲渡に係る権利の移転の登記がある場合)
27 担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記が国税の法定納期限等以前にあることについては、徴収職員が調査の上確認しなければならない。
(譲渡に係る権利の移転の登記がない場合)
28 譲渡担保財産が権利移転の登記の制度がないものであるときは、譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている事実を、その財産の売却決定の日の前日(譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日)までに証明しなければ、法第24条第1項の規定が適用される(法24条6項、令8条3項後段)。この場合の証明手続については、第15条関係25に準ずる(令8条3項前段、4条1項、2項)。 (注) 上記の場合の証明の期限については、通則法第10条第2項((期限の特例))の規定の適用がない(通則令2条7号)。
(法定納期限等以前)
29 法第24条第6項の「法定納期限等以前」には、その法定納期限等に当たる日を含む。したがって、その日に設定された譲渡担保も、法定納期限等以前に設定された譲渡担保となる。
(譲渡担保財産が集合物である場合)
30 集合物が譲渡担保財産である場合において、その担保権設定後その集合物に財産を加えたときにおける法第24条第6項の規定の適用に当たっては、その加えられた財産が集合物として同一性がある限り、当初の譲渡担保設定のための譲渡の時期をもって、その財産の譲渡担保財産となった時として取り扱う。 (注)1 構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となり得る(昭和54.2.15最高判)。
この集合物としての譲渡担保が認められたものとしては、特定の倉庫に存する商品の全部(昭和30.12.6大阪地判)、自社の出版物の全部(昭和32.3.19東京地判)、特定の店舗に存する一切の什器、備品、商品(昭和47.3.29東京高判)等がある。
2 譲渡担保設定後その集合物に新たに財産が加えられたため、その譲渡担保財産の価額が、当初の譲渡担保財産の価額を超える場合には、その超えている部分に相当する財産については、譲渡担保を新たに設定したものとして取り扱う。
(譲渡担保財産が有価証券である場合)
31 有価証券が譲渡担保財産である場合において、その担保権設定後、その有価証券につき、有価証券による担保の差換えをしたときにおける法第24条第6項の規定の適用に当たっては、その差し換えた有価証券が譲渡担保財産として同一性がある限り、当初の譲渡担保設定のための譲渡の時期をもって、その有価証券の譲渡担保財産となった時として取り扱う。
譲渡担保権者が破産した場合
32 法第24条第3項又は第4項の規定による差押えをした後、譲渡担保権者について破産宣告があった場合には、滞納処分の続行ができる(第47条関係40,41参照)。
なお、譲渡担保権者が破産した場合には、その譲渡担保財産は破産財団を構成するものとなり、納税者はそれを取り戻すことができないが(破産法88条)、損害賠償請求権を取得し(民法415条後段)、その債権と譲渡担保財産により担保される債権とを相殺することができる(破産法104条4号ただし書)。
第25条関係 譲渡担保財産の換価の特例等
一括換価
(意義)
1 法第25条第1項の「一括して換価する」とは、法第24条第3項後段((第二次納税義務の通則に関する規定等の準用))において準用する第32条第4項((第二次納税義務者の財産の換価の順序))の規定にかかわらず、滞納者の財産である差押えをした買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記その他これに類する登記(以下第25条関係において「買戻権の登記等」という。)に係る権利と、法第24条第3項((譲渡担保財産に対する滞納処分))又は第4項((納税者の財産としてした譲渡担保財産に対する差押えの効力))の規定により差し押さえた譲渡担保財産を、一体のものとして換価することをいう。
(残余を交付すべき者)
2 法第25条第1項の規定により一括換価をした場合には、まず滞納者の財産である買戻権の登記等に係る権利を換価し、その後に譲渡担保財産を換価したものとして配当するものとし、配当した金銭に残余があるときは、その残余を譲渡担保権者に交付するものとする。ただし、その残余が譲渡担保財産の価額に相当する部分を超えるときは、その超える部分の残余は滞納者に交付するものとする。
(買戻権等に対抗できない担保権等の消滅)
3 法第25条第1項の規定による一括換価をした場合には、買戻権の登記等に係る権利に対抗できない担保権、用益物権、賃借権等の権利は、実体的に消滅するものとして換価する(第89条関係9参照)。
第5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
趣旨及び法第26条の類推適用
1 法第26条は、強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下第26条関係において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下第26条関係において「私債権」という。)と競合する場合において、国税と私債権の間の優先順位、地方税等とその私債権の間の優先順位及びその国税と地方税等の間の優先順位が交錯することによって、これら三者の優先順位を定めることができないとき(この場合の競合を「特殊な競合」という。以下第26条関係において同じ。)の具体的な配当の方法を定めたものである。
なお、上記以外の場合で、国税、地方税等及び私債権が競合し、これらの債権間の優先順位が交錯してその順位を定めることができないときは(第17条関係7、第18条関係6、法19条、20条等参照)、法第26条の規定を類推適用するものとする。 〔例〕 抵当権の被担保債権額(設定登記昭和57. 6.30)・・・・・・・10万円
差押国税 (法定納期限等昭和57. 7.31)・・・・・・・・・・・5万円
交付要求地方税 (法定納期限等昭和57. 4.30)・・・・・・・・・・3万円
滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17万円
※配当額の計算 イ まず、法第26条第1号の規定により、滞納処分費の1万円に充てる。
ロ 次に、法第26条第2号の規定により、抵当権設定の登記及び国税、地方税の法定納期限等の古い順に従って、国税及び地方税並びに私債権に充てるべき金額の総額を定めると、(1)交付要求地方税3万円、(2)抵当権10万円、(3)差押国税3万円となり、私債権の総額は10万円、国税及び地方税の総額は6万円となる。
ハ 次に、法第26条第3号の規定により、国税及び地方税に充てるべき金額は、法第12条((差押先着手による国税の優先))の規定により、差押国税5万円、交付要求地方税1万円となる。
ニ 法第26条第4号の規定により抵当権に10万円充てる。
ホ 上記の結果、配当額は次のとおりになる。 滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
交付要求地方税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
特殊な競合の原因となる規定
2 法第26条本文の「この章又は地方税法その他の法律の規定」とは、特殊な競合の直接の原因となる国税と地方税等との優先順位を定める規定(例えば、法8条、12条、13条、14条、令9条、これらに相当する地方税法14条、14条の6から14条の8までの規定、船員保険法13条の規定等公課の優先順位に関する規定等)並びに国税と私債権との優先順位を定める規定及び地方税等と私債権の優先順位を定める規定(例えば、法8条、15条、16条、20条、地方税法14条、14条の9,14条の1O,14条の14、船員保険法14条の規定等)をいい、私債権間の優先順位を定める規定及び法第26条第1号に規定する規定は、含まれない。
道府県たばこ税等の優先
3 法第26条第1号の「これに相当する優先権を有する地方税」とは、地方税法第13条の3((強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収))の規定により徴収する道府県たばこ税、市町村たばこ税、軽油引取税及び自治大臣の指定する法定外普通税(同法4条1項、3項、5条1項、3項参照)をいう。 〔参考〕 地方税法第14条の5((地方団体の徴収金のうちの優先順位))の規定は、同条の延滞金等と地方税間の内部的な徴収の順位を定めたものである。
質権等の設定等の時期
4 法第26条第2号の「設定、登記、譲渡若しくは成立の時期」については、次のとおりである。
(1) 「設定」の時期とは、登記することができない質権で有価証券以外のものを目的としているものについては、法第15条第3項((みなし質権設定日))又は地方税法第14条の9第4項((みなし質権設定日))の規定によりその質権が設定されたものとみなされた日をいい(第15条関係28参照)、登記することができない質権で有価証券を目的とするものについては、法第15条第2項前段((証明))又は地方税法第14条の9第3項((証明))の証明をした場合の占有した日をいう。
(2) 「登記」の時期とは、登記をすることができる質権、抵当権及び法第20条第1項第2号から第4号まで((不動産売買の先取特権等))に掲げる先取特権及び担保のための仮登記について、これらに係る設定又は保存の登記の日をいう(第15条関係30、33、第16条関係8、第18条関係15参照)。
(3) 「成立」の時期とは、法第20条第1項第1号((不動産賃貸等の先取特権))に掲げる先取特権について、同条第2項((証明))において準用する法第19条第2項((証明))の証明をした場合の成立の日をいう。
第2号のこの章又は地方税法その他の法律の規定
5 法第26条第2号の「この章又は地方税法その他の法律の規定」とは、法第26条第1号の費用等を除いたものにつき、その国税と私債権の優先順位又はその地方税等と私債権との優先順位を定める規定をいい、国税、地方税及び公課間の優先順位を定める規定並びに私債権間の優先順位を定める規定をいうものではない。
民法その他の法律の規定
6 法第26条第4号の「民法その他の法律の規定」とは、私債権の優先順位を定めるに当たって適用すべき法律の規定をいう。この場合においては、法第15条第4項((証明できなかった質権と他の質権との関係))又は地方税法第14条の9第5項((証明できなかった質権と他の質権との関係))の規定が適用される場合がある。
第1節 一般的優先の原則
第8条関係 国税優先の原則
納税者の総財産
1 法第8条の「納税者の総財産」とは、納税者に帰属する財産で差押えが禁止されているものを除いたすべての財産をいうが、次に掲げる場合には、それぞれに掲げる財産に限定される。
(1) 法第24条((譲渡担保権者の物的納税責任))の規定により、譲渡担保権者を第二次納税者とみなして納税者の国税をその譲渡担保財産から徴収する場合には、その譲渡担保財産
(2) 法第36条第1号((実質課税額等の第二次納税義務))の規定により、国税の賦課の基因となった収益が生じた財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産(取得財産を含む。)
(3) 法第36条第2号((実質課税額等の第二次納税義務))の規定により、国税の賦課の基因となった資産の貸付けに係る財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産(取得財産を含む。)
(4) 法第37条((共同的な事業者の第二次納税義務))の規定により、納税者の事業の遂行に欠くことができない第二次納税義務者の重要な財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産(取得財産を含む。)
(5) 法第38条((事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務))の規定により、納税者からの事業譲渡により譲り受けた財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産(取得財産を含む。)
(6) 法第41条第1項((人格のない社団等に係る名義人の第二次納税義務))の規定により、納税者の財産で法律上第二次納税義務者に帰属するとみられる財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産
(7) 通則法第52条第1項((担保の処分))の規定により、物上保証人が提供した担保財産から納税者の国税を徴収する場合には、その財産
(8) 限定承認をした相続人が承継した被相続人の国税を徴収する場合には、その相続により取得した財産
別段の定め
2 法第8条の「別段の定」とは、法第2章((国税と他の債権との調整))に規定する事項のうち第9条から第11条まで((強制換価手続の費用等の優先))、第15条から第21条まで((法定納期限等以前に設定された質権の優先等))、第23条((法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等))及び第26条((国税及び地方税等と私債権との競合の調整))に規定されている事項をいう。
国税の優先徴収
(その他の債権)
3 法第8条の「その他の債権」とは、国税、地方税及び公課以外の債権で金銭の給付を目的とするものをいう。
(優先徴収)
4 法第8条の「先だって徴収する」とは、納税者の財産が強制換価手続により換価された場合に、その換価代金から国税を優先して徴収することをいう。
国税の優先徴収の例外
(法における優先徴収の例外)
5 法第59条第3項後段及び第4項((動産の前払賃料の優先配当))並びに第71条第4項((自動車等の前払賃料の優先配当等の準用規定))の規定により、これらに規定する前払借賃に相当する債権が国税(法10条の滞納処分費を除く。)に先立って配当されることがある。
(他の法律における優先徴収の例外)
6 法以外の法律の規定により、国税が地方税、公課その他の債権と同順位又は後順位になる場合として、次のものがある。
(1) 地方税法第14条の4((強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先))又は第14条の8((担保を徴した地方税の優先))の規定により、道府県たばこ税、市町村たばこ税又は軽油引取税等の地方税に後れて配当を受けることがある。
(2) 収容貨物が関税法の規定により公売又は随意契約により売却された場合には、同法第85条第1項((公売代金等の充当))の規定により、公売又は随意契約による売却に要した費用、収容に要した費用、収容課金及び関税が国税に優先する。
(注) 上記の場合においては、国税は質権又は留置権により担保される債権に先立って配当される(関税法85条2項)。
(3) 国税を徴収すべき外国貨物について、関税を徴収するための換価又は交付要求をした場合には、関税法第9条の4第1項及び第2項後段((徴収の順位))の規定により、関税が国税に優先する。
公課が徴した担保との関係
7 公課が担保を徴している場合における当該公課と国税との関係は、公課に関する法律が国税に劣後する旨の優先順位を規定しているにかかわらず、法第2章第3節から第5節まで((国税と被担保債権との調整等))に規定する私債権と国税との関係と同様に取り扱うものとする。
第9条関係 強制換価手続の費用の優先
交付要求
1 法第9条の「交付要求」とは、法第82条第1項((交付要求の手続))、第86条第1項((参加差押えの手続))、第159条第9項((保全差押えに係る交付要求))(通則法38条4項において準用する場合を含む。)、滞調法第36条の10第1項((みなし交付要求))及び通則法第39条第3項(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)の交付要求をいう。
配当すべき金銭
2 法第9条の「配当すべき金銭」とは、それぞれ次に掲げる金銭をいう。
(1) 滞納処分(法5章)、滞納処分の例による処分、国税滞納処分の例による処分、国税徴収の例による処分、市町村税の滞納処分の例による処分等の場合は、法第129条第1項((配当の原則))の換価代金等又はこれに準ずる金銭(第128条関係5参照)
(2) 不動産、船舶、航空機、自動車及び建設機械に係る強制執行又は担保権の実行としての競売の場合は、その売却代金(執行法86条1項1号、121条、188条、189条、192条、193条、航空法8条の4第2項、道路運送車両法97条2項、建設機械抵当法26条2項、執行規則84条、97条、98条、175条から177条まで)
なお、上記の売却代金には、次のものが含まれる。 イ 差押債権者が、競売手続の取り消されることを回避するため提供した保証(手続費用及び優先債権の見込額を超える額で差押債権者が申し出た額と最低売却価額との差額)がある場合には、その申出額から現実に売却された売却代金の額を控除した額(執行法86条1項2号、63条2項2号) 〔例〕 最低売却価額・・・・・・・・・・・・・・・・・・110万円
執行費用及び優先債権額・・・・・・・・130万円
申出額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・131万円
提供した保証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21万円
売却代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・120万円
この場合には、売却代金120万円のほか、提供した保証21万円のうち11万円(131万円-120万円)も売却代金となる。
ロ 買受人が買受代金を納付しないことにより売却決定が取り消された場合(執行法80条参照)には、買受人が提供した保証(同法86条1項3号)
(3) 動産に係る強制執行又は担保権の実行としての競売の場合は、売得金、差押金銭又は手形等の支払金(執行法139条1項、192条)
(4) 債権及びその他の財産権に係る強制執行又は担保権の実行としての競売の場合は、次に掲げるもの(執行法166条1項、193条2項) イ 第三債務者が供託した場合(同法166条1項、2項、157条5項参照)供託金
ロ 売却命令により売却した場合売得金
ハ 動産の引渡請求権の執行としてその引渡しを受け売却した場合(同法163条2項参照)売得金
(5) 強制管理の場合は、執行法第98条第1項((債務者に対する収益等の分与))の規定による分与をした後の収益又はその換価代金から、不動産に対して課される租税その他の公課及び管理人の報酬その他の必要な費用を控除した金銭(同法106条1項)
(6) 農業用動産抵当権実行令の規定による競売の場合は、その売得金(同令1条、執行法139条1項、192条)
(7) 企業担保権の実行手続の場合は、売却代金と企業担保権の目的となる会社の金銭(管財人が費用及び報酬に充てた金銭を含む。)との合計額に相当する金銭(企業担保法52条)
(8) 鉄道抵当法第3章((強制競売及強制管理))、軌道ノ抵当ニ関スル法律又は運河法の規定による強制競売の場合は、その競落代金(鉄道抵当法68条、71条、77条ノ2、軌道ノ抵当ニ関スル法律1条、運河法13条)
(9) 鉄道抵当法第3章、軌道ノ抵当二関スル法律又は運河法の規定による強制管理の場合は、その鉄道財団、軌道財団又は運河財団の収入に係る金銭(鉄道抵当法87条等)
手続に係る費用
3 法第9条の「手続に係る費用」とは、それぞれ次に掲げるものをいう。
(1) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)の場合には、法第136条((滞納処分費の範囲))に規定する費用又はこれに準ずる費用
(注) 上記の「これに準ずる費用」としては、地方税の督促手数料がある(地方税法14条の3参照)。
(2) 強制執行の場合は、強制執行の準備費用としての執行文の付与、判決の送達、判決確定証明書の付与(裁判上の費用)、執行の申立てをするため出頭するに必要な旅費(裁判外の費用に限る。)等の費用と強制執行の開始によって生じた費用としての執行官の手数料、立替金、鑑定費用、保証供与の費用、差押財産の保存費用等(執行法42条1項参照)
(3) 担保権の実行としての競売の場合又は企業担保法による企業担保権の実行手続の場合は、(2)に準ずる費用(執行法194条及び企業担保法17条において準用する執行法42条参照)
(4) 鉄道抵当法、軌道ノ抵当二関スル法律又は運河法の規定による強制競売又は強制管理の場合は、(2)に準ずる費用(鉄道抵当法68条1項等参照)
(5) 破産手続の場合は、破産法第47条第1号((財団債権の範囲))に規定する裁判上の費用、第3号に規定する管理、換価及び配当に関する費用(破産管財人の報酬を含む。昭利45.10.30最高判)、同法第70条第1項ただし書((強制執行等の失効の特例))の規定により破産管財人が破産財団のために強制執行等の手続を続行する場合の費用(同法70条2項参照)
費用の優先権
4 法第9条の「次いで徴収する」とは、納税者の財産が強制換価手続により換価された場合に、その執行機関にした交付要求に係る国税は、その換価代金からその手続の費用に次いで徴収することをいう。したがって、その手続の費用は、交付要求に係る国税(滞納処分費を含む。)に優先して徴収する。
強制換価手続の費用が優先しない場合
(強制管理)
5 不動産の強制管理の場合には、執行法第106条第1項((配当等に充てるべき金銭等))の規定により不動産に対して課させる租税は、管理の費用に先立って弁済を受ける。
(破産)
6 破産手続の場合において破産財団が財団債権の総額を弁済するに不足することが明らかになったときは、破産法第51条第1項((財団不足の場合の弁済方法))の規定により、財団債権である破産手続上の費用(破産管財人の報酬を除く。)と財団債権である国税とは平等弁済を受ける。
第10条関係 直接の滞納処分費の優先
滞納処分による換価
1 法第10条の「滞納処分により換価」とは、公売(法94条、107条)、随意契約による売却(法109条、110条)、差押債権(法53条1項の保険金等の支払を受ける権利を含む。)又は差押有価証券若しくは差押無体財産権等に係る債権の取立て(法67条1項、57条1項、73条5項、74条)及び国税滞納処分の例による処分(通則法52条1項、53条)としての換価をいう。
滞納処分費の優先
(滞納処分に係る滞納処分費)
2 法第10条の「その滞納処分に係る滞納処分費」とは、納税者の財産につき滞納処分による換価をした場合において、その換価の目的となった財産についての滞納処分費(法136条)で、その換価の基因となった国税についての滞納処分費をいう。 〔例1〕 甲国税によりA財産とB財産とを差し押さえ、A財産についてだけ換価した場合には、A財産についての滞納処分費だけが法第10条の滞納処分費に該当し、B財産についての滞納処分費は、法第10条の滞納処分費には該当しない。
〔例2〕 甲国税によりA財産を差し押さえ、乙国税により当該差押えに対し交付要求をした場合の交付要求に係る国税の滞納処分費は、法第10条の滞納処分費には該当しない。
(前払借賃に対する滞納処分費の優先)
3 法第26条第1号((国税及び地方税等と私債権との競合の調整))、第59条第3項後段及び第4項((動産の前払賃料の優先配当))並びに第71条第4項((自動車等の前払賃料の優先配当等の準用規定))の規定においては、滞納処分がされた財産を占有していた第三者の有する前払借賃に相当する債権の配当順位が、その滞納処分に係る滞納処分費に次ぐものとして定められている。
第11条関係 強制換価の場合の消費税等の優先
消費税等
1 法第11条の「消費税等(その滞納処分費を含む。)」には、課税資産の譲渡等に係る消費税並びにその附帯税及び滞納処分費は含まれない。
優先徴収
(移出)
2 法第11条の「移出」とは、それぞれ次に掲げる場合の移出をいう。
(1) 酒税法第6条の3第1項第4号((酒類等の製造場に現存する酒類等が公売等により換価された場合のみなし移出))の規定に該当する場合
(注) 酒税法第28条第1項((未納税移出))の規定の適用を受けて酒類製造者が酒類の製造場から移出する酒類については、上記に該当することはない(同法6条の3第1項ただし書)。
(2) 揮発油税法第5条第3項((揮発油の製造場に現存する揮発油が公売等により換価された場合のみなし移出))の規定に該当する場合(地方道路税法7条1項参照)
(3) 地方道路税法第7条第1項((徴収))の規定により揮発油税に併せて徴収する地方道路税についは、その揮発油について揮発油税法第5条第3項の規定に該当する場合(地方道路税法5条1項参照)
(4) 石油ガス税法第5条第3項((石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスが公売等により換価された場合のみなし移出))の規定に該当する場合
(5) 石油税法第5条第3項((石油の採取場に現存する石油が公売等により換価された場合のみなし移出))の規定に該当する場合
(公売又は売却)
3 法第11条の「公売若しくは売却」とは、それぞれ次に掲げる場合の公売又は売却をいう(輸徴法8条1項2号、6号)。
(1) 関税法第84条第1項((収容貨物の公売))又は第3項((収容貨物の随意契約による売却))の規定により、公売又は随意契約による売却をする場合
(2) 関税法第134条第5項((領置物件又は差押物件の公売又は随意契約による売却))の規定により、公売又は随意契約による売却に係る代金を還付する場合
(換価代金)
4 法第11条の「換価代金」とは、それぞれ次に掲げるものをいう。
(1) 通則法第39条((強制換価の場合の消費税等の徴収の特例))の規定を適用する場合にあっては、同条第1項の売却代金
(2) 関税法第84条第1項((収容貨物の公売))又は第3項((収容貨物の随意契約による売却))の規定により公売又は随意契約による売却をする場合にあっては、その公売代金又は売却代金
(3) 関税法第134条第5項((領置物件又は差押物件の公売又は随意契約による売却))の規定により還付する場合にあっては、その還付に係る公売代金又は売却代金
徴収の手続
5 法第11条を適用する場合における徴収の手続については、次のことに留意する。
(1) 通則法第39条((強制換価の場合の消費税等の徴収の特例))の規定により徴収する場合には、同条第2項の規定により、執行機関及び納税者に対し、徴収すべき税額その他必要な事項を書面により通知しなければならない(国税通則法施行令(以下「通則令」という。)10条)。この通知の様式は、別に定めるところによる。
(注) 上記の通知は、強制換価手続により換価に付される物品に係る消費税等(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)の納税地を所轄する税務署長が行う(酒税法30条の2第1項等)。
(2) 輸徴法第8条第1項第2号又は第6号((公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収))の規定により徴収する場合には、通則法第36条第1項((納税の告知))の規定による納税の告知をする必要がない(輸徴法8条3項)。
第12条関係 差押先着手による国税の優先
差押先着手による優先
(交付要求)
1 法第12条第1項の「交付要求」とは、法第82条第1項((交付要求の手続))、第86条第1項((参加差押えの手続))、第159条第9項((保全差押えに係る交付要求))(通則法38条4項において準用する場合を含む。)、地方税法第68条第4項((法人等の道府県民税に係る交付要求))、第72条の68第4項((事業税に係る交付要求))等の規定による交付要求をいう。
(法第9条との関係)
2 法第12条第2項の「第9条(強制換価手続の費用の優先)の規定の適用を受ける費用を除く」とは、強制換価手続の費用の一般的優先は、法第9条で既に規定されているので、重複して規定することを避けることを明らかにしたものである。
(劣後徴収)
3 法第12条第2項の「次いで徴収する」とは、納税者の財産が国税又は地方税により差し押さえられた場合に、その執行機関に交付要求をした国税は、その換価代金につき、その差押えに係る国税又は地方税に劣後して徴収することをいう。
差押先着手が適用されない場合
4 法第11条((強制換価の場合の消費税等の優先))、第14条((担保を徴した国税の優先))、地方税法第14条の4((強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先))、第14条の8((担保を徴した地方税の優先))の規定の適用がある場合には、法第12条の規定は適用されない。
(注) 譲渡担保財産について、譲渡担保権者の国税により差押えがされ、その差押えに対し譲渡担保の設定者の国税により交付要求がされた場合には、その設定者の国税を優先して徴収するため、当該差押えを交付要求とみなし、交付要求を差押えとみなすことになっている(国税徴収法施行令(以下「令」という。)9条1項前段)。
第13条関係 交付要求先着手による国税の優先
交付要求先着手による優先
(交付要求)
1 法第13条の「交付要求」は、第12条関係1に掲げる交付要求のほか、滞調法第36条の1O第1項((みなし交付要求))に規定する交付要求が含まれる。
(交付要求の競合)
2 納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税又は地方税の交付要求が競合した時のその優先順位は交付要求のされた時の順位による。
なお、上記の交付要求のされた時とは、滞納処分にあっては、その行政機関等に交付要求書又は参加差押書が送達された時をいい、送達時が同時である場合には、これらの交付要求に係る国税及び地方税は同順位になるものとする。
この同順位の場合における国税及び地方税に配当する金額は、債権現在額申立書に記載されている税額によりあん分計算したところによる。
交付要求先着手が適用されない場合
3 法第11条((強制換価の場合の消費税等の優先))、第14条((担保を徴した国税の優先))、地方税法第14条の4((強制換価の場合の道府県たばこ税等の優先))、第14条の8((担保を徴した地方税の優先))の規定の適用がある場合には、法第13条の規定は適用されない。
(注)1 譲渡担保財産について行った譲渡担保の設定者の国税の交付要求は、譲渡担保権者の国税又は地方税の交付要求に後れていても、譲渡担保の設定者の国税を優先して徴収するため、譲渡担保の設定者の交付要求は、先にされたものとみなされる(令9条2項前段)。
2 滞調法第1O条第3項((強制執行続行の決定があった場合の交付要求))(11条の2,17条、19条、20条の8節1項、20条の1O又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(以下「滞調令」という。)12条の2等において準用する場合を含む。)の規定による交付要求に係る国税については、法第12条((差押先着手による国税の優先))の規定が適用される(滞調法10条4項、17条、19条、20条の8第1項、20条の10、滞調令12条の2等)。
第14条関係 担保を徴した国税の優先
担保財産があるとき
(担保提供に関する規定)
1 国税についての担保の提供に関する法律の規定としては、おおむね次に掲げるものがある。
(1) 納税の猶予、納期限の延長等の場合
通則法第46条第5項((納税の猶予の場合の担保の徴取))、租税特別措置法第70条の4第1項((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予))、第70条の6第1項((農地等についての相続税の納税猶予))、通則法第52条第6項((納税の猶予等の保証人についての準用))、法第32条第3項((納税の猶予等の第二次納税義務者についての準用))、第152条((換価の猶予に係る分割納付、通知等))、消費税法第51条((引取りに係る課税貨物についての納期限の延長))、酒税法第30条の6((納期限の延長))、たばこ税法第22条((納期限の延長))、揮発油税法第13条((納期限の延長))、地方道路税法第8条第1項((担保の提供))、石油ガス税法第20条((納期限の延長))、租税特別措置法第41条の8第1項((山林を現物出資した場合の納期限の延長))、所得税法第132条第1項((延払条件付譲渡に係る所得税額の延納))、相続税法第38条第4項((相続税及び贈与税の延納の場合の担保の提供))
(2) 保全担保の提供命令の場合
法第158条第1項及び第4項((保全担保の提供命令))、酒税法第31条第1項前段((保全担保の命令))、たばこ税法第23条第1項((保全担保の提供命令))、揮発油税法第18条第1項((保全担保の提供命令))、地方道路税法第8条第2項((保全担保の提供命令))、航空機燃料税法第16条第1項((保全担保の提供命令))、石油ガス税法第21条第1項((保全担保の提供命令))、石油税法第19条((保全担保の提供命令))、印紙税法第15条第1項((保全担保の提供命令))
(3) 繰上保全差押え等の場合
通則法第38条第4項((繰上保全差押えの場合の法159条4項の準用))、法第159条第4項((保全差押えの場合の担保提供))
(4) その他特殊な場合
通則法第51条第1項((増担保の提供命令等))、第105条第3項及び第5項((不服申立てをした者の担保の提供))、輸徴法第7条第6項((内国消費税の納付前に郵便物を受け取る場合の担保の提供))、第9条第2項((輸入の許可前における引取りの場合の内国消費税額に相当する担保の提供))、第10条第2項((保税工場外における保税作業の場合の内国消費税額に相当する担保の提供))、第11条第2項((保税運送等の場合の内国消費税額に相当する担保の提供))、第13条第2項((内国消費税を免除する場合の内国消費税額に相当する担保の提供))
(担保財産)
2 法第14条の「担保財産」とは、通則法第50条第1号から第5号まで((担保の種類))に掲げる財産で、国税に関する法律の規定により担保として提供された財産、法第158条第4項((保全担保))の規定により抵当権を設定したものとみなされた財産又は輸徴法第14条第2号及び第3号((担保の種類))に掲げる財産で、同法の規定(9条2項、10条2項、13条2項)により担保として提供された財産をいい、物上保証として提供された第三者の財産が含まれる。
なお、法第14条の「担保財産」には、民法第372条((他の担保物権の規定の準用))又は第350条((留置権等の規定の準用))の物上代位の規定により担保権の効力が及んだ財産が含まれる。
他の法律等との関係
(酒税法第34条との関係)
3 酒税法第31条第1項((酒類の保存))の規定により保存された酒類については、法第14条の規定が準用される(酒税法34条3項)。
(法第11条との関係)
4 担保を徴した国税は、法第11条(強制換価の場合の消費税等の優先)の規定により、強制換価の場合の消費税等(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)に劣後する。
(関税法第9条の4との関係)
5 関税が納付されていない外国貨物について滞納処分があった場合において、その外国貨物に係る関税と外国貨物を担保に徴している国税とが競合したときは、関税法第9条の4((徴収の順位))の規定により、外国貨物を担保に徴しているその国税はその関税に劣後する。
(民法等との関係)
6 法第14条又は地方税法第14条の8((担保を徴した地方税の優先))の規定の適用を受ける国税又は地方税が2以上ある場合におけるその国税又は地方税の優先順位は、それぞれの担保権の順位によるものとする(民法373条等)。
(注) 抵当権により担保される国税と他の国税との関係においては、被担保債権となる利息等の範囲を規定する民法第374条((被担保債権の範囲))の適用はないことに留意する((第82条関係3の(2)参照))。
担保を徴した国税の優先
7 法第14条の規定により、担保を徴した国税が、他の国税及び地方税に先立って徴収することができるのは、担保財産を通則法第52条((担保の処分))の規定に基づき滞納処分の例により処分した場合又は担保財産につき強制換価手続が行われた場合である。
先順位の担保権との関係
(担保財産が納税者に帰属する場合)
8 国税につき徴している納税者の担保財産(国税のための担保権の設定時において第三者に帰属していたものを除く。法17条、23条3項参照)に先順位の質権若しくは抵当権が設定されているとき又は担保のための仮登記(法23条1項に規定する担保のための仮登記をいう。以下同じ。)がされているときは、その被担保債権は、国税の法定納期限等(法15条1項参照)後に設定又は登記されたものに限り、国税に劣後する。
(担保財産が第三者に帰属する場合)
9 国税につき徴している第三者の担保財産(担保権の設定時において納税者に帰属していたものを含む。法22条参照)に先順位の質権若しくは抵当権が設定されているとき又は担保のための仮登記がされているときは、その被担保債権は、その国税に優先する。
第3節 国税と被担保債権との調整
第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先
法定納期限等
(第1号の法定納期限等)
1 法第15条第1項第1号に規定する法定納期限等については、次のことに留意する。
(1) 法定納期限以前に発せられる更正通知書若しくは決定通知書又は法定納期限以前に提出された期限後申告書又は修正申告書(例えば、法定申告期限が5月31日でその法定納期限が6月30日である石油ガス税について、6月1日に発した決定通知書又は6月15日に提出された修正申告書。石油ガス税法16条1項、18条1項参照)は、法第15条第1項第1号の更正通知書等には該当しない。
(2) 法第15条第1項第1号の「納税告知書を発した日」とは、通則法第36条第2項((納税告知書の送達等))の規定による納税告知書を発した日をいい、賦課決定通知書により確定した国税についても、その通知書を発した日ではなく、その国税に係る納税告知書を発した日が法第15条第1項第1号の法定納期限等に該当する。
(注) 法第15条第1項の「発した日」とは、更正通知書等を交付送達又は郵便による送達のため税務署から持って出た日(私設郵便差出箱に差し入れたときは、その差し入れた日)をいう。
また、公示送達による場合の「発した日」とは、通則法第14条第2項((公示送達の掲示))の規定による掲示を始めた日をいう。
(3) 賦課決定通知書と納税告知書とを発することとされている場合において、賦課決定通知書による国税の確定がその法定納期限以内であるときは、納税告知書を発した日が法定納期限後であっても、その告知に係る国税は、法第15条第1項第1号の国税には該当しない。
(注)1 法定納期限以前に賦課決定通知書により確定する国税には、揮発油税法第12条第2項((みなし移出等に係る揮発油についての揮発油税の徴収))等の規定によるものがある。
2 国税に関する法律の規定により、一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税のうち、賦課課税方式による国税(例えば、酒類、酵母、もろみの密造者、密造酒類を不法に所持し、譲渡し又は譲り受けた者、保存酒類又は検定前の酒類を処分し又は製造場から移出した者その他酒税法に違反した者に課される酒税(酒税法54条5項、56条3項))の確定は、すべて法定納期限後である。
(4) 再評価税が法定納期限後に更正又は決定により確定した場合には、更正又は決定の通知書を発した日ではなく、納税告知書を発した日が、その法定納期限等となる(資産再評価法71条4項)。
(5) 法第15条第1項第1号の「申告があった日」については、通則法第22条((郵送に係る納税申告書の提出時期))の規定により期限後申告書又は修正申告書が郵便物通信日付印により表示された日等に提出されたものとみなされる場合でも、換価代金の配当等に当たっては、これらの申告書が税務署に現に提出された日を法定納期限等として取り扱うものとする。
なお、期限後に提出された納税申告書が、通則法第22条の規定により、期限内に提出されたものとみなされた場合には、法定納期限後に納付すべき額が確定したものではないが、当該申告に係る国税の法定納期限等については、上記に準じて取り扱う。
(第2号の法定納期限等)
2 法定納期限前に通則法第38条第1項((繰上請求))の規定により繰上請求がされた国税の法定納期限等は、繰上請求書(又は納税告知書)により指定された納期限である。
(注) 法第15条第1項第3号の第二期分の所得税について繰上請求をした場合における第二期分の所得税の法定納期限等は、その繰上げに係る納期限と第一期分の所得税の納期限との、いずれか早い方の納期限である。
(第3号の法定納期限等)
3 通則法第11条((災害等による期限の延長))の規定により、第一期分の所得税の納期限の延長が認められた場合には、その延長された期限が、法第15条第1項第3号の納期限となる。
(第5号の2の法定納期限等)
4 法第15条第1項第5号の2の「その納付があった日」を法定納期限等とする国税は、同号の国税に係る附帯税及び滞納処分費に限られる。
(第6号の法定納期限等)
5 譲渡担保権者に対する告知又は法第159条第1項((保全差押え))若しくは通則法第38条第4項((保全差押えの規定の準用))の規定による差押えを受ける者に対する保全差押金額若しくは繰上保全差押金額(以下5において「保全差押金額等」という。)の通知に係る国税の法定納期限等は、次に掲げるところによる。
(1) 法第24条第2項((譲渡担保権者に対する告知等))の規定により金額の国税に係る法定納期限等は、法第24条第2項前段又は第4項後段((譲渡担保権者に対する告知等))の規定に基づく告知書を発した日である。
(2) 法第159条第3項((保全差押金額の通知))又は通則法第38条第4項((保全差押えの規定の準用))の規定により通知した金額の国税に係る法定納期限等は、これらの規定による通知書を発した日である。
(3) 保全差押金額等の納付すべき国税の額が確定していない場合でも、その保全差押金額等の国税があるものとして、法第15条第1項第6号の規定を適用するものとする。
(4) 国税の額が保全差押金額等を超えて確定した場合におけるその超える額に相当する国税の法定納期限等については、法第15条第1項第6号の規定の適用がない。
(第7号の法定納期限等)
6 法第15条第1項第7号に規定する法定納期限等については、次のことに留意する。
(1) 相続人(包括受遺者及び死因贈与(民法554条)により包括名義の贈与を受けた者を含む。以下同じ。)には、相続(包括遺贈及び包括名義の死因贈与を含む。以下同じ。)の放棄をした者は含まれない(同法939条)。
(注) 上記の「包括受遺者」とは、相続人以外の者で遺言によって遺産の全部又はその何分の一という割合によってその一部を与えられた者をいい(民法964条)、「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与をいい、その法律上の取扱いは、遺贈に関する規定に従う(同法554条)。
(2) 相続があった日とは、被相続人(包括遺贈者及び死因贈与により包括名義の贈与をした者を含む。以下同じ。)が死亡した日(民法882条)又は失そう宣告により死亡したとみなされた日(同法31条)をいい、包括遺贈の場合は、遺贈が無条件であれば遺言者が死亡した日、停止条件付であればその条件成就の日をいう。
(注) 上記の「死亡した日」については、民法第32条ノ2((同時死亡の推定))の規定がある。
(3) 破産宣告があった場合において、破産法第42条((相続財産破産における相続債権者の優先))、第43条((相続人の破産における相続債権者と固有債権者の順位))又は第44条((相続人の固有債権者の優先))の規定により、国税が私債権に劣後することとなるときは、法第15条第1項第7号の規定の適用はない。
(第8号の法定納期限等)
7 法第15条第1項第8号に規定する法定納期限等については、次のことに留意する。
(1) 「合併により消滅した法人」とは、吸収合併により消滅した法人及び新設合併により解散した法人をいう。
(2) 「合併後存続する法人」とは、吸収合併により他を吸収して存続する法人をいい、合併により設立した法人は含まれない。
(3) 「その合併のあった日」とは、合併後存続する法人又は合併により設立した法人が、合名会社、合資会社、株式会社又は有限会社であるときは、その法人が本店所在地において変更の登記又は設立の登記をした日をいう(商法101条、102条、147条、414条1項、416条1項、有限会社法62条、63条参照)。
(4) 「合併のあった日前にその納付すべき税額が確定したもの」は、通則法第15条第3項第2号から第4号まで及び第6号((納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税))に掲げる国税については、合併のあった日前に納税告知書を発したものに限られる(法15条1項7号)。
(附帯税及び滞納処分費の法定納期限等)
8 附帯税及び滞納処分費の法定納期限等は、その附帯税及び滞納処分費の納付又は徴収の基因となった国税の法定納期限等である(法2条10号ニ、15条1項本文)。
(連帯納付義務に係る相続税等の法定納期限等)
9 相続税法第34条((連帯納付の義務))に規定する連帯納付義務に係る相続税又は贈与税の法定納期限等は、本来の納税者の相続税又は贈与税に係る法定納期限等と同じである(昭和55.7.1最高判参照)。
(通則法第5条第3項の納付責任に係る国税の法定納期限等)
10 通則法第5条第3項((相続による国税の納付義務の承継))に規定する納付責任に係る国税を相続財産から徴収する場合における当該国税の法定納期限等は、相続により承継した本来の国税の法定納期限等と同じである。
(物納の撤回に係る相続税の法定納期限等)
11 物納の撤回に係る相続税の法定納期限等は、相続税法施行令第19条の4第4項((物納の撤回の手続及び承認))に規定する書面を発した日である(同令19条の4第8項)。
質権の優先
(質権)
12 法第15条の「質権」とは、民法第342条((質権の内容))に規定する質権(根質権を含む。)をいい、動産質、不動産質及び権利質がある。
なお、上記の「質権」には、仮登記(仮登録を含む。以下同じ。)がされた質権が含まれ、また、仮登記には、民事保全法(以下「保全法」という。)第53条第2項((不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行))(同法54条((不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行))において準用する場合を含む。)の限定による仮処分による仮登記(以下「保全仮登記」という。)が含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。
(質権を設定している場合)
13 法第15条第1項の「質権を設定している場合」には、納税者に対する債権について納税者の財産の上に質権を設定している場合のほか、納税者以外の者に対する債権について納税者の財産の上に質権を設定している場合(納税者が物上保証人となっている場合等)も含まれる。
(法定納期限等以前の設定)
14 法第15条第1項の「法定納期限等以前」には、その法定納期限等に当たる日を含む。したがって、その日に設定された質権も、法定納期限等以前に設定された質権となる。
(物上代位との関係)
15 質権は、その目的物が滅失等した場合の物上代位の目的物についても、優先権を行使することができる(民法350条、昭和31.11.26神戸地判参照)。ただし、このためには、物上代位の目的物が納税者に払渡し又は引渡しされる前に差し押さえることが必要である(民法304条1項ただし書、350条。法53条2項参照)。
(物上代位の目的物に対する差押えが競合する場合の優先関係)
16 質権の物上代位の目的物に対する差押えと当該目的物に対する滞納処分による差押えとが競合した場合における優先関係は、質権の設定と差押国税の法定納期限等との先後により判定する(昭和56.3.30東京高判)。
債権額の範囲
(質権の目的物の価額)
17 法第15条の「換価代金」には、質権の設定された財産のほか、従物、付加物、利息債権等質権の効力の及んでいるものの換価代金も含まれる。
(質権によって担保される債権額)
18 質権により担保される債権額の範囲は、民法第346条((被担保債権の範囲))の規定により、設定行為に別段の定めのない限り、元本のほか、利息、違約金、質権実行の費用、質物保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れたかしによって生じた損害の賠償金の一切に及ぶ。
なお、不動産質権により担保される債権額の範囲については、第16条関係6及び7と同様である(民法361条)。
登記又は登録をすることができる債権
(登記をすることができる質権)
19 法第15条第2項の「登記をすることができる質権」とは、土地、建物等を目的とする質権、地上権等を目的とする質権その他登記が第三者に対する対抗要件となっている質権をいう。
(登録をすることができる質権)
20 法第15条第2項の「登録をすることができる質権」とは、無体財産権質、電話加入権質、記名国債質、記名社債質その他登録が第三者に対する対抗要件又は効力要件となっている質権をいう。
有価証券
21 法第15条第2項の「有価証券」は、第56条関係13と同様である。
証明
(証明の必要)
22 法第15条第1項の規定の適用を受けるためには、質権者は、登記(登録を含む。以下同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その設定の事実を証明しなければならない(法15条2項)。
なお、19及び20の質権については、証明を要せず、徴収職員は、その質権の設定の事実を確認しなければならない。
(転質がある場合の証明)
23 民法第348条((転質権))の規定に基づく転質権者が、原質権につき法第15条第2項の証明をしたときは、法第15条第2項の質権者がその設定の事実を証明した場合に当たるものとする。
(証明の期限)
24 質権の証明は、次に掲げる日までにしなければならない(令4条3項)。
なお、証明の期限については、通則法第10条第2項((期限の特例))の規定の適用がない(通則令2条7号)。
(1) 債権を目的とする質権の証明その債権の第三債務者から給付を受けた金銭の配当計算書を作成する日の前日
(2) 有価証券に係る金銭債権を取り立てる場合のその有価証券を目的とする質権の証明 給付を受けた金銭の配当計算書を作成する日の前日
(3) その他の質権の証明 滞納処分に係る売却決定をする日の前日
(証明の方法)
25 滞納処分の場合における質権の証明は、次に掲げる方法によってしなければならない。
(1) 登記をすることができる質権以外の質権(有価証券を目的とする質権を除く。)の設定の事実の証明税務署長に対し、26から28までに定める証書のいずれかを提出すること又はそれらの証書を呈示するとともにその写しを提出すること(令4条2項)。
(2) 有価証券を目的とする質権(登録をすることができる質権を除く。)の設定の事実の証明 税務署長に対し、質権設定の事実を証する書面又はその事実を証するに足りる事項を記載した書面を提出すること(令4条1項)。
(公正証書)
26 法第15条第2項第1号の「公正証書」とは、公務員がその権限に基づき適法に作成した証書をいい、判決書、公証人の作成した公正証書及びこれらの謄本等がある。
(私署証書)
27 「私署証書」とは、私文書をいい、公正証書以外の文書はすべて私署証書であって、当事者の作成したものであるか、第三者の作成したものであるか、作成者の署名押印があるかどうかを問わないが、法第15条第2項第2号の「私署証書」とは、例えば、登記所又は公証人が認証し、その認証の年月日等の記載がされた契約書等をいう。 (注) 登記所は、当事者の請求に基づき私文書である「担保差入書」等に確定日付のある印章を押し(民法施行法5条2号)、確定日付簿にその旨を記入することとされている(確定日付簿及び日附印章調整規則参照)。
(内容証明を受けた証書)
28 法第15条第2項第3号の「内容証明を受けた証書」とは、郵便法第63条((内容証明))の規定により、内容証明を受けた文書をいう。
(確認)
29 質権の設定が法定納期限等以前であるかどうかについては、徴収職員が調査の上確認しなければならない。
質権設定の時期
(登記をすることができる質権)
30 登記をすることができる質権の設定の時期は、その質権の設定登記の日による。
(仮登記のある場合)
31 質権設定の仮登記又は質権設定請求権保全の仮登記がされた後において、その仮登記に基づく本登記(本登録を含む。以下同じ。)がされたときのその質権の設定の時期は、その仮登記がされた日によるものとする。
(登記をすることができる質権以外の質権)
32 登記をすることができる質権以外の質権(有価証券を目的とする質権を除く。)の設定の時期は、それぞれ次に掲げる日による(法15条3項)。ただし、その質権がその対抗要件を備えた日が次に掲げる日より遅いときは、その対抗要件を備えた日を法第15条の質権の設定の時期とする。
(1) 公正証書については、その日付の日
(2) 登記所又は公証人役場において日付のある印章が押されている私署証書については、その印章の日付の日
(3) 内容証明を受けた証書については、郵便局のその通信日付(郵便規則109条)の日
(有価証券を目的とする質権)
33 登録をすることができる質権以外の質権のうち、有価証券を目的とする質権の設定の時期は、質権者がその有価証券を占有した日による。
優先権行使の否認
(第4項の趣旨)
34 法第15条第4項は、国税に優先する質権者(登記をすることができる質権以外の質権を有する者に限る。)が2人以上ある場合において、先順位質権者が法第15条第2項の質権設定の証明をしなかったためその質権が国税に劣後することとなるときは、私法上の質権の優先順位にかかわらず、その劣後することとなる金額の範囲内において、国税に優先する後順位質権者に対して優先権を行使することができないことを定めたものである。 〔例1〕 第1順位 質 権・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万円
第2順位 質 権・・・・・・・・・・・・・・・・・・40万円
第3順位 国 税・・・・・・・・・・・・・・・・・・25万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100万円
上記の場合に、第1順位の質権者が質権により担保される債権50万円のうち20万円しか証明できず、第2順位の質権者が40万円につき証明したとすれば、まず第1順位の質権にその証明できた金額20万円を充て、次に第2順位の質権40万円を充て、次に第3順位の国税に25万円を充てる。そして残余金15万円は、第1順位の質権に充てる。したがって、第1順位の質権者に35万円、第2順位の質権者に40万円、第3順位の国税に25万円を配当することとなる(36,37参照)。
〔例2〕(法15条4項と法18条1項本文との関係)
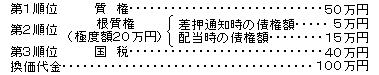
上記の場合に、第1順位の質権者が証明せず、第2順位の根質権者が証明したとすれば、まず根質権に5万円、国税に40万円を順次充て、次に、私法上の原則に従って第1順位の質権50万円を充て、残余金5万円を根質権に充てる。したがって、第1順位の質権者に50万円、第2順位の根質権者に10万円、第3順位の国税に40万円を配当することとなる(36,37参照)。
(証明をしなかった場合)
35 法第15条第4項の「証明をしなかった」場合には、証明の期限に後れて証明した場合が含まれる。
(国税に後れる金額の範囲内)
36 法第15条第4項の「国税におくれる金銭の範囲内」とは、先順位質権者が、その質権が国税に優先することを証明しなかったため、国税に後れることとなった結果、換価代金から配当を受けられなくなった金額の範囲内をいう。
(優先権を行うことができない)
37 法第15条第4項の「優先権を行うことができない」とは、先順位の質権は、後順位の質権に優先する私法上の原則にかかわらず、先順位の質権者が後順位の質権者に劣後することをいう。
第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先
抵当権の優先
(抵当権)
1 法第16条の「抵当権」とは、民法第369条((抵当権の内容))、鉄道抵当法第17条((抵当権の内容))、自動車抵当法第4条((抵当権の内容))、航空機抵当法第4条((抵当権の内容))及び建設機械抵当法第6条((抵当権の内容))に規定する抵当権(民法398条ノ2、鉄道抵当法7条2項、自動車抵当法19条の2、航空機抵当法22条の2及び建設機械抵当法24条の2に規定する根抵当権を含む。)をいい、その目的物には、不動産、地上権及び永小作権(民法369条)、立木(立木二関スル法律(以下「立木法」という。)2条2項)、工場財団(工場抵当法14条2項)、鉱業財団(鉱業抵当法3条)、漁業財団(漁業財団抵当法6条)、道路交通事業財団(道路交通事業抵当法9条)、港湾運送事業財団(港湾運送事業法23条)、鉱業権(採掘権に限る。鉱業法13条)、漁業権(漁業法23条1項)、採石権(採石法4条3項)、ダム使用権(特定多目的ダム法21条)、鉄道財団(鉄道抵当法4条)、軌道財団(軌道ノ抵当二関スル法律1条)、運河財団(運河法13条)、工場財団を組成しない工場(工場抵当法2条)、船舶(商法848条)、自動車(自動車抵当法3条)、航空機(航空機抵当法3条)、建設機械(建設機械抵当法5条)、農業用動産(農業動産信用法12条)並びに観光施設財団(観光施設財団抵当法9条)がある。
なお、上記の「抵当権」には、仮登記(保全仮登記を含む。)がされた抵当権も含まれる(法133条3項、令50条4項参照)。
(抵当権を設定している場合)
2 法第16条の「抵当権を設定しているとき」には、納税者に対する債権について納税者の財産の上に抵当権を設定している場合のほか、納税者以外の者に対する債権について納税者の財産の上に抵当権を設定している場合(納税者が物上保証人になっている場合等)も含まれる。
(法定納期限等以前の設定)
3 法第16条の「法定納期限等以前」には、その法定納期限等に当たる日を含む。したがって、その日に設定された抵当権も、法定納期限以前に設定された抵当権となる。
(物上代位の目的物に対する差押えが競合する場合の優先関係)
4 抵当権の物上代位の目的物に対する差押えと当該目的物に対する滞納処分による差押えとが競合した場合における優先関係は、第15条関係16と同様である。
債権額の範囲
(抵当権の目的物の価額)
5 法第16条の「換価代金」には、抵当権の設定された財産のほか、従物、付加物等抵当権の効力の及んでいるものの換価代金も含まれる。
(抵当権によって担保される債権額)
6 抵当権により担保される債権額の範囲については、次のことに留意する。
(1) 抵当権者が利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてだけその抵当権を行うことができる。ただし、それ以前の定期金であっても、満期後特別の登記をしたときは、その登記の時からこれを行うことを妨げない(民法374条1項)。
(2) 民法第374条第1項((被担保債権の範囲))の規定は、抵当権者が債務の不履行により生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合において、その最後の2年分についても適用される。ただし、利息その他の定期金と併せて2年分を超えることはできない(同法374条2項)。
(根抵当権によって担保される債権額)
7 根抵当権により担保される債権額の範囲は、確定した元本、利息、損害賠償金等を併せてその極度額の範囲に限られる(民法398条ノ3第1項)。
抵当権の設定時期
8 抵当権の設定の時期は、その登記がされた日によるものとする。また、抵当権設定の仮登記又は抵当権設定請求権保全の仮登記がされた後において、その仮登記に基づく本登記がされたときのその抵当権の設定の時期は、その仮登記がされた日によるものとする。
徴収職員の調査
9 法第16条の規定の適用については、抵当権者の証明を要件とするものではない。
なお、徴収職員は、抵当権の設定の事実及びその設定の時期が国税の法定納期限等以前であるかどうかにつき調査確認しなければならない。
第17条関係 譲受け前に設定された質権又は抵当権の優先
財産の譲受け
(譲り受けたとき)
1 法第17条の「財産を譲り受けたとき」とは、納税者が質権又は抵当権の設定されている財産を売買、贈与、交換、現物出資、代物弁済等により取得したときをいい、相続又は合併による承継の場合の取得は含まない。 (注)1 相続又は合併による財産の取得があった場合には、譲受人が通則法第5条((相続による国税の納付義務の承継))、第6条((法人の合併による国税の納付義務の承継))又は第7条((人格のない社団等に係る国税の納付義務の承継))の規定により、それぞれ納税義務を承継することになること及びその財産上の質権又は抵当権と国税との優先関係については、法第15条第1項第7号又は第8号((法定納期限等))の規定があることに留意する。
2 納税者の財産を譲り受けた者が、第三者のため質権又は抵当権を設定した後、その譲渡が取り消された場合(詐害行為として取り消された場合を含む。)、解除された場合又は無効である場合において、それらの効果を第三者である質権者又は抵当権者に対して主張できないとき(例えば、売買が虚偽表示である場合には、善意の第三者である質権者又は抵当権者に対して、その無効を主張することはできない。民法94条2項)は、その質権又は抵当権が法第17条の譲受け前に設定されたものとして、同条を適用するものとする。
(納税者が担保財産を再取得した場合)
2 納税者が所有する財産上に質権又は抵当権を設定した後その担保財産を第三者に譲渡し、更にその納税者がその担保財産を再取得した場合には、法第17条の規定を適用することなく、法第15条((法定納期限等以前に設定された質権の優先))又は第16条((法定納期限等以前に設定された抵当権の優先))の規定を適用するものとする。
(法定納期限等との関係)
3 納税者が、質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けた場合においては、その質権又は抵当権の設定の時期がその納税者の納付すべき国税の法定納期限等の以前であると後であるとを間わず、その質権又は抵当権により担保される債権は、その国税に優先する。
証明
(証明の期限等)
4 登記をすることができる質権(第15条関係19,20)以外の質権が法第17条第1項の規定の適用を受けるための証明については、第15条関係22から28までと同様である(法17条2項、令4条、通則令2条7号)。
(譲受け前であることの確認)
5 質権の設定の時期がその質権の目的となった財産の譲受け前であるかどうかについては、譲受け前であることを判断するに足りる書類を提出させ、徴収職員が調査確認するものとする。
法第26条との関係
(先順位の質権の証明がなかった場合)
6 法第17条第2項の証明をすべき質権が2以上ある場合において、先順位の質権について第2項の証明がなく、後順位の質権について第2項の証明があったときの配当については、法第26条((国税及び地方税と私債権との競合の調整))の規定を類推適用するものとする。 〔例〕 譲渡人を設定者とする先順位の質権甲・・・・・・・・3万円
譲渡人を設定者とする後順位の質権乙・・・・・・・・4万円
譲受人の国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9万円 (注)1 納税者が、甲質権及び乙質権の設定された財産を譲り受け、その後納税者の滞納国税につき滞納処分をした。
2 甲質権については法第17条第2項の証明がなく、乙質権について第2項の証明があった。したがって、甲質権は国税に後れるが乙質権に優先し、また乙質権は甲質権に後れるが国税に優先することになる。
※配当額の計算 イ 法第26条第2号の規定に準じて、国税及び私債権に充てるべき金額の総額は、法第17条の規定により、乙質権に4万円、国税に5万円(換価代金9万円-乙質権4万円)となり、国税の総額は5万円、私債権の総額は4万円となる。
ロ 法第26条第3号の規定により、国税に5万円を充てる。
ハ 法第26条第4号の規定により、私債権に充てるべき4万円は、民法第355条((動産質権の順位))の規定により、甲質権3万円、乙質権1万円(4万円-3万円)となる。
ニ 上記の結果、配当額は次のとおりになる。
甲質権・・・・・・・・・・・・・・3万円
乙質権・・・・・・・・・・・・・・1万円
国 税・・・・・・・・・・・・・・・5万円
(納税者が担保財産を再取得した場合において第三者が設定した質権又は抵当権があるとき)
7 納税者が所有する財産上に質権又は抵当権を設定した後、その担保財産を第三者に譲渡し、その第三者がその担保財産上に質権又は抵当権を設定し、更にその後納税者がその担保財産を再取得した場合のその納税者の国税及び担保財産上の質権又は抵当権により担保される債権に対する配当については、法第26条((国税及び地方税等と私債権との競合の調整))の規定を類推適用するものとする。 〔例〕 納税者を設定者とする抵当権甲(設定登記 昭和57. 7.31)・・4万円
譲受人を設定者とする抵当権乙(設定登記 昭和57.10.11)・・6万円
差押国税(法定納期限等 昭和57. 5.31)・・・・・・・・・・・・・・・・7万円
換価代金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
(注) 乙抵当権を設定した後納税者がその財産を再取得し、その後納税者の滞納国税につき滞納処分をした。
この場合には、甲抵当権は国税に後れるが乙抵当権に優先し、また、乙抵当権は甲抵当権に後れるが、法第17条の規定により国税に優先する。
※配当額の計算 イ 法第26条第2号の規定に準じて、国税及び私債権に充てるべき金額の総額は、
(1)まず法第17条の規定により乙抵当権に6万円、(2)次いで、甲抵当権の設定登記よりも法定納期限等の古い国税4万円(換価代金1O万円-乙抵当権6万円)となり、国税の総額は4万円、私債権の総額は6万円となる。
ロ 法第26条第3号の規定により、国税に4万円を充てる。
ハ 法第26条第4号の規定により、私債権に充てるべき金額は、民法第373条第1項((抵当権の順位))の規定により、甲抵当権4万円、乙抵当権2万円(6万円-4万円)となる。
ニ 上記の結果、配当額は次のとおりになる。
国 税・・・・・・・・・・・・・・4万円
甲抵当権・・・・・・・・・・・・・4万円
乙抵当権・・・・・・・・・・・・・2万円
第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等
優先債権額の範囲
(債権額の限度)
1 法第18条第1項の「債権額を限度とする」については、法第15条から第17条まで(法定納期限等以前に設定された質権の優先等)の規定により国税に優先する質権又は抵当権により担保される債権額のうち、法第18条第1項の規定により国税に優先する元本債権額は、その質権者又は抵当権者に2又は3の通知書が送達された時の元本債権額に相当する金額を限度として取り扱う。
なお、上記の通知書が送達された時までに根抵当権の元本債権額が確定しているときは、法第18条の規定が適用されないことに留意する。
(差押えの通知を受けた時)
2 法第18条第1項の「差押の通知を受けた時」とは、質権又は抵当権の目的となっている財産を差し押えた場合において、差押えの通知書(法55条)又は差押調書の謄本(令22条1項ただし書、2項)を、その質権者又は抵当権者に送達した時をいう。
(交付要求の通知を受けた時)
3 法第18条第1項の「交付要求の通知を受けた時」とは、質権又は抵当権の目的となっている財産につき交付要求又は参加差押えをした場合において、法第82条第3項(質権者等に対する交付要求の通知)の規定による交付要求の通知書又は第86条第4項(質権者等に対する参加差押えの通知)の規定による参加差押えの通知書を、その質権者又は抵当権者に送達した時をいう。
(根抵当権の確定との関係)
4 根抵当権の元本債権額は、根抵当権者が、根抵当権の目的となった財産に対する滞納処分による差押えがあったことを知った日から2週間を経過したときに確定する(民法398条ノ20第1項4号)が、国税に優先する根抵当権の元本債権額は根抵当権者に2の通知書が送達された時の元本債権額に相当する金額が限度となる(法18条1項本文)。
なお、滞納処分による差押えがあったことを知った日から元本確定(民法398条ノ20第1項)の日までの間に増加した根抵当権の元本債権額は、その根抵当権に後れて登記した担保権には優先する(同法373条1項)ことに留意する。
(根抵当権の確定事由の消滅との関係)
5 滞納処分による差押えが解除された場合には、根抵当権の担保すべき元本は確定しなかったものとみなされる(民法398条ノ20第2項)。当該差押えに対してした参加差押えは参加差押えをした時にさかのぼって差押えの効力を生じることになるから、この差押えとの関係においては、根抵当権者が参加差押えのあったことを知った日から2週間を経過したときに、根抵当権の担保すべき元本は確定する。
なお、次に掲げる場合には、差押えを解除しても、根抵当権の担保すべき元本の確定の効果は、消滅しないことに留意する。
(1) 根抵当権者である税務署長が、当該財産を滞納処分により差し押えたとき(民法398条ノ20第1項3号)。
(2) 根抵当権の担保すべき元本が確定した後において、その根抵当権又はその根抵当権を目的とする権利を取得した者がいるとき(民法398条ノ20第2項ただし書)。
(差押え又は交付要求の競合)
6 差押え又は数個の交付要求(参加差押えを含む。)が競合して行われた場合においては、それぞれの通知を受けた時の債権額を、それぞれの差押え又は交付要求に係る国税との関係において、法第18条第1項の債権額の限度とする(法第18条1項本文)。
なお、法第18条第1項本文の規定を適用すると、いわゆる「ぐるぐる回り」が生ずる場合には、法第26条(国税及び地方税等と私債権との競合の調整)の規定を適用又は類推適用するものとする。
〔例1〕 根抵当権(設定登記 昭和57. 7.30)極度額・・・・・・・・・・・・・10万円
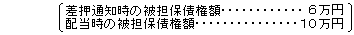
国税(法定納期限等 昭和58. 3.15)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円
※配当額の計算 イ 根抵当権の配当時における被担保債権額10万円のうち、法第18条第1項本文の規定により国税に優先するのは、差押通知時の債権額6万円である。したがって、換価代金15万円のうち6万円を根抵当権に充てる。
ロ 換価代金15万円のうち根抵当権に充てた6万円を控除した残額9万円のうち、法第18条第1項本文の規定により国税に7万円を充てる。
ハ 換価代金15万円のうち、上記イ及びロの金額を控除した残額2万円は、根抵当権がまだ4万円(配当時の被担保債権額10万円-上記のイの6万円)の配当を受ける権利があるので、これに充てる。
ニ 上記の結果、配当額は次のとおりになる。 根抵当権・・・・・・・8万円 (国税に優先する部分6万円十国税に劣後する部分2万円)
国 税・・・・・・・・7万円
〔例2〕 根抵当権(設定登記 昭和56. 7.30)極度額・・・・・・・・・・・・・11万円
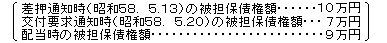
差押国税(法定納期限等 昭和58. 3.30・・・・・・・・・・・・・・・・・8万円
交付要求地方税(法定納期限等 昭和58. 1.31)・・・・・・・・・12万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20万円
※配当額の計算 イ 根抵当権の配当時における被担保債権額9万円のうち、根抵当権の交付要求通知時における被担保債権額7万円は差押通知時の被担保債権額10万円よりも小さく、この限度においては法第18条第1項本文の規定により国税及び地方税のいずれにも優先するから、換価代金20万円のうち7万円を根抵当権に充てる。
ロ 根抵当権の2万円(9万円-7万円)と国税8万円、地方税の12万円とは、次のとおり、三者間で優先順位が交錯していわゆる「ぐるぐる回り」が生ずることとなるので、法第26条の規定により配当額を定める。 (イ) 根抵当権と国税の間においては、根抵当権(2万円)は、差押通知時の被担保債権額(10万円)の範囲内であるから、法第18条第1項本文の規定により国税に優先する。
(ロ) 根抵当権と地方税の間においては、根抵当権(2万円)は、交付要求通知時の被担保債権額(7万円)の範囲外である(上記イで既に7万円の配当を受けることになっている。)から、法第18条第1項本文の規定により地方税に劣後する。
(ハ) 国税と地方税の間においては、国税は、法第12条第1項(差押先着手による国税の優先)の規定により地方税に優先する。
ハ 法第26条第2号の規定により、根抵当権の設定登記及び国税、地方税の法定納期限等の古い順に従って、換価代金13万円(20万円-7万円)を、(1)根抵当権1万円(換価代金20万円-イの金額7万円-地方税12万円=1万円)、(2)地方税12万円、(3)国税0と定める。
ニ 法第26条第3号の規定により、国税及び地方税に充てる金額は、法第12条((差押先着手による国税の優先))の規定により、差押国税8万円、交付要求地方税4万円となる。
ホ 法第26条第4号の規定により、根抵当権に1万円充てる。
ヘ 上記の結果、配当額は次のとおりになる。
根抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・8万円
差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・8万円
交付要求地方税・・・・・・・・・・・4万円
(破産手続等との関係)
7 破産手続又は企業担保権の実行手続との関係においては、法第18条第1項の規定が適用されることはない(令36条4項参照)。
第三者の担保財産に対する滞納処分等との関係
8 国税につき徴している第三者の担保財産(担保権の設定時において納税者に帰属していたものを含む。)を滞納処分の例により処分する場合には、担保権の効力として配当を受けることとなるため、法第18条第1項の規定は適用されない。また、法第22条第5項((担保権付財産が譲渡された場合の国税徴収のための交付要求))の規定により交付要求をする場合には、法第22条第1項に規定する質権者又は抵当権者が配当を受ける額から徴収するものであり、法第18条第1項の規定は適用されない。
第1項本文の規定の適用除外
(権利を害することとなるとき)
9 法第18条第1項ただし書の「権利を害することとなるとき」とは、差押え又は交付要求に係る国税に優先する先順位債権者の差押え等の通知後増加した部分の債権額は、その国税には劣後するが、その国税に優先する他の債権を有する者(以下第18条関係において「後順位債権者」という。)の債権に優先するため、先順位債権者に配当すべき当該増加した部分の債権額を法第18条第1項本文に従って国税に配当することにより、後順位債権者が配当を受けられなくなるときをいう。 〔例1〕 法第18条第1項ただし書の「権利を害することとなるとき」に該当する事例 第1順位 国税に優先する根抵当権の配当時の被担保債権甲・・10万円
差押通知書が債権者に送達された時の債権額・・・・・・・2万円
第2順位 国税に優先する抵当権の被担保債権乙・・・・・・・・・・・・4万円
第3順位 差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15万円
イ 法第18条第1項本文の規定によると、換価代金15万円は、(1)差押えの通知を受けた時の甲根抵当権の債権額2万円、(2)第2順位の乙抵当権4万円、(3)第3順位の国税5万円、(4)甲根抵当権4万円(15万円-(1)の2万円-(2)の4万円-(3)の5万円)にそれぞれ充てられる。
ロ しかし、第1順位の甲根抵当権は、第2順位の乙抵当権に優先するため、乙抵当権4万円は甲根抵当権に吸い上げられ、甲根抵当権10万円(イの①の2万円十イの(4)の4万円十イの(2)の乙抵当権4万円)、乙抵当権0、国税5万円という配当になる。
ハ この結果、乙抵当権者の権利は、国税が優先配当を受けることによって害されたことになる。したがって、法第18条第1項の規定は適用しないで、法第16条((法定納期限等以前に設定された抵当権の優先))の規定により配当計算をすることになるから、その優先順位どおり(1)甲根抵当権10万円、(2)乙抵当権4万円、(3)国税1万円(換価代金15万円-(1)の10万円-(2)の4万円)の配当額となる。
〔例2〕 法第18条第1項ただし書の「権利を害することとなるとき」に該当しない事例 第1順位 国税に優先する根抵当権の配当時の被担保債権甲・・・10万円
差押通知書が債権者に送達された時の債権額・・・・・・・・4万円
第2順位 国税に優先する抵当権の被担保債権乙・・・・・・・・・・・・・3万円
第3順位 差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
上記の場合においては、換価代金は10万円であり、配当時において、乙抵当権に優先する甲根抵当権の被担保債権額は1O万円であり、もともと乙抵当権者は民法その他の法律の規定(法18条1項本文の規定を除く。)によっては配当を受けることができないのであるから、乙抵当権者に配当をしないこととしても、その権利を害したことにはならない。
(他の債権を有する者)
10 法第18条第1項ただし書の「他の債権を有する者」には、先順位債権者と後順位債権者とが同一人である場合のその後順位債権者も含まれる。
(この限りでない)
11 法第18条第1項ただし書の「この限りでない」とは、同条第1項本文の規定を適用することにより後順位債権者の権利を害することとなる場合には、同条第1項本文の規定を適用しないことをいうものとする。
増額の付記登記
(根質等の増額の登記)
12 根質又は根抵当権の債権額を増加する登記には、次のような登記がある。
(1) 根質により担保される債権極度額又は元本極度額を増額する変更契約による極度額の登記
(2) 根抵当権により担保される極度額を増額する変更契約による極度額の登記
(3) 根質の債権極度額を元本極度額にする変更登記(変更登録を含む。以下同じ。)
(4) 利息若しくは遅延損害金を増加する変更登記又は利息若しくは遅延損害金に関する定めの登記がない場合にその定めを新たに登記する登記
(質権等の増額の登記)
13 質権又は抵当権の債権額を増加する登記には、次のような登記がある。
(1) 債権額の一部が被担保債権として登記されている場合においてその被担保債権額を増額する登記
(2) 利息を元本に組み入れる場合の債権額増額の登記
(3) 利息若しくは遅延損害金を増加する変更登記又は利息若しくは遅延損害金に関する定めの登記がない場合にその定めを新たに登記する登記
(付記登記)
14 債権額の増額の登記は、登記上利害関係を有する第三者の承諾書又はこれらの者に対抗することができる裁判の謄本を添付したときに限り、付記登記(付記登録を含む。以下同じ。)によりすることができる(不動産登記法56条、自動車登録令2条等)。
(設定の時期)
15 付記登記により債権額を増加する登記がされた場合には、その順位は主登記(主登録を含む。以下同じ。)の順位によるが(不動産登記法7条1項、自動車登録令3条等)、法第15条から第17条まで((法定納期限等以前に設定された質権の優先等))の規定の適用については、その付記登記がされた時に、その増加した債権額につき質権又は抵当権が設定されたものとみなされる(法18条2項)。
第19条関係 不動産保存の先取特権等の優先
不動産保存の先取特権等の優先
1 法第19条第1項各号に掲げる先取特権(仮登記(保全仮登記を含む。)がされたものを含む。法133条3項、令50条4項参照)は、特定の行為により財産の価値を保存した等の場合に成立するものであり、その行為によって国税も利益を受けること及びこれらの先取特権は質権又は抵当権よりも優先する効力を有するところから、法第20条第1項に規定する先取特権とは異なり、その成立の時期が国税の法定納期限等後である場合又は差押え後である場合にも、国税に優先する。
不動産保存の先取特権
(意義)
2 法第19条第1項第1号の「不動産保存の先取特権」は、不動産自体の保存費用又は不動産に関する権利の保存、追認若しくは実行のために要した費用について、その不動産の上に存する先取特権である(民法326条)。 (注)1 不動産の保存とは、不動産の現状を維持することをいう。
2 不動産の保存費用等は、次のような費用である。
(1) 不動産の保存費用とは、不動産の滅失又はき損を防ぐために行った修理の費用等である。
(2) 権利の保存費用とは、例えば、納税者の所有不動産を第三者が占有しており、取得時効が完成しようとしている場合において、納税者の債権者がその時効を中断したときに要した費用等である。
(3) 権利の追認に要した費用とは、(2)の例で占有者に対して納税者の所有権を承認させたときに要した費用等である。
(4) 権利の実行に要した費用とは、(2)の例で占有者が納税者へ不動産を返還させたときの費用等である。
(効力の保存)
3 不動産保存の先取特権は、保存行為の完了後直ちに、その債権額を登記することによってその効力を保存するものであるから(民法337条。不動産登記法115条参照)、登記をしていない場合はもちろん、遅滞して登記をしている場合は、先取特権としての優先権を行使できない。
(優先順位)
4 不動産保存の先取特権が、共益費用を除く一般の先取特権、他の特別の先取特権、抵当権又は不動産質権と競合した場合には、その登記の時期の前後にかかわらず、不動産保存の先取特権が優先する(民法329条2項、331条1項、339条、361条)。
不動産工事の先取特権
(意義)
5 法第19条第1項第2号の「不動産工事の先取特権」は、工匠(大工、左官等)、技師又は諸負人が不動産に関してした工事の費用について、その工事によって生じた不動産の増加が現存する場合に限り、その増加額についてだけ、その不動産の上に存する先取特権である(民法327条)。法第19条第1項第2号の「不動産工事の先取特権」は、工匠(大工、左官等)、技師又は諸負人が不動産に関してした工事の費用について、その工事によって生じた不動産の増加が現存する場合に限り、その増加額についてだけ、その不動産の上に存する先取特権である(民法327条)。 (注) 不動産の工事とは、不動産の保存と対比すべきものであって、例えば、倒れかかっている家屋を修理するのは保存であり、一定の計画に従って改造するのは工事である。また、一連の工事のうち、上棟までの費用を工事費とし、その後の費用を保存費とすることは許されない(明治43.1O.18大判)。
(増価額の評価)
6 不動産工事の先取特権の目的となっている不動産を換価する場合には、税務署長は、その工事による不動産の増価額を評価しなければならない。この場合において、税務署長は、必要があると認めるときは、鑑定人に評価を委託し、その評価額を参考として増価額を定めるものとする(令5条)。 (注) 民法第338条第2項((不動産工事による増価額の評価))では、不動産の増価額は配当加入のときに裁判所において選任した鑑定人をして評価させることを要する旨規定しているが、この規定は、滞納処分による換価の場合には適用されない。
(効力の保存)
7 不動産工事の先取特権は、工事を始める前に、費用の予算額を登記することによってその効力を保存するものであるから(民法338条1項本文。不動産登記法115条参照)、登記をしていない場合はもちろん、工事を始めてから登記をしている場合には、先取特権としての優先権を行使できない。
なお、登記した予算額よりも実際の費用が超過した場合には、先取特権は登記した予算額を限度として存在し(民法338条1項ただし書)、実際の費用が予算額よりも少ない場合には、実際の費用の額を限度として先取特権が存在する。
(優先順位)
8 不動産工事の先取特権は、不動産保存の先取特権に次ぐ順位の優先権を有するから(民法331条1項)、共益費用の先取特権を除く一般の先取特権、不動産保存の先取特権を除く他の特別の先取特権、抵当権及び不動産質権に優先する(同法329条2項、331条1項、339条、361条)。
都市再開発法第107条の施行者の先取特権
(意義)
9 都市再開発法第107条((先取特権))の先取特権は、施行者が施設建築物の一部を取得した者から徴収すべき清算金について、その施設建築物の一部の上に有する先取特権である(同条1項)。
(効力の保存)
10 都市再開発法第107条((先取特権))の先取特権は、同法第101条第1項((施設建築物に関する登記))の規定による登記(施設建築物及び施設建築物に関する権利についての必要な登記)の際に、清算金の予算額を登記することによってその効力を保存するものであるが、清算金の額がその予算額を超過するときは、その超過額については、先取特権が存在しない(同法107条2項)。
(みなし不動産工事の先取特権)
11 都市再開発法第107条((先取特権))の先取特権は、不動産工事の先取特権.(民法327条)とみなされ、また、10によってした登記は、民法第338条第1項本文((不動産工事の先取特権の保存))の規定に従ってした登記とみなされるから(都市再開発法107条3項)、優先順位については、8と同様である。
都市再開発法第118条の事業代行者の先取特権
(意義)
12 都市再開発法第118条((先取特権))の先取特権は、事業代行者である都道府県知事又は市町村長(同法114条参照)が統轄する地方公共団体が、市街地再開発組合の債務について保証契約をした場合(同法116条参照)において、その保証に係る債務を弁済したときに、その求償権に関し、市街地再開発組合の取得すべき施設建築物の一部の上に有する先取特権である(同法118条1項)。
(効力の保存等)
13 都市再開発法第118条((先取特権))の先取特権の効力の保存、優先順位等は、10及び11と同様である(同条2項、3項)。
立木の先取特権
(意義)
14 法第19条第1項第3号の「立木の先取特権に関する法律第1項(立木の先取特権)の先取特権」は、他人の土地の上に立木を有する者が、土地の所有者に対して、樹木伐採の時期にその樹木の価格に対する一定割合の地代を支払うべき契約をした場合において、その土地の所有者が地代についてその立木の上に有する先取特権である(立木ノ先取特権二関スル法律1項)。
(優先順位)
15 立木の先取特権は、他の権利に対して優先の効力を有するが、民法第329条第2項ただし書((共益費用の優先))の規定の適用は妨げられない(立木ノ先取特権二関スル法律2項)。
商法第810条の救助者の先取特権
(意義)
16 法第19条第1項第4号の「商法第810条(救助者の先取特権)の先取特権」は、船舶又は積荷の全部若しくは一部が海難にあつた場合において、義務なくしてこれを救助したときに、救助者が、その救助料債権について救助した積荷の上に有する先取特権である(商法800条参照)。
(救助料債権)
17 救助料債権については、次のことに留意する。
(1) 救助者の故意又は過失によって海難を引き起こした場合等にあっては、救助料の請求ができない(商法809条)。
(2) 救助料の額は、特約のない限り、救助した物の価額を超えることができず、また先順位の先取特権(19の(1)から(4)まで参照)があるときは、救助料の額はその先取特権者の債権額を控除した残額を超えることができない(商法803条)。
(3) 救助料の請求権は、救助した時から1年を経過したときは、時効によって消滅する(商法814条)。
(優先順位等)
18 商法第810条((救助者の先取特権))の先取特権については、船舶債権者の先取特権(同法842条)に関する規定が準用されているので(同法810条2項)、優先順位及び除斥期間については、21及び22の(1)とそれぞれ同様である。
また、商法第810条の救助者の先取特権は、その目的物である積荷が第三取得者に引き渡されたときは消滅する(同法813条)。
商法第842条の船舶債権者の先取特権
(先取特権を有する債権)
19 法第19条第1項第4号の「商法第842条(船舶債権者の先取特権)の先取特権」は、次の(1)から(8)までに掲げる債権について成立する先取特権である。
(1) 船舶及びその属具の競売に関する費用並びに競売手続開始後の保存費
(2) 最後の港における船舶及びその属具の保存費 (注) 「最後の港」とは、競売をする時において船舶の存在するところをいい、航海を終わって帰来した港等をいうものではない。
(3) 航海に関して船舶に課した諸税
(4) 水先案内料及びひき(挽)船料
(5) 救助料及び船舶の負担に属する共同海損(商法788条以下参照) (注) 上記の救助料は、義務なくして海難を救助した場合の救助料(商法800条)だけでなく、契約による救助料を含む(明治45.2.17大判)。
(6) 航海継続の必要によって生じた債権(商法715条、719条参照) (注) 船籍港内で発生した修繕費等の債権は、上記の「航海継続の必要によって生じた債権」に含まれない(昭和55.5.26福岡地判)。
(7) 雇用契約によって生じた船長その他の船員の債権。
(8) 船舶がその売買又は製造の後まだ航海をしない場合において、その売買又は製造及びぎ(艤)装によって生じた債権並びに最後の航海のためにする船舶のぎ(艤)装、食料及び燃料に関する債権(大正11.9.21長崎控判参照)
(先取特権の目的となる財産)
20 商法第842条((船舶債権の先取特権))の先取特権の目的となる財産は、19に掲げる債権の発生に係る船舶(同法684条参照)及びその属具並びに先取特権が生じた航海における運送賃でまだ受け取っていないものである(同法843条)。
(優先順位)
21 商法第842条((船舶債権者の先取特権))の先取特権は、他の先取特権、船舶抵当権及び船舶質権(登記した船舶は質権の目的とすることができない。同法850条)に優先する(同法845条、849条、民法334条)。また、商法第842条の船舶債権者の先取特権が競合した場合には、次により優先順位が定まる。
(1) 航海ごとに各群をつくり、後の航海で発生したものが前の航海の発生したものに優先する(商法844条3項)。
(2) 同一航海で発生したものの間における優先順位は、19の(1)から(8)までに掲げる順序に従うが、19の(4)から(6)までの債権相互間では、後に発生したものが前に発生したものに優先する(商法844条1項)。
(3) 同一順位のものの間では、債権額の割合に応じて弁済を受けるが、19の(4)から(6)までの債権相互間では、後に発生したものが前に発生したものに優先する(商法844条2項)。
(消滅原因)
22 商法第842条((船舶債権者の先取特権))の先取特権は、次に掲げる場合には消滅する。 (注) この期間は除斥期間である。
(1) 先取特権の発生後1年を経過したとき(商法847条1項)。
(2) 19の(8)に掲げる債権の先取特権については、船舶が発航したとき(商法847条2項。大正12.5.14大判参照)。
(3) 登記できる船舶の譲渡が行われた場合において、譲渡人が船舶譲渡の登記をした後、先取特権者に対して一定期間内(1月を下ることができない。)に債権の申出をすべき旨を公告したにかかわらず、先取特権者がその期間内にその申出をしないとき(商法846条)。
(4) 登記できない船舶(商法686条2項)又は船舶の属具が第三取得者に引き渡されたとき(民法333条)及び運送賃債権が譲渡されたとき。
国際海上物品運送法第19条の船舶先取特権
(意義)
23 法第19条第1項第4号の「国際海上物品運送法第19条(船舶先取特権)の先取特権」は、船舶の全部又は一部を運送契約の目的とした場合(よう(傭)船契約した場合)で、よう(傭)船者が更に第三者と運送契約をしたとき(再運送契約をしたとき)において、運送品に関する損害で船長の職務に属する範囲内で生じたものについて、賠償を請求できる者が、その債権について船舶及びその属具の上に有する先取特権である。
(優先順位等)
24 国際海上物品運送法第19条((船舶先取特権))の先取特権については、商法第842条((船舶債権者の先取特権))の先取特権と競合する場合には同条第9号の先取特権と同一順位とされており(国際海上物品運送法19条2項)、また商法第845条((他の先取特権に対する優先))、第849条((船舶抵当権に対する優先))、第844条第3項((後の航海で発生したものの優先))、第844条第2項((同一順位の場合のあん分等))、第847条第1項((除斥期間))及び第846条((船舶の譲渡と先取特権の消滅))の規定が準用されているので(国際海上物品運送法19条3項)、優先順位及び先取特権の消滅については、21並びに22の(1)及び(3)と同様である。
なお、登記できない船舶(商法686条2項)又は船舶の属具が第三取得者に引き渡されたときは、先取特権が消滅する(民法333条)。
船舳の所有者等の責任の制限に関する法律第95条の先取特権
(意義)
25 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(以下「船主責任制限法」という。)第95条(船舶先取特権)の先取特権は、航海に関して生じた生命又は身体が害されたことによる損害及び物の滅失又は損傷による損害に基づく債権につき、その債権者が事故に係る船舶、その属具及び受領していない運送賃の上に有する先取特権である(同条1項)。
(責任制限手続の開始の効果との関係)
26 責任制限手続(船主責任制限法に基づく責任制限手続をいう。以下27において同じ。)開始決定後においては、当該開始決定の取消し又は手続の廃止の決定が確定したときを除き(同法95条4項)、船主責任制限法第95条((船舶先取特権))の先取特権を行使することはできない(同法33条後段)。
(優先順位等)
27 船主責任制限法第95条((船舶先取特権))の先取特権は、商法第842条第8号((船舶先取特権のある債権))の先取特権に次ぐ(船主責任制限法95条2項)。この先取特権については、商法の船舶債権者の先取特権に関する規定の一部が準用されており(船主責任制限法95条3項)、優先順位及び除斥期間については、21の(1)及び(3)の前段並びに22の(1)及び(3)とそれぞれ同様である。
なお、上記の先取特権が発生後1年で消滅する前に、責任制限手続の開始決定があり、その後に当該開始決定の取消し又は手続の廃止の決定が確定したときは、当該取消し又は廃止の決定の確定後1年を経過した時に消滅する(船主責任制限法95条4項)。
油濁損害賠償保障法第40条の先取特権
(意義)
28 油濁損害賠償保障法(以下「油濁保障法」という。)第40条((船舶先取特権))の先取特権は、船舶から流出した油等による油濁損害に基づく債権につき、その債権者が事故に係る船舶、その属具及び受領していない運送賃の上に有する先取特権である(同法40条1項)。
(優先順位等)
29 責任制限手続(油濁保障法に基づく責任制限手続をいう。)の開始の効果と油濁保障法第40条((船舶先取特権))の先取特権との関係については、26と同様であり(同法38条)、同条の先取特権の優先順位及び除斥期間については、27と同様である(同法40条)。
優先債権等のための動産保存の先取特権
(国税に優先する債権)
30 法第19条第1項第5号の「国税に優先する債権」とは、法第15条から第20条まで((法定納期限等以前に設定された質権の優先等))の規定によって国税に優先する質権、抵当権及び先取特権(いずれも、動産に関するものに限る。)の被担保債権をいい、留置権の被担保債権等(同法21条、59条3項参照)は含まれないものとする。
(優先債権のために動産を保存した者の先取特権)
31 法第19条第1項第5号の「国税に優先する債権のために動産を保存した者の先取特権」とは、30の担保権付債権が成立した後、その動産を保存した者がその動産上に有するその動産保存の先取特権(民法321条)をいう。
なお農業動産信用法第4条第1項第1号((農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権))の先取特権(34参照)は、上記の動産保存の先取特権と同様に取り扱う(同法11条参照)。
(国税のために動産を保存した者の先取特権)
32 法第19条第1項第5号の「国税のために動産を保存した者の先取特権」とは、国税の滞納処分による差押えの効力が生じた時若しくは交付要求(参加差押えを含む。)の効力が生じた時又は国税に係る担保権の設定時の後において、その動産を保存した者がその動産上に有する動産保存の先取特権(民法321条)をいう。
なお、農業動産信用法第4条第1項第1号((農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権))の先取特権(34参照)は、これと同様に取り扱う(同法11条参照)。
(動産保存の先取特権)
33 動産保存の先取特権は、動産の保存費用又は動産に関する権利の保存、追認若しくは実行のために要した費用について、その動産の上に存する先取特権である(民法321条)。 (注)1 動産の保存とは、動産の現状を維持することをいう。
2 動産の保存費用等は、次のような費用である。
(1) 動産の保存費用とは、動産の滅失又はき損を防ぐために行った修理の費用等である。
(2) 権利の保存費用とは、例えば、納税者の所有物を第三者が占有しており、取得時効が完成しようとしている場合において、納税者の債権者がその時効を中断したときに要した費用等である。
(3) 権利の追認に要した費用とは、(2)の例で、占有者に対して納税者の所有権を承認させたときに要した費用等である。
(4) 権利の実行に要した費用とは、(2)の例で、占有者から納税者へ動産を返還させたときの費用等である。
(農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権)
34 農業動産信用法第4条第1項第1号((農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権))の先取特権は、農業用動産又は農業生産物について、その保存又はその物に関する権利の保存、追認若しくは実行のために必要な資金の貸付けをした場合において、農業協同組合等(同法4条参照)の貸付債権につき、その農業用動産又は農業生産物の上に存する先取特権である(同法5条)。
なお、上記の先取特権は、優先権の順位について、動産保存の先取特権とみなされる(同法11条)。
(優先順位)
35 動産保存の先取特権及び農業動産信用法第4条第1項第1号((農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権))の先取特権の優先順位は、次のとおりである。
(1) 動産保存の先取特権又は農業動産信用法第4条第1項第1号の先取特権が、他の特別の先取特権、質権又は抵当権と競合した場合には、第2順位の優先権を有する(民法330条1項。以下第19条及び第20条関係において、これら第2順位の先取特権を「第2順位担保権」という。)。したがって、第1順位の優先権を有する不動産賃貸の先取特権(同法312条)、旅店宿泊の先取特権(同法317条)、運輸の先取特権(同法318条)、動産質権(同法334条)、農業用動産抵当権(農業動産信用法16条)、自動車抵当権(自動車抵当法11条)、航空機抵当権(航空機抵当法11条)及び建設機械抵当権(建設機械抵当法15条。以下第19条及び第20条関係において、これらの担保権を「第1順位担保権」という。)には劣後し、第3順位の優先権を有する動産売買の先取特権(民法322条)、種苗肥料供給の先取特権(同法323条)、農工業労役の先取特権(同法324条)及び農業動産信用法第4条第1項第2号から第6号までの先取特権(同法11条。以下第19条及び第20条関係において、これらの先取特権を「第3順位担保権」という。)には優先する。ただし、(2)及び(3)の場合においては、この限りでない。
(2) 第1順位担保権を有する者が、その債権取得の当時において、既に第2順位担保権者又は第3順位担保権者があることを知っていたときは、その第2順位担保権又は第3順位担保権が第1順位担保権に優先する(民法330条2項前段、334条、農業動産信用法16条、自動車抵当法11条、航空機抵当法11条、建設機械抵当法15条)。
(3) 第1順位担保権が成立した後、その動産を保存したときの第2順位担保権は、その第1順位担保権に優先する(民法330条2項後段、334条、農業動産信用法16条、自動車抵当法11条、航空機抵当法11条、建設機械抵当法15条)。
(4) 第2順位担保権が競合したときは、後に保存したものが、前に保存したものに優先する(民法330条1項2号後段)。
(先取特権の消滅)
36 動産に関する先取特権は、その動産が第三取得者に引き渡されたときは消滅する(民法333条)。
証明の期限と方法
37 法第19条第1項第3号(登記したものを除く。)から第5号までの先取特権が第1項の規定の適用を受けるための証明については、第15条関係24及び25の(2)と同様である(法19条2項、令4条1項、3項、通則令2条7号)。
登記事項の調査確認
38 法第19条第1項第1号から第3号(登記したものに限る。)までの先取特権については、徴収職員がその登記されている先取特権がある事実を調査確認しなければならない。
第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先
不動産賃貸の先取特権等の優先
1 法第20条第1項各号に掲げる先取特権(仮登記(保全仮登記を含む。)に係るものを含む。法133条3項、令50条4項参照)は、法第19条第1項各号に規定する先取特権とは異なり、一定の条件の下に質権又は抵当権に優先し、又は同順位であるところから、先取特権の成立が国税の法定納期限等以前又は財産譲渡時以前であるときに限り、その被担保債権は、国税に優先する。
なお、法第20条第1項各号及び法第19条第1項各号((不動産保存の先取特権等の優先))の先取特権に該当しない先取特権の被担保債権は、国税に劣後することはもちろん、滞納処分手続においては劣後配当も受けられない。
法定納期限等以前からあるとき
2 法第20条第1項の「法定納期限等以前」には、その法定納期限等に当たる日を含む。したがって、その日に成立した先取特権も、法定納期限等以前にある先取特権となる。
財産譲渡との関係
(譲り受けたとき)
3 法第20条第1項の「財産を譲り受けたとき」は、第17条関係1と同様である。 (注) 先取特権のある財産が譲渡された場合における譲渡人の国税と先取特権との関係については、法第22条((担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収))の規定に相当する規定がないことに留意する。
(譲渡による先取特権の消滅)
4 法第20条第1項第1号の先取特権については、その目的となっている動産が第三取得者に引き渡されたときは消滅する(民法333条)。
不動産賃貸等の先取特権
(不動産賃貸の先取特権)
5 法第20条第1項第1号の「不動産賃貸の先取特権」は、不動産の賃貸料その他賃貸借関係から生ずる賃貸人の債権(損害賠償請求権等)について、賃借人の動産の上に成立するものであるが(民法312条)、その被担保債権及び目的財産については、次のことに留意する。
(1) 賃貸人が敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けることができない不足額についてだけ先取特権が成立する(民法316条)。また、賃借人の財産の総清算の場合(破産の場合等)には前期、当期及び次期の賃借料その他の債権並びに前期及び当期において生じた損害賠償についてだけ先取特権が成立する(同法315条)。
(2) 土地の賃貸人の先取特権の目的物は、賃借地又はその利用のためにする建物に備え付けた動産、その土地の利用に供した動産及び賃借人が占有しているその土地の果実であり(民法313条1項)、建物の賃貸人の先取特権の目的物は、賃借人がその建物に備え付けた動産である(同法313条2項)。
また、賃借権の譲渡又は転貸があった場合においては、賃借権の譲受人又は転借人の動産及び譲渡人又は転貸人の受けるべき金額(賃借権譲渡の対価等)にも、先取特権の効力が及ぶ(民法314条)。
(質権と同一順位の先取特権)
6 法第20条第1項第1号の「質権と同一の順位」の先取特権とは、不動産賃貸の先取特権のほか、旅店宿泊の先取特権(民法317条)及び運輸の先取特権(同法318条)をいい(同法330条1項、334条)、先取特権の目的財産が農業上の果実(収穫物)であるときは、農業の労役者の先取特権(同法324条)をいう(同法330条3項、334条)。
(旅店宿泊の先取特権)
7 「旅店宿泊の先取特権」は、旅客、その従者及び牛馬の宿泊料並びに飲食料の請求権について、その旅店にある債務者の手荷物の上に存する先取特権である(民法317条)。
(運輸の先取特権)
8 「運輸の先取特権」は、旅客又は荷物の運送賃及びそれに付随する費用(荷造費等)の請求権について、運送人の所持内にある荷物の上に存する先取特権である(民法318条)。
(動産保存の先取特権等)
9 「動産保存の先取特権」及び「農業動産信用法第4条第1項第1号((農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権))の先取特権」については、第19条関係33及び34と同様である。 (注) 上記の先取特権は、法第20条第1項第1号に該当する場合(14参照)のほか、法第19条第1項第5号に該当する場合(第19条関係31、32参照)と、これらいずれにも該当せず、劣後配当も受けられない場合とがある。
(動産売買の先取特権)
10 「動産売買の先取特権」は、動産の代価及びその利息について、その動産の上に存する先取特権である(民法322条)。
(種苗肥料供給の先取特権)
11 「種苗肥料供給の先取特権」は、種苗若しくは肥料の代価及びその利息又は蚕種若しくは蚕の飼養の供した桑葉の代価及びその利息について、その種苗若しくは肥料を用いた後、1年内にその用いた土地から生じた果実(収穫物)又はその蚕種若しくは桑葉から生じた物の上に存する先取特権である(民法323条)。
(農工業労役の先取特権)
12 「農工業労役の先取特権」は、農業労役者については最後の1年間、工業労役者については最後の3月間の賃金について、その労役によって生じた果実(農業収穫物)又は工業製作物の上に存する先取特権である(民法324条)。
(農業動産信用法の先取特権)
13 「農業動産信用法第4条第1項第2号から第6号まで((農業用動産の購入資金貸付けの先取特権等))の先取特権」は、貸し付けた債権の元本及び利息について、次に掲げる財産の上に存する先取特権である(同法4条1項1号の農業用動産等の保存資金貸付けの先取特権については、第19条関係34参照)。
なお、優先順位については、次の(1)及び(2)の先取特権は動産売買の先取特権(10参照)と、(3)から(5)までの先取特権は種苗肥料供給の先取特権(11参照)と、それぞれみなされる(農業動産信用法11条)。
(1) 農業用動産の購入資金貸付けの先取特権については、貸付けを受けた資金をもって購入した農業用動産(農業動産信用法6条)
(2) 薪炭原木の購入資金貸付けの先取特権については、貸付けを受けた資金をもって購入した薪炭原木から生産した薪炭(農業動産信用法9条)
(3) 種苗又は肥料の購入資金貸付けの先取特権については、貸付けを受けた資金をもって購入した種苗又は肥料を用いた後1年内にその用いた土地から生じた果実、また、桑樹の肥料購入資金貸付けの先取特権についてはその果実たる桑葉より生じた物(農業動産信用法7条)
(4) 蚕種又は桑葉の購入資金貸付けの先取特権については、貸付けを受けた資金をもって購入した蚕種又は桑葉より生じた物(農業動産信用法8条)
(5) 水産養殖用種苗又は水産養殖用じ(餌)料の購入資金貸付けの先取特権については、貸付けを受けた資金をもって購入した種苗を養殖した物又は貸付けを受けた資金をもって購入したじ(餌)料を用いて養殖した物(農業動産信用法10条)
(これらに優先する先取特権)
14 法第20条第1項第1号の「これらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第1項第3号から第5号までに掲げる先取特権を除く。)」とは、次のものをいう。
(1) 第1順位担保権(第19条関係35の(1)参照)を有する者が、その債権取得の当時において、既に第2順位担保権者(第19条関係35の(1)参照)又は第3順位担保権者(第19条関係35の(1)参照)のあることを知っていた場合におけるその第2順位担保権及び第3順位担保権(民法330条前段。第19条関係35の(2)参照)
(2) 第1順位担保権成立後第2順位担保権が成立した場合におけるその第2順位担保権(民法330条2項後段。第19条関係35の(3)参照) (注) 上記に該当しない場合、すなわち、第2順位担保権又は第3順位担保権と第1順位担保権との競合がない場合、第1順位担保権が第3順位担保権よりも先に成立した場合及び第1順位担保権の成立当時に第2順位担保権者又は第3順位担保権者のあることを知らなかった場合には、法第20条第1項第1号には該当しない。
(優先順位)
15 第20条関係5から14までの先取特権の優先順位は、第19条関係35と同様である(民法330条1項、2項)。ただし、先取特権の目的財産が農業上の果実である場合の優先順位は、第1順位が農業の労役者、第2順位が種苗又は肥料の供給者、第3順位が土地の賃貸人である(同法330条3項)。
不動産売買の先取特権
(意義)
16 法第20条第1項第2号の「不動産売買の先取特権」は、不動産の代価及びその利息について、その不動産の上に存する先取特権である(民法328条)。
(効力の保存)
17 不動産売買の先取特権は、売買契約と同時に(売買による所有権移転登記とともに)、また代価又はその利息の弁済がない旨を登記することによってその効力を保存するものであるから(民法340条)、登記をしない場合はもちろん、売買契約と同時に登記していない場合にも、先取特権としての優先権を行使できない。
(優先順位)
18 不動産売買の先取特権は、不動産保存の先取特権及び不動産工事の先取特権に次ぐ優先権を有し(民法331条1項)、抵当権又は不動産質権と競合した場合には、登記の前後によって優先順位が定まる(同法341条、373条)。また、同一の不動産について逐次の売買があった場合における売主相互間の順位は、売買の時期の前のものが後のものに優先する(同法331条2項)。
借地法第13条の土地所有者等の先取特権等
(借地法第13条の先取特権) 編注9
19 法第20条第1項第3号の「借地法第13条(土地所有者等の先取特権)に規定する先取特権」の意義等は、次のとおりである。
(1) 借地法第13条の先取特権は、土地所有者又は賃貸人が、弁済期に至った最後2年分の地代又は借賃について、借地権者がその土地に所有する建物の上に有する先取特権である(同法13条1項)。
(2) 借地法第13条の先取特権は、地上権又は賃貸借の登記をすることによって効力を保存するものであるから(同法13条2項)、これらの登記をしていない場合には、先取特権としての優先権を行使できない。
(3) 借地法第13条の先取特権は、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに(2)による登記前に登記されている質権及び抵当権には劣後するが、他の権利に対しては優先の効力を有する(同法14条)。
(罹災都市借地借家臨時処理法第8条の先取特権)
20 法第20条第1項第3号の「罹災都市借地借家臨時処理法第8条(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権」の意義等は、次のとおりである。
(1) 罹災都市借地借家臨時処理法第8条の先取特権は、賃借権の設定(同法2条)又は借地権の譲渡(同法3条)があった場合において、賃貸人又は借地権の譲渡人が、借賃の全額又は借地権の譲渡の対価について、借地権者がその土地に所有する建物の上に有する先取特権である(同法8条1項)。
(2) 罹災都市借地借家臨時処理法第8条の先取特権は、借賃についてはその額及び存続期間、借賃の支払時期の定めがあるときはその旨、弁済期の到来した借賃があるときはその旨、また譲渡の対価についてはその対価の弁済されない旨を登記することによって効力を保存するものであるから(同法8条2項)、これらの登記をしていない場合には、先取特権としての優先権を行使できない。
(3) 罹災都市借地借家臨時処理法第8条の先取特権は、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに(2)による登記前に登記されている質権及び抵当権には劣後するが、他の権利に対しては優先の効力を有する(同法8条3項)。
(接収不動産に関する借地借家臨時処理法第7条の先取特権)
21 法第20条第1項第3号の「接収不動産に関する借地借家臨時処理法第7条(賃貸人等の先取特権)に規定する先取特権」は、賃借権の設定(接収不動産に関する借地借家臨時処理法3条)又は借地権の譲渡(同法4条)があった場合において、賃貸人又は借地権の譲渡人が、借賃の全額及び貸借権の設定の対価又は借地権の譲渡の対価について、その賃借権の設定又は借地権の譲渡を受ける者がその土地に所有する建物の上に有する先取特権である(同法7条1項)。
なお、上記の先取特権の効力の保存及び優先の効力については、20の(2)及び(3)と同様である(同法7条2項、3項)。
一般の先取特権
(種類及び意義)
22 一般の先取特権には、次のものがある。
(1) 民法の規定による先取特権 イ 共益費用の先取特権(民法306条1号)は、各債権者の共同の利益のためにした債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在するが、これが総債権者のうちの一部の者にとってだけ利益となっているときは、その者に対してだけ存在する(同法307条)。
ロ 雇人給料の先取特権(民法306条2号)は、雇人が受けるべき最後の6月間の給料について存在する(同法308条)。
ハ 葬式費用の先取特権(民法306条3号)は、債務者の身分に応じてした葬式の費用(死亡者の財産の上に先取特権が成立する。)又は債務者がその扶養すべき親族の身分に応じてした葬式の費用(葬式をした者の財産の上に先取特権が成立する。)について存在する(同法309条)。
ニ 日用品供給の先取特権(民法306条4号)は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその使用人の生活に必要な最後の6月間の飲食品及び薪炭油の供給の代価について存在する(同法310条)。
(2) 商法の規定による先取特権
商法第295条((会社使用人の先取特権))の先取特権は、身元保証金の返還を目的とする債権その他会社と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する(同法295条1項)。
(3) 有限会社法の規定による先取特権
有限会社法第46条第2項((会社使用人の先取特権))の先取特権は、有限会社と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する(同法46条2項、商法295条1項)。
(優先順位等)
23 一般の先取特権の優先順位等は、次のとおりである。
(1) 一般の先取特権は、特別の先取特権には劣後するが、共益費用の先取特権だけは、その利益を受けた総債権者に対して優先の効力を有する(民法329条2項)。
また、登記をした一般の先取特権と抵当権又は不動産質権とが競合した場合には、登記の早いものが優先する(民法341条、373条参照)。
(2) 22の(1)の先取特権(民法の規定による先取特権)が競合した場合には、その優先順位は、22の(1)のイからニまでの順序に従う(民法329条1項)。また、22の(2)及び(3)の先取特権(会社使用人の先取特権)の優先順位は、22の(1)のイの先取特権(共益費用の先取特権)に次ぐ(商法295条2項、有限会社法46条2項)。
(3) 一般の先取特権は、まず不動産以外の財産について弁済を受けることを要し、その不足額についてだけ不動産から弁済を受けることができ(民法335条1項)、また不動産からの弁済についても、まず特別担保の目的となっていないものから弁済を受けることを要するのであって(同法335条2項)、これらの順序に従わず、配当加入を怠ったときは、配当加入をすれば弁済を受けたであろう限度において、登記をした第三者に対して先取特権を行使することができない(同法335条3項)。ただし、不動産以外の財産に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産に先立って特別担保の目的不動産の代価を配当すべきときは、この限りでない(同法335条4項)。
(共益費用の先取特権とみなされる先取特権)
24 建物の区分所有等に関する法律第6条の先取特権は、建物の区分所有者(同法2条2項)が共用部分(同法2条4項)又は建物の敷地につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利及び専用部分(同法2条3項)を所有するための建物の敷地に関する権利を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に有する先取特権であり(同法6条1項)、その優先権の順位及び効力については、共益費用の先取特権とみなされる(同法6条2項)。
証明の期限等
25 法第20条第1項第1号の先取特権が第1項の規定の適用を受けるための証明については、第15条関係24及び25の(2)と同様である(法20条2項、令4条1項、3項、通則令2条7号)。
なお、法第20条第1項第2号から第4号までの先取特権については、証明を要せず、徴収職員はその先取特権がある事実を確認しなければならず、また、法第20条第1項各号の先取特権が法定納期限等以前又は譲受け前からあるかどうかについては、徴収職員が調査確認しなければならない。 (注) 法第20条第1項第1号の先取特権は、その目的財産が第三取得者に引き渡されたときは消滅するから(民法333条)、財産の譲受けとの関係は考慮する必要がない。
第21条関係 留置権の優先
留置権
(留置権の種類)
1 法第21条の「留置権」とは、民法第295条((留置権の内容))に規定する民事留置権のほか、商事留置権である代理商の留置権(商法51条)、商人間の留置権(同法521条)、問屋の留置権(同法557条)、運送取扱人の留置権(同法562条)、運送人の留置権(同法589条)及び船舶所有者の留置権(同法753条2項)をいう。
(民事留置権)
2 民法の規定による留置権とは、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権を有する場合において、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる権利をいう(民法295条1項本文)。
なお、民事留置権については、次のことに留意する。
(1) 物に関して生じた債権とは、物と関連のある債権をいい、債権が物自体より発生した場合又は債権が物の返還義務と同一の法律関係若しくは事実関係より発生した場合のその債権が、これに当たる。 (注)1 債権が物自体より発生した場合の例としては、物のかしによる損害賠償請求権、物に加えた費用の償還請求権がある。
2 債権が物の返還義務と同一の法律関係より発生した場合の例としては、物の売買代金債権、物の修繕料債権がある。
(2) 他人の物とは、債権者(留置権者)以外の者の所有物をいい、債務者の物に限らず、第三者の物も含まれる。
(3) 債権が弁済期にない間は、留置権は発生しない(民法295条1項ただし書)。 (注) 債権の弁済期については、期限の利益喪失に関する民法第137条((期限の利益の喪失))及び破産法第17条((弁済期の到来))の規定があるほか、特約により期限の利益を失う場合がある。
(4) 物の占有が不法行為によって始まったときは、留置権は成立しない(民法295条2項)。
なお、留置権者が債務者に対抗できる占有の権原がなく、かつ、それを知り、又は過失により知らないで占有を始めた場合にも、留置権は成立しない(昭和30.3.11東京高判)。
(留置権と果実収取権)
3 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立ってこれを留置権により担保される債権の弁済に充てることができる(民法297条1項)。この場合において、収取した果実は債権の利息に充て、なお残余があるときは元本に充てなければならない(同法297条2項)。
(留置権と費用償還請求権)
4 留置権者は、留置物につき必要費を支出したときは、その物の所有者に対しその必要費の償還をさせることができる(民法299条1項)。また、留置権者は、留置物につき有益費を支出したときは、その価格の増加が留置物につき現存する場合に限り、その費用額又は増加額の償還をその留置物の所有者に対し請求することができるが、その所有者の請求により裁判所が期限につき相当期間の許与をした場合には、その有益費につき留置権を行使することができない(同法299条2項)。
(留置権の移転)
5 留置権の移転は、その担保される債権と目的物の占有とを、ともに移転することによって行うことができる。
(留置権の消滅)
6 留置権は、目的物の滅失、没収、収用、混同、留置権により担保される債権の消滅等によって消滅するほか、次に掲げる場合にも消滅する。
(1) 留置権者が、留置物につき善良な管理者の注意を怠り、債務者又は留置物の所有者の承諾なくして使用若しくは賃貸をし、又は担保に供したため、債務者又は留置物の所有者が、民法第298条第3項((債務者の消滅請求))の規定により留置権の消滅の請求をした場合
(2) 債務者又は留置物の所有者が、留置権者の承諾又はこれに代わるべき民法第414条第2項ただし書((履行の強制))の判決を得て相当の担保を提供して留置権の消滅を請求した場合(同法301条)
(3) 留置権者が、債務者又は留置物の所有者の承諾を得て賃貸又は質入れをした場合以外で、留置物の占有を喪失した場合(民法302条) (注) 留置権のある財産を滞納処分により差し押さえ、徴収職員がその財産を占有しても、私法上の占有関係には影響を及ぼさないことから、留置権は消滅しない。
(破産による留置権の失効等)
7 破産財団の財産上にある留置権のうち、商法の規定によるものはその破産財団に対しては特別の先取特権とみなされるが(破産法93条1項)、他の留置権は破産財団に対してはその効力を失う(同法93条2項)。また、更生会社の財産上にある商法の規定による留置権に限り、更生担保権となる(会社更生法123条1項)。
(代理商の留置権)
8 代理商の留置権とは、代理商が、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権が弁済期にあるときに、その弁済を受けるまで、本人のために占有する物又は有価証券を留置することができる権利をいう(商法51条)。
(商人間の留置権)
9 商人間の留置権とは、商人間においてその双方のために商行為である行為によって生じた債権が弁済期にあるときに、債権者が、債務の弁済を受けるまで、債務者との間の商行為によって自己の占有に帰した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができる権利をいう(商法521条)。
(問屋の留置権)
10 問屋の留置権とは、問屋が自己の名をもって第三者のために物品の販売又は買入れをしたことによって生じた債権が弁済期にあるときに、その弁済を受けるまで、債権者である問屋が、債務者であるその第三者のために占有している物又は有価証券を留置することができる権利をいう(商法557条、51条)。
(運送取扱人の留置権)
11 運送取扱人の留置権とは、運送取扱人が、運送品に関して受け取るべき報酬・運送賃その他委託者のためにした立替え又は前貸しについて、債務の弁済があるまで、その運送品(報酬等を請求できる運送品に限られるが、委託者の所有物であることを要しない。)を留置することができる権利をいう(商法562条)。
なお、運送中の運送品に対する留置権の行使は、荷送人としての運送品処分権(商法582条)の行使によって行う。 (注) 運送取扱人とは、運送品発送人の計算において、自己の名をもって運送人と運送契約を締結し、その他運送に必要な手配をすることを業(取次業)とする者をいい、荷送人としての権利を有する(運送品発送人は、この荷送人には該当しない。)。
(運送人の留置権)
12 運送人の留置権とは、運送人が、運送品に関して受け取るべき報酬、運送賃その他荷送人のためにした立替え又は前貸しについて、債務者の弁済があるまで、その運送品を留置することができる権利をいう(商法589条、562条)。
なお、運送人は、運送賃その他法定の債権(例えば、通関手続の費用、倉庫保管料等)につき、運送品に対して先取特権(民法318条)をも有する。
(船舶所有者の留置権)
13 船舶所有者の留置権とは、荷受人が運送契約又は船荷証券に定められる約定等によって運送賃、付随の費用、立替金、てい泊料及び運送品の価格に応じ共同海損又は救助のために負担すべき金額を支払わないときに、船長が、これらの支払があるまで、その運送品を留置することができる権利をいう(商法735条2項)。
留置権の優先
(同一債権につき留置権と先取特権とがある場合)
14 換価に付された財産上にある留置権により担保される債権が、同時にその財産についての先取特権によって担保されている場合(例えば、荷物の運輸の場合には、運送人は、運送賃についてその荷物の上に留置権を有すると同時に、動産の先取特権をも有する。民法318条)には、留置権により担保される債権は先取特権等に優先して配当を受け、先取特権により担保される債権は留置権により担保される債権に対して配当された額の範囲において消滅する。
(留置権の成立時期と法定納期限等との関係)
15 留置権の被担保債権は、その留置権の成立の時期が国税の法定納期限等の以前であると後であるとを問わず、国税に優先し、かつ、質権、抵当権、先取特権又は担保のための仮登記により担保される債権に先立って配当を受ける。
(差押え後に成立した留置権)
16 留置権の被担保債権は、その留置権の成立の時期が差押え後であっても、法第21条の規定により、国税等に優先して配当を受けられるものとする。ただし、留置権者が、差押債権者に対抗できる占有の権原がなく、かつ、それを知り、又は過失により知らないで占有を始めたときは、その留置権の成立をもって差押債権者に対抗できないものとする(2の(4)参照)。 (注) 上記ただし書の例としては、滞納者が自動車の差押えを受け、運行の許可がされないまま保管をしていた場合(法71条5項)において、その自動車の修理を業者に依頼し、その業者がそれらのを知りながら修理をしたときの留置権がある。すなわち、この例の場合には、修理代金についての差押自動車を目的物とする留置権の成立は、差押債権者に対抗することができず、したがって、法第21条の適用はないものとする。
証明の期限等
17 法第21条の留置権が、第1項の規定の適用を受けるための証明については、第15条関係24及び25の(2)と同様である(法21条2項、令4条1項、3項、通則令2条7号)。
留置権者が配当を受けられる場合
18 留置権者は納税者の財産が滞納処分によって換価される場合においてのみ、法第21条第1項の規定により配当を受けることができる。
第22条関係 担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収
徴収できる場合
(他に国税に充てるべき十分な財産がない場合)
1 法第22条第1項の「他の国税に充てるべき十分な財産がない場合」については、次のことに留意する。
(1) 「他に」とは、法第22条第1項の譲渡した財産を除外することをいう。
(2) 十分な財産がないかどうかは、4に準じて判定する。
(3) 上記(2)の判定は、法第22条第1項の財産譲渡の時の現況により行う。
(質権又は抵当権)
2 法第22条の「質権又は抵当権」は、登記したものに限られ、登記しない質権又は抵当権については、法第22条の規定の適用がない。 (注) 通則法、法その他の国税に関する法律の規定により担保を徴した国税に係る担保権については、法第14条の規定により担保を徴した国税が他の国税又は地方税に優先するため、法第22条の規定は適用されない。
(譲渡)
3 法第22条の「譲渡」は、第17条関係1と同様である。
なお、納税者が財産を譲渡した後、その譲受人が更にその財産を譲渡した場合においても、法第22条の規定の適用がある。
(国税に不足すると認められるとき)
4 法第22条第1項の「国税に不足すると認められるとき」とは、法第22条第4項の通知を発する時の現況において、納税者に帰属する財産(国税につき徴している担保財産で、第三者に帰属しているもの及び保証人の保証を含めるものとする。)で滞納処分(交付要求及び参加差押えを含む。)により徴収できるものの価額が、納税者の国税の総額に満たないと認められることをいい、その判定は、滞納処分を現実に執行した結果に基づいてする必要はないものとする。
なお、上記の場合における財産の価額の算定については、昭和55.6.5付徴徴2-9「公売財産評価事務提要の制定について」通達に定めるところによるが、次のことに留意する。
(1) 財産について、法その他の法律の規定により納税者の国税に優先する私債権、公課、地方税又は納税者以外の者の国税がある場合には、その優先する債権額に相当する金額をその財産の処分予定価額から控除して財産の価額を算定する。
(2) 法第76条第5項((給与の差押禁止の特例))の規定により納税者の承諾がある場合に限り差押えができる給料等がある場合には、原則として、その承諾が得られないものとしてその財産の価額を算定する。
(3) 財産について、その取立てをすることとされている場合には、換価するものとしてその財産の価額を算定する。
(4) 継続収入に係る債権又は将来生ずべき債権がある場合には、換価するものとしてその債権の価額を算定する。
(5) 交付要求に係る財産がある場合には、直ちにその財産を換価したとした場合において配当を受けることができると認められる金額を基準として、その財産の価額を算定する。
(6) 滞納処分費を要すると認められる場合には、その見込額を控除して財産の価額を算定する。
(徴収できることの意味)
5 法第22条第1項の「徴収することができる」とは、質権者又は抵当権者が強制換価手続において、質権又は抵当権の被担保債権につき配当を受けるべき金額のうちから、納税者の国税を徴収できることをいい、質権者又は抵当権者はその国税についての納付義務を負うものではない。
なお、質権者又は抵当権者は、通則法第41条第1項((第三者の納付))の規定による第三者納付の場合以外は、その国税を自己の名において納付することもできない。
(抵当権付債権の譲渡等と法第22条の適用)
6 法第22条第1項の質権又は抵当権の被担保債権が第三者に譲渡された場合にも、法第22条の規定を適用することができる。
なお、法第22条1項の質権又は抵当権の被担保債権が強制換価手続により差し押さえられた場合(転付命令があった場合を含む。)において、これらの担保権の目的財産が強制換価され、その差押債権者がその執行機関から配当を受ける場合についても、同様である。
(被担保債権の弁済等と法第22条の不適用)
7 法第22条の規定により質権者又は抵当権者から納税者の国税を徴収できるのは、質権者又は抵当権者が強制換価手続において配当を受けるべき金額がある場合に限られるので、次に掲げる場合には、法第22条の規定による徴収ができない。
(1) 強制換価手続終了前に質権又は抵当権の被担保債権が弁済、免除(民法519条)、混同(同法520条)等により消滅し、配当を受けるべき金額がない場合
(2) 民法第377条((代価弁済))、第378条((てき除))等の規定により、代価弁済又はてき除により抵当権が消滅した場合(不動産質権について、同法361条((抵当権の規定の準用))の規定によりてき除等をした場合を含む。)
徴収できる金額
8 法第22条第1項の規定により納税者の滞納国税(令6条1項2号参照)を徴収することができる金額は、(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した額と納税者の滞納国税の額とのうち、いずれか少ない額である(法22条2項)。 (1) 法第22条第1項の質権又は抵当権の被担保債権が、譲渡に係る財産の換価代金から配当を受けることができる金額(次の例において「配当金額」という。)
(2) 譲渡に係る財産を納税者の財産とみなして、その財産の換価代金につき納税者の国税の交付要求があったものとした場合において、法第22条第1項の質権又は抵当権の被担保債権が配当を受けることができる金額(次の例において「仮定配当金額」という。) 〔例1〕(抵当権が1つの場合)
A 譲渡人の国税(法定納期限等昭和58. 3.15)・・・・・・・・・・8万円
B 甲抵当権の被担保債権(設定登記昭和58. 4.11)・・・・・・6万円
C 換価代金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円 イ 配当金額(Bの全額)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6万円
ロ 仮定配当金額(Cの10万円-Aの8万円)・・・・・・・・・・・・2万円
ハ 徴収額の限度(イの6万円-ロの2万円)・・・・・・・・・・・・・4万円
※ 徴収できる金額(Aとハとの少額の方)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4万円
(甲抵当権者が配当を受けることができる金額6万円のうちから、4万円を徴収することができる。)
〔例2〕(抵当権が2以上ある場合)
A 譲渡人の国税(法定納期限等昭和57. 3.15)・・・・・・・・・・・6万円
B 甲抵当権の被担保債権(設定登記昭和57. 4.10)・・・・・・・3万円
C 乙抵当権の被担保債権(設定登記昭和57. 5. 1)・・・・・・・4万円
D 丙抵当権の被担保債権(設定登記昭和57. 6.21)・・・・・・・2万円
E 換価代金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円 (1) 配当金額
換価代金10万円の各抵当権に対する配当金額は、抵当権の順位により次のとおりとなる。 イ 甲抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3万円
ロ 乙抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4万円
ハ 丙抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円
(2) 仮定配当金額
換価代金10万円は、国税が交付要求をすると6万円配当され、残額の4万円は担当権の順位により次のとおりとなる。 ニ 甲抵当権(4万円の範囲内でBの全額)・・・・・・・・・・・・3万円
ホ 乙抵当権(Cは4万円あるが4万円-二の3万円)・・・・・1万円
ヘ 丙抵当権(4万円-二の3万円-ホの1万円)・・・・・・・・・・0円
(3) 徴収額の限度
各抵当権者から徴収することができる国税の金額は、(1)から(2)を控除した金額であることから、次のとおりとなる。 ト 甲抵当権(イの3万円-二の3万円)・・・・・・・・・・・・・・・・・O円
チ 乙抵当権(ロの4万円-ホの1万円)・・・・・・・・・・・・・・・3万円
リ 丙抵当権(ハの2万円-への0円)・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円
※ 徴収できる金額(トとチとリの合計額と、Aとの少額の方)・・・・5万円
(甲抵当権者が配当を受けることができる金額からは徴収できないが、乙抵当権者が配当を受けることができる金額4万円のうちから3万円 チ と丙抵当権者が配当を受けることができる金額2万円からその全額2万円 リ とを、徴収することができる。)
〔例3〕(優先抵当権と劣後抵当権とがある場合)
A 譲渡人の国税(法定納期限等昭和58. 3.15)・・・・・・・3万円
B 甲抵当権の被担保債権(設定登記昭和58. 2. 1)・・・・・・4万円
C 乙抵当権の被担保債権(設定登記昭和58. 4.10)・・・・・・5万円
D 換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円 (1) 配当金額
乙抵当権は、その設定登記の順位により甲抵当権に劣後する。そこで、乙抵当権に対する配当金額は、換価代金から甲の被担保債権を控除した残額の範囲で定まることになる。
Dの10万円-Bの4万円=6万円(ただし、乙抵当権の被担保債権は5万円であるので、5万円が配当金額となる。)・・・・・・・・・・・・5万円
(2) 仮定配当金額
法定納期限等と抵当権の設定順位に従い配当をするとすれば、国税に劣後する乙抵当権が配当を受けるべき金額は、次のとおりとなる。
Dの10万円-Bの4万円-Aの3万円・・・・・・・・・・・・・・3万円
(3) 徴収額の限度
乙抵当権者から徴収することができる国税の金額は、(1)から(2)を控除した金額であることから、次のとおりとなる。
(1)の5万円-(2)の3万円・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円
※徴収できる金額(Aと(3)との少額の方)・・・・・・・・・・・・・・・・・2万円
(乙抵当権者が配当を受けることができる金額5万円のうちから2万円を徴収することができるが、甲抵当権については法22条の適用がない。)
質権等の代位実行
(代 位)
9 法第22条第3項の「質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる」とは、税務署長が、質権者又は抵当権者の地位に立って、その質権又は抵当権を実行できることをいう。
なお、上記の場合において、質権又は抵当権の代位実行をするために民法第381条((てき除権者への抵当権実行の通知))の通知等の前提手続を必要とするときは、それらの手続についても代位することができる。
(他の代位権者がある場合と代位実行との関係)
10 質権者又は抵当権者に代位(民法392条、398条ノ16,499条等)してその質権又は抵当権を実行する者がいる場合には、これらの代位権者が配当を受けることができる金額からも、納税者の国税を徴収することができる(法22条1項)。
なお、上記の代位権者が質権又は抵当権の実行をしない場合には、税務署長は、その代位実行をすることができる(法22条3項)。
(実行)
11 法第22条第3項の「実行」とは、登記した質権又は抵当権が設定されている財産を執行法等の規定により売却し、その売却代金からこれらの担保権の被担保債権の弁済を受けることをいう。
なお、次に掲げる財産に対する実行は、それぞれに掲げる法令の規定により行う。
(1) 自動車抵当法の適用を受ける自動車、建設機械抵当法の適用を受ける建設機械又は航空機抵当法の適用を受ける航空機執行規則
(2) 農業動産信用法の適用を受ける農業用動産農業用動産抵当権実行令
(3) 鉄道抵当法の適用を受ける鉄道財団鉄道抵当法第3章((強制競売及強制管理))の規定のうち強制競売に関する規定
(4) 軌道ノ抵当二関スル法律の適用を受ける軌道財団又は運河法の適用を受ける運河財団軌道ノ抵当二関スル法律第1条((鉄道抵当法の準用))又は運河法第13条((運河抵当))の規定に基づき準用される鉄道抵当法第3章((強制競売及強制管理))の規定のうち強制競売に関する規定
(5) 電話加入権質に関する臨時特例法の規定により質権が登録された電話加入権執行法第193条((質権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等))の規定又は電話加入権質に関する臨時特例法第11条第1項本文((質権の実行としての特別の処分))の規定
(代位実行ができる場合)
12 法第22条第3項の規定による代位実行ができるのは、法第22条第1項の質権又は抵当権についてその実行をすることができる要件を充足した場合に限られる。この場合において、法第22条の規定により徴収することができる国税の範囲が、質権者又は抵当権者の配当を受けることができる金額の一部であるときでも、代位による実行ができる。
(原則的な実行の要件)
13 質権又は抵当権者の実行をすることができるのは、法律に特別の規定(14参照)がない限り、次に掲げる要件のすべてに該当している場合である。
(1) 登記がされている質権又は抵当権及びこれらの担保権により担保されている債権があること。
(2) 被担保債権が履行遅滞になっていること。
(3) 民法第378条((てき除))の第三取得者に対して質権又は抵当権の実行をしようとする旨の通知をし(同法381)、その通知後(第三取得者がその通知を受けた後)1月内に第三取得者から債務の弁済又はてき除の通知を受けていないこと(同法387条)。 (注) 民法第381条((てき除権者への抵当権実行の通知))の規定による抵当権実行の旨の通知については、次のことに留意する。 1 第三取得者とは、抵当不動産について所有権、地上権又は永小作権を取得した者をいい(民法378条)、抵当権者に対抗できる者に限られるから、登記をしていなければならない。しかし、これらの権利について仮登記をしている者があるときは、その者は通知を受けた後本登記をした上ででき除(同法378条)ができるので、その者に対しても、抵当権実行の旨の通知をするものとする。
2 抵当権実行の旨の通知をした後において、第三取得者から権利を承継した者が生じた場合又は新たに第三取得者が生じた場合には、それらの者には改めて通知をする必要がない(昭和4.11.20大決、昭和7.5.23大決)。
なお、上記の場合においては、第三取得者ができ除ができる期間内に限り、新たな第三取得者もでき除ができる(民法382条3項)。
3 抵当権実行の旨の通知は、登記簿記載の第三取得者の住所あてにすれば足り、その通知が到達しなかった場合において、通常到達したと認められる時から1月内に、第三取得者から債務の弁済又はてき除の通知を受けないときは、民法第387条((抵当権者の競売請求))の規定による競売の請求をすることができる(昭和6.12.11大決)。
(実行の要件の特例)
14 次に掲げる財産については、抵当権の実行ができる場合として、それぞれ次に掲げる特別の規定がある。
(1) 自動車 自動車抵当法第17条第1項及び第2項((抵当権の実行))
(2) 航空機 航空機抵当法第20条第1項及び第2項((抵当権の実行))
(3) 鉱業財団 鉱業抵当法第4条第2項及び第3項((採掘権の取消通知と抵当権の実行))並びに第5条((採掘権者の廃業通知と抵当権の実行))
(4) 漁業財団 漁業財団抵当法第4条第2項及び第3項((漁業権の取消通知と抵当権の実行))
(5) 道路交通事業財団 道路交通事業抵当法第14条第2項及び第3項((免許の取消し及び失効))
(6) 鉄道財団 鉄道抵当法第22条第1項及び第2項((免許の失効又は取消しと抵当権の実行))
(7) 軌道財団 軌道ノ抵当ニ関スル法律第1条((鉄道抵当法の準用))(鉄道抵当法22条1項、2項参照)
(8) 運河財団 運河法第13条((軌道ノ抵当ニ関スル法律の準用))(鉄道抵当法22条1項、2項参照)
(9) 採掘権 鉱業法第57条第2項((採掘権の取消しと抵当権))及び第58条((採掘権の放棄と抵当権))
(10) 漁業権 漁業法第41条第2項((抵当権者の保護))
(実行の手続)
15 法第22条第3項の規定により質権者又は抵当権者に代位して実行する手続は、質権者又は抵当権者がする実行手続と同様である。この場合においては、次のことに留意する。
(1) 競売申立ての書面には、代位実行の権利を有する者であることの証明書類として、法第22条第4項((質権者への通知))の通知書の謄本と同条第1項及び第2項の規定により徴収すべき国税があることを証する書類を添付する。
(2) 競売の申立ては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(以下「法務大臣の権限法」という。)の規定により法務省の関係部局に依頼して行う。
(滞調法との関係)
16 法第22条第1項の譲渡に係る財産について強制執行又は担保権の実行としての競売(法22条に該当する質権者又は抵当権者の申立てに係るものを除く。)が開始されている場合においても、重ねて法第22条第3項の規定による実行の申立てができる(執行法47条1項、188条等)。また、譲受人の国税により当該財産について滞納処分による差押えがされている場合にも、質権者又は抵当権者に代位して質権又は抵当権の実行の申立てができる(滞調法11条の2,20条等)。 (注) 法第22条第3項の規定による実行の申立てにより執行法等による競売が開始されている場合にも、譲受人の国税を徴収するため差押えをすることができる(滞調法28条の2,35条等)。
(代位実行に係る国税等の優先)
17 法第22条第3項の規定により質権又は抵当権を代位実行した場合のその実行に係る国税は、法第12条((差押先着手による国税の優先))の規定に準じて、その実行手続につき、交付要求をした他の国税又は地方税に、優先して徴収できるものとする(法22条5項、地方税法14条の16第5項)。また、地方税法第14条の16第3項((質権等の実行))の規定により質権又は抵当権の代位実行をした場合のその実行に係る地方税は、法第22条第5項の規定により交付要求をした国税に優先して徴収できるものとする(地方税法14条の6参照)。
質権者等への通知
(徴収の通知)
18 税務署長は、法第22条第1項の規定により納税者の国税を徴収しようとするときは、令第6条第1項各号((徴収の通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により、質権者又は抵当権者に通知しなければならない(法22条4項)。この書面の様式は、別に定めるところによる。
なお、上記のこの書面に記載する「法第22条第1項の規定により徴収しようとする金額」については、「法第22条第2項第1号の金額から第2号の金額を差し引いた金額」と記載するものとする。
(通知の時期)
19 法第22条第4項の通知は、法第22条第3項の規定による質権若しくは抵当権についての代位実行の申立て又は法第22条第5項の規定による執行機関に対する交付要求をする時までに行うものとする。
(質権の処分等があった場合の通知)
20 質権若しくは抵当権の処分(民法375条、361条、398条ノ11等)又は質権付若しくは抵当権付債権の譲渡があり、その旨が付記登記されている場合の法第22条第4項の通知は、付記登記に係る質権者又は抵当権者に対してする。この場合における通知は、登記されている住所又は居所(住所又は居所が登記されている所と異なることを知っているときは、その知れている住所又は居所)あてにするものとする。
交付要求による徴収
(交付要求書)
21 法第22条第5項の規定による交付要求は、令第6条第2項((交付要求の手続))に規定する事項を記載した令第36条第1項((交付要求書の記載事項))の交付要求書(国税徴収法施行規則(以下「規則」という。)3条に規定する別紙第7号書式)により行わなければならない(令6条2項)。
(交付要求ができる時期)
22 法第22条第5項に規定する交付要求は、その相手方執行機関が配当すべき金銭を、法第22条第1項の質権者又は抵当権者に交付する時まですることができる。
(交付要求の通知)
23 法第22条第5項の規定により交付要求をしたときは、法第82条第2項及び第3項((交付要求の手続))の規定に準じて交付要求の通知をすることに取り扱う。この場合においては、次のことに留意する。
(1) 法第82条第2項に準ずる通知は、法第22条第1項の質権者又は抵当権者に対して行う。
(2) 法第22条第5項の規定による交付要求をした旨の通知は、滞納者に対してもすることに取り扱う。
(3) 法第82条第3項に準ずる通知は、強制換価手続の目的財産上の利害関係人に対してするのではなく、法第22条第1項の質権又は抵当権上の利害関係人(例えば、抵当権付債権上に質権を有する者。法55条1号、3号参照)に対して行う。
(4)(1)から(3)までの通知については、令第36条第2項及び第3項((滞納者、質権者等に対する交付要求の通知))並びに第6条第2項((交付要求))に準じて処理する。
(交付要求の解除)
24 交付要求の解除については、法第84条((交付要求の解除))の規定に準じて処理する。
この場合における法第84条第3項に準ずる通知の相手方については、23と同様に取り扱う。
(税務署長が代位実行する場合)
25 税務署長が、法第22条第3項の規定により質権者又は抵当権者に代位して、その質権又は抵当権を実行する場合には、その滞納国税を徴収するため、法第22条第5項の規定による交付要求をする必要がない。
(交付要求先着手による国税又は地方税の優先)
26 法第22条第5項の規定により先にした交付要求に係る国税は、同項の規定又は地方税法第14条の16第5項((担保権付財産が譲渡された場合の地方税の交付要求))の規定により後れてした交付要求に係る国税又は地方税に、優先して徴収できる(法13条)。また、地方税法第14条の16第5項((担保権付財産が譲渡された場合の地方税の交付要求))の規定により先にした交付要求に係る地方税は、法第22条第5項の規定により後れてした交付要求に係る国税に、優先して徴収することができる(地方税法14条の7)。
(納税者の国税と譲受人の国税との関係)
27 法第22条第1項の譲渡に係る財産の権利者の国税及び地方税と同条及び地方税法第14条の16((担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収))の規定により徴収できる国税及び地方税とは、競合関係を生じない。 (注) 納税者の国税は、法第22条の規定により譲受人の国税に優先する質権又は抵当権の被担保債権額につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することになるので、法第12条((差押先着手による国税の優先))及び第13条((交付要求先着手による国税の優先))並びに地方税法第14条の6((差押先着手による地方税の優先))及び第14条の7((交付要求先着手による地方税の優先))の規定が適用されることはない。
第4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整
第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先
担保のための仮登記の優先
(仮登記担保契約)
1 法第23条第1項の「仮登記担保契約」とは、金銭債務を担保するため、その不履行があるときは債権者に債務者又は第三者に属する所有権その他の権利の移転等をすることを目的としてされた代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約で、その契約による権利について仮登記のできるものをいう(仮登記担保契約に関する法律(以下「仮登記担保法」という。)1条)。
(担保のための仮登記)
2 法第23条第1項の「担保のための仮登記」とは、仮登記担保契約で、土地又は建物の所有権又はその所有権以外の権利(先取特権、質権、抵当権及び企業担保権を除く。)の取得を目的とするものに基づく仮登記をいう(仮登記担保法1条、20条参照)。 (注) 仮登記担保契約の目的となる権利としては、土地又は建物の所有権、不動産登記法第1条(登記事項)に掲げる地上権、永小作権、地役権、賃借権及び採石権(同法2条)、立木法上の立木の所有権(同法2条)、船舶の所有権及び賃借権(商法686条、687条、船舶登記規則1条)、航空機の所有権(航空法3条の3、航空機登録令26条)、工場財団(工場抵当法14条)、鉱業財団(鉱業抵当法3条)、漁業財団(漁業財団抵当法6条)、港湾運送事業財団(港湾運送事業法26条)、道路交通事業財団(道路交通事業抵当法8条)及び観光施設財団(観光施設財団抵当法8条)の所有権、建設機械の所有権(建設機械抵当法7条、建設機械登録令9条)、ダム使用権(特定多目的ダム法20条、26条、ダム使用権登録令3条)、特許権(特許法27条、66条、98条、特許登録令2条)、実用新案権(実用新案法14条、26条、49条、実用新案登録令2条)、意匠権(意匠法20条、36条、61条、意匠登録令2条)、商標権(商標法6条、35条、71条、商標登録令2条)、漁業権(漁業法23条、50条、漁業登録令27条)及び入漁権(漁業法43条、50条、漁業登録令27条)がある。
(担保のための仮登記がされている場合)
3 法第23条第1項の「仮登記担保契約に関する法律第1条に規定する仮登記担保契約に基づく仮登記又は仮登録(以下「担保のための仮登記」という。)がされているとき」には、納税者に対する債権について納税者の財産の上に担保のための仮登記がされている場合のほか、納税者以外の者に対する債権について納税者の財産の上に担保のための仮登記がされている場合(納税者が物上保証人となっている場合)も含まれる。 (注) 債務不履行を停止条件とする代物弁済契約に基づく権利移転請求権保全の仮登記、代物弁済の予約に基づく権利移転請求権保全の仮登記、債務不履行を停止条件とする賃借権、地上権等の設定請求権保全の仮登記等実質的な意味で金銭債権担保の機能を果たしている仮登記は、担保のための仮登記に当たるものとする。
(法定納期限等以前にされている担保のための仮登記)
4 法第23条第1項の「法定納期限等以前」には、その法定納期限等に当たる日を含む。したがって、その日にされた担保のための仮登記も、法定納期限等以前にされた担保のための仮登記となる。
債権額の範囲
(担保のための仮登記の目的物の価額)
5 法第23条第1項の「換価代金」には、担保のための仮登記がされた財産のほか、従物、付加物等担保のための仮登記の効力の及んでいるものの換価代金も含まれる。
(担保のための仮登記によって担保される債権額)
6 担保のための仮登記によって担保される債権額の範囲については、次のことに留意する。
(1) 担保のための仮登記がされている財産につき強制換価手続が行われた場合において、その担保のための仮登記の権利者(以下「仮登記担保権者」という。)が、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の2年分についてのみ権利を行使することができる(仮登記担保法13条2項)。また、仮登記担保権者が債務の不履行により生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合においても、その最後の2年分について権利を行使することができる(同法13条3項本文)。ただし、利息その他の定期金と通算して2年分を超えることができない(同項ただし書)。
(2) 仮登記担保権者が、担保のための仮登記の実行の通知に基づき、その財産を取得する場合には、仮登記担保法第13条第2項及び第3項(20条において準用する場合を含む。)は適用されないから、利息その他の定期金は2年分に限定されない。
担保のための仮登記がある財産の差押え
(清算期間の経過前にされた本登記の効力)
7 清算期間の経過前に、仮登記担保権者のために担保のための仮登記に基づく本登記がされていても、その所有権等の移転の効力は生じない(仮登記担保法2条1項参照)から、この場合には、債務者である滞納者に代位しその本登記を抹消の上、担保のための仮登記がされている財産を差し押さえることができる。 (注) 清算期間とは、仮登記担保権者が仮登記担保契約によって財産を取得しようとする場合に行う清算金(仮登記担保法3条1項に規定する清算金をいう。)に係る見積額の通知書が、その契約の相手方である債務者又は第三者に到達した日から2月の期間をいう(同法2条1項参照)。
(清算期間の経過前にされた清算金の支払と財産の差押え)
8 清算期間を経過しなければ、担保のための仮登記がされた財産の権利移転の効力は生じない(仮登記担保法2条1項、20条)から、清算期間の経過前においては、清算金の支払がされても、その財産の差押えができる。
清算金の支払請求権に対して物上代位権の行使があった場合の優先
(清算金)
9 法第23条第2項の「清算金」とは、清算期間が経過した時における担保のための仮登記がある財産の価額から、その時の債権及び債務者又は第三者が負担すべき費用で仮登記担保権者が代わって負担したものの額(仮登記担保法2条2項参照)とを控除した額に相当する金銭をいう。
(物上代位)
10 仮登記担保法第4条第1項に規定する物上代位とは、担保のための仮登記がされている場合において、その仮登記後に登記がされた先取特権、質権又は抵当権を有する者が、債務者又は第三者の清算金の支払請求権を差し押さえることにより、先取特権等の効力をその順位に従って清算金の支払請求権に及ぼすことができることをいう。
なお、担保のための仮登記後にされた担保のための仮登記の権利者の物上代位についても同様である(仮登記担保法4条2項、3項)。
(物上代位権の行使があった場合の債権額の範囲)
11 物上代位権の行使に係る担保権によって担保される債権が弁済を受けることのできる金額の範囲は、担保のための仮登記がされた財産の換価代金から配当を受け得る場合と同様に、元本のほか最後の2年分の利息又は損害賠償債権等の金額に限られる(仮登記担保法4条3項、20条、民法374条等)。
清算金の支払請求権の差押え
(清算金の支払請求権者)
12 清算金の支払請求権を有する者は、担保のための仮登記がされた財産が譲渡された場合においても、仮登記担保契約の相手方である債務者又は第三者である(仮登記担保法3条1項、20条)。
(差し押さえることができる清算金支払請求権の範囲)
13 差し押さえることができる清算金の支払請求権(供託金の還付請求権を含む。以下14から16までにおいて同じ。)は、仮登記担保権者が行った担保のための仮登記の実行の通知に係る清算金の見積額の範囲内に限られない。したがって、通知した清算金の見積額が過少であると認められるときは、正当な清算金の額に達するまで差し押さえることができる。
(差押えをすることができる時期)
14 清算金の支払請求権に対する差押えは、仮登記担保権者が仮登記担保権の実行の通知をした後清算金の支払又は供託をするまでの間は、することができる。
(物上代位権者への差押えの通知)
15 清算金の支払請求権について差押え又は交付要求をした場合において、既に、その清算金の支払請求権に対する物上代位権の行使(仮登記担保法4条1項又は2項(物上代位)に規定する権利の行使をいう。)による差押えをした者があるときは、その者に対して書面により差押え(法55条)又は交付要求(法82条3項)の通知をするものとする。この場合の書面は、別に定めるところによる。
(受戻権の行使と清算金の支払請求権に対する滞納処分との関係)
16 清算金の支払請求権を差し押さえた場合において、仮登記担保権者が、清算期間経過後、清算金を差押債権者に支払又は供託する以前に、債務者又は第三者が、債権等の額(債権が消滅しなかったものとすれば債務者が支払うべき債権等の額をいう。)に相当する金銭(9参照)を仮登記担保権者に提供して、担保のための仮登記がされた財産の受戻権を行使したとき(仮登記担保法11条本文)は、清算金の支払請求権に対する差押えの効力は失われる。 (注) 受戻権とは、債務者又は第三者が、仮登記担保権者から清算金の支払債務の弁済を受けるまで、債権等の額に相当する金銭を仮登記担保権者に提供して、担保のための仮登記がされている財産の受戻しを請求することができる権利をいう。
根担保仮登記の効力
17 仮登記担保契約で消滅すべき金銭債務がその契約の時に特定されていないものに基づく仮登記は、強制換価手続においてはその効力を有しない(法23条4項、仮登記担保法14条、20条)ので、国税の徴収との関係においては、担保のための仮登記によって担保される債権が存在しないものとして取り扱われることになる。
第24条関係 譲渡担保権者の物的納税責任
譲渡担保財産からの徴収
(譲渡担保財産)
1 法第24条の「譲渡担保財産」とは、納税者がその所有する財産を債権者又は第三者に譲渡し、その譲渡により、自己又は第三者の債務の担保の目的となっている財産をいう(昭和5.10.8大判参照)。
なお、動産、有価証券、債権、不動産、無体財産権等のほか、法律上まだ権利と認められていないものであっても、譲渡できるもの(手形を除く。法附則5条4項)は、すべて譲渡担保の目的物とすることができる。 (注)1 譲渡担保設定契約には、次のようなものがある(昭和8.4.26大判参照)。 (1) 債権の担保の目的をもって担保の目的物を債権者に譲渡し、その担保に係る債務を履行した場合には債務者がその目的物の返還を受け、不履行の場合には債権者がその財産を換価して優先弁済を受けるか又はその財産を確定的に取得することができる旨の譲渡担保設定契約
(2) 担保のための権利の移転につき売買の形式をとるもので、売主が将来対価を支払って目的物を売主に買い戻す権利を留保した売買(買戻約款付売買)の形式をとる譲渡担保設定契約又は売却した目的物につき売主が将来予約完結権を行使することによって再度売買契約が成立し、その効果としてその目的物が再び売主に戻る旨の予約(再売買の予約)の形式をとる譲渡担保設定契約
2 債務不履行の場合には、譲渡担保財産を確定的に取得することができる旨の特約があっても、債務者が債務の履行をしないときは、債権者は譲渡担保財産を換価又はこれを評価した価額から債権額を控除し、残額を債務者に支払わなければならない(昭和46.3.25最高判)。
3 債務者は、弁済期を経過しても、帰属清算型(債権者が自らその目的物の帰属主体となり、その価額を適正に評価して差額を債務者に支払うもの)の譲渡担保の場合は、債権者がその実行をしない間は、元利金を弁済して譲渡担保財産を受け戻すことができる(昭和47.11.24最高判)。また、処分清算型(債権者が目的物を第三者に処分して、その換価代金のなかから元利金を差し引いた残額を債務者に支払うもの)の譲渡担保の場合においても、債権者が譲渡担保財産を換価するまでは(対抗要件として登記を必要とするものについては、第三者への移転登記をするまでの間をいう。昭和50.11.28最高判参照)、同様である(昭和43.3.7最高判)。
(国税に不足すると認められるとき)
2 法第24条第1項の「国税に不足すると認められるとき」とは、第22条関係4と同様である。
ただし、不足するかどうかの判定は、法第24条第2項の告知書を発する時の現況によるものとする。 (注) 譲渡担保財産上に滞納者が有する法第25条第1項((譲渡担保財産の換価の特例))の買戻権の登記等に係る権利がある場合には、その権利の価額と滞納者の有する滞納処分ができる他の財産との価額の合計により、上記の不足するかどうかの判定をする。
(譲渡担保権者に対する告知)
3 税務署長が、法第24条第2項前段の規定により譲渡担保権者に対してする告知は、令第8条第1項各号((告知書の記載事項))に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第1号書式の告知書により行う。
(徴収することができる金額)
4 譲渡担保財産から徴収することができる金額は、法第24条第1項及び第6項の規定の要件に該当することにより徴収することができる滞納国税(令8条1項2号参照)の全額であって、納税者の財産が徴収すべき滞納国税に不足すると認められる場合のその不足額に限られない。
(税務署長等に対する通知)
5 法第24条第2項後段の規定により、譲渡担保権者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)の所在地を所轄する税務署長及び納税者に対してする通知は、令第8条第2項各号((通知書に記載すべき事項))に掲げる事項を記載した書面により行う。この書面の様式は、別に定めるところによる。
譲渡担保財産に対する滞納処分
(10日を経過した日)
6 法第24条第3項の「告知書を発した日から10日を経過した日まで」とは、告知書を発した日を第1日として12日目の日までをいう(通則法10条1項1号参照)。
(注) 法第24条第3項の「発した日」については、第15条関係1の(2)の(注)と同様である。
(完納されていないとき)
7 法第24条第3項の「完納されていないとき」とは、納税者又は第三者(譲渡担保権者を含む。)の納付又は充当による完納がされていない場合のほか、免除、賦課の取消し等により徴収しようとする金額に係る納税者の国税の全額が消滅していないときをいう。
(みなし第二次納税義務者)
8 法第24条第3項の「第二次納税義務者とみなして」とは、譲渡担保財産に対する滞納処分の執行に限り、第二次納税義務者とみなすだけではなく、法の他の規定(法10章の規定を除く。)の適用についても第二次納税義務者とみなされることをいう(法24条7項参照)。
(譲渡担保財産からの徴収)
9 譲渡担保権者は、納税者の国税についての納付義務を負うものではないから、次の規定は、譲渡担保財産からの徴収については適用されない。
(1) 法第32条(3項から5項までを除く。)から第39条まで及び第41条第2項((第二次納税義務の通則等))
(2) 法第151条から第159条まで((滞納処分に関する猶予及び停止等))
(3) 通則法第4章第1節((納税の猶予))及び第55条((納付委託))
(督促の不要)
10 法第24条第2項の告知書を発した日から10日を経過した日までに告知書により告知した徴収しようとする金額が完納されていないときは、督促(納付催告書による督促を含む。)を要せず、直ちに滞納処分をすることができる。
(差押えの繰上げ)
11 通則法第38条第1項((繰上請求))の規定の準用に当たっては、同項の「納付すべき税額の確定した国税」は「法第24条第2項の告知をした徴収しようとする金額」を、また通則法第38条第1項の「納期限」は「法第24条第2項の告知書を発した日から10日を経過した日」を、それぞれいうものとする。
(納税者等が占有する譲渡担保財産に対する差押え等)
12 譲渡担保財産につき滞納処分を執行する場合において、当該譲渡担保財産を納税者又はその者の特殊関係者(令13条1項各号参照)が占有しているときは、法第58条((第三者が占有する動産等の差押手続))及び第59条((引渡命令を受けた第三者等の権利の保護))の規定(法71条4項等において準用する場合を含む。)は、適用されない(令24条4項、6項)。
(保険に付されている譲渡担保財産に対する差押えの効力)
13 譲渡担保財産を差し押さえた場合に、その財産が、譲渡担保権者を受取人とする法第53条第1項((保険に付されている財産に対する差押えの効力))の損害保険に付され又は共済の目的となっているときは、同項の規定が適用されるから、その財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知する。この通知については、第53条関係13に準じて行うものとする。 (注) 譲渡担保財産を差し押さえる前にその財産が火災その他により滅失等をし、これに基因して譲渡担保権者が保険金、共済金又は補償金を受領できる場合においては、それらに係る請求権等を譲渡担保財産として、法第24条の規定を適用することができる。
(譲渡担保財産の範囲)
14 法第24条第3項の規定により滞納処分ができる譲渡担保財産の範囲は、おおむね、次に掲げるとおりとする。
(1) 譲渡担保財産の付加物及び従物 (注) 付加物及び従物が除外される場合は、次に掲げる場合である。 1 設定行為に別段の定めがあったとき(民法370条ただし書参照)。
2 民法第424条((詐害行為取消権))の規定により、債権者が、債務者の行為を取り消すことができるとき(同法370条ただし書参照)。
3 納税者及び譲渡担保権者以外の第三者が、権原によりその財産につき付加行為をしたとき(民法242条ただし書、大正6.4.12大判)。
(2) 企業用動産等を一括して譲渡担保とした場合においては、集合物としての同一性のある限り、その譲渡担保権の設定後その集合物に加えられたもの(昭和30.12.6大阪地判)
(譲渡担保財産の譲渡の場合)
15 譲渡担保財産が譲渡担保権者から更に譲渡された場合において、その譲渡が法第24条第3項又は第4項の規定による差押え後にされたものであるときは、その差押えに係る滞納処分の続行ができる。
(第1項の要件に該当する場合)
16 法第24条第4項の「同項の要件に該当する場合」とは、次の要件を満たしている場合の納税者の国税に係る差押えをいう。
(1) 納税者が譲渡した財産で、その譲渡により担保の目的となっている財産があること。
(2) 納税者の財産につき滞納処分を執行しても、なお徴収すべき国税に不足すると認められること。
(3) 差押えに係る国税の法定納期限等が、その譲渡担保の譲渡に係る権利の移転の登記時前にあること(譲渡担保権者が法24条6項に規定する証明ができなかったときを含む。)。
(交付要求等をした場合の効力)
17 譲渡担保財産を法第24条第1項の納税者の財産としてした参加差押え又は交付要求については、次に掲げるところによる。
なお、参加差押え又は交付要求が有効である場合は、法第24条第4項後段に規定する告知及び通知をしなければならない。
(1) 参加差押え又は交付要求をした相手先の差押えが、法第24条第4項の規定に基づき、同条第3項の規定による差押えとして滞納処分を続行することができる場合には、同条の規定により譲渡担保財産から徴収することができる国税に係る参加差押え又は交付要求である場合に限り有効である。
(2) 参加差押え又は交付要求をした相手先の差押えが、法第24条第1項の要件を満たさないことにより同条第4項の規定の適用を受けないものであるときは、その差押えは取り消されるので、交付要求は効力を失うことになるが、参加差押えが法第24条第4項の規定によるものであるときは有効な差押えとなる。
(3) 法第24条第1項の要件を満たさないことにより同条の規定が適用されない国税に係る参加差押え又は交付要求は、同条第4項の規定が適用されず、取り消されるべきものである。
抵当権等との関係
(譲渡前に譲渡担保財産上に抵当権等がある場合)
18 質権、抵当権、先取特権等がある財産が譲渡され、その譲渡に係る譲渡担保財産が、強制換価手続により換価された場合の法第24条第1項の規定によりその譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税と、譲渡担保権者の国税及びその抵当権等の被担保債権との優先関係については、次に掲げるところによる。
(1) 納税者の国税と抵当権等の被担保債権との関係 イ 法第24条第1項の規定により譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税の法定納期限等は、法第15条第1項第6号((告知に係る法定納期限等))の規定により、法第24条第2項の告知書を発した日となるので、抵当権等の被担保債権は、原則としてその納税者の国税に優先する(法15条、16条、19条、20条)。
ロ 法第22条((担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収))の規定により、その登記された質権又は抵当権の被担保債権につき配当を受けるべき金額から納税者の国税を徴収できるときは、同条に規定する手続によりその国税を徴収することができる。
(2) 譲渡担保権者の国税と抵当権等の被担保債権との関係
抵当権等の被担保債権は、原則として譲渡担保権者の国税に優先する(法17条、19条、20条)。
(3) 納税者の国税と譲渡担保権者の国税との関係
法第24条第1項の規定により譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税は、譲渡担保権者の国税の法定納期限等とは関係なく、原則として、譲渡担保権者の国税に優先する(令9条)。 (注) 譲渡担保権者の国税が法第14条((担保を徴した国税の優先))の規定に該当する場合には、納税者の国税は譲渡担保権者の国税に劣後する。
(4) 納税者の国税と譲渡担保権者の国税と抵当権等の被担保債権との関係
原則として、まず第1に抵当権等の被担保債権に、第2に法第24条第1項の規定により譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税に、第3に譲渡担保権者の固有の国税に、それぞれ充てる。この場合に、第2の国税が満足を受けず、かつ、法第22条((担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収))の規定に該当するときは、上記(1)のロにより、その満足を受けない部分につき、第1の債権者が受ける金額からその国税を徴収する。
(譲渡後に譲渡担保財産に設定した抵当権等がある場合)
19 納税者の財産が担保の目的で譲渡され、その譲渡に係る譲渡担保財産に抵当権その他の担保権の設定等があった後、その財産が強制換価手続により換価された場合の法第24条第1項の規定によりその譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税と譲渡担保権者の国税と抵当権等の被担保債権との優先関係については、次による。
(1) 納税者の国税と抵当権等の被担保債権との関係
法第24条第1項の規定により譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税の法定納期限等は、法第15条第1項第6号の規定により、法第24条第2項の告知書を発した日となるので、その日と抵当権の設定等の日とを比較し、法第15条、第16条又は第18条から第20条まで((法定納期限等以前に設定された質権等の優先))の規定によりその優劣が定められる。
(2) 譲渡担保権者の国税と抵当権等の被担保債権との関係
譲渡担保権者の国税の法定納期限等と抵当権の設定等の日とを比較し、法第15条、第16条又は第18条から第20条まで((法定納期限等以前に設定された質権等の優先))の規定によりその優劣が定められる。
(3) 納税者の国税と譲渡担保権者の国税との関係
法第24条第1項の規定により譲渡担保財産から徴収できる納税者の国税は、原則として譲渡担保権者の国税に優先する(令9条)。 (注) 譲渡担保権者の国税が法第14条((担保を徴した国税の優先))の規定に該当する場合には、納税者の国税は譲渡担保権者の国税に劣後する。
(4) 納税者の国税と譲渡担保権者の国税と抵当権等の被担保債権との関係
(1)から(3)までによって優先関係を定めるが、なお定まらない場合には、法第26条((国税及び地方税等と私債権との競合の調整))の規定によって優先関係を定める。
(譲渡担保財産上に譲渡前後に抵当権等がある場合の抵当権等と納税者の国税と譲渡担保権者の国税との関係)
20 譲渡が仮にないとした場合において、納税者の国税(7万円)に劣後する抵当権(甲8万円)がその譲渡担保財産上にあり、その譲渡後その財産上に納税者の国税に優先し、譲渡担保権者の国税(4万円)に劣後する抵当権(乙3万円)が設定された場合において、その譲渡担保財産を譲渡担保権者の国税で換価し、その換価代金(13万円)を配当する場合の配当額は、次のようになる。
(1) 一次的の配当金額は、法第17条((譲受前に設定された質権又は抵当権の優先))の規定により甲抵当権に8万円、法第16条((法定納期限等以前に設定された抵当権の優先))の規定により譲渡担保権者の国税に4万円、乙抵当権に1万円となる。 (注) 納税者の国税は、乙抵当権の設定がその国税の法定納期限等(法15条1項6号)以前であることから、乙抵当権には劣後する。したがって、換価代金が13万円であることから、納税者の国税には配当はない。
(2) 納税者の国税は、令第9条((譲渡担保財産から徴収する国税及び地方税の調整の特例))の規定により譲渡担保権者の国税に先立って徴収するから、(1)による譲渡担保権者の国税の配当金額4万円は、その全額が納税者の国税に配当すべき金額となる。
(3) 納税者の国税は、(2)によっても徴収できない金額3万円(納税者の国税7万円-(2)の配当を受けた金額4万円)につき、法第22条((担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収))の規定により徴収できる範囲の金額2万円を、(1)による甲抵当権者の配当を受けるべき金額8万円から徴収できるので、納税者の国税は、更に2万円の配当を受ける。
(4)(1)から(3)までにより、甲抵当権に6万円、納税者の国税に6万円、乙抵当権に1万円の配当となる。
(第4項の規定の適用を受ける差押え)
21 法第24条第5項の「前項の規定の適用を受ける差押」とは、譲渡担保財産を納税者の財産としてした差押えであって、かつ、法第24条第1項及び第6項の要件に該当する差押えをいう。この場合には、法第24条第4項後段の規定に基づく第2項の告知及び通知をしていることは必要でない。
(その他弁済以外の理由)
22 法第24条第5項の「その他弁済以外の理由」とは、譲渡担保財産により担保される債権が消滅する場合において、譲渡担保財産が納税者に復帰しないこととなる場合のものをいう。したがって、相殺(民法505条)、免除(同法519条)、混同(同法520条)、消滅時効の完成(同法166条以下)等により、譲渡担保財産により担保される債権が消滅した場合は、これに該当しない。
(期限の経過)
23 法第24条第5項の「期限の経過」とは、それによって納税者が譲渡担保財産を自己に復帰させることを請求できないこととなる期限の経過をいう。なお、次のことに留意する。
(1) 買戻約款付売買の場合
買戻約款付売買契約において定められている買戻しができる期間は、民法第579条((買戻し特約))に規定する買戻権については次のとおりであり、その他の買戻約款付売買については契約に定められている期間による(昭和9.8.3大判、大正8.11.10東京地判、昭和8.4.26大判)。 イ 買戻しの期間は、10年を超えることができず、これより長い期間を定めたときは10年に短縮される(民法580条1項)。
ロ 買戻期間を定めたときは、その後この期間を伸長することができない(民法580条2項)。
ハ 買戻期間を定めないときは、5年内に限り買戻権の実行ができる(民法580条3項)。
(2) 再売買の予約の場合
再売買の予約による予約期間は、その契約の定めるところによるが、その期間の定めがない場合には、予約完結権はそれを行使できるときから20年間で消滅時効にかかる。
(契約の履行以外の理由)
24 法第24条第5項の「その他その契約の履行以外の理由」とは、納税者が譲渡担保財産を自己に復帰させることを請求できる権利が消滅することとなる理由のうち、期限の経過及びその契約の履行以外の理由をいい、買戻権又は再売買の予約の完結権の消滅時効の完成等がこれに該当する。
(第5項の適用がない場合)
25 法第24条第5項の規定により、譲渡担保財産として存続するものとみなして法第24条第3項の規定を適用できる場合であっても、法第24条第3項の差押え前に、譲渡担保財産が譲渡担保権者から更に譲渡された場合には、法第24条第5項の規定によって譲渡担保財産として存続するものとみなすことはできない(15参照)。
(譲渡担保財産が納税者に復帰した場合)
26 譲渡担保財産につき法第24条第3項の差押えをした後、その譲渡担保財産が納税者に復帰した場合には、その差押えは、納税者の財産としてした差押えとして、滞納処分の続行ができるものとする。この場合には、税務署長は、遅滞なく、譲渡担保権者及び納税者にその旨を通知するものとする。この通知は、原則として別に定める書面により行うものとする。
証 明
(譲渡に係る権利の移転の登記がある場合)
27 担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記が国税の法定納期限等以前にあることについては、徴収職員が調査の上確認しなければならない。
(譲渡に係る権利の移転の登記がない場合)
28 譲渡担保財産が権利移転の登記の制度がないものであるときは、譲渡担保権者が国税の法定納期限等以前に譲渡担保財産となっている事実を、その財産の売却決定の日の前日(譲渡担保財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、その取立ての日の前日)までに証明しなければ、法第24条第1項の規定が適用される(法24条6項、令8条3項後段)。この場合の証明手続については、第15条関係25に準ずる(令8条3項前段、4条1項、2項)。 (注) 上記の場合の証明の期限については、通則法第10条第2項((期限の特例))の規定の適用がない(通則令2条7号)。
(法定納期限等以前)
29 法第24条第6項の「法定納期限等以前」には、その法定納期限等に当たる日を含む。したがって、その日に設定された譲渡担保も、法定納期限等以前に設定された譲渡担保となる。
(譲渡担保財産が集合物である場合)
30 集合物が譲渡担保財産である場合において、その担保権設定後その集合物に財産を加えたときにおける法第24条第6項の規定の適用に当たっては、その加えられた財産が集合物として同一性がある限り、当初の譲渡担保設定のための譲渡の時期をもって、その財産の譲渡担保財産となった時として取り扱う。 (注)1 構成部分の変動する集合動産についても、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、1個の集合物として譲渡担保の目的となり得る(昭和54.2.15最高判)。
この集合物としての譲渡担保が認められたものとしては、特定の倉庫に存する商品の全部(昭和30.12.6大阪地判)、自社の出版物の全部(昭和32.3.19東京地判)、特定の店舗に存する一切の什器、備品、商品(昭和47.3.29東京高判)等がある。
2 譲渡担保設定後その集合物に新たに財産が加えられたため、その譲渡担保財産の価額が、当初の譲渡担保財産の価額を超える場合には、その超えている部分に相当する財産については、譲渡担保を新たに設定したものとして取り扱う。
(譲渡担保財産が有価証券である場合)
31 有価証券が譲渡担保財産である場合において、その担保権設定後、その有価証券につき、有価証券による担保の差換えをしたときにおける法第24条第6項の規定の適用に当たっては、その差し換えた有価証券が譲渡担保財産として同一性がある限り、当初の譲渡担保設定のための譲渡の時期をもって、その有価証券の譲渡担保財産となった時として取り扱う。
譲渡担保権者が破産した場合
32 法第24条第3項又は第4項の規定による差押えをした後、譲渡担保権者について破産宣告があった場合には、滞納処分の続行ができる(第47条関係40,41参照)。
なお、譲渡担保権者が破産した場合には、その譲渡担保財産は破産財団を構成するものとなり、納税者はそれを取り戻すことができないが(破産法88条)、損害賠償請求権を取得し(民法415条後段)、その債権と譲渡担保財産により担保される債権とを相殺することができる(破産法104条4号ただし書)。
第25条関係 譲渡担保財産の換価の特例等
一括換価
(意義)
1 法第25条第1項の「一括して換価する」とは、法第24条第3項後段((第二次納税義務の通則に関する規定等の準用))において準用する第32条第4項((第二次納税義務者の財産の換価の順序))の規定にかかわらず、滞納者の財産である差押えをした買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記その他これに類する登記(以下第25条関係において「買戻権の登記等」という。)に係る権利と、法第24条第3項((譲渡担保財産に対する滞納処分))又は第4項((納税者の財産としてした譲渡担保財産に対する差押えの効力))の規定により差し押さえた譲渡担保財産を、一体のものとして換価することをいう。
(残余を交付すべき者)
2 法第25条第1項の規定により一括換価をした場合には、まず滞納者の財産である買戻権の登記等に係る権利を換価し、その後に譲渡担保財産を換価したものとして配当するものとし、配当した金銭に残余があるときは、その残余を譲渡担保権者に交付するものとする。ただし、その残余が譲渡担保財産の価額に相当する部分を超えるときは、その超える部分の残余は滞納者に交付するものとする。
(買戻権等に対抗できない担保権等の消滅)
3 法第25条第1項の規定による一括換価をした場合には、買戻権の登記等に係る権利に対抗できない担保権、用益物権、賃借権等の権利は、実体的に消滅するものとして換価する(第89条関係9参照)。
第5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整
趣旨及び法第26条の類推適用
1 法第26条は、強制換価手続において国税が他の国税、地方税又は公課(以下第26条関係において「地方税等」という。)及びその他の債権(以下第26条関係において「私債権」という。)と競合する場合において、国税と私債権の間の優先順位、地方税等とその私債権の間の優先順位及びその国税と地方税等の間の優先順位が交錯することによって、これら三者の優先順位を定めることができないとき(この場合の競合を「特殊な競合」という。以下第26条関係において同じ。)の具体的な配当の方法を定めたものである。
なお、上記以外の場合で、国税、地方税等及び私債権が競合し、これらの債権間の優先順位が交錯してその順位を定めることができないときは(第17条関係7、第18条関係6、法19条、20条等参照)、法第26条の規定を類推適用するものとする。 〔例〕 抵当権の被担保債権額(設定登記昭和57. 6.30)・・・・・・・10万円
差押国税 (法定納期限等昭和57. 7.31)・・・・・・・・・・・5万円
交付要求地方税 (法定納期限等昭和57. 4.30)・・・・・・・・・・3万円
滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
換価代金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17万円
※配当額の計算 イ まず、法第26条第1号の規定により、滞納処分費の1万円に充てる。
ロ 次に、法第26条第2号の規定により、抵当権設定の登記及び国税、地方税の法定納期限等の古い順に従って、国税及び地方税並びに私債権に充てるべき金額の総額を定めると、(1)交付要求地方税3万円、(2)抵当権10万円、(3)差押国税3万円となり、私債権の総額は10万円、国税及び地方税の総額は6万円となる。
ハ 次に、法第26条第3号の規定により、国税及び地方税に充てるべき金額は、法第12条((差押先着手による国税の優先))の規定により、差押国税5万円、交付要求地方税1万円となる。
ニ 法第26条第4号の規定により抵当権に10万円充てる。
ホ 上記の結果、配当額は次のとおりになる。 滞納処分費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
抵当権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
差押国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
交付要求地方税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1万円
特殊な競合の原因となる規定
2 法第26条本文の「この章又は地方税法その他の法律の規定」とは、特殊な競合の直接の原因となる国税と地方税等との優先順位を定める規定(例えば、法8条、12条、13条、14条、令9条、これらに相当する地方税法14条、14条の6から14条の8までの規定、船員保険法13条の規定等公課の優先順位に関する規定等)並びに国税と私債権との優先順位を定める規定及び地方税等と私債権の優先順位を定める規定(例えば、法8条、15条、16条、20条、地方税法14条、14条の9,14条の1O,14条の14、船員保険法14条の規定等)をいい、私債権間の優先順位を定める規定及び法第26条第1号に規定する規定は、含まれない。
道府県たばこ税等の優先
3 法第26条第1号の「これに相当する優先権を有する地方税」とは、地方税法第13条の3((強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収))の規定により徴収する道府県たばこ税、市町村たばこ税、軽油引取税及び自治大臣の指定する法定外普通税(同法4条1項、3項、5条1項、3項参照)をいう。 〔参考〕 地方税法第14条の5((地方団体の徴収金のうちの優先順位))の規定は、同条の延滞金等と地方税間の内部的な徴収の順位を定めたものである。
質権等の設定等の時期
4 法第26条第2号の「設定、登記、譲渡若しくは成立の時期」については、次のとおりである。
(1) 「設定」の時期とは、登記することができない質権で有価証券以外のものを目的としているものについては、法第15条第3項((みなし質権設定日))又は地方税法第14条の9第4項((みなし質権設定日))の規定によりその質権が設定されたものとみなされた日をいい(第15条関係28参照)、登記することができない質権で有価証券を目的とするものについては、法第15条第2項前段((証明))又は地方税法第14条の9第3項((証明))の証明をした場合の占有した日をいう。
(2) 「登記」の時期とは、登記をすることができる質権、抵当権及び法第20条第1項第2号から第4号まで((不動産売買の先取特権等))に掲げる先取特権及び担保のための仮登記について、これらに係る設定又は保存の登記の日をいう(第15条関係30、33、第16条関係8、第18条関係15参照)。
(3) 「成立」の時期とは、法第20条第1項第1号((不動産賃貸等の先取特権))に掲げる先取特権について、同条第2項((証明))において準用する法第19条第2項((証明))の証明をした場合の成立の日をいう。
第2号のこの章又は地方税法その他の法律の規定
5 法第26条第2号の「この章又は地方税法その他の法律の規定」とは、法第26条第1号の費用等を除いたものにつき、その国税と私債権の優先順位又はその地方税等と私債権との優先順位を定める規定をいい、国税、地方税及び公課間の優先順位を定める規定並びに私債権間の優先順位を定める規定をいうものではない。
民法その他の法律の規定
6 法第26条第4号の「民法その他の法律の規定」とは、私債権の優先順位を定めるに当たって適用すべき法律の規定をいう。この場合においては、法第15条第4項((証明できなかった質権と他の質権との関係))又は地方税法第14条の9第5項((証明できなかった質権と他の質権との関係))の規定が適用される場合がある。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















