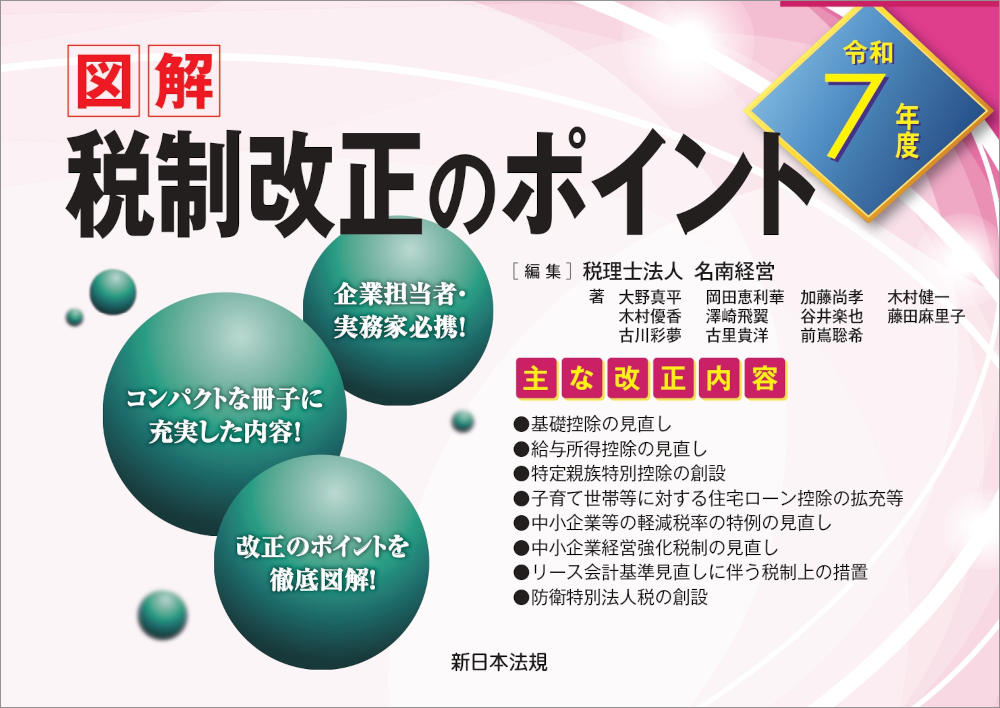資料2004年03月27日 【税務通達等】 国税徴収法基本通達 第3章 第二次納税義務
第3章 第二次納税義務
第32条関係 第二次納税義務の通則
納税義務の成立
1 第二次納税義務は、法第33条から第39条まで又は第41条((無限責任社員等の第二次納税義務))に規定する特定の納税者が国税を滞納し、かつ、それらの条に規定する要件を満たすことによって成立する。
なお、第二次納税義務が成立し、納付通知書による告知をした後にその成立要件となった事実に変更があっても、いったん確定した第二次納税義務には影響がない(昭和47.5.25最高判)。
納付通知書による告知
(告知)
2 法第32条第1項の規定による告知は、抽象的に成立していた第二次納税義務を具体的に確定する効力を有するもので、通則法第36条((納税の告知))の規定による納税の告知と同様の法律的性質を有する(昭和37.3.23大阪地判、昭和42.11.21名古屋地判)。この場合において、その効力は、納付通知書が送達された時に生ずる。 (注)1 納付通知書は、主たる納税者(第二次納税義務の基因となった納税義務を負う者をいう。以下同じ。)に対する督促の有無を問わず発することができる。
2 法第32条第1項の規定による告知は、主たる納税者の国税が滞納になっている間はすることができる(昭和50.8.27最高判参照)。
(納付通知書)
3 法第32条第1項の「納付通知書」とは、令第11条第1項各号(納付通知書の記載事項)に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第1号書式による。
(徴収しようとする金額)
4 納付通知書に記載すべき令第11条第1項第3号((納付通知書に記載すべき事項))の「徴収しようとする金額」については、それぞれ次に掲げる旨を記載するものとする。 (1) 無限責任社員の第二次納税義務(法33条)については、主たる納税者の滞納国税(第二次納税義務の基因となった国税に限る。以下4において同じ。)の全額
(2) 財産等の価額を限度とする第二次納税義務(法34条、35条、36条3号、39条、41条2項)については、その財産等の価額(金額で表示する。)を限度として主たる納税者の滞納国税の全額
(3) 財産を限度とする第二次納税義務(法36条1号、36条2号、37条、38条、41条1項。以下第32条関係において「物的第二次納税義務」という。)については、その財産(財産自体を表示する。)を限度として主たる納税者の滞納国税の全額 (注) 一つの財産が、物的第二次納税義務に係る財産(以下「追及財産」という。)と他の財産とで構成されている場合における納付通知書に記載する「徴収しようとする金額」には、「追及財産が一つの財産に対して占める割合を限度とする」旨付記する(16の(1)参照)。
(滞納処分費との関係)
5 4の「徴収しようとする金額」を第二次納税義務者から徴収するために要した滞納処分費は、その「徴収しようとする金額」のほかに徴収することができる。ただし、物的第二次納税義務の場合には、その財産以外のものからは徴収(任意納付を含まない。)できないものとする。
(納付の期限)
6 法第32条第1項の納付通知書に記載する納付の期限は、納付通知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日としなければならない(令11条4項)。
(第二次納税義務に関する規定)
7 令第11条第1項第4号((納付通知書に記載すべき事項))の「その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定」とは、第二次納税義務者につき適用することとした法第33条、第34条、第35条、第36条第1号、第36条第2号、第36条第3号、第37条、第38条、第39条、第41条第1項又は同条第2項((無限責任社員等の第二次納税義務))の規定をいう。
(納付の手続)
8 第二次納税義務に係る国税は、主たる納税者の国税であることを記載した納付書によって、その第二次納税義務者の名義により納付させるものとする(国税通則法施行規則(以下「通則規則」という。)5条に規定する別紙第1号書式備考9参照)。
(税務署長に対する通知)
9 法第32条第1項後段の規定により、第二次納税義務者の住所又は居所の所在地を管轄する税務署長に対する通知は、令第11条第2項各号((通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により行う。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(納付催告書)
10 「納付催告書」とは、令第11条第1項第1号に掲げる事項及び同項第3号((納付通知書に記載すべき事項))に規定する金額を記載した、規則第3条((書式))に規定する別紙第2号書式による。
(別段の定め)
11 法第32条第2項後段の「国税に関する法律に別段の定めがあるもの」とは、通則法第48条第1項((納税の猶予の効果))の規定により新たに督促ができない場合をいうが、同法第105条第2項((不服申立てがあった場合の徴収の猶予等))の規定による徴収の猶予の場合等も、督促が制限される。
通則法の準用
(繰上請求)
12 法第32条第3項において準用する通則法第38条第1項((繰上請求))の規定は、次のとおり読み替えて準用する。 (1) 「納付すべき税額の確定した国税」は、納付通知書により告知した金額
(2) 「納期限」は、納付通知書に記載された納付の期限
(納税の猶予)
13 法第32条第3項において準用する通則法第46条第1項第1号、第2号((災害に係る納税の猶予の要件))及び通則令第15条第1項((納税の猶予の申請書の記載事項))の規定は、次のとおり読み替えて準用する。
なお、通則法第46条第1項第3号及び第3項((納税の猶予の要件))の規定は、準用されない。 (1) 「納期限」は、納付通知書に記載された納付の期限
(2) 「納付すべき税額の確定したもの」は、納付通知書により告知した金額
(3) 「納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額」は、納付通知書に記載された告知年月日、納付の期限及び納付すべき金額並びに主たる納税者の住所、氏名及び滞納税額の年度、税目、納期限、金額
(換価の制限)
14 法第32条第4項に規定する第二次納税義務者の財産の換価の制限については、次のことに留意する。 (1) 法第32条第4項の「換価に付した」とは、公売期日(随意契約により売却する場合には、その売却する期日)を開いたことをいう。 (注) 公売期日を開いた場合には、入札者の有無を問わず「換価に付した」ことになることに留意する。
(2) 第二次納税義務者の差押財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、法第32条第4項の制限を受けない。しかし、当該差押財産につき、支払命令の申立て、給付の訴えの提起等の強制的な取立ては、やむを得ない場合を除き、行わないものとする。
(3) 主たる納税者の差押財産が金銭による取立ての方法により換価するもので第二次納税義務者の差押財産が換価するものであるときは、法第32条第4項の制限を受けない。
(価額が著しく減少するおそれがあるとき)
15 法第32条第4項の「価額が著しく減少するおそれがあるとき」とは、差押財産を速やかに換価しなければその価額が著しく減少するおそれがあるときをいい、保存費を多額に要する場合を含むものとする。
物的第二次納税義務の特質
16 物的第二次納税義務については、次のことに留意する。 (1) 第二次納税義務者に対する滞納処分は、追及財産以外のものについては、することができない。
なお、追及財産と他の財産とが一つの財産を構成している場合には、その財産について滞納処分をすることができるものとする。この場合において、公売期日等の前日までに、その財産を追及財産と他の財産とに分割し、その旨及び差押えを解除すべき旨の申出があったときは、他の財産の部分について差押えを解除するものとする。 (注) 一つの財産が、追及財産と他の財産とに分割されないまま換価された場合には、換価代金のうち他の財産の部分に相当するものは、滞納者(第二次納税義務者)に交付する(第129条関係6参照)。
(2) 第二次納税義務者が納付する場合には、追及財産の価額にかかわらず、その第二次納税義務の基因となった主たる納税者の滞納国税が存する限り、その金額に相当する第二次納税義務額について納付しなければならない。ただし、法第37条((共同的な事業者の第二次納税義務))又は第38条((事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務))の規定による物的第二次納税義務額について、追及財産の価額に相当する金額を一時に納付した場合で、徴収上弊害がないと認められるときは、その後は、その第二次納税義務額について追及しない取扱いとしても差し支えない。
(3) 第二次納税義務者が過誤納金及びその還付加算金の請求権を有する場合には、その請求権が追及財産であるときを除き、第二次納税義務者の意思に反する充当はしないものとする(通則令22条1項参照)。
主たる納税義務との関係
(財産の差押えの時期)
17 第二次納税義務者の財産は、主たる納税者の財産の差押えに着手する前に差し押さえても差し支えない。
(納税の猶予)
18 主たる納税者の国税について納税の猶予をしている間は、その国税の第二次納税義務について納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることはできないが、第二次納税義務者に対してした納税の猶予は、主たる納税者には効力を及ぼさない。
(換価の猶予)
19 主たる納税者の国税につき換価の猶予をしても、その国税の第二次納税義務について納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることは妨げないが、換価については法第32条第4項の規定による制限がある。
(履行等)
20 第二次納税義務者が、その第二次納税義務を履行した場合には、その第二次納税義務の基因となった主たる納税者の納税義務はその履行した額の範囲内において消滅することはもちろんであるが、主たる納税者がその納税義務の一部を履行した場合においても、なお徴収すべき残額の範囲において、その第二次納税義務者の第二次納税義務は存続する。
なお、過誤納金等(国税に係る過誤納金、国税に関する法律の規定による国税の還付金及びこれらについての還付加算金をいう。以下同じ。)の充当による納税義務の消滅についても、上記と同様である。
(免除)
21 第二次納税義務者に対する第二次納税義務の免除は、主たる納税者に対しては効力を及ぼさないが、主たる納税者に対する納税義務の免除は、その納税義務が第二次納税義務の範囲に含まれている限り、その効力が及ぶ。
(更生手続の開始決定の特則)
22 主たる納税者につき会社更生法による更生手続の開始決定があった場合においても、その者の国税に係る第二次納税義務者に対して滞納処分をすることができる(昭和45.7.16最高判)。
(滞納処分の停止による消滅)
23 第二次納税義務者がその第二次納税義務について滞納処分の停止を受け、法第153条第4項又は第5項((滞納処分の停止に係る納税義務の消滅))の規定によりその第二次納税義務が消滅した場合においても、その効力は、主たる納税者に及ばない(第153条関係7参照)。
(過誤納金の還付)
24 納税者及び第二次納税義務者の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする(通則令22条1項)。
なお、上記による還付又は充当をした場合においては、国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)、税務署長又税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)は、その旨を主たる納税者に通知しなければならない(通則令22条2項)。
(限定承認の効果)
25 主たる納税者の相続人が相続財産について限定承認をした場合においても、その責任は相続財産に限定されるにすぎないものであることから(通則法5条1項後段)、第二次納税義務に係る国税の納付義務の額には増減がない。 (注) 相続人全員が相続の放棄をした場合又は相続人が不存在の場合には、被相続人の国税を徴収するため、相続財産法人(民法951条)を主たる納税者として、被相続人が生存していたときに第二次納税義務者となるべき者に対し、第二次納税義務の追及をすることができる。
(会社更生法による免責の効果)
26 株式会社である主たる納税者が会社更生法第241条((更生債権等の免責等))の規定により国税の納付義務について免責された場合においても、その効力は株式会社の債務を負担する者に対して有する権利には影響を及ぼさないことから(同法240条2項)、第二次納税義務に係る国税の納付義務の額には増減がない。
(第二次納税義務を負うべき者の破産との関係)
27 第二次納税義務を負うべき者が破産宣告を受けた場合において、破産宣告前に第二次納税義務の成立要件を満たしているとき(ただし、徴収すべき額に不足するかどうかの判定については第33条関係1、第22条関係4参照)は、破産宣告後に納付通知書による告知をした第二次納税義務に係る国税は、財団債権(破産法47条2号)になる。
(時効の中断)
28 第二次納税義務の時効中断の効力は、主たる納税者の納税義務には及ばないが、主たる納税者の納税義務の時効中断の効力は、第二次納税義務に及ぶものとする(民法457条1項参照)。 (注) 主たる納税者の納税義務が時効の完成により消滅するおそれがある場合には、その納税義務の存在確認の訴えの提起等時効中断の措置をとることに留意する(昭和39.3.26東京地判、昭和47.10.17静岡地判等)。
この訴訟において国が勝訴した場合には、主たる納税者の国税の徴収権の消滅時効は10年になる(通則法72条3項、民法174条ノ2第1項)。
第二次納税義務の重複賦課
29 第二次納税義務の成立要件を満たす場合において、その基因となった処分等に基づき税務署長又は他の行政機関等が既に第二次納税義務を負わせているときにおいても、重ねて第二次納税義務を負わせることができる(昭和45.7.29東京地判)。
第二次納税義務に係る国税についての第二次納税義務
30 第二次納税義務者がその第二次納税義務に係る国税を滞納した場合において、他に第二次納税義務の成立要件を満たす第三者がいるときは、第二次納税義務者を主たる納税者として、その第三者に対し、更に第二次納税義務を負わせることができる。
なお、第二次納税義務の成立要件との関係から第二次納税義務に係る国税についての第二次納税義務が成立しない場合がある。例えば、特定の国税(実質所得者課税の原則により課された国税等)についてだけ第二次納税義務を追及できることとされている場合においては、第二次納税義務に係る国税は、この特定の国税に該当しない。
第二次納税義務と詐害行為取消権との関係
31 滞納者が行った法律行為が、第二次納税義務の成立要件と詐害行為取消権の要件(通則法42条、民法424条)の双方を満たす場合には、いずれによることもできる。
第33条関係 無限責任社員の第二次納税義務
納税義務の成立
1 法第33条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
納税義務を負う者
(合名会社又は合資会社)
2 法第33条の「合名会社」とは、無限責任社員だけから成る会社をいい(商法80条参照)、「合資会社」とは、有限責任社員(同法157条参照)と無限責任社員とから成る会社をいう(同法146条)。
(社員又は無限責任社員)
3 法第33条の「社員」又は「無限責任社員」とは、会社の債務につき、一定の条件の下に、会社債権者に対し、直接に連帯無限の責任を負担する社員をいう(商法80条、147条)。
(新入社員等の責任)
4 会社が成立した後に無限責任社員となった者(例えば、新たに無限責任社員として加入した者、合資会社の有限責任社員から無限責任社員となった者、無限責任社員の持分を譲り受けた者、定款の定めるところに従い被相続人に代わって無限責任社員となった相続人等をいう。)は、無限責任社員となる前に成立した会社の国税についても責任を負う(商法82条、147条、160条)。
(退社した社員等の責任)
5 退社し、又は持分の全部を譲渡した無限責任社員及び合資会社の無限責任社員から有限責任社員となった者は、本店の所在地において退社の登記又は責任変更の登記をする前に成立した会社の国税について責任を負うが、この責任は、その登記後2年内に納付通知書による告知又はその予告をしなかった場合には、登記後2年(除斥期間)を経過した時に消滅する(商法93条、147条、160条参照)。 (注) 上記の予告については、次のことに留意する。 1 成立した会社の国税について、その税額の確定前においても、予告をすることができる。
2 予告は、書面により、将来納付通知書による告知をすることがある旨を記載して行うものとする。
(解散後の責任)
6 合名会社又は合資会社が解散した場合において、本店所在地において解散の登記をした後5年内に納付通知書による告知又はその予告をしなかったときは、無限責任社員の責任は、その登記後5年(除斥期間)を経過した時に消滅する(商法145条1項、147条)。
(無限責任社員の相続人)
7 無限責任社員が死亡した場合には、死亡前に成立した会社の国税についての無限責任社員の責任は相続人に承継されるが、死亡後退社登記前に成立した会社の国税についての無限責任社員の責任は承継されない(昭和10.3.9大判)。
なお、相続人が承継する責任の存続期間は、被相続人の負担する責任の存続期間の残存期間であるから、例えば、その無限責任社員が死亡により退社したとき又は既に生前退社していたときは、本店所在地における退社の登記日から2年間であり、解散登記後に死亡したときは、解散登記日から5年間である。
納税義務の範囲
(不足額との関係)
8 無限責任社員から徴収することができる金額は、合名会社又は合資会社から滞納処分により徴収することができる滞納に係る国税の全額であって、会社財産が徴収すべき国税の額に不足すると認められる場合のその不足する額に限られない。
(連帯納税義務)
9 法第33条の無限責任社員相互間における「連帯」については、通則法第8条((国税の連帯納付義務についての民法の準用))の規定が適用される。
第34条関係 清算人等の第二次納税義務
納税義務の成立
(法人が解散した場合)
1 法第34条の「法人が解散した場合」とは、株主総会その他これに準ずる総会等で解散の日を定めたときはその日が経過したとき、解散の日を定めなかったときは解散決議をしたとき、解散事由の発生により解散したときはその事由が発生したとき、裁判所の命令又は裁判により解散したときはその命令又は裁判が確定したとき、主務大臣の命令により解散したときはその命令が効力を生じたとき、休眠会社がみなす解散となったとき等をいう(商法58条、112条、147条、406条ノ2,406条ノ3、有限会社法71条ノ2、中小企業等協同組合法106条2項、宗教法人法43条1項、2項、会社更生法261条1項等)。ただし、商法第101条((合併の登記))、第114条((組織変更の登記))、有限会社法第62条((合併の登記))等の規定による解散の登記をしたときは含まれない。
なお、上記の解散は、その登記の有無を問わない。 (注)1 法人が解散しないで事実上解散状態にある場合には、その法人の財産の配分等がされているときでも、法第34条の規定を適用することはできないが、法第39条((無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務))、通則法第42条((債権者の代位及び詐害行為の取消し))等の規定を適用できる場合があることに留意する。
2 1人の株主が発行済株式の全部を所有する株式会社(以下「一人会社」という。)にあっては、客観的事実(例えば、営業譲渡をした後に廃業しているような場合)から解散したと認められる場合には、法第34条の「解散した場合」に該当する(昭和44.3.18大阪地判、昭和46.6.24最高判参照)。また、一人会社と同様に認められるような株式会社又は有限会社についても、同様である(昭和52.2.14最高判参照)。
(課されるべき国税)
2 法第34条の「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」とは、法人が結果的に納付しなければならないこととなるすべての国税をいい、解散の時又は残余財産の分配又は引渡し(以下第34条関係において「分配等」という。)の時において成立していた国税に限られない。
(分配又は引渡し)
3 法第34条の「分配」とは、法人が清算する場合において、残余財産を社員、株主、組合員、会員等(以下第34条関係において「社員等」という。)に、原則としてその出資額に応じて分配することをいい(民法688条2項、商法68条、147条、425条、有限会社法73条等)、「引渡」とは、法人が清算する場合において、残余財産を民法第72条((残余財産の帰属))等の規定により処分することをいう(宗教法人法50条、医療法56条等)。
なお、上記の「分配」又は「引渡」は、法人が解散した後に行ったものに限らず、解散を前提にそれ以前に行った分配又は引渡しも含まれる(昭和47.9.18東京地判)。
(不足すると認められる場合)
4 法第34条の「徴収すべき額に不足すると認められる場合」は、第22条関係4と同様である。
ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
納税義務を負う者
(清算人)
5 法第34条の「清算人」とは、解散法人(合併により解散した法人及び破産した法人を除く。)の清算事務を執行する者で分配等をした者をいい、納付通知書を発する時において清算人でない者も含まれる。
なお、分配等が清算人会の決議に基づいてされたときは、その決議に賛成した清算人はその分配等をしたものとみなし、またその議事録に異議をとどめなかった清算人はその決議に賛成したものと推定するものとする(商法430条2項、266条2項、3項参照)。また、清算人に就任することを承諾した上、清算事務を第三者に一任している者は、直接に清算事務に関与しなくても法第34条の「清算人」に該当する(昭和52.2.14最高判)。
(任意清算の場合)
6 商法第117条第1項((任意清算))(147条において準用する場合を含む。)の規定による任意清算の場合には、清算人が置かれないことがあるが、この場合にも、分配等を受けた者については、法第34条の規定が適用される。
納税義務の範囲
(責めに任ずる)
7 法第34条ただし書の「責に任ずる」とは、清算人は分配等をした財産の価額を、分配等を受けた者はその受けた財産の価額を、それぞれ限度として第二次納税義務を負うことをいうものとする。
(財産の価額)
8 法第34条の「財産の価額」とは、分配等がされた時におけるその財産の価額をいう。
(清算人が2人以上ある場合)
9 清算人が2人以上ある場合における第二次納税義務の範囲については、次のことに留意する。 (1) 各清算人がそれぞれ別個に分配等をした場合は、その分配等をした財産の価額を、それぞれその限度とする。
(2) 清算人が分配等に係る清算人会の決議に賛成した場合は、その分配等に係る財産の価額の全額を、それぞれその限度とする(5のなお書参照)。
(3) 清算人が共同行為により分配等をした場合は、その分配等をした財産の価額の全額を、それぞれその限度とする。
(第二次納税義務者相互の関係)
10 同一の分配等に基づく法第34条の第二次納税義務者が2人以上ある場合には、それらの者相互の関係は、次のとおりとする。 (注) 2回以上の分配等が行われ、それぞれの分配等ごとに法第34条の第二次納税義務者がある場合においては、第二次納税義務者の1人につき生じた事由は、異なる回の分配等に基づく第二次納税義務者には、影響を及ぼさない。
なお、上記の場合において、第二次納税義務者の納付等により主たる納税者の国税が消滅したときは、その主たる納税者の国税につき生じた効果が、他の第二次納税義務者に影響を及ぼす場合があることはもちろんである(第32条関係20参照)。 (1) 第二次納税義務者の1人につき生じた履行(納付、過誤納金等の充当、法129条1項及び2項の規定に基づく国税の消滅をいう。以下10において同じ。)以外の事由は、他の第二次納税義務者の第二次納税義務には、影響を及ぼさない。
(2) 第二次納税義務者の1人がその第二次納税義務を履行した場合には、その履行による第二次納税義務の消滅が他の第二次納税義務者の第二次納税義務の範囲に含まれている限り、その第二次納税義務も消滅する。この場合における「範囲に含まれている」かどうかの判定は、分配等に係る財産の価額を基準として行う。 (注) 分配等に係る財産の価額から第二次納税義務者の限度額を控除した額を超える額につき、他の第二次納税義務者の履行があったときは、その超える額が、上記の「範囲に含まれている」ことになる。 〔例〕 主たる納税者の国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万円
分配をした財産の価額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
精算人 甲・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
限度額 分配を受けた者 乙・・・・・・・・・・・・・6万円
分配を受けた者 丙・・・・・・・・・・・・・4万円
イ 甲が3万円履行したとき。
甲の責任は、残額7万円(甲の限度額10万円-甲の履行額3万円)となる。乙、丙の限度額はその7万円に満たないから、甲の履行は乙及び丙には影響がない。
ロ 甲が5万円履行したとき。
甲の責任は、残額5万円(甲の限度額10万円-甲の履行額5万円)となる。甲の履行によりその残額5万円が責任の最高限度になることから、乙の責任は、1万円減少(乙の限度額6万円-その残額5万円)して残額5万円となる。丙の責任(4万円)は、5万円に満たないから、甲の履行は丙には影響がない。
ハ 甲が7万円履行したとき。
甲の責任は、残額3万円(甲の限度額10万円-甲の履行額7万円)となる。甲の履行によりその残額3万円が責任の最高限度になることから、乙の責任は、3万円減少(乙の限度額6万円-その残額3万円)して残額3万円に、丙の責任は、1万円減少(丙の限度額4万円-その残額3万円)して残額3万円となる。
ニ 乙が2万円履行したとき。
乙の責任は、残額4万円(乙の限度額6万円-己の履行額2万円)となる。乙の履行により8万円が責任の最高限度になることから、甲の責任は、2万円減少(甲の限度額10万円-その残額8万円)して残額8万円となる。丙の責任(4万円)は、8万円に満たないから、乙の履行は丙には影響がない。
ホ 乙が6万円履行したとき。
乙の責任は、0(乙の限度額6万円-乙の履行額6万円)となる。乙の履行によりその残額4万円が責任の最高限度になることから、甲の責任は、6万円減少(甲の限度額10万円-その残額4万円)して残額4万円となる。丙の責任(4万円)は、4万円と同額であることから、乙の履行は丙には影響がない。
ヘ 丙が4万円履行したとき。
丙の責任は、O(丙の限度額4万円-丙の履行額4万円)となる。丙の履行によりその残額6万円が責任の最高限度になることから、甲の責任は、4万円減少(甲の限度額10万円-その残額6万円)して残額6万円となる。乙の責任の残額(6万円)は6万円と同額であることから、丙の履行は乙には影響がない。
商法との関係
(商法第118条等との関係)
11 任意清算中の合名会社が、商法第117条第3項((任意清算))において準用する第100条第1項又は第3項((債権者の異議))の規定に違反して財産を処分した場合において、その処分が残余財産の分配に該当するときは、法第34条の規定の適用があるが、その他の処分であるときは、同法第118条((会社債権者の保護))の規定により、その処分の取消しを裁判所に請求することができる。
なお、合資会社の場合も上記と同様である(商法147条)。
(商法第421条等との関係)
12 商法第421条((会社債権者に対する催告))(有限会社法75条1項、信用金庫法64条等において準用する場合を含む。)の規定は、国税については適用されない(明治38.10.11行判)。
(清算結了登記との関係)
13 株式会社等が課されるべき国税又は納付すべき国税を完納しないで清算結了の登記をしても、その登記は適法な清算結了に基づくものではないから、会社は清算のために必要な範囲においてなお存続し、課されるべき国税又は納付すべき国税は消滅しない(大正6.7.24行判)。
(商法第406条等との関係)
14 株式会社、有限会社等が解散し、残余財産を分配した後において、商法第406条((会社の継続))、有限会社法第70条((会社の継続))等の規定により会社を継続した場合には、継続の特別決議によって残余財産の分配の効果は将来に向かって消滅する。したがって、この継続の特別決議後は、残余財産はなかったことになるから、法第34条の規定による第二次納税義務を負わせることはできない。
第35条関係 同族会社の第二次納税義務
納税義務の成立
(会社)
1 法第35条第1項の「会社」とは、合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社をいい(商法53条、有限会社法89条)、相互会社(保険業法3章参照)は含まれない。
(同族会社の判定)
2 法第35条第1項の「同族会社」に該当するかどうかの判定は、会社の株主又は社員のうち、滞納者とその持株数(端株数を含む。以下第35条関係において同じ。)又は出資の金額が最も大きい者から順次に選定した株主(端株主を含む。以下第35条関係において同じ。)又は社員との組合せによって、法人税法第2条第10号((同族会社の定義))の同族会社に該当するかどうかにより行うものとする。
なお、法第35条の株主又は社員は、株主名簿、社員名簿、端株原簿の記載等にかかわらず、実質上の株主又は社員をいい、また株券の発行前における株式の譲渡がされている場合には、その譲受人をいうものとする。 (注) 端株とは、記名株式の1株に満たない端数で、1株の100分の1の整数倍に当たるものをいう(商法230条ノ2)。
(出 資)
3 法第35条の「出資」とは、合名会社、合資会社又は有限会社の持分をいう。
(不足すると認められるとき)
4 法第35条第1項の「徴収すべき国税に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
(買受人がない場合)
5 法第35条第1項第1号の「買受人がない」とは、滞納処分による換価をした場合において、売却決定を受けた者がないとき及び売却決定が取り消されたときをいう。
(合名会社等の持分の譲渡制限)
6 合名会社及び合資会社の持分は、商法第73条(持分の譲渡)、第147条((合名会社の規定の準用))及び第154条((有限責任社員の持分の譲渡))の規定によって無限責任社員全員の同意がなければ譲渡できないから、例えば、換価前に無限責任社員のうち1人でも換価による持分の譲渡に反対の意思表示をした場合は、法第35条第1項第2号に該当する。
(株券又は端株券が発行されていない場合)
7 法第35条第1項第2号の「株券若しくは端株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること」とは、株券又は端株券の作成及び交付がされていないために、株式を差し押さえて換価することにつき支障があることをいう。
なお、この場合においては、次のことに留意する。 (1) 合理的な期間内に株券又は端株券が発行される(商法226条1項、230条ノ3第1項参照)見込みがあるとき及び株式の申込証拠金領収証等の書面を株券に準じて差し押さえて換価できるとき(第56条関係16参照)は、法第35条第1項第2号の事由に当たらないものとして取り扱う。
(2) 株券又は端株券が発行されていない場合において、その交付請求権を差し押さえたにもかかわらず、指定した期限までに会社が株券又は端株券を交付しないときは、法第35条第1項第2号の事由に当たる。
納税義務の範囲
(納付すべき国税)
8 法第35条第1項の「納付すべき国税」には、所得税法第142条第2項((純損失の繰戻しによる還付))(166条において準用する場合を含む。)又は法人税法第81条第6項((欠損金の繰戻しによる還付))の規定により還付した金額に係る還付加算金(通則法58条1項)があったときは、その還付加算金のうち修正申告又は更正によって減少する還付金の額に相当する所得税額又は法人税額に対応する部分の金額が含まれる(通則法19条4項3号ハ、28条2項3号ハ参照)。
(申告等があった日)
9 法第35条第1項の「還付の基因となった申告、更正又は決定があった日」とは、還付金の額に相当する国税を減少させる修正申告又は更正があった場合において、還付の基因となった申告、更正又は決定があった日をいう。
なお、修正申告又は更正により納付すべき国税が還付金の額を超えることとなった場合には、その超えることとなった国税の額に相当する部分の国税の法定納期限は、当該国税の本来の法定納期限である。 〔例1〕
所得税の確定申告により生じた還付金10万円を還付した後、その還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告により納付すべき所得税が1万円生じた場合については、その確定申告があった日が法定納期限となる。 (注) 申告書が郵便により提出された場合の「申告があった日」については、通則法第22条((郵送に係る納税申告書の提出時期))の規定の適用がある。
〔例2〕
所得税の減額更正により生じた還付金8万円を還付した後、その還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告により納付すべき所得税が1万円生じた場合については、その減額更正があった日が法定納期限となる。
〔例3〕
通則法第25条((決定))の規定による決定により生じた還付金6万円を還付した後、その還付金の額に相当する税額を減少させる再更正により納付すべき法人税1万円が生じた場合については、その決定があった日が法定納期限となる。
(1年以上前)
10 法第35条第1項の「1年以上前に取得したものを除く」とは、法定納期限の1年前の応当日以前に取得したものを除くことをいう。この場合の応当日については、通則法第10条第2項((期限の特例))の規定は適用されない。
(相続等があった場合の株式等の取得時期)
11 相続等があった場合における法第35条第1項の「取得」の時期は、次による。 (1) 相続により承継された国税と相続により承継した株式又は出資との関係においては、被相続人が株式又は出資を取得した日
(2) 相続人の固有の国税と相続により承継した株式又は出資との関係においては、相続があった日
(3) 合併により承継された国税と合併により承継した株式又は出資との関係においては、合併により消滅した法人が株式又は出資を取得した日
(4) 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の固有の国税と合併により承継した株式又は出資との関係においては、合併があった日
(5) 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資の取得が、合併により消滅した法人の株式又は出資を有していたことによる場合は、合併があった日
(徴収できる国税と株式又は出資との関係)
12 法第35条の規定により同族会社に対して第二次納税義務を負わせることができる場合の国税は、その会社の株式又は出資を納税者が取得した日から起算して1年を経過する日以前にその法定納期限があるものに限られる(法35条1項)。
(資産及び負債の額の計算)
13 法第35条第2項の「資産の総額」及び「負債の総額」の算定に当たっては、法第32条第1項((納付通知書による告知等))の規定による納付通知書を発する日における財産目録又は貸借対照表を参考として、その日における会社財産の適正な価額を計算するものとする。この場合において、上記の納付通知に係る第二次納税義務は、負債に含めないものとする。
なお、上記の資産及び負債の額の計算は、原則として納付通知書を発する日の現況によるが、特に徴収上支障がない限り、その日の直前の決算期(中間決算を含む。)の貸借対照表、財産目録又は法人税の決議書を参考として行っても差し支えない。
(現物、労務又は信用による出資)
14 法第35条第2項の「出資の数」については、現物、労務又は信用をもって出資の目的とした場合には、出資の評価についての定款による価額又は評価の基準によって、納税者の有する出資の価額を計算し、その価額を現金による出資の価額と同様に取り扱って、出資の数を計算するものとする。
第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
納税義務の成立
(滞納者)
1 法第36条の「滞納者」には、第二次納税義務者及び保証人は含まれない。
(国 税)
2 法第36条第1号から第3号に規定する規定により課された国税(以下2において「実質課税に係る部分の国税」という。)が、一つの国税(一つの申告、更正又は決定の通知によって国税の額が確定したものをいう。以下2、第37条関係3及び第38条関係13において同じ。)の一部であるときは、その国税の額の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 法第36条第1号又は第3号に規定する規定により課された国税の額は、次の算式により計算して得た金額とする(令12条1項)。
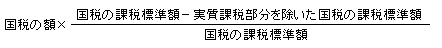
(注)1 上記の課税標準額とは、一つの国税の額に対応する課税標準額をいうものとする。
2 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税について上記の計算をする場合には、上記の課税標準額は、これらの加算税の計算の基礎となった国税の課税標準額をいうものとする。
(2) 法第36条第2号に規定する規定により課された消費税の額は、次の算式により計算して得た金額とする(令12条1項)。
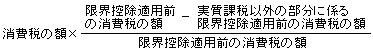
(注) 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税について上記の計第をする場合は、上記の「限界控除適用前の消費税の額」は、これらの加算税の計算の基礎となった限界控除適用前の消費税の額をいうものとする。
(3) 国税の一部につき納付又は充当があった場合は、その納付又は充当は、まず、上記(1)又は(2)以外の部分の金額についてされたものとする(令12条2項)。
(4) 国税の一部につき免除があった場合は、その免除は、まず、上記(1)又は(2)以外の部分の金額についてされたものとする(令12条2項)。ただし、その免除が、実質課税に係る国税についてされたことが明らかであるときは、実質課税に係る部分の国税について免除されたものとする。
(5) 国税の一部につき更正の取消し、軽減等があり税額が減少した場合における実質課税に係る部分の国税の額の計算は、(4)に準ずる。
(不足すると認められるとき)
3 法第36条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。
ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
(実質課税)
4 法第36条第1号の「所得税法第12条(実質所得者課税の原則)又は法人税法第11条(実質所得者課税の原則)の規定により課された国税」及び法第36条第2号の「消費税法(昭和63年法律第108号)第13条(資産の譲渡等を行った者の実質判定)の規定により課された国税」は、その所得税、法人税又は消費税が、申告、更正又は決定のいずれによるかを問わない。
(所得の帰属推定による課税)
5 法第36条第1号の「所得税法第158条(事業所の所得の帰属の推定)の規定により課された国税」とは、通則法第24条から第26条まで(更正、決定、再更正)の規定による更正又は決定に係る所得税をいう。
(資産の譲渡等を行った者の実質判定)
6 法第36条第2号の「消費税法(昭和63年法律第108号)第13条(資産の譲渡等を行った者の実質判定)の規定により課された国税(同法第2条第1項第8号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。)」とは、消費税法第13条の規定により課された消費税のうち、事業として対価を得て行われる資産の貸付けに基因して課されたものに限られることに留意する。
(同族会社の行為計算否認による課税)
7 法第36条第3号の「所得税法第157条(同族会社等の行為又は計算の否認)、法人税法第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)又は相続税法第64条(同族会社の行為又は計算の否認)の規定により課された国税」とは、通則法第24条から第26条まで(更正、決定、再更正)の規定による更正若しくは決定に係る所得税、法人税、相続税又は贈与税をいう。
納税義務を負う者
(第1号の場合)
8 法第36条第1号の「収益が法律上帰属するとみられる者」とは、4の実質課税の場合には、所有権の名義人又は事業の名義人等、通常であれば、その者がその財産又は事業から生ずる収益を享受する者であるとみられる者をいい、5の所得の帰属推定による課税の場合には、事業所の属する法人をいう。
(第2号の場合)
9 法第36条第2号の「貸付けを法律上行ったとみられる者」とは、単なる名義人であってその資産の貸付けに係る対価を享受しない者をいう。
(第3号の場合)
10 法第36条第3号の「否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となった行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者」については、次のことに留意する。 (1) 「納税者」とは、6の同族会社等の行為計算否認による課税により国税の納税義務を負う者をいい、納税者の「行為」とは、納税者が当事者となっている行為をいう。
(2) 「否認された計算の基礎となった行為」とは、同族会社等の行為(例えば、譲渡行為)自体は否認しないが、その行為に係る計算(例えば、譲渡価額の計算)を否認した場合におけるその計算のもととなった行為(例えば、上記の譲渡行為)をいう。
(3) 「利益を受けたものとされる者」とは、納税者の行為について、行為又は計算の否認理由との関係からみて不当な経済的利益を受けたと認められる者をいう。
納税義務の範囲
(収益が生じた財産)
11 法第36条の「収益が生じた財産」とは、資産から生じた収益に関する実質課税の場合にはその資産、事業から生じた収益に関する実質課税の場合にはその事業に属する資産、法人の事業所の所得の帰属推定による課税の場合にはその事業所の事業に属する資産をいうが、なお次のことに留意する。 (1) 収益が生じた資産又は事業(事業所の事業を含む。以下第36条関係において同じ。)が、譲渡等により、滞納処分時において、既に8の第二次納税義務者に法律上帰属するとみられない場合には、その資産又は事業に属する資産に対しては、第二次納税義務を追及できない(取得財産に対する追及については、12参照)。
(2) 事業に属する資産は、滞納処分時現在において、その事業に属するものである。したがって、資産がその事業に属することとなった時期が、課税時又は納付通知等の前であるか後であるかを問わない。 (注) 事業に属していた資産が、譲渡等により滞納処分時現在において事業に属しない場合には、その資産に対しては第二次納税義務を追及できない(この場合の取得財産に対する追及については、12の(2)参照)。
(3) 事業に属する資産であっても、その事業の名義人である第二次納税義務者に法律上帰属するとみられない資産(例えば、第三者から賃借している資産)に対しては、第二次納税義務を追及できない。
(異動によって取得した財産)
12 法第36条の「その財産の異動により取得した財産」とは、11の収益が生じた財産(資産又は事業)及び14の貸付けに係る財産について、その交換によって取得した財産(資産又は事業)、売却によって取得した代金、滅失によって取得した保険金等をいうが、なお次のことに留意する。 (1) 2回以上の異動により取得した財産(例えば、収益が生じた財産の売却代金をもって購入した財産)も、その異動の経過が明らかなものは、異動により取得した財産とする。
(2) 事業に属する資産の異動によって取得した資産は、それがその事業に属しない場合に限り、収益が生じた財産の異動により取得した財産に含まれる。 (注) 事業に属する資産の異動によって取得した資産が、その事業に属する場合については、11の(2)参照。
(3) 収益が生じた財産の異動により取得した財産が、第二次納税義務者に法律上帰属するとみられない場合には、その財産に対しては、第二次納税義務を追及できない。
(基因して取得した財産)
13 法第36条の「これらの財産に基因して取得した財産」とは、11の収益が生じた財産及び12の異動により取得した財産について、その天然又は法定の果実及び権利の使用料等をいう。
(貸付けに係る財産)
14 法第36条第2号の「貸付けに係る財産」とは、事業として対価を得て行われる資産の貸付けの目的となる財産をいうが、なお次のことに留意する。 (1) 「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む(消費税法2条2項)。 (注)1 「資産に係る権利の設定」とは、例えば、土地に係る地上権若しくは地役権、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)に係る実施権若しくは使用権又は著作物に係る出版権の設定をいう。
2 「資産を使用させる一切の行為」とは、例えば次のものをいう。 (1) 工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)の使用、提供又は伝授
(2) 著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為
(2) 貸付けに係る財産が、譲渡等により、課税の基礎となった貸付けを法律上行ったとみられる者に、滞納処分時現在において既に法律上帰属すると認められない場合は、第二次納税義務を追及できない(この場合の取得財産に対する追及については、12及び13参照)。
(受けた利益の額)
15 法第36条の「受けた利益の額」とは、10の(3)の利益を受けたものとされる者(第二次納税義務者)が受けたその利益の額をいう。
なお、上記の利益が、滞納処分時現在において現存するかどうかは、法第36条第3号の第二次納税義務には関係ない。
第37条関係 共同的な事業者の第二次納税義務
納税義務の成立
(重要な財産)
1 法第37条の「事業の遂行に欠くことができない重要な財産(以下第37条関係において「重要財産」という。)であるかどうかは、納税者の事業の種類、規模等に応じ判断すべきであるが、一般には、判断の対象とする財産がないものと仮定した場合に、その事業の遂行が不可能になるか又は不可能になるおそれがある状態になると認められる程度に、その事業の遂行に関係を有する財産をいう。
なお、法第37条第1号又は第2号に掲げる者が2人以上ある場合には、納税者の事業に供しているこれらの者が有する財産を一体として考え、それが事業の遂行に欠くことができない重要財産であるかどうかを判定するものとする (注) 法第37条の「重要な財産」には、滞納処分ができる財産だけでなく、滞納処分ができない財産も含まれる。
(財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている場合)
2 法第37条の「財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている場合」とは、重要財産から直接又は間接に生ずる所得が納税者の所得となっている場合及び所得税法その他の法律の規定又はその規定に基づく処分により納税者の所得とされる場合をいうものとし、例えば、次に掲げる場合がある。 (1) 所得税法第56条((事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例))の規定により、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族がその納税義務者の経営する事業で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべきものから所得を受ける場合で、その所得が納税者の所得とされる場合
(2) 法人税法第132条((同族会社等の行為又は計算の否認))の規定により、同族会社の判定の基礎となった株主又は社員の所得が同族会社の所得とされる場合
(3) 同族会社の判定の基礎となった株主又は社員の所有する財産をその同族会社が時価より低額で賃借りしているため、その時価に相当する借賃の金額とその低額な借賃の金額との差額に相当するものが同族会社の実質的な所得となっている場合(昭和48.10.15広島高岡山支判)
(4) 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する公債、社債、無記名の株式又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券について、納税者が利子、配当、利益又は収益の支払を受けている場合
(5) 納税者の事業の収支計算では損失が生じているが、重要財産から直接又は間接に生ずる収入が納税者の収益に帰属している場合
(供されている事業に係る国税)
3 法第37条の「供されている事業に係る国税」が、一つの国税の一部である場合の国税の額の算定については、第36条関係2と同様である(令12条3項)。
なお、重要財産が供されている事業に係る国税は、その納税者の事業に係る国税のうち、その重要財産が供されていた期間に対応する部分の国税の額に限るものとする。
(事業に係る国税)
4 法第37条の「事業に係る国税」とは、納税者が同族会社であるときはすべての国税を、個人であるときは次に掲げる国税を、それぞれいうものとする。 (1) 所得税のうち所得税法第27条((事業所得))の事業所得に係るもの
(2) 所得税(源泉所得税を含む。)のうち(1)の事業所得に係る所得税以外の所得に係る所得税については、これらの事業に係るもの(例えば、納税者が小売業を経営している場合において、その事業に係る所得と譲渡所得とがある場合には、事業所得に係る所得税を、また小売業の従業員に係る源泉所得税と家事使用人に係る源泉所得税とがある場合には、その小売業の従業員に係るもの)
(3) 消費税等(消費税を除く)については、重要財産が供されている物品に係るもの
(4) 消費税
(5) 登録免許税、再評価税、有価証券取引税及び印紙税は、事業に係るこれらの国税
(不足すると認められるとき)
5 法第37条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。
ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
納税義務を負う者
(生計を一にする)
6 法第37条第1号の「生計を一にする」とは、有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい、納税者がその親族と起居をともにしていない場合においても、常に生活費、学資金又は療養費等を送金して扶養しているときは、生計を一にするものとする。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
(親族)
7 法第37条第1号の「親族」とは、民法第725条各号((親族の範囲))に掲げる者のうち、配偶者以外の納税者と生計を一にする者、すなわち納税者と生計を一にする者の六親等内の血族及び三親等内の姻族をいう。
(納税者の経営する事業)
8 法第37条第1号の「納税者の経営する事業」とは、納税者が経営する事業のすべてをいい、重要財産が供されている事業だけをいうものではない。
(所得を受けている)
9 法第37条第1号の「所得を受けている」とは、納税者から、その経営する事業の計算において給料、賃貸料、配当、利息又は収益の分配等その名称のいかんを問わず実質的に所得を受けていることをいう。
(第1号の判定の時期)
10 重要財産を有している者が、法第37条第1号に掲げる者に該当するかどうかは、その財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている時期の現況において判定するものとする。
(第2号の判定の時期)
11 法第37条第2号の「その事実のあった時」とは、同族会社の判定の基礎となった株主又は社員が重要財産を有し、かつ、その財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている事実があった時期をいう。
納税義務の範囲 編注13
12 法第37条の「取得財産」の意義については、第36条関係10及び11と同様である。
第38条関係 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
納税義務の成立
(特殊関係者)
1 法第38条の「その親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの」とは、令第13条第1項((納税者の特殊関係者の範囲))に規定する者(以下「親族その他の特殊関係者」という。)をいう。この場合において、同項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況によるから(令13条2項)、その後離婚、解雇等によって各号に掲げる者に該当しないこととなっても、法第38条の規定が適用される。 (注) 財産分与(民法768条、771条)として行われた事業譲渡について、その事業譲渡が財産分与として祉会通念上相当と認められる場合には、法第38条の規定を適用しないものとする。
(配偶者、直系血族等)
2 令第13条第1項第1号((納税者の特殊関係者の範囲))の「配偶者」又は「直系血族及び兄弟姉妹」には、納税者と生計を一にしていない者も含まれる。
(親 族)
3 令第13条第1項第2号((納税者の特殊関係者の範囲))の「親族」とは、民法第725条((親族の範囲))に規定する親族のうち、配偶者、直系血族及び兄第姉妹を除いた六親等内の血族及び三親等内の姻族をいう。
(生計を一にする)
4 令第13条第1項第2号((納税者の特殊関係者の範囲))の「生計を一にする」は、第37関係6と同様である。
(生計の維持)
5 令第13条第1項第2号から第4号まで((納税者の特殊関係者の範囲))の「生計を維持」とは、給付を受けた金銭その他の財産及びその金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分(おおむね2分の1以上とする。)としていることをいう。
(特別の金銭等)
6 令第13条第1項第3号及び第4号((納税者の特殊関係者の範囲))の「特別の金銭」とは、給料、俸給、報酬、売却代金等の役務又は物の提供の対価として受ける金銭以外で、対価なく又はゆえなく対価以上に受ける金銭をいい、また、「特別の財産」についても、おおむねこれと同様である。
(財産の提供)
7 令第13条第1項第4号((納税者の特殊関係者の範囲))の「財産を提供して」いる場合には、財産を譲渡している場合のほか、賃貸等により利用させている場合も含まれる。
(同族会社に該当する他の会社)
8 令第13条第1項第7号((納税者の特殊関係者の範囲))の「同族会社に該当する他の会社」とは、具体的には下図のA1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1及びE2をいう。
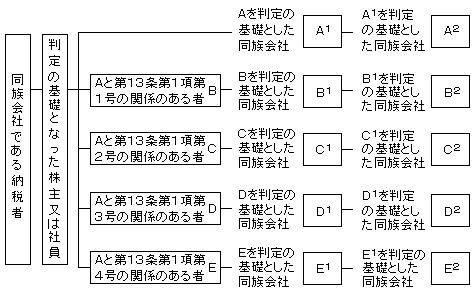
(注)1 上図のうちA,B,C,D及びEは、令第13条第1項第5号((納税者の特殊関係者の範囲))に該当する。
2 令第13条.第1項第7号かっこ書((納税者の特殊関係者の範囲))のうち前者の「これらの者」とは上図のAをいい、後者の「これらの者」とは上図のA,B,C,D及びEをいう。
(事業譲渡)
9 法第38条の「事業の譲渡」とは、納税者が一個の債権契約で、一定の事業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を納税者の親族その他の特殊関係者に譲渡することをいうが、一個の債権契約によらないものであつても、社会通念上同様と認められるものはこれに該当する(昭和46.4.9最高判参照)。したがって、得意先、事業上の秘けつ又はのれん等を除外して、工場、店舗、機械、商品等の事業用財産だけを譲渡する場合は、法第38条の事業譲渡には該当しない。
なお、事業譲渡については、次のことに留意する。 (1) 合名会社又は合資会社にあっては、原則として事業譲渡につき総社員の同意が必要である(商法72条、127条、147条)。
(2) 株式会社又は有限会社にあっては、事業譲渡につき株主総会又は社員総会の特別決議が必要である(商法245条1項、有限会社法40条1項)。 (注) 一人会社にあっては、客観的な事実(例えば、営業譲渡をした後に廃業しているような場合)から事業譲渡の特別決議があったと認められる場合には、法第38条の「事業の譲渡」に該当する(昭和44.3.18大阪地判、昭和46.6.24最高判参照)。また、一人会社と同様に認められるような株式会社又は有限会社についても同様である(昭和52.2.14最高判参照)。
(3) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定により事業の譲受けにつき制限を受ける場合がある(同法15条から17条まで参照)。
(同一とみられる場所)
10 法第38条の「同一とみられる場所」とは、同一の場所のほか、社会通念上同一の場所と認められる場所をいう。
(類似の事業)
11 法第38条の「類似の事業」とは、譲り受けた事業につき重要な事業活動の施設又は態様の変更をその事業内容に加えることなく事業活動が行われているような場合のその譲受け後の事業をいう。
(同一とみられる場所等の判定の時期)
12 法第38条の「同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる」かどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。 (注) 事業譲渡の当時においては「同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合」に当たらなくても、納付通知書を発する時においてこれに該当するときは、法第38条が適用される。
(事業に係る国税)
13 法第38条の「事業に係る国税」が一つの国税の一部である場合の国税の額の算定は、第36条関係2と同様である(令12条3項)。
(不足すると認められるとき)
14 法第38条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
(1年以上前)
15 法第38条の「1年以上前にされている場合は、この限りでない」とは、法定納期限の1年前の応当日以前に譲渡した場合は法第38条の規定の適用がないことをいう。この場合の応当日については、通則法第10条第2項((期限の特例))の規定は適用されない。
納税義務の範囲
(譲受財産)
16 法第38条の「譲受財産」とは、譲受けに係る事業に属する積極財産をいい、事業の譲受け後に取得した財産(取得財産を除く。)は含まれない。
(取得財産)
17 法第38条の「取得財産」の意義については、第36条関係10及び11と同様である。
第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
納税義務の成立
(不足すると認められる場合)
1 法第39条の「徴収すべき額に不足すると認められる場合」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
(1年前の日以後の判定)
2 法第39条の「1年前の日以後」であるかどうかの判定については、次のことに留意する。
なお、法第39条の「1年前の日以後」は、第35条関係10と同様に取り扱うものとする。したがって、法定納期限の1年前の応当日にされた譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分については、法第39条の規定を適用しない取扱いとする。 (1) 契約が成立した時とそれに基づき譲渡等の処分がされた時(権利を取得し、又は義務を免れた時)が異なるときは、譲渡等の処分がされた時によって、1年前の日以後であるかどうかを判定する。
(2) 譲渡等の処分につき登記等の対抗要件又は効力要件の具備を必要とするときは、その要件を具備した日によって、1年前の日以後であるかどうかを判定する(昭和55.3.14東京高判)。 (注)1 上記の場合において、仮登記とそれに基づく本登記があるときは、本登記によって判定する。ただし、担保のための仮登記については、仮登記の日によって判定する。
2 譲渡等の処分がされた時が登記等の日後であることが訴訟等により明らかにされている場合には、その日によって判定する。
(譲渡)
3 法第39条の「譲渡」とは、贈与、特定遺贈、売買、交換、債権譲渡、出資、代物弁済等による財産権の移転をいい、相続等の一般承継によるものを含まない。この場合において、売買、交換、債権譲渡についてはそれにより取得した金銭又は財産が、出資についてはそれにより取得した持分又は株式が、代物弁済についてはそれにより消滅した債務が、それぞれ法第39条の「対価」である。 (注)1 包括遺贈(民法964条参照)があった場合には、通則法第5条((相続による国税の納付義務の承継))の規定の適用がある。
2 強制換価手続による所有権の移転は、上記の譲渡には含まれない。
3 滞納者が、例えば、生計を一にする親族(第37条関係6、民法725条)の生活費、学費等に充てるためにした社会通念上相当と認められる範囲の金銭又は物品の交付は、法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」には当たらない。
(債務の免除)
4 法第39条の「債務の免除」には、民法第519条((免除))の規定による債務免除のほか、契約による免除も含まれる。この場合において、債務の免除と対価関係にある反対給付があるときは、それが法第39条の「対価」に当たる。
(第三者に利益を与える処分)
5 法第39条の「その他第三者に利益を与える処分」とは、譲渡、債務の免除以外の処分のうち、滞納者の積極財産の減少の結果(滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使又は不行使の結果によるものを除く。)、第三者に利益を与えることとなる処分をいい、例えば、地上権、抵当権、賃借権等の設定処分がある。この場合において、地上権等の設定により受けた反対給付(例えば、権利金、礼金等)があるときは、それが法第39条の「対価」に当たる。
(著しく低い額の対価の判定)
6 法第39条の「著しく低い額の対価」によるものであるかどうかは、社会通念上、通常の取引に比べ著しく低い額の対価であるかどうかによって判定する。 (注)1 値幅のある財産については、特別の事情がない限り、時価のおおむね2分の1に満たない価額をもって著しく低いと判定しても差し支えない(昭和54.4.24大阪高判)。
2 対価が時価の2分の1を超えている場合においても、その行為の実態に照らし、時価と対価との差額に相当する金員等の無償譲渡等の処分がされていると認められる場合があることに留意する。
(著しく低いかどうかの判定の時期)
7 法第39条の「著しく低い額の対価」によるものであるかどうかの判定は、原則として、その譲渡等の処分の基因となった契約が成立した時の現況による。したがって、条件付契約、予約契約、効力発生要件が別にある場合の契約等、契約が成立した時とそれに基づき譲渡等の処分がされた時(権利を取得し、又は義務を免れた時)が異なる場合であっても、契約が成立した時の現況により判定する。
(基因すると認められるとき)
8 法第39条の「不足すると認められること」(以下8において「徴収不足」という。)が無償譲渡等の処分(国及び法人税法2条5号((公共法人の定義))に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分をいう(令14条)。以下第39条関係において同じ。)に「基因すると認められるとき」とは、その無償譲渡等の処分がなかったならば、現在の徴収不足は生じなかったであろう場合をいう。
納税義務を負う者
(権利を取得し、又は義務を免れた者)
9 法第39条の「権利を取得し、又は義務を免れた者」とは、無償譲渡等の処分により所有権、地上権、賃借権、無体財産権その他の財産権を取得した者又は債務の免除により債務を免れた者若しくは負うべき債務を免れた者をいう。
(親族その他の特殊関係者)
10 法第39条の「親族その他の特殊関係者」は、第38条関係1から8までと同様である。ただし、法第39条の親族その他の特殊関係者に該当するかどうかの判定は、原則として、無償譲渡等の処分の基因となった契約が成立した時の現況によるものとする。したがって、権利を取得し、又は義務を免れた時に特殊関係者に当たらなくても、契約が成立した時に特殊関係者に当たる場合には、法第39条の規定が適用される。
第三者の場合の納税義務の範囲
(受けた利益が金銭以外の物である場合)
11 無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が金銭以外の物である場合には、法第39条の「利益が現に存する限度」の額は、次により定める取扱いとする。ただし、その額が、15により算定した「受けた利益」の額を超える場合には、その受けた利益の額を限度とする。 (1) 受けた物がそのまま現存する場合には、納付通知書を発する時の現況による受けた物の価額を算定する。 (注) 受けた物から生じた果実は、現に存する利益の額には加えない。ただし、その果実が受益財産の一部となっている場合には、(2)による。
(2) 受けた物が、加工等により価額が増加した場合には、納付通知書を発する時の現況によるその物の価額から、その物の価額を増加させるために要した費用を控除した額を算定する。
(3) 受けた物について、その後譲受人が設定等をした地上権等の用益物権、賃借権、抵当権等がある場合には、納付通知書を発する時の現況による受けた物の価額に、用益物権等の設定等に伴い得た利益(例えば、権利金、礼金等)のうち現に存するものの額(注)参照)を加え、用益物権等の設定等に伴い要した費用(例えば、契約の費用等)の額を算定する。 (注) 上記の「現に存するものの額」の算定は、その「得た利益」が受けた利益に当たるものとして、その種類に従い、それぞれ11から14に準じて行う。
(4) 受けた物の全部又は一部が売買、贈与、き損、盗難、火災等により現存しない場合には、納付通知書を発する時における残存する財産の価額に、現存しないこととなったことに伴い得た利益(例えば、売却代金、保険金、共済金、損害賠償請求権等)のうち現に存する物の額((注)1参照)を加え、その利益を得るために要した費用(例えば、売買の費用、当該保険料、損害賠償請求のための通信費、交通費等)を控除した額を算定する。 (注)1 上記の「現に存するもの」の算定は、(3)の(注)と同様である。
2 受けた物に自己の固有財産を加えたものを譲渡し、他の財産を取得した場合には、納付通知書を発する時の現況による取得した財産の価額に、譲渡した財産の総額のうち受けた物の価額(譲渡時の価額)が占める割合をかけた額が、上記の「現存しないこととなったことに伴い得た利益のうち現に存する物の額」に当たるものとする。
(5) (1)から(4)までにより算定した額から、次に掲げる額を控除する。 イ その物を譲り受けるために支払った対価の額(無償譲渡等の処分があった時の対価の額)
ロ その物の譲受けのために支払った費用及びこれに類するもののうち、その物の譲受けと直接関係のある物の額(例えば、契約に要した費用、不動産取得税、登録免許税等(これらの租税に係る附帯税を除く。)があるが、その物の保管料、譲受人に課された固定資産税、その譲受けを基因として課された市町村民税等はこれに当たらない(昭和51.1O.8最高判)。)
ハ その物を譲り受けたことを直接の理由とする特別の消費及びこれに類する財産の減少の額(例えば、その物を譲り受けたことを直接の理由として浪費し又は他の物を他人に贈与した場合等がある。)
(6) 上記(5)の対価又は費用には、その金額が確定していなくても、その存在が確実と認められるものについては、納付通知書を発する時の現況によって確実と認められる範囲の金額を含めるものとする。
(受けた利益が金銭である場合)
12 無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が金銭である場合には、法第39条の「利益が現に存する限度」の額は、次により定める取扱いとする。 (1) 受けた金銭の額から、11の(5)に掲げる額を控除する。
(2) (1)により算定した額は、現に存するものと推定する(明治39.1O.11大判参照)。
(3) 金銭を受けたことを直接の理由として特別に財産を取得した場合には、上記(1)及び(2)により算定した額からその取得に要した金銭の額を控除したものに、その取得した財産のうち現に存するものの額((注)1参照)を加える。 (注)1 上記の「現に存するもの」の算定は、11の(3)の(注)と同様である。
2 受けた金銭と自己の固有財産とを合わせて財産を取得した場合には、納付通知書を発する時の現況による取得した財産の価額に、その取得に要した財産の総額のうち受けた金銭の額が占める割合をかけた額が、上記の「現に存するものの額」に当たるものとする。
(受けた利益が債務の免除である場合)
13 無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が債務の免除である場合には、債務者の支払能力、弁済期等を考慮し、その債権を換価する場合と同様に、その債務が免除された時におけるその債権の価額を算定し、その額が受けた利益の額に当たるものとして、12によって法第39条の「利益が現に存する限度」の額を定める取扱いとする。
(受けた利益が地上権の設定等である場合)
14 無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が地上権等の用益物権の設定、賃借権の設定、抵当権等の担保権の設定等である場合には、11に準じて法第39条の「利益が現に存する限度」の額を定める取扱いとする。この場合において、受けた利益が抵当権等の担保権の設定である場合には、物上保証をした者に通常支払われるべき保証料の額が、受けた利益に当たる。
特殊関係者の場合の納税義務の範囲
15 法第39条の「受けた利益の限度」の額は、次に定めるところによる。 (1) 無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が金銭であるときはその額を、金銭以外のものであるときは無償譲渡等の処分がされた時の現況によるその物の価額を、債務の免除であるときは債務が免除された時の現況によるその債権の価額を、地上権の設定等であるときはその設定等がされた時の現況によるその地上権等の価額を、それぞれ算定する。 (注) 無償譲渡等の処分後において、受けた利益が滅失等により現存しない場合、受けた財産について費用を支出した場合、受けた財産に用益物権、担保権、賃借権等を設定した場合、受けた財産から生じた果実がある場合等であっても、これらの事情は考慮しない。
(2) (1)により算定した額から、11の(5)のイ及びロに掲げる額を控除する。
第41条関係 人格のない社団等に係る第二次納税義務
納税義務の成立
(第三者)
1 法第41条第1項の「第三者」には、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)の構成員も含まれる。
(法律上帰属するとみられる財産)
2 法第41条第1項の「法律上帰属するとみられる財産」とは、登記を対抗要件又は効力要件としている財産で、第三者が名義人となっているものをいうほか、電話加入権で第三者が名義人となっているものを含むものとする。
(不足すると認められるとき)
3 法第41条第1項の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
(滞納者)
4 法第41条第2項の「滞納者」とは、納付通知書を発する先において人格のない社団等が滞納者であれば足り、その財産の払戻し又は分配をした時において滞納者であることを要しない。
(法第34条との関係)
5 人格のない社団等が、解散の決議をしたときその他社会通念上解散したとみられるときは、法第41条第2項の規定の適用はなく、法第34条((清算人等の第二次納税義務))の規定が適用される場合がある。
(1年以上前)
6 法第41条第2項の「1年以上前にされている場合は、この限りでない」とは、法定納期限の1年前の応答日以前に払戻し又は分配した場合は法第41条第2項の規定の適用がないことをいう。この場合の応答日については、通則法第10条第2項((期限の特例))の規定は適用されない。
納税義務の範囲
7 法第41条第2項の「財産の価額」とは、払戻し又は分配がされた時におけるその財産の価額をいう。
第32条関係 第二次納税義務の通則
納税義務の成立
1 第二次納税義務は、法第33条から第39条まで又は第41条((無限責任社員等の第二次納税義務))に規定する特定の納税者が国税を滞納し、かつ、それらの条に規定する要件を満たすことによって成立する。
なお、第二次納税義務が成立し、納付通知書による告知をした後にその成立要件となった事実に変更があっても、いったん確定した第二次納税義務には影響がない(昭和47.5.25最高判)。
納付通知書による告知
(告知)
2 法第32条第1項の規定による告知は、抽象的に成立していた第二次納税義務を具体的に確定する効力を有するもので、通則法第36条((納税の告知))の規定による納税の告知と同様の法律的性質を有する(昭和37.3.23大阪地判、昭和42.11.21名古屋地判)。この場合において、その効力は、納付通知書が送達された時に生ずる。 (注)1 納付通知書は、主たる納税者(第二次納税義務の基因となった納税義務を負う者をいう。以下同じ。)に対する督促の有無を問わず発することができる。
2 法第32条第1項の規定による告知は、主たる納税者の国税が滞納になっている間はすることができる(昭和50.8.27最高判参照)。
(納付通知書)
3 法第32条第1項の「納付通知書」とは、令第11条第1項各号(納付通知書の記載事項)に掲げる事項を記載した規則第3条((書式))に規定する別紙第1号書式による。
(徴収しようとする金額)
4 納付通知書に記載すべき令第11条第1項第3号((納付通知書に記載すべき事項))の「徴収しようとする金額」については、それぞれ次に掲げる旨を記載するものとする。 (1) 無限責任社員の第二次納税義務(法33条)については、主たる納税者の滞納国税(第二次納税義務の基因となった国税に限る。以下4において同じ。)の全額
(2) 財産等の価額を限度とする第二次納税義務(法34条、35条、36条3号、39条、41条2項)については、その財産等の価額(金額で表示する。)を限度として主たる納税者の滞納国税の全額
(3) 財産を限度とする第二次納税義務(法36条1号、36条2号、37条、38条、41条1項。以下第32条関係において「物的第二次納税義務」という。)については、その財産(財産自体を表示する。)を限度として主たる納税者の滞納国税の全額 (注) 一つの財産が、物的第二次納税義務に係る財産(以下「追及財産」という。)と他の財産とで構成されている場合における納付通知書に記載する「徴収しようとする金額」には、「追及財産が一つの財産に対して占める割合を限度とする」旨付記する(16の(1)参照)。
(滞納処分費との関係)
5 4の「徴収しようとする金額」を第二次納税義務者から徴収するために要した滞納処分費は、その「徴収しようとする金額」のほかに徴収することができる。ただし、物的第二次納税義務の場合には、その財産以外のものからは徴収(任意納付を含まない。)できないものとする。
(納付の期限)
6 法第32条第1項の納付通知書に記載する納付の期限は、納付通知書を発する日の翌日から起算して1月を経過する日としなければならない(令11条4項)。
(第二次納税義務に関する規定)
7 令第11条第1項第4号((納付通知書に記載すべき事項))の「その者につき適用すべき第二次納税義務に関する規定」とは、第二次納税義務者につき適用することとした法第33条、第34条、第35条、第36条第1号、第36条第2号、第36条第3号、第37条、第38条、第39条、第41条第1項又は同条第2項((無限責任社員等の第二次納税義務))の規定をいう。
(納付の手続)
8 第二次納税義務に係る国税は、主たる納税者の国税であることを記載した納付書によって、その第二次納税義務者の名義により納付させるものとする(国税通則法施行規則(以下「通則規則」という。)5条に規定する別紙第1号書式備考9参照)。
(税務署長に対する通知)
9 法第32条第1項後段の規定により、第二次納税義務者の住所又は居所の所在地を管轄する税務署長に対する通知は、令第11条第2項各号((通知書の記載事項))に掲げる事項を記載した書面により行う。この書面の様式は、別に定めるところによる。
(納付催告書)
10 「納付催告書」とは、令第11条第1項第1号に掲げる事項及び同項第3号((納付通知書に記載すべき事項))に規定する金額を記載した、規則第3条((書式))に規定する別紙第2号書式による。
(別段の定め)
11 法第32条第2項後段の「国税に関する法律に別段の定めがあるもの」とは、通則法第48条第1項((納税の猶予の効果))の規定により新たに督促ができない場合をいうが、同法第105条第2項((不服申立てがあった場合の徴収の猶予等))の規定による徴収の猶予の場合等も、督促が制限される。
通則法の準用
(繰上請求)
12 法第32条第3項において準用する通則法第38条第1項((繰上請求))の規定は、次のとおり読み替えて準用する。 (1) 「納付すべき税額の確定した国税」は、納付通知書により告知した金額
(2) 「納期限」は、納付通知書に記載された納付の期限
(納税の猶予)
13 法第32条第3項において準用する通則法第46条第1項第1号、第2号((災害に係る納税の猶予の要件))及び通則令第15条第1項((納税の猶予の申請書の記載事項))の規定は、次のとおり読み替えて準用する。
なお、通則法第46条第1項第3号及び第3項((納税の猶予の要件))の規定は、準用されない。 (1) 「納期限」は、納付通知書に記載された納付の期限
(2) 「納付すべき税額の確定したもの」は、納付通知書により告知した金額
(3) 「納付すべき国税の年度、税目、納期限及び金額」は、納付通知書に記載された告知年月日、納付の期限及び納付すべき金額並びに主たる納税者の住所、氏名及び滞納税額の年度、税目、納期限、金額
(換価の制限)
14 法第32条第4項に規定する第二次納税義務者の財産の換価の制限については、次のことに留意する。 (1) 法第32条第4項の「換価に付した」とは、公売期日(随意契約により売却する場合には、その売却する期日)を開いたことをいう。 (注) 公売期日を開いた場合には、入札者の有無を問わず「換価に付した」ことになることに留意する。
(2) 第二次納税義務者の差押財産が金銭による取立ての方法により換価するものであるときは、法第32条第4項の制限を受けない。しかし、当該差押財産につき、支払命令の申立て、給付の訴えの提起等の強制的な取立ては、やむを得ない場合を除き、行わないものとする。
(3) 主たる納税者の差押財産が金銭による取立ての方法により換価するもので第二次納税義務者の差押財産が換価するものであるときは、法第32条第4項の制限を受けない。
(価額が著しく減少するおそれがあるとき)
15 法第32条第4項の「価額が著しく減少するおそれがあるとき」とは、差押財産を速やかに換価しなければその価額が著しく減少するおそれがあるときをいい、保存費を多額に要する場合を含むものとする。
物的第二次納税義務の特質
16 物的第二次納税義務については、次のことに留意する。 (1) 第二次納税義務者に対する滞納処分は、追及財産以外のものについては、することができない。
なお、追及財産と他の財産とが一つの財産を構成している場合には、その財産について滞納処分をすることができるものとする。この場合において、公売期日等の前日までに、その財産を追及財産と他の財産とに分割し、その旨及び差押えを解除すべき旨の申出があったときは、他の財産の部分について差押えを解除するものとする。 (注) 一つの財産が、追及財産と他の財産とに分割されないまま換価された場合には、換価代金のうち他の財産の部分に相当するものは、滞納者(第二次納税義務者)に交付する(第129条関係6参照)。
(2) 第二次納税義務者が納付する場合には、追及財産の価額にかかわらず、その第二次納税義務の基因となった主たる納税者の滞納国税が存する限り、その金額に相当する第二次納税義務額について納付しなければならない。ただし、法第37条((共同的な事業者の第二次納税義務))又は第38条((事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務))の規定による物的第二次納税義務額について、追及財産の価額に相当する金額を一時に納付した場合で、徴収上弊害がないと認められるときは、その後は、その第二次納税義務額について追及しない取扱いとしても差し支えない。
(3) 第二次納税義務者が過誤納金及びその還付加算金の請求権を有する場合には、その請求権が追及財産であるときを除き、第二次納税義務者の意思に反する充当はしないものとする(通則令22条1項参照)。
主たる納税義務との関係
(財産の差押えの時期)
17 第二次納税義務者の財産は、主たる納税者の財産の差押えに着手する前に差し押さえても差し支えない。
(納税の猶予)
18 主たる納税者の国税について納税の猶予をしている間は、その国税の第二次納税義務について納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることはできないが、第二次納税義務者に対してした納税の猶予は、主たる納税者には効力を及ぼさない。
(換価の猶予)
19 主たる納税者の国税につき換価の猶予をしても、その国税の第二次納税義務について納付通知書若しくは納付催告書を発し、又は滞納処分をすることは妨げないが、換価については法第32条第4項の規定による制限がある。
(履行等)
20 第二次納税義務者が、その第二次納税義務を履行した場合には、その第二次納税義務の基因となった主たる納税者の納税義務はその履行した額の範囲内において消滅することはもちろんであるが、主たる納税者がその納税義務の一部を履行した場合においても、なお徴収すべき残額の範囲において、その第二次納税義務者の第二次納税義務は存続する。
なお、過誤納金等(国税に係る過誤納金、国税に関する法律の規定による国税の還付金及びこれらについての還付加算金をいう。以下同じ。)の充当による納税義務の消滅についても、上記と同様である。
(免除)
21 第二次納税義務者に対する第二次納税義務の免除は、主たる納税者に対しては効力を及ぼさないが、主たる納税者に対する納税義務の免除は、その納税義務が第二次納税義務の範囲に含まれている限り、その効力が及ぶ。
(更生手続の開始決定の特則)
22 主たる納税者につき会社更生法による更生手続の開始決定があった場合においても、その者の国税に係る第二次納税義務者に対して滞納処分をすることができる(昭和45.7.16最高判)。
(滞納処分の停止による消滅)
23 第二次納税義務者がその第二次納税義務について滞納処分の停止を受け、法第153条第4項又は第5項((滞納処分の停止に係る納税義務の消滅))の規定によりその第二次納税義務が消滅した場合においても、その効力は、主たる納税者に及ばない(第153条関係7参照)。
(過誤納金の還付)
24 納税者及び第二次納税義務者の納付に係る国税の一部につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金の還付又は充当に関しては、まず、第二次納税義務者が納付した額につきその過誤納が生じたものとする(通則令22条1項)。
なお、上記による還付又は充当をした場合においては、国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)、税務署長又税関長(沖縄地区税関長を含む。以下同じ。)は、その旨を主たる納税者に通知しなければならない(通則令22条2項)。
(限定承認の効果)
25 主たる納税者の相続人が相続財産について限定承認をした場合においても、その責任は相続財産に限定されるにすぎないものであることから(通則法5条1項後段)、第二次納税義務に係る国税の納付義務の額には増減がない。 (注) 相続人全員が相続の放棄をした場合又は相続人が不存在の場合には、被相続人の国税を徴収するため、相続財産法人(民法951条)を主たる納税者として、被相続人が生存していたときに第二次納税義務者となるべき者に対し、第二次納税義務の追及をすることができる。
(会社更生法による免責の効果)
26 株式会社である主たる納税者が会社更生法第241条((更生債権等の免責等))の規定により国税の納付義務について免責された場合においても、その効力は株式会社の債務を負担する者に対して有する権利には影響を及ぼさないことから(同法240条2項)、第二次納税義務に係る国税の納付義務の額には増減がない。
(第二次納税義務を負うべき者の破産との関係)
27 第二次納税義務を負うべき者が破産宣告を受けた場合において、破産宣告前に第二次納税義務の成立要件を満たしているとき(ただし、徴収すべき額に不足するかどうかの判定については第33条関係1、第22条関係4参照)は、破産宣告後に納付通知書による告知をした第二次納税義務に係る国税は、財団債権(破産法47条2号)になる。
(時効の中断)
28 第二次納税義務の時効中断の効力は、主たる納税者の納税義務には及ばないが、主たる納税者の納税義務の時効中断の効力は、第二次納税義務に及ぶものとする(民法457条1項参照)。 (注) 主たる納税者の納税義務が時効の完成により消滅するおそれがある場合には、その納税義務の存在確認の訴えの提起等時効中断の措置をとることに留意する(昭和39.3.26東京地判、昭和47.10.17静岡地判等)。
この訴訟において国が勝訴した場合には、主たる納税者の国税の徴収権の消滅時効は10年になる(通則法72条3項、民法174条ノ2第1項)。
第二次納税義務の重複賦課
29 第二次納税義務の成立要件を満たす場合において、その基因となった処分等に基づき税務署長又は他の行政機関等が既に第二次納税義務を負わせているときにおいても、重ねて第二次納税義務を負わせることができる(昭和45.7.29東京地判)。
第二次納税義務に係る国税についての第二次納税義務
30 第二次納税義務者がその第二次納税義務に係る国税を滞納した場合において、他に第二次納税義務の成立要件を満たす第三者がいるときは、第二次納税義務者を主たる納税者として、その第三者に対し、更に第二次納税義務を負わせることができる。
なお、第二次納税義務の成立要件との関係から第二次納税義務に係る国税についての第二次納税義務が成立しない場合がある。例えば、特定の国税(実質所得者課税の原則により課された国税等)についてだけ第二次納税義務を追及できることとされている場合においては、第二次納税義務に係る国税は、この特定の国税に該当しない。
第二次納税義務と詐害行為取消権との関係
31 滞納者が行った法律行為が、第二次納税義務の成立要件と詐害行為取消権の要件(通則法42条、民法424条)の双方を満たす場合には、いずれによることもできる。
第33条関係 無限責任社員の第二次納税義務
納税義務の成立
1 法第33条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
納税義務を負う者
(合名会社又は合資会社)
2 法第33条の「合名会社」とは、無限責任社員だけから成る会社をいい(商法80条参照)、「合資会社」とは、有限責任社員(同法157条参照)と無限責任社員とから成る会社をいう(同法146条)。
(社員又は無限責任社員)
3 法第33条の「社員」又は「無限責任社員」とは、会社の債務につき、一定の条件の下に、会社債権者に対し、直接に連帯無限の責任を負担する社員をいう(商法80条、147条)。
(新入社員等の責任)
4 会社が成立した後に無限責任社員となった者(例えば、新たに無限責任社員として加入した者、合資会社の有限責任社員から無限責任社員となった者、無限責任社員の持分を譲り受けた者、定款の定めるところに従い被相続人に代わって無限責任社員となった相続人等をいう。)は、無限責任社員となる前に成立した会社の国税についても責任を負う(商法82条、147条、160条)。
(退社した社員等の責任)
5 退社し、又は持分の全部を譲渡した無限責任社員及び合資会社の無限責任社員から有限責任社員となった者は、本店の所在地において退社の登記又は責任変更の登記をする前に成立した会社の国税について責任を負うが、この責任は、その登記後2年内に納付通知書による告知又はその予告をしなかった場合には、登記後2年(除斥期間)を経過した時に消滅する(商法93条、147条、160条参照)。 (注) 上記の予告については、次のことに留意する。 1 成立した会社の国税について、その税額の確定前においても、予告をすることができる。
2 予告は、書面により、将来納付通知書による告知をすることがある旨を記載して行うものとする。
(解散後の責任)
6 合名会社又は合資会社が解散した場合において、本店所在地において解散の登記をした後5年内に納付通知書による告知又はその予告をしなかったときは、無限責任社員の責任は、その登記後5年(除斥期間)を経過した時に消滅する(商法145条1項、147条)。
(無限責任社員の相続人)
7 無限責任社員が死亡した場合には、死亡前に成立した会社の国税についての無限責任社員の責任は相続人に承継されるが、死亡後退社登記前に成立した会社の国税についての無限責任社員の責任は承継されない(昭和10.3.9大判)。
なお、相続人が承継する責任の存続期間は、被相続人の負担する責任の存続期間の残存期間であるから、例えば、その無限責任社員が死亡により退社したとき又は既に生前退社していたときは、本店所在地における退社の登記日から2年間であり、解散登記後に死亡したときは、解散登記日から5年間である。
納税義務の範囲
(不足額との関係)
8 無限責任社員から徴収することができる金額は、合名会社又は合資会社から滞納処分により徴収することができる滞納に係る国税の全額であって、会社財産が徴収すべき国税の額に不足すると認められる場合のその不足する額に限られない。
(連帯納税義務)
9 法第33条の無限責任社員相互間における「連帯」については、通則法第8条((国税の連帯納付義務についての民法の準用))の規定が適用される。
第34条関係 清算人等の第二次納税義務
納税義務の成立
(法人が解散した場合)
1 法第34条の「法人が解散した場合」とは、株主総会その他これに準ずる総会等で解散の日を定めたときはその日が経過したとき、解散の日を定めなかったときは解散決議をしたとき、解散事由の発生により解散したときはその事由が発生したとき、裁判所の命令又は裁判により解散したときはその命令又は裁判が確定したとき、主務大臣の命令により解散したときはその命令が効力を生じたとき、休眠会社がみなす解散となったとき等をいう(商法58条、112条、147条、406条ノ2,406条ノ3、有限会社法71条ノ2、中小企業等協同組合法106条2項、宗教法人法43条1項、2項、会社更生法261条1項等)。ただし、商法第101条((合併の登記))、第114条((組織変更の登記))、有限会社法第62条((合併の登記))等の規定による解散の登記をしたときは含まれない。
なお、上記の解散は、その登記の有無を問わない。 (注)1 法人が解散しないで事実上解散状態にある場合には、その法人の財産の配分等がされているときでも、法第34条の規定を適用することはできないが、法第39条((無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務))、通則法第42条((債権者の代位及び詐害行為の取消し))等の規定を適用できる場合があることに留意する。
2 1人の株主が発行済株式の全部を所有する株式会社(以下「一人会社」という。)にあっては、客観的事実(例えば、営業譲渡をした後に廃業しているような場合)から解散したと認められる場合には、法第34条の「解散した場合」に該当する(昭和44.3.18大阪地判、昭和46.6.24最高判参照)。また、一人会社と同様に認められるような株式会社又は有限会社についても、同様である(昭和52.2.14最高判参照)。
(課されるべき国税)
2 法第34条の「法人に課されるべき、又はその法人が納付すべき国税」とは、法人が結果的に納付しなければならないこととなるすべての国税をいい、解散の時又は残余財産の分配又は引渡し(以下第34条関係において「分配等」という。)の時において成立していた国税に限られない。
(分配又は引渡し)
3 法第34条の「分配」とは、法人が清算する場合において、残余財産を社員、株主、組合員、会員等(以下第34条関係において「社員等」という。)に、原則としてその出資額に応じて分配することをいい(民法688条2項、商法68条、147条、425条、有限会社法73条等)、「引渡」とは、法人が清算する場合において、残余財産を民法第72条((残余財産の帰属))等の規定により処分することをいう(宗教法人法50条、医療法56条等)。
なお、上記の「分配」又は「引渡」は、法人が解散した後に行ったものに限らず、解散を前提にそれ以前に行った分配又は引渡しも含まれる(昭和47.9.18東京地判)。
(不足すると認められる場合)
4 法第34条の「徴収すべき額に不足すると認められる場合」は、第22条関係4と同様である。
ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
納税義務を負う者
(清算人)
5 法第34条の「清算人」とは、解散法人(合併により解散した法人及び破産した法人を除く。)の清算事務を執行する者で分配等をした者をいい、納付通知書を発する時において清算人でない者も含まれる。
なお、分配等が清算人会の決議に基づいてされたときは、その決議に賛成した清算人はその分配等をしたものとみなし、またその議事録に異議をとどめなかった清算人はその決議に賛成したものと推定するものとする(商法430条2項、266条2項、3項参照)。また、清算人に就任することを承諾した上、清算事務を第三者に一任している者は、直接に清算事務に関与しなくても法第34条の「清算人」に該当する(昭和52.2.14最高判)。
(任意清算の場合)
6 商法第117条第1項((任意清算))(147条において準用する場合を含む。)の規定による任意清算の場合には、清算人が置かれないことがあるが、この場合にも、分配等を受けた者については、法第34条の規定が適用される。
納税義務の範囲
(責めに任ずる)
7 法第34条ただし書の「責に任ずる」とは、清算人は分配等をした財産の価額を、分配等を受けた者はその受けた財産の価額を、それぞれ限度として第二次納税義務を負うことをいうものとする。
(財産の価額)
8 法第34条の「財産の価額」とは、分配等がされた時におけるその財産の価額をいう。
(清算人が2人以上ある場合)
9 清算人が2人以上ある場合における第二次納税義務の範囲については、次のことに留意する。 (1) 各清算人がそれぞれ別個に分配等をした場合は、その分配等をした財産の価額を、それぞれその限度とする。
(2) 清算人が分配等に係る清算人会の決議に賛成した場合は、その分配等に係る財産の価額の全額を、それぞれその限度とする(5のなお書参照)。
(3) 清算人が共同行為により分配等をした場合は、その分配等をした財産の価額の全額を、それぞれその限度とする。
(第二次納税義務者相互の関係)
10 同一の分配等に基づく法第34条の第二次納税義務者が2人以上ある場合には、それらの者相互の関係は、次のとおりとする。 (注) 2回以上の分配等が行われ、それぞれの分配等ごとに法第34条の第二次納税義務者がある場合においては、第二次納税義務者の1人につき生じた事由は、異なる回の分配等に基づく第二次納税義務者には、影響を及ぼさない。
なお、上記の場合において、第二次納税義務者の納付等により主たる納税者の国税が消滅したときは、その主たる納税者の国税につき生じた効果が、他の第二次納税義務者に影響を及ぼす場合があることはもちろんである(第32条関係20参照)。 (1) 第二次納税義務者の1人につき生じた履行(納付、過誤納金等の充当、法129条1項及び2項の規定に基づく国税の消滅をいう。以下10において同じ。)以外の事由は、他の第二次納税義務者の第二次納税義務には、影響を及ぼさない。
(2) 第二次納税義務者の1人がその第二次納税義務を履行した場合には、その履行による第二次納税義務の消滅が他の第二次納税義務者の第二次納税義務の範囲に含まれている限り、その第二次納税義務も消滅する。この場合における「範囲に含まれている」かどうかの判定は、分配等に係る財産の価額を基準として行う。 (注) 分配等に係る財産の価額から第二次納税義務者の限度額を控除した額を超える額につき、他の第二次納税義務者の履行があったときは、その超える額が、上記の「範囲に含まれている」ことになる。 〔例〕 主たる納税者の国税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50万円
分配をした財産の価額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
精算人 甲・・・・・・・・・・・・・・・・・・10万円
限度額 分配を受けた者 乙・・・・・・・・・・・・・6万円
分配を受けた者 丙・・・・・・・・・・・・・4万円
イ 甲が3万円履行したとき。
甲の責任は、残額7万円(甲の限度額10万円-甲の履行額3万円)となる。乙、丙の限度額はその7万円に満たないから、甲の履行は乙及び丙には影響がない。
ロ 甲が5万円履行したとき。
甲の責任は、残額5万円(甲の限度額10万円-甲の履行額5万円)となる。甲の履行によりその残額5万円が責任の最高限度になることから、乙の責任は、1万円減少(乙の限度額6万円-その残額5万円)して残額5万円となる。丙の責任(4万円)は、5万円に満たないから、甲の履行は丙には影響がない。
ハ 甲が7万円履行したとき。
甲の責任は、残額3万円(甲の限度額10万円-甲の履行額7万円)となる。甲の履行によりその残額3万円が責任の最高限度になることから、乙の責任は、3万円減少(乙の限度額6万円-その残額3万円)して残額3万円に、丙の責任は、1万円減少(丙の限度額4万円-その残額3万円)して残額3万円となる。
ニ 乙が2万円履行したとき。
乙の責任は、残額4万円(乙の限度額6万円-己の履行額2万円)となる。乙の履行により8万円が責任の最高限度になることから、甲の責任は、2万円減少(甲の限度額10万円-その残額8万円)して残額8万円となる。丙の責任(4万円)は、8万円に満たないから、乙の履行は丙には影響がない。
ホ 乙が6万円履行したとき。
乙の責任は、0(乙の限度額6万円-乙の履行額6万円)となる。乙の履行によりその残額4万円が責任の最高限度になることから、甲の責任は、6万円減少(甲の限度額10万円-その残額4万円)して残額4万円となる。丙の責任(4万円)は、4万円と同額であることから、乙の履行は丙には影響がない。
ヘ 丙が4万円履行したとき。
丙の責任は、O(丙の限度額4万円-丙の履行額4万円)となる。丙の履行によりその残額6万円が責任の最高限度になることから、甲の責任は、4万円減少(甲の限度額10万円-その残額6万円)して残額6万円となる。乙の責任の残額(6万円)は6万円と同額であることから、丙の履行は乙には影響がない。
商法との関係
(商法第118条等との関係)
11 任意清算中の合名会社が、商法第117条第3項((任意清算))において準用する第100条第1項又は第3項((債権者の異議))の規定に違反して財産を処分した場合において、その処分が残余財産の分配に該当するときは、法第34条の規定の適用があるが、その他の処分であるときは、同法第118条((会社債権者の保護))の規定により、その処分の取消しを裁判所に請求することができる。
なお、合資会社の場合も上記と同様である(商法147条)。
(商法第421条等との関係)
12 商法第421条((会社債権者に対する催告))(有限会社法75条1項、信用金庫法64条等において準用する場合を含む。)の規定は、国税については適用されない(明治38.10.11行判)。
(清算結了登記との関係)
13 株式会社等が課されるべき国税又は納付すべき国税を完納しないで清算結了の登記をしても、その登記は適法な清算結了に基づくものではないから、会社は清算のために必要な範囲においてなお存続し、課されるべき国税又は納付すべき国税は消滅しない(大正6.7.24行判)。
(商法第406条等との関係)
14 株式会社、有限会社等が解散し、残余財産を分配した後において、商法第406条((会社の継続))、有限会社法第70条((会社の継続))等の規定により会社を継続した場合には、継続の特別決議によって残余財産の分配の効果は将来に向かって消滅する。したがって、この継続の特別決議後は、残余財産はなかったことになるから、法第34条の規定による第二次納税義務を負わせることはできない。
第35条関係 同族会社の第二次納税義務
納税義務の成立
(会社)
1 法第35条第1項の「会社」とは、合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社をいい(商法53条、有限会社法89条)、相互会社(保険業法3章参照)は含まれない。
(同族会社の判定)
2 法第35条第1項の「同族会社」に該当するかどうかの判定は、会社の株主又は社員のうち、滞納者とその持株数(端株数を含む。以下第35条関係において同じ。)又は出資の金額が最も大きい者から順次に選定した株主(端株主を含む。以下第35条関係において同じ。)又は社員との組合せによって、法人税法第2条第10号((同族会社の定義))の同族会社に該当するかどうかにより行うものとする。
なお、法第35条の株主又は社員は、株主名簿、社員名簿、端株原簿の記載等にかかわらず、実質上の株主又は社員をいい、また株券の発行前における株式の譲渡がされている場合には、その譲受人をいうものとする。 (注) 端株とは、記名株式の1株に満たない端数で、1株の100分の1の整数倍に当たるものをいう(商法230条ノ2)。
(出 資)
3 法第35条の「出資」とは、合名会社、合資会社又は有限会社の持分をいう。
(不足すると認められるとき)
4 法第35条第1項の「徴収すべき国税に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
(買受人がない場合)
5 法第35条第1項第1号の「買受人がない」とは、滞納処分による換価をした場合において、売却決定を受けた者がないとき及び売却決定が取り消されたときをいう。
(合名会社等の持分の譲渡制限)
6 合名会社及び合資会社の持分は、商法第73条(持分の譲渡)、第147条((合名会社の規定の準用))及び第154条((有限責任社員の持分の譲渡))の規定によって無限責任社員全員の同意がなければ譲渡できないから、例えば、換価前に無限責任社員のうち1人でも換価による持分の譲渡に反対の意思表示をした場合は、法第35条第1項第2号に該当する。
(株券又は端株券が発行されていない場合)
7 法第35条第1項第2号の「株券若しくは端株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること」とは、株券又は端株券の作成及び交付がされていないために、株式を差し押さえて換価することにつき支障があることをいう。
なお、この場合においては、次のことに留意する。 (1) 合理的な期間内に株券又は端株券が発行される(商法226条1項、230条ノ3第1項参照)見込みがあるとき及び株式の申込証拠金領収証等の書面を株券に準じて差し押さえて換価できるとき(第56条関係16参照)は、法第35条第1項第2号の事由に当たらないものとして取り扱う。
(2) 株券又は端株券が発行されていない場合において、その交付請求権を差し押さえたにもかかわらず、指定した期限までに会社が株券又は端株券を交付しないときは、法第35条第1項第2号の事由に当たる。
納税義務の範囲
(納付すべき国税)
8 法第35条第1項の「納付すべき国税」には、所得税法第142条第2項((純損失の繰戻しによる還付))(166条において準用する場合を含む。)又は法人税法第81条第6項((欠損金の繰戻しによる還付))の規定により還付した金額に係る還付加算金(通則法58条1項)があったときは、その還付加算金のうち修正申告又は更正によって減少する還付金の額に相当する所得税額又は法人税額に対応する部分の金額が含まれる(通則法19条4項3号ハ、28条2項3号ハ参照)。
(申告等があった日)
9 法第35条第1項の「還付の基因となった申告、更正又は決定があった日」とは、還付金の額に相当する国税を減少させる修正申告又は更正があった場合において、還付の基因となった申告、更正又は決定があった日をいう。
なお、修正申告又は更正により納付すべき国税が還付金の額を超えることとなった場合には、その超えることとなった国税の額に相当する部分の国税の法定納期限は、当該国税の本来の法定納期限である。 〔例1〕
所得税の確定申告により生じた還付金10万円を還付した後、その還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告により納付すべき所得税が1万円生じた場合については、その確定申告があった日が法定納期限となる。 (注) 申告書が郵便により提出された場合の「申告があった日」については、通則法第22条((郵送に係る納税申告書の提出時期))の規定の適用がある。
〔例2〕
所得税の減額更正により生じた還付金8万円を還付した後、その還付金の額に相当する税額を減少させる修正申告により納付すべき所得税が1万円生じた場合については、その減額更正があった日が法定納期限となる。
〔例3〕
通則法第25条((決定))の規定による決定により生じた還付金6万円を還付した後、その還付金の額に相当する税額を減少させる再更正により納付すべき法人税1万円が生じた場合については、その決定があった日が法定納期限となる。
(1年以上前)
10 法第35条第1項の「1年以上前に取得したものを除く」とは、法定納期限の1年前の応当日以前に取得したものを除くことをいう。この場合の応当日については、通則法第10条第2項((期限の特例))の規定は適用されない。
(相続等があった場合の株式等の取得時期)
11 相続等があった場合における法第35条第1項の「取得」の時期は、次による。 (1) 相続により承継された国税と相続により承継した株式又は出資との関係においては、被相続人が株式又は出資を取得した日
(2) 相続人の固有の国税と相続により承継した株式又は出資との関係においては、相続があった日
(3) 合併により承継された国税と合併により承継した株式又は出資との関係においては、合併により消滅した法人が株式又は出資を取得した日
(4) 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の固有の国税と合併により承継した株式又は出資との関係においては、合併があった日
(5) 合併後存続する法人又は合併により設立した法人の株式又は出資を有する場合において、その株式又は出資の取得が、合併により消滅した法人の株式又は出資を有していたことによる場合は、合併があった日
(徴収できる国税と株式又は出資との関係)
12 法第35条の規定により同族会社に対して第二次納税義務を負わせることができる場合の国税は、その会社の株式又は出資を納税者が取得した日から起算して1年を経過する日以前にその法定納期限があるものに限られる(法35条1項)。
(資産及び負債の額の計算)
13 法第35条第2項の「資産の総額」及び「負債の総額」の算定に当たっては、法第32条第1項((納付通知書による告知等))の規定による納付通知書を発する日における財産目録又は貸借対照表を参考として、その日における会社財産の適正な価額を計算するものとする。この場合において、上記の納付通知に係る第二次納税義務は、負債に含めないものとする。
なお、上記の資産及び負債の額の計算は、原則として納付通知書を発する日の現況によるが、特に徴収上支障がない限り、その日の直前の決算期(中間決算を含む。)の貸借対照表、財産目録又は法人税の決議書を参考として行っても差し支えない。
(現物、労務又は信用による出資)
14 法第35条第2項の「出資の数」については、現物、労務又は信用をもって出資の目的とした場合には、出資の評価についての定款による価額又は評価の基準によって、納税者の有する出資の価額を計算し、その価額を現金による出資の価額と同様に取り扱って、出資の数を計算するものとする。
第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務
納税義務の成立
(滞納者)
1 法第36条の「滞納者」には、第二次納税義務者及び保証人は含まれない。
(国 税)
2 法第36条第1号から第3号に規定する規定により課された国税(以下2において「実質課税に係る部分の国税」という。)が、一つの国税(一つの申告、更正又は決定の通知によって国税の額が確定したものをいう。以下2、第37条関係3及び第38条関係13において同じ。)の一部であるときは、その国税の額の算定は、次に掲げるところによる。
(1) 法第36条第1号又は第3号に規定する規定により課された国税の額は、次の算式により計算して得た金額とする(令12条1項)。
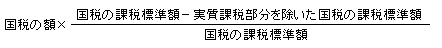
(注)1 上記の課税標準額とは、一つの国税の額に対応する課税標準額をいうものとする。
2 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税について上記の計算をする場合には、上記の課税標準額は、これらの加算税の計算の基礎となった国税の課税標準額をいうものとする。
(2) 法第36条第2号に規定する規定により課された消費税の額は、次の算式により計算して得た金額とする(令12条1項)。
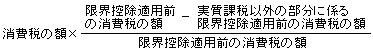
(注) 過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税について上記の計第をする場合は、上記の「限界控除適用前の消費税の額」は、これらの加算税の計算の基礎となった限界控除適用前の消費税の額をいうものとする。
(3) 国税の一部につき納付又は充当があった場合は、その納付又は充当は、まず、上記(1)又は(2)以外の部分の金額についてされたものとする(令12条2項)。
(4) 国税の一部につき免除があった場合は、その免除は、まず、上記(1)又は(2)以外の部分の金額についてされたものとする(令12条2項)。ただし、その免除が、実質課税に係る国税についてされたことが明らかであるときは、実質課税に係る部分の国税について免除されたものとする。
(5) 国税の一部につき更正の取消し、軽減等があり税額が減少した場合における実質課税に係る部分の国税の額の計算は、(4)に準ずる。
(不足すると認められるとき)
3 法第36条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。
ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
(実質課税)
4 法第36条第1号の「所得税法第12条(実質所得者課税の原則)又は法人税法第11条(実質所得者課税の原則)の規定により課された国税」及び法第36条第2号の「消費税法(昭和63年法律第108号)第13条(資産の譲渡等を行った者の実質判定)の規定により課された国税」は、その所得税、法人税又は消費税が、申告、更正又は決定のいずれによるかを問わない。
(所得の帰属推定による課税)
5 法第36条第1号の「所得税法第158条(事業所の所得の帰属の推定)の規定により課された国税」とは、通則法第24条から第26条まで(更正、決定、再更正)の規定による更正又は決定に係る所得税をいう。
(資産の譲渡等を行った者の実質判定)
6 法第36条第2号の「消費税法(昭和63年法律第108号)第13条(資産の譲渡等を行った者の実質判定)の規定により課された国税(同法第2条第1項第8号(定義)に規定する貸付けに係る部分に限る。)」とは、消費税法第13条の規定により課された消費税のうち、事業として対価を得て行われる資産の貸付けに基因して課されたものに限られることに留意する。
(同族会社の行為計算否認による課税)
7 法第36条第3号の「所得税法第157条(同族会社等の行為又は計算の否認)、法人税法第132条(同族会社等の行為又は計算の否認)又は相続税法第64条(同族会社の行為又は計算の否認)の規定により課された国税」とは、通則法第24条から第26条まで(更正、決定、再更正)の規定による更正若しくは決定に係る所得税、法人税、相続税又は贈与税をいう。
納税義務を負う者
(第1号の場合)
8 法第36条第1号の「収益が法律上帰属するとみられる者」とは、4の実質課税の場合には、所有権の名義人又は事業の名義人等、通常であれば、その者がその財産又は事業から生ずる収益を享受する者であるとみられる者をいい、5の所得の帰属推定による課税の場合には、事業所の属する法人をいう。
(第2号の場合)
9 法第36条第2号の「貸付けを法律上行ったとみられる者」とは、単なる名義人であってその資産の貸付けに係る対価を享受しない者をいう。
(第3号の場合)
10 法第36条第3号の「否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となった行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者」については、次のことに留意する。 (1) 「納税者」とは、6の同族会社等の行為計算否認による課税により国税の納税義務を負う者をいい、納税者の「行為」とは、納税者が当事者となっている行為をいう。
(2) 「否認された計算の基礎となった行為」とは、同族会社等の行為(例えば、譲渡行為)自体は否認しないが、その行為に係る計算(例えば、譲渡価額の計算)を否認した場合におけるその計算のもととなった行為(例えば、上記の譲渡行為)をいう。
(3) 「利益を受けたものとされる者」とは、納税者の行為について、行為又は計算の否認理由との関係からみて不当な経済的利益を受けたと認められる者をいう。
納税義務の範囲
(収益が生じた財産)
11 法第36条の「収益が生じた財産」とは、資産から生じた収益に関する実質課税の場合にはその資産、事業から生じた収益に関する実質課税の場合にはその事業に属する資産、法人の事業所の所得の帰属推定による課税の場合にはその事業所の事業に属する資産をいうが、なお次のことに留意する。 (1) 収益が生じた資産又は事業(事業所の事業を含む。以下第36条関係において同じ。)が、譲渡等により、滞納処分時において、既に8の第二次納税義務者に法律上帰属するとみられない場合には、その資産又は事業に属する資産に対しては、第二次納税義務を追及できない(取得財産に対する追及については、12参照)。
(2) 事業に属する資産は、滞納処分時現在において、その事業に属するものである。したがって、資産がその事業に属することとなった時期が、課税時又は納付通知等の前であるか後であるかを問わない。 (注) 事業に属していた資産が、譲渡等により滞納処分時現在において事業に属しない場合には、その資産に対しては第二次納税義務を追及できない(この場合の取得財産に対する追及については、12の(2)参照)。
(3) 事業に属する資産であっても、その事業の名義人である第二次納税義務者に法律上帰属するとみられない資産(例えば、第三者から賃借している資産)に対しては、第二次納税義務を追及できない。
(異動によって取得した財産)
12 法第36条の「その財産の異動により取得した財産」とは、11の収益が生じた財産(資産又は事業)及び14の貸付けに係る財産について、その交換によって取得した財産(資産又は事業)、売却によって取得した代金、滅失によって取得した保険金等をいうが、なお次のことに留意する。 (1) 2回以上の異動により取得した財産(例えば、収益が生じた財産の売却代金をもって購入した財産)も、その異動の経過が明らかなものは、異動により取得した財産とする。
(2) 事業に属する資産の異動によって取得した資産は、それがその事業に属しない場合に限り、収益が生じた財産の異動により取得した財産に含まれる。 (注) 事業に属する資産の異動によって取得した資産が、その事業に属する場合については、11の(2)参照。
(3) 収益が生じた財産の異動により取得した財産が、第二次納税義務者に法律上帰属するとみられない場合には、その財産に対しては、第二次納税義務を追及できない。
(基因して取得した財産)
13 法第36条の「これらの財産に基因して取得した財産」とは、11の収益が生じた財産及び12の異動により取得した財産について、その天然又は法定の果実及び権利の使用料等をいう。
(貸付けに係る財産)
14 法第36条第2号の「貸付けに係る財産」とは、事業として対価を得て行われる資産の貸付けの目的となる財産をいうが、なお次のことに留意する。 (1) 「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含む(消費税法2条2項)。 (注)1 「資産に係る権利の設定」とは、例えば、土地に係る地上権若しくは地役権、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。)に係る実施権若しくは使用権又は著作物に係る出版権の設定をいう。
2 「資産を使用させる一切の行為」とは、例えば次のものをいう。 (1) 工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権並びにこれらの権利に係る出願権及び実施権をいう。)の使用、提供又は伝授
(2) 著作物の複製、上演、放送、展示、上映、翻訳、編曲、脚色、映画化その他著作物を利用させる行為
(2) 貸付けに係る財産が、譲渡等により、課税の基礎となった貸付けを法律上行ったとみられる者に、滞納処分時現在において既に法律上帰属すると認められない場合は、第二次納税義務を追及できない(この場合の取得財産に対する追及については、12及び13参照)。
(受けた利益の額)
15 法第36条の「受けた利益の額」とは、10の(3)の利益を受けたものとされる者(第二次納税義務者)が受けたその利益の額をいう。
なお、上記の利益が、滞納処分時現在において現存するかどうかは、法第36条第3号の第二次納税義務には関係ない。
第37条関係 共同的な事業者の第二次納税義務
納税義務の成立
(重要な財産)
1 法第37条の「事業の遂行に欠くことができない重要な財産(以下第37条関係において「重要財産」という。)であるかどうかは、納税者の事業の種類、規模等に応じ判断すべきであるが、一般には、判断の対象とする財産がないものと仮定した場合に、その事業の遂行が不可能になるか又は不可能になるおそれがある状態になると認められる程度に、その事業の遂行に関係を有する財産をいう。
なお、法第37条第1号又は第2号に掲げる者が2人以上ある場合には、納税者の事業に供しているこれらの者が有する財産を一体として考え、それが事業の遂行に欠くことができない重要財産であるかどうかを判定するものとする (注) 法第37条の「重要な財産」には、滞納処分ができる財産だけでなく、滞納処分ができない財産も含まれる。
(財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている場合)
2 法第37条の「財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている場合」とは、重要財産から直接又は間接に生ずる所得が納税者の所得となっている場合及び所得税法その他の法律の規定又はその規定に基づく処分により納税者の所得とされる場合をいうものとし、例えば、次に掲げる場合がある。 (1) 所得税法第56条((事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例))の規定により、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族がその納税義務者の経営する事業で不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべきものから所得を受ける場合で、その所得が納税者の所得とされる場合
(2) 法人税法第132条((同族会社等の行為又は計算の否認))の規定により、同族会社の判定の基礎となった株主又は社員の所得が同族会社の所得とされる場合
(3) 同族会社の判定の基礎となった株主又は社員の所有する財産をその同族会社が時価より低額で賃借りしているため、その時価に相当する借賃の金額とその低額な借賃の金額との差額に相当するものが同族会社の実質的な所得となっている場合(昭和48.10.15広島高岡山支判)
(4) 納税者と生計を一にする配偶者その他の親族が所有する公債、社債、無記名の株式又は無記名の貸付信託若しくは証券投資信託の受益証券について、納税者が利子、配当、利益又は収益の支払を受けている場合
(5) 納税者の事業の収支計算では損失が生じているが、重要財産から直接又は間接に生ずる収入が納税者の収益に帰属している場合
(供されている事業に係る国税)
3 法第37条の「供されている事業に係る国税」が、一つの国税の一部である場合の国税の額の算定については、第36条関係2と同様である(令12条3項)。
なお、重要財産が供されている事業に係る国税は、その納税者の事業に係る国税のうち、その重要財産が供されていた期間に対応する部分の国税の額に限るものとする。
(事業に係る国税)
4 法第37条の「事業に係る国税」とは、納税者が同族会社であるときはすべての国税を、個人であるときは次に掲げる国税を、それぞれいうものとする。 (1) 所得税のうち所得税法第27条((事業所得))の事業所得に係るもの
(2) 所得税(源泉所得税を含む。)のうち(1)の事業所得に係る所得税以外の所得に係る所得税については、これらの事業に係るもの(例えば、納税者が小売業を経営している場合において、その事業に係る所得と譲渡所得とがある場合には、事業所得に係る所得税を、また小売業の従業員に係る源泉所得税と家事使用人に係る源泉所得税とがある場合には、その小売業の従業員に係るもの)
(3) 消費税等(消費税を除く)については、重要財産が供されている物品に係るもの
(4) 消費税
(5) 登録免許税、再評価税、有価証券取引税及び印紙税は、事業に係るこれらの国税
(不足すると認められるとき)
5 法第37条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。
ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
納税義務を負う者
(生計を一にする)
6 法第37条第1号の「生計を一にする」とは、有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい、納税者がその親族と起居をともにしていない場合においても、常に生活費、学資金又は療養費等を送金して扶養しているときは、生計を一にするものとする。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
(親族)
7 法第37条第1号の「親族」とは、民法第725条各号((親族の範囲))に掲げる者のうち、配偶者以外の納税者と生計を一にする者、すなわち納税者と生計を一にする者の六親等内の血族及び三親等内の姻族をいう。
(納税者の経営する事業)
8 法第37条第1号の「納税者の経営する事業」とは、納税者が経営する事業のすべてをいい、重要財産が供されている事業だけをいうものではない。
(所得を受けている)
9 法第37条第1号の「所得を受けている」とは、納税者から、その経営する事業の計算において給料、賃貸料、配当、利息又は収益の分配等その名称のいかんを問わず実質的に所得を受けていることをいう。
(第1号の判定の時期)
10 重要財産を有している者が、法第37条第1号に掲げる者に該当するかどうかは、その財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている時期の現況において判定するものとする。
(第2号の判定の時期)
11 法第37条第2号の「その事実のあった時」とは、同族会社の判定の基礎となった株主又は社員が重要財産を有し、かつ、その財産に関して生ずる所得が納税者の所得となっている事実があった時期をいう。
納税義務の範囲 編注13
12 法第37条の「取得財産」の意義については、第36条関係10及び11と同様である。
第38条関係 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務
納税義務の成立
(特殊関係者)
1 法第38条の「その親族その他納税者と特殊な関係のある個人又は同族会社(これに類する法人を含む。)で政令で定めるもの」とは、令第13条第1項((納税者の特殊関係者の範囲))に規定する者(以下「親族その他の特殊関係者」という。)をいう。この場合において、同項各号に掲げる者に該当するかどうかの判定は、納税者がその事業を譲渡した時の現況によるから(令13条2項)、その後離婚、解雇等によって各号に掲げる者に該当しないこととなっても、法第38条の規定が適用される。 (注) 財産分与(民法768条、771条)として行われた事業譲渡について、その事業譲渡が財産分与として祉会通念上相当と認められる場合には、法第38条の規定を適用しないものとする。
(配偶者、直系血族等)
2 令第13条第1項第1号((納税者の特殊関係者の範囲))の「配偶者」又は「直系血族及び兄弟姉妹」には、納税者と生計を一にしていない者も含まれる。
(親 族)
3 令第13条第1項第2号((納税者の特殊関係者の範囲))の「親族」とは、民法第725条((親族の範囲))に規定する親族のうち、配偶者、直系血族及び兄第姉妹を除いた六親等内の血族及び三親等内の姻族をいう。
(生計を一にする)
4 令第13条第1項第2号((納税者の特殊関係者の範囲))の「生計を一にする」は、第37関係6と同様である。
(生計の維持)
5 令第13条第1項第2号から第4号まで((納税者の特殊関係者の範囲))の「生計を維持」とは、給付を受けた金銭その他の財産及びその金銭その他の財産の運用によって生ずる収入を日常生活の資の主要部分(おおむね2分の1以上とする。)としていることをいう。
(特別の金銭等)
6 令第13条第1項第3号及び第4号((納税者の特殊関係者の範囲))の「特別の金銭」とは、給料、俸給、報酬、売却代金等の役務又は物の提供の対価として受ける金銭以外で、対価なく又はゆえなく対価以上に受ける金銭をいい、また、「特別の財産」についても、おおむねこれと同様である。
(財産の提供)
7 令第13条第1項第4号((納税者の特殊関係者の範囲))の「財産を提供して」いる場合には、財産を譲渡している場合のほか、賃貸等により利用させている場合も含まれる。
(同族会社に該当する他の会社)
8 令第13条第1項第7号((納税者の特殊関係者の範囲))の「同族会社に該当する他の会社」とは、具体的には下図のA1,A2,B1,B2,C1,C2,D1,D2,E1及びE2をいう。
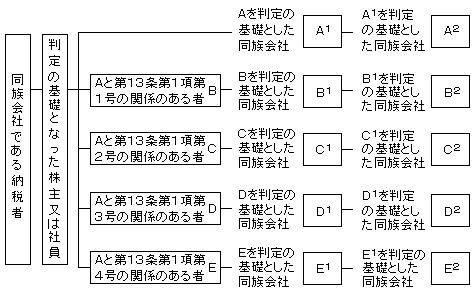
(注)1 上図のうちA,B,C,D及びEは、令第13条第1項第5号((納税者の特殊関係者の範囲))に該当する。
2 令第13条.第1項第7号かっこ書((納税者の特殊関係者の範囲))のうち前者の「これらの者」とは上図のAをいい、後者の「これらの者」とは上図のA,B,C,D及びEをいう。
(事業譲渡)
9 法第38条の「事業の譲渡」とは、納税者が一個の債権契約で、一定の事業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を納税者の親族その他の特殊関係者に譲渡することをいうが、一個の債権契約によらないものであつても、社会通念上同様と認められるものはこれに該当する(昭和46.4.9最高判参照)。したがって、得意先、事業上の秘けつ又はのれん等を除外して、工場、店舗、機械、商品等の事業用財産だけを譲渡する場合は、法第38条の事業譲渡には該当しない。
なお、事業譲渡については、次のことに留意する。 (1) 合名会社又は合資会社にあっては、原則として事業譲渡につき総社員の同意が必要である(商法72条、127条、147条)。
(2) 株式会社又は有限会社にあっては、事業譲渡につき株主総会又は社員総会の特別決議が必要である(商法245条1項、有限会社法40条1項)。 (注) 一人会社にあっては、客観的な事実(例えば、営業譲渡をした後に廃業しているような場合)から事業譲渡の特別決議があったと認められる場合には、法第38条の「事業の譲渡」に該当する(昭和44.3.18大阪地判、昭和46.6.24最高判参照)。また、一人会社と同様に認められるような株式会社又は有限会社についても同様である(昭和52.2.14最高判参照)。
(3) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定により事業の譲受けにつき制限を受ける場合がある(同法15条から17条まで参照)。
(同一とみられる場所)
10 法第38条の「同一とみられる場所」とは、同一の場所のほか、社会通念上同一の場所と認められる場所をいう。
(類似の事業)
11 法第38条の「類似の事業」とは、譲り受けた事業につき重要な事業活動の施設又は態様の変更をその事業内容に加えることなく事業活動が行われているような場合のその譲受け後の事業をいう。
(同一とみられる場所等の判定の時期)
12 法第38条の「同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる」かどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。 (注) 事業譲渡の当時においては「同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合」に当たらなくても、納付通知書を発する時においてこれに該当するときは、法第38条が適用される。
(事業に係る国税)
13 法第38条の「事業に係る国税」が一つの国税の一部である場合の国税の額の算定は、第36条関係2と同様である(令12条3項)。
(不足すると認められるとき)
14 法第38条の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
(1年以上前)
15 法第38条の「1年以上前にされている場合は、この限りでない」とは、法定納期限の1年前の応当日以前に譲渡した場合は法第38条の規定の適用がないことをいう。この場合の応当日については、通則法第10条第2項((期限の特例))の規定は適用されない。
納税義務の範囲
(譲受財産)
16 法第38条の「譲受財産」とは、譲受けに係る事業に属する積極財産をいい、事業の譲受け後に取得した財産(取得財産を除く。)は含まれない。
(取得財産)
17 法第38条の「取得財産」の意義については、第36条関係10及び11と同様である。
第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
納税義務の成立
(不足すると認められる場合)
1 法第39条の「徴収すべき額に不足すると認められる場合」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
(1年前の日以後の判定)
2 法第39条の「1年前の日以後」であるかどうかの判定については、次のことに留意する。
なお、法第39条の「1年前の日以後」は、第35条関係10と同様に取り扱うものとする。したがって、法定納期限の1年前の応当日にされた譲渡、債務の免除その他第三者に利益を与える処分については、法第39条の規定を適用しない取扱いとする。 (1) 契約が成立した時とそれに基づき譲渡等の処分がされた時(権利を取得し、又は義務を免れた時)が異なるときは、譲渡等の処分がされた時によって、1年前の日以後であるかどうかを判定する。
(2) 譲渡等の処分につき登記等の対抗要件又は効力要件の具備を必要とするときは、その要件を具備した日によって、1年前の日以後であるかどうかを判定する(昭和55.3.14東京高判)。 (注)1 上記の場合において、仮登記とそれに基づく本登記があるときは、本登記によって判定する。ただし、担保のための仮登記については、仮登記の日によって判定する。
2 譲渡等の処分がされた時が登記等の日後であることが訴訟等により明らかにされている場合には、その日によって判定する。
(譲渡)
3 法第39条の「譲渡」とは、贈与、特定遺贈、売買、交換、債権譲渡、出資、代物弁済等による財産権の移転をいい、相続等の一般承継によるものを含まない。この場合において、売買、交換、債権譲渡についてはそれにより取得した金銭又は財産が、出資についてはそれにより取得した持分又は株式が、代物弁済についてはそれにより消滅した債務が、それぞれ法第39条の「対価」である。 (注)1 包括遺贈(民法964条参照)があった場合には、通則法第5条((相続による国税の納付義務の承継))の規定の適用がある。
2 強制換価手続による所有権の移転は、上記の譲渡には含まれない。
3 滞納者が、例えば、生計を一にする親族(第37条関係6、民法725条)の生活費、学費等に充てるためにした社会通念上相当と認められる範囲の金銭又は物品の交付は、法第39条に規定する「無償又は著しく低い額の対価による譲渡」には当たらない。
(債務の免除)
4 法第39条の「債務の免除」には、民法第519条((免除))の規定による債務免除のほか、契約による免除も含まれる。この場合において、債務の免除と対価関係にある反対給付があるときは、それが法第39条の「対価」に当たる。
(第三者に利益を与える処分)
5 法第39条の「その他第三者に利益を与える処分」とは、譲渡、債務の免除以外の処分のうち、滞納者の積極財産の減少の結果(滞納者の身分上の一身専属権である権利の行使又は不行使の結果によるものを除く。)、第三者に利益を与えることとなる処分をいい、例えば、地上権、抵当権、賃借権等の設定処分がある。この場合において、地上権等の設定により受けた反対給付(例えば、権利金、礼金等)があるときは、それが法第39条の「対価」に当たる。
(著しく低い額の対価の判定)
6 法第39条の「著しく低い額の対価」によるものであるかどうかは、社会通念上、通常の取引に比べ著しく低い額の対価であるかどうかによって判定する。 (注)1 値幅のある財産については、特別の事情がない限り、時価のおおむね2分の1に満たない価額をもって著しく低いと判定しても差し支えない(昭和54.4.24大阪高判)。
2 対価が時価の2分の1を超えている場合においても、その行為の実態に照らし、時価と対価との差額に相当する金員等の無償譲渡等の処分がされていると認められる場合があることに留意する。
(著しく低いかどうかの判定の時期)
7 法第39条の「著しく低い額の対価」によるものであるかどうかの判定は、原則として、その譲渡等の処分の基因となった契約が成立した時の現況による。したがって、条件付契約、予約契約、効力発生要件が別にある場合の契約等、契約が成立した時とそれに基づき譲渡等の処分がされた時(権利を取得し、又は義務を免れた時)が異なる場合であっても、契約が成立した時の現況により判定する。
(基因すると認められるとき)
8 法第39条の「不足すると認められること」(以下8において「徴収不足」という。)が無償譲渡等の処分(国及び法人税法2条5号((公共法人の定義))に規定する法人以外の者に対する処分で無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分をいう(令14条)。以下第39条関係において同じ。)に「基因すると認められるとき」とは、その無償譲渡等の処分がなかったならば、現在の徴収不足は生じなかったであろう場合をいう。
納税義務を負う者
(権利を取得し、又は義務を免れた者)
9 法第39条の「権利を取得し、又は義務を免れた者」とは、無償譲渡等の処分により所有権、地上権、賃借権、無体財産権その他の財産権を取得した者又は債務の免除により債務を免れた者若しくは負うべき債務を免れた者をいう。
(親族その他の特殊関係者)
10 法第39条の「親族その他の特殊関係者」は、第38条関係1から8までと同様である。ただし、法第39条の親族その他の特殊関係者に該当するかどうかの判定は、原則として、無償譲渡等の処分の基因となった契約が成立した時の現況によるものとする。したがって、権利を取得し、又は義務を免れた時に特殊関係者に当たらなくても、契約が成立した時に特殊関係者に当たる場合には、法第39条の規定が適用される。
第三者の場合の納税義務の範囲
(受けた利益が金銭以外の物である場合)
11 無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が金銭以外の物である場合には、法第39条の「利益が現に存する限度」の額は、次により定める取扱いとする。ただし、その額が、15により算定した「受けた利益」の額を超える場合には、その受けた利益の額を限度とする。 (1) 受けた物がそのまま現存する場合には、納付通知書を発する時の現況による受けた物の価額を算定する。 (注) 受けた物から生じた果実は、現に存する利益の額には加えない。ただし、その果実が受益財産の一部となっている場合には、(2)による。
(2) 受けた物が、加工等により価額が増加した場合には、納付通知書を発する時の現況によるその物の価額から、その物の価額を増加させるために要した費用を控除した額を算定する。
(3) 受けた物について、その後譲受人が設定等をした地上権等の用益物権、賃借権、抵当権等がある場合には、納付通知書を発する時の現況による受けた物の価額に、用益物権等の設定等に伴い得た利益(例えば、権利金、礼金等)のうち現に存するものの額(注)参照)を加え、用益物権等の設定等に伴い要した費用(例えば、契約の費用等)の額を算定する。 (注) 上記の「現に存するものの額」の算定は、その「得た利益」が受けた利益に当たるものとして、その種類に従い、それぞれ11から14に準じて行う。
(4) 受けた物の全部又は一部が売買、贈与、き損、盗難、火災等により現存しない場合には、納付通知書を発する時における残存する財産の価額に、現存しないこととなったことに伴い得た利益(例えば、売却代金、保険金、共済金、損害賠償請求権等)のうち現に存する物の額((注)1参照)を加え、その利益を得るために要した費用(例えば、売買の費用、当該保険料、損害賠償請求のための通信費、交通費等)を控除した額を算定する。 (注)1 上記の「現に存するもの」の算定は、(3)の(注)と同様である。
2 受けた物に自己の固有財産を加えたものを譲渡し、他の財産を取得した場合には、納付通知書を発する時の現況による取得した財産の価額に、譲渡した財産の総額のうち受けた物の価額(譲渡時の価額)が占める割合をかけた額が、上記の「現存しないこととなったことに伴い得た利益のうち現に存する物の額」に当たるものとする。
(5) (1)から(4)までにより算定した額から、次に掲げる額を控除する。 イ その物を譲り受けるために支払った対価の額(無償譲渡等の処分があった時の対価の額)
ロ その物の譲受けのために支払った費用及びこれに類するもののうち、その物の譲受けと直接関係のある物の額(例えば、契約に要した費用、不動産取得税、登録免許税等(これらの租税に係る附帯税を除く。)があるが、その物の保管料、譲受人に課された固定資産税、その譲受けを基因として課された市町村民税等はこれに当たらない(昭和51.1O.8最高判)。)
ハ その物を譲り受けたことを直接の理由とする特別の消費及びこれに類する財産の減少の額(例えば、その物を譲り受けたことを直接の理由として浪費し又は他の物を他人に贈与した場合等がある。)
(6) 上記(5)の対価又は費用には、その金額が確定していなくても、その存在が確実と認められるものについては、納付通知書を発する時の現況によって確実と認められる範囲の金額を含めるものとする。
(受けた利益が金銭である場合)
12 無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が金銭である場合には、法第39条の「利益が現に存する限度」の額は、次により定める取扱いとする。 (1) 受けた金銭の額から、11の(5)に掲げる額を控除する。
(2) (1)により算定した額は、現に存するものと推定する(明治39.1O.11大判参照)。
(3) 金銭を受けたことを直接の理由として特別に財産を取得した場合には、上記(1)及び(2)により算定した額からその取得に要した金銭の額を控除したものに、その取得した財産のうち現に存するものの額((注)1参照)を加える。 (注)1 上記の「現に存するもの」の算定は、11の(3)の(注)と同様である。
2 受けた金銭と自己の固有財産とを合わせて財産を取得した場合には、納付通知書を発する時の現況による取得した財産の価額に、その取得に要した財産の総額のうち受けた金銭の額が占める割合をかけた額が、上記の「現に存するものの額」に当たるものとする。
(受けた利益が債務の免除である場合)
13 無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が債務の免除である場合には、債務者の支払能力、弁済期等を考慮し、その債権を換価する場合と同様に、その債務が免除された時におけるその債権の価額を算定し、その額が受けた利益の額に当たるものとして、12によって法第39条の「利益が現に存する限度」の額を定める取扱いとする。
(受けた利益が地上権の設定等である場合)
14 無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が地上権等の用益物権の設定、賃借権の設定、抵当権等の担保権の設定等である場合には、11に準じて法第39条の「利益が現に存する限度」の額を定める取扱いとする。この場合において、受けた利益が抵当権等の担保権の設定である場合には、物上保証をした者に通常支払われるべき保証料の額が、受けた利益に当たる。
特殊関係者の場合の納税義務の範囲
15 法第39条の「受けた利益の限度」の額は、次に定めるところによる。 (1) 無償譲渡等の処分により、滞納者から受けた利益が金銭であるときはその額を、金銭以外のものであるときは無償譲渡等の処分がされた時の現況によるその物の価額を、債務の免除であるときは債務が免除された時の現況によるその債権の価額を、地上権の設定等であるときはその設定等がされた時の現況によるその地上権等の価額を、それぞれ算定する。 (注) 無償譲渡等の処分後において、受けた利益が滅失等により現存しない場合、受けた財産について費用を支出した場合、受けた財産に用益物権、担保権、賃借権等を設定した場合、受けた財産から生じた果実がある場合等であっても、これらの事情は考慮しない。
(2) (1)により算定した額から、11の(5)のイ及びロに掲げる額を控除する。
第41条関係 人格のない社団等に係る第二次納税義務
納税義務の成立
(第三者)
1 法第41条第1項の「第三者」には、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)の構成員も含まれる。
(法律上帰属するとみられる財産)
2 法第41条第1項の「法律上帰属するとみられる財産」とは、登記を対抗要件又は効力要件としている財産で、第三者が名義人となっているものをいうほか、電話加入権で第三者が名義人となっているものを含むものとする。
(不足すると認められるとき)
3 法第41条第1項の「徴収すべき額に不足すると認められるとき」は、第22条関係4と同様である。ただし、不足するかどうかの判定は、納付通知書を発する時の現況によるものとする。
(滞納者)
4 法第41条第2項の「滞納者」とは、納付通知書を発する先において人格のない社団等が滞納者であれば足り、その財産の払戻し又は分配をした時において滞納者であることを要しない。
(法第34条との関係)
5 人格のない社団等が、解散の決議をしたときその他社会通念上解散したとみられるときは、法第41条第2項の規定の適用はなく、法第34条((清算人等の第二次納税義務))の規定が適用される場合がある。
(1年以上前)
6 法第41条第2項の「1年以上前にされている場合は、この限りでない」とは、法定納期限の1年前の応答日以前に払戻し又は分配した場合は法第41条第2項の規定の適用がないことをいう。この場合の応答日については、通則法第10条第2項((期限の特例))の規定は適用されない。
納税義務の範囲
7 法第41条第2項の「財産の価額」とは、払戻し又は分配がされた時におけるその財産の価額をいう。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.