解説記事2004年05月03日 【相続税務に必要な民法のミニ知識】 法人に対する遺贈(2004年5月3日号・№065)
実務解説
相続税務に必要な民法のミニ知識5
法人に対する遺贈
税理士・公認会計士 田中義幸
遺言で、法人に遺贈した場合、その法人の性格によって、どういう違いが生じるのでしょうか。
1 法人に対する遺贈
遺言によって財産を無償譲与することを遺贈といい、遺贈は相続人に対しても、第三者に対しても行うことができます。遺贈を受ける者として遺言中に指定されている者を受遺者といいますが、受遺者は自然人だけでなく法人もなることができます。たとえば、学校法人や宗教法人、社会福祉法人などへの遺贈はよく見られますし、人格のない社団・財団への遺贈も有効に行われます。
遺贈は、遺言者の死亡によって効力を生じるとされ(民985)、受遺者は遺言者の死亡の時点で存在していなければなりませんので(民994①)、法人も遺言の効力が発生した時点で存在している必要があると解されています。
なお、受遺者は遺贈を受けることを強制されるわけではなく、遺贈を放棄することができることになっています(民986)。
2 会社に対する遺贈
(1)遺贈者の課税
個人が法人に対して土地・建物等の財産を遺贈した場合、遺贈の効力が生じた時点において時価で譲渡したものとみなして、その譲渡所得に対して所得税が課されることになっています(所法59①一)。
この譲渡所得は、遺贈した被相続人の所得となりますので、相続人は準確定申告によって納税する必要が生じますが(所法125)、これは被相続人の所得に対する所得税額として債務控除の対象となる公租公課の金額に含まれます(相14②)。
(2)受遺者の課税
遺贈を受けた法人の方は、無償による資産の譲受けとして、益金に算入することになり、法人税等が課されることになります(法22②)。
なお、会社への遺贈によって株式または出資の価額が増加した場合、相続人等に「みなし相続財産」が生じることがあるため注意が必要です(相9)。
3 公益法人等に対する遺贈
(1)遺贈者の課税
法人に対する遺贈であっても、国または地方公共団体に対する遺贈については、無条件で所得税法の「みなし譲渡」の適用はないことになっています。
また、公益を目的とする事業を営む法人に対する財産の遺贈で、その遺贈が公益の増進に著しく寄与することその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものであるときも、「みなし譲渡」の適用はないことになっています(措法40①)。
(2)受遺者の課税
公益法人等は収益事業から生じた所得に対してのみ課税を受けますので、遺贈によって取得した財産に対して法人税等の課税を受けることはないのが原則です(法7)。
しかしながら、その遺贈により遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、法人税の所得計算において益金に算入されている場合を除いて、その公益法人等は「個人」とみなされて相続税の納税義務を負うことになるとされています(相66④)。
4 人格のない社団等に対する遺贈
(1)遺贈者の課税
法人でない任意の団体で代表者または管理人の定めがある、いわゆる人格のない社団等に対する財産の遺贈には、公益法人等を設立するための設立準備委員会等に対するものを除いて、「みなし譲渡」が適用されることになっています(措通40-3)。
(2)受遺者の課税
人格のない社団等も収益事業から生じた所得に対してのみ課税を受けますので、遺贈によって取得した財産に対して法人税等の課税を受けることはないのが原則です(法7)。
しかしながら、人格のない社団等に対して財産の遺贈があった場合には、法人税の所得計算において益金に算入されている場合を除いて、その人格のない社団等は「個人」とみなされて相続税の納税義務を負うとされています(相66①)。
ただし、その財産を公益事業に供することが確実であるなどの一定の要件を満たす場合には、「公益事業用財産」として相続税の非課税財産の規定が適用されることになりますので、公益法人等と同じように課税を受けることはありません(相12①三、相令2)。
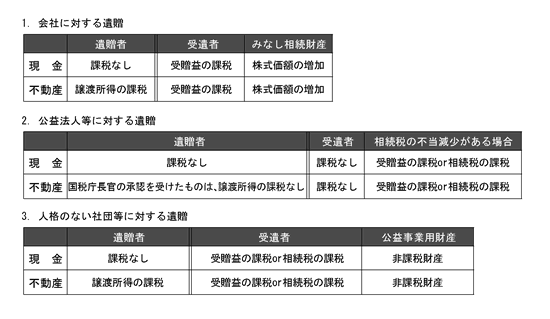
相続税務に必要な民法のミニ知識5
法人に対する遺贈
税理士・公認会計士 田中義幸
遺言で、法人に遺贈した場合、その法人の性格によって、どういう違いが生じるのでしょうか。
1 法人に対する遺贈
遺言によって財産を無償譲与することを遺贈といい、遺贈は相続人に対しても、第三者に対しても行うことができます。遺贈を受ける者として遺言中に指定されている者を受遺者といいますが、受遺者は自然人だけでなく法人もなることができます。たとえば、学校法人や宗教法人、社会福祉法人などへの遺贈はよく見られますし、人格のない社団・財団への遺贈も有効に行われます。
遺贈は、遺言者の死亡によって効力を生じるとされ(民985)、受遺者は遺言者の死亡の時点で存在していなければなりませんので(民994①)、法人も遺言の効力が発生した時点で存在している必要があると解されています。
なお、受遺者は遺贈を受けることを強制されるわけではなく、遺贈を放棄することができることになっています(民986)。
2 会社に対する遺贈
(1)遺贈者の課税
個人が法人に対して土地・建物等の財産を遺贈した場合、遺贈の効力が生じた時点において時価で譲渡したものとみなして、その譲渡所得に対して所得税が課されることになっています(所法59①一)。
この譲渡所得は、遺贈した被相続人の所得となりますので、相続人は準確定申告によって納税する必要が生じますが(所法125)、これは被相続人の所得に対する所得税額として債務控除の対象となる公租公課の金額に含まれます(相14②)。
(2)受遺者の課税
遺贈を受けた法人の方は、無償による資産の譲受けとして、益金に算入することになり、法人税等が課されることになります(法22②)。
なお、会社への遺贈によって株式または出資の価額が増加した場合、相続人等に「みなし相続財産」が生じることがあるため注意が必要です(相9)。
3 公益法人等に対する遺贈
(1)遺贈者の課税
法人に対する遺贈であっても、国または地方公共団体に対する遺贈については、無条件で所得税法の「みなし譲渡」の適用はないことになっています。
また、公益を目的とする事業を営む法人に対する財産の遺贈で、その遺贈が公益の増進に著しく寄与することその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものであるときも、「みなし譲渡」の適用はないことになっています(措法40①)。
(2)受遺者の課税
公益法人等は収益事業から生じた所得に対してのみ課税を受けますので、遺贈によって取得した財産に対して法人税等の課税を受けることはないのが原則です(法7)。
しかしながら、その遺贈により遺贈をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税または贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、法人税の所得計算において益金に算入されている場合を除いて、その公益法人等は「個人」とみなされて相続税の納税義務を負うことになるとされています(相66④)。
4 人格のない社団等に対する遺贈
(1)遺贈者の課税
法人でない任意の団体で代表者または管理人の定めがある、いわゆる人格のない社団等に対する財産の遺贈には、公益法人等を設立するための設立準備委員会等に対するものを除いて、「みなし譲渡」が適用されることになっています(措通40-3)。
(2)受遺者の課税
人格のない社団等も収益事業から生じた所得に対してのみ課税を受けますので、遺贈によって取得した財産に対して法人税等の課税を受けることはないのが原則です(法7)。
しかしながら、人格のない社団等に対して財産の遺贈があった場合には、法人税の所得計算において益金に算入されている場合を除いて、その人格のない社団等は「個人」とみなされて相続税の納税義務を負うとされています(相66①)。
ただし、その財産を公益事業に供することが確実であるなどの一定の要件を満たす場合には、「公益事業用財産」として相続税の非課税財産の規定が適用されることになりますので、公益法人等と同じように課税を受けることはありません(相12①三、相令2)。
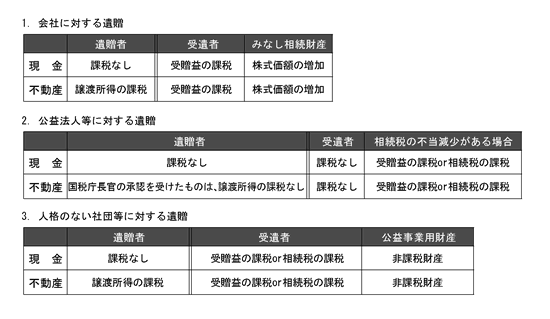
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























