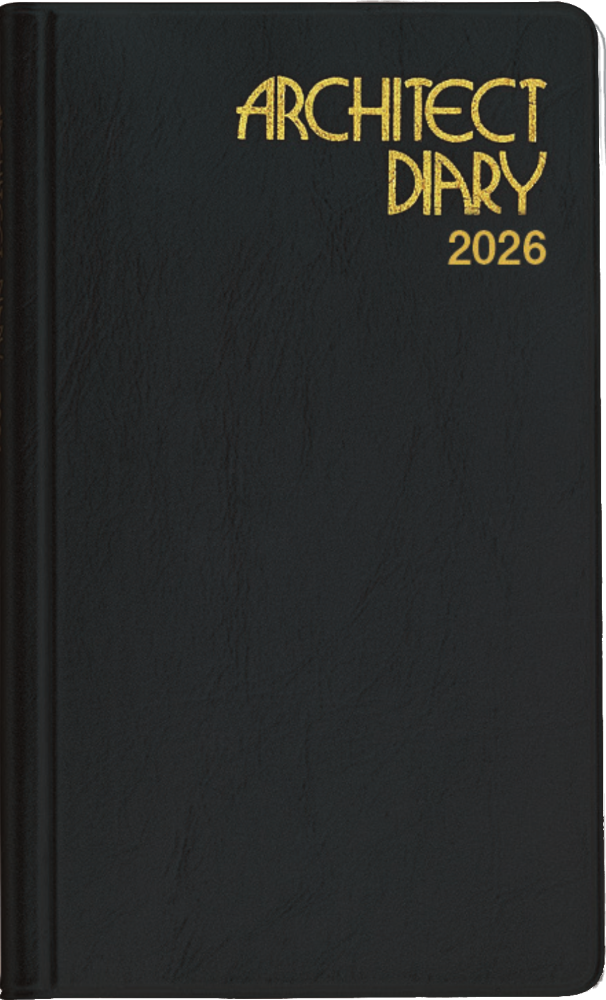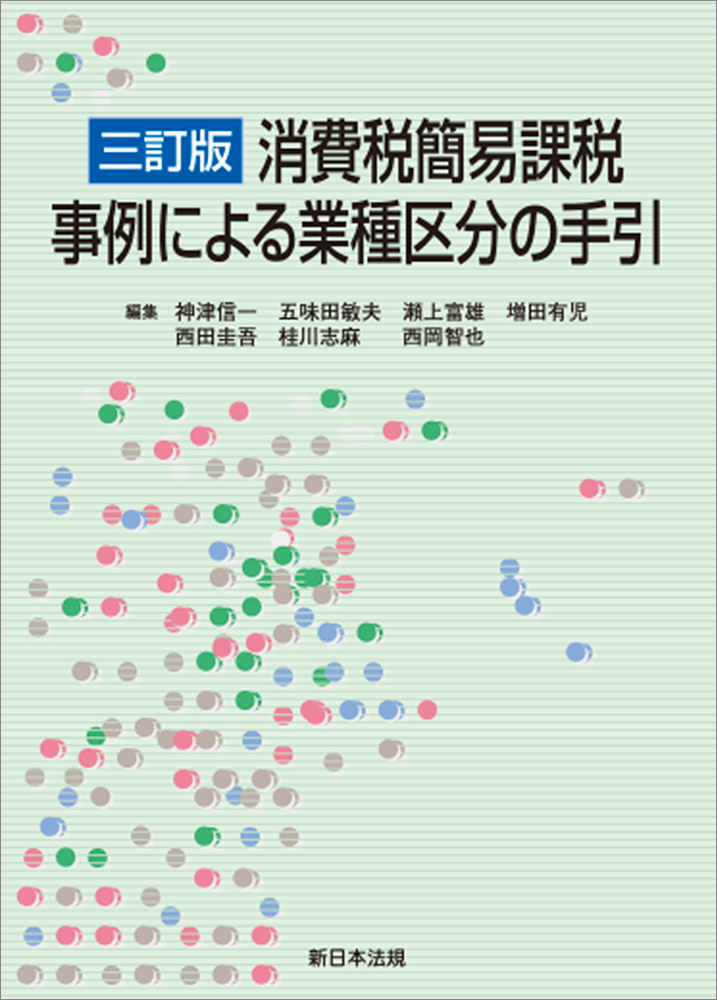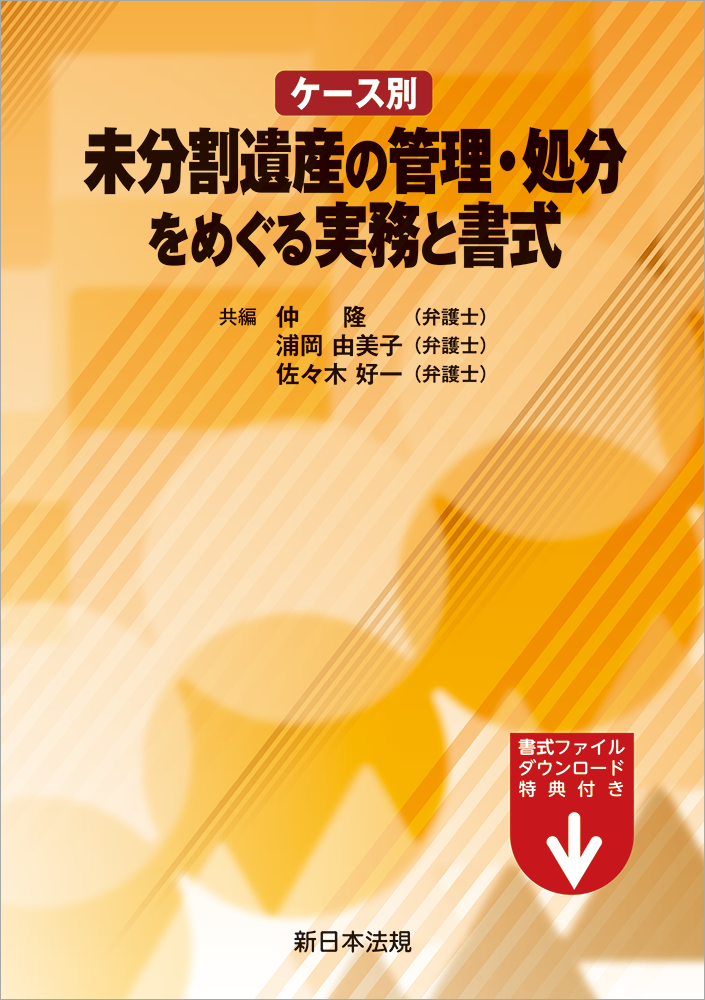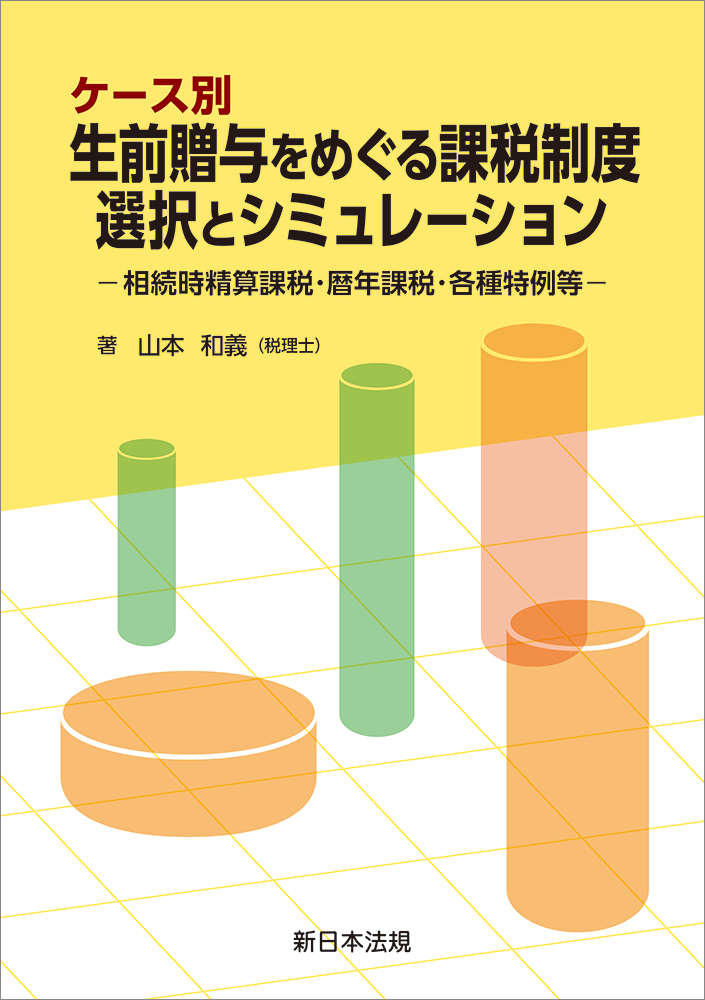解説記事2004年05月17日 【編集部解説】 アメリカ大使館職員事件判決 東京地裁民事3部は、「慣行」との整合性で判断(2004年5月17日号・№066)
解説
アメリカ大使館職員事件判決
東京地裁民事3部は、「慣行」との整合性で判断
編集部
平成16年4月19日、東京地裁民事3部(藤山雅行裁判長、藤山判事は異動のため、鶴岡稔彦裁判長が代読)では、在日米国大使館の日本人職員に対する追徴課税事件(5件)について、判決を言渡した。5件は、基本的な争点(「偽りその他不正の行為(通則法70条5項)」に該当するか否か)を同じくするものだが、2件については請求棄却・2件については請求認容・残りの1件は請求一部認容というように個々の事件内容によって裁判所の判断は分かれることになった。
本判決に先立つ平成16年2月12日においても、東京地裁民事3部は在日米国大使館の日本人職員に対する追徴課税事件(1件)について請求棄却の判決を下している。
このほか、大阪地裁平成15年12月3日判決・さいたま地裁平成16年3月17日判決では、同旨の争点で争われたが、納税者の請求はいずれも棄却されている。
以上8件の判決から、アメリカ大使館職員事件に対する裁判所の判断を検証してみることにしよう。
アメリカ大使館職員事件とは
在日外国公館には、現地職員として日本人職員が勤務している。これらの日本人職員に対して支払われる給与等について、所得税法(183条1項)には特段の定めは見られない。しかし、国際法上、外国政府(又は外国公館)がわが国の所得税法上の源泉徴収義務を負うと解することはできないため、源泉徴収することなく支払われ、支払を受けた日本人職員が確定申告義務を負うものと理解されている(この取扱いが一部事件の争点となっている)。
米国大使館の日本人職員に対する給与については、昭和30年に、米国大使館総務部長と国税庁担当者との間で折衝(合意)が行われ、その結果、基本給(総支給額の60%程度)で申告するとの考え方が定着したと原告(日本人職員)側は主張しているが、被告(国)は米国大使館職員の申告を過去において特別扱いしたことはないとして、原告の主張するような慣行(基本給での申告)を否定している。
昭和30年の合意については、①それまでGHQ時代も含めて日本人職員の多くが確定申告をしてこなかったこと、②米国大使館の日本人職員には労働基準法等の日本法が適用されず、日本の一般的な企業が非課税給として給付している社会保険料等が給与として支給されているなどの特殊な事情があったこと、等の事情に配慮したものと見られるが、法令上非課税と規定されるものではなかった。
平成11年頃、在外公館の日本人職員が支払を受けた給与について、一斉の税務調査が行われ、平成12年2月には、「調査対象は250人、申告漏れ総額は約50億円、追徴税額は約14億円」と各マスコミに大々的に報道されている。
米国大使館の日本人職員については、上記の合意に基づく慣行による申告が国税通則法70条5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するものとして、通常の更正の期間制限(3年)を超える7年分の追徴課税(本税・過少申告加算税)処分が行われた。「慣行」を信じて確定申告をしたとする原告らは、主に「偽りその他不正の行為」に該当するものではないとして、課税処分について争ったものである。
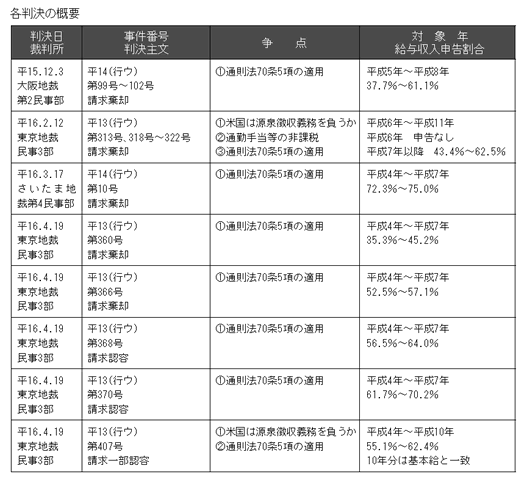
争点の微妙な違いが「正当な理由」に発展
米国大使館職員事件については、上記の各判決を確認しているのでこれらを対象にして検証してみることにする。いずれの事件も、国税通則法70条5項(「偽りその他不正の行為」)の適用を受けて、通常3年の更正の期間制限(通則法70①一)を超えて7年の追徴課税(本税・過少申告加算税)を受けているが、租税逋脱犯や重加算税の賦課対象とはなっていない。
原告らは、主に通則法70条5項の適用を争っているが、外国政府(在日公館)の源泉徴収義務を争うものについては、通常の更正の期間制限(3年)内の追徴課税処分についても争うこととになる。また、「通勤手当及び住宅手当は非課税となるか」が争点となっている事件があるが、個別の事情を反映した面と、米国大使館日本人職員の特殊な給与形態への配慮を求めた争点ということになる。
東京地裁民事3部は、一部事件の争点となった「外国政府(在日公館)の源泉徴収義務」について、「米国は、米国大使館における現地職員への給与の支払に際し、源泉徴収義務を免除されると解するのが相当」と判示し、「原告らには、米国大使館からの給与について申告義務がある。」とし、もう一つの争点である「通勤手当及び住宅手当は非課税となるか」について、「通勤手当相当額は、本件処分の際に非課税として計算しているため、この他に非課税とされる給付はない。」として原告の主張を斥けた。
結果的には、いずれの訴訟も「偽りその他不正の行為」が主たる争点となるのだが、平13(行ウ)第407号事件では、「慣行(基本給での申告)」に基づいた申告であり、「原告がこのような申告方法を正しいものと信じたことは、真にやむを得なかったものというべきであり、原告にはこの点について何らの責められるべき点も認められない。」と判示し、通則法65条4項の「正当な理由」が認められるとして、通常の更正の期間制限内の更正処分に伴う過少申告加算税賦課決定も取り消すことになった。
納税者に優しい東京地裁民事3部、納税者に厳しいさいたま地裁
各判決は、いずれも納税者の確定申告の状況を確認しているが、「偽りその他不正の行為」の有無の判断だけに、結果としての納税者の(過少申告)行為が、「慣行に従って正しい申告であると信じて行われたものと認めることが出来るのか」、あるいは、「慣行を奇貨として、これを積極的に利用して課税を免れようとしたか」を見極めることになる。
大阪地裁事件では、申告された給与収入の額が慣行としてアドバイスされた金額(給与収入の額の60%程度)に概ね及ばないことから、「真実の収入金額と信じていたものとみることは到底できず、」と認定して、「偽りその他不正の行為」に当たるものとされている。
東京地裁民事3部も基本的には、慣行との整合性でもって、「偽りその他不正の行為」の該当性を判断している。
一方、さいたま地裁は、給与収入の申告割合(72.3%~75.0%)は、慣行(60%程度)の水準を超えているが、「結局、原告は法令等の規定に基づく具体的な根拠に基づくことなく、給与等の収入金の一部を除外し、当該確定申告に係る収入金額が実際の収入金額とは乖離するものであることを知りながら収入金額の一部のみの申告をしていたといわざるを得ない。」と判示して、「偽りその他の不正行為」に当たるものと判断している。
行為の事実認定による裁判所の判断であるから、必ずしも慣行との整合性だけが「偽りその他不正の行為」に該当するかの判断の基準とはいえないのだろうが、いずれの判決も納税者の申告行為を判断材料としていただけに、東京地裁民事3部判決の「納税者に対するものわかりの良さ」と、さいたま地裁判決の「納税者に対する厳しさ」は、明解な対比をなしているように思われる。
アメリカ大使館職員事件判決
東京地裁民事3部は、「慣行」との整合性で判断
編集部
平成16年4月19日、東京地裁民事3部(藤山雅行裁判長、藤山判事は異動のため、鶴岡稔彦裁判長が代読)では、在日米国大使館の日本人職員に対する追徴課税事件(5件)について、判決を言渡した。5件は、基本的な争点(「偽りその他不正の行為(通則法70条5項)」に該当するか否か)を同じくするものだが、2件については請求棄却・2件については請求認容・残りの1件は請求一部認容というように個々の事件内容によって裁判所の判断は分かれることになった。
本判決に先立つ平成16年2月12日においても、東京地裁民事3部は在日米国大使館の日本人職員に対する追徴課税事件(1件)について請求棄却の判決を下している。
このほか、大阪地裁平成15年12月3日判決・さいたま地裁平成16年3月17日判決では、同旨の争点で争われたが、納税者の請求はいずれも棄却されている。
以上8件の判決から、アメリカ大使館職員事件に対する裁判所の判断を検証してみることにしよう。
アメリカ大使館職員事件とは
在日外国公館には、現地職員として日本人職員が勤務している。これらの日本人職員に対して支払われる給与等について、所得税法(183条1項)には特段の定めは見られない。しかし、国際法上、外国政府(又は外国公館)がわが国の所得税法上の源泉徴収義務を負うと解することはできないため、源泉徴収することなく支払われ、支払を受けた日本人職員が確定申告義務を負うものと理解されている(この取扱いが一部事件の争点となっている)。
米国大使館の日本人職員に対する給与については、昭和30年に、米国大使館総務部長と国税庁担当者との間で折衝(合意)が行われ、その結果、基本給(総支給額の60%程度)で申告するとの考え方が定着したと原告(日本人職員)側は主張しているが、被告(国)は米国大使館職員の申告を過去において特別扱いしたことはないとして、原告の主張するような慣行(基本給での申告)を否定している。
昭和30年の合意については、①それまでGHQ時代も含めて日本人職員の多くが確定申告をしてこなかったこと、②米国大使館の日本人職員には労働基準法等の日本法が適用されず、日本の一般的な企業が非課税給として給付している社会保険料等が給与として支給されているなどの特殊な事情があったこと、等の事情に配慮したものと見られるが、法令上非課税と規定されるものではなかった。
平成11年頃、在外公館の日本人職員が支払を受けた給与について、一斉の税務調査が行われ、平成12年2月には、「調査対象は250人、申告漏れ総額は約50億円、追徴税額は約14億円」と各マスコミに大々的に報道されている。
米国大使館の日本人職員については、上記の合意に基づく慣行による申告が国税通則法70条5項に規定する「偽りその他不正の行為」に該当するものとして、通常の更正の期間制限(3年)を超える7年分の追徴課税(本税・過少申告加算税)処分が行われた。「慣行」を信じて確定申告をしたとする原告らは、主に「偽りその他不正の行為」に該当するものではないとして、課税処分について争ったものである。
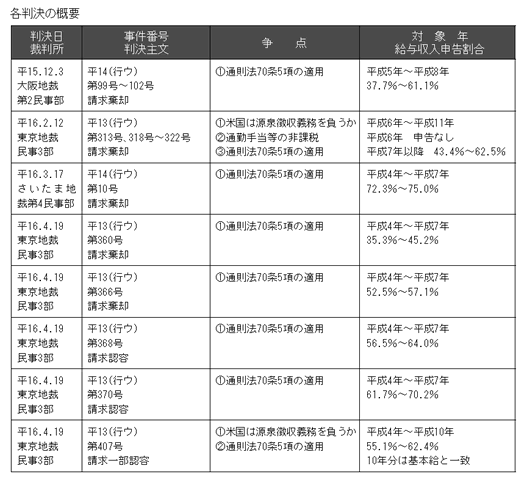
争点の微妙な違いが「正当な理由」に発展
米国大使館職員事件については、上記の各判決を確認しているのでこれらを対象にして検証してみることにする。いずれの事件も、国税通則法70条5項(「偽りその他不正の行為」)の適用を受けて、通常3年の更正の期間制限(通則法70①一)を超えて7年の追徴課税(本税・過少申告加算税)を受けているが、租税逋脱犯や重加算税の賦課対象とはなっていない。
原告らは、主に通則法70条5項の適用を争っているが、外国政府(在日公館)の源泉徴収義務を争うものについては、通常の更正の期間制限(3年)内の追徴課税処分についても争うこととになる。また、「通勤手当及び住宅手当は非課税となるか」が争点となっている事件があるが、個別の事情を反映した面と、米国大使館日本人職員の特殊な給与形態への配慮を求めた争点ということになる。
東京地裁民事3部は、一部事件の争点となった「外国政府(在日公館)の源泉徴収義務」について、「米国は、米国大使館における現地職員への給与の支払に際し、源泉徴収義務を免除されると解するのが相当」と判示し、「原告らには、米国大使館からの給与について申告義務がある。」とし、もう一つの争点である「通勤手当及び住宅手当は非課税となるか」について、「通勤手当相当額は、本件処分の際に非課税として計算しているため、この他に非課税とされる給付はない。」として原告の主張を斥けた。
結果的には、いずれの訴訟も「偽りその他不正の行為」が主たる争点となるのだが、平13(行ウ)第407号事件では、「慣行(基本給での申告)」に基づいた申告であり、「原告がこのような申告方法を正しいものと信じたことは、真にやむを得なかったものというべきであり、原告にはこの点について何らの責められるべき点も認められない。」と判示し、通則法65条4項の「正当な理由」が認められるとして、通常の更正の期間制限内の更正処分に伴う過少申告加算税賦課決定も取り消すことになった。
納税者に優しい東京地裁民事3部、納税者に厳しいさいたま地裁
各判決は、いずれも納税者の確定申告の状況を確認しているが、「偽りその他不正の行為」の有無の判断だけに、結果としての納税者の(過少申告)行為が、「慣行に従って正しい申告であると信じて行われたものと認めることが出来るのか」、あるいは、「慣行を奇貨として、これを積極的に利用して課税を免れようとしたか」を見極めることになる。
大阪地裁事件では、申告された給与収入の額が慣行としてアドバイスされた金額(給与収入の額の60%程度)に概ね及ばないことから、「真実の収入金額と信じていたものとみることは到底できず、」と認定して、「偽りその他不正の行為」に当たるものとされている。
東京地裁民事3部も基本的には、慣行との整合性でもって、「偽りその他不正の行為」の該当性を判断している。
一方、さいたま地裁は、給与収入の申告割合(72.3%~75.0%)は、慣行(60%程度)の水準を超えているが、「結局、原告は法令等の規定に基づく具体的な根拠に基づくことなく、給与等の収入金の一部を除外し、当該確定申告に係る収入金額が実際の収入金額とは乖離するものであることを知りながら収入金額の一部のみの申告をしていたといわざるを得ない。」と判示して、「偽りその他の不正行為」に当たるものと判断している。
行為の事実認定による裁判所の判断であるから、必ずしも慣行との整合性だけが「偽りその他不正の行為」に該当するかの判断の基準とはいえないのだろうが、いずれの判決も納税者の申告行為を判断材料としていただけに、東京地裁民事3部判決の「納税者に対するものわかりの良さ」と、さいたま地裁判決の「納税者に対する厳しさ」は、明解な対比をなしているように思われる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -