解説記事2004年06月14日 【ニュース特集】 公認会計士・税理士が担う新制度「会計参与」を分析(2004年6月14日号・№070)
公認会計士・税理士が担う
新制度「会計参与」を分析
6月2日に開催された法制審議会会社法(現代化関係)部会において、要綱案(案)の一項目に新たに会計参与(仮称)制度が提案されました。昨年10月に公表された要綱試案には盛り込まれていなかった制度であるとともに、公認会計士・税理士にとっては新たなビジネス・チャンスともいえるだけに関係者の注目を集めています。今回の特集では、新制度「会計参与」の概要について、法制審議会会社法(現代化関係)部会資料をもとに解説します。
会計参与って何?
会計参与制度とは、株主総会で選任された会計参与が株式会社の機関として計算書類の作成・保存・開示を担う役目を有するという制度です。なお、計算書類とは、B/S、P/L、営業報告書、附属明細書のことです(商法施行規則2条1項14号及び2項参照)。
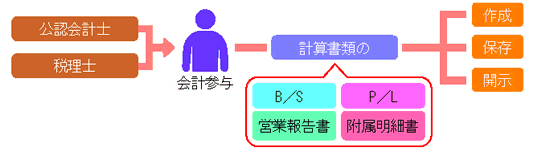
会計参与になることができるのは、公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人)だけ。もっとも、会計参与は、会社又は子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人又は支配人その他の使用人を兼ねることはできません。なお、会計監査人を設置した会社が会計参与を設置することはOKとされています。
会計参与は株主総会で選任され、任期・報酬等については取締役と同様の規律に従うものとされています。任期については、委員会等設置会社以外の会計参与については、原則として最大2年(ただし、最長10年まで伸長することができるという案が提示されています)、委員会等設置会社の会計参与の任期は譲渡制限の有無にかかわらず原則として1年とされています。
会計参与の職務と責任
会計参与の主な職務は次のとおりです。
計算書類の作成:取締役・執行役と共同して、計算書類を作成します。
株主総会における説明義務:会計参与は株主総会において、自己が作成した計算書類に関して株主が求めた事項について説明しなければなりません(商法237条ノ3参照)。
計算書類の保存:会計参与は、計算書類を5年間保存しなければなりません(商法282条1項参照)。
計算書類の開示:株主及び会社の債権者は、会計参与に対して、いつでも計算書類の閲覧等を請求することができます(商法282条2項参照)。
一方で、会計参与は会社の機関としての責任を有することとなります。具体的には対会社責任(商法266条参照)及び対第三者責任(商法266条ノ3参照)を負います。会社に対する責任については株主の代表訴訟の対象となります。もっとも、報酬等の2年分を限度に責任を免除することができるとともに、事前の責任軽減契約が認められる旨提案されています。
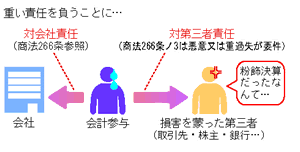
どのような会社で会計参与の設置が認められるか
では、どのような会社で会計参与の設置が認められるのでしょうか。それを検討するに先立って、要綱案(案)における株式会社の機関設計をみてみることにしましょう。
要綱案(案)では、株式会社と有限会社の両会社類型について、1つの会社類型として規律する方向で検討されています。その上で、「株式会社は、株主総会及び取締役を設置しなければならないものとする」とされています。ここで注意したいのは、設置が必要となるのは「取締役会」ではなく、「取締役」であるということ。現行の有限会社を意識したものとなっています。
また、現行商法においては株式会社の取締役は取締役会の構成員に過ぎませんが、要綱案では、原則として単独の取締役が業務執行権・代表権を持つとした上で、取締役会を設置した株式譲渡制限会社又は取締役会を設置しなければならない「株式譲渡制限会社以外の会社」においては、取締役各自の業務執行権・代表権は喪失するというたてつけになる予定です。
さて、会社の規模やどのような機関設計を採用したかに関わらず、会計参与の設置は任意となっています。もっとも、定款で取締役会を設置した株式譲渡制限会社は下表のようにイロハのうちどれか一つを選択することとなります。なお、会計参与制度の採用を選択する会社では定款でその旨規定する必要があります。
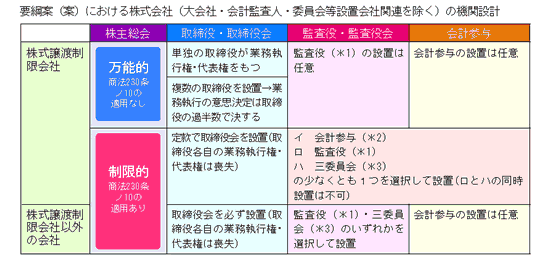
*1:定款で監査役会を設置することも可。
*2:監査役・三委員会を選択した上で、会計参与を任意で選択することも可。なお、会計参与のみを設置した場合には、株主は裁判所の許可を得ることなく(商法260条ノ4第6項参照)、取締役会議事録を閲覧することができる。
*3:監査委員会・指名委員会・報酬委員会の3つを指す。執行役は必須でないことから委員会等設置会社そのものではないことに注意。
会計参与制度の問題点
会計参与制度についての素朴な疑問点をQ&A形式でまとめてみました。
会社にとってどういうメリットがあるのか?
A. 適切な計算書類の作成は経営者のアカウンタビリティ(説明責任)の観点から必須といえます。もっとも、規模が大きくない株式会社では、経理部の人手不足・経験不足から、法定の計算書類を十分に作成できていないケースがよく見受けられます。公認会計士・税理士が重い責任を抱えながら作成する計算書類は、現状と比べて格段に質が向上することと思われ、これにより経営者がアカウンタビリティを果たすことが可能となってきます。また、金融機関が会計参与制度を採用した中小企業を金利面で優遇することも期待できます(エージェンシーコストの低下を反映)。
税務代理人が会計参与に就くことは可能か?
A. 当該税務代理人が、会社又は子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人又は支配人その他の使用人でない限り、会計参与に就くことは可能です。もっとも、中小会社では税務代理人が監査役を兼ねるケース がよく見受けられますが、そのような場合監査役を辞めない限り会計参与に就くことはできません。
税務代理人である公認会計士・税理士が会計参与に就くメリットは?
A. メリットとしては、報酬のアップ及び任期の安定という点が指摘できます。もっとも、責任が増えるとともに、代表訴訟の対象となる等のデメリットもあることに注意が必要です。
会計参与の氏名等は登記事項か?
A. 6月2日に開催された法制審議会会社法(現代化関係)部会において配布された資料中には、会計参与が登記事項か否かは触れられていません。もっとも、株主が計算書類の開示を会計参与に請求するに際して、誰が会計参与かを特定し易くする必要があることを考慮すると登記事項とされることと思われます。
会計参与のところに税務調査が入ることになるのか?
A. 元帳・補助簿といった帳簿や請求書・契約書といった証憑類は計算書類には含まれません。帳簿・証憑類は従前どおり会社での保管となり、会社の税務調査も会計参与ではなく会社に入ることとなります。
会計参与は株主総会に出席する必要があるのか?
A. 要綱案(案)では、会計参与は株主総会において、自己が作成した計算書類に関して株主が求めた事項について説明する必要があるとされています(商法237条ノ3参照)。それに備えて、会計参与は株主総会に出席する必要が生じることとなります。
会計参与制度の中小会社会計に与える影響は?
A. 会計参与が計算書類作成に際し準拠することとなるのは「一般に公正妥当と認められる会計基準」であり、企業会計原則を筆頭とする企業会計審議会が公表した会計基準及び企業会計基準委員会が公表した一連の会計基準等がこれに該当します。会計参与が制度化された場合、実際に同制度を導入するのは、中小会社が中心となると思われますが、現在でも多くの中小会社の計算書類はこれら一連の会計基準に100%準拠しているとはとてもいえない状況です。これまでは、中小会社の計算書類が「一般に公正妥当と認められる会計基準」に準拠しなくとも、それを是正すべき環境や誘因が存在しませんでした。しかし、公認会計士・税理士といった国家資格の保有者が責任を伴いつつ「会計参与」制度に組み込まれることで、状況は大きく変化するものと思われます。中小会社独自の会計基準を認めるかどうか、議論が高まることが予想されます。
新制度「会計参与」を分析
6月2日に開催された法制審議会会社法(現代化関係)部会において、要綱案(案)の一項目に新たに会計参与(仮称)制度が提案されました。昨年10月に公表された要綱試案には盛り込まれていなかった制度であるとともに、公認会計士・税理士にとっては新たなビジネス・チャンスともいえるだけに関係者の注目を集めています。今回の特集では、新制度「会計参与」の概要について、法制審議会会社法(現代化関係)部会資料をもとに解説します。
会計参与って何?
会計参与制度とは、株主総会で選任された会計参与が株式会社の機関として計算書類の作成・保存・開示を担う役目を有するという制度です。なお、計算書類とは、B/S、P/L、営業報告書、附属明細書のことです(商法施行規則2条1項14号及び2項参照)。
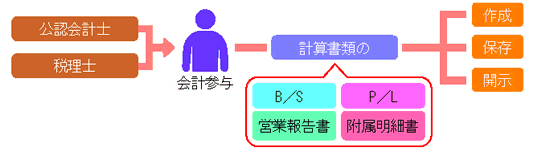
会計参与になることができるのは、公認会計士(監査法人)・税理士(税理士法人)だけ。もっとも、会計参与は、会社又は子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人又は支配人その他の使用人を兼ねることはできません。なお、会計監査人を設置した会社が会計参与を設置することはOKとされています。
会計参与は株主総会で選任され、任期・報酬等については取締役と同様の規律に従うものとされています。任期については、委員会等設置会社以外の会計参与については、原則として最大2年(ただし、最長10年まで伸長することができるという案が提示されています)、委員会等設置会社の会計参与の任期は譲渡制限の有無にかかわらず原則として1年とされています。
会計参与の職務と責任
会計参与の主な職務は次のとおりです。
計算書類の作成:取締役・執行役と共同して、計算書類を作成します。
株主総会における説明義務:会計参与は株主総会において、自己が作成した計算書類に関して株主が求めた事項について説明しなければなりません(商法237条ノ3参照)。
計算書類の保存:会計参与は、計算書類を5年間保存しなければなりません(商法282条1項参照)。
計算書類の開示:株主及び会社の債権者は、会計参与に対して、いつでも計算書類の閲覧等を請求することができます(商法282条2項参照)。
一方で、会計参与は会社の機関としての責任を有することとなります。具体的には対会社責任(商法266条参照)及び対第三者責任(商法266条ノ3参照)を負います。会社に対する責任については株主の代表訴訟の対象となります。もっとも、報酬等の2年分を限度に責任を免除することができるとともに、事前の責任軽減契約が認められる旨提案されています。
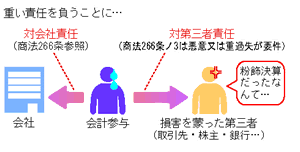
どのような会社で会計参与の設置が認められるか
では、どのような会社で会計参与の設置が認められるのでしょうか。それを検討するに先立って、要綱案(案)における株式会社の機関設計をみてみることにしましょう。
要綱案(案)では、株式会社と有限会社の両会社類型について、1つの会社類型として規律する方向で検討されています。その上で、「株式会社は、株主総会及び取締役を設置しなければならないものとする」とされています。ここで注意したいのは、設置が必要となるのは「取締役会」ではなく、「取締役」であるということ。現行の有限会社を意識したものとなっています。
また、現行商法においては株式会社の取締役は取締役会の構成員に過ぎませんが、要綱案では、原則として単独の取締役が業務執行権・代表権を持つとした上で、取締役会を設置した株式譲渡制限会社又は取締役会を設置しなければならない「株式譲渡制限会社以外の会社」においては、取締役各自の業務執行権・代表権は喪失するというたてつけになる予定です。
さて、会社の規模やどのような機関設計を採用したかに関わらず、会計参与の設置は任意となっています。もっとも、定款で取締役会を設置した株式譲渡制限会社は下表のようにイロハのうちどれか一つを選択することとなります。なお、会計参与制度の採用を選択する会社では定款でその旨規定する必要があります。
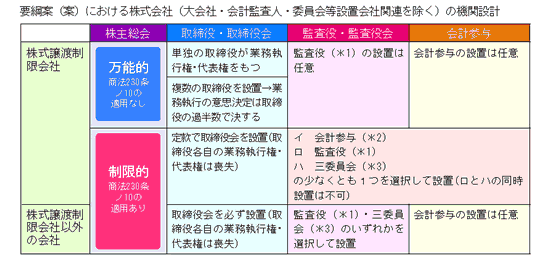
*1:定款で監査役会を設置することも可。
*2:監査役・三委員会を選択した上で、会計参与を任意で選択することも可。なお、会計参与のみを設置した場合には、株主は裁判所の許可を得ることなく(商法260条ノ4第6項参照)、取締役会議事録を閲覧することができる。
*3:監査委員会・指名委員会・報酬委員会の3つを指す。執行役は必須でないことから委員会等設置会社そのものではないことに注意。
会計参与制度の問題点
会計参与制度についての素朴な疑問点をQ&A形式でまとめてみました。
会社にとってどういうメリットがあるのか?
A. 適切な計算書類の作成は経営者のアカウンタビリティ(説明責任)の観点から必須といえます。もっとも、規模が大きくない株式会社では、経理部の人手不足・経験不足から、法定の計算書類を十分に作成できていないケースがよく見受けられます。公認会計士・税理士が重い責任を抱えながら作成する計算書類は、現状と比べて格段に質が向上することと思われ、これにより経営者がアカウンタビリティを果たすことが可能となってきます。また、金融機関が会計参与制度を採用した中小企業を金利面で優遇することも期待できます(エージェンシーコストの低下を反映)。
税務代理人が会計参与に就くことは可能か?
A. 当該税務代理人が、会社又は子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人又は支配人その他の使用人でない限り、会計参与に就くことは可能です。もっとも、中小会社では税務代理人が監査役を兼ねるケース がよく見受けられますが、そのような場合監査役を辞めない限り会計参与に就くことはできません。
税務代理人である公認会計士・税理士が会計参与に就くメリットは?
A. メリットとしては、報酬のアップ及び任期の安定という点が指摘できます。もっとも、責任が増えるとともに、代表訴訟の対象となる等のデメリットもあることに注意が必要です。
会計参与の氏名等は登記事項か?
A. 6月2日に開催された法制審議会会社法(現代化関係)部会において配布された資料中には、会計参与が登記事項か否かは触れられていません。もっとも、株主が計算書類の開示を会計参与に請求するに際して、誰が会計参与かを特定し易くする必要があることを考慮すると登記事項とされることと思われます。
会計参与のところに税務調査が入ることになるのか?
A. 元帳・補助簿といった帳簿や請求書・契約書といった証憑類は計算書類には含まれません。帳簿・証憑類は従前どおり会社での保管となり、会社の税務調査も会計参与ではなく会社に入ることとなります。
会計参与は株主総会に出席する必要があるのか?
A. 要綱案(案)では、会計参与は株主総会において、自己が作成した計算書類に関して株主が求めた事項について説明する必要があるとされています(商法237条ノ3参照)。それに備えて、会計参与は株主総会に出席する必要が生じることとなります。
会計参与制度の中小会社会計に与える影響は?
A. 会計参与が計算書類作成に際し準拠することとなるのは「一般に公正妥当と認められる会計基準」であり、企業会計原則を筆頭とする企業会計審議会が公表した会計基準及び企業会計基準委員会が公表した一連の会計基準等がこれに該当します。会計参与が制度化された場合、実際に同制度を導入するのは、中小会社が中心となると思われますが、現在でも多くの中小会社の計算書類はこれら一連の会計基準に100%準拠しているとはとてもいえない状況です。これまでは、中小会社の計算書類が「一般に公正妥当と認められる会計基準」に準拠しなくとも、それを是正すべき環境や誘因が存在しませんでした。しかし、公認会計士・税理士といった国家資格の保有者が責任を伴いつつ「会計参与」制度に組み込まれることで、状況は大きく変化するものと思われます。中小会社独自の会計基準を認めるかどうか、議論が高まることが予想されます。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















