資料2004年06月30日 【裁決事例】 1.本件開発地のうちに借地が存していても、その借地は賃借権に基づき専属的に使用する権限を有しているものと認められるので、当該借地を含む開発地一体を一画地の土地として評価するのが相当とした事例 2.本件賃貸借契約は、建物が完成し、その賃借人が店舗を開店した時から建物を賃貸するという停止条件付契約であるので、それ以前に賃貸借契約が締結されていたとしても、本件土地に賃借人の支配権が及ばないから、貸家建付地評価は相当ではないとした事例(平成10年4月7日相続開始に係る相続税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分/一部取消ほか)
(平15.6.6裁決、裁決事例集No.65 622頁)
《裁決書(抄)》
1 事実
(1)事案の概要
本件は、審査請求人K及び同L(以下、それぞれ「K」及び「L」といい、両名を併せて「請求人ら」という。)のうち、Kが相続により取得した土地について、他の土地と併せて1画地として評価すべきか否か、また、当該土地が貸家の目的に供されている宅地(以下「貸家建付地」という。)に当たるか否かを主な争点とする事案である。
(2)審査請求に至る経緯及び内容
イ 請求人らは、平成10年4月7日に死亡した父M(以下「被相続人」という。)の相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告書に、別表1の「申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。
ロ その後、請求人らは、Kが本件相続により取得した別表2の番号1ないし3の土地(以下、これらを併せて「本件土地」という。)について、実測面積が申告した面積を上回っていること及び利用区分が定期借地権付きの土地ではなく貸家建付地であるとして、平成11年12月2日に、別表1の「修正申告等」欄のとおり記載した相続税の修正申告書(以下「本件修正申告書」という。)を提出した。
ハ 請求人らは、平成11年12月10日に、本件相続により取得した本件土地以外の土地について評価誤りがあるとして、別表1の「更正の請求」欄のとおり記載した相続税の更正の請求書を提出し、原処分庁は、平成11年12月15日付で、別表1の「更正処分等(減)」欄のとおり相続税の更正処分をした。
ニ 原処分庁は、原処分庁所属職員の調査に基づき、本件土地について、貸家建付地ではなく自用地として評価すべきであるとして、平成13年12月20日付で、別表1の「更正処分等」欄のとおり、相続税の各更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をした。
ホ 請求人らは、上記ニの処分を不服として、平成14年2月13日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、別表1の「異議決定」欄のとおり、平成14年5月13日付で、Kについてはいずれも棄却、Lについては、その一部をいずれも取り消す異議決定をした。
ヘ 請求人らは、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成14年6月11日に審査請求をした。
(3)関係法令等
イ 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。平成11年7月19日付課評2-12による改正前のものをいい、以下「評価通達」という。)は、次のとおり定めている。
(イ)評価通達5《評価方法の定めのない財産の評価》は、評価通達に評価方法の定めのない財産の価額は、この通達に定める評価方法に準じて評価する旨定めている。
(ロ)評価通達10《評価単位》は、宅地の価額は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)ごとに評価することとし、宅地の上に存する権利の価額についても、同様とする旨定めている。
(ハ)評価通達16《側方路線影響加算》は、正面と側方に路線がある宅地の価額は、次のA及びBに掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する旨定めている。
A 正面路線(原則として、評価通達15《奥行価格補正》により計算した1平方メートル当たりの価格の高い方の路線をいう。)の路線価(以下「正面路線価」という。)に基づき計算した価額
B 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に「側方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価額
(ニ)評価通達17《二方路線影響加算》は、正面と裏面に路線がある宅地の価額は、次のA及びBに掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する旨定めている。
A 正面路線価に基づき計算した価額
B 裏面路線の路線価を正面路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に「二方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価額
(ホ)評価通達20《不整形地、無道路地、間口が狭小な宅地等、がけ地等の評価》の(1)は、不整形地の価額は、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、不整形地を区分して得られる整形地等の価額を基とし、その近傍の宅地との均衡を考慮して、その価額からその価額の100分の30の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する旨定めている。
また、評価通達20の(2)の注書において、無道路地とは、路線に接しない宅地をいう旨定めている。
さらに、評価通達20の(4)は、がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちに存するがけ地等ががけ地等でないとした場合の価額に、その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じて「がけ地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する旨定めている。
(ヘ)評価通達24-3《造成中の宅地の評価》は、造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手直前の地目により評価した課税時期における価額に、その宅地の造成に係る費用現価の100分の80に相当する金額を加算した金額によって評価する旨定めている。
(ト)評価通達24-4《広大地の評価》は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条《定義》第12号に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(以下「広大地」という。)の価額は、その広大地が路線価地域に所在する場合には、原則として、次の算式により計算した数値を評価通達15に定める補正率として評価通達15から20までの定めによって計算した金額によって評価する旨定めている。
広大地の補正率=公共公益的用地となる部分の地積÷広大地の地積
(チ)評価通達26《貸家建付地の評価》は、貸家建付地の価額は、その宅地の自用地としての価額から、その自用地としての価額に、評価通達27《借地権の評価》の定めによるその宅地に係る借地権割合と評価通達94《借家権の評価》の定めによるその貸家に係る借家権割合との相乗積を乗じて計算した価額を控除した価額によって評価する旨定めている。
(リ)評価通達91《建築中の家屋の評価》は、課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する旨定めている。
ロ N国税局長が定めた平成10年分の財産評価基準書(以下「財産評価基準書」という。)は、市街地農地等の平坦な土地を宅地に転用するために通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額について、その土地の現況に応じ、次に掲げる造成工事の費目別の工事量(体積又は面積)を積算し、当該積算した工事量に費目別の工事単価を乗じて計算した金額の合計額を当該土地の地積で除して求めた金額とする旨定めている。
(イ)伐採・抜根費は、伐採・抜根をする土地の面積1平方メートル当たり500円
(ロ)地盤改良費は、地盤改良する土地の面積1平方メートル当たり900円
(ハ)整地費は、地ならしする土地の面積1平方メートル当たり850円
(ニ)土盛費は、埋め立てる土砂の体積1立方メートル当たり4,200円
(ホ)土止費は、構築する擁壁の面積1平方メートル当たり41,000円
ハ 租税特別措置法通達(平成元年5月8日付直資2-208国税庁長官通達。平成10年6月18日付課資2-242による改正前のものをいい、以下「措置法通達」という。)69の3-2《事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合》は、事業場の移転又は建て替えのため被相続人等の事業の用に供されていた建物等を取り壊し、又は譲渡し、これらの建物等に代わるべき建物等で、被相続人等の事業の用に供されると認められるものの建築中に、又は当該建物等の取得後被相続人等が事業の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合において、当該被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族等が当該建物等を相続税の申告書の提出期限までに事業の用に供しているときは、当該建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、租税特別措置法(平成11年法律第9号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第69条の3《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等に当たるものとして取り扱う旨定めている。
ニ 農地法第4条《農地の転用の制限》第1項5号において、市街化区域内にある農地を農地以外のものにする者は、あらかじめ農業委員会に届け出なければならない旨規定し、また、農地法第5条《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》第1項3号は、市街化区域内にある農地を農地以外のものにするため、これらの土地について、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他使用収益を目的とする権利を設定し若しくは移転する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出なければならない旨規定している。
(4)基礎事実
以下の事実は、請求人ら及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所が調査したところによっても、その事実が認められる。
イ 建物賃貸借に関する覚書
被相続人、本件土地の隣接地の所有者であるP(以下、「P」といい、被相続人と併せて「被相続人ら」という。)及びQ生活協同組合(以下、「Q生協」といい、被相続人らと併せて「本件敷地所有者」という。)の三者は、平成5年10月26日に、建物賃貸借に関する覚書(以下「本件覚書」という。)を交わしており、その要旨は次のとおりである。
(イ)本件敷地所有者は、本件土地、P所有の別表2の番号4及び5の土地並びにQ生協が取得する予定の別表2の番号6ないし9の土地(以下、これら別表2の番号1ないし9の土地を併せて「本件建物敷地」という。)に、三者共同の商業施設関連建物(以下「本件建物」という。)を建築し、それを共有する。
(ロ)Q生協は、本件覚書の締結と同時に、契約証拠金として被相続人に19,500,000円、Pに3,000,000円を差し入れた。
(ハ)本件覚書は、本契約を締結する日まで有効とする。
ロ 土地建物賃貸借契約
本件敷地所有者は、平成7年9月7日付で、本件覚書に基づき土地建物賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結しており、その要旨は次のとおりである。
(イ)本件敷地所有者は、本件建物敷地にQ生協が希望する本件建物を建築し、これを共有する。
(ロ)Q生協は、本件建物敷地及び本件建物を専用で使用するものとし、被相続人らが本件建物敷地及び本件建物の使用権を放棄する代償として、賃借料総額3,761,000円を、被相続人らの所有する土地のそれぞれの評価額に応じた比率で振り分け、被相続人に対して2,745,906円、Pに対して1,015,094円をそれぞれ毎月支払う。
(ハ)本件建物の建築着工は、許認可手続、地元調整、商業調整等が解決し、農地法第4条の許可が下りた後とする。ただし、平成7年11月1日を経過してもなお、着工の見通しがつかない場合は、協議の上契約継続の可否を決定する。
(ニ)本件建物の許認可に関するすべての手続(開発行為・建築確認・近隣住民との調整等)については、Q生協が主となって実務を行う。
(ホ)本件建物の持分比率は、本件建物敷地の持分比率と同比率とし、被相続人が45.38パーセント、Pが13.44パーセント及びQ生協が41.18パーセントとする。
また、本件建物が完成後、当該持分比率により共有登記を行う。
(ヘ)Q生協は、被相続人らに対して、Q生協の開店日から賃借料を支払うものとし、賃貸借期間は、Q生協の開店日から満20年間とする。
(ト)Q生協が本件覚書に基づいて差し入れた契約証拠金は、本件賃貸借契約に係る証拠金(以下「本件証拠金」という。)に充当し、後日、本件建物の建築費が決定した時点で建築協力金の一部に充当する。
(チ)Q生協は、本件建物の建築費が決定した時点で、本件建物の持分比率に従って建築協力金の額を決定する。
(リ)当事者の一方が、本件賃貸借契約に定めた事項を履行しないときは、相手方は催告を要せず直ちに当該契約を解除することができ、被相続人らが契約不履行の場合には、Q生協に対し、本件証拠金を返還するほか同額の違約金を支払い、Q生協が契約不履行の場合には、本件証拠金を放棄するものとする。
なお、これらの違約金を超過する損害金が生じたときは、被相続人らが、その超過損害金も賠償するものとする。
(ヌ)被相続人らが中途解約する場合には、被相続人らは、保証金残額及び敷金をQ生協に返却し、Q生協は、被相続人らの有する本件建物の共有持分を買い取り、被相続人らの土地に借地権を設定する。
ハ 追加契約
被相続人らは、平成9年4月7日に、Q生協と建築協力金、保証金及び敷金についての追加契約(以下「本件追加契約」という。)を締結しており、その要旨は次のとおりである。
(イ)被相続人は、建築協力金の総額225,000,000円のうち、164,272,500円を取得し、そのうち、49,281,750円を敷金とし、114,990,750円を保証金とする。
(ロ)Q生協は、上記(イ)の被相続人の建築協力金から、本件証拠金19,500,000円を差し引いた144,772,500円を、建築費の支払時期に支払う。
(ハ)本件建物の持分比率は、本件賃貸借契約の定めに関係なく、本件建物の建築費総額に対して本件敷地所有者が支払う金額の比率とする。
ニ 計画遅延による迷惑料
株式会社R(以下「R社」という。)は、被相続人らに対して、平成9年3月26日付の「計画遅延による迷惑料について」と題する書面(以下「本件迷惑料書面」という。)を差し入れており、その要旨は次のとおりである。
(イ)事業計画が遅れて迷惑をかけているので、本件賃貸借契約に関係なく平成9年4月から本件賃貸借契約に基づく賃料支払時までの間、被相続人らの土地所有面積に対し坪当たり500円、総額426,560円を毎月支払う(以下、この支払を「本件迷惑料」という。)。
(ロ)被相続人への支払額は、上記金額の73.01パーセントに当たる311,431円である。
ホ 嘆願書
被相続人は、Q生協に対して、平成9年11月17日付の「嘆願書」と題する書面(以下「本件嘆願書」という。)を差し入れており、その要旨は次のとおりである。
(イ)事業計画が遅れ、被相続人の家計のやりくりが不可能となったので、平成9年11月末日から本件賃貸借契約に基づく賃貸料が発生するまで、当該契約による月額2,745,906円の賃貸料のうち745,906円を前倒しで支払い願いたい。
(ロ)本件賃貸借契約に基づく賃貸料が発生した後の支払額は、上記(イ)の前払期間と同期間について、当該契約による賃貸料から前払分を控除して毎月2,000,000円とする。
ヘ 賃借料前払に係る覚書
被相続人とQ生協は、本件嘆願書に基づいて、平成9年11月25日付で覚書(以下「本件賃借料覚書」という。)を交わしており、その要旨は次のとおりである。
(イ)Q生協は、被相続人に対して、平成9年12月1日からQ生協の店舗が開店する日までの間、月額745,906円の賃借料を前払する(以下、この支払を「本件前払賃借料」という。)。
(ロ)本件前払賃借料は、前払した期間分について、Q生協の店舗の開店日以降に支払う賃借料2,745,906円から控除する。
ト 工事請負契約
本件敷地所有者は、株式会社S(以下「S社」という。)と、平成10年3月2日付で、本件建物の請負金額を427,684,744円(そのうち工事価格407,318,804円、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額20,365,940円)、工期を平成10年2月12日着工で、平成10年8月25日完成予定とする本件建物等に係る工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。
チ その他
(イ)Q生協の開発部統括部長(現常務理事)T(以下「T」という。)が平成10年3月2日付で作成した書面によれば、本件賃貸借契約に基づく、Q生協コープU新築工事(以下「本件新築工事」という。)に係る工事代金の総額は427,684,744円(消費税等込み)で、そのうち、被相続人が164,272,500円(38.4パーセント)、Pが60,727,500円(14.2パーセント)及びQ生協が202,684,744円(47.4パーセント)を、それぞれ負担する旨記載されている。
(ロ)被相続人は、平成10年3月2日にS社に対し、本件建物等の被相続人の持分に係る工事代金の前払として32,909,500円を支払った。
(ハ)S社が作成した「出来高明細総括表」と題する書面によれば、本件相続開始日である平成10年4月7日現在の本件新築工事に係る累計出来高は、11,800,000円(消費税別)であり、その内訳は、本体建物建築費2,080,000円、屋外施設費等5,691,260円及び総合仮設費等4,028,740円である。
(ニ)本件建物の登記事項証明書によれば、平成10年10月19日付で、平成10年9月14日新築を原因として、有限会社V、P及びQ生協を権利者とする所有権保存登記がされ、その共有持分は、それぞれ1000分の384、1000分の142及び1000分の474である。
なお、有限会社Vは、平成10年9月7日にKが設立し、平成10年9月23日に、本件賃貸借契約における賃貸人の地位を承継した。
(ホ)請求人らは、本件修正申告書において、本件前払賃借料の合計額3,729,530円を被相続人の債務として控除している。
2 主張
(1)請求人らの主張
原処分は、次のとおり違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 本件更正処分
(イ)本件土地の評価
A 本件土地の評価単位
原処分庁は、本件土地を2つに区分してそれぞれ評価しているが、本件土地は、W県知事の開発許可を受け、Q生協の店舗用地として他の土地と一体となって利用されるのであるから、当該開発許可を受けた土地のうち、借地である部分を除く本件建物敷地は、1画地の宅地として評価すべきである。
B 本件土地の評価方法
本件土地の評価額は、次のとおり、本件建物敷地の評価額を算定し、その評価額に本件建物敷地に占める本件土地の面積の割合を乗じて算出すべきである。
(A)本件建物敷地の自用地としての評価額
本件建物敷地の自用地としての評価額は、評価通達に基づき、次により算定すべきである。
a 本件建物敷地は、宅地として評価する。
b 正面路線は、路線価の高い国道○○号線とする。
c 本件建物敷地は、花びら形をした広大な土地で、他人の土地が4箇所にわたって囲むように食い込んでいるため、諸施設の建築等に支障を来たし利用が制限され、また、間口が狭小で奥行きが長大であるから、不整形地として、その評価額を30パーセント減額する。
d 本件建物敷地は、国道○○号線と市道○○線の交差点に位置し、交差点付近に出入口を設けると交通渋滞を起こす原因となるため、正面路線である国道○○号線に接する別表2の番号4の土地から出入りができないことになるから、無道路地として、その評価額を20パーセント減額する。
e 本件建物敷地は、北より西側へ1.5メートル、南側へ1.5メートル下る緩やかなスロープ状の土地であり、その20パーセントががけ地であるから、がけ地補正(補正率0.93パーセント)をする。
f 別表2の番号2の土地は、公的な児童公園に指定された余遊地であり、自由に利用できないことから、その評価額を40パーセント減額すべきである。
g 以上のことから、本件建物敷地の自用地としての評価額は、別表4の(1)のとおり、647,938,409円となる。
(B)本件建物敷地の貸家建付地としての評価
本件建物敷地については、本件相続開始時において、本件賃貸借契約が結ばれていることから、評価通達26に定める貸家建付地として評価すべきである。
また、措置法通達69の3-2では、貸家を取り壊した後に、新たに貸家を建築中であった場合においても、その敷地は貸家建付地としての評価が認められているところ、本件建物も本件相続開始時において建築中であるが、本件申告時には、本件賃貸借契約どおり、本件建物が完成し、賃貸借が開始しているのであるから、本件建物敷地を貸家建付地に準じて評価しても不合理ではない。
(C)本件建物敷地の賃借権が付着した土地としての評価
本件建物敷地が、貸家建付地に該当しないとしても、次のとおり、本件相続開始時において、本件土地にはQ生協の賃借権が存在するから、その評価額を減額すべきである。
a 被相続人がX市農業委員会に提出した本件土地に係る農地法第5条第1項第3号の規定による農地転用届出書(以下「本件農地転用届出書」という。)において、「権利を設定、移転しようとする契約の内容」欄には、賃貸借権の設定である旨記載し、また、当該権利の設定時期、存続期間についても、受理後20年間と記載しているから、その提出日である平成10年1月23日に、Q生協の賃借権が設定されている。
b 本件前払賃借料は、地代の授受と同じであるから、それを受け取った時点で、本件建物敷地には賃借権が生じている。
c 本件迷惑料は、賃貸料の補償であり、地代に当たるから、それを受け取った時点で、本件建物敷地には賃借権が生じている。
(D)評価方法に定めのない財産としての評価
本件建物敷地は、上記(B)及び(C)に該当しないとしても、次のとおり、その評価額を減額すべき事情があるから、評価通達5に定める「評価方法に定めのない財産」に該当する。
そうすると、本件建物敷地の評価額は、貸家建付地の評価方法に準じて算定すべきであり、そのように評価したとしても、社会通念上、不適切、不公平なものとはいえない。
a 本件賃貸借契約は、本件相続開始前に結ばれており、この契約は相続人に引き継がれているから、本件土地は、不特定多数の間において、自由な売買ができない拘束された土地である。
b 本件建物は、本件相続開始時において建築中であり、完成後、Q生協に賃貸されることが決定していることから、本件土地の利用が制限されている。
c 被相続人らが、本件賃貸借契約を一方的に破棄し、第三者に本件土地を譲渡するためには、賃借人が解約時までに支出した計画立案費用、建築費用等の莫大な金額を損害賠償金として支払わねばならないから、当該金額を本件土地の評価額から控除すべきである。
(E)本件土地の評価額
以上のことから、本件土地の評価額は、別表4のとおり、本件建物敷地を貸家建付地の評価方法により算定した額に、本件建物敷地に占める本件土地の面積の割合を乗じて算出した、223,470,644円とすべきである。
(ロ)債務控除
被相続人が支払うべき平成10年分の固定資産税及び住民税の額は、債務として、相続税の計算において控除すべきである。
ロ 本件賦課決定処分
上記イのとおり、本件更正処分は取り消されるべきであるから、本件更正処分に基づく本件賦課決定処分も取り消されるべきである。
(2)原処分庁の主張
原処分は、次のとおり適法であるから、本件審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 本件更正処分
(イ)本件土地の評価
A 本件土地の評価単位
本件土地は、本件相続開始時において、Q生協に貸し付けられていたとは認められないことから、本件建物敷地を同一の目的に供されている1画地の土地として評価することはできず、別表2の番号1及び2と番号3の土地を、それぞれ別個に評価すべきである。
B 本件土地の評価方法
(A)本件建物敷地の自用地としての評価額
請求人らは、本件建物敷地を1画地の土地として評価することを前提として、本件建物敷地の形状等に応じた補正等を行うべきである旨主張するが、上記Aのとおり、本件建物敷地は、1画地の土地として評価することができないから、評価上の補正等の必要性も認められない。
(B)本件建物敷地の貸家建付地としての評価
a 本件建物は、本件相続開始時において、建築中であり、現実には貸し付けられておらず、また、Q生協に本件建物の引渡しも行われていないのであるから、Q生協が、本件相続開始時に、本件建物の賃借権を有していたものとは認められない。
また、本件賃貸借契約書によれば、本件建物の賃貸借期間は、Q生協の開店日から満20年間とされているところ、本件相続開始時において、本件建物が未完成であり、Q生協が開店していないのであるから、本件建物に、Q生協の賃借権が生じていたとは認められない。
なお、請求人らは、措置法通達69の3-2を引用して、本件建物が建築中であっても、その敷地を貸家建付地として評価できる旨主張するが、当該通達は、措置法第69条の3の規定の適用の可否についての取扱いであり、評価の方法を定めたものではない。
したがって、本件土地は、貸家建付地として評価することはできない。
b 請求人らは、本件土地が貸家建付地に該当しないとしても、本件相続開始時に、Q生協の賃借権が存在するから、本件土地の評価額を減額すべきである旨主張するが、次のとおり、請求人の主張には理由がない。
(a)農地法第5条第1項第3号の規定による農地転用の届出は、農地法の制約を解除するためのものであって、当該届出によって直ちに賃借権が設定されるものではないから、本件土地に賃借権が生じているとはいえない。
(b)被相続人は本件前払賃借料の支払を受けているが、本件賃貸借契約によれば、賃貸借期間は、Q生協の開店日から満20年間とされており、本件相続開始時において、Q生協に賃借料の支払義務は発生していない。
さらに、請求人らは、本件修正申告書において、本件前払賃借料相当額を債務に計上しており、本件相続開始時において、未だ賃貸料を受け取るべきことが確定していないことを自認しているのであるから、本件相続開始時において、本件土地に控除すべき権利が存していたとは認められない。
(c)本件迷惑料は、本件建物の建築が遅れたため、被相続人が賃貸料の支払を受けられないことから支払われたものであり、地代には該当せず、当該支払によって賃借権が生じたものとは認められない。
c また、請求人らは、上記a及びbの主張が認められないとしても、本件土地の評価額を減額すべき事情があるから、評価通達5に定める「評価方法の定めのない財産」に該当し、本件土地を貸家建付地の評価方法に準じて算定すべきである旨主張するが、次のとおり、請求人の主張には理由がない。
(a)本件相続開始時において、本件賃貸借契約が締結されているとしても、本件建物にQ生協の賃借権が生じていないのであるから、Q生協に、本件土地の評価に影響を与える何らかの権利が生じているとはいえず、本件土地が、法的に拘束された土地であるとはいえない。
(b)本件建物は、本件建物敷地上に建築されるものであり、このことは、自己の土地に自己の建物を建築することと同様であり、他人から利用の制限を受けているとは認められないから、そのような事情を評価上考慮できない。
(c)本件相続開始時において、本件賃貸借契約が解約された事実はなく、仮に本件相続開始後、本件賃貸借契約が解約され、違約金等を負担することとなったとしても、この負担は、被相続人に帰属するものではないから、そのような事情を評価上考慮できない。
C 本件土地の評価額
以上のことから、本件土地の評価額は、評価通達に基づき自用地として算定すべきものであり、別表5のとおりとなる。
(ロ)債務控除
固定資産税及び住民税の未納税額については、原処分の段階において主張がなく、本件に係る調査関係書類においても、これらを認めるに足る事実は認められない。
(ハ)以上のとおり、請求人らの本件相続に係る税額等は、別表10の「原処分庁主張額」欄のとおりとなるから、この金額でされた本件更正処分は適法である。
ロ 本件賦課決定処分
上記イのとおり、本件更正処分は適法であるから、本件賦課決定処分も適法である。
3 判断
(1)本件更正処分
イ 認定事実
請求人ら提出資料、原処分関係資料及び当審判所が調査したところによれば、次の事実が認められる。
(イ)財産評価基準書によれば、本件建物敷地が接する路線に付された路線価は、国道○○号線が280,000円、市道○○線が266,000円であり、地区区分は、普通商業・併用住宅地区である。
(ロ)Tが当審判所に提出した本件新築工事に係る関係資料の内容の要旨は、次のとおりである。
A Q生協は、平成9年12月26日付でW県知事に対して、都市計画法第29条《開発行為の許可》の規定に基づき、〔1〕開発区域に含まれる地域を別表2の土地(以下「本件開発許可地」という。なお、位置関係については別表3参照。)、〔2〕開発区域の面積を5,320.87平方メートル、〔3〕予定建築物等の用途を物販店舗であるとする開発許可申請を行っている(以下、この申請を「本件開発申請」という。)。
また、本件開発申請は、W県知事から平成10年1月21日付で許可されている(以下、この許可を「本件開発許可」という。)。
B Q生協が平成9年11月5日付でX市長に提出した都市計画法第 32条《公共施設の管理者の同意等》の規定に基づく「都市計画法第32条による協議について」と題する書類によると、本件開発許可地に新たに設置される公共施設用地は、道路193.18平方メートル、緑地163.73平方メートル及び水路敷147.59平方メートルであり、従前の公共施設用地は里道敷106.18平方メートル(別表2の番号13ないし16の土地)である旨記載されている。
C Q生協は、平成7年12月29日付の土地賃貸借契約書により、別表2の番号11の土地について、借地期間を平成9年1月1日から平成28年12月31日までの20年間とする事業用借地権を設定している。
D Q生協は、平成8年11月11日付の土地賃貸借契約書により、Z(以下「Z」という。)が所有するX市m町○丁目○番○所在の土地の一部(分筆後の所在地番は○番○。)と、被相続人の所有する別表2の番号3の土地の一部(分筆後の所在地番は○○番○。)とを交換するまで、Zに対して、本件新築工事の着工月の翌月から上記交換予定地の賃借料を支払う旨約している。
E Q生協は、別表2の番号10の土地を、平成9年12月24日付の売買契約により取得した。
(ハ)S社のnが当審判所に提出した本件新築工事に係る本件開発許可地の測量図面及び本件建物の設計図の内容の要旨は、次のとおりである。
A 本件開発許可地は、市道○○線及び国道○○号線に接しており、その間口距離は、市道○○線側が96.37メートル、国道○○号線側が株式会社qを挟んで西側が20.00メートルで東側が17.90メートルである。
また、市道○○線側に基準点を設けた高低差測量によると、本件開発許可地が接する双方の道路は、その交差点を基点に緩やかな上り勾配があり、市道○○線側が交差点から約96メートルの地点で1.85メートル高くなっており、国道○○号線側が交差点から約80メートルの地点で1.23メートル高くなっている。
なお、測量によれば、本件開発許可地は、そのほとんどが道路面より低い位置に所在する。
B 本件建物は、市道○○線側を正面玄関として建築する予定である。
(ニ)Kは、当審判所に対して、次のとおり答述した。
A 本件土地では、平成7年まで米を作っていたが、それ以降は耕作していない。
B 本件開発許可地は、造成工事のために建設機械が入り、本件相続開始時には、段差がなくなり、各土地の境界線が分からない状態であった。
C 別表2の番号3の畑には、ヒバや柿の木が植えてあったが、本件相続開始時には既に伐採されていた。
D Q生協との開発行為に係る交渉は被相続人が行っており、請求人らは、被相続人から、〔1〕警察関係者の意見では、交通渋滞を起こさないため、国道○○号線側に進入路を確保しなければ開発許可が下りないこと、及び、〔2〕Q生協が市道○○線側からの進入路として使用する土地を賃借するということを聞いていた。
E 本件賃貸借契約を破棄した場合に相手方から要求されると想定される損害賠償金の額は、〔1〕受取保証金の倍返しの額39,000,000円、〔2〕建築費用総額427,684,744円、〔3〕喪失費用の額4,276,847円、〔4〕逸失利益の額213,842,372円、及び、〔5〕訴訟費用等の額12,916,079円の合計697,720,042円である。
F 本件迷惑料については、R社と書面を交わしたが、実際の支払者はQ生協である。
また、本件迷惑料を受領することとなった理由は、本件賃貸借契約で「工事は速やかに始める。」となっていたにもかかわらず、余りにも工事に取り掛かるのが遅れたことによるものである。
G 本件賃貸借契約では、完成後の建物は土地の面積比率と同率で共有登記とすることになっており、契約当事者相互間での借地権は発生しないことで合意している。
H 被相続人、Q生協及びZの三者は、道路となっているZ所有の別表2の番号12の土地と被相続人所有の別表2の番号3の土地の一部を交換し、被相続人が別表2の番号12の土地をX市に寄附することで合意していると被相続人から聞いていたので、平成13年6月にこれを実行した。
(ホ)Tは、当審判所に対し、次のとおり答述した。
A 本件前払賃借料は、被相続人から本件嘆願書により申出があったため、Q生協が店舗の開店日以後に支払うべき賃借料を前払したものであり、本件土地及び本件建物の賃借料ではない。
なお、本件賃貸借契約に基づく賃借料は、Q生協の開店日である平成10年9月23日から支払っている。
B 本件迷惑料は、当初のオープン予定が大幅に遅れることとなったため、平成9年4月1日から地代相当分として被相続人へ月額311,431円を支払ったが、迷惑料とは考えていない。
また、本件迷惑料については、金額的には、駐車場として利用した場合の地代の30パーセント程度と固定資産税分相当額に当たると思うが、Q生協は、本件建物が完成するまで、本件土地を使用しておらず、その引渡しも受けていないのであるから、本件賃貸借契約を拘束するための支払であると考える。
C 本件開発許可地内に所在する別表2の番号13及び14の里道敷は、平成10年11月27日に国から払い下げを受けたが、別表2の番号15及び16の里道敷は、国有地からX市の帰属になったが、国又はX市から賃借していない。
D 被相続人、Q生協及びZの三者は、被相続人所有のX市m町○丁目○○番○の土地とZ所有の別表2の番号12の土地を交換し、交換後に同所○番○をX市に寄附する旨を合意しており、この合意に基づいて、Q生協は、Zが交換により取得する予定の同所○○番○について、Zと土地賃貸借契約書を交わした。
なお、Q生協は、上記交換による所有権移転登記まで、Zが所有する別表2の番号12の土地に対して、賃借料を支払うことにしているので、当該土地に賃借権を有している。
(ヘ)S社のrは、当審判所に対し、要旨次のとおり答述した。
A 本件建物の建築工事は、宅地造成工事と並行して行った。
B 平成10年4月7日現在の宅地造成費の額は、出来高明細総括表によれば、屋外施設等5,691,260円(消費税別)となる。
なお、工事の明細は残っていないが、進入路の造成や擁壁の工事費に係るものであると記憶している。
(ト)X市役所都市整備部の担当者は、当審判所に対し、要旨次のとおり答述した。
A 公園、広場等は、都市計画法施行令第25条《法第33条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目》第6号の規定により、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあっては、その面積の3パーセント以上を設けなければならないが、予定建築物が商業施設である場合には特に設置する必要がない。
ただし、W県の条例では、予定建築物の用途が商業施設であっても、公共施設に当たる広場等を敷地の3パーセント以上設けるよう指導することになっている。
なお、設置した広場等は、X市の帰属とはならない。
B 本件開発許可地の開発に関しては、同地が市道○○線に接していることから、都市計画法上、開発区域内道路を設置する必要はないが、予定建築物の用途、状況等を勘案して、国道○○号線側にも進入路を設けることになった。
なお、当該進入路は、Q生協との間で工事完成後、公共施設としてX市に帰属させる旨協議済である。
(チ)被相続人及びQ生協は、本件農地転用届出書を平成10年1月23日にX市農業委員会へ提出し、同市農業委員会は、平成10年2月4日に本件農地転用届出書の受理通知を交付した。
なお、本件農地転用届出書の「権利を設定、移転しようとする契約の内容」欄には、権利の種類は賃貸借権の設定、「権利設定の時期」欄には当該届出書の受理後、及び「存続期間」欄には20年間との記載がある。
また、本件農地転用届出書には、本件開発許可書の写しが添付されている。
(リ)X市農業委員会の職員は、当審判所に対し、要旨次のとおり答述した。
A 敷地内に共有建物を建築する場合には、農地法第4条ではなく同法第5条の規定による申請又は届出を行うよう指導している。
B 本件農地転用届出書は、本件土地にQ生協が建物を建築する旨の本件開発許可書の写しが添付されているため、転用目的を賃貸借権の設定としたものと思われる。
(ヌ)請求人らの代理人であるt税理士は、当審判所に対し、要旨次のとおり答述した。
A 本件建物敷地の評価において、正面路線を国道○○号線とした理由は、国道○○号線の路線価の方が市道○○線の路線価より高いためである。
B 不整形地補正は、評価通達において30パーセントの範囲内で控除できることになっているので、本件建物敷地の形状から最大の30パーセントが妥当であると判断したものであって、具体的な算定根拠はない。
(ル)本件相続開始時の被相続人に係る固定資産税及び住民税の未納額は、別表10のとおり2,936,500円である。
なお、当該未納額の負担者は、Kである。
ロ 本件土地の評価について、上記1の(4)の基礎事実及び上記イの認定事実を上記1の(3)の関係法令等に照らして、以下審理する。
なお、請求人ら及び原処分庁の双方とも、上記1の(3)のイの評価通達の定めによることに異議がなく、当審判所においても当該評価通達の定めを相当と認める。
(イ)本件土地の評価
A 本件土地の評価単位
(A)原処分庁は、本件相続開始時において、本件建物敷地が一体となって利用されているとは認められないから、本件土地を2区画の土地として評価すべきである旨主張する。
a ところで、宅地の評価の単位については、評価通達では、上記1の(3)のイの(ロ)のとおり、利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価することとされており、個別の土地が他の筆の土地と一体となって利用され、これと併せて利用の単位である1画地の土地を構成しているか否かについては、数筆の土地が相続開始時には空閑地であって、一体となって利用されるに至っていない段階であっても、その土地全体の状況と利用目的とを総合的に考慮し、近い将来それを1画地として利用する目的が具体的に定まっており、かつ、土地の状況その他から見てその実現が確定的であると認められるような場合においては、その数筆の土地が利用の単位となる1画地の土地を構成するものとして、当該1画地の土地についての価額の評価を通じて個別の土地の価額を評価することが相当であると解される。
b また、土地の所有者が隣接している土地を借りてその土地を専属的に使用できる場合において、これを自己の所有する土地と一体として利用するときは、当該借地についても、自己の所有する土地と併せて1画地の土地を構成するものとして評価することが相当であると解される。
(B)これを本件についてみると、本件相続開始時において、〔1〕上記1の(4)のロのとおり、本件敷地所有者が本件建物敷地に本件建物を建築して、Q生協が店舗として賃借するという本件賃貸借契約を締結していること、〔2〕上記イの(ロ)のAのとおり、Q生協は、本件建物敷地を含む本件開発許可地について、本件開発許可を受けていること、及び、〔3〕上記1の(4)のト及びチの(ハ)のとおり、平成10年3月2日付で本件請負契約が締結され、本件相続開始時には、本件新築工事に着手していることからして、本件敷地所有者が、本件建物敷地に、Q生協が店舗として使用する本件建物を建築することは明らかであり、本件建物敷地が1画地の店舗用地として使用されることは確定的であると認められる。
そうすると、本件土地を含む本件建物敷地は、本件建物の敷地として一体として利用される土地であるというべきであるから、本件建物敷地が一体として利用されていないとする原処分庁の主張は、採用することができない。
(C)一方、請求人らは、一体として利用されている土地の範囲について、本件開発許可地には借地が存在するから、本件建物敷地のみを1画地の土地として評価すべきである旨主張する。
a しかしながら、本件開発許可地のうち別表2の番号11ないし16の土地については、本件相続開始時において、本件敷地所有者が所有権を有していないが、〔1〕上記イの(ロ)のC及びD並びに(ホ)のDのとおり、別表2の番号11及び12の土地については、本件敷地所有者のうちのQ生協が、それぞれの所有者から賃借して専属的に使用する権利を得ており、また、〔2〕上記イの(ホ)のCのとおり、別表2の番号13及び14の土地については、Q生協が国から払い下げを受けることとなっており、さらに、別表2の番号15及び16の土地については、国又はX市からの賃借がされていないことが認められる。
b そうすると、Q生協は、本件開発許可地のうち別表2の番号11ないし14の土地について、その所有権又は賃借権に基づいて専属的に使用できる権限を有しているものと認められ、他方、別表2の番号15及び16の土地については、本件敷地所有者に賃借権がなく、本件敷地所有者が専属的に使用できるものとは認められないから、別表2の番号15及び16の土地を除く本件開発許可地(以下「本件単位土地」という。)を一体となって利用されている1画地の土地として評価するのが相当である。
c したがって、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
B 本件土地の評価方法
本件土地の評価額については、上記Aのとおり、本件単位土地を1画地の土地として評価することから、本件単位土地の評価額を算定し、その評価額に本件単位土地に占める本件土地の面積の割合を乗じて算出することとなる。
(A)本件単位土地の自用地としての評価額
a 土地の評価上の区分
請求人らは、本件建物敷地を宅地として評価すべきである旨主張するが、本件建物敷地を含む本件単位土地は、上記イの(ニ)のB及びC並びに(ヘ)のとおり、本件相続開始時において、宅地造成工事を行っている途中のものであることから、上記1の(3)のイの(ヘ)の造成中の宅地として評価するのが相当である。
そうすると、本件相続開始時における本件単位土地の自用地としての価額は、本件単位土地の造成工事着手直前の地目により評価した価額(本件単位土地は、造成工事着手直前が市街化区域農地であるから、それが宅地であるとした場合の価額から、本件単位土地を宅地に転用するとした場合において通常必要と認められる造成費に相当する金額を控除した価額)に、本件相続開始時までに投下した本件単位土地の造成に係る費用現価の額の80パーセントに相当する金額を加算した価額になる。
b 正面路線
請求人らは、路線価の高い国道○○号線に付された路線を正面路線とすべきである旨主張する。
(a)ところで、正面路線は、上記1の(3)のイの(ハ)のとおり、原則として路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した1平方メートル当たりの価格の高い方の路線とするのであるが、上記路線を正面とすることが評価土地の最有効利用につながるとはいえない場合及び同路線が評価土地の価額に与える影響が著しく低いと認められる場合は、これを正面路線にしないことができるものと解される。
(b)これを本件についてみると、上記イの(イ)の双方の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算すると、確かに、国道○○号線の方が1平方メートル当たりの価格の高い路線となるが、本件単位土地の場合は、上記イの(ハ)のAのとおり、〔1〕国道○○号線に接する間口距離に比べ、市道○○線に接する間口距離の方が相当に長いこと、〔2〕国道○○号線側は、間口が中央で大きく分離されていること、及び、〔3〕市道○○線側を正面として本件建物の建築が予定されていることなどからみて、市道○○線の方が敷地全体の価額に与える影響度合いが高く、市道○○線を正面路線とした場合に本件単位土地の最有効利用が図られるものと認められることから、市道○○線を正面路線とし、当該路線に付された路線価を正面路線価とするのが相当である。
c 不整形地補正率
請求人らは、本件建物敷地が土地の形状からみて利用が著しく制限された不整形地であるため、整形地としての価額から30パーセントを控除すべきである旨主張する。
(a)確かに、本件建物敷地を含む本件単位土地は、別表3のとおり、不整形地であることから、減価補正を必要とする土地であると認められる。
(b)ところで、評価通達20の(1)は、上記1の(3)のイの(ホ)のとおり、不整形地について、土地の形状が悪いことによって、整形地に比べ宅地としてその効用を十分に発揮できないことから、その程度に応じて、30パーセントの範囲内で減価補正することとしているところ、その不整形地の程度に応じた減価補正の割合について、その具体的基準を示して課税の公平・簡素化を図る観点から、「不整形地補正率について」(平成4年3月3日付資産評価企画官情報第1号。以下「本件情報」という。)が公表され、不整形地の評価は本件情報に基づいて統一的に行われていることが認められる。
(c)本件情報による減価補正の方法は、不整形地である評価対象地に対応する整形地を想定して、当該想定整形地に占める想定整形地と評価対象地との地積の差の割合(以下「かげ地割合」という。)を基に、評価対象地が所在する地区区分及び評価対象地の地積の大小に応じて減価補正する割合を求めるというもので、評価上勘案すべき不整形の程度、その地域の最有効使用、標準的な画地が考慮されており、当審判所においても合理的な減価補正の方法であると認めることができる。
(d)そうすると、本件単位土地について、当審判所が本件情報を基に算定すると、別表6の(1)のとおり、本件単位土地の想定整形地におけるかげ地割合は49.66パーセントとなり、このかげ地割合における不整形地補正率は0.98となる。
(e)これに対し、請求人らが主張する不整形地補正率は、評価通達に定められた補正割合の範囲内ではあるが、上記イの(ヌ)のBのとおり、具体的な算定根拠に基づいて算出された合理的なものとは認められず、請求人らの主張を採用することはできない。
d 無道路地補正
請求人らは、本件建物敷地の正面路線は国道○○号線であり、それに接する土地が進入路として利用できないから、無道路地に該当する旨主張する。
(a)ところで、無道路地とは、上記1の(3)のイの(ホ)のとおり、路線に接していない土地をいうのであって、土地が路線に接していれば、その土地の利用状況いかんにかかわらず、無道路地として評価することはできないものと解される。
(b)これを本件単位土地についてみると、別表3のとおり、別表2の番号2及び5の土地が市道○○線に接し、別表2の番号4の土地が国道○○号線に接しているのであるから、本件単位土地が無道路地に該当しないことは明らかである。
(c)したがって、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
e がけ地補正率
請求人らは、本件建物敷地がスロープ状の土地であり、その20パーセントががけ地であるとして、減価補正すべきである旨主張する。
(a)ところで、評価通達20の(4)は、がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地について、その宅地の評価額を減価補正する旨定めている。
(b)これを本件単位土地についてみると、上記イの(ハ)のAのとおり、市道○○線と国道○○号線の交差点を基点として、それぞれ緩やかな勾配が認められるが、本件開発許可地の測量図面からみて、本件単位土地には通常の用途に供することができないがけ地等は認められない。
(c)また、本件単位土地は、上記イの(ハ)のAのとおり、道路面より低い位置に所在することから、宅地造成が必要な土地ではあるが、後記hのとおり、本件単位土地を宅地造成することにより、そのすべてが通常の用途に供することができる宅地になるものと認められる。
(d)したがって、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
f 児童公園の指定による補正率
請求人らは、本件建物敷地のうち児童公園に指定された部分の土地は、その評価額を40パーセント減額すべきである旨主張する。
(a)しかしながら、本件相続開始時においては、本件単位土地は何ら公園として使用されていないのであるから、当該部分を公園として評価することはできず、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
(b)ただし、上記イの(ロ)のBのとおり、本件開発許可地の開発に当たっては、公共施設として道路、緑地及び水路敷の設置を義務付けられていることから、本件単位土地の評価に当たっては、公共公益的施設用地について、後記gの広大地としての評価においてしんしゃくすべきである。
g 広大地の補正率
(a)本件開発許可地における公共公益的施設用地は、上記イの(ロ)のBのとおり、道路193.18平方メートル、緑地163.73平方メートル及び水路敷147.59平方メートルであるが、水路敷の中には本件単位土地に含まれない別表2の番号15及び16の土地が含まれているため、これを除くと、本件単位土地に係る公共公益的施設用地の面積は、451.69平方メートルとなる。
(b)当審判所が、広大地の評価について、上記面積を上記1の(3)のイの(ト)の評価通達24-4の算式に当てはめて計算すると、別表6の(1)のとおり、広大地の補正率は0.91となり、本件単位土地の奥行価格補正率0.94(別表6の(1)参照)より小さくなることから、広大地の補正率を奥行価格補正率に代えて適用するのが相当である。
h 宅地造成費
(a)本件単位土地については、上記aのとおり、造成中の宅地として、造成工事着手直前の地目(市街化区域農地)に従い、それが宅地であるとした場合の価額から、土盛、土止費等の宅地造成費に相当する金額を控除して評価することになる。
また、一般的に、宅地造成工事の方法は、その使用者の利用目的等により異なるが、本件単位土地の評価に当たっては、宅地造成費について、当審判所に提出された本件開発許可地に係る測量図に基づき、そのうち土盛費については、上記イの(ハ)のAの正面路線である市道○○線の高低差の中間点10.88(基準点10.00、最高点11.80、最低点9.95)を想定平面として宅地造成費に相当する金額を算定するのが合理的であると認められる。
(b)そうすると、本件単位土地の宅地造成費相当額は、当審判所において相当と認める財産評価基準書に基づき算定すると、別表7のとおり、1平方メートル当たり6,848円となる。
i 本件単位土地に係る宅地造成工事の費用現価
本件相続開始時における本件単位土地に係る宅地造成工事の費用現価の額は、上記1の(4)のチの(ハ)及び上記イの(ヘ)のBのとおり、5,691,260円に消費税等を加算した5,975,823円となるから、本件単位土地の造成工事着手直前の地目により評価した価額に加算する金額は、当該費用現価の額の80パーセントに相当する4,780,658円となる。
j 以上のことから、本件単位土地の自用地としての評価額は、別表6の(1)のとおり、1,253,958,849円となる。
(B)本件単位土地の貸家建付地としての評価
a 請求人らは、本件相続開始時において、本件賃貸借契約が結ばれていることから、本件建物敷地が貸家建付地に該当する旨主張する。
(a)ところで、上記1の(3)のチの評価通達26の趣旨は、借家人には借家権はあっても借地権はないのであるが、経済的に見れば、その借家の敷地である宅地に対してもその建物の賃借権に基づいてある程度の支配権を有していると認められるため、その支配権を消滅させるために、いわゆる立ち退き料の支払を要する場合もあるし、また、その支配権が付着したままの状態でその土地を譲渡することとした場合は、その支配権が付着していないとした価額より低い価額でしか譲渡できないこととなるため、その経済的価値が低くなるという事情を考慮したものであるから、貸家建付地として評価額を減額するには、上記のような経済的価値が低くなるような事情がある場合に限られるというべきである。
(b)そうすると、評価通達にいう貸家建付地とは、現に借家権の目的となっている建物の敷地の用に供されている宅地をいうものと解され、また、相続税法第22条《評価の原則》が、相続により取得した財産の価格はその取得の時における時価によるものとしていることからすると、貸家建付地に当たるか否かは、相続開始時を基準として判断されるべきである。
(c)これを本件についてみると、本件相続開始時において、本件建物は建築中であり、本件単位土地上に借家権の目的となっている建物が存在していないのであるから、本件単位土地が貸家建付地に該当しないことは明らかである。
(d)これに対し、請求人らは、本件相続開始時において、既に本件賃貸借契約が締結されている旨主張するが、当該契約は、上記1の(4)のロの(ヘ)のとおり、本件建物が完成し、Q生協の店舗が開店した時から、Q生協が請求人らの共有持分に係る本件建物を賃借するという停止条件付契約であるところ、本件相続開始時においては、本件建物は完成しておらず、開店もしていないのであるから、本件賃貸借契約が締結されていたとしても、本件単位土地にQ生協の支配権が及んでいるものとは認められない。
(e)したがって、この点に関する請求人らの主張は理由がない。
b また、請求人らは、本件建物敷地の評価を措置法通達69の3-2に準じて行うべきである旨主張する。
しかしながら、措置法第69条の3は、相続人等の生活基盤の維持、個人事業者等の事業継承を図ることを目的として、相続財産の経済的な価値には関係なく、特に、相続税の課税価格の軽減を図る優遇措置を認めたものであり、措置法通達69の3-2は、その適用に当たり、相続開始時において建築中である建物の敷地が事業の用に供されているか否かの判断基準を示したものであって、相続財産の一般的な評価方法を定めたものではないから、事業用に供されているか否かの判断と関係のない本件単位土地の評価に当たり、当該措置法通達を準用することはできない。
したがって、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
(C)本件単位土地の賃借権の付着した土地としての評価
請求人らは、次のとおり、本件土地が賃借権の付着した土地に該当するから、その評価額を減額すべきである旨主張するが、いずれも理由がなく、請求人らの主張は採用できない。
a 請求人らは、上記2の(1)のイのBの(C)のaのとおり、本件農地転用届出書が受理された時点で、本件土地には、Q生協の賃借権が生じている旨主張する。
(a)しかしながら、本件農地転用届出書は、農地法第5条第1項第3号の規定による届出であり、当該農地に係る農地法上の制約を解除するためのものであって、これによって賃借権等の権利を設定するというものではなく、当該届出書の受理通知は、届出した農地をその記載した用途に使用することができるという承認を得たにすぎないと解すべきである。
(b)そうすると、本件農地転用届出書の受理通知が交付されたことは、本件土地に本件建物を建築する承認を得たとはいえるが、当該受理通知の交付によって、直ちに本件土地の賃貸借が開始されたということにはならない。
(c)また、本件農地転用届出書では、上記イの(チ)のとおり、設定する権利の種類を賃貸借権とし、権利設定の時期及び存続期間を受理後20年間としているところ、本件賃貸借契約においては、上記1の(4)のロの(ヘ)のとおり、賃貸借期間はQ生協の開店日から20年間となっているのであるから、本件農地転用届出書が受理された時点をもって、Q生協の賃借権が生じたものとは認められない。
b 請求人らは、本件前払賃借料の支払を受けていることから、本件相続開始時点において、本件土地の賃貸借が開始されている旨主張する。
(a)しかしながら、〔1〕本件賃借料覚書によれば、上記1の(4)のホ及びへのとおり、本件前払賃借料は、被相続人の経済的な理由による嘆願に応じて、Q生協が支払うとしたものであること、及び、Q生協の開店日以降は、本件前払賃借料の前払期間分について、本来の賃貸料から控除して支払うとされていることが認められ、また、〔2〕上記1の(4)のチの(ホ)のとおり、本件前払賃借料の合計額は、本件修正申告書において、被相続人の負債として計上されていることが認められる。さらに、〔3〕上記イの(ホ)のAのTの答述からすると、Q生協が、本件前払賃借料を本件建物に係る賃借料と認識していたとは認められない。
(b)そうすると、本件前払賃借料は、Q生協の開店日以降に成立する賃貸借について、将来発生が見込まれる賃借料の前払を受けたもので、被相続人のQ生協からの借入金に相当するものであり、本件建物の賃借料と認められないから、本件前払賃借料の授受によりQ生協に賃借権が生じたものとは認められない。
c 請求人らは、被相続人がQ生協から迷惑料の名目で金員の支払を受けているが、当該支払は賃貸料の補償であり地代である旨主張する。
(a)しかしながら、〔1〕本件迷惑料書面によると、上記1の(4)のニの(イ)のとおり、本件迷惑料は、本件新築工事の事業計画が遅延したことによるものであるから、本件賃貸借契約に関係なく、本来の賃貸料が支払われるまで支払われるものであり、また、〔2〕上記イの(ホ)のBのとおり、Q生協のTは、本件迷惑料の金額を、駐車場として利用した場合の30パーセント程度として算定しているが、本件建物が完成するまで、本件土地を使用しておらず、その引渡しも受けていないのであるから、本件迷惑料は、本件土地の賃借料としての支払ではなく、本件賃貸借契約を拘束するための支払である旨答述している。
(b)そうすると、本件迷惑料は、本件賃貸借契約とは別に、本件賃貸借契約を存続させることを前提として支払われたものであり、本件土地を使用するために支払われた賃借料ではないから、本件迷惑料の支払によって、Q生協に本件土地の賃借権が生じたと認めることはできない。
(D)請求人らは、次のとおり、本件土地が評価方法の定めのない財産に該当するから、貸家建付地の評価方法に準じて本件土地の評価額を減額すべきである旨主張するが、いずれも理由がなく、請求人らの主張は採用できない。
a 請求人らは、本件賃貸借契約が本件土地を強く拘束し、不特定多数の間で自由な取引ができない旨主張する。
(a)確かに、上記(B)のaで述べたとおり、本件賃貸借契約は、本件建物が完成してQ生協が開店した時からQ生協に賃貸するという条件付の契約であり、請求人が主張するように、本件土地の取引に、何らかの制約があることは認められる。
(b)しかしながら、被相続人は、本件土地の有効利用を図るために、自己の意思に基づいてQ生協及びPと共同で、本件土地を含む本件単位土地に店舗用の本件建物を建築するという事業を行うこととしたもので、被相続人の相続人であるKも、本件賃貸借契約上の被相続人の地位を承継し、当該事業を継続しているのであり、また、当該事業の遂行に当たり、本件相続開始時までに、本件土地について、上記(B)及び(C)のとおり、賃貸料を収受している事実も認められないのであるから、本件土地を不特定多数の間で自由な取引ができないとしても、そのことが、本件土地の経済的な価値を低下させるものであるとは認められない。
b また、請求人らは、本件相続開始時において本件建物が建築中であり、その建物が完成後に賃貸することが決まっていることから、本件土地についての利用が制限されている旨主張する。
しかしながら、〔1〕本件賃貸借契約は、上記1の(4)のロのとおり、本件敷地所有者が、それぞれの所有地を一体として使用して、その上に本件建物を建築することとし、完成後の本件建物は、本件敷地所有者における合理的な計算に基づいてそれぞれの所有分を割り当て、共有とすることが定められていること、及び〔2〕上記イの(ニ)のGのとおり、本件敷地所有者相互間において、借地権が発生しないことで合意している旨のKの答述からすると、本件敷地所有者は、それぞれが所有する土地の上に、自己の建物を建設したことと同一の効果を生じさせようとするものであるから、本件建物が建築中であり、完成後に本件建物を賃貸することが決まっていたとしても、このことが、本件相続開始時において、本件土地の評価に影響を及ぼす制約であるとは認められない。
c さらに、請求人らは、本件賃貸借契約を一方的に破棄し、本件土地を第三者に譲渡するためには多大な損害賠償金を支払わなければならないため、本件土地の評価額から、上記イの(ニ)のEの損害賠償金を差し引いた金額が評価額となる旨主張する。
(a)確かに、本件賃貸借契約では、上記1の(4)のロの(リ)のとおり、被相続人らが一方的に当該契約を破棄した場合、被相続人らは、Q生協に対し本件証拠金を返還するほか違約金として本件証拠金と同額を支払い、また、この違約金を超過する損害が生じた場合は、その損害金も賠償する旨定められている。
(b)しかしながら、本件相続開始時において、本件賃貸借契約は解約されておらず、損害賠償金を支払う義務は生じてないのであるから、本件賃貸借契約書に損害賠償金について定められていることが、本件土地の経済的価値に影響を与えるものとは認められない。
(c)なお、仮に、本件相続開始時において、損害賠償金の支払義務が生じていたとしても、それは、相続税の課税価格の計算上、当該支払義務を被相続人の債務として控除すべきか否かの問題であり、本件土地の時価をいかに評価すべきかとは別個の問題である。
C 本件土地の評価額
以上のことから、本件土地の評価額は、別表6の(2)のとおり、本件単位土地の自用地としての評価額に、本件単位土地の地積に占める本件土地の地積の割合を乗じて算出した517,944,802円となる。
(ロ)本件建物の被相続人の持分に係る評価額
本件建物の本件相続開始時の累計出来高には、上記1の(4)のチの(ハ)のとおり、宅地造成に係る費用が含まれていることから、本件相続開始時における本件建物の費用現価の額は、本件建物等の累計出来高11,800,000円から宅地造成に係る費用現価5,691,260円を差し引いた6,108,740円に消費税等を加算した6,414,177円になる。
そうすると、本件建物の被相続人の持分に係る評価額は、別表8のとおり、本件建物の費用現価の額に被相続人の持分比率(38.4パーセント)を乗じた2,463,043円に70パーセントを乗じた1,724,130円となる。
(ハ)前渡金の評価額
被相続人がS社に本件建物等の工事代金として支払っていた額は、上記1の(4)のチの(ロ)のとおり32,909,500円であるが、前渡金の評価額は、別表9のとおり、当該支払額から上記(ロ)で求めた本件相続開始時における本件建物の被相続人の持分価額2,463,043円及び上記(イ)のBの(A)のiで求めた本件単位土地の宅地造成に係る費用現価に占める本件土地の宅地造成に係る費用現価2,468,299円を控除した27,978,158円となる。
(ニ)債務控除の額
被相続人の平成10年度分の固定資産税2,933,000円及び住民税3,500円は、別表10のとおり、本件相続開始時において未納であり、その負担者はKであることから、本件相続に係る相続税の債務として、Kの取得財産の価額から控除すべきである。
ハ 以上の結果、別表11の「審判所認定額」欄に記載のとおり、納付すべき相続税額は、Kが297,859,800円及びLが27,419,400円となり、これらの額はいずれも本件更正処分の額を下回るから、いずれもその一部を取り消すべきである。
(2)本件賦課決定処分
上記(1)のとおり、本件更正処分の一部がそれぞれ取り消されることに伴い、Kに係る過少申告加算税の計算の基礎となる税額は63,200,000円となるところ、この納付すべき税額の基礎となった事実について、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項の規定に基づいて過少申告加算税の額を算定すると6,320,000円となり、また、Lに係る過少申告加算税の計算の基礎となる税額は40,000円となり、過少申告加算税の額は、国税通則法第 119条《国税の確定金額の端数計算等》第4項の規定により零円となり、これらの金額は、いずれも本件賦課決定処分の金額に満たないから、本件賦課決定処分は、Kについてその一部を、また、Lについてその全部を取り消すべきである。
(3)原処分のその他の部分については、請求人らは争わず、当審判所の調査によっても、これを不相当とする理由は認められない。
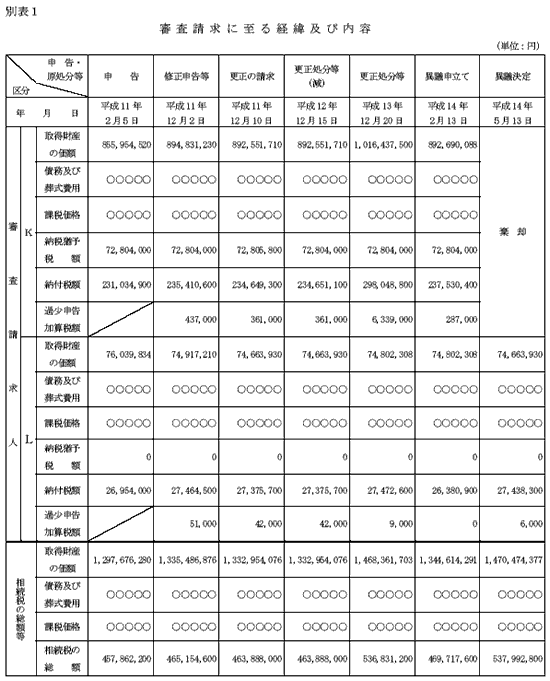
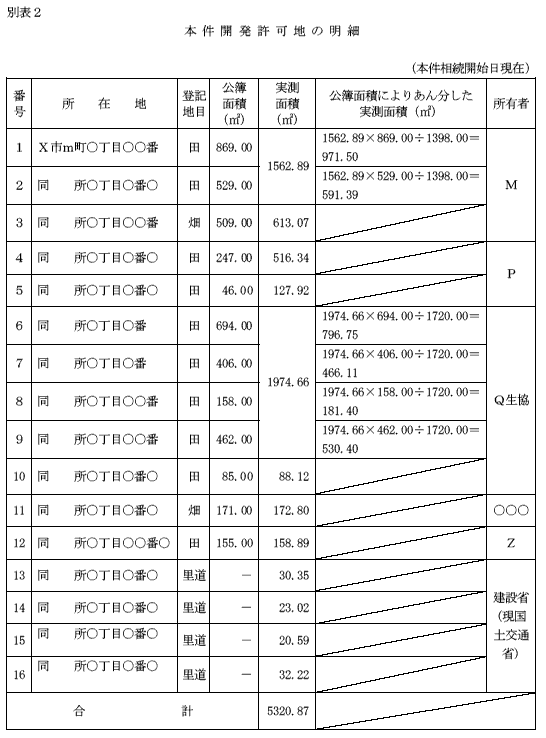
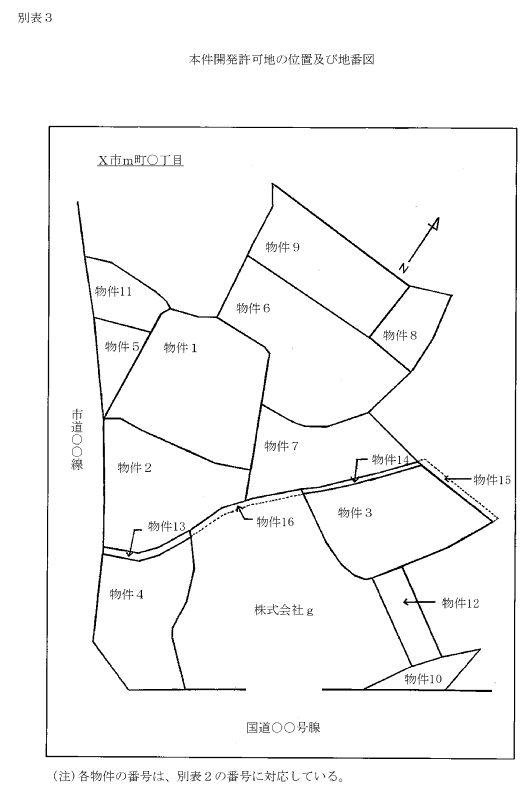
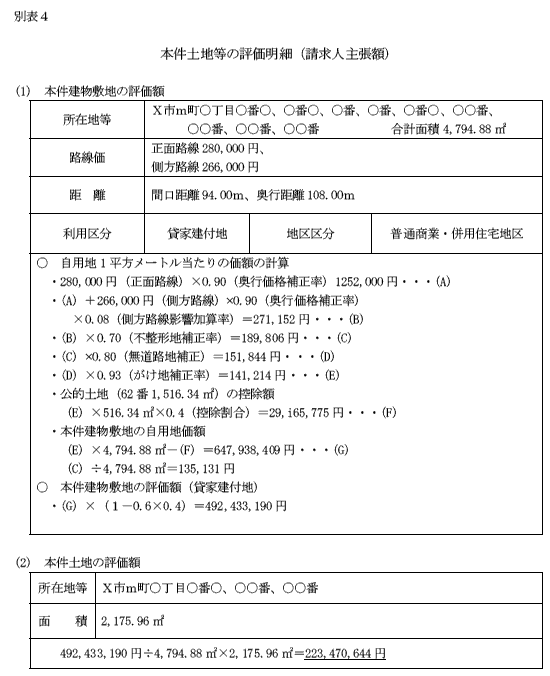
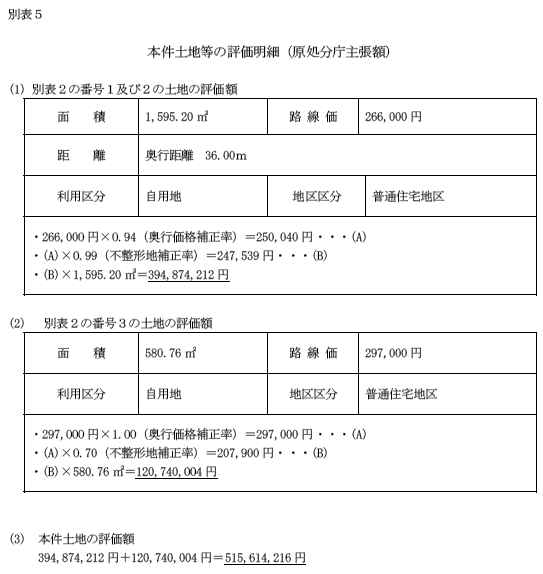
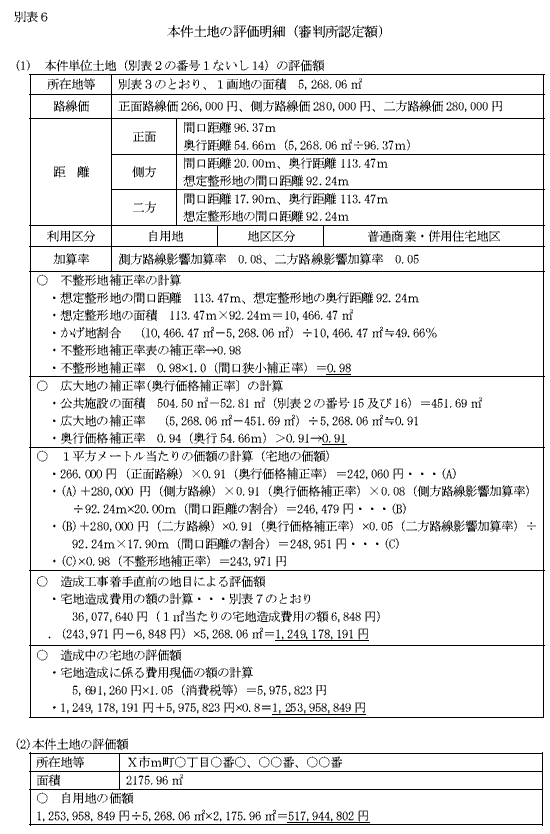
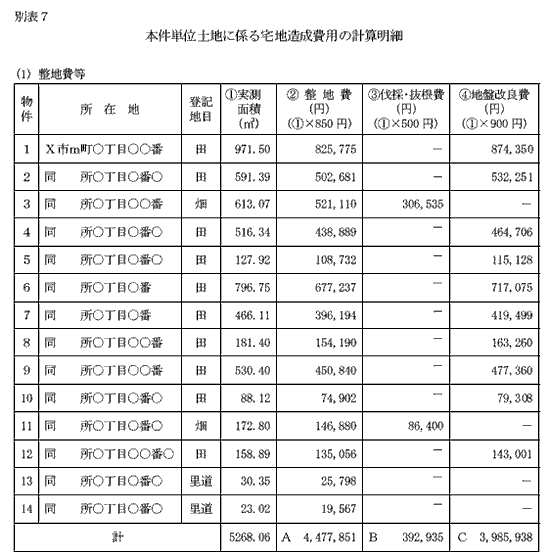
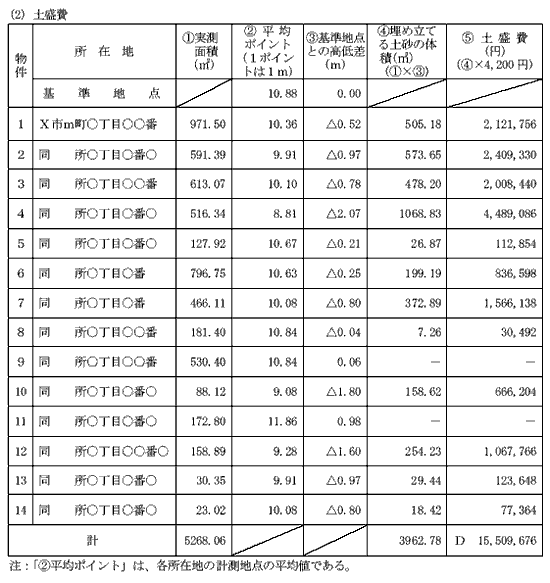
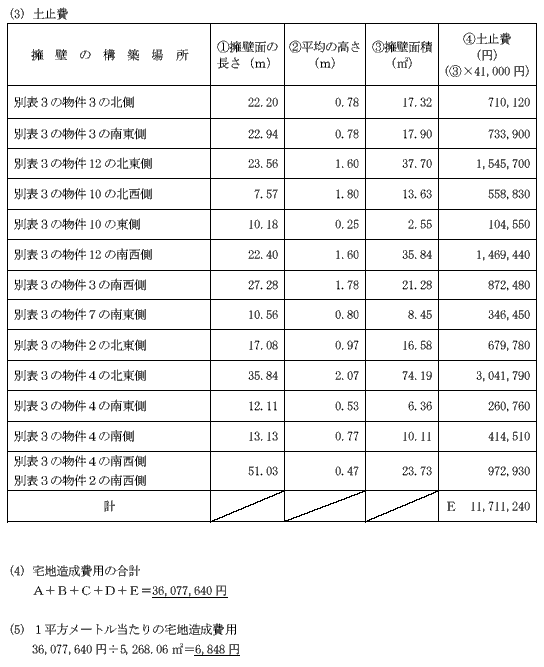
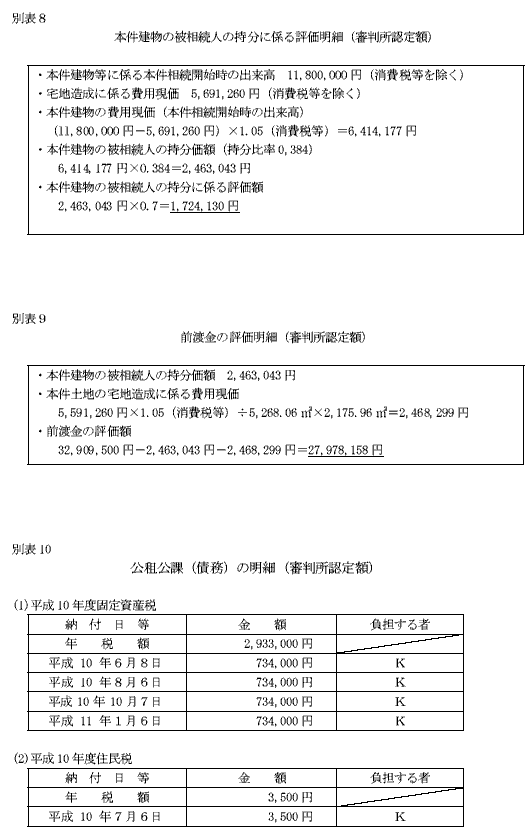
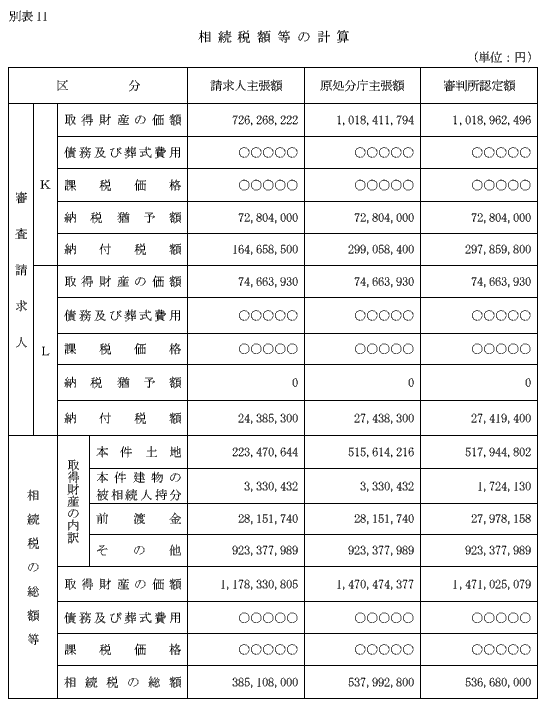
《裁決書(抄)》
1 事実
(1)事案の概要
本件は、審査請求人K及び同L(以下、それぞれ「K」及び「L」といい、両名を併せて「請求人ら」という。)のうち、Kが相続により取得した土地について、他の土地と併せて1画地として評価すべきか否か、また、当該土地が貸家の目的に供されている宅地(以下「貸家建付地」という。)に当たるか否かを主な争点とする事案である。
(2)審査請求に至る経緯及び内容
イ 請求人らは、平成10年4月7日に死亡した父M(以下「被相続人」という。)の相続(以下「本件相続」という。)に係る相続税の申告書に、別表1の「申告」欄のとおり記載して、法定申告期限までに申告した。
ロ その後、請求人らは、Kが本件相続により取得した別表2の番号1ないし3の土地(以下、これらを併せて「本件土地」という。)について、実測面積が申告した面積を上回っていること及び利用区分が定期借地権付きの土地ではなく貸家建付地であるとして、平成11年12月2日に、別表1の「修正申告等」欄のとおり記載した相続税の修正申告書(以下「本件修正申告書」という。)を提出した。
ハ 請求人らは、平成11年12月10日に、本件相続により取得した本件土地以外の土地について評価誤りがあるとして、別表1の「更正の請求」欄のとおり記載した相続税の更正の請求書を提出し、原処分庁は、平成11年12月15日付で、別表1の「更正処分等(減)」欄のとおり相続税の更正処分をした。
ニ 原処分庁は、原処分庁所属職員の調査に基づき、本件土地について、貸家建付地ではなく自用地として評価すべきであるとして、平成13年12月20日付で、別表1の「更正処分等」欄のとおり、相続税の各更正処分(以下「本件更正処分」という。)及び過少申告加算税の各賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)をした。
ホ 請求人らは、上記ニの処分を不服として、平成14年2月13日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、別表1の「異議決定」欄のとおり、平成14年5月13日付で、Kについてはいずれも棄却、Lについては、その一部をいずれも取り消す異議決定をした。
ヘ 請求人らは、異議決定を経た後の原処分に不服があるとして、平成14年6月11日に審査請求をした。
(3)関係法令等
イ 財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56ほか国税庁長官通達。平成11年7月19日付課評2-12による改正前のものをいい、以下「評価通達」という。)は、次のとおり定めている。
(イ)評価通達5《評価方法の定めのない財産の評価》は、評価通達に評価方法の定めのない財産の価額は、この通達に定める評価方法に準じて評価する旨定めている。
(ロ)評価通達10《評価単位》は、宅地の価額は、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいう。)ごとに評価することとし、宅地の上に存する権利の価額についても、同様とする旨定めている。
(ハ)評価通達16《側方路線影響加算》は、正面と側方に路線がある宅地の価額は、次のA及びBに掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する旨定めている。
A 正面路線(原則として、評価通達15《奥行価格補正》により計算した1平方メートル当たりの価格の高い方の路線をいう。)の路線価(以下「正面路線価」という。)に基づき計算した価額
B 側方路線(正面路線以外の路線をいう。)の路線価を正面路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に「側方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価額
(ニ)評価通達17《二方路線影響加算》は、正面と裏面に路線がある宅地の価額は、次のA及びBに掲げる価額の合計額にその宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価する旨定めている。
A 正面路線価に基づき計算した価額
B 裏面路線の路線価を正面路線価とみなし、その路線価に基づき計算した価額に「二方路線影響加算率表」に定める加算率を乗じて計算した価額
(ホ)評価通達20《不整形地、無道路地、間口が狭小な宅地等、がけ地等の評価》の(1)は、不整形地の価額は、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、不整形地を区分して得られる整形地等の価額を基とし、その近傍の宅地との均衡を考慮して、その価額からその価額の100分の30の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価する旨定めている。
また、評価通達20の(2)の注書において、無道路地とは、路線に接しない宅地をいう旨定めている。
さらに、評価通達20の(4)は、がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちに存するがけ地等ががけ地等でないとした場合の価額に、その宅地の総地積に対するがけ地部分等通常の用途に供することができないと認められる部分の地積の割合に応じて「がけ地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する旨定めている。
(ヘ)評価通達24-3《造成中の宅地の評価》は、造成中の宅地の価額は、その土地の造成工事着手直前の地目により評価した課税時期における価額に、その宅地の造成に係る費用現価の100分の80に相当する金額を加算した金額によって評価する旨定めている。
(ト)評価通達24-4《広大地の評価》は、その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で、都市計画法第4条《定義》第12号に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの(以下「広大地」という。)の価額は、その広大地が路線価地域に所在する場合には、原則として、次の算式により計算した数値を評価通達15に定める補正率として評価通達15から20までの定めによって計算した金額によって評価する旨定めている。
広大地の補正率=公共公益的用地となる部分の地積÷広大地の地積
(チ)評価通達26《貸家建付地の評価》は、貸家建付地の価額は、その宅地の自用地としての価額から、その自用地としての価額に、評価通達27《借地権の評価》の定めによるその宅地に係る借地権割合と評価通達94《借家権の評価》の定めによるその貸家に係る借家権割合との相乗積を乗じて計算した価額を控除した価額によって評価する旨定めている。
(リ)評価通達91《建築中の家屋の評価》は、課税時期において現に建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する旨定めている。
ロ N国税局長が定めた平成10年分の財産評価基準書(以下「財産評価基準書」という。)は、市街地農地等の平坦な土地を宅地に転用するために通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額について、その土地の現況に応じ、次に掲げる造成工事の費目別の工事量(体積又は面積)を積算し、当該積算した工事量に費目別の工事単価を乗じて計算した金額の合計額を当該土地の地積で除して求めた金額とする旨定めている。
(イ)伐採・抜根費は、伐採・抜根をする土地の面積1平方メートル当たり500円
(ロ)地盤改良費は、地盤改良する土地の面積1平方メートル当たり900円
(ハ)整地費は、地ならしする土地の面積1平方メートル当たり850円
(ニ)土盛費は、埋め立てる土砂の体積1立方メートル当たり4,200円
(ホ)土止費は、構築する擁壁の面積1平方メートル当たり41,000円
ハ 租税特別措置法通達(平成元年5月8日付直資2-208国税庁長官通達。平成10年6月18日付課資2-242による改正前のものをいい、以下「措置法通達」という。)69の3-2《事業用建物等の建築中等に相続が開始した場合》は、事業場の移転又は建て替えのため被相続人等の事業の用に供されていた建物等を取り壊し、又は譲渡し、これらの建物等に代わるべき建物等で、被相続人等の事業の用に供されると認められるものの建築中に、又は当該建物等の取得後被相続人等が事業の用に供する前に被相続人について相続が開始した場合において、当該被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族等が当該建物等を相続税の申告書の提出期限までに事業の用に供しているときは、当該建物等の敷地の用に供されていた宅地等は、租税特別措置法(平成11年法律第9号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第69条の3《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第1項に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等に当たるものとして取り扱う旨定めている。
ニ 農地法第4条《農地の転用の制限》第1項5号において、市街化区域内にある農地を農地以外のものにする者は、あらかじめ農業委員会に届け出なければならない旨規定し、また、農地法第5条《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》第1項3号は、市街化区域内にある農地を農地以外のものにするため、これらの土地について、所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権、その他使用収益を目的とする権利を設定し若しくは移転する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出なければならない旨規定している。
(4)基礎事実
以下の事実は、請求人ら及び原処分庁の双方に争いがなく、当審判所が調査したところによっても、その事実が認められる。
イ 建物賃貸借に関する覚書
被相続人、本件土地の隣接地の所有者であるP(以下、「P」といい、被相続人と併せて「被相続人ら」という。)及びQ生活協同組合(以下、「Q生協」といい、被相続人らと併せて「本件敷地所有者」という。)の三者は、平成5年10月26日に、建物賃貸借に関する覚書(以下「本件覚書」という。)を交わしており、その要旨は次のとおりである。
(イ)本件敷地所有者は、本件土地、P所有の別表2の番号4及び5の土地並びにQ生協が取得する予定の別表2の番号6ないし9の土地(以下、これら別表2の番号1ないし9の土地を併せて「本件建物敷地」という。)に、三者共同の商業施設関連建物(以下「本件建物」という。)を建築し、それを共有する。
(ロ)Q生協は、本件覚書の締結と同時に、契約証拠金として被相続人に19,500,000円、Pに3,000,000円を差し入れた。
(ハ)本件覚書は、本契約を締結する日まで有効とする。
ロ 土地建物賃貸借契約
本件敷地所有者は、平成7年9月7日付で、本件覚書に基づき土地建物賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)を締結しており、その要旨は次のとおりである。
(イ)本件敷地所有者は、本件建物敷地にQ生協が希望する本件建物を建築し、これを共有する。
(ロ)Q生協は、本件建物敷地及び本件建物を専用で使用するものとし、被相続人らが本件建物敷地及び本件建物の使用権を放棄する代償として、賃借料総額3,761,000円を、被相続人らの所有する土地のそれぞれの評価額に応じた比率で振り分け、被相続人に対して2,745,906円、Pに対して1,015,094円をそれぞれ毎月支払う。
(ハ)本件建物の建築着工は、許認可手続、地元調整、商業調整等が解決し、農地法第4条の許可が下りた後とする。ただし、平成7年11月1日を経過してもなお、着工の見通しがつかない場合は、協議の上契約継続の可否を決定する。
(ニ)本件建物の許認可に関するすべての手続(開発行為・建築確認・近隣住民との調整等)については、Q生協が主となって実務を行う。
(ホ)本件建物の持分比率は、本件建物敷地の持分比率と同比率とし、被相続人が45.38パーセント、Pが13.44パーセント及びQ生協が41.18パーセントとする。
また、本件建物が完成後、当該持分比率により共有登記を行う。
(ヘ)Q生協は、被相続人らに対して、Q生協の開店日から賃借料を支払うものとし、賃貸借期間は、Q生協の開店日から満20年間とする。
(ト)Q生協が本件覚書に基づいて差し入れた契約証拠金は、本件賃貸借契約に係る証拠金(以下「本件証拠金」という。)に充当し、後日、本件建物の建築費が決定した時点で建築協力金の一部に充当する。
(チ)Q生協は、本件建物の建築費が決定した時点で、本件建物の持分比率に従って建築協力金の額を決定する。
(リ)当事者の一方が、本件賃貸借契約に定めた事項を履行しないときは、相手方は催告を要せず直ちに当該契約を解除することができ、被相続人らが契約不履行の場合には、Q生協に対し、本件証拠金を返還するほか同額の違約金を支払い、Q生協が契約不履行の場合には、本件証拠金を放棄するものとする。
なお、これらの違約金を超過する損害金が生じたときは、被相続人らが、その超過損害金も賠償するものとする。
(ヌ)被相続人らが中途解約する場合には、被相続人らは、保証金残額及び敷金をQ生協に返却し、Q生協は、被相続人らの有する本件建物の共有持分を買い取り、被相続人らの土地に借地権を設定する。
ハ 追加契約
被相続人らは、平成9年4月7日に、Q生協と建築協力金、保証金及び敷金についての追加契約(以下「本件追加契約」という。)を締結しており、その要旨は次のとおりである。
(イ)被相続人は、建築協力金の総額225,000,000円のうち、164,272,500円を取得し、そのうち、49,281,750円を敷金とし、114,990,750円を保証金とする。
(ロ)Q生協は、上記(イ)の被相続人の建築協力金から、本件証拠金19,500,000円を差し引いた144,772,500円を、建築費の支払時期に支払う。
(ハ)本件建物の持分比率は、本件賃貸借契約の定めに関係なく、本件建物の建築費総額に対して本件敷地所有者が支払う金額の比率とする。
ニ 計画遅延による迷惑料
株式会社R(以下「R社」という。)は、被相続人らに対して、平成9年3月26日付の「計画遅延による迷惑料について」と題する書面(以下「本件迷惑料書面」という。)を差し入れており、その要旨は次のとおりである。
(イ)事業計画が遅れて迷惑をかけているので、本件賃貸借契約に関係なく平成9年4月から本件賃貸借契約に基づく賃料支払時までの間、被相続人らの土地所有面積に対し坪当たり500円、総額426,560円を毎月支払う(以下、この支払を「本件迷惑料」という。)。
(ロ)被相続人への支払額は、上記金額の73.01パーセントに当たる311,431円である。
ホ 嘆願書
被相続人は、Q生協に対して、平成9年11月17日付の「嘆願書」と題する書面(以下「本件嘆願書」という。)を差し入れており、その要旨は次のとおりである。
(イ)事業計画が遅れ、被相続人の家計のやりくりが不可能となったので、平成9年11月末日から本件賃貸借契約に基づく賃貸料が発生するまで、当該契約による月額2,745,906円の賃貸料のうち745,906円を前倒しで支払い願いたい。
(ロ)本件賃貸借契約に基づく賃貸料が発生した後の支払額は、上記(イ)の前払期間と同期間について、当該契約による賃貸料から前払分を控除して毎月2,000,000円とする。
ヘ 賃借料前払に係る覚書
被相続人とQ生協は、本件嘆願書に基づいて、平成9年11月25日付で覚書(以下「本件賃借料覚書」という。)を交わしており、その要旨は次のとおりである。
(イ)Q生協は、被相続人に対して、平成9年12月1日からQ生協の店舗が開店する日までの間、月額745,906円の賃借料を前払する(以下、この支払を「本件前払賃借料」という。)。
(ロ)本件前払賃借料は、前払した期間分について、Q生協の店舗の開店日以降に支払う賃借料2,745,906円から控除する。
ト 工事請負契約
本件敷地所有者は、株式会社S(以下「S社」という。)と、平成10年3月2日付で、本件建物の請負金額を427,684,744円(そのうち工事価格407,318,804円、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の額20,365,940円)、工期を平成10年2月12日着工で、平成10年8月25日完成予定とする本件建物等に係る工事請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。
チ その他
(イ)Q生協の開発部統括部長(現常務理事)T(以下「T」という。)が平成10年3月2日付で作成した書面によれば、本件賃貸借契約に基づく、Q生協コープU新築工事(以下「本件新築工事」という。)に係る工事代金の総額は427,684,744円(消費税等込み)で、そのうち、被相続人が164,272,500円(38.4パーセント)、Pが60,727,500円(14.2パーセント)及びQ生協が202,684,744円(47.4パーセント)を、それぞれ負担する旨記載されている。
(ロ)被相続人は、平成10年3月2日にS社に対し、本件建物等の被相続人の持分に係る工事代金の前払として32,909,500円を支払った。
(ハ)S社が作成した「出来高明細総括表」と題する書面によれば、本件相続開始日である平成10年4月7日現在の本件新築工事に係る累計出来高は、11,800,000円(消費税別)であり、その内訳は、本体建物建築費2,080,000円、屋外施設費等5,691,260円及び総合仮設費等4,028,740円である。
(ニ)本件建物の登記事項証明書によれば、平成10年10月19日付で、平成10年9月14日新築を原因として、有限会社V、P及びQ生協を権利者とする所有権保存登記がされ、その共有持分は、それぞれ1000分の384、1000分の142及び1000分の474である。
なお、有限会社Vは、平成10年9月7日にKが設立し、平成10年9月23日に、本件賃貸借契約における賃貸人の地位を承継した。
(ホ)請求人らは、本件修正申告書において、本件前払賃借料の合計額3,729,530円を被相続人の債務として控除している。
2 主張
(1)請求人らの主張
原処分は、次のとおり違法であるから、その全部の取消しを求める。
イ 本件更正処分
(イ)本件土地の評価
A 本件土地の評価単位
原処分庁は、本件土地を2つに区分してそれぞれ評価しているが、本件土地は、W県知事の開発許可を受け、Q生協の店舗用地として他の土地と一体となって利用されるのであるから、当該開発許可を受けた土地のうち、借地である部分を除く本件建物敷地は、1画地の宅地として評価すべきである。
B 本件土地の評価方法
本件土地の評価額は、次のとおり、本件建物敷地の評価額を算定し、その評価額に本件建物敷地に占める本件土地の面積の割合を乗じて算出すべきである。
(A)本件建物敷地の自用地としての評価額
本件建物敷地の自用地としての評価額は、評価通達に基づき、次により算定すべきである。
a 本件建物敷地は、宅地として評価する。
b 正面路線は、路線価の高い国道○○号線とする。
c 本件建物敷地は、花びら形をした広大な土地で、他人の土地が4箇所にわたって囲むように食い込んでいるため、諸施設の建築等に支障を来たし利用が制限され、また、間口が狭小で奥行きが長大であるから、不整形地として、その評価額を30パーセント減額する。
d 本件建物敷地は、国道○○号線と市道○○線の交差点に位置し、交差点付近に出入口を設けると交通渋滞を起こす原因となるため、正面路線である国道○○号線に接する別表2の番号4の土地から出入りができないことになるから、無道路地として、その評価額を20パーセント減額する。
e 本件建物敷地は、北より西側へ1.5メートル、南側へ1.5メートル下る緩やかなスロープ状の土地であり、その20パーセントががけ地であるから、がけ地補正(補正率0.93パーセント)をする。
f 別表2の番号2の土地は、公的な児童公園に指定された余遊地であり、自由に利用できないことから、その評価額を40パーセント減額すべきである。
g 以上のことから、本件建物敷地の自用地としての評価額は、別表4の(1)のとおり、647,938,409円となる。
(B)本件建物敷地の貸家建付地としての評価
本件建物敷地については、本件相続開始時において、本件賃貸借契約が結ばれていることから、評価通達26に定める貸家建付地として評価すべきである。
また、措置法通達69の3-2では、貸家を取り壊した後に、新たに貸家を建築中であった場合においても、その敷地は貸家建付地としての評価が認められているところ、本件建物も本件相続開始時において建築中であるが、本件申告時には、本件賃貸借契約どおり、本件建物が完成し、賃貸借が開始しているのであるから、本件建物敷地を貸家建付地に準じて評価しても不合理ではない。
(C)本件建物敷地の賃借権が付着した土地としての評価
本件建物敷地が、貸家建付地に該当しないとしても、次のとおり、本件相続開始時において、本件土地にはQ生協の賃借権が存在するから、その評価額を減額すべきである。
a 被相続人がX市農業委員会に提出した本件土地に係る農地法第5条第1項第3号の規定による農地転用届出書(以下「本件農地転用届出書」という。)において、「権利を設定、移転しようとする契約の内容」欄には、賃貸借権の設定である旨記載し、また、当該権利の設定時期、存続期間についても、受理後20年間と記載しているから、その提出日である平成10年1月23日に、Q生協の賃借権が設定されている。
b 本件前払賃借料は、地代の授受と同じであるから、それを受け取った時点で、本件建物敷地には賃借権が生じている。
c 本件迷惑料は、賃貸料の補償であり、地代に当たるから、それを受け取った時点で、本件建物敷地には賃借権が生じている。
(D)評価方法に定めのない財産としての評価
本件建物敷地は、上記(B)及び(C)に該当しないとしても、次のとおり、その評価額を減額すべき事情があるから、評価通達5に定める「評価方法に定めのない財産」に該当する。
そうすると、本件建物敷地の評価額は、貸家建付地の評価方法に準じて算定すべきであり、そのように評価したとしても、社会通念上、不適切、不公平なものとはいえない。
a 本件賃貸借契約は、本件相続開始前に結ばれており、この契約は相続人に引き継がれているから、本件土地は、不特定多数の間において、自由な売買ができない拘束された土地である。
b 本件建物は、本件相続開始時において建築中であり、完成後、Q生協に賃貸されることが決定していることから、本件土地の利用が制限されている。
c 被相続人らが、本件賃貸借契約を一方的に破棄し、第三者に本件土地を譲渡するためには、賃借人が解約時までに支出した計画立案費用、建築費用等の莫大な金額を損害賠償金として支払わねばならないから、当該金額を本件土地の評価額から控除すべきである。
(E)本件土地の評価額
以上のことから、本件土地の評価額は、別表4のとおり、本件建物敷地を貸家建付地の評価方法により算定した額に、本件建物敷地に占める本件土地の面積の割合を乗じて算出した、223,470,644円とすべきである。
(ロ)債務控除
被相続人が支払うべき平成10年分の固定資産税及び住民税の額は、債務として、相続税の計算において控除すべきである。
ロ 本件賦課決定処分
上記イのとおり、本件更正処分は取り消されるべきであるから、本件更正処分に基づく本件賦課決定処分も取り消されるべきである。
(2)原処分庁の主張
原処分は、次のとおり適法であるから、本件審査請求を棄却するとの裁決を求める。
イ 本件更正処分
(イ)本件土地の評価
A 本件土地の評価単位
本件土地は、本件相続開始時において、Q生協に貸し付けられていたとは認められないことから、本件建物敷地を同一の目的に供されている1画地の土地として評価することはできず、別表2の番号1及び2と番号3の土地を、それぞれ別個に評価すべきである。
B 本件土地の評価方法
(A)本件建物敷地の自用地としての評価額
請求人らは、本件建物敷地を1画地の土地として評価することを前提として、本件建物敷地の形状等に応じた補正等を行うべきである旨主張するが、上記Aのとおり、本件建物敷地は、1画地の土地として評価することができないから、評価上の補正等の必要性も認められない。
(B)本件建物敷地の貸家建付地としての評価
a 本件建物は、本件相続開始時において、建築中であり、現実には貸し付けられておらず、また、Q生協に本件建物の引渡しも行われていないのであるから、Q生協が、本件相続開始時に、本件建物の賃借権を有していたものとは認められない。
また、本件賃貸借契約書によれば、本件建物の賃貸借期間は、Q生協の開店日から満20年間とされているところ、本件相続開始時において、本件建物が未完成であり、Q生協が開店していないのであるから、本件建物に、Q生協の賃借権が生じていたとは認められない。
なお、請求人らは、措置法通達69の3-2を引用して、本件建物が建築中であっても、その敷地を貸家建付地として評価できる旨主張するが、当該通達は、措置法第69条の3の規定の適用の可否についての取扱いであり、評価の方法を定めたものではない。
したがって、本件土地は、貸家建付地として評価することはできない。
b 請求人らは、本件土地が貸家建付地に該当しないとしても、本件相続開始時に、Q生協の賃借権が存在するから、本件土地の評価額を減額すべきである旨主張するが、次のとおり、請求人の主張には理由がない。
(a)農地法第5条第1項第3号の規定による農地転用の届出は、農地法の制約を解除するためのものであって、当該届出によって直ちに賃借権が設定されるものではないから、本件土地に賃借権が生じているとはいえない。
(b)被相続人は本件前払賃借料の支払を受けているが、本件賃貸借契約によれば、賃貸借期間は、Q生協の開店日から満20年間とされており、本件相続開始時において、Q生協に賃借料の支払義務は発生していない。
さらに、請求人らは、本件修正申告書において、本件前払賃借料相当額を債務に計上しており、本件相続開始時において、未だ賃貸料を受け取るべきことが確定していないことを自認しているのであるから、本件相続開始時において、本件土地に控除すべき権利が存していたとは認められない。
(c)本件迷惑料は、本件建物の建築が遅れたため、被相続人が賃貸料の支払を受けられないことから支払われたものであり、地代には該当せず、当該支払によって賃借権が生じたものとは認められない。
c また、請求人らは、上記a及びbの主張が認められないとしても、本件土地の評価額を減額すべき事情があるから、評価通達5に定める「評価方法の定めのない財産」に該当し、本件土地を貸家建付地の評価方法に準じて算定すべきである旨主張するが、次のとおり、請求人の主張には理由がない。
(a)本件相続開始時において、本件賃貸借契約が締結されているとしても、本件建物にQ生協の賃借権が生じていないのであるから、Q生協に、本件土地の評価に影響を与える何らかの権利が生じているとはいえず、本件土地が、法的に拘束された土地であるとはいえない。
(b)本件建物は、本件建物敷地上に建築されるものであり、このことは、自己の土地に自己の建物を建築することと同様であり、他人から利用の制限を受けているとは認められないから、そのような事情を評価上考慮できない。
(c)本件相続開始時において、本件賃貸借契約が解約された事実はなく、仮に本件相続開始後、本件賃貸借契約が解約され、違約金等を負担することとなったとしても、この負担は、被相続人に帰属するものではないから、そのような事情を評価上考慮できない。
C 本件土地の評価額
以上のことから、本件土地の評価額は、評価通達に基づき自用地として算定すべきものであり、別表5のとおりとなる。
(ロ)債務控除
固定資産税及び住民税の未納税額については、原処分の段階において主張がなく、本件に係る調査関係書類においても、これらを認めるに足る事実は認められない。
(ハ)以上のとおり、請求人らの本件相続に係る税額等は、別表10の「原処分庁主張額」欄のとおりとなるから、この金額でされた本件更正処分は適法である。
ロ 本件賦課決定処分
上記イのとおり、本件更正処分は適法であるから、本件賦課決定処分も適法である。
3 判断
(1)本件更正処分
イ 認定事実
請求人ら提出資料、原処分関係資料及び当審判所が調査したところによれば、次の事実が認められる。
(イ)財産評価基準書によれば、本件建物敷地が接する路線に付された路線価は、国道○○号線が280,000円、市道○○線が266,000円であり、地区区分は、普通商業・併用住宅地区である。
(ロ)Tが当審判所に提出した本件新築工事に係る関係資料の内容の要旨は、次のとおりである。
A Q生協は、平成9年12月26日付でW県知事に対して、都市計画法第29条《開発行為の許可》の規定に基づき、〔1〕開発区域に含まれる地域を別表2の土地(以下「本件開発許可地」という。なお、位置関係については別表3参照。)、〔2〕開発区域の面積を5,320.87平方メートル、〔3〕予定建築物等の用途を物販店舗であるとする開発許可申請を行っている(以下、この申請を「本件開発申請」という。)。
また、本件開発申請は、W県知事から平成10年1月21日付で許可されている(以下、この許可を「本件開発許可」という。)。
B Q生協が平成9年11月5日付でX市長に提出した都市計画法第 32条《公共施設の管理者の同意等》の規定に基づく「都市計画法第32条による協議について」と題する書類によると、本件開発許可地に新たに設置される公共施設用地は、道路193.18平方メートル、緑地163.73平方メートル及び水路敷147.59平方メートルであり、従前の公共施設用地は里道敷106.18平方メートル(別表2の番号13ないし16の土地)である旨記載されている。
C Q生協は、平成7年12月29日付の土地賃貸借契約書により、別表2の番号11の土地について、借地期間を平成9年1月1日から平成28年12月31日までの20年間とする事業用借地権を設定している。
D Q生協は、平成8年11月11日付の土地賃貸借契約書により、Z(以下「Z」という。)が所有するX市m町○丁目○番○所在の土地の一部(分筆後の所在地番は○番○。)と、被相続人の所有する別表2の番号3の土地の一部(分筆後の所在地番は○○番○。)とを交換するまで、Zに対して、本件新築工事の着工月の翌月から上記交換予定地の賃借料を支払う旨約している。
E Q生協は、別表2の番号10の土地を、平成9年12月24日付の売買契約により取得した。
(ハ)S社のnが当審判所に提出した本件新築工事に係る本件開発許可地の測量図面及び本件建物の設計図の内容の要旨は、次のとおりである。
A 本件開発許可地は、市道○○線及び国道○○号線に接しており、その間口距離は、市道○○線側が96.37メートル、国道○○号線側が株式会社qを挟んで西側が20.00メートルで東側が17.90メートルである。
また、市道○○線側に基準点を設けた高低差測量によると、本件開発許可地が接する双方の道路は、その交差点を基点に緩やかな上り勾配があり、市道○○線側が交差点から約96メートルの地点で1.85メートル高くなっており、国道○○号線側が交差点から約80メートルの地点で1.23メートル高くなっている。
なお、測量によれば、本件開発許可地は、そのほとんどが道路面より低い位置に所在する。
B 本件建物は、市道○○線側を正面玄関として建築する予定である。
(ニ)Kは、当審判所に対して、次のとおり答述した。
A 本件土地では、平成7年まで米を作っていたが、それ以降は耕作していない。
B 本件開発許可地は、造成工事のために建設機械が入り、本件相続開始時には、段差がなくなり、各土地の境界線が分からない状態であった。
C 別表2の番号3の畑には、ヒバや柿の木が植えてあったが、本件相続開始時には既に伐採されていた。
D Q生協との開発行為に係る交渉は被相続人が行っており、請求人らは、被相続人から、〔1〕警察関係者の意見では、交通渋滞を起こさないため、国道○○号線側に進入路を確保しなければ開発許可が下りないこと、及び、〔2〕Q生協が市道○○線側からの進入路として使用する土地を賃借するということを聞いていた。
E 本件賃貸借契約を破棄した場合に相手方から要求されると想定される損害賠償金の額は、〔1〕受取保証金の倍返しの額39,000,000円、〔2〕建築費用総額427,684,744円、〔3〕喪失費用の額4,276,847円、〔4〕逸失利益の額213,842,372円、及び、〔5〕訴訟費用等の額12,916,079円の合計697,720,042円である。
F 本件迷惑料については、R社と書面を交わしたが、実際の支払者はQ生協である。
また、本件迷惑料を受領することとなった理由は、本件賃貸借契約で「工事は速やかに始める。」となっていたにもかかわらず、余りにも工事に取り掛かるのが遅れたことによるものである。
G 本件賃貸借契約では、完成後の建物は土地の面積比率と同率で共有登記とすることになっており、契約当事者相互間での借地権は発生しないことで合意している。
H 被相続人、Q生協及びZの三者は、道路となっているZ所有の別表2の番号12の土地と被相続人所有の別表2の番号3の土地の一部を交換し、被相続人が別表2の番号12の土地をX市に寄附することで合意していると被相続人から聞いていたので、平成13年6月にこれを実行した。
(ホ)Tは、当審判所に対し、次のとおり答述した。
A 本件前払賃借料は、被相続人から本件嘆願書により申出があったため、Q生協が店舗の開店日以後に支払うべき賃借料を前払したものであり、本件土地及び本件建物の賃借料ではない。
なお、本件賃貸借契約に基づく賃借料は、Q生協の開店日である平成10年9月23日から支払っている。
B 本件迷惑料は、当初のオープン予定が大幅に遅れることとなったため、平成9年4月1日から地代相当分として被相続人へ月額311,431円を支払ったが、迷惑料とは考えていない。
また、本件迷惑料については、金額的には、駐車場として利用した場合の地代の30パーセント程度と固定資産税分相当額に当たると思うが、Q生協は、本件建物が完成するまで、本件土地を使用しておらず、その引渡しも受けていないのであるから、本件賃貸借契約を拘束するための支払であると考える。
C 本件開発許可地内に所在する別表2の番号13及び14の里道敷は、平成10年11月27日に国から払い下げを受けたが、別表2の番号15及び16の里道敷は、国有地からX市の帰属になったが、国又はX市から賃借していない。
D 被相続人、Q生協及びZの三者は、被相続人所有のX市m町○丁目○○番○の土地とZ所有の別表2の番号12の土地を交換し、交換後に同所○番○をX市に寄附する旨を合意しており、この合意に基づいて、Q生協は、Zが交換により取得する予定の同所○○番○について、Zと土地賃貸借契約書を交わした。
なお、Q生協は、上記交換による所有権移転登記まで、Zが所有する別表2の番号12の土地に対して、賃借料を支払うことにしているので、当該土地に賃借権を有している。
(ヘ)S社のrは、当審判所に対し、要旨次のとおり答述した。
A 本件建物の建築工事は、宅地造成工事と並行して行った。
B 平成10年4月7日現在の宅地造成費の額は、出来高明細総括表によれば、屋外施設等5,691,260円(消費税別)となる。
なお、工事の明細は残っていないが、進入路の造成や擁壁の工事費に係るものであると記憶している。
(ト)X市役所都市整備部の担当者は、当審判所に対し、要旨次のとおり答述した。
A 公園、広場等は、都市計画法施行令第25条《法第33条第1項各号を適用するについて必要な技術的細目》第6号の規定により、開発区域の面積が0.3ヘクタール以上5ヘクタール未満の開発行為にあっては、その面積の3パーセント以上を設けなければならないが、予定建築物が商業施設である場合には特に設置する必要がない。
ただし、W県の条例では、予定建築物の用途が商業施設であっても、公共施設に当たる広場等を敷地の3パーセント以上設けるよう指導することになっている。
なお、設置した広場等は、X市の帰属とはならない。
B 本件開発許可地の開発に関しては、同地が市道○○線に接していることから、都市計画法上、開発区域内道路を設置する必要はないが、予定建築物の用途、状況等を勘案して、国道○○号線側にも進入路を設けることになった。
なお、当該進入路は、Q生協との間で工事完成後、公共施設としてX市に帰属させる旨協議済である。
(チ)被相続人及びQ生協は、本件農地転用届出書を平成10年1月23日にX市農業委員会へ提出し、同市農業委員会は、平成10年2月4日に本件農地転用届出書の受理通知を交付した。
なお、本件農地転用届出書の「権利を設定、移転しようとする契約の内容」欄には、権利の種類は賃貸借権の設定、「権利設定の時期」欄には当該届出書の受理後、及び「存続期間」欄には20年間との記載がある。
また、本件農地転用届出書には、本件開発許可書の写しが添付されている。
(リ)X市農業委員会の職員は、当審判所に対し、要旨次のとおり答述した。
A 敷地内に共有建物を建築する場合には、農地法第4条ではなく同法第5条の規定による申請又は届出を行うよう指導している。
B 本件農地転用届出書は、本件土地にQ生協が建物を建築する旨の本件開発許可書の写しが添付されているため、転用目的を賃貸借権の設定としたものと思われる。
(ヌ)請求人らの代理人であるt税理士は、当審判所に対し、要旨次のとおり答述した。
A 本件建物敷地の評価において、正面路線を国道○○号線とした理由は、国道○○号線の路線価の方が市道○○線の路線価より高いためである。
B 不整形地補正は、評価通達において30パーセントの範囲内で控除できることになっているので、本件建物敷地の形状から最大の30パーセントが妥当であると判断したものであって、具体的な算定根拠はない。
(ル)本件相続開始時の被相続人に係る固定資産税及び住民税の未納額は、別表10のとおり2,936,500円である。
なお、当該未納額の負担者は、Kである。
ロ 本件土地の評価について、上記1の(4)の基礎事実及び上記イの認定事実を上記1の(3)の関係法令等に照らして、以下審理する。
なお、請求人ら及び原処分庁の双方とも、上記1の(3)のイの評価通達の定めによることに異議がなく、当審判所においても当該評価通達の定めを相当と認める。
(イ)本件土地の評価
A 本件土地の評価単位
(A)原処分庁は、本件相続開始時において、本件建物敷地が一体となって利用されているとは認められないから、本件土地を2区画の土地として評価すべきである旨主張する。
a ところで、宅地の評価の単位については、評価通達では、上記1の(3)のイの(ロ)のとおり、利用の単位となっている1画地の宅地ごとに評価することとされており、個別の土地が他の筆の土地と一体となって利用され、これと併せて利用の単位である1画地の土地を構成しているか否かについては、数筆の土地が相続開始時には空閑地であって、一体となって利用されるに至っていない段階であっても、その土地全体の状況と利用目的とを総合的に考慮し、近い将来それを1画地として利用する目的が具体的に定まっており、かつ、土地の状況その他から見てその実現が確定的であると認められるような場合においては、その数筆の土地が利用の単位となる1画地の土地を構成するものとして、当該1画地の土地についての価額の評価を通じて個別の土地の価額を評価することが相当であると解される。
b また、土地の所有者が隣接している土地を借りてその土地を専属的に使用できる場合において、これを自己の所有する土地と一体として利用するときは、当該借地についても、自己の所有する土地と併せて1画地の土地を構成するものとして評価することが相当であると解される。
(B)これを本件についてみると、本件相続開始時において、〔1〕上記1の(4)のロのとおり、本件敷地所有者が本件建物敷地に本件建物を建築して、Q生協が店舗として賃借するという本件賃貸借契約を締結していること、〔2〕上記イの(ロ)のAのとおり、Q生協は、本件建物敷地を含む本件開発許可地について、本件開発許可を受けていること、及び、〔3〕上記1の(4)のト及びチの(ハ)のとおり、平成10年3月2日付で本件請負契約が締結され、本件相続開始時には、本件新築工事に着手していることからして、本件敷地所有者が、本件建物敷地に、Q生協が店舗として使用する本件建物を建築することは明らかであり、本件建物敷地が1画地の店舗用地として使用されることは確定的であると認められる。
そうすると、本件土地を含む本件建物敷地は、本件建物の敷地として一体として利用される土地であるというべきであるから、本件建物敷地が一体として利用されていないとする原処分庁の主張は、採用することができない。
(C)一方、請求人らは、一体として利用されている土地の範囲について、本件開発許可地には借地が存在するから、本件建物敷地のみを1画地の土地として評価すべきである旨主張する。
a しかしながら、本件開発許可地のうち別表2の番号11ないし16の土地については、本件相続開始時において、本件敷地所有者が所有権を有していないが、〔1〕上記イの(ロ)のC及びD並びに(ホ)のDのとおり、別表2の番号11及び12の土地については、本件敷地所有者のうちのQ生協が、それぞれの所有者から賃借して専属的に使用する権利を得ており、また、〔2〕上記イの(ホ)のCのとおり、別表2の番号13及び14の土地については、Q生協が国から払い下げを受けることとなっており、さらに、別表2の番号15及び16の土地については、国又はX市からの賃借がされていないことが認められる。
b そうすると、Q生協は、本件開発許可地のうち別表2の番号11ないし14の土地について、その所有権又は賃借権に基づいて専属的に使用できる権限を有しているものと認められ、他方、別表2の番号15及び16の土地については、本件敷地所有者に賃借権がなく、本件敷地所有者が専属的に使用できるものとは認められないから、別表2の番号15及び16の土地を除く本件開発許可地(以下「本件単位土地」という。)を一体となって利用されている1画地の土地として評価するのが相当である。
c したがって、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
B 本件土地の評価方法
本件土地の評価額については、上記Aのとおり、本件単位土地を1画地の土地として評価することから、本件単位土地の評価額を算定し、その評価額に本件単位土地に占める本件土地の面積の割合を乗じて算出することとなる。
(A)本件単位土地の自用地としての評価額
a 土地の評価上の区分
請求人らは、本件建物敷地を宅地として評価すべきである旨主張するが、本件建物敷地を含む本件単位土地は、上記イの(ニ)のB及びC並びに(ヘ)のとおり、本件相続開始時において、宅地造成工事を行っている途中のものであることから、上記1の(3)のイの(ヘ)の造成中の宅地として評価するのが相当である。
そうすると、本件相続開始時における本件単位土地の自用地としての価額は、本件単位土地の造成工事着手直前の地目により評価した価額(本件単位土地は、造成工事着手直前が市街化区域農地であるから、それが宅地であるとした場合の価額から、本件単位土地を宅地に転用するとした場合において通常必要と認められる造成費に相当する金額を控除した価額)に、本件相続開始時までに投下した本件単位土地の造成に係る費用現価の額の80パーセントに相当する金額を加算した価額になる。
b 正面路線
請求人らは、路線価の高い国道○○号線に付された路線を正面路線とすべきである旨主張する。
(a)ところで、正面路線は、上記1の(3)のイの(ハ)のとおり、原則として路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した1平方メートル当たりの価格の高い方の路線とするのであるが、上記路線を正面とすることが評価土地の最有効利用につながるとはいえない場合及び同路線が評価土地の価額に与える影響が著しく低いと認められる場合は、これを正面路線にしないことができるものと解される。
(b)これを本件についてみると、上記イの(イ)の双方の路線価に奥行価格補正率を乗じて計算すると、確かに、国道○○号線の方が1平方メートル当たりの価格の高い路線となるが、本件単位土地の場合は、上記イの(ハ)のAのとおり、〔1〕国道○○号線に接する間口距離に比べ、市道○○線に接する間口距離の方が相当に長いこと、〔2〕国道○○号線側は、間口が中央で大きく分離されていること、及び、〔3〕市道○○線側を正面として本件建物の建築が予定されていることなどからみて、市道○○線の方が敷地全体の価額に与える影響度合いが高く、市道○○線を正面路線とした場合に本件単位土地の最有効利用が図られるものと認められることから、市道○○線を正面路線とし、当該路線に付された路線価を正面路線価とするのが相当である。
c 不整形地補正率
請求人らは、本件建物敷地が土地の形状からみて利用が著しく制限された不整形地であるため、整形地としての価額から30パーセントを控除すべきである旨主張する。
(a)確かに、本件建物敷地を含む本件単位土地は、別表3のとおり、不整形地であることから、減価補正を必要とする土地であると認められる。
(b)ところで、評価通達20の(1)は、上記1の(3)のイの(ホ)のとおり、不整形地について、土地の形状が悪いことによって、整形地に比べ宅地としてその効用を十分に発揮できないことから、その程度に応じて、30パーセントの範囲内で減価補正することとしているところ、その不整形地の程度に応じた減価補正の割合について、その具体的基準を示して課税の公平・簡素化を図る観点から、「不整形地補正率について」(平成4年3月3日付資産評価企画官情報第1号。以下「本件情報」という。)が公表され、不整形地の評価は本件情報に基づいて統一的に行われていることが認められる。
(c)本件情報による減価補正の方法は、不整形地である評価対象地に対応する整形地を想定して、当該想定整形地に占める想定整形地と評価対象地との地積の差の割合(以下「かげ地割合」という。)を基に、評価対象地が所在する地区区分及び評価対象地の地積の大小に応じて減価補正する割合を求めるというもので、評価上勘案すべき不整形の程度、その地域の最有効使用、標準的な画地が考慮されており、当審判所においても合理的な減価補正の方法であると認めることができる。
(d)そうすると、本件単位土地について、当審判所が本件情報を基に算定すると、別表6の(1)のとおり、本件単位土地の想定整形地におけるかげ地割合は49.66パーセントとなり、このかげ地割合における不整形地補正率は0.98となる。
(e)これに対し、請求人らが主張する不整形地補正率は、評価通達に定められた補正割合の範囲内ではあるが、上記イの(ヌ)のBのとおり、具体的な算定根拠に基づいて算出された合理的なものとは認められず、請求人らの主張を採用することはできない。
d 無道路地補正
請求人らは、本件建物敷地の正面路線は国道○○号線であり、それに接する土地が進入路として利用できないから、無道路地に該当する旨主張する。
(a)ところで、無道路地とは、上記1の(3)のイの(ホ)のとおり、路線に接していない土地をいうのであって、土地が路線に接していれば、その土地の利用状況いかんにかかわらず、無道路地として評価することはできないものと解される。
(b)これを本件単位土地についてみると、別表3のとおり、別表2の番号2及び5の土地が市道○○線に接し、別表2の番号4の土地が国道○○号線に接しているのであるから、本件単位土地が無道路地に該当しないことは明らかである。
(c)したがって、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
e がけ地補正率
請求人らは、本件建物敷地がスロープ状の土地であり、その20パーセントががけ地であるとして、減価補正すべきである旨主張する。
(a)ところで、評価通達20の(4)は、がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分を有する宅地について、その宅地の評価額を減価補正する旨定めている。
(b)これを本件単位土地についてみると、上記イの(ハ)のAのとおり、市道○○線と国道○○号線の交差点を基点として、それぞれ緩やかな勾配が認められるが、本件開発許可地の測量図面からみて、本件単位土地には通常の用途に供することができないがけ地等は認められない。
(c)また、本件単位土地は、上記イの(ハ)のAのとおり、道路面より低い位置に所在することから、宅地造成が必要な土地ではあるが、後記hのとおり、本件単位土地を宅地造成することにより、そのすべてが通常の用途に供することができる宅地になるものと認められる。
(d)したがって、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
f 児童公園の指定による補正率
請求人らは、本件建物敷地のうち児童公園に指定された部分の土地は、その評価額を40パーセント減額すべきである旨主張する。
(a)しかしながら、本件相続開始時においては、本件単位土地は何ら公園として使用されていないのであるから、当該部分を公園として評価することはできず、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
(b)ただし、上記イの(ロ)のBのとおり、本件開発許可地の開発に当たっては、公共施設として道路、緑地及び水路敷の設置を義務付けられていることから、本件単位土地の評価に当たっては、公共公益的施設用地について、後記gの広大地としての評価においてしんしゃくすべきである。
g 広大地の補正率
(a)本件開発許可地における公共公益的施設用地は、上記イの(ロ)のBのとおり、道路193.18平方メートル、緑地163.73平方メートル及び水路敷147.59平方メートルであるが、水路敷の中には本件単位土地に含まれない別表2の番号15及び16の土地が含まれているため、これを除くと、本件単位土地に係る公共公益的施設用地の面積は、451.69平方メートルとなる。
(b)当審判所が、広大地の評価について、上記面積を上記1の(3)のイの(ト)の評価通達24-4の算式に当てはめて計算すると、別表6の(1)のとおり、広大地の補正率は0.91となり、本件単位土地の奥行価格補正率0.94(別表6の(1)参照)より小さくなることから、広大地の補正率を奥行価格補正率に代えて適用するのが相当である。
h 宅地造成費
(a)本件単位土地については、上記aのとおり、造成中の宅地として、造成工事着手直前の地目(市街化区域農地)に従い、それが宅地であるとした場合の価額から、土盛、土止費等の宅地造成費に相当する金額を控除して評価することになる。
また、一般的に、宅地造成工事の方法は、その使用者の利用目的等により異なるが、本件単位土地の評価に当たっては、宅地造成費について、当審判所に提出された本件開発許可地に係る測量図に基づき、そのうち土盛費については、上記イの(ハ)のAの正面路線である市道○○線の高低差の中間点10.88(基準点10.00、最高点11.80、最低点9.95)を想定平面として宅地造成費に相当する金額を算定するのが合理的であると認められる。
(b)そうすると、本件単位土地の宅地造成費相当額は、当審判所において相当と認める財産評価基準書に基づき算定すると、別表7のとおり、1平方メートル当たり6,848円となる。
i 本件単位土地に係る宅地造成工事の費用現価
本件相続開始時における本件単位土地に係る宅地造成工事の費用現価の額は、上記1の(4)のチの(ハ)及び上記イの(ヘ)のBのとおり、5,691,260円に消費税等を加算した5,975,823円となるから、本件単位土地の造成工事着手直前の地目により評価した価額に加算する金額は、当該費用現価の額の80パーセントに相当する4,780,658円となる。
j 以上のことから、本件単位土地の自用地としての評価額は、別表6の(1)のとおり、1,253,958,849円となる。
(B)本件単位土地の貸家建付地としての評価
a 請求人らは、本件相続開始時において、本件賃貸借契約が結ばれていることから、本件建物敷地が貸家建付地に該当する旨主張する。
(a)ところで、上記1の(3)のチの評価通達26の趣旨は、借家人には借家権はあっても借地権はないのであるが、経済的に見れば、その借家の敷地である宅地に対してもその建物の賃借権に基づいてある程度の支配権を有していると認められるため、その支配権を消滅させるために、いわゆる立ち退き料の支払を要する場合もあるし、また、その支配権が付着したままの状態でその土地を譲渡することとした場合は、その支配権が付着していないとした価額より低い価額でしか譲渡できないこととなるため、その経済的価値が低くなるという事情を考慮したものであるから、貸家建付地として評価額を減額するには、上記のような経済的価値が低くなるような事情がある場合に限られるというべきである。
(b)そうすると、評価通達にいう貸家建付地とは、現に借家権の目的となっている建物の敷地の用に供されている宅地をいうものと解され、また、相続税法第22条《評価の原則》が、相続により取得した財産の価格はその取得の時における時価によるものとしていることからすると、貸家建付地に当たるか否かは、相続開始時を基準として判断されるべきである。
(c)これを本件についてみると、本件相続開始時において、本件建物は建築中であり、本件単位土地上に借家権の目的となっている建物が存在していないのであるから、本件単位土地が貸家建付地に該当しないことは明らかである。
(d)これに対し、請求人らは、本件相続開始時において、既に本件賃貸借契約が締結されている旨主張するが、当該契約は、上記1の(4)のロの(ヘ)のとおり、本件建物が完成し、Q生協の店舗が開店した時から、Q生協が請求人らの共有持分に係る本件建物を賃借するという停止条件付契約であるところ、本件相続開始時においては、本件建物は完成しておらず、開店もしていないのであるから、本件賃貸借契約が締結されていたとしても、本件単位土地にQ生協の支配権が及んでいるものとは認められない。
(e)したがって、この点に関する請求人らの主張は理由がない。
b また、請求人らは、本件建物敷地の評価を措置法通達69の3-2に準じて行うべきである旨主張する。
しかしながら、措置法第69条の3は、相続人等の生活基盤の維持、個人事業者等の事業継承を図ることを目的として、相続財産の経済的な価値には関係なく、特に、相続税の課税価格の軽減を図る優遇措置を認めたものであり、措置法通達69の3-2は、その適用に当たり、相続開始時において建築中である建物の敷地が事業の用に供されているか否かの判断基準を示したものであって、相続財産の一般的な評価方法を定めたものではないから、事業用に供されているか否かの判断と関係のない本件単位土地の評価に当たり、当該措置法通達を準用することはできない。
したがって、この点に関する請求人らの主張は採用できない。
(C)本件単位土地の賃借権の付着した土地としての評価
請求人らは、次のとおり、本件土地が賃借権の付着した土地に該当するから、その評価額を減額すべきである旨主張するが、いずれも理由がなく、請求人らの主張は採用できない。
a 請求人らは、上記2の(1)のイのBの(C)のaのとおり、本件農地転用届出書が受理された時点で、本件土地には、Q生協の賃借権が生じている旨主張する。
(a)しかしながら、本件農地転用届出書は、農地法第5条第1項第3号の規定による届出であり、当該農地に係る農地法上の制約を解除するためのものであって、これによって賃借権等の権利を設定するというものではなく、当該届出書の受理通知は、届出した農地をその記載した用途に使用することができるという承認を得たにすぎないと解すべきである。
(b)そうすると、本件農地転用届出書の受理通知が交付されたことは、本件土地に本件建物を建築する承認を得たとはいえるが、当該受理通知の交付によって、直ちに本件土地の賃貸借が開始されたということにはならない。
(c)また、本件農地転用届出書では、上記イの(チ)のとおり、設定する権利の種類を賃貸借権とし、権利設定の時期及び存続期間を受理後20年間としているところ、本件賃貸借契約においては、上記1の(4)のロの(ヘ)のとおり、賃貸借期間はQ生協の開店日から20年間となっているのであるから、本件農地転用届出書が受理された時点をもって、Q生協の賃借権が生じたものとは認められない。
b 請求人らは、本件前払賃借料の支払を受けていることから、本件相続開始時点において、本件土地の賃貸借が開始されている旨主張する。
(a)しかしながら、〔1〕本件賃借料覚書によれば、上記1の(4)のホ及びへのとおり、本件前払賃借料は、被相続人の経済的な理由による嘆願に応じて、Q生協が支払うとしたものであること、及び、Q生協の開店日以降は、本件前払賃借料の前払期間分について、本来の賃貸料から控除して支払うとされていることが認められ、また、〔2〕上記1の(4)のチの(ホ)のとおり、本件前払賃借料の合計額は、本件修正申告書において、被相続人の負債として計上されていることが認められる。さらに、〔3〕上記イの(ホ)のAのTの答述からすると、Q生協が、本件前払賃借料を本件建物に係る賃借料と認識していたとは認められない。
(b)そうすると、本件前払賃借料は、Q生協の開店日以降に成立する賃貸借について、将来発生が見込まれる賃借料の前払を受けたもので、被相続人のQ生協からの借入金に相当するものであり、本件建物の賃借料と認められないから、本件前払賃借料の授受によりQ生協に賃借権が生じたものとは認められない。
c 請求人らは、被相続人がQ生協から迷惑料の名目で金員の支払を受けているが、当該支払は賃貸料の補償であり地代である旨主張する。
(a)しかしながら、〔1〕本件迷惑料書面によると、上記1の(4)のニの(イ)のとおり、本件迷惑料は、本件新築工事の事業計画が遅延したことによるものであるから、本件賃貸借契約に関係なく、本来の賃貸料が支払われるまで支払われるものであり、また、〔2〕上記イの(ホ)のBのとおり、Q生協のTは、本件迷惑料の金額を、駐車場として利用した場合の30パーセント程度として算定しているが、本件建物が完成するまで、本件土地を使用しておらず、その引渡しも受けていないのであるから、本件迷惑料は、本件土地の賃借料としての支払ではなく、本件賃貸借契約を拘束するための支払である旨答述している。
(b)そうすると、本件迷惑料は、本件賃貸借契約とは別に、本件賃貸借契約を存続させることを前提として支払われたものであり、本件土地を使用するために支払われた賃借料ではないから、本件迷惑料の支払によって、Q生協に本件土地の賃借権が生じたと認めることはできない。
(D)請求人らは、次のとおり、本件土地が評価方法の定めのない財産に該当するから、貸家建付地の評価方法に準じて本件土地の評価額を減額すべきである旨主張するが、いずれも理由がなく、請求人らの主張は採用できない。
a 請求人らは、本件賃貸借契約が本件土地を強く拘束し、不特定多数の間で自由な取引ができない旨主張する。
(a)確かに、上記(B)のaで述べたとおり、本件賃貸借契約は、本件建物が完成してQ生協が開店した時からQ生協に賃貸するという条件付の契約であり、請求人が主張するように、本件土地の取引に、何らかの制約があることは認められる。
(b)しかしながら、被相続人は、本件土地の有効利用を図るために、自己の意思に基づいてQ生協及びPと共同で、本件土地を含む本件単位土地に店舗用の本件建物を建築するという事業を行うこととしたもので、被相続人の相続人であるKも、本件賃貸借契約上の被相続人の地位を承継し、当該事業を継続しているのであり、また、当該事業の遂行に当たり、本件相続開始時までに、本件土地について、上記(B)及び(C)のとおり、賃貸料を収受している事実も認められないのであるから、本件土地を不特定多数の間で自由な取引ができないとしても、そのことが、本件土地の経済的な価値を低下させるものであるとは認められない。
b また、請求人らは、本件相続開始時において本件建物が建築中であり、その建物が完成後に賃貸することが決まっていることから、本件土地についての利用が制限されている旨主張する。
しかしながら、〔1〕本件賃貸借契約は、上記1の(4)のロのとおり、本件敷地所有者が、それぞれの所有地を一体として使用して、その上に本件建物を建築することとし、完成後の本件建物は、本件敷地所有者における合理的な計算に基づいてそれぞれの所有分を割り当て、共有とすることが定められていること、及び〔2〕上記イの(ニ)のGのとおり、本件敷地所有者相互間において、借地権が発生しないことで合意している旨のKの答述からすると、本件敷地所有者は、それぞれが所有する土地の上に、自己の建物を建設したことと同一の効果を生じさせようとするものであるから、本件建物が建築中であり、完成後に本件建物を賃貸することが決まっていたとしても、このことが、本件相続開始時において、本件土地の評価に影響を及ぼす制約であるとは認められない。
c さらに、請求人らは、本件賃貸借契約を一方的に破棄し、本件土地を第三者に譲渡するためには多大な損害賠償金を支払わなければならないため、本件土地の評価額から、上記イの(ニ)のEの損害賠償金を差し引いた金額が評価額となる旨主張する。
(a)確かに、本件賃貸借契約では、上記1の(4)のロの(リ)のとおり、被相続人らが一方的に当該契約を破棄した場合、被相続人らは、Q生協に対し本件証拠金を返還するほか違約金として本件証拠金と同額を支払い、また、この違約金を超過する損害が生じた場合は、その損害金も賠償する旨定められている。
(b)しかしながら、本件相続開始時において、本件賃貸借契約は解約されておらず、損害賠償金を支払う義務は生じてないのであるから、本件賃貸借契約書に損害賠償金について定められていることが、本件土地の経済的価値に影響を与えるものとは認められない。
(c)なお、仮に、本件相続開始時において、損害賠償金の支払義務が生じていたとしても、それは、相続税の課税価格の計算上、当該支払義務を被相続人の債務として控除すべきか否かの問題であり、本件土地の時価をいかに評価すべきかとは別個の問題である。
C 本件土地の評価額
以上のことから、本件土地の評価額は、別表6の(2)のとおり、本件単位土地の自用地としての評価額に、本件単位土地の地積に占める本件土地の地積の割合を乗じて算出した517,944,802円となる。
(ロ)本件建物の被相続人の持分に係る評価額
本件建物の本件相続開始時の累計出来高には、上記1の(4)のチの(ハ)のとおり、宅地造成に係る費用が含まれていることから、本件相続開始時における本件建物の費用現価の額は、本件建物等の累計出来高11,800,000円から宅地造成に係る費用現価5,691,260円を差し引いた6,108,740円に消費税等を加算した6,414,177円になる。
そうすると、本件建物の被相続人の持分に係る評価額は、別表8のとおり、本件建物の費用現価の額に被相続人の持分比率(38.4パーセント)を乗じた2,463,043円に70パーセントを乗じた1,724,130円となる。
(ハ)前渡金の評価額
被相続人がS社に本件建物等の工事代金として支払っていた額は、上記1の(4)のチの(ロ)のとおり32,909,500円であるが、前渡金の評価額は、別表9のとおり、当該支払額から上記(ロ)で求めた本件相続開始時における本件建物の被相続人の持分価額2,463,043円及び上記(イ)のBの(A)のiで求めた本件単位土地の宅地造成に係る費用現価に占める本件土地の宅地造成に係る費用現価2,468,299円を控除した27,978,158円となる。
(ニ)債務控除の額
被相続人の平成10年度分の固定資産税2,933,000円及び住民税3,500円は、別表10のとおり、本件相続開始時において未納であり、その負担者はKであることから、本件相続に係る相続税の債務として、Kの取得財産の価額から控除すべきである。
ハ 以上の結果、別表11の「審判所認定額」欄に記載のとおり、納付すべき相続税額は、Kが297,859,800円及びLが27,419,400円となり、これらの額はいずれも本件更正処分の額を下回るから、いずれもその一部を取り消すべきである。
(2)本件賦課決定処分
上記(1)のとおり、本件更正処分の一部がそれぞれ取り消されることに伴い、Kに係る過少申告加算税の計算の基礎となる税額は63,200,000円となるところ、この納付すべき税額の基礎となった事実について、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項の規定に基づいて過少申告加算税の額を算定すると6,320,000円となり、また、Lに係る過少申告加算税の計算の基礎となる税額は40,000円となり、過少申告加算税の額は、国税通則法第 119条《国税の確定金額の端数計算等》第4項の規定により零円となり、これらの金額は、いずれも本件賦課決定処分の金額に満たないから、本件賦課決定処分は、Kについてその一部を、また、Lについてその全部を取り消すべきである。
(3)原処分のその他の部分については、請求人らは争わず、当審判所の調査によっても、これを不相当とする理由は認められない。
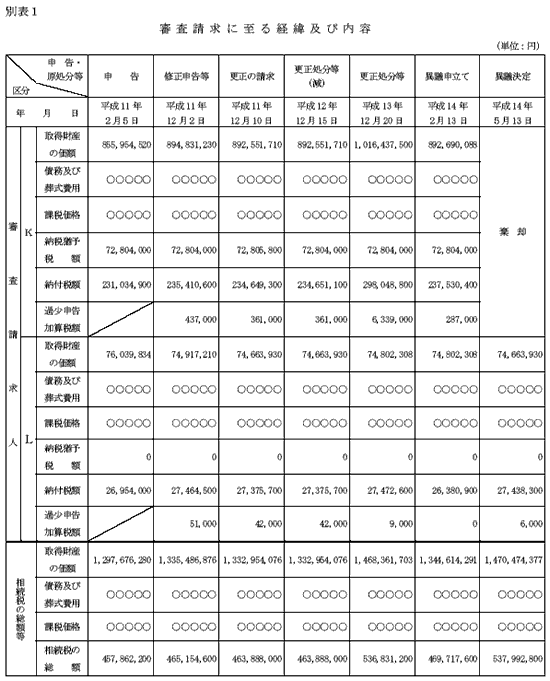
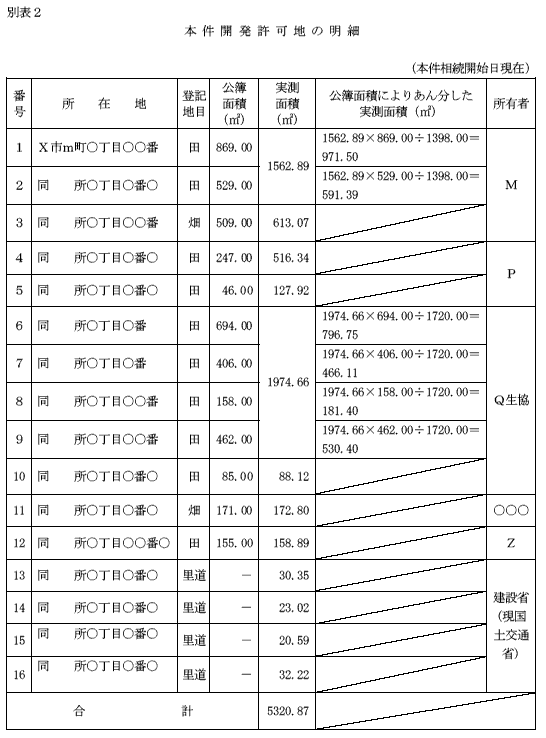
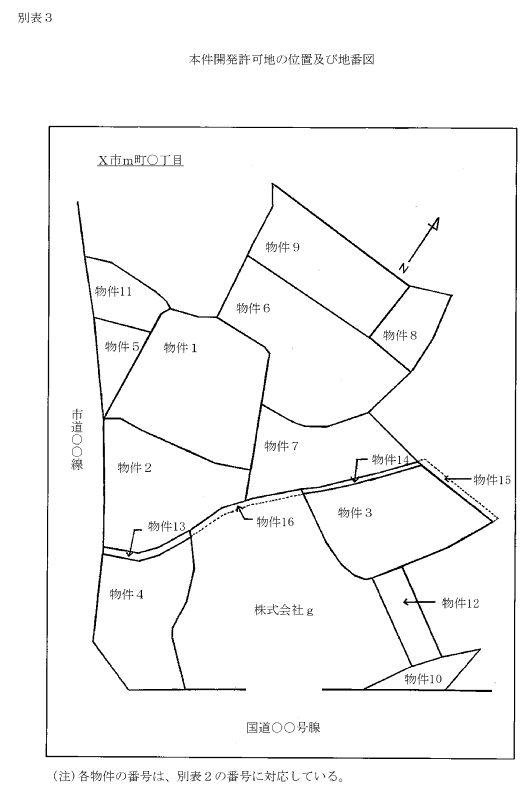
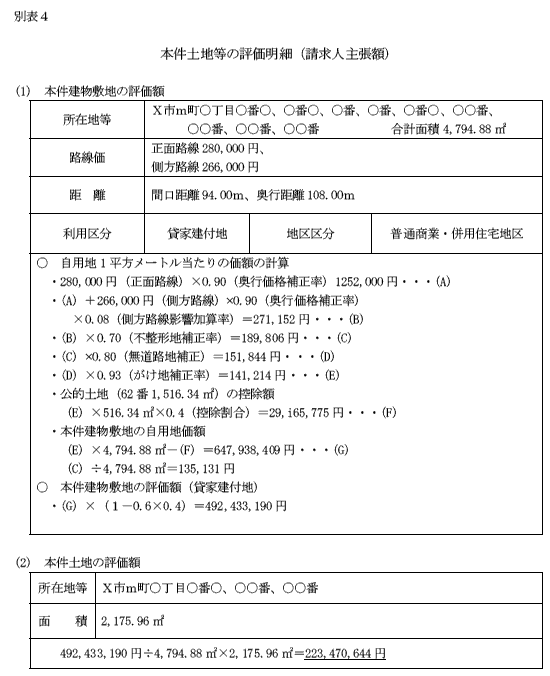
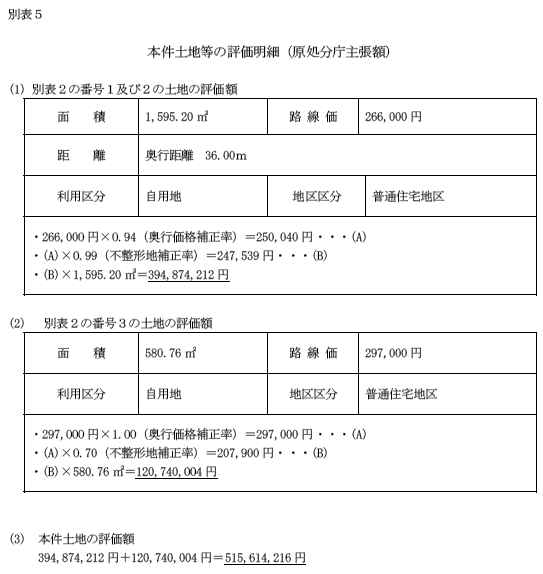
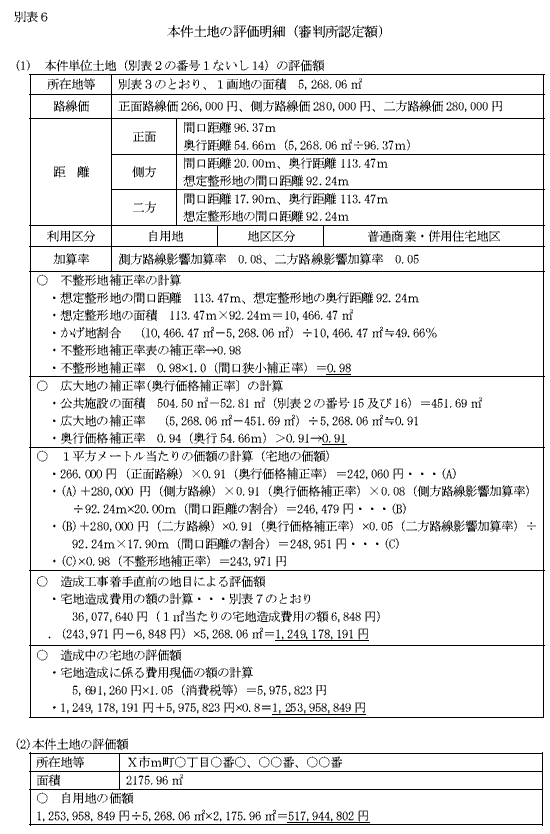
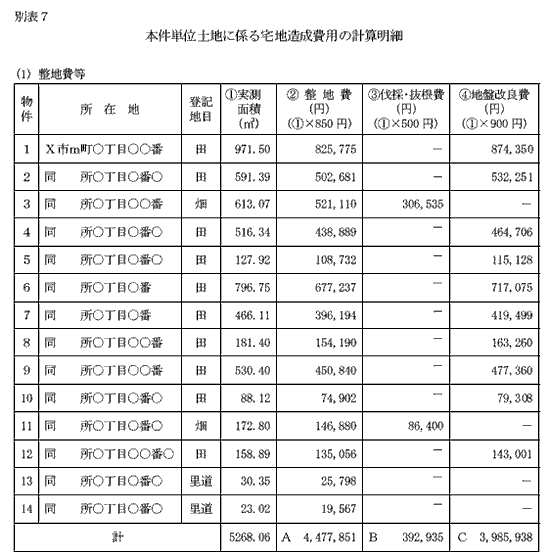
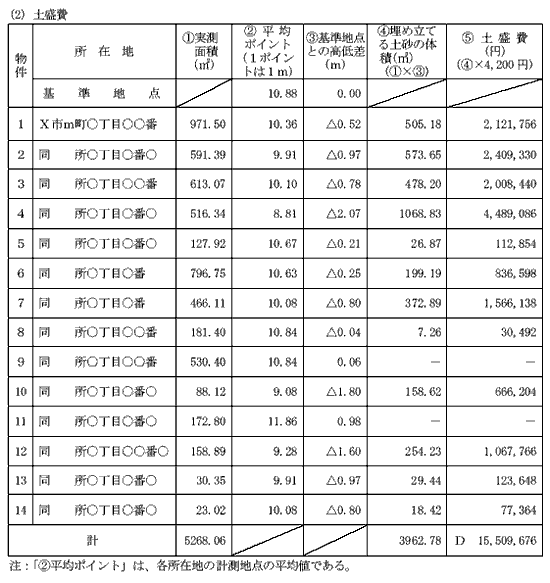
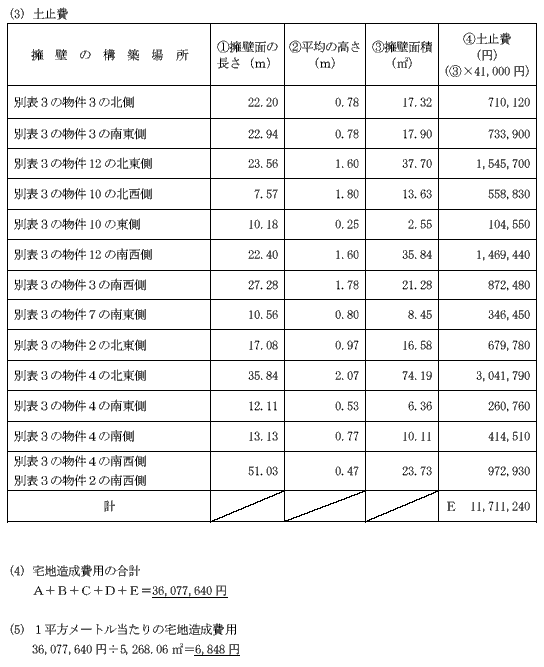
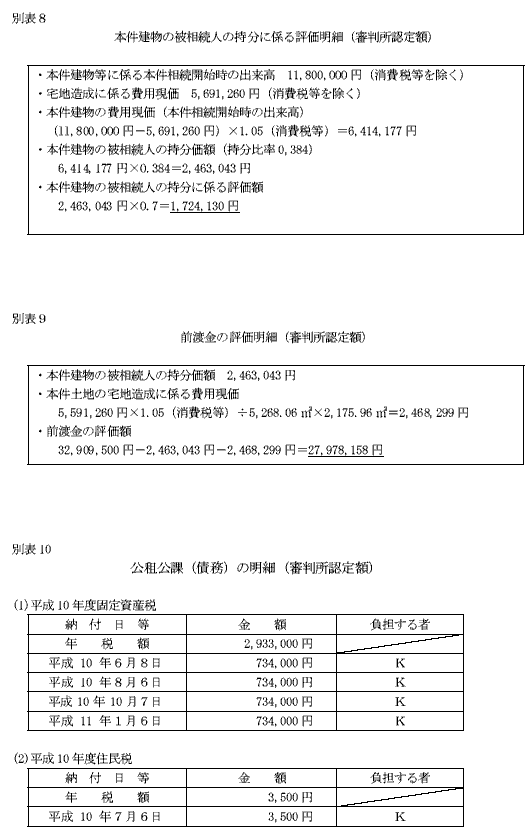
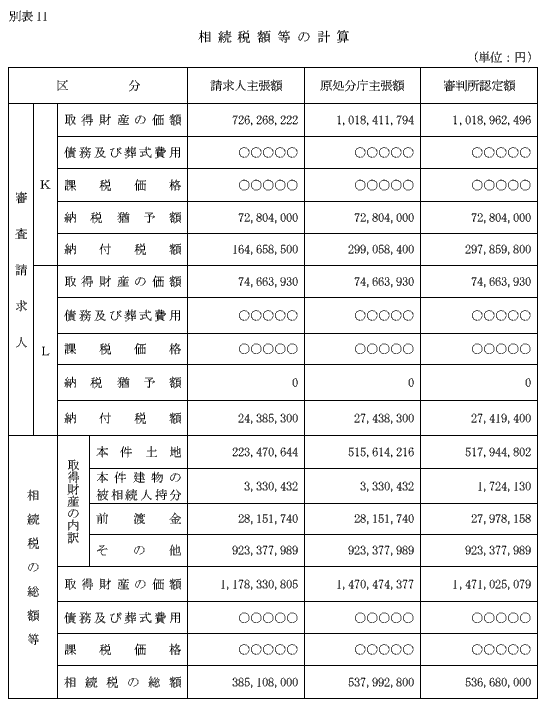
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















