資料2004年07月19日 【会計資料】 討議資料『財務会計の概念フレームワーク』の公表にあたって(2004年7月19日号・№075)
討議資料『財務会計の概念フレームワーク』の公表にあたって
下記資料は、(財)財務会計基準機構のホームページより同財団の許可を得て転載しています。なお、同財団の公表物は、著作権等により保護されており、同財団の許可なく複写・転載すること等は禁じられています。利用等に当たっては、同財団事務局(tel:03-5561-9618)へご連絡下さい。
討議資料『財務会計の概念フレームワーク』公表の経緯
企業会計基準委員会(以下、委員会という)は、わが国の会計基準を設定するにあたって、概念フレームワークを明文化する必要性が各方面から指摘されたのを受け、委員会のもとに外部の研究者を中心としたワーキング・グループを組織して、その問題の検討を委託した。ワーキング・グループには委員会から常勤委員や事務局メンバーも加わり、委員会の委員長が座長となって合計46回に及ぶ会議を統括した。そこで得られた結論をとりまとめたのが、この討議資料『財務会計の概念フレームワーク』(以下、討議資料という)である。
したがって、この討議資料に示されているのは、委員会の見解ではなく、委員会に報告される当ワーキング・グループの見解である。むろん、これは、今後の基準設定の過程で有用性をテストされ、市場関係者等の意見を受けてさらに整備・改善されれば、いずれはデファクト・スタンダードとしての性格を持つことになるであろう。委員会がその経緯をみながら、この討議資料を素材に必要な議論を重ねていくことを、当ワーキング・グループとしても期待するものである。
概念フレームワークを記述する体系には、本来、多様な選択肢がありうるが、この討議資料の構成は、大枠で海外の先例に従っている。海外の主な会計基準設定主体が公表した概念書は、わが国でもすでに広く知られているため、それと構成を揃えることで関係者の理解が容易になり、この討議資料の機能がより効率的に発揮されると期待できるからである。さらに、海外と同一の構成を採用することによって、会計基準の国際的調和をめぐるコミュニケーションも、より円滑になるであろう。
討議資料の役割
この討議資料では、現行の企業会計(とくに財務会計)の基礎にある前提や概念が要約・整理されており、その内容は、将来の会計基準設定の指針になると期待されている。その指針によって、会計基準の体系的安定性が得られれば、会計基準の変化についての予見可能性が高まるであろう。そのことを通じて不確実な将来への対応をより的確なものとし、企業や利害関係者に無用なコストが生じる事態を避けることも、この討議資料に期待されている重要な役割である。
基本となる前提や概念を要約・整理しておくことには、海外の基準設定主体との円滑なコミュニケーションに資する役割も期待されている。会計基準の国際的な調和(または収斂)が求められるなかで、会計基準の相違が何に起因しているのかについて説明が求められる機会は少なくない。この討議資料には、そうした説明のための有効な基盤となることも期待されている。
この討議資料には、現行の会計基準をつとめて体系的に整理するだけでなく、前述のとおり、将来の基準設定に指針を与える役割も求められている。そのため、この討議資料の内容には、現行会計基準の一部を説明できないものが含まれていたり、いまだ基準化されていないものが含まれていたりする。しかし、この討議資料は個別具体的な会計基準の設定・改廃をただちに提案するものではない。その役割は、あくまでも基礎概念の整理を通じて基本的指針を提示することにある。
会計基準を取り巻く環境
この討議資料は、現行の会計基準の基礎にある前提や概念を要約し体系化したものであるから、財務報告を取り巻く現在の制約要因を前提としている。ここでいう制約要因とは、具体的には、市場慣行、投資家の情報分析能力、法の体系を支える基本的な考え方、および基準設定の経済的影響に係る社会的な価値判断などを指す。
今日ではそれらの制約要因について等質化が進んでおり、各国の違いは、少なくとも部分的には解消されつつある。この傾向がとりわけ顕著なのはビジネス環境であり、財・サービス・マネー・人材などの国際的な移動に対する障壁が取り払われ、共通のルールに基づく自由な取引が実現されつつある。その一環で、会計基準についても国際的な調和や統合が進められているのが現状である。
とはいえ、歴史的・地理的な初期条件の相違に起因する上記の制約要因の相違は、完全に解消されたわけではない。会計基準のありかたは、依然として違いが残るこれら制約要因から影響を受けている。この討議資料に集約された基礎概念は、そうした制約要因を前提としたものであり、その違いを超えた普遍性を必ずしも有しているわけではない。この討議資料に記載されている内容は、初期条件の異なる各国の概念書と異なりうる。また、それは環境の変化とともに変化しうる。つまり、制約要因が変化すれば、それに応じて会計基準も変化し、ひいては基礎概念も変化するであろう。
討議資料の限界
この討議資料は、会計基準の基礎にある前提や概念を要約・整理したものであるから、その記述内容はおのずから抽象的にならざるをえず、個別基準の設定・改廃に際しては、討議資料の内容に係る解釈が必要になる。そのため、この討議資料だけでは、個別の会計基準の具体的な内容を直接規定できない。
また、この討議資料で要約・整理された財務報告の目的などは、委員会の中心的な役割との関係上、原則として証券取引法上のディスクロージャー制度を念頭に置いて記述されたものである点にも留意しなければならない。ここでは公開企業を中心とする証券市場への情報開示が前提とされている。
討議資料『財務報告の目的』
【序 文】
この討議資料では、財務報告を支える基本的な前提や概念のなかでも、とりわけその目的に主眼が置かれ、意見の集約が試みられている。基礎概念の整理・要約に際し、財務報告の目的を最初にとりあげたのは、一般に社会のシステムは、その目的が基本的な性格を決めているからである。財務報告のシステムも、その例外ではない。
ただし、どのような社会のシステムも、時代や環境の違いを超えた普遍的な目的を持つわけではない。財務報告制度の目的は、社会からの要請によって与えられるものであり、自然に決まってくるのではない。とすれば、この制度に対し、いま社会からいかなる要請がなされているのかを確かめることは、そのありかたを検討する際に最優先すべき作業であろう。
財務報告はさまざまな役割を果たしているが、この討議資料では、その目的が、投資家による企業成果の予測と企業価値の評価に役立つような、企業の財務状況の開示にあると考える。自己の責任で将来を予測し投資の判断をする人々のために、企業の投資のポジション(ストック)とその成果(フロー)が開示されるとみるのである。
もちろん、企業価値の推定に利用することを会計情報の用途として位置づけているからといって、その他の用途を無視して財務報告のありかたを論じることが許されるわけではない。会計情報の副次的な用途にはどのようなものがありうるのか、会計基準の設定にあたり副次的な用途にどう対応すればよいのかについても、この討議資料で意見の集約が試みられている。
【本 文】
〔ディスクロージャー制度と財務報告の目的〕
1. 企業が生み出す将来のキャッシュフローを予測するうえで、企業の直面している状況に関する情報は不可欠であるが、その情報を入手する機会について、投資家と経営者の間には一般に大きな格差がある。このような状況のもとで、情報開示が不十分にしか行われないと、企業の発行する株式や社債などの価値を推定する際に投資家が自己責任を負うことはできず、それらの証券の円滑な発行・流通が妨げられることにもなる。情報の非対称性を緩和し、それが生み出す市場の機能障害を解決するため、経営者による私的情報の開示を促進するのがディスクロージャー制度の存在意義である。
2. 投資家は不確実な将来キャッシュフローへの期待のもとに、みずからの意思で自己の資金を企業に投下する。その不確実な成果を予測して意思決定をする際、投資家は企業が資金をどのように投資し、実際にどれだけの成果をあげているかについての情報を必要としている。経営者に開示が求められるのは、基本的にはこうした投資のポジションとその成果に関する情報である(脚注1)。投資家の意思決定に資するディスクロージャー制度の一環として、それらを測定して開示するのが、財務報告の目的である。
3. 財務報告において提供される情報のなかで、特に重要なのは投資の成果を表す利益情報である。利益は基本的に過去の成果であるが、企業価値評価の基礎となる将来キャッシュフローの予測に広く用いられている。利益の情報を重視することは、同時に、資本(純利益を生み出す投資の正味ストック)の情報を重視することも含意している。投資の成果の絶対的な大きさのみならず、それを生み出した資本と比較した収益性(あるいは効率性)も重視されるからである。
〔会計基準の役割〕
4. 経営者は本来、投資家の保守的なリスク評価によって企業価値が損なわれないよう、自分の持つ私的な企業情報を自発的に開示する誘因を有している。それゆえ、たとえ公的な規制がなくても、投資家に必要な情報はある程度まで自然に開示されるはずである。ただし、その場合でも、虚偽情報を排除するとともに情報の等質性を確保する最小限のルールは必要であり、それを当事者間の交渉(契約)に委ねていたのではコストがかかりすぎることになる。それを社会的に削減するべく、標準的な契約を一般化して、会計基準が形成される。ディスクロージャー制度を支える社会規範としての役割が、会計基準に求められている。
5. 会計基準が「最小限のルール(ミニマム・スタンダード)」として有効に機能するか否かは、契約の標準化ないし画一化による便益がそれに伴うコストを上回っているか否かに依存する。そこでいうコストや便益は環境に依存して決まるため、その環境変化に応じて、会計基準のありかたも変わりうる。
〔ディスクロージャー制度における各当事者の役割〕
6. ディスクロージャー制度の主たる当事者としては、情報を利用して企業に資金を提供する投資家、情報を開示して資金を調達する経営者、および両者の間に介在して情報に対して保証を付与する監査人の三者を想定できる。
7. 投資家とは、株式や社債を現に保有する者のほか、証券市場の参加者、さらにはいわゆる与信者も含んだ者を指す。投資家は開示された情報を利用して、自己の責任で将来の企業成果を予想し、現在の企業価値を評価する。投資家の中には会計情報の分析能力に優れた者のほか、専門家の助けを必要とする者も含まれているが、証券市場が効率的であれば、情報処理能力の差は投資家の間に不公正をもたらさない。それゆえ、会計基準の設定にあたっては、原則として、一定以上の分析能力を持った投資家を想定すればよい。
8. 経営者には、投資家がその役割を果たすのに必要な情報を開示することが期待されている。予測は投資家の自己責任で行われるべきであり、経営者が負うべき責任は基本的には事実の開示である。会計情報を開示するうえで経営者自身の予測が必要な場合でも、それを開示する目的は原則として現在の事実を明らかにすることにある。
9. 監査人は、投資家の必要とする会計情報を経営者が適正に開示しているか否かを確かめる。具体的には、一般に公正妥当と認められた会計基準への準拠性について、一般に公正妥当と認められた監査基準に従って監査することを、その役割としている。監査人には経営者が作成した情報を監査する責任が課されているだけであり、財務情報の作成責任はあくまでも経営者が負う。
10.ディスクロージャー制度の当事者はそれぞれ、会計基準が遵守されることで便益を享受する。会計基準に従って作成され、独立した監査人の監査を受けた情報は、一般に投資家の信頼を得られやすい。そうした情報を低いコストで入手できることは、投資家にとっての便益となる。それによって投資家の要求する資本のコストが下がり、企業価値が高まれば、経営者も会計基準から便益を享受することとなる。また経営者は、投資家の情報要求を個別に確かめるためのコストを削減できるという点でも、便益を享受する。投資家の最低限の情報要求に応えるには、どのような会計情報を提供すればよいのかを、会計基準が明らかにするからである。さらに会計基準は、監査上の判断の基礎を提供する機能を果たし、監査人にも便益を与える。
〔会計情報の副次的な利用〕
11.ディスクロージャー制度において開示される会計情報は、企業関係者の間の私的契約等を通じた利害調整にも副次的に利用されている。また、会計情報は不特定多数を対象とするいくつかの関連諸法規や政府等の規制においても副次的に利用されている。その典型例は、配当制限(商法)、税務申告制度(税法)、金融規制(例えば自己資本比率規制、ソルベンシー・マージン規制)などである。
12.会計基準の設定にあたり最も重視されるべきは、第2項に記述されている目的の達成である。しかし、会計情報が副次的な用途にも利用されている事実は、会計基準を設定・改廃する際の制約となることがある。すなわち会計基準の設定・改廃を進める際には、それが公的規制や私的契約等を通じた利害調整に及ぼす影響も、同時に考慮の対象となる。そうした副次的な利用との関係も検討しながら、財務報告の目的の達成が図られる。
【結論の根拠と背景説明】
〔ディスクロージャー制度と財務報告の目的〕
13.情報の非対称性は、証券の発行市場のみならず流通市場においても問題となる。将来の売却機会が保証されないかぎり、投資家はそもそも証券の発行市場においてさえその購入に応じようとしないであろう。企業が証券市場で資金調達をするかぎり、企業には、証券売買を円滑にするように情報の非対称性を緩和する努力が継続的に求められる。
14.情報の非対称性を緩和するための会計情報や、その内容を規制する会計基準は、市場が効率的であれば不要になるわけではない。市場の効率性は、提供された情報を市場参加者が正しく理解しているか否か、市場価格はそれを速やかに反映するか否かに関わる問題であり、何を開示するのかという「情報のなかみ」は効率性とは別問題である。市場参加者の合理的な行動と効率的市場を前提としても、開示すべき会計情報の内容については、なお会計基準による規制が必要である。
15.会計情報は技術的な制約や環境制約のもとで作成されるものである。会計情報だけで投資家からの要求のすべてに応えることはできない。
16.会計情報は企業価値の推定に資することが期待されているが、企業価値それ自体を表現するものではない。企業価値を主体的に見積もるのはみずからの意思で投資を行う投資家であり、会計情報には、その見積もりにあたって必要な、予想形成に役立つ基礎を提供する役割だけが期待されている。
〔ディスクロージャー制度における各当事者の役割〕
17.今日の証券市場においてはさまざまな情報仲介者が存在し、洗練されていない(十分な分析能力を持たない)投資家に代わって証券投資に必要な情報の分析を行っている。洗練されていない投資家は、これらの仲介者を利用することにより、分析能力を高めるのに必要なコストを節約しながら証券投資を行うことができる。情報仲介者の間で市場競争が行われているとすれば、洗練されていない投資家にも会計情報は効率的に伝播するであろう。今日のディスクロージャー制度はこうした市場の効率性を前提としているため、この討議資料では一定以上の分析能力を持った(洗練された)投資家を情報の主要な受け手として想定している。
18.第7項および第8項に述べた投資家と経営者との役割分担とは異なり、特定の事業について情報優位にある経営者は企業価値の推定についても投資家より高い能力を持つという考え方から、その推定値の開示を経営者に期待する向きもある。しかし経営者自身による企業価値の開示は、証券の発行体が、その証券の価値に関する自己の判断を示して投資家に売買を勧誘することになりかねない。それは、証券取引法の精神に反するだけでなく、経営者としてもその判断に責任を負うのは難しい(脚注2)。そのため、財務報告の目的は事実の開示に限定される。
19.経営者にとっては、自己(または自社)の利益を図るうえで、事実に反した会計情報の開示も一つの選択肢となりうる。しかし投資家は、その可能性に対して、企業の発行する証券の価格を引き下げたり、経営者を解任したり、あるいは経営者報酬を引き下げたりするといった対抗手段を有している。合理的な経営者は、そのような事態をあらかじめ避けるため、むしろ監査人による監査を積極的に受け入れる誘因を持つ。すなわちディスクロージャー制度のもとで会計監査は、投資家に不利益が生じないよう、経営者が自身の行動を束縛する「ボンディング」の一環としての役割を果たしている。
20.会計監査が社会的に信頼され、有効に機能するのは、監査人の職業倫理だけでなく、経営者と監査人との関係に一定の規律を与える仕組みが補完的な役割を果たしているからである。監査の質を維持するために監査基準が存在することに加えて、監査人の選任等をめぐる競争原理が働いていることによっても、監査人の利己的な行為は抑止されているはずである。すなわち監査の信頼性は、監査人に求められる職業倫理とともに、監査人自身のボンディングなどを含む市場規律の働きによっても高められている。
21.会計基準は、財務報告の目的を効率的に達成できるか否かという観点から決められるものである。その決定過程において、適用しうる監査技法の集合は、重要な制約条件として考慮の対象となる。しかしながら、それはあくまでも目的達成のための制約条件であって、監査のコストを低めるような会計基準を設定すること自体が達成目標なのではない。
〔会計情報の副次的な利用〕
22.会計情報は、公的な規制や私的な契約等を通じた利害調整にも利用されている。会計情報の副次的な利用者は、個別の政策目的・契約目的に応じて、ディスクロージャー制度で開示される会計情報を適宜、加工・修正して利用する。それぞれの目的に適う会計情報を別個に作成するよりも、コストの節約が期待できる場合には、会計情報がそのように利用されることもある。しかし会計基準の設定・改廃の際、規制や契約のすべてを視野に収める必要はない。当事者の多くが関わる規制や契約については、会計基準の設定・改廃がそれらに及ぼす影響を考慮しなければならないが、ごく少数の当事者しか関わらない契約等については、必ずしも同様の配慮が求められるわけではない。その契約に関わらない多数の当事者にまで会計基準の変更に伴う再契約のコストを負担させることと、それに伴う便益とのバランスを考慮する必要があるからである。
脚注
1 キャッシュ・フロー計算書の開示についても、その重要性が浸透しつつある。
2 企業の経営者は独自の内部情報を有しているため、将来のキャッシュフローを決定する要因のうち、企業固有の要因を把握することについては優位な立場にある。しかし、景気、金利、為替など経済全体に関わる要因については、経営者が優位な立場にあるとは限らない。将来キャッシュフローに基づく企業価値の推定を経営者に委ねないのはそのためである。
討議資料『会計情報の質的特性』
【序 文】
この討議資料では、財務報告の目的を達成するにあたり、会計情報が備えるべき質的な特性を論じている。財務報告の目的は、投資家による企業成果の予測や企業評価のために、将来キャッシュフローの予測に役立つ情報を提供することである。会計情報に求められる最も重要な特性は、その目的にとっての有用性である。この討議資料では、この特性を意思決定有用性(decision usefulness)と称している。これは、すべての会計情報とそれを生み出すすべての会計基準に要求される規範として機能する。
しかし、その特性は具体性や操作性に欠けるため、それだけでは、将来の基準設定の指針として十分ではない。この討議資料は、意思決定有用性を支える下位の諸特性を具体化して、整理するとともに、特性間の関係を記述することにより、意思決定有用性という特性が機能できるようにすることを目的としている。したがって、この討議資料は現行の会計基準や会計実務を帰納要約的に記述したものではなく、その内容には、財務報告の目的の達成にとって有益であるか否か、必要であるか否かという判断が反映されている。
この討議資料で扱う会計情報の質的特性は、しばしば会計基準を設定する際の象徴的な標語としてひとり歩きし、自己目的化する危険性を有している。そのような危険をなくすため、海外の先例における諸特性を議論の出発点にしながら、歴史的にも地域的にもそれらを相対化・客観化する検討作業を経て、この討議資料はまとめられている。その検討結果に基づき、この討議資料では、諸特性の並列・対立関係と上下の階層関係などに対して特別な注意を払うとともに、諸特性の記述に際しては、常に財務報告の目的との関連が意識されている。
ただし、この討議資料に記した諸特性は、予定調和的に体系を形成しているものでもなければ、相互排他的な関係にあるわけでもない。会計基準の設定にあたり、どの特性をどれほど重視するのか、複数の特性がトレード・オフの関係にある場合に、どのようにバランスをとるのかは、与えられた環境条件の下で、財務報告の目的にてらして個々に判断されなければならない。この討議資料の目的は、その判断の指針を示すことではなく、もっぱら諸特性の意義と相互関係を明らかにすることに向けられている。
【本 文】
〔会計情報の基本的な特性-意思決定有用性-〕
1. 財務報告の目的は、企業価値評価の基礎となる企業成果、つまり将来キャッシュフローの予測に役立つ情報を提供することである。この目的を達成するにあたり、会計情報に求められる最も基本的な特性は、意思決定有用性である。すなわち会計情報には、投資家が企業の不確実な成果を予測するのに有用であることが期待されている。
2. 会計情報が投資家の意思決定に有用であることは、意思決定目的に関連する情報であること(relevance to decision)、内的な整合性のある会計基準に従って作成された情報であること(internal consistency)、および一定の水準で信頼できる情報であること(reliability)に支えられている。
〔有用性を支える特性(1):意思決定との関連性〕
3. このうち意思決定との関連性とは、会計情報が将来の投資の成果についての予測に関連する内容を含んでおり、企業価値の推定を通じた投資家による意思決定に積極的な影響を与えて貢献することを指す。
4. 会計情報が投資家の意思決定に貢献するか否かは、第一に、それが情報価値を有しているか否かと関わっている。ここでいう情報価値とは、投資家の予測や行動が当該情報の入手によって改善されることをいう。ただし、会計基準の設定局面において、新たな基準に基づく会計情報の情報価値は不確かな場合も多い(脚注1)。そのケースでは、投資家による情報ニーズ(information needs)の存在が、情報価値を期待させる。そのような期待に基づいて、情報価値の存否について事前に確たることがいえない場合であっても、投資家からの要求に応えるために会計基準の設定・改廃が行われることもある。この意味で、情報価値の存在と情報ニーズの充足は、意思決定との関連性を支える二つの特性と位置づけられる。
5. もっとも、情報開示のニーズがある会計情報のすべてが投資家の意思決定と関連しているとは限らない。投資家の意思決定に関連する情報はディスクロージャー制度以外の情報源からも投資家に提供されており、投資家の情報ニーズのすべてをディスクロージャー制度で応えるべきか否かは、慎重な検討を要する問題である。この点で、意思決定との関連性が基準設定で果たす役割には一定の限界がある。
〔有用性を支える特性(2):内的な整合性〕
6. 会計情報の有用性は、意思決定との関連性のほか、その情報を生み出す会計基準の内的な整合性にも支えられている。内的な整合性とは、個別の会計基準が、会計基準全体を支える基本的な考え方と矛盾しないことを指す。会計基準は、少数の基礎概念に支えられた一つの体系をなしている。その体系と矛盾しない基準に依拠した会計情報は、矛盾を抱えた基準に依拠した会計情報よりも有用なものとみなしうる。会計基準の現在の体系が実際に利用されて定着している事実は、その体系のもとで有用な情報が提供されてきたことの証拠とみなせるからである。特別な反証のないかぎり、その体系性を損なわない基準の設定・改廃が求められることとなる。
7. 内的な整合性は、環境条件が大きく変化していないかぎり、新たな経済事象や新たな形態の取引に関して会計基準を設定する際の判断規準として、とりわけ重要である。前提となる環境条件が一定であれば、既存の会計基準の体系と整合的な会計基準は有用な情報を生み出すという推定が働く。その状況では、関連する会計基準と矛盾が生じないように留意するだけでよい。このような形で進められる基準設定は、会計基準を決めるための具体的な手がかりがあらかじめ与えられていることから、会計情報の価値をそのつど推定しながら進める基準設定より効率的なものとなりうる(脚注2)。
8. 他方、財務報告を取り巻く環境が変化した場合には、旧来の環境条件に適合した会計基準との整合性を問うことの意味が失われる。内的な整合性に着目した基準設定が意味を持つのは、環境が変わらない状況下で、個別具体的な会計処理のありかたが追加的に問われる状況に限られる。それが変化した場合は、既存の体系に固執することなく、新たな環境に適合する会計基準の体系を模索することとなる。
〔有用性を支える特性(3):信頼性〕
9. 会計情報の有用性は、信頼性にも支えられている。信頼性とは、中立性・検証可能性・表現の忠実性などに支えられ、会計情報が信頼に足る情報であることを指す。
10.会計情報の作成者である経営者の利害は、投資家の利害と必ずしも一致していない。そのため、経営者の自己申告による情報を投資家が全面的に信頼するのは難しい。利害の不一致に起因する弊害を小さく抑えるためには、一部の関係者の利害だけを偏重することのない財務報告が求められる(中立性)。また、利益の測定では将来事象の見積もりが不可欠であるが、見積もりによる測定値は、誰が見積もるのかによって、大きなバラツキが生じることがある。このような利益情報には、ある種のノイズが含まれており、見積もりのみに基づく情報を投資家が完全に信頼するのは難しい。そのような事態を避けるには、測定者の主観には左右されない事実に基づく財務報告が求められる(検証可能性)。さらに企業が直面した事実を会計データの形で表現しようとする際、もともと多様な事実を少数の会計上の項目へと分類しなければならない。しかし、その分類規準に解釈の余地が残されている場合は、分類結果を信頼できない事態も起こりうる。このような事態を避けるため、事実と会計上の分類項目との明確な対応関係が求められる(表現の忠実性)。
〔特性間の関係〕
11.意思決定との関連性、内的な整合性、信頼性、これら三つの特性はすべてが同時に満たされることもあれば、いくつかの特性間にトレード・オフの関係がみられることもある。ある種の情報が、いずれかの特性を高める反面で、残りの特性を損なうケースもありうる。特性間にトレード・オフの関係がみられる場合は、すべての特性を考慮に入れたうえで、新たな基準のもとで期待される会計情報の有用性を総合的に判断することになる。
【結論の根拠と背景説明】
〔質的特性の意義〕
12.この討議資料のとりまとめに際しては、現在の基準設定のありかたを記述するのが目的なのか、それとも望ましい基準設定のありかたを論じ、将来の指針たりうる規範を示すのが目的なのかが議論された。この討議資料は基準設定の指針として機能することが期待されているため、ここでは単に事実を記述するのではなく、その機能を果たすための価値判断を含んだ記述を行うこととした。
〔内的な整合性〕
13.この討議資料と、海外の概念書との最大の違いは、会計情報の意思決定有用性を支える特性として、意思決定との関連性と信頼性に加え、内的な整合性をとりあげた点にある。整合的な基準から生み出された会計情報は有用であるとみるのが、広く合意された考え方だからである。新たな会計基準による情報の価値が事前にはわからない場合、整合性は情報価値を推定する補完的役割を果たすが、整合性に裏づけられた会計情報の有用性は、意思決定との関連性にいう情報価値の有無とは異なる意味でいわれることもある。こうしたことから、この討議資料では整合性に独立した地位を与えた。
14.新たな基準設定の際に整合性を問う対象として重要なのは、会計基準を支えている基本的な考え方である。内的な整合性の参照対象は、会計基準、会計実務、会計研究などについての歴史的経験と集積された知識の総体である。そのうち、会計基準の設定にとって重要な部分は、この討議資料で記述されているが、その全貌を示したものではない。それゆえ、この討議資料に準拠して会計基準を設定することは、内的な整合性の達成にとって必要条件であって、十分条件ではない。この討議資料には限界があることを十分に認識しなければならない。
15.米国や英国などの慣習法国家と異なり、日本の法秩序は、成文法の体系に支えられている。その環境条件のもとでは、基準設定に際し、会計基準の内的な整合性を尊重することが、秩序安定のためにとりわけ強く求められる。一般に成文法のもとでは、ルールの設定・改廃に際し、既存のルールとの関係を常に考慮しなければならない。しかしこうした事実について、これまで国際的な理解が十分には得られてこなかった。ここで整合性を重視する必要性や、整合性に着目する方法の限界を明らかにすることは、基準設定のありかたをめぐる国際的な相互理解の助けになると期待されている。
16.なお、この討議資料でいう内的な整合性は、いわゆる首尾一貫性(consistency)とは異なっている。後者は特定の会計手続が毎期継続的に(中間報告と決算報告とで同一の手続きが)適用されることを要請するものであるのに対し、前者は現行基準の体系と矛盾しない個別基準を採用するよう要請するものである。
〔特性間の関係〕
17.この討議資料のとりまとめに際しては、意思決定との関連性・内的な整合性・信頼性の三者を並列させるのか、それとも意思決定との関連性と内的な整合性を下位に置く新たな上位概念を想定し、その上位概念と信頼性とを並列させるべきなのかが論じられた。この討議資料では、内的な整合性に固有の意義を認めて、意思決定との関連性と内的な整合性とを並列させることにした。
18.また、信頼性は他の特性と並列の関係にあるのか、それとも、他の特性よりも上位の制約条件であるのかも議論された。信頼性が他の特性から独立し、かつ常に他の特性よりも優先されるなら、信頼性は上位の制約条件として機能することになる。しかし、信頼性は意思決定との関連性から完全に独立しているわけではない(脚注3)。また、最優先すべきは意思決定有用性であり、下位の三つの特性の間に優劣関係は見出せない。それゆえ、この討議資料においては、信頼性を他の特性と並列して位置づけた。
〔信頼性の下位概念〕
19.諸外国で信頼性の下位概念とされている中立性・検証可能性・表現の忠実性については、それらを改めて定義し直すべきか否かが議論の対象となった。それらのなかには、原義から離れた使われ方をしているものもあるという意見も出された。しかし、それらの用語はすでに会計実践で定着しており、それを変更すれば無用な混乱を招きかねない。それは、将来の基準設定に指針を提供するという討議資料の役割、および整合性を重視するという基本姿勢などに反する帰結であろう。そうした事態を避けるため、この討議資料では、それらの定義については、海外の先例を踏襲することとした。
〔一般的な制約条件〕
20.諸外国では一般的な制約条件などに位置づけられている比較可能性・理解可能性・重要性・コストとベネフィットの斟酌などについては、これらを会計情報の質的特性に含めるか否かが検討された。まず、質的特性を簡潔な体系として記述するという基本方針が確認され、自明なもの、他の特性と重複するもの、その意義について疑念が残るものなどは記述しないことにした。
21.比較可能性については、多くの時間が議論に費やされた。本来、表現の忠実性は「異なる事実には異なる会計処理を、同様の事実には同じ会計処理を」要請するものであって、異質な事実を一括りにして画一的な会計処理を要求し、経営者による裁量の余地を過度に狭めると、むしろ投資家にとっての意思決定有用性が損なわれかねないという議論がなされた。会計処理の画一的な統一に対する懸念が表明されたのである。また、表現の忠実性をそのように理解すると、比較可能性は表現の忠実性に包摂されてしまうのではないか、という議論もなされた。それらの議論を踏まえて、この討議資料では比較可能性を記述しないこととした。
22.理解可能性については、洗練された投資家を想定することと矛盾するのではないかという指摘や、人間の合理性には限界があるという意味なら自明であるとの指摘がなされた。さらに、この特性が将来の基準設定の指針としていかなる機能を果たすのか明らかではないという意見も出された。また、重要性、およびコストとベネフィットの勘酌についても、経済合理性の観点からすれば自明であるとの議論がなされた。それらの議論を踏まえて、この討議資料では、理解可能性・重要性・コストとベネフィットの斟酌を記述しないこととした。
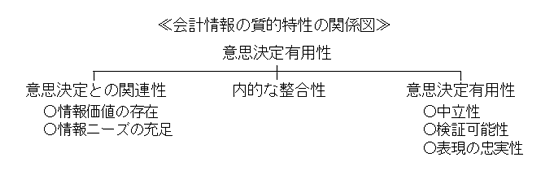
脚注
1 特定の情報が投資家の行動を改善するか否かについて、事前に確たることをいうのは難しい。投資家の意思決定モデルを特定するのが困難なうえ、予想される多様な結果を社会全体としてどのように評価したらよいのか、評価の尺度を特定するのも困難だからである。
2 内的な整合性を保つことは、会計基準の変化を予見できるようにする点でも優れている。例えば、新たな形態の取引の登場に応じて会計基準がどう変化するのかを予想できれば、情報の作成者や利用者はみずからの行動を少しずつ新しい環境に適合させていくことができるからである。
3 例えば信頼性についての議論のうち表現の忠実性に係る部分(第9項および第10項)で触れたように、事実を会計データにどう置き換えるのかは、会計情報の情報価値を左右する問題でもある。
下記資料は、(財)財務会計基準機構のホームページより同財団の許可を得て転載しています。なお、同財団の公表物は、著作権等により保護されており、同財団の許可なく複写・転載すること等は禁じられています。利用等に当たっては、同財団事務局(tel:03-5561-9618)へご連絡下さい。
討議資料『財務会計の概念フレームワーク』公表の経緯
企業会計基準委員会(以下、委員会という)は、わが国の会計基準を設定するにあたって、概念フレームワークを明文化する必要性が各方面から指摘されたのを受け、委員会のもとに外部の研究者を中心としたワーキング・グループを組織して、その問題の検討を委託した。ワーキング・グループには委員会から常勤委員や事務局メンバーも加わり、委員会の委員長が座長となって合計46回に及ぶ会議を統括した。そこで得られた結論をとりまとめたのが、この討議資料『財務会計の概念フレームワーク』(以下、討議資料という)である。
したがって、この討議資料に示されているのは、委員会の見解ではなく、委員会に報告される当ワーキング・グループの見解である。むろん、これは、今後の基準設定の過程で有用性をテストされ、市場関係者等の意見を受けてさらに整備・改善されれば、いずれはデファクト・スタンダードとしての性格を持つことになるであろう。委員会がその経緯をみながら、この討議資料を素材に必要な議論を重ねていくことを、当ワーキング・グループとしても期待するものである。
概念フレームワークを記述する体系には、本来、多様な選択肢がありうるが、この討議資料の構成は、大枠で海外の先例に従っている。海外の主な会計基準設定主体が公表した概念書は、わが国でもすでに広く知られているため、それと構成を揃えることで関係者の理解が容易になり、この討議資料の機能がより効率的に発揮されると期待できるからである。さらに、海外と同一の構成を採用することによって、会計基準の国際的調和をめぐるコミュニケーションも、より円滑になるであろう。
討議資料の役割
この討議資料では、現行の企業会計(とくに財務会計)の基礎にある前提や概念が要約・整理されており、その内容は、将来の会計基準設定の指針になると期待されている。その指針によって、会計基準の体系的安定性が得られれば、会計基準の変化についての予見可能性が高まるであろう。そのことを通じて不確実な将来への対応をより的確なものとし、企業や利害関係者に無用なコストが生じる事態を避けることも、この討議資料に期待されている重要な役割である。
基本となる前提や概念を要約・整理しておくことには、海外の基準設定主体との円滑なコミュニケーションに資する役割も期待されている。会計基準の国際的な調和(または収斂)が求められるなかで、会計基準の相違が何に起因しているのかについて説明が求められる機会は少なくない。この討議資料には、そうした説明のための有効な基盤となることも期待されている。
この討議資料には、現行の会計基準をつとめて体系的に整理するだけでなく、前述のとおり、将来の基準設定に指針を与える役割も求められている。そのため、この討議資料の内容には、現行会計基準の一部を説明できないものが含まれていたり、いまだ基準化されていないものが含まれていたりする。しかし、この討議資料は個別具体的な会計基準の設定・改廃をただちに提案するものではない。その役割は、あくまでも基礎概念の整理を通じて基本的指針を提示することにある。
会計基準を取り巻く環境
この討議資料は、現行の会計基準の基礎にある前提や概念を要約し体系化したものであるから、財務報告を取り巻く現在の制約要因を前提としている。ここでいう制約要因とは、具体的には、市場慣行、投資家の情報分析能力、法の体系を支える基本的な考え方、および基準設定の経済的影響に係る社会的な価値判断などを指す。
今日ではそれらの制約要因について等質化が進んでおり、各国の違いは、少なくとも部分的には解消されつつある。この傾向がとりわけ顕著なのはビジネス環境であり、財・サービス・マネー・人材などの国際的な移動に対する障壁が取り払われ、共通のルールに基づく自由な取引が実現されつつある。その一環で、会計基準についても国際的な調和や統合が進められているのが現状である。
とはいえ、歴史的・地理的な初期条件の相違に起因する上記の制約要因の相違は、完全に解消されたわけではない。会計基準のありかたは、依然として違いが残るこれら制約要因から影響を受けている。この討議資料に集約された基礎概念は、そうした制約要因を前提としたものであり、その違いを超えた普遍性を必ずしも有しているわけではない。この討議資料に記載されている内容は、初期条件の異なる各国の概念書と異なりうる。また、それは環境の変化とともに変化しうる。つまり、制約要因が変化すれば、それに応じて会計基準も変化し、ひいては基礎概念も変化するであろう。
討議資料の限界
この討議資料は、会計基準の基礎にある前提や概念を要約・整理したものであるから、その記述内容はおのずから抽象的にならざるをえず、個別基準の設定・改廃に際しては、討議資料の内容に係る解釈が必要になる。そのため、この討議資料だけでは、個別の会計基準の具体的な内容を直接規定できない。
また、この討議資料で要約・整理された財務報告の目的などは、委員会の中心的な役割との関係上、原則として証券取引法上のディスクロージャー制度を念頭に置いて記述されたものである点にも留意しなければならない。ここでは公開企業を中心とする証券市場への情報開示が前提とされている。
討議資料『財務報告の目的』
【序 文】
この討議資料では、財務報告を支える基本的な前提や概念のなかでも、とりわけその目的に主眼が置かれ、意見の集約が試みられている。基礎概念の整理・要約に際し、財務報告の目的を最初にとりあげたのは、一般に社会のシステムは、その目的が基本的な性格を決めているからである。財務報告のシステムも、その例外ではない。
ただし、どのような社会のシステムも、時代や環境の違いを超えた普遍的な目的を持つわけではない。財務報告制度の目的は、社会からの要請によって与えられるものであり、自然に決まってくるのではない。とすれば、この制度に対し、いま社会からいかなる要請がなされているのかを確かめることは、そのありかたを検討する際に最優先すべき作業であろう。
財務報告はさまざまな役割を果たしているが、この討議資料では、その目的が、投資家による企業成果の予測と企業価値の評価に役立つような、企業の財務状況の開示にあると考える。自己の責任で将来を予測し投資の判断をする人々のために、企業の投資のポジション(ストック)とその成果(フロー)が開示されるとみるのである。
もちろん、企業価値の推定に利用することを会計情報の用途として位置づけているからといって、その他の用途を無視して財務報告のありかたを論じることが許されるわけではない。会計情報の副次的な用途にはどのようなものがありうるのか、会計基準の設定にあたり副次的な用途にどう対応すればよいのかについても、この討議資料で意見の集約が試みられている。
【本 文】
〔ディスクロージャー制度と財務報告の目的〕
1. 企業が生み出す将来のキャッシュフローを予測するうえで、企業の直面している状況に関する情報は不可欠であるが、その情報を入手する機会について、投資家と経営者の間には一般に大きな格差がある。このような状況のもとで、情報開示が不十分にしか行われないと、企業の発行する株式や社債などの価値を推定する際に投資家が自己責任を負うことはできず、それらの証券の円滑な発行・流通が妨げられることにもなる。情報の非対称性を緩和し、それが生み出す市場の機能障害を解決するため、経営者による私的情報の開示を促進するのがディスクロージャー制度の存在意義である。
2. 投資家は不確実な将来キャッシュフローへの期待のもとに、みずからの意思で自己の資金を企業に投下する。その不確実な成果を予測して意思決定をする際、投資家は企業が資金をどのように投資し、実際にどれだけの成果をあげているかについての情報を必要としている。経営者に開示が求められるのは、基本的にはこうした投資のポジションとその成果に関する情報である(脚注1)。投資家の意思決定に資するディスクロージャー制度の一環として、それらを測定して開示するのが、財務報告の目的である。
3. 財務報告において提供される情報のなかで、特に重要なのは投資の成果を表す利益情報である。利益は基本的に過去の成果であるが、企業価値評価の基礎となる将来キャッシュフローの予測に広く用いられている。利益の情報を重視することは、同時に、資本(純利益を生み出す投資の正味ストック)の情報を重視することも含意している。投資の成果の絶対的な大きさのみならず、それを生み出した資本と比較した収益性(あるいは効率性)も重視されるからである。
〔会計基準の役割〕
4. 経営者は本来、投資家の保守的なリスク評価によって企業価値が損なわれないよう、自分の持つ私的な企業情報を自発的に開示する誘因を有している。それゆえ、たとえ公的な規制がなくても、投資家に必要な情報はある程度まで自然に開示されるはずである。ただし、その場合でも、虚偽情報を排除するとともに情報の等質性を確保する最小限のルールは必要であり、それを当事者間の交渉(契約)に委ねていたのではコストがかかりすぎることになる。それを社会的に削減するべく、標準的な契約を一般化して、会計基準が形成される。ディスクロージャー制度を支える社会規範としての役割が、会計基準に求められている。
5. 会計基準が「最小限のルール(ミニマム・スタンダード)」として有効に機能するか否かは、契約の標準化ないし画一化による便益がそれに伴うコストを上回っているか否かに依存する。そこでいうコストや便益は環境に依存して決まるため、その環境変化に応じて、会計基準のありかたも変わりうる。
〔ディスクロージャー制度における各当事者の役割〕
6. ディスクロージャー制度の主たる当事者としては、情報を利用して企業に資金を提供する投資家、情報を開示して資金を調達する経営者、および両者の間に介在して情報に対して保証を付与する監査人の三者を想定できる。
7. 投資家とは、株式や社債を現に保有する者のほか、証券市場の参加者、さらにはいわゆる与信者も含んだ者を指す。投資家は開示された情報を利用して、自己の責任で将来の企業成果を予想し、現在の企業価値を評価する。投資家の中には会計情報の分析能力に優れた者のほか、専門家の助けを必要とする者も含まれているが、証券市場が効率的であれば、情報処理能力の差は投資家の間に不公正をもたらさない。それゆえ、会計基準の設定にあたっては、原則として、一定以上の分析能力を持った投資家を想定すればよい。
8. 経営者には、投資家がその役割を果たすのに必要な情報を開示することが期待されている。予測は投資家の自己責任で行われるべきであり、経営者が負うべき責任は基本的には事実の開示である。会計情報を開示するうえで経営者自身の予測が必要な場合でも、それを開示する目的は原則として現在の事実を明らかにすることにある。
9. 監査人は、投資家の必要とする会計情報を経営者が適正に開示しているか否かを確かめる。具体的には、一般に公正妥当と認められた会計基準への準拠性について、一般に公正妥当と認められた監査基準に従って監査することを、その役割としている。監査人には経営者が作成した情報を監査する責任が課されているだけであり、財務情報の作成責任はあくまでも経営者が負う。
10.ディスクロージャー制度の当事者はそれぞれ、会計基準が遵守されることで便益を享受する。会計基準に従って作成され、独立した監査人の監査を受けた情報は、一般に投資家の信頼を得られやすい。そうした情報を低いコストで入手できることは、投資家にとっての便益となる。それによって投資家の要求する資本のコストが下がり、企業価値が高まれば、経営者も会計基準から便益を享受することとなる。また経営者は、投資家の情報要求を個別に確かめるためのコストを削減できるという点でも、便益を享受する。投資家の最低限の情報要求に応えるには、どのような会計情報を提供すればよいのかを、会計基準が明らかにするからである。さらに会計基準は、監査上の判断の基礎を提供する機能を果たし、監査人にも便益を与える。
〔会計情報の副次的な利用〕
11.ディスクロージャー制度において開示される会計情報は、企業関係者の間の私的契約等を通じた利害調整にも副次的に利用されている。また、会計情報は不特定多数を対象とするいくつかの関連諸法規や政府等の規制においても副次的に利用されている。その典型例は、配当制限(商法)、税務申告制度(税法)、金融規制(例えば自己資本比率規制、ソルベンシー・マージン規制)などである。
12.会計基準の設定にあたり最も重視されるべきは、第2項に記述されている目的の達成である。しかし、会計情報が副次的な用途にも利用されている事実は、会計基準を設定・改廃する際の制約となることがある。すなわち会計基準の設定・改廃を進める際には、それが公的規制や私的契約等を通じた利害調整に及ぼす影響も、同時に考慮の対象となる。そうした副次的な利用との関係も検討しながら、財務報告の目的の達成が図られる。
【結論の根拠と背景説明】
〔ディスクロージャー制度と財務報告の目的〕
13.情報の非対称性は、証券の発行市場のみならず流通市場においても問題となる。将来の売却機会が保証されないかぎり、投資家はそもそも証券の発行市場においてさえその購入に応じようとしないであろう。企業が証券市場で資金調達をするかぎり、企業には、証券売買を円滑にするように情報の非対称性を緩和する努力が継続的に求められる。
14.情報の非対称性を緩和するための会計情報や、その内容を規制する会計基準は、市場が効率的であれば不要になるわけではない。市場の効率性は、提供された情報を市場参加者が正しく理解しているか否か、市場価格はそれを速やかに反映するか否かに関わる問題であり、何を開示するのかという「情報のなかみ」は効率性とは別問題である。市場参加者の合理的な行動と効率的市場を前提としても、開示すべき会計情報の内容については、なお会計基準による規制が必要である。
15.会計情報は技術的な制約や環境制約のもとで作成されるものである。会計情報だけで投資家からの要求のすべてに応えることはできない。
16.会計情報は企業価値の推定に資することが期待されているが、企業価値それ自体を表現するものではない。企業価値を主体的に見積もるのはみずからの意思で投資を行う投資家であり、会計情報には、その見積もりにあたって必要な、予想形成に役立つ基礎を提供する役割だけが期待されている。
〔ディスクロージャー制度における各当事者の役割〕
17.今日の証券市場においてはさまざまな情報仲介者が存在し、洗練されていない(十分な分析能力を持たない)投資家に代わって証券投資に必要な情報の分析を行っている。洗練されていない投資家は、これらの仲介者を利用することにより、分析能力を高めるのに必要なコストを節約しながら証券投資を行うことができる。情報仲介者の間で市場競争が行われているとすれば、洗練されていない投資家にも会計情報は効率的に伝播するであろう。今日のディスクロージャー制度はこうした市場の効率性を前提としているため、この討議資料では一定以上の分析能力を持った(洗練された)投資家を情報の主要な受け手として想定している。
18.第7項および第8項に述べた投資家と経営者との役割分担とは異なり、特定の事業について情報優位にある経営者は企業価値の推定についても投資家より高い能力を持つという考え方から、その推定値の開示を経営者に期待する向きもある。しかし経営者自身による企業価値の開示は、証券の発行体が、その証券の価値に関する自己の判断を示して投資家に売買を勧誘することになりかねない。それは、証券取引法の精神に反するだけでなく、経営者としてもその判断に責任を負うのは難しい(脚注2)。そのため、財務報告の目的は事実の開示に限定される。
19.経営者にとっては、自己(または自社)の利益を図るうえで、事実に反した会計情報の開示も一つの選択肢となりうる。しかし投資家は、その可能性に対して、企業の発行する証券の価格を引き下げたり、経営者を解任したり、あるいは経営者報酬を引き下げたりするといった対抗手段を有している。合理的な経営者は、そのような事態をあらかじめ避けるため、むしろ監査人による監査を積極的に受け入れる誘因を持つ。すなわちディスクロージャー制度のもとで会計監査は、投資家に不利益が生じないよう、経営者が自身の行動を束縛する「ボンディング」の一環としての役割を果たしている。
20.会計監査が社会的に信頼され、有効に機能するのは、監査人の職業倫理だけでなく、経営者と監査人との関係に一定の規律を与える仕組みが補完的な役割を果たしているからである。監査の質を維持するために監査基準が存在することに加えて、監査人の選任等をめぐる競争原理が働いていることによっても、監査人の利己的な行為は抑止されているはずである。すなわち監査の信頼性は、監査人に求められる職業倫理とともに、監査人自身のボンディングなどを含む市場規律の働きによっても高められている。
21.会計基準は、財務報告の目的を効率的に達成できるか否かという観点から決められるものである。その決定過程において、適用しうる監査技法の集合は、重要な制約条件として考慮の対象となる。しかしながら、それはあくまでも目的達成のための制約条件であって、監査のコストを低めるような会計基準を設定すること自体が達成目標なのではない。
〔会計情報の副次的な利用〕
22.会計情報は、公的な規制や私的な契約等を通じた利害調整にも利用されている。会計情報の副次的な利用者は、個別の政策目的・契約目的に応じて、ディスクロージャー制度で開示される会計情報を適宜、加工・修正して利用する。それぞれの目的に適う会計情報を別個に作成するよりも、コストの節約が期待できる場合には、会計情報がそのように利用されることもある。しかし会計基準の設定・改廃の際、規制や契約のすべてを視野に収める必要はない。当事者の多くが関わる規制や契約については、会計基準の設定・改廃がそれらに及ぼす影響を考慮しなければならないが、ごく少数の当事者しか関わらない契約等については、必ずしも同様の配慮が求められるわけではない。その契約に関わらない多数の当事者にまで会計基準の変更に伴う再契約のコストを負担させることと、それに伴う便益とのバランスを考慮する必要があるからである。
脚注
1 キャッシュ・フロー計算書の開示についても、その重要性が浸透しつつある。
2 企業の経営者は独自の内部情報を有しているため、将来のキャッシュフローを決定する要因のうち、企業固有の要因を把握することについては優位な立場にある。しかし、景気、金利、為替など経済全体に関わる要因については、経営者が優位な立場にあるとは限らない。将来キャッシュフローに基づく企業価値の推定を経営者に委ねないのはそのためである。
討議資料『会計情報の質的特性』
【序 文】
この討議資料では、財務報告の目的を達成するにあたり、会計情報が備えるべき質的な特性を論じている。財務報告の目的は、投資家による企業成果の予測や企業評価のために、将来キャッシュフローの予測に役立つ情報を提供することである。会計情報に求められる最も重要な特性は、その目的にとっての有用性である。この討議資料では、この特性を意思決定有用性(decision usefulness)と称している。これは、すべての会計情報とそれを生み出すすべての会計基準に要求される規範として機能する。
しかし、その特性は具体性や操作性に欠けるため、それだけでは、将来の基準設定の指針として十分ではない。この討議資料は、意思決定有用性を支える下位の諸特性を具体化して、整理するとともに、特性間の関係を記述することにより、意思決定有用性という特性が機能できるようにすることを目的としている。したがって、この討議資料は現行の会計基準や会計実務を帰納要約的に記述したものではなく、その内容には、財務報告の目的の達成にとって有益であるか否か、必要であるか否かという判断が反映されている。
この討議資料で扱う会計情報の質的特性は、しばしば会計基準を設定する際の象徴的な標語としてひとり歩きし、自己目的化する危険性を有している。そのような危険をなくすため、海外の先例における諸特性を議論の出発点にしながら、歴史的にも地域的にもそれらを相対化・客観化する検討作業を経て、この討議資料はまとめられている。その検討結果に基づき、この討議資料では、諸特性の並列・対立関係と上下の階層関係などに対して特別な注意を払うとともに、諸特性の記述に際しては、常に財務報告の目的との関連が意識されている。
ただし、この討議資料に記した諸特性は、予定調和的に体系を形成しているものでもなければ、相互排他的な関係にあるわけでもない。会計基準の設定にあたり、どの特性をどれほど重視するのか、複数の特性がトレード・オフの関係にある場合に、どのようにバランスをとるのかは、与えられた環境条件の下で、財務報告の目的にてらして個々に判断されなければならない。この討議資料の目的は、その判断の指針を示すことではなく、もっぱら諸特性の意義と相互関係を明らかにすることに向けられている。
【本 文】
〔会計情報の基本的な特性-意思決定有用性-〕
1. 財務報告の目的は、企業価値評価の基礎となる企業成果、つまり将来キャッシュフローの予測に役立つ情報を提供することである。この目的を達成するにあたり、会計情報に求められる最も基本的な特性は、意思決定有用性である。すなわち会計情報には、投資家が企業の不確実な成果を予測するのに有用であることが期待されている。
2. 会計情報が投資家の意思決定に有用であることは、意思決定目的に関連する情報であること(relevance to decision)、内的な整合性のある会計基準に従って作成された情報であること(internal consistency)、および一定の水準で信頼できる情報であること(reliability)に支えられている。
〔有用性を支える特性(1):意思決定との関連性〕
3. このうち意思決定との関連性とは、会計情報が将来の投資の成果についての予測に関連する内容を含んでおり、企業価値の推定を通じた投資家による意思決定に積極的な影響を与えて貢献することを指す。
4. 会計情報が投資家の意思決定に貢献するか否かは、第一に、それが情報価値を有しているか否かと関わっている。ここでいう情報価値とは、投資家の予測や行動が当該情報の入手によって改善されることをいう。ただし、会計基準の設定局面において、新たな基準に基づく会計情報の情報価値は不確かな場合も多い(脚注1)。そのケースでは、投資家による情報ニーズ(information needs)の存在が、情報価値を期待させる。そのような期待に基づいて、情報価値の存否について事前に確たることがいえない場合であっても、投資家からの要求に応えるために会計基準の設定・改廃が行われることもある。この意味で、情報価値の存在と情報ニーズの充足は、意思決定との関連性を支える二つの特性と位置づけられる。
5. もっとも、情報開示のニーズがある会計情報のすべてが投資家の意思決定と関連しているとは限らない。投資家の意思決定に関連する情報はディスクロージャー制度以外の情報源からも投資家に提供されており、投資家の情報ニーズのすべてをディスクロージャー制度で応えるべきか否かは、慎重な検討を要する問題である。この点で、意思決定との関連性が基準設定で果たす役割には一定の限界がある。
〔有用性を支える特性(2):内的な整合性〕
6. 会計情報の有用性は、意思決定との関連性のほか、その情報を生み出す会計基準の内的な整合性にも支えられている。内的な整合性とは、個別の会計基準が、会計基準全体を支える基本的な考え方と矛盾しないことを指す。会計基準は、少数の基礎概念に支えられた一つの体系をなしている。その体系と矛盾しない基準に依拠した会計情報は、矛盾を抱えた基準に依拠した会計情報よりも有用なものとみなしうる。会計基準の現在の体系が実際に利用されて定着している事実は、その体系のもとで有用な情報が提供されてきたことの証拠とみなせるからである。特別な反証のないかぎり、その体系性を損なわない基準の設定・改廃が求められることとなる。
7. 内的な整合性は、環境条件が大きく変化していないかぎり、新たな経済事象や新たな形態の取引に関して会計基準を設定する際の判断規準として、とりわけ重要である。前提となる環境条件が一定であれば、既存の会計基準の体系と整合的な会計基準は有用な情報を生み出すという推定が働く。その状況では、関連する会計基準と矛盾が生じないように留意するだけでよい。このような形で進められる基準設定は、会計基準を決めるための具体的な手がかりがあらかじめ与えられていることから、会計情報の価値をそのつど推定しながら進める基準設定より効率的なものとなりうる(脚注2)。
8. 他方、財務報告を取り巻く環境が変化した場合には、旧来の環境条件に適合した会計基準との整合性を問うことの意味が失われる。内的な整合性に着目した基準設定が意味を持つのは、環境が変わらない状況下で、個別具体的な会計処理のありかたが追加的に問われる状況に限られる。それが変化した場合は、既存の体系に固執することなく、新たな環境に適合する会計基準の体系を模索することとなる。
〔有用性を支える特性(3):信頼性〕
9. 会計情報の有用性は、信頼性にも支えられている。信頼性とは、中立性・検証可能性・表現の忠実性などに支えられ、会計情報が信頼に足る情報であることを指す。
10.会計情報の作成者である経営者の利害は、投資家の利害と必ずしも一致していない。そのため、経営者の自己申告による情報を投資家が全面的に信頼するのは難しい。利害の不一致に起因する弊害を小さく抑えるためには、一部の関係者の利害だけを偏重することのない財務報告が求められる(中立性)。また、利益の測定では将来事象の見積もりが不可欠であるが、見積もりによる測定値は、誰が見積もるのかによって、大きなバラツキが生じることがある。このような利益情報には、ある種のノイズが含まれており、見積もりのみに基づく情報を投資家が完全に信頼するのは難しい。そのような事態を避けるには、測定者の主観には左右されない事実に基づく財務報告が求められる(検証可能性)。さらに企業が直面した事実を会計データの形で表現しようとする際、もともと多様な事実を少数の会計上の項目へと分類しなければならない。しかし、その分類規準に解釈の余地が残されている場合は、分類結果を信頼できない事態も起こりうる。このような事態を避けるため、事実と会計上の分類項目との明確な対応関係が求められる(表現の忠実性)。
〔特性間の関係〕
11.意思決定との関連性、内的な整合性、信頼性、これら三つの特性はすべてが同時に満たされることもあれば、いくつかの特性間にトレード・オフの関係がみられることもある。ある種の情報が、いずれかの特性を高める反面で、残りの特性を損なうケースもありうる。特性間にトレード・オフの関係がみられる場合は、すべての特性を考慮に入れたうえで、新たな基準のもとで期待される会計情報の有用性を総合的に判断することになる。
【結論の根拠と背景説明】
〔質的特性の意義〕
12.この討議資料のとりまとめに際しては、現在の基準設定のありかたを記述するのが目的なのか、それとも望ましい基準設定のありかたを論じ、将来の指針たりうる規範を示すのが目的なのかが議論された。この討議資料は基準設定の指針として機能することが期待されているため、ここでは単に事実を記述するのではなく、その機能を果たすための価値判断を含んだ記述を行うこととした。
〔内的な整合性〕
13.この討議資料と、海外の概念書との最大の違いは、会計情報の意思決定有用性を支える特性として、意思決定との関連性と信頼性に加え、内的な整合性をとりあげた点にある。整合的な基準から生み出された会計情報は有用であるとみるのが、広く合意された考え方だからである。新たな会計基準による情報の価値が事前にはわからない場合、整合性は情報価値を推定する補完的役割を果たすが、整合性に裏づけられた会計情報の有用性は、意思決定との関連性にいう情報価値の有無とは異なる意味でいわれることもある。こうしたことから、この討議資料では整合性に独立した地位を与えた。
14.新たな基準設定の際に整合性を問う対象として重要なのは、会計基準を支えている基本的な考え方である。内的な整合性の参照対象は、会計基準、会計実務、会計研究などについての歴史的経験と集積された知識の総体である。そのうち、会計基準の設定にとって重要な部分は、この討議資料で記述されているが、その全貌を示したものではない。それゆえ、この討議資料に準拠して会計基準を設定することは、内的な整合性の達成にとって必要条件であって、十分条件ではない。この討議資料には限界があることを十分に認識しなければならない。
15.米国や英国などの慣習法国家と異なり、日本の法秩序は、成文法の体系に支えられている。その環境条件のもとでは、基準設定に際し、会計基準の内的な整合性を尊重することが、秩序安定のためにとりわけ強く求められる。一般に成文法のもとでは、ルールの設定・改廃に際し、既存のルールとの関係を常に考慮しなければならない。しかしこうした事実について、これまで国際的な理解が十分には得られてこなかった。ここで整合性を重視する必要性や、整合性に着目する方法の限界を明らかにすることは、基準設定のありかたをめぐる国際的な相互理解の助けになると期待されている。
16.なお、この討議資料でいう内的な整合性は、いわゆる首尾一貫性(consistency)とは異なっている。後者は特定の会計手続が毎期継続的に(中間報告と決算報告とで同一の手続きが)適用されることを要請するものであるのに対し、前者は現行基準の体系と矛盾しない個別基準を採用するよう要請するものである。
〔特性間の関係〕
17.この討議資料のとりまとめに際しては、意思決定との関連性・内的な整合性・信頼性の三者を並列させるのか、それとも意思決定との関連性と内的な整合性を下位に置く新たな上位概念を想定し、その上位概念と信頼性とを並列させるべきなのかが論じられた。この討議資料では、内的な整合性に固有の意義を認めて、意思決定との関連性と内的な整合性とを並列させることにした。
18.また、信頼性は他の特性と並列の関係にあるのか、それとも、他の特性よりも上位の制約条件であるのかも議論された。信頼性が他の特性から独立し、かつ常に他の特性よりも優先されるなら、信頼性は上位の制約条件として機能することになる。しかし、信頼性は意思決定との関連性から完全に独立しているわけではない(脚注3)。また、最優先すべきは意思決定有用性であり、下位の三つの特性の間に優劣関係は見出せない。それゆえ、この討議資料においては、信頼性を他の特性と並列して位置づけた。
〔信頼性の下位概念〕
19.諸外国で信頼性の下位概念とされている中立性・検証可能性・表現の忠実性については、それらを改めて定義し直すべきか否かが議論の対象となった。それらのなかには、原義から離れた使われ方をしているものもあるという意見も出された。しかし、それらの用語はすでに会計実践で定着しており、それを変更すれば無用な混乱を招きかねない。それは、将来の基準設定に指針を提供するという討議資料の役割、および整合性を重視するという基本姿勢などに反する帰結であろう。そうした事態を避けるため、この討議資料では、それらの定義については、海外の先例を踏襲することとした。
〔一般的な制約条件〕
20.諸外国では一般的な制約条件などに位置づけられている比較可能性・理解可能性・重要性・コストとベネフィットの斟酌などについては、これらを会計情報の質的特性に含めるか否かが検討された。まず、質的特性を簡潔な体系として記述するという基本方針が確認され、自明なもの、他の特性と重複するもの、その意義について疑念が残るものなどは記述しないことにした。
21.比較可能性については、多くの時間が議論に費やされた。本来、表現の忠実性は「異なる事実には異なる会計処理を、同様の事実には同じ会計処理を」要請するものであって、異質な事実を一括りにして画一的な会計処理を要求し、経営者による裁量の余地を過度に狭めると、むしろ投資家にとっての意思決定有用性が損なわれかねないという議論がなされた。会計処理の画一的な統一に対する懸念が表明されたのである。また、表現の忠実性をそのように理解すると、比較可能性は表現の忠実性に包摂されてしまうのではないか、という議論もなされた。それらの議論を踏まえて、この討議資料では比較可能性を記述しないこととした。
22.理解可能性については、洗練された投資家を想定することと矛盾するのではないかという指摘や、人間の合理性には限界があるという意味なら自明であるとの指摘がなされた。さらに、この特性が将来の基準設定の指針としていかなる機能を果たすのか明らかではないという意見も出された。また、重要性、およびコストとベネフィットの勘酌についても、経済合理性の観点からすれば自明であるとの議論がなされた。それらの議論を踏まえて、この討議資料では、理解可能性・重要性・コストとベネフィットの斟酌を記述しないこととした。
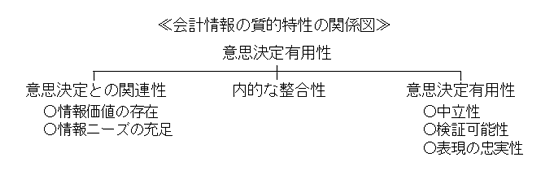
脚注
1 特定の情報が投資家の行動を改善するか否かについて、事前に確たることをいうのは難しい。投資家の意思決定モデルを特定するのが困難なうえ、予想される多様な結果を社会全体としてどのように評価したらよいのか、評価の尺度を特定するのも困難だからである。
2 内的な整合性を保つことは、会計基準の変化を予見できるようにする点でも優れている。例えば、新たな形態の取引の登場に応じて会計基準がどう変化するのかを予想できれば、情報の作成者や利用者はみずからの行動を少しずつ新しい環境に適合させていくことができるからである。
3 例えば信頼性についての議論のうち表現の忠実性に係る部分(第9項および第10項)で触れたように、事実を会計データにどう置き換えるのかは、会計情報の情報価値を左右する問題でもある。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















