解説記事2004年09月20日 【実務解説】 資本政策の実務 第2回 商法改正と資本政策(2004年9月20日号・№083)
実務解説
資本政策の実務
第2回 商法改正と資本政策
公認会計士 中嶋克久
公認会計士・税理士 棟田裕幸
1. はじめに
前回は、上場のための資本政策の基本的考え方を解説しましたが、実際の資本政策を検討するにあたっては、商法、証券取引法、税法等の法律、上場基準など制度面の様々な規制を考慮していかなければなりません。今回は、資本政策に関連する諸制度の内、商法規定に焦点をあて、平成13年~14年にかけて行われた商法改正で制度の枠組みが大きく変更された種類株式と新株予約権の2つの制度を解説していきます。
2. 種類株式
(1)種類株式とは
種類株式と言うと、商法第222条第1項に規定する数種の株式(優先株式等)を指すことが多いのですが、転換株式等も含めて、ここでは普通株式と異なる株主の権利を付与(又は制限)した株式を種類株式とみなして解説します。
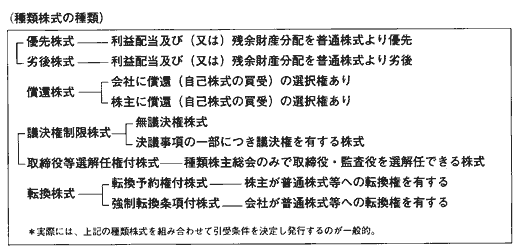
(2)上場準備会社に種類株式が活用されてこなかった理由
一連の商法改正により、種類株式の設計の自由度は高まり、種類株式が広く活用されることを期待されています。しかし、デット・エクイティ・スワップによる種類株式の発行など事業再生を図る会社に利用されるケースは増えてきているものの、上場準備会社での活用は最近になってベンチャー・キャピタル(VC)が利用し始めたのが実態です。
① 上場準備会社に発行事例が少ない理由
欧米のベンチャー・キャピタルは種類株式による投資が基本であるにもかかわらず、日本において種類株式の活用が少なかった理由は、「種類株式設計の多様化―ベンチャー企業におけ・る種類株式の活用―(上)(下)高橋達広著」(商事法務1702、1703)に詳しく説明されていますが、要は、ベンチャー企業に対して種類株式が実務的に使えるかものかどうかの見極めができていないことによるものと思われます。
高橋氏の分析は、商法上の実務面から詳述されていますが、税務の観点からの困難性も活用されていない理由かと思います。すなわち、税務上、非上場会社の普通株式の評価方法は、財産評価基本通達等によって詳しく規定されていますが、非上場会社の種類株式のそれは、何ら手懸りとなる規定がなく、発行価格によっては課税のおそれがあると危惧され発行に踏み切れないのです。
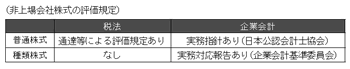
しかしながら、確立された評価方法がないから種類株式を活用しないのも、本末転倒の論議かと思います。確立された方法がなければ、個々に合理的と考える評価方法を考え、前向きに種類株式の活用を図ることが、商法改正の制度趣旨に沿うものと考えます。過去にも金融機能早期健全化法に基づき、預金保険機構(実際の株主は整理回収機構)が、非上場銀行の転換権付優先株式を引受けた例(新生銀行、あおぞら銀行等)や最近のVCの活用例があり、その活用は可能なはずです。なお、実際の活用にあたっては、金融工学を専門とするアドバイザー(証券会社等の専門家等)と種類株式の評価に関する議論を行い、種類株式の引受条件の商品性(適正性)に関する意見書を入手することが必要でしょう。
②上場準備会社の種類株式の評価方法
上場準備会社の種類株式の評価方法は、税務上、指針となる規定はありませんが、企業会計の取扱いとして「実務対応報告第十号 種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」(平成15年3月13日 企業会計基準委員会)が公表されています。
この実務対応報告は、市場価格のない種類株式の評価方法として、金融工学を利用した評価モデルによる評価方法を原則としていますが、評価モデルを利用できない場合の評価方法も示しています。
(市場価格のない種類株式の評価方法)
(ⅰ)評価モデルを利用する方法
(ⅱ)1株当たりの純資産額を基礎とする方法
(ⅲ)優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法
(ⅰ)評価モデルを利用する方法
評価モデルの利用が困難であると認められる場合を除き、将来割引キャッシュ・フロー法やオプション価格モデルなどを利用した評価モデルで評価します。優先株式については、将来割引キャッシュ・フロー法、転換株式については、オプション価格モデルで評価することになるでしょう。
(ⅱ)1株当たりの純資産額を基礎とする方法
利益配当請求権に関する普通株式との異同や転換を請求できる権利の条件等を考慮して、種類株式の普通株式相当数を算定することが可能な場合の評価方法です。
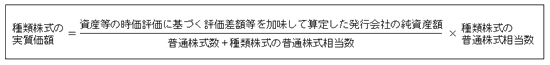
(ⅲ)優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法
普通株式よりも利益配当請求権及び残余財産分配請求権が優先的であるような場合には、優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法によって実質価額を算定することもできるとしています。
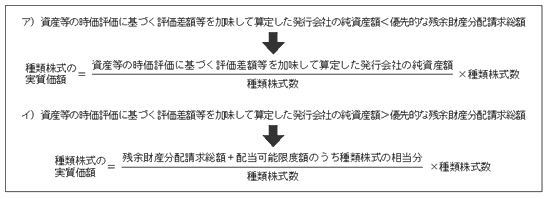
(ⅱ)1株当たりの純資産額を基礎とする方法は、転換株式の評価方法であり、(ⅲ)優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法は、優先株式の評価方法です。いずれも簡便的な評価方法ですが、このような評価方法も企業会計の取扱い方法の1つとして提示されています。
(3)上場のための資本政策で活用する種類株式
上場のための資本政策における種類株式の活用について論じられるのは、ベンチャー・キャピタルの投資の観点からがほとんどですが、ここでは、主にオーナー経営者等の既存株主の観点からみた活用方法を考えていきたいと思います。
① そもそも経営権の維持の本質をどう考えるべきか
オーナー経営者等にとって資本政策の最大の関心事は、経営権の維持にあり持株比率の維持をどのように図るかにあります。その方策としては、オーナーの持株数そのものを増やすことにありますが、株式を引き受ける資金に制約がある以上、限界があります。また、研究開発型のベンチャー企業などは、創業時から、ベンチャー・キャピタルによる多額の投資を受けて研究開発を行うことが多く、持株比率でシェアを確保することは無理な話です。
そこで、経営権の維持を図るということは、結局何を目指すことなのかを考えて、対策を考えることが重要です。経営権の維持とは、一般に株主総会における議決権行使を通じて、経営上の意思決定を自由にコントロールすることを考えている方が多いのではないかと思います。
② 株主総会の決議事項
それでは、株主総会で決議する事項とは何かを整理してみましょう。
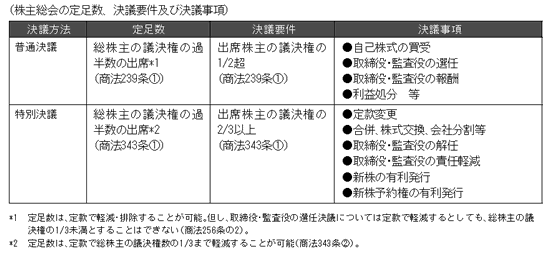
株主総会の決議事項は、次の4つに分類できます。
(ア)取締役・監査役などの選任・解任に関する事項
(イ)会社の基礎的事項に関する事項(定款変更、合併、株式交換、会社分割等)
(ウ)株主の重要な利益に関する事項(利益処分、新株の有利発行、新株予約権の有利発行等)
(エ)取締役にゆだねたのでは株主の利益が害されるおそれが高いと考えられる事項(取締役・監査役の報酬等)
③ オーナー経営者は総会決議事項の何にこだわるのか
(ウ)株主の重要な利益に関する事項や(エ)取締役にゆだねたのでは株主の利益が害されるおそれが高いと考えられる事項は、経営行為の意思決定に関する事項ではなく、株主の利益保護を目的にしたものであり、オーナー経営者がこれを自由にコントロールすべきでないことはご理解いただけるでしょう。中には創業以来、取締役である自身の報酬を自由にコントロールしてきたので、これらもコントロールしたいと思う方がいるかもしれませんが、そのような方は、資本政策を考える経営に移行したことを自覚し、株主の利益保護の重要性を再認識すべきでしょう。
また、(イ)会社の基礎的事項に関する事項は、経営戦略に関わる事項であり、オーナー経営者が自由にコントロールしたいと考えるかもしれません。このように考えること自体、その気持ちをわからないわけではありませんが、合併等の会社の基礎的事項は、株主の利益に大きな影響を及ぼす事項であり、株主総会の決議に判断をゆだねるべきです。経営者は、むしろ、株主の同意を得られるように提出議案の合理性についての説明に注力するものと考えるべきです。
最後に、(ア)取締役・監査役などの選任・解任に関する事項ですが、この事項については、オーナー経営者によるコントロールを認めて良いのではないかと思います。取締役の業務執行の是非で、大株主と取締役とが対立し、取締役が解任されることがあり得るからです。このようなことがあっては、オーナー経営者は、安心して経営に注力できなくなります。
このようなことを回避するにあたっては、平成14年商法改正で認められた取締役等選解任権付株式が有効な手段です。
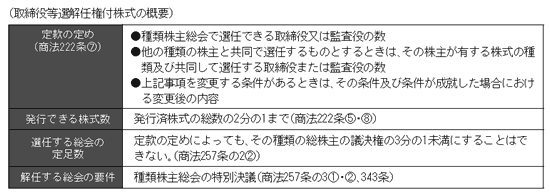
④ 取締役等選解任権付株式(商法222条①六)
株式譲渡制限会社に限って認められる取締役等選解任権付株式は、その種類の株主の総会(他の種類の株主と共同で開催することも可)において、取締役及び監査役を選解任することができる種類株式です。この種類の株式の発行数は発行済株式の総数の2分の1まで認められます。
⑤ その他の種類株式の活用
(ⅰ)優先株式(商法222条①一、二)
利益配当及び(又は)残余財産分配を普通株式より優先する株式ですが、VC等の投資目的で保有する株主が、資金回収のリスクを考慮して活用される可能性が高いと考えます。
(ⅱ)償還株式(買受株式)
会社が買受けを予定する株式を買受株式(商法222条①三)、配当可能利益による消却が予定されている株式を償還株式(同条①四)といいます。前者は、買受後、消却するか、保有し続けるかの選択を可能とするため償還株式と区別されますが、実質的な違いはないので、両者を含めて償還株式と呼ぶこともあります。
これは、投資回収のリスクから株主が償還を請求できる権利をもつ株式として発行する場合と、会社が将来の配当負担を軽減する目的で発行する場合の2つのパターンが考えられますが、上場準備会社の場合、VC等からの要求によって前者の株式を発行する可能性があると思います。
(ⅲ)議決権制限株式(商法222条①五)
敢えて、議決権を制限する株式を欲する投資家は、少ないので実際の活用はあまりないと思います。
但し、一部の決議事項(総会のみならず取締役会の決議事項も含む)を種類株主総会の決議事項とする株式(商法222条⑨、⑩)の活用は、オーナー経営者、VC等、いずれの立場からでも、その活用可能性はあると思います。すなわち、種類株主総会で否決しますと、普通株主等による総会の決議が無効となり拒否権をもった株式として機能します(次頁上図参照)。
(ⅳ)転換株式(商法222条の2①、222条の8)
種類株式を普通株式へ転換する株式として活用する可能性が高いと思います。新規上場にあたっては、普通株式に転換して市場売却することが要請されるからです。また、従来、新規上場に際して、発行する株式が単一銘柄(普通株式)であることを上場基準において定めていたこともあり(この基準は撤廃されましたが現状でも新生銀行を除いて単一銘柄で上場しています)、活用される可能性は高いと思います。
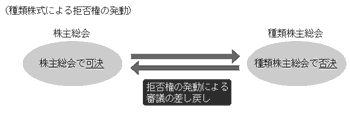
3. 新株予約権
(1)新株予約権、ストック・オプションとは
新株予約権は、平成14年4月施行商法改正により登場しました。新株予約権とは、権利者(新株予約権者)があらかじめ定められた期間(権利行使期間)にあらかじめ定められた価格(権利行使価格)を発行会社に払い込むと、発行会社から一定の新株の発行(又は自己株式の移転)を受けることのできる権利をいいます(商280の19①)。
新株予約権を取得した者は、この会社の株価が将来どんなに上昇してもあらかじめ定められた価額(権利行使価額)で株式を取得できる権利がありますが、逆にこの会社の株価が、権利行使価額よりも安くなった場合には、その権利を行使せず放棄してしまうでしょう。このように新株予約権は、株式取得に関する選択権(コール・オプション、すなわち買う権利)の性格を有しています。
改正商法は、このようなオプションとしての価値を有価証券として認知し、オプションの単独発行も認めました。
このように新株予約権は有価証券であるため、本来的には有償で発行されるものですが、単独で無償にて発行される(ストック・オプション)場合及び新株予約権付社債として発行される場合があります。まとめると以下のような発行形態となります。
① 新株予約権の単独発行
ⅰ 通常発行(有償取得)
ⅱ 有利発行(第三者割当の無償発行であるストック・オプションが典型例)
② 新株予約権付社債
ⅰ 新株予約権付社債(従来の転換社債、従来の非分離型新株引受権付社債)
ⅱ 新株予約権+社債(従来の分離型新株引受権付社債)
現状の実務における発行は、①単独発行においては、取締役、従業員等へのインセンティブプランとして、無償発行であるストック・オプション(上記①ii)を発行するケースが多く、②新株予約権付社債においては、代用払込型としての転換社債型新株予約権付社債(上記②i)として発行するケースが多いようです。
(2)ストック・オプション普及の制度的背景
繰り返しますが、ストック・オプションとは、新株予約権の単独発行のうち無償で発行するものです(商法280条の20及び280条の21)。
以前からインセンティブプランとしてのストック・オプションの必要性は高まってはいたものの、商法上ストック・オプションの制度がなく、そのため平成7年以降は、本来は資金調達手段であるはずの分離型新株引受権付社債を利用した擬似ストック・オプションが実務界では多く発行されていました。その後平成9年の商法改正により、商法上のストック・オプションとしての自己株式譲渡方式のストック・オプション及び新株引受権付与方式のストック・オプションの制度が導入されましたが、これらは、様々な制約があることから、実務界では依然として制約の少ない擬似ストック・オプションが多く発行されていました。以上のことから、ストック・オプション制度をより活用しやすく、実効性のあるものにすべく要請から、平成14年4月施行商法改正により以下のものに変容・進化しました。
① 付与可能な株式制限数を撤廃
従来の発行株式総数の1/10を超えない範囲としていた付与株式数の制限を撤廃。
② 権利行使可能期間の制限の撤廃
権利行使可能期間を株主総会付与決議日から10年以内としていた制限を撤廃。
③ 付与対象者の制限を撤廃
付与対象者を、会社の取締役・使用人に限定していた制限を撤廃。これにより、付与対象者は、監査役、パートタイマー、他社からの出向社員、派遣社員、外部コンサルタント、弁護士、税理士、公認会計士、取引先、子会社・関連会社の取締役等へとその付与が可能となりました。
④ 付与対象者の氏名、付与決議の種類・数等についての株主総会決議が不要
なお、これらの株主総会決議は不要ですが、ストック・オプションの付与自体は、新株予約権の有利発行のため、株主総会の特別決議が必要です。
⑤ 権利行使時に引渡す株式の選択が自由
新株引受権が行使されたときに新株予約権者に渡す株式を、新株を発行するか、金庫株を渡すかをあらかじめ決めずに、権利行使時に会社が選択できるようになりました。
(3)新株予約権の発行手続
新株予約権の発行は、取締役会決議で行なえることとなりましたが、有利発行の場合(ストック・オプションの発行は有利発行に該当する)は、株主総会の特別決議を必要とします。新株予約権の商法上の発行手続フローをまとめると次頁のようになります。
次頁は新株予約権の単独発行の手続ですが、新株予約権付社債の発行手続も商法上ほとんど同様です。新株予約権の有利発行には、次頁の通り株主総会の特別決議が必要ですが、この特別決議は、決議の日から1年内に発行価額の払込み(無償発行の場合は発行)をすべき新株予約権についてのみ効力を有します(商法280条の21②、280条の27②)。
(4)新株予約権の証券取引法規制
証券取引法上、新株予約権は有価証券と定義されています(証取法2条①六)。したがって、証券取引法の有価証券届出書等の届出義務の対象となりますので注意が必要です。
しかし、新株予約権をストック・オプションとして発行した場合には、届出義務の対象とならない特例が設けられています(証取例1の4③・1の8②、開示ガイドライン2-2)。この特例対象となるためには、以下の条件を満たす必要があり、これを満たした場合には50名の人数基準において、該当者を人数に含めないことができます。
① その譲渡につき取締役会の承認を要すること。
② その付与対象者が、発行会社及び当該発行会社が日本国内に設立した100%子会社の取締役、執行役、監査役または使用人のみに限定していること。
③ 非公開会社の場合は、付与の直前期の商法施行規則により作成した計算書類を使用人に書類又は電磁的方法により交付すること。
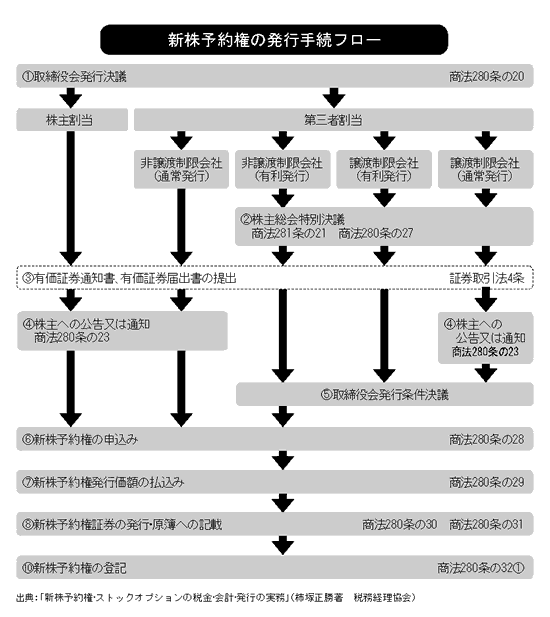
(5)上場のための資本政策で活用する新株予約権
新株予約権のうち現状の実務で多く発行されているのは、前述の通り、その無償発行であるストック・オプション並びに転換社債型新株予約権付社債ですが、株式上場のための資本政策においては、インセンティブプランとして、また、持株比率の調整のために新株予約権の単独発行(とりわけストック・オプション)が活用されることが多いため、以下これについて検討します。
株式上場を視野に入れて、取引先やベンチャーキャピタル等からの資本参加は受けたいが、社長・役員等の一定の持株比率の確保が必要な場合、安定株主である社長、役員等に上場前の早い段階で新株予約権を発行しておくと資本参加後の持株比率の低下を防ぐことができます。例えば上記の例のように、ベンチャーキャピタルによる第三者割当増資の引受けがあり、その後に従前の社長、役員等の持株比率が大きく低下する場合、これを活用できます(上表参照)。
この例からも明らかなように、新株予約権を株価が低い(5万円)うちに発行しておくと、その後ベンチャーキャピタル等の資本参加により、社長等安定株主の持株比率が低くなっても、その後の株価上昇(20万円)にも影響されない低い価格での権利行使価格により株式取得ができ、安定株主比率を幾分かでも復活させることができます。
なおここで注意を要するのは、株式上場時に未行使残を多く残さないことです。それは、平成13年9月4日以降、潜在株は権利未行使のまま株式上場できるようにはなったものの、株式上場審査上は多数の潜在株の存在は、その後の株式の希薄化をもたらし、投資家保護の観点から問題視されるからです。最近は潜在株を残したままの上場例は増えてはきたものの、発行済株式数の10%程度以内の例が大半であり、やはりこの程度にしておくことが望ましいといえましょう。
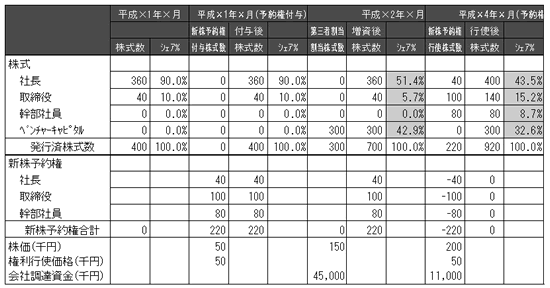
(6)新株予約権の評価
株式上場の資本政策では、取締役や従業員にインセンティブとして、無償で新株予約権をいわゆるストック・オプションとして発行するケースが多く見られます。しかし、新株予約権を単独発行の有償で発行することも考えられます。
とりわけ、有償発行の新株予約権を時価で取得すると、その権利行使時における株式時価と権利行使価額との差額部分の課税が生じません(これについては次回に説明します)。
それではその評価はいかに行うのでしょうか。新株予約権の公正な発行価額を評価する方法には、オプションの経済的価値を評価するモデルとしての、「ブラック=ショールズ・モデル」や「2項モデル」があります。これらモデルは①評価時点の株価、②権利行使価額、③権利行使期間、④株価のボラティリティ(変動率)、⑤無リスクレート等のパラメーターにより算定します。上場株式ならばその算定はできますが、未上場会社の場合、とりわけ上記④の株価変動率を算出できないことに限界があり、算定は極めて困難と考えられます。それでもあえて算定するならば、当該会社と類似する上場会社のボラティリティを参考にして算定することも考えられますが、そもそもボラティリティのない会社に無理にこれを持ち込むことがよいのかという問題もあるかと思われます。
未上場会社においては、かかる算定上の限界から、あまりその評価が浸透していないのが現状のようです。しかし今後、未上場会社における有用かつ妥当な評価方法が登場し認知されれば、新株予約権の有償発行も広く浸透することになりましょう。
中嶋克久(なかしまかつひさ)
公認会計士
85年青山監査法人(現中央青山監査法人)入所。ジャフコ及び預金保険機構の出向を経て2004年7月に監査法人を退職。現在公認会計士中嶋事務所所長、(株)日本資本政策研究所代表取締役。
棟田裕幸(むねたひろゆき)
公認会計士・税理士
青山監査法人(現中央青山監査法人)、三優監査法人社員を経て、現在棟田公認会計士事務所所長、赤坂マネジメント・コンサルタント代表取締役。日本公認会計士協会東京会税務委員会副委員長 http://www2.odn.ne.jp/amc
資本政策の実務
第2回 商法改正と資本政策
公認会計士 中嶋克久
公認会計士・税理士 棟田裕幸
1. はじめに
前回は、上場のための資本政策の基本的考え方を解説しましたが、実際の資本政策を検討するにあたっては、商法、証券取引法、税法等の法律、上場基準など制度面の様々な規制を考慮していかなければなりません。今回は、資本政策に関連する諸制度の内、商法規定に焦点をあて、平成13年~14年にかけて行われた商法改正で制度の枠組みが大きく変更された種類株式と新株予約権の2つの制度を解説していきます。
2. 種類株式
(1)種類株式とは
種類株式と言うと、商法第222条第1項に規定する数種の株式(優先株式等)を指すことが多いのですが、転換株式等も含めて、ここでは普通株式と異なる株主の権利を付与(又は制限)した株式を種類株式とみなして解説します。
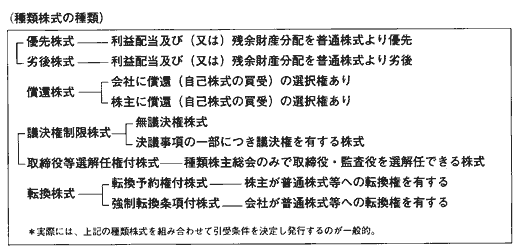
(2)上場準備会社に種類株式が活用されてこなかった理由
一連の商法改正により、種類株式の設計の自由度は高まり、種類株式が広く活用されることを期待されています。しかし、デット・エクイティ・スワップによる種類株式の発行など事業再生を図る会社に利用されるケースは増えてきているものの、上場準備会社での活用は最近になってベンチャー・キャピタル(VC)が利用し始めたのが実態です。
① 上場準備会社に発行事例が少ない理由
欧米のベンチャー・キャピタルは種類株式による投資が基本であるにもかかわらず、日本において種類株式の活用が少なかった理由は、「種類株式設計の多様化―ベンチャー企業におけ・る種類株式の活用―(上)(下)高橋達広著」(商事法務1702、1703)に詳しく説明されていますが、要は、ベンチャー企業に対して種類株式が実務的に使えるかものかどうかの見極めができていないことによるものと思われます。
高橋氏の分析は、商法上の実務面から詳述されていますが、税務の観点からの困難性も活用されていない理由かと思います。すなわち、税務上、非上場会社の普通株式の評価方法は、財産評価基本通達等によって詳しく規定されていますが、非上場会社の種類株式のそれは、何ら手懸りとなる規定がなく、発行価格によっては課税のおそれがあると危惧され発行に踏み切れないのです。
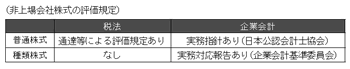
しかしながら、確立された評価方法がないから種類株式を活用しないのも、本末転倒の論議かと思います。確立された方法がなければ、個々に合理的と考える評価方法を考え、前向きに種類株式の活用を図ることが、商法改正の制度趣旨に沿うものと考えます。過去にも金融機能早期健全化法に基づき、預金保険機構(実際の株主は整理回収機構)が、非上場銀行の転換権付優先株式を引受けた例(新生銀行、あおぞら銀行等)や最近のVCの活用例があり、その活用は可能なはずです。なお、実際の活用にあたっては、金融工学を専門とするアドバイザー(証券会社等の専門家等)と種類株式の評価に関する議論を行い、種類株式の引受条件の商品性(適正性)に関する意見書を入手することが必要でしょう。
②上場準備会社の種類株式の評価方法
上場準備会社の種類株式の評価方法は、税務上、指針となる規定はありませんが、企業会計の取扱いとして「実務対応報告第十号 種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」(平成15年3月13日 企業会計基準委員会)が公表されています。
この実務対応報告は、市場価格のない種類株式の評価方法として、金融工学を利用した評価モデルによる評価方法を原則としていますが、評価モデルを利用できない場合の評価方法も示しています。
(市場価格のない種類株式の評価方法)
(ⅰ)評価モデルを利用する方法
(ⅱ)1株当たりの純資産額を基礎とする方法
(ⅲ)優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法
(ⅰ)評価モデルを利用する方法
評価モデルの利用が困難であると認められる場合を除き、将来割引キャッシュ・フロー法やオプション価格モデルなどを利用した評価モデルで評価します。優先株式については、将来割引キャッシュ・フロー法、転換株式については、オプション価格モデルで評価することになるでしょう。
(ⅱ)1株当たりの純資産額を基礎とする方法
利益配当請求権に関する普通株式との異同や転換を請求できる権利の条件等を考慮して、種類株式の普通株式相当数を算定することが可能な場合の評価方法です。
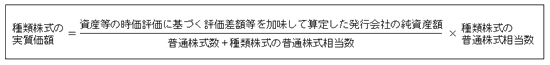
(ⅲ)優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法
普通株式よりも利益配当請求権及び残余財産分配請求権が優先的であるような場合には、優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法によって実質価額を算定することもできるとしています。
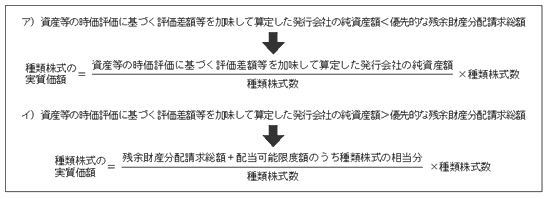
(ⅱ)1株当たりの純資産額を基礎とする方法は、転換株式の評価方法であり、(ⅲ)優先的な残余財産分配請求額を基礎とする方法は、優先株式の評価方法です。いずれも簡便的な評価方法ですが、このような評価方法も企業会計の取扱い方法の1つとして提示されています。
(3)上場のための資本政策で活用する種類株式
上場のための資本政策における種類株式の活用について論じられるのは、ベンチャー・キャピタルの投資の観点からがほとんどですが、ここでは、主にオーナー経営者等の既存株主の観点からみた活用方法を考えていきたいと思います。
① そもそも経営権の維持の本質をどう考えるべきか
オーナー経営者等にとって資本政策の最大の関心事は、経営権の維持にあり持株比率の維持をどのように図るかにあります。その方策としては、オーナーの持株数そのものを増やすことにありますが、株式を引き受ける資金に制約がある以上、限界があります。また、研究開発型のベンチャー企業などは、創業時から、ベンチャー・キャピタルによる多額の投資を受けて研究開発を行うことが多く、持株比率でシェアを確保することは無理な話です。
そこで、経営権の維持を図るということは、結局何を目指すことなのかを考えて、対策を考えることが重要です。経営権の維持とは、一般に株主総会における議決権行使を通じて、経営上の意思決定を自由にコントロールすることを考えている方が多いのではないかと思います。
② 株主総会の決議事項
それでは、株主総会で決議する事項とは何かを整理してみましょう。
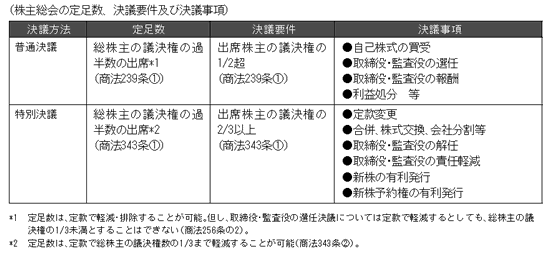
株主総会の決議事項は、次の4つに分類できます。
(ア)取締役・監査役などの選任・解任に関する事項
(イ)会社の基礎的事項に関する事項(定款変更、合併、株式交換、会社分割等)
(ウ)株主の重要な利益に関する事項(利益処分、新株の有利発行、新株予約権の有利発行等)
(エ)取締役にゆだねたのでは株主の利益が害されるおそれが高いと考えられる事項(取締役・監査役の報酬等)
③ オーナー経営者は総会決議事項の何にこだわるのか
(ウ)株主の重要な利益に関する事項や(エ)取締役にゆだねたのでは株主の利益が害されるおそれが高いと考えられる事項は、経営行為の意思決定に関する事項ではなく、株主の利益保護を目的にしたものであり、オーナー経営者がこれを自由にコントロールすべきでないことはご理解いただけるでしょう。中には創業以来、取締役である自身の報酬を自由にコントロールしてきたので、これらもコントロールしたいと思う方がいるかもしれませんが、そのような方は、資本政策を考える経営に移行したことを自覚し、株主の利益保護の重要性を再認識すべきでしょう。
また、(イ)会社の基礎的事項に関する事項は、経営戦略に関わる事項であり、オーナー経営者が自由にコントロールしたいと考えるかもしれません。このように考えること自体、その気持ちをわからないわけではありませんが、合併等の会社の基礎的事項は、株主の利益に大きな影響を及ぼす事項であり、株主総会の決議に判断をゆだねるべきです。経営者は、むしろ、株主の同意を得られるように提出議案の合理性についての説明に注力するものと考えるべきです。
最後に、(ア)取締役・監査役などの選任・解任に関する事項ですが、この事項については、オーナー経営者によるコントロールを認めて良いのではないかと思います。取締役の業務執行の是非で、大株主と取締役とが対立し、取締役が解任されることがあり得るからです。このようなことがあっては、オーナー経営者は、安心して経営に注力できなくなります。
このようなことを回避するにあたっては、平成14年商法改正で認められた取締役等選解任権付株式が有効な手段です。
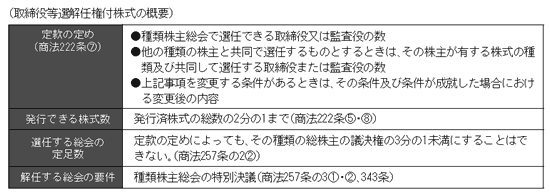
④ 取締役等選解任権付株式(商法222条①六)
株式譲渡制限会社に限って認められる取締役等選解任権付株式は、その種類の株主の総会(他の種類の株主と共同で開催することも可)において、取締役及び監査役を選解任することができる種類株式です。この種類の株式の発行数は発行済株式の総数の2分の1まで認められます。
⑤ その他の種類株式の活用
(ⅰ)優先株式(商法222条①一、二)
利益配当及び(又は)残余財産分配を普通株式より優先する株式ですが、VC等の投資目的で保有する株主が、資金回収のリスクを考慮して活用される可能性が高いと考えます。
(ⅱ)償還株式(買受株式)
会社が買受けを予定する株式を買受株式(商法222条①三)、配当可能利益による消却が予定されている株式を償還株式(同条①四)といいます。前者は、買受後、消却するか、保有し続けるかの選択を可能とするため償還株式と区別されますが、実質的な違いはないので、両者を含めて償還株式と呼ぶこともあります。
これは、投資回収のリスクから株主が償還を請求できる権利をもつ株式として発行する場合と、会社が将来の配当負担を軽減する目的で発行する場合の2つのパターンが考えられますが、上場準備会社の場合、VC等からの要求によって前者の株式を発行する可能性があると思います。
(ⅲ)議決権制限株式(商法222条①五)
敢えて、議決権を制限する株式を欲する投資家は、少ないので実際の活用はあまりないと思います。
但し、一部の決議事項(総会のみならず取締役会の決議事項も含む)を種類株主総会の決議事項とする株式(商法222条⑨、⑩)の活用は、オーナー経営者、VC等、いずれの立場からでも、その活用可能性はあると思います。すなわち、種類株主総会で否決しますと、普通株主等による総会の決議が無効となり拒否権をもった株式として機能します(次頁上図参照)。
(ⅳ)転換株式(商法222条の2①、222条の8)
種類株式を普通株式へ転換する株式として活用する可能性が高いと思います。新規上場にあたっては、普通株式に転換して市場売却することが要請されるからです。また、従来、新規上場に際して、発行する株式が単一銘柄(普通株式)であることを上場基準において定めていたこともあり(この基準は撤廃されましたが現状でも新生銀行を除いて単一銘柄で上場しています)、活用される可能性は高いと思います。
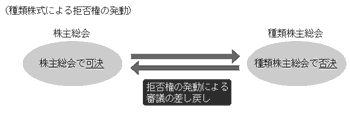
3. 新株予約権
(1)新株予約権、ストック・オプションとは
新株予約権は、平成14年4月施行商法改正により登場しました。新株予約権とは、権利者(新株予約権者)があらかじめ定められた期間(権利行使期間)にあらかじめ定められた価格(権利行使価格)を発行会社に払い込むと、発行会社から一定の新株の発行(又は自己株式の移転)を受けることのできる権利をいいます(商280の19①)。
新株予約権を取得した者は、この会社の株価が将来どんなに上昇してもあらかじめ定められた価額(権利行使価額)で株式を取得できる権利がありますが、逆にこの会社の株価が、権利行使価額よりも安くなった場合には、その権利を行使せず放棄してしまうでしょう。このように新株予約権は、株式取得に関する選択権(コール・オプション、すなわち買う権利)の性格を有しています。
改正商法は、このようなオプションとしての価値を有価証券として認知し、オプションの単独発行も認めました。
このように新株予約権は有価証券であるため、本来的には有償で発行されるものですが、単独で無償にて発行される(ストック・オプション)場合及び新株予約権付社債として発行される場合があります。まとめると以下のような発行形態となります。
① 新株予約権の単独発行
ⅰ 通常発行(有償取得)
ⅱ 有利発行(第三者割当の無償発行であるストック・オプションが典型例)
② 新株予約権付社債
ⅰ 新株予約権付社債(従来の転換社債、従来の非分離型新株引受権付社債)
ⅱ 新株予約権+社債(従来の分離型新株引受権付社債)
現状の実務における発行は、①単独発行においては、取締役、従業員等へのインセンティブプランとして、無償発行であるストック・オプション(上記①ii)を発行するケースが多く、②新株予約権付社債においては、代用払込型としての転換社債型新株予約権付社債(上記②i)として発行するケースが多いようです。
(2)ストック・オプション普及の制度的背景
繰り返しますが、ストック・オプションとは、新株予約権の単独発行のうち無償で発行するものです(商法280条の20及び280条の21)。
以前からインセンティブプランとしてのストック・オプションの必要性は高まってはいたものの、商法上ストック・オプションの制度がなく、そのため平成7年以降は、本来は資金調達手段であるはずの分離型新株引受権付社債を利用した擬似ストック・オプションが実務界では多く発行されていました。その後平成9年の商法改正により、商法上のストック・オプションとしての自己株式譲渡方式のストック・オプション及び新株引受権付与方式のストック・オプションの制度が導入されましたが、これらは、様々な制約があることから、実務界では依然として制約の少ない擬似ストック・オプションが多く発行されていました。以上のことから、ストック・オプション制度をより活用しやすく、実効性のあるものにすべく要請から、平成14年4月施行商法改正により以下のものに変容・進化しました。
① 付与可能な株式制限数を撤廃
従来の発行株式総数の1/10を超えない範囲としていた付与株式数の制限を撤廃。
② 権利行使可能期間の制限の撤廃
権利行使可能期間を株主総会付与決議日から10年以内としていた制限を撤廃。
③ 付与対象者の制限を撤廃
付与対象者を、会社の取締役・使用人に限定していた制限を撤廃。これにより、付与対象者は、監査役、パートタイマー、他社からの出向社員、派遣社員、外部コンサルタント、弁護士、税理士、公認会計士、取引先、子会社・関連会社の取締役等へとその付与が可能となりました。
④ 付与対象者の氏名、付与決議の種類・数等についての株主総会決議が不要
なお、これらの株主総会決議は不要ですが、ストック・オプションの付与自体は、新株予約権の有利発行のため、株主総会の特別決議が必要です。
⑤ 権利行使時に引渡す株式の選択が自由
新株引受権が行使されたときに新株予約権者に渡す株式を、新株を発行するか、金庫株を渡すかをあらかじめ決めずに、権利行使時に会社が選択できるようになりました。
(3)新株予約権の発行手続
新株予約権の発行は、取締役会決議で行なえることとなりましたが、有利発行の場合(ストック・オプションの発行は有利発行に該当する)は、株主総会の特別決議を必要とします。新株予約権の商法上の発行手続フローをまとめると次頁のようになります。
次頁は新株予約権の単独発行の手続ですが、新株予約権付社債の発行手続も商法上ほとんど同様です。新株予約権の有利発行には、次頁の通り株主総会の特別決議が必要ですが、この特別決議は、決議の日から1年内に発行価額の払込み(無償発行の場合は発行)をすべき新株予約権についてのみ効力を有します(商法280条の21②、280条の27②)。
(4)新株予約権の証券取引法規制
証券取引法上、新株予約権は有価証券と定義されています(証取法2条①六)。したがって、証券取引法の有価証券届出書等の届出義務の対象となりますので注意が必要です。
しかし、新株予約権をストック・オプションとして発行した場合には、届出義務の対象とならない特例が設けられています(証取例1の4③・1の8②、開示ガイドライン2-2)。この特例対象となるためには、以下の条件を満たす必要があり、これを満たした場合には50名の人数基準において、該当者を人数に含めないことができます。
① その譲渡につき取締役会の承認を要すること。
② その付与対象者が、発行会社及び当該発行会社が日本国内に設立した100%子会社の取締役、執行役、監査役または使用人のみに限定していること。
③ 非公開会社の場合は、付与の直前期の商法施行規則により作成した計算書類を使用人に書類又は電磁的方法により交付すること。
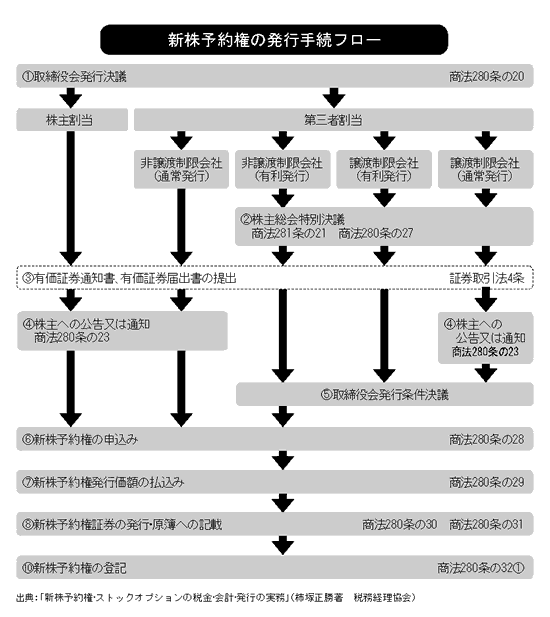
(5)上場のための資本政策で活用する新株予約権
新株予約権のうち現状の実務で多く発行されているのは、前述の通り、その無償発行であるストック・オプション並びに転換社債型新株予約権付社債ですが、株式上場のための資本政策においては、インセンティブプランとして、また、持株比率の調整のために新株予約権の単独発行(とりわけストック・オプション)が活用されることが多いため、以下これについて検討します。
株式上場を視野に入れて、取引先やベンチャーキャピタル等からの資本参加は受けたいが、社長・役員等の一定の持株比率の確保が必要な場合、安定株主である社長、役員等に上場前の早い段階で新株予約権を発行しておくと資本参加後の持株比率の低下を防ぐことができます。例えば上記の例のように、ベンチャーキャピタルによる第三者割当増資の引受けがあり、その後に従前の社長、役員等の持株比率が大きく低下する場合、これを活用できます(上表参照)。
この例からも明らかなように、新株予約権を株価が低い(5万円)うちに発行しておくと、その後ベンチャーキャピタル等の資本参加により、社長等安定株主の持株比率が低くなっても、その後の株価上昇(20万円)にも影響されない低い価格での権利行使価格により株式取得ができ、安定株主比率を幾分かでも復活させることができます。
なおここで注意を要するのは、株式上場時に未行使残を多く残さないことです。それは、平成13年9月4日以降、潜在株は権利未行使のまま株式上場できるようにはなったものの、株式上場審査上は多数の潜在株の存在は、その後の株式の希薄化をもたらし、投資家保護の観点から問題視されるからです。最近は潜在株を残したままの上場例は増えてはきたものの、発行済株式数の10%程度以内の例が大半であり、やはりこの程度にしておくことが望ましいといえましょう。
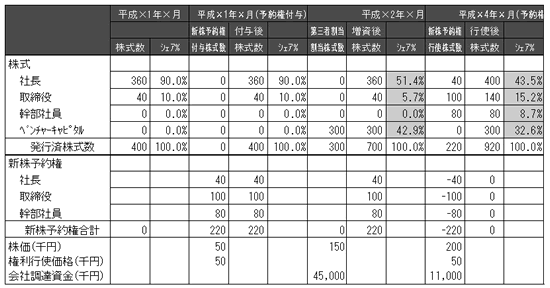
(6)新株予約権の評価
株式上場の資本政策では、取締役や従業員にインセンティブとして、無償で新株予約権をいわゆるストック・オプションとして発行するケースが多く見られます。しかし、新株予約権を単独発行の有償で発行することも考えられます。
とりわけ、有償発行の新株予約権を時価で取得すると、その権利行使時における株式時価と権利行使価額との差額部分の課税が生じません(これについては次回に説明します)。
それではその評価はいかに行うのでしょうか。新株予約権の公正な発行価額を評価する方法には、オプションの経済的価値を評価するモデルとしての、「ブラック=ショールズ・モデル」や「2項モデル」があります。これらモデルは①評価時点の株価、②権利行使価額、③権利行使期間、④株価のボラティリティ(変動率)、⑤無リスクレート等のパラメーターにより算定します。上場株式ならばその算定はできますが、未上場会社の場合、とりわけ上記④の株価変動率を算出できないことに限界があり、算定は極めて困難と考えられます。それでもあえて算定するならば、当該会社と類似する上場会社のボラティリティを参考にして算定することも考えられますが、そもそもボラティリティのない会社に無理にこれを持ち込むことがよいのかという問題もあるかと思われます。
未上場会社においては、かかる算定上の限界から、あまりその評価が浸透していないのが現状のようです。しかし今後、未上場会社における有用かつ妥当な評価方法が登場し認知されれば、新株予約権の有償発行も広く浸透することになりましょう。
中嶋克久(なかしまかつひさ)
公認会計士
85年青山監査法人(現中央青山監査法人)入所。ジャフコ及び預金保険機構の出向を経て2004年7月に監査法人を退職。現在公認会計士中嶋事務所所長、(株)日本資本政策研究所代表取締役。
棟田裕幸(むねたひろゆき)
公認会計士・税理士
青山監査法人(現中央青山監査法人)、三優監査法人社員を経て、現在棟田公認会計士事務所所長、赤坂マネジメント・コンサルタント代表取締役。日本公認会計士協会東京会税務委員会副委員長 http://www2.odn.ne.jp/amc
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















