解説記事2004年10月04日 【実務解説】 資本政策の実務 第4回 資本政策の作成手順と事例(2004年10月4日号・№085)
実 務 解 説
資本政策の実務
第4回 資本政策の作成手順と事例
公認会計士 中嶋克久
公認会計士・税理士 棟田裕幸
1. はじめに
資本政策の実務の最終回として、本稿では資本政策のシミュレーションの仕方について、具体例を見ながら考えていきたいと思います。第1回目では、上場のための資本政策の策定ステップについても解説しましたが、今回は、これを踏まえつつ実際の策定上の留意事項を確認していきます。
2. 資本策定の策定上の準備事項と留意事項
(1)資本政策の策定上の準備事項
資本政策の策定にあたっては、まず、第1に自社の現状について確認します。確認事項は、発行済株式数、新株予約権の残高及び保有構成、株主構成、直近の決算などです。
第2に、上場申請年度までの事業計画です。事業計画は、必要とする資金調達額の把握と上場までの新株の発行価額の見積もりの基礎として利用します。第3に、上場時の条件を想定することです。具体的には上場時の目標項目を設定することであり、第1回目で解説した項目を想定します。すなわち、①上場時の資金調達額、②安定株主対策を考慮した株主構成を大目標とします。また、上場後一定の出来高を確保することによって株価を安定させるため、③株式の流動性を確保するための発行済株式数の水準と市場に放出する株式数を設定することも重要な項目となります。その他に、必須項目ではありませんが、④役員、従業員に付与するストック・オプション等のインセンティブ・プランがあります。また、社歴の長い中堅企業の上場にあっては、⑤オーナーの創業者利潤の確保と事業承継も目標項目になります。
上場時の株主構成については、現状の株主構成からスタートすると、必要とする資金調達額に応じてオーナー経営者の持株比率が低下することから、安定株主対策の観点から誰に割り当てるかを見込んで設定します。これらの検討は、大雑把なシミュレーションによって、ゴールとしての上場時の株主構成を見込んでいきます。
(資本政策の策定にあたって準備する事項)
●現状の把握 発行済株式数、新株予約権の残高及び保有構成、株主構成、直近の決算等
●事業計画 損益計画、資金調達計画等
●上場時の目標項目
必須事項:
①上場時の資金調達額
②安定株主対策を考慮した株主構成
③発行済株式数の水準・市場に放出する株式数の設定
任意事項:
④ストック・オプション等のインセンティブ・プラン
⑤オーナーの創業者利潤の確保と事業承継
(2)資本政策の策定上の留意事項
上場のための資本政策を策定するにあたっては、上場規則によって第三者割当増資等に一定の規制を受けます。また、証券取引法等の規制にも準拠していかなければなりません。以下では、これらの主な留意事項を説明していきます。
①上場前の第三者割当等による新株発行等の規制
上場前の新株発行の割当を受けた者が、短期間に利益を得ることを防止するため、上場規則によって一定の制限を受けます。具体的には、上場申請日の直前事業年度の1年前の日以後に第三者割当増資を受けた者は、上場日以後6ヶ月間を経過する日又は新株発行日から1年間経過する日のいずれか遅い日まで継続所有しなければなりません。したがって、上場申請日の直前事業年度の1年前の日以後に発行した株式については、上場時の売り出しの対象とすることはできません。
②上場前の第三者割当等による新株予約権等の規制
①の上場前の第三者割当等による新株発行等の規制と同様の規制が、新株予約権及び新株予約権付社債についてもあります。すなわち、上場申請日の直前事業年度の1年前の日以後に新株予約権又は新株予約権付社債の割当を受けた者は、上場日以後6ヶ月間を経過する日又は新株発行日から1年間経過する日のいずれか遅い日まで継続所有しなければなりません。なお、新株予約権の権利行使をした場合は、当該株式について引き続き継続所有しなければなりませんが、継続所有期間に変更はありません。
なお、下記の③ストック・オプションに該当する新株予約権は、上記と異なる取扱いとなります。
③ストック・オプションとしての新株予約権の規制
ストック・オプションとしての新株予約権とは、申請会社(子会社を含む)の役員(取締役・監査役・執行役)又は従業員等に報酬として発行した新株予約権(上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後に発行されたものに限定)であって、次の(i)及び(ii)を満たす新株予約権をいいます。
(i)申請会社が新株予約権の発行によってその新株予約権証券を役員又は従業員等に取得させていること。
(ii)(i)の新株予約権証券について、申請会社と当該役員及び従業員等との間で、書面により当該新株予約権の継続所有等、証券取引所等が必要と認める事項等の確約を行っていること。
このストック・オプションの継続所有期間は発行日から上場日の前日までとなります。
また、権利行使時の課税が繰り延べられる税制適格ストック・オプションは、付与決議から2年を経過する日まで行使できないことにも留意する必要があります。
④ 証券取引法上の規制
証券取引法上、一定の要件に該当する場合には、「有価証券届出書」の提出義務が生じます。この「有価証券届出書」は、上場申請時に提出するものと同じものであり、相当の手数を要し、2年間の会計監査も必要とされます。この届出書の提出義務が生じることを考慮せずに新株発行すると証券取引法違反となりますので、この提出義務に抵触しない範囲で上場前の新株発行を行うのが一般的です。なお、提出義務が生じる場合とは、証券取引法上の募集(50名以上)に該当し、かつ、発行価額の総額が1億円以上となる場合等です。なお、募集に該当するかどうかの判定には、「6ヶ月間人数通算」ルールや「2年間金額通算」ルールがあるなど、複雑な規定となっていますので、割当人数が多くなる場合等の新株発行を行う場合には、弁護士等の専門家と慎重に相談することが必要です。
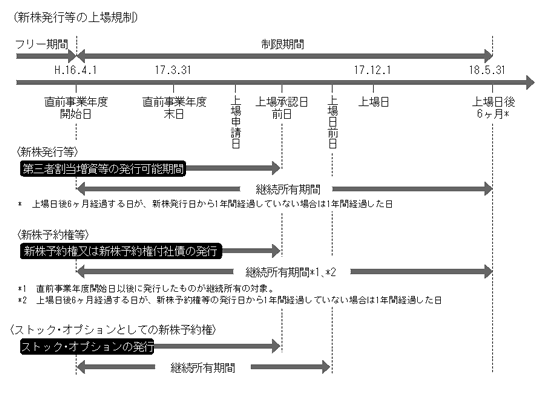
3. 資本政策シミュレーション例
(1)事例1: 種類株式を活用した研究開発型ベンチャーの事例
このシミュレーションでは、以下の①の前提条件に基づいて資本政策を検討するものとし、検討プロセスを②に示します。その上で、資本政策案を③で解説していきます。
①前提条件
(i)現 状
発行済株式数:1,000株、株主構成:社長500株、役員500株
新株予約権の残高:なし
直近の決算:B/S 資本金50,000千円、純資産50,000千円
P/L 当期純利益0円
(ii)事業計画
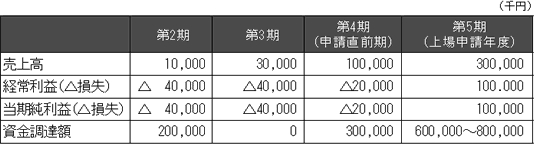
なお、上記の期間中には配当等の利益処分による社外流出はない。
(iii)上場時の想定
● 第4期を申請直前期として、東証マザーズで上場
● 上場時の株主構成:社長、役員、従業員及び取引先の合計持株比率が50%以上、
市場に流通する一般投資家持株比率は30%前後
● 発行済株式数の水準:株価が50万円未満となる株式数とする。
● 公募・売出し:6億円から8億円の公募増資
上場時の株主構成を実現する範囲内で、社長、役員及びVCが売出し
● 公開価格:PER50倍と仮定
(iv)その他
● 第2期の資金調達2億円は、ベンチャー・キャピタル(VC)から90%を調達し、10%は、社長と役員から調達する。
● 上場時の想定株主構成を実現するために、第4期に必要な第三者割当増資を実施。
② 上場時の想定条件に基づく検討
(i)上場時の時価総額の設定
PER50倍の条件から、上場申請年度の当期純利益1億円の50倍が上場時の時価総額となる。
→時価総額=1億円×50=50億円
(ii)上場時の発行済株式数の設定
上場時の株価を50万円未満とすることから、
上場時の発行済株式数>時価総額50億円÷50万円=10,000株
上場時の発行済株式数は、10,000株超となる。
(iii)上場時の安定株主構成の設定
社長、役員、従業員及び取引先:
合計持株比率を50%以上とすることから、これらの株式数は、
上場時の発行済株式数10,000株×50%=5,000株 程度以上とする。
一般投資家:
一般投資家の持株比率は30%前後とすることから、
上場時の発行済株式数10,000株×30%=3,000株 程度とする。
VC:
上記以外の持株は、VCの持株となることから、
上場時の発行済株式数10,000株-(5,000株+3,000株)=2,000株 程度とする。
③資本政策の策定例の各ステップの説明
(i)第1回第三者割当増資
第2期に事業計画上の必要資金をVC、社長、役員から調達する。
なお、VC、社長、役員に割り当てる株式は、株式公開申請が決定した時点で普通株式へ強制転換する条項がある種類株式とする。なお、普通株式への転換比率は、1:1とする。また、VC、社長、役員に割り当てるA種類株式及びB種類株式は、それぞれの種類株主総会で取締役2名を選任できる議決権があるものとし、VCに割り当てる種類株式にはさらに配当優先権を付すものとする。
割当先 銘 柄 発行価額 割当株式数 発行総額
VC A種類株 200,000円 900株 180,000千円
社長 B種類株 200,000円 50株 10,000千円
役員 B種類株 200,000円 50株 10,000千円
合計 1,000株 200,000千円
なお、発行価額は、VCとの交渉により合理的な根拠に基づいて決定したものとする。
(ii)第2回第三者割当増資
上場申請直前期(第4期)に、安定株主対策の観点から、取引先、及び従業員に普通株式を割り当てる。
割当先 銘 柄 発行価額 割当株式数 発行総額
取引先 普通株 250,000円 710株 177,500千円
従業員 普通株 250,000円 100株 25,000千円
合計 810株 202,500千円
なお、発行価額は、取引先との交渉により合理的な根拠に基づいて決定したものとする。
(iii)種類株式の普通株への転換
第5期の上場申請が決定する時点で種類株式を普通株に転換する。
(iv)株式分割
株価が50万円未満となるような発行済株式数(10,000株超)とするため1株を3株とする株式分割を実施。
(v)公募及び売出し
公募増資は、事業計画で計画した6億円~8億円の資金調達を実現する程度の規模とし、1,600株、発行価額49.9万円とする。
なお、発行価額は便宜的に
上場申請年度の1株当たり利益(EPS)9,970円×PER 50倍 ≒ 499,000円
として設定している。
売出しは、安定株主である社長、役員、従業員及び取引先の合計持株比率が50%強となる程度となるように社長330株、役員200株、VC900株の売出しを行う。
<売出しによる入金総額>
社長 499,000円×330株 = 164,670千円
役員 499,000円×200株 = 99,800千円
VC 499,000円×900株 = 449,100千円
合計 1,430株 713,570千円
<売出人の税額等>
社長:
1株当たり取得価額の算定
(50,000円×500株+200,000円×50株)÷1,650株=21,212円
キャピタルゲイン課税
(499,000円-21,212円)×330株×10%=15,767,004円
キャピタルゲイン課税控除後収入金額
499,000円×330株-15,767,004円=148,902,996円
上場時投資倍率=499,000円÷21,212円=23.5倍
役員:
1株当たり取得価額の算定
(50,000円×500株+200,000円×50円)÷1,650株=21,212円
キャピタルゲイン課税
(499,000円-21,212円)×200株×10%=9,555,760円
キャピタルゲイン課税控除後収入金額
499,000円×200株-9,555,760円=90,244,240円
上場時投資倍率=499,000円÷21,212円=23.5倍
VC:
1株当たり取得価額の算定
(200,000円×900株)÷2,700株=66,666円
キャピタルゲイン課税
(499,000円-66,666円)×1,600株×42%(法人税率)=290,528,448円
キャピタルゲイン課税控除後収入金額
499,000円×1,600株-290,528,449円=507,871,552円
上場時投資倍率=499,000円÷66,666円=7.5倍
④ 資本政策のチェックポイント
資本政策を策定するには、上場基準、商法等の規制をクリアしていることが必要です。
以下では、主な規制のチェックポイントを示し、資本政策案の適正性を検証してみます。
<上場規則のチェックポイント>
● 時価総額基準を設定する取引所を想定する場合は、それを充たしているか。
→ 今回のシミュレーションでは、東証マザーズでの上場を前提とし、マザーズの基準は時価総額10億円以上としています。資本政策案の時価総額は50億円であり問題ないものと判断できます。
● 上場時の株価は、取引所等が要請する1投資単位50万円未満となっているか。
→ 上場時の株価49.9万円<50万円となっており問題ありません。
● 公開株式数は、想定する市場の基準を充たしているか。
→ マザーズの基準では、1,000単位以上の公募又は公募及び売出し(ただし、公募は500単位以上)としていますが、
公募1,600株+売出し1,430株=3,030株>1,000株
となっており、基準を充たしています。
● 少数特定者持株比率、浮動株式数の上場規則を充たしているか。
→ マザーズでは、当該基準がないため検討の必要はありません。
● 売出株数は継続所有(制限期間内の第三者割当増資等)の対象株数を含んでいないか。
→ フリー期間(第3期まで)の取得株数のみの売出しであれば問題ありません。
社長のフリー期間の取得株数= 500株×株式分割(1+2)
= 1,500株 > 売出株数330株
役員のフリー期間の取得株数= 500株×株式分割(1+2)
= 1,500株 > 売出株数200株
VCのフリー期間の取得株数 = 900株×株式分割(1+2)
= 2,700株 > 売出株数1,600株
上記のとおり、いずれも売出株数はフリー期間の取得株数を下回っており問題ありません。
<発行価額のチェックポイント>
● 上場時の時価総額に使用するPERは、類似業種の水準からみて適正か。
→ PER50倍を設定。一般の事業会社の平均は20倍弱ですが、成長性の高い研究開発型ベンチャーゆえ、問題ないものと判断できます(但し、もっと低いPERを利用した資本政策案も作成し、比較検討することは必要)。
● 上場前の第三者割当増資等の発行価額は、税務上、問題ないか。
→ VC、取引先に対する発行価額は、純粋な経済行為として合理的な算定根拠をもって決定したものであり、租税回避行為にあたらず、税務上の問題はないと判断できます。
また、同時に割り当てた社長及び役員に対する発行価額は、同時に割り当てたVC及び取引先のものと同額であるため特段の問題はないと判断できます。
● 発行価額は、キャピタルゲインを確保できる水準か。
→ 「③資本政策の策定例の各ステップの説明-(v)公募及び売出し」で確認しているように、いずれの株主もキャピタルゲインを確保しており問題ありません。
<種類株式のチェックポイント>
● 取締役等選解任権付株式の総数は、発行済株式総数の2分の1を超えていないか(商法222⑧、⑤)。
→ 種類株式を発行した時点の状況は次のとおりであり、問題ありません。
取締役等選解任権付株式の総数1,000株 ≦(普通株1,000株+種類株1,000株)×1/2
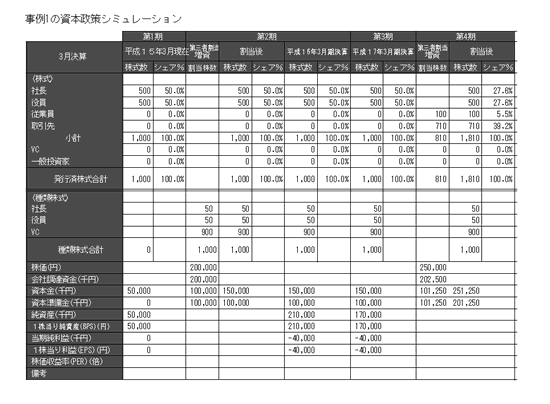
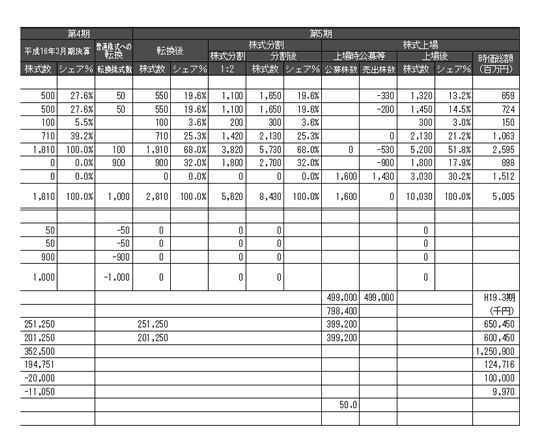
(2)事例2: 新株予約権を活用した郊外店舗運営会社の事例
① 前提条件
(i)現 状
発行済株式数:880株、株主構成:社長760株、役員120株
新株予約権の残高:なし
直近の決算:B/S 資本金44,000千円、純資産80,644千円
P/L 当期純利益28,644千円
(ii)事業計画
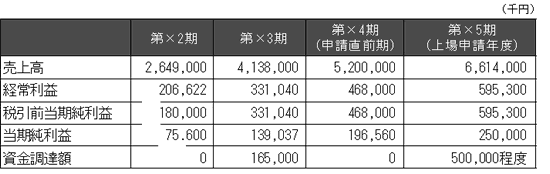
なお、上記の期間中には、配当等の利益処分による社外流出はない。
(iii)上場時の想定
● 第×4期を申請直前期として、東証マザーズで上場。
● 上場時の株主構成:社長、役員、従業員及び取引先の合計持株比率が60%以上、
市場に流通する一般投資家持株比率は20%前後
● 発行済株式数の水準:株価が50万円未満となる株式数とする。
● 公募:5億円程度の公募増資。
売出し:上記、上場時の株主構成を実現する範囲内で、社長、役員及びVCが売出し。
● 公開価格:PER約20倍と仮定(同業他社を参考として)。
(iv)その他
● 第×3期の資金調達額165百万円は、ベンチャー・キャピタル(VC)から120百万円、取引先から45百万円を調達。
② 上場時の想定条件に基づく検討
(i)上場時の時価総額の設定
PER20倍の条件から、上場申請年度の当期純利益250百万円の20倍が上場時の時価総額となる。→ 時価総額=250百万円×20=50億円
(ii)上場時の発行済株式数の設定
上場時の株価を50万円未満とすることから、
上場時の発行済株式数>時価総額50億円÷50万円≒10,000株
上場時の発行済株式数は、10,000株超となる。
(iii)上場時の安定株主構成の設定
社長、役員、従業員及び取引先:
合計持株比率を60%以上とすることから、これらの株式数は、
上場時の発行済株式数10,000株×60%=6,000株 程度以上とする。
一般投資家:
一般投資家の持株比率は20%前後とすることから、
上場時の発行済株式数10,000株×20%=2,000株 程度とする。
VC:
上記以外の持株は、VCの持株となることから、
上場時の発行済株式数10,000株-(6,000株+2,000株)=2,000株 程度とする。
③ 資本政策策定例の各ステップの説明
(i)ストック・オプション付与
第×2期に下記内容のストック・オプションを付与。
(対象者、付与個数)社長200個、役員150個、従業員150個
税制適格のストック・オプションは、権利行使時にその時の株式時価と権利行使価額との差額に課税(給与所得課税等)されず、株式譲渡時まで課税が繰延べられます。その資格要件は、非公開株式の場合、付与決議時における持株数が、発行済株式数の1/3以下であることが必要です。したがって、社長はその資格要件を満たしません。
(権利行使価額)92,000円
税制適格のストック・オプションの要件として、権利行使価額が付与契約時の株式時価以上である必要がある。直近決算(平成16年3月期)の1株当たり純資産価額91,641円をもとに92,000円とする。
(ii)第三者割当増資
第×3期に取引先及びベンチャーキャピタルが引受ける第三者割当増資を行う。取引先150株、ベンチャーキャピタル400株、計550株引き受けることを想定。株価は直近決算期(平成17年3月期)の1株当たり純資産額によれば、177,550円であるが、VC、取引先との交渉により合理的な根拠に基づいて300,000円に決定。この結果、以下の金額を調達する。
(150株+400株)×300,000円=165,000,000円
この時、持株比率は下記のように変化。
・社長 86.4% → 53.1% (-33.3%)
・役員 13.6% → 8.4% (-5.2%)
・取引先 0% → 10.5% (+10.5%)
・VC 0% → 28.0% (+28.0%)
(iii)ストック・オプションの権利行使
第×5期(上場申請年度)に、第×2期に付与したストック・オプションの権利行使を行う。内訳は以下の通りで、会社はこの340株の株式発行により、31,280千円を調達。
・社長 200株(残存なし) 200株×92,000円= 18,400,000円
・役員 70株 (残存50個) 70株×92,000円= 6,440,000円
・従業員 70株 (残存50個) 70株×92,000円= 6,440,000円
340株 31,280,000円
この場合の課税関係は次の通り。なお、このときの株式時価は直近決算期末(平成19年3月期)の1株当たり純資産価額553,735円から、554,000円と想定する。
税制適格ストック・オプションであれば、権利行使時の株式時価554,000円と権利行使価額92,000円との差額(462,000円)は課税されずに株式譲渡の時まで繰延べできる。しかし、税制不適格であればその差額分が給与所得等により課税される。この場合、社長は前述の通り付与決議時の持株数が発行済株式数の1/3超所有していたため、税制適格ストック・オプションの対象にならない。
・社長 200株×(554,000円-92,000円)=92,400,000円(課税対象)
この金額が給与所得として源泉所得税対象となる。
・役員 70株×(554,000円-92,000円)=32,340,000円(課税繰延べ)
・従業員 70株×(554,000円-92,000円)=32,340,000円(課税繰延べ)
上記の社長の課税負担はかなり重い。そこで、この分は他の新株予約権とは区別して発行時に適正な時価による有償取得とすることも一考である。こうすると権利行使時課税は生じず、株式譲渡時のキャピタルゲイン課税のみとなる。
また、役員、従業員の課税繰延べの適用は、権利行使者各個人について権利行使金額の年間合計額1,200万円までなので注意が必要である。
なお、第三者割当増資により低下した社長、役員及び従業員の持株比率は、ストック・オプションの権利行使により以下のように上昇し、逆に取引先、VCの持分比率は低下している。
・社長 53.1% → 54.2% (+1.1%)
・役員 8.4% → 10.7% (+2.3%)
・従業員 0% → 4.0% (+4.0%)
・取引先 10.5% → 8.5% (-2.0%)
・VC 28.0% → 22.6% (-5.4%)
(iv)株式分割
株価が50万円未満となるような発行済株式数(10,000株超)とするため、株式分割(1株を6株に分割)を実施。
(v)公募及び売出し
(公募)
公募増資は、事業計画の5億円程度の資金調達を実現できる程度の規模とし、1,200株、発行価額42万円とする。
なお、発行価額は便宜的に、
上場申請年度の1株当たり利益(EPS)21,151円×PER 20倍 ≒ 420,000円
として設定している。
以上から、会社の資金調達額は以下の通り。
1,200株×420,000円 =504,000千円
(売出し)
売出しは、安定株主である社長、役員、従業員及び取引先の合計持株比率が60%強となるように、社長500株、役員180株、VC500株の計 1,180株を実施する。
<売出しによる入金総額>
社長 500株×420,000円 = 210,000千円
役員 180株×420,000円 = 75,600千円
VC 500株×420,000円 = 210,000千円
合計 1,180株 495,600千円
<売出し人の税額等>
社長:
潜在株式の取得を以下の2ケースに分けて検討します。
(ケース1)適制不適格ストック・オプション権利行使のケース
1株当たり取得価額の算定
(50,000円×760株+554,000円×200株)÷960株÷6=25,833円
キャピタルゲイン課税
(420,000円-25,833円)×500株×10%=19,708,350円
キャピタルゲイン控除後収入金額
420,000円×500株-19,708,350円=190,291,650円
上場時投資倍率=420,000円÷25,833円=16.2倍
(ケース2)新株予約権を有償取得し権利行使したケース
新株予約権を適正時価(例えば10,000円)で有償取得したと想定。
1株当たり取得価額の算定
{50,000円×760株+(10,000円+92,000円)×200株}÷960株÷6=10,139円
キャピタルゲイン課税
(420,000円-10,139円)×500株×10%=20,493,050円
キャピタルゲイン控除後収入金額
420,000円×500株-20,493,050円=189,506,950円
上場時投資倍率=420,000円÷10,139円=41.4倍
役員:
1株当たり取得価額の算定
(50,000円×120株+92,000円×70株)÷190株÷6=10,912円
キャピタルゲイン課税
(420,000円-10,912円)×200株×10%=8,181,760円
キャピタルゲイン控除後収入金額
420,000円×200株-8,181,760円=75,818,240円
上場時投資倍率=420,000円÷10,912円=38.5倍
VC:
1株当たり取得価額の算定
(300,000円×400株)÷400株÷6=50,000円
キャピタルゲイン課税
(420,000円-50,000円)×500株×42%(法人税率)=77,700,000円
キャピタルゲイン控除後収入金額
420,000円×500株-77,700,000円=132,300,000円
上場時投資倍率=420,000円÷50,000円=8.4倍
(vi)上場時持分比率(潜在株式を含めて)
上場時の各株主の持株比率は事例の通りですが、潜在株式(ストック・オプションの未行使分)を考慮した場合には以下のように変わります。
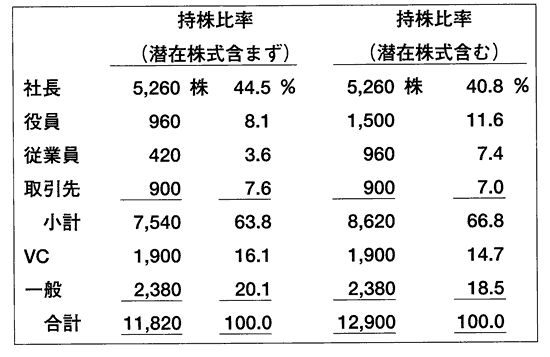
なお、平成13年9月4日以降、新株予約権等の潜在株式は未行使のままでも上場できることになりましたが、上場審査においては、上場時の新株予約権等の潜在株の未行使残は、発行済株式数の10%程度までが望ましいとされています(第2回参照)。最近はこれを超える事例も出てきてはいますが投資家保護の観点からは課題となりますので、意識する必要はあるといえましょう。
④ 資本政策チェックポイント
資本政策を策定するには、上場基準、商法等の規制をクリアしていることが必要です。
以下では、主な規制のチェックポイントを示し、資本政策案の適正性を検証してみます。
<上場規則のチェックポイント>
● 時価総額基準を設定する取引所を想定する場合は、それを充たしているか。
→ 今回のシミュレーションでは、東証マザーズでの上場を前提とし、マザーズの基準は時価総額10億円以上としています。資本政策案の時価総額は50億円であり問題ないものと判断できます。
● 上場時の株価は、取引所等が要請する1投資単位50万円未満となっているか。
→ 上場時の株価42万円<50万円となっており問題ありません。
● 公開株式数は、想定する市場の基準を充たしているか。
→ マザーズの基準では、1,000単位以上の公募又は公募及び売出し(ただし、公募は500単位以上)としていますが、
公募1,200株+売出し1,180株=2,380株>1,000株
となっており、基準を充たしています。
● 少数特定者持株比率、浮動株式数の上場規則を充たしているか。
→ マザーズでは、当該基準がないため検討の必要はありません。
● 売出株数は継続所有(制限期間内の第三者割当増資等)の対象株数を含んでいないか。
→ フリー期間(第×3期まで)の取得株数のみの売出しであれば問題ありません。
社長のフリー期間の取得株数= 760株×株式分割(1+5)
= 4,560株 > 売出株数500株
役員のフリー期間の取得株数= 120株×株式分割(1+5)
= 720株 > 売出株数200株
VCのフリー期間の取得株数 = 400株×株式分割(1+5)
= 2,400株 > 売出株数500株
上記のとおり、いずれも売出し株数はフリー期間の取得株数を下回っており問題ありません。
<発行価額のチェックポイント>
● 上場時の時価総額に使用するPERは、類似業種の水準からみて適正か。
→ PER20倍を設定。一般の事業会社の平均は20倍弱であり、成長性の高いロードサイド型郊外店舗運営会社の平均的なPERもこの程度であり、問題ないものと判断できます(但し、もっと低いPERを利用した堅実な資本政策案も作成し、比較検討することは必要)。
● 上場前の第三者割当増資等の発行価額は、税務上、問題ないか。
→ VC、取引先に対する発行価額は、純粋な経済行為として合理的な算定根拠をもって決定したものであり、租税回避行為にあたらず、税務上の問題はないと判断できます。
● 発行価額は、キャピタルゲインを確保できる水準か。
→ 「③資本政策策定例の各ステップの説明-(v)公募及び売出し」で確認しているように、いずれの株主もキャピタルゲインを確保しており問題ありません。
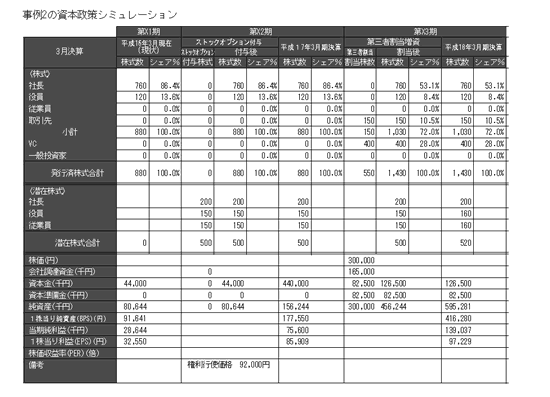

中嶋克久(なかしまかつひさ)
公認会計士
85年青山監査法人(現中央青山監査法人)入所。ジャフコ及び預金保険機構の出向を経て2004年7月に監査法人を退職。現在公認会計士中嶋事務所所長、(株)日本資本政策研究所代表取締役。
棟田裕幸(むねたひろゆき)
公認会計士・税理士
青山監査法人(現中央青山監査法人)、三優監査法人社員を経て、現在棟田公認会計士事務所所長、赤坂マネジメント・コンサルタント代表取締役。日本公認会計士協会東京会税務委員会副委員長 http://www2.odn.ne.jp/amc
今月号のCDに資本政策のエクセルシートが入っています!(編集部)
今号に同封されているCDに、18頁と26頁で用いた資本政策のエクセルシートのデータ(文責:編集部)が格納されています(資料カテゴリー内の「「資本政策の実務」第4回 特別資料」を選択してください。)。本解説を参考にして適宜修正することで、簡単に資本政策のシートを作成することができます。是非、ご利用ください。
資本政策の実務
第4回 資本政策の作成手順と事例
公認会計士 中嶋克久
公認会計士・税理士 棟田裕幸
1. はじめに
資本政策の実務の最終回として、本稿では資本政策のシミュレーションの仕方について、具体例を見ながら考えていきたいと思います。第1回目では、上場のための資本政策の策定ステップについても解説しましたが、今回は、これを踏まえつつ実際の策定上の留意事項を確認していきます。
2. 資本策定の策定上の準備事項と留意事項
(1)資本政策の策定上の準備事項
資本政策の策定にあたっては、まず、第1に自社の現状について確認します。確認事項は、発行済株式数、新株予約権の残高及び保有構成、株主構成、直近の決算などです。
第2に、上場申請年度までの事業計画です。事業計画は、必要とする資金調達額の把握と上場までの新株の発行価額の見積もりの基礎として利用します。第3に、上場時の条件を想定することです。具体的には上場時の目標項目を設定することであり、第1回目で解説した項目を想定します。すなわち、①上場時の資金調達額、②安定株主対策を考慮した株主構成を大目標とします。また、上場後一定の出来高を確保することによって株価を安定させるため、③株式の流動性を確保するための発行済株式数の水準と市場に放出する株式数を設定することも重要な項目となります。その他に、必須項目ではありませんが、④役員、従業員に付与するストック・オプション等のインセンティブ・プランがあります。また、社歴の長い中堅企業の上場にあっては、⑤オーナーの創業者利潤の確保と事業承継も目標項目になります。
上場時の株主構成については、現状の株主構成からスタートすると、必要とする資金調達額に応じてオーナー経営者の持株比率が低下することから、安定株主対策の観点から誰に割り当てるかを見込んで設定します。これらの検討は、大雑把なシミュレーションによって、ゴールとしての上場時の株主構成を見込んでいきます。
(資本政策の策定にあたって準備する事項)
●現状の把握 発行済株式数、新株予約権の残高及び保有構成、株主構成、直近の決算等
●事業計画 損益計画、資金調達計画等
●上場時の目標項目
必須事項:
①上場時の資金調達額
②安定株主対策を考慮した株主構成
③発行済株式数の水準・市場に放出する株式数の設定
任意事項:
④ストック・オプション等のインセンティブ・プラン
⑤オーナーの創業者利潤の確保と事業承継
(2)資本政策の策定上の留意事項
上場のための資本政策を策定するにあたっては、上場規則によって第三者割当増資等に一定の規制を受けます。また、証券取引法等の規制にも準拠していかなければなりません。以下では、これらの主な留意事項を説明していきます。
①上場前の第三者割当等による新株発行等の規制
上場前の新株発行の割当を受けた者が、短期間に利益を得ることを防止するため、上場規則によって一定の制限を受けます。具体的には、上場申請日の直前事業年度の1年前の日以後に第三者割当増資を受けた者は、上場日以後6ヶ月間を経過する日又は新株発行日から1年間経過する日のいずれか遅い日まで継続所有しなければなりません。したがって、上場申請日の直前事業年度の1年前の日以後に発行した株式については、上場時の売り出しの対象とすることはできません。
②上場前の第三者割当等による新株予約権等の規制
①の上場前の第三者割当等による新株発行等の規制と同様の規制が、新株予約権及び新株予約権付社債についてもあります。すなわち、上場申請日の直前事業年度の1年前の日以後に新株予約権又は新株予約権付社債の割当を受けた者は、上場日以後6ヶ月間を経過する日又は新株発行日から1年間経過する日のいずれか遅い日まで継続所有しなければなりません。なお、新株予約権の権利行使をした場合は、当該株式について引き続き継続所有しなければなりませんが、継続所有期間に変更はありません。
なお、下記の③ストック・オプションに該当する新株予約権は、上記と異なる取扱いとなります。
③ストック・オプションとしての新株予約権の規制
ストック・オプションとしての新株予約権とは、申請会社(子会社を含む)の役員(取締役・監査役・執行役)又は従業員等に報酬として発行した新株予約権(上場申請日の直前事業年度の末日の1年前の日以後に発行されたものに限定)であって、次の(i)及び(ii)を満たす新株予約権をいいます。
(i)申請会社が新株予約権の発行によってその新株予約権証券を役員又は従業員等に取得させていること。
(ii)(i)の新株予約権証券について、申請会社と当該役員及び従業員等との間で、書面により当該新株予約権の継続所有等、証券取引所等が必要と認める事項等の確約を行っていること。
このストック・オプションの継続所有期間は発行日から上場日の前日までとなります。
また、権利行使時の課税が繰り延べられる税制適格ストック・オプションは、付与決議から2年を経過する日まで行使できないことにも留意する必要があります。
④ 証券取引法上の規制
証券取引法上、一定の要件に該当する場合には、「有価証券届出書」の提出義務が生じます。この「有価証券届出書」は、上場申請時に提出するものと同じものであり、相当の手数を要し、2年間の会計監査も必要とされます。この届出書の提出義務が生じることを考慮せずに新株発行すると証券取引法違反となりますので、この提出義務に抵触しない範囲で上場前の新株発行を行うのが一般的です。なお、提出義務が生じる場合とは、証券取引法上の募集(50名以上)に該当し、かつ、発行価額の総額が1億円以上となる場合等です。なお、募集に該当するかどうかの判定には、「6ヶ月間人数通算」ルールや「2年間金額通算」ルールがあるなど、複雑な規定となっていますので、割当人数が多くなる場合等の新株発行を行う場合には、弁護士等の専門家と慎重に相談することが必要です。
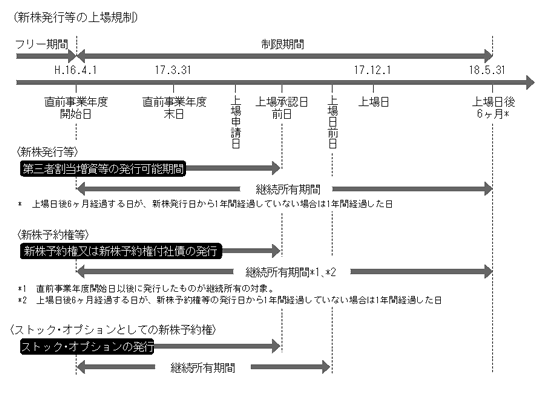
3. 資本政策シミュレーション例
(1)事例1: 種類株式を活用した研究開発型ベンチャーの事例
このシミュレーションでは、以下の①の前提条件に基づいて資本政策を検討するものとし、検討プロセスを②に示します。その上で、資本政策案を③で解説していきます。
①前提条件
(i)現 状
発行済株式数:1,000株、株主構成:社長500株、役員500株
新株予約権の残高:なし
直近の決算:B/S 資本金50,000千円、純資産50,000千円
P/L 当期純利益0円
(ii)事業計画
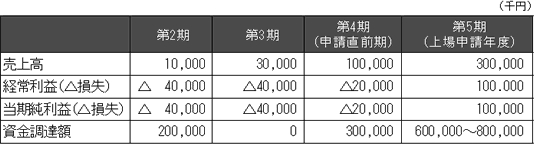
なお、上記の期間中には配当等の利益処分による社外流出はない。
(iii)上場時の想定
● 第4期を申請直前期として、東証マザーズで上場
● 上場時の株主構成:社長、役員、従業員及び取引先の合計持株比率が50%以上、
市場に流通する一般投資家持株比率は30%前後
● 発行済株式数の水準:株価が50万円未満となる株式数とする。
● 公募・売出し:6億円から8億円の公募増資
上場時の株主構成を実現する範囲内で、社長、役員及びVCが売出し
● 公開価格:PER50倍と仮定
(iv)その他
● 第2期の資金調達2億円は、ベンチャー・キャピタル(VC)から90%を調達し、10%は、社長と役員から調達する。
● 上場時の想定株主構成を実現するために、第4期に必要な第三者割当増資を実施。
② 上場時の想定条件に基づく検討
(i)上場時の時価総額の設定
PER50倍の条件から、上場申請年度の当期純利益1億円の50倍が上場時の時価総額となる。
→時価総額=1億円×50=50億円
(ii)上場時の発行済株式数の設定
上場時の株価を50万円未満とすることから、
上場時の発行済株式数>時価総額50億円÷50万円=10,000株
上場時の発行済株式数は、10,000株超となる。
(iii)上場時の安定株主構成の設定
社長、役員、従業員及び取引先:
合計持株比率を50%以上とすることから、これらの株式数は、
上場時の発行済株式数10,000株×50%=5,000株 程度以上とする。
一般投資家:
一般投資家の持株比率は30%前後とすることから、
上場時の発行済株式数10,000株×30%=3,000株 程度とする。
VC:
上記以外の持株は、VCの持株となることから、
上場時の発行済株式数10,000株-(5,000株+3,000株)=2,000株 程度とする。
③資本政策の策定例の各ステップの説明
(i)第1回第三者割当増資
第2期に事業計画上の必要資金をVC、社長、役員から調達する。
なお、VC、社長、役員に割り当てる株式は、株式公開申請が決定した時点で普通株式へ強制転換する条項がある種類株式とする。なお、普通株式への転換比率は、1:1とする。また、VC、社長、役員に割り当てるA種類株式及びB種類株式は、それぞれの種類株主総会で取締役2名を選任できる議決権があるものとし、VCに割り当てる種類株式にはさらに配当優先権を付すものとする。
割当先 銘 柄 発行価額 割当株式数 発行総額
VC A種類株 200,000円 900株 180,000千円
社長 B種類株 200,000円 50株 10,000千円
役員 B種類株 200,000円 50株 10,000千円
合計 1,000株 200,000千円
なお、発行価額は、VCとの交渉により合理的な根拠に基づいて決定したものとする。
(ii)第2回第三者割当増資
上場申請直前期(第4期)に、安定株主対策の観点から、取引先、及び従業員に普通株式を割り当てる。
割当先 銘 柄 発行価額 割当株式数 発行総額
取引先 普通株 250,000円 710株 177,500千円
従業員 普通株 250,000円 100株 25,000千円
合計 810株 202,500千円
なお、発行価額は、取引先との交渉により合理的な根拠に基づいて決定したものとする。
(iii)種類株式の普通株への転換
第5期の上場申請が決定する時点で種類株式を普通株に転換する。
(iv)株式分割
株価が50万円未満となるような発行済株式数(10,000株超)とするため1株を3株とする株式分割を実施。
(v)公募及び売出し
公募増資は、事業計画で計画した6億円~8億円の資金調達を実現する程度の規模とし、1,600株、発行価額49.9万円とする。
なお、発行価額は便宜的に
上場申請年度の1株当たり利益(EPS)9,970円×PER 50倍 ≒ 499,000円
として設定している。
売出しは、安定株主である社長、役員、従業員及び取引先の合計持株比率が50%強となる程度となるように社長330株、役員200株、VC900株の売出しを行う。
<売出しによる入金総額>
社長 499,000円×330株 = 164,670千円
役員 499,000円×200株 = 99,800千円
VC 499,000円×900株 = 449,100千円
合計 1,430株 713,570千円
<売出人の税額等>
社長:
1株当たり取得価額の算定
(50,000円×500株+200,000円×50株)÷1,650株=21,212円
キャピタルゲイン課税
(499,000円-21,212円)×330株×10%=15,767,004円
キャピタルゲイン課税控除後収入金額
499,000円×330株-15,767,004円=148,902,996円
上場時投資倍率=499,000円÷21,212円=23.5倍
役員:
1株当たり取得価額の算定
(50,000円×500株+200,000円×50円)÷1,650株=21,212円
キャピタルゲイン課税
(499,000円-21,212円)×200株×10%=9,555,760円
キャピタルゲイン課税控除後収入金額
499,000円×200株-9,555,760円=90,244,240円
上場時投資倍率=499,000円÷21,212円=23.5倍
VC:
1株当たり取得価額の算定
(200,000円×900株)÷2,700株=66,666円
キャピタルゲイン課税
(499,000円-66,666円)×1,600株×42%(法人税率)=290,528,448円
キャピタルゲイン課税控除後収入金額
499,000円×1,600株-290,528,449円=507,871,552円
上場時投資倍率=499,000円÷66,666円=7.5倍
④ 資本政策のチェックポイント
資本政策を策定するには、上場基準、商法等の規制をクリアしていることが必要です。
以下では、主な規制のチェックポイントを示し、資本政策案の適正性を検証してみます。
<上場規則のチェックポイント>
● 時価総額基準を設定する取引所を想定する場合は、それを充たしているか。
→ 今回のシミュレーションでは、東証マザーズでの上場を前提とし、マザーズの基準は時価総額10億円以上としています。資本政策案の時価総額は50億円であり問題ないものと判断できます。
● 上場時の株価は、取引所等が要請する1投資単位50万円未満となっているか。
→ 上場時の株価49.9万円<50万円となっており問題ありません。
● 公開株式数は、想定する市場の基準を充たしているか。
→ マザーズの基準では、1,000単位以上の公募又は公募及び売出し(ただし、公募は500単位以上)としていますが、
公募1,600株+売出し1,430株=3,030株>1,000株
となっており、基準を充たしています。
● 少数特定者持株比率、浮動株式数の上場規則を充たしているか。
→ マザーズでは、当該基準がないため検討の必要はありません。
● 売出株数は継続所有(制限期間内の第三者割当増資等)の対象株数を含んでいないか。
→ フリー期間(第3期まで)の取得株数のみの売出しであれば問題ありません。
社長のフリー期間の取得株数= 500株×株式分割(1+2)
= 1,500株 > 売出株数330株
役員のフリー期間の取得株数= 500株×株式分割(1+2)
= 1,500株 > 売出株数200株
VCのフリー期間の取得株数 = 900株×株式分割(1+2)
= 2,700株 > 売出株数1,600株
上記のとおり、いずれも売出株数はフリー期間の取得株数を下回っており問題ありません。
<発行価額のチェックポイント>
● 上場時の時価総額に使用するPERは、類似業種の水準からみて適正か。
→ PER50倍を設定。一般の事業会社の平均は20倍弱ですが、成長性の高い研究開発型ベンチャーゆえ、問題ないものと判断できます(但し、もっと低いPERを利用した資本政策案も作成し、比較検討することは必要)。
● 上場前の第三者割当増資等の発行価額は、税務上、問題ないか。
→ VC、取引先に対する発行価額は、純粋な経済行為として合理的な算定根拠をもって決定したものであり、租税回避行為にあたらず、税務上の問題はないと判断できます。
また、同時に割り当てた社長及び役員に対する発行価額は、同時に割り当てたVC及び取引先のものと同額であるため特段の問題はないと判断できます。
● 発行価額は、キャピタルゲインを確保できる水準か。
→ 「③資本政策の策定例の各ステップの説明-(v)公募及び売出し」で確認しているように、いずれの株主もキャピタルゲインを確保しており問題ありません。
<種類株式のチェックポイント>
● 取締役等選解任権付株式の総数は、発行済株式総数の2分の1を超えていないか(商法222⑧、⑤)。
→ 種類株式を発行した時点の状況は次のとおりであり、問題ありません。
取締役等選解任権付株式の総数1,000株 ≦(普通株1,000株+種類株1,000株)×1/2
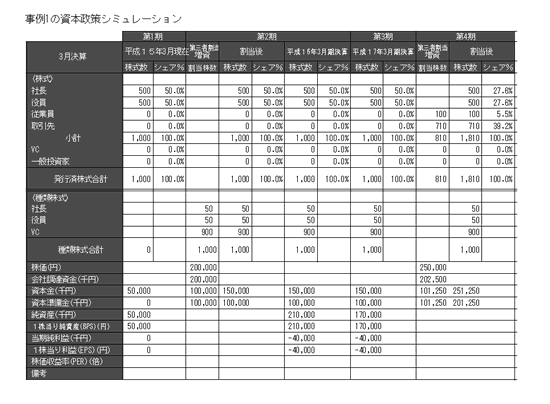
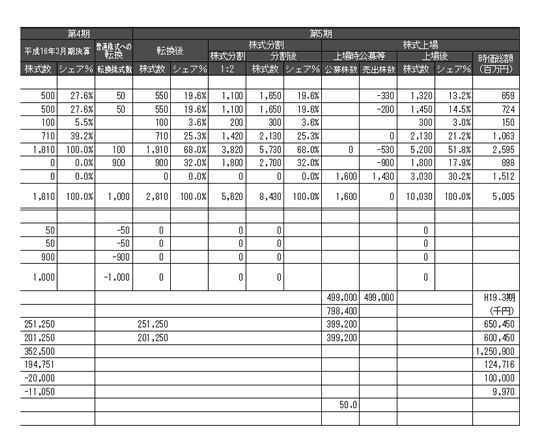
(2)事例2: 新株予約権を活用した郊外店舗運営会社の事例
① 前提条件
(i)現 状
発行済株式数:880株、株主構成:社長760株、役員120株
新株予約権の残高:なし
直近の決算:B/S 資本金44,000千円、純資産80,644千円
P/L 当期純利益28,644千円
(ii)事業計画
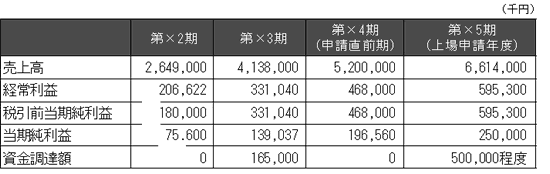
なお、上記の期間中には、配当等の利益処分による社外流出はない。
(iii)上場時の想定
● 第×4期を申請直前期として、東証マザーズで上場。
● 上場時の株主構成:社長、役員、従業員及び取引先の合計持株比率が60%以上、
市場に流通する一般投資家持株比率は20%前後
● 発行済株式数の水準:株価が50万円未満となる株式数とする。
● 公募:5億円程度の公募増資。
売出し:上記、上場時の株主構成を実現する範囲内で、社長、役員及びVCが売出し。
● 公開価格:PER約20倍と仮定(同業他社を参考として)。
(iv)その他
● 第×3期の資金調達額165百万円は、ベンチャー・キャピタル(VC)から120百万円、取引先から45百万円を調達。
② 上場時の想定条件に基づく検討
(i)上場時の時価総額の設定
PER20倍の条件から、上場申請年度の当期純利益250百万円の20倍が上場時の時価総額となる。→ 時価総額=250百万円×20=50億円
(ii)上場時の発行済株式数の設定
上場時の株価を50万円未満とすることから、
上場時の発行済株式数>時価総額50億円÷50万円≒10,000株
上場時の発行済株式数は、10,000株超となる。
(iii)上場時の安定株主構成の設定
社長、役員、従業員及び取引先:
合計持株比率を60%以上とすることから、これらの株式数は、
上場時の発行済株式数10,000株×60%=6,000株 程度以上とする。
一般投資家:
一般投資家の持株比率は20%前後とすることから、
上場時の発行済株式数10,000株×20%=2,000株 程度とする。
VC:
上記以外の持株は、VCの持株となることから、
上場時の発行済株式数10,000株-(6,000株+2,000株)=2,000株 程度とする。
③ 資本政策策定例の各ステップの説明
(i)ストック・オプション付与
第×2期に下記内容のストック・オプションを付与。
(対象者、付与個数)社長200個、役員150個、従業員150個
税制適格のストック・オプションは、権利行使時にその時の株式時価と権利行使価額との差額に課税(給与所得課税等)されず、株式譲渡時まで課税が繰延べられます。その資格要件は、非公開株式の場合、付与決議時における持株数が、発行済株式数の1/3以下であることが必要です。したがって、社長はその資格要件を満たしません。
(権利行使価額)92,000円
税制適格のストック・オプションの要件として、権利行使価額が付与契約時の株式時価以上である必要がある。直近決算(平成16年3月期)の1株当たり純資産価額91,641円をもとに92,000円とする。
(ii)第三者割当増資
第×3期に取引先及びベンチャーキャピタルが引受ける第三者割当増資を行う。取引先150株、ベンチャーキャピタル400株、計550株引き受けることを想定。株価は直近決算期(平成17年3月期)の1株当たり純資産額によれば、177,550円であるが、VC、取引先との交渉により合理的な根拠に基づいて300,000円に決定。この結果、以下の金額を調達する。
(150株+400株)×300,000円=165,000,000円
この時、持株比率は下記のように変化。
・社長 86.4% → 53.1% (-33.3%)
・役員 13.6% → 8.4% (-5.2%)
・取引先 0% → 10.5% (+10.5%)
・VC 0% → 28.0% (+28.0%)
(iii)ストック・オプションの権利行使
第×5期(上場申請年度)に、第×2期に付与したストック・オプションの権利行使を行う。内訳は以下の通りで、会社はこの340株の株式発行により、31,280千円を調達。
・社長 200株(残存なし) 200株×92,000円= 18,400,000円
・役員 70株 (残存50個) 70株×92,000円= 6,440,000円
・従業員 70株 (残存50個) 70株×92,000円= 6,440,000円
340株 31,280,000円
この場合の課税関係は次の通り。なお、このときの株式時価は直近決算期末(平成19年3月期)の1株当たり純資産価額553,735円から、554,000円と想定する。
税制適格ストック・オプションであれば、権利行使時の株式時価554,000円と権利行使価額92,000円との差額(462,000円)は課税されずに株式譲渡の時まで繰延べできる。しかし、税制不適格であればその差額分が給与所得等により課税される。この場合、社長は前述の通り付与決議時の持株数が発行済株式数の1/3超所有していたため、税制適格ストック・オプションの対象にならない。
・社長 200株×(554,000円-92,000円)=92,400,000円(課税対象)
この金額が給与所得として源泉所得税対象となる。
・役員 70株×(554,000円-92,000円)=32,340,000円(課税繰延べ)
・従業員 70株×(554,000円-92,000円)=32,340,000円(課税繰延べ)
上記の社長の課税負担はかなり重い。そこで、この分は他の新株予約権とは区別して発行時に適正な時価による有償取得とすることも一考である。こうすると権利行使時課税は生じず、株式譲渡時のキャピタルゲイン課税のみとなる。
また、役員、従業員の課税繰延べの適用は、権利行使者各個人について権利行使金額の年間合計額1,200万円までなので注意が必要である。
なお、第三者割当増資により低下した社長、役員及び従業員の持株比率は、ストック・オプションの権利行使により以下のように上昇し、逆に取引先、VCの持分比率は低下している。
・社長 53.1% → 54.2% (+1.1%)
・役員 8.4% → 10.7% (+2.3%)
・従業員 0% → 4.0% (+4.0%)
・取引先 10.5% → 8.5% (-2.0%)
・VC 28.0% → 22.6% (-5.4%)
(iv)株式分割
株価が50万円未満となるような発行済株式数(10,000株超)とするため、株式分割(1株を6株に分割)を実施。
(v)公募及び売出し
(公募)
公募増資は、事業計画の5億円程度の資金調達を実現できる程度の規模とし、1,200株、発行価額42万円とする。
なお、発行価額は便宜的に、
上場申請年度の1株当たり利益(EPS)21,151円×PER 20倍 ≒ 420,000円
として設定している。
以上から、会社の資金調達額は以下の通り。
1,200株×420,000円 =504,000千円
(売出し)
売出しは、安定株主である社長、役員、従業員及び取引先の合計持株比率が60%強となるように、社長500株、役員180株、VC500株の計 1,180株を実施する。
<売出しによる入金総額>
社長 500株×420,000円 = 210,000千円
役員 180株×420,000円 = 75,600千円
VC 500株×420,000円 = 210,000千円
合計 1,180株 495,600千円
<売出し人の税額等>
社長:
潜在株式の取得を以下の2ケースに分けて検討します。
(ケース1)適制不適格ストック・オプション権利行使のケース
1株当たり取得価額の算定
(50,000円×760株+554,000円×200株)÷960株÷6=25,833円
キャピタルゲイン課税
(420,000円-25,833円)×500株×10%=19,708,350円
キャピタルゲイン控除後収入金額
420,000円×500株-19,708,350円=190,291,650円
上場時投資倍率=420,000円÷25,833円=16.2倍
(ケース2)新株予約権を有償取得し権利行使したケース
新株予約権を適正時価(例えば10,000円)で有償取得したと想定。
1株当たり取得価額の算定
{50,000円×760株+(10,000円+92,000円)×200株}÷960株÷6=10,139円
キャピタルゲイン課税
(420,000円-10,139円)×500株×10%=20,493,050円
キャピタルゲイン控除後収入金額
420,000円×500株-20,493,050円=189,506,950円
上場時投資倍率=420,000円÷10,139円=41.4倍
役員:
1株当たり取得価額の算定
(50,000円×120株+92,000円×70株)÷190株÷6=10,912円
キャピタルゲイン課税
(420,000円-10,912円)×200株×10%=8,181,760円
キャピタルゲイン控除後収入金額
420,000円×200株-8,181,760円=75,818,240円
上場時投資倍率=420,000円÷10,912円=38.5倍
VC:
1株当たり取得価額の算定
(300,000円×400株)÷400株÷6=50,000円
キャピタルゲイン課税
(420,000円-50,000円)×500株×42%(法人税率)=77,700,000円
キャピタルゲイン控除後収入金額
420,000円×500株-77,700,000円=132,300,000円
上場時投資倍率=420,000円÷50,000円=8.4倍
(vi)上場時持分比率(潜在株式を含めて)
上場時の各株主の持株比率は事例の通りですが、潜在株式(ストック・オプションの未行使分)を考慮した場合には以下のように変わります。
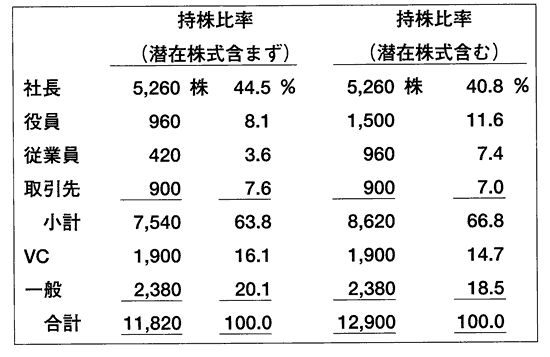
なお、平成13年9月4日以降、新株予約権等の潜在株式は未行使のままでも上場できることになりましたが、上場審査においては、上場時の新株予約権等の潜在株の未行使残は、発行済株式数の10%程度までが望ましいとされています(第2回参照)。最近はこれを超える事例も出てきてはいますが投資家保護の観点からは課題となりますので、意識する必要はあるといえましょう。
④ 資本政策チェックポイント
資本政策を策定するには、上場基準、商法等の規制をクリアしていることが必要です。
以下では、主な規制のチェックポイントを示し、資本政策案の適正性を検証してみます。
<上場規則のチェックポイント>
● 時価総額基準を設定する取引所を想定する場合は、それを充たしているか。
→ 今回のシミュレーションでは、東証マザーズでの上場を前提とし、マザーズの基準は時価総額10億円以上としています。資本政策案の時価総額は50億円であり問題ないものと判断できます。
● 上場時の株価は、取引所等が要請する1投資単位50万円未満となっているか。
→ 上場時の株価42万円<50万円となっており問題ありません。
● 公開株式数は、想定する市場の基準を充たしているか。
→ マザーズの基準では、1,000単位以上の公募又は公募及び売出し(ただし、公募は500単位以上)としていますが、
公募1,200株+売出し1,180株=2,380株>1,000株
となっており、基準を充たしています。
● 少数特定者持株比率、浮動株式数の上場規則を充たしているか。
→ マザーズでは、当該基準がないため検討の必要はありません。
● 売出株数は継続所有(制限期間内の第三者割当増資等)の対象株数を含んでいないか。
→ フリー期間(第×3期まで)の取得株数のみの売出しであれば問題ありません。
社長のフリー期間の取得株数= 760株×株式分割(1+5)
= 4,560株 > 売出株数500株
役員のフリー期間の取得株数= 120株×株式分割(1+5)
= 720株 > 売出株数200株
VCのフリー期間の取得株数 = 400株×株式分割(1+5)
= 2,400株 > 売出株数500株
上記のとおり、いずれも売出し株数はフリー期間の取得株数を下回っており問題ありません。
<発行価額のチェックポイント>
● 上場時の時価総額に使用するPERは、類似業種の水準からみて適正か。
→ PER20倍を設定。一般の事業会社の平均は20倍弱であり、成長性の高いロードサイド型郊外店舗運営会社の平均的なPERもこの程度であり、問題ないものと判断できます(但し、もっと低いPERを利用した堅実な資本政策案も作成し、比較検討することは必要)。
● 上場前の第三者割当増資等の発行価額は、税務上、問題ないか。
→ VC、取引先に対する発行価額は、純粋な経済行為として合理的な算定根拠をもって決定したものであり、租税回避行為にあたらず、税務上の問題はないと判断できます。
● 発行価額は、キャピタルゲインを確保できる水準か。
→ 「③資本政策策定例の各ステップの説明-(v)公募及び売出し」で確認しているように、いずれの株主もキャピタルゲインを確保しており問題ありません。
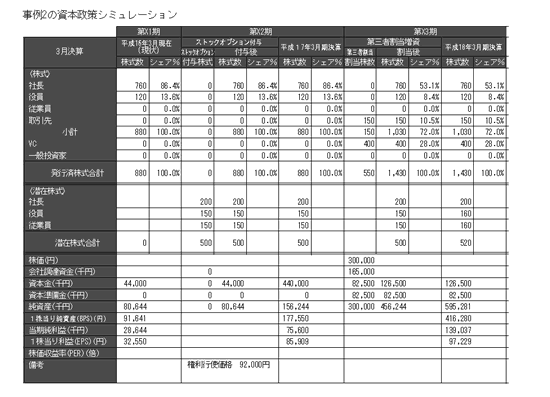

中嶋克久(なかしまかつひさ)
公認会計士
85年青山監査法人(現中央青山監査法人)入所。ジャフコ及び預金保険機構の出向を経て2004年7月に監査法人を退職。現在公認会計士中嶋事務所所長、(株)日本資本政策研究所代表取締役。
棟田裕幸(むねたひろゆき)
公認会計士・税理士
青山監査法人(現中央青山監査法人)、三優監査法人社員を経て、現在棟田公認会計士事務所所長、赤坂マネジメント・コンサルタント代表取締役。日本公認会計士協会東京会税務委員会副委員長 http://www2.odn.ne.jp/amc
今月号のCDに資本政策のエクセルシートが入っています!(編集部)
今号に同封されているCDに、18頁と26頁で用いた資本政策のエクセルシートのデータ(文責:編集部)が格納されています(資料カテゴリー内の「「資本政策の実務」第4回 特別資料」を選択してください。)。本解説を参考にして適宜修正することで、簡単に資本政策のシートを作成することができます。是非、ご利用ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























