解説記事2004年10月18日 【ニュース特集】 揺れる「日本版LLP制度」とパススルー課税(2004年10月18日号・№087)
ニュース特集
財務省は「組合税制全体を見直す必要あり」とコメント!
揺れる「日本版LLP制度」とパススルー課税
経済産業省は、「有限責任事業組合制度に関する研究会(以下、「日本版LLP研究会」)」を発足、9月17日と10月8日に研究会を開催しました。また、平成17年度税制改正要望でも、LLP制度を創設し、「税務上、民法組合と同様の取扱いとすること」を要望しています。日本版LLP研究会では、年内に報告書案を取りまとめ、来年の通常国会に法案を提出する考えです。
しかし、ここにきて、財務省がLLPでのパススルー課税に黄色信号を点しました。財務省は10月7日、本誌の取材に対し、「民法組合としてLLP制度を創設するなら、組合税制全体を見直す必要がある」として、LLPに対応する新たな法制を整備する必要があるという見解を示しています。
今回の特集は、揺れる「日本版LLP制度」とその課税問題について検証します。
1. 日本版LLPってなあに!?
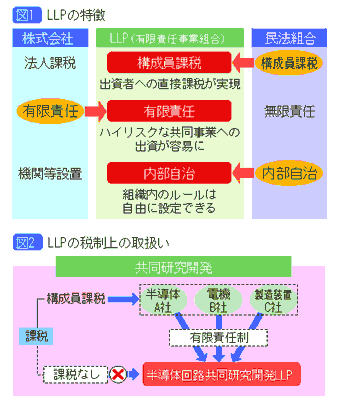
経産省が創設に向けて動き出したLLP制度は、株式会社と同様に、出資者は出資額の範囲で責任を負う有限責任とする一方、民法組合としてパススルー課税及び自由な組織の設計を認めるという新しい組織制度です( 図1 参照)。専門的能力を有する人材や法人を、リスクの高い事業や研究開発等に参画しやすくすることが目的です。経産省は、「創業、事業再編、産学連携などを推進、研究開発や高度サービス等を振興させる、新産業創造の重要な担い手」と位置付けています( 図2 参照)。
パススルー課税のメリットと問題点
LLPは法人格を持たないのでLLP自体には課税されず、LLPの構成員に対して課税されます。この「パススルー課税」は、株式会社にみられるような法人段階と出資者段階での「二重課税」を避けることができるほか、事業開始当初などに生じる損失を出資者の他の所得などから差し引けるメリットがあります。このために、アメリカやイギリスではベンチャー企業の立ち上げや共同研究に適した事業形態として広く普及しているのです( 図3 参照)。
一方、故意に損失を分配し、出資者の所得などを圧縮する「租税回避」に悪用される可能性もあるため、財務省はパススルー課税の適用に従来から慎重な姿勢を示していました。
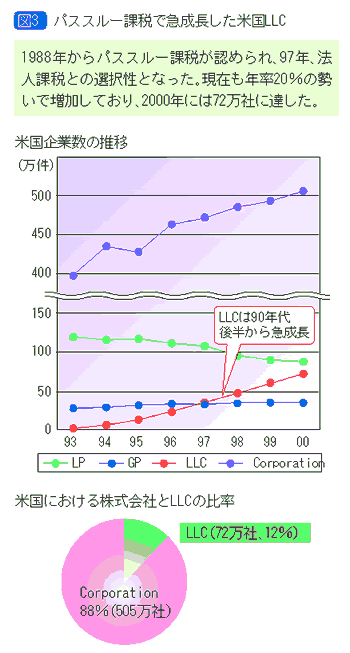
経産省が「急遽」動き出した背景
経産省がLLPの創設に動き出した背景には、会社法制の現代化に関する要綱案(第二次案)に盛り込まれ、来年の通常国会で提出が予定されている日本版LLC(合同会社)が法人格を有するため、パススルー課税できない可能性が高まってきたことにあります。法人格の有無がパススルー課税のメルクマールになるとすれば、LLPの創設によってパススルー課税が実現されるのではないか、と思われるからです。財務省も、当初はLLPでのパススルー課税に前向きな姿勢を示していたようです。経産省が今夏、LLP制度の創設に向けて「急遽」動き出したように見えるのも、こうした財務省の姿勢を受けて、「LLPならパススルーできる」と踏んだからだと思われます。
LLPでの構成員課税に「待った」
しかし、冒頭にも記述したように、財務省は、LLPを「税務上、民法組合と同様の取扱いとすること(法基通14-1-1、14-1-2及び所基通36・37共-19、36・37共-20の適用)」について否定的な考えを示し、LLPに対応する新たな法律や政令を整備することを示唆しています。ここで問題となるのが、財務省のいう「LLPに対応する新たな法制」が「LLPのみを対象とするもの」を指しているのか「組合税制全体を見直す」ことを指しているのかということです。「組合課税全体を見直す」ことになれば、組合員と組合の取引の問題や、消費税、資産税の問題なども浮上し、その検討作業は膨大なものとなります。
財務省は、この点について、「一つの商品を投入する場合、ラインナップ全体を見直すのは当然のこと」として、「民法組合としてLLP制度を創設するなら、組合税制全体を見直す必要がある」との認識を明らかにしました。また、組合税制全体を見直す作業を「年末までにまとめるのは厳しい」としています(下記「民法組合の課税問題」参照)。
第1回の日本版LLP研究会では、経産省が示した案(次頁参照)に対し、「縛りがきつすぎる」とする意見も多く、今後の研究会では、いかに、制度の「縛りを緩め、使いやすいしくみ」にできるかが焦点となっていました。しかし、前記のような財務省の見解によると、「税務上、民法組合と同様の取扱い」としながら、「使い勝手のよい制度」とすることは難しくなったといえるでしょう。一方で、財務省は、「ジョイントベンチャーや産学連携といった局部的な位置付けでのLLPならあり得るのではないか」とコメントしています。
民法組合の課税問題
現行の法人税法・所得税法では、民法上の任意組合について、特に法規定されていません。現在のところ、組合に対する課税は、通達(法基通14-1-1、14-1-2及び所基通36・37共-19、36・37共-20)があるだけで、租税法律主義の観点からも疑問が残ります。民法上の規定を前提として明確な税法の適用・解釈が可能なら、通達での対応も許容されるのかもしれませんが、現行の民法上の組合規定も任意規定がほとんど。今後、LLCやLLPなどの多様な事業体に対応していくためには、立法面での基本的な見直しが必要であるといわれています。
2. 日本版LLP制度の論点
日本版LLP研究会における検討項目は、①有限責任制の導入と債権者保護、②事業体として活用する上での手当て、③税制上の論点、の三点。具体的には、以下のような項目が話し合われる予定です。
①有限責任制の導入と債権者保護
法人格を有しない組合への有限責任制付与の可能性
債権者保護に関する措置(責任財産充実、名称制限、開示)
組合債務と出資者の有限責任との関係
②事業体として活用する上での手当て
現行の民法組合でも問題とならないと考える事項(契約行為の主体・訴訟当事者能力等)
登記・登録制度に関する措置
許可・認可・届出制度に関する措置
③税制上の論点
租税回避行為の防止
共同事業性の確保( 図4 参照)
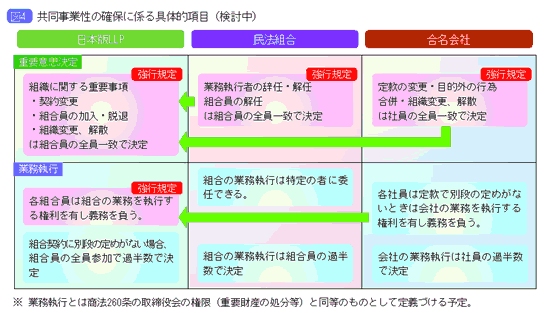
縛りがきつい!?経産省案
経産省案は、「①有限責任制の導入と債権者保護」の中で、「出資者=構成員」を有限責任とすることによって、出資者のリスクを制限し、事業への参加を容易にするとしています。このため、会社法現代化で提案されているLLCや投資事業有限責任組合における債権者保護規定を参考にしつつ、「適切な債権者保護規定を講じる」としています。
また、「②事業体として活用する上での手当て」の中で、法人格を持たない組合が事業を行うことについて、組合の代表者(業務執行組合員)名義で契約を結ぶことや、組合自身が訴訟行為を行うことなどは「現行の民法組合でも問題とならないと考える事項」としながら、不動産登記制度等の財産の公示手続きにおいて、組合が手続主体になれない等の問題が存在するため、「①登記・登録制度、②許可・認可・届出制度(営業の禁止・制限の解除)について、LLP法で新たに措置を行う予定」としています。
さらに、「③税制上の論点」の中では、日本版LLPが構成員課税となることから、「民法組合の柔軟な内部規定をそのまま準用すると、業務に参加しない出資者が多数存在するといったような法人と同様のLLPの組成も可能」と指摘。業務執行や意思決定に関して、 図4 のような「構成員の事業参加を強制する共同事業性の確保のための措置を講じる」ことを提案しています。
3. 海外のLLPってどんな制度?
Q1 アメリカのLLPはどんな制度なの?
米国LLPは、経営に参加するジェネラルパートナーシップについて、すべてのパートナーに有限責任を認める形態です。1991年、テキサス州において、無限連帯責任を求められていた法律事務所や会計事務所等の専門職の団体を対象に、不法行為に関与しないパートナーには有限責任を認める仕組み(自らの行為に基づく責任は無限責任)として開始され、全米に広がりました。州により有限責任となる範囲に制限がありますが、ニューヨーク州のLLPは全パートナーにほぼ完全な有限責任を認めており、LLCと実態上の差異はなくなりつつあります。
Q2 アメリカのLLP・LLCは、なぜ普及したの?
米国内国歳入庁は1988年、「キントナー規則」を公表し、LLCについてもその要件を満たせば、税務上、会社ではなくパートナーシップとして扱うことを明らかにしました。また1997年、チェック・ザ・ボックス規則を導入し、LLPやLLCの事業者が法人課税とパススルー課税のいずれかを選択できることとなり、普及に拍車がかかりました。
Q3 イギリスのLLPはどんな制度なの?
2000年に制定された新しい制度です。法人格を有し、パートナーは有限責任によっています。従来のパートナーシップの組織面における柔軟性に有限責任制を付加した制度です。法人格を有しますが、税制面では特別措置として、従来のパートナーシップへのパススルー課税を踏襲しています。ただ、LLPが清算段階に入った場合には、課税上も法人として取扱われます。また、非営利活動LLPの場合も、実務上の要請に基づき、課税上も法人として取扱われます。職業専門家が有限責任で組織運営したいとの要請により制定されましたが、あらゆる事業において用いることができるよう法整備されました。2001年の施行以来、現在までに8,400のLLPが登記されています。
Q4 シンガポールでもLLPができるって本当?
本当です。創業や高度サービス産業の振興のために、現在、創設を検討しているところです。アメリカのLLCや、イギリスのLLPを参考として、2004年中に創設が予定されています。
投資事業有限責任組合とLLPの関係
平成10年11月に施行された「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」は、業務執行を行わない組合員が負う責任を出資額にとどめることを法的に担保し、幅広い投資家層による中小・ベンチャー企業への資金供給を促進するものです。平成16年4月には、「投資事業有限責任組合契約に関する法律(略称:ファンド法)」に改正され、投資事業有限責任組合の投資範囲を中小ベンチャー企業だけにとどめず、大企業や公開企業にまで拡充されました。
今回、経産省が創設に向けて動き出した日本版LLP制度は、その事業範囲を「投資」だけでなく、「共同事業」に拡大するもので、「ファンド法の拡充」とも位置付けられます。
なお、イギリスでは、「投資LLPについての特別規定」があり、投資、特に不動産投資を行うための導管として利用されているLLPに限り、企業年金等、税の免除を受けるパートナーが税制上の不利益を被らないよう、また、税制が投資判断に影響を与えないよう、特別な措置が講じられています。
財務省は「組合税制全体を見直す必要あり」とコメント!
揺れる「日本版LLP制度」とパススルー課税
経済産業省は、「有限責任事業組合制度に関する研究会(以下、「日本版LLP研究会」)」を発足、9月17日と10月8日に研究会を開催しました。また、平成17年度税制改正要望でも、LLP制度を創設し、「税務上、民法組合と同様の取扱いとすること」を要望しています。日本版LLP研究会では、年内に報告書案を取りまとめ、来年の通常国会に法案を提出する考えです。
しかし、ここにきて、財務省がLLPでのパススルー課税に黄色信号を点しました。財務省は10月7日、本誌の取材に対し、「民法組合としてLLP制度を創設するなら、組合税制全体を見直す必要がある」として、LLPに対応する新たな法制を整備する必要があるという見解を示しています。
今回の特集は、揺れる「日本版LLP制度」とその課税問題について検証します。
1. 日本版LLPってなあに!?
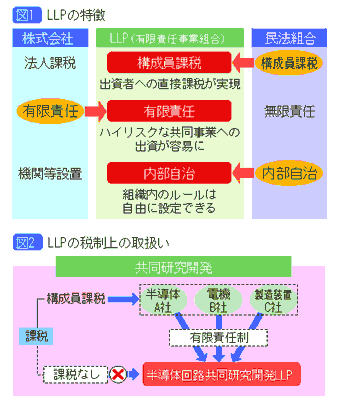
経産省が創設に向けて動き出したLLP制度は、株式会社と同様に、出資者は出資額の範囲で責任を負う有限責任とする一方、民法組合としてパススルー課税及び自由な組織の設計を認めるという新しい組織制度です( 図1 参照)。専門的能力を有する人材や法人を、リスクの高い事業や研究開発等に参画しやすくすることが目的です。経産省は、「創業、事業再編、産学連携などを推進、研究開発や高度サービス等を振興させる、新産業創造の重要な担い手」と位置付けています( 図2 参照)。
パススルー課税のメリットと問題点
LLPは法人格を持たないのでLLP自体には課税されず、LLPの構成員に対して課税されます。この「パススルー課税」は、株式会社にみられるような法人段階と出資者段階での「二重課税」を避けることができるほか、事業開始当初などに生じる損失を出資者の他の所得などから差し引けるメリットがあります。このために、アメリカやイギリスではベンチャー企業の立ち上げや共同研究に適した事業形態として広く普及しているのです( 図3 参照)。
一方、故意に損失を分配し、出資者の所得などを圧縮する「租税回避」に悪用される可能性もあるため、財務省はパススルー課税の適用に従来から慎重な姿勢を示していました。
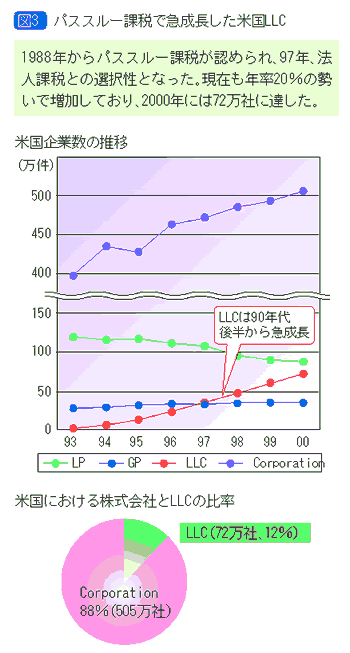
経産省が「急遽」動き出した背景
経産省がLLPの創設に動き出した背景には、会社法制の現代化に関する要綱案(第二次案)に盛り込まれ、来年の通常国会で提出が予定されている日本版LLC(合同会社)が法人格を有するため、パススルー課税できない可能性が高まってきたことにあります。法人格の有無がパススルー課税のメルクマールになるとすれば、LLPの創設によってパススルー課税が実現されるのではないか、と思われるからです。財務省も、当初はLLPでのパススルー課税に前向きな姿勢を示していたようです。経産省が今夏、LLP制度の創設に向けて「急遽」動き出したように見えるのも、こうした財務省の姿勢を受けて、「LLPならパススルーできる」と踏んだからだと思われます。
LLPでの構成員課税に「待った」
しかし、冒頭にも記述したように、財務省は、LLPを「税務上、民法組合と同様の取扱いとすること(法基通14-1-1、14-1-2及び所基通36・37共-19、36・37共-20の適用)」について否定的な考えを示し、LLPに対応する新たな法律や政令を整備することを示唆しています。ここで問題となるのが、財務省のいう「LLPに対応する新たな法制」が「LLPのみを対象とするもの」を指しているのか「組合税制全体を見直す」ことを指しているのかということです。「組合課税全体を見直す」ことになれば、組合員と組合の取引の問題や、消費税、資産税の問題なども浮上し、その検討作業は膨大なものとなります。
財務省は、この点について、「一つの商品を投入する場合、ラインナップ全体を見直すのは当然のこと」として、「民法組合としてLLP制度を創設するなら、組合税制全体を見直す必要がある」との認識を明らかにしました。また、組合税制全体を見直す作業を「年末までにまとめるのは厳しい」としています(下記「民法組合の課税問題」参照)。
第1回の日本版LLP研究会では、経産省が示した案(次頁参照)に対し、「縛りがきつすぎる」とする意見も多く、今後の研究会では、いかに、制度の「縛りを緩め、使いやすいしくみ」にできるかが焦点となっていました。しかし、前記のような財務省の見解によると、「税務上、民法組合と同様の取扱い」としながら、「使い勝手のよい制度」とすることは難しくなったといえるでしょう。一方で、財務省は、「ジョイントベンチャーや産学連携といった局部的な位置付けでのLLPならあり得るのではないか」とコメントしています。
民法組合の課税問題
現行の法人税法・所得税法では、民法上の任意組合について、特に法規定されていません。現在のところ、組合に対する課税は、通達(法基通14-1-1、14-1-2及び所基通36・37共-19、36・37共-20)があるだけで、租税法律主義の観点からも疑問が残ります。民法上の規定を前提として明確な税法の適用・解釈が可能なら、通達での対応も許容されるのかもしれませんが、現行の民法上の組合規定も任意規定がほとんど。今後、LLCやLLPなどの多様な事業体に対応していくためには、立法面での基本的な見直しが必要であるといわれています。
2. 日本版LLP制度の論点
日本版LLP研究会における検討項目は、①有限責任制の導入と債権者保護、②事業体として活用する上での手当て、③税制上の論点、の三点。具体的には、以下のような項目が話し合われる予定です。
①有限責任制の導入と債権者保護
法人格を有しない組合への有限責任制付与の可能性
債権者保護に関する措置(責任財産充実、名称制限、開示)
組合債務と出資者の有限責任との関係
②事業体として活用する上での手当て
現行の民法組合でも問題とならないと考える事項(契約行為の主体・訴訟当事者能力等)
登記・登録制度に関する措置
許可・認可・届出制度に関する措置
③税制上の論点
租税回避行為の防止
共同事業性の確保( 図4 参照)
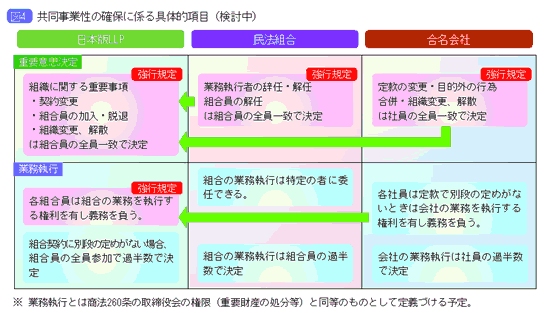
縛りがきつい!?経産省案
経産省案は、「①有限責任制の導入と債権者保護」の中で、「出資者=構成員」を有限責任とすることによって、出資者のリスクを制限し、事業への参加を容易にするとしています。このため、会社法現代化で提案されているLLCや投資事業有限責任組合における債権者保護規定を参考にしつつ、「適切な債権者保護規定を講じる」としています。
また、「②事業体として活用する上での手当て」の中で、法人格を持たない組合が事業を行うことについて、組合の代表者(業務執行組合員)名義で契約を結ぶことや、組合自身が訴訟行為を行うことなどは「現行の民法組合でも問題とならないと考える事項」としながら、不動産登記制度等の財産の公示手続きにおいて、組合が手続主体になれない等の問題が存在するため、「①登記・登録制度、②許可・認可・届出制度(営業の禁止・制限の解除)について、LLP法で新たに措置を行う予定」としています。
さらに、「③税制上の論点」の中では、日本版LLPが構成員課税となることから、「民法組合の柔軟な内部規定をそのまま準用すると、業務に参加しない出資者が多数存在するといったような法人と同様のLLPの組成も可能」と指摘。業務執行や意思決定に関して、 図4 のような「構成員の事業参加を強制する共同事業性の確保のための措置を講じる」ことを提案しています。
3. 海外のLLPってどんな制度?
Q1 アメリカのLLPはどんな制度なの?
米国LLPは、経営に参加するジェネラルパートナーシップについて、すべてのパートナーに有限責任を認める形態です。1991年、テキサス州において、無限連帯責任を求められていた法律事務所や会計事務所等の専門職の団体を対象に、不法行為に関与しないパートナーには有限責任を認める仕組み(自らの行為に基づく責任は無限責任)として開始され、全米に広がりました。州により有限責任となる範囲に制限がありますが、ニューヨーク州のLLPは全パートナーにほぼ完全な有限責任を認めており、LLCと実態上の差異はなくなりつつあります。
Q2 アメリカのLLP・LLCは、なぜ普及したの?
米国内国歳入庁は1988年、「キントナー規則」を公表し、LLCについてもその要件を満たせば、税務上、会社ではなくパートナーシップとして扱うことを明らかにしました。また1997年、チェック・ザ・ボックス規則を導入し、LLPやLLCの事業者が法人課税とパススルー課税のいずれかを選択できることとなり、普及に拍車がかかりました。
Q3 イギリスのLLPはどんな制度なの?
2000年に制定された新しい制度です。法人格を有し、パートナーは有限責任によっています。従来のパートナーシップの組織面における柔軟性に有限責任制を付加した制度です。法人格を有しますが、税制面では特別措置として、従来のパートナーシップへのパススルー課税を踏襲しています。ただ、LLPが清算段階に入った場合には、課税上も法人として取扱われます。また、非営利活動LLPの場合も、実務上の要請に基づき、課税上も法人として取扱われます。職業専門家が有限責任で組織運営したいとの要請により制定されましたが、あらゆる事業において用いることができるよう法整備されました。2001年の施行以来、現在までに8,400のLLPが登記されています。
Q4 シンガポールでもLLPができるって本当?
本当です。創業や高度サービス産業の振興のために、現在、創設を検討しているところです。アメリカのLLCや、イギリスのLLPを参考として、2004年中に創設が予定されています。
投資事業有限責任組合とLLPの関係
平成10年11月に施行された「中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律」は、業務執行を行わない組合員が負う責任を出資額にとどめることを法的に担保し、幅広い投資家層による中小・ベンチャー企業への資金供給を促進するものです。平成16年4月には、「投資事業有限責任組合契約に関する法律(略称:ファンド法)」に改正され、投資事業有限責任組合の投資範囲を中小ベンチャー企業だけにとどめず、大企業や公開企業にまで拡充されました。
今回、経産省が創設に向けて動き出した日本版LLP制度は、その事業範囲を「投資」だけでなく、「共同事業」に拡大するもので、「ファンド法の拡充」とも位置付けられます。
なお、イギリスでは、「投資LLPについての特別規定」があり、投資、特に不動産投資を行うための導管として利用されているLLPに限り、企業年金等、税の免除を受けるパートナーが税制上の不利益を被らないよう、また、税制が投資判断に影響を与えないよう、特別な措置が講じられています。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























