解説記事2004年10月25日 【実務解説】 税理士の合併・分割体験記(2)― 吸収分割の提案書 ―(2004年10月25日号・№088)
実 務 解 説
税理士の合併・分割体験記(2)― 吸収分割の提案書 ―
税理士 岡野 訓
税理士 江崎一恵
平成13年商法改正・組織再編税制のセミナーなどに何度も出席したのですが、内容を理解するには至りませんでした。改正前に実行した、合併、変態現物出資、株式の利益消却等の知識は、改正法を理解する上でむしろ邪魔になるというような話も聞き、次第に組織再編税制から遠ざかっていくようになりました。しかし、こちらの思惑に関係なく、組織再編成に係わらざるを得ない状況になることもあります。
本件では、十分な熟慮期間がなく実行するに至った様子をお話する過程で、吸収分割の仕組みと、株価計算の方法を御説明したいと思います。株価計算については、通常行っている株式評価の復習ということにもなりますが、クライアントが持ち込んだ他の会計事務所の提案にどう対応し、そしてどのような結果になったかについては、御参考になる点が多いと考えます。
1.顧客からの要請
平成14年秋、顧問先の社長から、1冊の提案書を提示されました。それは、U会計事務所が作成した、事業再構築の計画書でした。グループ会社甲社の営業のうち、経理・総務・企画部門を会社分割により乙社に移転して、グループ全体の経営を効率化することが目的であり、さらに、相続税・法人税の節税効果も期待できるというものです。
当事務所は「会社分割」に関与する予定がなかったので、まさに晴天の霹靂です。提案書を一読しても内容がよく解りません。しかしオーナーは、経営の効率化と多額の節税が見込まれるその「提案」に、すっかり乗り気になっていました。これまで、当事務所のクライアントが他の事務所に移らなかったのは、他と比較して遜色がなかったからであり、他の事務所では対応できない仕事をこなした結果、移ってきた会社もあることから、この提案書に対応できなければ、顧客を失うことになるだろうと憂慮しました。
2.会社の概要と資本関係
甲社の経営内容は良好で、毎期多額の内部留保が蓄積されています。これまでの余剰資金は、別会社丙社の土地・建物の取得に充てられ、丙社は、それを関係会社・一般利用者に貸し付ける不動産賃貸業を行って、順調な収益を上げています。そして乙社が、甲社・丙社の株を所有し、オーナー一族(以下オーナーと言います)が、3社の株式を直接・間接に100%保有している、という関係になっています。
会社の概況と、オーナー・関連会社の株の保有状況は、図1のようになっています。
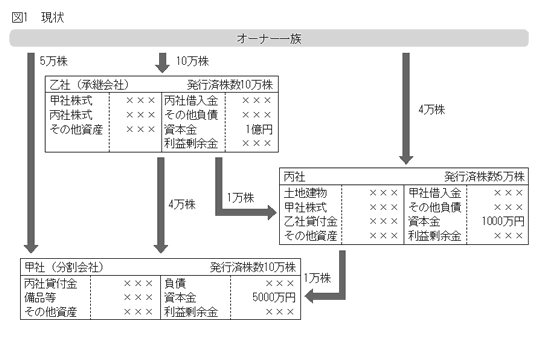
3.提案書の内容と検討事項
①移転する事業
グループ経営を効率化するために、甲社の企画・総務・経理部門の事業を移転します。これに携わる従業員を50人以上移籍し、移転部門に係る、丙社貸付金・備品等を移転します。グループ全体の集中管理が目的ですから、乙社において管理・運用することが望ましい資産が対象になります。
分割後の乙社の事業収益は、企画部門の売上、総務・経理部門のアウトソーシング収益、貸付金利息などになります。
②税制適格か否かの検討
甲社の資産を乙社に移転する見返りに、乙社は、甲社の株主に対して新株を発行します。この形が「分割型吸収分割」です。税制適格の場合は課税問題が生じませんが、非適格の場合は、分割法人である甲社に移転資産の譲渡益課税が行われ、また、乙社株の交付を受ける分割会社の株主に、多額のみなし配当課税が発生することになります。
税法上、適格か非適格かについては、法令に規定される要件を満たしているかどうかの判定を行うことになりますが、ここで議論になるのが、i)本件が、商法上、会社分割に該当するかということと、ii)そもそも、商法上の会社分割に該当することが、税務上も要求されるのかということです。
しかし、平成12年商法改正により創設された会社分割法制を受けての税法である以上、商法上の会社分割に該当することが前提である、という主張に立ったとき、本件が、商法上の会社分割に該当するかどうかの判断に当たっては、イ)移転部門の業務を「営業」とみなすことができるのか、ロ)移転した資産が会社分割の対象となるのか、の2点についての検証が必要になります。
4.会社分割後の状態
会社分割後の会社の概要と株式保有関係は、図2のようになります。
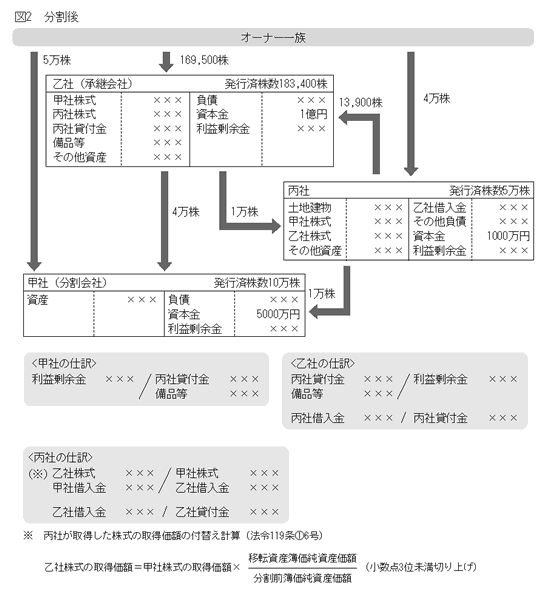
提案書によれば、グループ経営効率化のために組織再編成を行うと、結果として、相続税・法人税の節税が可能になるということです。
会社分割後のオーナーの所有株式の相続税評価額が、約12億円減少する試算結果が出ていますので、まず、どのような計算過程を経て株価が減少するのか、提案書に提示されているその節税効果をご紹介します。
5.分割前と分割後の株価の比較
《1》3社の株式の相続税評価額(現状)
■甲社(分割会社)株の相続税評価額
従業員が100人以上であるため、大会社となり、類似業種比準価額65,280円が1株当りの相続税評価額になります。
相評
移転部門の資産 10,000,000千円
その他資産 13,400,000千円
負債 △7,000,000千円
純資産価額 16,400,000千円
1株当りの純資産価額 149,720円
類似業種比準価額 65,280円
■乙社(承継会社)株の相続税評価額
簿価総資産価額が約2億円、従業員1名、1年間の取引金額が8000万円未満であるため、小会社に該当し、さらに、株式保有割合が50%以上であるため「株式保有特定会社」に該当します。S1とS2の合計が純資産価額より低いため、17,639円が1株当りの相続税評価額になります。
相評
甲社株式 2,611,200千円
丙社株式 304,460千円
その他資産 100,000千円
負債 △50,000千円
純資産価額 2,965,660千円
1株当りの純資産価額 17,793円
S1とS2の合計 17,639円
■丙社株の相続税評価額
会社の規模は「中会社」に該当し、1株当りの相続税評価額は29,396円になります。(ただし、乙社株の相評を計算する場合の丙社株の評価額(出資金評価額)は、42%控除前の株価である30,446円になります。)
相評
土地建物他 9,847,200千円
甲社株式 652,800千円
負債 △8,000,000千円
純資産価額 2,500,000千円
1株当りの純資産価額 45,800円
類似業種比準価額 23,928円
Lの割合=0.75
《2》オーナーの所有株式の相続税評価額(現状)
上記により、オーナーの所有する3社株式の合計は、6,203,740千円になります。
持株数 相評
甲社株 50,000株 @65,280 3,264,000千円
乙社株 100,000株 @17,639 1,763,900千円
丙社株 40,000株 @29,396 1,175,840千円
合計6,203,740千円
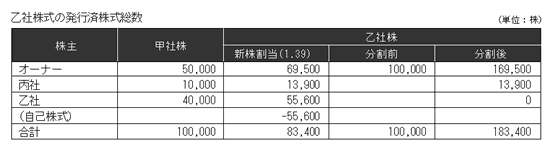
《3》分割比率の算定
乙社は、甲社から承継する移転部門の資産(負債は考慮しないこととします)の対価として新株を発行しますが、分割型分割の場合には、分割会社の従来の株主の持分比率に応じて株式の交付がなされることが要求されています。分割交付比率は、「1株当りの分割部分の価額÷承継会社の1株の価額」です。
【1株当りの分割部分の価額】
移転部門の資産の時価 10,000,000千円÷100,000株=100,000円
【承継会社の1株当りの時価純資産価額】
甲社株式 6,360,000千円 (※1)
丙社株式 778,000千円 (※2)
その他資産 100,000千円
負債 △50,000千円
純資産価額 7,188,000千円
発行済株式数 10万株
1株当り時価純資産価額 71,880円
※1(甲社株式の時価)
移転部門の資産の時価 10,000,000千円+その他資産の時価12,900,000千円-負債7,000,000千円=時価純資産価額15,900,000千円/10万株=@159,000円
※2(丙社株式の時価)
土地建物他の時価10,300,000千円+甲社株式の時価1,590,000千円-負債8,000,000千円=3,890,000千円/5万株=@77,800円
分割比率=(100,000円/71,880円)≒1.39
乙社が、甲社の株主に、その所有する甲社株1株に対して、1.39株の乙社株を発行する場合は、下表のように、83,400株の新株が発行され、分割後の乙社の発行済株式総数は183,400株になります。
《4》分割後の株価
■甲社(分割会社)株
相評
資産 13,400,000千円
負債 △7,000,000千円
純資産価額 6,400,000千円
1株当りの純資産価額 49,720円
類似業種比準価額 56,913円
乙社に従業員が55人移籍しましたが、依然100人以上の従業員数であるため、大会社のままです。類似業種比準価額よりも純資産価額の方が低いので、株価は49,720円になります。類似業種比準価額が現状より下落しているのは、比準価額の計算要素である利益積立金が減少したことにより、簿価純資産価額が下がったのが大きな原因です。
■乙社(承継会社)株
相評
承継資産 10,000,000千円
甲社株式 2,276,520千円
丙社株式 305,550千円
その他資産 100,000千円
負債 △50,000千円
純資産価額 12,632,070千円
1株当りの純資産価額 63,012円
類似業種比準価額 7,596円
現在は小会社の株式保有特定会社に該当しますが、分割後の乙社は、簿価総資産価額20億円超、従業員50人超となりますので、大会社に該当し、株価は7,596円になります。
「甲社から資産を承継したことによる簿価純資産価額の増加」「売上高の増加による年利益金額の増加」は、類似業種比準価額を増加させる要因になります。
また、1株当りの比準価額の計算の基となる「類似業種の株価」は、評価会社の事業が該当する業種目によって変わります。業種目は1年間の取引金額に基づいて判定されるため、乙社株式の「業種目番号」が変更になる可能性があります。
■丙社株
相評
土地建物他 9,847,200千円
甲社株式 569,130千円
乙社株式 105,584千円
負債 △8,000,000千円
純資産価額 2,521,914千円
1株当りの純資産価額 46,054円
類似業種比準価額 23,928円
Lの割合=0.75
相続税評価額は、29,459円になります。
《5》オーナーの所有株式の相続税評価額(分割後)
持株数 分割後の相評
甲社株 50,000株 @49,720円 2,486,000千円
乙社株 169,500株 @7,596円 1,287,522千円
丙社株 40,000株 @29,459円 1,178,360千円
合計4,951,882千円
《6》分割前と分割後の株式の相続税評価額の比較
分割前の相続税評価額は6,203,740千円でしたが、分割後は4,951,882千円になりますので、1,251,858千円減少するという結果になります。
6.同族会社の特別税率の不適用
①留保金課税の停止措置の導入
平成15年度税制改正で「同族会社の留保金課税停止措置」が新設されました。資本金1億円以下で、自己資本比率が50%以下である場合は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する各事業年度において、留保金課税が停止されます(措置法第68条の2第1項第4号)。分割法人甲社は、自己資本比率が相当高いため、この停止措置の適用を受けることはできません。
②分割型吸収分割を行った場合
しかし、例えばB/Sが次のような場合、営業の移転に伴い、乙社(承継法人)に、資産10.000,000千円を移転すると、分割法人の自己資本比率は50%以下になります。各年度ごとに判定して要件を満たせば、3年間、留保金課税が停止されることになります。
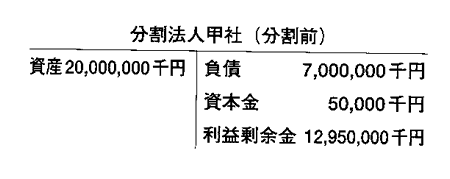
7.会社分割の実行
関係会社間の不動産賃貸借及び資金の貸借等に係る事務処理は相当の負担になっておりましたし、乙社が財務・経理を集中管理することによって、グループ経営を効率化する必要性も確かに認められます。その結果として多額の節税効果が見込まれるということであれば、顧客としては、それを実行してくれる会計事務所を選ぶという結論になるはずです。
グループ事業を再構築する方法は他にもあるのかもしれませんが、オーナーの要望は、すぐにでも実行したいということでしたので、当事務所のほうで、検討事項をクリアーした上、組織再編成に協力したいと申し出ました。諸問題の検証と実行の過程については、次号でご説明したいと思います。
◆参考文献
田中義幸「企業組織再編の会計処理と税務申告」税務弘報2001.8
岡野 訓 (おかのさとる)
平成13年税理士登録
平成14年岡野会計事務所開設
【著書】
『税務会計実務全書(共著)』(日本実業出版社)
『事業承継とその税務対策』(金融経済新聞社)
江崎一恵 (えざきかずえ)
昭和61年税理士登録
平成14年江崎一恵税理士事務所開設
【著書(共著)】
『国税裁決例実務活用マニュアル』(ぎょうせい)
『民事再生法と税理士の実務』(税務研究会出版局)
税理士の合併・分割体験記(2)― 吸収分割の提案書 ―
税理士 岡野 訓
税理士 江崎一恵
平成13年商法改正・組織再編税制のセミナーなどに何度も出席したのですが、内容を理解するには至りませんでした。改正前に実行した、合併、変態現物出資、株式の利益消却等の知識は、改正法を理解する上でむしろ邪魔になるというような話も聞き、次第に組織再編税制から遠ざかっていくようになりました。しかし、こちらの思惑に関係なく、組織再編成に係わらざるを得ない状況になることもあります。
本件では、十分な熟慮期間がなく実行するに至った様子をお話する過程で、吸収分割の仕組みと、株価計算の方法を御説明したいと思います。株価計算については、通常行っている株式評価の復習ということにもなりますが、クライアントが持ち込んだ他の会計事務所の提案にどう対応し、そしてどのような結果になったかについては、御参考になる点が多いと考えます。
1.顧客からの要請
平成14年秋、顧問先の社長から、1冊の提案書を提示されました。それは、U会計事務所が作成した、事業再構築の計画書でした。グループ会社甲社の営業のうち、経理・総務・企画部門を会社分割により乙社に移転して、グループ全体の経営を効率化することが目的であり、さらに、相続税・法人税の節税効果も期待できるというものです。
当事務所は「会社分割」に関与する予定がなかったので、まさに晴天の霹靂です。提案書を一読しても内容がよく解りません。しかしオーナーは、経営の効率化と多額の節税が見込まれるその「提案」に、すっかり乗り気になっていました。これまで、当事務所のクライアントが他の事務所に移らなかったのは、他と比較して遜色がなかったからであり、他の事務所では対応できない仕事をこなした結果、移ってきた会社もあることから、この提案書に対応できなければ、顧客を失うことになるだろうと憂慮しました。
2.会社の概要と資本関係
甲社の経営内容は良好で、毎期多額の内部留保が蓄積されています。これまでの余剰資金は、別会社丙社の土地・建物の取得に充てられ、丙社は、それを関係会社・一般利用者に貸し付ける不動産賃貸業を行って、順調な収益を上げています。そして乙社が、甲社・丙社の株を所有し、オーナー一族(以下オーナーと言います)が、3社の株式を直接・間接に100%保有している、という関係になっています。
会社の概況と、オーナー・関連会社の株の保有状況は、図1のようになっています。
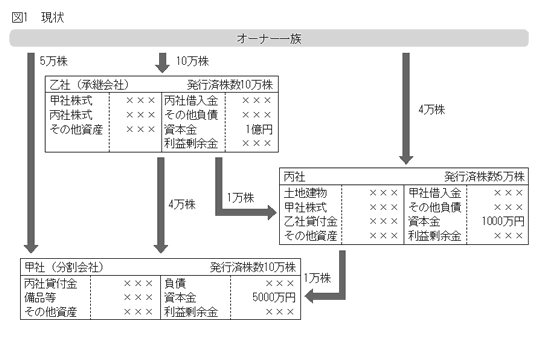
3.提案書の内容と検討事項
①移転する事業
グループ経営を効率化するために、甲社の企画・総務・経理部門の事業を移転します。これに携わる従業員を50人以上移籍し、移転部門に係る、丙社貸付金・備品等を移転します。グループ全体の集中管理が目的ですから、乙社において管理・運用することが望ましい資産が対象になります。
分割後の乙社の事業収益は、企画部門の売上、総務・経理部門のアウトソーシング収益、貸付金利息などになります。
②税制適格か否かの検討
甲社の資産を乙社に移転する見返りに、乙社は、甲社の株主に対して新株を発行します。この形が「分割型吸収分割」です。税制適格の場合は課税問題が生じませんが、非適格の場合は、分割法人である甲社に移転資産の譲渡益課税が行われ、また、乙社株の交付を受ける分割会社の株主に、多額のみなし配当課税が発生することになります。
税法上、適格か非適格かについては、法令に規定される要件を満たしているかどうかの判定を行うことになりますが、ここで議論になるのが、i)本件が、商法上、会社分割に該当するかということと、ii)そもそも、商法上の会社分割に該当することが、税務上も要求されるのかということです。
しかし、平成12年商法改正により創設された会社分割法制を受けての税法である以上、商法上の会社分割に該当することが前提である、という主張に立ったとき、本件が、商法上の会社分割に該当するかどうかの判断に当たっては、イ)移転部門の業務を「営業」とみなすことができるのか、ロ)移転した資産が会社分割の対象となるのか、の2点についての検証が必要になります。
4.会社分割後の状態
会社分割後の会社の概要と株式保有関係は、図2のようになります。
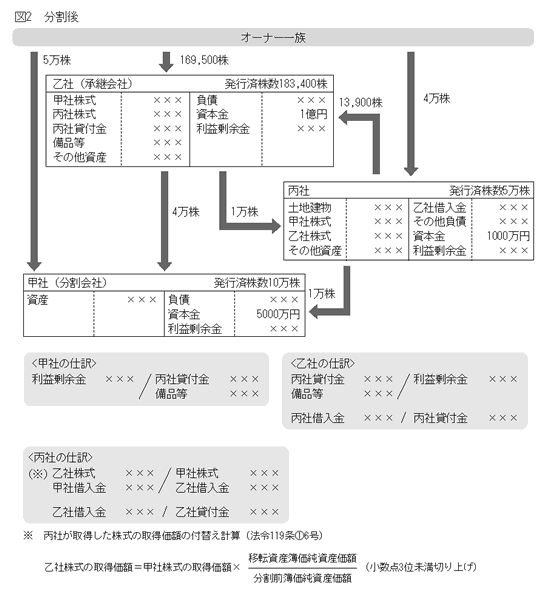
提案書によれば、グループ経営効率化のために組織再編成を行うと、結果として、相続税・法人税の節税が可能になるということです。
会社分割後のオーナーの所有株式の相続税評価額が、約12億円減少する試算結果が出ていますので、まず、どのような計算過程を経て株価が減少するのか、提案書に提示されているその節税効果をご紹介します。
5.分割前と分割後の株価の比較
《1》3社の株式の相続税評価額(現状)
■甲社(分割会社)株の相続税評価額
従業員が100人以上であるため、大会社となり、類似業種比準価額65,280円が1株当りの相続税評価額になります。
相評
移転部門の資産 10,000,000千円
その他資産 13,400,000千円
負債 △7,000,000千円
純資産価額 16,400,000千円
1株当りの純資産価額 149,720円
類似業種比準価額 65,280円
■乙社(承継会社)株の相続税評価額
簿価総資産価額が約2億円、従業員1名、1年間の取引金額が8000万円未満であるため、小会社に該当し、さらに、株式保有割合が50%以上であるため「株式保有特定会社」に該当します。S1とS2の合計が純資産価額より低いため、17,639円が1株当りの相続税評価額になります。
相評
甲社株式 2,611,200千円
丙社株式 304,460千円
その他資産 100,000千円
負債 △50,000千円
純資産価額 2,965,660千円
1株当りの純資産価額 17,793円
S1とS2の合計 17,639円
■丙社株の相続税評価額
会社の規模は「中会社」に該当し、1株当りの相続税評価額は29,396円になります。(ただし、乙社株の相評を計算する場合の丙社株の評価額(出資金評価額)は、42%控除前の株価である30,446円になります。)
相評
土地建物他 9,847,200千円
甲社株式 652,800千円
負債 △8,000,000千円
純資産価額 2,500,000千円
1株当りの純資産価額 45,800円
類似業種比準価額 23,928円
Lの割合=0.75
《2》オーナーの所有株式の相続税評価額(現状)
上記により、オーナーの所有する3社株式の合計は、6,203,740千円になります。
持株数 相評
甲社株 50,000株 @65,280 3,264,000千円
乙社株 100,000株 @17,639 1,763,900千円
丙社株 40,000株 @29,396 1,175,840千円
合計6,203,740千円
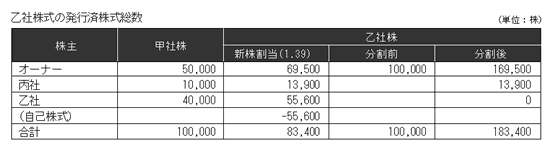
《3》分割比率の算定
乙社は、甲社から承継する移転部門の資産(負債は考慮しないこととします)の対価として新株を発行しますが、分割型分割の場合には、分割会社の従来の株主の持分比率に応じて株式の交付がなされることが要求されています。分割交付比率は、「1株当りの分割部分の価額÷承継会社の1株の価額」です。
【1株当りの分割部分の価額】
移転部門の資産の時価 10,000,000千円÷100,000株=100,000円
【承継会社の1株当りの時価純資産価額】
甲社株式 6,360,000千円 (※1)
丙社株式 778,000千円 (※2)
その他資産 100,000千円
負債 △50,000千円
純資産価額 7,188,000千円
発行済株式数 10万株
1株当り時価純資産価額 71,880円
※1(甲社株式の時価)
移転部門の資産の時価 10,000,000千円+その他資産の時価12,900,000千円-負債7,000,000千円=時価純資産価額15,900,000千円/10万株=@159,000円
※2(丙社株式の時価)
土地建物他の時価10,300,000千円+甲社株式の時価1,590,000千円-負債8,000,000千円=3,890,000千円/5万株=@77,800円
分割比率=(100,000円/71,880円)≒1.39
乙社が、甲社の株主に、その所有する甲社株1株に対して、1.39株の乙社株を発行する場合は、下表のように、83,400株の新株が発行され、分割後の乙社の発行済株式総数は183,400株になります。
《4》分割後の株価
■甲社(分割会社)株
相評
資産 13,400,000千円
負債 △7,000,000千円
純資産価額 6,400,000千円
1株当りの純資産価額 49,720円
類似業種比準価額 56,913円
乙社に従業員が55人移籍しましたが、依然100人以上の従業員数であるため、大会社のままです。類似業種比準価額よりも純資産価額の方が低いので、株価は49,720円になります。類似業種比準価額が現状より下落しているのは、比準価額の計算要素である利益積立金が減少したことにより、簿価純資産価額が下がったのが大きな原因です。
■乙社(承継会社)株
相評
承継資産 10,000,000千円
甲社株式 2,276,520千円
丙社株式 305,550千円
その他資産 100,000千円
負債 △50,000千円
純資産価額 12,632,070千円
1株当りの純資産価額 63,012円
類似業種比準価額 7,596円
現在は小会社の株式保有特定会社に該当しますが、分割後の乙社は、簿価総資産価額20億円超、従業員50人超となりますので、大会社に該当し、株価は7,596円になります。
「甲社から資産を承継したことによる簿価純資産価額の増加」「売上高の増加による年利益金額の増加」は、類似業種比準価額を増加させる要因になります。
また、1株当りの比準価額の計算の基となる「類似業種の株価」は、評価会社の事業が該当する業種目によって変わります。業種目は1年間の取引金額に基づいて判定されるため、乙社株式の「業種目番号」が変更になる可能性があります。
■丙社株
相評
土地建物他 9,847,200千円
甲社株式 569,130千円
乙社株式 105,584千円
負債 △8,000,000千円
純資産価額 2,521,914千円
1株当りの純資産価額 46,054円
類似業種比準価額 23,928円
Lの割合=0.75
相続税評価額は、29,459円になります。
《5》オーナーの所有株式の相続税評価額(分割後)
持株数 分割後の相評
甲社株 50,000株 @49,720円 2,486,000千円
乙社株 169,500株 @7,596円 1,287,522千円
丙社株 40,000株 @29,459円 1,178,360千円
合計4,951,882千円
《6》分割前と分割後の株式の相続税評価額の比較
分割前の相続税評価額は6,203,740千円でしたが、分割後は4,951,882千円になりますので、1,251,858千円減少するという結果になります。
6.同族会社の特別税率の不適用
①留保金課税の停止措置の導入
平成15年度税制改正で「同族会社の留保金課税停止措置」が新設されました。資本金1億円以下で、自己資本比率が50%以下である場合は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する各事業年度において、留保金課税が停止されます(措置法第68条の2第1項第4号)。分割法人甲社は、自己資本比率が相当高いため、この停止措置の適用を受けることはできません。
②分割型吸収分割を行った場合
しかし、例えばB/Sが次のような場合、営業の移転に伴い、乙社(承継法人)に、資産10.000,000千円を移転すると、分割法人の自己資本比率は50%以下になります。各年度ごとに判定して要件を満たせば、3年間、留保金課税が停止されることになります。
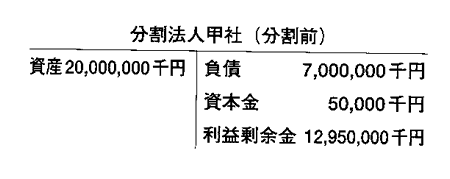
7.会社分割の実行
関係会社間の不動産賃貸借及び資金の貸借等に係る事務処理は相当の負担になっておりましたし、乙社が財務・経理を集中管理することによって、グループ経営を効率化する必要性も確かに認められます。その結果として多額の節税効果が見込まれるということであれば、顧客としては、それを実行してくれる会計事務所を選ぶという結論になるはずです。
グループ事業を再構築する方法は他にもあるのかもしれませんが、オーナーの要望は、すぐにでも実行したいということでしたので、当事務所のほうで、検討事項をクリアーした上、組織再編成に協力したいと申し出ました。諸問題の検証と実行の過程については、次号でご説明したいと思います。
◆参考文献
田中義幸「企業組織再編の会計処理と税務申告」税務弘報2001.8
岡野 訓 (おかのさとる)
平成13年税理士登録
平成14年岡野会計事務所開設
【著書】
『税務会計実務全書(共著)』(日本実業出版社)
『事業承継とその税務対策』(金融経済新聞社)
江崎一恵 (えざきかずえ)
昭和61年税理士登録
平成14年江崎一恵税理士事務所開設
【著書(共著)】
『国税裁決例実務活用マニュアル』(ぎょうせい)
『民事再生法と税理士の実務』(税務研究会出版局)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















