解説記事2004年11月22日 【ニュース特集】 税理士会の裁判外紛争手続とADR法案の関係に迫る!(2004年11月22日号・№091)
ニュース特集
税賠リスク増大!?ビジネスチャンス!?
税理士会の裁判外紛争手続とADR法案の関係に迫る!
平成14年4月に施行された改正税理士法で新たに創設された「紛議調停制度」をご存知でしょうか?これは、税理士が行った業務に関連して紛争が生じてしまったときに、裁判外紛争解決手続の一つとして、各税理士会が調停を行う制度のことです。
「紛議調停制度」に関連する法律として、10月12日に、ADR法案(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案)が国会に提出されました。この法案は、裁判外紛争解決手続についての基本理念を定め、上記の「紛議調停制度」のような民間型ADRに対し、一定の要件の元に認証の制度を設けるという制度です。
今回の特集は、税理士法における「紛議調停制度」とADR法案の関係などについて解説します。
1 「紛議調停制度」ってなあに?
この制度は、税理士が行った業務に関連して紛争が生じてしまったときに、その税理士が所属する各税理士会が、会員である税理士または紛争の当事者や関係人の請求により紛議の調停を申し立てることができるという制度で、裁判外紛争解決手続の一つとして税理士法の規定(第49条の10)に基づいて行われるものです。例えば、税理士と業務委嘱契約を結んでいる依頼者が、税理士に対して調停を申し立てた場合の紛議の調停関係図は下記のようになります( 図1 参照)。
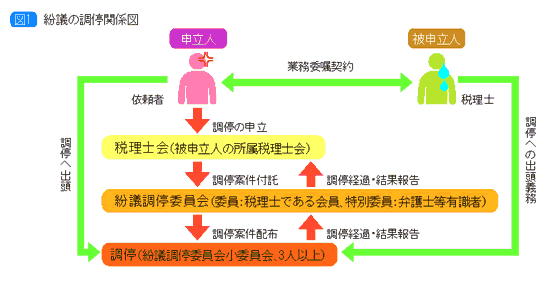
申立てができるのはどんな紛争なの?
各税理士会に紛議の調停の申立てができる紛争は、各税理士会の会員(税理士法人を含む)が、「税理士」または「税理士法人」の名称を用いて、日本国内において行った業務に関し生じたものです。つまり、「税理士」以外の資格で行った業務や海外で行った業務に関して生じた紛争は、調停の申立てを行うことができません。また、例えば、東京に住んでいる依頼者であっても、東京税理士会の会員以外の税理士または税理士法人以外との間で紛争が生じた場合は、その税理士または税理士法人が所属する税理士会に対し調停の申立てを行わなければなりません。
具体的な事例としては、①顧問契約を解約された税理士による嫌がらせに耐えかねた会社経営者からの申立て、②担当顧客を引き連れたまま退職した税理士に対する所長税理士からの損害賠償の申立て、③顧問税理士が報酬額に見合う職務を果たしていないとして、会社経営者が税理士に対し報酬の返還を求める申立てなどがあったようです。
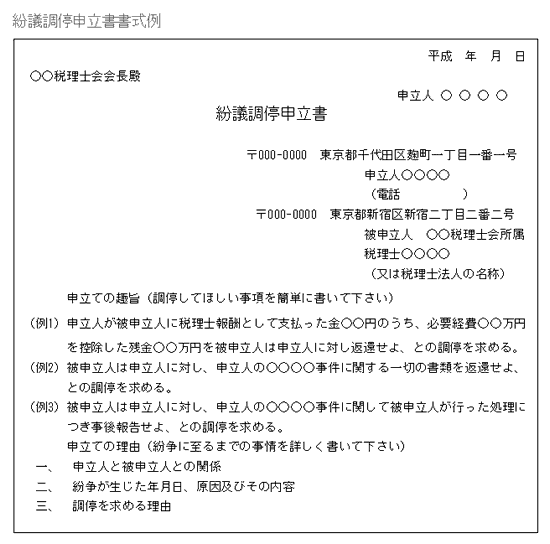
申立てするにはどうしたらいいの?
次に、具体的な申立て手続についてみていきましょう。紛議の調停を申し立てるためには、被申立人が所属する税理士会に申立書(右:申立書書式例参照)を提出する必要があります。申立書の様式は任意ですが、書式例を参考にして、紛議の相手方の氏名、申立ての趣旨、理由等をA4判2~3枚程度にまとめ、申立人が個人の場合は住民票1通、法人の場合は登記簿謄本を添付する必要があります。なお、申立書は、証拠書類も含め、被申立人の数プラス1通(コピーでも可)を用意する必要があります。
調停で成立した和解には効力があるの?
税理士会の調停により成立した和解は、民法(696条)上の和解としての効力を有することになります。しかし、現行の民事執行制度ではADRによる和解が成立した結果には執行力が付与されていません。将来の実現を確実に確保しようとする場合は、他の手続(即決和解、公証仲裁)を追加的に行う必要があります。なお、日税連は、全国の税理士会が同一ルールで対処できるよう、標準的な「紛議調停規則」を制定し、各税理士会ではほぼこれにならった規則を設けています。
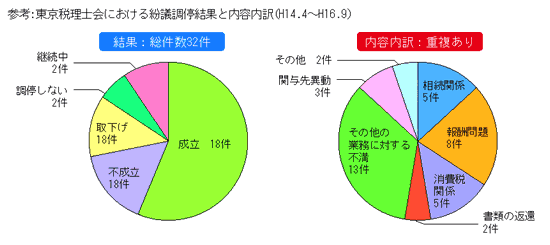
2 紛議調停制度とADR法案はどう関係しているの?
民間型ADRである税理士会の「紛議調停委員会」と、「ADR法案」とはどのように関係するのでしょうか?
ADR法案ってどんな法律案なの?
ADR法案は、裁判外紛争解決手続について、基本理念等を定め、税理士会の「紛議調停委員会」のような民間型ADRの業務に対して法務大臣の認証の制度を設けようとする制度です。これと同時に、時効の中断等、法律上の効果を付与するとしています。これにより、暴力団員等、一定の事由に該当する「民間型ADR」は、認証を受けることができない一方、認証を受けた事業者は、これを掲げることで、利用者が選択する際の目安を提供できることになります。また、認証ADRにおける紛争解決手続の終了後、1ヶ月以内に訴訟手続に移行する等、一定の要件を満たす場合には、認証ADRにおける請求時に遡って時効中断の効力が発生するなど、法律上の効果が付与されます。つまり、時効の期間などを気にせず安心してADRによる交渉を進められることになるのです。
どんなADRが認証されるの?
認証の基準としては、①業務対象となる紛争範囲に応じて適切なあっせん人・調停人を選任するための方法、②そのあっせん人・調停人が紛争当事者と利害関係を有する場合等にその人を排除するための方法、③弁護士でない者があっせん人・調停人となる場合の弁護士の関与に関する措置等、を定めていることなどが必要とされています。また、認証の欠格事由として、「暴力団員等一定の事由に該当する者は認証を受けることができないものとする」と明記されています。
なお、ADR法案は、「公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行するものとする」とされています。
税理士は認証ADRにおける「代理権」を取得できるか!?
~日税連が司法制度改革推進本部へ意見書を提出~
日税連は、ADR法の施行に向け、税理士会の「紛議調停委員会」が認証ADRとなることの可否について調査研究を開始しています。しかし、日税連が検討を進めているのは、これだけではありません。
ADR法の施行により、税理士会の「紛議調停委員会」のほかにも、多種多様なADRが創設されることが予想されます。それらで調停が行われる紛争の中には、①租税に関する法令の適用に関する紛争(納税義務者と税務官公署との紛争を除く)や、②財産の相続又は贈与に関する紛争が出てくることも予想されます。そこで、日税連は、多種多様なADRの場で、税務の専門家である税理士がADR手続実施者の一人として紛争の当事者の代理人として活用(下図参照)されるよう、司法制度改革推進本部に対し『「税理士に対する裁判外紛争解決手続における代理権付与」についての意見』を提出し、①や②のような紛争における税理士への代理権の付与を要望しています。
認証ADRにおける代理権を「誰に付与するか」という問題は、司法制度改革推進本部により、今月末には正式決定される見通しです。
現段階では、訴訟代理権のある弁護士や、一部の訴訟で代理権が認められている司法書士や弁理士に加え、訴訟代理権のない社労士や土地家屋調査士にもADRにおける代理権が認められる方向だといわれています。しかし、税理士や不動産鑑定士、行政書士については、「実態を見極めて再度検討する」とされ、まだ、流動的な状態です。
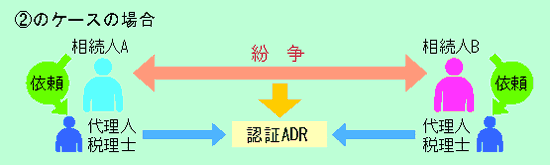
税賠リスク増大!?ビジネスチャンス!?
税理士会の裁判外紛争手続とADR法案の関係に迫る!
平成14年4月に施行された改正税理士法で新たに創設された「紛議調停制度」をご存知でしょうか?これは、税理士が行った業務に関連して紛争が生じてしまったときに、裁判外紛争解決手続の一つとして、各税理士会が調停を行う制度のことです。
「紛議調停制度」に関連する法律として、10月12日に、ADR法案(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律案)が国会に提出されました。この法案は、裁判外紛争解決手続についての基本理念を定め、上記の「紛議調停制度」のような民間型ADRに対し、一定の要件の元に認証の制度を設けるという制度です。
今回の特集は、税理士法における「紛議調停制度」とADR法案の関係などについて解説します。
1 「紛議調停制度」ってなあに?
この制度は、税理士が行った業務に関連して紛争が生じてしまったときに、その税理士が所属する各税理士会が、会員である税理士または紛争の当事者や関係人の請求により紛議の調停を申し立てることができるという制度で、裁判外紛争解決手続の一つとして税理士法の規定(第49条の10)に基づいて行われるものです。例えば、税理士と業務委嘱契約を結んでいる依頼者が、税理士に対して調停を申し立てた場合の紛議の調停関係図は下記のようになります( 図1 参照)。
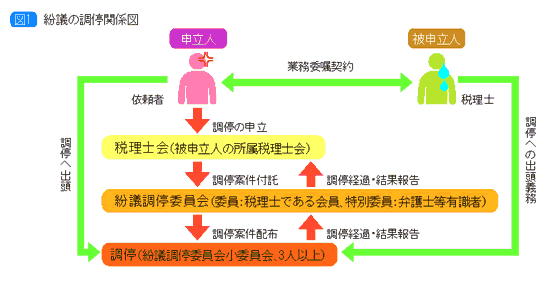
申立てができるのはどんな紛争なの?
各税理士会に紛議の調停の申立てができる紛争は、各税理士会の会員(税理士法人を含む)が、「税理士」または「税理士法人」の名称を用いて、日本国内において行った業務に関し生じたものです。つまり、「税理士」以外の資格で行った業務や海外で行った業務に関して生じた紛争は、調停の申立てを行うことができません。また、例えば、東京に住んでいる依頼者であっても、東京税理士会の会員以外の税理士または税理士法人以外との間で紛争が生じた場合は、その税理士または税理士法人が所属する税理士会に対し調停の申立てを行わなければなりません。
具体的な事例としては、①顧問契約を解約された税理士による嫌がらせに耐えかねた会社経営者からの申立て、②担当顧客を引き連れたまま退職した税理士に対する所長税理士からの損害賠償の申立て、③顧問税理士が報酬額に見合う職務を果たしていないとして、会社経営者が税理士に対し報酬の返還を求める申立てなどがあったようです。
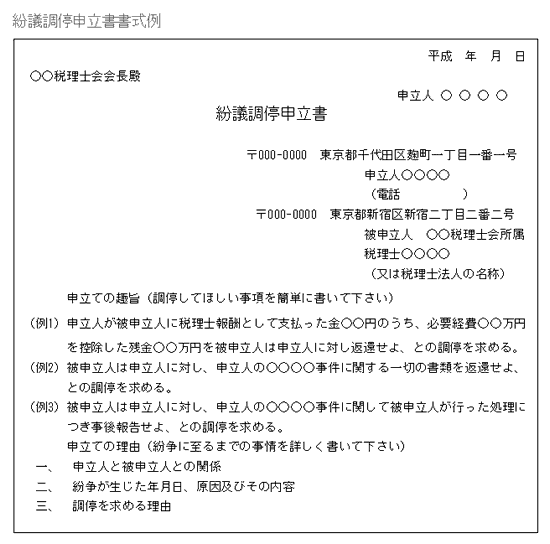
申立てするにはどうしたらいいの?
次に、具体的な申立て手続についてみていきましょう。紛議の調停を申し立てるためには、被申立人が所属する税理士会に申立書(右:申立書書式例参照)を提出する必要があります。申立書の様式は任意ですが、書式例を参考にして、紛議の相手方の氏名、申立ての趣旨、理由等をA4判2~3枚程度にまとめ、申立人が個人の場合は住民票1通、法人の場合は登記簿謄本を添付する必要があります。なお、申立書は、証拠書類も含め、被申立人の数プラス1通(コピーでも可)を用意する必要があります。
調停で成立した和解には効力があるの?
税理士会の調停により成立した和解は、民法(696条)上の和解としての効力を有することになります。しかし、現行の民事執行制度ではADRによる和解が成立した結果には執行力が付与されていません。将来の実現を確実に確保しようとする場合は、他の手続(即決和解、公証仲裁)を追加的に行う必要があります。なお、日税連は、全国の税理士会が同一ルールで対処できるよう、標準的な「紛議調停規則」を制定し、各税理士会ではほぼこれにならった規則を設けています。
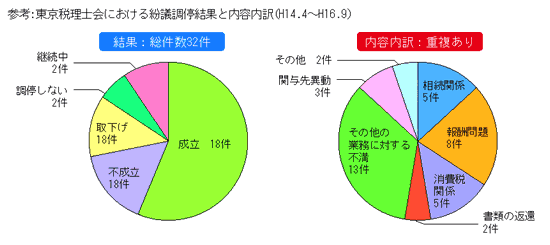
2 紛議調停制度とADR法案はどう関係しているの?
民間型ADRである税理士会の「紛議調停委員会」と、「ADR法案」とはどのように関係するのでしょうか?
ADR法案ってどんな法律案なの?
ADR法案は、裁判外紛争解決手続について、基本理念等を定め、税理士会の「紛議調停委員会」のような民間型ADRの業務に対して法務大臣の認証の制度を設けようとする制度です。これと同時に、時効の中断等、法律上の効果を付与するとしています。これにより、暴力団員等、一定の事由に該当する「民間型ADR」は、認証を受けることができない一方、認証を受けた事業者は、これを掲げることで、利用者が選択する際の目安を提供できることになります。また、認証ADRにおける紛争解決手続の終了後、1ヶ月以内に訴訟手続に移行する等、一定の要件を満たす場合には、認証ADRにおける請求時に遡って時効中断の効力が発生するなど、法律上の効果が付与されます。つまり、時効の期間などを気にせず安心してADRによる交渉を進められることになるのです。
どんなADRが認証されるの?
認証の基準としては、①業務対象となる紛争範囲に応じて適切なあっせん人・調停人を選任するための方法、②そのあっせん人・調停人が紛争当事者と利害関係を有する場合等にその人を排除するための方法、③弁護士でない者があっせん人・調停人となる場合の弁護士の関与に関する措置等、を定めていることなどが必要とされています。また、認証の欠格事由として、「暴力団員等一定の事由に該当する者は認証を受けることができないものとする」と明記されています。
なお、ADR法案は、「公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日から施行するものとする」とされています。
税理士は認証ADRにおける「代理権」を取得できるか!?
~日税連が司法制度改革推進本部へ意見書を提出~
日税連は、ADR法の施行に向け、税理士会の「紛議調停委員会」が認証ADRとなることの可否について調査研究を開始しています。しかし、日税連が検討を進めているのは、これだけではありません。
ADR法の施行により、税理士会の「紛議調停委員会」のほかにも、多種多様なADRが創設されることが予想されます。それらで調停が行われる紛争の中には、①租税に関する法令の適用に関する紛争(納税義務者と税務官公署との紛争を除く)や、②財産の相続又は贈与に関する紛争が出てくることも予想されます。そこで、日税連は、多種多様なADRの場で、税務の専門家である税理士がADR手続実施者の一人として紛争の当事者の代理人として活用(下図参照)されるよう、司法制度改革推進本部に対し『「税理士に対する裁判外紛争解決手続における代理権付与」についての意見』を提出し、①や②のような紛争における税理士への代理権の付与を要望しています。
認証ADRにおける代理権を「誰に付与するか」という問題は、司法制度改革推進本部により、今月末には正式決定される見通しです。
現段階では、訴訟代理権のある弁護士や、一部の訴訟で代理権が認められている司法書士や弁理士に加え、訴訟代理権のない社労士や土地家屋調査士にもADRにおける代理権が認められる方向だといわれています。しかし、税理士や不動産鑑定士、行政書士については、「実態を見極めて再度検討する」とされ、まだ、流動的な状態です。
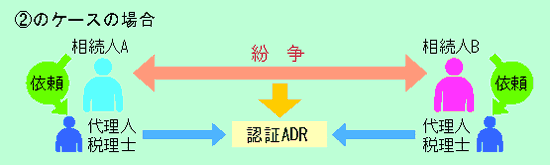
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























