解説記事2005年01月24日 【実務解説】 実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」の解説(2005年1月24日号・№099)
実 務 解 説
実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」の解説
企業会計基準委員会 研究員 中居正明
1 はじめに
企業会計基準委員会(以下「ASB」という。)から、平成16年11月30日に、実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)が公表された。本稿では、本実務対応報告の概要を中心に解説する。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを申し添える。
2 検討の経緯と範囲
平成16年4月、ASBは排出権の取得に関する会計処理の取扱いを明確にする必要性があると判断し、専門委員会を設置して会計処理の検討を開始した。それ以降、計5回の専門委員会が開催され、排出量取引に係る参考人の方々との意見交換や、専門委員、関係省庁の方々との議論を踏まえるなど検討を重ねた。ASBでは、同年9月29日に公開草案を公表し、これに対して寄せられたコメントも踏まえ、審議の結果、本実務対応報告を公表したものである。
このように、後述する京都議定書の発効を待たずに排出量取引の会計処理に関する検討が開始されたのは、既に一部の企業において自主的に京都議定書に基づくクレジット(以下「排出クレジット」という。)の取得に向けたファンド購入やプロジェクトの実施等の経済実態が先行しているという事実を踏まえてのことである。
また、本実務対応報告は、当面必要と考えられる会計処理のみを検討対象としているため、いわゆるキャップ・アンド・トレード(排出量を一定内とする義務を負い、余剰や不足については売買する仕組み)が導入されるような場合や、排出クレジットの活発な売買取引マーケットが今後整備され、非金融資産と位置付けられる排出クレジットを対象としたトレーディング目的での取引(金融投資)が行われる場合など、前提条件が変化した場合には別途検討の必要性があるとされている。
3 京都議定書の概要と我が国企業が直面する国内制度
(1) 京都議定書の概要
京都議定書自体の説明は、本稿の目的とするところではないが、以後の解説をする上での前提事項として、簡潔に言及する(脚注1)。
① 京都議定書の特徴
京都議定書の特徴は、先進国(附属書Ⅰ国)に対して、2008年から2012年における二酸化炭素などの排出量を、1990年比で欧州は8%、日本は6%削減する数値目標を定めた点や、限界コストの安い国で削減することを認めた柔軟措置を定めた点(京都メカニズム)の2つであるといわれる。
② 京都メカニズム
特に欧米に比較して1990年当時であってもエネルギー効率の高かったといわれている我が国の場合、6%の削減目標を達成するためには、補完的手段として京都議定書で定められた柔軟措置、すなわちクリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development mechanism)、共同実施(JI:Joint Implementation)及び排出量取引(Emission Trading)の活用が不可欠と言われている。この京都メカニズムのコンセプトは、地球上に存在する二酸化炭素等を削減するには、どこの地域、どこの国で削減しても効果は同じであることから、限界削減コストの安い地域、国で削減することを認めた点にある。
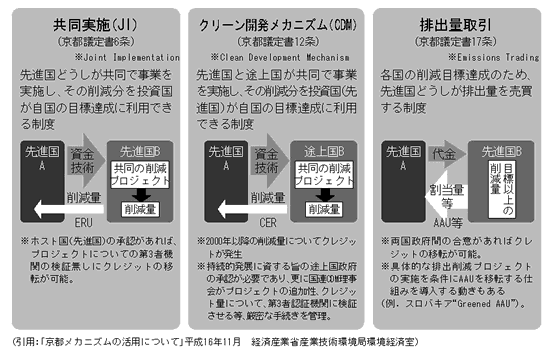
③ 国の排出量削減達成の仕組み
京都議定書で定められている国の排出量削減義務を達成するためには、実績排出量に見合う排出クレジットを国の管理する国別登録簿上の償却口座に移転しなければならない。
(2) 我が国企業が直面する国内制度と企業行動
現行の国内制度では、企業ごと又は業界ごとに排出量削減義務が課されていない。業界団体又は個別企業が、自主的な行動目標として二酸化炭素等の排出削減量を外部に公表し、毎期、その取り組み状況をフォローアップしていく形での二酸化炭素削減策が主となっている。この排出量削減に充てるために、排出クレジットを獲得しようとする企業や、将来の何らかの規制強化に備えて排出クレジット取得を行う企業がある。その一方で、国内における排出クレジット市場が今後拡大することを見越し、売り手として第三者に販売する目的で排出クレジット獲得を図る企業がある。
4 対象とされる排出クレジットとその性格
本実務対応報告では、京都メカニズムにおける排出クレジットが対象とされ、また京都メカニズム以外の排出クレジットについても、会計上の性格の類似性に鑑みて同様に会計処理を行うものとされている。会計上の性格の類似性とは、京都メカニズム以外の排出クレジットを企業が取得した場合でも、会計上、現金で購入して転売したり費消したりするという点では、京都メカニズムに基づく排出クレジットを購入する場合と変わらないことを示していると考えられる。
また、京都議定書に由来する排出クレジットの性格の特徴として、①京都議定書における国際的な約束を各締約国が履行するために用いられる数値であること、②国別登録簿においてのみ存在すること、及び③所有権の対象となる有体物ではなく、法定された無体財産権ではないことが挙げられている。その特徴を踏まえ、売買に際しては有償で取引されるという財産的価値に着目して会計上は無形固定資産に近いものと考えられるとされている。
なお、排出クレジットが、金融資産に該当するかどうかに関しては、「金融商品に係る会計基準」(以下、「金融商品会計基準」という。)第一一において具体的に例示されている金融資産の形態と類似性がない点や、排出クレジット保有者は、「金融商品会計に関する実務指針」第4項に規定する、現金を受け取る契約上の権利がない点を理由として、排出クレジットは、金融資産に該当しないものと位置付けられている。
5 会計処理の考え方
(1) 投資の性質
本実務対応報告では、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」や「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」の考え方を踏まえ、資産の評価に際して時価評価するのか、取得原価評価するのかは、資産の外形的特質(金融資産かどうかなど)によるのではなく、投資の性質によるものとされている。
ここで企業の投資は、一般に金融投資と事業投資に大別されるとした上で、金融投資は、売買市場が整備され、売却することについて事業上の制約がないものであり、時価の変動が事前に期待した成果に対応する事実と考えられるため、時価評価がなじむとされている。
他方、事業投資は、売却することについて事業上の制約があり、事前に期待する投資の成果は、投資資産の時価の変動ではなく、その後の資金の獲得であることから、取得原価評価がなじむものとされている。
(2)事業投資として扱われる排出クレジット取得に係る投資
排出クレジットの取得に係る投資は、現時点では活発に取引される売買市場が存在するとはいえないことから、たとえ時価の変動によって利益を得ることを目的としても、金融投資には該当しないものと位置付けられている。すなわち、同じ排出クレジットの保有者であっても、販売先や価格水準の決定などその保有者の経営努力により、資金流入金額は異なるものと考えられるため、本実務対応報告では、排出クレジットに係る投資は、事業投資に該当するものとされている。したがって、金融投資に該当するようなトレーディング目的での排出クレジットの獲得は、本実務対応報告の対象とされていない。
(3) 対象とされている排出クレジットの取引
本実務対応報告では、排出クレジット取得の目的を2つに場合分けし、さらに取得方法を2つに場合分けし、組み合わせにより次の4つのケースにおける会計処理が示されている。
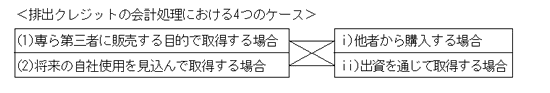
ここで(2)「将来の自社使用を見込んで取得する場合」とは、将来、自社の排出削減量に充てることを想定して排出クレジットを取得、保有するものの、自社の削減量に充てないことが明らかになったときには、第三者へ売却する可能性を残している場合をいうとされている。その上で、個々の企業に排出量削減義務が課されていないことを踏まえると、その財産的価値に着目し、資産計上することが妥当であると結論付けられている。逆に排出量削減に充てるため、保有する排出クレジットを国別登録簿の償却口座へ移転した際には、第三者への売却可能性がないことから、資産計上の根拠は失われ、費用に計上することになるとされている。
6 本実務対応報告における具体的会計処理
(1)専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合の会計処理
i)他者から購入する場合
専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合には、通常の商品の購入と同様の会計処理を行うものとされており、非金融商品である排出クレジットの売買契約が締結された段階では何ら会計処理を行わないとされている。したがって、排出クレジットの引渡前に現金等の支出があった場合には、「前渡金」とされ、引渡時にはたな卸資産の仕入として会計処理される。ただし、時価が取得原価より著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とする(強制評価減)ことが必要であり、また、時価が取得原価よりも下落した場合には時価による方法を適用して算定する(低価法)ことができる(企業会計原則 第三五A参照)。その後の販売時には、たな卸資産の売上として会計処理されることとなる。
なお、排出クレジットの引渡の前に現金等を支払った際にも、毎期末、強制評価減の要否を検討するものとしているが、その取扱いは、日本公認会計士協会監査委員会報告第69号「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」においても見受けられる。強制評価減の要否を毎期検討する旨の規定がなされた背景には、排出クレジットの取得は、前渡金支出から引渡までの期間が長期になると想定されるからとされている。これは、排出クレジットの時価が取得原価より著しく下落し、回復する見込みがあると認められない限り、前渡金に計上しているという理由だけで、長期間にわたり含み損を抱えておくような不合理な状態を回避すべきという考えに基づいたものと思われる。
ii)出資を通じて取得する場合
出資を通じて取得する場合とは、例えばCDM等の排出クレジット獲得を目的としたプロジェクトを実施している会社等への出資を行い、その投資の成果の一部として、又は出資に付随して排出クレジットを取得することをいうものとされている。またファンド出資の場合についての会計処理が言及されていることから、「会社等」という意味には、企業への出資だけでなく、ファンド出資のような任意組合、匿名組合、パートナーシップ、リミテッドパートナーシップ等への出資も含まれているものと考えられる。
個別財務諸表上の処理としては、「金融商品会計に係る会計基準」に従うこととされているが、排出クレジットが分配された場合の具体的な会計処理に関しては、投資の成果であるときには収益として認識し、投資の回収であるときには投資元本の帳簿価額から減額するという基本的な考え方のみが示されている。その理由は、出資を通じた排出クレジットの取得は、現物分配の会計処理であるとの認識を示した上で、現在、法制審議会(現代化関係)部会における検討状況を踏まえ、ASBでは会計処理について検討する予定であるとされているためである(脚注2)。
出資先が子会社又は関連会社であるときには、連結又は持分法により会計処理する。また、排出クレジットの取得原価は、適正な原価計算基準に従い算定することが示されている。このため、例えば、排出クレジット獲得のためのプロジェクトを実施している企業において、排出クレジットの獲得が主たる生産物の製造過程から必然に派生する場合には、副産物として扱うため、総合原価計算においては、その価額を算定して、これを主産物の総合原価から控除する一方、生じる排出クレジットが軽微な場合には、これを売却して得た収入を原価計算外の収益とすることもできると考えられる(「原価計算基準」第28項参照)。
なお、契約等により出資のリターン及び出資元本の返還のほとんどが、現金ではなく排出クレジットの分配によりなされる場合であって、当該出資が排出クレジットの長期購入契約の締結及び前渡金支出と経済実質的には同じであると考えられる場合には、通常の商品購入と同様に「前渡金」として会計処理するものとされている。このため、排出クレジットの取得原価は、出資額(帳簿価額)に基づき算定される。
(2)将来の自社使用を見込んで取得する場合の会計処理
i)他者から購入する場合
将来の自社使用を見込んで排出クレジットを他者から購入する場合、「無形固定資産」又は「投資その他の資産」の購入として処理することとされている。また、取得した排出クレジットは、時の経過による減価や陳腐化がないと考えられる。このため減価償却は行われないものの、固定資産の減損会計の対象となるとされる。固定資産の減損会計適用に際しては、そもそも排出クレジットの資産性が、第三者への有償での売却可能性に立脚しているものである以上、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として取り扱われ、他の資産とのグルーピングは不適当とされている。資産として計上された排出クレジットは、今後整備・運用される国別登録簿における償却口座に自社の保有口座から排出クレジットが振り替えられた時点で費用計上(原則として、「販売費及び一般管理費」とすることが考えられると示されている。)するものとされている。これは、償却口座に振り替えられた時点以降、第三者に売却する可能性がないことから、資産計上の根拠が失われることによる。また、実際に償却口座に将来移転することが確実な場合や、第三者へ売却する可能性がないと見込まれる場合にも、資産計上の根拠がないため、費用とすることが適当とされる。
ii)出資を通じて取得する場合
排出クレジット取得のための出資が、排出クレジットの長期購入契約の締結と前渡金支出と経済実質的には同じと考えられるときには、「無形固定資産」又は「投資その他の資産」の区分に当該前渡金支出を示す適当な科目で計上するとされ、それ以外に関しては、専ら第三者に販売する目的で取得する場合と同様であるとされている。
7 本実務対応報告における連結財務諸表の在外子会社及び関連会社の会計処理
(1)同一環境下における同一経済取引に該当する場合
在外子会社及び関連会社における排出量取引の会計処理についても、本来、本実務対応報告を適用し統一されるべきと考えられるが、その子会社の所在地国の会計基準において認められている会計処理が、企業集団として統一しようとしている会計処理と異なる場合であっても、当面、親会社と子会社との間で統一する必要はないとされている。なお在外子会社が採用している会計処理が合理的でないと認められる場合には、連結決算手続上で修正することになることは明らかである(日本公認会計士協会監査委員会報告第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」5参照)。
(2)同一環境下における同一経済取引に該当しない場合
反対に我が国とは異なり、在外子会社又は関連会社に排出削減義務が課され、同一環境下における同一経済取引に該当しない場合には、合理的と考えられる会計処理を採用することとされている。
8 適用時期
本実務対応報告の適用は、平成17年4月1日以後開始する事業年度から適用するものとされ、それ以前の事業年度に係る財務諸表から早期適用することも認められている。
脚注
1 京都議定書及び京都メカニズムの詳細に関しては、経済産業省のホームページ(http://www.meti.go.jp/policy/global_environment/)又は環境省のホームページ(http://www.env.go.jp/earth/)を参照のこと。
2 このような背景としては、本質的には支払側の分配の原資により、自動的に受取側の会計処理が決定されるわけではない(企業会計基準適用指針第3号 「その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理」第15項参照)という認識があるものの、さりとてそれ以外にどのような方法が考えられるかという問題があるものと考えられる。さらに、現金での分配と異なり、現物での分配の場合には、投資の回収であっても、当初出資額(帳簿価額)に基づき投資元本を減額するのか(投資が継続していると考えられる場合)、当該現物の時価に基づき減額するのか(投資の清算にあたる場合。ただし、この場合にも、部分的な回収であるときに損益が計上されるのか、原価回収基準のように損益が計上されないのかという論点が考えられる。)などの問題もあることによるものと考えられる。
実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」の解説
企業会計基準委員会 研究員 中居正明
1 はじめに
企業会計基準委員会(以下「ASB」という。)から、平成16年11月30日に、実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「本実務対応報告」という。)が公表された。本稿では、本実務対応報告の概要を中心に解説する。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることを申し添える。
2 検討の経緯と範囲
平成16年4月、ASBは排出権の取得に関する会計処理の取扱いを明確にする必要性があると判断し、専門委員会を設置して会計処理の検討を開始した。それ以降、計5回の専門委員会が開催され、排出量取引に係る参考人の方々との意見交換や、専門委員、関係省庁の方々との議論を踏まえるなど検討を重ねた。ASBでは、同年9月29日に公開草案を公表し、これに対して寄せられたコメントも踏まえ、審議の結果、本実務対応報告を公表したものである。
このように、後述する京都議定書の発効を待たずに排出量取引の会計処理に関する検討が開始されたのは、既に一部の企業において自主的に京都議定書に基づくクレジット(以下「排出クレジット」という。)の取得に向けたファンド購入やプロジェクトの実施等の経済実態が先行しているという事実を踏まえてのことである。
また、本実務対応報告は、当面必要と考えられる会計処理のみを検討対象としているため、いわゆるキャップ・アンド・トレード(排出量を一定内とする義務を負い、余剰や不足については売買する仕組み)が導入されるような場合や、排出クレジットの活発な売買取引マーケットが今後整備され、非金融資産と位置付けられる排出クレジットを対象としたトレーディング目的での取引(金融投資)が行われる場合など、前提条件が変化した場合には別途検討の必要性があるとされている。
3 京都議定書の概要と我が国企業が直面する国内制度
(1) 京都議定書の概要
京都議定書自体の説明は、本稿の目的とするところではないが、以後の解説をする上での前提事項として、簡潔に言及する(脚注1)。
① 京都議定書の特徴
京都議定書の特徴は、先進国(附属書Ⅰ国)に対して、2008年から2012年における二酸化炭素などの排出量を、1990年比で欧州は8%、日本は6%削減する数値目標を定めた点や、限界コストの安い国で削減することを認めた柔軟措置を定めた点(京都メカニズム)の2つであるといわれる。
② 京都メカニズム
特に欧米に比較して1990年当時であってもエネルギー効率の高かったといわれている我が国の場合、6%の削減目標を達成するためには、補完的手段として京都議定書で定められた柔軟措置、すなわちクリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development mechanism)、共同実施(JI:Joint Implementation)及び排出量取引(Emission Trading)の活用が不可欠と言われている。この京都メカニズムのコンセプトは、地球上に存在する二酸化炭素等を削減するには、どこの地域、どこの国で削減しても効果は同じであることから、限界削減コストの安い地域、国で削減することを認めた点にある。
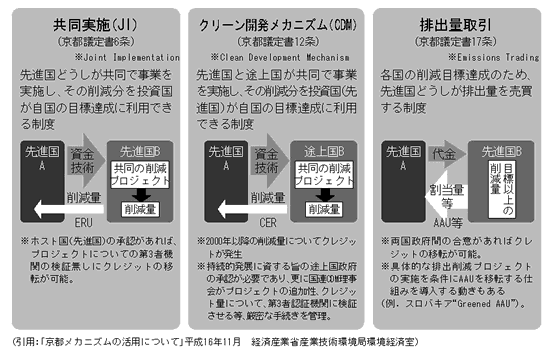
③ 国の排出量削減達成の仕組み
京都議定書で定められている国の排出量削減義務を達成するためには、実績排出量に見合う排出クレジットを国の管理する国別登録簿上の償却口座に移転しなければならない。
(2) 我が国企業が直面する国内制度と企業行動
現行の国内制度では、企業ごと又は業界ごとに排出量削減義務が課されていない。業界団体又は個別企業が、自主的な行動目標として二酸化炭素等の排出削減量を外部に公表し、毎期、その取り組み状況をフォローアップしていく形での二酸化炭素削減策が主となっている。この排出量削減に充てるために、排出クレジットを獲得しようとする企業や、将来の何らかの規制強化に備えて排出クレジット取得を行う企業がある。その一方で、国内における排出クレジット市場が今後拡大することを見越し、売り手として第三者に販売する目的で排出クレジット獲得を図る企業がある。
4 対象とされる排出クレジットとその性格
本実務対応報告では、京都メカニズムにおける排出クレジットが対象とされ、また京都メカニズム以外の排出クレジットについても、会計上の性格の類似性に鑑みて同様に会計処理を行うものとされている。会計上の性格の類似性とは、京都メカニズム以外の排出クレジットを企業が取得した場合でも、会計上、現金で購入して転売したり費消したりするという点では、京都メカニズムに基づく排出クレジットを購入する場合と変わらないことを示していると考えられる。
また、京都議定書に由来する排出クレジットの性格の特徴として、①京都議定書における国際的な約束を各締約国が履行するために用いられる数値であること、②国別登録簿においてのみ存在すること、及び③所有権の対象となる有体物ではなく、法定された無体財産権ではないことが挙げられている。その特徴を踏まえ、売買に際しては有償で取引されるという財産的価値に着目して会計上は無形固定資産に近いものと考えられるとされている。
なお、排出クレジットが、金融資産に該当するかどうかに関しては、「金融商品に係る会計基準」(以下、「金融商品会計基準」という。)第一一において具体的に例示されている金融資産の形態と類似性がない点や、排出クレジット保有者は、「金融商品会計に関する実務指針」第4項に規定する、現金を受け取る契約上の権利がない点を理由として、排出クレジットは、金融資産に該当しないものと位置付けられている。
5 会計処理の考え方
(1) 投資の性質
本実務対応報告では、「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」や「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」の考え方を踏まえ、資産の評価に際して時価評価するのか、取得原価評価するのかは、資産の外形的特質(金融資産かどうかなど)によるのではなく、投資の性質によるものとされている。
ここで企業の投資は、一般に金融投資と事業投資に大別されるとした上で、金融投資は、売買市場が整備され、売却することについて事業上の制約がないものであり、時価の変動が事前に期待した成果に対応する事実と考えられるため、時価評価がなじむとされている。
他方、事業投資は、売却することについて事業上の制約があり、事前に期待する投資の成果は、投資資産の時価の変動ではなく、その後の資金の獲得であることから、取得原価評価がなじむものとされている。
(2)事業投資として扱われる排出クレジット取得に係る投資
排出クレジットの取得に係る投資は、現時点では活発に取引される売買市場が存在するとはいえないことから、たとえ時価の変動によって利益を得ることを目的としても、金融投資には該当しないものと位置付けられている。すなわち、同じ排出クレジットの保有者であっても、販売先や価格水準の決定などその保有者の経営努力により、資金流入金額は異なるものと考えられるため、本実務対応報告では、排出クレジットに係る投資は、事業投資に該当するものとされている。したがって、金融投資に該当するようなトレーディング目的での排出クレジットの獲得は、本実務対応報告の対象とされていない。
(3) 対象とされている排出クレジットの取引
本実務対応報告では、排出クレジット取得の目的を2つに場合分けし、さらに取得方法を2つに場合分けし、組み合わせにより次の4つのケースにおける会計処理が示されている。
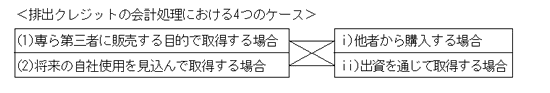
ここで(2)「将来の自社使用を見込んで取得する場合」とは、将来、自社の排出削減量に充てることを想定して排出クレジットを取得、保有するものの、自社の削減量に充てないことが明らかになったときには、第三者へ売却する可能性を残している場合をいうとされている。その上で、個々の企業に排出量削減義務が課されていないことを踏まえると、その財産的価値に着目し、資産計上することが妥当であると結論付けられている。逆に排出量削減に充てるため、保有する排出クレジットを国別登録簿の償却口座へ移転した際には、第三者への売却可能性がないことから、資産計上の根拠は失われ、費用に計上することになるとされている。
6 本実務対応報告における具体的会計処理
(1)専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合の会計処理
i)他者から購入する場合
専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合には、通常の商品の購入と同様の会計処理を行うものとされており、非金融商品である排出クレジットの売買契約が締結された段階では何ら会計処理を行わないとされている。したがって、排出クレジットの引渡前に現金等の支出があった場合には、「前渡金」とされ、引渡時にはたな卸資産の仕入として会計処理される。ただし、時価が取得原価より著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とする(強制評価減)ことが必要であり、また、時価が取得原価よりも下落した場合には時価による方法を適用して算定する(低価法)ことができる(企業会計原則 第三五A参照)。その後の販売時には、たな卸資産の売上として会計処理されることとなる。
なお、排出クレジットの引渡の前に現金等を支払った際にも、毎期末、強制評価減の要否を検討するものとしているが、その取扱いは、日本公認会計士協会監査委員会報告第69号「販売用不動産等の強制評価減の要否の判断に関する監査上の取扱い」においても見受けられる。強制評価減の要否を毎期検討する旨の規定がなされた背景には、排出クレジットの取得は、前渡金支出から引渡までの期間が長期になると想定されるからとされている。これは、排出クレジットの時価が取得原価より著しく下落し、回復する見込みがあると認められない限り、前渡金に計上しているという理由だけで、長期間にわたり含み損を抱えておくような不合理な状態を回避すべきという考えに基づいたものと思われる。
ii)出資を通じて取得する場合
出資を通じて取得する場合とは、例えばCDM等の排出クレジット獲得を目的としたプロジェクトを実施している会社等への出資を行い、その投資の成果の一部として、又は出資に付随して排出クレジットを取得することをいうものとされている。またファンド出資の場合についての会計処理が言及されていることから、「会社等」という意味には、企業への出資だけでなく、ファンド出資のような任意組合、匿名組合、パートナーシップ、リミテッドパートナーシップ等への出資も含まれているものと考えられる。
個別財務諸表上の処理としては、「金融商品会計に係る会計基準」に従うこととされているが、排出クレジットが分配された場合の具体的な会計処理に関しては、投資の成果であるときには収益として認識し、投資の回収であるときには投資元本の帳簿価額から減額するという基本的な考え方のみが示されている。その理由は、出資を通じた排出クレジットの取得は、現物分配の会計処理であるとの認識を示した上で、現在、法制審議会(現代化関係)部会における検討状況を踏まえ、ASBでは会計処理について検討する予定であるとされているためである(脚注2)。
出資先が子会社又は関連会社であるときには、連結又は持分法により会計処理する。また、排出クレジットの取得原価は、適正な原価計算基準に従い算定することが示されている。このため、例えば、排出クレジット獲得のためのプロジェクトを実施している企業において、排出クレジットの獲得が主たる生産物の製造過程から必然に派生する場合には、副産物として扱うため、総合原価計算においては、その価額を算定して、これを主産物の総合原価から控除する一方、生じる排出クレジットが軽微な場合には、これを売却して得た収入を原価計算外の収益とすることもできると考えられる(「原価計算基準」第28項参照)。
なお、契約等により出資のリターン及び出資元本の返還のほとんどが、現金ではなく排出クレジットの分配によりなされる場合であって、当該出資が排出クレジットの長期購入契約の締結及び前渡金支出と経済実質的には同じであると考えられる場合には、通常の商品購入と同様に「前渡金」として会計処理するものとされている。このため、排出クレジットの取得原価は、出資額(帳簿価額)に基づき算定される。
(2)将来の自社使用を見込んで取得する場合の会計処理
i)他者から購入する場合
将来の自社使用を見込んで排出クレジットを他者から購入する場合、「無形固定資産」又は「投資その他の資産」の購入として処理することとされている。また、取得した排出クレジットは、時の経過による減価や陳腐化がないと考えられる。このため減価償却は行われないものの、固定資産の減損会計の対象となるとされる。固定資産の減損会計適用に際しては、そもそも排出クレジットの資産性が、第三者への有償での売却可能性に立脚しているものである以上、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として取り扱われ、他の資産とのグルーピングは不適当とされている。資産として計上された排出クレジットは、今後整備・運用される国別登録簿における償却口座に自社の保有口座から排出クレジットが振り替えられた時点で費用計上(原則として、「販売費及び一般管理費」とすることが考えられると示されている。)するものとされている。これは、償却口座に振り替えられた時点以降、第三者に売却する可能性がないことから、資産計上の根拠が失われることによる。また、実際に償却口座に将来移転することが確実な場合や、第三者へ売却する可能性がないと見込まれる場合にも、資産計上の根拠がないため、費用とすることが適当とされる。
ii)出資を通じて取得する場合
排出クレジット取得のための出資が、排出クレジットの長期購入契約の締結と前渡金支出と経済実質的には同じと考えられるときには、「無形固定資産」又は「投資その他の資産」の区分に当該前渡金支出を示す適当な科目で計上するとされ、それ以外に関しては、専ら第三者に販売する目的で取得する場合と同様であるとされている。
7 本実務対応報告における連結財務諸表の在外子会社及び関連会社の会計処理
(1)同一環境下における同一経済取引に該当する場合
在外子会社及び関連会社における排出量取引の会計処理についても、本来、本実務対応報告を適用し統一されるべきと考えられるが、その子会社の所在地国の会計基準において認められている会計処理が、企業集団として統一しようとしている会計処理と異なる場合であっても、当面、親会社と子会社との間で統一する必要はないとされている。なお在外子会社が採用している会計処理が合理的でないと認められる場合には、連結決算手続上で修正することになることは明らかである(日本公認会計士協会監査委員会報告第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱い」5参照)。
(2)同一環境下における同一経済取引に該当しない場合
反対に我が国とは異なり、在外子会社又は関連会社に排出削減義務が課され、同一環境下における同一経済取引に該当しない場合には、合理的と考えられる会計処理を採用することとされている。
8 適用時期
本実務対応報告の適用は、平成17年4月1日以後開始する事業年度から適用するものとされ、それ以前の事業年度に係る財務諸表から早期適用することも認められている。
脚注
1 京都議定書及び京都メカニズムの詳細に関しては、経済産業省のホームページ(http://www.meti.go.jp/policy/global_environment/)又は環境省のホームページ(http://www.env.go.jp/earth/)を参照のこと。
2 このような背景としては、本質的には支払側の分配の原資により、自動的に受取側の会計処理が決定されるわけではない(企業会計基準適用指針第3号 「その他資本剰余金の処分による配当を受けた株主の会計処理」第15項参照)という認識があるものの、さりとてそれ以外にどのような方法が考えられるかという問題があるものと考えられる。さらに、現金での分配と異なり、現物での分配の場合には、投資の回収であっても、当初出資額(帳簿価額)に基づき投資元本を減額するのか(投資が継続していると考えられる場合)、当該現物の時価に基づき減額するのか(投資の清算にあたる場合。ただし、この場合にも、部分的な回収であるときに損益が計上されるのか、原価回収基準のように損益が計上されないのかという論点が考えられる。)などの問題もあることによるものと考えられる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















