解説記事2005年01月31日 【実務解説】 病院会計準則改正と医療法人会計基準の創設に向けて(2005年1月31日号・№100)
実務解説
病院会計準則改正と医療法人会計基準の創設に向けて
税理士法人青木会計 税理士 青木惠一
はじめに
病院という施設の会計基準として昭和40年に制定された後、昭和58年に1度だけ改正されたままであった「病院会計準則」が、平成16年8月19日、厚生労働省医政局長による各都道府県知事への通知により改正された。21年ぶりの改正である。厚生労働省において平成13年10月に設置された「これからの医業経営の在り方に関する検討会」(座長:田中滋慶應義塾大学大学院教授)での議論をもとに、平成14年度の厚生労働科学特別研究事業である「病院会計準則見直し等に関する研究」(主任研究者:会田一雄慶応義塾大学総合政策学部教授)における総括研究報告書をベースにした全面改正である。
主な改正内容は、財務諸表から「利益金処分計算書(損失金処理計算書)」を除き、新しく「キャッシュ・フロー計算書」を追加した。また、退職給付会計・研究開発費会計・リース会計・税効果会計など企業会計の新たな基準が適用可能な形で導入されている点である。
病院会計準則は、病院という「施設会計」の基準であるが、一概に病院と言っても様々な開設主体があり、改正前にはそれらすべての病院について病院会計準則が使われていたわけではない。しかし、改正後は、開設主体の異なる各種病院の財政状態や運営状態を体系的かつ統一的に捉えるための施設会計基準であることを明確にし、病院の経営を行うに際し有益な会計情報を提供する管理会計であるとの認識を明示した。特に公的病院においては、財政面を中心に、開設主体の異なる病院間での会計情報の比較可能性の確保が必要であるとの認識のもと、厚生労働省では、率先して病院会計準則の積極的な活用を促す通知を関係各機関に送っている。
1 病院会計準則の制定から今次の改正までの流れ
(1)昭和40年10月の病院会計準則制定
昭和38年、当時の厚生省医務局編で「病院勘定科目とその解説」が公表された。これを受け、昭和40年、厚生省医務局から各都道府県知事宛に通知(昭和40年10月15日付厚生省医務局通知第1233号)という形で病院のための施設会計基準である病院会計準則が制定された。病院会計準則を制定するに至ったのは、当時、多くの病院が現金主義会計をとり、作成する決算書は収支計算書と財産目録が中心であった。そのような状況では、病院の正確な経営状況や財務内容を把握できないため、企業会計の諸原則に基づいた財務諸表の作成基準として病院会計準則が制定された。
(2)昭和58年8月の改正
昭和40年の病院会計準則制定の後、病院経営の実情が変化したことや、企業会計原則の改正(昭和49年、昭和57年)を受けて、昭和56年に厚生行政科学研究「病院会計準則に関する研究」(研究者:染谷恭次郎先生)が公表され、その後、昭和58年に病院会計準則の全面的な改正(厚生省医務局長通知、昭和58年8月22日付医発824号)がされた。
(3)平成16年8月の全面改正
平成14年6月26日、四病院団体協議会病院会計準則研究委員会が「病院会計準則等の見直しに関して(中間報告)」を公表した。厚生労働省では、この中間報告を受けて、厚生労働特別研究事業「病院会計準則及び医療法人の会計基準の必要性に関する研究」の研究班を組織し、専門家による議論を開始した。平成15年4月10日、研究班より「病院会計準則見直し等に係る研究報告書」が厚生労働省に提出された(厚生労働省のホームページには平成15年9月に公表された。)。そして、「これからの医業経営の在り方に関する検討会」での議論などをもとに、平成16年8月19日、厚生労働省医政局長による各都道府県知事への通知により全面改正がされた。改正後は、当面、独立行政法人国立病院機構など公的病院を中心に積極的な活用を促すよう関係各機関に通知した。
2 病院会計準則改正の必要性
今般、病院会計準則改正に至った理由はいくつかある。
まず、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神病院協会のいわゆる四病院団体協議会(四病協)が将来の診療報酬引き締め(引下げ)策に対応するため各種病院の財政状態や運営状態を体系的かつ統一的に捉えたいと考えたことである。ところが、病院の開設主体には独立行政法人や公的医療機関(自治体、日赤、済生会、厚生連等)、社会保険関係団体(全社連、健康保険組合等)や医療法人などそれぞれがあり、これらの開設主体が違う病院はそれぞれに決められた会計基準(注)で経理処理しており、有益な経営情報を得ることができない状況にあった。そこで、開設主体が違うすべての病院に共通して適用する会計基準制定が必要との認識が持たれることになった。
(注)開設主体別に決められた会計基準の例示としては、独立行政法人は独立行政法人会計基準、学校法人立病院は学校法人会計基準、日赤は日本赤十字社医療施設特別会計規則、医療法人は病院会計準則などとなっている。また、個人病院は決算届出義務がないため事実上任意の状況であった。
次に、パブリックセクターからの必要性として、財政改革の一環で税金の投入がされている公的病院のあり方が検討され、経営の効率性などについて、民間病院などとの経営比較の必要性が叫ばれるようになったことである。この場合にも、開設主体を横断する共通の会計基準が必要となる。
さらに、プライベートセクターからの必要性として、経済財政諮問会議等で財政的側面から医療費抑制の切り札として株式会社の医業経営参入論が唱えられたことに対し、現在の非営利を基本とした病院の真の経営情報の透明性を担保し、運営の効率性を立証するための体系的かつ統一的な物差しが必要になったことである。
これらいくつかの要因が重なり合って病院会計準則改正すべしとの方向性ができたことが今回の改正につながった。
3 改正病院会計準則のポイント
改正された病院会計準則の「目次」及び「第1章総則」は(表1)・(表2)のとおりである。具体的な病院会計準則改正のポイントは次のとおりである。
(1)病院会計準則が病院の「施設会計」基準であることを明確にした。そして、開設主体の異なるすべての病院の財政状態や運営状態を体系的かつ統一的に捉えるための「管理会計」としての会計基準であることも明示した。(なお、厚生労働省の通知では、改正後の病院会計準則を各病院が採用することについて、病院会計準則が経営把握のための管理会計であるため、まず、公的病院の積極的採用を促し、民間病院については準備が整った病院から時機をとらえて自主的に活用するようにアナウンスしている。)
(2)財務諸表に貸借対照表・損益計算書のほか「キャッシュ・フロー計算書」が加えられ、「附属明細表」、「重要な会計方針、注記」が充実した。また、施設会計ゆえ改正前にはあった「利益金処分計算書(損失金処理計算書)」が除かれた。
(注)財務諸表の体系及び区分・配列などについて(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の様式例参照のこと)
① 従来の病院会計準則における財務諸表の体系は損益計算書、貸借対照表、利益金処分計算書(損失金処理計算書)、附属明細表が掲げられていた。しかし、たとえば医療法人が複数の病院を経営している場合、利益処分をするのは総体としての医療法人であり、個別の施設である病院には利益の処分行為が予定されないので、まず、利益金処分計算書(損失金処理計算書)が体系から除外された。続いて、貸借対照表の資産・負債差額の本質を再確認し、これを資本としてではなく、「純資産」として位置付けている。その結果、貸借対照表における表示区分は、資産の部、負債の部及び「純資産の部」となる。
② 損益計算書は、医業収益から医業費用を控除して医業利益(医業損失)を算出し、そこから、医業外収益と医業外費用を加味して経常利益(経常損失)を計算する。そして臨時収益・臨時費用を考慮の後に税引前当期純利益(税引前当期純損失)の算出をし、法人税、住民税及び事業税負担額(「負担額」とあるのは、法人税等は法人全体で計算され、これを施設会計である病院会計準則により個別の病院に割振るためである)を控除して最後に当期純利益(当期純損失)を計算するという段階区分になっている。なお、医業費用には通常の売上原価項目はない。これは、医業の分野で売上原価項目を設けると単に医薬品などだけでなく一部人件費など製造業的計算が必要になると考えられているためである。
③ キャッシュ・フロー計算書においては、業務活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの各区分を設け、病院におけるキャッシュ・フローをわかりやすく描写することとされている。
(3)貸借対照表において繰延資産勘定は設けず、その支出の内容を個別的に検討し、資産性が認められる支出については固定資産の「その他の資産」の区分に表示する。
(4)病院が受け取る補助金は、非償却資産の取得に充てられるものを除き、これを貸借対照表において負債の部に記載(長期前受補助金)し、業務の進行に応じて収益計上することとした。収益化を行った補助金は、損益計算書上医業外収益の区分に記載する。また、設備の取得に対して補助金が交付された場合は、その対象設備の耐用年数にわたってこれを配分することとされた。なお、非償却資産の取得に充てられる補助金は純資産の部に計上する。
(5)消費税・地方消費税(以下「消費税」という。)の会計処理方法が税抜き処理に統一された。管理会計である病院会計準則では消費税について税込み処理の方法はない。そして病院が支払った消費税について、損益計算書上で控除対象外消費税等負担額または資産に係る控除対象外消費税等負担額として計上することとしている。(これは消費税を実質的に経営上のコストとして認識していることである。これにより、各病院が負担した消費税を明確にし社会保険診療報酬の改定時に参考とする意図があるようである。)
(6)土地・建物等を無償使用している場合にはその旨注記が必要とされた。これはいわゆる公的病院において多い事例だと考えられる。病院を経営するうえで、設備関係費に属する項目である地代家賃など土地・建物に関するコストは民間病院では無償ということは考えられない。病院間の経営比較をする際には重要な要素と考えられる。
(7)近時の会計国際化への対応として「退職給付会計」「リース会計」「研究開発費会計」「税効果会計」などが取り入れられた(表3参照)。このうち、退職給付会計については、病院という施設の運営が労働集約型であるため、自己資本比率が著しく低下するなど財務諸表に与える影響は大きいと考えられる。病院や介護老人保健施設を開設する医療法人の場合、法人の安定性及び継続性の確保を図る観点から、資産総額の20%(特別医療法人にあっては30%)に相当する自己資本比率を有しなければならない(医療法施行規則30の34①)とされており、この自己資本比率のキープに悩む医療法人などが多数でてくる懸念がある。さらに、自己資本比率の低下に拍車をかけるのがファイナンス・リース取引のオンバランス化である。病院は医療用器械など多額な設備投資が必要であり、これをファイナンス・リースで調達することも多い。自己資本比率20%堅持が達成できない医療法人もでてくるものと思われる。
(表1)病院会計準則目次
第1章 総則
第2章 一般原則及び一般原則注解
第3章 貸借対照表原則、貸借対照表原則注解及び様式例
第4章 損益計算書原則、損益計算書注解及び様式例
第5章 キャッシュ・フロー計算書原則、キャッシュ・フロー計算書原則注解及び様式例
第6章 附属明細表原則及び様式例
別表 勘定科目の説明
(表2)病院会計準則の総則
第1章 総 則
第1 目 的
病院会計準則は、病院を対象に、会計の基準を定め、病院の財政状態及び運営状況を適正に把握し、病院の経営体質の強化、改善向上に資することを目的とする。
第2 適用の原則
1 病院会計準則は、病院ごとに作成される財務諸表の作成基準を示したものである。
2 病院会計準則において定めのない取引及び事象については、開設主体の会計基準及び一般
に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとする。
3 病院の開設主体が会計規則を定める場合には、この会計準則に従うものとする。
第3 会計期間
病院の会計期間は1年とし、開設主体が設定する。
第4 会計単位
病院の開設主体は、それぞれの病院を会計単位として財務諸表を作成しなければならない。
第5 財務諸表の範囲
病院の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表とする。
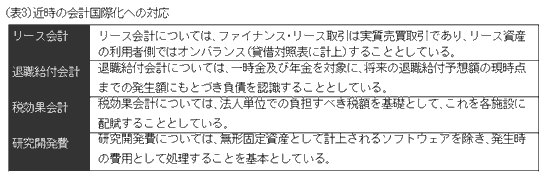
4 改正後の病院会計準則と税務上の留意点
病院会計準則自体は管理会計処理の基準であり、直接税務上の取り扱いと関連することはない。しかし、以下の点において留意する必要がある。
(1)病院会計準則は、開設主体の異なる各種病院の財政状態や運営状態を体系的かつ統一的に捉えるための会計基準であり、財務諸表の比較という点に重きを置いている。そのため会計処理の方法が画一的で、選択適用という概念はない。特に会計処理するうえで、消費税・地方消費税の処理は必ず税抜き処理をしなければならない。これは消費税・地方消費税について、原則課税の対象となる課税事業者は勿論のこと、免税事業者・簡易課税を選択した事業者においても同様である。
(2)上記(1)と同様の理由から、減価償却資産の種類(たとえば、建物付属設備という税務会計的概念は様式例の貸借対照表の勘定科目にはなく、勘定科目の解説をみると建物に包含されている。)や償却費の計上(たとえば医療用機器の特別償却という税法上の特例は、あくまでも税務の考え方と認識し財務諸表に表すことになると思われる。)、繰延資産の取り扱いなど税務会計上の取扱いは一切考慮しないと考える必要がある。
(3)上記(1)と同様の理由から、改正後の病院会計準則の様式例における「損益計算書」の「医業収益」の勘定科目をみると入院診療収益や外来診療収益など経営比較的要素に重点を置いた区分になっている。これに対し、税務申告を考えた場合、医業収益に関しては、消費税について、課税・非課税・不課税の区分を明確にしておくことが重要である。また、事業税の課税対象となる医業収益と非課税となる医業収益の区分も把握する必要がある。つまり、医業収益は経営比較的要素による区分と税務申告の観点における区分が必要になり、複雑さが増す。
5 医療法人会計基準の導入の必要性
病院会計準則は、複数の病院を経営する医療法人の、その各個別の病院の財務諸表を作成する際の施設会計基準という位置付けであり、原則的に単一施設の会計基準となっている。
ところで、医療法人については医療施設である病院・診療所の経営はもとより、介護施設である介護老人保健施設の開設を本来業務として行うことができる(現状、介護老人保健施設の概ね70%について医療法人が経営母体となっている。)。また、医療法第42条の規定により附帯業務として、訪問看護ステーションやグループホームなどの運営もでき事業内容が多様化している。医療法人が病院のほかに複数の施設を経営する場合にあってはその施設に合致した会計処理基準を使って財務諸表を作成することになる。たとえば、病院は病院会計準則、介護老人保健施設は介護老人保健施設会計・経理準則、訪問看護ステーションは指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理準則などである。このような医療法人では、医療法人の病院事業に対する財務諸表と病院事業以外の事業に対する財務諸表を合算して、医療法人全体の財政状態や経営成績が適正に把握できる基準が必要とされる。しかし現状においてこのような医療法人全体の財務諸表を作成する会計基準はない。そこで多様な施設を経営する医療法人の全体を統括した財務諸表を作成する新たな会計基準として「医療法人会計基準」の導入が検討されている。検討されている医療法人会計基準は、病院会計準則の改正内容を全面的に取り入れ、また、介護老人保健施設会計・経理準則や指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理準則なども同様の改正がされるという想定のもと、これらの会計基準を整合した形で医療法人全体の財政状態や経営成績が適正に把握できるものが想定される。
6 医療法人会計基準の適用範囲の検討
新設が検討されている医療法人会計基準はこれを医療法人に義務として適用する予定である。この医療法人会計基準は、多様な施設を経営する大規模医療法人を想定し、その会計情報の表示のあり方を検討したものである。これに対し、医療法人には、単一の病院のみを経営する中規模の医療法人や、無床の診療所を経営するいわゆる一人医師医療法人など小規模なものも多数存在している。これら中小の医療法人に医療法人会計基準の適用を義務化した場合、事務負担が過重になることが考えられるため、中小の医療法人には、記載内容の省略、簡略化等の宥恕規定が設けられることも予想される。
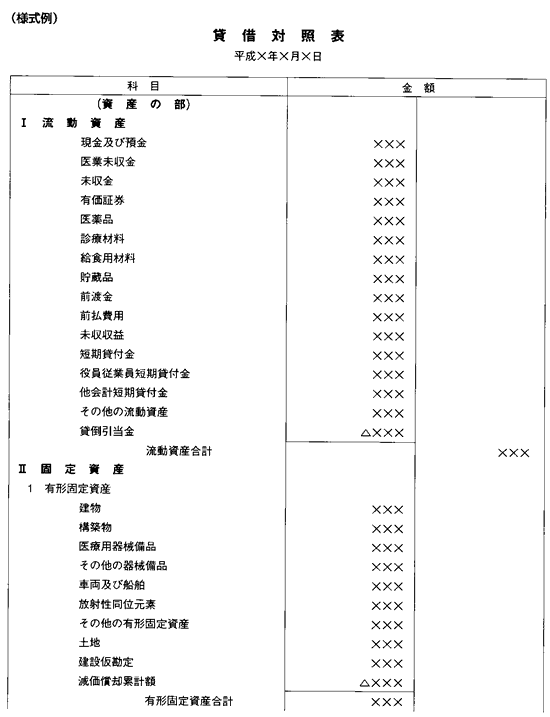
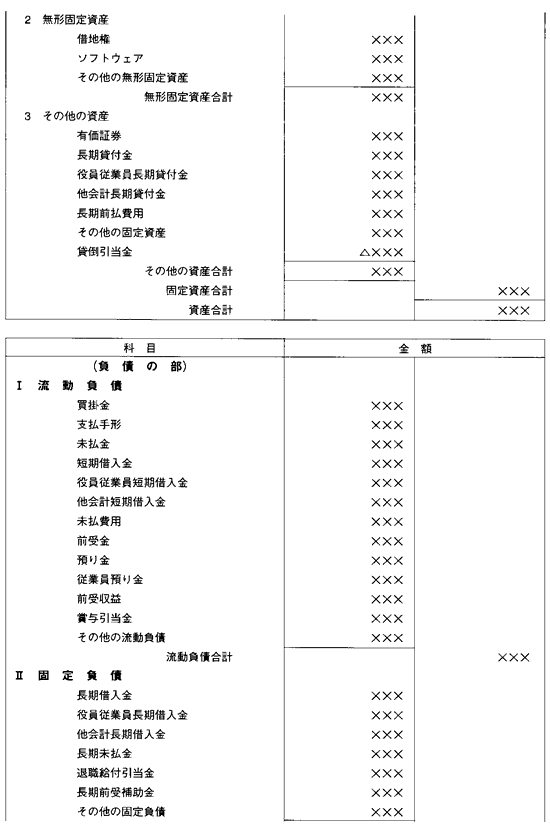
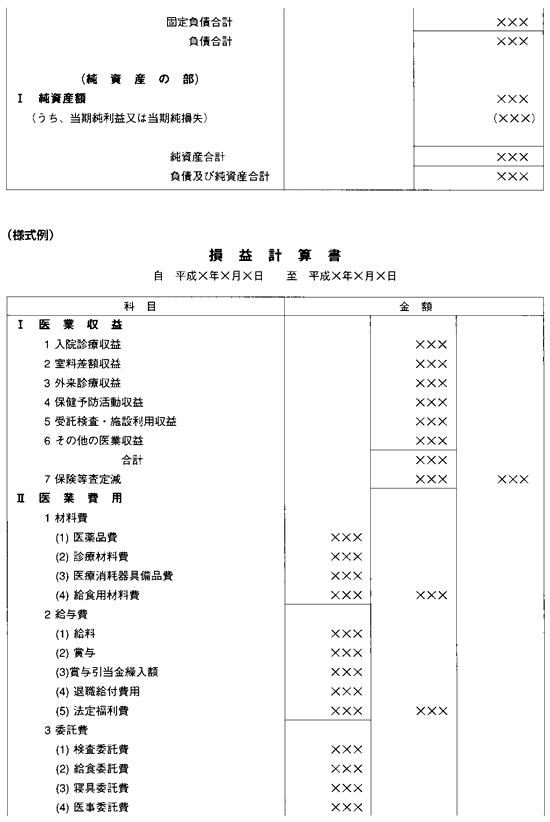
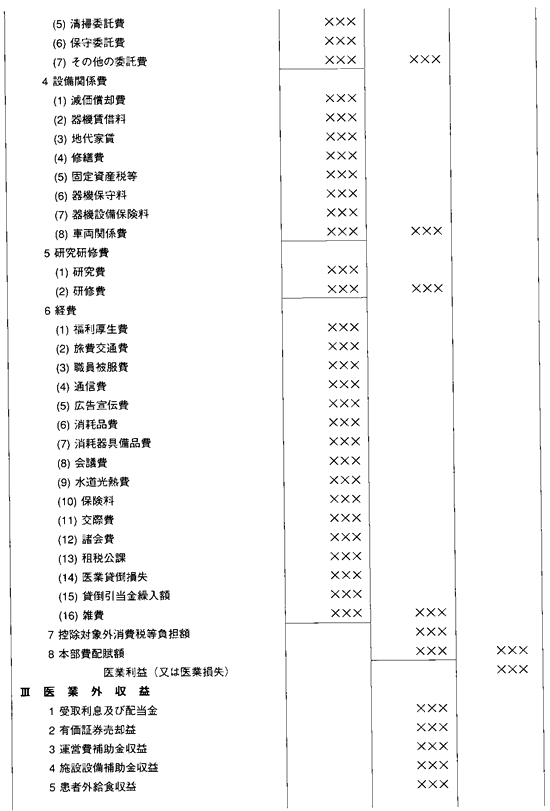
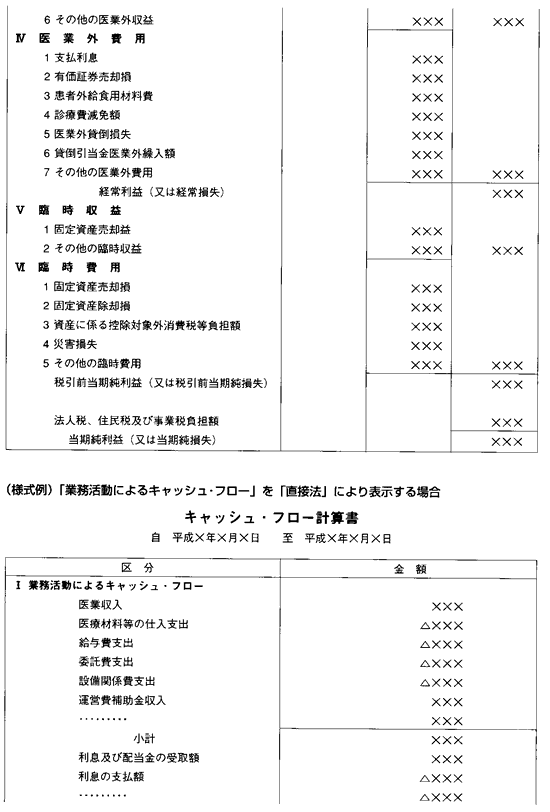
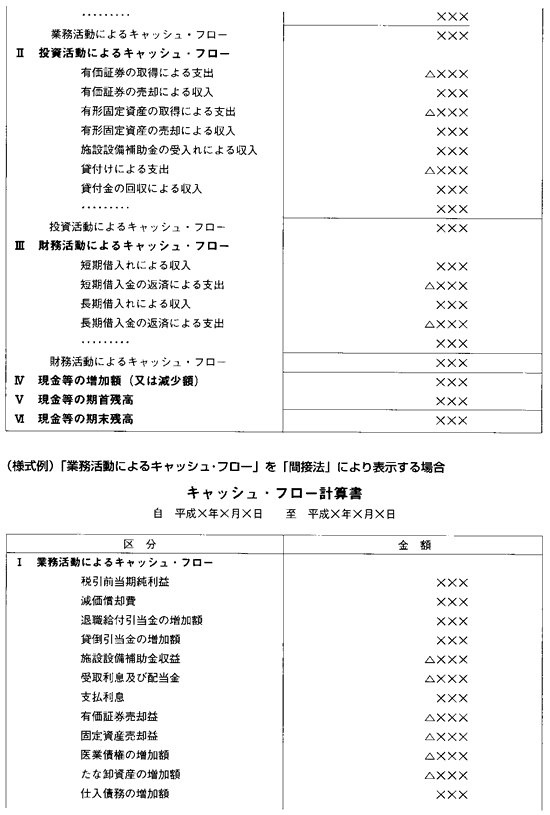
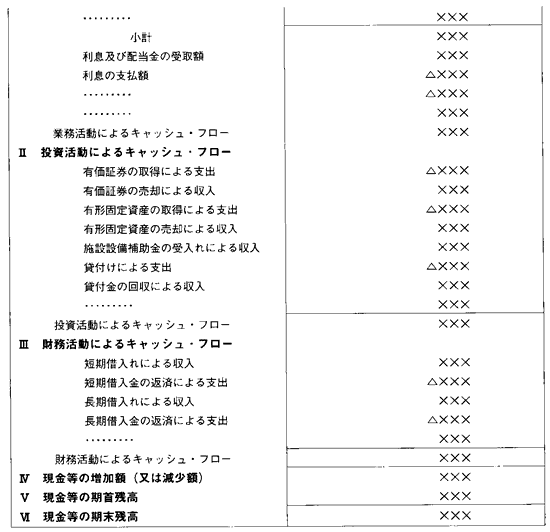
病院会計準則改正と医療法人会計基準の創設に向けて
税理士法人青木会計 税理士 青木惠一
はじめに
病院という施設の会計基準として昭和40年に制定された後、昭和58年に1度だけ改正されたままであった「病院会計準則」が、平成16年8月19日、厚生労働省医政局長による各都道府県知事への通知により改正された。21年ぶりの改正である。厚生労働省において平成13年10月に設置された「これからの医業経営の在り方に関する検討会」(座長:田中滋慶應義塾大学大学院教授)での議論をもとに、平成14年度の厚生労働科学特別研究事業である「病院会計準則見直し等に関する研究」(主任研究者:会田一雄慶応義塾大学総合政策学部教授)における総括研究報告書をベースにした全面改正である。
主な改正内容は、財務諸表から「利益金処分計算書(損失金処理計算書)」を除き、新しく「キャッシュ・フロー計算書」を追加した。また、退職給付会計・研究開発費会計・リース会計・税効果会計など企業会計の新たな基準が適用可能な形で導入されている点である。
病院会計準則は、病院という「施設会計」の基準であるが、一概に病院と言っても様々な開設主体があり、改正前にはそれらすべての病院について病院会計準則が使われていたわけではない。しかし、改正後は、開設主体の異なる各種病院の財政状態や運営状態を体系的かつ統一的に捉えるための施設会計基準であることを明確にし、病院の経営を行うに際し有益な会計情報を提供する管理会計であるとの認識を明示した。特に公的病院においては、財政面を中心に、開設主体の異なる病院間での会計情報の比較可能性の確保が必要であるとの認識のもと、厚生労働省では、率先して病院会計準則の積極的な活用を促す通知を関係各機関に送っている。
1 病院会計準則の制定から今次の改正までの流れ
(1)昭和40年10月の病院会計準則制定
昭和38年、当時の厚生省医務局編で「病院勘定科目とその解説」が公表された。これを受け、昭和40年、厚生省医務局から各都道府県知事宛に通知(昭和40年10月15日付厚生省医務局通知第1233号)という形で病院のための施設会計基準である病院会計準則が制定された。病院会計準則を制定するに至ったのは、当時、多くの病院が現金主義会計をとり、作成する決算書は収支計算書と財産目録が中心であった。そのような状況では、病院の正確な経営状況や財務内容を把握できないため、企業会計の諸原則に基づいた財務諸表の作成基準として病院会計準則が制定された。
(2)昭和58年8月の改正
昭和40年の病院会計準則制定の後、病院経営の実情が変化したことや、企業会計原則の改正(昭和49年、昭和57年)を受けて、昭和56年に厚生行政科学研究「病院会計準則に関する研究」(研究者:染谷恭次郎先生)が公表され、その後、昭和58年に病院会計準則の全面的な改正(厚生省医務局長通知、昭和58年8月22日付医発824号)がされた。
(3)平成16年8月の全面改正
平成14年6月26日、四病院団体協議会病院会計準則研究委員会が「病院会計準則等の見直しに関して(中間報告)」を公表した。厚生労働省では、この中間報告を受けて、厚生労働特別研究事業「病院会計準則及び医療法人の会計基準の必要性に関する研究」の研究班を組織し、専門家による議論を開始した。平成15年4月10日、研究班より「病院会計準則見直し等に係る研究報告書」が厚生労働省に提出された(厚生労働省のホームページには平成15年9月に公表された。)。そして、「これからの医業経営の在り方に関する検討会」での議論などをもとに、平成16年8月19日、厚生労働省医政局長による各都道府県知事への通知により全面改正がされた。改正後は、当面、独立行政法人国立病院機構など公的病院を中心に積極的な活用を促すよう関係各機関に通知した。
2 病院会計準則改正の必要性
今般、病院会計準則改正に至った理由はいくつかある。
まず、日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神病院協会のいわゆる四病院団体協議会(四病協)が将来の診療報酬引き締め(引下げ)策に対応するため各種病院の財政状態や運営状態を体系的かつ統一的に捉えたいと考えたことである。ところが、病院の開設主体には独立行政法人や公的医療機関(自治体、日赤、済生会、厚生連等)、社会保険関係団体(全社連、健康保険組合等)や医療法人などそれぞれがあり、これらの開設主体が違う病院はそれぞれに決められた会計基準(注)で経理処理しており、有益な経営情報を得ることができない状況にあった。そこで、開設主体が違うすべての病院に共通して適用する会計基準制定が必要との認識が持たれることになった。
(注)開設主体別に決められた会計基準の例示としては、独立行政法人は独立行政法人会計基準、学校法人立病院は学校法人会計基準、日赤は日本赤十字社医療施設特別会計規則、医療法人は病院会計準則などとなっている。また、個人病院は決算届出義務がないため事実上任意の状況であった。
次に、パブリックセクターからの必要性として、財政改革の一環で税金の投入がされている公的病院のあり方が検討され、経営の効率性などについて、民間病院などとの経営比較の必要性が叫ばれるようになったことである。この場合にも、開設主体を横断する共通の会計基準が必要となる。
さらに、プライベートセクターからの必要性として、経済財政諮問会議等で財政的側面から医療費抑制の切り札として株式会社の医業経営参入論が唱えられたことに対し、現在の非営利を基本とした病院の真の経営情報の透明性を担保し、運営の効率性を立証するための体系的かつ統一的な物差しが必要になったことである。
これらいくつかの要因が重なり合って病院会計準則改正すべしとの方向性ができたことが今回の改正につながった。
3 改正病院会計準則のポイント
改正された病院会計準則の「目次」及び「第1章総則」は(表1)・(表2)のとおりである。具体的な病院会計準則改正のポイントは次のとおりである。
(1)病院会計準則が病院の「施設会計」基準であることを明確にした。そして、開設主体の異なるすべての病院の財政状態や運営状態を体系的かつ統一的に捉えるための「管理会計」としての会計基準であることも明示した。(なお、厚生労働省の通知では、改正後の病院会計準則を各病院が採用することについて、病院会計準則が経営把握のための管理会計であるため、まず、公的病院の積極的採用を促し、民間病院については準備が整った病院から時機をとらえて自主的に活用するようにアナウンスしている。)
(2)財務諸表に貸借対照表・損益計算書のほか「キャッシュ・フロー計算書」が加えられ、「附属明細表」、「重要な会計方針、注記」が充実した。また、施設会計ゆえ改正前にはあった「利益金処分計算書(損失金処理計算書)」が除かれた。
(注)財務諸表の体系及び区分・配列などについて(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の様式例参照のこと)
① 従来の病院会計準則における財務諸表の体系は損益計算書、貸借対照表、利益金処分計算書(損失金処理計算書)、附属明細表が掲げられていた。しかし、たとえば医療法人が複数の病院を経営している場合、利益処分をするのは総体としての医療法人であり、個別の施設である病院には利益の処分行為が予定されないので、まず、利益金処分計算書(損失金処理計算書)が体系から除外された。続いて、貸借対照表の資産・負債差額の本質を再確認し、これを資本としてではなく、「純資産」として位置付けている。その結果、貸借対照表における表示区分は、資産の部、負債の部及び「純資産の部」となる。
② 損益計算書は、医業収益から医業費用を控除して医業利益(医業損失)を算出し、そこから、医業外収益と医業外費用を加味して経常利益(経常損失)を計算する。そして臨時収益・臨時費用を考慮の後に税引前当期純利益(税引前当期純損失)の算出をし、法人税、住民税及び事業税負担額(「負担額」とあるのは、法人税等は法人全体で計算され、これを施設会計である病院会計準則により個別の病院に割振るためである)を控除して最後に当期純利益(当期純損失)を計算するという段階区分になっている。なお、医業費用には通常の売上原価項目はない。これは、医業の分野で売上原価項目を設けると単に医薬品などだけでなく一部人件費など製造業的計算が必要になると考えられているためである。
③ キャッシュ・フロー計算書においては、業務活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの各区分を設け、病院におけるキャッシュ・フローをわかりやすく描写することとされている。
(3)貸借対照表において繰延資産勘定は設けず、その支出の内容を個別的に検討し、資産性が認められる支出については固定資産の「その他の資産」の区分に表示する。
(4)病院が受け取る補助金は、非償却資産の取得に充てられるものを除き、これを貸借対照表において負債の部に記載(長期前受補助金)し、業務の進行に応じて収益計上することとした。収益化を行った補助金は、損益計算書上医業外収益の区分に記載する。また、設備の取得に対して補助金が交付された場合は、その対象設備の耐用年数にわたってこれを配分することとされた。なお、非償却資産の取得に充てられる補助金は純資産の部に計上する。
(5)消費税・地方消費税(以下「消費税」という。)の会計処理方法が税抜き処理に統一された。管理会計である病院会計準則では消費税について税込み処理の方法はない。そして病院が支払った消費税について、損益計算書上で控除対象外消費税等負担額または資産に係る控除対象外消費税等負担額として計上することとしている。(これは消費税を実質的に経営上のコストとして認識していることである。これにより、各病院が負担した消費税を明確にし社会保険診療報酬の改定時に参考とする意図があるようである。)
(6)土地・建物等を無償使用している場合にはその旨注記が必要とされた。これはいわゆる公的病院において多い事例だと考えられる。病院を経営するうえで、設備関係費に属する項目である地代家賃など土地・建物に関するコストは民間病院では無償ということは考えられない。病院間の経営比較をする際には重要な要素と考えられる。
(7)近時の会計国際化への対応として「退職給付会計」「リース会計」「研究開発費会計」「税効果会計」などが取り入れられた(表3参照)。このうち、退職給付会計については、病院という施設の運営が労働集約型であるため、自己資本比率が著しく低下するなど財務諸表に与える影響は大きいと考えられる。病院や介護老人保健施設を開設する医療法人の場合、法人の安定性及び継続性の確保を図る観点から、資産総額の20%(特別医療法人にあっては30%)に相当する自己資本比率を有しなければならない(医療法施行規則30の34①)とされており、この自己資本比率のキープに悩む医療法人などが多数でてくる懸念がある。さらに、自己資本比率の低下に拍車をかけるのがファイナンス・リース取引のオンバランス化である。病院は医療用器械など多額な設備投資が必要であり、これをファイナンス・リースで調達することも多い。自己資本比率20%堅持が達成できない医療法人もでてくるものと思われる。
(表1)病院会計準則目次
第1章 総則
第2章 一般原則及び一般原則注解
第3章 貸借対照表原則、貸借対照表原則注解及び様式例
第4章 損益計算書原則、損益計算書注解及び様式例
第5章 キャッシュ・フロー計算書原則、キャッシュ・フロー計算書原則注解及び様式例
第6章 附属明細表原則及び様式例
別表 勘定科目の説明
(表2)病院会計準則の総則
第1章 総 則
第1 目 的
病院会計準則は、病院を対象に、会計の基準を定め、病院の財政状態及び運営状況を適正に把握し、病院の経営体質の強化、改善向上に資することを目的とする。
第2 適用の原則
1 病院会計準則は、病院ごとに作成される財務諸表の作成基準を示したものである。
2 病院会計準則において定めのない取引及び事象については、開設主体の会計基準及び一般
に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとする。
3 病院の開設主体が会計規則を定める場合には、この会計準則に従うものとする。
第3 会計期間
病院の会計期間は1年とし、開設主体が設定する。
第4 会計単位
病院の開設主体は、それぞれの病院を会計単位として財務諸表を作成しなければならない。
第5 財務諸表の範囲
病院の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表とする。
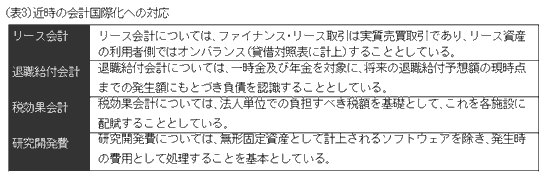
4 改正後の病院会計準則と税務上の留意点
病院会計準則自体は管理会計処理の基準であり、直接税務上の取り扱いと関連することはない。しかし、以下の点において留意する必要がある。
(1)病院会計準則は、開設主体の異なる各種病院の財政状態や運営状態を体系的かつ統一的に捉えるための会計基準であり、財務諸表の比較という点に重きを置いている。そのため会計処理の方法が画一的で、選択適用という概念はない。特に会計処理するうえで、消費税・地方消費税の処理は必ず税抜き処理をしなければならない。これは消費税・地方消費税について、原則課税の対象となる課税事業者は勿論のこと、免税事業者・簡易課税を選択した事業者においても同様である。
(2)上記(1)と同様の理由から、減価償却資産の種類(たとえば、建物付属設備という税務会計的概念は様式例の貸借対照表の勘定科目にはなく、勘定科目の解説をみると建物に包含されている。)や償却費の計上(たとえば医療用機器の特別償却という税法上の特例は、あくまでも税務の考え方と認識し財務諸表に表すことになると思われる。)、繰延資産の取り扱いなど税務会計上の取扱いは一切考慮しないと考える必要がある。
(3)上記(1)と同様の理由から、改正後の病院会計準則の様式例における「損益計算書」の「医業収益」の勘定科目をみると入院診療収益や外来診療収益など経営比較的要素に重点を置いた区分になっている。これに対し、税務申告を考えた場合、医業収益に関しては、消費税について、課税・非課税・不課税の区分を明確にしておくことが重要である。また、事業税の課税対象となる医業収益と非課税となる医業収益の区分も把握する必要がある。つまり、医業収益は経営比較的要素による区分と税務申告の観点における区分が必要になり、複雑さが増す。
5 医療法人会計基準の導入の必要性
病院会計準則は、複数の病院を経営する医療法人の、その各個別の病院の財務諸表を作成する際の施設会計基準という位置付けであり、原則的に単一施設の会計基準となっている。
ところで、医療法人については医療施設である病院・診療所の経営はもとより、介護施設である介護老人保健施設の開設を本来業務として行うことができる(現状、介護老人保健施設の概ね70%について医療法人が経営母体となっている。)。また、医療法第42条の規定により附帯業務として、訪問看護ステーションやグループホームなどの運営もでき事業内容が多様化している。医療法人が病院のほかに複数の施設を経営する場合にあってはその施設に合致した会計処理基準を使って財務諸表を作成することになる。たとえば、病院は病院会計準則、介護老人保健施設は介護老人保健施設会計・経理準則、訪問看護ステーションは指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理準則などである。このような医療法人では、医療法人の病院事業に対する財務諸表と病院事業以外の事業に対する財務諸表を合算して、医療法人全体の財政状態や経営成績が適正に把握できる基準が必要とされる。しかし現状においてこのような医療法人全体の財務諸表を作成する会計基準はない。そこで多様な施設を経営する医療法人の全体を統括した財務諸表を作成する新たな会計基準として「医療法人会計基準」の導入が検討されている。検討されている医療法人会計基準は、病院会計準則の改正内容を全面的に取り入れ、また、介護老人保健施設会計・経理準則や指定老人訪問看護の事業及び指定訪問看護の事業の会計・経理準則なども同様の改正がされるという想定のもと、これらの会計基準を整合した形で医療法人全体の財政状態や経営成績が適正に把握できるものが想定される。
6 医療法人会計基準の適用範囲の検討
新設が検討されている医療法人会計基準はこれを医療法人に義務として適用する予定である。この医療法人会計基準は、多様な施設を経営する大規模医療法人を想定し、その会計情報の表示のあり方を検討したものである。これに対し、医療法人には、単一の病院のみを経営する中規模の医療法人や、無床の診療所を経営するいわゆる一人医師医療法人など小規模なものも多数存在している。これら中小の医療法人に医療法人会計基準の適用を義務化した場合、事務負担が過重になることが考えられるため、中小の医療法人には、記載内容の省略、簡略化等の宥恕規定が設けられることも予想される。
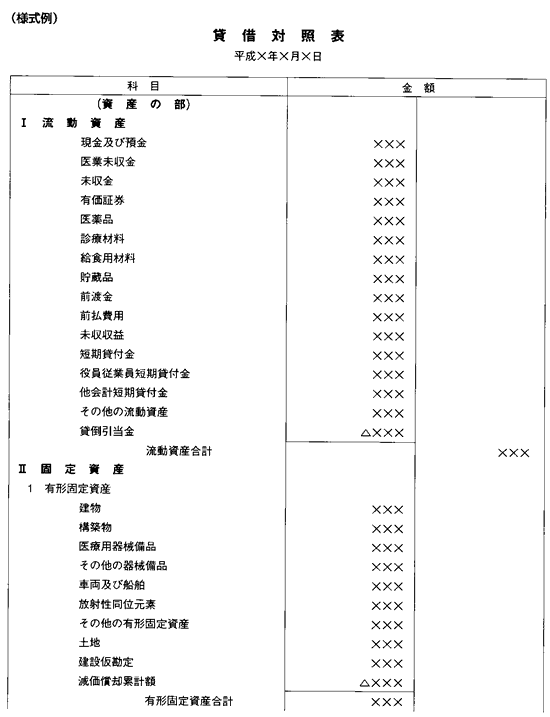
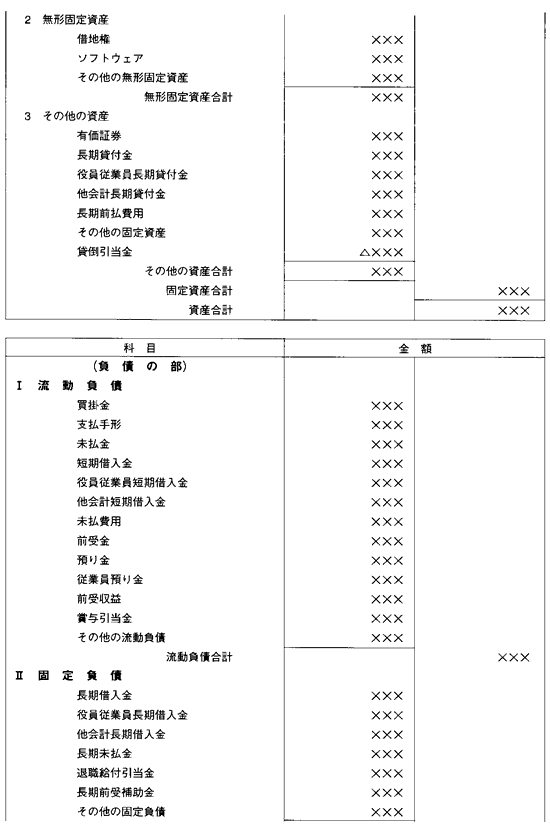
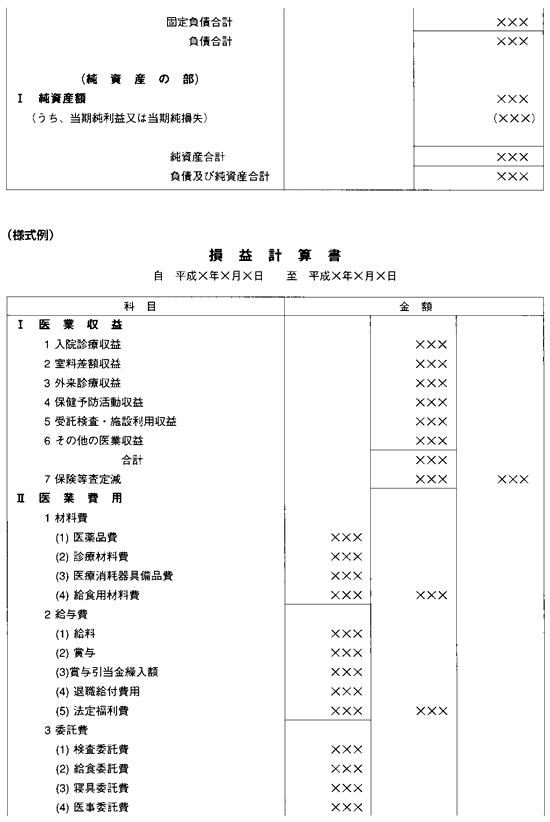
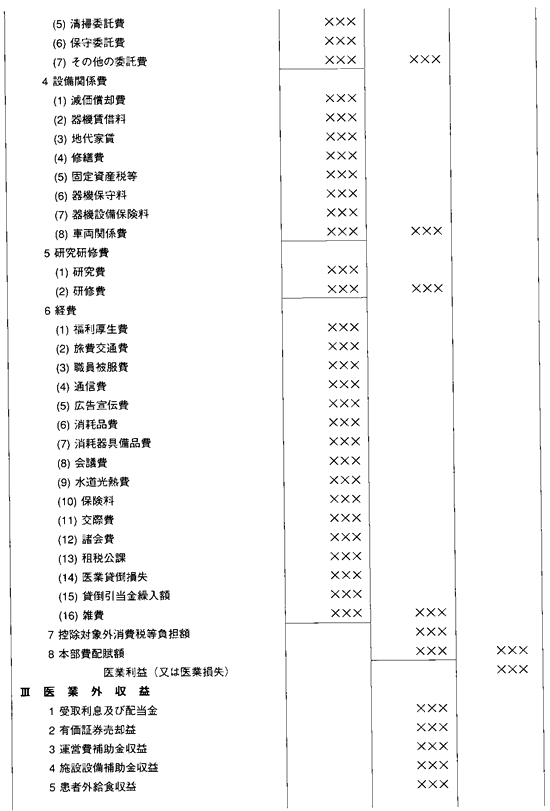
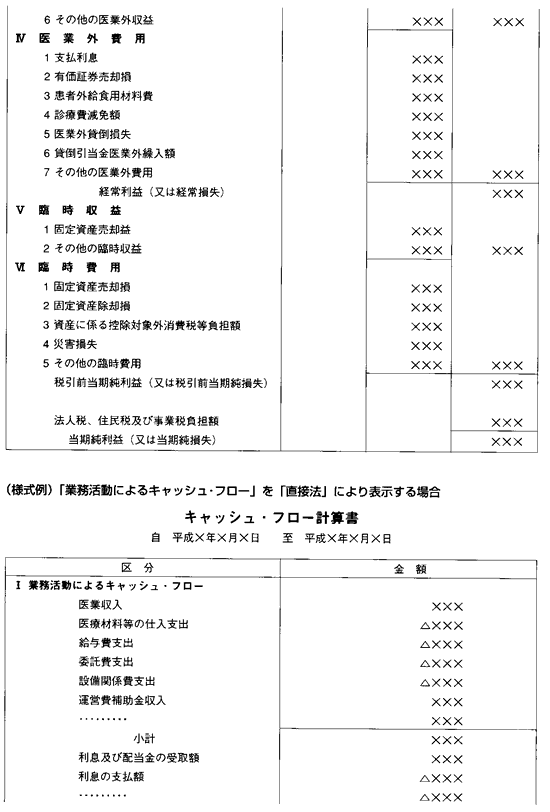
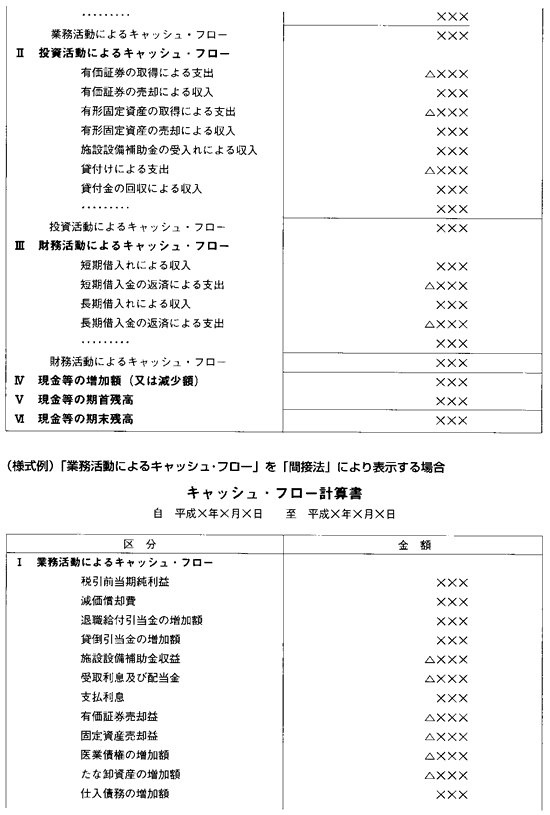
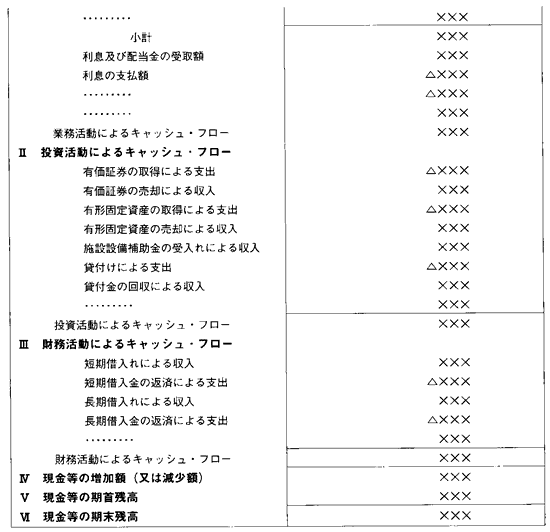
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















