資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(法人税)報酬、給料、賞与及び退職給与等
(報酬、給料、賞与及び退職給与等)
1 議決権のない株式を発行している場合の使用人兼務役員の判定
2 相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
3 役員報酬の既往減給分を一括支給した場合の取扱い
4 過大役員報酬の判定基準
5 名目だけの監査役に対して支給した賞与
6 出向先法人が支出する給与負担金のうち賞与に係る部分の損金不算入
7 解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与
8 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
9 役員及び使用人に支給する家族移転助成費
議決権のない株式を発行している場合の使用人兼務役員の判定
【 照会要旨】
法人税法施行令第71条第1項第4号((使用人兼務役員とされない役員))の持株割合による使用人兼務役員の判定に当たって、法人が議決権のない株式を発行している(4,300株)場合には、当該議決権のない株式の数を同条第2項に規定する発行済株式の総数に含めないことができますか。
なお、法人の株主はすべて個人株主であり、株主間に特殊の関係(法人税法施行令第71条第2項)はありません。
① 議決権のない株式を含めない場合
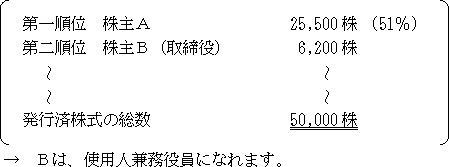
② 議決権のない株式を含める場合
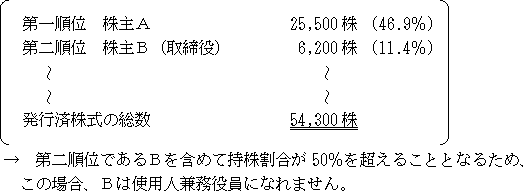
【 回答要旨】
法人税法施行令第71条第2項に規定する発行済株式の総数には、議決権のない株式が含まれます。
( 理 由)
商法第222条第1項において、会社は「数種の株式」を発行することができる旨が規定されており、議決権のない株式の発行も可能ですが、法人税法施行令第71条第2項の規定上、同項に規定する発行済株式の数から議決権のない株式の数を除外するとは規定されていません。
【 関係法令通達】
法人税法施行令第71第1項第4号、第2項
法人税基本通達1-3-1
商法第222条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
【 照会要旨】
発行済株式の98%を有していた代表者が死亡しましたが、その遺産相続に関して紛争が生じたため、相続財産の中に含まれる当該株式が未分割の状態になっています。
その株式が未分割の状態で、当社の取締役である長男、二男、三男及び四男(いずれも代表者の相続人であり、代表者死亡までは持株はありません。)に賞与を支給しましたが、これらの者が使用人兼務役員であるかどうかの判定に当たってその持株割合はどのように計算したらよいでしょうか。
【 回答要旨】
各人の相続分に応じた持株数により判定することになります。
( 理 由)
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属するものとされており(民法第898条)、相続の放棄、限定承認等がされない限り、法定又は指定相続分に応じて持分を有することになりますから、その相続分に応じた持分に基づいて持株割合を計算することになります。
(注) 民法第909条では遺産分割に遡及効を認めていますが、この規定自体、遡及的に共有状態の存在の事実までも否定するものではありませんので、現実の分割が相続分と異なったとしても、後日、その持株割合を修正する必要はないと考えられます。
【 関係法令通達】
法人税法施行令第71条
民法第898条、第909条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
役員報酬の既往減給分を一括支給した場合の取扱い
【 照会要旨】
当社は、かつて業績が不振でしたので、その回復を図るための対策の一つとして、2年前に株主総会の決議により役員報酬を従来に比し約20%減額し、そのまま現在に至っています。最近ようやく業績が好転してきたので、役員報酬を減額前の金額に戻し、併せて、既往の減額分の合計額を一括して支給したいと考えています。この既往の減額分の一括支給額は、税務上役員報酬として損金算入することが認められますか。
なお、現在の役員はいずれも2年前から引き続き在職しており、かつ、今回の増額後の役員報酬は、税務上も適正額の範囲内です。
【 回答要旨】
照会の役員報酬の既往減額分の一括支給は、税務上は役員賞与を支給したものとして、損金算入は認められません。
( 理 由)
役員報酬の増額があった場合には、定時株主総会において増額支給を決議した日を含む事業年度の期首にさかのぼって差額支給をする場合を除き、それ以前に遡及する差額支給は、すべて臨時の給与(賞与)として取り扱うこととされています(法人税基本通達9-2-9の2)。
したがって、照会のように、仮に業績不振のためにした減額分を回復するための増額であっても、減額時までさかのぼって増額支給するようなものは、役員賞与として取り扱われることになります。
【 関係法令通達】
法人税法第35条第1項
法人税基本通達9-2-9の2、9-2-13
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
過大役員報酬の判定基準
【 照会要旨】
A社は、その創立総会において、役員報酬の年額を総額1億円とすることとし、その各人別内訳は役員会で決定する旨を決議しました。
この決議に伴い、役員会において、甲取締役(代表者)は月額100万円以内、乙及び丙取締役(いずれも非常勤)は月額10万円以内と定めました。その後、この金額を改訂していないため、甲については、その支給額が1,200万円(100万円×12ヶ月)を超えることとなっていますが、甲、乙、丙の合計額では1億円を超えていません。
この場合において、役員報酬が過大であるか否かは、次のいずれによることになるのでしょうか。
① 創立総会決定の1億円を基準として判定する。
② 役員会決定の1,200万円(月額100万円)を基準として、個別で判定する。
(注) A社の常勤役員は、代表者のみです。
【 回答要旨】
創立総会においては支給額の総枠を定め、各人ごとの支給限度額の決定を役員会に一任したのですから、創立総会において各人ごとの支給限度額を定めたものと解されますので、役員会決定による各人ごとの支給限度額を基準として②により判定することになります。
【 関係法令通達】
法人税法第34条
法人税法施行令第69条第2号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
名目だけの監査役に対して支給した賞与
【 照会要旨】
同族会社が、使用人Aを名義株主とし、かつ、監査役に選任しましたが、同人は実質的には使用人にすぎませんので、その賞与は使用人賞与として損金算入が認められますか。
【 回答要旨】
法人が正規の手続を経て監査役に選任した者については、仮に実質的には使用人にすぎないとしても、税務上監査役でないとすることはできません。
監査役については、その性質に顧み使用人兼務役員としても認められないことになっていますので、その賞与の損金算入は認められません。
【 関係法令通達】
法人税法第35条第1項、第2項、第5項
法人税法施行令第71条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出向先法人が支出する給与負担金のうち賞与に係る部分の損金不算入
【 照会要旨】
B社は、親会社のA社から専務取締役として甲を受け入れています(甲はA社にあっては使用人)が、A社の甲に対する支給年額1,200万円(給与月額80万円、賞与(年2回)240万円)の負担額として、毎月100万円(年額1,200万円)をA社に支払っています。
法人税基本通達9-2-33((出向先法人が支出する給与負担金))によれば、B社のA社に対する給与負担金の支出は、B社から甲に対して給与を支給したものとして取り扱われ、さらに、その支出は定期的かつ定額であるので、全額役員報酬として損金の額に算入されると解して差し支えありませんか。
【 回答要旨】
B社の給与負担金1,200万円のうち240万円は役員賞与として損金不算入となります。
( 理 由)
法人税基本通達9-2-33は、出向者に対する給与を出向元法人が支給することとしているため、その原資として出向先法人が給与負担金を出向元法人に支払うこととしている場合において、その支出した給与負担金につき出向先法人自ら出向者に給与を支給したものとして取り扱うことが明らかにされているのであり、その給与が報酬又は賞与のいずれに該当するかについては、法人税基本通達9-2-34((出向先法人が支出する給与負担金に係る報酬と賞与の区分))によることとなります。
すなわち、B社がA社に対して支払う年額1,200万円の給与負担金のうち、A社が出向者である甲に支給した定期の給与の額960万円を超える部分の金額240万円は、B社の甲に対する役員賞与となります。
したがって、出向先法人から出向元法人に対する給与負担金の支出が定期的でなくとも、そのことのみをもって直ちに賞与となるわけではありませんし、また、定期的であればすべて報酬となるわけでもありません。
【 関係法令通達】
法人税基本通達9-2-13、9-2-33、9-2-34
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与
【 照会要旨】
法人が解散した場合において、引き続き清算人として清算事務に従事する旧役員に対しその解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与については、法人税法上退職給与として取り扱われますか。
【 回答要旨】
退職給与として取り扱われます。
( 理 由)
法人が解散した場合において、引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与は、所得税法上退職手当等として取り扱われています(所得税基本通達30-2(6))ので、法人税法上も退職給与として取り扱うことが相当と考えられます。
【 関係法令通達】
法人税法第36条
所得税基本通達30-2(6)
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
【 照会要旨】
当社では退職金の年功加算率が高いため、最近退職金の要支給額の増加傾向が著しくなっています。
そこで、労働組合と話し合って、退職金制度を改訂し、従来の勤続年数を打ち切って改訂時から起算して勤続年数を計算することにしました。ただし、改訂時の旧規程による退職金については、その2分の1を打切支給し、残りの2分の1は新規程による退職金に上積みして退職時に支給します。
この場合、改訂時における2分の1の打切支給は退職金として認められますか。
【 回答要旨】
退職金として認められません。
( 理 由)
退職給与の打切支給は、特定事由の発生時に、既往分の全部を打切支給する場合についてのみ認められます。
部分的な打切支給は退職給与としては認められませんので、賞与として取り扱うことになります。
【 関係法令通達】
法人税基本通達9-2-24
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
役員及び使用人に支給する家族移転助成費
【 照会要旨】
A社は、役員又は使用人が転任のため家族の全部又は一部を残して赴任した場合で、後日当該家族を転任先に呼び寄せることとしたときには、その家族の移転費用(金額は実費とし、領収証等により確認する。)の1/2相当額を支給することとしています。当該移転費用の助成費は、税務上賞与として取り扱われますか、それとも単純損金で差し支えありませんか。
この支給根拠として、使用人については就業規則に定めがありますが、役員については使用人に準じて支給することとしています。
なお、転任者自身の転居費用は、実費(全額)を支給しています。
【 回答要旨】
家族の移転費用の助成費は、家族の移転が本人の転任時から相当期間内に行われ、家族の移転と本人の転任との間に相当因果関係があり、その法人の業務のために使用したことが明らかな場合には、単純損金として取り扱われます。
なお、役員について支給に関する定めがない場合であっても、使用人と同様のルールに従って支給されているときには、同様に取り扱われることとなります。
【 関係法令通達】
法人税基本通達9-2-10(9)、(10)
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 議決権のない株式を発行している場合の使用人兼務役員の判定
2 相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
3 役員報酬の既往減給分を一括支給した場合の取扱い
4 過大役員報酬の判定基準
5 名目だけの監査役に対して支給した賞与
6 出向先法人が支出する給与負担金のうち賞与に係る部分の損金不算入
7 解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与
8 勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
9 役員及び使用人に支給する家族移転助成費
議決権のない株式を発行している場合の使用人兼務役員の判定
【 照会要旨】
法人税法施行令第71条第1項第4号((使用人兼務役員とされない役員))の持株割合による使用人兼務役員の判定に当たって、法人が議決権のない株式を発行している(4,300株)場合には、当該議決権のない株式の数を同条第2項に規定する発行済株式の総数に含めないことができますか。
なお、法人の株主はすべて個人株主であり、株主間に特殊の関係(法人税法施行令第71条第2項)はありません。
① 議決権のない株式を含めない場合
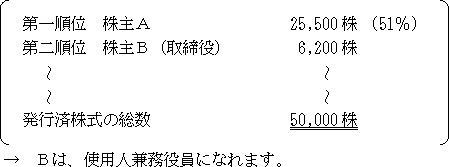
② 議決権のない株式を含める場合
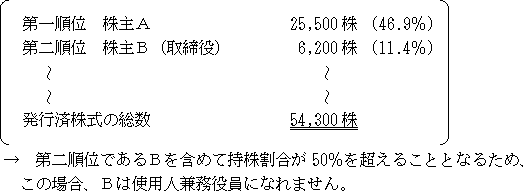
【 回答要旨】
法人税法施行令第71条第2項に規定する発行済株式の総数には、議決権のない株式が含まれます。
( 理 由)
商法第222条第1項において、会社は「数種の株式」を発行することができる旨が規定されており、議決権のない株式の発行も可能ですが、法人税法施行令第71条第2項の規定上、同項に規定する発行済株式の数から議決権のない株式の数を除外するとは規定されていません。
【 関係法令通達】
法人税法施行令第71第1項第4号、第2項
法人税基本通達1-3-1
商法第222条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
相続財産に含まれる株式が未分割である場合の使用人兼務役員の判定
【 照会要旨】
発行済株式の98%を有していた代表者が死亡しましたが、その遺産相続に関して紛争が生じたため、相続財産の中に含まれる当該株式が未分割の状態になっています。
その株式が未分割の状態で、当社の取締役である長男、二男、三男及び四男(いずれも代表者の相続人であり、代表者死亡までは持株はありません。)に賞与を支給しましたが、これらの者が使用人兼務役員であるかどうかの判定に当たってその持株割合はどのように計算したらよいでしょうか。
【 回答要旨】
各人の相続分に応じた持株数により判定することになります。
( 理 由)
相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属するものとされており(民法第898条)、相続の放棄、限定承認等がされない限り、法定又は指定相続分に応じて持分を有することになりますから、その相続分に応じた持分に基づいて持株割合を計算することになります。
(注) 民法第909条では遺産分割に遡及効を認めていますが、この規定自体、遡及的に共有状態の存在の事実までも否定するものではありませんので、現実の分割が相続分と異なったとしても、後日、その持株割合を修正する必要はないと考えられます。
【 関係法令通達】
法人税法施行令第71条
民法第898条、第909条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
役員報酬の既往減給分を一括支給した場合の取扱い
【 照会要旨】
当社は、かつて業績が不振でしたので、その回復を図るための対策の一つとして、2年前に株主総会の決議により役員報酬を従来に比し約20%減額し、そのまま現在に至っています。最近ようやく業績が好転してきたので、役員報酬を減額前の金額に戻し、併せて、既往の減額分の合計額を一括して支給したいと考えています。この既往の減額分の一括支給額は、税務上役員報酬として損金算入することが認められますか。
なお、現在の役員はいずれも2年前から引き続き在職しており、かつ、今回の増額後の役員報酬は、税務上も適正額の範囲内です。
【 回答要旨】
照会の役員報酬の既往減額分の一括支給は、税務上は役員賞与を支給したものとして、損金算入は認められません。
( 理 由)
役員報酬の増額があった場合には、定時株主総会において増額支給を決議した日を含む事業年度の期首にさかのぼって差額支給をする場合を除き、それ以前に遡及する差額支給は、すべて臨時の給与(賞与)として取り扱うこととされています(法人税基本通達9-2-9の2)。
したがって、照会のように、仮に業績不振のためにした減額分を回復するための増額であっても、減額時までさかのぼって増額支給するようなものは、役員賞与として取り扱われることになります。
【 関係法令通達】
法人税法第35条第1項
法人税基本通達9-2-9の2、9-2-13
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
過大役員報酬の判定基準
【 照会要旨】
A社は、その創立総会において、役員報酬の年額を総額1億円とすることとし、その各人別内訳は役員会で決定する旨を決議しました。
この決議に伴い、役員会において、甲取締役(代表者)は月額100万円以内、乙及び丙取締役(いずれも非常勤)は月額10万円以内と定めました。その後、この金額を改訂していないため、甲については、その支給額が1,200万円(100万円×12ヶ月)を超えることとなっていますが、甲、乙、丙の合計額では1億円を超えていません。
この場合において、役員報酬が過大であるか否かは、次のいずれによることになるのでしょうか。
① 創立総会決定の1億円を基準として判定する。
② 役員会決定の1,200万円(月額100万円)を基準として、個別で判定する。
(注) A社の常勤役員は、代表者のみです。
【 回答要旨】
創立総会においては支給額の総枠を定め、各人ごとの支給限度額の決定を役員会に一任したのですから、創立総会において各人ごとの支給限度額を定めたものと解されますので、役員会決定による各人ごとの支給限度額を基準として②により判定することになります。
【 関係法令通達】
法人税法第34条
法人税法施行令第69条第2号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
名目だけの監査役に対して支給した賞与
【 照会要旨】
同族会社が、使用人Aを名義株主とし、かつ、監査役に選任しましたが、同人は実質的には使用人にすぎませんので、その賞与は使用人賞与として損金算入が認められますか。
【 回答要旨】
法人が正規の手続を経て監査役に選任した者については、仮に実質的には使用人にすぎないとしても、税務上監査役でないとすることはできません。
監査役については、その性質に顧み使用人兼務役員としても認められないことになっていますので、その賞与の損金算入は認められません。
【 関係法令通達】
法人税法第35条第1項、第2項、第5項
法人税法施行令第71条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出向先法人が支出する給与負担金のうち賞与に係る部分の損金不算入
【 照会要旨】
B社は、親会社のA社から専務取締役として甲を受け入れています(甲はA社にあっては使用人)が、A社の甲に対する支給年額1,200万円(給与月額80万円、賞与(年2回)240万円)の負担額として、毎月100万円(年額1,200万円)をA社に支払っています。
法人税基本通達9-2-33((出向先法人が支出する給与負担金))によれば、B社のA社に対する給与負担金の支出は、B社から甲に対して給与を支給したものとして取り扱われ、さらに、その支出は定期的かつ定額であるので、全額役員報酬として損金の額に算入されると解して差し支えありませんか。
【 回答要旨】
B社の給与負担金1,200万円のうち240万円は役員賞与として損金不算入となります。
( 理 由)
法人税基本通達9-2-33は、出向者に対する給与を出向元法人が支給することとしているため、その原資として出向先法人が給与負担金を出向元法人に支払うこととしている場合において、その支出した給与負担金につき出向先法人自ら出向者に給与を支給したものとして取り扱うことが明らかにされているのであり、その給与が報酬又は賞与のいずれに該当するかについては、法人税基本通達9-2-34((出向先法人が支出する給与負担金に係る報酬と賞与の区分))によることとなります。
すなわち、B社がA社に対して支払う年額1,200万円の給与負担金のうち、A社が出向者である甲に支給した定期の給与の額960万円を超える部分の金額240万円は、B社の甲に対する役員賞与となります。
したがって、出向先法人から出向元法人に対する給与負担金の支出が定期的でなくとも、そのことのみをもって直ちに賞与となるわけではありませんし、また、定期的であればすべて報酬となるわけでもありません。
【 関係法令通達】
法人税基本通達9-2-13、9-2-33、9-2-34
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与
【 照会要旨】
法人が解散した場合において、引き続き清算人として清算事務に従事する旧役員に対しその解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与については、法人税法上退職給与として取り扱われますか。
【 回答要旨】
退職給与として取り扱われます。
( 理 由)
法人が解散した場合において、引き続き役員又は使用人として清算事務に従事する者に対し、その解散前の勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与は、所得税法上退職手当等として取り扱われています(所得税基本通達30-2(6))ので、法人税法上も退職給与として取り扱うことが相当と考えられます。
【 関係法令通達】
法人税法第36条
所得税基本通達30-2(6)
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
勤続年数の打切りに伴う退職給与の一部打切支給
【 照会要旨】
当社では退職金の年功加算率が高いため、最近退職金の要支給額の増加傾向が著しくなっています。
そこで、労働組合と話し合って、退職金制度を改訂し、従来の勤続年数を打ち切って改訂時から起算して勤続年数を計算することにしました。ただし、改訂時の旧規程による退職金については、その2分の1を打切支給し、残りの2分の1は新規程による退職金に上積みして退職時に支給します。
この場合、改訂時における2分の1の打切支給は退職金として認められますか。
【 回答要旨】
退職金として認められません。
( 理 由)
退職給与の打切支給は、特定事由の発生時に、既往分の全部を打切支給する場合についてのみ認められます。
部分的な打切支給は退職給与としては認められませんので、賞与として取り扱うことになります。
【 関係法令通達】
法人税基本通達9-2-24
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
役員及び使用人に支給する家族移転助成費
【 照会要旨】
A社は、役員又は使用人が転任のため家族の全部又は一部を残して赴任した場合で、後日当該家族を転任先に呼び寄せることとしたときには、その家族の移転費用(金額は実費とし、領収証等により確認する。)の1/2相当額を支給することとしています。当該移転費用の助成費は、税務上賞与として取り扱われますか、それとも単純損金で差し支えありませんか。
この支給根拠として、使用人については就業規則に定めがありますが、役員については使用人に準じて支給することとしています。
なお、転任者自身の転居費用は、実費(全額)を支給しています。
【 回答要旨】
家族の移転費用の助成費は、家族の移転が本人の転任時から相当期間内に行われ、家族の移転と本人の転任との間に相当因果関係があり、その法人の業務のために使用したことが明らかな場合には、単純損金として取り扱われます。
なお、役員について支給に関する定めがない場合であっても、使用人と同様のルールに従って支給されているときには、同様に取り扱われることとなります。
【 関係法令通達】
法人税基本通達9-2-10(9)、(10)
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















