資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)不動産等の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)
(不動産等の譲渡に関する契約書(第1号の1文書))
1 土地贈与契約書
2 不動産購入申込書
3 不動産の範囲
4 無体財産権の範囲
5 船舶の範囲
6 航空機の範囲
7 営業の譲渡の意義
8 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
9 土地売買契約書
10 協定書
11 不動産の売渡証書
12 土地交換契約書
土地贈与契約書
【 照会要旨】
土地の贈与契約書に贈与する土地の評価額を記載した場合、その評価額は記載金額になるのでしょうか。
【 回答要旨】
不動産をその同一性を保持させつつ他人に移転させることを内容とするものは、対価を受けるかどうかを問わず、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。
なお、贈与は無償契約ですから、贈与契約書に土地の評価額が記載されていても、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではありませんので、記載金額には該当しません。
譲渡契約の原因としては、売買、交換、贈与、代物弁済、法人等に対する現物出資、寄付行為等があります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
不動産購入申込書
【 照会要旨】
この文書は、建売住宅の購入申込者が2部複写の方法により所要事項を記載して販売会社へ提出し、うち1部に販売会社の宅地建物取引主任の氏名(押印を含む。)を記載して購入申込者に返却するものですが、別途売買契約書を作成することにしていることから、いずれも課税文書に該当しないと考えてよいのでしょうか。
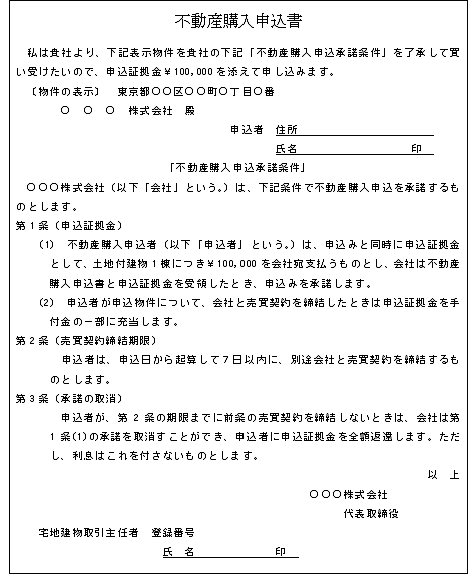
【 回答要旨】
販売会社が保存するものは、課税文書には該当しませんが、申込者が保存するものは、記載金額のない第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。
販売会社が保存するものは、当該申込書を受理することによって自動的に契約が成立することとなっていますが、別途売買契約書を作成することが記載されていることから、印紙税法上の契約書としては取り扱われません(基通第21条2項1号)。
申込者が保存するものは、販売会社が申込みに対する承諾事実を証明して申込者に交付するものですから、第1号の1文書に該当します。
申込証拠金は、契約金額ではありませんから、記載金額にはなりません。
なお、物件の表示欄に不動産の金額を記載している場合には、その記載金額に応じて所要の印紙税を納付することになります。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第21条第2項第1号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
不動産の範囲
【 照会要旨】
第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当する「不動産」とは、民法第86条に規定する「土地及び土地の定着物」と考えてよいのでしょうか。
【 回答要旨】
印紙税法における「不動産」には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含めることにしています(第1号文書の定義欄)。
例えば、工場抵当法に規定する工場財団は、同法第14条において、「工場財団はこれを1個の不動産とみなす」と規定していますから、印紙税法上は、財団を組成するものの全体を1個の不動産として取り扱うことになります。
印紙税法上、不動産として取り扱われるものは、おおむね次のとおりです(基通第1号の1文書の1)。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第86条に規定する不動産
(2) 工場抵当法(明治38年法律第54号)第9条の規定により登記された工場財団
(3) 鉱業抵当法(明治38年法律第55号)第3条の規定により登記された鉱業財団
(4) 漁業財団抵当法(大正14年法律第9号)第6条の規定により登記された漁業財団
(5) 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第26条《工場抵当法の準用》の規定により登記された港湾運送事業財団
(6) 道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号)第6条《所有権保存の登記》規定により登記された道路交通事業財団
(7) 観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号)第7条《所有権保存の登記》の規定により登記された観光施設財団
(8) 立木ニ関スル法律(昭和42年法律第22号)の規定により登記された立木
ただし、登記されていない立木であっても明認方法を施したものは、不動産として取り扱われます。
なお、いずれの場合においても、立木を立木としてではなく、伐採して木材等とするものとして譲渡することが明らかであるときは、不動産として取り扱わず、物品として取り扱われます。
(9) 鉄道抵当法(明治38年法律第53号)第28条の2の規定により登録された鉄道財団
(10) 軌道ノ抵当ニ関スル法律(明治42年法律第28号)第1条の規定により登録された軌道財団
(11) 自動車交通事業法(昭和6年法律第52号)第38条の規定により登録された自動車交通事業財団
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
無体財産権の範囲
【 照会要旨】
第1号の1文書として無体財産権の譲渡に関する契約書が掲げられていますが、この無体財産権の範囲等について説明してください。
【 回答要旨】
第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)は、無体財産権そのものの権利を他人に譲渡する場合の契約書であり、無体財産権を利用できる権利(実施権又は使用権)を他人に与えたり、その与えられたところの無体財産権を利用できる権利をさらにそのまま第三者に譲渡したりする場合の契約書は、これには当たりません。
無体財産権という用語は、一般に物権及び債権を除いたところの財産権として用いられていますが、印紙税法では、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権ということにしています(第1号文書の定義欄参照)。
したがって、ノウハウなどこれ以外の無体財産権については、これを譲渡する契約書を作成しても、課税文書に該当しないということになります。
印紙税法上の無体財産権の内容は、次のとおりです。
(1) 特許権
特許権とは、特許発明を独占的排他的に支配する権利で、設定の登録により発生します。したがって、特許法(昭和34年法律第121号)第66条《特許権の設定の登録》の規定により登録されたものが特許権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは、特許権には該当しません。
なお、「特許権として登録された場合には譲渡する」ことを内容とする契約書は、特許権そのものの譲渡を約する(予約又は条件付契約)ものですから、第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)に該当します。
(2) 実用新案権
実用新案権とは、実用新案を独占的排他的に支配する権利で、設定の登録により発生します。したがって、実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条《実用新案権の設定の登録》の規定により登録されたものが、実用新案権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは含まれません。
(3) 商標権
商標権とは、商標を独占的排他的に使用する権利で、設定の登録により発生します。したがって、商標法(昭和34年法律第127号)第18条《商標権の設定の登録》の規定により登録されたものが、商標権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは含まれません。
(4) 意匠権
意匠権とは、工業上利用できる意匠を排他的に支配する権利で、設定の登録により発生します。したがって、意匠法(昭和34年法律第125号)第20条《意匠権の設定の登録》の規定により登録されたものが意匠権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは含まれません。
(5) 回路配置利用権
回路配置利用権とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第3条《回路配置利用権の設定の登録》の規定により、登録されたものをいいます。
(6) 育成者権
育成者権とは、種苗法上の品種登録を受けている登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として排他的に利用する権利で、品種登録により発生します。
(7) 商号
商号とは、商人の氏、氏名その他の名称のことです。商号の登記は第三者への対抗要件にすぎませんから、登記のない商号も商号に含まれます。
(8) 著作権
著作権とは、文芸、芸術、美術の範囲に属する著作物を独占的排他的に支配する権利で、文書等を著作することにより発生します。著作権の登録は第三者への対抗要件にすぎませんから、登録のない著作権も著作権に含まれます。 (注) 現在では著作権の範囲が広まり、コンピュータ・プログラム等についても著作権に含まれています。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
船舶の範囲
【 照会要旨】
第1号の1文書として船舶の譲渡に関する契約書が掲げられていますが、この船舶の範囲について説明してください。
【 回答要旨】
船舶とは、船舶法(明治32年法律第46号)第5条に規定する船舶原簿に登録を要する総トン数20トン以上の船舶及びこれに類する外国籍の船舶をいい、その他の船舶は物品として取り扱われます。
なお、櫓櫂(ろかい)のみをもって運転し又は主として櫓櫂をもって運転する舟には船舶法第5条の規定は適用されず、また、推進器を有しない浚渫(しゅんせつ)船は船舶とみなされないこととされていることから、これらの船は総トン数が20トン以上であっても物品として取り扱うことになります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
航空機の範囲
【 照会要旨】
第1号の1文書に該当する「航空機の譲渡」には、ヘリコプターなどの譲渡も含まれるのでしょうか。
【 回答要旨】
航空機の意義については、航空法(昭和27年法律第231号)第2条《定義》に規定する航空機をいいます。
同条によりますと、航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいいます。
したがって、ヘリコプターの譲渡も当然航空機の譲渡に含まれます。なお、航空法では、航空機は航空機登録原簿に登録することとされていますが、この登録がなされているかどうかは印紙税の取扱い上全く関係ありません(基通第1号の1文書の21)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の1文書
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
営業の譲渡の意義
【 照会要旨】
第1号の1文書に該当する「営業の譲渡」には、例えば、営業活動中の一部門を譲渡する場合も含まれるのでしょうか。
【 回答要旨】
営業という語は二つの意味に用いられます。一つは継続的、集団的に同種の営利行為を行うこと、すなわち営業活動を意味し(主観的な意味の営業)、もう一つは特定の目的に供される総括的な財産的組織体、すなわち企業組織体を意味します(客観的な意味の営業)。ここにいう営業は後者であり、課税物件表第17号の非課税物件欄に規定する営業は前者です。
営業の譲渡の場合の営業とは、このような財産的組織体、いわゆる営業活動を構成している動産、不動産、債権、債務等を包括した一体的な権利、財産としてとらえられるものをいいますので、営業活動における一部門であっても、財産的組織体として譲渡する限りにおいては、営業の譲渡に含まれます。
営業譲渡契約書の記載金額は、その組織体を構成している動産、不動産の個々の金額(又はその合計額)をいうのではなく、その組織体を譲渡することについて対価として支払われるべき金額をいいます(基通第1号の1文書の22)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の1文書
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
【 照会要旨】
平成9年4月から、不動産売買契約書について印紙税が軽減されていると聞きましたが、具体的な取扱いについて説明してください。
【 回答要旨】
租税特別措置法の一部が改正されたことにより、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられました。その概要等は次のとおりです。
【 軽減措置の概要】
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。
【 軽減後の税率】
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりになります。
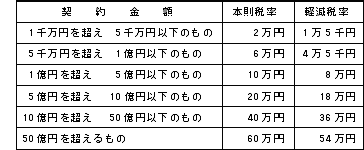
【 軽減措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書の範囲】
軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表第1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいますが、一の文書が、不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象になります。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第91条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
土地売買契約書
【 照会要旨】
会社員である乙野一郎は将来のマイホーム建設に備えて、次のような土地売買契約書を不動産業者と結びましたが、どのように取り扱えばよいのでしょうか。また、印紙をちょう付する義務のある者は誰でしょうか。
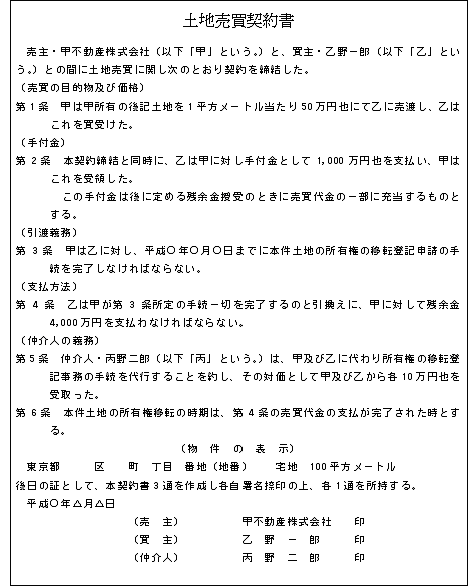
【 回答要旨】
ご質問の文書は、記載金額5,000万円の第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。
記載金額は、1平方メートル当たりの金額(50万円)と面積(100平方メートル)を乗じて得た金額です。
手付金(1,000万円)及び仲介手数料(計20万円)の受領事実については、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当しますが、通則3のイの規定により、この文書全体が第1号の1文書になります。
なお、納税義務者は、契約当事者である売主及び買主ですが、仲介人の所持する文書も課税対象になります。
(注) 平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書(記載された契約金額が1千万円を超えるもの)については、税率が軽減されています。
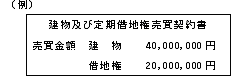
この契約書に記載された契約金額は60,000,000円(建物売買代金40,000,000円+借地権売買代金20,000,000円)ですから、印紙税額は45,000円になります。
【 軽減措置の概要】
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。
【 軽減後の税率】
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりになります。
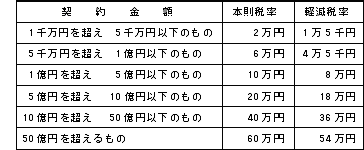
【 軽減措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書の範囲】
軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表第1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいますが、一の文書が、不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象になります。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第91条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
協定書
【 照会要旨】
不動産の売買に当たり次の協定書を作成しましたが、これは、後日正式契約を取り交わすこととしていますので、不課税文書と考えてよろしいのでしょうか。
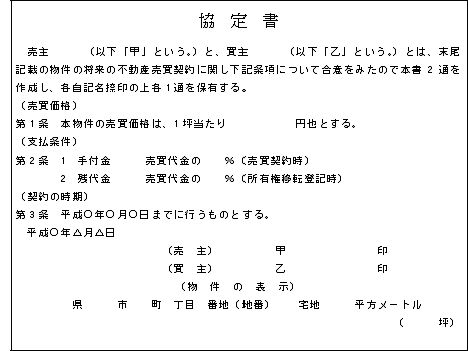
【 回答要旨】
ご質問の文書は、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当し、記載金額に応じた収入印紙をちょう付しなければなりません。記載金額は、1坪当たりの金額と面積を乗じて得た金額です。
課税物件表に掲げられている契約書については、通則5にその定義規定を置いていますが、その概要は次のとおりです。
すなわち、契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約当事者間において作成する文書で、
① 契約(その予約を含みます。)の成立又は更改の事実を証明する目的で作成する文書
② 契約内容の変更又は補充の事実を証明する目的で作成する文書
をいい、さらに
③ 念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証する文書を含むことにしています。
ここにいう契約の予約とは、契約の当事者のうち、いずれかが将来希望したときに一定の内容の契約を締結することを約する契約、すなわち、本契約を将来成立させることを約する契約をいいます。
経済取引に関連して作成される文書は、多種多様であり、予約契約書についても、契約証書、協定書、念書、覚書、約定書、承諾書、証明書など様々な名称が用いられていますので、課税文書に該当するかどうかの判断に当たっては特に注意が必要と思われます。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
不動産の売渡証書
【 照会要旨】
不動産の売渡証書とその売渡代金の受領事実とを記載した文書ですが、印紙をはる必要があるのでしょうか。
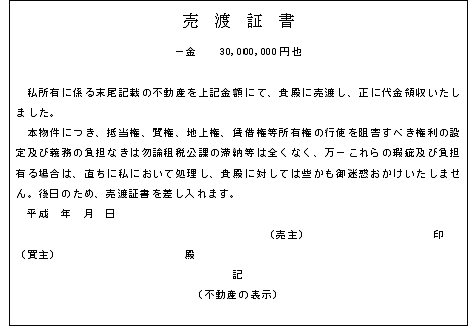
【 回答要旨】
ご質問の文書は、不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)と売上代金に係る金銭の受取書(第17号の1文書)に該当しますが、通則3のイの規定により、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書になります。売渡証書は、登記をする際、売主が改めて売渡物件を表示して、その売渡事実を証明し、併せて代金の受領事実を記載し買主に交付するものですが、たとえ、別に不動産の売買契約書を作成している場合であっても、不動産の譲渡に関する契約書として課税されます。
なお、文書の名称は、売渡証書、売渡証明、念書その他名称のいかんを問いません。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
土地交換契約書
【 照会要旨】
次の土地交換契約書は、どのように取り扱われるのでしょうか。
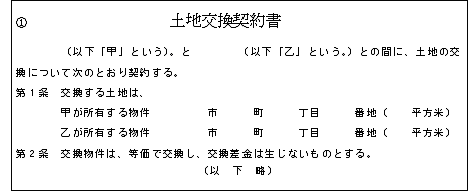
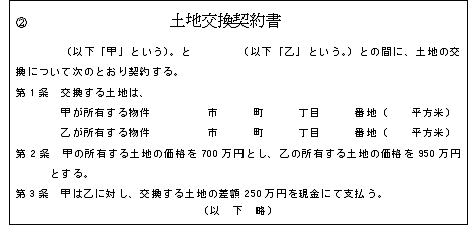
【 回答要旨】
①の文書は、記載金額のない第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)です。
②の文書は、記載金額950万円の第1号の1文書です。
土地の交換契約書は、土地の所有権を移転させることを内容とするものですから、第1号の1文書に該当します。
交換金額が記載されていないときは、記載金額のないものになります。
交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額が、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金がそれぞれ記載金額になります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 土地贈与契約書
2 不動産購入申込書
3 不動産の範囲
4 無体財産権の範囲
5 船舶の範囲
6 航空機の範囲
7 営業の譲渡の意義
8 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
9 土地売買契約書
10 協定書
11 不動産の売渡証書
12 土地交換契約書
土地贈与契約書
【 照会要旨】
土地の贈与契約書に贈与する土地の評価額を記載した場合、その評価額は記載金額になるのでしょうか。
【 回答要旨】
不動産をその同一性を保持させつつ他人に移転させることを内容とするものは、対価を受けるかどうかを問わず、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。
なお、贈与は無償契約ですから、贈与契約書に土地の評価額が記載されていても、その評価額は不動産譲渡の対価としての金額ではありませんので、記載金額には該当しません。
譲渡契約の原因としては、売買、交換、贈与、代物弁済、法人等に対する現物出資、寄付行為等があります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
不動産購入申込書
【 照会要旨】
この文書は、建売住宅の購入申込者が2部複写の方法により所要事項を記載して販売会社へ提出し、うち1部に販売会社の宅地建物取引主任の氏名(押印を含む。)を記載して購入申込者に返却するものですが、別途売買契約書を作成することにしていることから、いずれも課税文書に該当しないと考えてよいのでしょうか。
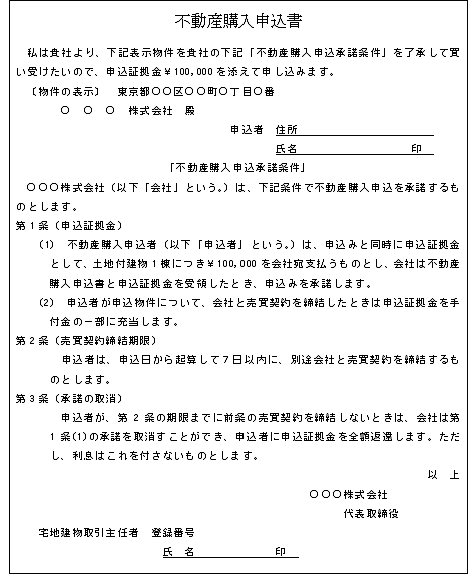
【 回答要旨】
販売会社が保存するものは、課税文書には該当しませんが、申込者が保存するものは、記載金額のない第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。
販売会社が保存するものは、当該申込書を受理することによって自動的に契約が成立することとなっていますが、別途売買契約書を作成することが記載されていることから、印紙税法上の契約書としては取り扱われません(基通第21条2項1号)。
申込者が保存するものは、販売会社が申込みに対する承諾事実を証明して申込者に交付するものですから、第1号の1文書に該当します。
申込証拠金は、契約金額ではありませんから、記載金額にはなりません。
なお、物件の表示欄に不動産の金額を記載している場合には、その記載金額に応じて所要の印紙税を納付することになります。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第21条第2項第1号
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
不動産の範囲
【 照会要旨】
第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当する「不動産」とは、民法第86条に規定する「土地及び土地の定着物」と考えてよいのでしょうか。
【 回答要旨】
印紙税法における「不動産」には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含めることにしています(第1号文書の定義欄)。
例えば、工場抵当法に規定する工場財団は、同法第14条において、「工場財団はこれを1個の不動産とみなす」と規定していますから、印紙税法上は、財団を組成するものの全体を1個の不動産として取り扱うことになります。
印紙税法上、不動産として取り扱われるものは、おおむね次のとおりです(基通第1号の1文書の1)。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第86条に規定する不動産
(2) 工場抵当法(明治38年法律第54号)第9条の規定により登記された工場財団
(3) 鉱業抵当法(明治38年法律第55号)第3条の規定により登記された鉱業財団
(4) 漁業財団抵当法(大正14年法律第9号)第6条の規定により登記された漁業財団
(5) 港湾運送事業法(昭和26年法律第161号)第26条《工場抵当法の準用》の規定により登記された港湾運送事業財団
(6) 道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号)第6条《所有権保存の登記》規定により登記された道路交通事業財団
(7) 観光施設財団抵当法(昭和43年法律第91号)第7条《所有権保存の登記》の規定により登記された観光施設財団
(8) 立木ニ関スル法律(昭和42年法律第22号)の規定により登記された立木
ただし、登記されていない立木であっても明認方法を施したものは、不動産として取り扱われます。
なお、いずれの場合においても、立木を立木としてではなく、伐採して木材等とするものとして譲渡することが明らかであるときは、不動産として取り扱わず、物品として取り扱われます。
(9) 鉄道抵当法(明治38年法律第53号)第28条の2の規定により登録された鉄道財団
(10) 軌道ノ抵当ニ関スル法律(明治42年法律第28号)第1条の規定により登録された軌道財団
(11) 自動車交通事業法(昭和6年法律第52号)第38条の規定により登録された自動車交通事業財団
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
無体財産権の範囲
【 照会要旨】
第1号の1文書として無体財産権の譲渡に関する契約書が掲げられていますが、この無体財産権の範囲等について説明してください。
【 回答要旨】
第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)は、無体財産権そのものの権利を他人に譲渡する場合の契約書であり、無体財産権を利用できる権利(実施権又は使用権)を他人に与えたり、その与えられたところの無体財産権を利用できる権利をさらにそのまま第三者に譲渡したりする場合の契約書は、これには当たりません。
無体財産権という用語は、一般に物権及び債権を除いたところの財産権として用いられていますが、印紙税法では、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権の8種類のものに限って無体財産権ということにしています(第1号文書の定義欄参照)。
したがって、ノウハウなどこれ以外の無体財産権については、これを譲渡する契約書を作成しても、課税文書に該当しないということになります。
印紙税法上の無体財産権の内容は、次のとおりです。
(1) 特許権
特許権とは、特許発明を独占的排他的に支配する権利で、設定の登録により発生します。したがって、特許法(昭和34年法律第121号)第66条《特許権の設定の登録》の規定により登録されたものが特許権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは、特許権には該当しません。
なお、「特許権として登録された場合には譲渡する」ことを内容とする契約書は、特許権そのものの譲渡を約する(予約又は条件付契約)ものですから、第1号の1文書(無体財産権の譲渡に関する契約書)に該当します。
(2) 実用新案権
実用新案権とは、実用新案を独占的排他的に支配する権利で、設定の登録により発生します。したがって、実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条《実用新案権の設定の登録》の規定により登録されたものが、実用新案権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは含まれません。
(3) 商標権
商標権とは、商標を独占的排他的に使用する権利で、設定の登録により発生します。したがって、商標法(昭和34年法律第127号)第18条《商標権の設定の登録》の規定により登録されたものが、商標権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは含まれません。
(4) 意匠権
意匠権とは、工業上利用できる意匠を排他的に支配する権利で、設定の登録により発生します。したがって、意匠法(昭和34年法律第125号)第20条《意匠権の設定の登録》の規定により登録されたものが意匠権ということになり、未登録のものや外国法に基づくものは含まれません。
(5) 回路配置利用権
回路配置利用権とは、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第3条《回路配置利用権の設定の登録》の規定により、登録されたものをいいます。
(6) 育成者権
育成者権とは、種苗法上の品種登録を受けている登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として排他的に利用する権利で、品種登録により発生します。
(7) 商号
商号とは、商人の氏、氏名その他の名称のことです。商号の登記は第三者への対抗要件にすぎませんから、登記のない商号も商号に含まれます。
(8) 著作権
著作権とは、文芸、芸術、美術の範囲に属する著作物を独占的排他的に支配する権利で、文書等を著作することにより発生します。著作権の登録は第三者への対抗要件にすぎませんから、登録のない著作権も著作権に含まれます。 (注) 現在では著作権の範囲が広まり、コンピュータ・プログラム等についても著作権に含まれています。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
船舶の範囲
【 照会要旨】
第1号の1文書として船舶の譲渡に関する契約書が掲げられていますが、この船舶の範囲について説明してください。
【 回答要旨】
船舶とは、船舶法(明治32年法律第46号)第5条に規定する船舶原簿に登録を要する総トン数20トン以上の船舶及びこれに類する外国籍の船舶をいい、その他の船舶は物品として取り扱われます。
なお、櫓櫂(ろかい)のみをもって運転し又は主として櫓櫂をもって運転する舟には船舶法第5条の規定は適用されず、また、推進器を有しない浚渫(しゅんせつ)船は船舶とみなされないこととされていることから、これらの船は総トン数が20トン以上であっても物品として取り扱うことになります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
航空機の範囲
【 照会要旨】
第1号の1文書に該当する「航空機の譲渡」には、ヘリコプターなどの譲渡も含まれるのでしょうか。
【 回答要旨】
航空機の意義については、航空法(昭和27年法律第231号)第2条《定義》に規定する航空機をいいます。
同条によりますと、航空機とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいいます。
したがって、ヘリコプターの譲渡も当然航空機の譲渡に含まれます。なお、航空法では、航空機は航空機登録原簿に登録することとされていますが、この登録がなされているかどうかは印紙税の取扱い上全く関係ありません(基通第1号の1文書の21)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の1文書
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
営業の譲渡の意義
【 照会要旨】
第1号の1文書に該当する「営業の譲渡」には、例えば、営業活動中の一部門を譲渡する場合も含まれるのでしょうか。
【 回答要旨】
営業という語は二つの意味に用いられます。一つは継続的、集団的に同種の営利行為を行うこと、すなわち営業活動を意味し(主観的な意味の営業)、もう一つは特定の目的に供される総括的な財産的組織体、すなわち企業組織体を意味します(客観的な意味の営業)。ここにいう営業は後者であり、課税物件表第17号の非課税物件欄に規定する営業は前者です。
営業の譲渡の場合の営業とは、このような財産的組織体、いわゆる営業活動を構成している動産、不動産、債権、債務等を包括した一体的な権利、財産としてとらえられるものをいいますので、営業活動における一部門であっても、財産的組織体として譲渡する限りにおいては、営業の譲渡に含まれます。
営業譲渡契約書の記載金額は、その組織体を構成している動産、不動産の個々の金額(又はその合計額)をいうのではなく、その組織体を譲渡することについて対価として支払われるべき金額をいいます(基通第1号の1文書の22)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達別表第一 第1号の1文書
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
【 照会要旨】
平成9年4月から、不動産売買契約書について印紙税が軽減されていると聞きましたが、具体的な取扱いについて説明してください。
【 回答要旨】
租税特別措置法の一部が改正されたことにより、不動産の譲渡に関する契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられました。その概要等は次のとおりです。
【 軽減措置の概要】
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。
【 軽減後の税率】
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりになります。
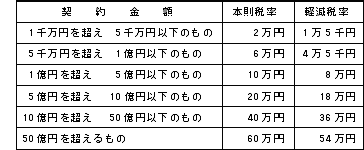
【 軽減措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書の範囲】
軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表第1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいますが、一の文書が、不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象になります。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第91条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
土地売買契約書
【 照会要旨】
会社員である乙野一郎は将来のマイホーム建設に備えて、次のような土地売買契約書を不動産業者と結びましたが、どのように取り扱えばよいのでしょうか。また、印紙をちょう付する義務のある者は誰でしょうか。
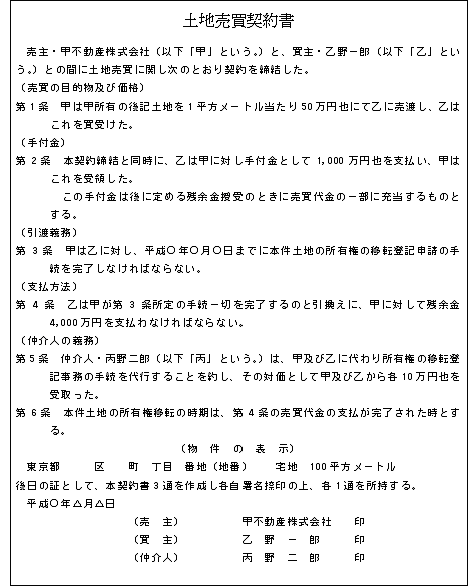
【 回答要旨】
ご質問の文書は、記載金額5,000万円の第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当します。
記載金額は、1平方メートル当たりの金額(50万円)と面積(100平方メートル)を乗じて得た金額です。
手付金(1,000万円)及び仲介手数料(計20万円)の受領事実については、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当しますが、通則3のイの規定により、この文書全体が第1号の1文書になります。
なお、納税義務者は、契約当事者である売主及び買主ですが、仲介人の所持する文書も課税対象になります。
(注) 平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書(記載された契約金額が1千万円を超えるもの)については、税率が軽減されています。
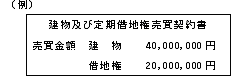
この契約書に記載された契約金額は60,000,000円(建物売買代金40,000,000円+借地権売買代金20,000,000円)ですから、印紙税額は45,000円になります。
【 軽減措置の概要】
軽減措置の対象となる契約書は、不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、土地・建物の売買の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。
【 軽減後の税率】
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりになります。
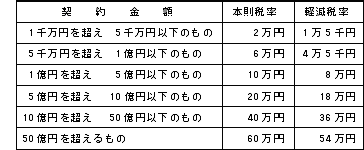
【 軽減措置の対象となる不動産の譲渡に関する契約書の範囲】
軽減措置の対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、課税物件表第1号文書の物件名欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」をいいますが、一の文書が、不動産の譲渡に関する契約書と同号に掲げる他の契約書とに該当するものも軽減措置の対象になります。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第91条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
協定書
【 照会要旨】
不動産の売買に当たり次の協定書を作成しましたが、これは、後日正式契約を取り交わすこととしていますので、不課税文書と考えてよろしいのでしょうか。
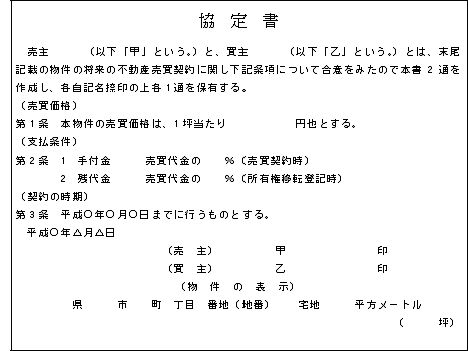
【 回答要旨】
ご質問の文書は、第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)に該当し、記載金額に応じた収入印紙をちょう付しなければなりません。記載金額は、1坪当たりの金額と面積を乗じて得た金額です。
課税物件表に掲げられている契約書については、通則5にその定義規定を置いていますが、その概要は次のとおりです。
すなわち、契約書とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約当事者間において作成する文書で、
① 契約(その予約を含みます。)の成立又は更改の事実を証明する目的で作成する文書
② 契約内容の変更又は補充の事実を証明する目的で作成する文書
をいい、さらに
③ 念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証する文書を含むことにしています。
ここにいう契約の予約とは、契約の当事者のうち、いずれかが将来希望したときに一定の内容の契約を締結することを約する契約、すなわち、本契約を将来成立させることを約する契約をいいます。
経済取引に関連して作成される文書は、多種多様であり、予約契約書についても、契約証書、協定書、念書、覚書、約定書、承諾書、証明書など様々な名称が用いられていますので、課税文書に該当するかどうかの判断に当たっては特に注意が必要と思われます。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
不動産の売渡証書
【 照会要旨】
不動産の売渡証書とその売渡代金の受領事実とを記載した文書ですが、印紙をはる必要があるのでしょうか。
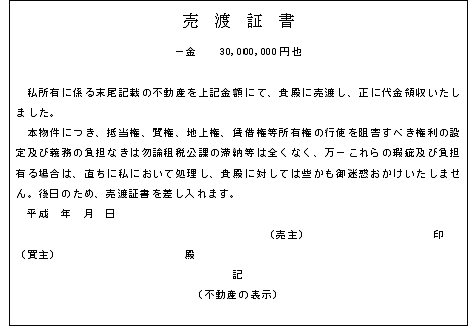
【 回答要旨】
ご質問の文書は、不動産の譲渡に関する契約書(第1号の1文書)と売上代金に係る金銭の受取書(第17号の1文書)に該当しますが、通則3のイの規定により、記載金額3,000万円の不動産の譲渡に関する契約書になります。売渡証書は、登記をする際、売主が改めて売渡物件を表示して、その売渡事実を証明し、併せて代金の受領事実を記載し買主に交付するものですが、たとえ、別に不動産の売買契約書を作成している場合であっても、不動産の譲渡に関する契約書として課税されます。
なお、文書の名称は、売渡証書、売渡証明、念書その他名称のいかんを問いません。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
土地交換契約書
【 照会要旨】
次の土地交換契約書は、どのように取り扱われるのでしょうか。
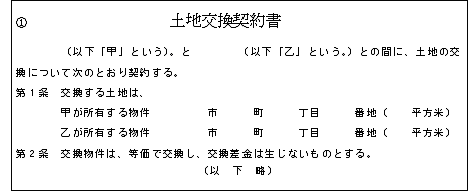
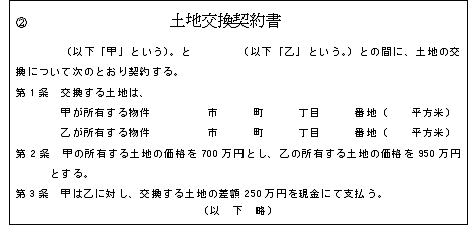
【 回答要旨】
①の文書は、記載金額のない第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)です。
②の文書は、記載金額950万円の第1号の1文書です。
土地の交換契約書は、土地の所有権を移転させることを内容とするものですから、第1号の1文書に該当します。
交換金額が記載されていないときは、記載金額のないものになります。
交換対象物の双方の価額が記載されているときはいずれか高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額が、交換差金のみが記載されているときは当該交換差金がそれぞれ記載金額になります。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















