資料2005年01月12日 【税務通達等】 質疑応答事例(印紙税)請負に関する契約書(第2号文書)
(請負に関する契約書(第2号文書))
1 請負の意義
2 請負と売買の判断基準(1)
3 請負と売買の判断基準(2)
4 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
5 取付工事を行う機械の売買契約書
6 物品販売の注文請書
7 工事注文請書
8 工事注文書等
9 基本契約に基づき下請業者に交付する注文書
10 基本契約に基づき作成する加工明細等
11 見積書とワンライティングで作成する注文書
12 受付印を押なつした工事注文書控
13 仮請負契約書と本契約書
14 国等と締結した請負契約書
15 請負契約書の変更契約書
16 注文請書の記載金額
17 契約金額が明らかである請負契約書
18 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
19 注文番号を記載した注文請書の記載金額
20 個別契約書の変更契約書と記載金額
21 広告契約書
22 エレベーターの保守契約書
23 修理品の承り票、引受票等
24 プログラムの設計・開発契約書
請負の意義
【 照会要旨】
印紙税が課税される請負契約の基本について、説明してください。
【 回答要旨】
「請負」とは、当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいい、民法第632条に規定する「請負」のことをいいます。
この「請負」は、完成された仕事の結果を目的とする点に特質があり、仕事が完成されるならば、下請負に出してもよく、その仕事を完成させなければ、債務不履行責任を負うような契約です。
民法では、典型契約として請負契約を規定していますが、実際の取引においては各種変形したいわゆる「混合契約」といわれるものが多く、印紙税法上どの契約としてとらえるべきものであるか判定の困難なものが多く見受けられるところです。例えば、紳士服の仕立ての発注は請負であり、既製服の発注は売買としているところですが、それでは、イージーオーダーはどうなるか、寸法直しを伴う既製服の発注はどうなるかという問題です。
印紙税法では、通則2において、「一の文書で1若しくは2以上の号に掲げる事項とその他の事項が併記又は混合記載されているものは、それぞれの号に該当する文書」と規定されています。
このように一部の請負の事項が併記された契約書又は請負とその他の事項が混然一体として記載された契約書は、印紙税法上、請負契約に該当することになり、民法上、例えば、委任契約に近いといわれる混合契約であっても、印紙税法上は請負契約となるものも生ずることになります。
請負の目的物には、家屋の建築、道路の建設、橋りょうの架設、洋服の仕立て、船舶の建造、車両及び機械の製作、機械の修理のような有形なもののほか、シナリオの作成、音楽の演奏、舞台への出演、講演、機械の保守、建物の清掃のような無形のものも含まれます。
また、請負とは仕事の完成と報酬の支払とが対価関係にあることが必要ですから、仕事の完成の有無にかかわらず報酬が支払われるものは請負契約にはならないものが多く、また、報酬が全く支払われないようなものは請負には該当しません(おおむね委任に該当します。)。
なお、運送契約は契約の類型上、請負契約に含まれると考えられますが、一般の請負と明確に区別できることから、第1号の4文書(運送に関する契約書)として別に掲名されています。 (注) 印紙税では、紳士服等のイージーオーダーは、請負契約として取り扱っています。また、寸法直しを伴う既製服等の発注については、既製服部分は物品の譲渡契約、報酬のある寸法直し部分は請負契約として取り扱っています。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
請負と売買の判断基準(1)
【 照会要旨】
請負になるか売買になるかによって、印紙税の取扱いはどのように異なってくるのでしょうか。また、請負契約か売買契約かを明確に判断できないものは、どのような基準で区分するのでしょうか。
【 回答要旨】
請負契約になりますと、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります(通則3のイ)。
また、物品の売買契約になりますと、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。
請負契約か売買契約かの判断基準は、契約当事者の意思が、仕事の完成に重きをおいているか、物の所有権移転に重きをおいているかによって判断します。
しかし、具体的な取引においては、必ずしもその判別が明確なものばかりとはいえません。したがって、印紙税法の取扱いでは、その判別が困難な場合には、次のような基準で判断することにしています(基通第2号文書の2)。
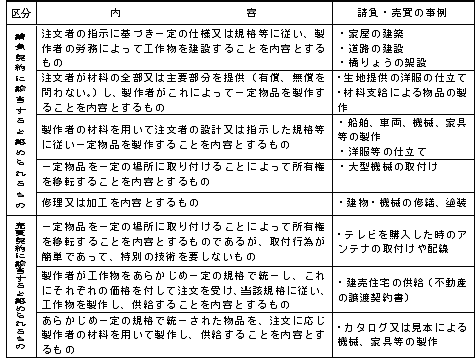
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一第2号文書の2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
請負と売買の判断基準(2)
【 照会要旨】
契約書を作成する場合、請負契約になるか売買契約になるかによって、印紙税の取扱いはどのように異なってくるのでしょうか。また、その判断基準を説明してください。
【 回答要旨】
印紙税法の通則の規定により、請負契約になりますと、おおむね、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
また、物品の売買契約になりますと、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。
請負契約に該当した場合の印紙税の取扱いは、次のとおりになります。
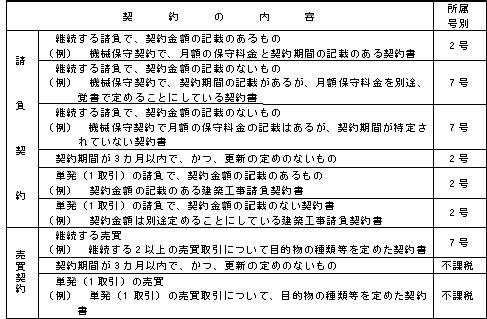
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
【 照会要旨】
平成9年4月から、建設工事請負契約書について印紙税が軽減されたと聞きましたが、具体的な取扱いについて説明してください。
【 回答要旨】
租税特別措置法の一部が改正されたことにより、建設工事の請負に伴って作成される請負契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられました。その概要等は次のとおりです(不動産の譲渡に関する契約書についても軽減されております。)。
【 軽減措置の概要】
軽減措置の対象となる契約書は、請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)のうち、記載金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、建設請負の当初に作成される契約書のほか、工事金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。
【 軽減後の税率】
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりになります。
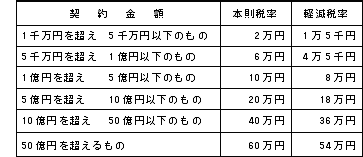
【 軽減措置の対象となる請負に関する契約書の範囲】
軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは、課税物件表第2号文書に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。
この場合において建設工事とは、土木建築に関する工事の全般をいいますが、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は機械等の制作若しくは修理等については、建設業法第2条第1項に規定する建設工事には該当しません。
なお、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても、軽減措置の対象になります。
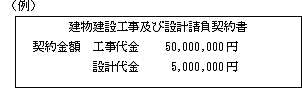
この契約書に記載された契約金額は55,000,000円(建物建設工事代金50,000,000円+設計請負代金5,000,000円)ですから、印紙税額は45,000円になります。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第91条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
取付工事を行う機械の売買契約書
【 照会要旨】
当社では、一定の規格で統一した大型機械のカタログ販売を行っています。
この場合、機械の引渡しは、一定の場所に取り付けた後に行うこととし、取付工事費を請求することとしていますが、契約書(注文請書等)の書き方によって印紙税額が異なると聞きましたので、その内容について具体例をあげて説明してください。
なお、注文者からの指示のあった規格等により、機械を製作した請負に該当する場合についても説明してください。
【 回答要旨】
ご質問の場合の機械の販売については、あらかじめ一定の規格で統一した機械をカタログ販売するわけですから物品の売買契約に該当し、取付工事については請負に該当することになります。
請負に該当する機械の製作、物品の売買契約に該当する機械の販売及びそれぞれ請負に該当する取付工事について、機械本体の価格が500万円、取付工事費が100万円とする内容の契約書を作成したとして説明します。
この場合において、注文者の指示する一定の規格での機械の製作及び取付工事が請負に該当しますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することは明らかですが、機械本体の価格と取付工事費の記載の方法によって、印紙税法の取扱い(記載金額)は次のとおりになります。
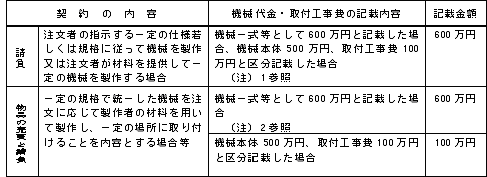
(注)1 注文者の指示する一定の仕様又は規格に従って機械を製作する場合等は、単なる機械の売買(譲渡)ではなく、一定の機械を製作することを内容とする請負契約になり、機械本体の取付けも請負契約ですから、機械本体と取付工事費を区分記載している、していないにかかわらず記載金額600万円の第2号文書(請負に関する契約書)になります。
2 不課税の物品売買契約と機械本体の取付けという請負契約に該当し、通則2の規定により、第2号文書になります。
なお、機械の売買代金と取付工事費は別のものであり、それを区分記載していれば、請負に係る金額(取付工事費)をその契約書の記載金額として取り扱うこととなりますが、区分記載していない場合は、契約書に記載されている600万円が記載金額になります。
3 機械の取付け(据付け)等はすべて請負になるというものではなく、機械等を購入した場合には通常サービスにより取り付けられるようなもの、例えば、テレビを購入したときのアンテナの取付け、配線のように取付行為が簡単であって特別の技術を要しないものは、本体の売買に付随して行うことにしても、その取付行為を請負として判定しないで、全体をその本体の売買を内容とする契約書として取り扱います。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
物品販売の注文請書
【 照会要旨】
当社では、得意先から注文のあったカタログ商品の販売を受注した際に、「注文請書」を作成交付していますが、その表題が「請書」となっているため第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになるのでしょうか。
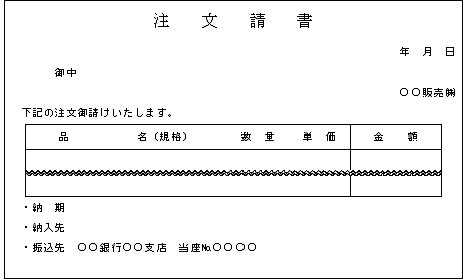
【 回答要旨】
第2号文書(請負に関する契約書)に該当するかどうかの判断は、その文書の表題が「請書」になっているかどうかにかかわらず、契約の内容が請負であるか、物品の譲渡契約であるかどうかによって判断することになります。
ご質問の文書の場合には、カタログ商品の売買契約を内容としていますから、物品の譲渡契約に該当し、第2号文書には該当しません。 (注) 物品の譲渡契約については、平成元年3月までは、物品の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として課税の対象になっていました。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
工事注文請書
【 照会要旨】
当社は、土木工事を請け負った際に、発注先に対して「工事注文請書」を作成交付していますが、契約当事者双方の署名押印のない文書が第2号文書(請負に関する契約書)として課税対象になるのは、なぜでしょうか。
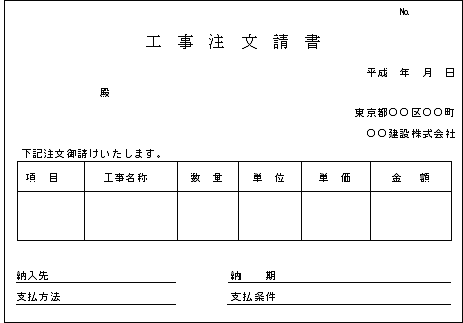
【 回答要旨】
請負契約は、請負人がある仕事の完成を約し、注文者がこれに報酬を支払うことを約することによって成立する契約です。土木工事を請け負った際作成する「注文請書」は、請負契約の成立を証明する文書で、印紙税法上の契約書には念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書も含まれます(通則5)から、請負者のみが署名押印する当該文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
工事注文書等
【 照会要旨】
工事を発注した際に「注文書」を作成し、受注者に交付しています。この「注文書」でも第2号文書(請負に関する契約書)に該当するものがあるとのことですが、具体的にはどのような場合なのでしょうか。
【 回答要旨】
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書は、一般的に契約の申込みの事実を証明する目的で作成されるものですから、契約書には該当しませんが、契約の成立を証明する目的で作成されるものは、原則として契約書に該当することになります。
具体的な取扱いについて「工事注文書」を例に説明しますと次のとおりになります。
1 基本契約書等に基づく工事注文書
契約当事者間の基本契約書、規約又は約款等に基づくことが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することになっている場合における工事注文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります(基通第21条第2項第1号)。
なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、第2号文書に該当しないことに取り扱っています。
(1) 第2号文書に該当するもの
次の工事注文書には、基本契約書に基づく申込みであることが記載されていることから、当該注文書の交付により自動的に個々の契約が成立することになっている場合は、第2号文書に該当します。
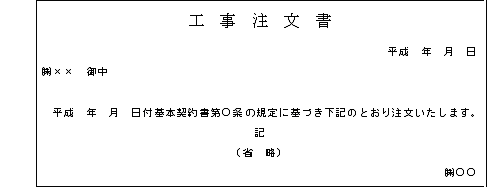
(2) 第2号文書として取り扱わないもの
次の工事注文書には、基本契約書に基づく申込みであることが記載されていますが、別途、請書(契約の成立を証明する文書)を作成することが記載されていますので、課税文書に該当しないものとして取り扱っています。
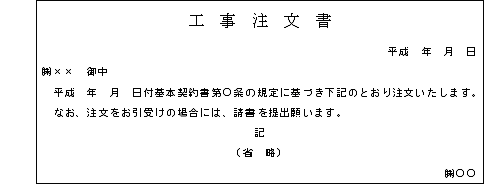
2 見積書等に基づく工事注文書
見積書その他契約の相手方の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている工事注文書は、第2号文書に該当することになります(基通第21条第2項第2号)。
なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、第2号文書に該当しないことに取り扱っています。
(1) 第2号文書に該当するもの
次の工事注文書には、見積書に基づく申込みであることが記載されていることから第2号文書に該当します。
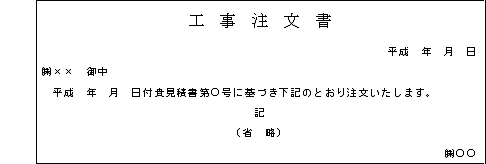
(2) 第2号文書として取り扱わないもの
次の工事注文書には、見積書に基づく申込みであることが記載されていますが、別途、請書(契約の成立を証明する文書)を作成することが記載されていますので、課税文書に該当しないことに取り扱っています。
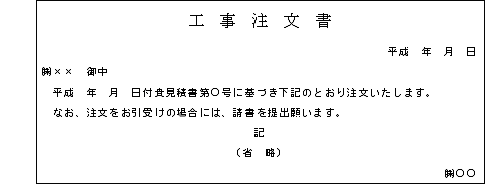
3 契約当事者双方の署名又は押印のある工事注文書
次の工事注文書には、契約当事者双方の署名押印がありますので、契約の申込みの事実を証明する一般的な申込書とは異なり、契約の成立の事実を証明する文書と認められ、第2号文書に該当することになります(基通第21条第2項第3号)。
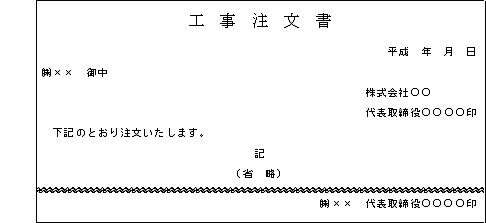
(注) 別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものであっても、契約の事実を証明する文書ですから第2号文書に該当します。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第21条第2項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
基本契約に基づき下請業者に交付する注文書
【 照会要旨】
当社の作成する「注文書」は、あらかじめ取引基本契約を締結している下請業者との間において、製造委託又は修理委託を発注する場合にその内容を記載して交付するものですが、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになるのでしょうか。
なお、取引基本契約には、次のような条項があります。
第○条(個別契約の成立)
個別契約は、甲より前条の取引内容を記載した注文書を乙に交付し、乙がこれを承諾することによって成立する。
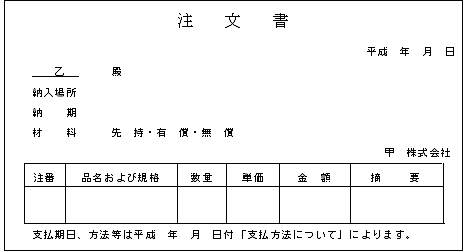
【 回答要旨】
下請業者との間で締結している基本契約書の記載内容からみて、製造委託又は修理委託の契約は、注文書の交付を受けた下請業者が注文書の内容を承諾することによって成立します。
したがって、ご質問の文書は、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される申込文書であり、契約の成立等の事実を証明する文書ではありませんから、印紙税法上の契約書には該当しません。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第21条第2項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
基本契約に基づき作成する加工明細等
【 照会要旨】
物品の加工取引を行う際に、当社(発注者)から受注者に対して「加工明細」を交付し、受注者から当社には、「請求書兼加工明細」が交付されます。
この場合、あらかじめ取り交わしている加工請負基本契約書の中に「加工明細等は、個々の加工取引の成立内容の確認の証とする。」旨の条項がありますから、それぞれ第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになりますか。
なお、加工明細、請求書兼加工明細には、「加工明細等は、個々の加工取引の成立内容の確認の証とする。」旨の記載及び加工請負基本契約書を引用する旨の記載はありません。
【 回答要旨】
文書が課税文書に該当するかどうかの判断については、基通第3条(課税文書に該当するかどうかの判断)の規定によることにしていますので、ご質問の文書については、「加工明細」等の標題等を用いることについての当事者間の了解、基本契約等を加味して、総合的に行うことになります。
ご質問の文書の場合には、いずれも契約当事者間において個々の物品の請負契約の成立の事実を証すべきものとすることについての了解があり、かつ、その成立を証明する目的で作成するものであることが加工請負基本契約書からみて明らかになっていますから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
(注) 課税文書に該当するかどうかの判断は、一般的には基通第3条の規定により行いますが、基通第21条(申込書等と表示された文書の取扱い)の規定は、これを受けて申込書等と表示された文書についての取扱いを具体的に規定したものです。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第3条、第21条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
見積書とワンライティングで作成する注文書
【 照会要旨】
当社では、機械修理の見積り依頼を受けた場合に、①の「見積書」と②の「注文書」を事務簡素化のため、ワンライティングで作成してその依頼者に交付しています。
依頼者が機械修理を注文する場合は、①の「注文書」に署名押印の上当社に返送することになっていますが、この注文書の番号が①の「見積書」の番号と同一になっていますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。
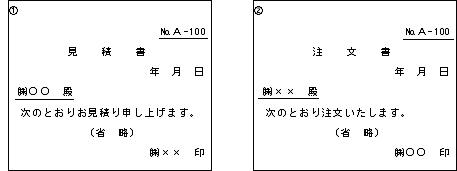
【 回答要旨】
ご質問の「注文書」は、見積書と番号が同一となっていますが、事務簡素化の目的で作成されたものであり、その注文書上には、見積書に基づく申込みである旨が記載されていませんので、契約書には該当しません(基通第21条第2項第2号)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第21条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
受付印を押なつした工事注文書控
【 照会要旨】
当社では、工事の注文があった場合に契約の相手方から、ワンライティングで作成した「注文書」と「注文書控」の2部を提出してもらい、「注文書控」に受付印を押なつして、契約の相手方に返戻していますが、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。
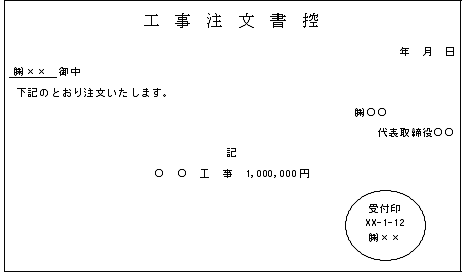
【 回答要旨】
申込者から2部提出された申込書の1部に、申込みを受けた者が署名又は押印して申込者に返却する場合における当該文書については、一般的に申込みに対する応諾文書と認められますので、原則として、契約書に該当することになります。
しかし、ご質問の文書に押なつしている受付印は、契約の申込みに対する応諾の証である署名押印ではなく、単なる申込書の受付印と認められますから課税文書には該当しません。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
仮請負契約書と本契約書
【 照会要旨】
当社では、大口の建設工事を受注した場合には、発注者との間で「仮請負契約書」を作成することにしています。この「仮請負契約書」は、後日、本契約を締結することにしていますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当しないことになるのでしょうか。
また、「仮請負契約書」が第2号文書に該当した場合に、本契約書に契約金額を記載せずに「仮請負契約書」の契約金額を引用した場合の取扱いはどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
通則5の規定によって、印紙税法上の契約書には「予約契約書」も含まれることになっています。したがって、ご質問の場合には、請負契約の予約契約書となることから、たとえ、後日、本契約を締結することとしている場合であっても、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
本契約書を作成すれば、その本契約書も第2号文書として課税の対象になりますが、例えば、本契約書に「○年○月○日付の仮請負契約書の内容を本契約とする。」旨を記載して契約金額を記載しない場合には、引用している「○年○月○日付の仮請負契約書」は課税文書ですから、本契約書は記載金額のない第2号文書として取り扱われます(通則4のホ(2)のかっこ書)。 (注) 予約契約書については、協定書、念書、覚書等様々な名称が用いられていますが、その標題にとらわれることなく記載内容によって課否の判定を行うことになります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ、5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国等と締結した請負契約書
【 照会要旨】
当社は、ある機械の保守業務を行っており、地方公共団体と「機械の保守に関する請負契約書」を共同で作成しています。この場合、地方公共団体の作成するものは非課税と聞きましたが、印紙税の課税される文書は、地方公共団体の所持するもの又は当社で所持するもののいずれになるのでしょうか。
また、この「機械の保守に関する請負契約書」では、継続する保守の目的物の種類、対価の支払方法等について定めていますが、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当することになるのでしょうか。
【 回答要旨】
国等(国、地方公共団体、法別表第2に掲げる者)が作成した課税文書については、法第5条により非課税になります。
また、国等と国等以外の者が共同作成した課税文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなしています(法第4条第5項)。
したがって、ご質問の場合には、国等以外の者である貴社が所持する「機械の保守に関する請負契約書」は非課税文書となり、地方公共団体の所持するものは貴社が納税義務者となる第2文書(請負に関する契約書)として課税の対象になります。
次に、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するかどうかのご質問ですが、国等は「営業者」にはなり得ませんので、令第26条第1号に規定する「営業者の間」の継続取引とはなりません。したがって、国等と継続する請負契約について定めた文書は、第7号文書には該当しません。
(注) 印紙税法上の営業者とは、第17号文書の非課税物件欄に規定する営業を行う者をいいます。
【 関係法令通達】
印紙税法第4条第5項、第5条、別表第一課税物件表第17号文書、印紙税法施行令第26条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
請負契約書の変更契約書
【 照会要旨】
当社では、建設工事についての工事請負契約書を発注者と共同して作成していますが、その工事請負契約書に記載されている支払方法を変更することにして「覚書」を発注者と共同で作成しました。
このような「覚書」も第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
すでに存在している契約の同一性を失わせないで、その内容を変更する変更契約書及び契約の内容として欠けている事項を補充する契約書についても、通則5の規定により、印紙税法上の契約書に該当することになります。
ご質問の「覚書」の場合には、工事請負契約書にすでに定められている重要な事項である支払方法を変更するものですから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
印紙税法の取扱いでは、契約の変更及び補充の場合に、課税の対象とする重要な事項を基通別表第2に定めており、第2号文書の重要な事項は次のとおりになります。
(1) 請負の内容(方法を含みます。)
(2) 請負の期日又は期限
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達別表第二
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
注文請書の記載金額
【 照会要旨】
事例1、2の①の「注文請書」は、②の「注文書」を引用していますが、このように契約金額の記載されていない第2号文書(請負に関する契約書)の記載金額はどのように取り扱うのでしょうか。
なお、「注文書」では、それぞれ③の「見積書」を引用しています。
( 事例1)
注文書には、契約金額の記載はないが、その注文書で引用している見積書に、第2号文書に係る契約金額10万円の記載のある場合
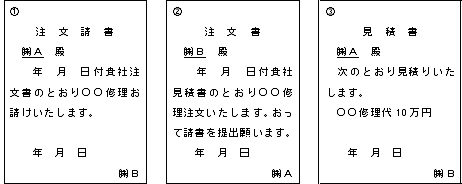
( 事例2)
注文書には、合計金額110万円と記載されているが、その注文書で引用している見積書に、第2号文書に係る契約金額10万円の記載のある場合
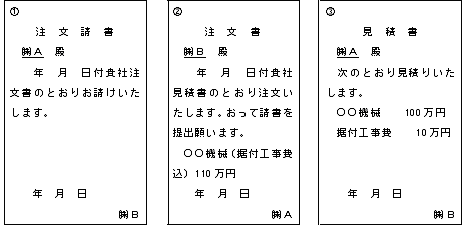
(注) 機械は規格品である。
【 回答要旨】
見積書等を引用した契約書については、「契約金額」が明らかであるときは、その金額が記載金額になります(通則4のホ(2))。
事例1、2の注文請書については、見積書によって請負に係る金額が10万円と明らかになりますから、記載金額10万円の第2号文書(請負に関する契約書)になります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
契約金額が明らかである請負契約書
【 照会要旨】
見積書等を引用した第2号文書(請負に関する契約書)については、その見積書等に記載されている契約金額が記載金額とされることとなっていますが、通則4のホ(2)にいう「契約金額が明らかであるとき」及び「契約金額の計算ができるとき」とは、どういうことをいうのでしょうか。
【 回答要旨】
通則4のホ(2)に規定する「契約金額が明らかであるとき」とは、当該文書に係る契約についての契約金額が記載されている見積書等を特定できる事項の記載があることにより、その引用されている見積書等をみれば契約金額が明らかになるときをいいます。
また、通則4のホ(2)に規定する「契約金額の計算ができるとき」とは、当該文書に係る契約についての単価、数量等の記載のある見積書等を特定できる事項の記載があることにより、その引用されている見積書等に記載されている単価及び数量等に基づき、又は見積書等に記載されている単価等と見積書等を引用している文書に記載されている数量等に基づき、契約金額の計算をすることができるときをいいます。
具体的には、次の事例のような場合をいいます。
1 「契約金額が明らかであるとき」の事例
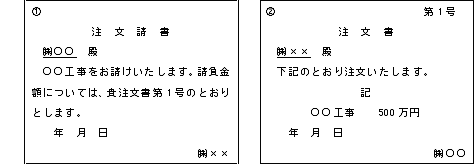
事例のように、工事請負に関する注文請書(第2号文書)に「請負金額については、貴注文書第1号のとおりとします。」との記載があり、引用されている注文書に記載されている請負金額が500万円であるときは、この500万円が事例の注文請書の記載金額になります。
2 「契約金額の計算ができるとき」の事例
(1) 数量、単価の引用による計算
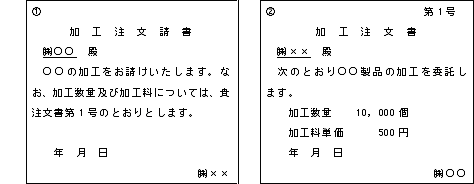
事例のように、物品の加工注文請書(第2号文書)に、「加工数量及び加工料については、貴注文書第1号のとおりとします。」と記載されていて、引用されている加工注文書に記載されている数量が1万個で、加工料単価が500円である場合には、加工注文書の数量と単価に基づいて計算した500万円(500円×1万個)が加工注文請書の記載金額になります。
(2) 数量の引用による計算
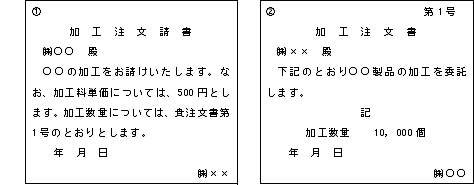
事例のように、物品の加工注文請書(第2号文書)に、「加工料単価については、500円とします。」と定められていて、「加工数量については、貴注文書第1号のとおりとします。」と記載されている場合においては、加工注文請書に記載されている単価と引用されている加工注文書に記載されている数量に基づいて計算した500万円(500円×1万個)が加工注文請書の記載金額になります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4のホ
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
【 照会要旨】
第2号文書(請負に関する契約書)に単価と数量が記載されている場合には、それを掛け算した金額が記載金額として取り扱われるとのことですが、このほかにも同じような取扱いはあるのでしょうか。
【 回答要旨】
記載金額の取扱いに関しては、通則4のホ(1)に「当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。」と規定されています。
そこで、単価、数量、記号などにより、記載金額の計算をすることができる場合又は記号等そのものが金額を意味するものである場合には、記載金額のある文書として取り扱われます(基通第25条)。
( 記載金額が計算できる事例)
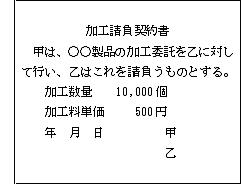
この事例の場合の記載金額は、500万円(加工数量1万個×加工料単価500円)になります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ、印紙税法基本通達第25条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
注文番号を記載した注文請書の記載金額
【 照会要旨】
第2号文書(請負に関する契約書)の記載金額については、その文書に契約金額の記載がなくても、契約金額の記載のある注文書等を引用している場合はその契約金額を第2号文書の記載金額にするとしていますが、①の「注文請書」に②の「注文書」の引用をしないで、「注文請書」と「注文書」に同一の番号を記載した場合はどうなるのでしょうか。
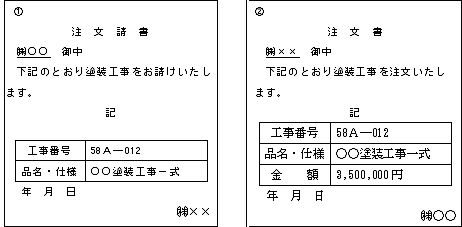
【 回答要旨】
通則4のホ(2)では、「注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより」と規定されています。
ご質問の「注文請書」に記載されている注文番号(工事番号)は、このうちの記号又は番号に該当しますので、当該注文請書については、通則4のホ(2)の規定が適用されて、記載金額350万円の第2号文書(請負に関する契約書)になります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
個別契約書の変更契約書と記載金額
【 照会要旨】
当社は、発注者と工事請負契約を締結し、個別の請負契約書を作成していますが、工事価格を変更した場合には、変更契約書を作成しています。この場合、当初の契約金額を増額したり、減額した場合の変更契約書の印紙税の取扱いはどうなりますか。
【 回答要旨】
変更契約書は、当初の請負契約の重要な事項である契約金額を変更するものですから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。この場合、記載金額をどのように判定するかが問題になります。
変更契約書に対する印紙税の取扱いについては、「当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額が記載されている場合には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額はないものとする。」と規定されています(通則4のニ)。
例えば、当初に契約金額が2億円の建設工事請負契約書(以下「原契約書」といいます。)を作成した後に契約金額を変更する「覚書」を作成した場合の取扱いを説明します。
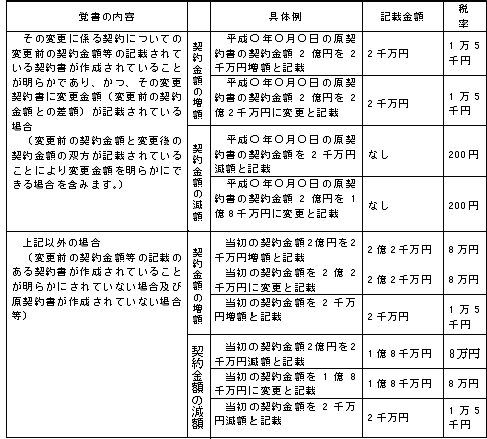
(注) 平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に係る契約書(記載された契約金額が1千万円を超えるもの)については、税率が引き下げられています。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4のニ、租税特別措置法第91条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
広告契約書
【 照会要旨】
新聞広告、コマーシャル放送等の広告契約書を作成しましたが、広告契約は請負になるのでしょうか。また、請負となった場合にその契約の方法によって第2号文書(請負に関する契約書)以外の第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して報酬を支払う契約ですから請負契約に該当し、広告契約書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
また、営業者間において将来行われる2以上の広告について共通して適用される取引条件(数量、単価、対価の支払方法など)を定めるものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当しますが、この場合には、通則3のイの規定によって所属を決定することになります(基通第2号文書の12)。
(注)1 通則3のイでは、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する文書は、第7号文書に所属が決定されます。
2 1回の広告契約で単に広告の登載等が数回にわたるものは、2以上の取引に共通して適用される取引条件を定めるものではありませんから、第7号文書には該当しません。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一 第2号文書の12
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
エレベーターの保守契約書
【 照会要旨】
エレベーターの保守について、毎月一定の料金で継続して保守を行うこととする際に作成する「エレベーターの保守に関する契約書」は、保守の対象となるエレベーター、仕事の内容、料金及び料金の支払方法等を定めるものですが、第2号文書(請負に関する契約書)、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)のいずれに該当するのでしょうか。
なお、契約書には、月額の料金と契約期間を記載しています。
【 回答要旨】
エレベーターの保守契約は、エレベーターを常に安全に運転できるような状態に保ち、これに対して一定の料金を支払うことを約していますから請負契約に該当します(基通第2号文書の13)。
この場合、個々の場合における保守契約を定めるものは、第2号文書(請負に関する契約書)になりますが、ご質問の文書のように、営業者間において継続的に生じる保守について共通的に適用される仕事の内容、料金及び料金の支払方法等の基本的なことを定めるものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当し、通則3のイの規定によりその所属が決定されることになります。
通則3のイでは、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する文書は、第7号文書に所属が決定されることになりますので、契約金額が記載されているかどうかが問題になりますが、ご質問の文書には、月額料金と契約期間が記載されていますので、「月額料金×契約期間の月数」により計算できる契約金額が記載金額になり、第2号文書として取り扱われることになります。 ( 契約金額が計算できる事例)
エレベーターの保守に関する契約書に月額料金10万円で契約期間が1年間と記載されている場合には、記載金額120万円(10万円×12ヵ月)の第2号文書になります。
なお、この場合において「契約当事者からの申し出がない限り○年間延長する。」旨の定めがあっても、この定めは契約の更新に関する定めですから契約期間の月数としては取り扱いません(基通第29条)。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達第29条、別表第一 第2号文書の13
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
修理品の承り票、引受票等
【 照会要旨】
百貨店等が時計、ライター等の修理、加工の依頼を受けた場合にその依頼者に交付する文書については、第2号文書(請負に関する契約書)に該当したり、しなかったりするものがあるとのことですが、どのような取扱いになっているのでしょうか。
【 回答要旨】
物品の修理・加工依頼を受けた際に交付する文書には、承り票、引受票、修理票、引換証、預り証、受取書、整理券等さまざまな名称のものがありますが、物品の受領事実のみが記載されている物品受領書や単なる整理券等に該当するものを除いて、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
なお、具体的な取扱いについては、次のとおりです。
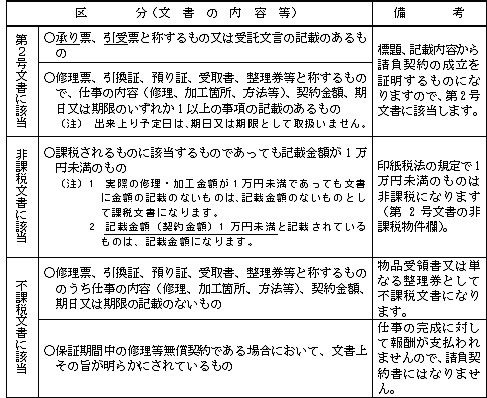
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
プログラムの設計・開発契約書
【 照会要旨】
当社では、電子計算機のプログラムの作成について他社から委託を受けた場合に「プログラム設計・開発契約書」を作成していますが、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
電子計算機のプログラムを作成するという仕事の完成に対して報酬が支払われますので、請負に該当することになります。したがって、ご質問の場合には第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
なお、一般に支援業務等といわれるような契約の相手方の指揮監督下において、単に労務だけを供給するような契約については、委任契約に該当しますので、支援業務等のみについて定めている契約書は、課税文書に該当しません。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
1 請負の意義
2 請負と売買の判断基準(1)
3 請負と売買の判断基準(2)
4 建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
5 取付工事を行う機械の売買契約書
6 物品販売の注文請書
7 工事注文請書
8 工事注文書等
9 基本契約に基づき下請業者に交付する注文書
10 基本契約に基づき作成する加工明細等
11 見積書とワンライティングで作成する注文書
12 受付印を押なつした工事注文書控
13 仮請負契約書と本契約書
14 国等と締結した請負契約書
15 請負契約書の変更契約書
16 注文請書の記載金額
17 契約金額が明らかである請負契約書
18 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
19 注文番号を記載した注文請書の記載金額
20 個別契約書の変更契約書と記載金額
21 広告契約書
22 エレベーターの保守契約書
23 修理品の承り票、引受票等
24 プログラムの設計・開発契約書
請負の意義
【 照会要旨】
印紙税が課税される請負契約の基本について、説明してください。
【 回答要旨】
「請負」とは、当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいい、民法第632条に規定する「請負」のことをいいます。
この「請負」は、完成された仕事の結果を目的とする点に特質があり、仕事が完成されるならば、下請負に出してもよく、その仕事を完成させなければ、債務不履行責任を負うような契約です。
民法では、典型契約として請負契約を規定していますが、実際の取引においては各種変形したいわゆる「混合契約」といわれるものが多く、印紙税法上どの契約としてとらえるべきものであるか判定の困難なものが多く見受けられるところです。例えば、紳士服の仕立ての発注は請負であり、既製服の発注は売買としているところですが、それでは、イージーオーダーはどうなるか、寸法直しを伴う既製服の発注はどうなるかという問題です。
印紙税法では、通則2において、「一の文書で1若しくは2以上の号に掲げる事項とその他の事項が併記又は混合記載されているものは、それぞれの号に該当する文書」と規定されています。
このように一部の請負の事項が併記された契約書又は請負とその他の事項が混然一体として記載された契約書は、印紙税法上、請負契約に該当することになり、民法上、例えば、委任契約に近いといわれる混合契約であっても、印紙税法上は請負契約となるものも生ずることになります。
請負の目的物には、家屋の建築、道路の建設、橋りょうの架設、洋服の仕立て、船舶の建造、車両及び機械の製作、機械の修理のような有形なもののほか、シナリオの作成、音楽の演奏、舞台への出演、講演、機械の保守、建物の清掃のような無形のものも含まれます。
また、請負とは仕事の完成と報酬の支払とが対価関係にあることが必要ですから、仕事の完成の有無にかかわらず報酬が支払われるものは請負契約にはならないものが多く、また、報酬が全く支払われないようなものは請負には該当しません(おおむね委任に該当します。)。
なお、運送契約は契約の類型上、請負契約に含まれると考えられますが、一般の請負と明確に区別できることから、第1号の4文書(運送に関する契約書)として別に掲名されています。 (注) 印紙税では、紳士服等のイージーオーダーは、請負契約として取り扱っています。また、寸法直しを伴う既製服等の発注については、既製服部分は物品の譲渡契約、報酬のある寸法直し部分は請負契約として取り扱っています。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
請負と売買の判断基準(1)
【 照会要旨】
請負になるか売買になるかによって、印紙税の取扱いはどのように異なってくるのでしょうか。また、請負契約か売買契約かを明確に判断できないものは、どのような基準で区分するのでしょうか。
【 回答要旨】
請負契約になりますと、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります(通則3のイ)。
また、物品の売買契約になりますと、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。
請負契約か売買契約かの判断基準は、契約当事者の意思が、仕事の完成に重きをおいているか、物の所有権移転に重きをおいているかによって判断します。
しかし、具体的な取引においては、必ずしもその判別が明確なものばかりとはいえません。したがって、印紙税法の取扱いでは、その判別が困難な場合には、次のような基準で判断することにしています(基通第2号文書の2)。
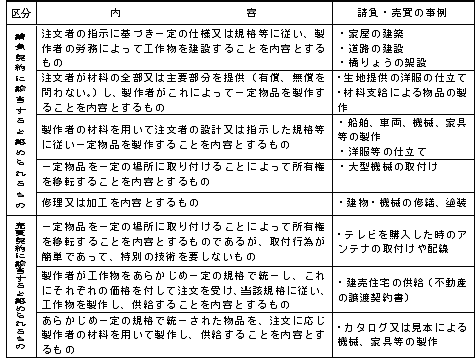
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一第2号文書の2
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
請負と売買の判断基準(2)
【 照会要旨】
契約書を作成する場合、請負契約になるか売買契約になるかによって、印紙税の取扱いはどのように異なってくるのでしょうか。また、その判断基準を説明してください。
【 回答要旨】
印紙税法の通則の規定により、請負契約になりますと、おおむね、記載金額がある場合は階級定額税率が適用される第2号文書(請負に関する契約書)になり、記載金額のない請負契約で継続するものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)になります。
また、物品の売買契約になりますと、継続する売買契約で第7号文書になるものを除き、不課税文書になります。
請負契約に該当した場合の印紙税の取扱いは、次のとおりになります。
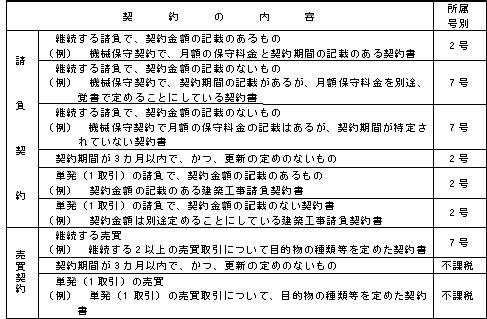
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置
【 照会要旨】
平成9年4月から、建設工事請負契約書について印紙税が軽減されたと聞きましたが、具体的な取扱いについて説明してください。
【 回答要旨】
租税特別措置法の一部が改正されたことにより、建設工事の請負に伴って作成される請負契約書について、印紙税の軽減措置が講じられ、税率が引き下げられました。その概要等は次のとおりです(不動産の譲渡に関する契約書についても軽減されております。)。
【 軽減措置の概要】
軽減措置の対象となる契約書は、請負に関する契約書(建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限られます。)のうち、記載金額が1千万円を超えるもので、平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成されるものになります。なお、これらの契約書に該当するものであれば、建設請負の当初に作成される契約書のほか、工事金額の変更や工事請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象になります。
【 軽減後の税率】
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、課税物件表の規定にかかわらず、次表のとおりになります。
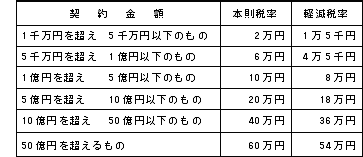
【 軽減措置の対象となる請負に関する契約書の範囲】
軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは、課税物件表第2号文書に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいいます。
この場合において建設工事とは、土木建築に関する工事の全般をいいますが、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は機械等の制作若しくは修理等については、建設業法第2条第1項に規定する建設工事には該当しません。
なお、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記されていても、軽減措置の対象になります。
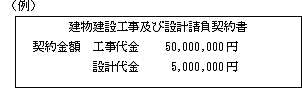
この契約書に記載された契約金額は55,000,000円(建物建設工事代金50,000,000円+設計請負代金5,000,000円)ですから、印紙税額は45,000円になります。
【 関係法令通達】
租税特別措置法第91条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
取付工事を行う機械の売買契約書
【 照会要旨】
当社では、一定の規格で統一した大型機械のカタログ販売を行っています。
この場合、機械の引渡しは、一定の場所に取り付けた後に行うこととし、取付工事費を請求することとしていますが、契約書(注文請書等)の書き方によって印紙税額が異なると聞きましたので、その内容について具体例をあげて説明してください。
なお、注文者からの指示のあった規格等により、機械を製作した請負に該当する場合についても説明してください。
【 回答要旨】
ご質問の場合の機械の販売については、あらかじめ一定の規格で統一した機械をカタログ販売するわけですから物品の売買契約に該当し、取付工事については請負に該当することになります。
請負に該当する機械の製作、物品の売買契約に該当する機械の販売及びそれぞれ請負に該当する取付工事について、機械本体の価格が500万円、取付工事費が100万円とする内容の契約書を作成したとして説明します。
この場合において、注文者の指示する一定の規格での機械の製作及び取付工事が請負に該当しますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することは明らかですが、機械本体の価格と取付工事費の記載の方法によって、印紙税法の取扱い(記載金額)は次のとおりになります。
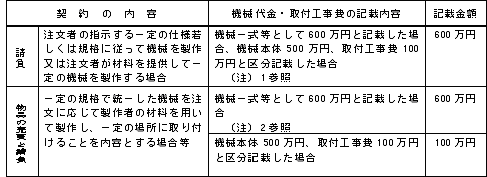
(注)1 注文者の指示する一定の仕様又は規格に従って機械を製作する場合等は、単なる機械の売買(譲渡)ではなく、一定の機械を製作することを内容とする請負契約になり、機械本体の取付けも請負契約ですから、機械本体と取付工事費を区分記載している、していないにかかわらず記載金額600万円の第2号文書(請負に関する契約書)になります。
2 不課税の物品売買契約と機械本体の取付けという請負契約に該当し、通則2の規定により、第2号文書になります。
なお、機械の売買代金と取付工事費は別のものであり、それを区分記載していれば、請負に係る金額(取付工事費)をその契約書の記載金額として取り扱うこととなりますが、区分記載していない場合は、契約書に記載されている600万円が記載金額になります。
3 機械の取付け(据付け)等はすべて請負になるというものではなく、機械等を購入した場合には通常サービスにより取り付けられるようなもの、例えば、テレビを購入したときのアンテナの取付け、配線のように取付行為が簡単であって特別の技術を要しないものは、本体の売買に付随して行うことにしても、その取付行為を請負として判定しないで、全体をその本体の売買を内容とする契約書として取り扱います。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
物品販売の注文請書
【 照会要旨】
当社では、得意先から注文のあったカタログ商品の販売を受注した際に、「注文請書」を作成交付していますが、その表題が「請書」となっているため第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになるのでしょうか。
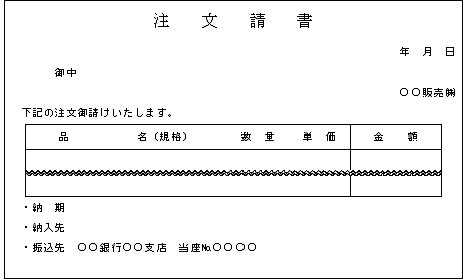
【 回答要旨】
第2号文書(請負に関する契約書)に該当するかどうかの判断は、その文書の表題が「請書」になっているかどうかにかかわらず、契約の内容が請負であるか、物品の譲渡契約であるかどうかによって判断することになります。
ご質問の文書の場合には、カタログ商品の売買契約を内容としていますから、物品の譲渡契約に該当し、第2号文書には該当しません。 (注) 物品の譲渡契約については、平成元年3月までは、物品の譲渡に関する契約書(旧第19号文書)として課税の対象になっていました。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
工事注文請書
【 照会要旨】
当社は、土木工事を請け負った際に、発注先に対して「工事注文請書」を作成交付していますが、契約当事者双方の署名押印のない文書が第2号文書(請負に関する契約書)として課税対象になるのは、なぜでしょうか。
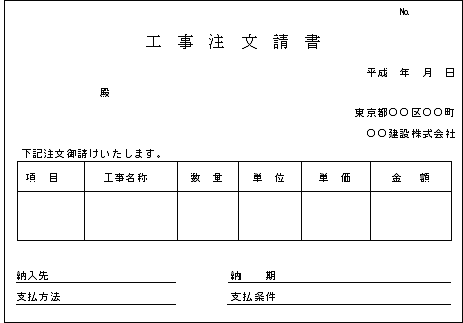
【 回答要旨】
請負契約は、請負人がある仕事の完成を約し、注文者がこれに報酬を支払うことを約することによって成立する契約です。土木工事を請け負った際作成する「注文請書」は、請負契約の成立を証明する文書で、印紙税法上の契約書には念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書も含まれます(通則5)から、請負者のみが署名押印する当該文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
工事注文書等
【 照会要旨】
工事を発注した際に「注文書」を作成し、受注者に交付しています。この「注文書」でも第2号文書(請負に関する契約書)に該当するものがあるとのことですが、具体的にはどのような場合なのでしょうか。
【 回答要旨】
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書は、一般的に契約の申込みの事実を証明する目的で作成されるものですから、契約書には該当しませんが、契約の成立を証明する目的で作成されるものは、原則として契約書に該当することになります。
具体的な取扱いについて「工事注文書」を例に説明しますと次のとおりになります。
1 基本契約書等に基づく工事注文書
契約当事者間の基本契約書、規約又は約款等に基づくことが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することになっている場合における工事注文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります(基通第21条第2項第1号)。
なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、第2号文書に該当しないことに取り扱っています。
(1) 第2号文書に該当するもの
次の工事注文書には、基本契約書に基づく申込みであることが記載されていることから、当該注文書の交付により自動的に個々の契約が成立することになっている場合は、第2号文書に該当します。
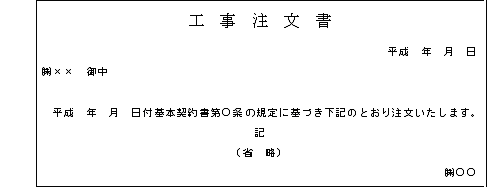
(2) 第2号文書として取り扱わないもの
次の工事注文書には、基本契約書に基づく申込みであることが記載されていますが、別途、請書(契約の成立を証明する文書)を作成することが記載されていますので、課税文書に該当しないものとして取り扱っています。
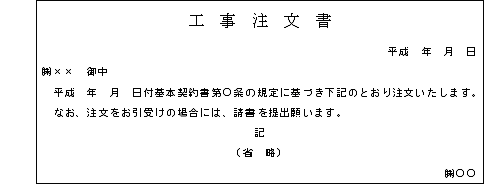
2 見積書等に基づく工事注文書
見積書その他契約の相手方の作成した文書等に基づく申込みであることが記載されている工事注文書は、第2号文書に該当することになります(基通第21条第2項第2号)。
なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、第2号文書に該当しないことに取り扱っています。
(1) 第2号文書に該当するもの
次の工事注文書には、見積書に基づく申込みであることが記載されていることから第2号文書に該当します。
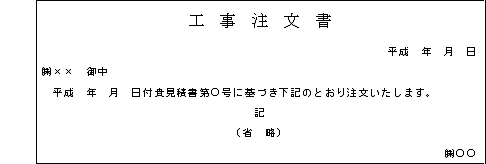
(2) 第2号文書として取り扱わないもの
次の工事注文書には、見積書に基づく申込みであることが記載されていますが、別途、請書(契約の成立を証明する文書)を作成することが記載されていますので、課税文書に該当しないことに取り扱っています。
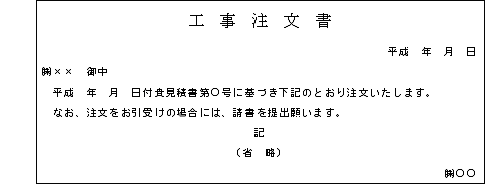
3 契約当事者双方の署名又は押印のある工事注文書
次の工事注文書には、契約当事者双方の署名押印がありますので、契約の申込みの事実を証明する一般的な申込書とは異なり、契約の成立の事実を証明する文書と認められ、第2号文書に該当することになります(基通第21条第2項第3号)。
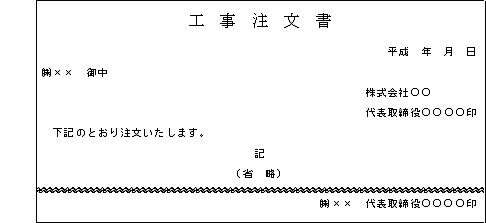
(注) 別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものであっても、契約の事実を証明する文書ですから第2号文書に該当します。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第21条第2項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
基本契約に基づき下請業者に交付する注文書
【 照会要旨】
当社の作成する「注文書」は、あらかじめ取引基本契約を締結している下請業者との間において、製造委託又は修理委託を発注する場合にその内容を記載して交付するものですが、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになるのでしょうか。
なお、取引基本契約には、次のような条項があります。
第○条(個別契約の成立)
個別契約は、甲より前条の取引内容を記載した注文書を乙に交付し、乙がこれを承諾することによって成立する。
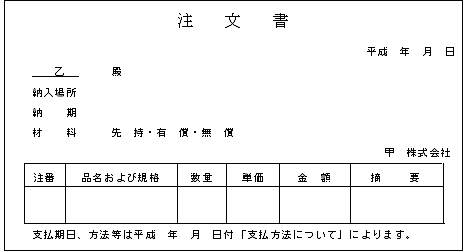
【 回答要旨】
下請業者との間で締結している基本契約書の記載内容からみて、製造委託又は修理委託の契約は、注文書の交付を受けた下請業者が注文書の内容を承諾することによって成立します。
したがって、ご質問の文書は、契約の申込みの事実を証明する目的で作成される申込文書であり、契約の成立等の事実を証明する文書ではありませんから、印紙税法上の契約書には該当しません。
【関係法令通達】
印紙税法基本通達第21条第2項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
基本契約に基づき作成する加工明細等
【 照会要旨】
物品の加工取引を行う際に、当社(発注者)から受注者に対して「加工明細」を交付し、受注者から当社には、「請求書兼加工明細」が交付されます。
この場合、あらかじめ取り交わしている加工請負基本契約書の中に「加工明細等は、個々の加工取引の成立内容の確認の証とする。」旨の条項がありますから、それぞれ第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになりますか。
なお、加工明細、請求書兼加工明細には、「加工明細等は、個々の加工取引の成立内容の確認の証とする。」旨の記載及び加工請負基本契約書を引用する旨の記載はありません。
【 回答要旨】
文書が課税文書に該当するかどうかの判断については、基通第3条(課税文書に該当するかどうかの判断)の規定によることにしていますので、ご質問の文書については、「加工明細」等の標題等を用いることについての当事者間の了解、基本契約等を加味して、総合的に行うことになります。
ご質問の文書の場合には、いずれも契約当事者間において個々の物品の請負契約の成立の事実を証すべきものとすることについての了解があり、かつ、その成立を証明する目的で作成するものであることが加工請負基本契約書からみて明らかになっていますから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
(注) 課税文書に該当するかどうかの判断は、一般的には基通第3条の規定により行いますが、基通第21条(申込書等と表示された文書の取扱い)の規定は、これを受けて申込書等と表示された文書についての取扱いを具体的に規定したものです。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第3条、第21条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
見積書とワンライティングで作成する注文書
【 照会要旨】
当社では、機械修理の見積り依頼を受けた場合に、①の「見積書」と②の「注文書」を事務簡素化のため、ワンライティングで作成してその依頼者に交付しています。
依頼者が機械修理を注文する場合は、①の「注文書」に署名押印の上当社に返送することになっていますが、この注文書の番号が①の「見積書」の番号と同一になっていますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。
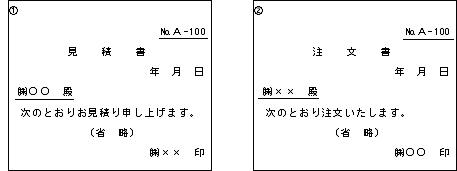
【 回答要旨】
ご質問の「注文書」は、見積書と番号が同一となっていますが、事務簡素化の目的で作成されたものであり、その注文書上には、見積書に基づく申込みである旨が記載されていませんので、契約書には該当しません(基通第21条第2項第2号)。
【 関係法令通達】
印紙税法基本通達第21条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
受付印を押なつした工事注文書控
【 照会要旨】
当社では、工事の注文があった場合に契約の相手方から、ワンライティングで作成した「注文書」と「注文書控」の2部を提出してもらい、「注文書控」に受付印を押なつして、契約の相手方に返戻していますが、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。
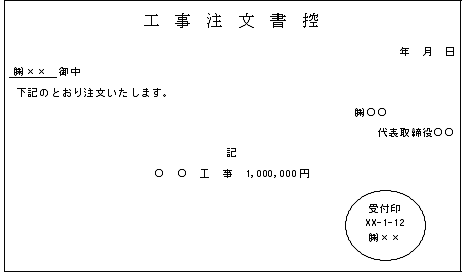
【 回答要旨】
申込者から2部提出された申込書の1部に、申込みを受けた者が署名又は押印して申込者に返却する場合における当該文書については、一般的に申込みに対する応諾文書と認められますので、原則として、契約書に該当することになります。
しかし、ご質問の文書に押なつしている受付印は、契約の申込みに対する応諾の証である署名押印ではなく、単なる申込書の受付印と認められますから課税文書には該当しません。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
仮請負契約書と本契約書
【 照会要旨】
当社では、大口の建設工事を受注した場合には、発注者との間で「仮請負契約書」を作成することにしています。この「仮請負契約書」は、後日、本契約を締結することにしていますので、第2号文書(請負に関する契約書)に該当しないことになるのでしょうか。
また、「仮請負契約書」が第2号文書に該当した場合に、本契約書に契約金額を記載せずに「仮請負契約書」の契約金額を引用した場合の取扱いはどうなるのでしょうか。
【 回答要旨】
通則5の規定によって、印紙税法上の契約書には「予約契約書」も含まれることになっています。したがって、ご質問の場合には、請負契約の予約契約書となることから、たとえ、後日、本契約を締結することとしている場合であっても、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
本契約書を作成すれば、その本契約書も第2号文書として課税の対象になりますが、例えば、本契約書に「○年○月○日付の仮請負契約書の内容を本契約とする。」旨を記載して契約金額を記載しない場合には、引用している「○年○月○日付の仮請負契約書」は課税文書ですから、本契約書は記載金額のない第2号文書として取り扱われます(通則4のホ(2)のかっこ書)。 (注) 予約契約書については、協定書、念書、覚書等様々な名称が用いられていますが、その標題にとらわれることなく記載内容によって課否の判定を行うことになります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ、5
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
国等と締結した請負契約書
【 照会要旨】
当社は、ある機械の保守業務を行っており、地方公共団体と「機械の保守に関する請負契約書」を共同で作成しています。この場合、地方公共団体の作成するものは非課税と聞きましたが、印紙税の課税される文書は、地方公共団体の所持するもの又は当社で所持するもののいずれになるのでしょうか。
また、この「機械の保守に関する請負契約書」では、継続する保守の目的物の種類、対価の支払方法等について定めていますが、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当することになるのでしょうか。
【 回答要旨】
国等(国、地方公共団体、法別表第2に掲げる者)が作成した課税文書については、法第5条により非課税になります。
また、国等と国等以外の者が共同作成した課税文書については、国等が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者が保存するものは国等が作成したものとみなしています(法第4条第5項)。
したがって、ご質問の場合には、国等以外の者である貴社が所持する「機械の保守に関する請負契約書」は非課税文書となり、地方公共団体の所持するものは貴社が納税義務者となる第2文書(請負に関する契約書)として課税の対象になります。
次に、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当するかどうかのご質問ですが、国等は「営業者」にはなり得ませんので、令第26条第1号に規定する「営業者の間」の継続取引とはなりません。したがって、国等と継続する請負契約について定めた文書は、第7号文書には該当しません。
(注) 印紙税法上の営業者とは、第17号文書の非課税物件欄に規定する営業を行う者をいいます。
【 関係法令通達】
印紙税法第4条第5項、第5条、別表第一課税物件表第17号文書、印紙税法施行令第26条第1項
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
請負契約書の変更契約書
【 照会要旨】
当社では、建設工事についての工事請負契約書を発注者と共同して作成していますが、その工事請負契約書に記載されている支払方法を変更することにして「覚書」を発注者と共同で作成しました。
このような「覚書」も第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
すでに存在している契約の同一性を失わせないで、その内容を変更する変更契約書及び契約の内容として欠けている事項を補充する契約書についても、通則5の規定により、印紙税法上の契約書に該当することになります。
ご質問の「覚書」の場合には、工事請負契約書にすでに定められている重要な事項である支払方法を変更するものですから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
印紙税法の取扱いでは、契約の変更及び補充の場合に、課税の対象とする重要な事項を基通別表第2に定めており、第2号文書の重要な事項は次のとおりになります。
(1) 請負の内容(方法を含みます。)
(2) 請負の期日又は期限
(3) 契約金額
(4) 取扱数量
(5) 単価
(6) 契約金額の支払方法又は支払期日
(7) 割戻金等の計算方法又は支払方法
(8) 契約期間
(9) 契約に付される停止条件又は解除条件
(10) 債務不履行の場合の損害賠償の方法
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則5、印紙税法基本通達別表第二
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
注文請書の記載金額
【 照会要旨】
事例1、2の①の「注文請書」は、②の「注文書」を引用していますが、このように契約金額の記載されていない第2号文書(請負に関する契約書)の記載金額はどのように取り扱うのでしょうか。
なお、「注文書」では、それぞれ③の「見積書」を引用しています。
( 事例1)
注文書には、契約金額の記載はないが、その注文書で引用している見積書に、第2号文書に係る契約金額10万円の記載のある場合
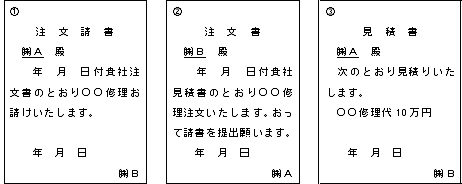
( 事例2)
注文書には、合計金額110万円と記載されているが、その注文書で引用している見積書に、第2号文書に係る契約金額10万円の記載のある場合
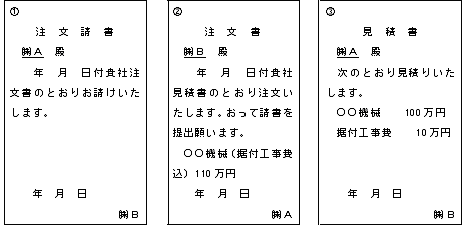
(注) 機械は規格品である。
【 回答要旨】
見積書等を引用した契約書については、「契約金額」が明らかであるときは、その金額が記載金額になります(通則4のホ(2))。
事例1、2の注文請書については、見積書によって請負に係る金額が10万円と明らかになりますから、記載金額10万円の第2号文書(請負に関する契約書)になります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
契約金額が明らかである請負契約書
【 照会要旨】
見積書等を引用した第2号文書(請負に関する契約書)については、その見積書等に記載されている契約金額が記載金額とされることとなっていますが、通則4のホ(2)にいう「契約金額が明らかであるとき」及び「契約金額の計算ができるとき」とは、どういうことをいうのでしょうか。
【 回答要旨】
通則4のホ(2)に規定する「契約金額が明らかであるとき」とは、当該文書に係る契約についての契約金額が記載されている見積書等を特定できる事項の記載があることにより、その引用されている見積書等をみれば契約金額が明らかになるときをいいます。
また、通則4のホ(2)に規定する「契約金額の計算ができるとき」とは、当該文書に係る契約についての単価、数量等の記載のある見積書等を特定できる事項の記載があることにより、その引用されている見積書等に記載されている単価及び数量等に基づき、又は見積書等に記載されている単価等と見積書等を引用している文書に記載されている数量等に基づき、契約金額の計算をすることができるときをいいます。
具体的には、次の事例のような場合をいいます。
1 「契約金額が明らかであるとき」の事例
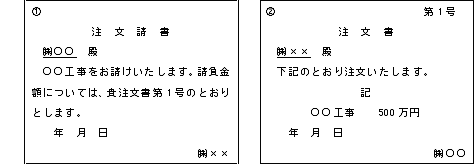
事例のように、工事請負に関する注文請書(第2号文書)に「請負金額については、貴注文書第1号のとおりとします。」との記載があり、引用されている注文書に記載されている請負金額が500万円であるときは、この500万円が事例の注文請書の記載金額になります。
2 「契約金額の計算ができるとき」の事例
(1) 数量、単価の引用による計算
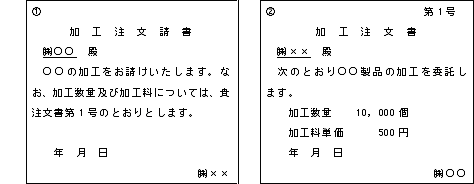
事例のように、物品の加工注文請書(第2号文書)に、「加工数量及び加工料については、貴注文書第1号のとおりとします。」と記載されていて、引用されている加工注文書に記載されている数量が1万個で、加工料単価が500円である場合には、加工注文書の数量と単価に基づいて計算した500万円(500円×1万個)が加工注文請書の記載金額になります。
(2) 数量の引用による計算
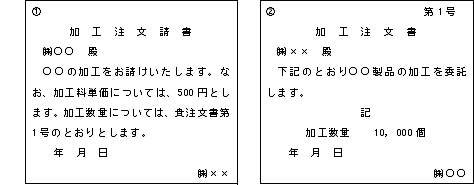
事例のように、物品の加工注文請書(第2号文書)に、「加工料単価については、500円とします。」と定められていて、「加工数量については、貴注文書第1号のとおりとします。」と記載されている場合においては、加工注文請書に記載されている単価と引用されている加工注文書に記載されている数量に基づいて計算した500万円(500円×1万個)が加工注文請書の記載金額になります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4のホ
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
【 照会要旨】
第2号文書(請負に関する契約書)に単価と数量が記載されている場合には、それを掛け算した金額が記載金額として取り扱われるとのことですが、このほかにも同じような取扱いはあるのでしょうか。
【 回答要旨】
記載金額の取扱いに関しては、通則4のホ(1)に「当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその契約金額等の計算をすることができるときは、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。」と規定されています。
そこで、単価、数量、記号などにより、記載金額の計算をすることができる場合又は記号等そのものが金額を意味するものである場合には、記載金額のある文書として取り扱われます(基通第25条)。
( 記載金額が計算できる事例)
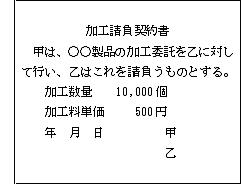
この事例の場合の記載金額は、500万円(加工数量1万個×加工料単価500円)になります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ、印紙税法基本通達第25条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
注文番号を記載した注文請書の記載金額
【 照会要旨】
第2号文書(請負に関する契約書)の記載金額については、その文書に契約金額の記載がなくても、契約金額の記載のある注文書等を引用している場合はその契約金額を第2号文書の記載金額にするとしていますが、①の「注文請書」に②の「注文書」の引用をしないで、「注文請書」と「注文書」に同一の番号を記載した場合はどうなるのでしょうか。
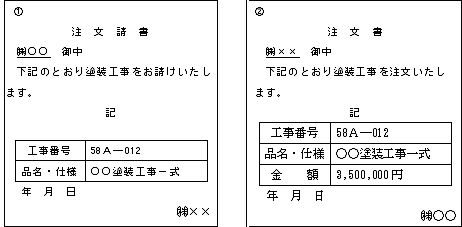
【 回答要旨】
通則4のホ(2)では、「注文書その他これらに類する文書(この表に掲げる文書を除く。)の名称、発行の日、記号、番号その他の記載があることにより」と規定されています。
ご質問の「注文請書」に記載されている注文番号(工事番号)は、このうちの記号又は番号に該当しますので、当該注文請書については、通則4のホ(2)の規定が適用されて、記載金額350万円の第2号文書(請負に関する契約書)になります。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則4のホ
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
個別契約書の変更契約書と記載金額
【 照会要旨】
当社は、発注者と工事請負契約を締結し、個別の請負契約書を作成していますが、工事価格を変更した場合には、変更契約書を作成しています。この場合、当初の契約金額を増額したり、減額した場合の変更契約書の印紙税の取扱いはどうなりますか。
【 回答要旨】
変更契約書は、当初の請負契約の重要な事項である契約金額を変更するものですから、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。この場合、記載金額をどのように判定するかが問題になります。
変更契約書に対する印紙税の取扱いについては、「当該文書に係る契約についての変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが明らかであり、かつ、変更の事実を証すべき文書により変更金額が記載されている場合には、当該変更金額が変更前の契約金額等を増加させるものであるときは、当該変更金額を当該文書の記載金額とし、当該変更金額が変更前の契約金額等を減少させるものであるときは、当該文書の記載金額はないものとする。」と規定されています(通則4のニ)。
例えば、当初に契約金額が2億円の建設工事請負契約書(以下「原契約書」といいます。)を作成した後に契約金額を変更する「覚書」を作成した場合の取扱いを説明します。
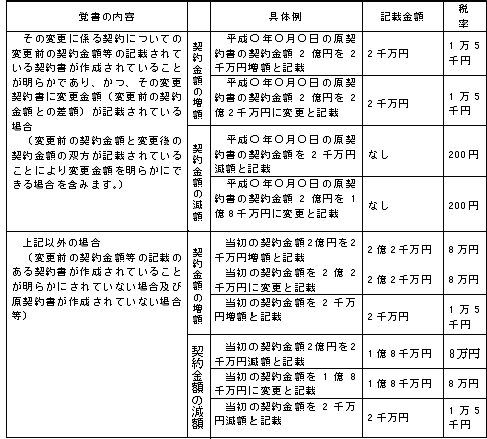
(注) 平成9年4月1日から平成17年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に係る契約書(記載された契約金額が1千万円を超えるもの)については、税率が引き下げられています。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一課税物件表の適用に関する通則4のニ、租税特別措置法第91条
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
広告契約書
【 照会要旨】
新聞広告、コマーシャル放送等の広告契約書を作成しましたが、広告契約は請負になるのでしょうか。また、請負となった場合にその契約の方法によって第2号文書(請負に関する契約書)以外の第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
広告契約は、広告という仕事を行い、それに対して報酬を支払う契約ですから請負契約に該当し、広告契約書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
また、営業者間において将来行われる2以上の広告について共通して適用される取引条件(数量、単価、対価の支払方法など)を定めるものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当しますが、この場合には、通則3のイの規定によって所属を決定することになります(基通第2号文書の12)。
(注)1 通則3のイでは、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する文書は、第7号文書に所属が決定されます。
2 1回の広告契約で単に広告の登載等が数回にわたるものは、2以上の取引に共通して適用される取引条件を定めるものではありませんから、第7号文書には該当しません。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達別表第一 第2号文書の12
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
エレベーターの保守契約書
【 照会要旨】
エレベーターの保守について、毎月一定の料金で継続して保守を行うこととする際に作成する「エレベーターの保守に関する契約書」は、保守の対象となるエレベーター、仕事の内容、料金及び料金の支払方法等を定めるものですが、第2号文書(請負に関する契約書)、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)のいずれに該当するのでしょうか。
なお、契約書には、月額の料金と契約期間を記載しています。
【 回答要旨】
エレベーターの保守契約は、エレベーターを常に安全に運転できるような状態に保ち、これに対して一定の料金を支払うことを約していますから請負契約に該当します(基通第2号文書の13)。
この場合、個々の場合における保守契約を定めるものは、第2号文書(請負に関する契約書)になりますが、ご質問の文書のように、営業者間において継続的に生じる保守について共通的に適用される仕事の内容、料金及び料金の支払方法等の基本的なことを定めるものは、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当し、通則3のイの規定によりその所属が決定されることになります。
通則3のイでは、契約金額の記載のない第2号文書と第7号文書に該当する文書は、第7号文書に所属が決定されることになりますので、契約金額が記載されているかどうかが問題になりますが、ご質問の文書には、月額料金と契約期間が記載されていますので、「月額料金×契約期間の月数」により計算できる契約金額が記載金額になり、第2号文書として取り扱われることになります。 ( 契約金額が計算できる事例)
エレベーターの保守に関する契約書に月額料金10万円で契約期間が1年間と記載されている場合には、記載金額120万円(10万円×12ヵ月)の第2号文書になります。
なお、この場合において「契約当事者からの申し出がない限り○年間延長する。」旨の定めがあっても、この定めは契約の更新に関する定めですから契約期間の月数としては取り扱いません(基通第29条)。
【 関係法令通達】
印紙税法別表第一 課税物件表の適用に関する通則3のイ、印紙税法基本通達第29条、別表第一 第2号文書の13
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
修理品の承り票、引受票等
【 照会要旨】
百貨店等が時計、ライター等の修理、加工の依頼を受けた場合にその依頼者に交付する文書については、第2号文書(請負に関する契約書)に該当したり、しなかったりするものがあるとのことですが、どのような取扱いになっているのでしょうか。
【 回答要旨】
物品の修理・加工依頼を受けた際に交付する文書には、承り票、引受票、修理票、引換証、預り証、受取書、整理券等さまざまな名称のものがありますが、物品の受領事実のみが記載されている物品受領書や単なる整理券等に該当するものを除いて、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります。
なお、具体的な取扱いについては、次のとおりです。
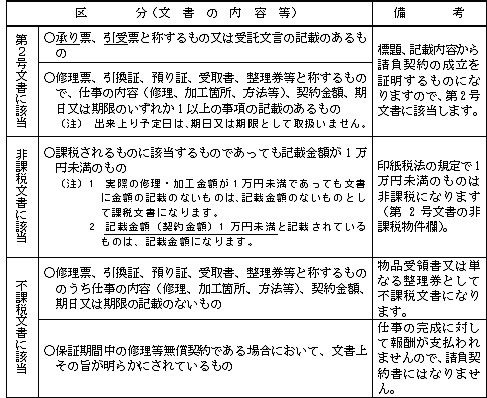
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
プログラムの設計・開発契約書
【 照会要旨】
当社では、電子計算機のプログラムの作成について他社から委託を受けた場合に「プログラム設計・開発契約書」を作成していますが、第2号文書(請負に関する契約書)に該当するのでしょうか。
【 回答要旨】
電子計算機のプログラムを作成するという仕事の完成に対して報酬が支払われますので、請負に該当することになります。したがって、ご質問の場合には第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。
なお、一般に支援業務等といわれるような契約の相手方の指揮監督下において、単に労務だけを供給するような契約については、委任契約に該当しますので、支援業務等のみについて定めている契約書は、課税文書に該当しません。
【 関係法令通達】
注記
平成16年10月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















