解説記事2005年04月04日 【ニュース特集】 人材投資促進税制の教育訓練費の内容を読み解く(2005年4月4日号・№109)
ニュース特集
税額控除の対象費用となるものは?
人材投資促進税制の教育訓練費の内容を読み解く
平成17年度税制改正では、人材投資促進税制が創設されたが、対象となる教育訓練費の内容が明らかとなった。今回の特集では、同制度の概要及び教育訓練費の詳細についてお伝えする。
人材投資促進税制とは?
人材投資促進税制とは、基本的には、青色申告書を提出する法人又は個人(個人事業主)において、適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される教育訓練費(※連結納税選択の場合は、連結法人各々で教育訓練費を算出して足した金額)を前2事業年度の平均額である比較教育訓練費(※連結納税選択の場合は、連結法人各々で比較教育訓練費を算出して足した金額)より増加させた場合、その増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額から控除できるというもの。
ただし、当期の法人税額の10%相当額が限度とされている。
中小企業の特例あり~法人住民税も適用
また、中小企業(※措置法第42条の4第7項に規定する中小企業者又は農業協同組合等に該当する法人等)については特例が設けられている。
具体的には、教育訓練費を基準額より増加させた場合、教育訓練費の総額に対し、増加率の2分の1に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期の法人税額から控除できる(前記の基本制度との選択が可能)。こちらも当期の法人税額の10%相当額が限度とされている。
なお、中小企業の特例の場合には、法人住民税においても人材投資促進税制が適用される。具体的には、同制度における税額控除額の17.3%(都道府県民税5%、市町村民税12.3%(標準税率))に相当する金額が法人税割の税額から控除されることになる。
人材投資促進税制の対象者などの留意点
以上が人材投資促進税制の概要だが、いくつかの留意点がある。まず、教育訓練の対象者の範囲だ。対象範囲は、使用人又は個人のその事業に係る使用人。使用人とは、正社員、契約社員、パート・アルバイト、請負社員、派遣社員などが該当する。 一方、役員や個人事業主、これらの親族に該当する者などは対象外となる(下図参照)。また、企業の内定者に対して入社前に研修を行うケースがあるが、この場合も対象外となっているので注意したい。
比較教育訓練費についてだが、これは、適用年度の前2事業年度の各事業年度の教育訓練費の額の平均額だが、適用年度の前2年以内に事業年度の変更などにより、適用年度の期間の月数と異なる事業年度が生じた場合には、「その異なる事業年度の教育訓練費の額×適用年度の月数÷その異なる事業年度月数」で計算する。
また、同制度の対象外となる事業年度は、①設立の日を含む事業年度(合併による設立を除く)、②解散の日を含む事業年度(合併による設立を除く)、③清算中の各事業年度とされている。
その他、本誌No.98(1月17日号・36頁)でもすでにお伝えしているが、国等から教育訓練費に充てるために交付を受けた補助金については教育訓練費を計算する上で、補助金相当額を控除する必要がある。補助金については、例えば、厚生労働省の「キャリア形成助成金」が該当する。
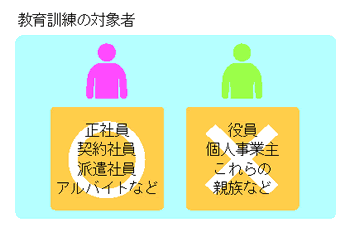
確定申告書に明細書を添付
なお、同制度を適用する場合には、確定申告書等に控除を受ける金額を記載し、かつ、当該金額の計算に関する明細書を添付することが必要となる。教育訓練費の根拠となる証憑等をすべて税務署に提出する必要はないが、領収書等の証拠書類は保存しておく必要がある。
教育訓練費の対象とは?
対象となる教育訓練費は、外部講師謝金の他、外部施設等の使用料についても対象となる(下表参照)。以下、それぞれについて、具体的にみてみよう。
なお、使用人に支払う教育訓練中の人件費(日当を含む)や研修等の開催場所までの交通費、旅費あるいは宿泊費、食費等については対象外となっている。
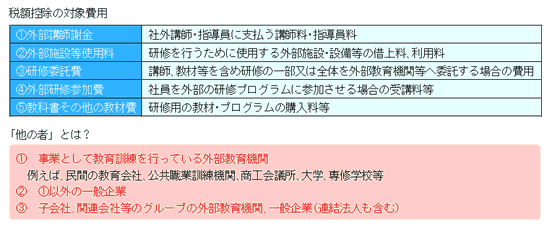
① 外部講師謝金
法人がその使用人に対して、外部から講師又は指導員を招聘し、講義・指導等の教育訓練等を自ら行う場合であることをいい、専門知識の伝授、大学等の教授等による研修のほか、技術指導員等による技術・技能の現場指導なども対象となる。
招聘する外部講師は、当該法人の役員又は使用人以外の者でなければならないが、当該法人の子会社、関連会社等のグループ企業の役員又は使用人の場合はOKだ。また、外部の専門家・技術者と契約により、継続して講義・指導等の実施を依頼する場合の費用も対象となる。
外部講師謝金については、講義・指導等の対価だけに限らず、招聘に要する費用も対象となる。
例えば、外部講師等の交通費、旅費、宿泊費、食費等の費用が該当する。
② 外部施設等使用料
外部施設等使用料については、外部教育機関などの他の者(下記参照)の所有する施設等を使用等する際に要する費用(使用料、利用料、貸借料、借上料、レンタル料、リース料等)とされている。ただし、施設等の光熱費、維持管理費等や減価償却費等については対象外となっている。
また、施設等の具体的内容については、①施設(研修施設、会議室、実習室等)、②設備(教育訓練用シュミレーター設備等)、③器具・備品(OHP、プロジェクター、ホワイトボード、パソコン等)、④eラーニングにおける教育訓練コンテンツの使用料などとなっている。
③ 研修委託費
研修委託費(外部教育機関等に委託する場合)については、法人が使用人の職務に必要な技術・知識の習得又は向上のための教育訓練等を外部教育機関などの他の者(下記参照)に委託して行う場合の費用とされており、講師の人件費、教材費、施設使用料等の委託費用が該当する。
④ 外部研修参加費用
外部研修参加費用(外部教育機関等が行う教育訓練に参加させる場合)については、法人が使用人の職務に必要な技術・知識の習得又は向上のため、外部教育機関等が行う教育訓練(研修講座、講習会、研修セミナー、技術指導、各種検定試験等)に使用人を参加させるための費用とされている。
費用とは、講座等の授業料、受講料、参加料、指導料、通信教育に係る費用の他、資格や免許取得のための受験料も対象となる。
また、国内外の大学院コース等に留学させる場合の授業料や教科書等の費用(所得税法上、学資金等として給与に該当するものは除外)も対象となるが、法人がその使用人に対して支払う報奨金や留学期間中の人件費、大学等への寄附金などは対象外となる。
なお、講座等へ参加する場合において、使用人が費用の一部を負担している場合には、その負担した金額は教育訓練費から控除することになる。
⑤ 教科書その他の教材費
教材費については、教育訓練に直接使用する教科書等の購入や製作した場合が対象となる。教材作成の際に生じるライセンス料や監修料等の関連費用も対象だ。
なお、資産計上される教材(減価償却資産)については対象外となるが、使用可能期間が1年未満の教材又は取得価額が10万円未満で損金経理した場合には対象となる。
その他、教科書等を製作した場合に係る人件費や材料費等、教育訓練用コンテンツをソフトウェアと同時に製作・開発を委託した場合に発生する費用(ソフトウェアと一体不可分なもの)で、無形固定資産として資産計上した場合には対象外となる。
また、人材開発部門が教育訓練を実施するに際し、内部検討用に使用するために購入した参考図書費、使用人に書籍を買い与えるだけの教育行為が伴っていない場合の図書費等も対象外となる。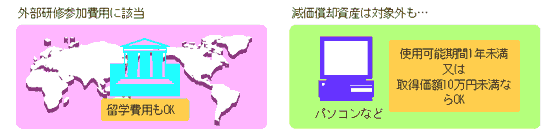
税額控除を計算してみよう!
それでは、経済産業省の資料をもとに簡単に税額控除の計算をしてみよう。
大企業では?
まずは、大企業のケース。当期の教育訓練費1億円、前期が7,000万円、前々期が5,000万円、当期法人税額が2億円である場合には、以下のようになる。
① 適用年度の教育訓練費の額(平成17年度)1億円
② 比較教育訓練費の額6,000万円(=7,000万円+5,000万円)÷2
③ 増加教育訓練費の額=(①適用年度の教育訓練費の額)-②比較教育訓練費の額
4,000万円=1億円-6,000万円
④ 税額控除額=(③増加教育訓練費の額×税額控除率)
1,000万円=4,000万円×25%
⑤ 税額控除限度額=法人税額×10%
2,000万円=2億円(法人税額)×10%
税額控除額の1,000万円は、控除限度額2,000万円を超えていないため、適用年度において1,000万円の税額控除が可能となる。
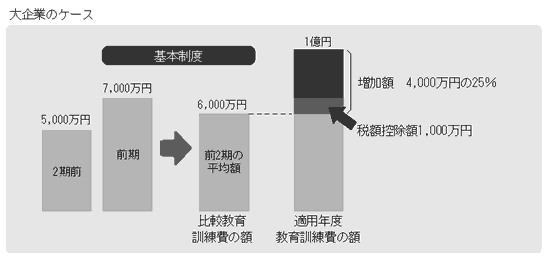
中小企業では?
次は、中小企業のケース。当期の教育訓練費1,000万円、前期が650万円、前々期が550万円、当期法人税額が2,500万円である場合には、以下のようになる。
① 適用年度の教育訓練費の額(平成17年度)1,000万円
② 比較教育訓練費の額600万円(=650万円+550万円)÷2
③ 教育訓練費の増加割合=(①適用年度の教育訓練費の額-②比較教育訓練費の額)÷②比較教育訓練費の額
67%=(1,000万円-600万円)÷600万円
④ 税額控除率=(①適用年度の教育訓練費の額(総額)×税額控除率)
200万円=1,000万円×20%(増加割合が40%以上であるため税額控除率は20%)
仮に③教育訓練増加割合が20%である場合は、増加割合が40%未満であるため、税額控除率は20%×0.5%=10%となる。
⑤ 税額控除限度額=法人税額×10%
250万円=2,500万円(法人税額)×10%
⑥ 地方税(法人住民税の法人割)では、税額控除額200万円×17.3%=34.6万円
したがって、200万円の税額控除及び法人住民税の減額34.6万円で合計322.6万円の税額を減らすことが可能となる。
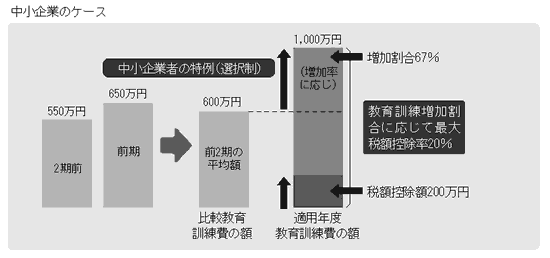
税額控除の対象費用となるものは?
人材投資促進税制の教育訓練費の内容を読み解く
平成17年度税制改正では、人材投資促進税制が創設されたが、対象となる教育訓練費の内容が明らかとなった。今回の特集では、同制度の概要及び教育訓練費の詳細についてお伝えする。
人材投資促進税制とは?
人材投資促進税制とは、基本的には、青色申告書を提出する法人又は個人(個人事業主)において、適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される教育訓練費(※連結納税選択の場合は、連結法人各々で教育訓練費を算出して足した金額)を前2事業年度の平均額である比較教育訓練費(※連結納税選択の場合は、連結法人各々で比較教育訓練費を算出して足した金額)より増加させた場合、その増加額の25%に相当する金額を当期の法人税額から控除できるというもの。
ただし、当期の法人税額の10%相当額が限度とされている。
中小企業の特例あり~法人住民税も適用
また、中小企業(※措置法第42条の4第7項に規定する中小企業者又は農業協同組合等に該当する法人等)については特例が設けられている。
具体的には、教育訓練費を基準額より増加させた場合、教育訓練費の総額に対し、増加率の2分の1に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期の法人税額から控除できる(前記の基本制度との選択が可能)。こちらも当期の法人税額の10%相当額が限度とされている。
なお、中小企業の特例の場合には、法人住民税においても人材投資促進税制が適用される。具体的には、同制度における税額控除額の17.3%(都道府県民税5%、市町村民税12.3%(標準税率))に相当する金額が法人税割の税額から控除されることになる。
人材投資促進税制の対象者などの留意点
以上が人材投資促進税制の概要だが、いくつかの留意点がある。まず、教育訓練の対象者の範囲だ。対象範囲は、使用人又は個人のその事業に係る使用人。使用人とは、正社員、契約社員、パート・アルバイト、請負社員、派遣社員などが該当する。 一方、役員や個人事業主、これらの親族に該当する者などは対象外となる(下図参照)。また、企業の内定者に対して入社前に研修を行うケースがあるが、この場合も対象外となっているので注意したい。
比較教育訓練費についてだが、これは、適用年度の前2事業年度の各事業年度の教育訓練費の額の平均額だが、適用年度の前2年以内に事業年度の変更などにより、適用年度の期間の月数と異なる事業年度が生じた場合には、「その異なる事業年度の教育訓練費の額×適用年度の月数÷その異なる事業年度月数」で計算する。
また、同制度の対象外となる事業年度は、①設立の日を含む事業年度(合併による設立を除く)、②解散の日を含む事業年度(合併による設立を除く)、③清算中の各事業年度とされている。
その他、本誌No.98(1月17日号・36頁)でもすでにお伝えしているが、国等から教育訓練費に充てるために交付を受けた補助金については教育訓練費を計算する上で、補助金相当額を控除する必要がある。補助金については、例えば、厚生労働省の「キャリア形成助成金」が該当する。
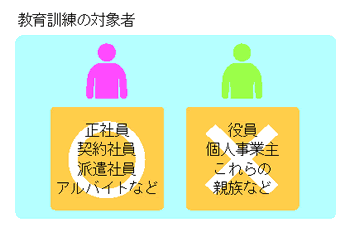
確定申告書に明細書を添付
なお、同制度を適用する場合には、確定申告書等に控除を受ける金額を記載し、かつ、当該金額の計算に関する明細書を添付することが必要となる。教育訓練費の根拠となる証憑等をすべて税務署に提出する必要はないが、領収書等の証拠書類は保存しておく必要がある。
教育訓練費の対象とは?
対象となる教育訓練費は、外部講師謝金の他、外部施設等の使用料についても対象となる(下表参照)。以下、それぞれについて、具体的にみてみよう。
なお、使用人に支払う教育訓練中の人件費(日当を含む)や研修等の開催場所までの交通費、旅費あるいは宿泊費、食費等については対象外となっている。
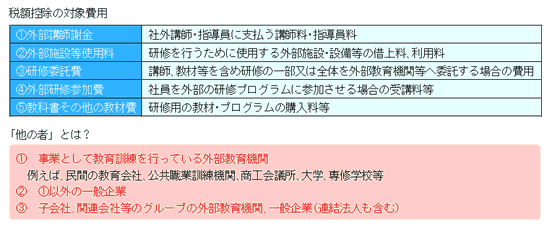
① 外部講師謝金
法人がその使用人に対して、外部から講師又は指導員を招聘し、講義・指導等の教育訓練等を自ら行う場合であることをいい、専門知識の伝授、大学等の教授等による研修のほか、技術指導員等による技術・技能の現場指導なども対象となる。
招聘する外部講師は、当該法人の役員又は使用人以外の者でなければならないが、当該法人の子会社、関連会社等のグループ企業の役員又は使用人の場合はOKだ。また、外部の専門家・技術者と契約により、継続して講義・指導等の実施を依頼する場合の費用も対象となる。
外部講師謝金については、講義・指導等の対価だけに限らず、招聘に要する費用も対象となる。
例えば、外部講師等の交通費、旅費、宿泊費、食費等の費用が該当する。
② 外部施設等使用料
外部施設等使用料については、外部教育機関などの他の者(下記参照)の所有する施設等を使用等する際に要する費用(使用料、利用料、貸借料、借上料、レンタル料、リース料等)とされている。ただし、施設等の光熱費、維持管理費等や減価償却費等については対象外となっている。
また、施設等の具体的内容については、①施設(研修施設、会議室、実習室等)、②設備(教育訓練用シュミレーター設備等)、③器具・備品(OHP、プロジェクター、ホワイトボード、パソコン等)、④eラーニングにおける教育訓練コンテンツの使用料などとなっている。
③ 研修委託費
研修委託費(外部教育機関等に委託する場合)については、法人が使用人の職務に必要な技術・知識の習得又は向上のための教育訓練等を外部教育機関などの他の者(下記参照)に委託して行う場合の費用とされており、講師の人件費、教材費、施設使用料等の委託費用が該当する。
④ 外部研修参加費用
外部研修参加費用(外部教育機関等が行う教育訓練に参加させる場合)については、法人が使用人の職務に必要な技術・知識の習得又は向上のため、外部教育機関等が行う教育訓練(研修講座、講習会、研修セミナー、技術指導、各種検定試験等)に使用人を参加させるための費用とされている。
費用とは、講座等の授業料、受講料、参加料、指導料、通信教育に係る費用の他、資格や免許取得のための受験料も対象となる。
また、国内外の大学院コース等に留学させる場合の授業料や教科書等の費用(所得税法上、学資金等として給与に該当するものは除外)も対象となるが、法人がその使用人に対して支払う報奨金や留学期間中の人件費、大学等への寄附金などは対象外となる。
なお、講座等へ参加する場合において、使用人が費用の一部を負担している場合には、その負担した金額は教育訓練費から控除することになる。
⑤ 教科書その他の教材費
教材費については、教育訓練に直接使用する教科書等の購入や製作した場合が対象となる。教材作成の際に生じるライセンス料や監修料等の関連費用も対象だ。
なお、資産計上される教材(減価償却資産)については対象外となるが、使用可能期間が1年未満の教材又は取得価額が10万円未満で損金経理した場合には対象となる。
その他、教科書等を製作した場合に係る人件費や材料費等、教育訓練用コンテンツをソフトウェアと同時に製作・開発を委託した場合に発生する費用(ソフトウェアと一体不可分なもの)で、無形固定資産として資産計上した場合には対象外となる。
また、人材開発部門が教育訓練を実施するに際し、内部検討用に使用するために購入した参考図書費、使用人に書籍を買い与えるだけの教育行為が伴っていない場合の図書費等も対象外となる。
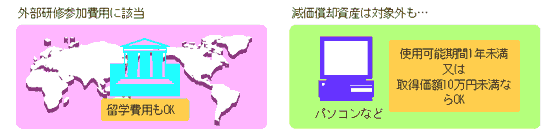
税額控除を計算してみよう!
それでは、経済産業省の資料をもとに簡単に税額控除の計算をしてみよう。
大企業では?
まずは、大企業のケース。当期の教育訓練費1億円、前期が7,000万円、前々期が5,000万円、当期法人税額が2億円である場合には、以下のようになる。
① 適用年度の教育訓練費の額(平成17年度)1億円
② 比較教育訓練費の額6,000万円(=7,000万円+5,000万円)÷2
③ 増加教育訓練費の額=(①適用年度の教育訓練費の額)-②比較教育訓練費の額
4,000万円=1億円-6,000万円
④ 税額控除額=(③増加教育訓練費の額×税額控除率)
1,000万円=4,000万円×25%
⑤ 税額控除限度額=法人税額×10%
2,000万円=2億円(法人税額)×10%
税額控除額の1,000万円は、控除限度額2,000万円を超えていないため、適用年度において1,000万円の税額控除が可能となる。
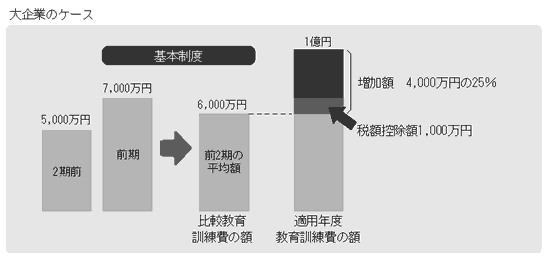
中小企業では?
次は、中小企業のケース。当期の教育訓練費1,000万円、前期が650万円、前々期が550万円、当期法人税額が2,500万円である場合には、以下のようになる。
① 適用年度の教育訓練費の額(平成17年度)1,000万円
② 比較教育訓練費の額600万円(=650万円+550万円)÷2
③ 教育訓練費の増加割合=(①適用年度の教育訓練費の額-②比較教育訓練費の額)÷②比較教育訓練費の額
67%=(1,000万円-600万円)÷600万円
④ 税額控除率=(①適用年度の教育訓練費の額(総額)×税額控除率)
200万円=1,000万円×20%(増加割合が40%以上であるため税額控除率は20%)
仮に③教育訓練増加割合が20%である場合は、増加割合が40%未満であるため、税額控除率は20%×0.5%=10%となる。
⑤ 税額控除限度額=法人税額×10%
250万円=2,500万円(法人税額)×10%
⑥ 地方税(法人住民税の法人割)では、税額控除額200万円×17.3%=34.6万円
したがって、200万円の税額控除及び法人住民税の減額34.6万円で合計322.6万円の税額を減らすことが可能となる。
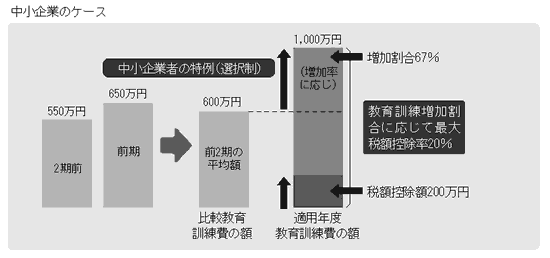
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















