解説記事2005年07月04日 【税制改正関連解説】 連結納税における投資簿価修正に関する平成17年度税制における改正点(2005年7月4日号・№121)
連結納税における投資簿価修正に関する平成17年度税制における改正点
(社)日本経済団体連合会 経済本部 小畑良晴
平成17年度税制改正では、連結納税制度における投資簿価修正について、投資簿価修正額から解散をする連結子法人の連結欠損金個別帰属額を除く等所要の整備が行われている(編注)。
1 連結グループ内の適格分割型分割、適格合併の際の投資簿価修正額の引継ぎ
投資簿価修正の対象となるのは、その対象となる連結子法人の連結期間中(修正事由の生じた日の属する連結事業年度開始の日から当該事由の生じた日の前日までの期間を含みます(法令9の2②一ロ後段、ハ)。)の連結利益積立金発生額(当該連結子法人が有する他の連結子法人株式の投資簿価修正額を含みます(法令9の2②一ニ)。)であり、当該連結子法人の連結利益積立金額のうち、連結開始前の利益積立金額である最終利益積立金(法法2十八の二本文)は対象とはなりません(法令9の2②一イ)。
また、前述の連結利益積立金発生額のうち、すでに投資簿価修正が適用された金額も対象から除かれます(法令9の2②一本文)。ただし、これまでは、簡便性の観点から、連結グループ内での適格合併や適格分割型分割により当該連結子法人が他の連結子法人から引継ぎいだ連結個別利益積立金額は、最終利益積立金額もすでに投資簿価修正の対象になった連結利益積立金発生額もすべて、以後の投資簿価修正の対象となるものとして取り扱うこととされていました(法令9の2②一イ、法法2十八の二ヘト)。
そのため、他の連結法人と適格合併や適格分割型分割を行ったことのある連結子法人の投資簿価修正対象額は本来対象とすべき金額と乖離するおそれがありました。
概要
① 連結グループ内の適格合併、適格分割型分割に伴い、被合併法人から合併法人へ、分割法人から分割承継法人に、被合併法人あるいは分割法人の利益積立金が引き継がれますが、被合併法人あるいは分割法人における利益積立金のうち、連結納税開始前の利益積立金である最終利益積立金、すでに投資簿価修正の対象となったもの、今後投資簿価修正の対象となるもの、という3つの分類に応じ、それぞれ合併法人や分割承継法人に引き継がれることになります。
② 連結欠損金個別帰属額を有する連結子法人が解散をした場合、当該連結子法人株式の帳簿価額を修正するにあたっては、当該連結子法人の解散の日の翌日の属する事業年度開始の時における繰越欠損金額をベースとした金額を投資簿価修正の額から除くこととされており、当該繰越欠損金額をベースとした金額は当該連結グループの連結所得計算上、当該連結子法人株式の清算損とすることができます。
こうしたことから、平成17年度税制改正において、投資簿価修正対象額の計算を精緻化し、連結グループ内の適格合併や適格分割型分割が行われた場合も、最終利益積立金額、すでに投資簿価修正の対象となった連結利益積立金発生額、今後対象となる連結利益積立金発生額の区分を維持したまま、引き継ぎを行うこととされました(法令9の2②本文、③)。
すなわち、投資簿価修正の対象となる連結子法人の連結期間中の連結利益積立金発生額から「既修正額」を減算するのではなく、「既修正額等」を減算することとし(法令9の2②本文)、「既修正額等」とは「既修正額」に、次の場合に応じて、それぞれの金額を加減算したものとすることで、対応しています。
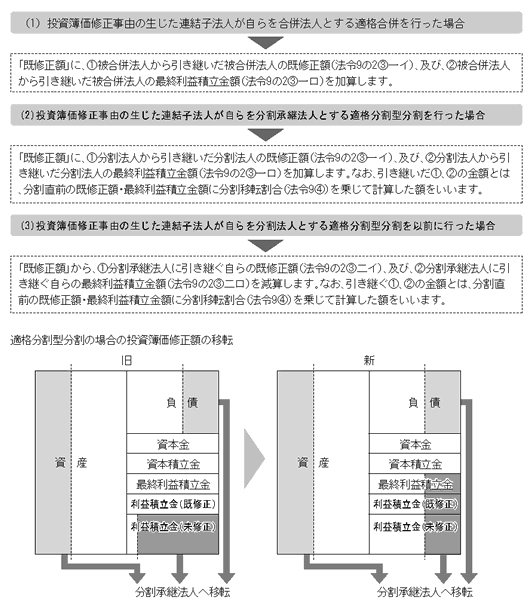
2 解散による離脱の場合の投資簿価修正の額
連結子法人が解散(合併による解散を除きます。)をした場合、解散の日の翌日において連結納税の承認が取り消されたものとみなされます(法法4の5②四)。解散の日が連結事業年度の中途である場合は、①解散の日の属する連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、②解散の日の翌日から当該連結事業年度終了の日までの期間、③当該終了の日の翌日から解散法人の単体の事業年度終了の日までの期間を、それぞれ一の事業年度とみなすこととなります(法法14十)。解散法人に連結欠損金個別帰属額(7年以内)があるときは、解散法人の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度(前記①の期間)以後の各事業年度において、単体の欠損金額とみなして繰越控除を行います(法法57⑥)。
連結グループ離脱の事由が解散でない場合は、離脱法人が事業活動を継続していく過程で、欠損金の繰越控除を行うことができますが、解散する場合には、結果として、欠損金は繰越控除されないままになってしまう可能性があります。
一方、連結子法人の解散による連結グループからの離脱は、当該連結子法人株式を有する連結法人における、当該連結子法人株式の帳簿価額の修正事由とされており(法令9の2①三)、当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額は帳簿価額のマイナス項目となります(法令9の2②一)。その結果、当該離脱法人の清算損もそれだけ減少することになります。
つまり、解散する連結子法人の連結欠損金個別帰属額は、当該連結子法人においても、その株式を有する連結法人においても損金算入する機会が失われることになるのです。
このような不都合を解消するため、平成17年度税制改正において、連結子法人の解散の場合の帳簿価額の修正額については、通常の修正額から、当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額をベースとして計算した金額を除外することとされました。
より具体的には、①解散した連結子法人の連結欠損金個別帰属額(解散の日の翌日からは、単体納税期間となるので、より正確には、法人税法57条6項によって当該法人の欠損金額とみなされる金額ということになります。これを「調整欠損金額」といいます(法令9の2④一)。)と、②当該連結子法人のマイナスの連結利益積立金発生額の絶対値の、いずれか少ない金額を、通常の修正額(法令9の2②一)から除外します(法令9の2④本文)。
ただし、上記②のマイナスの連結利益積立金発生額に対して、当該連結子法人が解散前の各連結事業年度中に当該連結子法人を合併法人とした適格合併を行った場合の被合併法人から引き継いだ被合併法人の最終利益積立金額を減算したり(法令9の2④二イ(1))、当該連結子法人が自らを分割法人とする適格分割型分割を行い分割承継法人に引き継いだ当該連結子法人の最終利益積立金額を加算したり(法令9の2④二イ(2))することによって、連結欠損金個別帰属額と関係のない連結納税開始以前の利益積立金(最終利益積立金)の影響を排除する必要があります。
また、当該連結子法人が債務超過の場合には、解散の時における債務超過額(負債の帳簿価額の合計額-資産の帳簿価額の合計額)を上記②の金額から控除します(法令9の2④二ロ)。
なお、この改正は平成17年4月1日以後に投資簿価修正の対象となる事実が発生した場合に適用されることになります(改正法令附則4②)。4月1日に連結納税の承認が取り消されたものとみなされれば、この改正は適用になります。連結子法人の解散の場合、解散の日の翌日に連結納税の承認は取り消されたものとみなされることから(法法4の5②四)、平成17年3月31日に解散をしたものから適用されることになります。
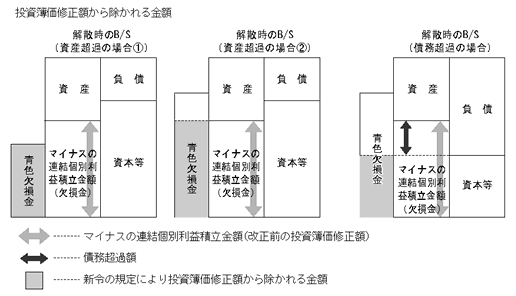
(社)日本経済団体連合会 経済本部 小畑良晴
平成17年度税制改正では、連結納税制度における投資簿価修正について、投資簿価修正額から解散をする連結子法人の連結欠損金個別帰属額を除く等所要の整備が行われている(編注)。
1 連結グループ内の適格分割型分割、適格合併の際の投資簿価修正額の引継ぎ
投資簿価修正の対象となるのは、その対象となる連結子法人の連結期間中(修正事由の生じた日の属する連結事業年度開始の日から当該事由の生じた日の前日までの期間を含みます(法令9の2②一ロ後段、ハ)。)の連結利益積立金発生額(当該連結子法人が有する他の連結子法人株式の投資簿価修正額を含みます(法令9の2②一ニ)。)であり、当該連結子法人の連結利益積立金額のうち、連結開始前の利益積立金額である最終利益積立金(法法2十八の二本文)は対象とはなりません(法令9の2②一イ)。
また、前述の連結利益積立金発生額のうち、すでに投資簿価修正が適用された金額も対象から除かれます(法令9の2②一本文)。ただし、これまでは、簡便性の観点から、連結グループ内での適格合併や適格分割型分割により当該連結子法人が他の連結子法人から引継ぎいだ連結個別利益積立金額は、最終利益積立金額もすでに投資簿価修正の対象になった連結利益積立金発生額もすべて、以後の投資簿価修正の対象となるものとして取り扱うこととされていました(法令9の2②一イ、法法2十八の二ヘト)。
そのため、他の連結法人と適格合併や適格分割型分割を行ったことのある連結子法人の投資簿価修正対象額は本来対象とすべき金額と乖離するおそれがありました。
概要
① 連結グループ内の適格合併、適格分割型分割に伴い、被合併法人から合併法人へ、分割法人から分割承継法人に、被合併法人あるいは分割法人の利益積立金が引き継がれますが、被合併法人あるいは分割法人における利益積立金のうち、連結納税開始前の利益積立金である最終利益積立金、すでに投資簿価修正の対象となったもの、今後投資簿価修正の対象となるもの、という3つの分類に応じ、それぞれ合併法人や分割承継法人に引き継がれることになります。
② 連結欠損金個別帰属額を有する連結子法人が解散をした場合、当該連結子法人株式の帳簿価額を修正するにあたっては、当該連結子法人の解散の日の翌日の属する事業年度開始の時における繰越欠損金額をベースとした金額を投資簿価修正の額から除くこととされており、当該繰越欠損金額をベースとした金額は当該連結グループの連結所得計算上、当該連結子法人株式の清算損とすることができます。
こうしたことから、平成17年度税制改正において、投資簿価修正対象額の計算を精緻化し、連結グループ内の適格合併や適格分割型分割が行われた場合も、最終利益積立金額、すでに投資簿価修正の対象となった連結利益積立金発生額、今後対象となる連結利益積立金発生額の区分を維持したまま、引き継ぎを行うこととされました(法令9の2②本文、③)。
すなわち、投資簿価修正の対象となる連結子法人の連結期間中の連結利益積立金発生額から「既修正額」を減算するのではなく、「既修正額等」を減算することとし(法令9の2②本文)、「既修正額等」とは「既修正額」に、次の場合に応じて、それぞれの金額を加減算したものとすることで、対応しています。
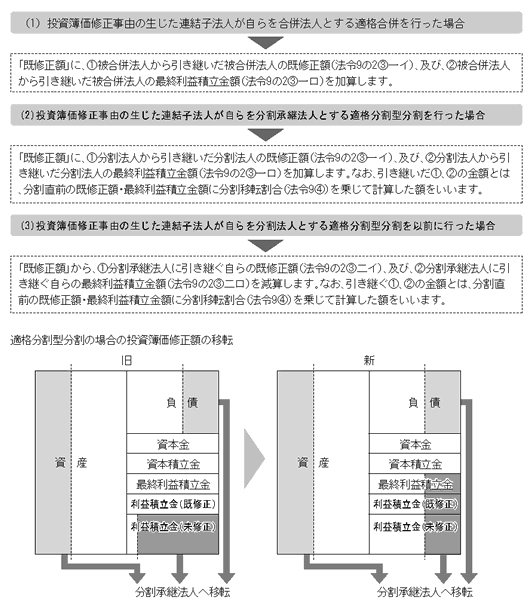
2 解散による離脱の場合の投資簿価修正の額
連結子法人が解散(合併による解散を除きます。)をした場合、解散の日の翌日において連結納税の承認が取り消されたものとみなされます(法法4の5②四)。解散の日が連結事業年度の中途である場合は、①解散の日の属する連結事業年度開始の日から解散の日までの期間、②解散の日の翌日から当該連結事業年度終了の日までの期間、③当該終了の日の翌日から解散法人の単体の事業年度終了の日までの期間を、それぞれ一の事業年度とみなすこととなります(法法14十)。解散法人に連結欠損金個別帰属額(7年以内)があるときは、解散法人の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度(前記①の期間)以後の各事業年度において、単体の欠損金額とみなして繰越控除を行います(法法57⑥)。
連結グループ離脱の事由が解散でない場合は、離脱法人が事業活動を継続していく過程で、欠損金の繰越控除を行うことができますが、解散する場合には、結果として、欠損金は繰越控除されないままになってしまう可能性があります。
一方、連結子法人の解散による連結グループからの離脱は、当該連結子法人株式を有する連結法人における、当該連結子法人株式の帳簿価額の修正事由とされており(法令9の2①三)、当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額は帳簿価額のマイナス項目となります(法令9の2②一)。その結果、当該離脱法人の清算損もそれだけ減少することになります。
つまり、解散する連結子法人の連結欠損金個別帰属額は、当該連結子法人においても、その株式を有する連結法人においても損金算入する機会が失われることになるのです。
このような不都合を解消するため、平成17年度税制改正において、連結子法人の解散の場合の帳簿価額の修正額については、通常の修正額から、当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額をベースとして計算した金額を除外することとされました。
より具体的には、①解散した連結子法人の連結欠損金個別帰属額(解散の日の翌日からは、単体納税期間となるので、より正確には、法人税法57条6項によって当該法人の欠損金額とみなされる金額ということになります。これを「調整欠損金額」といいます(法令9の2④一)。)と、②当該連結子法人のマイナスの連結利益積立金発生額の絶対値の、いずれか少ない金額を、通常の修正額(法令9の2②一)から除外します(法令9の2④本文)。
ただし、上記②のマイナスの連結利益積立金発生額に対して、当該連結子法人が解散前の各連結事業年度中に当該連結子法人を合併法人とした適格合併を行った場合の被合併法人から引き継いだ被合併法人の最終利益積立金額を減算したり(法令9の2④二イ(1))、当該連結子法人が自らを分割法人とする適格分割型分割を行い分割承継法人に引き継いだ当該連結子法人の最終利益積立金額を加算したり(法令9の2④二イ(2))することによって、連結欠損金個別帰属額と関係のない連結納税開始以前の利益積立金(最終利益積立金)の影響を排除する必要があります。
また、当該連結子法人が債務超過の場合には、解散の時における債務超過額(負債の帳簿価額の合計額-資産の帳簿価額の合計額)を上記②の金額から控除します(法令9の2④二ロ)。
なお、この改正は平成17年4月1日以後に投資簿価修正の対象となる事実が発生した場合に適用されることになります(改正法令附則4②)。4月1日に連結納税の承認が取り消されたものとみなされれば、この改正は適用になります。連結子法人の解散の場合、解散の日の翌日に連結納税の承認は取り消されたものとみなされることから(法法4の5②四)、平成17年3月31日に解散をしたものから適用されることになります。
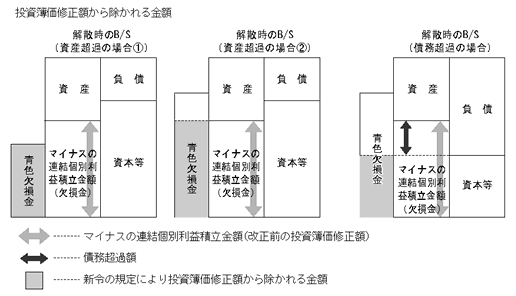
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















