解説記事2005年08月01日 【ニュース特集】 監査基準の改訂及び監査の品質管理基準案を読み解く(2005年8月1日号・№125)
ニュース特集
平成19年3月決算に係る監査から適用
監査基準の改訂及び監査の品質管理基準案を読み解く
企業会計審議会は7月20日、監査基準及び中間監査基準の改訂並びに監査に関する品質管理基準の設定について(公開草案)を公表した。監査法人等の内部管理体制をチェックするための品質管理基準や事業リスクを重視したリスクアプローチを監査基準及び中間監査基準に盛り込んでいる。なお、品質管理基準については、一般基準とは別に独立した基準として設けられる。8月22日まで意見募集した後、正式決定する。平成19年3月決算に係る財務諸表監査から実施する予定だ。特集では、公開草案の概要をお伝えする。
1 監査法人等の品質管理の向上を図る
まず、監査に関する品質管理基準の設定については、昨今の公認会計士監査をめぐる非違事例や国際的な動向を踏まえたものである。一般基準の改訂に加えて、別途、独立した基準として設けられることになった。
昨今では、学校法人東北文化学園大学に係る私立学校法に基づく財産目録監査及び私立学校振興助成法に基づく監査に関し、新日本監査法人及び公認会計士に対して戒告処分が行われている。また、あしぎんフィナンシャルグループ及び足利銀行に係る監査証明に関し、地方事務所に対する審査体制などの不備が認められたことから、中央青山監査法人に対して戒告処分が行われている。
このため、品質管理基準では、監査事務所(監査法人及び個人の公認会計士事務所)レベルの品質管理と個々の監査業務レベルでの品質管理に分け、監査業務の質を合理的に確保するため、監査契約の受任及び更新から監査計画の策定、監査業務の実施及び監査報告書の発行に至る各段階における品質管理システムの整備、運用を求めている。
また、監査実施者(監査実施の責任者と補助者)には、品質管理システムに従って監査業務を実施し、監査業務レベルで品質管理を行うことを求めている。加えて、監査事務所は、品質管理のシステムの整備及び運用の状況を適切に記録し、保存するための方針及び手続を定め、それらが遵守されていることを確かめることになっている。
品質管理のシステムの構築が必要
監査事務所については、①品質管理に関する責任者、②職業倫理及び独立性、③監査契約の受任及び更新、④監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任、⑤業務の実施、⑥品質管理のシステムの監視及び監査業務の検証-に関する方針及び手続からなる品質管理システムを設けなければならないとされた。
また、監査事務所内や外部の弁護士などの適切な者から見解を得た場合には、その見解が監査業務の実施及び監査意見の形成において十分に反映されているか確かめることが求められる。
一方、監査事務所は、監査業務に係る審査部門を設置し、監査業務に係る審査の内容及び結論を監査調書として記録し、保存することになる。仮に監査実施者と審査部門との間で判断の違いがあれば、これを解決しなければならない。解決がされない限りは、監査報告書を発行することができないことになる。
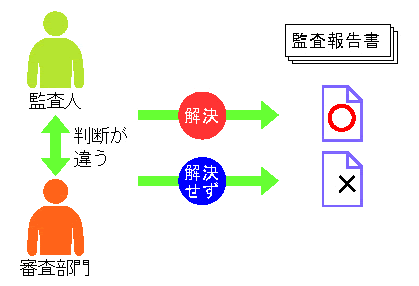
品質管理システム
① 品質管理に関する責任者
② 職業倫理及び独立性
③ 監査契約の受任及び更新
④ 監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任
⑤ 業務の実施
⑥ 品質管理のシステムの監視及び監査業務の検証
COLUMN
平成19年3月決算から適用も早期適用あり

改訂監査基準及び品質管理基準については、平成19年3月決算に係る財務諸表監査から実施する予定。また、改訂中間監査基準については、平成18年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施するほか、早期適用についても認められている。
なお、これらの基準の改正に伴う実務指針の作成については、日本公認会計士協会に対して、早急に行うことを求めている。
2 監査事務所間の引き継ぎを明記
その他、複数の監査事務所が共同して監査(共同監査)を行う場合には、他の監査事務所の品質管理のシステムが品質管理基準に準拠しているかどうかなどを監査の過程で確認しなければならないこととされた。
また、監査事務所間の引き継ぎについても明記されている。監査事務所は、後任の監査事務所への引き継ぎに関する方針及び手続を定め、遵守されていることを確かめなければならないとされている。仮に財務諸表における重要な虚偽表示に係る情報や状況を把握していた場合には、その旨を後任の監査事務所に伝えなければならない。
粉飾の疑いも
企業会計審議会の監査部会では、監査人の交代について、特に議論が集中して行われている。監査人が交代した後に会社が倒産するなど、粉飾決算をしていることが疑われるような事例が見受けられるからだ。
日本公認会計士協会が平成16年4月にまとめた監査人の交代に関するアンケート調査(平成14年1月から平成15年10月末までを対象)では、事業年度途中の交代は22件、期末決算日後の交代が3件あるとの報告がなされている(右表参照)。このうち、平成16年3月末までに民事再生法の適用申請に至った会社は4件となっている。また、監査業務の引き継ぎについては、前任監査人による回答があった101件のうち、80件(79.2%)が実施しているものの、残りの約20%については、未実施であることが明らかとなっている。
このため、今回の品質管理基準の策定により、監査事務所の引継については、厳格な運用が求められそうだ。
最終的には公認会計士・監査審査会がチェック
品質管理基準では、監査事務所は、品質管理のシステムの日常的監視及び監査業務の定期的な検証に関する方針及び手続を定め、遵守されていることを確かめることになる。ただ、これは、あくまでも監査事務所の内部管理体制をチェックするための基準である。
したがって、品質管理の妥当性については、まずは日本公認会計士協会が実施する品質管理レビューということになる。また、品質管理レビューの妥当性については、公認会計士・監査審査会がチェックすることになる。
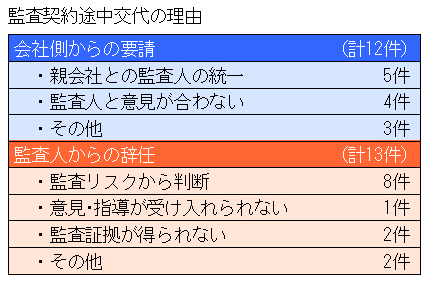
3 事業上のリスクを重視したリスク・アプローチを導入
改訂監査基準及び中間監査基準では、従来のリスク・アプローチを改善し、事業上のリスクを重視したリスク・アプローチを導入する。監査人が、内部統制を含む企業及び企業環境を考慮することを監査計画の策定や監査の実施における重要な要素と位置付け、基本原則に置いている。具体的には、財務諸表全体における虚偽表示のリスクを評価するトップ・ダウンの視点を追加。財務諸表において重要な虚偽の表示が生じる可能性を「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」の2つのレベルで「重要な虚偽表示のリスク」として評価することにしている。財務諸表全体としての「重要な虚偽表示のリスク」があると判断した場合には、リスクに応じて補助者の増員、専門家の配置、適切な監査時間の確保など、全般的な対応を監査計画に反映することが求められる(下記参照)。
現行の基準
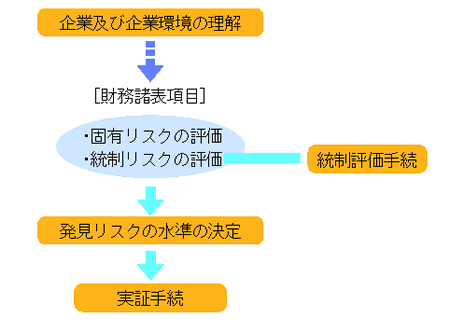
新しい基準
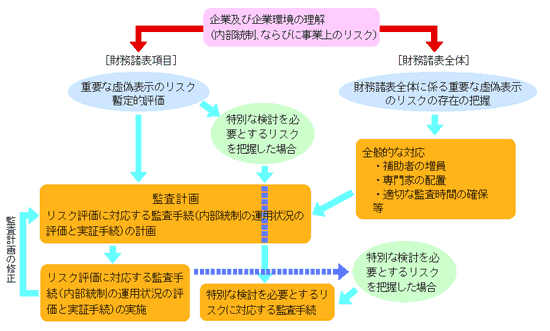
平成19年3月決算に係る監査から適用
監査基準の改訂及び監査の品質管理基準案を読み解く
企業会計審議会は7月20日、監査基準及び中間監査基準の改訂並びに監査に関する品質管理基準の設定について(公開草案)を公表した。監査法人等の内部管理体制をチェックするための品質管理基準や事業リスクを重視したリスクアプローチを監査基準及び中間監査基準に盛り込んでいる。なお、品質管理基準については、一般基準とは別に独立した基準として設けられる。8月22日まで意見募集した後、正式決定する。平成19年3月決算に係る財務諸表監査から実施する予定だ。特集では、公開草案の概要をお伝えする。
1 監査法人等の品質管理の向上を図る
まず、監査に関する品質管理基準の設定については、昨今の公認会計士監査をめぐる非違事例や国際的な動向を踏まえたものである。一般基準の改訂に加えて、別途、独立した基準として設けられることになった。
昨今では、学校法人東北文化学園大学に係る私立学校法に基づく財産目録監査及び私立学校振興助成法に基づく監査に関し、新日本監査法人及び公認会計士に対して戒告処分が行われている。また、あしぎんフィナンシャルグループ及び足利銀行に係る監査証明に関し、地方事務所に対する審査体制などの不備が認められたことから、中央青山監査法人に対して戒告処分が行われている。
このため、品質管理基準では、監査事務所(監査法人及び個人の公認会計士事務所)レベルの品質管理と個々の監査業務レベルでの品質管理に分け、監査業務の質を合理的に確保するため、監査契約の受任及び更新から監査計画の策定、監査業務の実施及び監査報告書の発行に至る各段階における品質管理システムの整備、運用を求めている。
また、監査実施者(監査実施の責任者と補助者)には、品質管理システムに従って監査業務を実施し、監査業務レベルで品質管理を行うことを求めている。加えて、監査事務所は、品質管理のシステムの整備及び運用の状況を適切に記録し、保存するための方針及び手続を定め、それらが遵守されていることを確かめることになっている。
品質管理のシステムの構築が必要
監査事務所については、①品質管理に関する責任者、②職業倫理及び独立性、③監査契約の受任及び更新、④監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任、⑤業務の実施、⑥品質管理のシステムの監視及び監査業務の検証-に関する方針及び手続からなる品質管理システムを設けなければならないとされた。
また、監査事務所内や外部の弁護士などの適切な者から見解を得た場合には、その見解が監査業務の実施及び監査意見の形成において十分に反映されているか確かめることが求められる。
一方、監査事務所は、監査業務に係る審査部門を設置し、監査業務に係る審査の内容及び結論を監査調書として記録し、保存することになる。仮に監査実施者と審査部門との間で判断の違いがあれば、これを解決しなければならない。解決がされない限りは、監査報告書を発行することができないことになる。
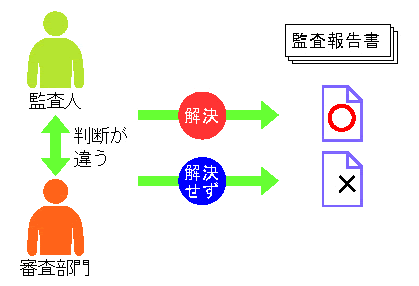
品質管理システム
① 品質管理に関する責任者
② 職業倫理及び独立性
③ 監査契約の受任及び更新
④ 監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任
⑤ 業務の実施
⑥ 品質管理のシステムの監視及び監査業務の検証
COLUMN
平成19年3月決算から適用も早期適用あり

改訂監査基準及び品質管理基準については、平成19年3月決算に係る財務諸表監査から実施する予定。また、改訂中間監査基準については、平成18年9月に終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から実施するほか、早期適用についても認められている。
なお、これらの基準の改正に伴う実務指針の作成については、日本公認会計士協会に対して、早急に行うことを求めている。
2 監査事務所間の引き継ぎを明記
その他、複数の監査事務所が共同して監査(共同監査)を行う場合には、他の監査事務所の品質管理のシステムが品質管理基準に準拠しているかどうかなどを監査の過程で確認しなければならないこととされた。
また、監査事務所間の引き継ぎについても明記されている。監査事務所は、後任の監査事務所への引き継ぎに関する方針及び手続を定め、遵守されていることを確かめなければならないとされている。仮に財務諸表における重要な虚偽表示に係る情報や状況を把握していた場合には、その旨を後任の監査事務所に伝えなければならない。
粉飾の疑いも
企業会計審議会の監査部会では、監査人の交代について、特に議論が集中して行われている。監査人が交代した後に会社が倒産するなど、粉飾決算をしていることが疑われるような事例が見受けられるからだ。
日本公認会計士協会が平成16年4月にまとめた監査人の交代に関するアンケート調査(平成14年1月から平成15年10月末までを対象)では、事業年度途中の交代は22件、期末決算日後の交代が3件あるとの報告がなされている(右表参照)。このうち、平成16年3月末までに民事再生法の適用申請に至った会社は4件となっている。また、監査業務の引き継ぎについては、前任監査人による回答があった101件のうち、80件(79.2%)が実施しているものの、残りの約20%については、未実施であることが明らかとなっている。
このため、今回の品質管理基準の策定により、監査事務所の引継については、厳格な運用が求められそうだ。
最終的には公認会計士・監査審査会がチェック
品質管理基準では、監査事務所は、品質管理のシステムの日常的監視及び監査業務の定期的な検証に関する方針及び手続を定め、遵守されていることを確かめることになる。ただ、これは、あくまでも監査事務所の内部管理体制をチェックするための基準である。
したがって、品質管理の妥当性については、まずは日本公認会計士協会が実施する品質管理レビューということになる。また、品質管理レビューの妥当性については、公認会計士・監査審査会がチェックすることになる。
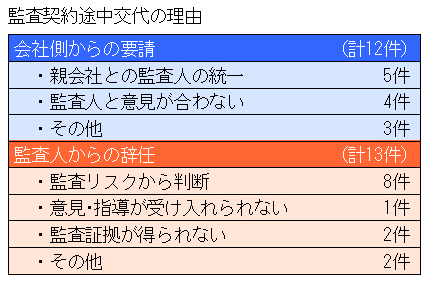
3 事業上のリスクを重視したリスク・アプローチを導入
改訂監査基準及び中間監査基準では、従来のリスク・アプローチを改善し、事業上のリスクを重視したリスク・アプローチを導入する。監査人が、内部統制を含む企業及び企業環境を考慮することを監査計画の策定や監査の実施における重要な要素と位置付け、基本原則に置いている。具体的には、財務諸表全体における虚偽表示のリスクを評価するトップ・ダウンの視点を追加。財務諸表において重要な虚偽の表示が生じる可能性を「財務諸表全体」及び「財務諸表項目」の2つのレベルで「重要な虚偽表示のリスク」として評価することにしている。財務諸表全体としての「重要な虚偽表示のリスク」があると判断した場合には、リスクに応じて補助者の増員、専門家の配置、適切な監査時間の確保など、全般的な対応を監査計画に反映することが求められる(下記参照)。
現行の基準
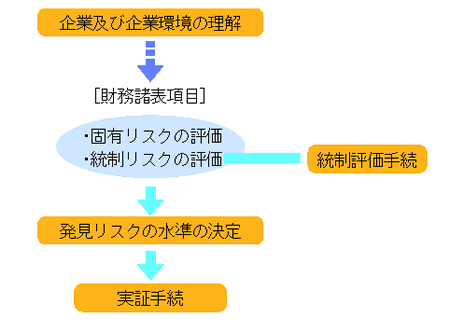
新しい基準
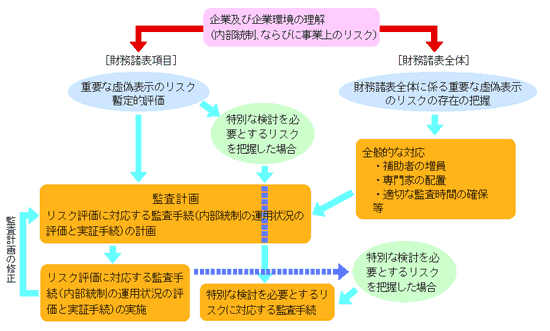
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























