資料2005年08月01日 【税務通達等】 広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)(2005年8月1日号・№125)
重要資料
平成17年6月17日
資産評価企画官情報 第1号 国税庁課税部 資産評価企画官
資産課税課情報 第7号 資産課税課
広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)
財産評価基本通達24-4に定める「広大地の評価」を適用する場合の広大地に該当するかどうかの判定に当たり留意すべき事項について、別紙のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。
別紙
広大地の判定に当たり留意すべき事項
広大地については、平成16年6月4日付課評2-7ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」により、その評価方法を改正し、その改正の趣旨等については、平成16年6月29日付資産評価企画官情報第2号「『財産評価基本通達の一部改正について』通達のあらましについて(情報)」(以下「情報第2号」という。)で明らかにしたところである。
広大地の定義については、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)において、「『その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条((定義))第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの』のうち、『大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるもの)』を除く」ものをいうとしている(評基通24-4)。
これを受けて、広大地に該当するかどうかを判定する場合の考え方について、情報第2号において整理したところであるが、本情報は、更なる考え方の統一性を図るために、以下に抜粋した部分のうち、アンダーラインを付した部分を中心に留意事項を取りまとめたものである。
○ 情報第2号「2 広大地の評価」(抜粋)
3 通達改正の概要
(2)広大地の範囲
評価通達における広大地は、①戸建住宅分譲用地として開発され、道路等の潰れ地が生じる土地を前提としていること、また、②「対象地がその存する地域の標準的な画地との比較において広大地と判定される画地であっても、一体利用することが市場の需給関係等を勘案して合理的と認められる場合には、地積過大による減価を行う必要がない」(「土地価格比準表の取扱いについて」、国土交通省)とされていることなどから、その宅地を中高層の集合住宅等の敷地として使用するのが最有効使用である場合、いわゆるマンション適地等については、広大地には該当しない旨を通達の中で明らかにした。
なお、「広大地に該当するもの、しないもの」の条件を例示的に示すと、以下のようになる。
(広大地に該当する条件の例示)
・普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準以上のもの(ただし、下記の該当しない条件の例示に該当するものを除く。)
(注)ミニ開発分譲が多い地域に存する土地については、開発許可を要する面積基準(例えば、三大都市圏500m2)に満たない場合であっても、広大地に該当する場合があることに留意する。
(広大地に該当しない条件の例示)
・既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地用地
・現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地(例えば、大規模店舗、ファミリーレストラン等)
・原則として容積率300%以上の地域に所在する土地
・公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地
(例)道路に面しており、間口が広く、奥行がそれほどではない土地
(道路が二方、三方、四方にある場合も同様)
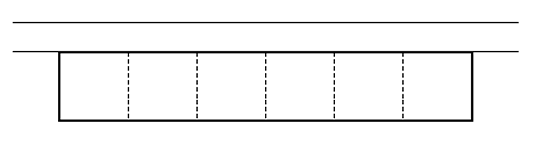
(3)マンション適地の判定
評価対象地について、中高層の集合住宅等の敷地、いわゆるマンション適地等として使用するのが最有効使用と認められるか否かの判断は、その土地の周辺地域の標準的使用の状況を参考とすることになるのであるが、戸建住宅とマンションが混在している地域(主に容積率200%の地域)にあっては、その土地の最有効使用を判断することが困難な場合もあると考えられる。
このような場合には、周囲の状況や専門家の意見等から判断して、明らかにマンション用地に適していると認められる土地を除き、戸建住宅用地として広大地の評価を適用することとして差し支えない。
(以下省略)
1 著しく広大であるかどうかの判定
上記の情報第2号「2 広大地の評価」(抜粋)のとおり、「普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準(以下「開発許可面積基準」という。)以上のもの」については、広大地に該当することとしている。これは、一定の面積を超えるものについて、開発行為を行うとした場合の公共公益的施設用地の負担を前提としており、その面積基準としては、基本的に、開発許可面積基準を指標とすることが適当である。
しかし、一部の都市においては、主要駅周辺の市街地についても市街化区域と市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き」)が行われていないところがある。線引きが行われていない地域の開発許可面積基準は3,000m2であることから、当該地域では、評価対象となる土地の面積が3,000m2以上でなければ、開発を行う場合に公共公益的施設用地の負担が生ずる場合であっても広大地に該当しないこととなる。
現行の都市計画制度において、線引きを行うかどうかは、首都圏の既成市街地等を除き、都道府県の選択に委ねることとされている。また、線引きが行われていない地域であっても、「用途地域が定められている地域においてはその目標とする市街地像の実現のために必要な都市施設を定めるべきである」(平成15年4月『都市計画運用指針』)とされている。つまり、線引きが行われていない地域のうち用途地域が定められている地域については、その用途地域の目指す環境実現のために市街化が進められていくものと考えられる。このことからすれば、開発許可面積基準は異なるものの、実態は市街化区域と区別する必要はないものと考えられることから、広大地の判定に当たっては、当該地域を市街化区域と同等に取り扱うのが相当である。
なお、開発許可面積基準以上であっても、その面積が地域の標準的な規模である場合は、当然のことながら、広大地に該当しない。
(注)著しく広大であるかどうかの判定は、当該土地上の建物の有無にかかわらず、当該土地の規模により判定することに留意する。
(面積基準)
原則として、次に掲げる面積以上の宅地については、面積基準の要件を満たすものとする。
① 市街化区域、非線引き都市計画区域(②に該当するものを除く。)
…… 都市計画法施行令第19条第1項及び第2項に定める面積(※)
※ 1 市街化区域
三大都市圏・・・500㎡
それ以外の地域・・・1,000㎡
2 非線引き都市計画区域・・・3,000㎡
② 用途地域が定められている非線引き都市計画区域
………………… 市街化区域に準じた面積
ただし、近隣の地域の状況から、地域の標準的な規模が上記面積以上である場合については、当該地域の標準的な土地の面積を超える面積のものとする。
(注)1 「非線引き都市計画区域」とは、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が行われていない都市計画区域をいう。
2 面積基準を図式化したものが(参考1)である。
2 現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地
前記の情報第2号「2 広大地の評価」(抜粋)のとおり、「大規模店舗、ファミリーレストラン等」は、「現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地」であることから、広大地に該当しないこととしている。
これは、比較的規模の大きい土地の有効利用の一形態として大規模店舗等を例示的に示したものである。したがって、大規模店舗等の敷地がその地域において有効利用されているといえるかどうか、言い換えれば、それらの敷地がその地域の土地の標準的使用といえるかどうかで判定するということであり、いわゆる「郊外路線商業地域」(都市の郊外の幹線道路(国道、都道府県道等)沿いにおいて、店舗、営業所等が連たんしているような地域)に存する大規模店舗等の敷地が、この「現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地」に該当する。
一方、例えば、戸建住宅が連たんする住宅街に存する大規模店舗やファミリーレストラン、ゴルフ練習場などは、その地域の標準的使用とはいえないことから、「現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地」には該当しない。
3 公共公益的施設用地の負担
評価通達において、「公共公益的施設用地」とは、「都市計画法第4条第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)」をいうこととしている。したがって、具体的には、教育施設のような大規模なものからごみ集積所のような小規模なものまでが「公共公益的施設」に該当することとなる。
しかし、広大地の評価は、戸建住宅分譲用地として開発した場合に相当規模の「公共公益的施設用地」の負担が生じる土地を前提としていることから、公共公益的施設用地の負担の必要性は、経済的に最も合理的に戸建住宅の分譲を行った場合の、当該開発区域内に開設される道路の開設の必要性により判定することが相当である。なお、ごみ集積所などの小規模な施設のみの開設が必要な土地は、「公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地」に該当するため、広大地に該当しない。
また、例えば、建築基準法第42条第2項の規定によるセットバックを必要とする場合の当該土地部分や、下図のように、セットバックを必要とする土地ではないが、開発行為を行う場合に道路敷きを提供しなければならない土地部分については、開発区域内の道路開設に当たらないことから、広大地に該当しない。
【図】開発指導等により、道路敷きとして一部土地を提供しなければならない場合
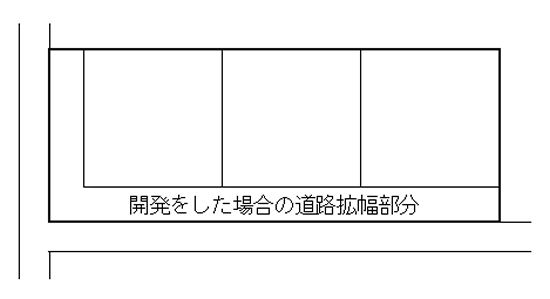
4 マンション適地の判定
評価しようとする土地が、課税時期においてマンション等の敷地でない場合、マンション等の敷地として使用するのが最有効使用と認められるかどうかの判定については、その土地の周辺地域の標準的使用の状況を参考とすることとなる。しかし、戸建住宅とマンション等が混在する地域(主に容積率200%の地域)は、最有効使用の判定が困難な場合もあることから、このような場合には、周囲の状況や専門家の意見から判断して、明らかにマンション等の敷地に適していると認められる土地を除き、広大地に該当する。
一方、容積率が300%以上の地域内にあり、かつ、開発許可面積基準以上の土地は、戸建住宅の敷地用地として利用するよりもマンション等の敷地として利用する方が最有効使用と判定される場合が多いことから、原則として、広大地に該当しないこととなる。
地域によっては、容積率が300%以上でありながら、戸建住宅が多く存在する地域もあるが、このような地域は都市計画で定めた容積率を十分に活用しておらず、①将来的に戸建住宅を取り壊したとすれば、マンション等が建築されるものと認められる地域か、あるいは、②何らかの事情(例えば道路の幅員)により都市計画法で定めた容積率を活用することができない地域であると考えられる。したがって、②のような例外的な場合を除き、容積率により判定することが相当である。
5 市街化調整区域内の土地に係る広大地の評価について
(1)市街化調整区域内の土地の分類
平成12年の「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」により、開発許可制度は、地域の実情に応じた土地利用規制を実現するために柔軟な規制が行える体系に整備されることとなった。具体的には、旧「既存宅地」制度を、経過措置を設けて廃止することとし、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下同じ。)が条例で区域を定め、その区域においては周辺環境の保全上支障がない用途の建築物の建築等を目的とする開発行為を許可対象とした(都市計画法第34条第八号の三)。
(注)旧「既存宅地」制度とは、改正前の都市計画法第43条第1項第6号に基づく制度で、市街化区域に近接し50戸以上の建築物が連たんするなどの地域に存し、市街化区域及び市街化調整区域の線引き前からの宅地であったとして、都道府県知事等の確認を受けた宅地を通常、既存宅地という。
上記の法律改正に伴い、市街化調整区域内の土地については、「条例指定区域内の土地」及び「それ以外の区域内の土地」の2つに分類することができる。
イ 条例指定区域内の土地
「条例指定区域内の土地」とは、上記の都市計画法の定めにより開発行為を許可することができることとされた区域内の土地であり、具体的には、「市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域」のうち、都道府県の条例で指定する区域内の土地をいう。
当該区域内の土地については、都道府県知事は、開発区域及びその周辺の地域の環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないものについて、開発を許可することができることとされている。したがって、その区域内のすべての土地について、都市計画法上の規制は一律となる一方、許可対象とされる区域の詳細や建築物の用途等は、都道府県の条例により定められることとなるため、それぞれの地域によってその内容が異なることとなる。
ロ それ以外の区域内の土地
上記イ以外の区域内の土地については、原則として、周辺地域住民の日常生活用品の店舗や農林漁業用の一定の建築物などの建築の用に供する目的など、一定のもの以外は開発行為を行うことができない。
(2)広大地に該当するかどうかの判定
上記(1)より、市街化調整区域内の宅地が広大地に該当するかどうかについては、「条例指定区域内の宅地」であり、都道府県の条例の内容により、戸建分譲を目的とした開発行為を行うことができる場合には広大地に該当するが、それ以外の区域内に存するものについては、広大地に該当しない。
また、市街化調整区域内の雑種地で、宅地に比準して評価する場合については、宅地の場合と同様に取り扱うことが相当である。
(参考1)
○ 広大地評価の面積基準のイメージ
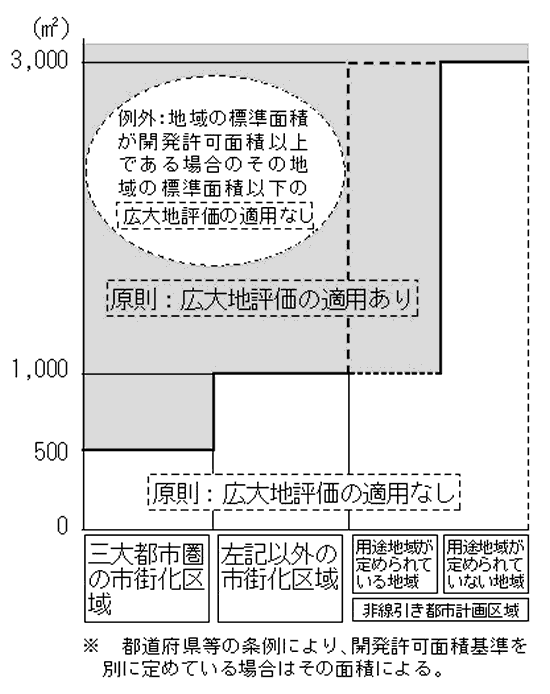
(参考2)
○ 広大地評価フローチャート
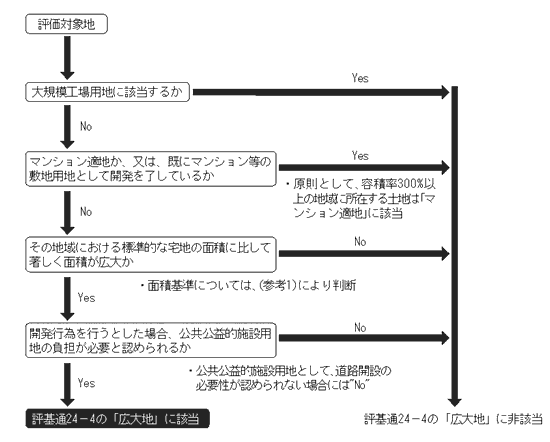
平成17年6月17日
資産評価企画官情報 第1号 国税庁課税部 資産評価企画官
資産課税課情報 第7号 資産課税課
広大地の判定に当たり留意すべき事項(情報)
財産評価基本通達24-4に定める「広大地の評価」を適用する場合の広大地に該当するかどうかの判定に当たり留意すべき事項について、別紙のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。
別紙
広大地の判定に当たり留意すべき事項
広大地については、平成16年6月4日付課評2-7ほか2課共同「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」により、その評価方法を改正し、その改正の趣旨等については、平成16年6月29日付資産評価企画官情報第2号「『財産評価基本通達の一部改正について』通達のあらましについて(情報)」(以下「情報第2号」という。)で明らかにしたところである。
広大地の定義については、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)において、「『その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で都市計画法第4条((定義))第12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるもの』のうち、『大規模工場用地に該当するもの及び中高層の集合住宅等の敷地用地に適しているもの(その宅地について、経済的に最も合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的とするものであると認められるもの)』を除く」ものをいうとしている(評基通24-4)。
これを受けて、広大地に該当するかどうかを判定する場合の考え方について、情報第2号において整理したところであるが、本情報は、更なる考え方の統一性を図るために、以下に抜粋した部分のうち、アンダーラインを付した部分を中心に留意事項を取りまとめたものである。
○ 情報第2号「2 広大地の評価」(抜粋)
3 通達改正の概要
(2)広大地の範囲
評価通達における広大地は、①戸建住宅分譲用地として開発され、道路等の潰れ地が生じる土地を前提としていること、また、②「対象地がその存する地域の標準的な画地との比較において広大地と判定される画地であっても、一体利用することが市場の需給関係等を勘案して合理的と認められる場合には、地積過大による減価を行う必要がない」(「土地価格比準表の取扱いについて」、国土交通省)とされていることなどから、その宅地を中高層の集合住宅等の敷地として使用するのが最有効使用である場合、いわゆるマンション適地等については、広大地には該当しない旨を通達の中で明らかにした。
なお、「広大地に該当するもの、しないもの」の条件を例示的に示すと、以下のようになる。
(広大地に該当する条件の例示)
・普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準以上のもの(ただし、下記の該当しない条件の例示に該当するものを除く。)
(注)ミニ開発分譲が多い地域に存する土地については、開発許可を要する面積基準(例えば、三大都市圏500m2)に満たない場合であっても、広大地に該当する場合があることに留意する。
(広大地に該当しない条件の例示)
・既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地用地
・現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地(例えば、大規模店舗、ファミリーレストラン等)
・原則として容積率300%以上の地域に所在する土地
・公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地
(例)道路に面しており、間口が広く、奥行がそれほどではない土地
(道路が二方、三方、四方にある場合も同様)
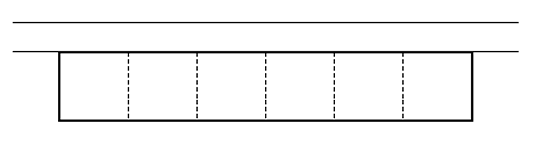
(3)マンション適地の判定
評価対象地について、中高層の集合住宅等の敷地、いわゆるマンション適地等として使用するのが最有効使用と認められるか否かの判断は、その土地の周辺地域の標準的使用の状況を参考とすることになるのであるが、戸建住宅とマンションが混在している地域(主に容積率200%の地域)にあっては、その土地の最有効使用を判断することが困難な場合もあると考えられる。
このような場合には、周囲の状況や専門家の意見等から判断して、明らかにマンション用地に適していると認められる土地を除き、戸建住宅用地として広大地の評価を適用することとして差し支えない。
(以下省略)
1 著しく広大であるかどうかの判定
上記の情報第2号「2 広大地の評価」(抜粋)のとおり、「普通住宅地区等に所在する土地で、各自治体が定める開発許可を要する面積基準(以下「開発許可面積基準」という。)以上のもの」については、広大地に該当することとしている。これは、一定の面積を超えるものについて、開発行為を行うとした場合の公共公益的施設用地の負担を前提としており、その面積基準としては、基本的に、開発許可面積基準を指標とすることが適当である。
しかし、一部の都市においては、主要駅周辺の市街地についても市街化区域と市街化調整区域の区域区分(いわゆる「線引き」)が行われていないところがある。線引きが行われていない地域の開発許可面積基準は3,000m2であることから、当該地域では、評価対象となる土地の面積が3,000m2以上でなければ、開発を行う場合に公共公益的施設用地の負担が生ずる場合であっても広大地に該当しないこととなる。
現行の都市計画制度において、線引きを行うかどうかは、首都圏の既成市街地等を除き、都道府県の選択に委ねることとされている。また、線引きが行われていない地域であっても、「用途地域が定められている地域においてはその目標とする市街地像の実現のために必要な都市施設を定めるべきである」(平成15年4月『都市計画運用指針』)とされている。つまり、線引きが行われていない地域のうち用途地域が定められている地域については、その用途地域の目指す環境実現のために市街化が進められていくものと考えられる。このことからすれば、開発許可面積基準は異なるものの、実態は市街化区域と区別する必要はないものと考えられることから、広大地の判定に当たっては、当該地域を市街化区域と同等に取り扱うのが相当である。
なお、開発許可面積基準以上であっても、その面積が地域の標準的な規模である場合は、当然のことながら、広大地に該当しない。
(注)著しく広大であるかどうかの判定は、当該土地上の建物の有無にかかわらず、当該土地の規模により判定することに留意する。
(面積基準)
原則として、次に掲げる面積以上の宅地については、面積基準の要件を満たすものとする。
① 市街化区域、非線引き都市計画区域(②に該当するものを除く。)
…… 都市計画法施行令第19条第1項及び第2項に定める面積(※)
※ 1 市街化区域
三大都市圏・・・500㎡
それ以外の地域・・・1,000㎡
2 非線引き都市計画区域・・・3,000㎡
② 用途地域が定められている非線引き都市計画区域
………………… 市街化区域に準じた面積
ただし、近隣の地域の状況から、地域の標準的な規模が上記面積以上である場合については、当該地域の標準的な土地の面積を超える面積のものとする。
(注)1 「非線引き都市計画区域」とは、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が行われていない都市計画区域をいう。
2 面積基準を図式化したものが(参考1)である。
2 現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地
前記の情報第2号「2 広大地の評価」(抜粋)のとおり、「大規模店舗、ファミリーレストラン等」は、「現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地」であることから、広大地に該当しないこととしている。
これは、比較的規模の大きい土地の有効利用の一形態として大規模店舗等を例示的に示したものである。したがって、大規模店舗等の敷地がその地域において有効利用されているといえるかどうか、言い換えれば、それらの敷地がその地域の土地の標準的使用といえるかどうかで判定するということであり、いわゆる「郊外路線商業地域」(都市の郊外の幹線道路(国道、都道府県道等)沿いにおいて、店舗、営業所等が連たんしているような地域)に存する大規模店舗等の敷地が、この「現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地」に該当する。
一方、例えば、戸建住宅が連たんする住宅街に存する大規模店舗やファミリーレストラン、ゴルフ練習場などは、その地域の標準的使用とはいえないことから、「現に宅地として有効利用されている建築物等の敷地」には該当しない。
3 公共公益的施設用地の負担
評価通達において、「公共公益的施設用地」とは、「都市計画法第4条第14項に規定する道路、公園等の公共施設の用に供される土地及び都市計画法施行令第27条に掲げる教育施設、医療施設等の公益的施設の用に供される土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む。)」をいうこととしている。したがって、具体的には、教育施設のような大規模なものからごみ集積所のような小規模なものまでが「公共公益的施設」に該当することとなる。
しかし、広大地の評価は、戸建住宅分譲用地として開発した場合に相当規模の「公共公益的施設用地」の負担が生じる土地を前提としていることから、公共公益的施設用地の負担の必要性は、経済的に最も合理的に戸建住宅の分譲を行った場合の、当該開発区域内に開設される道路の開設の必要性により判定することが相当である。なお、ごみ集積所などの小規模な施設のみの開設が必要な土地は、「公共公益的施設用地の負担がほとんど生じないと認められる土地」に該当するため、広大地に該当しない。
また、例えば、建築基準法第42条第2項の規定によるセットバックを必要とする場合の当該土地部分や、下図のように、セットバックを必要とする土地ではないが、開発行為を行う場合に道路敷きを提供しなければならない土地部分については、開発区域内の道路開設に当たらないことから、広大地に該当しない。
【図】開発指導等により、道路敷きとして一部土地を提供しなければならない場合
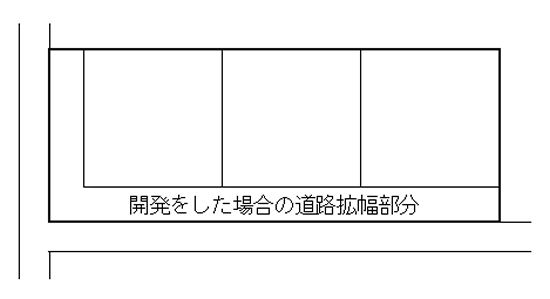
4 マンション適地の判定
評価しようとする土地が、課税時期においてマンション等の敷地でない場合、マンション等の敷地として使用するのが最有効使用と認められるかどうかの判定については、その土地の周辺地域の標準的使用の状況を参考とすることとなる。しかし、戸建住宅とマンション等が混在する地域(主に容積率200%の地域)は、最有効使用の判定が困難な場合もあることから、このような場合には、周囲の状況や専門家の意見から判断して、明らかにマンション等の敷地に適していると認められる土地を除き、広大地に該当する。
一方、容積率が300%以上の地域内にあり、かつ、開発許可面積基準以上の土地は、戸建住宅の敷地用地として利用するよりもマンション等の敷地として利用する方が最有効使用と判定される場合が多いことから、原則として、広大地に該当しないこととなる。
地域によっては、容積率が300%以上でありながら、戸建住宅が多く存在する地域もあるが、このような地域は都市計画で定めた容積率を十分に活用しておらず、①将来的に戸建住宅を取り壊したとすれば、マンション等が建築されるものと認められる地域か、あるいは、②何らかの事情(例えば道路の幅員)により都市計画法で定めた容積率を活用することができない地域であると考えられる。したがって、②のような例外的な場合を除き、容積率により判定することが相当である。
5 市街化調整区域内の土地に係る広大地の評価について
(1)市街化調整区域内の土地の分類
平成12年の「都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律」により、開発許可制度は、地域の実情に応じた土地利用規制を実現するために柔軟な規制が行える体系に整備されることとなった。具体的には、旧「既存宅地」制度を、経過措置を設けて廃止することとし、都道府県(指定都市等又は事務処理市町村の区域内にあっては、当該指定都市等又は事務処理市町村。以下同じ。)が条例で区域を定め、その区域においては周辺環境の保全上支障がない用途の建築物の建築等を目的とする開発行為を許可対象とした(都市計画法第34条第八号の三)。
(注)旧「既存宅地」制度とは、改正前の都市計画法第43条第1項第6号に基づく制度で、市街化区域に近接し50戸以上の建築物が連たんするなどの地域に存し、市街化区域及び市街化調整区域の線引き前からの宅地であったとして、都道府県知事等の確認を受けた宅地を通常、既存宅地という。
上記の法律改正に伴い、市街化調整区域内の土地については、「条例指定区域内の土地」及び「それ以外の区域内の土地」の2つに分類することができる。
イ 条例指定区域内の土地
「条例指定区域内の土地」とは、上記の都市計画法の定めにより開発行為を許可することができることとされた区域内の土地であり、具体的には、「市街化区域に隣接し、又は近接し、かつ、自然的社会的諸条件から市街化区域と一体的な日常生活圏を構成していると認められる地域であっておおむね50以上の建築物が連たんしている地域」のうち、都道府県の条例で指定する区域内の土地をいう。
当該区域内の土地については、都道府県知事は、開発区域及びその周辺の地域の環境の保全上支障があると認められる用途として都道府県の条例で定めるものに該当しないものについて、開発を許可することができることとされている。したがって、その区域内のすべての土地について、都市計画法上の規制は一律となる一方、許可対象とされる区域の詳細や建築物の用途等は、都道府県の条例により定められることとなるため、それぞれの地域によってその内容が異なることとなる。
ロ それ以外の区域内の土地
上記イ以外の区域内の土地については、原則として、周辺地域住民の日常生活用品の店舗や農林漁業用の一定の建築物などの建築の用に供する目的など、一定のもの以外は開発行為を行うことができない。
(2)広大地に該当するかどうかの判定
上記(1)より、市街化調整区域内の宅地が広大地に該当するかどうかについては、「条例指定区域内の宅地」であり、都道府県の条例の内容により、戸建分譲を目的とした開発行為を行うことができる場合には広大地に該当するが、それ以外の区域内に存するものについては、広大地に該当しない。
また、市街化調整区域内の雑種地で、宅地に比準して評価する場合については、宅地の場合と同様に取り扱うことが相当である。
(参考1)
○ 広大地評価の面積基準のイメージ
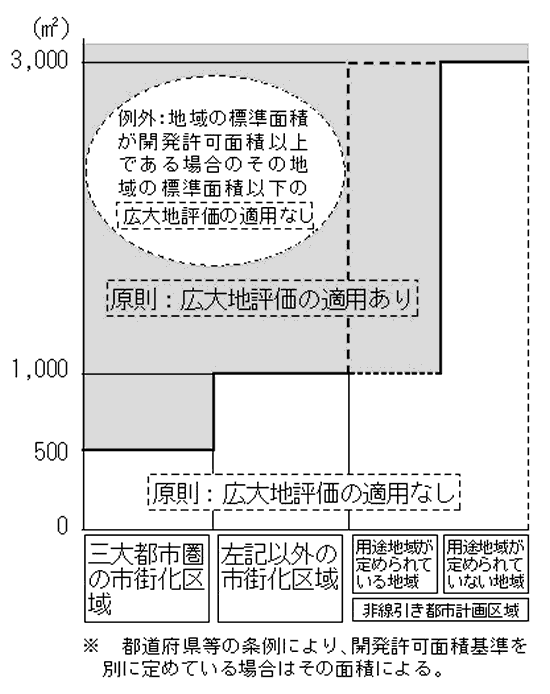
(参考2)
○ 広大地評価フローチャート
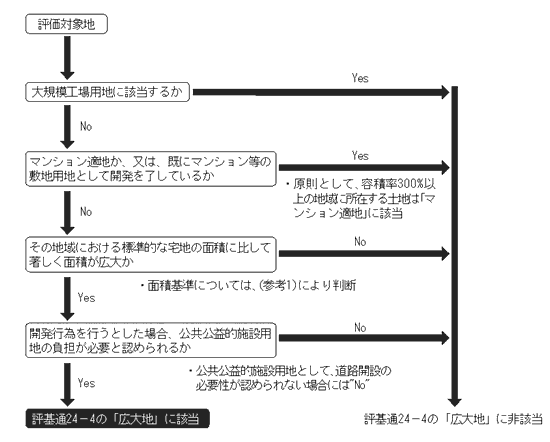
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















