解説記事2005年10月03日 【実務解説】 広大地評価の実務(2005年10月3日号・№132)
実 務 解 説
広大地評価の実務
税理士・名古屋経済大学大学院非常勤講師 浅野 洋
Ⅰ はじめに
財産評価基本通達には運用する際の解釈に困難を伴い、適用が可能かどうかの判断に迷う規定が散見される。これは同通達が上級庁から下級庁への行政処分であり、財産の時価評価を規定した相続税法第22条を補完する存在として法的拘束力を持たず、評価対象の財産が置かれる種々の状況下にあっても課税の公平を確保するべく考慮している結果でもあろう。しかし実務に当たっては、同通達が事実上財産評価の唯一の拠り所であるため、統一的な基準がある方が課税の公平にかなう場合もあると思われる。
財産評価基本通達24-4に規定されている広大地の評価は、その難解な通達の一例である。平成16年6月4日付で運用の改善を主眼とした改正が行われたが、改正後の現在でさえ広大地の評価にあたりこの通達を適用できるのか否かの判断に迷うケースが多い。本編では改正後の評価通達24-4に規定する適用要件を精研しその問題点を概観しつつ、実例を通じて課税庁がどのような広大地をこの通達の適用対象と想定しているのか具体的に推測したい。
Ⅱ 広大地評価の概要について
(1)評価方法
平成16年6月改正後の評価通達24-4によると、広大地は以下のように評価する。
広大地補正率について、同通達改正以前には広大地を鑑定評価額により評価する事例が多かったため、国税庁は鑑定評価事例を統計学的に分析し、評価上の簡便性・安全性に考慮して算出している。なおこの広大地補正率以外の各種補正率(評価通達15(奥行価格補正)から24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)までの各補正率)は適用しないが、評価通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)だけは個別事情の斟酌の必要性から重複適用可としている。
① 路線価地域に所在する場合
広大地の価額=正面路線価×広大地補正率(※)×地積
(※)広大地補正率=0.6-0.05×地積/1000m2
② 倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1m2当たりの価額を評価通達14に定める路線価として、上記①に準じて計算した金額
(2)適用対象となる広大地
評価通達24-4の適用対象となる広大地の要件は、同通達及び平成16年6月29日付資産評価企画官情報第2号「『財産評価基本通達の一部改正について』通達のあらましについて(情報)」(以下「あらまし」という)に規定されている。下記にその内容を要約した。
① その地域の標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であること。
② 都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められること。つまり戸建住宅分譲用地として開発され、道路等の潰れ地が生じる土地であること。
③ 普通住宅地区等に所在する土地で各自治体が定める開発許可を要する面積以上のもの。ただし、近隣の状況から、その地域の標準的な土地の規模が上記の面積以上である場合は、その面積を超えるもの。
(なお、ミニ開発分譲が多い地域についてはその面積基準を満たさなくても広大地に該当する場合がある。)
④ 次に掲げる土地に該当しないこと。
● 大規模工場用地
● 既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地
● マンションの敷地として使用するのが最も有効と考えられる土地
● 現に宅地として有効利用している構築物等の敷地(大規模店舗・ファミリーレストラン等)
● 原則として容積率300%以上の地域に所在する土地
<参考>面積基準
○市街化区域及び市街化区域と市街化調整区域の区分が行われていない区域(以下、「非線引き都市計画区域」という)については、都市計画法施行令第19条第1項及び第2項に定める次に掲げる面積以上のもの
市街化区域 三大都市圏・・・・・・・・・・ 500m2
それ以外の地域・・・・・・ 1,000m2
非線引き都市計画区域・・・・・・・・・・・・・・ 3,000m2
○用途地域が定められている非線引き都市計画区域は、市街化区域に準じた面積
(3)解説としての「留意事項」の内容
平成16年6月の評価通達24-4の改正によって、広大地は通常の評価額と比較して最大65%の評価減が可能となり大幅に納税者有利であることから、個別事例について同通達に規定する広大地に該当するかどうかの照会が課税庁に多数寄せられた。国税庁は広大地の判定について考え方の統一を図るため、平成17年6月17日付で「広大地の判定に当たり留意すべき事項」(以下「留意事項」という)と題する資産評価企画官情報を発表した。以下、その内容について概説する。
① 著しく広大であるかどうかの判断について
非線引き地域の開発許可基準は3,000m2であるが、このうち用途地域が定められている地域は市街地化が進んでいくと考えられるため、その地域を市街化区域と同等に取り扱うこととし、次頁の面積基準を明示した。
しかし、この開発許可面積基準以上であっても、その面積が地域の標準的な規模である場合は広大地に該当しないとの一文があり、判断基準としては不透明さが残る。
② 現に宅地として有効利用している構築物等の敷地について
例示された大規模店舗等の敷地がその地域の標準的使用といえる場合は「宅地として有効利用」されており、広大地に該当しないことが解説されている。「有効利用」の解釈として、賃料の多寡など利回りに関する判断基準が採用されていないことに留意する必要がある。
③ 公共公益的施設用地の負担について
施設の内容は、合理的に戸建住宅の分譲を行った場合に開発地域内に開設される道路であると明言されている。また、セットバックや開発に伴い提供する道路敷き部分はここでいう公共公益的施設用地に含まれていない。
④ マンション適地の判定について
国税庁はマンション適地の判定について、「あらまし」から引き続き「周辺地域の標準的使用の状況を参考とする」との見解を貫いており、専門家の意見等から判断して明らかにマンション適地と認められる土地を除き、戸建住宅用地として広大地の評価を適用するとしている。
また、容積率300%以上の地域に所在する土地については、戸建住宅よりもマンションとして利用する方が最有効利用であるため原則として広大地に該当せず、容積率が300%以上でありながら戸建住宅が多い地域についても、道路幅員など容積率を活用できない事情がない限りは広大地には該当しない旨を明らかにしている。
⑤ 市街化調整区域内の土地に係る広大地の評価について
条例指定区域内の宅地(都市計画法で開発が許可された区域内の土地)で、都道府県の条例により戸建分譲を目的とした開発ができる場合は広大地に該当するとの見解が示されている。
Ⅲ この通達の問題点
(1)広大地の判断の困難性
広大地に該当するか否かの判断基準のうち「あらまし」において漠然としていた適用要件のうち、上記Ⅱ(3)③の公共公益的施設用地など「留意事項」で明確にされた部分もある。
しかし客観性を欠く判断基準は「留意事項」の発表後も健在である。例えばⅡ(3)①の著しく広大であるかどうかの判断には『開発許可面積基準以上であっても、その面積が地域の標準的な規模である場合は、当然のことながら、広大地に該当しない。』との文言があるが、実務では、「開発許可面積以上ではあるが周辺宅地より顕著に広大とも言い切れない」程度の地積の土地に直面することは決して珍しくない。そのような土地が広大地に該当するか判定しようとしても、「地域の標準的な規模」とはどの面積をもって標準的とするのか、その標準規模の目安の計算方法も示されていないため釈然としない。同様の曖昧さは②現に宅地として有効利用している構築物等の敷地④マンション適地の判定においても見受けられる。専門家の意見を斟酌して判断するよう指導されてはいるが、専門家とは具体的にどのような知識を有する者なのか明らかでなく、納税者の立場からはその見解が課税当局に必ず是認されるという確信も抱きにくい。
結果として適用の是非の判断が感覚的にならざるを得ず、判断に個人差が生じてしまうため、明確な判断基準とは言い難い。
(2)マンション適地の考え方
「マンション適地を除く」との要件の趣旨は、既にマンションが林立する地域では一筆の広大地をマンション用地として分割せず売却できる可能性があるため、通常の評価額の方が時価をより反映しており、広大地評価を適用する必要はないというものである。戸建住宅の多い地域に存する広大地は分譲開発することが自然であるから、その開発に伴い生じる潰れ地等の負担を考慮した評価を認めている。この考え方は時価を評価額に反映するという意味で妥当なものといえる。
しかし、ある広大地について周辺地域にマンションは建設されているが、マンションより戸建住宅としての需要のほうがやや高い場合など、その広大地のマンション用地としての売価と戸建住宅用地として売価が大差ないケースも考えられる。このような場合、マンション適地と判断されてこの通達の適用除外となれば、売価と評価額に著しい乖離が生じる可能性もある。この通達の趣旨は敷地が広大であるが故に生ずる減価を評価額に反映させようというものであるから、面積が広大であることが減価要因にならないと真に認められる場合にのみこの通達の適用除外とすべきである。従ってマンション適地の判断は周辺状況のみでなく、売却した場合の用途別売価の観点からも慎重に行われることが望ましい。
(3)他の補正率の除外
広大地補正率は土地の個別要因の事情補正を加味されており、不整形、奥行長大などの特殊な形状、市街地農地等である広大地を評価する場合の宅地造成費等やセットバック部分の斟酌については改めて考慮しないが、都市計画道路予定地となる区域内においては、個々の地域に応じた土地の利用制限を受けることになるため、個別に斟酌するのが相当との考え方から、広大地補正率により評価した後で評価通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)を適用することになっている。
しかし、例えば評価対象地が宅地の場合と市街化農地の場合とでは宅地造成費相当額だけ評価額が異なるのが当然であり、不整形地か否かに関わらず同額で評価されるのも不合理である。また、個別に斟酌すべきとの理由で評価通達24-7のみが重複適用を認められているが、不整形地など他の補正率要因も個別事情ではないのだろうか。土地に関わる複雑な要因を極力評価額に反映する従来の評価通達のスタンスから見れば、この広大地の評価方法は簡便であるがゆえに本来の目的から離れる結果を招きかねない。
現行の広大地補正率を評価通達15(奥行価格補正)から24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)までの各補正率に相当する部分を減殺した補正率に改定し、その上で各補正率の重複適用を認めるなどの措置を検討すべきである。
Ⅳ 実例に見る判断の実態
上記の現状に鑑みると、評価通達24-4、「あらまし」及び「留意事項」の記載事項から広大地に該当するかどうかを客観的に判断するのは非常に困難だが、広大地に該当するか否かで評価額が大きく異なる場合もあるため、実務では所轄税務署に事前照会を行うことが多いであろう。特に「著しく広大」及び「マンション適地」の判断については個別に税務署と見解の一致を見ておくことが不可欠である。
そこで、実際に照会を行った広大地の状況とそれに対する課税当局の返答をまとめ、この通達の運用状況を概観する。
ケース1
(1)土地の状況
●地方都市に所在
●市街化区域内の普通住宅地区所在・路線価方式で評価
●建ぺい率60%・容積率200%
●地積1,300m2・間口35m・奥行40m・一方の路線にのみ面する
<概略図>
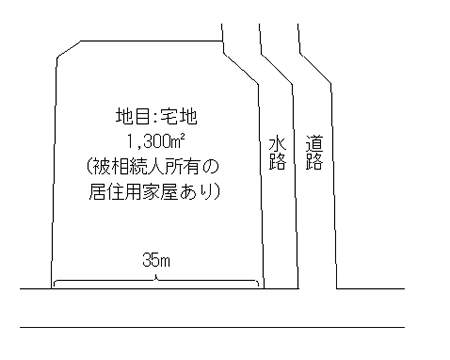
(2)周辺地域の状況
この土地は市中心部の東方約1.5kmに所在し、一般住宅の中に農地が混在する環境である。市中心部には官公庁の他一般企業も存在し、商業地にも近接している。市の人口は過去一貫して微増傾向であるが、周辺にマンションは少なく、現在建築工事中のものが多数あるとも言えない。
近隣の地価公示ポイントにおける平成17年国土交通省地価公示の「周辺の土地の利用現況」には「一般住宅を中心にアパート等が混在する住宅地域」と記載されている。古くからの農家住宅が多く、この土地と同等もしくはやや小さめの地積の住宅が中心的である。この土地を含む1ブロックの概要図は次のとおりである。
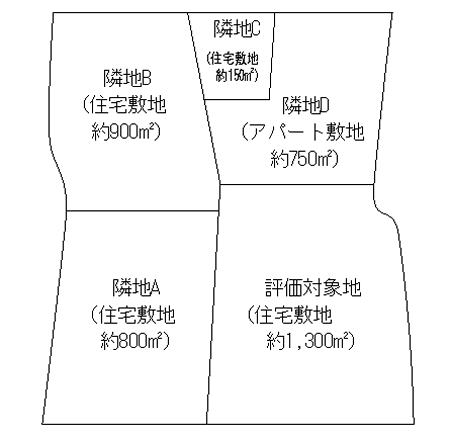
(3)国税局の見解
国税局からこの土地について以下の理由により、広大地に該当しないとの見解を受けた。
① 現に有効利用されている構築物等の敷地の該当性
評価土地上に居住用の家屋があることから、この土地が「現に有効利用されている構築物等の敷地」に該当するか否かが問題にされた。有効利用とはこの地域の標準的な使用がなされていることである。この場合の標準的使用状況は住宅であると考えられるが、「あらまし」で例示された大規模店舗、ファミリーレストラン等と居住用の住宅とを同一に考えることが適正と言い切れない面もあり、この問題に関しては回答を保留する。
② 著しく広大であるかどうかの判定
評価対象土地(1,300m2)は周辺宅地の標準的な地積(700~1,000m2)に比して広大であることは認められる。しかし、この地域の標準的規模と考えられる隣地Aや隣地Bと比較すると、評価対象地が必ずしも「著しく」広大であるとは断じがたい。
③ 開発行為を行う場合の道路負担の必要性について
開発行為を行う場合に市の許可が必要な面積ではあるが、評価対象地の東側に水路(巾約1.5m)を挟んで道路が存在し、戸建住宅として分譲時にこの道路も利用することを考慮すれば、開発に伴い潰れ地(道路)の負担はほとんど生じないと考えられる。
(4)判定に関する問題点
上記の判断から推察すると、「周辺の標準的な宅地の地積」の判断基準が明示されていないものの、標準的な地積より2、3割増し程度であれば「著しく広大」であるとは認められないようである。また、潰れ地の有無についても仮定の開発計画に基づく推測であり、条件の相違、例えば開発分譲する戸建住宅の規模によって必要となる潰れ地の規模も違うはずである。この実例の場合、評価対象地に130坪程度の戸建住宅を3戸分譲するのであれば潰れ地は不必要かもしれないが、仮に65坪の住宅を6戸分譲することを想定すれば道路は最少でも一本必要で、潰れ地が生じることも考えられる。このように判定結果に影響を及ぼす前提条件の設定が課税当局に委ねられたうえで広大地の判断がなされるのは、納税者の権利に配慮するという観点からはやや疑問である。
ケース2
(1)土地の状況
●中規模都市に所在
●市街化区域内の普通住宅地区所在・路線価方式で評価
●建ぺい率60%・容積率200%
●地積1,850m2(2筆の合計。A:1,700m2 B:150m2)・三方の路線に面する
<概略図>(右記参照)
(2)周辺地域の状況
この土地は、市中心部の南西約7kmに所在し、農業地帯の中に一般住宅が混在する地域である。住宅地図・公図を見る限りでは周辺の標準的な宅地の規模は300m2前後と思われる。上記A地の地目は宅地、B地の地目は畑であるが、実際の利用状況は図のようにA地・B地ともそれぞれ宅地部分と畑部分に分かれている。周辺にマンションはなく、現在建築工事中のものも見当たらない。
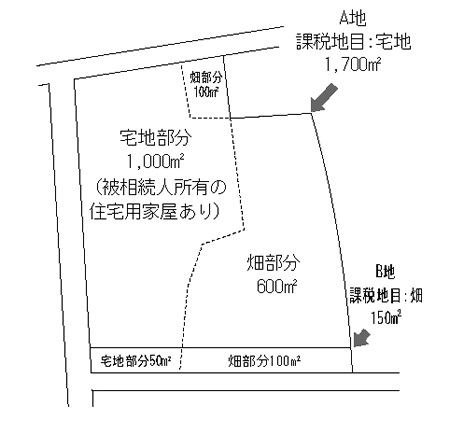
(3)国税局の見解
国税局からこの土地について以下の理由により、広大地に該当しないとの見解を受けた。
① 評価単位について
広大地の判定の際は、通常の土地評価時と同様にまず現況の地目別に区分し(評価通達7)、地目ごとに広大地の判定を行うこととする。従って宅地部分の1,000m2+50m2=1,050m2を判定単位とすることになる。
② 著しく広大であるかどうかの判定
標準的な宅地の規模は300m2前後と考えられるため、宅地部分の1,050m2は著しく広大であると認められる。
③ 開発行為を行う場合の道路負担の必要性について
開発行為を行う場合に市の許可が必要な面積ではあるが、評価対象地は三方に道路が接しており、周辺の標準的宅地と同規模の戸建住宅を分譲することを想定すると、開発に伴い潰れ地(道路)の負担は全く生じないと考えられる。
(4)判定に関する問題点
上記の土地を戸建住宅として開発する場合、宅地部分と畑部分の形状や地積を考慮すれば、両者を一括して開発申請することが十分考えられるが、課税当局は地目の区分を優先し、地目の異なるごとに別個の開発計画があるかのように判定している。開発許可面積を面積基準として採用している以上、実際に申請されるであろう開発計画を基準に「著しく広大」及び「潰れ地の有無」を判定するのでなければ実情に合わず、広大地としての使用可能性を加味した評価はできないのではないか。
また、宅地部分のみで判定するとしても、周辺の標準的宅地と同規模の戸建住宅の開発を想定するのは必ずしも合理的ではない。なぜなら、その「同規模の戸建住宅」が現在の社会情勢や地域に応じた需要を反映しているとは限らず、実際に開発申請する場合に提示される開発計画と内容が異なることがありうるからである。ケース1についても言えることだが、「あらまし」に規定されている「開発行為を行うとした場合」という要件を厳格化し、どのような開発行為かを明文化すべきである。現状では納税者は「実現可能性が最も高い地積の戸建住宅」を想定し、課税庁は「周辺の標準的な地積の戸建住宅」を前提としている傾向が見受けられる。前述した財産評価基本通達の趣旨に立ち返れば、前者を採用するのが自然であろうし、周辺の標準的な地積に依るのであればそれを明文化すべきであろう。
Ⅴ 最後に
Ⅳの実例を見る限り、要件に適合しない可能性が多少なりともある場合は広大地に該当しないと判断されるようである。特に「開発計画の内容」と「標準的な宅地の規模」の捉え方によって適否いずれにも解釈できるケースでは、納税者の意思どおり広大地と認定されるのは困難と思われる。
評価通達24-4(広大地の評価)は、広大地に該当するかどうかの判定基準の曖昧さをはじめ、解決すべき多くの問題を残している。明確な判断基準を設けるとかえって個別事由を斟酌できず、本来広大地であるものにこの通達が適用できなくなることを危惧する向きもあろう。しかし、そもそも評価通達は、租税の公平を実現するため相続税法22条に規定する時価の意義について統一的基準を示すものであるとの前提に立てば、このように適用要件が漠然とした通達の存在は評価制度の整合性を欠き、租税の公平を阻害する結果に繋がりかねない。広大地の判定に画一的な基準を設ければ、評価の実務負担は増大するであろうが、適用要件が明確であればこそ評価制度の普及を促進することにもなり、改善の余地は十分にあると思われる。前述の「地域の標準的な規模の面積」を例に取れば、一般の土地等の評価倍率表のように地域を区分し、その各地域について「標準的な宅地の地積」が明示されてもよい。
個々の事情を十分勘案して広大地の判定をすべきとの姿勢を維持しつつ、課税の公平も達成できる制度により近づくことも可能と考えるが、その取り組みがし尽くされていない感があるのが現状である。今後の改善により、より明確な運用が実現されることを期待する。
広大地評価の実務
税理士・名古屋経済大学大学院非常勤講師 浅野 洋
Ⅰ はじめに
財産評価基本通達には運用する際の解釈に困難を伴い、適用が可能かどうかの判断に迷う規定が散見される。これは同通達が上級庁から下級庁への行政処分であり、財産の時価評価を規定した相続税法第22条を補完する存在として法的拘束力を持たず、評価対象の財産が置かれる種々の状況下にあっても課税の公平を確保するべく考慮している結果でもあろう。しかし実務に当たっては、同通達が事実上財産評価の唯一の拠り所であるため、統一的な基準がある方が課税の公平にかなう場合もあると思われる。
財産評価基本通達24-4に規定されている広大地の評価は、その難解な通達の一例である。平成16年6月4日付で運用の改善を主眼とした改正が行われたが、改正後の現在でさえ広大地の評価にあたりこの通達を適用できるのか否かの判断に迷うケースが多い。本編では改正後の評価通達24-4に規定する適用要件を精研しその問題点を概観しつつ、実例を通じて課税庁がどのような広大地をこの通達の適用対象と想定しているのか具体的に推測したい。
Ⅱ 広大地評価の概要について
(1)評価方法
平成16年6月改正後の評価通達24-4によると、広大地は以下のように評価する。
広大地補正率について、同通達改正以前には広大地を鑑定評価額により評価する事例が多かったため、国税庁は鑑定評価事例を統計学的に分析し、評価上の簡便性・安全性に考慮して算出している。なおこの広大地補正率以外の各種補正率(評価通達15(奥行価格補正)から24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)までの各補正率)は適用しないが、評価通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)だけは個別事情の斟酌の必要性から重複適用可としている。
① 路線価地域に所在する場合
広大地の価額=正面路線価×広大地補正率(※)×地積
(※)広大地補正率=0.6-0.05×地積/1000m2
② 倍率地域に所在する場合
その広大地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1m2当たりの価額を評価通達14に定める路線価として、上記①に準じて計算した金額
(2)適用対象となる広大地
評価通達24-4の適用対象となる広大地の要件は、同通達及び平成16年6月29日付資産評価企画官情報第2号「『財産評価基本通達の一部改正について』通達のあらましについて(情報)」(以下「あらまし」という)に規定されている。下記にその内容を要約した。
① その地域の標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であること。
② 都市計画法に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められること。つまり戸建住宅分譲用地として開発され、道路等の潰れ地が生じる土地であること。
③ 普通住宅地区等に所在する土地で各自治体が定める開発許可を要する面積以上のもの。ただし、近隣の状況から、その地域の標準的な土地の規模が上記の面積以上である場合は、その面積を超えるもの。
(なお、ミニ開発分譲が多い地域についてはその面積基準を満たさなくても広大地に該当する場合がある。)
④ 次に掲げる土地に該当しないこと。
● 大規模工場用地
● 既に開発を了しているマンション・ビル等の敷地
● マンションの敷地として使用するのが最も有効と考えられる土地
● 現に宅地として有効利用している構築物等の敷地(大規模店舗・ファミリーレストラン等)
● 原則として容積率300%以上の地域に所在する土地
<参考>面積基準
○市街化区域及び市街化区域と市街化調整区域の区分が行われていない区域(以下、「非線引き都市計画区域」という)については、都市計画法施行令第19条第1項及び第2項に定める次に掲げる面積以上のもの
市街化区域 三大都市圏・・・・・・・・・・ 500m2
それ以外の地域・・・・・・ 1,000m2
非線引き都市計画区域・・・・・・・・・・・・・・ 3,000m2
○用途地域が定められている非線引き都市計画区域は、市街化区域に準じた面積
(3)解説としての「留意事項」の内容
平成16年6月の評価通達24-4の改正によって、広大地は通常の評価額と比較して最大65%の評価減が可能となり大幅に納税者有利であることから、個別事例について同通達に規定する広大地に該当するかどうかの照会が課税庁に多数寄せられた。国税庁は広大地の判定について考え方の統一を図るため、平成17年6月17日付で「広大地の判定に当たり留意すべき事項」(以下「留意事項」という)と題する資産評価企画官情報を発表した。以下、その内容について概説する。
① 著しく広大であるかどうかの判断について
非線引き地域の開発許可基準は3,000m2であるが、このうち用途地域が定められている地域は市街地化が進んでいくと考えられるため、その地域を市街化区域と同等に取り扱うこととし、次頁の面積基準を明示した。
しかし、この開発許可面積基準以上であっても、その面積が地域の標準的な規模である場合は広大地に該当しないとの一文があり、判断基準としては不透明さが残る。
② 現に宅地として有効利用している構築物等の敷地について
例示された大規模店舗等の敷地がその地域の標準的使用といえる場合は「宅地として有効利用」されており、広大地に該当しないことが解説されている。「有効利用」の解釈として、賃料の多寡など利回りに関する判断基準が採用されていないことに留意する必要がある。
③ 公共公益的施設用地の負担について
施設の内容は、合理的に戸建住宅の分譲を行った場合に開発地域内に開設される道路であると明言されている。また、セットバックや開発に伴い提供する道路敷き部分はここでいう公共公益的施設用地に含まれていない。
④ マンション適地の判定について
国税庁はマンション適地の判定について、「あらまし」から引き続き「周辺地域の標準的使用の状況を参考とする」との見解を貫いており、専門家の意見等から判断して明らかにマンション適地と認められる土地を除き、戸建住宅用地として広大地の評価を適用するとしている。
また、容積率300%以上の地域に所在する土地については、戸建住宅よりもマンションとして利用する方が最有効利用であるため原則として広大地に該当せず、容積率が300%以上でありながら戸建住宅が多い地域についても、道路幅員など容積率を活用できない事情がない限りは広大地には該当しない旨を明らかにしている。
⑤ 市街化調整区域内の土地に係る広大地の評価について
条例指定区域内の宅地(都市計画法で開発が許可された区域内の土地)で、都道府県の条例により戸建分譲を目的とした開発ができる場合は広大地に該当するとの見解が示されている。
Ⅲ この通達の問題点
(1)広大地の判断の困難性
広大地に該当するか否かの判断基準のうち「あらまし」において漠然としていた適用要件のうち、上記Ⅱ(3)③の公共公益的施設用地など「留意事項」で明確にされた部分もある。
しかし客観性を欠く判断基準は「留意事項」の発表後も健在である。例えばⅡ(3)①の著しく広大であるかどうかの判断には『開発許可面積基準以上であっても、その面積が地域の標準的な規模である場合は、当然のことながら、広大地に該当しない。』との文言があるが、実務では、「開発許可面積以上ではあるが周辺宅地より顕著に広大とも言い切れない」程度の地積の土地に直面することは決して珍しくない。そのような土地が広大地に該当するか判定しようとしても、「地域の標準的な規模」とはどの面積をもって標準的とするのか、その標準規模の目安の計算方法も示されていないため釈然としない。同様の曖昧さは②現に宅地として有効利用している構築物等の敷地④マンション適地の判定においても見受けられる。専門家の意見を斟酌して判断するよう指導されてはいるが、専門家とは具体的にどのような知識を有する者なのか明らかでなく、納税者の立場からはその見解が課税当局に必ず是認されるという確信も抱きにくい。
結果として適用の是非の判断が感覚的にならざるを得ず、判断に個人差が生じてしまうため、明確な判断基準とは言い難い。
(2)マンション適地の考え方
「マンション適地を除く」との要件の趣旨は、既にマンションが林立する地域では一筆の広大地をマンション用地として分割せず売却できる可能性があるため、通常の評価額の方が時価をより反映しており、広大地評価を適用する必要はないというものである。戸建住宅の多い地域に存する広大地は分譲開発することが自然であるから、その開発に伴い生じる潰れ地等の負担を考慮した評価を認めている。この考え方は時価を評価額に反映するという意味で妥当なものといえる。
しかし、ある広大地について周辺地域にマンションは建設されているが、マンションより戸建住宅としての需要のほうがやや高い場合など、その広大地のマンション用地としての売価と戸建住宅用地として売価が大差ないケースも考えられる。このような場合、マンション適地と判断されてこの通達の適用除外となれば、売価と評価額に著しい乖離が生じる可能性もある。この通達の趣旨は敷地が広大であるが故に生ずる減価を評価額に反映させようというものであるから、面積が広大であることが減価要因にならないと真に認められる場合にのみこの通達の適用除外とすべきである。従ってマンション適地の判断は周辺状況のみでなく、売却した場合の用途別売価の観点からも慎重に行われることが望ましい。
(3)他の補正率の除外
広大地補正率は土地の個別要因の事情補正を加味されており、不整形、奥行長大などの特殊な形状、市街地農地等である広大地を評価する場合の宅地造成費等やセットバック部分の斟酌については改めて考慮しないが、都市計画道路予定地となる区域内においては、個々の地域に応じた土地の利用制限を受けることになるため、個別に斟酌するのが相当との考え方から、広大地補正率により評価した後で評価通達24-7(都市計画道路予定地の区域内にある宅地の評価)を適用することになっている。
しかし、例えば評価対象地が宅地の場合と市街化農地の場合とでは宅地造成費相当額だけ評価額が異なるのが当然であり、不整形地か否かに関わらず同額で評価されるのも不合理である。また、個別に斟酌すべきとの理由で評価通達24-7のみが重複適用を認められているが、不整形地など他の補正率要因も個別事情ではないのだろうか。土地に関わる複雑な要因を極力評価額に反映する従来の評価通達のスタンスから見れば、この広大地の評価方法は簡便であるがゆえに本来の目的から離れる結果を招きかねない。
現行の広大地補正率を評価通達15(奥行価格補正)から24-6(セットバックを必要とする宅地の評価)までの各補正率に相当する部分を減殺した補正率に改定し、その上で各補正率の重複適用を認めるなどの措置を検討すべきである。
Ⅳ 実例に見る判断の実態
上記の現状に鑑みると、評価通達24-4、「あらまし」及び「留意事項」の記載事項から広大地に該当するかどうかを客観的に判断するのは非常に困難だが、広大地に該当するか否かで評価額が大きく異なる場合もあるため、実務では所轄税務署に事前照会を行うことが多いであろう。特に「著しく広大」及び「マンション適地」の判断については個別に税務署と見解の一致を見ておくことが不可欠である。
そこで、実際に照会を行った広大地の状況とそれに対する課税当局の返答をまとめ、この通達の運用状況を概観する。
ケース1
(1)土地の状況
●地方都市に所在
●市街化区域内の普通住宅地区所在・路線価方式で評価
●建ぺい率60%・容積率200%
●地積1,300m2・間口35m・奥行40m・一方の路線にのみ面する
<概略図>
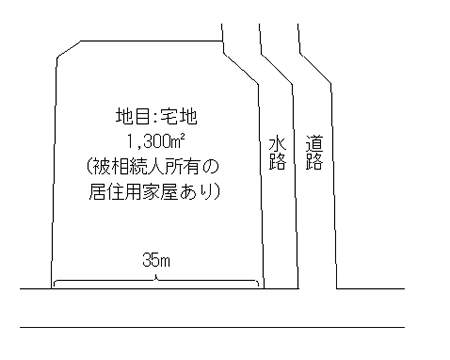
(2)周辺地域の状況
この土地は市中心部の東方約1.5kmに所在し、一般住宅の中に農地が混在する環境である。市中心部には官公庁の他一般企業も存在し、商業地にも近接している。市の人口は過去一貫して微増傾向であるが、周辺にマンションは少なく、現在建築工事中のものが多数あるとも言えない。
近隣の地価公示ポイントにおける平成17年国土交通省地価公示の「周辺の土地の利用現況」には「一般住宅を中心にアパート等が混在する住宅地域」と記載されている。古くからの農家住宅が多く、この土地と同等もしくはやや小さめの地積の住宅が中心的である。この土地を含む1ブロックの概要図は次のとおりである。
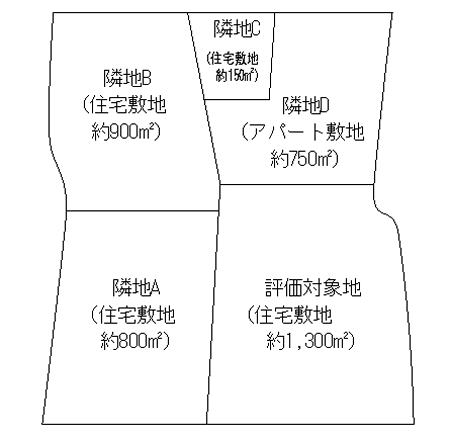
(3)国税局の見解
国税局からこの土地について以下の理由により、広大地に該当しないとの見解を受けた。
① 現に有効利用されている構築物等の敷地の該当性
評価土地上に居住用の家屋があることから、この土地が「現に有効利用されている構築物等の敷地」に該当するか否かが問題にされた。有効利用とはこの地域の標準的な使用がなされていることである。この場合の標準的使用状況は住宅であると考えられるが、「あらまし」で例示された大規模店舗、ファミリーレストラン等と居住用の住宅とを同一に考えることが適正と言い切れない面もあり、この問題に関しては回答を保留する。
② 著しく広大であるかどうかの判定
評価対象土地(1,300m2)は周辺宅地の標準的な地積(700~1,000m2)に比して広大であることは認められる。しかし、この地域の標準的規模と考えられる隣地Aや隣地Bと比較すると、評価対象地が必ずしも「著しく」広大であるとは断じがたい。
③ 開発行為を行う場合の道路負担の必要性について
開発行為を行う場合に市の許可が必要な面積ではあるが、評価対象地の東側に水路(巾約1.5m)を挟んで道路が存在し、戸建住宅として分譲時にこの道路も利用することを考慮すれば、開発に伴い潰れ地(道路)の負担はほとんど生じないと考えられる。
(4)判定に関する問題点
上記の判断から推察すると、「周辺の標準的な宅地の地積」の判断基準が明示されていないものの、標準的な地積より2、3割増し程度であれば「著しく広大」であるとは認められないようである。また、潰れ地の有無についても仮定の開発計画に基づく推測であり、条件の相違、例えば開発分譲する戸建住宅の規模によって必要となる潰れ地の規模も違うはずである。この実例の場合、評価対象地に130坪程度の戸建住宅を3戸分譲するのであれば潰れ地は不必要かもしれないが、仮に65坪の住宅を6戸分譲することを想定すれば道路は最少でも一本必要で、潰れ地が生じることも考えられる。このように判定結果に影響を及ぼす前提条件の設定が課税当局に委ねられたうえで広大地の判断がなされるのは、納税者の権利に配慮するという観点からはやや疑問である。
ケース2
(1)土地の状況
●中規模都市に所在
●市街化区域内の普通住宅地区所在・路線価方式で評価
●建ぺい率60%・容積率200%
●地積1,850m2(2筆の合計。A:1,700m2 B:150m2)・三方の路線に面する
<概略図>(右記参照)
(2)周辺地域の状況
この土地は、市中心部の南西約7kmに所在し、農業地帯の中に一般住宅が混在する地域である。住宅地図・公図を見る限りでは周辺の標準的な宅地の規模は300m2前後と思われる。上記A地の地目は宅地、B地の地目は畑であるが、実際の利用状況は図のようにA地・B地ともそれぞれ宅地部分と畑部分に分かれている。周辺にマンションはなく、現在建築工事中のものも見当たらない。
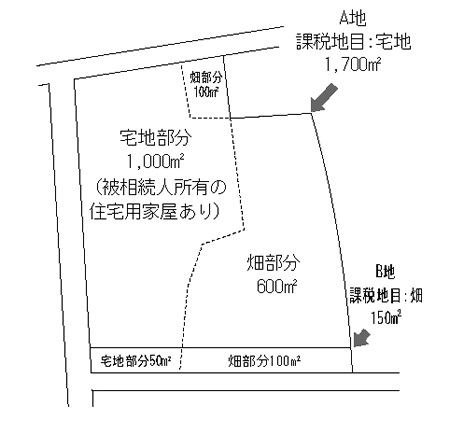
(3)国税局の見解
国税局からこの土地について以下の理由により、広大地に該当しないとの見解を受けた。
① 評価単位について
広大地の判定の際は、通常の土地評価時と同様にまず現況の地目別に区分し(評価通達7)、地目ごとに広大地の判定を行うこととする。従って宅地部分の1,000m2+50m2=1,050m2を判定単位とすることになる。
② 著しく広大であるかどうかの判定
標準的な宅地の規模は300m2前後と考えられるため、宅地部分の1,050m2は著しく広大であると認められる。
③ 開発行為を行う場合の道路負担の必要性について
開発行為を行う場合に市の許可が必要な面積ではあるが、評価対象地は三方に道路が接しており、周辺の標準的宅地と同規模の戸建住宅を分譲することを想定すると、開発に伴い潰れ地(道路)の負担は全く生じないと考えられる。
(4)判定に関する問題点
上記の土地を戸建住宅として開発する場合、宅地部分と畑部分の形状や地積を考慮すれば、両者を一括して開発申請することが十分考えられるが、課税当局は地目の区分を優先し、地目の異なるごとに別個の開発計画があるかのように判定している。開発許可面積を面積基準として採用している以上、実際に申請されるであろう開発計画を基準に「著しく広大」及び「潰れ地の有無」を判定するのでなければ実情に合わず、広大地としての使用可能性を加味した評価はできないのではないか。
また、宅地部分のみで判定するとしても、周辺の標準的宅地と同規模の戸建住宅の開発を想定するのは必ずしも合理的ではない。なぜなら、その「同規模の戸建住宅」が現在の社会情勢や地域に応じた需要を反映しているとは限らず、実際に開発申請する場合に提示される開発計画と内容が異なることがありうるからである。ケース1についても言えることだが、「あらまし」に規定されている「開発行為を行うとした場合」という要件を厳格化し、どのような開発行為かを明文化すべきである。現状では納税者は「実現可能性が最も高い地積の戸建住宅」を想定し、課税庁は「周辺の標準的な地積の戸建住宅」を前提としている傾向が見受けられる。前述した財産評価基本通達の趣旨に立ち返れば、前者を採用するのが自然であろうし、周辺の標準的な地積に依るのであればそれを明文化すべきであろう。
Ⅴ 最後に
Ⅳの実例を見る限り、要件に適合しない可能性が多少なりともある場合は広大地に該当しないと判断されるようである。特に「開発計画の内容」と「標準的な宅地の規模」の捉え方によって適否いずれにも解釈できるケースでは、納税者の意思どおり広大地と認定されるのは困難と思われる。
評価通達24-4(広大地の評価)は、広大地に該当するかどうかの判定基準の曖昧さをはじめ、解決すべき多くの問題を残している。明確な判断基準を設けるとかえって個別事由を斟酌できず、本来広大地であるものにこの通達が適用できなくなることを危惧する向きもあろう。しかし、そもそも評価通達は、租税の公平を実現するため相続税法22条に規定する時価の意義について統一的基準を示すものであるとの前提に立てば、このように適用要件が漠然とした通達の存在は評価制度の整合性を欠き、租税の公平を阻害する結果に繋がりかねない。広大地の判定に画一的な基準を設ければ、評価の実務負担は増大するであろうが、適用要件が明確であればこそ評価制度の普及を促進することにもなり、改善の余地は十分にあると思われる。前述の「地域の標準的な規模の面積」を例に取れば、一般の土地等の評価倍率表のように地域を区分し、その各地域について「標準的な宅地の地積」が明示されてもよい。
個々の事情を十分勘案して広大地の判定をすべきとの姿勢を維持しつつ、課税の公平も達成できる制度により近づくことも可能と考えるが、その取り組みがし尽くされていない感があるのが現状である。今後の改善により、より明確な運用が実現されることを期待する。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























