解説記事2005年10月10日 【会計関連解説】 企業会計基準公開草案第8号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第11号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」について(2005年10月10日号・№133)
実 務 解 説
企業会計基準公開草案第8号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第11号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」について
企業会計基準委員会 研究員 高津知之
Ⅰ はじめに
平成17年7月26日に公布された会社法(平成17年法律第86号)によれば、株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)を作成しなければならないとされている(会社法第435条第2項参照)。
この具体的な内容として、「会社法制の現代化に関する要綱」では、株式会社は、財務諸表として貸借対照表、損益計算書に加えて、「株主持分変動計算書」を作成し、株主に送付しなければならないことが示されている。
企業会計基準委員会(ASBJ)では、この「株主持分変動計算書」をどのような方法・様式で作成・開示するかについて、会社法対応専門委員会において審議を行った。この審議の結果、株主の持分の変動を示す計算書として、連結株主資本等変動計算書及び株主資本等変動計算書(以下「連結株主資本等変動計算書等」という。)を作成・開示することとし、企業会計基準公開草案第8号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準(案)」(以下「会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針公開草案第11号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「適用指針」という。)を取り纏めた。本公開草案は、平成17年8月26日に開催された第87回企業会計基準委員会での承認を経て、平成17年8月30日に公表されている。ASBJは平成17年10月11日まで本公開草案に関するコメントを募集している(脚注1)。
ここでは、本公開草案の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、また、本公開草案は最終的なものではなく今後、変更される可能性があるが、本稿では、最終的なものと同様の表現をしている場合があることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ 連結株主資本等変動計算書等の会計基準の概要
1 作成目的
連結株主資本等変動計算書等は、連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部の一会計期間の変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成するものである(会計基準第1項参照)。この連結株主資本等変動計算書等が開示されることによって、財務諸表の利用者は会社が行った増資や剰余金の配当、自己株式の取得などの資本取引などを一覧できるようになり、財務諸表の利便性は更に高まるものと思われる。
ASBJは、会計基準の公表に先立ち、平成17年8月10日に企業会計基準公開草案第6号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(案)」(以下「企業会計基準公開草案第6号」という。)を公表しているが、この公開草案において、資産と負債の差額を「純資産の部」として表示するものとされ、内訳として株主資本と株主資本以外の各項目に区分することが示されている。
企業会計基準公開草案第6号によれば、株主資本は資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分され、株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等(その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益等)、新株予約権及び少数株主持分とすることとされている。また、取得した自己株式についても、企業会計基準公開草案第7号「自己株式及び法定準備金の減少等に関する会計基準(案)」において、純資産の部の株主資本から控除することとされている。
2 表示方法
会計基準では、連結株主資本等変動計算書等は純資産の部のうち、株主資本の各項目の変動事由を利害関係者に報告することを重視し、株主資本以外の項目の取扱いとの間に差異を設けている。
(1)株主資本の各項目
連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとにその金額を表示する(会計基準第7項参照)。
・連結株主資本等変動計算書等における重要性の取扱い
会計基準では、個別財務諸表として作成される株主資本等変動計算書について重要性の取扱いを定めていない。しかし連結株主資本等変動計算書については、株主資本の各項目の変動事由ごとの金額に重要性が乏しいものについて、それらを一括して表示することができるとされている(適用指針第9項参照)。
・税務上の積立金
税務上の積立金(例えば、圧縮積立金)は、利益処分案の株主総会決議によって積立及び取崩がなされているが、会社法の下では、法人税等の税額算定を含む決算手続として会計処理することになる。具体的には、当期末の貸借対照表に税務上の積立金の積立及び取崩を反映させるとともに、株主資本等変動計算書に税務上の積立金の積立額と取崩額を記載し(注記により開示する場合を含む。)、株主総会又は取締役会で当該財務諸表を承認することになる。
このため、利益処分を経て翌期の貸借対照表に反映されている税務上の積立金の積立及び取崩は、今後は決算手続として当期末の貸借対照表に反映されることとなるため注意が必要である。
(2)株主資本以外の各項目
連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は純額で記載する。ただし、当期変動額については、主な変動事由ごとにその金額を表示(注記による開示を含む。)することができる(会計基準第9項参照)。
このような株主資本の各項目と株主資本以外の各項目との表示方法の取扱いの差異は、連結株主資本等変動計算書等に記載すべき項目の範囲を国際的な会計基準の動向をふまえ純資産の部の全ての項目としつつも、株主資本をより重視する考え方(脚注2)
及び事務負担への配慮等に基づくものである。したがって、株主資本項目以外の各項目の表示方法について、変動事由ごとにその金額を示すことを妨げる趣旨ではなく、事業年度または中間会計期間ごとに上記のいずれかの方法の選択が認められる。
株主資本以外の項目の表示方法は、変動事由又は金額の重要性などを勘案し、事業年度ごとに、企業の判断により選択することができるとされ、また、当該表示は項目ごとに選択することが認められている(適用指針第10項参照)。このため、変動事由ごとの記載については特に継続性は要求されておらず、作成する会社は株主資本以外の項目の変動事由又は金額の重要性等にしたがって、作成する都度、開示する項目及び変動事由を判断することができる。
3 作成にあたっての留意事項
本適用指針に示されている設例の解説を用いて、連結株主資本等変動計算書等を作成するにあたって問題となると思われるポイントを紹介する。
(1)設例1 株主資本等変動計算書-株主資本の増減のみがある場合
設例1では、個別財務諸表の純資産の部のうち、株主資本の増減のみがあるケースを示している。
現行の商法施行規則では、株式会社は附属明細書として「資本金、資本剰余金並びに利益準備金及び任意積立金の増減」を記載しなければならない(商法施行規則第107条参照)とされ、その他利益剰余金(現行の当期未処分利益)の変動事由及び変動額は、利益処分案(利益処分計算書)及び損益計算書の末尾(当期純利益より下)で開示されている。
設例1のようなケースでは、これらの作成・開示にあたって考慮していたすべての事項に加え、自己株式の期中の変動を把握し、これらの事項を株主資本等変動計算書の様式に従って開示するという手続になると考えられる。自己株式の期中の変動についても、他の株主資本項目同様、会計帳簿の記載に基づいて把握可能と考えられることから、これまでの作業に比べて、事務負担が著しく増えることなく株主資本等変動計算書を作成することができると考えられる。
(2)設例2 株主資本等変動計算書-株主資本以外の増減を含む場合
設例2では、個別財務諸表の純資産の部のうち、株主資本以外の増減を含むケースで、株主資本以外の項目の変動事由につき、変動事由ごとに開示した事例を示している。
個別財務諸表の純資産の部に含まれる株主資本以外の項目の変動事由の開示は、現行の商法施行規則や財務諸表等規則では要求されておらず、これらの作成・開示にあたっては、会社は新たに必要な情報を把握する必要があると考えられる。
なお、会計基準では、株主資本以外の各項目についての変動額は純額で記載することを原則としている。設例2以降の株主資本以外の各項目についての記載は、会社の判断により、当期変動額を変動事由ごとに表示する方法を採用したケースである点には留意して頂きたい。
・その他有価証券評価差額金の増減について
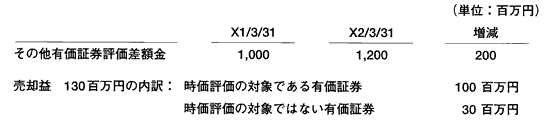
(その他有価証券の売却による損益への振替え)
時価評価の対象であるその他有価証券が売却された場合、関連する売却益(設例2では100百万円)は、損益計算書を通じて税効果が考慮された後、当期純利益の一部として株主資本であるその他利益剰余金を増加させる。しかし、この売却が行われたことによって、計上された有価証券売却益に相当する金額のその他有価証券評価差額金が減少(売却損であれば増加)することになる。
その他有価証券評価差額金も純資産の部を構成することから、この有価証券の売却によって会社の純資産の金額は変動せず、売却益(税効果考慮後)に相当する金額の評価差額金がその他利益剰余金に振り替えられたものとみることができる。こうした振替えはその他有価証券評価差額金の変動事由として株主資本等変動計算書に計上される。
設例2では、時価評価の対象となった有価証券の売却益100百万円に税効果を考慮した60百万円を「その他有価証券の売却による損益への振替え」として株主資本等変動計算書に記載している。適用指針によれば、設例2のように、税効果を考慮した金額をもって記載する方法の他、税効果考慮前の金額をもって記載し、税効果相当額を別の変動事由として記載する方法のいずれも認められるとしている(適用指針第13項参照)。また、売却だけではなく、時価評価の対象となるその他有価証券が減損処理された場合にも同様の取扱いとなる点に注意する。
(その他有価証券の期末時価評価)
設例2では、時価評価により純資産の部に計上されたその他有価証券評価差額金の増減について、「純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金」として260百万円計上している。この金額はその他有価証券評価差額金の純増加額200百万円に、上記の「その他有価証券の売却による損益への振替え」による減少60百万円を加算して算出している(この方法については、適用指針第20項を参照のこと。)。
設例2で用いられる方法による「純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金」の金額は、次の合計金額に税効果を考慮した金額に一致することになる。
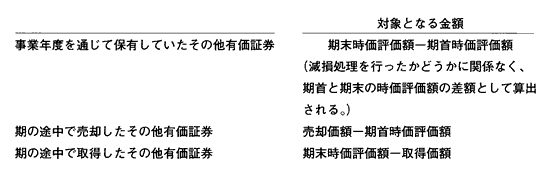
・繰延ヘッジ損益の増減について
A社のX1年3月31日及びX2年3月31日の繰延ヘッジ損益の増減は、次のとおりである
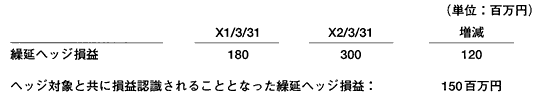
繰延ヘッジ損益について変動事由ごとに金額を記載する場合も、その他有価証券評価差額金の考え方と同様である。つまり、ヘッジ対象の損益認識又はヘッジ会計が終了したデリバティブ取引の繰延ヘッジ損益は評価・換算差額等の変動事由として計上される。設例2では「ヘッジ対象の損益認識による損益への振替え」に計上された90百万円(上記150百万円に税効果を考慮した金額)が該当する。
純資産の部に直接計上された繰延ヘッジ損益の増減についても、その他有価証券評価差額金同様、繰延ヘッジ損益の純増加額120百万円に上記の損益への振替え額90百万円を加算して算出している。
・新株予約権の増減について
A社のX1年3月31日及びX2年3月31日の新株予約権の増減は、次のとおりである
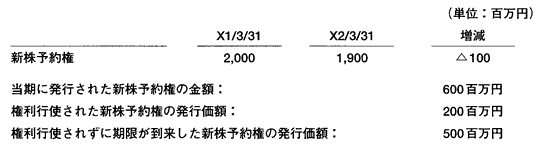
適用指針では、新株予約権の変動事由として、新株予約権の発行、新株予約権の取得、新株予約権の失効、自己新株予約権の消却、自己新株予約権の処分を例示している(適用指針第12項参照)。
新株予約権の発行者は新株予約権について、権利が行使された場合には資本金及び資本準備金へ振り替え、権利が行使されずに権利行使期限が到来したときは利益として処理するものとされている(脚注3)。
この取扱いに従い、権利行使された新株予約権の発行価額200百万円は資本金に振り替えられ、株主資本等変動計算書上、「新株予約権の行使に伴う新株の発行」に記載されている。また、権利行使されずに権利行使期限が到来した新株予約権の発行価額500百万円は損益計算書に特別利益として計上され、新株予約権の減少が株主資本等変動計算書上、「新株予約権の失効」として記載されている。
以上の結果、設例2のケースについて株主資本等変動計算書を適用指針に示されている「純資産の各項目を縦に並べる様式」にて示すと次のとおりである。
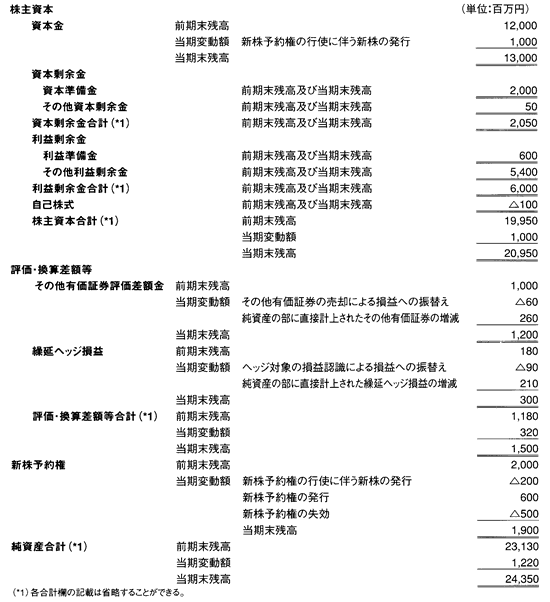
なお、その他有価証券評価差額金につき、当期変動額を純額で記載した場合には、次の記載となる。

(3)設例3 連結株主資本等変動計算書-株主資本以外の増減を含む場合
設例3以降は、連結株主資本等変動計算書を作成する設例となっている。連結財務諸表を作成するための連結修正仕訳及び連結精算表が合わせて示されており、会社の連結修正仕訳がどのように連結株主資本等変動計算書に反映されるのかを参照できる設例となっている。
設例3は基本となるケースとして、親会社の子会社に対する持株比率に変動がなく、在外子会社も存在しないケースを示している。
・その他有価証券評価差額金の増減について
設例3で特に問題となる事項は、その他有価証券評価差額金の増減の記載に関する部分であると思われる。
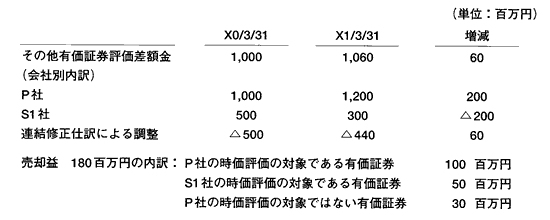
(その他有価証券の売却による損益への振替え)
時価評価の対象である有価証券が売却された場合、その他有価証券評価差額金の変動が連結株主資本等変動計算書に計上される点は、設例2に示されたとおりである。
ここで、連結株主資本等変動計算書では、親会社だけでなく、基本的には連結子会社の計上した有価証券売却損益についても同様の取扱いをする必要がある。
P社が計上した時価評価対象のその他有価証券の売却益100百万円に税効果を考慮した60百万円を「その他有価証券の売却による損益への振替え」として記載する点は、設例2と同様である。連結財務諸表の場合には、これと合わせて連結子会社の計上した時価評価対象のその他有価証券の売却損益のうち、親会社の持分相当額を合算して記載する。
この際に、売却したその他有価証券について、親会社の支配獲得時に投資と資本の相殺消去の対象となった評価差額がある場合には注意が必要である。
設例3では、前提条件として、売却した有価証券の支配獲得時の帳簿価額と時価は一致しているとの前提があるため、上記の点には考慮する必要が無い設例となっている。
このため、連結子会社の計上した時価評価対象の有価証券売却損益のうち、S1社の計上した売却益に税効果を考慮した金額(30百万円)に持分比率70%を乗じた21百万円がP社に帰属するその他有価証券評価差額金の変動として、残りの9百万円は少数株主持分の変動としてそれぞれ扱われる。説例3では、親会社と連結子会社は共に個別財務諸表上、売却益を計上しているため、その他有価証券評価差額金の変動としては売却益に相当する金額の減少として扱われることとなり、連結株主資本等変動計算書上にその他有価証券評価差額金及び少数株主持分の減少として記載されている。
(その他有価証券の期末時価評価)
設例3においても、設例2と同様に連結上のその他有価証券評価差額金の純増加額60百万円に、「その他有価証券の売却による損益への振替え」による減少81百万円を加算して、純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増加額141百万円を算出している。
(4)設例4 連結株主資本等変動計算書-持分比率の変動がある場合
設例4では親会社の連結子会社に対する持分比率が変動した場合の取扱いとして、持株比率が減少したケースが示されている。
・持分比率が減少した場合について
子会社の時価発行増資等に伴い親会社の親会社の持分比率が減少した場合には、子会社株式の一部売却に準じて処理し、個別財務諸表上のみなし売却簿価と連結貸借対照表の売却簿価との間に生じた差額は、原則として持分変動損益等の科目をもって連結損益計算書に計上することとされている(脚注4)。ただし、特定の場合においては利益剰余金に直接加減することも認められている(脚注5)。
この点につき、設例4では、持分変動損益を原則どおり、連結損益計算書に計上する方法によっている。
(少数株主持分の増加)
子会社の増資等に伴い親会社の親会社の持分比率が減少した場合には、少数株主持分が増加し、この変動は、連結株主資本等変動計算書上、「連結子会社の増資による持分の変動」による少数株主の増加として記載される。
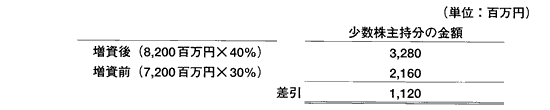
また、減少した持分割合に対応するS1社のその他有価証券評価差額金は少数株主持分に含まれることとなり、この場合にはその他有価証券評価差額金を直接加減する。支配獲得後のS1社のその他有価証券評価差額金の変動累計額のうち、減少した持分割合に対応する金額が少数株主持分として計上されることとなる。
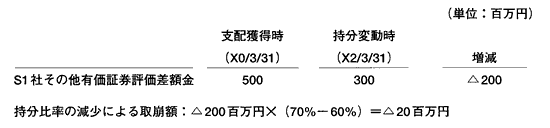
この結果、その他有価証券評価差額金の変動を含む少数株主持分について、連結修正仕訳を示すと、以下の仕訳となる。
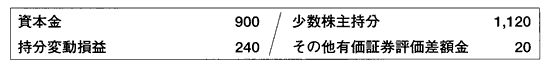
この連結修正仕訳の少数株主持分とその他有価証券評価差額金の変動が連結株主資本等変動計算書に記載されている。
(5)連結株主資本等変動計算書-在外子会社を連結子会社とする場合
設例5では、在外子会社を連結子会社とするケースを示し、為替換算調整勘定の取扱いが示されている。
・為替換算調整勘定の変動について
P社は前期末日であるX0年3月31日にS2社を設立している。そのため、設立出資日と期末日の為替レートは同一であり、X0年3月期の連結貸借対照表に為替換算調整勘定は計上されていない。
しかし、当期末日であるX1年3月31日の為替レートと出資時の為替レートが異なっているため、この為替変動が為替換算調整勘定としてX1年3月期の連結貸借対照表に計上される。
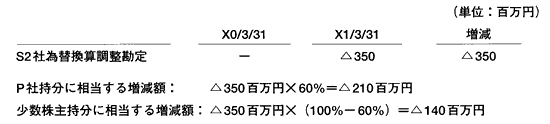
為替換算調整勘定の少数株主への振替仕訳は以下の仕訳となる。
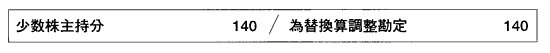
S2社為替換算調整勘定の減少額350百万円のうち、P社持分に相当する減少額210百万円は評価・換算差額等に計上されている為替換算調整勘定の変動事由として、少数株主持分に相当する減少額140百万円は少数株主持分の変動事由として、それぞれ連結株主資本等変動計算書に記載されている。
4 注記事項について
株主資本等変動計算書には、発行済株式の種類及び総数に関する事項、自己株式の種類及び株式数に関する事項、配当に関する事項を注記し、また、連結株主資本等変動計算書には、自己株式の種類及び株式数に関する事項を別途注記するものとされている(会計基準第10項参照)。
発行済株式に関する事項及び配当に関する事項は個別財務諸表と連結財務諸表との間に違いがないのに対し、自己株式に関する事項については連結子会社及び持分法適用会社が親会社株式(投資会社の株式)を保有する場合、両者の間に自己株式数に差異が生じる可能性があることから、自己株式に関する事項のみを連結株主資本等変動計算書に改めて注記することとしたものである。
Ⅲ 適用時期
会計基準及び適用指針は、会社法施行期日以後終了する事業年度から適用されることが予定されている。また、連結株主資本等変動計算書等の表示区分が、企業会計基準公開草案第6号に定める純資産の表示区分を前提としているため、会社法により連結株主資本等変動計算書等の作成が要請されることとなる場合、企業会計基準公開草案第6号の実施時期も影響を受けることとなる。
中間連結株主資本等変動計算書等については、会社法施行期日以後終了する事業年度の翌中間会計期間から適用するものとし、企業会計基準公開草案第6号の実施時期を考慮して、平成18年4月1日以後開始する中間会計期間から早期適用が認められる。
1 ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/j_ed/equity/equity.html)を参照。
2 財務報告における情報開示の中で、財務諸表利用者にとって特に重要な情報は投資の成果を表す利益の情報であり、当該情報の主要な利用者であり受益者である株主に対して、当期純利益とこれを生み出す株主資本との関係を示すことが重要であるとの考えである。
3 実務対応報告第1号「新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」Q1を参照のこと。
4 連結財務諸表原則第四の五の3及び会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」第49項を参照。
5 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」第49項ただし書きを参照。
企業会計基準公開草案第8号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第11号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」について
企業会計基準委員会 研究員 高津知之
Ⅰ はじめに
平成17年7月26日に公布された会社法(平成17年法律第86号)によれば、株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。)を作成しなければならないとされている(会社法第435条第2項参照)。
この具体的な内容として、「会社法制の現代化に関する要綱」では、株式会社は、財務諸表として貸借対照表、損益計算書に加えて、「株主持分変動計算書」を作成し、株主に送付しなければならないことが示されている。
企業会計基準委員会(ASBJ)では、この「株主持分変動計算書」をどのような方法・様式で作成・開示するかについて、会社法対応専門委員会において審議を行った。この審議の結果、株主の持分の変動を示す計算書として、連結株主資本等変動計算書及び株主資本等変動計算書(以下「連結株主資本等変動計算書等」という。)を作成・開示することとし、企業会計基準公開草案第8号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準(案)」(以下「会計基準」という。)及び企業会計基準適用指針公開草案第11号「連結株主資本等変動計算書等に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「適用指針」という。)を取り纏めた。本公開草案は、平成17年8月26日に開催された第87回企業会計基準委員会での承認を経て、平成17年8月30日に公表されている。ASBJは平成17年10月11日まで本公開草案に関するコメントを募集している(脚注1)。
ここでは、本公開草案の概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、また、本公開草案は最終的なものではなく今後、変更される可能性があるが、本稿では、最終的なものと同様の表現をしている場合があることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ 連結株主資本等変動計算書等の会計基準の概要
1 作成目的
連結株主資本等変動計算書等は、連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部の一会計期間の変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成するものである(会計基準第1項参照)。この連結株主資本等変動計算書等が開示されることによって、財務諸表の利用者は会社が行った増資や剰余金の配当、自己株式の取得などの資本取引などを一覧できるようになり、財務諸表の利便性は更に高まるものと思われる。
ASBJは、会計基準の公表に先立ち、平成17年8月10日に企業会計基準公開草案第6号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(案)」(以下「企業会計基準公開草案第6号」という。)を公表しているが、この公開草案において、資産と負債の差額を「純資産の部」として表示するものとされ、内訳として株主資本と株主資本以外の各項目に区分することが示されている。
企業会計基準公開草案第6号によれば、株主資本は資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分され、株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等(その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益等)、新株予約権及び少数株主持分とすることとされている。また、取得した自己株式についても、企業会計基準公開草案第7号「自己株式及び法定準備金の減少等に関する会計基準(案)」において、純資産の部の株主資本から控除することとされている。
2 表示方法
会計基準では、連結株主資本等変動計算書等は純資産の部のうち、株主資本の各項目の変動事由を利害関係者に報告することを重視し、株主資本以外の項目の取扱いとの間に差異を設けている。
(1)株主資本の各項目
連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとにその金額を表示する(会計基準第7項参照)。
・連結株主資本等変動計算書等における重要性の取扱い
会計基準では、個別財務諸表として作成される株主資本等変動計算書について重要性の取扱いを定めていない。しかし連結株主資本等変動計算書については、株主資本の各項目の変動事由ごとの金額に重要性が乏しいものについて、それらを一括して表示することができるとされている(適用指針第9項参照)。
・税務上の積立金
税務上の積立金(例えば、圧縮積立金)は、利益処分案の株主総会決議によって積立及び取崩がなされているが、会社法の下では、法人税等の税額算定を含む決算手続として会計処理することになる。具体的には、当期末の貸借対照表に税務上の積立金の積立及び取崩を反映させるとともに、株主資本等変動計算書に税務上の積立金の積立額と取崩額を記載し(注記により開示する場合を含む。)、株主総会又は取締役会で当該財務諸表を承認することになる。
このため、利益処分を経て翌期の貸借対照表に反映されている税務上の積立金の積立及び取崩は、今後は決算手続として当期末の貸借対照表に反映されることとなるため注意が必要である。
(2)株主資本以外の各項目
連結貸借対照表及び貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は純額で記載する。ただし、当期変動額については、主な変動事由ごとにその金額を表示(注記による開示を含む。)することができる(会計基準第9項参照)。
このような株主資本の各項目と株主資本以外の各項目との表示方法の取扱いの差異は、連結株主資本等変動計算書等に記載すべき項目の範囲を国際的な会計基準の動向をふまえ純資産の部の全ての項目としつつも、株主資本をより重視する考え方(脚注2)
及び事務負担への配慮等に基づくものである。したがって、株主資本項目以外の各項目の表示方法について、変動事由ごとにその金額を示すことを妨げる趣旨ではなく、事業年度または中間会計期間ごとに上記のいずれかの方法の選択が認められる。
株主資本以外の項目の表示方法は、変動事由又は金額の重要性などを勘案し、事業年度ごとに、企業の判断により選択することができるとされ、また、当該表示は項目ごとに選択することが認められている(適用指針第10項参照)。このため、変動事由ごとの記載については特に継続性は要求されておらず、作成する会社は株主資本以外の項目の変動事由又は金額の重要性等にしたがって、作成する都度、開示する項目及び変動事由を判断することができる。
3 作成にあたっての留意事項
本適用指針に示されている設例の解説を用いて、連結株主資本等変動計算書等を作成するにあたって問題となると思われるポイントを紹介する。
(1)設例1 株主資本等変動計算書-株主資本の増減のみがある場合
設例1では、個別財務諸表の純資産の部のうち、株主資本の増減のみがあるケースを示している。
現行の商法施行規則では、株式会社は附属明細書として「資本金、資本剰余金並びに利益準備金及び任意積立金の増減」を記載しなければならない(商法施行規則第107条参照)とされ、その他利益剰余金(現行の当期未処分利益)の変動事由及び変動額は、利益処分案(利益処分計算書)及び損益計算書の末尾(当期純利益より下)で開示されている。
設例1のようなケースでは、これらの作成・開示にあたって考慮していたすべての事項に加え、自己株式の期中の変動を把握し、これらの事項を株主資本等変動計算書の様式に従って開示するという手続になると考えられる。自己株式の期中の変動についても、他の株主資本項目同様、会計帳簿の記載に基づいて把握可能と考えられることから、これまでの作業に比べて、事務負担が著しく増えることなく株主資本等変動計算書を作成することができると考えられる。
(2)設例2 株主資本等変動計算書-株主資本以外の増減を含む場合
設例2では、個別財務諸表の純資産の部のうち、株主資本以外の増減を含むケースで、株主資本以外の項目の変動事由につき、変動事由ごとに開示した事例を示している。
個別財務諸表の純資産の部に含まれる株主資本以外の項目の変動事由の開示は、現行の商法施行規則や財務諸表等規則では要求されておらず、これらの作成・開示にあたっては、会社は新たに必要な情報を把握する必要があると考えられる。
なお、会計基準では、株主資本以外の各項目についての変動額は純額で記載することを原則としている。設例2以降の株主資本以外の各項目についての記載は、会社の判断により、当期変動額を変動事由ごとに表示する方法を採用したケースである点には留意して頂きたい。
・その他有価証券評価差額金の増減について
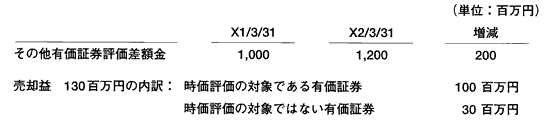
(その他有価証券の売却による損益への振替え)
時価評価の対象であるその他有価証券が売却された場合、関連する売却益(設例2では100百万円)は、損益計算書を通じて税効果が考慮された後、当期純利益の一部として株主資本であるその他利益剰余金を増加させる。しかし、この売却が行われたことによって、計上された有価証券売却益に相当する金額のその他有価証券評価差額金が減少(売却損であれば増加)することになる。
その他有価証券評価差額金も純資産の部を構成することから、この有価証券の売却によって会社の純資産の金額は変動せず、売却益(税効果考慮後)に相当する金額の評価差額金がその他利益剰余金に振り替えられたものとみることができる。こうした振替えはその他有価証券評価差額金の変動事由として株主資本等変動計算書に計上される。
設例2では、時価評価の対象となった有価証券の売却益100百万円に税効果を考慮した60百万円を「その他有価証券の売却による損益への振替え」として株主資本等変動計算書に記載している。適用指針によれば、設例2のように、税効果を考慮した金額をもって記載する方法の他、税効果考慮前の金額をもって記載し、税効果相当額を別の変動事由として記載する方法のいずれも認められるとしている(適用指針第13項参照)。また、売却だけではなく、時価評価の対象となるその他有価証券が減損処理された場合にも同様の取扱いとなる点に注意する。
(その他有価証券の期末時価評価)
設例2では、時価評価により純資産の部に計上されたその他有価証券評価差額金の増減について、「純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金」として260百万円計上している。この金額はその他有価証券評価差額金の純増加額200百万円に、上記の「その他有価証券の売却による損益への振替え」による減少60百万円を加算して算出している(この方法については、適用指針第20項を参照のこと。)。
設例2で用いられる方法による「純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金」の金額は、次の合計金額に税効果を考慮した金額に一致することになる。
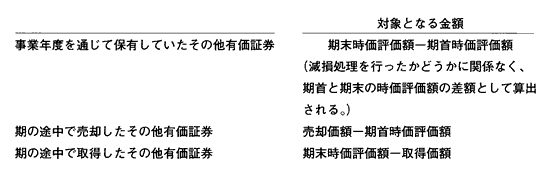
・繰延ヘッジ損益の増減について
A社のX1年3月31日及びX2年3月31日の繰延ヘッジ損益の増減は、次のとおりである
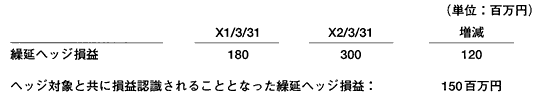
繰延ヘッジ損益について変動事由ごとに金額を記載する場合も、その他有価証券評価差額金の考え方と同様である。つまり、ヘッジ対象の損益認識又はヘッジ会計が終了したデリバティブ取引の繰延ヘッジ損益は評価・換算差額等の変動事由として計上される。設例2では「ヘッジ対象の損益認識による損益への振替え」に計上された90百万円(上記150百万円に税効果を考慮した金額)が該当する。
純資産の部に直接計上された繰延ヘッジ損益の増減についても、その他有価証券評価差額金同様、繰延ヘッジ損益の純増加額120百万円に上記の損益への振替え額90百万円を加算して算出している。
・新株予約権の増減について
A社のX1年3月31日及びX2年3月31日の新株予約権の増減は、次のとおりである
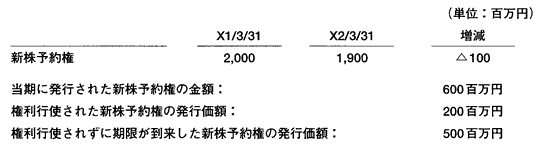
適用指針では、新株予約権の変動事由として、新株予約権の発行、新株予約権の取得、新株予約権の失効、自己新株予約権の消却、自己新株予約権の処分を例示している(適用指針第12項参照)。
新株予約権の発行者は新株予約権について、権利が行使された場合には資本金及び資本準備金へ振り替え、権利が行使されずに権利行使期限が到来したときは利益として処理するものとされている(脚注3)。
この取扱いに従い、権利行使された新株予約権の発行価額200百万円は資本金に振り替えられ、株主資本等変動計算書上、「新株予約権の行使に伴う新株の発行」に記載されている。また、権利行使されずに権利行使期限が到来した新株予約権の発行価額500百万円は損益計算書に特別利益として計上され、新株予約権の減少が株主資本等変動計算書上、「新株予約権の失効」として記載されている。
以上の結果、設例2のケースについて株主資本等変動計算書を適用指針に示されている「純資産の各項目を縦に並べる様式」にて示すと次のとおりである。
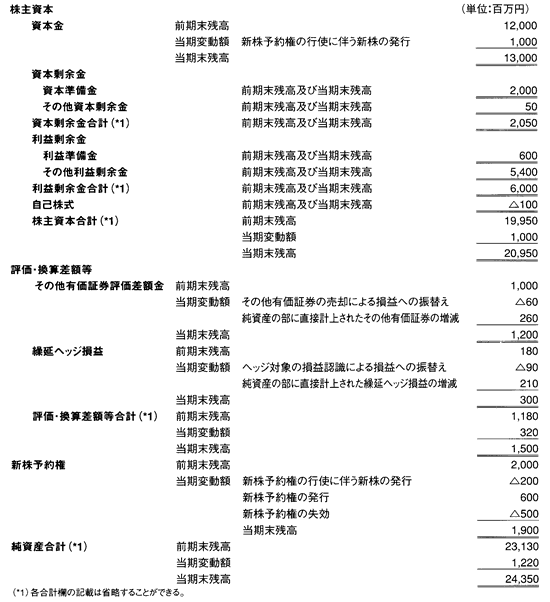
なお、その他有価証券評価差額金につき、当期変動額を純額で記載した場合には、次の記載となる。

(3)設例3 連結株主資本等変動計算書-株主資本以外の増減を含む場合
設例3以降は、連結株主資本等変動計算書を作成する設例となっている。連結財務諸表を作成するための連結修正仕訳及び連結精算表が合わせて示されており、会社の連結修正仕訳がどのように連結株主資本等変動計算書に反映されるのかを参照できる設例となっている。
設例3は基本となるケースとして、親会社の子会社に対する持株比率に変動がなく、在外子会社も存在しないケースを示している。
・その他有価証券評価差額金の増減について
設例3で特に問題となる事項は、その他有価証券評価差額金の増減の記載に関する部分であると思われる。
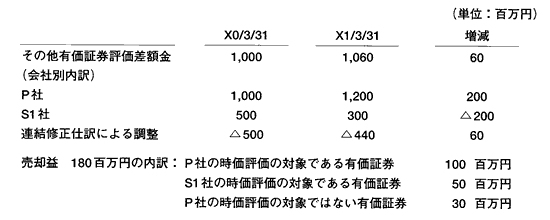
(その他有価証券の売却による損益への振替え)
時価評価の対象である有価証券が売却された場合、その他有価証券評価差額金の変動が連結株主資本等変動計算書に計上される点は、設例2に示されたとおりである。
ここで、連結株主資本等変動計算書では、親会社だけでなく、基本的には連結子会社の計上した有価証券売却損益についても同様の取扱いをする必要がある。
P社が計上した時価評価対象のその他有価証券の売却益100百万円に税効果を考慮した60百万円を「その他有価証券の売却による損益への振替え」として記載する点は、設例2と同様である。連結財務諸表の場合には、これと合わせて連結子会社の計上した時価評価対象のその他有価証券の売却損益のうち、親会社の持分相当額を合算して記載する。
この際に、売却したその他有価証券について、親会社の支配獲得時に投資と資本の相殺消去の対象となった評価差額がある場合には注意が必要である。
設例3では、前提条件として、売却した有価証券の支配獲得時の帳簿価額と時価は一致しているとの前提があるため、上記の点には考慮する必要が無い設例となっている。
このため、連結子会社の計上した時価評価対象の有価証券売却損益のうち、S1社の計上した売却益に税効果を考慮した金額(30百万円)に持分比率70%を乗じた21百万円がP社に帰属するその他有価証券評価差額金の変動として、残りの9百万円は少数株主持分の変動としてそれぞれ扱われる。説例3では、親会社と連結子会社は共に個別財務諸表上、売却益を計上しているため、その他有価証券評価差額金の変動としては売却益に相当する金額の減少として扱われることとなり、連結株主資本等変動計算書上にその他有価証券評価差額金及び少数株主持分の減少として記載されている。
(その他有価証券の期末時価評価)
設例3においても、設例2と同様に連結上のその他有価証券評価差額金の純増加額60百万円に、「その他有価証券の売却による損益への振替え」による減少81百万円を加算して、純資産の部に直接計上されたその他有価証券評価差額金の増加額141百万円を算出している。
(4)設例4 連結株主資本等変動計算書-持分比率の変動がある場合
設例4では親会社の連結子会社に対する持分比率が変動した場合の取扱いとして、持株比率が減少したケースが示されている。
・持分比率が減少した場合について
子会社の時価発行増資等に伴い親会社の親会社の持分比率が減少した場合には、子会社株式の一部売却に準じて処理し、個別財務諸表上のみなし売却簿価と連結貸借対照表の売却簿価との間に生じた差額は、原則として持分変動損益等の科目をもって連結損益計算書に計上することとされている(脚注4)。ただし、特定の場合においては利益剰余金に直接加減することも認められている(脚注5)。
この点につき、設例4では、持分変動損益を原則どおり、連結損益計算書に計上する方法によっている。
(少数株主持分の増加)
子会社の増資等に伴い親会社の親会社の持分比率が減少した場合には、少数株主持分が増加し、この変動は、連結株主資本等変動計算書上、「連結子会社の増資による持分の変動」による少数株主の増加として記載される。
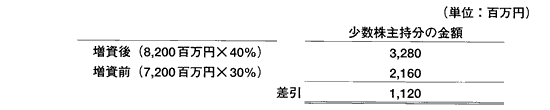
また、減少した持分割合に対応するS1社のその他有価証券評価差額金は少数株主持分に含まれることとなり、この場合にはその他有価証券評価差額金を直接加減する。支配獲得後のS1社のその他有価証券評価差額金の変動累計額のうち、減少した持分割合に対応する金額が少数株主持分として計上されることとなる。
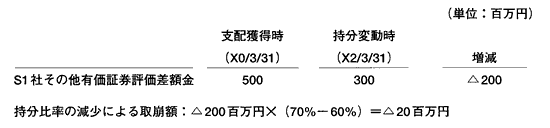
この結果、その他有価証券評価差額金の変動を含む少数株主持分について、連結修正仕訳を示すと、以下の仕訳となる。
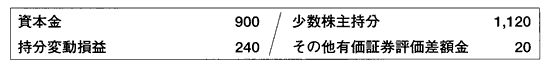
この連結修正仕訳の少数株主持分とその他有価証券評価差額金の変動が連結株主資本等変動計算書に記載されている。
(5)連結株主資本等変動計算書-在外子会社を連結子会社とする場合
設例5では、在外子会社を連結子会社とするケースを示し、為替換算調整勘定の取扱いが示されている。
・為替換算調整勘定の変動について
P社は前期末日であるX0年3月31日にS2社を設立している。そのため、設立出資日と期末日の為替レートは同一であり、X0年3月期の連結貸借対照表に為替換算調整勘定は計上されていない。
しかし、当期末日であるX1年3月31日の為替レートと出資時の為替レートが異なっているため、この為替変動が為替換算調整勘定としてX1年3月期の連結貸借対照表に計上される。
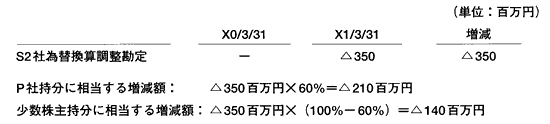
為替換算調整勘定の少数株主への振替仕訳は以下の仕訳となる。
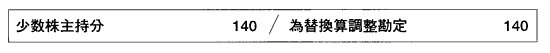
S2社為替換算調整勘定の減少額350百万円のうち、P社持分に相当する減少額210百万円は評価・換算差額等に計上されている為替換算調整勘定の変動事由として、少数株主持分に相当する減少額140百万円は少数株主持分の変動事由として、それぞれ連結株主資本等変動計算書に記載されている。
4 注記事項について
株主資本等変動計算書には、発行済株式の種類及び総数に関する事項、自己株式の種類及び株式数に関する事項、配当に関する事項を注記し、また、連結株主資本等変動計算書には、自己株式の種類及び株式数に関する事項を別途注記するものとされている(会計基準第10項参照)。
発行済株式に関する事項及び配当に関する事項は個別財務諸表と連結財務諸表との間に違いがないのに対し、自己株式に関する事項については連結子会社及び持分法適用会社が親会社株式(投資会社の株式)を保有する場合、両者の間に自己株式数に差異が生じる可能性があることから、自己株式に関する事項のみを連結株主資本等変動計算書に改めて注記することとしたものである。
Ⅲ 適用時期
会計基準及び適用指針は、会社法施行期日以後終了する事業年度から適用されることが予定されている。また、連結株主資本等変動計算書等の表示区分が、企業会計基準公開草案第6号に定める純資産の表示区分を前提としているため、会社法により連結株主資本等変動計算書等の作成が要請されることとなる場合、企業会計基準公開草案第6号の実施時期も影響を受けることとなる。
中間連結株主資本等変動計算書等については、会社法施行期日以後終了する事業年度の翌中間会計期間から適用するものとし、企業会計基準公開草案第6号の実施時期を考慮して、平成18年4月1日以後開始する中間会計期間から早期適用が認められる。
1 ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/j_ed/equity/equity.html)を参照。
2 財務報告における情報開示の中で、財務諸表利用者にとって特に重要な情報は投資の成果を表す利益の情報であり、当該情報の主要な利用者であり受益者である株主に対して、当期純利益とこれを生み出す株主資本との関係を示すことが重要であるとの考えである。
3 実務対応報告第1号「新株予約権及び新株予約権付社債の会計処理に関する実務上の取扱い」Q1を参照のこと。
4 連結財務諸表原則第四の五の3及び会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」第49項を参照。
5 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」第49項ただし書きを参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















