解説記事2005年11月14日 【ニュース特集】 大量保有報告制度の問題点を探る(2005年11月14日号・№138)
ニュース特集
特例制度の報告期限の短縮などが論点に
大量保有報告制度の問題点を探る
金融審議会金融分科会第一部会の公開買付制度等ワーキング・グループが10月28日に開催され、昨今から問題視されている大量保有報告制度について、その見直しに着手した。特例報告制度や5%ルールが論点として挙げられているが、一定の結論には至っておらず、次回(11月14日開催予定)に持ち越されている。また、経済産業省の企業価値研究会においても、大量保有報告制度を含め、買収ルールのあり方について検討する予定だ。今回の特集では、大量保有報告制度の問題点について概観する。
機関投資家等には特例制度
大量保有報告制度は、上場株券等の保有割合が5%を超える保有者に対して、5%を超えることとなった日から原則5営業日以内、以後1%以上の変動があった場合に情報を開示させるもの(いわゆる5%ルール)。市場の公正性、透明性を高め、投資家保護を徹底するため、株券等の大量保有に係る情報を開示させることを目的に、平成2年の証券取引法改正の際に導入された。
原則については、前記のとおりだが、証券会社、銀行、信託銀行、保険会社、投信会社、投資顧問会社等の機関投資家については、特例が認められている。具体的には、「当該基準日の属する月の翌月十五日まで」(※基準日とは「特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう」)に情報を開示すればよいことになっている(下表参照)。
これらの機関投資家等については、日常業務において、反復継続的に株券等の売買を行っており、取引の都度、詳細な情報開示を求めることになると、事務負担が過大になるといった理由により、特例制度が設けられたものだ。しかし、ニッポン放送株式をめぐる件をはじめ、注目を集める昨今の買収事案では、投資家サイドからみると、なかなか
大量保有報告書が提出されず、どの企業が売買したのか分からなかった経緯があり、見直し論が浮上していた。
自民党の企業統治委員会が7月7日にまとめた「公正なM&Aルールに関する提言」においても、公開買付制度や大量保有報告制度の見直しが明記されていた。これを踏まえ、金融庁では、金融審議会の下に公開買付制度等ワーキング・グループを設置し、検討を開始したものだ。
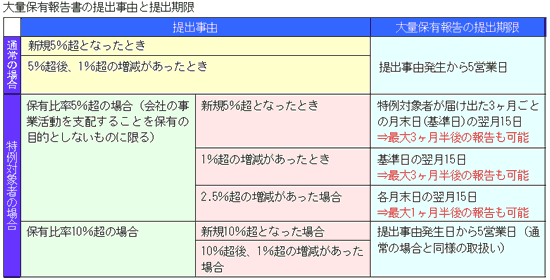
報告期限の短縮などが論点
公開買付制度等ワーキング・グループで検討課題に挙がっている点としては、①特例制度自体の是非、②適用対象範囲、③報告期限などだ。
特に報告期限については、最大で3ヶ月半後の報告も可能となっているため、短縮の余地があるか否かが論点となる。
また、適用対象範囲については、証券会社等に認められている点に関し、特例制度を維持しつつ、特定の業態、保有目的等について適用対象を縮小するか否かが論点となっている。
一方、特例制度以外では、まず、現行の提出義務者としている5%ルールが妥当かどうかが論点となっているほか、共同保有者の範囲、対象有価証券などが論点に挙がっている。対象有価証券については、現行、会社の発行する株券等に限定されているため、投資法人の発行する投資証券(不動産投資信託証券など)については、対象外となっている。しかし、議決権を有する証券を除外することは制度上、整合性がとれないと指摘している。
また、開示内容については、取引所市場内・外別の記載の有無、保有目的については、現行、「純投資」や「政策投資」といった簡略した開示しか求められていないため、より詳細な開示を求めるかどうかが論点となっている。
その他、罰則の実効性の確保なども論点として挙げられている。大量保有報告書については、罰則があるものの、ほとんど適用された事例はない(罰則が適用された事例としては、東天紅のTOBに関するものがある)。このため、運用面を厳格化するかどうかが論点となる。
MEMO
罰則
重要な事項につき虚偽記載のある大量保有報告書・変更報告書を提出した者
⇒3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科
大量保有報告書・変更報告書を提出しない者
⇒3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科
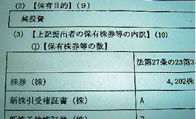 保有目的の詳細な開示を求めるか?
保有目的の詳細な開示を求めるか?
大量保有報告書等は提出日にEDINETで閲覧可能

大量保有報告書等については、EDINETによる提出が任意とされている。このため、従来は、紙で提出されたものについては、インターネット上で閲覧することができないほか、金融庁にある閲覧室の端末においても翌日からしか閲覧することができなかった。
しかし、金融庁では、10月3日から、大量保有報告書等については、紙又はEDINETによる提出にかかわらず、提出された日にインターネットで閲覧することを可能としている。
http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm
特例制度の報告期限の短縮などが論点に
大量保有報告制度の問題点を探る
金融審議会金融分科会第一部会の公開買付制度等ワーキング・グループが10月28日に開催され、昨今から問題視されている大量保有報告制度について、その見直しに着手した。特例報告制度や5%ルールが論点として挙げられているが、一定の結論には至っておらず、次回(11月14日開催予定)に持ち越されている。また、経済産業省の企業価値研究会においても、大量保有報告制度を含め、買収ルールのあり方について検討する予定だ。今回の特集では、大量保有報告制度の問題点について概観する。
機関投資家等には特例制度
大量保有報告制度は、上場株券等の保有割合が5%を超える保有者に対して、5%を超えることとなった日から原則5営業日以内、以後1%以上の変動があった場合に情報を開示させるもの(いわゆる5%ルール)。市場の公正性、透明性を高め、投資家保護を徹底するため、株券等の大量保有に係る情報を開示させることを目的に、平成2年の証券取引法改正の際に導入された。
原則については、前記のとおりだが、証券会社、銀行、信託銀行、保険会社、投信会社、投資顧問会社等の機関投資家については、特例が認められている。具体的には、「当該基準日の属する月の翌月十五日まで」(※基準日とは「特例対象株券等の保有者が内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に届出をした三月ごとの月の末日をいう」)に情報を開示すればよいことになっている(下表参照)。
これらの機関投資家等については、日常業務において、反復継続的に株券等の売買を行っており、取引の都度、詳細な情報開示を求めることになると、事務負担が過大になるといった理由により、特例制度が設けられたものだ。しかし、ニッポン放送株式をめぐる件をはじめ、注目を集める昨今の買収事案では、投資家サイドからみると、なかなか
大量保有報告書が提出されず、どの企業が売買したのか分からなかった経緯があり、見直し論が浮上していた。
自民党の企業統治委員会が7月7日にまとめた「公正なM&Aルールに関する提言」においても、公開買付制度や大量保有報告制度の見直しが明記されていた。これを踏まえ、金融庁では、金融審議会の下に公開買付制度等ワーキング・グループを設置し、検討を開始したものだ。
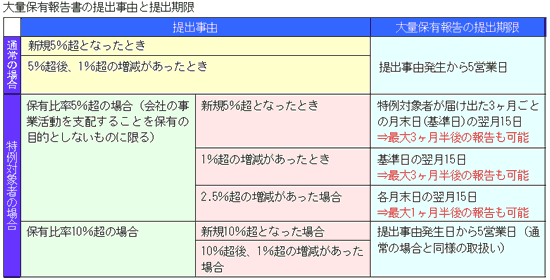
報告期限の短縮などが論点
公開買付制度等ワーキング・グループで検討課題に挙がっている点としては、①特例制度自体の是非、②適用対象範囲、③報告期限などだ。
特に報告期限については、最大で3ヶ月半後の報告も可能となっているため、短縮の余地があるか否かが論点となる。
また、適用対象範囲については、証券会社等に認められている点に関し、特例制度を維持しつつ、特定の業態、保有目的等について適用対象を縮小するか否かが論点となっている。
一方、特例制度以外では、まず、現行の提出義務者としている5%ルールが妥当かどうかが論点となっているほか、共同保有者の範囲、対象有価証券などが論点に挙がっている。対象有価証券については、現行、会社の発行する株券等に限定されているため、投資法人の発行する投資証券(不動産投資信託証券など)については、対象外となっている。しかし、議決権を有する証券を除外することは制度上、整合性がとれないと指摘している。
また、開示内容については、取引所市場内・外別の記載の有無、保有目的については、現行、「純投資」や「政策投資」といった簡略した開示しか求められていないため、より詳細な開示を求めるかどうかが論点となっている。
その他、罰則の実効性の確保なども論点として挙げられている。大量保有報告書については、罰則があるものの、ほとんど適用された事例はない(罰則が適用された事例としては、東天紅のTOBに関するものがある)。このため、運用面を厳格化するかどうかが論点となる。
MEMO
罰則
重要な事項につき虚偽記載のある大量保有報告書・変更報告書を提出した者
⇒3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科
大量保有報告書・変更報告書を提出しない者
⇒3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科
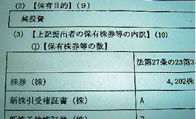 保有目的の詳細な開示を求めるか?
保有目的の詳細な開示を求めるか?大量保有報告書等は提出日にEDINETで閲覧可能

大量保有報告書等については、EDINETによる提出が任意とされている。このため、従来は、紙で提出されたものについては、インターネット上で閲覧することができないほか、金融庁にある閲覧室の端末においても翌日からしか閲覧することができなかった。
しかし、金融庁では、10月3日から、大量保有報告書等については、紙又はEDINETによる提出にかかわらず、提出された日にインターネットで閲覧することを可能としている。
http://info.edinet.go.jp/EdiHtml/main.htm
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























