解説記事2005年11月28日 【会計解説】 『棚卸資産の評価基準に関する論点の整理』の解説(2005年11月28日号・№140)
実 務 解 説
『棚卸資産の評価基準に関する論点の整理』の解説
企業会計基準委員会 専門研究員 江藤栄作
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)では、平成17年10月19日に「棚卸資産の評価基準に関する論点の整理」(以下「本論点整理」という。)を公表し、平成17年12月12日までコメントを募集している(脚注1)。本稿では、本論点整理の概要について解説するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見である。
Ⅱ.本論点整理の目的
ASBJでは、本論点整理に寄せられる意見も参考に、今後、棚卸資産の評価基準に関する会計基準等のとりまとめに向けた検討を続けていく予定である。本論点整理は、今後、棚卸資産の評価基準に関する企業会計基準や企業会計基準適用指針を開発するにあたって、広く意見を求めることを目的としている。なお、本論点整理の対象は、棚卸資産の評価基準に限定されていることから、評価方法(先入先出法、平均法、後入先出法等)に関しては、対象外とされている(脚注2)。
Ⅲ.検討開始の背景と経緯
我が国においては、これまで原価法と低価法が選択適用とされ、原価法を適用している場合でも、帳簿価額より時価が著しく下落したときには、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とする(強制評価減)という会計処理が定められている。そのため、低価法を適用している企業は、東京証券取引所第1部上場企業の2~3割程度である。こうした状況において、原価法と低価法の選択適用を見直すにあたっては、原価法と低価法が選択適用とされていることの意義や低価法の論拠について明らかにしつつ、なぜ今検討しなければならないかについても示す必要があると考えられることから、本論点整理においては、その背景説明が記述されている。
1 テーマ協議会からの提言
検討開始の背景として、第1にテーマ協議会からの提言が挙げられている。これは、レベル2(比較的優先順位の高いグループであるレベル1以外のグループ)の優先度として提言されており、企業の経営者の意思による原価法と低価法の選択適用に対する是非や、国際的な会計基準との調和の観点から行われた提言と捉えられている。
2 新たに整備された会計基準との整合性
近年、「金融商品に係る会計基準」や「固定資産の減損に係る会計基準」の整備により、投資の収益性が低下した場合には帳簿価額を切り下げる会計処理がされるなかにあって、棚卸資産のみ原価法と低価法の選択適用が継続性を条件としながらも企業経営者の判断に任されている状況に関して、そうした新しい会計基準との整合性が取れていないとする意見がある。後述するように本論点整理では、帳簿価額切下げの根拠においても、新たに整備された会計基準と同様に考えていることから、検討開始の背景として他の会計基準との整合性という観点が、重視されていると考えられる。
3 IASBとのコンバージェンス
ASBJは、平成16年9月以降、国際会計基準審議会(IASB)との間で両会計基準のコンバージェンスに向けた作業を進めており、その項目(脚注3)の1つとして棚卸資産の評価基準が採り上げられていることも当該検討開始の背景とされている。
なお、本論点整理は、平成16年9月に公表されている討議資料『財務会計の概念フレームワーク』の一部も素材に議論されたものである。これは、当該検討資料が、ASBJの見解ではなく、外部の研究者を中心としたワーキング・グループの見解であるものの、今後の基準設定の過程でその有用性をテストされ、市場関係者等の意見を受けてさらに整備・改善されれば、いずれはデファクト・スタンダードとしての性格を持つことが期待されているためである。これは、本論点整理の議論の過程において、様々な考え方や国際的な基準のほか、当該討議資料も議論の参考としたことを意味するものであって、当該討議資料に従って検討することを意味するものではないことに留意する必要がある。
Ⅳ.棚卸資産の検討範囲
(1)棚卸資産の範囲
本論点整理では、棚卸資産の評価基準というときの検討の範囲を明確にするために、棚卸資産の範囲について検討している。この結果、「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書 第四 棚卸資産の評価について」(以下「連続意見書」という。)を引用し、販売用不動産及び未成工事支出金とも棚卸資産の範囲に含めている。販売用不動産については、国際会計基準では棚卸資産の範囲に含まれると解されるが、米国基準では棚卸資産を有形の動産に限定し不動産を含めていない。また、未成工事支出金に関しては、国際的な会計基準では、棚卸資産ではなく、発注者への債権として取り扱われている。このように、国際的な会計基準と我が国における棚卸資産の範囲は、細部での相違はあるものの、概ね等しいと考えられることから、範囲に関する検討は行わないこととしている。その上で本論点整理における棚卸資産の範囲は、次に示すように、連続意見書に示す棚卸資産と同じものとして、各論点の検討が行われている。
① 通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
② 販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
③ 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期的に消費されるべき財貨
④ 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
(2)検証対象から除く資産
有価証券業者が通常の営業過程において販売するために保有する有価証券や、市場販売目的及び自社利用ソフトウェアの製作費に関しては、連続意見書の解釈に従えば棚卸資産に含まれるものの、本論点整理の検討対象外としている。これは、それぞれ、「金融商品に係る会計基準」及び「研究開発費等に係る会計基準」において、その会計処理が別途定められているからである。もっとも、受注製作のソフトウェアについては、請負工事の会計処理に準じた処理を行うこととされているため、本論点整理の検討対象に含まれる。
Ⅴ.各論点の解説
1 【論点1】原価法と低価法の選択適用の見直し
(1)現行会計基準における棚卸資産の評価基準の考え方
本論点整理では、まず、国際的な会計基準においては、低価法が原則とされているが、我が国の会計基準においては例外的処理とされている理由について、図表(1)のように触れられている。
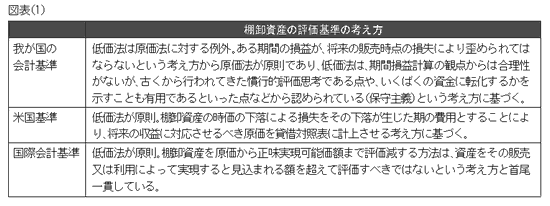
(2)原価法における強制評価減の位置付け
本論点整理では、我が国においては原価法を採用している場合であっても、いわゆる強制評価減の計上が求められていることから、強制評価減は低価法とどのような関係にあるのかに関して検討されている。商法改正(昭和37年)において、資産評価の一般原則としての取得原価主義の新設に伴ない、強制評価減が定められた際、企業会計原則に強制評価減が導入されたという経緯はあったものの、今日では強制評価減を含む原価法は、会計慣行として広く定着しており、会計上も強制評価損の計上は適当と考えられるとされている。
このような強制評価減に対しては、時価が著しく下落していること、その時価の回復可能性が認められないことの2要件を満たしたときに計上が求められることから、本論点整理では、これらの要件の充足は、収益性の低下に基づき帳簿価額を切り下げるかどうかを判断する1つの規準であるという見方が示されている。そのような見方に立つならば、現行の会計基準において、後述するような収益性の低下があったときには帳簿価額を切り下げることが、棚卸資産の会計処理において既に確立されているのではないかと考えられ、その場合には、むしろこの2要件からなる収益性低下の判断規準を見直す必要があるのではないかと換言できるとされている。
そうした見方がある一方で、時価の回復可能性規準に関しては、そもそも時価は将来に関する平均的な予測を反映したものであり、その反騰可能性を合理的に予測することは不可能であるという意見や、強制評価減と低価法の選択適用があるということは、比較可能性を阻害するものであるという指摘が示され、強制評価減に関して否定的な見方も示されている。
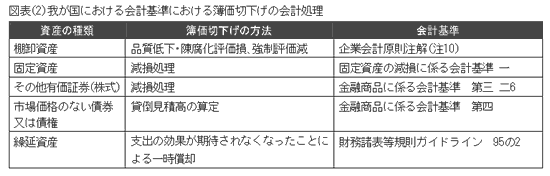
(3)低価法を原価法の例外とする位置付けに対する見方
本論点整理では、低価法を原価法の例外と位置付けている我が国の会計基準の考え方に対して、2つの問題点を指摘している。第1の問題点としては、取得原価基準の本質を将来の収益を生み出すという意味において有用な原価だけを繰り越そうという考え方にあるとすれば、低価法は、収益性が低下した部分について帳簿価額を切り下げるという考え方と両立するのではないかという点である。第2の問題点としては、低価法を原価法の例外とする考え方は、連続意見書が制定された頃には支配的だったかもしれないが、今日のように簿価切下げに関する会計処理が広く受け入れられている状況下では、むしろ一定の条件のもとでの簿価切下げを必要としていると解釈する方が適切であるという点である。
今日の会計基準における簿価切下げの会計処理としては、固定資産の減損処理、品質低下・陳腐化が生じた棚卸資産の評価損、棚卸資産の強制評価減、債権の貸倒見積高の算定、売買目的以外の有価証券の減損処理、支出の効果が期待されなくなったことによる繰延資産の一時的償却などが挙げられる。
(4)収益性の低下と帳簿価額の切下げ
本論点整理では、近年整備されてきた会計基準との整合性を踏まえると、棚卸資産についても、品質低下や陳腐化が生じた場合に限らず、収益性が低下した場合には帳簿価額を切り下げるという考え方を適用することが妥当と考えている。すなわち、棚卸資産の低価法は、当該会計処理に固有の新たな考え方があるということを示すのではなく、現行の固定資産の減損処理やその他有価証券の減損処理の背後にある考え方と同じ理由により、棚卸資産の帳簿価額が切り下げられるのではないかという考え方が示されている。
この際、現在の会計基準において、それぞれの資産の会計処理は、基本的に、投資の性質に対応して定められていると考えられることから、本論点整理では、収益性の低下の有無に関する判断規準も、投資が回収される形態に応じて判断するものと考えられている。例えば、固定資産の場合には、将来キャッシュ・フローの見積りが主観的にならざるを得ないことを考慮し、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回るときには、収益性が低下していると判断され、減損損失を認識することとされている。また、いわゆる持合株式に代表されるその他有価証券の保有の場合には、その保有を通じた取引関係の強化や毎期の配当による資金回収が、主な投資の回収形態であり、そのような関係を終了させる際には株式の売却により投資を回収するものと考えられる。その場合でも、市場価格のある株式の時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、期待した投資額の回収が見込めなくなったものとみることができるような収益性の低下が生じていると判断される。
ここで、棚卸資産の場合には、投資の回収形態が、企業経営者の努力に基づく販売による点に特徴がある。固定資産、その他有価証券及び市場価格のない債券(又は債権)の場合でも、第三者への売却という回収手段は採り得るものの、メインの投資の回収形態ではないと考えられる。このような投資の回収形態の相違に着目してみると、図表(3)のように、販売によってしか投資が回収できない棚卸資産の場合には、評価時点において帳簿価額よりも時価が下落しているときには、期待していた利益はもちろん、投下した資金の一部すら回収できないことから、収益性が低下しているとみることが考えられる。
本論点整理では、昭和37年の商法改正により導入され、現行の会計慣行として広く定着している強制評価減を含む原価法の考え方の背景を考察したうえで、近年整備されてきた会計基準との整合性を踏まえると、収益性が低下した場合には帳簿価額を切り下げるという考え方を棚卸資産についても適用することが妥当ではないかと考えている。このような考え方は、基本的に、原価法ではなく低価法を適用する会計処理と同様の結果をもたらすものと考えられるが、このような評価基準の考え方を整理しつつ、引き続き検討するものとしている。
なお、論点2~7については、収益性が低下した場合に帳簿価額を切り下げるという考え方を採ったことを前提に整理されている。
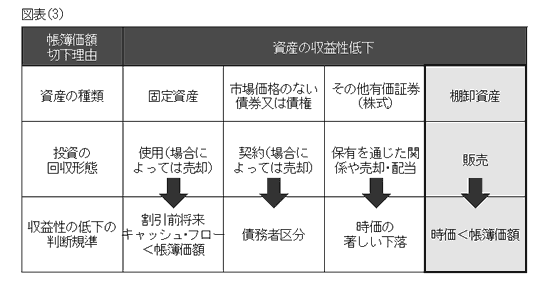
2 【論点2】低価法の適用除外とする場合
反対に、時価が下落していても収益性の低下に結びつかないときには、帳簿価額を時価まで切り下げる必要はないものとされ、本論点整理では、以下の具体例が示されている。
① 販売価格が契約により決定している場合
通常、投資が回収できるよう、帳簿価額以上の販売価格で契約が締結されることを前提とすれば、時価が下落していようとも収益性は低下していないと考えられる。
② 一定の売価決定計算式により利幅が確保されている場合
一定の利幅が得られるよう調達原価に連動する形で販売価格が決定されている場合、時価が下落しても収益性は低下しないと考えられる。
③ 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
我が国の会計基準においては、このような資産は、棚卸資産に含められるが、販売による資金回収を前提としていない以上、収益性の低下の有無に関して判断する必要がないと考えられる。
その他、本論点整理では、建設業における未成工事支出金やその他の請負契約における仕掛品等に関しては、低価法を適用すべきではないという意見が示されている。これは、未成工事支出金等に関しては、本論点整理では棚卸資産としているものの、請負契約に基づく発注者に対する債権の性格を有していることや、未成工事支出金等に損失の発生が見込まれる場合には、工事損失引当金等により損失は既に計上されているということを理由としている。しかし、請負契約に関しては、損失発生見込みが確実と判断される場合に、常に損失に係る引当金を計上するという会計慣行が成立しているわけではないという意見もあるため、本論点整理では、両方の意見が示されているものと思われる。
また、派生論点として、棚卸資産の時価が帳簿価額よりも低下しているものの、例えば固定価格の受取・変動価格の支払による先物売建契約の締結により、価格変動がヘッジされているときの会計処理が示されている。このような場合には、帳簿価額よりも時価が下落した部分に関しては、ヘッジ対象の一部消滅によるヘッジの終了として、繰延処理しているデリバティブ損益を当期の損益とすることが示されている。
3 【論点3】低価法適用時の時価
本論点整理では、低価法適用時の時価として、一般に正味実現可能価額と再調達原価があるとされるが、どの時価を採用すべきかは、低価法の論拠と関連して決まるのか、あるいは無関係に決まるのかが論点とされている。また、正味実現可能価額と再調達原価以外にも採用すべき時価としてどのようなものがあるかという点も論点とされているが、これらについても、引き続き検討するものとされている。
(1)正味実現可能価額
収益性の低下があったときに帳簿価額を切り下げるという本論点整理での考え方に従えば、評価時点における回収可能額を示す時価として、正味実現可能価額が最も適当であり、その考え方は、国際会計基準や連続意見書においても同様であるとされている。これには、収益性の低下した資産からは、資本のコストすら回収できないとみて、その後の会計上の利益がゼロとなるようにする考え方、又は収益性が低下しても投資を中断せずに保有されている資産は、その形態どおり同じ投資が続いているとみて、かつ、短期間の投資であることから割り引かないものとして、将来における販売時の正味実現可能価額とする考え方も含むものと考えられる。
(2)再調達原価
低価法は棚卸資産の原価に残存する有用性を表現する手段であると解釈し、その有用性は、通常の営業過程において、その取得のために支出しなければならない価額であるとする立場からは、再調達原価への簿価切下げが意味を持つという考え方が示されている。また、収益性が低下しているにもかかわらず、投資を中断せずに継続されている資産は、いったん売却し再投資されたというように、実質的に新たな投資に切り替えられたとみる場合には、本来の投資と同様に正常利益が得られる水準である再調達原価まで引き下げることが意味を持つとされている。それ以外に、製造業における原材料の価格のように再調達原価の方が把握しやすいなど実務上の要請の観点から再調達原価が望ましいという見解も挙げられている。
(3)その他の時価
本論点整理では、まず、再調達原価の代替として簡便的に用いられるものとして、最終取得原価や正味実現可能価額から正常利益を控除した金額を利用することに関しても言及されている。また、期末時の時価の把握に際して、実務上、期末月の平均時価が採用される場合があるという意見や、合理的に参照できる時価が存在しない場合には取得原価を時価とみなすという意見も示されている。その他、合理的に参照できる時価が存在しないようなときでも、すでに当該棚卸資産の陳腐化が生じている場合にはゼロ又は備忘価額まで帳簿価額を切り下げる実務があるように、収益性の低下に基づき簿価を切り下げる場合にも、その他の代替的な方法が認められるのではないかという意見が示されている。
4 【論点4】洗替え法と切放し法
本論点整理では、低価法を適用した際に、前期末において計上した低価法評価損を戻し入れるかどうか、すなわち洗替え法を採用するか切放し法を採用するかについて、簿価切下げの論拠との関係及び採用する時価との関係に依存するかどうかという観点から整理しているものの、その他の観点も含め、引き続き検討するものとされている。
(1)簿価切下げの論拠との関係
収益性の低下を論拠として簿価を切り下げる場合でも、棚卸資産における収益性の低下の判断においては、損失発生の可能性の高さを要件としていないことから、事後的に時価が回復した際に評価損を戻し入れることも否定できないとされている。その場合、同じ収益性の低下に基づく簿価切下げである固定資産の減損処理やその他有価証券の減損損失が切放し法とされている理由に関しては、それらは損失発生の可能性を要件としているためとされている。
(2)採用する時価との関係
時価との関係では、正味実現可能価額としたときには、収益性が回復した際に評価損を戻し入れないとまで言い切れないとされている。国際会計基準においては、時価が回復した場合には、帳簿価額まで過去の評価損を戻し入れることとされている。
再調達原価としたときには、再投資の仮定に拠っているとすれば、戻入れは行われないとされている。米国基準においては、このような考え方により、切放し法とされている。
5 【論点5】低価法の適用単位(グルーピングの可否)
棚卸資産における投資の成果の確定は、通常、個別品目ごとに販売された時点で確定されることから、低価法の適用単位も個別品目ごとであるのが原則であると考えられる。しかしながら、複数の棚卸資産が補完的な関係にあるような場合において、いずれか一方の販売だけでは正常な水準を超えるような収益を見込めないようなときには、グルーピングによる低価法の適用に対して積極的な意義付けができるとしている。また、それ以外のグルーピング、例えば、地域別セグメント、事業別セグメント、材料・仕掛品・製品という棚卸資産の種類ごとに低価法を適用することは、どこまで認められるかという点が問題となる。本論点整理では、低価法の適用単位は、どのような考え方に基づき、どのような場合にグルーピングすることが適当かに関して、引き続き検討することとしている。
6 【論点6】評価方法と低価法の適用
本論点整理では、後入先出法等につき論点の整理を行っているが、前述のように評価方法に関する検討等については、他の機会に委ねられている。
(1)後入先出法と低価法
後入先出法を採用している場合には、法人税法上、切放し方が認められていないことから、仮に切放し法のみとした場合には、企業に何らかの追加的な負担が発生するとされている。
(2)売価還元法と低価法
小売業等で売価還元法を採用している場合には、連続意見書に定める売価還元低価法を採用することが適当であるという意見が示される一方、値札に記載される売価が実勢売価を示しており、かつ原価率が100%以下であるときには、売価による回収見込額は帳簿価額よりも大きいことから、売価還元平均原価法を採用していても問題は生じないという反対の意見も示されている。この点に関しては、引き続き検討することとしている。
7【論点7】損益計算書における低価法評価損の計上区分
企業会計原則注解(注10)において、低価法評価損の損益計算書における計上区分は、品質低下・陳腐化評価損や強制評価減の計上区分と異なっている。現行の会計基準においては、期間損益計算の観点から低価法が位置付けられているわけではなく、当期の収益とは対応関係がないものと考えられていることによる。
本論点整理では、収益性の低下に基づき低価法評価損を計上する場合には、低価法評価損を営業外費用として処理することを積極的に支持する根拠を見出しにくいとしている。
低価法を採用する場合には、強制評価減は、低価法評価損に含まれると想定しているため、簿価切下げ額を強制評価減として営業外費用又は特別損失に計上することは不要になるものと考えている。また、低価法評価損と品質低下・陳腐化評価損は、その原因は異なるとしつつも、実務上区分が難しいため損益計算書における計上区分を同じにすべきという意見があるとされている。
8【論点8】金融投資と考えられる棚卸資産の時価評価
金融投資として保有する非金融資産に関して、現行の会計基準では、流動資産の評価に関する規定から、原価法か低価法の選択しか認められないと解されているが、今後、時価評価し、評価差額を当期の損益とすることが検討することとされている。これは棚卸資産として取り扱われている現物商品の中には、流動性が高く時価を容易に算定できる市場の存在を前提に、当該市場での価格の変動に基づいて利益を獲得するために、同一現物商品について反復的な購入と売却が行われているものがあるためである。そのような現物商品は、金融資産ではないものの、売買目的有価証券と同様に金融投資としての側面が強いため、時価評価し、評価差額を当期の損益とすることが考えられる。これらの関係は、図表(4)のように整理される。
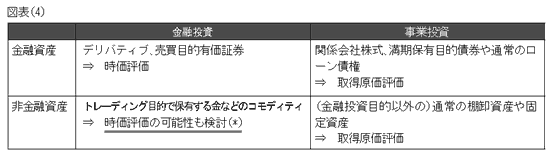
Ⅵ.おわりに
本論点整理に寄せられる意見を踏まえASBJでは、棚卸資産の評価基準に関する企業会計基準や同適用指針の開発を以下のスケジュールで行うことを予定している。
・平成18年前半 企業会計基準(案)及び同適用指針(案)の公開草案を公表
・平成18年内 企業会計基準及び同適用指針を公表
1 ASBJのHP(http://www.asb.or.jp/summary_issue/lcm/lcm.html)を参照のこと。
2 本論点整理の注3では、「国際会計基準(IAS第2号)において、棚卸資産の評価方法として後入先出法は認められていない。なお、後入先出法を含む棚卸資産の評価方法に関する検討は、本論点整理の対象とはされておらず、他の機会に委ねられている。」とされている。
3 IASBとのコンバージェンスに向けた共同プロジェクトにおける第1フェーズ検討5項目は、①棚卸資産の評価基準(IAS第2号)、②セグメント情報(IAS第14号)、③関連当事者の開示(IAS第24号)、④在外子会社の会計基準の統一(IAS第27号)、⑤投資不動産(IAS第40号)である。
『棚卸資産の評価基準に関する論点の整理』の解説
企業会計基準委員会 専門研究員 江藤栄作
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)では、平成17年10月19日に「棚卸資産の評価基準に関する論点の整理」(以下「本論点整理」という。)を公表し、平成17年12月12日までコメントを募集している(脚注1)。本稿では、本論点整理の概要について解説するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見である。
Ⅱ.本論点整理の目的
ASBJでは、本論点整理に寄せられる意見も参考に、今後、棚卸資産の評価基準に関する会計基準等のとりまとめに向けた検討を続けていく予定である。本論点整理は、今後、棚卸資産の評価基準に関する企業会計基準や企業会計基準適用指針を開発するにあたって、広く意見を求めることを目的としている。なお、本論点整理の対象は、棚卸資産の評価基準に限定されていることから、評価方法(先入先出法、平均法、後入先出法等)に関しては、対象外とされている(脚注2)。
Ⅲ.検討開始の背景と経緯
我が国においては、これまで原価法と低価法が選択適用とされ、原価法を適用している場合でも、帳簿価額より時価が著しく下落したときには、回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とする(強制評価減)という会計処理が定められている。そのため、低価法を適用している企業は、東京証券取引所第1部上場企業の2~3割程度である。こうした状況において、原価法と低価法の選択適用を見直すにあたっては、原価法と低価法が選択適用とされていることの意義や低価法の論拠について明らかにしつつ、なぜ今検討しなければならないかについても示す必要があると考えられることから、本論点整理においては、その背景説明が記述されている。
1 テーマ協議会からの提言
検討開始の背景として、第1にテーマ協議会からの提言が挙げられている。これは、レベル2(比較的優先順位の高いグループであるレベル1以外のグループ)の優先度として提言されており、企業の経営者の意思による原価法と低価法の選択適用に対する是非や、国際的な会計基準との調和の観点から行われた提言と捉えられている。
2 新たに整備された会計基準との整合性
近年、「金融商品に係る会計基準」や「固定資産の減損に係る会計基準」の整備により、投資の収益性が低下した場合には帳簿価額を切り下げる会計処理がされるなかにあって、棚卸資産のみ原価法と低価法の選択適用が継続性を条件としながらも企業経営者の判断に任されている状況に関して、そうした新しい会計基準との整合性が取れていないとする意見がある。後述するように本論点整理では、帳簿価額切下げの根拠においても、新たに整備された会計基準と同様に考えていることから、検討開始の背景として他の会計基準との整合性という観点が、重視されていると考えられる。
3 IASBとのコンバージェンス
ASBJは、平成16年9月以降、国際会計基準審議会(IASB)との間で両会計基準のコンバージェンスに向けた作業を進めており、その項目(脚注3)の1つとして棚卸資産の評価基準が採り上げられていることも当該検討開始の背景とされている。
なお、本論点整理は、平成16年9月に公表されている討議資料『財務会計の概念フレームワーク』の一部も素材に議論されたものである。これは、当該検討資料が、ASBJの見解ではなく、外部の研究者を中心としたワーキング・グループの見解であるものの、今後の基準設定の過程でその有用性をテストされ、市場関係者等の意見を受けてさらに整備・改善されれば、いずれはデファクト・スタンダードとしての性格を持つことが期待されているためである。これは、本論点整理の議論の過程において、様々な考え方や国際的な基準のほか、当該討議資料も議論の参考としたことを意味するものであって、当該討議資料に従って検討することを意味するものではないことに留意する必要がある。
Ⅳ.棚卸資産の検討範囲
(1)棚卸資産の範囲
本論点整理では、棚卸資産の評価基準というときの検討の範囲を明確にするために、棚卸資産の範囲について検討している。この結果、「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書 第四 棚卸資産の評価について」(以下「連続意見書」という。)を引用し、販売用不動産及び未成工事支出金とも棚卸資産の範囲に含めている。販売用不動産については、国際会計基準では棚卸資産の範囲に含まれると解されるが、米国基準では棚卸資産を有形の動産に限定し不動産を含めていない。また、未成工事支出金に関しては、国際的な会計基準では、棚卸資産ではなく、発注者への債権として取り扱われている。このように、国際的な会計基準と我が国における棚卸資産の範囲は、細部での相違はあるものの、概ね等しいと考えられることから、範囲に関する検討は行わないこととしている。その上で本論点整理における棚卸資産の範囲は、次に示すように、連続意見書に示す棚卸資産と同じものとして、各論点の検討が行われている。
① 通常の営業過程において販売するために保有する財貨又は用役
② 販売を目的として現に製造中の財貨又は用役
③ 販売目的の財貨又は用役を生産するために短期的に消費されるべき財貨
④ 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
(2)検証対象から除く資産
有価証券業者が通常の営業過程において販売するために保有する有価証券や、市場販売目的及び自社利用ソフトウェアの製作費に関しては、連続意見書の解釈に従えば棚卸資産に含まれるものの、本論点整理の検討対象外としている。これは、それぞれ、「金融商品に係る会計基準」及び「研究開発費等に係る会計基準」において、その会計処理が別途定められているからである。もっとも、受注製作のソフトウェアについては、請負工事の会計処理に準じた処理を行うこととされているため、本論点整理の検討対象に含まれる。
Ⅴ.各論点の解説
1 【論点1】原価法と低価法の選択適用の見直し
(1)現行会計基準における棚卸資産の評価基準の考え方
本論点整理では、まず、国際的な会計基準においては、低価法が原則とされているが、我が国の会計基準においては例外的処理とされている理由について、図表(1)のように触れられている。
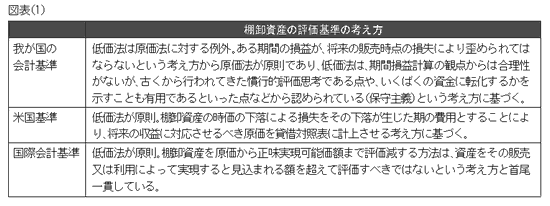
(2)原価法における強制評価減の位置付け
本論点整理では、我が国においては原価法を採用している場合であっても、いわゆる強制評価減の計上が求められていることから、強制評価減は低価法とどのような関係にあるのかに関して検討されている。商法改正(昭和37年)において、資産評価の一般原則としての取得原価主義の新設に伴ない、強制評価減が定められた際、企業会計原則に強制評価減が導入されたという経緯はあったものの、今日では強制評価減を含む原価法は、会計慣行として広く定着しており、会計上も強制評価損の計上は適当と考えられるとされている。
このような強制評価減に対しては、時価が著しく下落していること、その時価の回復可能性が認められないことの2要件を満たしたときに計上が求められることから、本論点整理では、これらの要件の充足は、収益性の低下に基づき帳簿価額を切り下げるかどうかを判断する1つの規準であるという見方が示されている。そのような見方に立つならば、現行の会計基準において、後述するような収益性の低下があったときには帳簿価額を切り下げることが、棚卸資産の会計処理において既に確立されているのではないかと考えられ、その場合には、むしろこの2要件からなる収益性低下の判断規準を見直す必要があるのではないかと換言できるとされている。
そうした見方がある一方で、時価の回復可能性規準に関しては、そもそも時価は将来に関する平均的な予測を反映したものであり、その反騰可能性を合理的に予測することは不可能であるという意見や、強制評価減と低価法の選択適用があるということは、比較可能性を阻害するものであるという指摘が示され、強制評価減に関して否定的な見方も示されている。
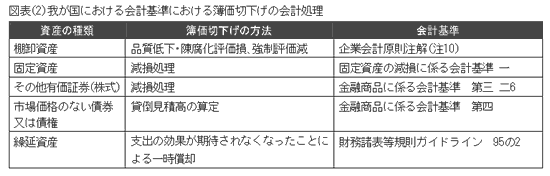
(3)低価法を原価法の例外とする位置付けに対する見方
本論点整理では、低価法を原価法の例外と位置付けている我が国の会計基準の考え方に対して、2つの問題点を指摘している。第1の問題点としては、取得原価基準の本質を将来の収益を生み出すという意味において有用な原価だけを繰り越そうという考え方にあるとすれば、低価法は、収益性が低下した部分について帳簿価額を切り下げるという考え方と両立するのではないかという点である。第2の問題点としては、低価法を原価法の例外とする考え方は、連続意見書が制定された頃には支配的だったかもしれないが、今日のように簿価切下げに関する会計処理が広く受け入れられている状況下では、むしろ一定の条件のもとでの簿価切下げを必要としていると解釈する方が適切であるという点である。
今日の会計基準における簿価切下げの会計処理としては、固定資産の減損処理、品質低下・陳腐化が生じた棚卸資産の評価損、棚卸資産の強制評価減、債権の貸倒見積高の算定、売買目的以外の有価証券の減損処理、支出の効果が期待されなくなったことによる繰延資産の一時的償却などが挙げられる。
(4)収益性の低下と帳簿価額の切下げ
本論点整理では、近年整備されてきた会計基準との整合性を踏まえると、棚卸資産についても、品質低下や陳腐化が生じた場合に限らず、収益性が低下した場合には帳簿価額を切り下げるという考え方を適用することが妥当と考えている。すなわち、棚卸資産の低価法は、当該会計処理に固有の新たな考え方があるということを示すのではなく、現行の固定資産の減損処理やその他有価証券の減損処理の背後にある考え方と同じ理由により、棚卸資産の帳簿価額が切り下げられるのではないかという考え方が示されている。
この際、現在の会計基準において、それぞれの資産の会計処理は、基本的に、投資の性質に対応して定められていると考えられることから、本論点整理では、収益性の低下の有無に関する判断規準も、投資が回収される形態に応じて判断するものと考えられている。例えば、固定資産の場合には、将来キャッシュ・フローの見積りが主観的にならざるを得ないことを考慮し、割引前将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回るときには、収益性が低下していると判断され、減損損失を認識することとされている。また、いわゆる持合株式に代表されるその他有価証券の保有の場合には、その保有を通じた取引関係の強化や毎期の配当による資金回収が、主な投資の回収形態であり、そのような関係を終了させる際には株式の売却により投資を回収するものと考えられる。その場合でも、市場価格のある株式の時価が著しく下落したときは、回復する見込みがあると認められる場合を除き、期待した投資額の回収が見込めなくなったものとみることができるような収益性の低下が生じていると判断される。
ここで、棚卸資産の場合には、投資の回収形態が、企業経営者の努力に基づく販売による点に特徴がある。固定資産、その他有価証券及び市場価格のない債券(又は債権)の場合でも、第三者への売却という回収手段は採り得るものの、メインの投資の回収形態ではないと考えられる。このような投資の回収形態の相違に着目してみると、図表(3)のように、販売によってしか投資が回収できない棚卸資産の場合には、評価時点において帳簿価額よりも時価が下落しているときには、期待していた利益はもちろん、投下した資金の一部すら回収できないことから、収益性が低下しているとみることが考えられる。
本論点整理では、昭和37年の商法改正により導入され、現行の会計慣行として広く定着している強制評価減を含む原価法の考え方の背景を考察したうえで、近年整備されてきた会計基準との整合性を踏まえると、収益性が低下した場合には帳簿価額を切り下げるという考え方を棚卸資産についても適用することが妥当ではないかと考えている。このような考え方は、基本的に、原価法ではなく低価法を適用する会計処理と同様の結果をもたらすものと考えられるが、このような評価基準の考え方を整理しつつ、引き続き検討するものとしている。
なお、論点2~7については、収益性が低下した場合に帳簿価額を切り下げるという考え方を採ったことを前提に整理されている。
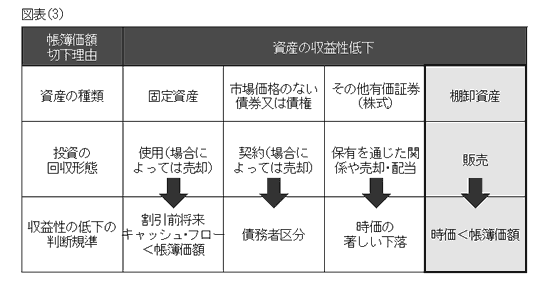
2 【論点2】低価法の適用除外とする場合
反対に、時価が下落していても収益性の低下に結びつかないときには、帳簿価額を時価まで切り下げる必要はないものとされ、本論点整理では、以下の具体例が示されている。
① 販売価格が契約により決定している場合
通常、投資が回収できるよう、帳簿価額以上の販売価格で契約が締結されることを前提とすれば、時価が下落していようとも収益性は低下していないと考えられる。
② 一定の売価決定計算式により利幅が確保されている場合
一定の利幅が得られるよう調達原価に連動する形で販売価格が決定されている場合、時価が下落しても収益性は低下しないと考えられる。
③ 販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるべき財貨
我が国の会計基準においては、このような資産は、棚卸資産に含められるが、販売による資金回収を前提としていない以上、収益性の低下の有無に関して判断する必要がないと考えられる。
その他、本論点整理では、建設業における未成工事支出金やその他の請負契約における仕掛品等に関しては、低価法を適用すべきではないという意見が示されている。これは、未成工事支出金等に関しては、本論点整理では棚卸資産としているものの、請負契約に基づく発注者に対する債権の性格を有していることや、未成工事支出金等に損失の発生が見込まれる場合には、工事損失引当金等により損失は既に計上されているということを理由としている。しかし、請負契約に関しては、損失発生見込みが確実と判断される場合に、常に損失に係る引当金を計上するという会計慣行が成立しているわけではないという意見もあるため、本論点整理では、両方の意見が示されているものと思われる。
また、派生論点として、棚卸資産の時価が帳簿価額よりも低下しているものの、例えば固定価格の受取・変動価格の支払による先物売建契約の締結により、価格変動がヘッジされているときの会計処理が示されている。このような場合には、帳簿価額よりも時価が下落した部分に関しては、ヘッジ対象の一部消滅によるヘッジの終了として、繰延処理しているデリバティブ損益を当期の損益とすることが示されている。
3 【論点3】低価法適用時の時価
本論点整理では、低価法適用時の時価として、一般に正味実現可能価額と再調達原価があるとされるが、どの時価を採用すべきかは、低価法の論拠と関連して決まるのか、あるいは無関係に決まるのかが論点とされている。また、正味実現可能価額と再調達原価以外にも採用すべき時価としてどのようなものがあるかという点も論点とされているが、これらについても、引き続き検討するものとされている。
(1)正味実現可能価額
収益性の低下があったときに帳簿価額を切り下げるという本論点整理での考え方に従えば、評価時点における回収可能額を示す時価として、正味実現可能価額が最も適当であり、その考え方は、国際会計基準や連続意見書においても同様であるとされている。これには、収益性の低下した資産からは、資本のコストすら回収できないとみて、その後の会計上の利益がゼロとなるようにする考え方、又は収益性が低下しても投資を中断せずに保有されている資産は、その形態どおり同じ投資が続いているとみて、かつ、短期間の投資であることから割り引かないものとして、将来における販売時の正味実現可能価額とする考え方も含むものと考えられる。
(2)再調達原価
低価法は棚卸資産の原価に残存する有用性を表現する手段であると解釈し、その有用性は、通常の営業過程において、その取得のために支出しなければならない価額であるとする立場からは、再調達原価への簿価切下げが意味を持つという考え方が示されている。また、収益性が低下しているにもかかわらず、投資を中断せずに継続されている資産は、いったん売却し再投資されたというように、実質的に新たな投資に切り替えられたとみる場合には、本来の投資と同様に正常利益が得られる水準である再調達原価まで引き下げることが意味を持つとされている。それ以外に、製造業における原材料の価格のように再調達原価の方が把握しやすいなど実務上の要請の観点から再調達原価が望ましいという見解も挙げられている。
(3)その他の時価
本論点整理では、まず、再調達原価の代替として簡便的に用いられるものとして、最終取得原価や正味実現可能価額から正常利益を控除した金額を利用することに関しても言及されている。また、期末時の時価の把握に際して、実務上、期末月の平均時価が採用される場合があるという意見や、合理的に参照できる時価が存在しない場合には取得原価を時価とみなすという意見も示されている。その他、合理的に参照できる時価が存在しないようなときでも、すでに当該棚卸資産の陳腐化が生じている場合にはゼロ又は備忘価額まで帳簿価額を切り下げる実務があるように、収益性の低下に基づき簿価を切り下げる場合にも、その他の代替的な方法が認められるのではないかという意見が示されている。
4 【論点4】洗替え法と切放し法
本論点整理では、低価法を適用した際に、前期末において計上した低価法評価損を戻し入れるかどうか、すなわち洗替え法を採用するか切放し法を採用するかについて、簿価切下げの論拠との関係及び採用する時価との関係に依存するかどうかという観点から整理しているものの、その他の観点も含め、引き続き検討するものとされている。
(1)簿価切下げの論拠との関係
収益性の低下を論拠として簿価を切り下げる場合でも、棚卸資産における収益性の低下の判断においては、損失発生の可能性の高さを要件としていないことから、事後的に時価が回復した際に評価損を戻し入れることも否定できないとされている。その場合、同じ収益性の低下に基づく簿価切下げである固定資産の減損処理やその他有価証券の減損損失が切放し法とされている理由に関しては、それらは損失発生の可能性を要件としているためとされている。
(2)採用する時価との関係
時価との関係では、正味実現可能価額としたときには、収益性が回復した際に評価損を戻し入れないとまで言い切れないとされている。国際会計基準においては、時価が回復した場合には、帳簿価額まで過去の評価損を戻し入れることとされている。
再調達原価としたときには、再投資の仮定に拠っているとすれば、戻入れは行われないとされている。米国基準においては、このような考え方により、切放し法とされている。
5 【論点5】低価法の適用単位(グルーピングの可否)
棚卸資産における投資の成果の確定は、通常、個別品目ごとに販売された時点で確定されることから、低価法の適用単位も個別品目ごとであるのが原則であると考えられる。しかしながら、複数の棚卸資産が補完的な関係にあるような場合において、いずれか一方の販売だけでは正常な水準を超えるような収益を見込めないようなときには、グルーピングによる低価法の適用に対して積極的な意義付けができるとしている。また、それ以外のグルーピング、例えば、地域別セグメント、事業別セグメント、材料・仕掛品・製品という棚卸資産の種類ごとに低価法を適用することは、どこまで認められるかという点が問題となる。本論点整理では、低価法の適用単位は、どのような考え方に基づき、どのような場合にグルーピングすることが適当かに関して、引き続き検討することとしている。
6 【論点6】評価方法と低価法の適用
本論点整理では、後入先出法等につき論点の整理を行っているが、前述のように評価方法に関する検討等については、他の機会に委ねられている。
(1)後入先出法と低価法
後入先出法を採用している場合には、法人税法上、切放し方が認められていないことから、仮に切放し法のみとした場合には、企業に何らかの追加的な負担が発生するとされている。
(2)売価還元法と低価法
小売業等で売価還元法を採用している場合には、連続意見書に定める売価還元低価法を採用することが適当であるという意見が示される一方、値札に記載される売価が実勢売価を示しており、かつ原価率が100%以下であるときには、売価による回収見込額は帳簿価額よりも大きいことから、売価還元平均原価法を採用していても問題は生じないという反対の意見も示されている。この点に関しては、引き続き検討することとしている。
7【論点7】損益計算書における低価法評価損の計上区分
企業会計原則注解(注10)において、低価法評価損の損益計算書における計上区分は、品質低下・陳腐化評価損や強制評価減の計上区分と異なっている。現行の会計基準においては、期間損益計算の観点から低価法が位置付けられているわけではなく、当期の収益とは対応関係がないものと考えられていることによる。
本論点整理では、収益性の低下に基づき低価法評価損を計上する場合には、低価法評価損を営業外費用として処理することを積極的に支持する根拠を見出しにくいとしている。
低価法を採用する場合には、強制評価減は、低価法評価損に含まれると想定しているため、簿価切下げ額を強制評価減として営業外費用又は特別損失に計上することは不要になるものと考えている。また、低価法評価損と品質低下・陳腐化評価損は、その原因は異なるとしつつも、実務上区分が難しいため損益計算書における計上区分を同じにすべきという意見があるとされている。
8【論点8】金融投資と考えられる棚卸資産の時価評価
金融投資として保有する非金融資産に関して、現行の会計基準では、流動資産の評価に関する規定から、原価法か低価法の選択しか認められないと解されているが、今後、時価評価し、評価差額を当期の損益とすることが検討することとされている。これは棚卸資産として取り扱われている現物商品の中には、流動性が高く時価を容易に算定できる市場の存在を前提に、当該市場での価格の変動に基づいて利益を獲得するために、同一現物商品について反復的な購入と売却が行われているものがあるためである。そのような現物商品は、金融資産ではないものの、売買目的有価証券と同様に金融投資としての側面が強いため、時価評価し、評価差額を当期の損益とすることが考えられる。これらの関係は、図表(4)のように整理される。
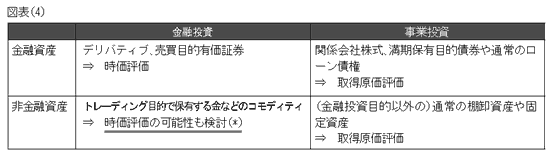
Ⅵ.おわりに
本論点整理に寄せられる意見を踏まえASBJでは、棚卸資産の評価基準に関する企業会計基準や同適用指針の開発を以下のスケジュールで行うことを予定している。
・平成18年前半 企業会計基準(案)及び同適用指針(案)の公開草案を公表
・平成18年内 企業会計基準及び同適用指針を公表
1 ASBJのHP(http://www.asb.or.jp/summary_issue/lcm/lcm.html)を参照のこと。
2 本論点整理の注3では、「国際会計基準(IAS第2号)において、棚卸資産の評価方法として後入先出法は認められていない。なお、後入先出法を含む棚卸資産の評価方法に関する検討は、本論点整理の対象とはされておらず、他の機会に委ねられている。」とされている。
3 IASBとのコンバージェンスに向けた共同プロジェクトにおける第1フェーズ検討5項目は、①棚卸資産の評価基準(IAS第2号)、②セグメント情報(IAS第14号)、③関連当事者の開示(IAS第24号)、④在外子会社の会計基準の統一(IAS第27号)、⑤投資不動産(IAS第40号)である。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















