解説記事2006年02月13日 【会計解説】 企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」について(2006年2月13日号・№150)
実 務 解 説
企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」について
企業会計基準委員会 研究員 大橋裕子
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)では、平成17年12月27日に以下の会計基準等を公表した(脚注1)。
企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)
企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。)
ここでは、これらの概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ.公表の経緯
近年の会計基準の新設又は改正により、その他有価証券評価差額金や為替換算調整勘定のように従来の資本の部に直接計上される項目が増えていること、また商法の改正による自己株式の取得、処分及び消却等、資本の部の変動要因が増加していることなどから、ASBJのテーマ協議会の提言書(平成13年11月12日)において、ディスクロージャーの透明性確保のため、株主の持分の変動に関する開示制度の導入が望まれるとされていた。こうした中、平成17年7月に公布された会社法(平成17年法律第86号)では、すべての株式会社は株主資本等変動計算書を作成しなければならないこととしており、ASBJでは、会社法対応専門委員会においての討議を含め、これらの問題に対する審議を行ってきた。平成17年8月30日には、本会計基準及び本適用指針の公開草案を公表し広く各界からの意見を求めており、寄せられた意見も参考にしてさらに審議を行った。本会計基準及び本適用指針は公開草案の内容を一部修正して公表されたものである。
Ⅲ.本会計基準及び本適用指針の概要
1 表示区分
(1)様式
連結株主資本等変動計算書及び個別株主資本等変動計算書(以下合わせて「株主資本等変動計算書」という。)の表示は、純資産の各項目を横に並べる様式により作成する。ただし、純資産の各項目を縦に並べる様式により作成することもできる。
(2)表示区分
株主資本等変動計算書等の表示区分は、以下の表示例のように、企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」に定める貸借対照表の純資産の部の表示区分に従う。
すなわち、株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に区分し、株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等、新株予約権及び少数株主持分(連結株主資本等変動計算書の場合)に区分する。また、個別株主資本等変動計算書については、資本剰余金は資本準備金及びその他資本剰余金に区分し、利益剰余金は、利益準備金及びその他利益剰余金に区分する。評価・換算差額等は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、土地再評価差額金及び為替換算調整勘定(連結株主資本等変動計算書の場合)等その内容を示す科目をもって表示する。なお、該当が無い表示区分又は科目は、記載不要である。
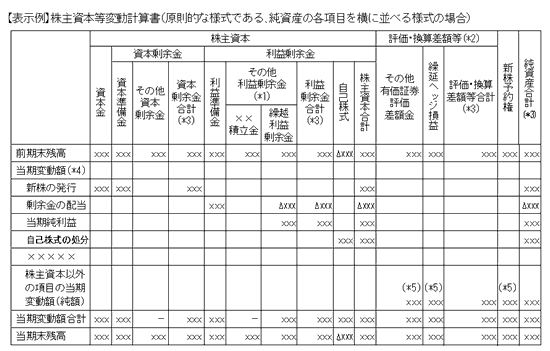
(*1)その他利益剰余金については、その内訳科目の前期末残高、当期変動額及び当期末残高の各金額を注記により開示することができる。この場合、その他利益剰余金の前期末残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を個別株主資本等変動計算書に記載する(本適用指針第4項参照)。
(*2)評価・換算差額等については、その内訳科目の前期末残高、当期変動額及び当期末残高の各金額を注記により開示することができる。この場合、評価・換算差額等の前期末残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を個別株主資本等変動計算書に記載する(本適用指針第5項参照)
(*3)各合計欄の記載は省略することができる。
(*4)株主資本の各項目の変動事由及びその金額の記載は、概ね個別貸借対照表における表示の順序による。
(*5)株主資本以外の各項目は、当期変動額を純額で記載することに代えて、変動事由ごとにその金額を個別株主資本等変動計算書又は注記により表示することができる(本適用指針第9項から第12項参照)。また、変動事由ごとにその金額を個別株主資本等変動計算書に記載する場合には、概ね株主資本の各項目に関係する変動事由の次に記載する。
2 表示方法
株主資本等変動計算書に表示される株主資本及び株主資本以外の各項目の前期末残高及び当期末残高は、以下のように、貸借対照表の純資産の部における各項目の期末残高と整合したものでなければならない。また、連結損益計算書の当期純利益又は当期純損失(以下「当期純損益」という。)は、以下のように連結株主資本等変動計算書において利益剰余金の変動事由として表示し、個別損益計算書の当期純損益は個別株主資本等変動計算書においてその他利益剰余金又はその内訳科目である繰越利益剰余金の変動事由として表示する。これは、株主資本等変動計算書が財務諸表の1つであり、財務諸表間での開示項目及び金額の整合が必要であるためである。
(1)株主資本の各項目
貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとにその金額を表示する。
当期変動額及び変動事由の記載
前述のように、当期純損益は、金額の大小を問わず、利益剰余金、その他利益剰余金又はその内訳科目である繰越利益剰余金の変動事由として表示する。このほか、株主資本の各項目の変動事由としては、本適用指針第6項に示されているように、新株の発行又は自己株式の処分、剰余金の配当、自己株式の取得、自己株式の消却、企業結合(合併、会社分割、株式交換、株式移転など)による増加又は分割型の会社分割による減少、株主資本の計数の変動(資本金から準備金又は剰余金への振替、準備金から資本金又は剰余金への振替、剰余金から資本金又は準備金への振替、剰余金の内訳科目間の振替)、及び連結範囲の変動又は持分法の適用範囲の変動(連結子会社又は持分法適用会社の増加又は減少)等が考えられる。これらの変動事由は例示であるため、企業の判断により変動事由の内容を適切に表す他の名称をもって記載することを妨げるものではない。なお、株主資本等変動計算書は、一会計期間における株主資本等の増減を適切な変動事由ごとに集約して表示することを目的としており、必ずしも会計帳簿の記載そのものを反映するものではない。
税法上の積立金
税法上の積立金(例えば、圧縮積立金)は、これまで利益処分案の株主総会決議によって積立て及び取崩しがなされていたが、会社法の下では、法人税等の税額計算を含む決算手続として会計処理することになる。具体的には、当期末の個別貸借対照表に税法上の積立金の積立て及び取崩しを反映させるとともに、個別株主資本等変動計算書に税法上の積立金の積立額と取崩額を記載(注記により開示する場合を含む。)し、株主総会又は取締役会で当該財務諸表を承認することになる。
(2)株主資本以外の各項目
貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は純額(前期末残高と当期末残高の差異)で表示する。
ただし、これは純資産の部における株主資本以外の各項目について変動事由ごとにその金額を表示することを妨げる趣旨ではないため、重要性を勘案の上、株主資本以外の各項目についても、当期変動額について主な変動事由ごとにその金額を表示(注記による開示を含む。)することができることとした。
当期変動事由の記載
本適用指針第11項に記載した変動事由は例示であるため、企業の判断により変動事由の内容を適切に示す他の名称をもって記載することを妨げるものではない。なお、その場合の変動事由及びその金額の記載は必ずしも会計帳簿の記載そのものを反映するものではないことは前述の株主資本の各項目の場合と同様である。
変動事由を表示する場合の主な変動事由及び金額の表示方法の選択
株主資本以外の各項目の当期変動額について主な変動事由ごとにその金額を表示する場合、株主資本等変動計算書に主な変動事由及びその金額を記載する方法と株主資本等変動計算書には当期変動額を純額で記載し、主な変動事由及びその金額を注記する方法のいずれかの方法を選択できる。
その他有価証券評価差額金の損益への振替額の算定及び評価・換算差額等に係る税効果の取扱い
その他有価証券評価差額金について、主な変動事由及びその金額を表示する場合で、その他有価証券の売却・減損処理による増減は、原則として①損益計算書に計上されたその他有価証券売却損益等の額を表示する方法と、②損益計算書に計上されたその他有価証券売却損益等の額に税効果を調整した後の額を表示する方法のいずれかの方法による。なお、①の方法による場合、その他有価証券評価差額金に対する税効果の額を、別の変動事由として表示することとなるが、この場合当該税効果の額の表示は、評価・換算差額等の内訳項目ごとに行う方法、その他有価証券評価差額金を含む評価・換算差額等に対する税効果の額の合計による方法のいずれによることもできる。また、税効果の調整の方法としては、例えば、その他有価証券評価差額金の増減があった事業年度の法定実効税率を使用する方法や繰延税金資産の回収可能性を考慮した税率を使用する方法などがある。
なお、評価・換算差額等に含まれる他の項目(繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定)についても、同様の取扱いとなる。
3 注記事項
連結株主資本等変動計算書には発行済株式の種類及び総数に関する事項、自己株式の種類及び株式数に関する事項、新株予約権及び自己新株予約権に関する事項、配当に関する事項を注記する。また、個別株主資本等変動計算書には、自己株式の種類及び株式数に関する事項を別途注記する。
連結株主資本等変動計算書への注記事項を主とする上記の取扱いは、現在の情報開示の中心が連結財務諸表であることを考慮したためであり、個別株主資本等変動計算書に自己株式の種類及び株式数に関する事項以外の注記を行うことを妨げる趣旨ではない。従って、連結株主資本等変動計算書への注記に加え、個別株主資本等変動計算書に発行済株式の種類及び総数に関する事項、新株予約権及び自己新株予約権に関する事項、配当に関する事項を注記することも可能である。
連結財務諸表を作成しない会社においては、上記の連結株主資本等変動計算書の注記事項に準ずる事項を個別株主資本等変動計算書に注記することとなる。
発行済株式の種類及び総数に関する事項、自己株式の種類及び株式数に関する事項
発行済株式の種類及び総数に関する事項については、発行済株式の種類ごとに、前期末及び当期末の発行済株式総数、並びに当期に増加又は減少した発行済株式数を記載し、発行済株式の種類ごとに変動事由の概要を記載する。自己株式の種類及び株式数に関する事項については、自己株式の種類ごとに、前期末及び当期末の自己株式数、並びに当期に増加又は減少した自己株式数を記載し、自己株式の種類ごとに変動事由の概要を記載する。
我が国の連結財務諸表は親会社説に基づいており、発行済株式の種類及び総数並びに配当に関する事項については連結財務諸表と個別財務諸表間での差異は生じない。一方、自己株式の種類及び株式数については、連結子会社及び持分法適用会社が親会社株式(又は投資会社の株式)を保有する場合、その親会社持分相当分について連結財務諸表と個別財務諸表とで差異が生じる可能性がある。そのため、連結株主資本等変動計算書で記載される事項と同様の注記事項は重複開示を避け、個別株主資本等変動計算書に重ねての記載を求めないとする一方、連結財務諸表と個別財務諸表とで差異が生じる可能性がある自己株式の種類及び株式数に関する事項は個別株主資本等変動計算書への注記も求めることとした。
なお、連結株主資本等変動計算書への自己株式の種類及び株式数に関する事項の記載にあたっての自己株式数は、親会社が保有する自己株式の株式数と、子会社又は関連会社が保有する親会社株式又は投資会社の株式の株式数のうち、親会社又は投資会社の持分に相当する株式数の合計となる。
また、従来、期末の発行済株式数及び自己株式数は貸借対照表の注記事項とされていたが、株主資本等変動計算書の作成に伴い、前期末及び当期増加・減少株式数並びに自己株式数の記載と合わせて当期末の発行済株式数及び自己株式数は株主資本等変動計算書の注記事項となる。
新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権及び自己新株予約権に関する事項については、新株予約権の目的となる株式の種類、新株予約権の目的となる株式の数(権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数)、新株予約権の当期末残高を記載する。また自己新株予約権に関する事項については、親会社が発行した新株予約権を親会社が保有している場合(親会社の自己新株予約権)には、上記新株予約権に関する事項の記載に準じた注記を行い、連結子会社が発行した新株予約権を当該子会社が保有している場合(連結子会社の自己新株予約権)には、当期末残高を記載する。
新株予約権及び自己新株予約権に関する事項の注記対象となる新株予約権及び自己新株予約権は、株主資本等変動計算書が貸借対照表の純資産の部の一会計期間の変動額を報告するために作成されるものであることから、純資産の部に計上されていない新株予約権に関する事項については、注記を求めないこととした。従って、例えば、敵対的買収防止策として付与される自社株式オプションは注記対象に含まれるが、一括法により負債に計上されるいわゆる転換社債型新株予約権付社債は含まれないこととなる。なお、前者については、上記の理由に加え、権利行使された場合の増加株式数が発行済株式総数に対して重要な影響を与える可能性があることから、純資産の部に帳簿価額がゼロの新株予約権が計上されているものとみなして注記対象としている。従って、この趣旨から、仮に注記対象とされる新株予約権ではない場合であっても、それが権利行使された場合、発行済株式総数に対する重要な影響がある場合、その情報は有用であることから企業が自主的にそれを開示することを妨げるものではない。
新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数は、連結株主資本等変動計算書においても親会社が発行した新株予約権のみを注記の対象としている。これは発行済株式総数及び自己株式数の注記事項が親会社の株式を対象としており、親会社の発行済株式総数への影響を開示するためである。但し、ストック・オプション会計基準により別途開示されるものについては、重複開示を避けるため注記対象としていない。
新株予約権の当期末残高の注記については、ストック・オプション等として交付されたものを含み、また連結子会社の新株予約権の当期末残高(ストック・オプション等として交付されたものを含む。)を親会社の新株予約権の当期末残高(ストック・オプション等として交付されたものを含む。)と区別して注記することとなる。当期末残高について連結子会社の発行した新株予約権残高及びストック・オプションとして交付されたものを含むこととしたのは、連結貸借対照表に計上されている新株予約権残高との整合性を考慮したことによる。
配当に関する事項
配当の基準日及び配当の効力発生日が当期となるものについては、株式の種類ごとの配当金の総額(配当財産が金銭の場合)又は株式の種類ごとに配当財産の種類並びに配当財産の帳簿価額(配当財産が金銭以外の場合)、1株当たり配当額、基準日及び効力発生日を記載する。また、配当の基準日は当期に属するものの配当の効力発生日が翌期となるものについて上記に準ずる事項の他、配当の原資の記載を求めることとした。これは、配当の基準日は当期に属するものの効力の発生日が翌期となる場合、株主資本等変動計算書に配当の原資が示されず、別途開示することが有用と考えられるためである。
4 中間株主資本等変動計算書の作成
中間連結株主資本等変動計算書及び中間個別株主資本等変動計算書(以下合わせて「中間株主資本等変動計算書」という。)は、株主資本等変動計算書に準じて作成する。
5 適用時期
株主資本等変動計算書は、会社法施行日以後終了する連結会計年度及び事業年度から作成する。中間株主資本等変動計算書は会社法施行日以後終了する中間連結会計期間及び中間会計期間から作成する。
なお、会社法施行日以後終了する連結会計年度及び事業年度から株主資本等変動計算書を作成した場合でも、いわゆる中間・年度の首尾一貫性が保持されていない場合には該当しない。これは、会社法施行日前に終了する中間連結会計期間及び中間会計期間においては、中間株主資本等変動計算書に関する制度自体が存在しておらず、また、連結会計年度及び事業年度からの株主資本等変動計算書の作成は企業の選択によるものではなく、本会計基準及び会社法の定めによるものであるためである。
また、従来、個別損益計算書に示されていた当期未処分利益(又は当期未処理損失)の計算は個別株主資本等変動計算書に示されることから、個別株主資本等変動計算書を作成するときから、個別損益計算書の末尾は当期純利益(又は、当期純損失)となる。加えて、連結上の剰余金の増減は連結株主資本等変動計算書に包含されることから、連結剰余金計算書は廃止されることになる。
脚注
1 本会計基準及び本適用指針については、ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/j_technical_topics_reports/equity/)を参照のこと。
企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」について
企業会計基準委員会 研究員 大橋裕子
Ⅰ.はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)では、平成17年12月27日に以下の会計基準等を公表した(脚注1)。
企業会計基準第6号「株主資本等変動計算書に関する会計基準」(以下「本会計基準」という。)
企業会計基準適用指針第9号「株主資本等変動計算書に関する会計基準の適用指針」(以下「本適用指針」という。)
ここでは、これらの概要を紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ.公表の経緯
近年の会計基準の新設又は改正により、その他有価証券評価差額金や為替換算調整勘定のように従来の資本の部に直接計上される項目が増えていること、また商法の改正による自己株式の取得、処分及び消却等、資本の部の変動要因が増加していることなどから、ASBJのテーマ協議会の提言書(平成13年11月12日)において、ディスクロージャーの透明性確保のため、株主の持分の変動に関する開示制度の導入が望まれるとされていた。こうした中、平成17年7月に公布された会社法(平成17年法律第86号)では、すべての株式会社は株主資本等変動計算書を作成しなければならないこととしており、ASBJでは、会社法対応専門委員会においての討議を含め、これらの問題に対する審議を行ってきた。平成17年8月30日には、本会計基準及び本適用指針の公開草案を公表し広く各界からの意見を求めており、寄せられた意見も参考にしてさらに審議を行った。本会計基準及び本適用指針は公開草案の内容を一部修正して公表されたものである。
Ⅲ.本会計基準及び本適用指針の概要
1 表示区分
(1)様式
連結株主資本等変動計算書及び個別株主資本等変動計算書(以下合わせて「株主資本等変動計算書」という。)の表示は、純資産の各項目を横に並べる様式により作成する。ただし、純資産の各項目を縦に並べる様式により作成することもできる。
(2)表示区分
株主資本等変動計算書等の表示区分は、以下の表示例のように、企業会計基準第5号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」に定める貸借対照表の純資産の部の表示区分に従う。
すなわち、株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に区分し、株主資本以外の各項目は、評価・換算差額等、新株予約権及び少数株主持分(連結株主資本等変動計算書の場合)に区分する。また、個別株主資本等変動計算書については、資本剰余金は資本準備金及びその他資本剰余金に区分し、利益剰余金は、利益準備金及びその他利益剰余金に区分する。評価・換算差額等は、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、土地再評価差額金及び為替換算調整勘定(連結株主資本等変動計算書の場合)等その内容を示す科目をもって表示する。なお、該当が無い表示区分又は科目は、記載不要である。
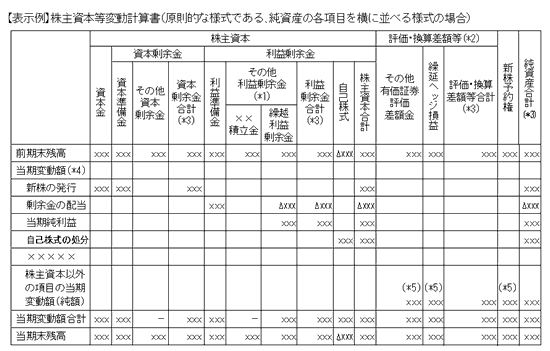
(*1)その他利益剰余金については、その内訳科目の前期末残高、当期変動額及び当期末残高の各金額を注記により開示することができる。この場合、その他利益剰余金の前期末残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を個別株主資本等変動計算書に記載する(本適用指針第4項参照)。
(*2)評価・換算差額等については、その内訳科目の前期末残高、当期変動額及び当期末残高の各金額を注記により開示することができる。この場合、評価・換算差額等の前期末残高、当期変動額及び当期末残高の各合計額を個別株主資本等変動計算書に記載する(本適用指針第5項参照)
(*3)各合計欄の記載は省略することができる。
(*4)株主資本の各項目の変動事由及びその金額の記載は、概ね個別貸借対照表における表示の順序による。
(*5)株主資本以外の各項目は、当期変動額を純額で記載することに代えて、変動事由ごとにその金額を個別株主資本等変動計算書又は注記により表示することができる(本適用指針第9項から第12項参照)。また、変動事由ごとにその金額を個別株主資本等変動計算書に記載する場合には、概ね株主資本の各項目に関係する変動事由の次に記載する。
2 表示方法
株主資本等変動計算書に表示される株主資本及び株主資本以外の各項目の前期末残高及び当期末残高は、以下のように、貸借対照表の純資産の部における各項目の期末残高と整合したものでなければならない。また、連結損益計算書の当期純利益又は当期純損失(以下「当期純損益」という。)は、以下のように連結株主資本等変動計算書において利益剰余金の変動事由として表示し、個別損益計算書の当期純損益は個別株主資本等変動計算書においてその他利益剰余金又はその内訳科目である繰越利益剰余金の変動事由として表示する。これは、株主資本等変動計算書が財務諸表の1つであり、財務諸表間での開示項目及び金額の整合が必要であるためである。
(1)株主資本の各項目
貸借対照表の純資産の部における株主資本の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は変動事由ごとにその金額を表示する。
当期変動額及び変動事由の記載
前述のように、当期純損益は、金額の大小を問わず、利益剰余金、その他利益剰余金又はその内訳科目である繰越利益剰余金の変動事由として表示する。このほか、株主資本の各項目の変動事由としては、本適用指針第6項に示されているように、新株の発行又は自己株式の処分、剰余金の配当、自己株式の取得、自己株式の消却、企業結合(合併、会社分割、株式交換、株式移転など)による増加又は分割型の会社分割による減少、株主資本の計数の変動(資本金から準備金又は剰余金への振替、準備金から資本金又は剰余金への振替、剰余金から資本金又は準備金への振替、剰余金の内訳科目間の振替)、及び連結範囲の変動又は持分法の適用範囲の変動(連結子会社又は持分法適用会社の増加又は減少)等が考えられる。これらの変動事由は例示であるため、企業の判断により変動事由の内容を適切に表す他の名称をもって記載することを妨げるものではない。なお、株主資本等変動計算書は、一会計期間における株主資本等の増減を適切な変動事由ごとに集約して表示することを目的としており、必ずしも会計帳簿の記載そのものを反映するものではない。
税法上の積立金
税法上の積立金(例えば、圧縮積立金)は、これまで利益処分案の株主総会決議によって積立て及び取崩しがなされていたが、会社法の下では、法人税等の税額計算を含む決算手続として会計処理することになる。具体的には、当期末の個別貸借対照表に税法上の積立金の積立て及び取崩しを反映させるとともに、個別株主資本等変動計算書に税法上の積立金の積立額と取崩額を記載(注記により開示する場合を含む。)し、株主総会又は取締役会で当該財務諸表を承認することになる。
(2)株主資本以外の各項目
貸借対照表の純資産の部における株主資本以外の各項目は、前期末残高、当期変動額及び当期末残高に区分し、当期変動額は純額(前期末残高と当期末残高の差異)で表示する。
ただし、これは純資産の部における株主資本以外の各項目について変動事由ごとにその金額を表示することを妨げる趣旨ではないため、重要性を勘案の上、株主資本以外の各項目についても、当期変動額について主な変動事由ごとにその金額を表示(注記による開示を含む。)することができることとした。
当期変動事由の記載
本適用指針第11項に記載した変動事由は例示であるため、企業の判断により変動事由の内容を適切に示す他の名称をもって記載することを妨げるものではない。なお、その場合の変動事由及びその金額の記載は必ずしも会計帳簿の記載そのものを反映するものではないことは前述の株主資本の各項目の場合と同様である。
変動事由を表示する場合の主な変動事由及び金額の表示方法の選択
株主資本以外の各項目の当期変動額について主な変動事由ごとにその金額を表示する場合、株主資本等変動計算書に主な変動事由及びその金額を記載する方法と株主資本等変動計算書には当期変動額を純額で記載し、主な変動事由及びその金額を注記する方法のいずれかの方法を選択できる。
その他有価証券評価差額金の損益への振替額の算定及び評価・換算差額等に係る税効果の取扱い
その他有価証券評価差額金について、主な変動事由及びその金額を表示する場合で、その他有価証券の売却・減損処理による増減は、原則として①損益計算書に計上されたその他有価証券売却損益等の額を表示する方法と、②損益計算書に計上されたその他有価証券売却損益等の額に税効果を調整した後の額を表示する方法のいずれかの方法による。なお、①の方法による場合、その他有価証券評価差額金に対する税効果の額を、別の変動事由として表示することとなるが、この場合当該税効果の額の表示は、評価・換算差額等の内訳項目ごとに行う方法、その他有価証券評価差額金を含む評価・換算差額等に対する税効果の額の合計による方法のいずれによることもできる。また、税効果の調整の方法としては、例えば、その他有価証券評価差額金の増減があった事業年度の法定実効税率を使用する方法や繰延税金資産の回収可能性を考慮した税率を使用する方法などがある。
なお、評価・換算差額等に含まれる他の項目(繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定)についても、同様の取扱いとなる。
3 注記事項
連結株主資本等変動計算書には発行済株式の種類及び総数に関する事項、自己株式の種類及び株式数に関する事項、新株予約権及び自己新株予約権に関する事項、配当に関する事項を注記する。また、個別株主資本等変動計算書には、自己株式の種類及び株式数に関する事項を別途注記する。
連結株主資本等変動計算書への注記事項を主とする上記の取扱いは、現在の情報開示の中心が連結財務諸表であることを考慮したためであり、個別株主資本等変動計算書に自己株式の種類及び株式数に関する事項以外の注記を行うことを妨げる趣旨ではない。従って、連結株主資本等変動計算書への注記に加え、個別株主資本等変動計算書に発行済株式の種類及び総数に関する事項、新株予約権及び自己新株予約権に関する事項、配当に関する事項を注記することも可能である。
連結財務諸表を作成しない会社においては、上記の連結株主資本等変動計算書の注記事項に準ずる事項を個別株主資本等変動計算書に注記することとなる。
発行済株式の種類及び総数に関する事項、自己株式の種類及び株式数に関する事項
発行済株式の種類及び総数に関する事項については、発行済株式の種類ごとに、前期末及び当期末の発行済株式総数、並びに当期に増加又は減少した発行済株式数を記載し、発行済株式の種類ごとに変動事由の概要を記載する。自己株式の種類及び株式数に関する事項については、自己株式の種類ごとに、前期末及び当期末の自己株式数、並びに当期に増加又は減少した自己株式数を記載し、自己株式の種類ごとに変動事由の概要を記載する。
我が国の連結財務諸表は親会社説に基づいており、発行済株式の種類及び総数並びに配当に関する事項については連結財務諸表と個別財務諸表間での差異は生じない。一方、自己株式の種類及び株式数については、連結子会社及び持分法適用会社が親会社株式(又は投資会社の株式)を保有する場合、その親会社持分相当分について連結財務諸表と個別財務諸表とで差異が生じる可能性がある。そのため、連結株主資本等変動計算書で記載される事項と同様の注記事項は重複開示を避け、個別株主資本等変動計算書に重ねての記載を求めないとする一方、連結財務諸表と個別財務諸表とで差異が生じる可能性がある自己株式の種類及び株式数に関する事項は個別株主資本等変動計算書への注記も求めることとした。
なお、連結株主資本等変動計算書への自己株式の種類及び株式数に関する事項の記載にあたっての自己株式数は、親会社が保有する自己株式の株式数と、子会社又は関連会社が保有する親会社株式又は投資会社の株式の株式数のうち、親会社又は投資会社の持分に相当する株式数の合計となる。
また、従来、期末の発行済株式数及び自己株式数は貸借対照表の注記事項とされていたが、株主資本等変動計算書の作成に伴い、前期末及び当期増加・減少株式数並びに自己株式数の記載と合わせて当期末の発行済株式数及び自己株式数は株主資本等変動計算書の注記事項となる。
新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
新株予約権及び自己新株予約権に関する事項については、新株予約権の目的となる株式の種類、新株予約権の目的となる株式の数(権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数)、新株予約権の当期末残高を記載する。また自己新株予約権に関する事項については、親会社が発行した新株予約権を親会社が保有している場合(親会社の自己新株予約権)には、上記新株予約権に関する事項の記載に準じた注記を行い、連結子会社が発行した新株予約権を当該子会社が保有している場合(連結子会社の自己新株予約権)には、当期末残高を記載する。
新株予約権及び自己新株予約権に関する事項の注記対象となる新株予約権及び自己新株予約権は、株主資本等変動計算書が貸借対照表の純資産の部の一会計期間の変動額を報告するために作成されるものであることから、純資産の部に計上されていない新株予約権に関する事項については、注記を求めないこととした。従って、例えば、敵対的買収防止策として付与される自社株式オプションは注記対象に含まれるが、一括法により負債に計上されるいわゆる転換社債型新株予約権付社債は含まれないこととなる。なお、前者については、上記の理由に加え、権利行使された場合の増加株式数が発行済株式総数に対して重要な影響を与える可能性があることから、純資産の部に帳簿価額がゼロの新株予約権が計上されているものとみなして注記対象としている。従って、この趣旨から、仮に注記対象とされる新株予約権ではない場合であっても、それが権利行使された場合、発行済株式総数に対する重要な影響がある場合、その情報は有用であることから企業が自主的にそれを開示することを妨げるものではない。
新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数は、連結株主資本等変動計算書においても親会社が発行した新株予約権のみを注記の対象としている。これは発行済株式総数及び自己株式数の注記事項が親会社の株式を対象としており、親会社の発行済株式総数への影響を開示するためである。但し、ストック・オプション会計基準により別途開示されるものについては、重複開示を避けるため注記対象としていない。
新株予約権の当期末残高の注記については、ストック・オプション等として交付されたものを含み、また連結子会社の新株予約権の当期末残高(ストック・オプション等として交付されたものを含む。)を親会社の新株予約権の当期末残高(ストック・オプション等として交付されたものを含む。)と区別して注記することとなる。当期末残高について連結子会社の発行した新株予約権残高及びストック・オプションとして交付されたものを含むこととしたのは、連結貸借対照表に計上されている新株予約権残高との整合性を考慮したことによる。
配当に関する事項
配当の基準日及び配当の効力発生日が当期となるものについては、株式の種類ごとの配当金の総額(配当財産が金銭の場合)又は株式の種類ごとに配当財産の種類並びに配当財産の帳簿価額(配当財産が金銭以外の場合)、1株当たり配当額、基準日及び効力発生日を記載する。また、配当の基準日は当期に属するものの配当の効力発生日が翌期となるものについて上記に準ずる事項の他、配当の原資の記載を求めることとした。これは、配当の基準日は当期に属するものの効力の発生日が翌期となる場合、株主資本等変動計算書に配当の原資が示されず、別途開示することが有用と考えられるためである。
4 中間株主資本等変動計算書の作成
中間連結株主資本等変動計算書及び中間個別株主資本等変動計算書(以下合わせて「中間株主資本等変動計算書」という。)は、株主資本等変動計算書に準じて作成する。
5 適用時期
株主資本等変動計算書は、会社法施行日以後終了する連結会計年度及び事業年度から作成する。中間株主資本等変動計算書は会社法施行日以後終了する中間連結会計期間及び中間会計期間から作成する。
なお、会社法施行日以後終了する連結会計年度及び事業年度から株主資本等変動計算書を作成した場合でも、いわゆる中間・年度の首尾一貫性が保持されていない場合には該当しない。これは、会社法施行日前に終了する中間連結会計期間及び中間会計期間においては、中間株主資本等変動計算書に関する制度自体が存在しておらず、また、連結会計年度及び事業年度からの株主資本等変動計算書の作成は企業の選択によるものではなく、本会計基準及び会社法の定めによるものであるためである。
また、従来、個別損益計算書に示されていた当期未処分利益(又は当期未処理損失)の計算は個別株主資本等変動計算書に示されることから、個別株主資本等変動計算書を作成するときから、個別損益計算書の末尾は当期純利益(又は、当期純損失)となる。加えて、連結上の剰余金の増減は連結株主資本等変動計算書に包含されることから、連結剰余金計算書は廃止されることになる。
脚注
1 本会計基準及び本適用指針については、ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/j_technical_topics_reports/equity/)を参照のこと。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















