解説記事2006年02月20日 【会計解説】 企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」について(2006年2月20日号・№151)
実 務 解 説
企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」について
企業会計基準委員会 専門研究員 河本圭介
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成17年12月27日に、以下を公表している(脚注1)。
●企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」(以下「事業分離等会計基準」という。)
●企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(以下「適用指針」という。)
事業分離等会計基準については、平成15年10月に企業会計審議会によって公表された「企業結合に係る会計基準」(以下「企業結合会計基準」という。)を受けて、企業結合会計基準では取り扱われていなかった分離元企業の会計処理や結合当事企業の株主に係る会計処理などの組織再編に係る会計処理を定めたものである。また、適用指針については、ある1つの組織再編が、企業結合及び事業分離さらには関連する株主の会計処理にも関係することが多いことから、2つの会計基準の適用に関する指針を一体として示した方が利用者の便宜に資するとして、2つの会計基準の適用に関する指針を組織再編の形式ごとに統合して示しているものである。
本稿では、事業分離等会計基準及び適用指針の概要について紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ 企業結合の会計処理
1. 企業結合とは
企業結合とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが1つの報告単位に統合されることをいう(企業結合会計基準 二 1.)。例えば、合併の場合は企業と企業とが、また共同新設分割の場合は事業と事業とが1つの報告単位に統合されるので、これらは企業結合に該当する。また、株式交換により、ある企業が他の企業(第三者)を完全子会社とした場合も、連結財務諸表上、企業と企業が1つの報告単位に統合されるので、企業結合に該当する。なお、親会社が子会社を株式交換により完全子会社とする場合は、もともと連結財務諸表上、報告単位は統合されているので、企業結合には該当しないが、企業結合会計基準では、当該取引を少数株主との取引として、その会計処理を定めている。
また、例えば、現金を対価としてある企業の株式を取得して子会社化した場合も、連結財務諸表上、ある企業と他の企業が1つの報告単位に統合されるので、企業結合に該当することになるが、当該会計処理は、企業結合会計基準の定めではなく、連結財務諸表原則の定めに従うことになる(企業結合会計基準 一)。もっとも、この場合も、基本的に取得の会計処理(パーチェス法)と同様の会計処理となる。
2. 企業結合の会計上の分類と適用される会計処理
適用指針では、企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書(以下「企業結合会計意見書」という) 四 3.の定めに従い、組織再編の形式ごと(合併、会社分割、株式交換、株式移転等)に個別財務諸表及び連結財務諸表の会計処理を示している。
ただし、会計上は、組織再編の形式にかかわらず、企業結合の会計上の4つの分類(取得、持分の結合、共同支配企業の形成、共通支配下の取引)ごとに適用すべき会計処理が決定される。
このため、企業結合の会計処理を行うにあたり、最初に、当該企業結合がどの企業結合の分類に識別されるのかを検討しなければならない(【図表1】参照)。
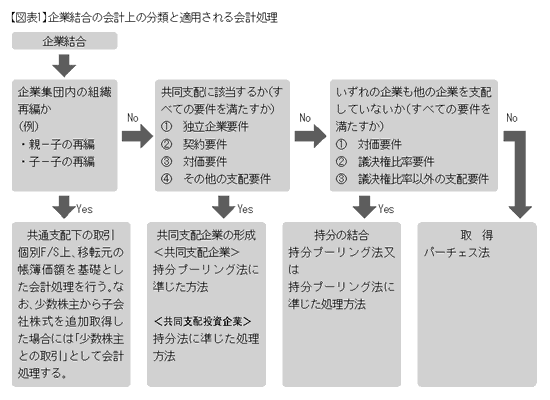
3. 取得と持分の結合の識別
(1)取得と持分の結合とは
共同支配企業の形成又は共通支配下の取引以外の企業結合は、取得又は持分の結合のいずれかに識別されることになる(企業結合会計基準 三 1.(1))。取得とは、ある企業が他の企業又は企業を構成する事業に対する支配を獲得して1つの報告単位となることをいい(企業結合会計基準 二 4.)、持分の結合とは、いずれの企業(又は事業)の株主も他の企業(又は事業)を支配したとは認められず、結合後企業のリスクや便益を引き続き相互に共有することを達成するため、それぞれの事業のすべて又は事実上のすべてを統合して1つの報告単位となることをいう(企業結合会計基準 二 5.)。
取得と持分の結合の識別は、概念上、結合当事企業の株主の持分が継続しているかどうかによることになるが、具体的な判定に当たっては、上記の定義から明らかなように、支配の有無が重視される。
(2)取得と持分の結合の識別規準
取得と持分の結合の識別規準としては、①対価要件、②議決権比率要件、③議決権比率以外の支配要件を順次判定し、すべての要件を満たした場合には持分の結合と判定し、1つでも要件を満たさなかった場合には、その時点で取得と判定することになる(企業結合会計基準 三 1.(1))。また、取得と判定された場合には、取得企業も、同時に決定されることになる(企業結合会計意見書 三 3.(1))。
4. 取得の会計処理
企業結合が取得と判定された場合には、連結財務諸表上及び個別財務諸表上、ともにパーチェス法を適用する(企業結合会計意見書 三 3.(6))。パーチェス法とは、取得企業が被取得企業から受入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう(【図表2】参照)。
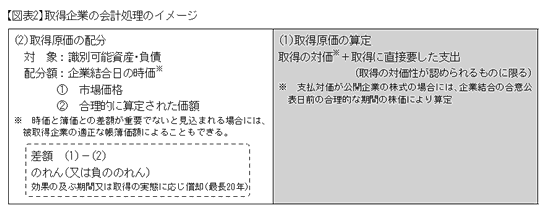
5. 持分の結合の会計処理
企業結合が持分の結合と判定された場合には、【図表3】のように会計処理を行う。
持分プーリング法とは、すべての結合当事企業の資産、負債及び資本(純資産)を、それぞれの適正な帳簿価額で引き継ぐ方法とされている(【図表4】参照)。したがって、結合当事企業の純資産の各項目も、原則として、結合後企業にそのまま引き継がなければならない。
持分プーリング法に準じた処理方法とは、株主資本の内訳の引継方法と企業結合年度の連結財務諸表の作成に係る規定の2点を除き、持分プーリング法と同一の処理方法をいう(企業結合会計基準注解(注15))(【図表5】参照)。事業分離を伴う企業結合においては、分離元企業の資本の内訳に変動は生じないため、分離先企業において、分離元企業の資本構成を引き継ぐことが困難であること等により、持分プーリング法に準じた処理方法を適用することになる。
なお、これらの2つの会計処理に共通する「適正な帳簿価額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した帳簿価額をいう(企業結合会計意見書 三 4.(1))。したがって、結合当事企業の帳簿価額に誤りがある場合には、その引継ぎ前に修正が行われることが必要である点に留意する必要がある。また、持分の結合と判定された場合には、企業結合に要した支出額は、すべて費用として処理される。
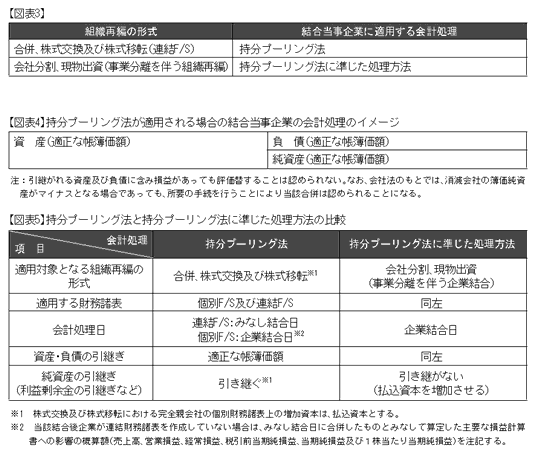
6. 共同支配企業の形成5. 持分の結合の会計処理
(1)共同支配企業及び共同支配投資企業とは
支配従属関係のない2社が、共同支配契約を締結するなど、(2)の要件を満たした合弁会社を設立したものとする。この場合、合弁会社を共同支配企業、合弁会社の株主を共同支配投資企業という(【図表6】参照)。
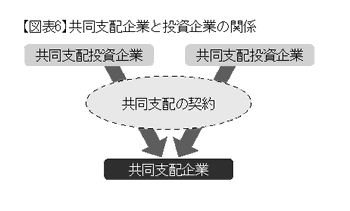
(2)共同支配企業の形成の判定規準
企業結合のうち、①独立企業要件、②契約要件、③対価要件、④その他の支配要件のすべてを満たすものは共同支配企業の形成と判定することになる(企業結合会計基準 二 3.及び同三 1.(2))。
(3)共同支配企業の形成の会計処理
以下では、組織再編の形式として共同新設分割を前提に記載する。
① 共同支配企業(新設分割設立会社)の会計処理
共同支配企業の形成には、持分プーリング法に準じた処理方法を適用する(企業結合会計基準 三 3.(7))。
② 共同支配投資企業(新設分割会社)の会計処理
a 個別財務諸表上の会計処理
共同支配投資企業は、移転した事業に係る資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額に基づいて当該共同支配企業に対する投資(新設分割設立会社の株式)の取得原価を算定する(企業結合会計基準 三 3.(7)ただし書き)。したがって、事業の移転時に損益は発生しない。
b 連結財務諸表上の会計処理
共同支配投資企業は、共同支配企業に対する投資について持分法に準ずる処理方法を適用する。持分法に準ずる処理方法とは、企業結合時に生じるのれん(又は負ののれん)及び持分変動差額を認識しない点を除き、持分法と同一の処理方法をいう。したがって、連結財務諸表上も、事業の移転時に損益(持分変動差額)やのれんは発生しない。
7. 共通支配下の取引
(1)共通支配下の取引の範囲
共通支配下の取引とは、親会社と子会社との合併や親会社の支配下にある子会社同士の合併など、結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企業結合をいう(企業結合会計基準 二 10.)(【図表7】参照)。
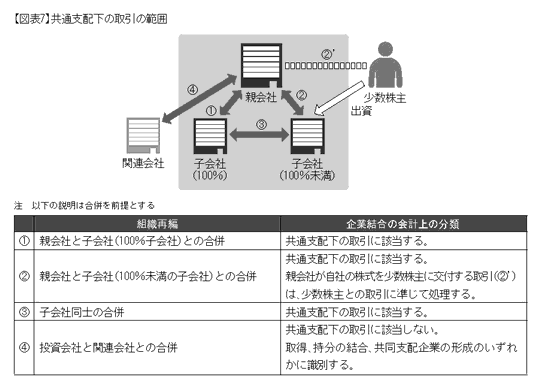
適用指針では、支配の主体である「同一の企業」には個人を含むものとし「同一の株主」として取り扱うこととしている。
(2)共通支配下の取引等の会計処理の概要
企業集団内における組織再編の会計処理には、共通支配下の取引と少数株主との取引(以下、あわせて「共通支配下の取引等」という。)がある。
共通支配下の取引は、親会社の立場からは内部取引と考えられるため、個別財務諸表上、事業の移転元の適正な帳簿価額を基礎として会計処理し、また、連結財務諸表上は、すべて消去することになる。なお、個別財務諸表上の増加する株主資本は原則として払込資本とするが、例えば、事業分離を伴わない組織再編である子会社による親会社の吸収合併や子会社同士の合併で、対価が株式のみの場合については、消滅会社の株主資本の内訳を引継ぐことができる。
一方、少数株主との取引は、親会社が子会社を株式交換により完全子会社とする場合など、親会社が少数株主から子会社株式を追加取得する取引等に適用される。当該取引は、親会社の立場からは外部取引と考えられるため、追加取得した子会社株式の取得原価は時価で算定する。このため、連結財務諸表上は、のれん(又は負ののれん)が計上されることになる。
企業集団内の組織再編の会計処理は、適正な帳簿価額による会計処理を基本としつつ、どの取引を外部取引として捉え、少数株主との取引の会計処理を適用するのか(のれん(又は負ののれん)を認識するのか)が主要な論点となる。適用指針では、組織再編の手法が異なっていても、組織再編後の経済的実態が同じであれば、連結財務諸表上(合併の場合には個別財務諸表上)も同じ結果が得られるように会計処理を定めている。
Ⅲ 事業分離等の会計処理
1. 分離元企業の会計処理
事業分離等会計基準は、一般に事業の成果をとらえる際の「投資の継続・清算」という概念に基づき、実現損益を認識するかどうかという観点から、分離元企業の会計処理を考えている。これは、企業結合の会計処理を一般的な会計処理と整合させるために考えられた「持分の継続・非継続」という概念の根底にある考え方である。
この結果、分離した事業に対する投資が継続しているとみるか清算されたとみるかによって、分離元企業において移転損益が認識される場合と認識されない場合が考えられる。これを判断するための観察可能な具体的要件として、事業分離等会計基準では、一般的な売却や交換の会計処理の考え方を踏まえ、対価が移転した事業と異なるかどうかという「対価の種類」を用い、さらに、企業結合会計基準では、共通支配下の取引の会計処理を定めているため、これとの整合性を前提にして、分離先企業が子会社にあたる場合を手がかりに、分離元企業の会計処理を考えている。
このため、事業分離等会計基準は、まず、受取対価が、(1)現金等の財産のみである場合、(2)分離先企業の株式のみである場合、(3)現金等の財産と分離先企業の株式である場合に大別し、それぞれにおいて、分離先企業が①子会社の場合、②関連会社の場合、③子会社や関連会社以外の場合に分けて、会計処理を定めている。ここでは紙幅の関係により、(1)(2)の概要についてのみ記述する。
(1)受取対価が現金等の財産のみである場合
事業分離により、企業が従来負っていた成果の変動性(すなわち事業投資のリスク)を免れるようになった場合に、当該事業への投資は清算されたものとみなされるため、分離元企業が、現金など、移転した事業と明らかに異なる財産を受取対価としてある事業を移転した場合には、通常、移転損益が認識される。
このとき、分離先企業が子会社となる場合や子会社を分離先企業とする場合には、企業結合会計基準における共通支配下の取引又はこれに準ずる取引に該当し、分離元企業が受け取った現金等の財産の移転前に付された適正な帳簿価額と移転した事業の適正な帳簿価額との間に生ずる差額が移転損益として認識されることとなる。また、分離先企業が子会社以外となる場合には、分離元企業が受け取った現金等の財産の時価と移転した事業の適正な帳簿価額との差額が移転損益として認識されることとなる(【図表8】参照)。
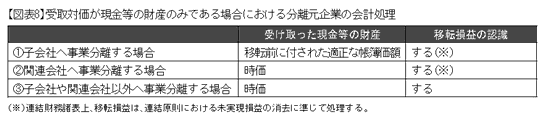
(2)受取対価が分離先企業の株式のみである場合
① 事業分離により分離先企業が子会社となる場合
企業結合会計基準からも明らかなように、この場合には、経済実態として分離元企業における当該事業に対する投資がそのまま継続していると考えられるため、親会社となる分離元企業において移転損益は認識されない。
しかしながら、分離元企業の連結財務諸表上、分離元企業の事業が移転されたとみなされる額(分離元企業の移転した事業の時価に、減少した分離元企業の持分比率を乗じた額)と、移転した事業に係る親会社の持分の減少額(移転した事業に係る適正な帳簿価額による純資産額に減少した分離元企業の持分比率を乗じた額)との差額(脚注2)は、連結原則における子会社の時価発行増資等に伴い生ずる親会社持分の増減額(持分変動差額)として取り扱うものとしている。
また、分離元企業は、分離先企業を取得する(既に子会社である場合の追加取得は「少数株主との取引」に該当する。)ため、連結財務諸表上、パーチェス法を適用し、分離先企業に対して(追加)投資したとみなされる額と、これに対応する分離先企業の事業分離直前の資本との間に生ずる差額については、のれん(又は負ののれん)とすることとなる(【図表9】①参照)。
② 事業分離により分離先企業が関連会社となる場合
この場合、分離元企業による当該事業に対する投資は清算されたものとみて移転損益を認識するという見方と、投資が継続しているものとみて移転損益を認識しないという見方がある。事業分離等会計基準では、(i)関連会社株式は、金融商品会計基準において、子会社株式の場合と同じく事実上の事業投資と同様の会計処理をすることとされていること、(ii)現行の会計基準等では、持分法は連結法(完全連結)のいわば簡便的な会計処理であることなどから、投資の継続に該当するという見方をとっている。
すなわち、事業分離の会計処理を考えるにあたっては、移転された事業に対する分離元企業の支配が継続しているか失われたかが最も重要であるという立場も有力であるが、事業分離等会計基準では、その立場をとってまで他の会計基準等を含む体系に影響を与える意義は薄いという考え方により、必ずしも支配が失われることをもって投資の清算とみることとはしていない(【図表9】②参照)。
(3)分離元企業の税効果会計
適用指針では、分離元企業における繰延税金資産及び繰延税金負債(以下「繰延税金資産等」という。)の計上について、【図表10】のように取扱うこととしている。
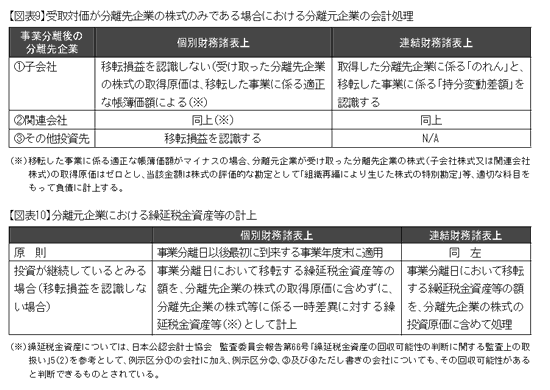
2. 結合当事企業の株主に係る会計処理
(1)被結合企業の株主に係る会計処理
企業結合により、保有していた被結合企業の株式が、結合企業の株式などの財と引き換えられた場合に、その投資が継続しているとみるか清算されたとみるかによって、被結合企業の株主に係る会計処理でも、交換損益が認識される場合と認識されない場合が考えられる。事業分離等会計基準では、事業分離における分離元企業(例えば、吸収分割会社)と、100%子会社を被結合企業とする企業結合における当該被結合企業の株主(親会社)とでは、経済的効果が実質的に同じであることから、両者の会計処理を整合的なものとしている。さらに、被結合企業の株主が親会社である場合には、被結合企業の株式をすべて保有しているとき(被結合企業が100%子会社の場合)でも、すべては保有していないとき(被結合企業が100%子会社以外の子会社の場合)でも整合的な会計処理とすることが適当とされている。
このため、分離元企業の会計処理と同様に、まず、受取対価が、(1)現金等の財産のみである場合(【図表11】参照)、(2)結合企業の株式のみである場合(【図表12】参照)、(3)現金等の財産と結合企業の株式である場合に大別し、それぞれにおいて、被結合企業が①子会社の場合、②関連会社の場合、③子会社や関連会社以外の場合に分けて、会計処理を定めている。
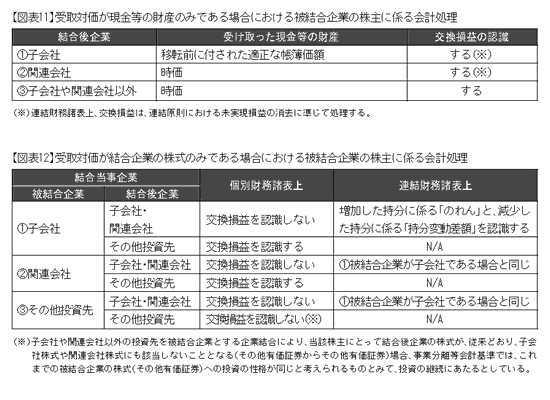
(2)結合企業の株主に係る会計処理
個々の株主にとっては、企業結合により被結合企業の株主が新たに結合企業の株主となる場合であっても、引き続き結合企業の株主である場合であっても、その経済的効果は実質的に同じであるものと考えられる。このため、事業分離等会計基準では、結合企業の株主に係る会計処理は、受取対価が結合企業の株式のみである場合の被結合企業の株主に係る会計処理に準じて定めている。
(3)分割型の会社分割における分割会社の株主及び現金以外の財産の分配を受けた場合の株主に係る会計処理
いわゆる分割型の会社分割や現物配当については企業結合に該当しないが、事業分離等会計基準では、当該分割会社の株主に係る会計処理や、株主が現物分配(現金以外の財産の分配)を受けた場合における当該株主の会計処理も定めている。
Ⅳ 適用時期
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準の適用時期は、平成18年4月1日以後開始事業年度から適用することになるが、会社法は、事業年度にかかわりなく、企業結合日又は事業分離日が会社法施行日以後の企業結合又は事業分離について適用される。このため、以下の期間における企業結合又は事業分離等に係る会計処理は、次のように取扱うことになると考えられる。
(1)平成18年4月1日以後に開始する事業年度のうち、会社法施行期日前の期間(会社法適用前期間)における取扱い
企業結合日又は事業分離日が会社法適用前期間となる企業結合又は事業分離等に係る会計処理については、旧商法に定める範囲内で企業結合会計基準又は事業分離等会計基準を適用することとなる。なお、例えば、合併期日が平成18年4月1日であり、企業結合会計基準に従ってのれんを計上し、これを20年以内の期間で償却することは、その償却を行うこととなる事業年度末において会社法が施行されている場合には、認められる。
(2)平成18年3月31日以前に開始する事業年度のうち、会社法施行期日以後の期間(会社法適用後期間)における取扱い
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準の適用前であるが、これらの会計基準に準じて処理することができる。
なお、会社法適用後期間においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う(会社法第431条)とともに、会社法に関する法務省令に準拠することに留意する必要がある。
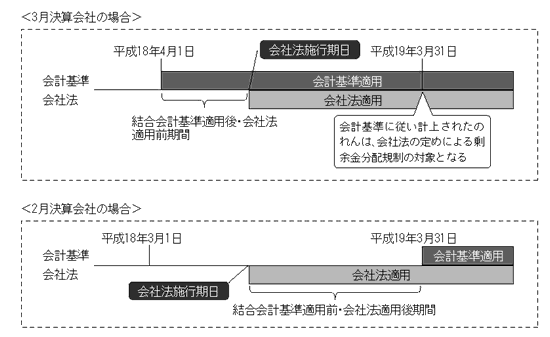
脚注
1 これらの全文については、ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/j_technical_topics_reports/combination/)参照のこと。
2 これは、移転した事業の適正な帳簿価額による純資産額とこれに対応する分離元企業(親会社)の持分との差額にあたる。
企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」について
企業会計基準委員会 専門研究員 河本圭介
Ⅰ はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成17年12月27日に、以下を公表している(脚注1)。
●企業会計基準第7号「事業分離等に関する会計基準」(以下「事業分離等会計基準」という。)
●企業会計基準適用指針第10号「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(以下「適用指針」という。)
事業分離等会計基準については、平成15年10月に企業会計審議会によって公表された「企業結合に係る会計基準」(以下「企業結合会計基準」という。)を受けて、企業結合会計基準では取り扱われていなかった分離元企業の会計処理や結合当事企業の株主に係る会計処理などの組織再編に係る会計処理を定めたものである。また、適用指針については、ある1つの組織再編が、企業結合及び事業分離さらには関連する株主の会計処理にも関係することが多いことから、2つの会計基準の適用に関する指針を一体として示した方が利用者の便宜に資するとして、2つの会計基準の適用に関する指針を組織再編の形式ごとに統合して示しているものである。
本稿では、事業分離等会計基準及び適用指針の概要について紹介するが、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であることをあらかじめお断りしておく。
Ⅱ 企業結合の会計処理
1. 企業結合とは
企業結合とは、ある企業又はある企業を構成する事業と他の企業又は他の企業を構成する事業とが1つの報告単位に統合されることをいう(企業結合会計基準 二 1.)。例えば、合併の場合は企業と企業とが、また共同新設分割の場合は事業と事業とが1つの報告単位に統合されるので、これらは企業結合に該当する。また、株式交換により、ある企業が他の企業(第三者)を完全子会社とした場合も、連結財務諸表上、企業と企業が1つの報告単位に統合されるので、企業結合に該当する。なお、親会社が子会社を株式交換により完全子会社とする場合は、もともと連結財務諸表上、報告単位は統合されているので、企業結合には該当しないが、企業結合会計基準では、当該取引を少数株主との取引として、その会計処理を定めている。
また、例えば、現金を対価としてある企業の株式を取得して子会社化した場合も、連結財務諸表上、ある企業と他の企業が1つの報告単位に統合されるので、企業結合に該当することになるが、当該会計処理は、企業結合会計基準の定めではなく、連結財務諸表原則の定めに従うことになる(企業結合会計基準 一)。もっとも、この場合も、基本的に取得の会計処理(パーチェス法)と同様の会計処理となる。
2. 企業結合の会計上の分類と適用される会計処理
適用指針では、企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書(以下「企業結合会計意見書」という) 四 3.の定めに従い、組織再編の形式ごと(合併、会社分割、株式交換、株式移転等)に個別財務諸表及び連結財務諸表の会計処理を示している。
ただし、会計上は、組織再編の形式にかかわらず、企業結合の会計上の4つの分類(取得、持分の結合、共同支配企業の形成、共通支配下の取引)ごとに適用すべき会計処理が決定される。
このため、企業結合の会計処理を行うにあたり、最初に、当該企業結合がどの企業結合の分類に識別されるのかを検討しなければならない(【図表1】参照)。
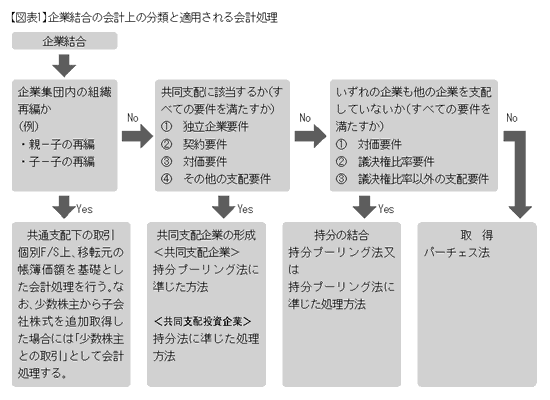
3. 取得と持分の結合の識別
(1)取得と持分の結合とは
共同支配企業の形成又は共通支配下の取引以外の企業結合は、取得又は持分の結合のいずれかに識別されることになる(企業結合会計基準 三 1.(1))。取得とは、ある企業が他の企業又は企業を構成する事業に対する支配を獲得して1つの報告単位となることをいい(企業結合会計基準 二 4.)、持分の結合とは、いずれの企業(又は事業)の株主も他の企業(又は事業)を支配したとは認められず、結合後企業のリスクや便益を引き続き相互に共有することを達成するため、それぞれの事業のすべて又は事実上のすべてを統合して1つの報告単位となることをいう(企業結合会計基準 二 5.)。
取得と持分の結合の識別は、概念上、結合当事企業の株主の持分が継続しているかどうかによることになるが、具体的な判定に当たっては、上記の定義から明らかなように、支配の有無が重視される。
(2)取得と持分の結合の識別規準
取得と持分の結合の識別規準としては、①対価要件、②議決権比率要件、③議決権比率以外の支配要件を順次判定し、すべての要件を満たした場合には持分の結合と判定し、1つでも要件を満たさなかった場合には、その時点で取得と判定することになる(企業結合会計基準 三 1.(1))。また、取得と判定された場合には、取得企業も、同時に決定されることになる(企業結合会計意見書 三 3.(1))。
4. 取得の会計処理
企業結合が取得と判定された場合には、連結財務諸表上及び個別財務諸表上、ともにパーチェス法を適用する(企業結合会計意見書 三 3.(6))。パーチェス法とは、取得企業が被取得企業から受入れる資産及び負債の取得原価を、対価として交付する現金及び株式等の時価とする方法をいう(【図表2】参照)。
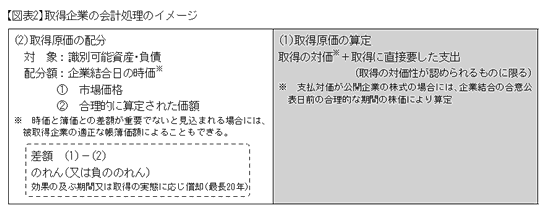
5. 持分の結合の会計処理
企業結合が持分の結合と判定された場合には、【図表3】のように会計処理を行う。
持分プーリング法とは、すべての結合当事企業の資産、負債及び資本(純資産)を、それぞれの適正な帳簿価額で引き継ぐ方法とされている(【図表4】参照)。したがって、結合当事企業の純資産の各項目も、原則として、結合後企業にそのまま引き継がなければならない。
持分プーリング法に準じた処理方法とは、株主資本の内訳の引継方法と企業結合年度の連結財務諸表の作成に係る規定の2点を除き、持分プーリング法と同一の処理方法をいう(企業結合会計基準注解(注15))(【図表5】参照)。事業分離を伴う企業結合においては、分離元企業の資本の内訳に変動は生じないため、分離先企業において、分離元企業の資本構成を引き継ぐことが困難であること等により、持分プーリング法に準じた処理方法を適用することになる。
なお、これらの2つの会計処理に共通する「適正な帳簿価額」とは、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠した帳簿価額をいう(企業結合会計意見書 三 4.(1))。したがって、結合当事企業の帳簿価額に誤りがある場合には、その引継ぎ前に修正が行われることが必要である点に留意する必要がある。また、持分の結合と判定された場合には、企業結合に要した支出額は、すべて費用として処理される。
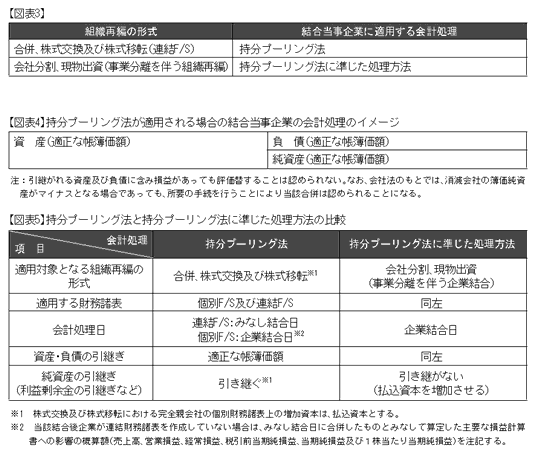
6. 共同支配企業の形成5. 持分の結合の会計処理
(1)共同支配企業及び共同支配投資企業とは
支配従属関係のない2社が、共同支配契約を締結するなど、(2)の要件を満たした合弁会社を設立したものとする。この場合、合弁会社を共同支配企業、合弁会社の株主を共同支配投資企業という(【図表6】参照)。
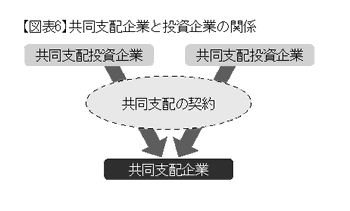
(2)共同支配企業の形成の判定規準
企業結合のうち、①独立企業要件、②契約要件、③対価要件、④その他の支配要件のすべてを満たすものは共同支配企業の形成と判定することになる(企業結合会計基準 二 3.及び同三 1.(2))。
(3)共同支配企業の形成の会計処理
以下では、組織再編の形式として共同新設分割を前提に記載する。
① 共同支配企業(新設分割設立会社)の会計処理
共同支配企業の形成には、持分プーリング法に準じた処理方法を適用する(企業結合会計基準 三 3.(7))。
② 共同支配投資企業(新設分割会社)の会計処理
a 個別財務諸表上の会計処理
共同支配投資企業は、移転した事業に係る資産及び負債の移転直前の適正な帳簿価額による純資産額に基づいて当該共同支配企業に対する投資(新設分割設立会社の株式)の取得原価を算定する(企業結合会計基準 三 3.(7)ただし書き)。したがって、事業の移転時に損益は発生しない。
b 連結財務諸表上の会計処理
共同支配投資企業は、共同支配企業に対する投資について持分法に準ずる処理方法を適用する。持分法に準ずる処理方法とは、企業結合時に生じるのれん(又は負ののれん)及び持分変動差額を認識しない点を除き、持分法と同一の処理方法をいう。したがって、連結財務諸表上も、事業の移転時に損益(持分変動差額)やのれんは発生しない。
7. 共通支配下の取引
(1)共通支配下の取引の範囲
共通支配下の取引とは、親会社と子会社との合併や親会社の支配下にある子会社同士の合併など、結合当事企業(又は事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企業結合をいう(企業結合会計基準 二 10.)(【図表7】参照)。
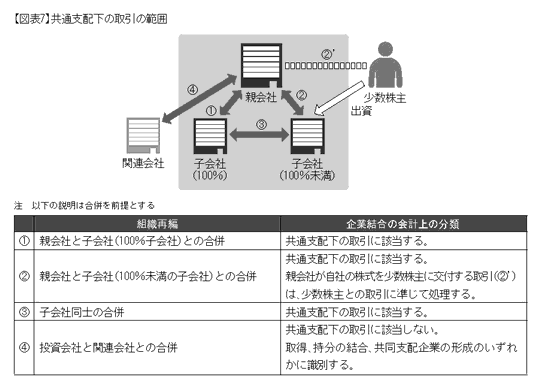
適用指針では、支配の主体である「同一の企業」には個人を含むものとし「同一の株主」として取り扱うこととしている。
(2)共通支配下の取引等の会計処理の概要
企業集団内における組織再編の会計処理には、共通支配下の取引と少数株主との取引(以下、あわせて「共通支配下の取引等」という。)がある。
共通支配下の取引は、親会社の立場からは内部取引と考えられるため、個別財務諸表上、事業の移転元の適正な帳簿価額を基礎として会計処理し、また、連結財務諸表上は、すべて消去することになる。なお、個別財務諸表上の増加する株主資本は原則として払込資本とするが、例えば、事業分離を伴わない組織再編である子会社による親会社の吸収合併や子会社同士の合併で、対価が株式のみの場合については、消滅会社の株主資本の内訳を引継ぐことができる。
一方、少数株主との取引は、親会社が子会社を株式交換により完全子会社とする場合など、親会社が少数株主から子会社株式を追加取得する取引等に適用される。当該取引は、親会社の立場からは外部取引と考えられるため、追加取得した子会社株式の取得原価は時価で算定する。このため、連結財務諸表上は、のれん(又は負ののれん)が計上されることになる。
企業集団内の組織再編の会計処理は、適正な帳簿価額による会計処理を基本としつつ、どの取引を外部取引として捉え、少数株主との取引の会計処理を適用するのか(のれん(又は負ののれん)を認識するのか)が主要な論点となる。適用指針では、組織再編の手法が異なっていても、組織再編後の経済的実態が同じであれば、連結財務諸表上(合併の場合には個別財務諸表上)も同じ結果が得られるように会計処理を定めている。
Ⅲ 事業分離等の会計処理
1. 分離元企業の会計処理
事業分離等会計基準は、一般に事業の成果をとらえる際の「投資の継続・清算」という概念に基づき、実現損益を認識するかどうかという観点から、分離元企業の会計処理を考えている。これは、企業結合の会計処理を一般的な会計処理と整合させるために考えられた「持分の継続・非継続」という概念の根底にある考え方である。
この結果、分離した事業に対する投資が継続しているとみるか清算されたとみるかによって、分離元企業において移転損益が認識される場合と認識されない場合が考えられる。これを判断するための観察可能な具体的要件として、事業分離等会計基準では、一般的な売却や交換の会計処理の考え方を踏まえ、対価が移転した事業と異なるかどうかという「対価の種類」を用い、さらに、企業結合会計基準では、共通支配下の取引の会計処理を定めているため、これとの整合性を前提にして、分離先企業が子会社にあたる場合を手がかりに、分離元企業の会計処理を考えている。
このため、事業分離等会計基準は、まず、受取対価が、(1)現金等の財産のみである場合、(2)分離先企業の株式のみである場合、(3)現金等の財産と分離先企業の株式である場合に大別し、それぞれにおいて、分離先企業が①子会社の場合、②関連会社の場合、③子会社や関連会社以外の場合に分けて、会計処理を定めている。ここでは紙幅の関係により、(1)(2)の概要についてのみ記述する。
(1)受取対価が現金等の財産のみである場合
事業分離により、企業が従来負っていた成果の変動性(すなわち事業投資のリスク)を免れるようになった場合に、当該事業への投資は清算されたものとみなされるため、分離元企業が、現金など、移転した事業と明らかに異なる財産を受取対価としてある事業を移転した場合には、通常、移転損益が認識される。
このとき、分離先企業が子会社となる場合や子会社を分離先企業とする場合には、企業結合会計基準における共通支配下の取引又はこれに準ずる取引に該当し、分離元企業が受け取った現金等の財産の移転前に付された適正な帳簿価額と移転した事業の適正な帳簿価額との間に生ずる差額が移転損益として認識されることとなる。また、分離先企業が子会社以外となる場合には、分離元企業が受け取った現金等の財産の時価と移転した事業の適正な帳簿価額との差額が移転損益として認識されることとなる(【図表8】参照)。
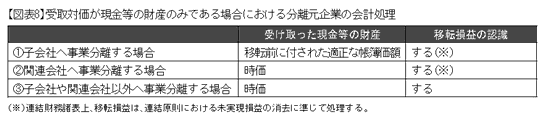
(2)受取対価が分離先企業の株式のみである場合
① 事業分離により分離先企業が子会社となる場合
企業結合会計基準からも明らかなように、この場合には、経済実態として分離元企業における当該事業に対する投資がそのまま継続していると考えられるため、親会社となる分離元企業において移転損益は認識されない。
しかしながら、分離元企業の連結財務諸表上、分離元企業の事業が移転されたとみなされる額(分離元企業の移転した事業の時価に、減少した分離元企業の持分比率を乗じた額)と、移転した事業に係る親会社の持分の減少額(移転した事業に係る適正な帳簿価額による純資産額に減少した分離元企業の持分比率を乗じた額)との差額(脚注2)は、連結原則における子会社の時価発行増資等に伴い生ずる親会社持分の増減額(持分変動差額)として取り扱うものとしている。
また、分離元企業は、分離先企業を取得する(既に子会社である場合の追加取得は「少数株主との取引」に該当する。)ため、連結財務諸表上、パーチェス法を適用し、分離先企業に対して(追加)投資したとみなされる額と、これに対応する分離先企業の事業分離直前の資本との間に生ずる差額については、のれん(又は負ののれん)とすることとなる(【図表9】①参照)。
② 事業分離により分離先企業が関連会社となる場合
この場合、分離元企業による当該事業に対する投資は清算されたものとみて移転損益を認識するという見方と、投資が継続しているものとみて移転損益を認識しないという見方がある。事業分離等会計基準では、(i)関連会社株式は、金融商品会計基準において、子会社株式の場合と同じく事実上の事業投資と同様の会計処理をすることとされていること、(ii)現行の会計基準等では、持分法は連結法(完全連結)のいわば簡便的な会計処理であることなどから、投資の継続に該当するという見方をとっている。
すなわち、事業分離の会計処理を考えるにあたっては、移転された事業に対する分離元企業の支配が継続しているか失われたかが最も重要であるという立場も有力であるが、事業分離等会計基準では、その立場をとってまで他の会計基準等を含む体系に影響を与える意義は薄いという考え方により、必ずしも支配が失われることをもって投資の清算とみることとはしていない(【図表9】②参照)。
(3)分離元企業の税効果会計
適用指針では、分離元企業における繰延税金資産及び繰延税金負債(以下「繰延税金資産等」という。)の計上について、【図表10】のように取扱うこととしている。
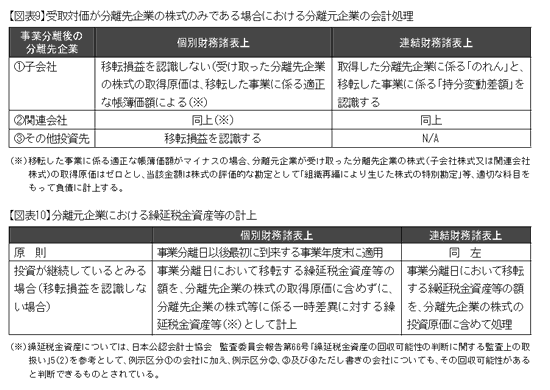
2. 結合当事企業の株主に係る会計処理
(1)被結合企業の株主に係る会計処理
企業結合により、保有していた被結合企業の株式が、結合企業の株式などの財と引き換えられた場合に、その投資が継続しているとみるか清算されたとみるかによって、被結合企業の株主に係る会計処理でも、交換損益が認識される場合と認識されない場合が考えられる。事業分離等会計基準では、事業分離における分離元企業(例えば、吸収分割会社)と、100%子会社を被結合企業とする企業結合における当該被結合企業の株主(親会社)とでは、経済的効果が実質的に同じであることから、両者の会計処理を整合的なものとしている。さらに、被結合企業の株主が親会社である場合には、被結合企業の株式をすべて保有しているとき(被結合企業が100%子会社の場合)でも、すべては保有していないとき(被結合企業が100%子会社以外の子会社の場合)でも整合的な会計処理とすることが適当とされている。
このため、分離元企業の会計処理と同様に、まず、受取対価が、(1)現金等の財産のみである場合(【図表11】参照)、(2)結合企業の株式のみである場合(【図表12】参照)、(3)現金等の財産と結合企業の株式である場合に大別し、それぞれにおいて、被結合企業が①子会社の場合、②関連会社の場合、③子会社や関連会社以外の場合に分けて、会計処理を定めている。
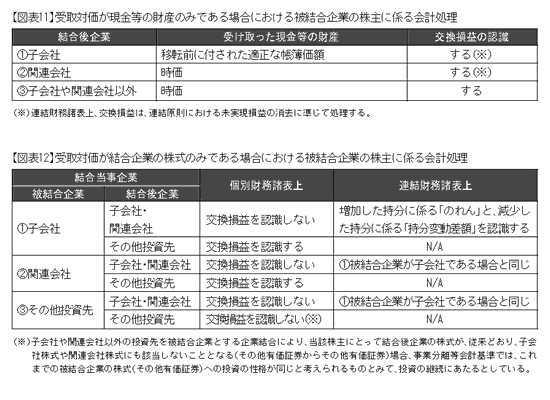
(2)結合企業の株主に係る会計処理
個々の株主にとっては、企業結合により被結合企業の株主が新たに結合企業の株主となる場合であっても、引き続き結合企業の株主である場合であっても、その経済的効果は実質的に同じであるものと考えられる。このため、事業分離等会計基準では、結合企業の株主に係る会計処理は、受取対価が結合企業の株式のみである場合の被結合企業の株主に係る会計処理に準じて定めている。
(3)分割型の会社分割における分割会社の株主及び現金以外の財産の分配を受けた場合の株主に係る会計処理
いわゆる分割型の会社分割や現物配当については企業結合に該当しないが、事業分離等会計基準では、当該分割会社の株主に係る会計処理や、株主が現物分配(現金以外の財産の分配)を受けた場合における当該株主の会計処理も定めている。
Ⅳ 適用時期
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準の適用時期は、平成18年4月1日以後開始事業年度から適用することになるが、会社法は、事業年度にかかわりなく、企業結合日又は事業分離日が会社法施行日以後の企業結合又は事業分離について適用される。このため、以下の期間における企業結合又は事業分離等に係る会計処理は、次のように取扱うことになると考えられる。
(1)平成18年4月1日以後に開始する事業年度のうち、会社法施行期日前の期間(会社法適用前期間)における取扱い
企業結合日又は事業分離日が会社法適用前期間となる企業結合又は事業分離等に係る会計処理については、旧商法に定める範囲内で企業結合会計基準又は事業分離等会計基準を適用することとなる。なお、例えば、合併期日が平成18年4月1日であり、企業結合会計基準に従ってのれんを計上し、これを20年以内の期間で償却することは、その償却を行うこととなる事業年度末において会社法が施行されている場合には、認められる。
(2)平成18年3月31日以前に開始する事業年度のうち、会社法施行期日以後の期間(会社法適用後期間)における取扱い
企業結合会計基準及び事業分離等会計基準の適用前であるが、これらの会計基準に準じて処理することができる。
なお、会社法適用後期間においては、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う(会社法第431条)とともに、会社法に関する法務省令に準拠することに留意する必要がある。
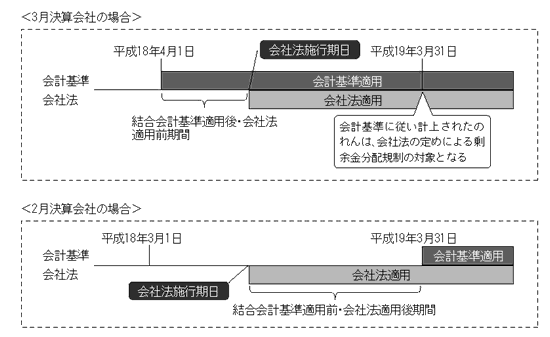
脚注
1 これらの全文については、ASBJのホームページ(http://www.asb.or.jp/j_technical_topics_reports/combination/)参照のこと。
2 これは、移転した事業の適正な帳簿価額による純資産額とこれに対応する分離元企業(親会社)の持分との差額にあたる。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















