解説記事2006年02月27日 【会社法解説】 図解でわかる法務省令講座―株式・新株予約権・社債の要点―(2006年2月27日号・№152)
図解でわかる法務省令講座
―株式・新株予約権・社債の要点―
法務省民事局付 郡谷大輔
前回までに公布版法務省令の全体像を俯瞰した上で、新法下の株主総会に関する規律をまとめて解説した。今回は、会社法施行規則に規定する株式、新株予約権および社債に関する規律について述べる。これらに関する省令委任事項は多岐にわたるため、本稿で最重要ポイントを押さえたい。
人物紹介
マミ 霞が関の監査法人に勤める公認会計士。経済産業省・法務省において政策立案・立法作業に携わる。そのビボウに加え、ポンチ絵や図表の作成でも非凡な才能を発揮することから、同僚は「ビジュアル・クィーン」と呼ぶ。
カナ 赤坂の法律事務所に勤める弁護士。法務省において立法作業に携わる。各方面からの問合せや同僚の不適切な発言をときに厳しく、ときに平然とさばく姿勢には定評がある。マミの指導のもと、会計の勉強中。
Ⅰ 株式・新株予約権
1 種類株式
施行規則20条は、ある種類の株式の内容について、定款ではその要綱のみを定め、その後の株主総会・取締役会等において具体的な内容を定めることができる事項(会社法108条3項参照)を規定したものである。
具体的に、定款で定めなければならない事項は、図表1のとおりである。
施行規則20条1項においては、対価の種類や決議事項など予め定めることが容易なもの、実質的には事後に定めることとなるもの、定めの内容が平等ではないものなどが定款で定めなければならない事項とされている。
なお、株式の譲渡制限に関する事項(会社法108条2項4号)や、会社法108条2項各号に掲げる事項以外の株式の種類ごとに定款の定めを設けることができる権利の内容については、定款でその内容を定めなければならない。
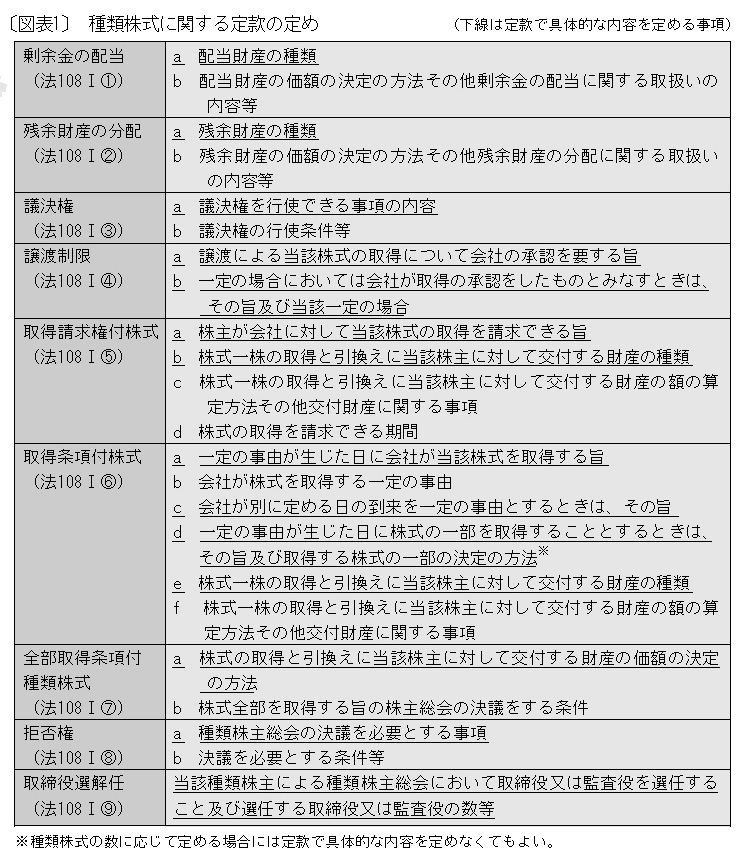
2 株式の名義書換の手続
施行規則22条は、譲渡人および譲受人の共同申請によらなくても、名義書換請求ができる場合を規定したものである。
(1)株券を発行していない場合
株券を発行していない株式について、単独で請求が可能な場合とは、次のとおりである(施行規則22条1項)。
① 確定判決等がある場合
a 株式取得者が株主として株主名簿に記載がされた者(またはその一般承継人)に対して、当該株式取得者の取得した株式に係る株主名簿記載事項の株主名簿への記載等の請求(会社法133条1項の規定による請求)をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項1号)
b 株式取得者がaの確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項2号)
② 株式会社が譲受人を承知している場合
a 株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項3号)
b 株式取得者が会社法197条(株式の競売)1項の株式を取得した者である場合において、同条2項の規定による売却代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項8号)
c 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く)(同項9号)
③ 株式交換・株式移転の場合
a 株式取得者が株式交換により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、請求をしたとき(同項6号)
b 株式取得者が株式移転により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、請求をしたとき(同項7号)
④ その他単独請求を認めることが相当な場合
a 株式取得者が一般承継により当該株式会社 の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項4号)
b 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項5号)
(2)株券を発行している場合
株券を発行している場合について、単独請求が可能な場合とは、次のとおりである(施行規則22条2項)。
原則としては、株券を提示して請求することとなる(同項1号)が、株式交換(同項2号)・株式移転(同項3号)・所在不明株主の株式の売却(同項4号)については、株券を提示しなくても譲受人が単独で請求することができるものとしている。
株券を発行していない場合との差異をみると、確定判決を得た場合や競売の場合等は、株券を提示して請求することとなるため、そのような場合については特別な定めを設けていない。
3 子会社による親会社株式の取得
施行規則23条は、子会社による親会社株式の取得が許される場合(会社法135条2項1号から4号までに掲げられている場合を除く)について規定するものである。
取得事由の分類に応じて、子会社が親会社株式を取得できる場合とは、図表2のとおりである。
なお、親会社株式を無償で取得する場合、連結配当規制適用会社の子会社同士が譲渡する場合も、現行法と異なり、子会社による親会社株式取得の禁止の例外とされている(同項4号・12号)。
これらのうち、連結配当規制適用会社の子会社の場合、会社法上の要請としては、その保有する親会社株式を早期に処分する必要性自体が乏しくなっており、会社法135条3項の「相当の時期」の解釈についても、連結配当規制適用会社以外の子会社とは異なったものとなると考えられる。
このため、親会社株式の貸借対照表上の表示区分についても、現行法のように流動資産に限定する(現行商法施行規則58条)ことなく、「親会社株式の各表示区分別の金額」を注記させることとし、場合によっては投資その他の資産として計上することもありうることを想定している(会社計算規則134条9号)。
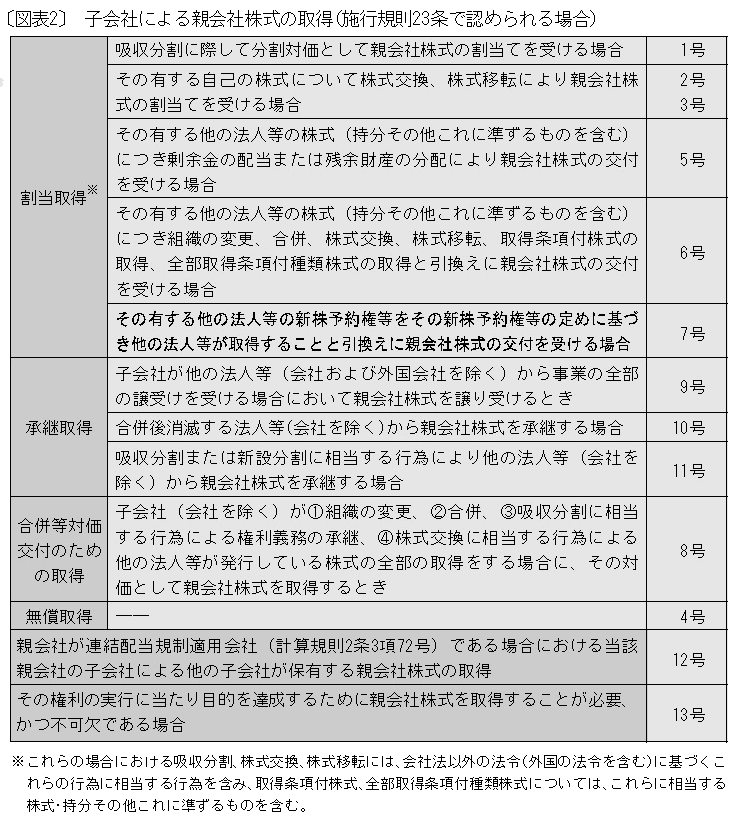
4 一株当たり純資産額
施行規則25条は、一株当たり純資産額の算定方法について規律している。
現行商法では、一株当たり純資産額の算定方法については特に規定を設けていなかったが、会社法では、一株当たり純資産額の算定に当たっての自己株式・種類株式の取扱い、算定基準日等を明らかにしている。
具体的には、図表3のとおりである。
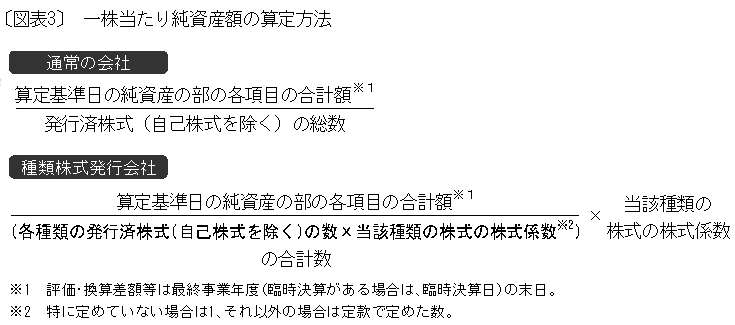
5 自己株式の取得
施行規則27条は、会社法155条1号から12号までに該当する場合以外に、株式会社が自己株式を取得することができる場合について規定している。
施行規則の規定による自己株式を取得できる場合とは、図表4のとおりである。
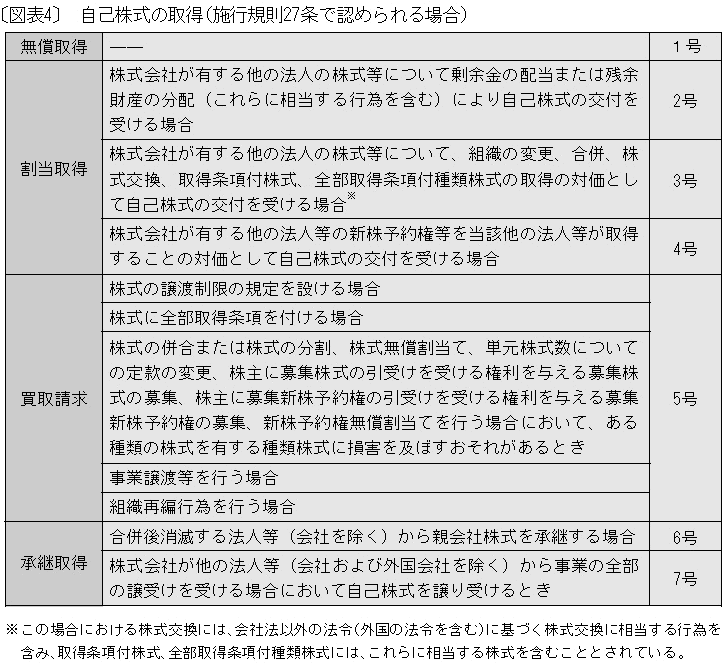
6 市場価格
会社法の各種の行為によって、株式、社債等について、1に満たない端数が生ずる場合や単元未満株式の買取請求等があった場合には、当該株式等の価格の決定方法として、市場価格が用いられる。
この場合の市場価格については、施行規則全体を通じて同様の基準が定められており、具体的には、図表5のような方法によって決定される。
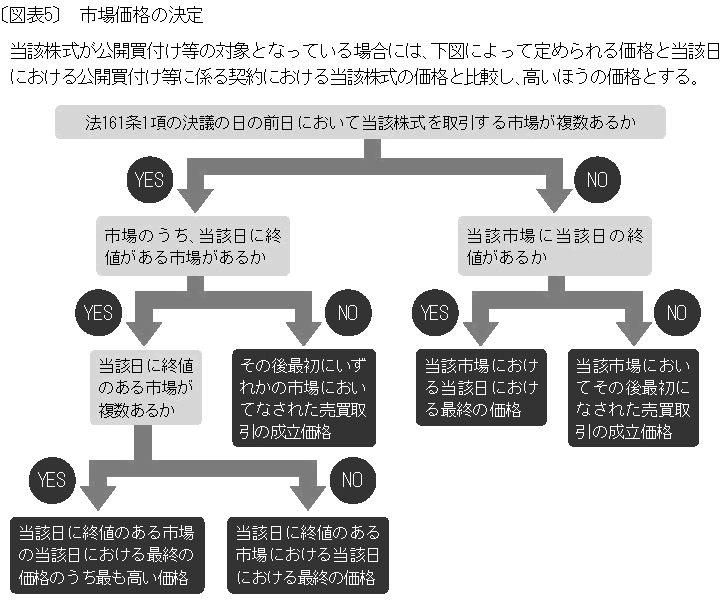
POINT~ここに注意~
・種類株式
~定款で定めるべき事項が列挙されている。
・名義書換
~単独で名義書換請求ができる場合が列挙されている。
・子会社による親会社株式の取得
~子会社による親会社株式取得ができる場合が列挙されている。
7 単元株式数
(1)数の制限
施行規則34条は、単元株式数の制限についての規律である。施行規則では、千を超えてはならないとするのみであり、現行商法で設けられている発行済株式の総数の200分の1に当たる数未満という規制は、廃止している。
(2)単元未満株式についての権利
施行規則35条は、定款の定めによっても奪うことができない単元未満株式の権利について規定している。
その内容と現行商法の端株主の権利とを比較すると、図表6のとおりとなっている。
8 募集手続
(1)株主に通知を要しない場合
施行規則40条は、公開会社が取締役会において募集事項を定めた場合において、株主に対する通知・公告をしなくてもよい場合について定めるものである。
具体的には、有価証券届出書(証券取引法4条1項または2項、5条1項)、発行登録書(同法23条の3第1項)、発行登録追補書類(同法23条の8第1項)等が提出され、縦覧に供されているような場合である。
(2)引受申込者に通知すべき事項
施行規則41条は、募集株式の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項のうち、会社法203条1項1号から3号までに掲げられている事項以外の事項を定めている。
具体的には、発行可能株式総数、発行可能種類株式総数、各種類の株式の内容、単元株式数、特定の事項についての定款の定めがある場合におけるその規定、その他定款に定めがある事項であって申込みをしようとした者が請求した事項がこれに該当する。
(3)引受申込者に通知を要しない場合
施行規則42条は、募集株式の申込みをしようとする者に対する募集事項等の通知(会社法203条1項)を省略できる場合を定めている。
これは、証券取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合など、実質的に当該通知と同等である行為をした場合には、会社法203条1項の通知を不要とするものである。
9 パブリック・コメント版からの変更
株式に係る規定のパブリック・コメント版からの主な変更点をまとめると、図表7のとおりである。
10 新株予約権
施行規則2編3章は、新株予約権に関する省令委任事項を定めているが、その内容は、相当する株式に関する委任事項と基本的に変わりはない。
施行規則の具体的な対応関係は、図表8のとおりである。
これまでに掲げたPoint~ここに注意~も、新株予約権について読み替えられるものとなっていので参照されたい。
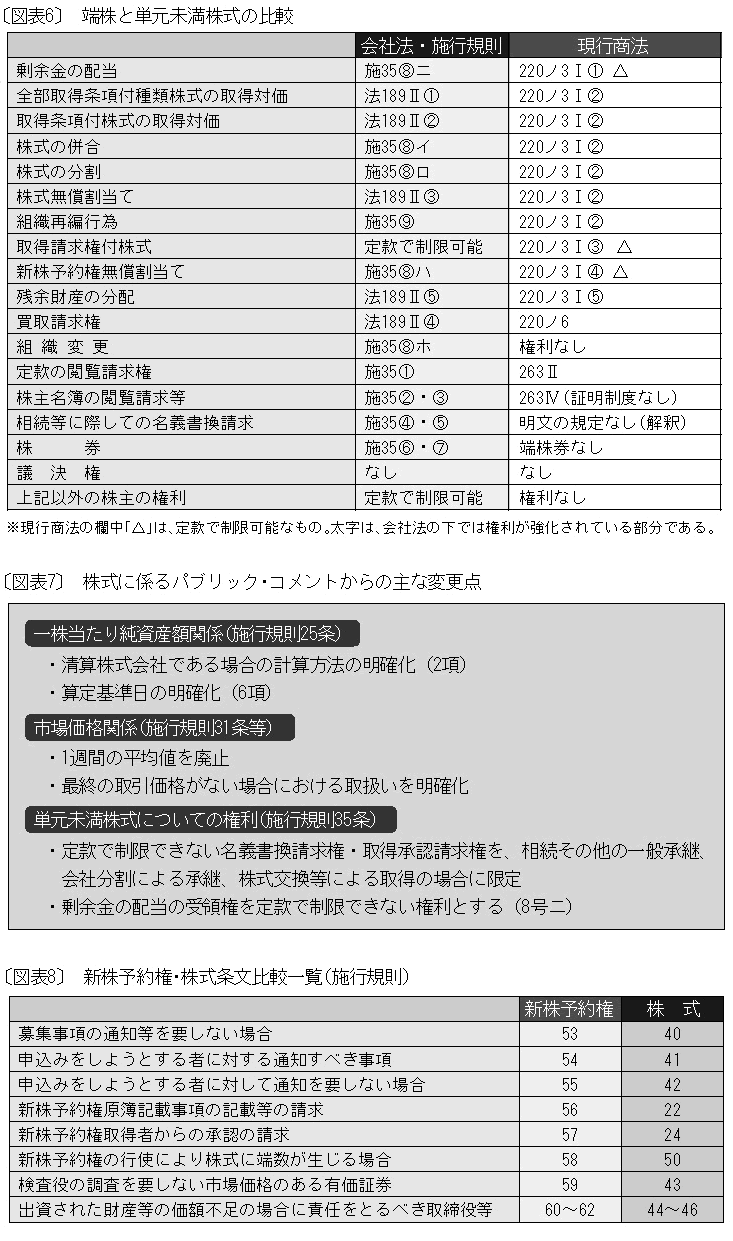
POINT~ここに注意~
・市場価格
~市場価格は、最終取引価格を基本として、TOB価格なども考慮して定められる。
・単元株式数
~単元株式数は、千を超えてはならない。
~単元未満株主の権利については、制限できない権利が列挙されている。
~剰余金の配当は制限することができない。
・募集手続
~一定の通知を要しない場合等が定められている。
Ⅱ 社 債
1 取締役会の決議
施行規則99条は、取締役会設置会社において、募集社債を引き受ける者を募集する際、その都度決定すべき募集事項のうち、特定の取締役に委任することができず、取締役会の決議で決定しなければならない事項を定めるものである。
具体的には、
▲二以上の募集に係る募集事項の決定を取締役に委任するときは、その旨(同条1号)
▲募集社債の総額(二以上の募集を委任する場合には、各募集に係る募集社債の総額)の上限(同条2号)
▲募集社債の利率に関する事項の要綱(同条3号)
▲募集社債の払込金額に関する事項の要綱(同条4号)
が掲げられている。
2 種 類
施行規則165条は、社債の種類について定める。
本条各号に掲げる事項、すなわち、社債の権利の内容が同一であれば、その発行時期等の如何にかかわらず同一の「種類」の社債となって、いわゆる「銘柄統合」がされることになる。
社債の種類を特定する事項について、具体的には、次のとおりとなっている。
▲社債の利率(同条1号)
▲社債の償還の方法および期限(同条2号)
▲利息支払の方法および期限(同条3号)
▲社債券を発行するときは、その旨(同条4号)
▲社債権者が記名式と無記名式との間の転換の請求(会社法698条の規定による請求)の全部または一部をすることができないこととするときは、その旨(同条5号)
▲社債管理者が社債権者集会の決議によらずに当該社債の全部についてする訴訟行為等(会社法706条1項2号に掲げる行為)をすることができることとするときは、その旨(同条6号)
▲他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨および各会社の負担部分(同条7号)
▲社債管理者を定めたときは、その名称および住所ならびに社債管理者に対する弁済の受領等の委託(会社法702条の規定による委託)に係る契約の内容(同条8号)
▲社債原簿管理人を定めたときは、その氏名または名称および住所(同条9号)
▲社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)19条1項1号、11号および13号に掲げる事項(同条10号)
3 社債管理者
(1)社債管理者を設置することを要しない場合
現行商法は、各社債の金額が1億円以上である場合および社債の総額を社債の最低額をもって除した額が50未満である場合には、社債管理者の設置義務を負わないものとされている(現行商法297条)。
前者の場合は、会社法702条で規律されているが、後者については、施行規則169条で「ある種類の社債の総額を各社債の金額の最低額で除した数が50未満である場合」と規定して、その実質を維持している。
なお、50で除すべきものは、「募集社債」ではなく、「ある種類の社債」の総額であるから、その数が50未満であったが、銘柄統合により、同一種類の社債に係る当該数が増加して50以上となる場合にも、社債管理者の設置義務が課せられることとなる。
このような場合には、社債管理者の設置義務が生じた時点で、会社は社債権者集会を開催し、社債管理者を選任しなければならないこととなる。
(2)社債管理者の資格
施行規則170条は、社債管理者となることができる者としての資格のうち、会社法に規定しない資格を定めるものである。
現行法では、保険業法、信用金庫法など、他の金融機関等に関する法律で社債管理会社となることができるものとされていた金融機関を列挙するものである。
具体的にこれらの金融機関を挙げると、
▲商工組合中央金庫、農林中央金庫(同条2号、9号)
▲信用事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会および協同組合連合会(同条3号、4号)
▲信用協同組合、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会(同条4号~6号)
▲長期信用銀行(同条7号)
▲保険会社(同条8号)
となっている。
なお、同条1号に規定する担保付社債信託法5条1項の免許を受けた者は、現行商法に規定されているものである。
(3)特別の関係
施行規則171条は、社債発行会社が社債の償還もしくは利息の支払いを怠るなどした後またはその前3か月以内に、社債管理者が自らの債権を譲り渡したことについて、反証のない限り損害賠償責任を負うことになる当該社債管理者とその譲受人とに「特別の関係」があるとされる場合を定めるものである。
具体的には、直接または間接に、当該社債管理者と形式的な基準(議決権の50%超)により親子会社関係になっている場合である(同条1項1号、2項参照)。
なお、会社法における親子会社のように特別の関係について実質支配力基準を用いなかったのは、この規律の趣旨が立証責任が転換される基準を設定するためのものであり、仮にその基準自体に実質支配力基準を用いると、そもそもその基準に該当するかどうかの立証を社債権者がすることとなり、社債権者の立証の負担を軽減しようとする趣旨が失われるおそれがあるからである。
POINT~ここに注意~
・社 債
~募集事項のうち、取締役会設置会社において取締役会で決めなければならない事項を明確に定めている。
・種 類
~発行時期にかかわらず、同じ内容の社債は同じ種類と扱うことができるが、その種類を特定するための事項について定めている。
今週のおさらい3
● 種類株式の内容の一部は定款でその要綱を規定
株式の譲渡制限に関する事項等は定款でその内容を規定する。
● 子会社による親会社株式の取得ができる場合、自己株式の取得ができる場合を列挙
子会社による親会社株式取得は施行規則23条、自己株式取得は27条を参照する。
● 一株当たり純資産額の算定方法を規定
自己株式・種類株式の取扱い、算定基準日等を明らかにした。
● 募集株式の発行時に株主等への通知を省略できる場合を規定
募集株式の引受申込者に対する通知についても同様の規定を置いている。
● 募集社債の取締役会決議事項を明確化
社債の種類、社債管理者の資格に関する詳細も列挙されている。
―株式・新株予約権・社債の要点―
法務省民事局付 郡谷大輔
前回までに公布版法務省令の全体像を俯瞰した上で、新法下の株主総会に関する規律をまとめて解説した。今回は、会社法施行規則に規定する株式、新株予約権および社債に関する規律について述べる。これらに関する省令委任事項は多岐にわたるため、本稿で最重要ポイントを押さえたい。
人物紹介
マミ 霞が関の監査法人に勤める公認会計士。経済産業省・法務省において政策立案・立法作業に携わる。そのビボウに加え、ポンチ絵や図表の作成でも非凡な才能を発揮することから、同僚は「ビジュアル・クィーン」と呼ぶ。
カナ 赤坂の法律事務所に勤める弁護士。法務省において立法作業に携わる。各方面からの問合せや同僚の不適切な発言をときに厳しく、ときに平然とさばく姿勢には定評がある。マミの指導のもと、会計の勉強中。
Ⅰ 株式・新株予約権
1 種類株式
施行規則20条は、ある種類の株式の内容について、定款ではその要綱のみを定め、その後の株主総会・取締役会等において具体的な内容を定めることができる事項(会社法108条3項参照)を規定したものである。
具体的に、定款で定めなければならない事項は、図表1のとおりである。
施行規則20条1項においては、対価の種類や決議事項など予め定めることが容易なもの、実質的には事後に定めることとなるもの、定めの内容が平等ではないものなどが定款で定めなければならない事項とされている。
なお、株式の譲渡制限に関する事項(会社法108条2項4号)や、会社法108条2項各号に掲げる事項以外の株式の種類ごとに定款の定めを設けることができる権利の内容については、定款でその内容を定めなければならない。
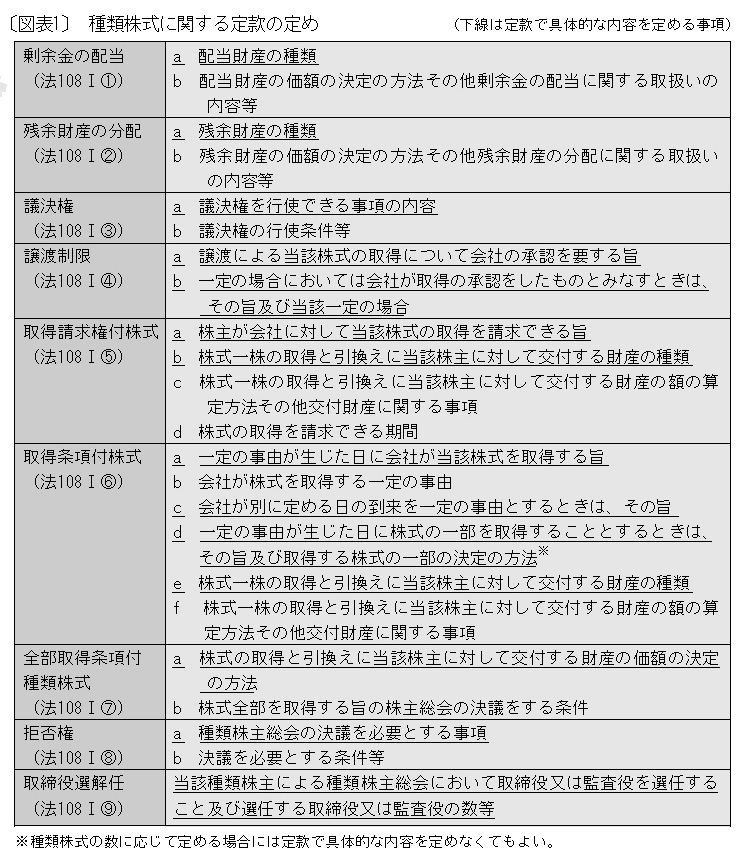
2 株式の名義書換の手続
施行規則22条は、譲渡人および譲受人の共同申請によらなくても、名義書換請求ができる場合を規定したものである。
(1)株券を発行していない場合
株券を発行していない株式について、単独で請求が可能な場合とは、次のとおりである(施行規則22条1項)。
① 確定判決等がある場合
a 株式取得者が株主として株主名簿に記載がされた者(またはその一般承継人)に対して、当該株式取得者の取得した株式に係る株主名簿記載事項の株主名簿への記載等の請求(会社法133条1項の規定による請求)をすべきことを命ずる確定判決を得た場合において、当該確定判決の内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項1号)
b 株式取得者がaの確定判決と同一の効力を有するものの内容を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項2号)
② 株式会社が譲受人を承知している場合
a 株式取得者が指定買取人である場合において、譲渡等承認請求者に対して売買代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項3号)
b 株式取得者が会社法197条(株式の競売)1項の株式を取得した者である場合において、同条2項の規定による売却代金の全部を支払ったことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項8号)
c 株式取得者が株券喪失登録者である場合において、当該株式取得者が株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日以降に、請求をしたとき(株券喪失登録が当該日前に抹消された場合を除く)(同項9号)
③ 株式交換・株式移転の場合
a 株式取得者が株式交換により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した会社である場合において、請求をしたとき(同項6号)
b 株式取得者が株式移転により当該株式会社の発行済株式の全部を取得した株式会社である場合において、請求をしたとき(同項7号)
④ その他単独請求を認めることが相当な場合
a 株式取得者が一般承継により当該株式会社 の株式を取得した者である場合において、当該一般承継を証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項4号)
b 株式取得者が当該株式会社の株式を競売により取得した者である場合において、当該競売により取得したことを証する書面その他の資料を提供して請求をしたとき(同項5号)
(2)株券を発行している場合
株券を発行している場合について、単独請求が可能な場合とは、次のとおりである(施行規則22条2項)。
原則としては、株券を提示して請求することとなる(同項1号)が、株式交換(同項2号)・株式移転(同項3号)・所在不明株主の株式の売却(同項4号)については、株券を提示しなくても譲受人が単独で請求することができるものとしている。
株券を発行していない場合との差異をみると、確定判決を得た場合や競売の場合等は、株券を提示して請求することとなるため、そのような場合については特別な定めを設けていない。
3 子会社による親会社株式の取得
施行規則23条は、子会社による親会社株式の取得が許される場合(会社法135条2項1号から4号までに掲げられている場合を除く)について規定するものである。
取得事由の分類に応じて、子会社が親会社株式を取得できる場合とは、図表2のとおりである。
なお、親会社株式を無償で取得する場合、連結配当規制適用会社の子会社同士が譲渡する場合も、現行法と異なり、子会社による親会社株式取得の禁止の例外とされている(同項4号・12号)。
これらのうち、連結配当規制適用会社の子会社の場合、会社法上の要請としては、その保有する親会社株式を早期に処分する必要性自体が乏しくなっており、会社法135条3項の「相当の時期」の解釈についても、連結配当規制適用会社以外の子会社とは異なったものとなると考えられる。
このため、親会社株式の貸借対照表上の表示区分についても、現行法のように流動資産に限定する(現行商法施行規則58条)ことなく、「親会社株式の各表示区分別の金額」を注記させることとし、場合によっては投資その他の資産として計上することもありうることを想定している(会社計算規則134条9号)。
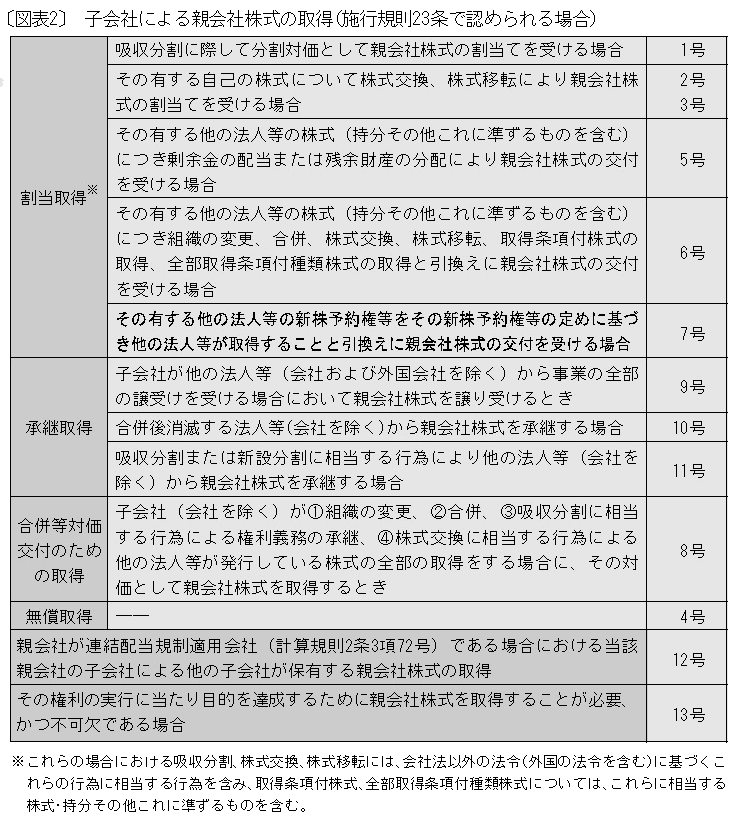
4 一株当たり純資産額
施行規則25条は、一株当たり純資産額の算定方法について規律している。
現行商法では、一株当たり純資産額の算定方法については特に規定を設けていなかったが、会社法では、一株当たり純資産額の算定に当たっての自己株式・種類株式の取扱い、算定基準日等を明らかにしている。
具体的には、図表3のとおりである。
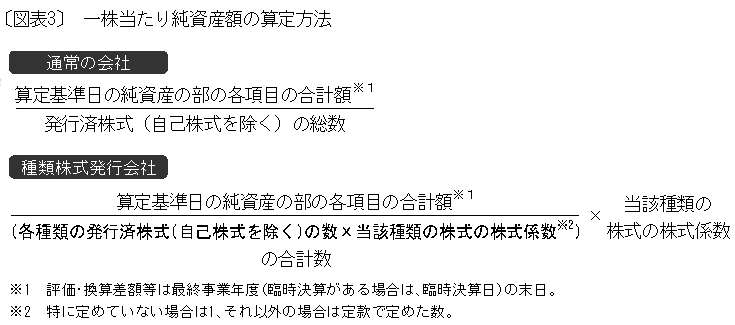
5 自己株式の取得
施行規則27条は、会社法155条1号から12号までに該当する場合以外に、株式会社が自己株式を取得することができる場合について規定している。
施行規則の規定による自己株式を取得できる場合とは、図表4のとおりである。
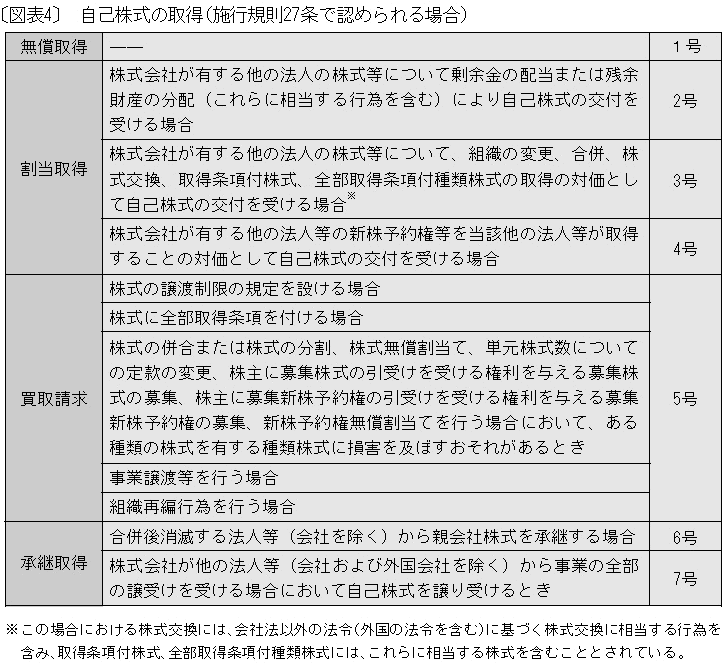
6 市場価格
会社法の各種の行為によって、株式、社債等について、1に満たない端数が生ずる場合や単元未満株式の買取請求等があった場合には、当該株式等の価格の決定方法として、市場価格が用いられる。
この場合の市場価格については、施行規則全体を通じて同様の基準が定められており、具体的には、図表5のような方法によって決定される。
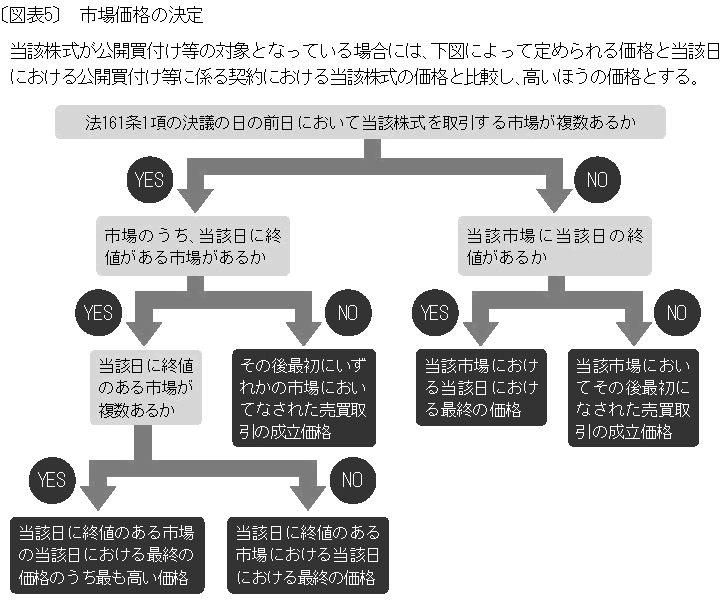
POINT~ここに注意~
・種類株式
~定款で定めるべき事項が列挙されている。
・名義書換
~単独で名義書換請求ができる場合が列挙されている。
・子会社による親会社株式の取得
~子会社による親会社株式取得ができる場合が列挙されている。
7 単元株式数
(1)数の制限
施行規則34条は、単元株式数の制限についての規律である。施行規則では、千を超えてはならないとするのみであり、現行商法で設けられている発行済株式の総数の200分の1に当たる数未満という規制は、廃止している。
(2)単元未満株式についての権利
施行規則35条は、定款の定めによっても奪うことができない単元未満株式の権利について規定している。
その内容と現行商法の端株主の権利とを比較すると、図表6のとおりとなっている。
8 募集手続
(1)株主に通知を要しない場合
施行規則40条は、公開会社が取締役会において募集事項を定めた場合において、株主に対する通知・公告をしなくてもよい場合について定めるものである。
具体的には、有価証券届出書(証券取引法4条1項または2項、5条1項)、発行登録書(同法23条の3第1項)、発行登録追補書類(同法23条の8第1項)等が提出され、縦覧に供されているような場合である。
(2)引受申込者に通知すべき事項
施行規則41条は、募集株式の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項のうち、会社法203条1項1号から3号までに掲げられている事項以外の事項を定めている。
具体的には、発行可能株式総数、発行可能種類株式総数、各種類の株式の内容、単元株式数、特定の事項についての定款の定めがある場合におけるその規定、その他定款に定めがある事項であって申込みをしようとした者が請求した事項がこれに該当する。
(3)引受申込者に通知を要しない場合
施行規則42条は、募集株式の申込みをしようとする者に対する募集事項等の通知(会社法203条1項)を省略できる場合を定めている。
これは、証券取引法の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合など、実質的に当該通知と同等である行為をした場合には、会社法203条1項の通知を不要とするものである。
9 パブリック・コメント版からの変更
株式に係る規定のパブリック・コメント版からの主な変更点をまとめると、図表7のとおりである。
10 新株予約権
施行規則2編3章は、新株予約権に関する省令委任事項を定めているが、その内容は、相当する株式に関する委任事項と基本的に変わりはない。
施行規則の具体的な対応関係は、図表8のとおりである。
これまでに掲げたPoint~ここに注意~も、新株予約権について読み替えられるものとなっていので参照されたい。
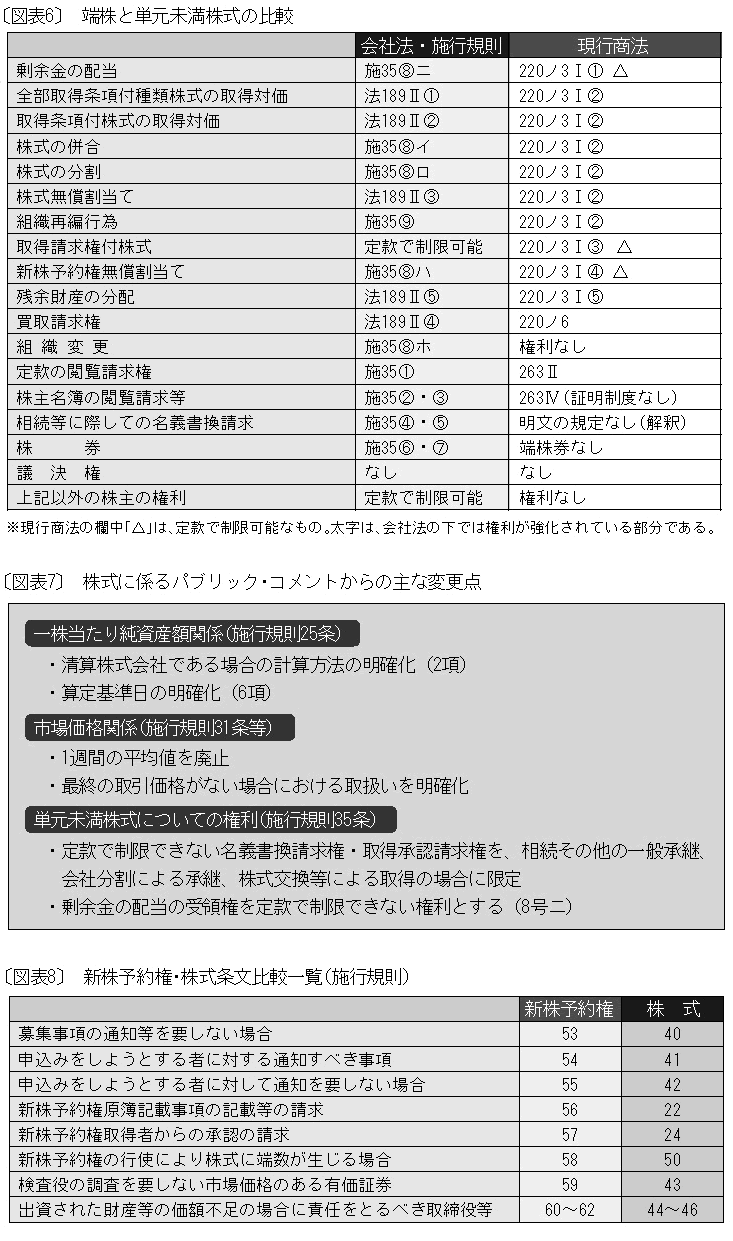
POINT~ここに注意~
・市場価格
~市場価格は、最終取引価格を基本として、TOB価格なども考慮して定められる。
・単元株式数
~単元株式数は、千を超えてはならない。
~単元未満株主の権利については、制限できない権利が列挙されている。
~剰余金の配当は制限することができない。
・募集手続
~一定の通知を要しない場合等が定められている。
Ⅱ 社 債
1 取締役会の決議
施行規則99条は、取締役会設置会社において、募集社債を引き受ける者を募集する際、その都度決定すべき募集事項のうち、特定の取締役に委任することができず、取締役会の決議で決定しなければならない事項を定めるものである。
具体的には、
▲二以上の募集に係る募集事項の決定を取締役に委任するときは、その旨(同条1号)
▲募集社債の総額(二以上の募集を委任する場合には、各募集に係る募集社債の総額)の上限(同条2号)
▲募集社債の利率に関する事項の要綱(同条3号)
▲募集社債の払込金額に関する事項の要綱(同条4号)
が掲げられている。
2 種 類
施行規則165条は、社債の種類について定める。
本条各号に掲げる事項、すなわち、社債の権利の内容が同一であれば、その発行時期等の如何にかかわらず同一の「種類」の社債となって、いわゆる「銘柄統合」がされることになる。
社債の種類を特定する事項について、具体的には、次のとおりとなっている。
▲社債の利率(同条1号)
▲社債の償還の方法および期限(同条2号)
▲利息支払の方法および期限(同条3号)
▲社債券を発行するときは、その旨(同条4号)
▲社債権者が記名式と無記名式との間の転換の請求(会社法698条の規定による請求)の全部または一部をすることができないこととするときは、その旨(同条5号)
▲社債管理者が社債権者集会の決議によらずに当該社債の全部についてする訴訟行為等(会社法706条1項2号に掲げる行為)をすることができることとするときは、その旨(同条6号)
▲他の会社と合同して募集社債を発行するときは、その旨および各会社の負担部分(同条7号)
▲社債管理者を定めたときは、その名称および住所ならびに社債管理者に対する弁済の受領等の委託(会社法702条の規定による委託)に係る契約の内容(同条8号)
▲社債原簿管理人を定めたときは、その氏名または名称および住所(同条9号)
▲社債が担保付社債であるときは、担保付社債信託法(明治38年法律第52号)19条1項1号、11号および13号に掲げる事項(同条10号)
3 社債管理者
(1)社債管理者を設置することを要しない場合
現行商法は、各社債の金額が1億円以上である場合および社債の総額を社債の最低額をもって除した額が50未満である場合には、社債管理者の設置義務を負わないものとされている(現行商法297条)。
前者の場合は、会社法702条で規律されているが、後者については、施行規則169条で「ある種類の社債の総額を各社債の金額の最低額で除した数が50未満である場合」と規定して、その実質を維持している。
なお、50で除すべきものは、「募集社債」ではなく、「ある種類の社債」の総額であるから、その数が50未満であったが、銘柄統合により、同一種類の社債に係る当該数が増加して50以上となる場合にも、社債管理者の設置義務が課せられることとなる。
このような場合には、社債管理者の設置義務が生じた時点で、会社は社債権者集会を開催し、社債管理者を選任しなければならないこととなる。
(2)社債管理者の資格
施行規則170条は、社債管理者となることができる者としての資格のうち、会社法に規定しない資格を定めるものである。
現行法では、保険業法、信用金庫法など、他の金融機関等に関する法律で社債管理会社となることができるものとされていた金融機関を列挙するものである。
具体的にこれらの金融機関を挙げると、
▲商工組合中央金庫、農林中央金庫(同条2号、9号)
▲信用事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会および協同組合連合会(同条3号、4号)
▲信用協同組合、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫連合会(同条4号~6号)
▲長期信用銀行(同条7号)
▲保険会社(同条8号)
となっている。
なお、同条1号に規定する担保付社債信託法5条1項の免許を受けた者は、現行商法に規定されているものである。
(3)特別の関係
施行規則171条は、社債発行会社が社債の償還もしくは利息の支払いを怠るなどした後またはその前3か月以内に、社債管理者が自らの債権を譲り渡したことについて、反証のない限り損害賠償責任を負うことになる当該社債管理者とその譲受人とに「特別の関係」があるとされる場合を定めるものである。
具体的には、直接または間接に、当該社債管理者と形式的な基準(議決権の50%超)により親子会社関係になっている場合である(同条1項1号、2項参照)。
なお、会社法における親子会社のように特別の関係について実質支配力基準を用いなかったのは、この規律の趣旨が立証責任が転換される基準を設定するためのものであり、仮にその基準自体に実質支配力基準を用いると、そもそもその基準に該当するかどうかの立証を社債権者がすることとなり、社債権者の立証の負担を軽減しようとする趣旨が失われるおそれがあるからである。
POINT~ここに注意~
・社 債
~募集事項のうち、取締役会設置会社において取締役会で決めなければならない事項を明確に定めている。
・種 類
~発行時期にかかわらず、同じ内容の社債は同じ種類と扱うことができるが、その種類を特定するための事項について定めている。
今週のおさらい3
● 種類株式の内容の一部は定款でその要綱を規定
株式の譲渡制限に関する事項等は定款でその内容を規定する。
● 子会社による親会社株式の取得ができる場合、自己株式の取得ができる場合を列挙
子会社による親会社株式取得は施行規則23条、自己株式取得は27条を参照する。
● 一株当たり純資産額の算定方法を規定
自己株式・種類株式の取扱い、算定基準日等を明らかにした。
● 募集株式の発行時に株主等への通知を省略できる場合を規定
募集株式の引受申込者に対する通知についても同様の規定を置いている。
● 募集社債の取締役会決議事項を明確化
社債の種類、社債管理者の資格に関する詳細も列挙されている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
最近閲覧した記事
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























