解説記事2006年03月27日 【解説】 議案の決定と定款変更(1)定款変更の概要(2006年3月27日号・№156)
議案の決定と定款変更
会社法下の株主総会関係書類・直前総チェック
(1)定款変更の概要
三菱UFJ信託銀行 執行役員証券代行部長 中西敏和
Ⅰ 定款変更事項の概要
本年は、会社法施行に伴い各社とも定款を大幅に見直すものと考えられる。
会社法は現代語化と併せて体系を大きく変更しており、現行定款が会社法の下での定款とみなされ(整備法66条2項)、会社法施行後も、その記載事項の有効性が原則として維持されるとしても(整備法76条1項)、会社法に即したものとすべく、用語の見直しや引用条文の修正等、所要の変更を加える必要がある。
次に、会社法においては、これまでの一連の改正を受けて規制緩和がさらに進められており、その採否は会社の意思決定に委ねられているところから、本年総会に付議するかどうかも含めて、スケジュール感をもって検討を進める必要がある。この中には、これまでの改正で採用を見送った事項も当然含まれる。
さらに、まったく別の観点から定款を変更すべき事項がある。会社法は、これまで商法、商法特例法、有限会社法に分かれて規定されていた株式会社に関する法令を一つの法規に統合するに際して、機関設計のベースを最も簡素な有限会社を参考に、株主総会と取締役のみを基本的な機関とし、これ以外の機関の設置については、定款の定めを要するものとしている。
他方、会社法は、公開会社に取締役会の設置を義務付け、大会社に会計監査人の設置を義務付けるなど、現行の機関設計を念頭に置いたルールを付加しているため、この調整が必要となる。
整備法は、このような不具合を調整すべく、法で定められた手続を踏むことなく円滑に会社法に対応できるよう、一定の事項について法の定めによる定款変更を認めている。いわゆる「みなし変更」である。
具体的にどの条文をどのように変更するかについては、全国株懇連合会等のモデルが公表されており、これが参考になる(全株懇の定款モデルについては、http://www.kabukon.net/pic/9_1.PDFを参照)。
Ⅱ 本年6月総会への対応とみなし変更
定款変更については、上述のとおり、(1)整備法によるみなし変更、(2)会社法の施行に伴う用語・引用条文の変更、(3)定款自治の拡大等に伴う会社の意思決定による変更といった異なる要素の変更事項がある。
このうち、整備法によるみなし変更は、図表1のとおりであり、これらの事項については株主総会による定款変更決議はもちろんのこと、取締役会の決議すら要しない。したがって、代表取締役の職権により、事実として定款を変更すればそれで足りる。
また、同じ整備法で、会社法施行後に株主および債権者から定款の閲覧・謄写等の請求があり、これに応じる場合には、「当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、……定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。」としているところから(整備法77条)、施行を期して何らかの対応が必要であることは間違いない。
しかし、手続面と株主の理解しやすさを考えれば、みなし変更を含めて、すべての変更事項を新旧対照表にまとめ、これに変更事項に見合った理由を付けて付議することが考えられる。
もちろん、一括して定款変更議案を付議するところから、万が一否決された場合には、はなはだ具合が悪い。みなし変更の効力に問題が生じるとは考えられないが、体裁が悪いことは間違いない。
これを慮って、みなし変更事項についてはそもそも付議しないとか、報告事項とするといった考えもあろうが、そこまで杓子定規に考えることもないものと思われる。
図表1の(1)に掲げたうち、機関の設置については、現行定款に類似する規定がないだけに具体的な規定の仕方に迷うところがあるが、図表2のとおり、総則に一括して規定する方法と、図表3のように、これまでの関連する規定に追加する方法とがある。
後者の場合には、特に会計監査人のようにまったく新しく登場した事項についてどの章に入れるか、章の新設を含めて悩むところである。あまり難しく考えることもないが、将来、機関を弾力的に変更することを考えている場合には、総則に一括して規定するのが便利である。
〔図表1〕 整備法によるみなし定款変更事項等
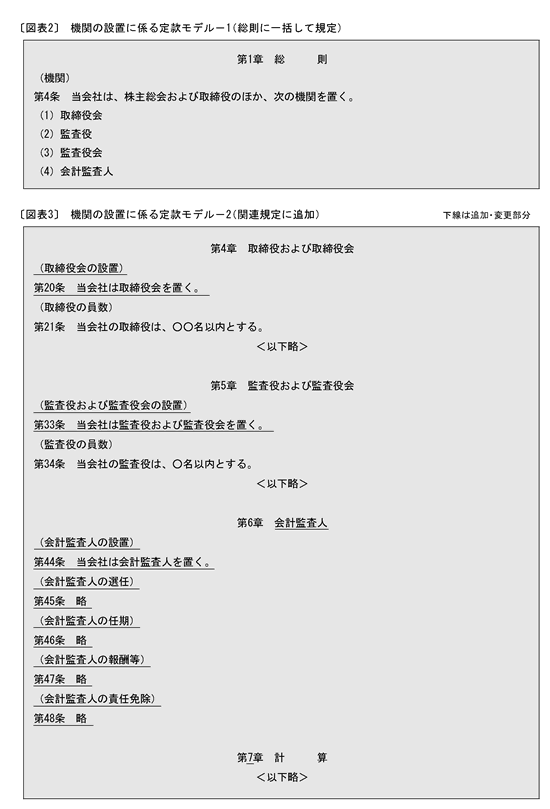
会社法下の株主総会関係書類・直前総チェック
(1)定款変更の概要
三菱UFJ信託銀行 執行役員証券代行部長 中西敏和
Ⅰ 定款変更事項の概要
本年は、会社法施行に伴い各社とも定款を大幅に見直すものと考えられる。
会社法は現代語化と併せて体系を大きく変更しており、現行定款が会社法の下での定款とみなされ(整備法66条2項)、会社法施行後も、その記載事項の有効性が原則として維持されるとしても(整備法76条1項)、会社法に即したものとすべく、用語の見直しや引用条文の修正等、所要の変更を加える必要がある。
次に、会社法においては、これまでの一連の改正を受けて規制緩和がさらに進められており、その採否は会社の意思決定に委ねられているところから、本年総会に付議するかどうかも含めて、スケジュール感をもって検討を進める必要がある。この中には、これまでの改正で採用を見送った事項も当然含まれる。
さらに、まったく別の観点から定款を変更すべき事項がある。会社法は、これまで商法、商法特例法、有限会社法に分かれて規定されていた株式会社に関する法令を一つの法規に統合するに際して、機関設計のベースを最も簡素な有限会社を参考に、株主総会と取締役のみを基本的な機関とし、これ以外の機関の設置については、定款の定めを要するものとしている。
他方、会社法は、公開会社に取締役会の設置を義務付け、大会社に会計監査人の設置を義務付けるなど、現行の機関設計を念頭に置いたルールを付加しているため、この調整が必要となる。
整備法は、このような不具合を調整すべく、法で定められた手続を踏むことなく円滑に会社法に対応できるよう、一定の事項について法の定めによる定款変更を認めている。いわゆる「みなし変更」である。
具体的にどの条文をどのように変更するかについては、全国株懇連合会等のモデルが公表されており、これが参考になる(全株懇の定款モデルについては、http://www.kabukon.net/pic/9_1.PDFを参照)。
Ⅱ 本年6月総会への対応とみなし変更
定款変更については、上述のとおり、(1)整備法によるみなし変更、(2)会社法の施行に伴う用語・引用条文の変更、(3)定款自治の拡大等に伴う会社の意思決定による変更といった異なる要素の変更事項がある。
このうち、整備法によるみなし変更は、図表1のとおりであり、これらの事項については株主総会による定款変更決議はもちろんのこと、取締役会の決議すら要しない。したがって、代表取締役の職権により、事実として定款を変更すればそれで足りる。
また、同じ整備法で、会社法施行後に株主および債権者から定款の閲覧・謄写等の請求があり、これに応じる場合には、「当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、……定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。」としているところから(整備法77条)、施行を期して何らかの対応が必要であることは間違いない。
しかし、手続面と株主の理解しやすさを考えれば、みなし変更を含めて、すべての変更事項を新旧対照表にまとめ、これに変更事項に見合った理由を付けて付議することが考えられる。
もちろん、一括して定款変更議案を付議するところから、万が一否決された場合には、はなはだ具合が悪い。みなし変更の効力に問題が生じるとは考えられないが、体裁が悪いことは間違いない。
これを慮って、みなし変更事項についてはそもそも付議しないとか、報告事項とするといった考えもあろうが、そこまで杓子定規に考えることもないものと思われる。
図表1の(1)に掲げたうち、機関の設置については、現行定款に類似する規定がないだけに具体的な規定の仕方に迷うところがあるが、図表2のとおり、総則に一括して規定する方法と、図表3のように、これまでの関連する規定に追加する方法とがある。
後者の場合には、特に会計監査人のようにまったく新しく登場した事項についてどの章に入れるか、章の新設を含めて悩むところである。あまり難しく考えることもないが、将来、機関を弾力的に変更することを考えている場合には、総則に一括して規定するのが便利である。
〔図表1〕 整備法によるみなし定款変更事項等
定款変更事項 | |
| (1)整備法によるみなし定款変更(公開会社) | ① 「名義書換代理人」⇒「株主名簿管理人」 ② 委員会設置会社以外の株式会社における「監査役及び取締役会を置く」旨の定款の定め ③ 大会社で監査役会設置会社における「監査役会及び会計監査人を置く」旨の定款の定め ④ 旧株式会社で株券を発行しない旨の定めがない場合の「株券を発行する」旨の定め |
| (2)用語、引用条文の変更により変更が必要な事項 | 【用語の変更】 ① 「発行する株式の総数」⇒「発行可能株式総数」 ② 「1単元の株式の数」⇒「単元株式数」 ③ 常勤監査役の選任につき「監査役の互選により」⇒「監査役会は……選任」 ④ 「営業年度」⇒「事業年度」 ⑤ 「利益配当金」⇒「剰余金の配当」など 【根拠条文の変更】 ① 取締役会決議による自己株式の取得(商法211条ノ3第1項2号⇒会社法165条2項) ② 特別決議の定足数緩和(商法343条⇒会社法309条2項) ③ 取締役の責任免除(商法266条12項⇒会社法426条) ④ 社外取締役責任限定契約(商法266条19項⇒会社法427条) ⑤ 監査役の責任免除(商法280条1項⇒会社法426条) ⑥ 中間配当(商法293条ノ5⇒会社法454条5項) |
| (3)採用するには定款の規定が必要な事項 | (次号以下参照) |
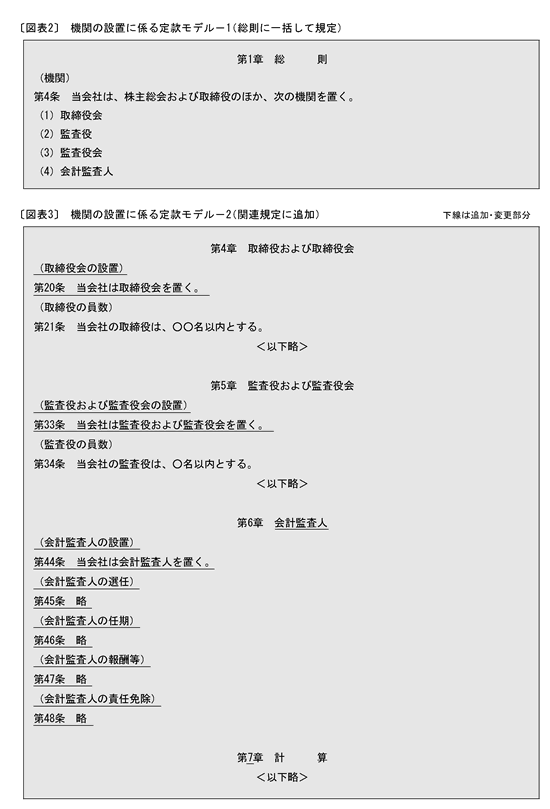
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























