解説記事2006年04月17日 【会社法解説】 図解でわかる法務省令講座―分配可能額の計算は複雑なのか―(2006年4月17日号・№159)
図解でわかる法務省令講座
―分配可能額の計算は複雑なのか―
前法務省民事局付 郡谷大輔
前3回で計算書類の作成等について解説した。今回は、会社の計算に関する法務省令の解説の最終稿として、分配可能額の計算について解説する。分配可能額の計算は、関連する規定が多数あり、足したり、引いたり、引くものから引いたりなど規定自体もテクニカルで複雑といえる。そこで、分配可能額の計算方法は本当に複雑であるのか、確認しておきたい。
人物紹介
マミ:霞が関の監査法人に勤める公認会計士。経済産業省・法務省において政策立案・立法作業に携わる。変わらず会社法施行対応に追われる中で、出会いと別れの季節に一抹の寂しさをおぼえる日々をすごしている。
カナ:赤坂の法律事務所に勤める弁護士。法務省において立法作業に携わる。会社法関係省令の公布後、他省令の改正案作りも無事まっとうし、3年10か月ぶりにおそるおそる赤坂に出勤する日々を迎えている。
Ⅰ 分配可能額の算定に関連する規定
分配可能額については、会社法461条2項に定義されている。しかし、分配可能額の具体的な算定に当たっては、同項の規定のみで計算できるわけではなく、その前提となる剰余金の額(会社法446条、計算規則177条・178条)、臨時決算の場合の増減額(計算規則184条・185条)なども関係する。
さらに、分配可能額からの控除額を定める計算規則186条も関係がある。
これらの規定構造をみると、図表1のとおりである。もっとも、このような規定構造を理解しても、必ずしも分配可能額の算定方法が理解できるわけではない。
なぜなら、分配可能額に関する上記の規定の整理は、剰余金・分配可能額に係る加算額・減算額がどのように書き分けられているかということのみを明らかにするものであるからである。
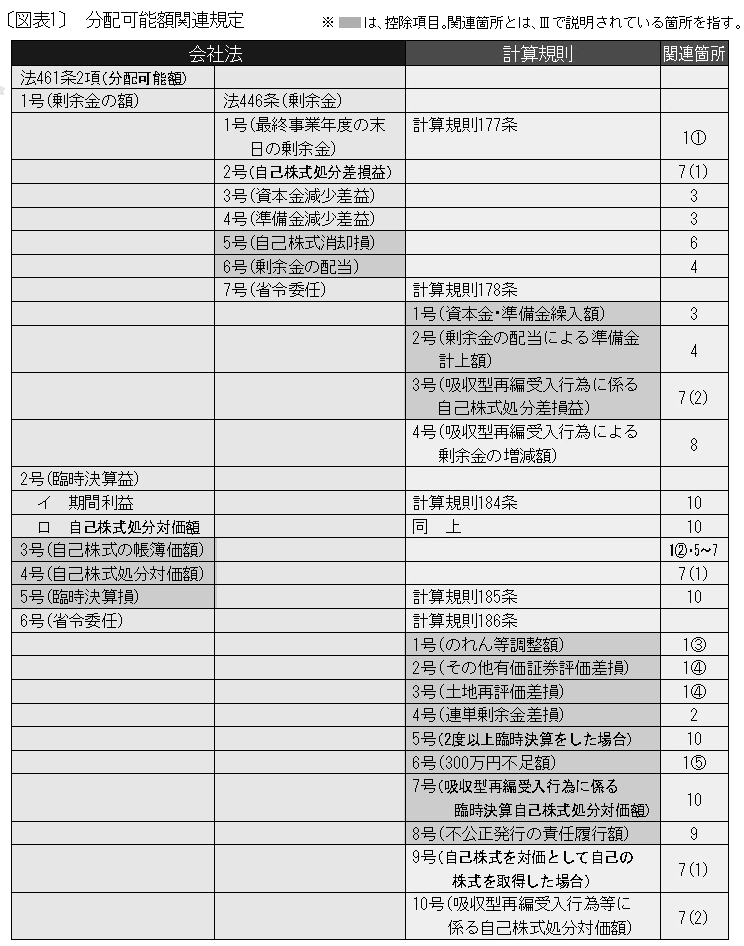
Ⅱ 剰余金と分配可能額の関係
分配可能額の算定方法は、どのように理解すべきか。これは、分配可能額の規定構造よりも、考え方の構造を理解しなければならない。
まず、上記の規定構造をみれば、分配可能額の計算においては、剰余金の額の変動に伴う分配可能額の変動事由と、分配可能額固有の変動事由に分かれていることが理解できる。
前者は剰余金の額の変動として会社法446条に、後者は分配可能額の変動として会社法461条2項に、それぞれ区別して規定が設けられている。
まず、剰余金の額に関する会社法446条は、期中の資本取引を含めて、各時点において、剰余金の額、すなわち、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額がどのように変動しているのかということについてのみ規定している。これは、会社法の概念というよりも、一定の会計基準等に従って行われる会計処理の結果、決定される概念であるといえる。
他方、分配可能額についての会社法461条は、会計処理や会計基準とはまったく無関係に、分配可能額の算定の基礎となる剰余金の額から何を減額するのか、またはどのような事態が起こったときに何を加算し、または減算するのかという、もっぱら会社法上の政策的な理由で決まるものについての規定である。
このような理由から、両者は区別して規定されている。
Ⅲ 分配可能額の算定順序の考え方
分配可能額は、理論上は剰余金の配当等を行う時点において会社法および計算規則に登場する順に加減算を行えば導き出すことはできるが、その算定方法を考える上では、次のように考えるとわかりやすい。
1 最終事業年度の末日における状況
分配可能額は、基本的に、最終事業年度の末日の貸借対照表における計数から計算を開始する。
具体的には、次の①の額から②~⑤の合計額を減額した額である。
① 剰余金の額(会社法461条2項1号・446条1号・計算規則177条)
最終事業年度に係る貸借対照表上の「その他資本剰余金」および「その他利益剰余金」の合計額である。
② 自己株式の帳簿価額(会社法461条2項3号)
最終事業年度に係る貸借対照表上の「自己株式」の額である。
③ のれん等調整額(会社法461条2項6号・計算規則186条1号)
最終事業年度に係る貸借対照表上の「のれん」および「繰延資産」に基づき算定される。
④ 評価・換算差額金(会社法461条2項6号・計算規則186条2号・3号)
最終事業年度に係る貸借対照表上の「その他有価証券評価差額金」および「土地再評価差額金」に基づき算定される。
⑤ 300万円不足額(会社法461条2項6号・計算規則186条6号)
最終事業年度に係る貸借対照表上の「資本金」「資本準備金」「利益準備金」「新株予約権」「評価・換算差額等」の額に基づき算定される。
POINT
~ここに注意~
⇒剰 余 金
~剰余金は、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額であり、会計上の概念である。
⇒分配可能額
~分配可能額は、剰余金の額に、政策的な理由から一定の計数を加減算して計算される会社法の固有の概念である。
⇒臨時決算
~臨時決算は、剰余金には影響を与えず、分配可能額についてのみ影響を与える。
2 連結配当規制適用会社
連結配当規制適用会社(計算規則2条3項72号)については、1の額から連単株主資本差損額(最終事業年度に係る貸借対照表・連結貸借対照表上の「株主資本」等の額に基づき算定される)を減額することとなる(会社法461条2項6号・計算規則186条4号)。
3 最終事業年度の末日後の項目の振替による剰余金の増減
最終事業年度の末日後に資本金・準備金を剰余金に振り替えれば分配可能額が増加し(会社法446条3号・4号)、剰余金を資本金・準備金に振り替えれば分配可能額が減少する(同条7号・計算規則178条1号)。
4 最終事業年度の末日後の剰余金の配当
最終事業年度の末日後に剰余金の配当をすると、配当財産の帳簿価額(会社法446条6号)および準備金計上額分(同条7号・計算規則178条2号)だけ減少する。
5 最終事業年度の末日後の自己株式の取得
最終事業年度の末日後に自己株式を取得すると、取得価額相当分(会社法461条2項3号)だけ減少する。
ただし、取得対価が自己株式である場合における自己株式の取得については、当該取得部分に係るものは変わらない(計算規則186条9号)。
6 最終事業年度の末日後の自己株式の消却
最終事業年度の末日後に自己株式を消却しても、分配可能額は変わらない(会社法446条5号・461条2項3号)。
7 最終事業年度の末日後の自己株式の処分
(1)通常の自己株式処分
最終事業年度の末日後に自己株式を処分しても、原則として分配可能額は変わらない(増加額(会社法446条2号・461条2項3号)と減少額(同項4号)が同じ)。
(2)吸収型組織再編行為等の自己株式処分
最終事業年度の末日後に吸収型組織再編行為等により自己株式を処分した場合における自己株式処分部分は、組織再編行為に係る規定において処理される(計算規則178条3号、186条10号)。
8 吸収型組織再編行為
最終事業年度の末日後に吸収型組織再編行為が行われた場合には、その前後の剰余金の差額により分配可能額が変動する(計算規則178条4号)。
9 その他の変動要因
最終事業年度の末日後に不公正発行に伴う責任が履行された場合であっても、分配可能額は変わらない(計算規則186条8号)。
10 臨時決算
最終事業年度の末日後に臨時決算をすると、臨時決算日までの期間損益(会社法461条2項2号イ・計算規則184条1号、会社法461条2項5号・計算規則185条)と自己株式対価額等(会社法461条2項2号ロ・計算規則184条2号)が反映される。
ただし、最終事業年度の末日後に吸収型組織再編行為等により自己株式を処分した場合における自己株式処分部分は、既に算入されているので、考慮されない(計算規則186条7号)。
また、2度以上臨時決算をした場合には、その前の臨時決算に係るものは消去されることとなる(同条5号)。
マミ:分配可能額の算定は、まず、最終事業年度の末日の貸借対照表上の計数の加減算を行うのよ。
カナ:その後で、事業年度の末日後の行為による剰余金と分配可能額の変動を勘案するのね。
Ⅳ 分配可能額の具体的算定
1 考え方
会社法における分配可能額の計算は、債権者との関係で株主に対して処分しても構わないと考えられる額はどれだけかという観点から計算される。
このため、計算のスタートは、その他利益剰余金(会社が対外的な活動によってあげた利益の集積であり、株主が分配を主張できるもの)とその他資本剰余金(払込資本のうち、債権者との関係で払戻しが可能なもの)の合計額から行われ、ここから分配可能額の計算上、政策的に算入すべきではないと考えられる資産等の額を減額する。
次に、事業年度の末日後、剰余金や分配可能額に変動を生じさせる行為があった場合には、その行為によって変動する額を、随時分配可能額に反映していくことになる。
これを整理すると、図表2のようになり、以下では特に解説を要するものについて述べる。
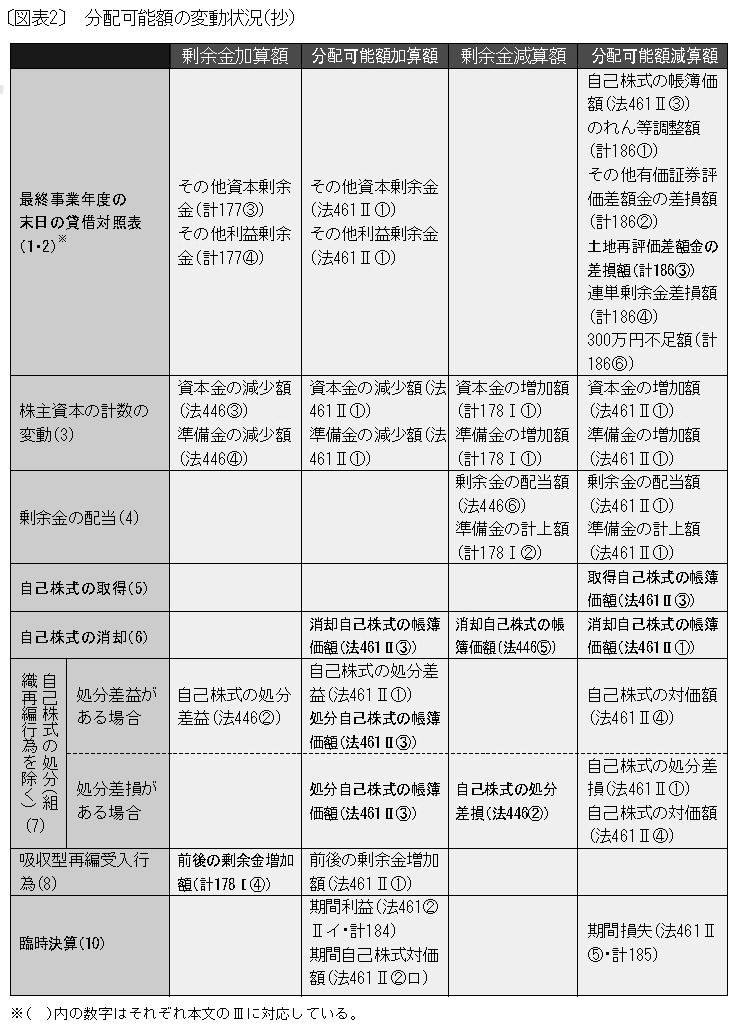
2 のれん等調整額
のれん等調整額は、のれんの2分の1と繰延資産の額の合計額である。
そして、その大きさによって、減額すべき額は、次のように定められることとなる。
① のれん等調整額が資本金・資本準備金以下の場合には、のれん等調整額として減額すべき額はない(計算規則186条1号イ)。
② のれん等調整額が資本金・準備金・その他資本剰余金の合計額以下の場合には、のれん等調整額から資本金・準備金の額を減じて得た額を減額することとなる(同号ロ)。
③ のれん等調整額が資本金・準備金・その他資本剰余金の合計額を超える場合には、のれんの2分の1は、その他資本剰余金の額を限度とし、繰延資産は、基本的に全額が控除される(同号ハ)。
3 その他有価証券評価差損額等
(1)評価差損
その他有価証券評価差額金の差損額が減額されるのは、その他有価証券の評価差額に関する限りは、旧商法と変わるところはない(貸借対照表上の資産の減少額から、これに係る繰延税金負債を減額した額ということになる)。
他方、売買目的有価証券の評価差損についても、当期純損失となり、その他利益剰余金から減額されているので、評価差損部分については取扱いは異ならない。
(2)評価差益
その他有価証券評価差額金につき評価差益が生じても、剰余金の額に影響を与えることはなく、結果として、分配可能額にも影響を与えない(結果として、旧商法と同様である)。
他方、売買目的有価証券の評価差益については、当期純利益となり、その他利益剰余金が増加するため、分配可能額も増加する。
この点は、当期純利益に反映される評価差益も配当可能利益から減額していた旧商法とは異なる。これは、表示の問題として、その流動性が金銭等と等価であり、時価評価を認め、かつ、その評価差益を当期損益に反映させるべき性質であるものと整理されているのであれば、分配可能額計算上も、特に、これを減額する理由が見当たらないことによる(すなわち、処分可能性と当該価額での換価可能性が確保されているのであれば、債権者との関係でも問題は少ない(少なくとも、償却資産の未償却部分を引当てに配当を認めていることと比較して問題が多いとはいえない))。
4 連単剰余金差損額
連単剰余金差損額とは、連結配当規制を適用することを定めた会社(計算規則2条3項72号)に適用されるものである。
株主資本の額から、その他有価証券と土地の評価差損額とのれん等の調整額を控除した額を連結ベースと単体ベースで比較し、連結ベースの方が小さいときには、その差額を連単剰余金差損額として、分配可能額から減額することとなる。
なお、連結配当規制適用会社には、次のような特例が設けられている。
連結子会社が保有する親会社株式については、相当の時期の処分規制および処分先に関する規制が緩和されている(施行規則23条12号)。
子会社と吸収合併・吸収分割・株式交換をする場合において、差損がある場合であっても、株主総会の決議を要しない(施行規則195条)。
POINT
~ここに注意~
⇒のれん等調整額
~のれんの2分の1と繰延資産は、分配可能額から減額すべき場合がある。
⇒評価差損
~純資産の部に計上された評価差損は、繰延ヘッジを除き、分配可能額から減額される。
⇒連単剰余金差損
~連結配当規制を適用すると、連結ベースの剰余金が少ない場合には、分配可能額から減額すべき場合がある。
5 300万円不足額
現行商法の最低資本金規制の廃止に伴い、現行商法で唯一最低資本金制度が債権者保護のために役立っていた配当規制に関する部分の規律を維持しようとするものである。
300万円の留保額から控除されるのは、配当財源に組み入れられない純資産の部の計数であり、具体的には、資本金・資本準備金・利益準備金(計算規則186条6号イ)と新株予約権(同号ロ)、評価・換算差額等(差益がある場合のみ)(同号ハ)である。
6 自己株式の処分
自己株式の処分をすると、会社の純資産額は自己株式の対価相当額分だけ増加することとなり、かつ、自己株式の処分に際しての相手勘定は資本金等、分配可能額に組み入れられない項目に計上する必要はない。このため、何らの手当てをしなければ、自己株式の対価額分の分配可能額が増加する。
これを剰余金等の動きと連動させて考えると、自己株式の対価額=自己株式の帳簿価額+自己株式の差損益となり、減少する自己株式の帳簿価額は分配可能額の増加要因となり、自己株式の差損益も剰余金の増減を通じて分配可能額の増減要因となる。
しかし、自己株式の対価額については、通常の決算か、臨時決算を経ない限り、分配可能額に組み入れないこととしている(会社法461条2項4号)。
したがって、通常の自己株式の処分では、自己株式の対価額と(処分差損益+帳簿価額)が同額となり、相殺されるので、分配可能額は変わらない(図表3参照)。
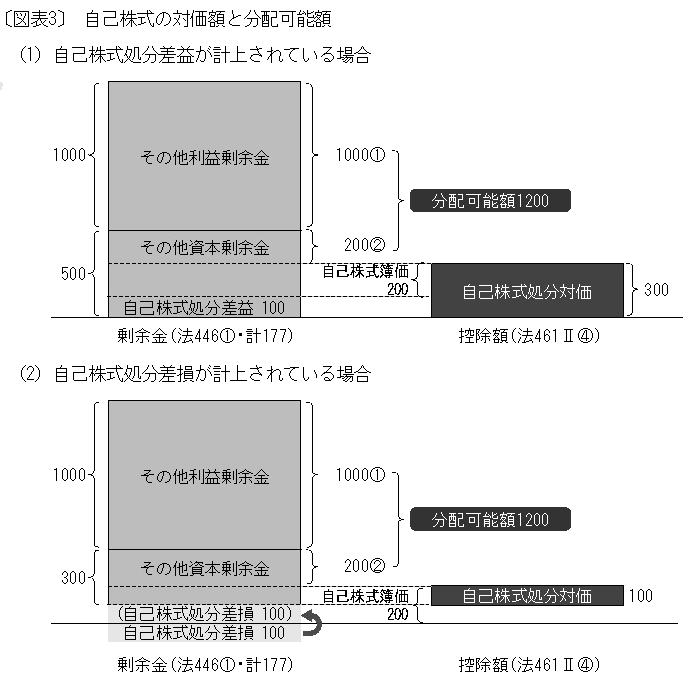
7 吸収型再編受入行為
吸収合併・吸収分割・株式交換をした場合には、一定の会計処理に従って、組織再編行為前後の剰余金が定まる。そして、その剰余金の変動額を、直接、分配可能額にも反映させることとしている。
組織再編行為が行われた場合における純資産の部の増加項目は、資本金、資本準備金、その他資本剰余金に会社の判断によって組み入れられることとなる(債権者保護手続を行わない株式交換については、株式発行部分について拘束がある)。
また、組織再編行為前後で分配可能額が減少する場合もある。
なお、現行商法で吸収合併や人的分割に際して認められていた利益剰余金の引継ぎは、会社法では、
吸収合併において持分プーリング法または共通支配下の会計処理を適用すべき場合
共通支配下の取引に該当する吸収分割において、分割対価の全部を分割会社の株主に交付する場合
にのみ認められており、前者については会社が任意に引き継ぐ利益剰余金の額を定めるのではなく、消滅会社が計上していた利益剰余金のみを引き継ぐこととなる。
POINT
~ここに注意~
⇒自己株式の処分
~自己株式の消却・処分によっては、原則として、分配可能額は変動しない。
⇒組織再編による変動
~組織再編行為による剰余金の変動は、即時に分配可能額に反映される。
8 臨時決算
臨時決算とは、事業年度の途中で、決算をし、その期間内の純利益・純損失および自己株式対価額を分配可能額に組み入れる手続である(剰余金は変動しないことに留意が必要である)。
この場合には、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額が加算される(会社法461条2項2号イ・184条、461条2項5号・185条)ほか、自己株式対価額(会社法461条2項2号ロ)も加算される。
また、のれん等調整額、その他有価証券評価差額金、土地再評価差額金は、臨時決算をした場合、臨時計算書類の貸借対照表の数値に改められる。
Ⅴ その他計数等に関する事項
1 資本金等の額の減少の手続
資本金・準備金の額を減少する場合には、原則として株主総会の決議(会社法447条・448条)と、債権者保護手続(会社法449条)が必要となるところ、計算規則では、これらの手続が緩和されることとなる要件(計算規則179条)と、債権者保護手続における計算書類に関する事項の公告内容(計算規則180条)について定めている。
(1)準備金の減少に際して債権者保護手続を要しない場合の要件
債権者保護手続をすることなく準備金の額を減少することができるのは、計算書類の確定時に行われる減少であって、分配可能額がマイナスとなっている場合において、当該マイナス相当額以下の額を減少する場合である(計算規則179条)。
(2)債権者保護手続における計算書類に関する事項の公告内容
計算規則180条は、債権者保護手続で公告すべき計算書類に関する事項を、債権者保護手続を開始する時の会社や決算公告の状況に応じ定めている。
具体的には、図表4のとおりである。
なお、この公告は、会社の公告方法を官報で行うこととしている場合には、以後決算公告として取り扱うことができるが、電子公告や日刊新聞紙である場合には、別途公告をしなければならない。
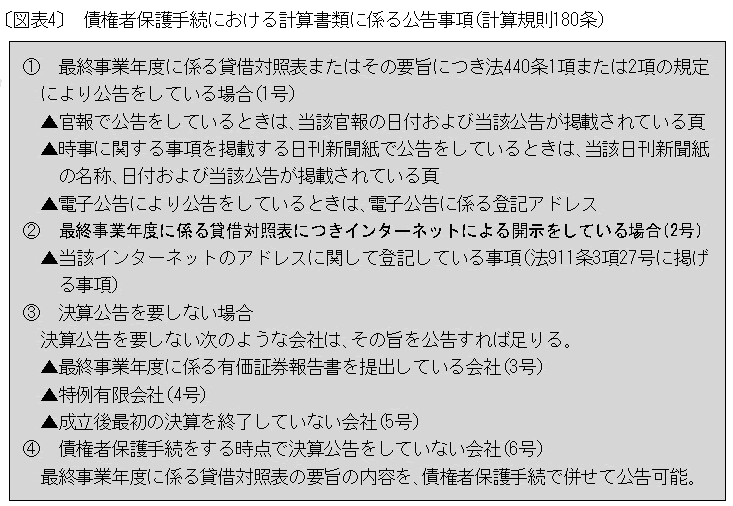
POINT
~ここに注意~
⇒債権者保護手続を要しない場合
~分配可能額がマイナスの場合で、これを0にするための準備金の減少の場合は要しない。
2 剰余金の処分
計算規則181条は、会社法452条の規定による剰余金の処分、すなわち、社外への財産流出がない、剰余金内部の項目の振替を行う場合において決定すべき内容として、振り替える剰余金の項目とその額を決議すべきものとしている。
他方、計算規則181条2項では、会社法452条の規定による株主総会の決議(会社法459条の定款の定めがある場合にあっては、取締役会の決議を含む)が要求されない剰余金の処分について規定している(図表5参照)。
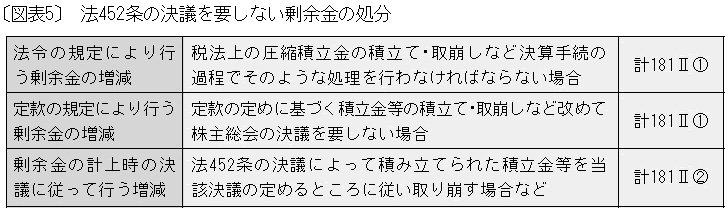
しかし、すべての項目の振替について株主総会の決議が要求されるわけではなく、計算規則181条2項は、そのような場合を明らかにしている。
まず、同項1号では、例えば、税法上の圧縮積立金の積立て・取崩しなど決算手続の過程でそのような処理を行わなければならない場合や、定款の定めに基づく積立金等の積立て・取崩しなど改めて株主総会の決議を要しない場合を規定している。
次に、同項2号は、会社法452条の決議によって積み立てられた積立金等を当該決議の定めるところに従って取り崩す場合等であり、当初の決議で定められているので改めて決議を要しない。
今週のおさらい 10
◎分配可能額の計算は剰余金の額の変動に伴う分配可能額の変動事由と分配可能額固有の変動事由で構成
前者は会社法446条に、後者は会社法461条に区別して規定されている。
◎分配可能額の算定は基本的に最終事業年度末日の貸借対照表上の計数から開始
その後、事業年度末日後の行為による剰余金・分配可能額の変動を勘案する。
◎剰余金の処分で会社法452条の決議が不要な場合を計算規則181条で規定
税法上の圧縮積立金の積立て・取崩しなどの場合が同条2項に定められている。
―分配可能額の計算は複雑なのか―
前法務省民事局付 郡谷大輔
前3回で計算書類の作成等について解説した。今回は、会社の計算に関する法務省令の解説の最終稿として、分配可能額の計算について解説する。分配可能額の計算は、関連する規定が多数あり、足したり、引いたり、引くものから引いたりなど規定自体もテクニカルで複雑といえる。そこで、分配可能額の計算方法は本当に複雑であるのか、確認しておきたい。
人物紹介
マミ:霞が関の監査法人に勤める公認会計士。経済産業省・法務省において政策立案・立法作業に携わる。変わらず会社法施行対応に追われる中で、出会いと別れの季節に一抹の寂しさをおぼえる日々をすごしている。
カナ:赤坂の法律事務所に勤める弁護士。法務省において立法作業に携わる。会社法関係省令の公布後、他省令の改正案作りも無事まっとうし、3年10か月ぶりにおそるおそる赤坂に出勤する日々を迎えている。
Ⅰ 分配可能額の算定に関連する規定
分配可能額については、会社法461条2項に定義されている。しかし、分配可能額の具体的な算定に当たっては、同項の規定のみで計算できるわけではなく、その前提となる剰余金の額(会社法446条、計算規則177条・178条)、臨時決算の場合の増減額(計算規則184条・185条)なども関係する。
さらに、分配可能額からの控除額を定める計算規則186条も関係がある。
これらの規定構造をみると、図表1のとおりである。もっとも、このような規定構造を理解しても、必ずしも分配可能額の算定方法が理解できるわけではない。
なぜなら、分配可能額に関する上記の規定の整理は、剰余金・分配可能額に係る加算額・減算額がどのように書き分けられているかということのみを明らかにするものであるからである。
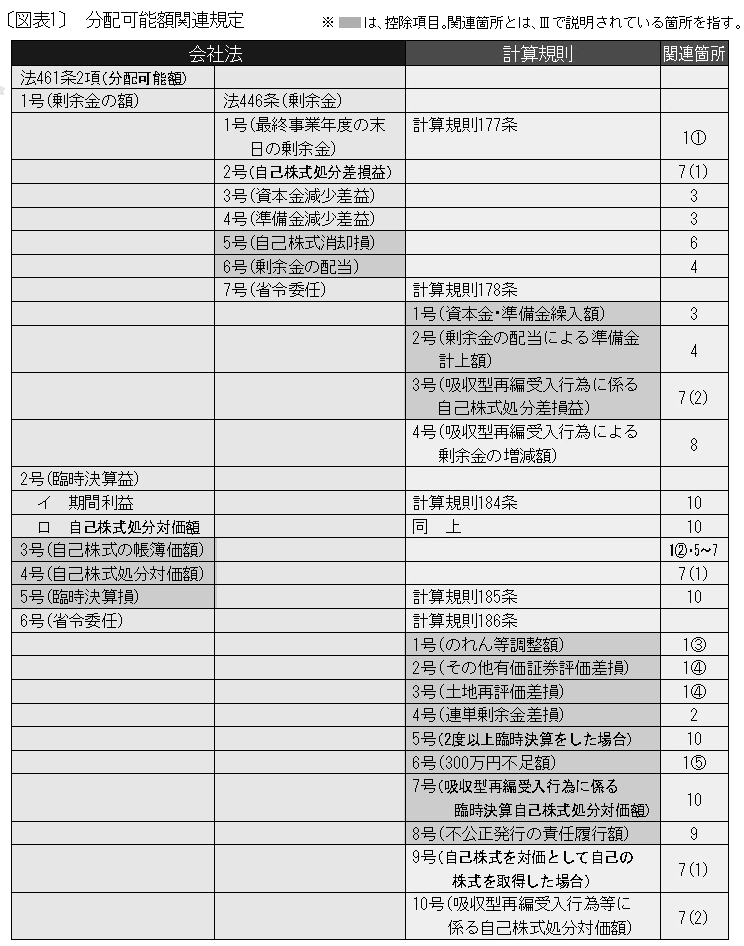
Ⅱ 剰余金と分配可能額の関係
分配可能額の算定方法は、どのように理解すべきか。これは、分配可能額の規定構造よりも、考え方の構造を理解しなければならない。
まず、上記の規定構造をみれば、分配可能額の計算においては、剰余金の額の変動に伴う分配可能額の変動事由と、分配可能額固有の変動事由に分かれていることが理解できる。
前者は剰余金の額の変動として会社法446条に、後者は分配可能額の変動として会社法461条2項に、それぞれ区別して規定が設けられている。
まず、剰余金の額に関する会社法446条は、期中の資本取引を含めて、各時点において、剰余金の額、すなわち、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額がどのように変動しているのかということについてのみ規定している。これは、会社法の概念というよりも、一定の会計基準等に従って行われる会計処理の結果、決定される概念であるといえる。
他方、分配可能額についての会社法461条は、会計処理や会計基準とはまったく無関係に、分配可能額の算定の基礎となる剰余金の額から何を減額するのか、またはどのような事態が起こったときに何を加算し、または減算するのかという、もっぱら会社法上の政策的な理由で決まるものについての規定である。
このような理由から、両者は区別して規定されている。
Ⅲ 分配可能額の算定順序の考え方
分配可能額は、理論上は剰余金の配当等を行う時点において会社法および計算規則に登場する順に加減算を行えば導き出すことはできるが、その算定方法を考える上では、次のように考えるとわかりやすい。
1 最終事業年度の末日における状況
分配可能額は、基本的に、最終事業年度の末日の貸借対照表における計数から計算を開始する。
具体的には、次の①の額から②~⑤の合計額を減額した額である。
① 剰余金の額(会社法461条2項1号・446条1号・計算規則177条)
最終事業年度に係る貸借対照表上の「その他資本剰余金」および「その他利益剰余金」の合計額である。
② 自己株式の帳簿価額(会社法461条2項3号)
最終事業年度に係る貸借対照表上の「自己株式」の額である。
③ のれん等調整額(会社法461条2項6号・計算規則186条1号)
最終事業年度に係る貸借対照表上の「のれん」および「繰延資産」に基づき算定される。
④ 評価・換算差額金(会社法461条2項6号・計算規則186条2号・3号)
最終事業年度に係る貸借対照表上の「その他有価証券評価差額金」および「土地再評価差額金」に基づき算定される。
⑤ 300万円不足額(会社法461条2項6号・計算規則186条6号)
最終事業年度に係る貸借対照表上の「資本金」「資本準備金」「利益準備金」「新株予約権」「評価・換算差額等」の額に基づき算定される。
POINT
~ここに注意~
⇒剰 余 金
~剰余金は、その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計額であり、会計上の概念である。
⇒分配可能額
~分配可能額は、剰余金の額に、政策的な理由から一定の計数を加減算して計算される会社法の固有の概念である。
⇒臨時決算
~臨時決算は、剰余金には影響を与えず、分配可能額についてのみ影響を与える。
2 連結配当規制適用会社
連結配当規制適用会社(計算規則2条3項72号)については、1の額から連単株主資本差損額(最終事業年度に係る貸借対照表・連結貸借対照表上の「株主資本」等の額に基づき算定される)を減額することとなる(会社法461条2項6号・計算規則186条4号)。
3 最終事業年度の末日後の項目の振替による剰余金の増減
最終事業年度の末日後に資本金・準備金を剰余金に振り替えれば分配可能額が増加し(会社法446条3号・4号)、剰余金を資本金・準備金に振り替えれば分配可能額が減少する(同条7号・計算規則178条1号)。
4 最終事業年度の末日後の剰余金の配当
最終事業年度の末日後に剰余金の配当をすると、配当財産の帳簿価額(会社法446条6号)および準備金計上額分(同条7号・計算規則178条2号)だけ減少する。
5 最終事業年度の末日後の自己株式の取得
最終事業年度の末日後に自己株式を取得すると、取得価額相当分(会社法461条2項3号)だけ減少する。
ただし、取得対価が自己株式である場合における自己株式の取得については、当該取得部分に係るものは変わらない(計算規則186条9号)。
6 最終事業年度の末日後の自己株式の消却
最終事業年度の末日後に自己株式を消却しても、分配可能額は変わらない(会社法446条5号・461条2項3号)。
7 最終事業年度の末日後の自己株式の処分
(1)通常の自己株式処分
最終事業年度の末日後に自己株式を処分しても、原則として分配可能額は変わらない(増加額(会社法446条2号・461条2項3号)と減少額(同項4号)が同じ)。
(2)吸収型組織再編行為等の自己株式処分
最終事業年度の末日後に吸収型組織再編行為等により自己株式を処分した場合における自己株式処分部分は、組織再編行為に係る規定において処理される(計算規則178条3号、186条10号)。
8 吸収型組織再編行為
最終事業年度の末日後に吸収型組織再編行為が行われた場合には、その前後の剰余金の差額により分配可能額が変動する(計算規則178条4号)。
9 その他の変動要因
最終事業年度の末日後に不公正発行に伴う責任が履行された場合であっても、分配可能額は変わらない(計算規則186条8号)。
10 臨時決算
最終事業年度の末日後に臨時決算をすると、臨時決算日までの期間損益(会社法461条2項2号イ・計算規則184条1号、会社法461条2項5号・計算規則185条)と自己株式対価額等(会社法461条2項2号ロ・計算規則184条2号)が反映される。
ただし、最終事業年度の末日後に吸収型組織再編行為等により自己株式を処分した場合における自己株式処分部分は、既に算入されているので、考慮されない(計算規則186条7号)。
また、2度以上臨時決算をした場合には、その前の臨時決算に係るものは消去されることとなる(同条5号)。
マミ:分配可能額の算定は、まず、最終事業年度の末日の貸借対照表上の計数の加減算を行うのよ。
カナ:その後で、事業年度の末日後の行為による剰余金と分配可能額の変動を勘案するのね。
Ⅳ 分配可能額の具体的算定
1 考え方
会社法における分配可能額の計算は、債権者との関係で株主に対して処分しても構わないと考えられる額はどれだけかという観点から計算される。
このため、計算のスタートは、その他利益剰余金(会社が対外的な活動によってあげた利益の集積であり、株主が分配を主張できるもの)とその他資本剰余金(払込資本のうち、債権者との関係で払戻しが可能なもの)の合計額から行われ、ここから分配可能額の計算上、政策的に算入すべきではないと考えられる資産等の額を減額する。
次に、事業年度の末日後、剰余金や分配可能額に変動を生じさせる行為があった場合には、その行為によって変動する額を、随時分配可能額に反映していくことになる。
これを整理すると、図表2のようになり、以下では特に解説を要するものについて述べる。
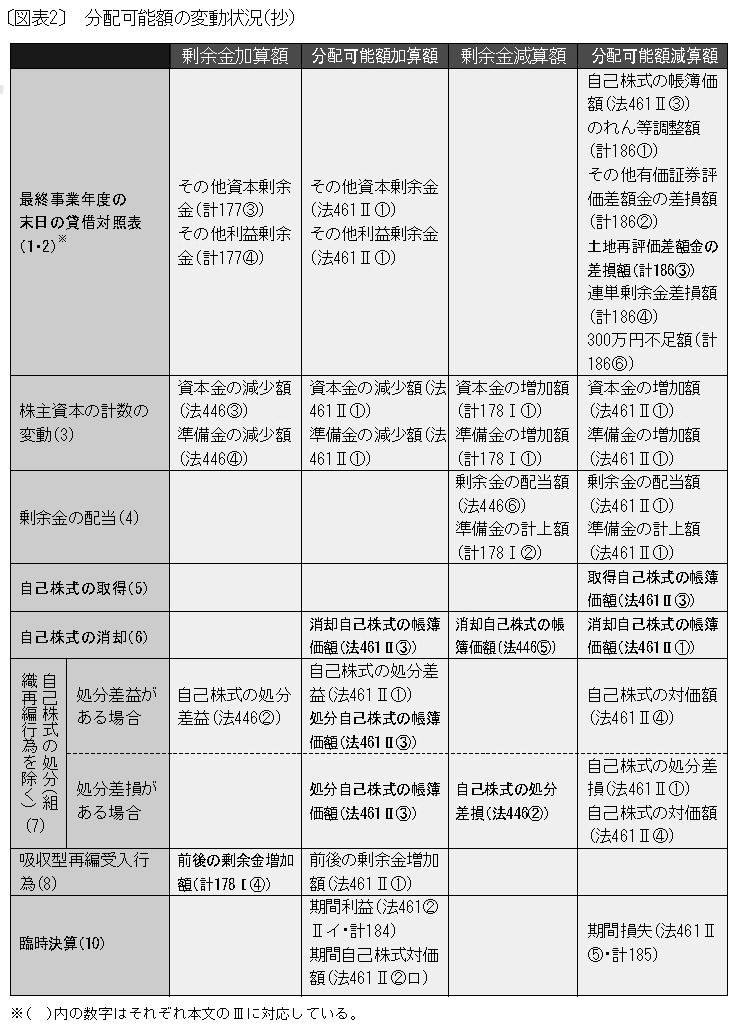
2 のれん等調整額
のれん等調整額は、のれんの2分の1と繰延資産の額の合計額である。
そして、その大きさによって、減額すべき額は、次のように定められることとなる。
① のれん等調整額が資本金・資本準備金以下の場合には、のれん等調整額として減額すべき額はない(計算規則186条1号イ)。
② のれん等調整額が資本金・準備金・その他資本剰余金の合計額以下の場合には、のれん等調整額から資本金・準備金の額を減じて得た額を減額することとなる(同号ロ)。
③ のれん等調整額が資本金・準備金・その他資本剰余金の合計額を超える場合には、のれんの2分の1は、その他資本剰余金の額を限度とし、繰延資産は、基本的に全額が控除される(同号ハ)。
3 その他有価証券評価差損額等
(1)評価差損
その他有価証券評価差額金の差損額が減額されるのは、その他有価証券の評価差額に関する限りは、旧商法と変わるところはない(貸借対照表上の資産の減少額から、これに係る繰延税金負債を減額した額ということになる)。
他方、売買目的有価証券の評価差損についても、当期純損失となり、その他利益剰余金から減額されているので、評価差損部分については取扱いは異ならない。
(2)評価差益
その他有価証券評価差額金につき評価差益が生じても、剰余金の額に影響を与えることはなく、結果として、分配可能額にも影響を与えない(結果として、旧商法と同様である)。
他方、売買目的有価証券の評価差益については、当期純利益となり、その他利益剰余金が増加するため、分配可能額も増加する。
この点は、当期純利益に反映される評価差益も配当可能利益から減額していた旧商法とは異なる。これは、表示の問題として、その流動性が金銭等と等価であり、時価評価を認め、かつ、その評価差益を当期損益に反映させるべき性質であるものと整理されているのであれば、分配可能額計算上も、特に、これを減額する理由が見当たらないことによる(すなわち、処分可能性と当該価額での換価可能性が確保されているのであれば、債権者との関係でも問題は少ない(少なくとも、償却資産の未償却部分を引当てに配当を認めていることと比較して問題が多いとはいえない))。
4 連単剰余金差損額
連単剰余金差損額とは、連結配当規制を適用することを定めた会社(計算規則2条3項72号)に適用されるものである。
株主資本の額から、その他有価証券と土地の評価差損額とのれん等の調整額を控除した額を連結ベースと単体ベースで比較し、連結ベースの方が小さいときには、その差額を連単剰余金差損額として、分配可能額から減額することとなる。
なお、連結配当規制適用会社には、次のような特例が設けられている。
連結子会社が保有する親会社株式については、相当の時期の処分規制および処分先に関する規制が緩和されている(施行規則23条12号)。
子会社と吸収合併・吸収分割・株式交換をする場合において、差損がある場合であっても、株主総会の決議を要しない(施行規則195条)。
POINT
~ここに注意~
⇒のれん等調整額
~のれんの2分の1と繰延資産は、分配可能額から減額すべき場合がある。
⇒評価差損
~純資産の部に計上された評価差損は、繰延ヘッジを除き、分配可能額から減額される。
⇒連単剰余金差損
~連結配当規制を適用すると、連結ベースの剰余金が少ない場合には、分配可能額から減額すべき場合がある。
5 300万円不足額
現行商法の最低資本金規制の廃止に伴い、現行商法で唯一最低資本金制度が債権者保護のために役立っていた配当規制に関する部分の規律を維持しようとするものである。
300万円の留保額から控除されるのは、配当財源に組み入れられない純資産の部の計数であり、具体的には、資本金・資本準備金・利益準備金(計算規則186条6号イ)と新株予約権(同号ロ)、評価・換算差額等(差益がある場合のみ)(同号ハ)である。
6 自己株式の処分
自己株式の処分をすると、会社の純資産額は自己株式の対価相当額分だけ増加することとなり、かつ、自己株式の処分に際しての相手勘定は資本金等、分配可能額に組み入れられない項目に計上する必要はない。このため、何らの手当てをしなければ、自己株式の対価額分の分配可能額が増加する。
これを剰余金等の動きと連動させて考えると、自己株式の対価額=自己株式の帳簿価額+自己株式の差損益となり、減少する自己株式の帳簿価額は分配可能額の増加要因となり、自己株式の差損益も剰余金の増減を通じて分配可能額の増減要因となる。
しかし、自己株式の対価額については、通常の決算か、臨時決算を経ない限り、分配可能額に組み入れないこととしている(会社法461条2項4号)。
したがって、通常の自己株式の処分では、自己株式の対価額と(処分差損益+帳簿価額)が同額となり、相殺されるので、分配可能額は変わらない(図表3参照)。
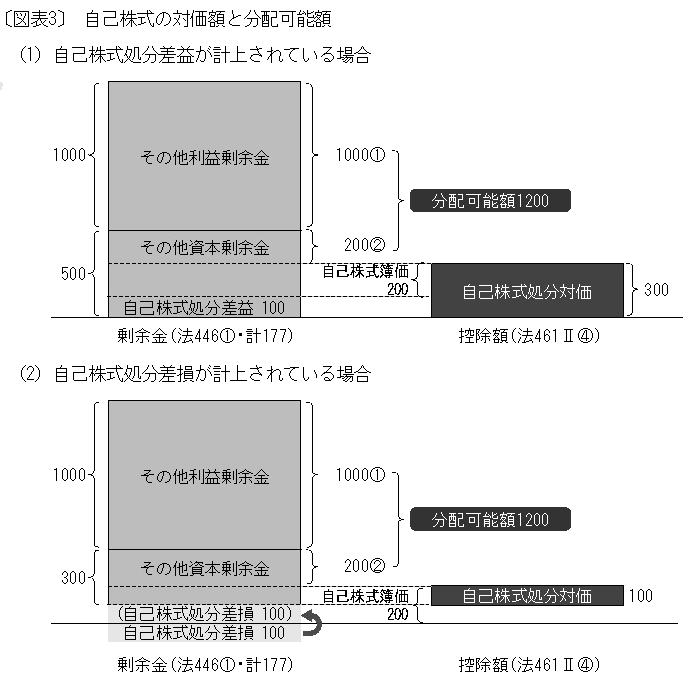
7 吸収型再編受入行為
吸収合併・吸収分割・株式交換をした場合には、一定の会計処理に従って、組織再編行為前後の剰余金が定まる。そして、その剰余金の変動額を、直接、分配可能額にも反映させることとしている。
組織再編行為が行われた場合における純資産の部の増加項目は、資本金、資本準備金、その他資本剰余金に会社の判断によって組み入れられることとなる(債権者保護手続を行わない株式交換については、株式発行部分について拘束がある)。
また、組織再編行為前後で分配可能額が減少する場合もある。
なお、現行商法で吸収合併や人的分割に際して認められていた利益剰余金の引継ぎは、会社法では、
吸収合併において持分プーリング法または共通支配下の会計処理を適用すべき場合
共通支配下の取引に該当する吸収分割において、分割対価の全部を分割会社の株主に交付する場合
にのみ認められており、前者については会社が任意に引き継ぐ利益剰余金の額を定めるのではなく、消滅会社が計上していた利益剰余金のみを引き継ぐこととなる。
POINT
~ここに注意~
⇒自己株式の処分
~自己株式の消却・処分によっては、原則として、分配可能額は変動しない。
⇒組織再編による変動
~組織再編行為による剰余金の変動は、即時に分配可能額に反映される。
8 臨時決算
臨時決算とは、事業年度の途中で、決算をし、その期間内の純利益・純損失および自己株式対価額を分配可能額に組み入れる手続である(剰余金は変動しないことに留意が必要である)。
この場合には、臨時計算書類の損益計算書に計上された当期純損益金額が加算される(会社法461条2項2号イ・184条、461条2項5号・185条)ほか、自己株式対価額(会社法461条2項2号ロ)も加算される。
また、のれん等調整額、その他有価証券評価差額金、土地再評価差額金は、臨時決算をした場合、臨時計算書類の貸借対照表の数値に改められる。
Ⅴ その他計数等に関する事項
1 資本金等の額の減少の手続
資本金・準備金の額を減少する場合には、原則として株主総会の決議(会社法447条・448条)と、債権者保護手続(会社法449条)が必要となるところ、計算規則では、これらの手続が緩和されることとなる要件(計算規則179条)と、債権者保護手続における計算書類に関する事項の公告内容(計算規則180条)について定めている。
(1)準備金の減少に際して債権者保護手続を要しない場合の要件
債権者保護手続をすることなく準備金の額を減少することができるのは、計算書類の確定時に行われる減少であって、分配可能額がマイナスとなっている場合において、当該マイナス相当額以下の額を減少する場合である(計算規則179条)。
(2)債権者保護手続における計算書類に関する事項の公告内容
計算規則180条は、債権者保護手続で公告すべき計算書類に関する事項を、債権者保護手続を開始する時の会社や決算公告の状況に応じ定めている。
具体的には、図表4のとおりである。
なお、この公告は、会社の公告方法を官報で行うこととしている場合には、以後決算公告として取り扱うことができるが、電子公告や日刊新聞紙である場合には、別途公告をしなければならない。
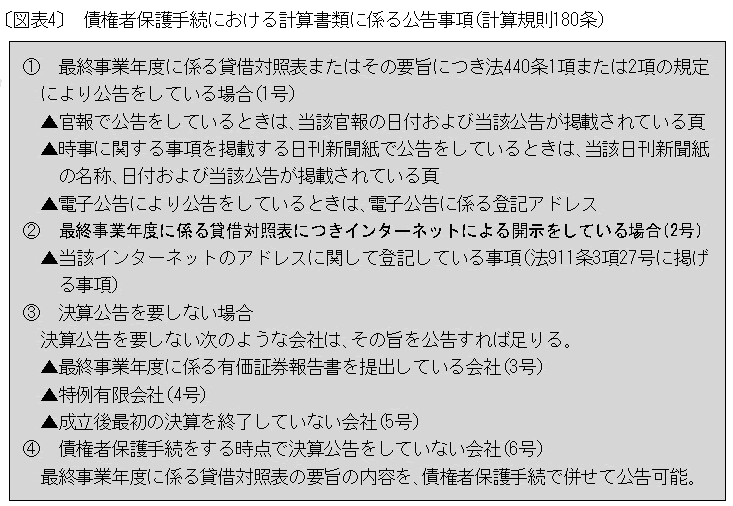
POINT
~ここに注意~
⇒債権者保護手続を要しない場合
~分配可能額がマイナスの場合で、これを0にするための準備金の減少の場合は要しない。
2 剰余金の処分
計算規則181条は、会社法452条の規定による剰余金の処分、すなわち、社外への財産流出がない、剰余金内部の項目の振替を行う場合において決定すべき内容として、振り替える剰余金の項目とその額を決議すべきものとしている。
他方、計算規則181条2項では、会社法452条の規定による株主総会の決議(会社法459条の定款の定めがある場合にあっては、取締役会の決議を含む)が要求されない剰余金の処分について規定している(図表5参照)。
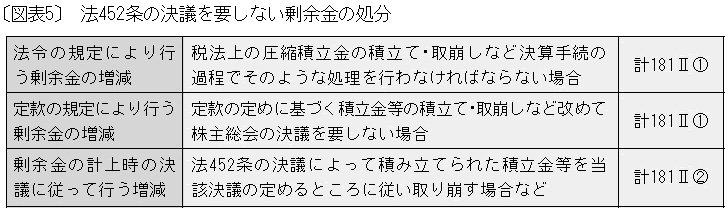
しかし、すべての項目の振替について株主総会の決議が要求されるわけではなく、計算規則181条2項は、そのような場合を明らかにしている。
まず、同項1号では、例えば、税法上の圧縮積立金の積立て・取崩しなど決算手続の過程でそのような処理を行わなければならない場合や、定款の定めに基づく積立金等の積立て・取崩しなど改めて株主総会の決議を要しない場合を規定している。
次に、同項2号は、会社法452条の決議によって積み立てられた積立金等を当該決議の定めるところに従って取り崩す場合等であり、当初の決議で定められているので改めて決議を要しない。
今週のおさらい 10
◎分配可能額の計算は剰余金の額の変動に伴う分配可能額の変動事由と分配可能額固有の変動事由で構成
前者は会社法446条に、後者は会社法461条に区別して規定されている。
◎分配可能額の算定は基本的に最終事業年度末日の貸借対照表上の計数から開始
その後、事業年度末日後の行為による剰余金・分配可能額の変動を勘案する。
◎剰余金の処分で会社法452条の決議が不要な場合を計算規則181条で規定
税法上の圧縮積立金の積立て・取崩しなどの場合が同条2項に定められている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.



















