解説記事2006年05月15日 【最新判決研究】 海外子会社株式に係る含み益の増資移転における収益認識と当該株式の評価方法―オーブンシャホールディング事件―(2006年5月15日号・№162)
海外子会社株式に係る含み益の増資移転における収益認識と当該株式の評価方法―オーブンシャホールディング事件―
東京地裁平成13年11月9日判決 訟務月報 49巻8号2410頁
東京高裁平成16年1月28日判決 訟務月報 50巻8号2512頁
最高裁平成18年1月24日第三小法廷判決 判例タイムズ 1203号108頁
早稲田大学大学院客員教授(専任)
筑波大学名誉教授
品川 芳宣
一、事実
(1)本件は、X会社(原告・被控訴人・上告人)が、非上場株式を現物出資(100%支配)してオランダに設立した外国子会社であるAT社の株主総会において、新たに発行する新株全部をX会社の外国における関連会社であるAF社に著しく有利な価額で割り当てる決議(以下「本件決議」という。)を行わせ、X会社が保有していたAT社株式の資産価値を何らの対価も得ずにAF社に移転させた場合に、Y(被告・控訴人・被上告人)税務署長が、その移転した資産価値相当額をAF社に対する寄附金と認定し、X会社の平成6年10月1日から平成7年9月30日までの事業年度(以下「平成7年9月期」という。)の法人税の更正処分(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定」という。)をしたため、X会社が、本件更正処分のうち納付すべき税額2億6,494万円余を超える部分及び本件賦課決定はいずれも違法であるとしてその取消しを求めた事案である。
(2)本件の取引の概要は、次のとおりである。
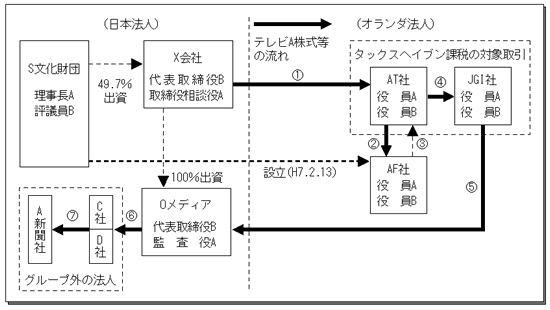
〈取引の説明〉
① 平成3年9月4日
当時の法人税法51条の圧縮記帳を利用して、所有していたテレビA株式(3,559株)、B放送株式等を現物出資し、AT社を設立(発行済株式数200株)、X会社の持株割合100%。
② 平成7年2月13日
本件決議に基づきAT社をして、増資新株3,000株をAF社に割当てさせる(以下「本件増資」という。)。
③ 平成7年2月15日
②の割当てにより、AF社が本件増資払込303万0,303ギルダー(邦貨換算額1億7,627万2,725円)を払い込む。X会社の持株割合は6.25%に低下。
④ 平成8年7月30日
テレビA株式(3,559株)を28,649百万円で売却。AF社の持株割合93.75%分については、S文化財団が公益法人であるためタックスヘイブン課税の対象とならず。
⑤ 平成8年9月5日
テレビA株式(3,559株)を28,932百万円で売却。
⑥ 平成8年12月2日
企業買収により、テレビA株式を保有するOメディア株式をグループ外へ売却。
⑦ 平成9年3月31日、同年4月1日
A新聞社は、テレビA株式を保有するOメディア株式(商号変更により株式名は変更した後のもの)をC社及びD社から企業買収により取得。
二、争点と当事者の主張
1 争点
(1)争点1(本件増資と法人税法(以下「法」という。)22条2項に規定する無償による資産の譲渡の有無等)
(2)争点2(本件増資による資産の移転額、課税額)
(3)争点3(本件増資と法132条1項1号に基づく課税の当否)
(4)争点4(訴訟手続、課税手続上の問題、課税の憲法違反)
① 法22条2項の適用に関するYの主張と時機に後れた攻撃防御方法
② 本件更正の理由附記についての不備
③ 本件更正の理由の差替えの法130条2項違反、憲法14条等違反
2 Yの主張
(1)本件増資は、X会社、AT社及びAF社の合意に基づき、AT社株式の資産価値を分割し、対価を得ることなく、その資産価値の一部をX会社からAF社に移転させたもので、法22条2項の無償による資産の譲渡又はその他の取引及び法37条2項の寄附金に該当する。
(2)AT社の株式は、独立当事者間の適当な売買実例がないこと、株式公開途上にはなく、公募等の価格がないこと、同社と事業の種類や収益の状況等において類似する法人がないことから、法人税基本通達9-1-14(4)(平成12年改正前のもの、以下同じ)に基づき、時価純資産価額方式により評価した。AT社の資産の大部分をしめるテレビA株式及びB放送株式も、本件増資当時、いずれも非上場であり、同様に評価することとすると、AT社の純資産価額は、テレビA株式188億円余、B放送株式82億円余となり、その他の資産、負債を加減して計算することとなる。
なお、清算所得に対する法人税額等の控除(51%)は、時価純資産価額方式により評価する場合、企業の継続を前提とした客観的交換価値を求めるため、しない。
(3)法132条1項1号の「行為」は、必ずしも法22条2項の資産の譲渡等の取引に当たる必要はなく、不当な法人税の減少をもたらす一切の行為がこれに当たる。本件増資決議における議決権の行使は、法132条1項1号の行為に当たる。
(4)X会社が主張するような訴訟手続及び課税手続上の違反はなく、また、憲法違反も存しない。
3 X会社の主張
(1)キャピタルゲインへの課税は、株主が会社に対する管理支配権を行使したかどうかではなく、当該キャピタルゲインが株主に帰属したか否かによる。本件増資においては、X会社の保有する旧株式200株についてのキャピタルゲインの全部又は一部が、抽象的所有権に止まったまま(利得が実現されることなく)、失われたのであり、未だ実現していない利得は、課税されるべきではない。法22条2項は、すべての無償による資産の譲渡又はその他の無償取引から必ず益金が発生する旨を規定しているのではなく、同条4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って益金を計算するに際し、「無償による資産の譲渡」又は「その他の無償取引」から益金が発生する場合があり得ることを規定しているにすぎない。
(2)AT社の株式の評価については、法人税基本通達9-1-14と9-1-15の有利な方を適用でき、後者を適用すると、テレビA株式等は配当還元方式を、B放送株式等は時価純資産価額方式を基礎として算定すべきであり、X会社の有価証券に係る利益の計上もれは24億円余となる。
なお、AT社の保有する株式をすべて時価純資産価額方式により評価する場合、清算所得に対する法人税額等(本件増資当時51%。財産評価基本通達185、186-2)を控除すべきで、これによるとX会社の有価証券に係る利益の計上もれは177億円余となる。
(3)法132条1項1号は、税務署長が法人税の負担を不当に減少させると判断した場合、裁量で課税できると定め、客観的、合理的基準により課税される保障がなく、租税法律主義、課税要件明確主義を定めた憲法84条、30条に違反する。また、①株式の第三者有利発行の際、旧株主には課税されず、②平成10年の法51条改正前には、圧縮記帳された現物出資に係る資産の含み益に対し、結果的に日本国の課税権が及ばなかったことなどの事情から見ると、本来課税できない被控訴人の行為、計算にのみ法132条1項1号を適用してした本件更正は、平等主義を定めた憲法14条に違反する。
なお、AF社は、増資の対価を支払うなら、X会社にではなく、保有株の価値を高めるためにAT社に払い込むのであり、X会社への支払いを合理的な行為というYの主張は、法132条1項1号の前提を欠く。
(4)Yが本件更正の法的根拠として第6回口頭弁論において法132条を主張するのは、時機に後れた攻撃防御となり(民事訴訟法157条)、本件更正には理由附記不備の違法があり、かつ、更正の理由の差替えを認めることには憲法14条違反となる等の手続上の違法がある。
三、一審判決要旨
請求認容。
(1)本件決議はAT社の株主総会が内部的な意思決定をしたのにほかならず、その段階では未だ増資の効果は生じていないのであって、AF社が本件増資により資産価値を取得したとすれば、それは、法形式においては、AT社の執行機関が本件決議を受けて同社の行為として増資を実行し、AF社が新株の引受人として払込行為をしたことによるものである。そうすると、本件増資は、AT社自体による本件増資の実行という行為とそれに応じてAF社がAT社に対して新株の払込みをするという行為により構成されており、本件増資の結果、AF社の払込金額と本件増資により発行される株式の時価との差額がAF社に帰属することとなったとの取引的行為としてとらえるとすれば、本件増資をして新株の払込みを受けたAT社と有利な条件でAT社から新株の発行を受けたAF社の間の行為にほかならず、X会社はAF社に対して何らの行為もしていないというほかない。
(2)本件更正処分の理由として法132条を適用すべき旨のYの主張は、X会社自らの行為によりその保有するAT社株式の資産価値がAF社に移転したとの事実を前提として、同資産価値の移転について法132条を適用して課税しようとするものである。しかしながら、X会社の保有するAT社株式の資産価値がAF社に移転したことが、X会社自らの行為によるものとは認められないことは、前示判示のとおりである。したがって、Yの主張については、その余の点について判断するまでもなく理由がないことは明らかである。
(3)前記結論によると、X会社が保有していた株式に関する多額の含み益については、何らの課税もされない結果が生ずることとなるが、これは、法51条がその定める特定出資についていわゆる圧縮記帳による課税の繰延べを認め、しかも平成10年改正前には外国法人の設立についても同条の適用が認められていたことに端を発するものである。
四、控訴審判決要旨
原判決取消し、請求棄却。
原審の理由説示を次のとおり一部付加するほか、これを引用する。
(1)本件のAT社における持株割合の変化は、各法人及び役員等が意思を相通じた結果にほかならず、X会社は、AF社との合意に基づき、同社からなんらの対価を得ることもなく、AT社の資産につき、株主として保有する持分16分の15及び株主としての支配権を失い、AF社がこれらを取得したと認定評価することができる。そして、X会社が上記資産に係る株主として有する持分をAF社からなんらの対価を得ることもなく喪失し、同社がこれを取得した事実は、それが両社の合意に基づくと認められる以上、両社間において無償による上記持分の譲渡がされたと認定することができる。すなわち、両社間における無償による上記持分の譲渡は、法22条2項に規定する「無償による資産の譲渡」に当たると認定判断することができる。
本件増資は、いわゆる節税を意図して企画されたことは明らかで、納税者として、いわゆる節税を図ることは、もとより、なんら正義に反することではない。本件訴訟につき、AT社とAF社間の行為で、X会社とAF社間に何らの行為もないことを理由に法22条2項の適用を否定するのは、裁判所としての事実認定の責務を果たしておらず、判決の理由としても、不備がある。
原審は、関係当事者の意思及びその結果生じた事実を全体として見ず、一部を恣意的に切り取って結論を導いた誹りを免れず、争点について判断し、紛争を解決に導くべき裁判所の責任を疎かにするものと評せざるを得ない。
(2)AT社は、その株式につき、独立当事者間の適当な売買実例及び公募等がなく、株式公開途上にもなく、同社と事業の種類や収益の状況等において類似する法人もない。このため、その評価は、法人税基本通達9-1-14(4)に基づき、時価純資産価額方式(資産負債を時価評価して純資産価額を算出し、1株当たりの価額を算出する方法)に従ってすべきである。また、同社の保有するテレビA及びB放送の各株式も、本件増資当時非上場で、その評価は、AT社株式と同様、同9-1-14(4)に基づき、時価純資産価額方式に従ってすべきである。なお、本件においては、企業の継続を前提とした客観的交換価値を求めるのであり、清算所得に対する法人税額等を控除しないのが相当である。
(3)以上のように解すると、争点3に対する判断を要しない。
(4)本件においては、Yの法22条2項に基づく課税の主張は、時機に後れた攻撃防御方法に当たらず、本件更正に理由附記の不備はなく、本訴における更正理由の追加的主張も許容され、かつ、X会社が主張する憲法違反にもそれぞれ理由がない。
五、上告審判決要旨
原判決破棄、原審差戻し。
(1)前記事実関係等によれば、X会社は、AT社の唯一の株主であったというのであるから、第三者割当により同社の新株の発行を行うかどうか、だれに対してどのような条件で新株発行を行うかを自由に決定することができる立場にあり、著しく有利な価額による第三者割当増資を同社に行わせることによって、その保有する同社株式に表章された同社の資産価値を、同株式から切り離して、対価を得ることなく第三者に移転させることができたものということができる。そして、X会社が、AT社の唯一の株主の立場において、同社に発行済株式総数の15倍の新株を著しく有利な価額で発行させたのは、X会社のAT社に対する持株割合を100%から6.25%に減少させ、AF社の持株割合を93.75%とすることによって、AT社株式200株に表章されていた同社の資産価値の相当部分を対価を得ることなくAF社に移転させることを意図したものということができる。
以上によれば、X会社の保有するAT社株式に表章された同社の資産価値については、X会社が支配し、処分することができる利益として明確に認めることができるところ、X会社は、このような利益を、AF社との合意に基づいて同社に移転したというべきである。したがって、この資産価値の移転は、X会社の支配の及ばない外的要因によって生じたものではなく、X会社において意図し、かつ、AFにおいて了解したところが実現したものということができるから、法22条2項にいう取引に当たるというべきである。
(2)法人税基本通達9-1-14(4)のような一般的、抽象的な評価方法の定めのみに基づいて株式の価額を算定することは困難であり、他方、財産評価基本通達の定める非上場株式の評価方法は、相続又は贈与における財産評価手法として一般的に合理性を有し、課税実務上も定着しているものであるから、これと著しく異なる評価方法を法人税の課税において導入すると、混乱を招くこととなる。このような観点から、法人税基本通達9-1-15は、財産評価基本通達の定める非上場株式の評価方法を、原則として法人税課税においても是認することを明らかにするとともに、この評価方法を無条件で法人税課税において採用することは弊害があることから、1株当たりの純資産価額の計算に当たって株式の発行会社の有する土地を相続税路線価ではなく時価で評価するなどの条件を付して採用することとしている。したがって、財産評価基本通達185が定める1株当たりの純資産価額の算定方式を法人税課税においてそのまま採用すると、相続税や贈与税との性質の違いにより課税上の弊害が生ずる場合には、これを解消するために修正を加えるべきであるが、このような修正をした上で同通達所定の1株当たりの純資産価額の算定方式にのっとって算定された価額は、一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして、法人税基本通達9-1-14(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきである。そして、このように解される同通達9-1-14(4)、9-1-15の定めは、法人の収益の額を算定する前提として株式の価額を評価する場合においても合理性を有するものとして妥当するというべきである。
ところで、財産評価基本通達185が、1株当たりの純資産価額の算定に当たり法人税額等相当額を控除するものとしているのは、個人が財産を直接所有し、支配している場合と、個人が当該財産を会社を通じて間接的に所有し、支配している場合との評価の均衡を図るためであり、評価の対象となる会社が現実に解散されることを前提としていることによるものではない。したがって、営業活動を順調に行って存続している会社の株式の相続及び贈与に係る相続税及び贈与税の課税においても、法人税額等相当額を控除して当該会社の1株当たりの純資産価額を算定することは、一般的に合理性があるものとして、課税実務の取扱いとして定着していたものである。
法人税基本通達については、平成12年課法2-7による改正により、法人税課税における1株当たりの純資産価額の評価に当たり法人税額等相当額を控除しないことが規定されるに至ったのであって、この改正前の平成7年2月ころに、財産評価基本通達185が定める1株当たりの純資産価額の算定方式のうち法人税額等相当額を控除する部分が、法人税課税における評価に当てはまらないということを関係通達から読み取ることは、一般の納税義務者にとっては不可能である。取引相場のない株式の取引は、法人税額等相当額を控除した純資産価額を上回る価額でされることもあり得るが、一般にその取引の当事者は上記関係通達の定める評価方法に関心を有するものであり、その評価方法が取引の実情に影響を与え得るものであったことは否定し難く、これとかけ離れたところに取引通念があったということはできない。
したがって、企業の継続を前提とした株式の評価を行う場合であっても、法人税額等相当額を控除して算定された1株当たりの純資産価額は、平成7年2月当時において、一般には通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものであり、これを前提に法人の収益の額を算定することは、法人税法の解釈として合理性を有するということができる。
(3)B放送及びJGI社が保有するFテレビ株式は、同通達188(1)にいう「同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以外の株主の取得した株式」に該当し、同通達188、財産評価基本通達188-2においては配当還元方式により評価すべきこととなる。同通達が、上記株式の評価を配当還元方式によることとしているのは、少数株主が取得した株式については、株主は単に配当を期待するにとどまるという実質を考慮したものである。もっとも、X会社の主張するB放送及びJGI社の合計持株比率は、同族株主に該当するかどうかの基準である30%を下回り、筆頭株主の持株比率に劣るものの、その割合は低いものではないから、事業経営への影響力の実情によっては、B放送及びJGI社が単に配当を期待してFテレビ株式を保有していたと評価するのが適当でないこともあると考えられ、そうであるとすれば、本件において同株式を配当還元方式により評価することが著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらす場合もあると考えられる。
ところが、原審は、上記の持株比率や課税上の弊害について何ら審理判断することなく、Fテレビ株式を法人税基本通達9-1-14(4)に基づき時価純資産価額方式により評価すべきであるという結論を導いている。したがって、原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
仮にB放送及びJGI社が保有するFテレビ株式を配当還元方式により評価することに前記の課税上の弊害があるとすれば、法人税基本通達9-1-14(4)に基づき時価純資産価額方式により評価すべきことになる。この場合には、財産評価基本通達186-3の趣旨が妥当するところ、前記のとおり、B放送の純資産価額の算定において法人税額等相当額を控除するのであるから、Fテレビの純資産価額については、重ねて法人税額等相当額を控除することなく算定すべきである。
(4)前記事実関係等によれば、平成7年2月当時、AT社が保有するテレビA株式は、原審におけるX会社の主張によれば、そのころのテレビAの株主の持株比率は、その筆頭株主のグループが38.3%であり、AT社及びその同族関係者が合計21.4%であるから、同社が保有するテレビA株式は、同通達188(1)にいう「同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以外の株主の取得した株式」に該当し、同通達188、財産評価基本通達188-2においては配当還元方式により評価すべきこととなる。
もっとも、記録によれば、①X会社は、平成7年3月1日、100%出資の子会社であるOメディアを設立したこと、②X会社は、同月13日、Oメディアに対し、テレビA株式1,242株を1株当たり540万円で譲渡したこと、③ 同価額は、X会社が株式会社元マネージメントサービスに依頼して評価させた同月1日時点の同株式の時価純資産価額方式による評価額を基に算定されたこと、④X会社の主要株主である財団法人N協会は、同月24日、Oメディアに対し、テレビA株式335株を1株当たり540万円で譲渡したこと、以上の事実は当事者間に争いがなく、また、上記評価額は、法人税額等相当額を控除することなく算定されたことがうかがわれる。そうであるとすれば、上記のテレビA株式の各売買において譲渡価額が1株当たり540万円とされたのが、同株式を時価よりも高額で売買するという特別の目的によるものでない限り、上記各売買の当事者は、同株式を配当還元方式により評価するよりも時価純資産価額方式(法人税額等相当額を控除しない。)による方が適切であること、すなわち、同株式の価額を単に配当を期待して株式を保有する株主に妥当する配当還元方式によっては適正に評価することができないことを認識していたものというべきである。そうすると、上記各売買に近接した時期におけるX会社の100%出資の子会社であるAT社の認識も同様であった可能性があり、同社の認識がそのようなものであるとすれば、本件において同社の保有するテレビA株式を配当還元方式により評価することが著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらす場合もあると考えられる。
ところが、原審は、上記の持株比率や課税上の弊害について何ら審理判断することなく、テレビA株式を法人税基本通達9-1-14(4)に基づき時価純資産価額方式により評価すべきであるという結論を導いている。なお、原審は、テレビAが含み益を有する土地を所有することを摘示しているが、このことは、相続税基本通達にのっとり、同土地の相続税路線価を基に算定した1株当たりの純資産価額によってテレビA株式を評価することを不合理とする理由とはなるが、配当還元方式による評価を直ちに不合理とするものではない。したがって、原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
(5)以上によれば、原判決は破棄を免れない。そして、Fテレビ株式及びテレビA株式の評価方法に関して上記各点を審理するとともに、B放送株式を時価純資産価額方式(法人税額等相当額は控除する。)により評価し、これらに基づいてAT社の純資産価額、同社の資産価値のうちAF社に移転した額及びこれを前提としたX会社の納付すべき税額を算定させるため、本件を原審に差し戻すこととする。
六、解説
はじめに
(1)本件は、テレビA等の放送関連会社の株式を多量に所有していたX会社が、その株式等を現物出資(100%)してオランダ法人の子会社(AT社)を設立し、その子会社に増資決議(本件決議)させ、同族関係のオランダ法人の別子会社に著しく有利な価額(額面)で引受けさせた場合(これにより、X会社の子会社の支配割合が100%から6.25%に低下)に、X会社に法22条2項にいう無償取引に係る収益が生じたか否か(寄附金の存否)が主として争われたものである。
問題となったテレビA株式は、その後、オランダ国内のX会社の同族関係者間等を迂回し、最終的には、テレビA会社の親会社たるA新聞社に買取られることとなった。この間、オランダの課税制度を利用しながら、租税負担を回避することによって目的の株式移転が行われている。
このように、多額な含み益を有する株式を海外子会社に現物出資し、その株式を内外の関係会社又は海外に居住する親族に贈与又は低額譲渡をすることにより、法人税、相続税又は贈与税の負担を回避するというタックス・プランニングは、バブルの頃を中心に採用されたところでもある。そのため、平成10年度の法人税法改正では,特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮記帳制度(当時の法51条)において、当該現物出資によって外国法人を設立するものであるときは圧縮記帳を認めないこととされた。
(2)かくして、本訴においては、本件更正の違法性が争われる中で、本件のような場合に法22条2項が適用し得るか、また、法132条を適用し得るかが主として争われたものであるが、前記法人税法の改正との関係も問題とされたほか、本件更正が法132条を適用して行われたため、当初はその適否が争われたところ、本件訴訟の口頭弁論終結予定日の17日前になってY側が主位的主張を法22条2項の適用に切り替えたため、その主張が時機に後れた攻撃防御に当たるか否かも争われた。
また、前述したように、本訴においては、一審判決、控訴審判決及び上告審判決において三者三様の判断がされているところであるが、これも本件の複雑性を物語っていると言える。そこで、本稿では、争点1ないし、争点3に絞って解説することとし、争点4の手続上の論点については、一事例として紹介するに留めることとする。
1 本件増資と法22条2項の適用
(1)法22条2項は、益金の額に算入すべきものとして、別段の定めがあるものを除き、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。」と定めている。
この規定にいう「無償による資産の譲渡」、「無償による役務の提供」及び「無償による資産の譲受け」から収益が生じること(これらを一括して、通常、「無償取引に係る収益」と称される。)については、種々の議論があるが、本件においては、本件決議による増資がどのような理由で無償取引に係る収益を生じさせるかが問題となる。無償による資産の譲渡から収益が生じることについては、一般的には、「無償による譲渡の場合には、現実的には収益は生じないが、一旦収益が実現し、しかる後にそれが贈与されたものと考えるべきである。」(注1)と説明されるが、いずれにしても、含み益のある資産(権利)が譲渡(移転)された時には、当該譲渡資産(権利)に係る評価益相当額(キャピタル・ゲイン)が処分(清算)されたものであるから、譲渡益が実現したと認識され、収益が生じたものと解すべきである(注2)。
この無償による資産の譲渡から収益が生じることについては、企業会計においても問題とされるべきであるが(注3)、定説があるわけではなく、法22条4項の規定が適用される余地は乏しいようである。
(2)本件においては、本件決議と本件増資(払込み)によって、X会社が直接テレビA株式等を譲渡(移転)したわけではなく、本件増資に係る潜在的に有していた新株引受権又はAT社株式を通して保有していたテレビA株式等の含み益をX会社がAF社に譲渡(寄附)したものといえる。そして、この取引により、X会社は、AT社の株式を通して間接的に保有していたテレビA株式等の含み益を希薄化(譲渡)したものと認めることができる。このように解すれば、本件決議と本件増資について法22条2項を適用し、X会社側に収益が生じ寄附(当該取引において当該含み益をAF社に実質的に贈与したことは明らかである。)があったものと認定することもできる。
しかしながら、一審判決は、前述のように、X会社に対して法22条2項は適用できない旨結論付けている。
(3)これに対し、控訴審判決は、前述のように、一審判決を厳しく批判し、法22条2項の適用を認めた。
更に、上告審判決も、「この資産価値の移転は、X会社の支配の及ばない外的要因によって生じたものではなく、X会社において意図し、かつ、AF社において了解したところが実現したものということができるから、法22条2項にいう取引に当たるというべきである。」旨判示した。このような控訴審判決及び上告審判決については、法人税法の解釈を誤ったものとして厳しい批判(注4)も存するが、X会社、AT社及びAF社の株主構成と役員構成からすれば、本件決議も本件増資もX会社の意思決定の介在がなければ成立しないことがらであることは明白であるから、結局、控訴審判決及び上告審判決の方が相当であると解さざるを得ないであろう(注5)。
2 本件増資と法132条の適用
(1)当初、本件更正は法132条の適用によって行われたものであるが、本訴においては、Yは、当該規定の適用を予備的主張に変えている。しかしながら、一審判決は、前述のように、本件増資はAT社が行ったものでX会社の行為とは認められないから、本件において法132条の規定を適用する余地はない旨判示している。
これに対し、控訴審判決は、前述のように、本件増資についてX会社に対し法22条2項を適用し得ると判断した上で、法132条の適用の可否に関しては本件において判断を要しない旨判示している。また、上告審判決は、本件増資について法22条2項を適用し得ることを明確にし、法132条の適用問題について何ら言及していないが、言及するまでもないことが窺い知ることができる。
(2)ところで、本件において法22条2項を適用することの相当性については、前述のように、控訴審判決及び上告審判決が容認するところであり、その結論自体については妥当であると考えられる。しかしながら、本件増資が法22条2項にいう「資産の譲渡」に当たるのか、「その他の取引」に当たるのかについては、必ずしも判然としないところも存する。また、本件における一連の取引は、我が国の法人税負担を回避しようとしていることも明らかである。そうであれば、本件更正のような課税処分に当たっては、法132条の適用もあながち違法であるとも断定できないものと解される。もっとも、この場合、法132条の規定を単独で適用し得る場合も考えられるであろうし、法22条2項の規定の適用を補強する方法(援用)も考えられる。
3 法人税法における非上場株式の評価
(1)本件においては、X会社は、テレビA株式等の含み益の大きい資産を現物出資してAT社を設立し、当該含み益を顕現しないで済む圧縮記帳を利用した後、本件増資によってAT社の持分を減額させたものであるが、本件増資が法22条2項にいう「無償による資産の譲渡」に該当するとなると、当該無償部分についての価額認定を要することになる。この価額認定は、AT社株式の評価に先立って、AT社が保有することとなるテレビA株式等の価額が問題となるが、それらの株式の大部分が非上場株式であるため、当該株式の時価評価を要することになる。
この点、一審判決においては、本件増資が「無償による資産の譲渡」に当たらないと判断しているため、当該関係株式の時価評価が問題となることはない。また、控訴審判決においては、本件更正においてYが援用した評価方法(法人税基本通達9-1-14(4)の規定に基づく時価純資産価額方式で、評価差額に係る法人税額等相当額を控除しないもの)を容認しているため、判決上特に問題とされることはなかった。
これらの下級審判決に対し、上告審判決においては、本件増資については法22条2項の適用を認めた上で、無償部分の資産移転についてその基となるテレビA、B放送等の関係株式の評価額(評価方法)を問題視し、当該評価額と税額を正確に計算させるため、本件を原審に差し戻すこととした。
(2)法人税における非上場株式の価額の評価については、本来、法人税法の解釈(認定)として当該個別事案に対応して行われるべきものであろうが、裁判例においても、当該課税処分が取扱い通達に基づいていることもあって、当該通達における取扱いの合理性の有無を判断することによって行われる場合が多い。
本件の上告審判決においても、その例によっており、具体的には、当時(平成7年)の法人税基本通達9-1-14及び9-1-15の取扱いの合理性を容認し、かつ、9-1-15が「課税上弊害がない限り」原則として財産評価基本通達の取扱いの準用を定めていることに対応して、財産評価基本通達における取引相場のない株式の評価方法の合理性についても容認している。
そのため、本件においては、関係株式の価額の評価において純資産価額方式を適用する場合に、当時の財産評価基本通達において原則としてその控除が認められていた評価差額に係る法人税額等相当額の控除が本件更正において何故に認められなかったかが、上告審において最大の問題となった。
4 法人税額等相当額控除の可否と平成17年11月判決との対比
(1)ところで、純資産価額方式における評価差額に係る法人税額等相当額の控除の趣旨は、上告審判決も認めるように、「個人が株式の所有を通じて会社の資産を間接的に所有している場合と個人事業主として直接に事業用資産を所有する場合とでは、その所有形態の差異によりその処分性等に差があるものと認められるので、両者の評価上の均衡を図ろうとする配慮に基づくものである。」と、一般的にも解されている(注6)。また、このような直接所有と間接所有の評価バランスは、当然、法人が所有している場合にも適合することである。なお、このような間接所有(支配)と直接所有(支配)の評価上のバランスを図ることは、貸宅地の評価(評基通25)等にも配慮されている。
しかしながら、本件の控訴審判決は、本件のような企業の継続を前提とした客観的交換価値を求める場合には、法人税額等相当額の控除を要しない旨判示している。これに対し、上告審判決は、法人税額等相当額の控除は当該財産の直接所有と間接所有の評価バランスを図るためのものであり、評価会社が現実に解散することを前提としていないから、当該控除は一般的に合理性があるものとして、課税実務の取扱いにおいて定着していた旨判示し、平成12年の法人税基本通達の改正に敷衍しつつ、平成7年2月当時において、当該控除が、一般的には通常の取引における当事者の合理的意思に合致し、法人税法の解釈として合理性を有する旨判示している。
(2)このような上告審判決は、同じく最高裁判所第三小法廷から出された平成17年11月8日判決(平成14年(行ヒ)第112号、以下「平成17年11月判決」という。)(注7)と共通しているが、両者の間に重要な差異もある。すなわち、本件の上告審判決が法人税に係るもので、平成17年11月判決が所得税に係るものという税目上の差異はあるが、それ以上の重要性は、平成17年11月判決が昭和62年の取引に対するものであるのに対し、本件上告審判決が平成7年の取引に対するものという時間的差異と、平成17年11月判決が評価会社それ自体の株式の評価に係るものであるのに対し、本件上告審判決が評価会社(AT社)が所有しているテレビA株式やB放送株式の評価に係るものであるという差異である。
このような差異は、両判決が、関係通達の取扱いの変遷と課税実務上の定着状態を重視して、それぞれにおける法人税額等相当額の控除の必要性を指摘しているところから生じている。しかしながら、両判決が判示する関係通達の取扱いの変遷等の認定には不十分なところも見受けられるので、それらを明らかにする必要がある。
(3)すなわち、法人税額等相当額控除を巡る通達の変遷とその背景は、次のように認め得る(注8)。
まず、法人税額等相当額の控除が相続税財産評価に関する基本通達(財産評価基本通達の平成3年改正前のもの)に設けられたのは、昭和47年のことであるが、当時は、主として、中小企業の事業承継の円滑化に配慮したものであった。その後、法人税額等相当額の控除は、上告審判決が判示するように、個人事業主が直接財産を所有支配している場合と会社が所有している財産を間接的に所有支配している場合との評価のバランスを図るためのものであると一般に容認されている。昭和55年には、法人税基本通達が前記通達の準用規定を設けたが、当該控除等の制限規定を設けなかった。
ところが、平成元年3月には、いわゆる負担付贈与通達が発出され、土地、家屋等につき取引価額と評価額の開差を利用した過度な節税(租税回避)が封じられた。これを契機に、その秋には、所得税につき、土地等を低額で現物出資し、その取得株式の評価(収入金額の認定)において法人税額等相当額の控除を否認する旨の国税庁情報が出された。
その翌年の8月には、各財産の適正化を図って、上場株式と非上場株式の取引価額と評価額との開差を利用する過度な節税(租税回避)を封ずるために、相続税財産評価に関する基本通達の大改正が行われた。その改正では、純資産価額方式について、法人税額等相当額の控除につき、いわゆる累積控除を排除するために、評価会社の株式については控除を行うが、評価会社が所有している取引相場のない株式に係る法人税額等相当額の控除を認めないこととした。
この通達改正に対応して、いわゆるA社・B社方式が多発したこともあって、同通達6項を適用して法人税額等相当額控除を否認する課税処分が行われ、平成6年の通達改正では、取引相場のない株式を現物出資した場合にはその控除を否認することとし、平成11年の通達改正では、全ての財産を現物出資等をして取引相場のない株式を取得している場合には、その控除を否認することとした。
かくして、このような財産評価基本通達等の改正の前後において、所得税及び法人税の非上場株式の評価においても、法人税額等相当額の控除を否認する課税処分が増加し、それを追認するように、平成12年には、所得税基本通達及び法人税基本通達において、財産評価基本通達を準用する場合には、その控除を否定することを明記した。
(4)このような関係通達の変遷等を考慮してみると、平成17年11月判決と本件上告審判決については、次のような点が問題となる(注9)。まず、平成17年11月判決は、昭和62年当時には、法人税額等相当額の控除が解釈上定着していたと判断しているが、前述の関係通達等の改正の経緯に照らしても、その判断は妥当であると考えられる。
しかし、その判決は、法人税額等相当額の控除を行うことが所得税法の解釈上合理性を有すると判示しているのではあるが、そうであれば、その後の関係通達の改正の方が法の解釈の合理性に反することにもなる。さらに、法人税額等相当額の控除の容認は、昭和62年から何時まで可能であったのか、また、その可能な期間における法人税額等相当額の控除を容認した課税処分の効力がどうなるのかが問題となる。
かくして、本件上告審判決となったが、この判決にも、二つの問題がある。一つは、これは平成7年の非上場株式の現物による海外子会社の設立に関する課税であるが、平成7年には、前記の評価通達の改正もあって、法人税等においても、法人税額等相当額の控除を否認する課税処分が増えてきた頃であり、当該控除が容認されることが実務上定着していたわけでもなかった。にもかかわらず、上告審判決は、本件において当該控除を容認すべきとしているので、平成12年の改正まで全て容認すべきというにも読める。
また、平成2年の相続税財産評価に関する基本通達の改正は、前述のように、評価会社が所有している非上場株式に係る法人税額等相当額の控除を否認したものであるが、上告審判決は、評価会社であるAT社が所有しているテレビA株式やB放送株式に係るその控除を容認すべきとしている。これは、上告審判決が関係通達の改正の経緯を見誤ったものか、関係通達の改正とは別に当該控除のあり方に新たな一石を投じたものか、理解に苦しむところがある。いずれにしても、このような通達における取扱いと法人税法上の「価額」の解決が混同しているようであり、通達の法的位置付けが不十分である。
5 本件各判決の意義と問題点
(1)以上のように、本件各判決は、法22条2項の解釈と非上場株式の価額を純資産価額方式で評価する場合における法人税額等相当額の控除のあり方について、それぞれ重要な判断を示している。
前者については、完全支配関係にある親子会社間において子会社が多額な第三者割当増資を行って親会社の子会社に対する持分を大幅に減じた場合(注10)に、それが親会社の法22条2項にいう無償取引と認め得るか否かが問題となったのであるが、一審判決がそれを否定し、控訴審判決及び上告審判決がそれを肯定した。この問題は、法22条2項の解釈上微妙な論点を抱えているだけに、特に、上告審判決は、先例として重要な役割を果たすことが見込まれる。
後者については、法人税における非上場株式の価額の評価のあり方が問題となったものであるが、その中にも、法解釈における関係通達の位置付けが行われたことと、非上場株式の価額を純資産価額方式によって評価する場合の法人税額等相当額の控除のあり方が示されたことが注目される。
(2)しかしながら、上告審判決及び平成17年11月判決は、それぞれの課税取引時における関係通達の取扱いの合理性を容認し、法人税法又は所得税法の解釈上も合理性がある旨判示しているのであるが、そうであれば、その後の関係通達が当該取扱いを変更していることとの法解釈上の整合性が問題視されて然るべきであると考えられる。
また、純資産価額方式における法人税額等相当額の控除については、平成17年11月判決が昭和62年の取引について認めるべきとしたことは、関係通達の改正の経緯に照らし首肯できるが、本件上告審判決が平成7年の取引について同様の判断を示したことは、関係通達の改正の経緯に照らし、昭和62年当時と同様に論じられてよいのかということの疑問について既に指摘した。
更に、上告審判決は、評価会社となるAT社が所有しているテレビA株式やB放送株式の価額の評価についても法人税額等相当額の控除を容認すべき旨判示しているのであるが、平成2年の相続税財産評価に関する基本通達の改正等の経緯に照らすと、課税実務の定着状況の観点から疑問が残ることも指摘した。
これらの諸問題については、本件の差戻し審において明らかにされるであろうが、平成17年11月判決の差戻し審との関係もあるので、両者の差戻し審とも大いに注目されるところである。
(注1)沼田嘉穂ほか「会社税務釈義」(第一法規)1429頁。
(注2)品川芳宣「課税所得と企業利益」(税務研究会)17頁等参照。
(注3)企業会計審議会の「税法と企業会計との調整に関する意見書」(昭和41年10月17日)は、「資産を無償譲渡又は低額譲渡した場合に、当該資産の適正時価を導入した収益を計上することの当否については、企業会計原則上まだ何ら触れるところがないので、これを明らかにすることが妥当である。」(総論三の(7))と述べているが、その後これに対する答は出されていない。
(注4)大渕博義「法人税法解釈の判例理論の検証とその実践的展開」税経通信2006年3月号25頁参照。
(注5)品川芳宣「重要租税判決の実務研究増補改訂版」(大蔵財務協会)260頁、同「現物出資による海外子会社設立と当該子会社株式の移転」TKC税研情報2002年6月号45頁等参照。
(注6)品川芳宣「取引相場のない株式(出資)の時価と評価通達6項の適用要件(下)」T&Amaster2004年9月20日号28頁、最高裁平成17年11月8日第三小法廷判決(平成14年(行ヒ)第112号)(解説として、品川芳宣・T&Amaster2006年2月27日号24頁)等参照。
(注7)本判決の解説として、品川芳宣・T&Amaster2006年2月27日号24頁、同・TKC税研情報2006年4月3日号68頁参照。
(注8)詳細については、品川芳宣・緑川正博「相続税財産評価の理論と実践」(ぎょうせい)30頁以下参照。
(注9)品川芳宣「法人税額等相当額控除の行方?」旬刊速報税理2006年3月21日号14頁参照。
(注10)本件は、子会社が外国法人の場合であるが、子会社が内国法人であっても同様な問題が生じる(川田剛「外国子会社の第三者割当てと親会社への受贈益課税の可否」国際税務2006年3月号50頁参照)。
品川芳宣 (しながわよしのぶ)
国税庁審理課課長補佐、東京地裁調査官、税務大学校教育二部長、国税庁資産評価企画官、同徴収課長、同管理課長、高松国税局長などを経て、平成7年筑波大学教授。平成17年早稲田大学大学院客員教授(専任)、筑波大学名誉教授、税務大学校客員教授。弁護士
【主要著書】
『課税所得と企業利益』(税務研究会)、『役員給与税務事例集』(商事法務研究会)、『役員報酬の法律と実務』(同)、『附帯税の事例研究』(財経詳報社)、『法人税の判例』(ぎょうせい)、『相続税財産評価の論点』(同)、『重要租税判決の実務研究・増補改訂版』(大蔵財務協会)、『役員報酬の税務事例研究』(財経詳報社)、『租税法律主義と税務通達』(ぎょうせい)、『徹底解明相続税財産評価の理論と実践』(同)他多数。
東京地裁平成13年11月9日判決 訟務月報 49巻8号2410頁
東京高裁平成16年1月28日判決 訟務月報 50巻8号2512頁
最高裁平成18年1月24日第三小法廷判決 判例タイムズ 1203号108頁
早稲田大学大学院客員教授(専任)
筑波大学名誉教授
品川 芳宣
一、事実
(1)本件は、X会社(原告・被控訴人・上告人)が、非上場株式を現物出資(100%支配)してオランダに設立した外国子会社であるAT社の株主総会において、新たに発行する新株全部をX会社の外国における関連会社であるAF社に著しく有利な価額で割り当てる決議(以下「本件決議」という。)を行わせ、X会社が保有していたAT社株式の資産価値を何らの対価も得ずにAF社に移転させた場合に、Y(被告・控訴人・被上告人)税務署長が、その移転した資産価値相当額をAF社に対する寄附金と認定し、X会社の平成6年10月1日から平成7年9月30日までの事業年度(以下「平成7年9月期」という。)の法人税の更正処分(以下「本件更正」という。)及び過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定」という。)をしたため、X会社が、本件更正処分のうち納付すべき税額2億6,494万円余を超える部分及び本件賦課決定はいずれも違法であるとしてその取消しを求めた事案である。
(2)本件の取引の概要は、次のとおりである。
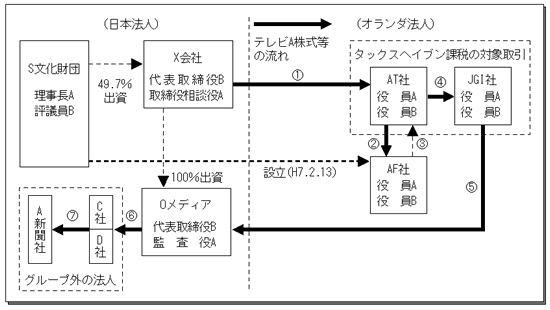
〈取引の説明〉
① 平成3年9月4日
当時の法人税法51条の圧縮記帳を利用して、所有していたテレビA株式(3,559株)、B放送株式等を現物出資し、AT社を設立(発行済株式数200株)、X会社の持株割合100%。
② 平成7年2月13日
本件決議に基づきAT社をして、増資新株3,000株をAF社に割当てさせる(以下「本件増資」という。)。
③ 平成7年2月15日
②の割当てにより、AF社が本件増資払込303万0,303ギルダー(邦貨換算額1億7,627万2,725円)を払い込む。X会社の持株割合は6.25%に低下。
④ 平成8年7月30日
テレビA株式(3,559株)を28,649百万円で売却。AF社の持株割合93.75%分については、S文化財団が公益法人であるためタックスヘイブン課税の対象とならず。
⑤ 平成8年9月5日
テレビA株式(3,559株)を28,932百万円で売却。
⑥ 平成8年12月2日
企業買収により、テレビA株式を保有するOメディア株式をグループ外へ売却。
⑦ 平成9年3月31日、同年4月1日
A新聞社は、テレビA株式を保有するOメディア株式(商号変更により株式名は変更した後のもの)をC社及びD社から企業買収により取得。
二、争点と当事者の主張
1 争点
(1)争点1(本件増資と法人税法(以下「法」という。)22条2項に規定する無償による資産の譲渡の有無等)
(2)争点2(本件増資による資産の移転額、課税額)
(3)争点3(本件増資と法132条1項1号に基づく課税の当否)
(4)争点4(訴訟手続、課税手続上の問題、課税の憲法違反)
① 法22条2項の適用に関するYの主張と時機に後れた攻撃防御方法
② 本件更正の理由附記についての不備
③ 本件更正の理由の差替えの法130条2項違反、憲法14条等違反
2 Yの主張
(1)本件増資は、X会社、AT社及びAF社の合意に基づき、AT社株式の資産価値を分割し、対価を得ることなく、その資産価値の一部をX会社からAF社に移転させたもので、法22条2項の無償による資産の譲渡又はその他の取引及び法37条2項の寄附金に該当する。
(2)AT社の株式は、独立当事者間の適当な売買実例がないこと、株式公開途上にはなく、公募等の価格がないこと、同社と事業の種類や収益の状況等において類似する法人がないことから、法人税基本通達9-1-14(4)(平成12年改正前のもの、以下同じ)に基づき、時価純資産価額方式により評価した。AT社の資産の大部分をしめるテレビA株式及びB放送株式も、本件増資当時、いずれも非上場であり、同様に評価することとすると、AT社の純資産価額は、テレビA株式188億円余、B放送株式82億円余となり、その他の資産、負債を加減して計算することとなる。
なお、清算所得に対する法人税額等の控除(51%)は、時価純資産価額方式により評価する場合、企業の継続を前提とした客観的交換価値を求めるため、しない。
(3)法132条1項1号の「行為」は、必ずしも法22条2項の資産の譲渡等の取引に当たる必要はなく、不当な法人税の減少をもたらす一切の行為がこれに当たる。本件増資決議における議決権の行使は、法132条1項1号の行為に当たる。
(4)X会社が主張するような訴訟手続及び課税手続上の違反はなく、また、憲法違反も存しない。
3 X会社の主張
(1)キャピタルゲインへの課税は、株主が会社に対する管理支配権を行使したかどうかではなく、当該キャピタルゲインが株主に帰属したか否かによる。本件増資においては、X会社の保有する旧株式200株についてのキャピタルゲインの全部又は一部が、抽象的所有権に止まったまま(利得が実現されることなく)、失われたのであり、未だ実現していない利得は、課税されるべきではない。法22条2項は、すべての無償による資産の譲渡又はその他の無償取引から必ず益金が発生する旨を規定しているのではなく、同条4項の「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に従って益金を計算するに際し、「無償による資産の譲渡」又は「その他の無償取引」から益金が発生する場合があり得ることを規定しているにすぎない。
(2)AT社の株式の評価については、法人税基本通達9-1-14と9-1-15の有利な方を適用でき、後者を適用すると、テレビA株式等は配当還元方式を、B放送株式等は時価純資産価額方式を基礎として算定すべきであり、X会社の有価証券に係る利益の計上もれは24億円余となる。
なお、AT社の保有する株式をすべて時価純資産価額方式により評価する場合、清算所得に対する法人税額等(本件増資当時51%。財産評価基本通達185、186-2)を控除すべきで、これによるとX会社の有価証券に係る利益の計上もれは177億円余となる。
(3)法132条1項1号は、税務署長が法人税の負担を不当に減少させると判断した場合、裁量で課税できると定め、客観的、合理的基準により課税される保障がなく、租税法律主義、課税要件明確主義を定めた憲法84条、30条に違反する。また、①株式の第三者有利発行の際、旧株主には課税されず、②平成10年の法51条改正前には、圧縮記帳された現物出資に係る資産の含み益に対し、結果的に日本国の課税権が及ばなかったことなどの事情から見ると、本来課税できない被控訴人の行為、計算にのみ法132条1項1号を適用してした本件更正は、平等主義を定めた憲法14条に違反する。
なお、AF社は、増資の対価を支払うなら、X会社にではなく、保有株の価値を高めるためにAT社に払い込むのであり、X会社への支払いを合理的な行為というYの主張は、法132条1項1号の前提を欠く。
(4)Yが本件更正の法的根拠として第6回口頭弁論において法132条を主張するのは、時機に後れた攻撃防御となり(民事訴訟法157条)、本件更正には理由附記不備の違法があり、かつ、更正の理由の差替えを認めることには憲法14条違反となる等の手続上の違法がある。
三、一審判決要旨
請求認容。
(1)本件決議はAT社の株主総会が内部的な意思決定をしたのにほかならず、その段階では未だ増資の効果は生じていないのであって、AF社が本件増資により資産価値を取得したとすれば、それは、法形式においては、AT社の執行機関が本件決議を受けて同社の行為として増資を実行し、AF社が新株の引受人として払込行為をしたことによるものである。そうすると、本件増資は、AT社自体による本件増資の実行という行為とそれに応じてAF社がAT社に対して新株の払込みをするという行為により構成されており、本件増資の結果、AF社の払込金額と本件増資により発行される株式の時価との差額がAF社に帰属することとなったとの取引的行為としてとらえるとすれば、本件増資をして新株の払込みを受けたAT社と有利な条件でAT社から新株の発行を受けたAF社の間の行為にほかならず、X会社はAF社に対して何らの行為もしていないというほかない。
(2)本件更正処分の理由として法132条を適用すべき旨のYの主張は、X会社自らの行為によりその保有するAT社株式の資産価値がAF社に移転したとの事実を前提として、同資産価値の移転について法132条を適用して課税しようとするものである。しかしながら、X会社の保有するAT社株式の資産価値がAF社に移転したことが、X会社自らの行為によるものとは認められないことは、前示判示のとおりである。したがって、Yの主張については、その余の点について判断するまでもなく理由がないことは明らかである。
(3)前記結論によると、X会社が保有していた株式に関する多額の含み益については、何らの課税もされない結果が生ずることとなるが、これは、法51条がその定める特定出資についていわゆる圧縮記帳による課税の繰延べを認め、しかも平成10年改正前には外国法人の設立についても同条の適用が認められていたことに端を発するものである。
四、控訴審判決要旨
原判決取消し、請求棄却。
原審の理由説示を次のとおり一部付加するほか、これを引用する。
(1)本件のAT社における持株割合の変化は、各法人及び役員等が意思を相通じた結果にほかならず、X会社は、AF社との合意に基づき、同社からなんらの対価を得ることもなく、AT社の資産につき、株主として保有する持分16分の15及び株主としての支配権を失い、AF社がこれらを取得したと認定評価することができる。そして、X会社が上記資産に係る株主として有する持分をAF社からなんらの対価を得ることもなく喪失し、同社がこれを取得した事実は、それが両社の合意に基づくと認められる以上、両社間において無償による上記持分の譲渡がされたと認定することができる。すなわち、両社間における無償による上記持分の譲渡は、法22条2項に規定する「無償による資産の譲渡」に当たると認定判断することができる。
本件増資は、いわゆる節税を意図して企画されたことは明らかで、納税者として、いわゆる節税を図ることは、もとより、なんら正義に反することではない。本件訴訟につき、AT社とAF社間の行為で、X会社とAF社間に何らの行為もないことを理由に法22条2項の適用を否定するのは、裁判所としての事実認定の責務を果たしておらず、判決の理由としても、不備がある。
原審は、関係当事者の意思及びその結果生じた事実を全体として見ず、一部を恣意的に切り取って結論を導いた誹りを免れず、争点について判断し、紛争を解決に導くべき裁判所の責任を疎かにするものと評せざるを得ない。
(2)AT社は、その株式につき、独立当事者間の適当な売買実例及び公募等がなく、株式公開途上にもなく、同社と事業の種類や収益の状況等において類似する法人もない。このため、その評価は、法人税基本通達9-1-14(4)に基づき、時価純資産価額方式(資産負債を時価評価して純資産価額を算出し、1株当たりの価額を算出する方法)に従ってすべきである。また、同社の保有するテレビA及びB放送の各株式も、本件増資当時非上場で、その評価は、AT社株式と同様、同9-1-14(4)に基づき、時価純資産価額方式に従ってすべきである。なお、本件においては、企業の継続を前提とした客観的交換価値を求めるのであり、清算所得に対する法人税額等を控除しないのが相当である。
(3)以上のように解すると、争点3に対する判断を要しない。
(4)本件においては、Yの法22条2項に基づく課税の主張は、時機に後れた攻撃防御方法に当たらず、本件更正に理由附記の不備はなく、本訴における更正理由の追加的主張も許容され、かつ、X会社が主張する憲法違反にもそれぞれ理由がない。
五、上告審判決要旨
原判決破棄、原審差戻し。
(1)前記事実関係等によれば、X会社は、AT社の唯一の株主であったというのであるから、第三者割当により同社の新株の発行を行うかどうか、だれに対してどのような条件で新株発行を行うかを自由に決定することができる立場にあり、著しく有利な価額による第三者割当増資を同社に行わせることによって、その保有する同社株式に表章された同社の資産価値を、同株式から切り離して、対価を得ることなく第三者に移転させることができたものということができる。そして、X会社が、AT社の唯一の株主の立場において、同社に発行済株式総数の15倍の新株を著しく有利な価額で発行させたのは、X会社のAT社に対する持株割合を100%から6.25%に減少させ、AF社の持株割合を93.75%とすることによって、AT社株式200株に表章されていた同社の資産価値の相当部分を対価を得ることなくAF社に移転させることを意図したものということができる。
以上によれば、X会社の保有するAT社株式に表章された同社の資産価値については、X会社が支配し、処分することができる利益として明確に認めることができるところ、X会社は、このような利益を、AF社との合意に基づいて同社に移転したというべきである。したがって、この資産価値の移転は、X会社の支配の及ばない外的要因によって生じたものではなく、X会社において意図し、かつ、AFにおいて了解したところが実現したものということができるから、法22条2項にいう取引に当たるというべきである。
(2)法人税基本通達9-1-14(4)のような一般的、抽象的な評価方法の定めのみに基づいて株式の価額を算定することは困難であり、他方、財産評価基本通達の定める非上場株式の評価方法は、相続又は贈与における財産評価手法として一般的に合理性を有し、課税実務上も定着しているものであるから、これと著しく異なる評価方法を法人税の課税において導入すると、混乱を招くこととなる。このような観点から、法人税基本通達9-1-15は、財産評価基本通達の定める非上場株式の評価方法を、原則として法人税課税においても是認することを明らかにするとともに、この評価方法を無条件で法人税課税において採用することは弊害があることから、1株当たりの純資産価額の計算に当たって株式の発行会社の有する土地を相続税路線価ではなく時価で評価するなどの条件を付して採用することとしている。したがって、財産評価基本通達185が定める1株当たりの純資産価額の算定方式を法人税課税においてそのまま採用すると、相続税や贈与税との性質の違いにより課税上の弊害が生ずる場合には、これを解消するために修正を加えるべきであるが、このような修正をした上で同通達所定の1株当たりの純資産価額の算定方式にのっとって算定された価額は、一般に通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものとして、法人税基本通達9-1-14(4)にいう「1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額」に当たるというべきである。そして、このように解される同通達9-1-14(4)、9-1-15の定めは、法人の収益の額を算定する前提として株式の価額を評価する場合においても合理性を有するものとして妥当するというべきである。
ところで、財産評価基本通達185が、1株当たりの純資産価額の算定に当たり法人税額等相当額を控除するものとしているのは、個人が財産を直接所有し、支配している場合と、個人が当該財産を会社を通じて間接的に所有し、支配している場合との評価の均衡を図るためであり、評価の対象となる会社が現実に解散されることを前提としていることによるものではない。したがって、営業活動を順調に行って存続している会社の株式の相続及び贈与に係る相続税及び贈与税の課税においても、法人税額等相当額を控除して当該会社の1株当たりの純資産価額を算定することは、一般的に合理性があるものとして、課税実務の取扱いとして定着していたものである。
法人税基本通達については、平成12年課法2-7による改正により、法人税課税における1株当たりの純資産価額の評価に当たり法人税額等相当額を控除しないことが規定されるに至ったのであって、この改正前の平成7年2月ころに、財産評価基本通達185が定める1株当たりの純資産価額の算定方式のうち法人税額等相当額を控除する部分が、法人税課税における評価に当てはまらないということを関係通達から読み取ることは、一般の納税義務者にとっては不可能である。取引相場のない株式の取引は、法人税額等相当額を控除した純資産価額を上回る価額でされることもあり得るが、一般にその取引の当事者は上記関係通達の定める評価方法に関心を有するものであり、その評価方法が取引の実情に影響を与え得るものであったことは否定し難く、これとかけ離れたところに取引通念があったということはできない。
したがって、企業の継続を前提とした株式の評価を行う場合であっても、法人税額等相当額を控除して算定された1株当たりの純資産価額は、平成7年2月当時において、一般には通常の取引における当事者の合理的意思に合致するものであり、これを前提に法人の収益の額を算定することは、法人税法の解釈として合理性を有するということができる。
(3)B放送及びJGI社が保有するFテレビ株式は、同通達188(1)にいう「同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以外の株主の取得した株式」に該当し、同通達188、財産評価基本通達188-2においては配当還元方式により評価すべきこととなる。同通達が、上記株式の評価を配当還元方式によることとしているのは、少数株主が取得した株式については、株主は単に配当を期待するにとどまるという実質を考慮したものである。もっとも、X会社の主張するB放送及びJGI社の合計持株比率は、同族株主に該当するかどうかの基準である30%を下回り、筆頭株主の持株比率に劣るものの、その割合は低いものではないから、事業経営への影響力の実情によっては、B放送及びJGI社が単に配当を期待してFテレビ株式を保有していたと評価するのが適当でないこともあると考えられ、そうであるとすれば、本件において同株式を配当還元方式により評価することが著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらす場合もあると考えられる。
ところが、原審は、上記の持株比率や課税上の弊害について何ら審理判断することなく、Fテレビ株式を法人税基本通達9-1-14(4)に基づき時価純資産価額方式により評価すべきであるという結論を導いている。したがって、原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
仮にB放送及びJGI社が保有するFテレビ株式を配当還元方式により評価することに前記の課税上の弊害があるとすれば、法人税基本通達9-1-14(4)に基づき時価純資産価額方式により評価すべきことになる。この場合には、財産評価基本通達186-3の趣旨が妥当するところ、前記のとおり、B放送の純資産価額の算定において法人税額等相当額を控除するのであるから、Fテレビの純資産価額については、重ねて法人税額等相当額を控除することなく算定すべきである。
(4)前記事実関係等によれば、平成7年2月当時、AT社が保有するテレビA株式は、原審におけるX会社の主張によれば、そのころのテレビAの株主の持株比率は、その筆頭株主のグループが38.3%であり、AT社及びその同族関係者が合計21.4%であるから、同社が保有するテレビA株式は、同通達188(1)にいう「同族株主のいる会社の株主のうち、同族株主以外の株主の取得した株式」に該当し、同通達188、財産評価基本通達188-2においては配当還元方式により評価すべきこととなる。
もっとも、記録によれば、①X会社は、平成7年3月1日、100%出資の子会社であるOメディアを設立したこと、②X会社は、同月13日、Oメディアに対し、テレビA株式1,242株を1株当たり540万円で譲渡したこと、③ 同価額は、X会社が株式会社元マネージメントサービスに依頼して評価させた同月1日時点の同株式の時価純資産価額方式による評価額を基に算定されたこと、④X会社の主要株主である財団法人N協会は、同月24日、Oメディアに対し、テレビA株式335株を1株当たり540万円で譲渡したこと、以上の事実は当事者間に争いがなく、また、上記評価額は、法人税額等相当額を控除することなく算定されたことがうかがわれる。そうであるとすれば、上記のテレビA株式の各売買において譲渡価額が1株当たり540万円とされたのが、同株式を時価よりも高額で売買するという特別の目的によるものでない限り、上記各売買の当事者は、同株式を配当還元方式により評価するよりも時価純資産価額方式(法人税額等相当額を控除しない。)による方が適切であること、すなわち、同株式の価額を単に配当を期待して株式を保有する株主に妥当する配当還元方式によっては適正に評価することができないことを認識していたものというべきである。そうすると、上記各売買に近接した時期におけるX会社の100%出資の子会社であるAT社の認識も同様であった可能性があり、同社の認識がそのようなものであるとすれば、本件において同社の保有するテレビA株式を配当還元方式により評価することが著しく不合理な結果を生じさせるなど課税上の弊害をもたらす場合もあると考えられる。
ところが、原審は、上記の持株比率や課税上の弊害について何ら審理判断することなく、テレビA株式を法人税基本通達9-1-14(4)に基づき時価純資産価額方式により評価すべきであるという結論を導いている。なお、原審は、テレビAが含み益を有する土地を所有することを摘示しているが、このことは、相続税基本通達にのっとり、同土地の相続税路線価を基に算定した1株当たりの純資産価額によってテレビA株式を評価することを不合理とする理由とはなるが、配当還元方式による評価を直ちに不合理とするものではない。したがって、原審の上記判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
(5)以上によれば、原判決は破棄を免れない。そして、Fテレビ株式及びテレビA株式の評価方法に関して上記各点を審理するとともに、B放送株式を時価純資産価額方式(法人税額等相当額は控除する。)により評価し、これらに基づいてAT社の純資産価額、同社の資産価値のうちAF社に移転した額及びこれを前提としたX会社の納付すべき税額を算定させるため、本件を原審に差し戻すこととする。
六、解説
はじめに
(1)本件は、テレビA等の放送関連会社の株式を多量に所有していたX会社が、その株式等を現物出資(100%)してオランダ法人の子会社(AT社)を設立し、その子会社に増資決議(本件決議)させ、同族関係のオランダ法人の別子会社に著しく有利な価額(額面)で引受けさせた場合(これにより、X会社の子会社の支配割合が100%から6.25%に低下)に、X会社に法22条2項にいう無償取引に係る収益が生じたか否か(寄附金の存否)が主として争われたものである。
問題となったテレビA株式は、その後、オランダ国内のX会社の同族関係者間等を迂回し、最終的には、テレビA会社の親会社たるA新聞社に買取られることとなった。この間、オランダの課税制度を利用しながら、租税負担を回避することによって目的の株式移転が行われている。
このように、多額な含み益を有する株式を海外子会社に現物出資し、その株式を内外の関係会社又は海外に居住する親族に贈与又は低額譲渡をすることにより、法人税、相続税又は贈与税の負担を回避するというタックス・プランニングは、バブルの頃を中心に採用されたところでもある。そのため、平成10年度の法人税法改正では,特定の現物出資により取得した有価証券の圧縮記帳制度(当時の法51条)において、当該現物出資によって外国法人を設立するものであるときは圧縮記帳を認めないこととされた。
(2)かくして、本訴においては、本件更正の違法性が争われる中で、本件のような場合に法22条2項が適用し得るか、また、法132条を適用し得るかが主として争われたものであるが、前記法人税法の改正との関係も問題とされたほか、本件更正が法132条を適用して行われたため、当初はその適否が争われたところ、本件訴訟の口頭弁論終結予定日の17日前になってY側が主位的主張を法22条2項の適用に切り替えたため、その主張が時機に後れた攻撃防御に当たるか否かも争われた。
また、前述したように、本訴においては、一審判決、控訴審判決及び上告審判決において三者三様の判断がされているところであるが、これも本件の複雑性を物語っていると言える。そこで、本稿では、争点1ないし、争点3に絞って解説することとし、争点4の手続上の論点については、一事例として紹介するに留めることとする。
1 本件増資と法22条2項の適用
(1)法22条2項は、益金の額に算入すべきものとして、別段の定めがあるものを除き、「資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。」と定めている。
この規定にいう「無償による資産の譲渡」、「無償による役務の提供」及び「無償による資産の譲受け」から収益が生じること(これらを一括して、通常、「無償取引に係る収益」と称される。)については、種々の議論があるが、本件においては、本件決議による増資がどのような理由で無償取引に係る収益を生じさせるかが問題となる。無償による資産の譲渡から収益が生じることについては、一般的には、「無償による譲渡の場合には、現実的には収益は生じないが、一旦収益が実現し、しかる後にそれが贈与されたものと考えるべきである。」(注1)と説明されるが、いずれにしても、含み益のある資産(権利)が譲渡(移転)された時には、当該譲渡資産(権利)に係る評価益相当額(キャピタル・ゲイン)が処分(清算)されたものであるから、譲渡益が実現したと認識され、収益が生じたものと解すべきである(注2)。
この無償による資産の譲渡から収益が生じることについては、企業会計においても問題とされるべきであるが(注3)、定説があるわけではなく、法22条4項の規定が適用される余地は乏しいようである。
(2)本件においては、本件決議と本件増資(払込み)によって、X会社が直接テレビA株式等を譲渡(移転)したわけではなく、本件増資に係る潜在的に有していた新株引受権又はAT社株式を通して保有していたテレビA株式等の含み益をX会社がAF社に譲渡(寄附)したものといえる。そして、この取引により、X会社は、AT社の株式を通して間接的に保有していたテレビA株式等の含み益を希薄化(譲渡)したものと認めることができる。このように解すれば、本件決議と本件増資について法22条2項を適用し、X会社側に収益が生じ寄附(当該取引において当該含み益をAF社に実質的に贈与したことは明らかである。)があったものと認定することもできる。
しかしながら、一審判決は、前述のように、X会社に対して法22条2項は適用できない旨結論付けている。
(3)これに対し、控訴審判決は、前述のように、一審判決を厳しく批判し、法22条2項の適用を認めた。
更に、上告審判決も、「この資産価値の移転は、X会社の支配の及ばない外的要因によって生じたものではなく、X会社において意図し、かつ、AF社において了解したところが実現したものということができるから、法22条2項にいう取引に当たるというべきである。」旨判示した。このような控訴審判決及び上告審判決については、法人税法の解釈を誤ったものとして厳しい批判(注4)も存するが、X会社、AT社及びAF社の株主構成と役員構成からすれば、本件決議も本件増資もX会社の意思決定の介在がなければ成立しないことがらであることは明白であるから、結局、控訴審判決及び上告審判決の方が相当であると解さざるを得ないであろう(注5)。
2 本件増資と法132条の適用
(1)当初、本件更正は法132条の適用によって行われたものであるが、本訴においては、Yは、当該規定の適用を予備的主張に変えている。しかしながら、一審判決は、前述のように、本件増資はAT社が行ったものでX会社の行為とは認められないから、本件において法132条の規定を適用する余地はない旨判示している。
これに対し、控訴審判決は、前述のように、本件増資についてX会社に対し法22条2項を適用し得ると判断した上で、法132条の適用の可否に関しては本件において判断を要しない旨判示している。また、上告審判決は、本件増資について法22条2項を適用し得ることを明確にし、法132条の適用問題について何ら言及していないが、言及するまでもないことが窺い知ることができる。
(2)ところで、本件において法22条2項を適用することの相当性については、前述のように、控訴審判決及び上告審判決が容認するところであり、その結論自体については妥当であると考えられる。しかしながら、本件増資が法22条2項にいう「資産の譲渡」に当たるのか、「その他の取引」に当たるのかについては、必ずしも判然としないところも存する。また、本件における一連の取引は、我が国の法人税負担を回避しようとしていることも明らかである。そうであれば、本件更正のような課税処分に当たっては、法132条の適用もあながち違法であるとも断定できないものと解される。もっとも、この場合、法132条の規定を単独で適用し得る場合も考えられるであろうし、法22条2項の規定の適用を補強する方法(援用)も考えられる。
3 法人税法における非上場株式の評価
(1)本件においては、X会社は、テレビA株式等の含み益の大きい資産を現物出資してAT社を設立し、当該含み益を顕現しないで済む圧縮記帳を利用した後、本件増資によってAT社の持分を減額させたものであるが、本件増資が法22条2項にいう「無償による資産の譲渡」に該当するとなると、当該無償部分についての価額認定を要することになる。この価額認定は、AT社株式の評価に先立って、AT社が保有することとなるテレビA株式等の価額が問題となるが、それらの株式の大部分が非上場株式であるため、当該株式の時価評価を要することになる。
この点、一審判決においては、本件増資が「無償による資産の譲渡」に当たらないと判断しているため、当該関係株式の時価評価が問題となることはない。また、控訴審判決においては、本件更正においてYが援用した評価方法(法人税基本通達9-1-14(4)の規定に基づく時価純資産価額方式で、評価差額に係る法人税額等相当額を控除しないもの)を容認しているため、判決上特に問題とされることはなかった。
これらの下級審判決に対し、上告審判決においては、本件増資については法22条2項の適用を認めた上で、無償部分の資産移転についてその基となるテレビA、B放送等の関係株式の評価額(評価方法)を問題視し、当該評価額と税額を正確に計算させるため、本件を原審に差し戻すこととした。
(2)法人税における非上場株式の価額の評価については、本来、法人税法の解釈(認定)として当該個別事案に対応して行われるべきものであろうが、裁判例においても、当該課税処分が取扱い通達に基づいていることもあって、当該通達における取扱いの合理性の有無を判断することによって行われる場合が多い。
本件の上告審判決においても、その例によっており、具体的には、当時(平成7年)の法人税基本通達9-1-14及び9-1-15の取扱いの合理性を容認し、かつ、9-1-15が「課税上弊害がない限り」原則として財産評価基本通達の取扱いの準用を定めていることに対応して、財産評価基本通達における取引相場のない株式の評価方法の合理性についても容認している。
そのため、本件においては、関係株式の価額の評価において純資産価額方式を適用する場合に、当時の財産評価基本通達において原則としてその控除が認められていた評価差額に係る法人税額等相当額の控除が本件更正において何故に認められなかったかが、上告審において最大の問題となった。
4 法人税額等相当額控除の可否と平成17年11月判決との対比
(1)ところで、純資産価額方式における評価差額に係る法人税額等相当額の控除の趣旨は、上告審判決も認めるように、「個人が株式の所有を通じて会社の資産を間接的に所有している場合と個人事業主として直接に事業用資産を所有する場合とでは、その所有形態の差異によりその処分性等に差があるものと認められるので、両者の評価上の均衡を図ろうとする配慮に基づくものである。」と、一般的にも解されている(注6)。また、このような直接所有と間接所有の評価バランスは、当然、法人が所有している場合にも適合することである。なお、このような間接所有(支配)と直接所有(支配)の評価上のバランスを図ることは、貸宅地の評価(評基通25)等にも配慮されている。
しかしながら、本件の控訴審判決は、本件のような企業の継続を前提とした客観的交換価値を求める場合には、法人税額等相当額の控除を要しない旨判示している。これに対し、上告審判決は、法人税額等相当額の控除は当該財産の直接所有と間接所有の評価バランスを図るためのものであり、評価会社が現実に解散することを前提としていないから、当該控除は一般的に合理性があるものとして、課税実務の取扱いにおいて定着していた旨判示し、平成12年の法人税基本通達の改正に敷衍しつつ、平成7年2月当時において、当該控除が、一般的には通常の取引における当事者の合理的意思に合致し、法人税法の解釈として合理性を有する旨判示している。
(2)このような上告審判決は、同じく最高裁判所第三小法廷から出された平成17年11月8日判決(平成14年(行ヒ)第112号、以下「平成17年11月判決」という。)(注7)と共通しているが、両者の間に重要な差異もある。すなわち、本件の上告審判決が法人税に係るもので、平成17年11月判決が所得税に係るものという税目上の差異はあるが、それ以上の重要性は、平成17年11月判決が昭和62年の取引に対するものであるのに対し、本件上告審判決が平成7年の取引に対するものという時間的差異と、平成17年11月判決が評価会社それ自体の株式の評価に係るものであるのに対し、本件上告審判決が評価会社(AT社)が所有しているテレビA株式やB放送株式の評価に係るものであるという差異である。
このような差異は、両判決が、関係通達の取扱いの変遷と課税実務上の定着状態を重視して、それぞれにおける法人税額等相当額の控除の必要性を指摘しているところから生じている。しかしながら、両判決が判示する関係通達の取扱いの変遷等の認定には不十分なところも見受けられるので、それらを明らかにする必要がある。
(3)すなわち、法人税額等相当額控除を巡る通達の変遷とその背景は、次のように認め得る(注8)。
まず、法人税額等相当額の控除が相続税財産評価に関する基本通達(財産評価基本通達の平成3年改正前のもの)に設けられたのは、昭和47年のことであるが、当時は、主として、中小企業の事業承継の円滑化に配慮したものであった。その後、法人税額等相当額の控除は、上告審判決が判示するように、個人事業主が直接財産を所有支配している場合と会社が所有している財産を間接的に所有支配している場合との評価のバランスを図るためのものであると一般に容認されている。昭和55年には、法人税基本通達が前記通達の準用規定を設けたが、当該控除等の制限規定を設けなかった。
ところが、平成元年3月には、いわゆる負担付贈与通達が発出され、土地、家屋等につき取引価額と評価額の開差を利用した過度な節税(租税回避)が封じられた。これを契機に、その秋には、所得税につき、土地等を低額で現物出資し、その取得株式の評価(収入金額の認定)において法人税額等相当額の控除を否認する旨の国税庁情報が出された。
その翌年の8月には、各財産の適正化を図って、上場株式と非上場株式の取引価額と評価額との開差を利用する過度な節税(租税回避)を封ずるために、相続税財産評価に関する基本通達の大改正が行われた。その改正では、純資産価額方式について、法人税額等相当額の控除につき、いわゆる累積控除を排除するために、評価会社の株式については控除を行うが、評価会社が所有している取引相場のない株式に係る法人税額等相当額の控除を認めないこととした。
この通達改正に対応して、いわゆるA社・B社方式が多発したこともあって、同通達6項を適用して法人税額等相当額控除を否認する課税処分が行われ、平成6年の通達改正では、取引相場のない株式を現物出資した場合にはその控除を否認することとし、平成11年の通達改正では、全ての財産を現物出資等をして取引相場のない株式を取得している場合には、その控除を否認することとした。
かくして、このような財産評価基本通達等の改正の前後において、所得税及び法人税の非上場株式の評価においても、法人税額等相当額の控除を否認する課税処分が増加し、それを追認するように、平成12年には、所得税基本通達及び法人税基本通達において、財産評価基本通達を準用する場合には、その控除を否定することを明記した。
(4)このような関係通達の変遷等を考慮してみると、平成17年11月判決と本件上告審判決については、次のような点が問題となる(注9)。まず、平成17年11月判決は、昭和62年当時には、法人税額等相当額の控除が解釈上定着していたと判断しているが、前述の関係通達等の改正の経緯に照らしても、その判断は妥当であると考えられる。
しかし、その判決は、法人税額等相当額の控除を行うことが所得税法の解釈上合理性を有すると判示しているのではあるが、そうであれば、その後の関係通達の改正の方が法の解釈の合理性に反することにもなる。さらに、法人税額等相当額の控除の容認は、昭和62年から何時まで可能であったのか、また、その可能な期間における法人税額等相当額の控除を容認した課税処分の効力がどうなるのかが問題となる。
かくして、本件上告審判決となったが、この判決にも、二つの問題がある。一つは、これは平成7年の非上場株式の現物による海外子会社の設立に関する課税であるが、平成7年には、前記の評価通達の改正もあって、法人税等においても、法人税額等相当額の控除を否認する課税処分が増えてきた頃であり、当該控除が容認されることが実務上定着していたわけでもなかった。にもかかわらず、上告審判決は、本件において当該控除を容認すべきとしているので、平成12年の改正まで全て容認すべきというにも読める。
また、平成2年の相続税財産評価に関する基本通達の改正は、前述のように、評価会社が所有している非上場株式に係る法人税額等相当額の控除を否認したものであるが、上告審判決は、評価会社であるAT社が所有しているテレビA株式やB放送株式に係るその控除を容認すべきとしている。これは、上告審判決が関係通達の改正の経緯を見誤ったものか、関係通達の改正とは別に当該控除のあり方に新たな一石を投じたものか、理解に苦しむところがある。いずれにしても、このような通達における取扱いと法人税法上の「価額」の解決が混同しているようであり、通達の法的位置付けが不十分である。
5 本件各判決の意義と問題点
(1)以上のように、本件各判決は、法22条2項の解釈と非上場株式の価額を純資産価額方式で評価する場合における法人税額等相当額の控除のあり方について、それぞれ重要な判断を示している。
前者については、完全支配関係にある親子会社間において子会社が多額な第三者割当増資を行って親会社の子会社に対する持分を大幅に減じた場合(注10)に、それが親会社の法22条2項にいう無償取引と認め得るか否かが問題となったのであるが、一審判決がそれを否定し、控訴審判決及び上告審判決がそれを肯定した。この問題は、法22条2項の解釈上微妙な論点を抱えているだけに、特に、上告審判決は、先例として重要な役割を果たすことが見込まれる。
後者については、法人税における非上場株式の価額の評価のあり方が問題となったものであるが、その中にも、法解釈における関係通達の位置付けが行われたことと、非上場株式の価額を純資産価額方式によって評価する場合の法人税額等相当額の控除のあり方が示されたことが注目される。
(2)しかしながら、上告審判決及び平成17年11月判決は、それぞれの課税取引時における関係通達の取扱いの合理性を容認し、法人税法又は所得税法の解釈上も合理性がある旨判示しているのであるが、そうであれば、その後の関係通達が当該取扱いを変更していることとの法解釈上の整合性が問題視されて然るべきであると考えられる。
また、純資産価額方式における法人税額等相当額の控除については、平成17年11月判決が昭和62年の取引について認めるべきとしたことは、関係通達の改正の経緯に照らし首肯できるが、本件上告審判決が平成7年の取引について同様の判断を示したことは、関係通達の改正の経緯に照らし、昭和62年当時と同様に論じられてよいのかということの疑問について既に指摘した。
更に、上告審判決は、評価会社となるAT社が所有しているテレビA株式やB放送株式の価額の評価についても法人税額等相当額の控除を容認すべき旨判示しているのであるが、平成2年の相続税財産評価に関する基本通達の改正等の経緯に照らすと、課税実務の定着状況の観点から疑問が残ることも指摘した。
これらの諸問題については、本件の差戻し審において明らかにされるであろうが、平成17年11月判決の差戻し審との関係もあるので、両者の差戻し審とも大いに注目されるところである。
(注1)沼田嘉穂ほか「会社税務釈義」(第一法規)1429頁。
(注2)品川芳宣「課税所得と企業利益」(税務研究会)17頁等参照。
(注3)企業会計審議会の「税法と企業会計との調整に関する意見書」(昭和41年10月17日)は、「資産を無償譲渡又は低額譲渡した場合に、当該資産の適正時価を導入した収益を計上することの当否については、企業会計原則上まだ何ら触れるところがないので、これを明らかにすることが妥当である。」(総論三の(7))と述べているが、その後これに対する答は出されていない。
(注4)大渕博義「法人税法解釈の判例理論の検証とその実践的展開」税経通信2006年3月号25頁参照。
(注5)品川芳宣「重要租税判決の実務研究増補改訂版」(大蔵財務協会)260頁、同「現物出資による海外子会社設立と当該子会社株式の移転」TKC税研情報2002年6月号45頁等参照。
(注6)品川芳宣「取引相場のない株式(出資)の時価と評価通達6項の適用要件(下)」T&Amaster2004年9月20日号28頁、最高裁平成17年11月8日第三小法廷判決(平成14年(行ヒ)第112号)(解説として、品川芳宣・T&Amaster2006年2月27日号24頁)等参照。
(注7)本判決の解説として、品川芳宣・T&Amaster2006年2月27日号24頁、同・TKC税研情報2006年4月3日号68頁参照。
(注8)詳細については、品川芳宣・緑川正博「相続税財産評価の理論と実践」(ぎょうせい)30頁以下参照。
(注9)品川芳宣「法人税額等相当額控除の行方?」旬刊速報税理2006年3月21日号14頁参照。
(注10)本件は、子会社が外国法人の場合であるが、子会社が内国法人であっても同様な問題が生じる(川田剛「外国子会社の第三者割当てと親会社への受贈益課税の可否」国際税務2006年3月号50頁参照)。
品川芳宣 (しながわよしのぶ)
国税庁審理課課長補佐、東京地裁調査官、税務大学校教育二部長、国税庁資産評価企画官、同徴収課長、同管理課長、高松国税局長などを経て、平成7年筑波大学教授。平成17年早稲田大学大学院客員教授(専任)、筑波大学名誉教授、税務大学校客員教授。弁護士
【主要著書】
『課税所得と企業利益』(税務研究会)、『役員給与税務事例集』(商事法務研究会)、『役員報酬の法律と実務』(同)、『附帯税の事例研究』(財経詳報社)、『法人税の判例』(ぎょうせい)、『相続税財産評価の論点』(同)、『重要租税判決の実務研究・増補改訂版』(大蔵財務協会)、『役員報酬の税務事例研究』(財経詳報社)、『租税法律主義と税務通達』(ぎょうせい)、『徹底解明相続税財産評価の理論と実践』(同)他多数。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















