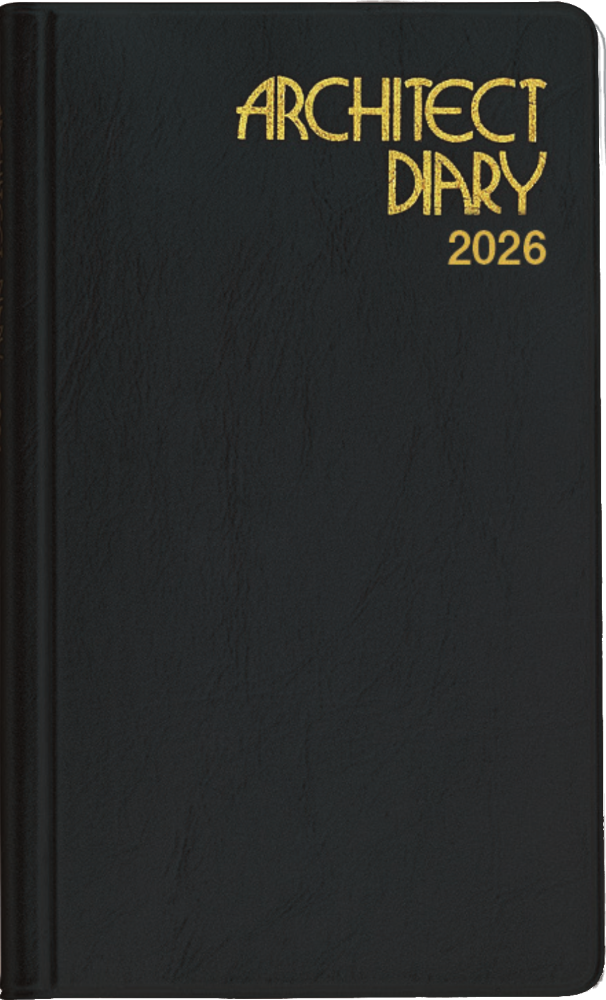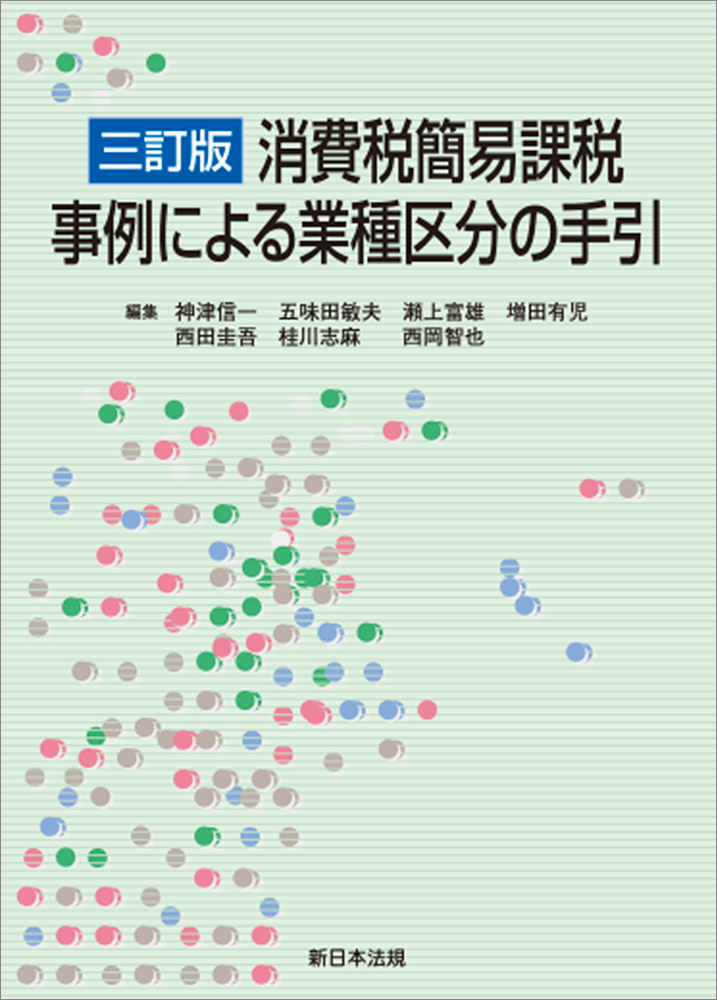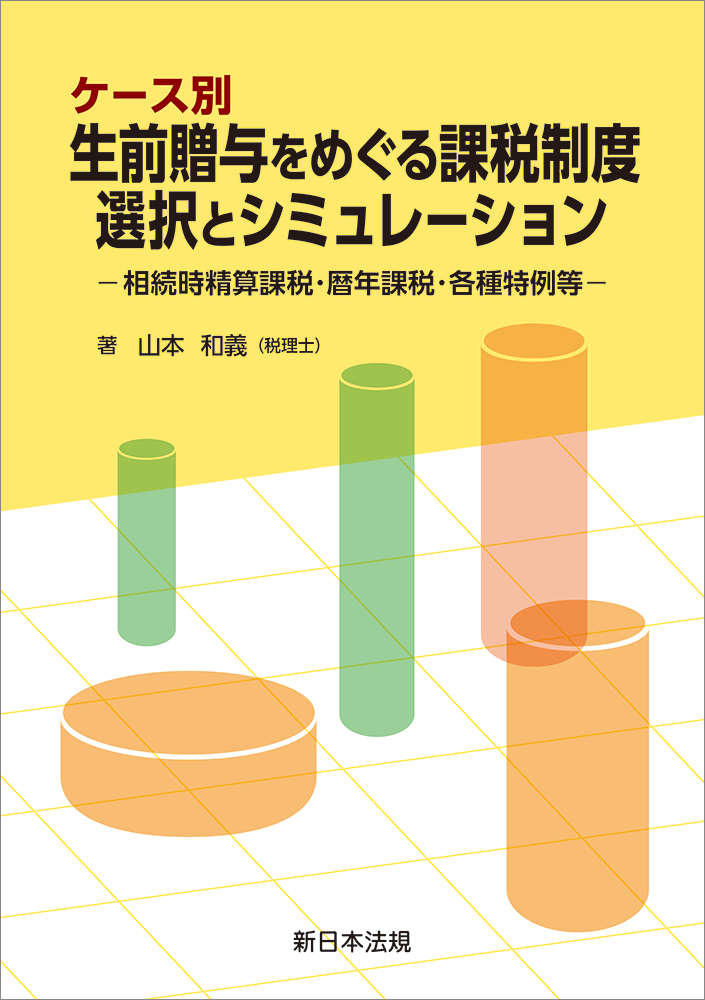解説記事2006年06月19日 【税務解説】 映画フィルムリースと航空機リースの違い(2006年6月19日号・№167)
解説
映画フィルムリースと航空機リースの違い
森・濱田松本法律事務所 弁護士 増田 晋
Ⅰ はじめに
最高裁判所は、2006年1月24日、任意組合を組成して映画フィルムを購入し、配給契約により事業(映画興行)をしたとする法人が、映画フィルムの減価償却費を損金算入して否認され裁判となった事件(以下、「映画フィルムリース事件」という)に関し、課税庁の処分を適法として上告を棄却した(以下、「本件最高裁判決」という)(脚注1)。映画フィルムリース事件としては、最初の最高裁判所の判断である。
他方、国税当局は、2005年11月、航空機オペレーティング・リースへ出資した個人投資家に勝訴判決を出した名古屋高裁判決(脚注2)への上告を断念し、全国で約140名に追徴した課税処分を全て再更正で取消すことにより、一連の航空機リース事件の幕を引いた。国税当局が、自らこれだけ多数の課税処分を一斉に取り消すのは極めて異例とされた(脚注3)。
共に任意組合が使われ、また、一見すると似た構造を有するリース取引の税法解釈について、わずか二、三ヶ月の間に、国税当局(その前提となる名古屋高裁や各地裁の判断)と最高裁判所が正反対の結論を出したことに対し、税理士等の税務専門家の間にも混乱が生じている。例えば、「節税スキームとしてはよく似た両者」なのに、「航空機リース節税をめぐる裁判では投資家勝訴となっている。なぜか―。」との疑問である(脚注4)。
しかしながら、映画フィルムリースはリース取引の中でも特殊なもので、航空機リースや船舶リースとは税務上の扱いを異にしなければならない必然性がある。本稿では、映画フィルムリースと航空機リースの事実関係を整理し、この両者の法律上(特に、税法上)の違いを明らかにすることにより、上記の疑問に対する回答を試みることとする。
また、船舶のオペレーティング・リースについても名古屋国税局管内における数件の課税処分に対して取消請求訴訟が提起され、裁判が係属している。名古屋地裁平成17年12月21日判決により航空機リース事件と同様の理由で納税者が勝訴し、現在名古屋高等裁判所にて審理中である。
Ⅱ 映画フィルムリース事件の概要
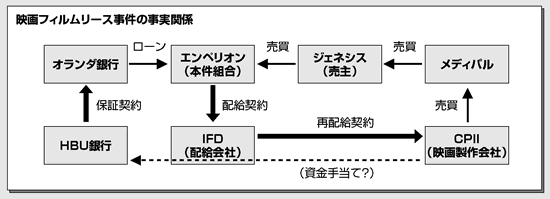
1.事実関係
映画フィルムリース事件は本件最高裁判決が出されたもの以外にも存在するが、その事実関係等は類似しているので、本稿では便宜上本件最高裁判決で認定された事案(パラツィーナ事件)を例にとって説明する。
納税者である株式会社パラツィーナは、自ら組合員となる任意組合の映画投資事業組合Empyrean Film Enterprises(以下、「本件組合」という)が、組合員の出資金及びオランダ銀行からの借入金により、直接の売主(以下、「ジェネシス」という)から、Columbia Pictures Industries,Inc.(以下、「CPII」という)が制作した2本の映画の映画フィルムを購入し、映画配給会社International Film Distributors,B.V.(以下、「IFD」という)に賃貸・配給したとして、その持分権を減価償却資産とし、その減価償却費を損金の額に算入した(脚注5)。これに対して、課税庁は、本件の実体は金融取引であると認定して、減価償却費の損金算入を否認する更正処分等を行ったもので、上記の事実関係を図にすると上記のようになる。
2.本件最高裁判決
最高裁は、まず原審の適法に確定した事実として、「① 本件組合は、本件売買契約と同時に、IFDとの間で本件配給契約を締結し、これにより、IFDに対し、本件映画につき、題名を選択し又は変更すること、編集すること、全世界で封切りをすること、ビデオテープ等を作成すること、広告宣伝をすること、著作権侵害に対する措置を執ることなどの権利を与えており、このようなIFDの本件映画に関する権利は、本件配給契約の解除、終了等により影響を受けず、IFDは、この契約上の地位等を譲渡することができ、また、本件映画に関する権利を取得することができる購入選択権を有するとされ、② 他方、本件組合は、IFDが本件配給契約上の義務に違反したとしても、IFDが有する上記の権利を制限したり、本件配給契約を解除することはできず、また、本件映画に関する権利をIFDの権利に悪影響を与えるように第三者に譲渡することはできないとされ」るとした。なお、原審の事実認定からは、IFDは再配給契約により、本件映画に関する権利をCPIIに戻しているとしている(以下、「権利循環」という)。
これに加えて、最高裁は同じく原審の認定事実として、「③ 本件組合が本件借入契約に基づいてオランダ銀行に返済すべき金額は、IFDが本件配給契約に基づいて購入選択権を行使した場合に本件映画の興行収入の大小を問わず本件組合に対して最低限支払うべきものとされる金額と合致し、また、IFDによる同金額の支払債務の大部分については、本件保証契約により、HBU銀行が保証して」いるとし、本件においては資金も関係当事者間で循環していることを指摘した(以下、「資金循環」という)。
その上で、最高裁は、映画フィルムリース事件の判決理由を「そうすると、本件組合は、本件売買契約により本件映画に関する所有権その他の権利を取得したとしても、本件映画に関する権利のほとんどは、本件売買契約と同じ日付で締結された本件配給契約によりIFDに移転しているのであって、実質的には、本件映画についての使用収益権限及び処分権限を失っているというべきである。」と述べ、結論としては原審の判断を維持した。
以上のとおり、最高裁判所は、本件取引で用いられた売買契約や配給契約などの各契約を尊重してその成立を認め、その上で、本件組合とIFDの間に締結された本件配給契約の内容・効力を検討し、上記①及び②の事実からは、「本件映画に関する権利」のほとんどがIFDへ再移転され、本件組合は本件映画の使用収益処分権限を失っていることを、上記③の事実からは、IFDの再移転対価の支払はHBU銀行が本件組合へ保証するという形でなされていることを認定して、本件組合はIFDに「本件映画に関する権利」を売却したと認定したのである(脚注6)。
Ⅲ 航空機リース事件の概要
1.事実関係
次に航空機リース事件として全国で裁判所や不服審判所に係属した事件は、個人が組合員となったものであるが、おおむね次の仕組を有する。現金を出資した組合員が任意組合を組成し、任意組合は銀行より融資を受けたうえ、組合員の出資金と合わせて航空機1機を市場より購入し、外国の航空会社にリースし、リース期間終了時には航空機を市場で売却して、航空機の賃貸事業を行なうというものである(脚注7)。
上記の事実関係を図にすると以下のようになるが、仕組は似ているというものの、以下の図から明らかなとおり、航空機リース事件では、映画フィルムリース事件にあるような権利循環も資金循環も存在しないし、数年間のリース期間中、賃貸事業は全て任意組合が行っているのである。
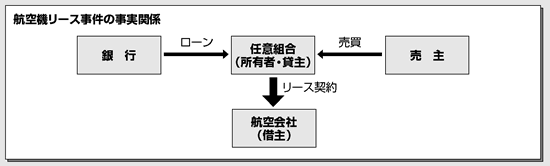
2.名古屋高裁判決(脚注8)
航空機リース事件での争点は多岐に渡るが、課税庁の論拠を端的に言えば、投資家は租税の回避・軽減効果を欲しかつ目的として任意組合に出資したにすぎず、その「実体ないし実質」を見れば、単に「利益」を得るためだけの利益配当契約であるべきだと言うものである。法律的に説明すれば、当事者の選択した任意組合という法形式は不成立か仮装で無効だと認定し、「当事者の真の合理的意思」を探求し認定すれば、より税額の高くなる利益配当契約と引き直して課税すべきだとの主張であり、これにより一般的な「租税回避行為の否認理論」(脚注9)と同一の課税結果を導こうとした。
これに対し、名古屋高裁判決は、国税当局が主張した節税目的は動機・目的の類であり、本件の各取引契約からは組合員の任意組合を組成して航空機賃貸事業をするという効果意思は明確に示されていると判示するとともに、現代社会の合理的経済人は税負担を考慮するのがむしろ通常であり、税負担の検討結果を経て選択した契約類型が真意に反すると認定されるのであれば、それは事実認定の名の下に、法的根拠のない法律行為の否認を行うのと異ならないと判示した。
加えて、国税当局の課税額減少それ自体を取引の主目的とするものと単に副次的効果であるものに分け、前者は否認し後者は許されるべきとの主張に対しても、効果意思と動機・目的を混同した主張を単に言葉を換えているに過ぎないと一蹴した(脚注10)。
Ⅳ 両事件の違い①―映画フィルムの特殊性
両事件については、節税目的や節税効果があること等の類似点はあるものの、前述の説明からも明らかなとおり、事実関係で多くの重要な違いがある。その中で、裁判所の判断に決定的な影響を与えたと思われる二点にしぼって、分析を試みる。
1.「映画に関する権利」と「フィルム」の分離
まず、任意組合が事業用資産を取得して賃貸等を行うリース取引の中で、「映画フィルム」はその客体として極めて特殊であり、そのために映画フィルムリースの税務上の位置付けが問題となる。
前記のとおり、本件最高裁判決は、原審における「映画に関する権利」の内容について詳細な認定を引用しているが、その権利は、有体物たる「フィルム」に関する権利ではなく、主として著作物たる「映画」に関する権利(著作権)である。即ち、映画フィルムリース事件では、「フィルム」の所有者たる組合が、配給会社に対し、「映画」の題名を選択・変更する権利、「映画」の編集・追加・変更等をする権利、「映画」を公開する権利、「映画」に関するテープ・ディスクを作成する第二次的配給をする権利、「映画」の広告・宣伝・普及等を行う権利等を付与し、その結果、映画の著作権と評価される権利のほとんどは配給会社に移転していること、その上、配給会社に付与された「映画に関する権利」(著作権)は、配給契約の失効・終了によっても影響を受けず、IFDの債務不履行によってすら剥奪されない契約となっていること等の原審の認定を引用しているのである(脚注11)。
そもそも、映画の興行事業は「フィルム」に化体された「映画」を上映し、あるいは、「映画」を複製して頒布することで収益を上げる事業であるから、その事業を遂行するために最も重要なのは、他人に有償で鑑賞させ、あるいは、「映画」を記録させたビデオ・テープやビデオ・ディスク等を販売するための「著作権」である。もちろん、有体物としての「フィルム」それ自体も取引の対象とはなり得るが、「フィルム」は単に「映画」を記録した媒体としての意味しかなく、その複製は容易である上、磨耗、毀損によりその価値はすぐに減価するから、映画の著作権との対比においてその価値は限りなく無に等しい。
かかる映画フィルムの特殊性に鑑みると、映画フィルムリース事件のような具体的事実関係の下では、任意組合が「フィルム」の所有権を有しているといっても、その所有権は「映画に関する権利」(著作権)の移転してしまった「フィルム」の所有権、すなわち、「映画」が化体していない裸の「フィルム」の所有権にすぎず、まさに実体のない「抜け殻」であるといわれてもやむを得ないのである(脚注12)。別の言い方をすれば、映画フィルムリース事件においては「形式」(フィルムを所有していること)と「実体」(著作権者であること)が分離してしまった対象物の、形式のみを所有していたもので、極めて特殊な事例と言えるのである(脚注13)。
2.「航空機に係る権利」は分離はない
これに対し、航空機リース事件では、任意組合は対象たる航空機の所有権を取得し、これをそのまま航空会社に賃貸し、リース期間中は賃料を収受する。ここでは「航空機」は言うまでもなく有体物であり、かつ、映画フィルムにおける著作権のようなより価値のある別個の権利が化体しているものでもない。即ち、「航空機」に対する所有権の他に、前記の「映画に関する権利」のような、所有権とは別個の「航空機に関する権利」など存在しないのである。
このように、航空機リース事件では、映画フィルムリース事件とは異なり、単なる有体物としての航空機の所有権のみが問題となるところ、航空機の所有権はリース期間中と言えども任意組合に帰属していることは法律上明らかで、かつ、リース契約終了後は、任意組合が本件各航空機の占有を回復し、航空機を再リースしたり売却するのである。
以上のとおり、航空機リース事件では、有体物としての航空機の所有権、即ち、自由に使用・収益・処分する権限は任意組合にあり、また、所有権の「形式」と「実体」も完全に一致して、いずれも所有者・賃貸人たる任意組合に帰属していることが明白な事例であったのである。
Ⅴ 両事件の違い②―権利循環と資金循環の有無
次に、映画フィルムリース事件の構造には、前述Ⅱで述べたとおり、権利循環と資金循環が組み込まれている。本件最高裁判決はかかる事実の存在を根拠に、映画に関する権利の移転を認定し、任意組合に減価償却費の計上を認めなかったのである(脚注14)。
しかしながら、航空機リース事件では、任意組合が取得した航空機の所有権は事業期間中もそのまま任意組合に存在しており、その全部又は一部が前主である売主やレッシーを含めた第三者に移転した事実は存在しない。航空機リース事件の裁判中、課税庁は、任意組合が銀行からの借入の担保として航空機の権利を移転している(モーゲージ)と主張したが、これは担保権を設定したまでのことで所有権は依然任意組合に残っていることは明らかである。又、航空会社へ賃貸しているので所有権の重要な特質たる使用権を失ったとも主張したが、任意組合は賃貸するという方法で使用権を行使していることは法律上自明であり、裁判所に一蹴されている。
加えて、航空機リース事件では、映画フィルムリース事件のHBU銀行のような任意組合の銀行への返済債務を保証したり、一定の収入を保証したりするような当事者は存在しない。従って、航空会社が倒産する等してリース料が支払われない場合には、それがそのまま航空機の担保実行に直結するなど、任意組合は事業リスクを負担しているのである。
Ⅵ まとめ
以上のとおり、映画フィルムリース事件は、対象物の特殊性、かかる特殊性に基づき任意組合が有する権利の実体、関係当事者間における権利及び資金の循環等の具体的事実関係の下で、任意組合が所有していた「映画フィルム」の「形式」と「実体」との間に看過できない不一致があった事例である。
これに対し、航空機リース事件では、映画フィルム事件におけるような「形式」と「実体」の不一致は認められず、まさに当事者が選択した法形式に則した権利関係の実体が存在しているのであって、当事者が選択した法形式及び契約の有効な成立が否定される理由はどこにもないのである。
以上が、両事件の結論が正反対に分かれた理由であると考える。
増田 晋(ますだすすむ)
弁護士(日本及びカリフォルニア州)
森・濱田松本法律事務所パートナー、大宮法科大学院教授・慶応義塾大学法科大学院講師。
東京大学法学部卒業、University of Washington School of Law(LL.M)卒業。
【主な著書・論文】
「可動物件の国際的権益に関する条約および航空機議定書の概要と仮訳」(国際商事法務)、『ビジネス・タックス―企業税制の理論と実務』(共著、有斐閣)、「「組合事業に関する租税回避防止」立法の問題点」本誌105号、「節税目的を理由とした税務否認に対する司法の判断―航空機リース事件を素材として―」(「税理」2006年3月号)他。
脚注
1 最高裁判所平成18年1月24日判決言渡(第三小法廷)。全文は、
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?actino_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=24942&hanreiKbn=01
に掲載。
2 名古屋高判平成17年10月27日(Lexis判例速報06年5月号92頁以下)、その原審は名古屋地判平成16年10月28日(判例タイムズ1204号224頁以下)。なお、航空機リース事件については、拙稿の「節税目的を理由とした税務否認に対する司法の判断―航空機リース事件を素材として―」(「税理」2006年3月号)及び「航空機リースと租税回避行為」(『ビジネス・タックス』373頁以下、有斐閣)を参照。
3 日本経済新聞2005.11.11(夕刊)他当日の各紙夕刊。同新聞2005.12.5「スイッチ・オン・マンデー」参照。
4 「納税通信」第2909号(2006年2月6日号)の「インサイド」等。
5 映画フィルムの法定耐用年数は2年であり(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一)、パラツィーナ事件で任意組合が取得した映画2本の購入代金は約85億円とされているので、短期間に多額の減価償却費が生じることとなる。
6 なお、最高裁は、本件組合やCPIIの主観的意思を重視し「私法上の真の意思」という概念を用いて判断した控訴審の理由付けを採用していない。この分析については、拙稿「映画フィルムリース事件に関する最高裁判決の検討」(「税理」2006年7月号)参照。
7 このような組成方法はオペレーティング・リースと一般に呼ばれている。なお、この他にレバレッジド・リースと呼ばれる組成方法もあるが、正確に区制されて使用されていないきらいがある。
8 前注2参照。
9 租税回避行為は税法上定義されてはいないが、講学上「私法上の選択可能性を利用し、私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに、通常用いられない法形式を利用することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること」と説明されるのが一般である。
10 前注2参照。
11 本件最高裁判決4頁。
12 逆に、原案の大阪高裁判決は、かかる事実の存在を根拠の一部として、総合的に任意組合が映画フィルムを取得していないと認定(売買契約を否認)したものである。この点については、前掲注5の拙稿参照。
13 なお、映画フィルムを映画の「著作権」だけであると考えた場合は、法人税法上「著作権」は減価償却資産として分類されていないので、映画フィルムの減価償却計上はできないこととなると思われる(「著作権」は時の経過とともに価値が減少するものではないと考えられている)。
14 逆に、原審の大阪高裁判決は、かかる事実の存在を根拠の一部として、任意組合が映画フィルムを取得した点を否認(売買契約を否認)したものと考える。この点については、前掲注6の拙稿参照。
映画フィルムリースと航空機リースの違い
森・濱田松本法律事務所 弁護士 増田 晋
Ⅰ はじめに
最高裁判所は、2006年1月24日、任意組合を組成して映画フィルムを購入し、配給契約により事業(映画興行)をしたとする法人が、映画フィルムの減価償却費を損金算入して否認され裁判となった事件(以下、「映画フィルムリース事件」という)に関し、課税庁の処分を適法として上告を棄却した(以下、「本件最高裁判決」という)(脚注1)。映画フィルムリース事件としては、最初の最高裁判所の判断である。
他方、国税当局は、2005年11月、航空機オペレーティング・リースへ出資した個人投資家に勝訴判決を出した名古屋高裁判決(脚注2)への上告を断念し、全国で約140名に追徴した課税処分を全て再更正で取消すことにより、一連の航空機リース事件の幕を引いた。国税当局が、自らこれだけ多数の課税処分を一斉に取り消すのは極めて異例とされた(脚注3)。
共に任意組合が使われ、また、一見すると似た構造を有するリース取引の税法解釈について、わずか二、三ヶ月の間に、国税当局(その前提となる名古屋高裁や各地裁の判断)と最高裁判所が正反対の結論を出したことに対し、税理士等の税務専門家の間にも混乱が生じている。例えば、「節税スキームとしてはよく似た両者」なのに、「航空機リース節税をめぐる裁判では投資家勝訴となっている。なぜか―。」との疑問である(脚注4)。
しかしながら、映画フィルムリースはリース取引の中でも特殊なもので、航空機リースや船舶リースとは税務上の扱いを異にしなければならない必然性がある。本稿では、映画フィルムリースと航空機リースの事実関係を整理し、この両者の法律上(特に、税法上)の違いを明らかにすることにより、上記の疑問に対する回答を試みることとする。
また、船舶のオペレーティング・リースについても名古屋国税局管内における数件の課税処分に対して取消請求訴訟が提起され、裁判が係属している。名古屋地裁平成17年12月21日判決により航空機リース事件と同様の理由で納税者が勝訴し、現在名古屋高等裁判所にて審理中である。
Ⅱ 映画フィルムリース事件の概要
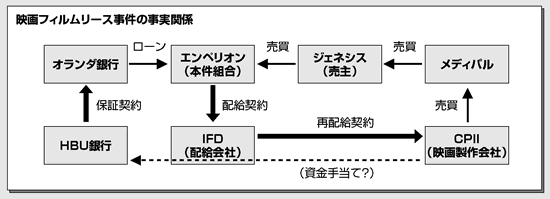
1.事実関係
映画フィルムリース事件は本件最高裁判決が出されたもの以外にも存在するが、その事実関係等は類似しているので、本稿では便宜上本件最高裁判決で認定された事案(パラツィーナ事件)を例にとって説明する。
納税者である株式会社パラツィーナは、自ら組合員となる任意組合の映画投資事業組合Empyrean Film Enterprises(以下、「本件組合」という)が、組合員の出資金及びオランダ銀行からの借入金により、直接の売主(以下、「ジェネシス」という)から、Columbia Pictures Industries,Inc.(以下、「CPII」という)が制作した2本の映画の映画フィルムを購入し、映画配給会社International Film Distributors,B.V.(以下、「IFD」という)に賃貸・配給したとして、その持分権を減価償却資産とし、その減価償却費を損金の額に算入した(脚注5)。これに対して、課税庁は、本件の実体は金融取引であると認定して、減価償却費の損金算入を否認する更正処分等を行ったもので、上記の事実関係を図にすると上記のようになる。
2.本件最高裁判決
最高裁は、まず原審の適法に確定した事実として、「① 本件組合は、本件売買契約と同時に、IFDとの間で本件配給契約を締結し、これにより、IFDに対し、本件映画につき、題名を選択し又は変更すること、編集すること、全世界で封切りをすること、ビデオテープ等を作成すること、広告宣伝をすること、著作権侵害に対する措置を執ることなどの権利を与えており、このようなIFDの本件映画に関する権利は、本件配給契約の解除、終了等により影響を受けず、IFDは、この契約上の地位等を譲渡することができ、また、本件映画に関する権利を取得することができる購入選択権を有するとされ、② 他方、本件組合は、IFDが本件配給契約上の義務に違反したとしても、IFDが有する上記の権利を制限したり、本件配給契約を解除することはできず、また、本件映画に関する権利をIFDの権利に悪影響を与えるように第三者に譲渡することはできないとされ」るとした。なお、原審の事実認定からは、IFDは再配給契約により、本件映画に関する権利をCPIIに戻しているとしている(以下、「権利循環」という)。
これに加えて、最高裁は同じく原審の認定事実として、「③ 本件組合が本件借入契約に基づいてオランダ銀行に返済すべき金額は、IFDが本件配給契約に基づいて購入選択権を行使した場合に本件映画の興行収入の大小を問わず本件組合に対して最低限支払うべきものとされる金額と合致し、また、IFDによる同金額の支払債務の大部分については、本件保証契約により、HBU銀行が保証して」いるとし、本件においては資金も関係当事者間で循環していることを指摘した(以下、「資金循環」という)。
その上で、最高裁は、映画フィルムリース事件の判決理由を「そうすると、本件組合は、本件売買契約により本件映画に関する所有権その他の権利を取得したとしても、本件映画に関する権利のほとんどは、本件売買契約と同じ日付で締結された本件配給契約によりIFDに移転しているのであって、実質的には、本件映画についての使用収益権限及び処分権限を失っているというべきである。」と述べ、結論としては原審の判断を維持した。
以上のとおり、最高裁判所は、本件取引で用いられた売買契約や配給契約などの各契約を尊重してその成立を認め、その上で、本件組合とIFDの間に締結された本件配給契約の内容・効力を検討し、上記①及び②の事実からは、「本件映画に関する権利」のほとんどがIFDへ再移転され、本件組合は本件映画の使用収益処分権限を失っていることを、上記③の事実からは、IFDの再移転対価の支払はHBU銀行が本件組合へ保証するという形でなされていることを認定して、本件組合はIFDに「本件映画に関する権利」を売却したと認定したのである(脚注6)。
Ⅲ 航空機リース事件の概要
1.事実関係
次に航空機リース事件として全国で裁判所や不服審判所に係属した事件は、個人が組合員となったものであるが、おおむね次の仕組を有する。現金を出資した組合員が任意組合を組成し、任意組合は銀行より融資を受けたうえ、組合員の出資金と合わせて航空機1機を市場より購入し、外国の航空会社にリースし、リース期間終了時には航空機を市場で売却して、航空機の賃貸事業を行なうというものである(脚注7)。
上記の事実関係を図にすると以下のようになるが、仕組は似ているというものの、以下の図から明らかなとおり、航空機リース事件では、映画フィルムリース事件にあるような権利循環も資金循環も存在しないし、数年間のリース期間中、賃貸事業は全て任意組合が行っているのである。
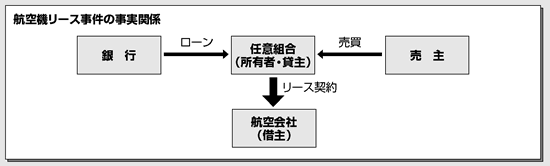
2.名古屋高裁判決(脚注8)
航空機リース事件での争点は多岐に渡るが、課税庁の論拠を端的に言えば、投資家は租税の回避・軽減効果を欲しかつ目的として任意組合に出資したにすぎず、その「実体ないし実質」を見れば、単に「利益」を得るためだけの利益配当契約であるべきだと言うものである。法律的に説明すれば、当事者の選択した任意組合という法形式は不成立か仮装で無効だと認定し、「当事者の真の合理的意思」を探求し認定すれば、より税額の高くなる利益配当契約と引き直して課税すべきだとの主張であり、これにより一般的な「租税回避行為の否認理論」(脚注9)と同一の課税結果を導こうとした。
これに対し、名古屋高裁判決は、国税当局が主張した節税目的は動機・目的の類であり、本件の各取引契約からは組合員の任意組合を組成して航空機賃貸事業をするという効果意思は明確に示されていると判示するとともに、現代社会の合理的経済人は税負担を考慮するのがむしろ通常であり、税負担の検討結果を経て選択した契約類型が真意に反すると認定されるのであれば、それは事実認定の名の下に、法的根拠のない法律行為の否認を行うのと異ならないと判示した。
加えて、国税当局の課税額減少それ自体を取引の主目的とするものと単に副次的効果であるものに分け、前者は否認し後者は許されるべきとの主張に対しても、効果意思と動機・目的を混同した主張を単に言葉を換えているに過ぎないと一蹴した(脚注10)。
Ⅳ 両事件の違い①―映画フィルムの特殊性
両事件については、節税目的や節税効果があること等の類似点はあるものの、前述の説明からも明らかなとおり、事実関係で多くの重要な違いがある。その中で、裁判所の判断に決定的な影響を与えたと思われる二点にしぼって、分析を試みる。
1.「映画に関する権利」と「フィルム」の分離
まず、任意組合が事業用資産を取得して賃貸等を行うリース取引の中で、「映画フィルム」はその客体として極めて特殊であり、そのために映画フィルムリースの税務上の位置付けが問題となる。
前記のとおり、本件最高裁判決は、原審における「映画に関する権利」の内容について詳細な認定を引用しているが、その権利は、有体物たる「フィルム」に関する権利ではなく、主として著作物たる「映画」に関する権利(著作権)である。即ち、映画フィルムリース事件では、「フィルム」の所有者たる組合が、配給会社に対し、「映画」の題名を選択・変更する権利、「映画」の編集・追加・変更等をする権利、「映画」を公開する権利、「映画」に関するテープ・ディスクを作成する第二次的配給をする権利、「映画」の広告・宣伝・普及等を行う権利等を付与し、その結果、映画の著作権と評価される権利のほとんどは配給会社に移転していること、その上、配給会社に付与された「映画に関する権利」(著作権)は、配給契約の失効・終了によっても影響を受けず、IFDの債務不履行によってすら剥奪されない契約となっていること等の原審の認定を引用しているのである(脚注11)。
そもそも、映画の興行事業は「フィルム」に化体された「映画」を上映し、あるいは、「映画」を複製して頒布することで収益を上げる事業であるから、その事業を遂行するために最も重要なのは、他人に有償で鑑賞させ、あるいは、「映画」を記録させたビデオ・テープやビデオ・ディスク等を販売するための「著作権」である。もちろん、有体物としての「フィルム」それ自体も取引の対象とはなり得るが、「フィルム」は単に「映画」を記録した媒体としての意味しかなく、その複製は容易である上、磨耗、毀損によりその価値はすぐに減価するから、映画の著作権との対比においてその価値は限りなく無に等しい。
かかる映画フィルムの特殊性に鑑みると、映画フィルムリース事件のような具体的事実関係の下では、任意組合が「フィルム」の所有権を有しているといっても、その所有権は「映画に関する権利」(著作権)の移転してしまった「フィルム」の所有権、すなわち、「映画」が化体していない裸の「フィルム」の所有権にすぎず、まさに実体のない「抜け殻」であるといわれてもやむを得ないのである(脚注12)。別の言い方をすれば、映画フィルムリース事件においては「形式」(フィルムを所有していること)と「実体」(著作権者であること)が分離してしまった対象物の、形式のみを所有していたもので、極めて特殊な事例と言えるのである(脚注13)。
2.「航空機に係る権利」は分離はない
これに対し、航空機リース事件では、任意組合は対象たる航空機の所有権を取得し、これをそのまま航空会社に賃貸し、リース期間中は賃料を収受する。ここでは「航空機」は言うまでもなく有体物であり、かつ、映画フィルムにおける著作権のようなより価値のある別個の権利が化体しているものでもない。即ち、「航空機」に対する所有権の他に、前記の「映画に関する権利」のような、所有権とは別個の「航空機に関する権利」など存在しないのである。
このように、航空機リース事件では、映画フィルムリース事件とは異なり、単なる有体物としての航空機の所有権のみが問題となるところ、航空機の所有権はリース期間中と言えども任意組合に帰属していることは法律上明らかで、かつ、リース契約終了後は、任意組合が本件各航空機の占有を回復し、航空機を再リースしたり売却するのである。
以上のとおり、航空機リース事件では、有体物としての航空機の所有権、即ち、自由に使用・収益・処分する権限は任意組合にあり、また、所有権の「形式」と「実体」も完全に一致して、いずれも所有者・賃貸人たる任意組合に帰属していることが明白な事例であったのである。
Ⅴ 両事件の違い②―権利循環と資金循環の有無
次に、映画フィルムリース事件の構造には、前述Ⅱで述べたとおり、権利循環と資金循環が組み込まれている。本件最高裁判決はかかる事実の存在を根拠に、映画に関する権利の移転を認定し、任意組合に減価償却費の計上を認めなかったのである(脚注14)。
しかしながら、航空機リース事件では、任意組合が取得した航空機の所有権は事業期間中もそのまま任意組合に存在しており、その全部又は一部が前主である売主やレッシーを含めた第三者に移転した事実は存在しない。航空機リース事件の裁判中、課税庁は、任意組合が銀行からの借入の担保として航空機の権利を移転している(モーゲージ)と主張したが、これは担保権を設定したまでのことで所有権は依然任意組合に残っていることは明らかである。又、航空会社へ賃貸しているので所有権の重要な特質たる使用権を失ったとも主張したが、任意組合は賃貸するという方法で使用権を行使していることは法律上自明であり、裁判所に一蹴されている。
加えて、航空機リース事件では、映画フィルムリース事件のHBU銀行のような任意組合の銀行への返済債務を保証したり、一定の収入を保証したりするような当事者は存在しない。従って、航空会社が倒産する等してリース料が支払われない場合には、それがそのまま航空機の担保実行に直結するなど、任意組合は事業リスクを負担しているのである。
Ⅵ まとめ
以上のとおり、映画フィルムリース事件は、対象物の特殊性、かかる特殊性に基づき任意組合が有する権利の実体、関係当事者間における権利及び資金の循環等の具体的事実関係の下で、任意組合が所有していた「映画フィルム」の「形式」と「実体」との間に看過できない不一致があった事例である。
これに対し、航空機リース事件では、映画フィルム事件におけるような「形式」と「実体」の不一致は認められず、まさに当事者が選択した法形式に則した権利関係の実体が存在しているのであって、当事者が選択した法形式及び契約の有効な成立が否定される理由はどこにもないのである。
以上が、両事件の結論が正反対に分かれた理由であると考える。
増田 晋(ますだすすむ)
弁護士(日本及びカリフォルニア州)
森・濱田松本法律事務所パートナー、大宮法科大学院教授・慶応義塾大学法科大学院講師。
東京大学法学部卒業、University of Washington School of Law(LL.M)卒業。
【主な著書・論文】
「可動物件の国際的権益に関する条約および航空機議定書の概要と仮訳」(国際商事法務)、『ビジネス・タックス―企業税制の理論と実務』(共著、有斐閣)、「「組合事業に関する租税回避防止」立法の問題点」本誌105号、「節税目的を理由とした税務否認に対する司法の判断―航空機リース事件を素材として―」(「税理」2006年3月号)他。
脚注
1 最高裁判所平成18年1月24日判決言渡(第三小法廷)。全文は、
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?actino_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=24942&hanreiKbn=01
に掲載。
2 名古屋高判平成17年10月27日(Lexis判例速報06年5月号92頁以下)、その原審は名古屋地判平成16年10月28日(判例タイムズ1204号224頁以下)。なお、航空機リース事件については、拙稿の「節税目的を理由とした税務否認に対する司法の判断―航空機リース事件を素材として―」(「税理」2006年3月号)及び「航空機リースと租税回避行為」(『ビジネス・タックス』373頁以下、有斐閣)を参照。
3 日本経済新聞2005.11.11(夕刊)他当日の各紙夕刊。同新聞2005.12.5「スイッチ・オン・マンデー」参照。
4 「納税通信」第2909号(2006年2月6日号)の「インサイド」等。
5 映画フィルムの法定耐用年数は2年であり(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一)、パラツィーナ事件で任意組合が取得した映画2本の購入代金は約85億円とされているので、短期間に多額の減価償却費が生じることとなる。
6 なお、最高裁は、本件組合やCPIIの主観的意思を重視し「私法上の真の意思」という概念を用いて判断した控訴審の理由付けを採用していない。この分析については、拙稿「映画フィルムリース事件に関する最高裁判決の検討」(「税理」2006年7月号)参照。
7 このような組成方法はオペレーティング・リースと一般に呼ばれている。なお、この他にレバレッジド・リースと呼ばれる組成方法もあるが、正確に区制されて使用されていないきらいがある。
8 前注2参照。
9 租税回避行為は税法上定義されてはいないが、講学上「私法上の選択可能性を利用し、私的経済取引プロパーの見地からは合理的理由がないのに、通常用いられない法形式を利用することによって、結果的には意図した経済的目的ないし経済的成果を実現しながら、通常用いられる法形式に対応する課税要件の充足を免れ、もって税負担を減少させあるいは排除すること」と説明されるのが一般である。
10 前注2参照。
11 本件最高裁判決4頁。
12 逆に、原案の大阪高裁判決は、かかる事実の存在を根拠の一部として、総合的に任意組合が映画フィルムを取得していないと認定(売買契約を否認)したものである。この点については、前掲注5の拙稿参照。
13 なお、映画フィルムを映画の「著作権」だけであると考えた場合は、法人税法上「著作権」は減価償却資産として分類されていないので、映画フィルムの減価償却計上はできないこととなると思われる(「著作権」は時の経過とともに価値が減少するものではないと考えられている)。
14 逆に、原審の大阪高裁判決は、かかる事実の存在を根拠の一部として、任意組合が映画フィルムを取得した点を否認(売買契約を否認)したものと考える。この点については、前掲注6の拙稿参照。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -