解説記事2006年07月10日 【ニュース特集】 例外処理を廃止するリース会計基準の試案(2006年7月10日号・№170)
⇒中小企業への弾力的運用を求める
税務上の取扱いの変更も!
例外処理を廃止するリース会計基準の試案
企業会計基準委員会(ASB)は7月5日、リース取引に関する会計基準(案)およびリース取引に関する会計基準の適用指針(案)を公表した。税制上の取扱いが不明であるため、適用時期については未定としている。このため、試案として公表した。8月25日まで意見募集した後、公開草案の策定に着手する。試案では、現在認められている所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理を廃止することを提案している。会計基準の変更により、税務上の取扱いも変更される可能性が大きく、リース事業協会を始め、産業界からの強い反対意見もある。今後の議論の動向を見守る必要がありそうだ。
今回の特集では、試案の概要をお伝えする。なお、試案の原文は同委員会のホームページからダウンロードすることができる。
現行は注記を要件に例外処理を認める
平成5年に策定された現行のリース会計基準では、ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしリース物件の所有権が借手に移転すると認められる以外の取引については、注記を要件として、例外的に、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことを認めている(今号42頁参照)。
しかし、今回の試案では、この所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理を廃止しており、大きな特長となっている(図1・2参照)。同委員会では、平成14年からリース会計専門委員会を設置し、検討を行ってきたものだ。
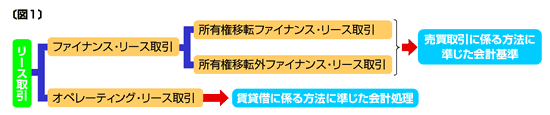
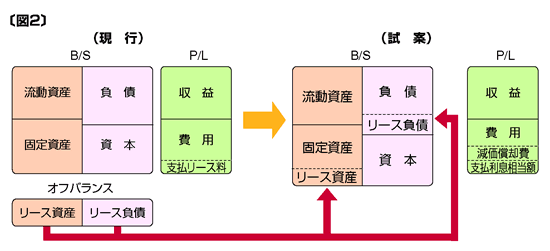
300万円以下のリース取引は賃貸借処理を認める
所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理(借手側)については、リース取引開始時にリース物件とこれに係る負債を、リース資産およびリース債務として計上する。リース資産とリース債務の計上額は、リース料総額の現在価値と貸手の購入価額等とのいずれか低い額によるとしている。
また、利息相当額の総額は、原則としてリース期間にわたり利息法により配分することになるが、リース資産総額に重要性がないと認められる場合は、①リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によることができる。この場合、リース資産およびリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上される、②利息相当額の総額をリース期間にわたり定額法で配分するのいずれかの方法を採用することができるとしている。
なお、リース契約1件当たりが300万円以下のリース取引など、少額のリース資産やリース期間が1年未満のリース取引については、簡便的方法を認め、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を行うことができるとしている。
貸手側、利息相当額は利息法により配分
一方、貸手側についてみると、貸手における利息相当額の総額は、リース取引開始時に合意されたリース料総額および見積残存価額の合計額から、これに対応するリース資産の取得価額を控除することによって算定する。利息相当額の総額は、原則として、リース期間にわたり利息法により配分することになるが、貸手としてのリース取引に重要性がないと認められる場合は、リース期間にわたり定額で配分することができるとしている。
なお、この場合には、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により「リース投資資産」(流動資産)として表示することになる。
中小企業への適用はどうなる?
所有権移転外ファイナンス・リース取引について、多くの企業が通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に変更することが予想されるが、適用初年度の取扱いを規定することにより、企業側に一定の配慮をみせている(詳細は本誌169号7頁参照)。
ただし、上場企業以上に影響を受けるのが中小企業であり、その対応が問題となる。特に中小企業に対しては、簡便法を求める声が強いものとなっている。このため、簡便法については、今後、企業会計基準委員会、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所の民間4団体で「中小企業の会計に関する指針」の見直しを検討するとしている。
会計基準の変更に伴い税務上のメリットも見直しへ
加えて、最大の問題が税務上の取扱いだ。現行、所有権移転外ファイナンス・リースについては、借手側は毎期の支払リース料を費用として処理し、貸手側はリース資産を貸借対照表に計上して減価償却費を費用処理し、受取リース料を収益として計上することになる。売買取引に準じて会計処理することになれば、借手側は固定資産税や保険料の納付などの事務負担が増えることになる。また、仮に申告調整ができたとしても、事務負担は増えることになり、リースを行うメリットは半減することになる。
一方、貸手側についても、減価償却費の計上ができなくなり、リース終了時まで減価償却費相当額の損金算入が認められない可能性がある。
このような税務上の懸念から、リース事業協会を始めとした産業界では、例外処理の廃止に強く反対してきたわけだ。今回の試案についても、税務上の取扱いが定まっていないことから適用時期は未定となっている。
税務当局では、現在のところ、取扱いを明確にしておらず、会計上の取扱いが変更になれば、税務上の取扱いについても検討するという立場をとっている。しかし、現行の税務上の取扱いが現行のリース会計基準を前提としているものだけに、会計基準が変更されることになれば、税務上の取扱いも変更される可能性が高いといえる。
現行のリース会計基準等からの改正点
税務上の取扱いの変更も!
例外処理を廃止するリース会計基準の試案
企業会計基準委員会(ASB)は7月5日、リース取引に関する会計基準(案)およびリース取引に関する会計基準の適用指針(案)を公表した。税制上の取扱いが不明であるため、適用時期については未定としている。このため、試案として公表した。8月25日まで意見募集した後、公開草案の策定に着手する。試案では、現在認められている所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理を廃止することを提案している。会計基準の変更により、税務上の取扱いも変更される可能性が大きく、リース事業協会を始め、産業界からの強い反対意見もある。今後の議論の動向を見守る必要がありそうだ。
今回の特集では、試案の概要をお伝えする。なお、試案の原文は同委員会のホームページからダウンロードすることができる。
現行は注記を要件に例外処理を認める
平成5年に策定された現行のリース会計基準では、ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしリース物件の所有権が借手に移転すると認められる以外の取引については、注記を要件として、例外的に、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことを認めている(今号42頁参照)。
しかし、今回の試案では、この所有権移転外ファイナンス・リース取引の例外処理を廃止しており、大きな特長となっている(図1・2参照)。同委員会では、平成14年からリース会計専門委員会を設置し、検討を行ってきたものだ。
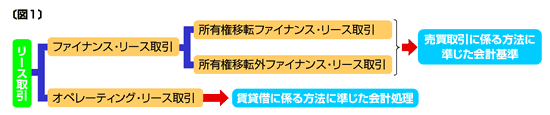
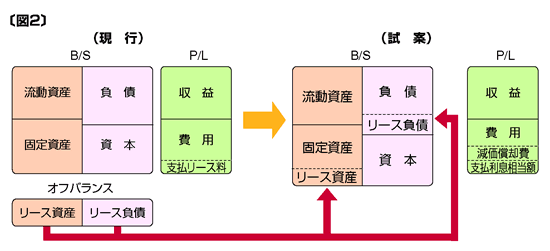
300万円以下のリース取引は賃貸借処理を認める
所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理(借手側)については、リース取引開始時にリース物件とこれに係る負債を、リース資産およびリース債務として計上する。リース資産とリース債務の計上額は、リース料総額の現在価値と貸手の購入価額等とのいずれか低い額によるとしている。
また、利息相当額の総額は、原則としてリース期間にわたり利息法により配分することになるが、リース資産総額に重要性がないと認められる場合は、①リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によることができる。この場合、リース資産およびリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上される、②利息相当額の総額をリース期間にわたり定額法で配分するのいずれかの方法を採用することができるとしている。
なお、リース契約1件当たりが300万円以下のリース取引など、少額のリース資産やリース期間が1年未満のリース取引については、簡便的方法を認め、オペレーティング・リース取引の会計処理に準じて、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を行うことができるとしている。
貸手側、利息相当額は利息法により配分
一方、貸手側についてみると、貸手における利息相当額の総額は、リース取引開始時に合意されたリース料総額および見積残存価額の合計額から、これに対応するリース資産の取得価額を控除することによって算定する。利息相当額の総額は、原則として、リース期間にわたり利息法により配分することになるが、貸手としてのリース取引に重要性がないと認められる場合は、リース期間にわたり定額で配分することができるとしている。
なお、この場合には、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により「リース投資資産」(流動資産)として表示することになる。
中小企業への適用はどうなる?
所有権移転外ファイナンス・リース取引について、多くの企業が通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に変更することが予想されるが、適用初年度の取扱いを規定することにより、企業側に一定の配慮をみせている(詳細は本誌169号7頁参照)。
ただし、上場企業以上に影響を受けるのが中小企業であり、その対応が問題となる。特に中小企業に対しては、簡便法を求める声が強いものとなっている。このため、簡便法については、今後、企業会計基準委員会、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所の民間4団体で「中小企業の会計に関する指針」の見直しを検討するとしている。
会計基準の変更に伴い税務上のメリットも見直しへ
加えて、最大の問題が税務上の取扱いだ。現行、所有権移転外ファイナンス・リースについては、借手側は毎期の支払リース料を費用として処理し、貸手側はリース資産を貸借対照表に計上して減価償却費を費用処理し、受取リース料を収益として計上することになる。売買取引に準じて会計処理することになれば、借手側は固定資産税や保険料の納付などの事務負担が増えることになる。また、仮に申告調整ができたとしても、事務負担は増えることになり、リースを行うメリットは半減することになる。
一方、貸手側についても、減価償却費の計上ができなくなり、リース終了時まで減価償却費相当額の損金算入が認められない可能性がある。
このような税務上の懸念から、リース事業協会を始めとした産業界では、例外処理の廃止に強く反対してきたわけだ。今回の試案についても、税務上の取扱いが定まっていないことから適用時期は未定となっている。
税務当局では、現在のところ、取扱いを明確にしておらず、会計上の取扱いが変更になれば、税務上の取扱いについても検討するという立場をとっている。しかし、現行の税務上の取扱いが現行のリース会計基準を前提としているものだけに、会計基準が変更されることになれば、税務上の取扱いも変更される可能性が高いといえる。
現行のリース会計基準等からの改正点
現 行 | 試 案 | |
| ① 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る通常の賃貸借処理の廃止 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引は、原則として通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うが、一定の注記を要件として、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことが可能。 | 廃止する。 |
| ② 利息相当額の各期への配分 | ファイナンス・リース取引に関して、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行う場合、利息相当額は、原則として利息法により各期に配分する。 | 原則は、現行どおりだが、リース資産に重要性がないと認められる場合には、①リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法。(この場合、リース資産およびリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上される)、②利息相当額の総額を定額法でリース期間にわたり配分する方法のいずれかの方法を適用することが可能。 |
| ③ 通常の保守等の役務提供相当額の処理 | ― | 維持管理費用に準じて、原則として、リース料総額から区分。 |
| ④ 貸借対照表の表示 | (借手側) リース資産は、有形固定資産の属する各科目に含めて表示。 | (借手側) リース資産については、原則として、有形固定資産、無形固定資産の別に、一括してリース資産として表示する。ただし、有形固定資産または無形固定資産の属する各科目に含めることもできる。 |
| (貸手側) リース債権として表示する。 | (貸手側) 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権および所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産は、流動資産に表示する。 | |
| ⑤ 注 記 | 所有権移転外ファイナンス・リース取引について、賃貸借取引に準じた会計処理を採用した場合、一定の注記を要する。 | (借手側) (1)リース資産について、その内容(資産の種類等)を注記する。 (2)リース債務について、貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額および5年超の返済予定額を注記する。 (貸手側) (1)リース投資資産について、リース料債権部分と見積残存価額および受取利息相当額を注記する。 (2)リース債権またはリース投資資産に係るリース料債権部分について、貸借対照表日後5年以内における1年ごとの回収予定額および5年超の回収予定額を注記する。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















