解説記事2006年07月10日 【会計解説】 企業会計基準公開草案第14号「関連当事者の開示に関する会計基準(案)」について(2006年7月10日号・№170)
実務解説
企業会計基準公開草案第14号「関連当事者の開示に関する会計基準(案)」について
企業会計基準委員会 専門研究員 五反田屋 信明
はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成18年6月6日に、企業会計基準公開草案第14号「関連当事者の開示に関する会計基準(案)」および企業会計基準適用指針公開草案第16号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「本公開草案」という)を公表し、平成18年7月20日までコメントを募集している。
本稿では、本公開草案の概要を紹介することとする。
なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、また、本公開草案は最終的なものではなく、本公開草案に寄せられたコメントを踏まえた検討により変更される可能性があることを予めお断りしておく。
Ⅰ 本公開草案の公表の経緯
関連当事者の開示に関しては、平成9年6月、企業会計審議会により公表された「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」で「関連当事者との取引」を連結財務諸表の注記とすることとされ、連結財務諸表規則および財務諸表等規則(以下「証券取引法関係規則」という)により、連結財務諸表(連結財務諸表を作成していない場合には個別の財務諸表)の注記事項とすることが定められている。また、監査上の実務指針として、平成11年4月に日本公認会計士協会監査委員会報告第62号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第62号」という)が公表され、開示の際の重要性などの判断指針として用いられている。
しかしながら現行の証券取引法関係規則は、連結子会社と関連当事者との取引を開示対象と扱っていないことなどの点で、米国会計基準や国際財務報告基準などの国際的な会計基準と異なっており、その内容を見直すべきではないかという指摘がある。さらに、平成17年3月には、ASBJと国際会計基準審議会(IASB)との会計基準のコンバージェンスに向けた共同プロジェクトにおいて、「関連当事者の開示」が検討項目のひとつに採り上げられている。これらの状況を踏まえ、ASBJでは関連当事者の開示に関する会計基準を整備することとし、このたび本公開草案を公表することとなった。
Ⅱ 会社法関係規則との関係
関連当事者開示については、会社計算規則でも新たに開示規定が盛り込まれたため、会計基準としてこれにどのように対応するかも検討を行った。
計算規則上の開示では、業務執行者の事業運営のあり方が適切かどうかという観点を付加して独自の開示除外事項を設けていることや、連結財務諸表作成会社においても個別注記表(個別財務諸表での注記)のみでの開示を求めているなど、会計基準のコンバージェンスを踏まえた検討との関係では異なる要素が含まれているため、これらの点に関しては会計基準上その取扱いを明記せず、関係当局の当該規則に関する見解などを踏まえた実務に委ねることとした。
Ⅲ 本公開草案の概要
1 関連当事者開示の目的
関連当事者の開示の目的は、国際的な会計基準と同様に、会社(連結財務諸表上は連結財務諸表作成会社および連結子会社をいう。以下同じ)と関連当事者との取引や関連当事者の存在が財務諸表に与えている影響を財務諸表利用者が把握できるように、適切な情報を提供することとしている(会計基準案第2項)。
2 関連当事者の範囲
本公開草案では、関連当事者に該当する者として、①親会社、②子会社、③財務諸表作成会社と同一の親会社を持つ会社、④財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社ならびにその親会社および子会社、⑤関連会社および当該関連会社の子会社、⑥財務諸表作成会社の主要株主およびその近親者、⑦財務諸表作成会社の役員およびその近親者、⑧親会社の役員およびその近親者、⑨重要な子会社の役員およびその近親者、⑩上記の⑥から⑨に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等およびその子会社、⑪従業員のための企業年金(会社とは明らかに独立して運営されているものを除く)を掲げている(会計基準案第5項(3))。
このうち、⑧親会社の役員およびその近親者、⑨重要な子会社の役員およびその近親者、⑪従業員のための企業年金などは、関連当事者開示の充実を図る観点から国際的な会計基準も参考にして新たに対象としたものである。なお、重要な子会社の役員の範囲については様々な議論があったが、本公開草案では、企業グループの事業運営に強い影響力を持つ者が子会社の役員にいる場合の当該役員をさすこととし、純粋持株会社における事業運営の中核となる子会社の役員を例示として示している(会計基準案第20項)。また、従業員の企業年金が関連当事者となるのは、資金運用の一環として当該企業グループと取引が行われている場合などに限定されるものと考えている(会計基準案第22項)。なお役員等の近親者については、現行の証券取引法関係規則と同様、二親等以内の親族としている(会計基準案第5項(8))。
また、連結財務諸表上で注記を行う場合、連結子会社は連結会社に含まれるため、関連当事者からは除かれることとした(一方、個別財務諸表上で開示を行う場合には、重要な子会社の役員等が除かれることとなる)(会計基準案第5項(3))。
3 関連当事者との取引に関する開示
(1)開示する取引の範囲
開示する取引の範囲については、国際的な会計基準と同様、連結子会社と関連当事者との取引も開示対象とした(図参照)。
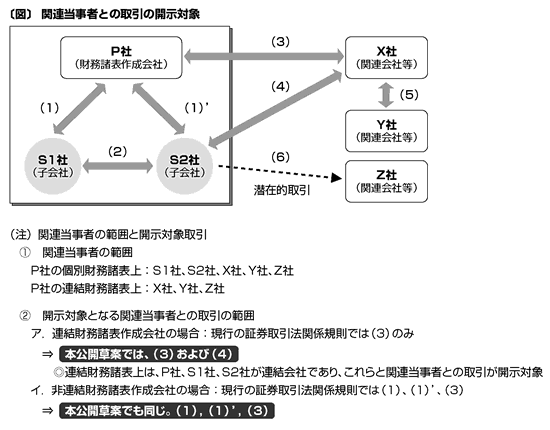
(2)開示対象外取引
現行の証券取引法関係規則と同様、①一般競争入札による取引ならびに預金利息および配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引と、②役員に対する報酬、賞与および退職慰労金の支払いを、開示対象外の取引とした(会計基準案第9項)。
(3)開示項目
重要な関連当事者との取引があった場合、現行の証券取引法関係規則と同様に、①関連当事者の概要、②会社と関連当事者との関係、③取引の内容(外見上が第三者との取引である場合は、形式上の取引先名を記載した上で、実質的には関連当事者との取引である旨を記載する)、④取引の種類ごとの取引金額、⑤取引条件および取引条件の決定方針、⑥取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高、⑦取引条件の変更があった場合は、その旨、変更内容、当該変更が財務諸表に与えている影響の内容、を開示することとした。
また、今回新たに、⑧関連当事者との取引に関わる貸倒懸念債権や破産更生債権等に係る情報として、貸倒引当金繰入額や貸倒損失などの開示も求めることとしている。この情報については、関連当事者の種類ごとに合算して記載することもできるとした(会計基準案第10項)。
(4)関連当事者との取引に関する重要性の判断規準
本公開草案では、監査委員会報告第62号による現行の取扱いと同様に、関連当事者が法人である場合と個人である場合に分けて、重要性の判断規準を示している。
<関連当事者が法人の場合(適用指針案第15項)>
① 連結損益計算書項目に関係する関連当事者との取引
イ 売上高、売上原価、販売費および一般管理費
売上高または売上原価と販売費および一般管理費の合計額の10%を超える取引
ロ 営業外収益、営業外費用
営業外収益または営業外費用の合計額の10%を超える損益に係る取引
ハ 特別利益、特別損失
1,000万円を超える損益に係る取引
ただし、ロおよびハに係る関連当事者との取引については、上記の基準に該当する場合であっても、その取引総額が、税金等調整前当期純損益または最近5年間の平均の税金等調整前当期純損益の10%以下となる場合には、開示を要しないものとしている。
② 連結貸借対照表項目に関係する関連当事者との取引および債務保証等および担保提供または受入れ
イ その金額が総資産の1%を超える取引
ロ 資金貸借取引、有形固定資産や有価証券の購入・売却取引等については、それぞれの残高が1%以下であっても、取引の発生総額(資金貸付額等)が総資産の1%を超える取引(ただし、取引が頻繁に行われている場合や、その発生総額の把握が困難である場合には、期中の平均残高が総資産の1%を超える取引を開示することもできるとした)
ハ 事業の譲受または譲渡の場合には、譲受または譲渡の対象となる資産や負債が個々に取引されるのではなく、一体として取引されると考えられることから、対象となる資産または負債の総額のいずれか大きい額が、総資産の1%を超える取引
<関連当事者が個人の場合(適用指針案第16項)>
関連当事者との取引が、連結損益計算書項目および連結貸借対照表項目等のいずれに係る取引についても、1,000万円を超える取引については、すべて開示対象とすることとしている。現行の取扱いでは、100万円を超える取引のすべてを開示対象とされているが、米国SEC規則の改正動向などを参考に金額基準を見直した。なお、会社の役員(親会社および重要な子会社の役員を含む)およびその近親者が他の法人の代表者を兼務し、当該役員等がその法人の代表者として会社と取引を行う場合には、法人の場合の重要性の判断規準を適用することとしたが、役員や個人主要株主が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等と取引する場合には、現行の取扱いと同様に、個人の重要性の判断を適用することとしている。
4 関連当事者の存在に関する開示
(1)親会社の情報
本公開草案では、親会社の情報を会社の連結財務諸表を理解する上で重要な情報と考え、新たに親会社の名称および公開の有無の開示を求めている(会計基準案第11項(1)および適用指針案第10項)。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社(共同支配企業を含む)の要約財務情報については、国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も踏まえ、我が国では関連当事者の存在に関する開示として、新たにこれを求めることとした。
要約財務情報の記載項目としては、持分法投資損益(共同支配企業の場合は持分法に準ずる処理を適用した場合の投資損益)の算定に用いた財務情報をもとに、主な貸借対照表項目および損益計算書項目を開示することとし、たとえば以下の内容を記載することとしている。
① 貸借対照表項目:
流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計
② 損益計算書項目:
売上高、税引前当期純損益、当期純損益 要約財務情報の開示方法としては、①個別に開示する方法、②重要な関連会社の要約財務情報を合算して開示する方法、③持分法投資損益の算定対象としたすべての関連会社の財務情報を合算して開示(その旨および重要な関連会社の名称を明記)する方法のいずれかを選択できることとしている(会計基準案第11項(2)および適用指針案第11項)。
(3)重要な関連会社の要約財務情報における重要性の判断規準
要約財務情報の開示(会計基準案第11項)を必要とする関連会社の重要性は、以下のいずれかの場合に該当するかにより判断することとしている(適用指針案第19項)。
① 各関連会社の総資産(持分相当額)が、会社の総資産の10%を超える場合
② 各関連会社の税引前当期純損益(持分相当額)が、会社の税金等調整前当期純損益の10%を超える場合
ただし、②については上記の基準を満たす場合であっても、会社の最近5年間の平均の税金等調整前当期純損益の10%を超えない場合には、開示を要しないとしている。
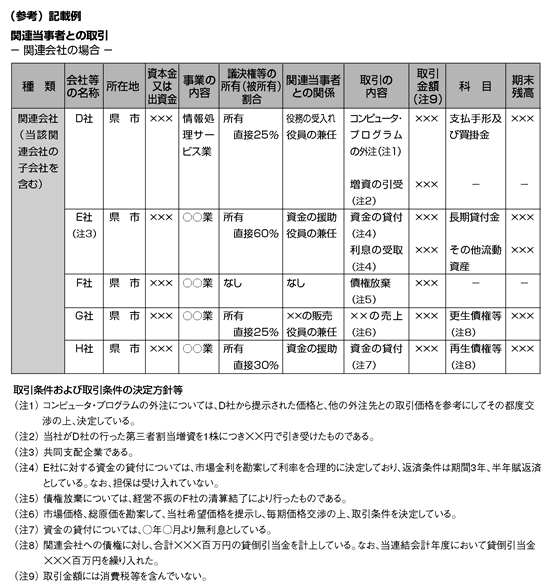
Ⅳ 適用時期等
関連当事者開示の会計基準の適用時期については、財務諸表作成者においてシステム対応等の受入準備が必要であることを考慮して、本公開草案では平成20年4月1日以後開始する連結会計年度または事業年度から適用することを提案している。ただし、平成19年4月1日以後に開始する連結会計年度または事業年度から適用することもできることとしている(会計基準案第12項)。(ごたんだや・のぶあき)
企業会計基準公開草案第14号「関連当事者の開示に関する会計基準(案)」について
企業会計基準委員会 専門研究員 五反田屋 信明
はじめに
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成18年6月6日に、企業会計基準公開草案第14号「関連当事者の開示に関する会計基準(案)」および企業会計基準適用指針公開草案第16号「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針(案)」(以下「本公開草案」という)を公表し、平成18年7月20日までコメントを募集している。
本稿では、本公開草案の概要を紹介することとする。
なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私見であり、また、本公開草案は最終的なものではなく、本公開草案に寄せられたコメントを踏まえた検討により変更される可能性があることを予めお断りしておく。
Ⅰ 本公開草案の公表の経緯
関連当事者の開示に関しては、平成9年6月、企業会計審議会により公表された「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」で「関連当事者との取引」を連結財務諸表の注記とすることとされ、連結財務諸表規則および財務諸表等規則(以下「証券取引法関係規則」という)により、連結財務諸表(連結財務諸表を作成していない場合には個別の財務諸表)の注記事項とすることが定められている。また、監査上の実務指針として、平成11年4月に日本公認会計士協会監査委員会報告第62号「関連当事者との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」(以下「監査委員会報告第62号」という)が公表され、開示の際の重要性などの判断指針として用いられている。
しかしながら現行の証券取引法関係規則は、連結子会社と関連当事者との取引を開示対象と扱っていないことなどの点で、米国会計基準や国際財務報告基準などの国際的な会計基準と異なっており、その内容を見直すべきではないかという指摘がある。さらに、平成17年3月には、ASBJと国際会計基準審議会(IASB)との会計基準のコンバージェンスに向けた共同プロジェクトにおいて、「関連当事者の開示」が検討項目のひとつに採り上げられている。これらの状況を踏まえ、ASBJでは関連当事者の開示に関する会計基準を整備することとし、このたび本公開草案を公表することとなった。
Ⅱ 会社法関係規則との関係
関連当事者開示については、会社計算規則でも新たに開示規定が盛り込まれたため、会計基準としてこれにどのように対応するかも検討を行った。
計算規則上の開示では、業務執行者の事業運営のあり方が適切かどうかという観点を付加して独自の開示除外事項を設けていることや、連結財務諸表作成会社においても個別注記表(個別財務諸表での注記)のみでの開示を求めているなど、会計基準のコンバージェンスを踏まえた検討との関係では異なる要素が含まれているため、これらの点に関しては会計基準上その取扱いを明記せず、関係当局の当該規則に関する見解などを踏まえた実務に委ねることとした。
Ⅲ 本公開草案の概要
1 関連当事者開示の目的
関連当事者の開示の目的は、国際的な会計基準と同様に、会社(連結財務諸表上は連結財務諸表作成会社および連結子会社をいう。以下同じ)と関連当事者との取引や関連当事者の存在が財務諸表に与えている影響を財務諸表利用者が把握できるように、適切な情報を提供することとしている(会計基準案第2項)。
2 関連当事者の範囲
本公開草案では、関連当事者に該当する者として、①親会社、②子会社、③財務諸表作成会社と同一の親会社を持つ会社、④財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社ならびにその親会社および子会社、⑤関連会社および当該関連会社の子会社、⑥財務諸表作成会社の主要株主およびその近親者、⑦財務諸表作成会社の役員およびその近親者、⑧親会社の役員およびその近親者、⑨重要な子会社の役員およびその近親者、⑩上記の⑥から⑨に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等およびその子会社、⑪従業員のための企業年金(会社とは明らかに独立して運営されているものを除く)を掲げている(会計基準案第5項(3))。
このうち、⑧親会社の役員およびその近親者、⑨重要な子会社の役員およびその近親者、⑪従業員のための企業年金などは、関連当事者開示の充実を図る観点から国際的な会計基準も参考にして新たに対象としたものである。なお、重要な子会社の役員の範囲については様々な議論があったが、本公開草案では、企業グループの事業運営に強い影響力を持つ者が子会社の役員にいる場合の当該役員をさすこととし、純粋持株会社における事業運営の中核となる子会社の役員を例示として示している(会計基準案第20項)。また、従業員の企業年金が関連当事者となるのは、資金運用の一環として当該企業グループと取引が行われている場合などに限定されるものと考えている(会計基準案第22項)。なお役員等の近親者については、現行の証券取引法関係規則と同様、二親等以内の親族としている(会計基準案第5項(8))。
また、連結財務諸表上で注記を行う場合、連結子会社は連結会社に含まれるため、関連当事者からは除かれることとした(一方、個別財務諸表上で開示を行う場合には、重要な子会社の役員等が除かれることとなる)(会計基準案第5項(3))。
3 関連当事者との取引に関する開示
(1)開示する取引の範囲
開示する取引の範囲については、国際的な会計基準と同様、連結子会社と関連当事者との取引も開示対象とした(図参照)。
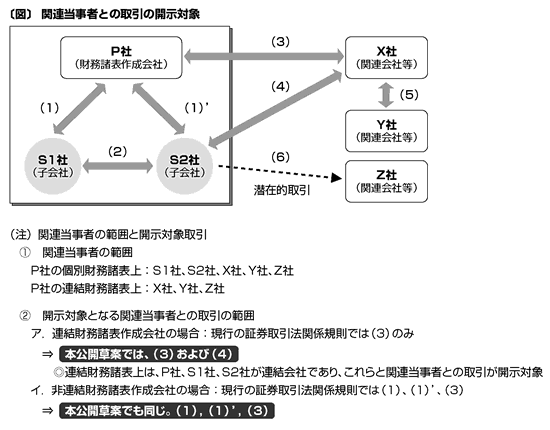
(2)開示対象外取引
現行の証券取引法関係規則と同様、①一般競争入札による取引ならびに預金利息および配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引と、②役員に対する報酬、賞与および退職慰労金の支払いを、開示対象外の取引とした(会計基準案第9項)。
(3)開示項目
重要な関連当事者との取引があった場合、現行の証券取引法関係規則と同様に、①関連当事者の概要、②会社と関連当事者との関係、③取引の内容(外見上が第三者との取引である場合は、形式上の取引先名を記載した上で、実質的には関連当事者との取引である旨を記載する)、④取引の種類ごとの取引金額、⑤取引条件および取引条件の決定方針、⑥取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高、⑦取引条件の変更があった場合は、その旨、変更内容、当該変更が財務諸表に与えている影響の内容、を開示することとした。
また、今回新たに、⑧関連当事者との取引に関わる貸倒懸念債権や破産更生債権等に係る情報として、貸倒引当金繰入額や貸倒損失などの開示も求めることとしている。この情報については、関連当事者の種類ごとに合算して記載することもできるとした(会計基準案第10項)。
(4)関連当事者との取引に関する重要性の判断規準
本公開草案では、監査委員会報告第62号による現行の取扱いと同様に、関連当事者が法人である場合と個人である場合に分けて、重要性の判断規準を示している。
<関連当事者が法人の場合(適用指針案第15項)>
① 連結損益計算書項目に関係する関連当事者との取引
イ 売上高、売上原価、販売費および一般管理費
売上高または売上原価と販売費および一般管理費の合計額の10%を超える取引
ロ 営業外収益、営業外費用
営業外収益または営業外費用の合計額の10%を超える損益に係る取引
ハ 特別利益、特別損失
1,000万円を超える損益に係る取引
ただし、ロおよびハに係る関連当事者との取引については、上記の基準に該当する場合であっても、その取引総額が、税金等調整前当期純損益または最近5年間の平均の税金等調整前当期純損益の10%以下となる場合には、開示を要しないものとしている。
② 連結貸借対照表項目に関係する関連当事者との取引および債務保証等および担保提供または受入れ
イ その金額が総資産の1%を超える取引
ロ 資金貸借取引、有形固定資産や有価証券の購入・売却取引等については、それぞれの残高が1%以下であっても、取引の発生総額(資金貸付額等)が総資産の1%を超える取引(ただし、取引が頻繁に行われている場合や、その発生総額の把握が困難である場合には、期中の平均残高が総資産の1%を超える取引を開示することもできるとした)
ハ 事業の譲受または譲渡の場合には、譲受または譲渡の対象となる資産や負債が個々に取引されるのではなく、一体として取引されると考えられることから、対象となる資産または負債の総額のいずれか大きい額が、総資産の1%を超える取引
<関連当事者が個人の場合(適用指針案第16項)>
関連当事者との取引が、連結損益計算書項目および連結貸借対照表項目等のいずれに係る取引についても、1,000万円を超える取引については、すべて開示対象とすることとしている。現行の取扱いでは、100万円を超える取引のすべてを開示対象とされているが、米国SEC規則の改正動向などを参考に金額基準を見直した。なお、会社の役員(親会社および重要な子会社の役員を含む)およびその近親者が他の法人の代表者を兼務し、当該役員等がその法人の代表者として会社と取引を行う場合には、法人の場合の重要性の判断規準を適用することとしたが、役員や個人主要株主が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等と取引する場合には、現行の取扱いと同様に、個人の重要性の判断を適用することとしている。
4 関連当事者の存在に関する開示
(1)親会社の情報
本公開草案では、親会社の情報を会社の連結財務諸表を理解する上で重要な情報と考え、新たに親会社の名称および公開の有無の開示を求めている(会計基準案第11項(1)および適用指針案第10項)。
(2)重要な関連会社の要約財務情報
重要な関連会社(共同支配企業を含む)の要約財務情報については、国際的な会計基準とのコンバージェンスの観点も踏まえ、我が国では関連当事者の存在に関する開示として、新たにこれを求めることとした。
要約財務情報の記載項目としては、持分法投資損益(共同支配企業の場合は持分法に準ずる処理を適用した場合の投資損益)の算定に用いた財務情報をもとに、主な貸借対照表項目および損益計算書項目を開示することとし、たとえば以下の内容を記載することとしている。
① 貸借対照表項目:
流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計
② 損益計算書項目:
売上高、税引前当期純損益、当期純損益 要約財務情報の開示方法としては、①個別に開示する方法、②重要な関連会社の要約財務情報を合算して開示する方法、③持分法投資損益の算定対象としたすべての関連会社の財務情報を合算して開示(その旨および重要な関連会社の名称を明記)する方法のいずれかを選択できることとしている(会計基準案第11項(2)および適用指針案第11項)。
(3)重要な関連会社の要約財務情報における重要性の判断規準
要約財務情報の開示(会計基準案第11項)を必要とする関連会社の重要性は、以下のいずれかの場合に該当するかにより判断することとしている(適用指針案第19項)。
① 各関連会社の総資産(持分相当額)が、会社の総資産の10%を超える場合
② 各関連会社の税引前当期純損益(持分相当額)が、会社の税金等調整前当期純損益の10%を超える場合
ただし、②については上記の基準を満たす場合であっても、会社の最近5年間の平均の税金等調整前当期純損益の10%を超えない場合には、開示を要しないとしている。
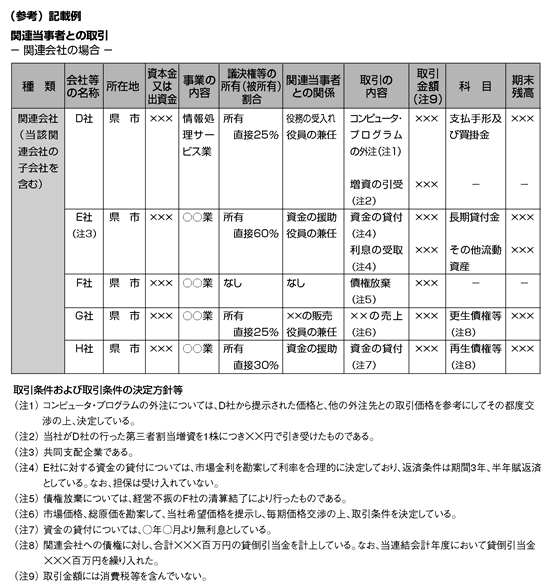
Ⅳ 適用時期等
関連当事者開示の会計基準の適用時期については、財務諸表作成者においてシステム対応等の受入準備が必要であることを考慮して、本公開草案では平成20年4月1日以後開始する連結会計年度または事業年度から適用することを提案している。ただし、平成19年4月1日以後に開始する連結会計年度または事業年度から適用することもできることとしている(会計基準案第12項)。(ごたんだや・のぶあき)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















