解説記事2006年07月31日 【実務解説】 【連載】企業結合審査を考える 第6回 ガイドライン改訂に向けた今後の課題(2006年7月31日号・№173)
実務解説
【連載】企業結合審査を考える 第6回 ガイドライン改訂に向けた今後の課題
経済産業省経済産業政策局産業組織課 競争環境整備室長 土井良治
今次連載で5回にわたり紹介してきた経済産業省「競争政策研究会報告書~グローバル競争下における企業結合審査の予見可能性の向上を目指して」の主な提言については、政府部内では、産業構造審議会新成長政策部会での審議、経済財政諮問会議での議論を経て、7月6日に、総理主宰による関係閣僚および与党幹部で構成される財政・経済一体改革会議が取りまとめた「経済成長戦略大綱」の中で、以下のような政府のコミットメントとして決定された。
「第1国際競争力の強化 ……/2.アジア等海外のダイナミズムの取り込み ……/
(2)アジア等との協働を促進し、グローバル化に対応する制度の整備 ……/
② 経済のグローバル化に対応した企業結合審査に関するガイドラインの見直し
『企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針』(平成16年5月31日)に関し、経済のグローバル化に伴う国際的な企業間競争の進展に対応し、企業の組織再編に当たっての予見可能性並びに手続の透明性及び迅速性を一層高める観点から、市場画定の在り方、独占禁止法上の問題が生じることがないと考えられる企業結合の範囲に関する基準、輸入圧力等の評価に関する基準等について、これまでの審査実績等を踏まえ、また、国際的整合性の確保にも留意しつつ見直しを行い、2006年度中に結論を得る。」
これを受け、今後、政府部内では、企業結合審査に係るガイドライン見直しが今年度中に行われるが、最終回の本稿では、改訂論議の中で重要な論点となる以下の3つの課題について問題意識を掘り下げてみたい(注:本稿において、意見にわたる部分は筆者の個人的見解である)。
1 市場シェアの目安に適正な指針を与える~市場シェア・HHI基準の見直し
研究会報告では、直近3年間の企業結合審査実績等を踏まえて、企業が不必要に企業結合に対して抑制的にならないよう、以下の点を提言している。
○ 独禁法上問題がないと判断される市場シェアを25%以下から35%以下に引上げ
○ 35%から50%の範囲については、独禁法上問題となる可能性が小さい旨を明確化
○ 50%以上の案件であっても競争要因が認められれば独禁法上問題はないと判断されることを明確化
○ HHI基準を競争制限性の判断基準とするのであれば、現実的水準へ大幅に見直し
これに対して、近年主要国の企業結合審査では、市場シェア以外の競争要因を評価することが主流であるとして、現行基準を見直すのであれば、米国のように、HHI基準だけにすることが適当との意見がある。しかし、当方の問題意識は、過去当局が25%ルールを一律的に適用していた経緯もあり、現在35%を超える合併は認められないと誤解している企業が多く存在しているという現実への対応である。近年の審査実績で35%以下はすべてシロ、50%まで広げても8割以上シロ、50%以上でも認められるケースは多々あるという実態を、ガイドラインに素直に記載することが、まさに企業へ適切な指針を与えるということである。
また、米国の最新の見直し論議においても、HHI:1000または1800という水準は、米国の審査実績からしても余りにも低いとの批判があることや、米英以外の主要国は市場シェア基準を採用しており、EUが25%と50%、仏国が25%と40%、韓国が50%とメルクマールには各国固有の判断により多様性があることに配意すべきである。また、市場シェアは、ある一定の%水準だけで競争制限性を機械的に判断する数値基準ではなく、あくまで実績を踏まえた目安を提示することにより、企業に対する予見可能性を高め、抑制的に誤解するリスクを除去するという効果を意図するものである。
2 国境を越えた競争評価~国際市場画定・輸入圧力評価の適正化
現行ガイドラインは、「当事会社の事業区域が国外に及んでいる場合であっても、法により保護すべき競争は日本国内における競争であると考えられるので、国内の取引先の事業活動を中心としてみることとなる。したがって、……通常、輸出先を含めた一定の取引分野が画定されることはない。」と明記している。独禁法の保護法益が、国内の一般消費者を対象とすることは疑う余地はないが、企業結合審査の要諦は、企業が結合するという市場構造の変化が有効で十分な競争を損い、消費者に不利益を及ぼさないかという競争環境の評価(競争評価)である。国境を越えた競争が有効に働き国内消費者の利益が守られているのであれば、競争評価は国際的に広がる市場を対象に行うべきである。「法により保護すべき」は国内消費者であり、競争評価は「日本国内における競争」に限定されるものでなく、競争が現に展開されている市場の広がりに依拠すべきものである。この観点から、国際市場での競争にさらされている多くの日本企業に誤解を与えている現行ガイドラインの改訂が求められる。
他方で昨年、2件の化学製品に係る合併案件が独禁法上問題との審査結果を受け合併を断念した。この両者に共通している判断根拠が、中国を中心にしたアジア市場の需給が逼迫しているために国際的に供給余力がない、したがって輸入圧力が十分でなく、合併によって国内市場の支配力が高まり競争が実質的に制限されることとなるというものである。この評価について様々な企業家の声が届いている。
○ たまたま需給逼迫時に交渉が整った合併は許可されず市況が緩めば許されるということか
○ そもそも合併規制とは市場の構造要因をベースに判断すべき規制と思っていたが景気循環要因が主要因となり得るのか
○ 好況時にこそ来たるべき不況時に備え贅肉を落とすことが先見性ある経営判断であり最終的に消費者利益にかなうのではないか
○ BRICs市場の急成長という好機をとらえシェア・規模を拡大し競争力を獲得した企業は容易に日本市場への参入はできるのではないか
といった疑問である。現行ガイドラインには、輸入圧力の判断要因が網羅的に列記されているが、このような声に明解に応えられる判断基準が設けられることが期待される。
さらに、日本経済を支えている輸出産業について、構造的変化が生じていることに留意が必要である。図表1にあるように、90年代に日本からの輸出は、中間財の輸出が最終財の輸出を追い抜いているが、これは図表2にあるように、アジアに立地する最終組立工程に日本から高付加価値の高機能部材やマザーマシーンを輸出し、最終製品はアジアから世界に輸出されるという稠密な国際分業構造が形成されてきたということを示している。このことは図表3・4のように、川上から川下の最終製品に至るほど日本製品の世界シェアが減少していることにも現れている。すなわち日本の製造業の競争優位が中間財にシフトしている中で、最終組立工程は必ずしも国内に立地しているとは限らず、中間財については輸出は存在しても、輸入圧力は構造的に存在しないというケースも生じる。国境を越えたサプライチェーンの最適構造化、モジュール型アーキテクチャーの進展等の現代製造業の高度な構造変化のなかでは、中間財の競争評価においては、ユーザーは誰でどこに存在し、評価すべき市場はどのレイヤーなのか、経済実態を的確に捉えた企業結合審査が必要である。
その他、国際的な市場経済のダイナミズムを適切に考慮する競争評価も重要である。すなわち、成長市場と成熟市場では、経営者・投資家の行動に大きな違いがあり、歴史的な市場拡大チャンスが到来しているBRICs等の成長市場では、国際的参入投資が旺盛で覇権争奪の競争が熾烈である。このような成長市場で築かれる競争優位は技術的な新規性も具備し、日本市場含め既存市場へ戦略的に国際展開することも容易である。このような成長市場のダイナミズムに直接関連する財に関わる企業の結合審査においては、単に現在の供給余力がないといった静態的要因に依拠するのではなく、成長市場のダイナミズムがもたらす参入圧力を構造的にとらえて的確に評価すべきである。
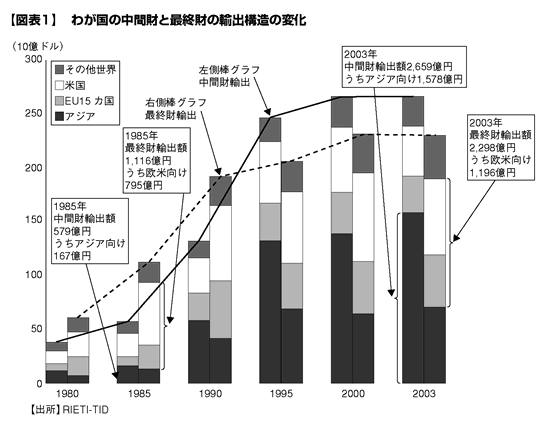
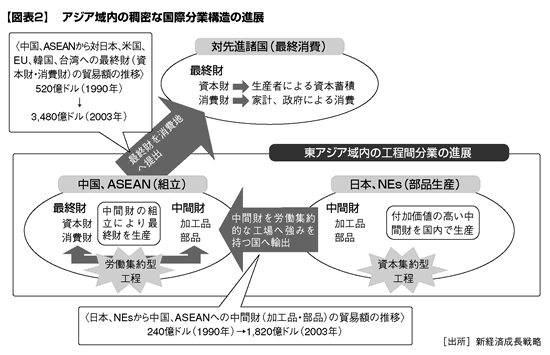
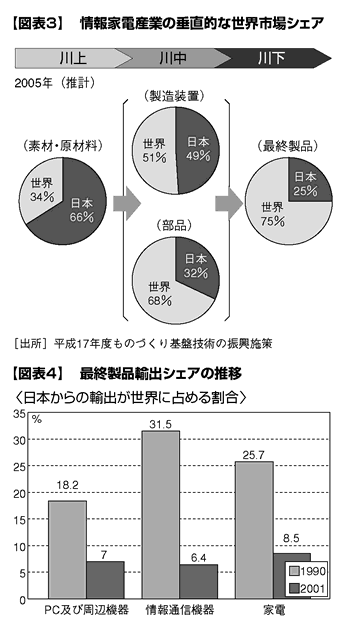
3 需要家からの構造的な競争圧力の適切な評価
企業結合審査ではユーザー調査の結果が重要な判断要因となるが、たとえば前述の国外に大手ユーザーが存在する中間財に係るユーザー調査において、国内に残っている一部の中小組立メーカーの声だけで輸入圧力を評価することは、当該中間財に係る適正な競争圧力の評価になっているとはいえない。このような場合は、国をまたぐ当該中間財市場全体を捉え、潜在的な参入圧力を加味した競争評価がなされることが適切である。
また、IT革命による電子商取引の進展、流通ビジネスモデルの進化による小売セクターからの価格圧力(例:ウォールマート、家電量販店)等を背景に、財の生産サイドに対して販売サイド・消費者サイドからかかる競争圧力は、近年構造的に増大している。このような需要家の市場支配力が構造的に高まっている財については、仮に供給サイドの寡占化が進展したとしても一般消費者の利益を損なう蓋然性は極めて低くなっていることを適切に評価すべきである。この需要家からの競争圧力は、パソコンとその中核的中間財たる半導体の価格低下にみられるように、前述の中間財に対するユーザー圧力の競争評価においても適切に扱われるよう明確な指針が示されることが重要である。(どい・りょうじ)
【連載】企業結合審査を考える 第6回 ガイドライン改訂に向けた今後の課題
経済産業省経済産業政策局産業組織課 競争環境整備室長 土井良治
今次連載で5回にわたり紹介してきた経済産業省「競争政策研究会報告書~グローバル競争下における企業結合審査の予見可能性の向上を目指して」の主な提言については、政府部内では、産業構造審議会新成長政策部会での審議、経済財政諮問会議での議論を経て、7月6日に、総理主宰による関係閣僚および与党幹部で構成される財政・経済一体改革会議が取りまとめた「経済成長戦略大綱」の中で、以下のような政府のコミットメントとして決定された。
「第1国際競争力の強化 ……/2.アジア等海外のダイナミズムの取り込み ……/
(2)アジア等との協働を促進し、グローバル化に対応する制度の整備 ……/
② 経済のグローバル化に対応した企業結合審査に関するガイドラインの見直し
『企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針』(平成16年5月31日)に関し、経済のグローバル化に伴う国際的な企業間競争の進展に対応し、企業の組織再編に当たっての予見可能性並びに手続の透明性及び迅速性を一層高める観点から、市場画定の在り方、独占禁止法上の問題が生じることがないと考えられる企業結合の範囲に関する基準、輸入圧力等の評価に関する基準等について、これまでの審査実績等を踏まえ、また、国際的整合性の確保にも留意しつつ見直しを行い、2006年度中に結論を得る。」
これを受け、今後、政府部内では、企業結合審査に係るガイドライン見直しが今年度中に行われるが、最終回の本稿では、改訂論議の中で重要な論点となる以下の3つの課題について問題意識を掘り下げてみたい(注:本稿において、意見にわたる部分は筆者の個人的見解である)。
1 市場シェアの目安に適正な指針を与える~市場シェア・HHI基準の見直し
研究会報告では、直近3年間の企業結合審査実績等を踏まえて、企業が不必要に企業結合に対して抑制的にならないよう、以下の点を提言している。
○ 独禁法上問題がないと判断される市場シェアを25%以下から35%以下に引上げ
○ 35%から50%の範囲については、独禁法上問題となる可能性が小さい旨を明確化
○ 50%以上の案件であっても競争要因が認められれば独禁法上問題はないと判断されることを明確化
○ HHI基準を競争制限性の判断基準とするのであれば、現実的水準へ大幅に見直し
これに対して、近年主要国の企業結合審査では、市場シェア以外の競争要因を評価することが主流であるとして、現行基準を見直すのであれば、米国のように、HHI基準だけにすることが適当との意見がある。しかし、当方の問題意識は、過去当局が25%ルールを一律的に適用していた経緯もあり、現在35%を超える合併は認められないと誤解している企業が多く存在しているという現実への対応である。近年の審査実績で35%以下はすべてシロ、50%まで広げても8割以上シロ、50%以上でも認められるケースは多々あるという実態を、ガイドラインに素直に記載することが、まさに企業へ適切な指針を与えるということである。
また、米国の最新の見直し論議においても、HHI:1000または1800という水準は、米国の審査実績からしても余りにも低いとの批判があることや、米英以外の主要国は市場シェア基準を採用しており、EUが25%と50%、仏国が25%と40%、韓国が50%とメルクマールには各国固有の判断により多様性があることに配意すべきである。また、市場シェアは、ある一定の%水準だけで競争制限性を機械的に判断する数値基準ではなく、あくまで実績を踏まえた目安を提示することにより、企業に対する予見可能性を高め、抑制的に誤解するリスクを除去するという効果を意図するものである。
2 国境を越えた競争評価~国際市場画定・輸入圧力評価の適正化
現行ガイドラインは、「当事会社の事業区域が国外に及んでいる場合であっても、法により保護すべき競争は日本国内における競争であると考えられるので、国内の取引先の事業活動を中心としてみることとなる。したがって、……通常、輸出先を含めた一定の取引分野が画定されることはない。」と明記している。独禁法の保護法益が、国内の一般消費者を対象とすることは疑う余地はないが、企業結合審査の要諦は、企業が結合するという市場構造の変化が有効で十分な競争を損い、消費者に不利益を及ぼさないかという競争環境の評価(競争評価)である。国境を越えた競争が有効に働き国内消費者の利益が守られているのであれば、競争評価は国際的に広がる市場を対象に行うべきである。「法により保護すべき」は国内消費者であり、競争評価は「日本国内における競争」に限定されるものでなく、競争が現に展開されている市場の広がりに依拠すべきものである。この観点から、国際市場での競争にさらされている多くの日本企業に誤解を与えている現行ガイドラインの改訂が求められる。
他方で昨年、2件の化学製品に係る合併案件が独禁法上問題との審査結果を受け合併を断念した。この両者に共通している判断根拠が、中国を中心にしたアジア市場の需給が逼迫しているために国際的に供給余力がない、したがって輸入圧力が十分でなく、合併によって国内市場の支配力が高まり競争が実質的に制限されることとなるというものである。この評価について様々な企業家の声が届いている。
○ たまたま需給逼迫時に交渉が整った合併は許可されず市況が緩めば許されるということか
○ そもそも合併規制とは市場の構造要因をベースに判断すべき規制と思っていたが景気循環要因が主要因となり得るのか
○ 好況時にこそ来たるべき不況時に備え贅肉を落とすことが先見性ある経営判断であり最終的に消費者利益にかなうのではないか
○ BRICs市場の急成長という好機をとらえシェア・規模を拡大し競争力を獲得した企業は容易に日本市場への参入はできるのではないか
といった疑問である。現行ガイドラインには、輸入圧力の判断要因が網羅的に列記されているが、このような声に明解に応えられる判断基準が設けられることが期待される。
さらに、日本経済を支えている輸出産業について、構造的変化が生じていることに留意が必要である。図表1にあるように、90年代に日本からの輸出は、中間財の輸出が最終財の輸出を追い抜いているが、これは図表2にあるように、アジアに立地する最終組立工程に日本から高付加価値の高機能部材やマザーマシーンを輸出し、最終製品はアジアから世界に輸出されるという稠密な国際分業構造が形成されてきたということを示している。このことは図表3・4のように、川上から川下の最終製品に至るほど日本製品の世界シェアが減少していることにも現れている。すなわち日本の製造業の競争優位が中間財にシフトしている中で、最終組立工程は必ずしも国内に立地しているとは限らず、中間財については輸出は存在しても、輸入圧力は構造的に存在しないというケースも生じる。国境を越えたサプライチェーンの最適構造化、モジュール型アーキテクチャーの進展等の現代製造業の高度な構造変化のなかでは、中間財の競争評価においては、ユーザーは誰でどこに存在し、評価すべき市場はどのレイヤーなのか、経済実態を的確に捉えた企業結合審査が必要である。
その他、国際的な市場経済のダイナミズムを適切に考慮する競争評価も重要である。すなわち、成長市場と成熟市場では、経営者・投資家の行動に大きな違いがあり、歴史的な市場拡大チャンスが到来しているBRICs等の成長市場では、国際的参入投資が旺盛で覇権争奪の競争が熾烈である。このような成長市場で築かれる競争優位は技術的な新規性も具備し、日本市場含め既存市場へ戦略的に国際展開することも容易である。このような成長市場のダイナミズムに直接関連する財に関わる企業の結合審査においては、単に現在の供給余力がないといった静態的要因に依拠するのではなく、成長市場のダイナミズムがもたらす参入圧力を構造的にとらえて的確に評価すべきである。
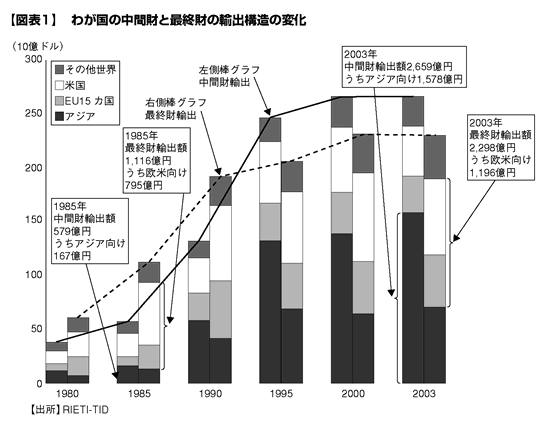
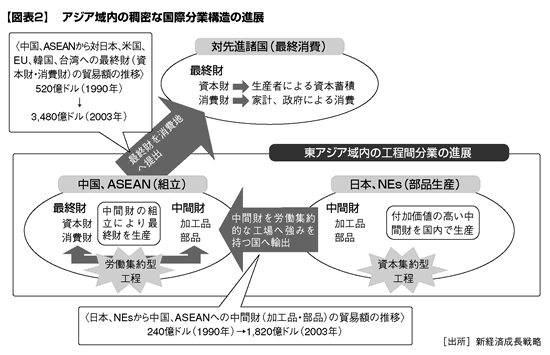
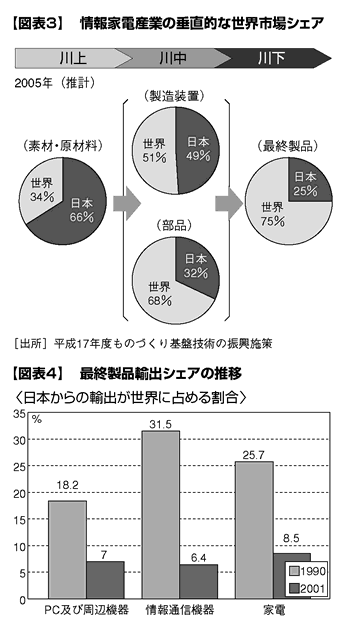
3 需要家からの構造的な競争圧力の適切な評価
企業結合審査ではユーザー調査の結果が重要な判断要因となるが、たとえば前述の国外に大手ユーザーが存在する中間財に係るユーザー調査において、国内に残っている一部の中小組立メーカーの声だけで輸入圧力を評価することは、当該中間財に係る適正な競争圧力の評価になっているとはいえない。このような場合は、国をまたぐ当該中間財市場全体を捉え、潜在的な参入圧力を加味した競争評価がなされることが適切である。
また、IT革命による電子商取引の進展、流通ビジネスモデルの進化による小売セクターからの価格圧力(例:ウォールマート、家電量販店)等を背景に、財の生産サイドに対して販売サイド・消費者サイドからかかる競争圧力は、近年構造的に増大している。このような需要家の市場支配力が構造的に高まっている財については、仮に供給サイドの寡占化が進展したとしても一般消費者の利益を損なう蓋然性は極めて低くなっていることを適切に評価すべきである。この需要家からの競争圧力は、パソコンとその中核的中間財たる半導体の価格低下にみられるように、前述の中間財に対するユーザー圧力の競争評価においても適切に扱われるよう明確な指針が示されることが重要である。(どい・りょうじ)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -























