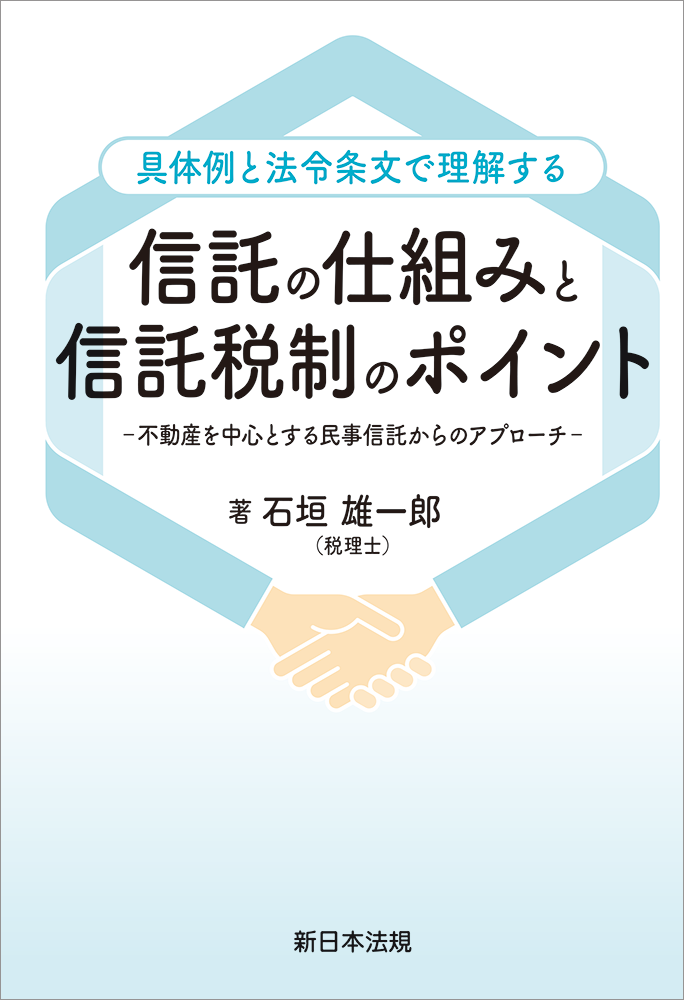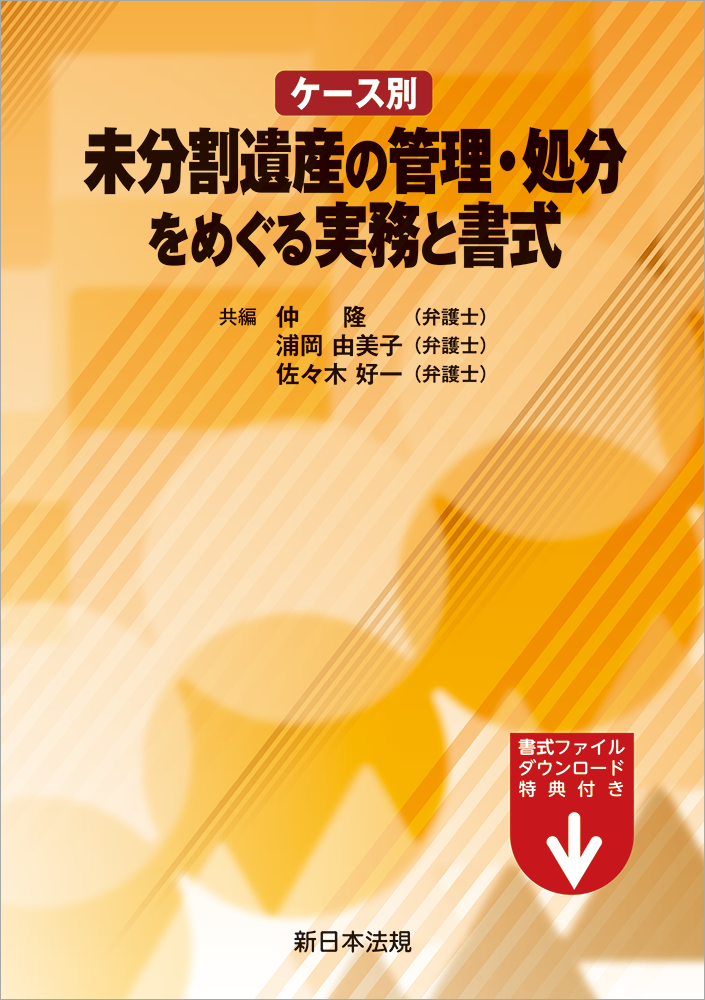解説記事2006年08月14日 【制度解説】 金融商品取引法制における新規制の要点③ 金融商品取引業者等に係る業規制・行為規制(2006年8月14日号・№175)
実務解説
金融商品取引法制における新規制の要点③
金融商品取引業者等に係る業規制・行為規制
金融庁総務企画局市場課金融商品取引法令準備室専門官 酒井敦史
はじめに
金融商品取引法(以下「金商法」という)は、第3章において、いわゆる業者規制として「金融商品取引業者等」(金融商品取引業者と登録金融機関の総称)に関する業規制および行為規制を規定している。これらの業規制および行為規制についても、今回の改正のキーワードである「包括化・横断化」および「柔軟化(柔構造化)」の観点から法整備が行われている(今号4頁参照)。
本稿では、このような「包括化・横断化」「柔軟化(柔構造化)」に即して、金商法の業規制および行為規制について紹介することとする。なお、文中、法律の題名を付さない条文は金商法における規定を示す。また、意見にわたる部分は筆者の個人的見解であるので予めお断りしておく。
Ⅰ 業規制の整備
1. 包括化・横断化の観点からの整備
金商法では、現行の縦割り業法を見直して規制の簡素化を図る(横断化)観点から、また対象商品・取引の拡大(包括化)に併せて、規制対象となる業の業務範囲を拡大している。
このような観点から、業について「金融商品取引業」(2条8項)と定義し、「販売・勧誘」「資産運用・助言」および「資産管理」を本来業務としている。
これにより、現行の証券取引法(以下「証取法」という)および外国証券業者法に基づく証券業、投資信託・投資法人法に基づく投資信託委託業および投資法人資産運用業、証券投資顧問業法に基づく投資顧問業および投資一任業務、金融先物取引法に基づく金融先物取引業、信託業法に基づく信託受益権販売業、抵当証券業規制法に基づく抵当証券業、商品ファンド法に基づく商品投資販売業が、金融商品取引業に統合されている。
統合の結果、たとえば、いわゆるラップ口座のサービスを提供する場合には、現行法では証券業と投資一任業務の兼業となるため、証取法に基づく証券業の登録および投資顧問業との兼業の届出と証券投資顧問業法に基づく投資顧問業の登録、投資一任業務の認可および証券業との兼業の認可といった手続が必要となるが、金商法では「金融商品取引業」の登録のみでこれを行うことが可能となる。
また、発行者自らが新たに発行する有価証券の取得の申込みの勧誘を行う行為(いわゆる自己募集)(2条8項7号)、投資顧問契約または投資一任契約の代理または媒介(同項13号)、集団投資スキーム等を組成して主として有価証券またはデリバティブ取引に係る権利に対して運用を行うこと(いわゆる自己運用)(同項15号)、有価証券取引等に関して顧客から金銭または有価証券の預託を受ける行為(同項16号)、社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと(同項17号)を対象としている。
以上の「金融商品取引業」の定義の内容をまとめたのが図表1である。
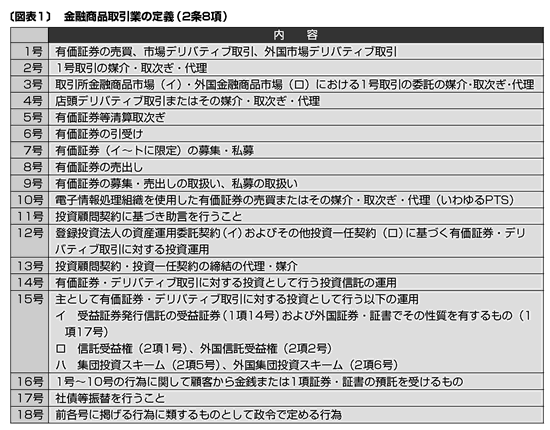
2. 柔軟化(柔構造化)の観点からの整備
(1)金融商品取引業の業規制における柔軟化
金商法における業規制については、金融商品取引業として包括化・横断化しつつ(2条8項)、業務内容の範囲に応じ、業を区分し、各区分に応じた参入規制等を設けることにより、業規制の柔軟化を図っている。
金融商品取引業の具体的な区分は、「第一種金融商品取引業」(28条1項)、「第二種金融商品取引業」(同条2項)、「投資助言・代理業」(同条3項)および「投資運用業」(同条4項)とされている。なお、金融商品取引業とは別に、「金融商品仲介業」(2条11項)、そして「金融商品仲介業者」(同条12項)が定められている。
金融商品取引業は登録制とされ(29条)、上記の区分に応じて登録拒否要件が定められている(29条の4第1項各号)。登録申請時に示される業務の種別(29条の2第1項5号)に相当する登録拒否要件に該当するかどうかが判断されることになる。
上記の区分ごとに登録拒否要件をまとめたのが図表2である。
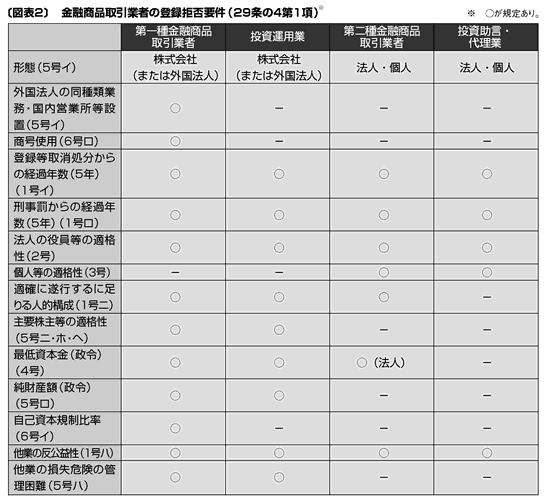
(2)集団投資スキームの業規制における柔軟化
集団投資スキーム(ファンド)の持分の販売・勧誘業(自己募集を含む)は第二種金融商品取引業であり(28条2項1号・2号)、その主として有価証券・デリバティブ取引に対する運用業は投資運用業(同条4項3号)であり、金融商品取引業の登録が必要となる。
一方、健全な活動を行っているファンドを通じた金融イノベーションを促進しつつ、市場の公正性・透明性を確保する観点から、いわゆるプロ向けファンドの販売・勧誘業(自己募集)または運用業については、登録制ではなく、最低限の実態把握を行うために「特例業務届出者」として届出制とし、業規制の柔軟化を図っている(63条2項)。
その具体的な範囲は、「適格機関投資家」(2条3項1号)および適格機関投資家以外の者であって49人(政令事項)以下を投資家とする場合である(63条1項)。
また、特例業務届出者に対する行為規制についても、限定的な規制とされている(63条4項)。
3. 登録金融機関
(1)有価証券関連業
現行の証取法65条におけるいわゆる銀・証分離については、金融機関による証券仲介業務の解禁について提言した金融審議会第一部会報告「市場機能を中核とする金融システムに向けて」(平成15年12月24日)において、「依然として金融システムにおける資金仲介の大宗を担っているのは銀行であり、65条の根拠となった利益相反や銀行の優越的地位の濫用の可能性は、今なお重要な論点である」と指摘されている。金商法においても、銀・証分離の考え方を維持して、同法33条において同じ趣旨の規定を整備している。
具体的には、金融機関について、金融商品取引業のうち現行の証券業に相当するもの(「有価証券関連業」)を行うことを原則として禁止したうえで(33条1項)、そのうち弊害が小さいと考えられる業務については例外的に当該禁止を解除する(同条2項)という現行の証取法65条の枠組みを維持している。
(2)有価証券関連業以外の登録金融機関業務
金商法では、金融商品取引業のうち現行の証券業に相当しないものを金融機関が行う場合には、金融商品取引業の登録に代えて登録金融機関としての登録を求めることとしている(33条3項、33条の2)。
これにより、現行の証取法では規制対象とされていない、金融機関による有価証券関連デリバティブ取引等以外のデリバティブ取引等(たとえば、金融先物取引や金利・通貨スワップ等)、投資助言・代理業および有価証券等管理業務等についても、登録金融機関としての登録が必要となり、金商法の行為規制が適用されることになる。
なお、金商法においてある業務が登録金融機関に認められているとしても、これを行おうとする金融機関を規制する各業法において当該業務が当該金融機関の業務範囲として認められているかどうかは別問題である。
このほか、金融機関による書面取次行為については、金融審議会第一部会「中間整理」(平成17年7月7日)において「金融機関による有価証券の書面取次ぎの特例については、行為規制が適用されないといった問題がある」との指摘がされたことを踏まえ、金商法においては、これについても登録金融機関としての登録を求め、同法の行為規制を適用することとしている。
以上の登録金融機関の業務範囲をまとめたものが図表3である。
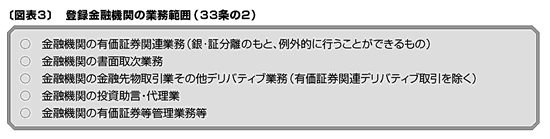
4. 経過措置
(1)みなし登録
現行の証券会社は、施行日において金商法29条の登録を受けたものとみなされる(証取法等改正法附則18条1項)が、施行日から起算して3か月以内に登録申請書記載事項(29条の2第1項各号)を記載した書面および添付書類(同条2項各号)を内閣総理大臣に提出する義務があり(附則18条2項)、内閣総理大臣はこれらの事項を金融商品取引業者登録簿に登録するとされている(同条3項)。
この点は、登録金融機関(附則54条)、投資信託委託業者(附則159条)、信託受益権販売業者(附則200条)、外国証券会社(整備等法2条)、投資顧問業者(整備等法37条)、認可投資顧問業者(整備等法41条)、金融先物取引業者(整備等法60条・61条)、商品投資販売業者(整備等法151条)等についても、同様である。
(2)商号規制
広く一般に定着した「証券会社」という名称に対する利用者の信頼を保護する観点から、金商法の施行後も、有価証券関連業を行う者(現行の証券会社および外国証券会社を含む)のみが「証券会社」という名称を用いることができることとしている(証取法等改正法附則25条2項)。
Ⅱ 行為規制の整備
1. 横断化の観点からの整備
(1)基本的考え方
今回の改正では、利用者保護ルールの徹底を図る観点から、同じ経済的機能を有する金融商品には同じルールを適用することにより、金商法を金融商品の販売・勧誘に関する一般的な性格を有するものと位置付け、既存の利用者保護法制の対象となっている金融商品についても、その行為規制(販売・勧誘ルール)を業態を問わず横断的に適用することとしている。
(2)金商法の行為規制の概要
「金融商品取引業者等」(金融商品取引業者と登録金融機関の総称)に対する具体的な行為規制としては、次のものが定められている。
① すべての業務に関するものとして、顧客に対する誠実公正義務(36条)、標識の掲示(36条の2)、名義貸しの禁止(36条の3)および社債の管理の禁止等(36条の4)
② 販売・勧誘等に関するものとして、広告等の規制(37条)、取引態様の事前明示義務(37条の2)、契約締結前の書面交付義務(37条の3)、契約締結時等の書面交付義務(37条の4)、保証金の受領に係る書面交付義務(37条の5)、書面による解除(クーリング・オフ)(37条の6)、禁止行為(虚偽告知・断定的判断等提供・不招請勧誘・勧誘受諾の意思不確認・再勧誘の禁止等)(38条)、損失補てん等の禁止(39条)、適合性の原則等(40条)、最良執行方針等を記載した書面交付義務(40条の2)および分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止(40条の3)
③ 投資助言・代理業(28条3項)および投資運用業(同条4項)に関するものとして、禁止行為(38条の2)
④ 投資助言業務(28条6項)に関するものとして、顧客に対する忠実義務・善管注意義務(41条)、禁止行為(41条の2)、有価証券の売買等の禁止(41条の3)、金銭・有価証券の預託の受入れ等の禁止(41条の4)および金銭・有価証券の貸付け等の禁止(41条の5)
⑤ 投資運用業に関するものとして、顧客に対する忠実義務・善管注意義務(42条)、禁止行為(42条の2)、運用権限の委託(42条の3)、分別管理(42条の4)、金銭・有価証券の預託の受入れ等の禁止(42条の5)、金銭・有価証券の貸付け等の禁止(42条の6)および運用報告書の交付義務(42条の7)
⑥ 有価証券等管理業務(28条5項)に関するものとして、善管注意義務(43条)、分別管理(43条の2、43条の3)および顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限(43条の4)
⑦ その他として、弊害防止措置等(44条~44条の4)
(3)関係法律における準用等
銀行、保険会社、信託会社等のように金融商品取引業者等にあたらない業者についても、銀行法、保険業法、信託業法等の各業法において、投資性の強い商品を取り扱う場合に金商法の販売・勧誘ルールを準用するなどの所要の整備を行っており、これにより、金商法の販売・勧誘ルールとの同等性を確保している。
銀行法、保険業法、信託業法において準用される販売・勧誘ルールを図表4~図表6にまとめたので参照されたい。
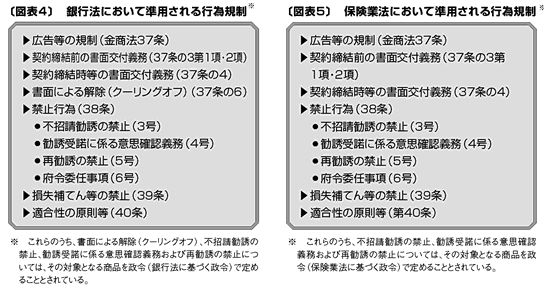
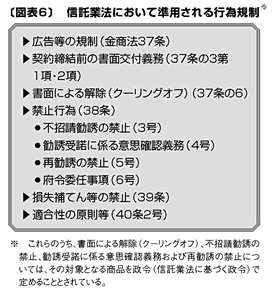
2. 柔軟化(柔構造化)の観点からの整備
(1)基本的考え方
現行の証取法等に基づく行為規制は、投資家の属性にかかわりなく一律に適用されるが、適切な利用者保護とリスク・キャピタルの供給の円滑化を両立させるなどの観点から、投資家を特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)に区分し、金融商品取引業者等が一般投資家との間で取引を行う場合には、投資者保護の観点から十分な行為規制を適用し、特定投資家との間で取引を行う場合には、たとえば契約締結前の書面交付義務等、情報格差の是正を目的とする行為規制の適用を除外する一方、損失補てんの禁止等、市場の公正確保をも目的とする行為規制は適用除外しないこととしている(34条~34条の5、45条)。
(2)特定投資家と一般投資家の区分
「特定投資家」の範囲は、適格機関投資家、国、日本銀行、投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人とされている(2条31項)。
このうち内閣府令で定める法人は、その申出により「特定投資家以外の顧客」(一般投資家)として取り扱われることができる(34条の2)。
一方、一般投資家についても、法人の場合は、同様に申出により特定投資家として取り扱われることができる(34条の3)。
個人は基本的にすべて一般投資家としつつ(2条31項参照)、知識・経験・財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人等について、その申出により、厳格な手続を経て特定投資家として取り扱われることができる(34条の4)。
以上の特定投資家と一般投資家の区分を図示したのが図表7である。
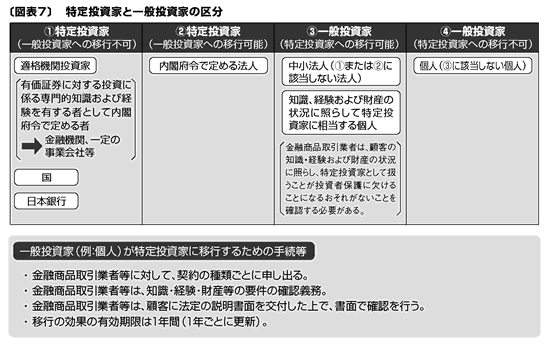
なお、銀行法、保険業法、信託業法等の各業法においては、規制の横断化を図る観点から金商法の行為規制を準用するのと併せて、規制の柔軟化を図る観点から特定投資家制度も準用している。(さかい・あつし)
金融商品取引法制における新規制の要点③
金融商品取引業者等に係る業規制・行為規制
金融庁総務企画局市場課金融商品取引法令準備室専門官 酒井敦史
はじめに
金融商品取引法(以下「金商法」という)は、第3章において、いわゆる業者規制として「金融商品取引業者等」(金融商品取引業者と登録金融機関の総称)に関する業規制および行為規制を規定している。これらの業規制および行為規制についても、今回の改正のキーワードである「包括化・横断化」および「柔軟化(柔構造化)」の観点から法整備が行われている(今号4頁参照)。
本稿では、このような「包括化・横断化」「柔軟化(柔構造化)」に即して、金商法の業規制および行為規制について紹介することとする。なお、文中、法律の題名を付さない条文は金商法における規定を示す。また、意見にわたる部分は筆者の個人的見解であるので予めお断りしておく。
Ⅰ 業規制の整備
1. 包括化・横断化の観点からの整備
金商法では、現行の縦割り業法を見直して規制の簡素化を図る(横断化)観点から、また対象商品・取引の拡大(包括化)に併せて、規制対象となる業の業務範囲を拡大している。
このような観点から、業について「金融商品取引業」(2条8項)と定義し、「販売・勧誘」「資産運用・助言」および「資産管理」を本来業務としている。
これにより、現行の証券取引法(以下「証取法」という)および外国証券業者法に基づく証券業、投資信託・投資法人法に基づく投資信託委託業および投資法人資産運用業、証券投資顧問業法に基づく投資顧問業および投資一任業務、金融先物取引法に基づく金融先物取引業、信託業法に基づく信託受益権販売業、抵当証券業規制法に基づく抵当証券業、商品ファンド法に基づく商品投資販売業が、金融商品取引業に統合されている。
統合の結果、たとえば、いわゆるラップ口座のサービスを提供する場合には、現行法では証券業と投資一任業務の兼業となるため、証取法に基づく証券業の登録および投資顧問業との兼業の届出と証券投資顧問業法に基づく投資顧問業の登録、投資一任業務の認可および証券業との兼業の認可といった手続が必要となるが、金商法では「金融商品取引業」の登録のみでこれを行うことが可能となる。
また、発行者自らが新たに発行する有価証券の取得の申込みの勧誘を行う行為(いわゆる自己募集)(2条8項7号)、投資顧問契約または投資一任契約の代理または媒介(同項13号)、集団投資スキーム等を組成して主として有価証券またはデリバティブ取引に係る権利に対して運用を行うこと(いわゆる自己運用)(同項15号)、有価証券取引等に関して顧客から金銭または有価証券の預託を受ける行為(同項16号)、社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと(同項17号)を対象としている。
以上の「金融商品取引業」の定義の内容をまとめたのが図表1である。
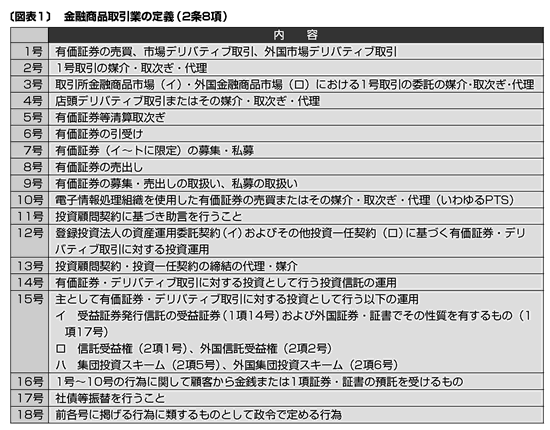
2. 柔軟化(柔構造化)の観点からの整備
(1)金融商品取引業の業規制における柔軟化
金商法における業規制については、金融商品取引業として包括化・横断化しつつ(2条8項)、業務内容の範囲に応じ、業を区分し、各区分に応じた参入規制等を設けることにより、業規制の柔軟化を図っている。
金融商品取引業の具体的な区分は、「第一種金融商品取引業」(28条1項)、「第二種金融商品取引業」(同条2項)、「投資助言・代理業」(同条3項)および「投資運用業」(同条4項)とされている。なお、金融商品取引業とは別に、「金融商品仲介業」(2条11項)、そして「金融商品仲介業者」(同条12項)が定められている。
金融商品取引業は登録制とされ(29条)、上記の区分に応じて登録拒否要件が定められている(29条の4第1項各号)。登録申請時に示される業務の種別(29条の2第1項5号)に相当する登録拒否要件に該当するかどうかが判断されることになる。
上記の区分ごとに登録拒否要件をまとめたのが図表2である。
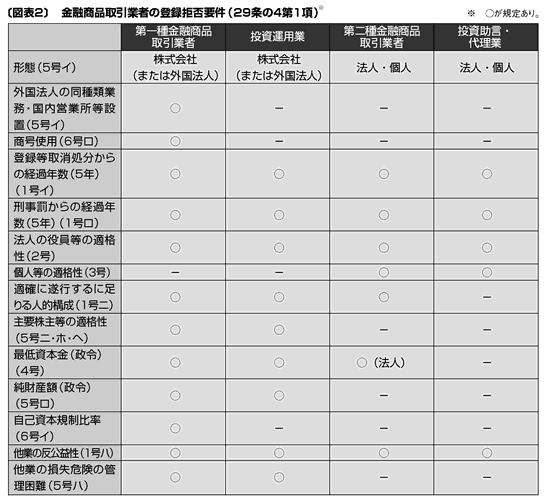
(2)集団投資スキームの業規制における柔軟化
集団投資スキーム(ファンド)の持分の販売・勧誘業(自己募集を含む)は第二種金融商品取引業であり(28条2項1号・2号)、その主として有価証券・デリバティブ取引に対する運用業は投資運用業(同条4項3号)であり、金融商品取引業の登録が必要となる。
一方、健全な活動を行っているファンドを通じた金融イノベーションを促進しつつ、市場の公正性・透明性を確保する観点から、いわゆるプロ向けファンドの販売・勧誘業(自己募集)または運用業については、登録制ではなく、最低限の実態把握を行うために「特例業務届出者」として届出制とし、業規制の柔軟化を図っている(63条2項)。
その具体的な範囲は、「適格機関投資家」(2条3項1号)および適格機関投資家以外の者であって49人(政令事項)以下を投資家とする場合である(63条1項)。
また、特例業務届出者に対する行為規制についても、限定的な規制とされている(63条4項)。
3. 登録金融機関
(1)有価証券関連業
現行の証取法65条におけるいわゆる銀・証分離については、金融機関による証券仲介業務の解禁について提言した金融審議会第一部会報告「市場機能を中核とする金融システムに向けて」(平成15年12月24日)において、「依然として金融システムにおける資金仲介の大宗を担っているのは銀行であり、65条の根拠となった利益相反や銀行の優越的地位の濫用の可能性は、今なお重要な論点である」と指摘されている。金商法においても、銀・証分離の考え方を維持して、同法33条において同じ趣旨の規定を整備している。
具体的には、金融機関について、金融商品取引業のうち現行の証券業に相当するもの(「有価証券関連業」)を行うことを原則として禁止したうえで(33条1項)、そのうち弊害が小さいと考えられる業務については例外的に当該禁止を解除する(同条2項)という現行の証取法65条の枠組みを維持している。
(2)有価証券関連業以外の登録金融機関業務
金商法では、金融商品取引業のうち現行の証券業に相当しないものを金融機関が行う場合には、金融商品取引業の登録に代えて登録金融機関としての登録を求めることとしている(33条3項、33条の2)。
これにより、現行の証取法では規制対象とされていない、金融機関による有価証券関連デリバティブ取引等以外のデリバティブ取引等(たとえば、金融先物取引や金利・通貨スワップ等)、投資助言・代理業および有価証券等管理業務等についても、登録金融機関としての登録が必要となり、金商法の行為規制が適用されることになる。
なお、金商法においてある業務が登録金融機関に認められているとしても、これを行おうとする金融機関を規制する各業法において当該業務が当該金融機関の業務範囲として認められているかどうかは別問題である。
このほか、金融機関による書面取次行為については、金融審議会第一部会「中間整理」(平成17年7月7日)において「金融機関による有価証券の書面取次ぎの特例については、行為規制が適用されないといった問題がある」との指摘がされたことを踏まえ、金商法においては、これについても登録金融機関としての登録を求め、同法の行為規制を適用することとしている。
以上の登録金融機関の業務範囲をまとめたものが図表3である。
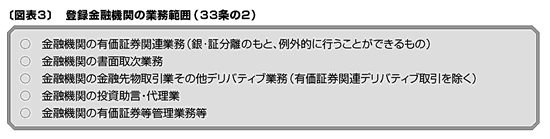
4. 経過措置
(1)みなし登録
現行の証券会社は、施行日において金商法29条の登録を受けたものとみなされる(証取法等改正法附則18条1項)が、施行日から起算して3か月以内に登録申請書記載事項(29条の2第1項各号)を記載した書面および添付書類(同条2項各号)を内閣総理大臣に提出する義務があり(附則18条2項)、内閣総理大臣はこれらの事項を金融商品取引業者登録簿に登録するとされている(同条3項)。
この点は、登録金融機関(附則54条)、投資信託委託業者(附則159条)、信託受益権販売業者(附則200条)、外国証券会社(整備等法2条)、投資顧問業者(整備等法37条)、認可投資顧問業者(整備等法41条)、金融先物取引業者(整備等法60条・61条)、商品投資販売業者(整備等法151条)等についても、同様である。
(2)商号規制
広く一般に定着した「証券会社」という名称に対する利用者の信頼を保護する観点から、金商法の施行後も、有価証券関連業を行う者(現行の証券会社および外国証券会社を含む)のみが「証券会社」という名称を用いることができることとしている(証取法等改正法附則25条2項)。
Ⅱ 行為規制の整備
1. 横断化の観点からの整備
(1)基本的考え方
今回の改正では、利用者保護ルールの徹底を図る観点から、同じ経済的機能を有する金融商品には同じルールを適用することにより、金商法を金融商品の販売・勧誘に関する一般的な性格を有するものと位置付け、既存の利用者保護法制の対象となっている金融商品についても、その行為規制(販売・勧誘ルール)を業態を問わず横断的に適用することとしている。
(2)金商法の行為規制の概要
「金融商品取引業者等」(金融商品取引業者と登録金融機関の総称)に対する具体的な行為規制としては、次のものが定められている。
① すべての業務に関するものとして、顧客に対する誠実公正義務(36条)、標識の掲示(36条の2)、名義貸しの禁止(36条の3)および社債の管理の禁止等(36条の4)
② 販売・勧誘等に関するものとして、広告等の規制(37条)、取引態様の事前明示義務(37条の2)、契約締結前の書面交付義務(37条の3)、契約締結時等の書面交付義務(37条の4)、保証金の受領に係る書面交付義務(37条の5)、書面による解除(クーリング・オフ)(37条の6)、禁止行為(虚偽告知・断定的判断等提供・不招請勧誘・勧誘受諾の意思不確認・再勧誘の禁止等)(38条)、損失補てん等の禁止(39条)、適合性の原則等(40条)、最良執行方針等を記載した書面交付義務(40条の2)および分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止(40条の3)
③ 投資助言・代理業(28条3項)および投資運用業(同条4項)に関するものとして、禁止行為(38条の2)
④ 投資助言業務(28条6項)に関するものとして、顧客に対する忠実義務・善管注意義務(41条)、禁止行為(41条の2)、有価証券の売買等の禁止(41条の3)、金銭・有価証券の預託の受入れ等の禁止(41条の4)および金銭・有価証券の貸付け等の禁止(41条の5)
⑤ 投資運用業に関するものとして、顧客に対する忠実義務・善管注意義務(42条)、禁止行為(42条の2)、運用権限の委託(42条の3)、分別管理(42条の4)、金銭・有価証券の預託の受入れ等の禁止(42条の5)、金銭・有価証券の貸付け等の禁止(42条の6)および運用報告書の交付義務(42条の7)
⑥ 有価証券等管理業務(28条5項)に関するものとして、善管注意義務(43条)、分別管理(43条の2、43条の3)および顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限(43条の4)
⑦ その他として、弊害防止措置等(44条~44条の4)
(3)関係法律における準用等
銀行、保険会社、信託会社等のように金融商品取引業者等にあたらない業者についても、銀行法、保険業法、信託業法等の各業法において、投資性の強い商品を取り扱う場合に金商法の販売・勧誘ルールを準用するなどの所要の整備を行っており、これにより、金商法の販売・勧誘ルールとの同等性を確保している。
銀行法、保険業法、信託業法において準用される販売・勧誘ルールを図表4~図表6にまとめたので参照されたい。
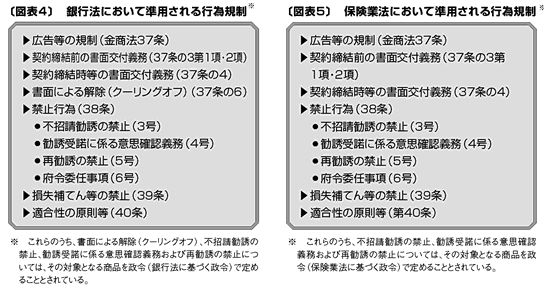
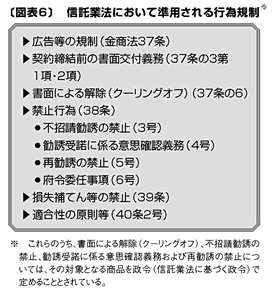
2. 柔軟化(柔構造化)の観点からの整備
(1)基本的考え方
現行の証取法等に基づく行為規制は、投資家の属性にかかわりなく一律に適用されるが、適切な利用者保護とリスク・キャピタルの供給の円滑化を両立させるなどの観点から、投資家を特定投資家(プロ)と一般投資家(アマ)に区分し、金融商品取引業者等が一般投資家との間で取引を行う場合には、投資者保護の観点から十分な行為規制を適用し、特定投資家との間で取引を行う場合には、たとえば契約締結前の書面交付義務等、情報格差の是正を目的とする行為規制の適用を除外する一方、損失補てんの禁止等、市場の公正確保をも目的とする行為規制は適用除外しないこととしている(34条~34条の5、45条)。
(2)特定投資家と一般投資家の区分
「特定投資家」の範囲は、適格機関投資家、国、日本銀行、投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人とされている(2条31項)。
このうち内閣府令で定める法人は、その申出により「特定投資家以外の顧客」(一般投資家)として取り扱われることができる(34条の2)。
一方、一般投資家についても、法人の場合は、同様に申出により特定投資家として取り扱われることができる(34条の3)。
個人は基本的にすべて一般投資家としつつ(2条31項参照)、知識・経験・財産の状況に照らして特定投資家に相当する者として内閣府令で定める要件に該当する個人等について、その申出により、厳格な手続を経て特定投資家として取り扱われることができる(34条の4)。
以上の特定投資家と一般投資家の区分を図示したのが図表7である。
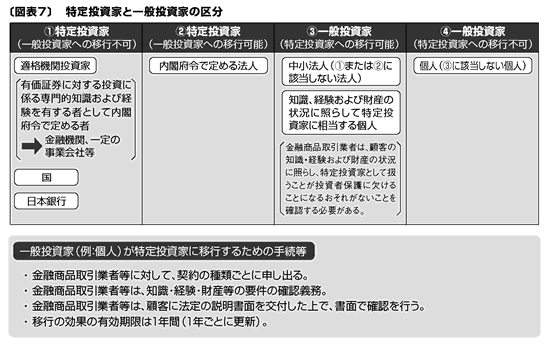
なお、銀行法、保険業法、信託業法等の各業法においては、規制の横断化を図る観点から金商法の行為規制を準用するのと併せて、規制の柔軟化を図る観点から特定投資家制度も準用している。(さかい・あつし)
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -