解説記事2006年09月04日 【実務解説】 会社法・会計基準と法人税法 第2回 自己株式を消却した場合の取扱い(2006年9月4日号・№177)
実務解説
会社法・会計基準と法人税法
第2回 自己株式を消却した場合の取扱い
T&Amaster編集部 佐治俊夫
平成18年5月1日の会社法・会社計算規則の施行により、会社の計算に関する事項が一新されています。新しい会社法・会計基準・法人税法に基づいて、変更点となる会計実務の取扱い・法人税申告実務の取扱いについて、解説します。
第2回では、第1回に引き続き、発行会社が自己株式を取得した場合の取扱いについて検討した上で、その取得した自己株式を消却した場合について検討を進めます。
Ⅰ 自己株式を取得した場合(承前)
2 上場株式を市場で取得した場合の取扱い
(1)原則的な取扱いと例外処理
第1回では、発行会社(非公開会社)が自己株式を相対取引で取得した場合の取扱いを検討しました。会計では、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除することになりますが、法人税法では、取得資本金額部分について資本金等の額から減算し、交付金銭等の額が取得資本金額を超える部分(=みなし配当とされる部分)について利益積立金額を減算します(法人税法施行令8条1項20号)。
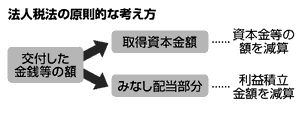
しかし、上場会社等が証券取引所の開設する市場等において自己株式を購入する場合など、みなし配当が生じないとされる自己株式の取得については、対価相当額又は時価相当額の資本金等の額を減算することになります(法人税法施行令8条1項21号)。
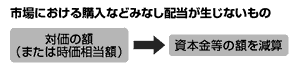
(2)設例と法人税別表への記載
B株式会社(上場会社)が証券市場において自己株式を取得しました。
取引対価は170,000円、購入時に支払った手数料は5,000円とします。
① 会計上の取扱い
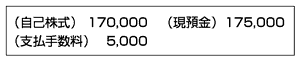
② 法人税法上の取扱い
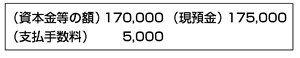
この結果、自己株式を市場で取得したB株式会社の資本金等の額の計算に関する明細書(別表五(一)の下部)の記載は上表のようになります。
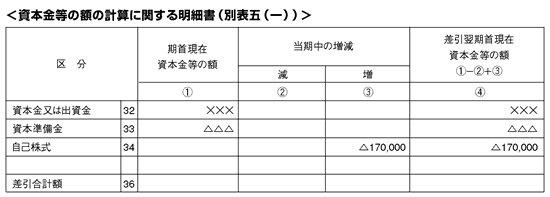
3 施行日に存する法人が自己株式を有している場合
(1)経過措置で帳簿価額を減算
また、平成18年4月1日に存する法人の資本金等の額は、平成18年3月31日の資本積立金額から同日において有する自己株式の(税務上の)帳簿価額を減算した金額になります(改正法人税法施行令附則4条1項)。平成18年4月1日に存する法人の利益積立金額は、平成18年3月31日の利益積立金額になります(改正法人税法施行令附則6条1項)。
(2)設例と法人税別表への記載
A株式会社(非公開会社)は、平成18年3月期以前に自己株式を対価170,000円で取得していました(そのうち取得資本金額は、120,000円)。
A株式会社の平成18年3月期の資本積立金額の明細上、自己株式に係る記載はありませんが、改正法人税法の施行日(平成18年4月1日)を含む事業年度の資本金等の額の計算に関する明細書では、「期首現在資本金等の額①」で、自己株式の施行日の(税務上の)帳簿価額(=120,000円)を減算することになります。
A株式会社の平成19年3月期の資本金等の額の計算に関する明細書(別表五(一)の下部)の記載は下表のようになります。
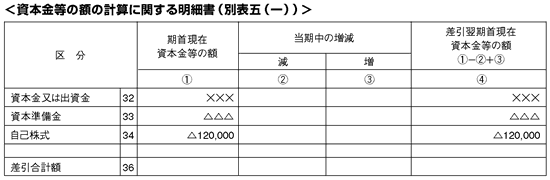
4 種類株式の発行法人が自己株式の取得を行った場合
(1)何が変わったのか
会社法では、①剰余金の配当についての種類株式、②残余財産の分配についての種類株式、③株主総会における議決権についての種類株式、④譲渡制限株式、⑤取得請求権付株式、⑥取得条項付株式、⑦全部取得条項付種類株式、⑧拒否権付株式というような異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができると規定し、種類株式の取扱いを整備しました。
株主資本等変動計算書においても、種類ごとの発行済株式の数などの注記(個別)が求められています(会社計算規則136条1号・2号)。
法人税法においても資本金等の額についてそれぞれの種類株式に係る種類資本金額を区分して管理することを求め、法人税申告書別表五(一)付表「種類資本金額の計算に関する明細書」が設けられています。
(2)法人税申告実務での取扱い
法人税法はこれまで種類ごとの株式を区分することなく、発行済株式の数で除して、1株当たりの資本等の金額および利益積立金額(みなし配当金額)を計算してきましたが、平成18年度税制改正により、種類株式ごとに区分された資本金等の額の計算を行うことになります。
(3)設例と法人税別表への記載
C株式会社はA種類株式40株、B種類株式10株を発行しています。
A種類株式の種類資本金額は、200,000円、B種類株式の種類資本金額は30,000円であり、C株式会社の利益積立金額は、100,000円です。
C株式会社は株主からA種類株式(自己株式)10株を対価70,000円で取得しました。
①会計上の取扱い
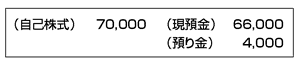
②法人税法上の取扱い
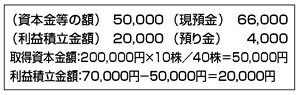
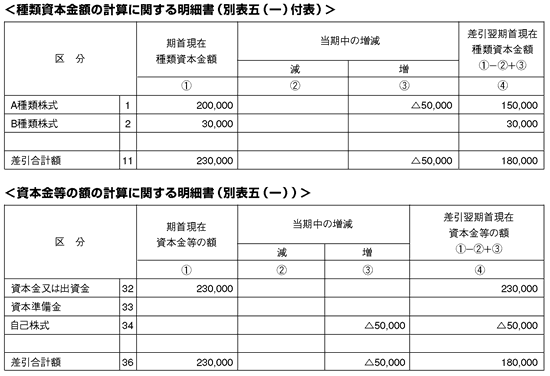
この結果、A種類株式を取得したC株式会社の法人税別表の記載は前頁のようになります。
Ⅱ 自己株式を消却した場合
1 自己株式を消却したA株式会社での取扱い
会社法では、株式の消却の概念を整理して、保有する自己株式の消却だけを認めることになりました(会社法178条)。また、会計処理については、自己株式を消却した場合の減額する資本項目の内訳(資本剰余金・利益剰余金)については、会社の意思決定に委ねられていましたが、会社計算規則が優先的に「その他資本剰余金」から減額することを規定したことを踏まえ、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」においても、これに合わせることにしました。
法人税法においては、自己株式の取得時において資本(資本金等の額・利益積立金額)の控除として取り扱うことになったため、保有する自己株式を消却した場合には、資本金等の額・利益積立金額に特段の調整を要しない(法人税法上の取引として認識しない)ことになりますが、会計上の処理に対応する調整を要することになります。
(1)何が変わったのか
① 旧商法においては、①保有する自己株式を消却する場合(旧商法212条1項)、②株主が有する株式を消却する場合(旧商法213条1項)などで株式の消却を規定していましたが、会社法においては、自己株式の取得および自己株式の消却という手続だけに統一して整備しています。
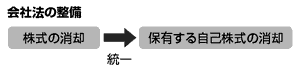
② 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」では、「自己株式を消却した場合、減額するその他資本剰余金またはその他利益剰余金(繰越利益剰余金)については、取締役会等の会社の意思決定機関で定められた結果に従い、消却手続きが完了したときに会計処理する(旧第12項)。」とされていましたが、会社計算規則47条3項において優先的にその他資本剰余金から控除することが規定されたことを踏まえ、次のように改正しました。
「11.自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額する。」
「12.第10項及び第11項の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。」
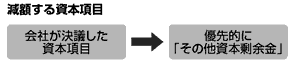
③ 法人税法上の資本の部を整備したことおよび法人税法が自己株式の取得を資本の控除として扱うことにしたことから、取得した自己株式の消却の際に当該帳簿価額を資本積立金額(減資した金額を減算)から減算する規定(旧法人税法2条17号ナ)は削除されています。
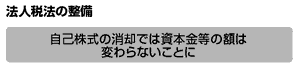
(2)会計実務での取扱い
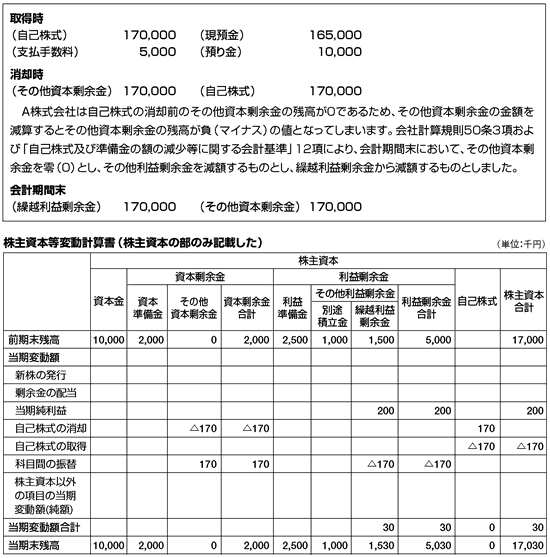
第1回の自己株式を取得した場合の事例を基に、取得した自己株式を直ちに消却した場合の会計上の仕訳および株主資本等変動計算書の記載は上記のようになります。
(3)法人税申告実務での取扱い
自己株式の取得・消却については、法人税法上、取得の際に以下の仕訳を行うだけで、消却については税務上の仕訳は生じないことになります。
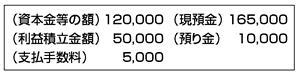
自己株式の消却に伴い、会計上(その他)資本剰余金と利益剰余金(繰越利益剰余金)の振替が行われていますが、税務上の資本金等の金額と利益積立金額は増減は生じないことになります。そのための法人税別表上(資本金等の額と利益積立金額との間での)調整を行うことになります。
この結果、自己株式を取得・消却したA株式会社の法人税別表の記載は次頁のようになります。
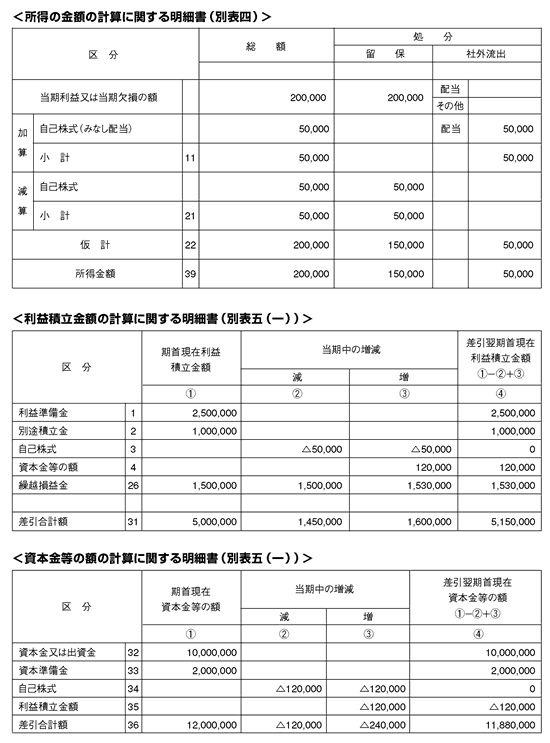
会社法・会計基準と法人税法
第2回 自己株式を消却した場合の取扱い
T&Amaster編集部 佐治俊夫
平成18年5月1日の会社法・会社計算規則の施行により、会社の計算に関する事項が一新されています。新しい会社法・会計基準・法人税法に基づいて、変更点となる会計実務の取扱い・法人税申告実務の取扱いについて、解説します。
第2回では、第1回に引き続き、発行会社が自己株式を取得した場合の取扱いについて検討した上で、その取得した自己株式を消却した場合について検討を進めます。
Ⅰ 自己株式を取得した場合(承前)
2 上場株式を市場で取得した場合の取扱い
(1)原則的な取扱いと例外処理
第1回では、発行会社(非公開会社)が自己株式を相対取引で取得した場合の取扱いを検討しました。会計では、取得原価をもって純資産の部の株主資本から控除することになりますが、法人税法では、取得資本金額部分について資本金等の額から減算し、交付金銭等の額が取得資本金額を超える部分(=みなし配当とされる部分)について利益積立金額を減算します(法人税法施行令8条1項20号)。
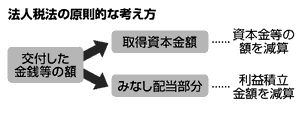
しかし、上場会社等が証券取引所の開設する市場等において自己株式を購入する場合など、みなし配当が生じないとされる自己株式の取得については、対価相当額又は時価相当額の資本金等の額を減算することになります(法人税法施行令8条1項21号)。
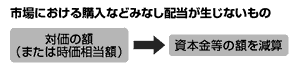
(2)設例と法人税別表への記載
B株式会社(上場会社)が証券市場において自己株式を取得しました。
取引対価は170,000円、購入時に支払った手数料は5,000円とします。
① 会計上の取扱い
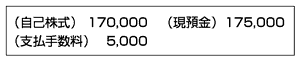
② 法人税法上の取扱い
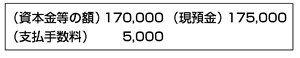
この結果、自己株式を市場で取得したB株式会社の資本金等の額の計算に関する明細書(別表五(一)の下部)の記載は上表のようになります。
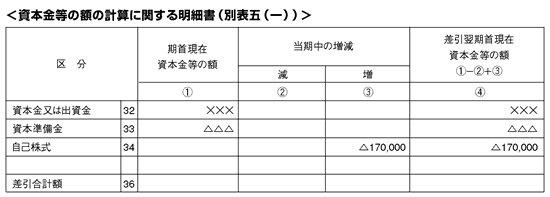
3 施行日に存する法人が自己株式を有している場合
(1)経過措置で帳簿価額を減算
また、平成18年4月1日に存する法人の資本金等の額は、平成18年3月31日の資本積立金額から同日において有する自己株式の(税務上の)帳簿価額を減算した金額になります(改正法人税法施行令附則4条1項)。平成18年4月1日に存する法人の利益積立金額は、平成18年3月31日の利益積立金額になります(改正法人税法施行令附則6条1項)。
(2)設例と法人税別表への記載
A株式会社(非公開会社)は、平成18年3月期以前に自己株式を対価170,000円で取得していました(そのうち取得資本金額は、120,000円)。
A株式会社の平成18年3月期の資本積立金額の明細上、自己株式に係る記載はありませんが、改正法人税法の施行日(平成18年4月1日)を含む事業年度の資本金等の額の計算に関する明細書では、「期首現在資本金等の額①」で、自己株式の施行日の(税務上の)帳簿価額(=120,000円)を減算することになります。
A株式会社の平成19年3月期の資本金等の額の計算に関する明細書(別表五(一)の下部)の記載は下表のようになります。
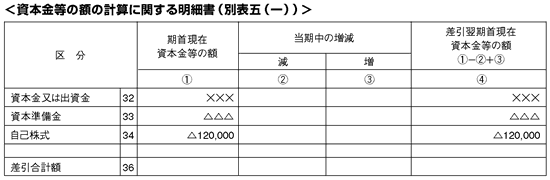
4 種類株式の発行法人が自己株式の取得を行った場合
(1)何が変わったのか
会社法では、①剰余金の配当についての種類株式、②残余財産の分配についての種類株式、③株主総会における議決権についての種類株式、④譲渡制限株式、⑤取得請求権付株式、⑥取得条項付株式、⑦全部取得条項付種類株式、⑧拒否権付株式というような異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができると規定し、種類株式の取扱いを整備しました。
株主資本等変動計算書においても、種類ごとの発行済株式の数などの注記(個別)が求められています(会社計算規則136条1号・2号)。
法人税法においても資本金等の額についてそれぞれの種類株式に係る種類資本金額を区分して管理することを求め、法人税申告書別表五(一)付表「種類資本金額の計算に関する明細書」が設けられています。
(2)法人税申告実務での取扱い
法人税法はこれまで種類ごとの株式を区分することなく、発行済株式の数で除して、1株当たりの資本等の金額および利益積立金額(みなし配当金額)を計算してきましたが、平成18年度税制改正により、種類株式ごとに区分された資本金等の額の計算を行うことになります。
(3)設例と法人税別表への記載
C株式会社はA種類株式40株、B種類株式10株を発行しています。
A種類株式の種類資本金額は、200,000円、B種類株式の種類資本金額は30,000円であり、C株式会社の利益積立金額は、100,000円です。
C株式会社は株主からA種類株式(自己株式)10株を対価70,000円で取得しました。
①会計上の取扱い
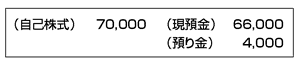
②法人税法上の取扱い
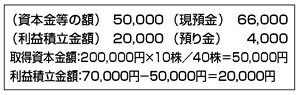
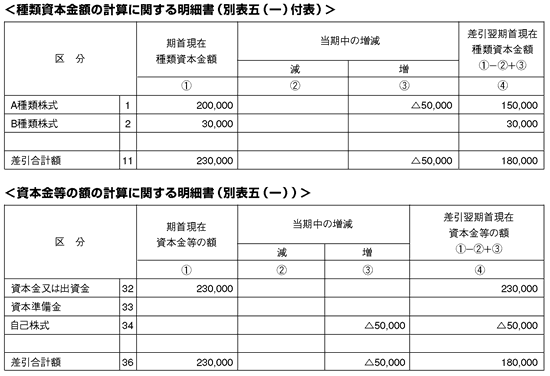
この結果、A種類株式を取得したC株式会社の法人税別表の記載は前頁のようになります。
Ⅱ 自己株式を消却した場合
1 自己株式を消却したA株式会社での取扱い
会社法では、株式の消却の概念を整理して、保有する自己株式の消却だけを認めることになりました(会社法178条)。また、会計処理については、自己株式を消却した場合の減額する資本項目の内訳(資本剰余金・利益剰余金)については、会社の意思決定に委ねられていましたが、会社計算規則が優先的に「その他資本剰余金」から減額することを規定したことを踏まえ、「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」においても、これに合わせることにしました。
法人税法においては、自己株式の取得時において資本(資本金等の額・利益積立金額)の控除として取り扱うことになったため、保有する自己株式を消却した場合には、資本金等の額・利益積立金額に特段の調整を要しない(法人税法上の取引として認識しない)ことになりますが、会計上の処理に対応する調整を要することになります。
(1)何が変わったのか
① 旧商法においては、①保有する自己株式を消却する場合(旧商法212条1項)、②株主が有する株式を消却する場合(旧商法213条1項)などで株式の消却を規定していましたが、会社法においては、自己株式の取得および自己株式の消却という手続だけに統一して整備しています。
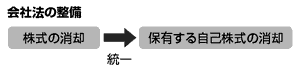
② 「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」では、「自己株式を消却した場合、減額するその他資本剰余金またはその他利益剰余金(繰越利益剰余金)については、取締役会等の会社の意思決定機関で定められた結果に従い、消却手続きが完了したときに会計処理する(旧第12項)。」とされていましたが、会社計算規則47条3項において優先的にその他資本剰余金から控除することが規定されたことを踏まえ、次のように改正しました。
「11.自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金から減額する。」
「12.第10項及び第11項の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、会計期間末において、その他資本剰余金を零とし、当該負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。」
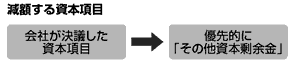
③ 法人税法上の資本の部を整備したことおよび法人税法が自己株式の取得を資本の控除として扱うことにしたことから、取得した自己株式の消却の際に当該帳簿価額を資本積立金額(減資した金額を減算)から減算する規定(旧法人税法2条17号ナ)は削除されています。
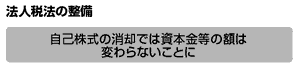
(2)会計実務での取扱い
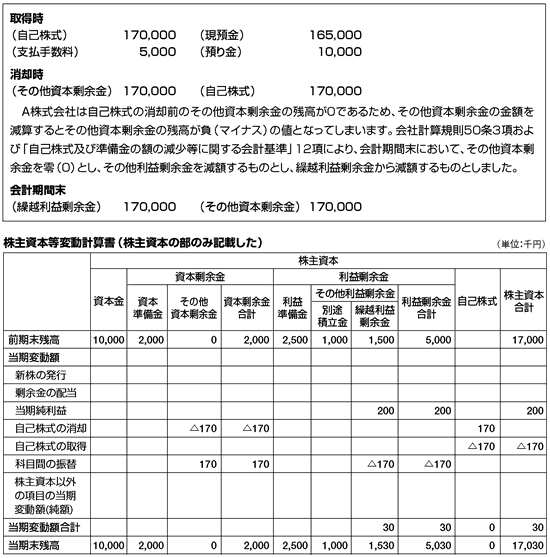
第1回の自己株式を取得した場合の事例を基に、取得した自己株式を直ちに消却した場合の会計上の仕訳および株主資本等変動計算書の記載は上記のようになります。
(3)法人税申告実務での取扱い
自己株式の取得・消却については、法人税法上、取得の際に以下の仕訳を行うだけで、消却については税務上の仕訳は生じないことになります。
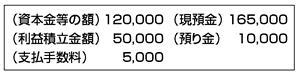
自己株式の消却に伴い、会計上(その他)資本剰余金と利益剰余金(繰越利益剰余金)の振替が行われていますが、税務上の資本金等の金額と利益積立金額は増減は生じないことになります。そのための法人税別表上(資本金等の額と利益積立金額との間での)調整を行うことになります。
この結果、自己株式を取得・消却したA株式会社の法人税別表の記載は次頁のようになります。
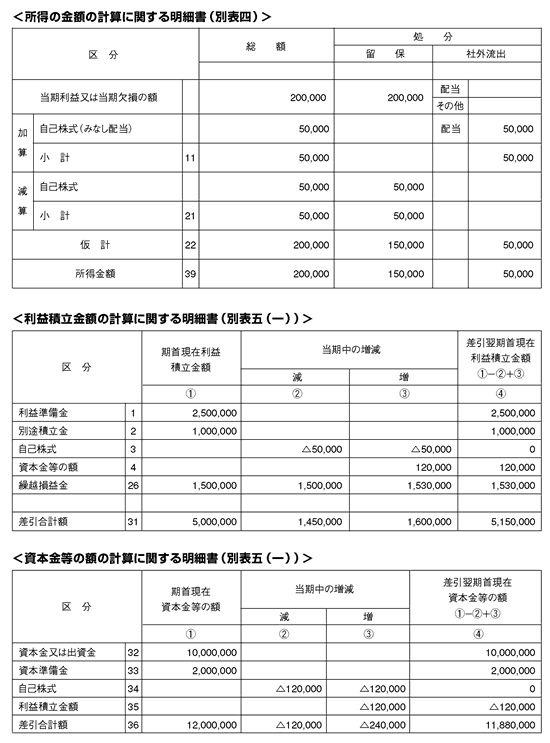
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















