解説記事2006年11月27日 【編集部解説】 ISS、買収防衛策の導入急増を警戒(2006年11月27日号・№188)
解説
ISS、買収防衛策の導入急増を警戒
投資ファンドや外国人じわり、「持合い」浮上の兆しも
text 編集部
日本企業の間で秋以降、敵対的買収防衛策の導入が再び活発化している。王子製紙が今夏、北越製紙に買収提案したことが契機となっているようだ。武富士やキッコーマンなど有力企業が10月下旬買収防衛策を相次ぎ導入した。内外の買付者から企業経営を守る買収防衛策を導入する機運が高まっているとともに、投資ファンドや外国人投資家の持株比率がじわりと高まりつつあるのが背景にある。また、キリンビールとメルシャンのように、株式持合いを前提とした業務提携など買収防衛の側面の強い業界再編も加速しそうだ。議決権行使会社最大手のインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)は安易な買収防衛策の導入が増加することを警戒しており、来年の株主総会で日本企業の議決権行使に影響を与えそうだ。
取締役が持株過半を保有も導入
ISSは、今夏の王子製紙の北越製紙への買収提案以降、日本企業の間で買収防衛策の導入が広がるとみている。日本企業には北越製紙以外にも時価総額に比べて純資産が多く、買収対象となりうる企業があるためだ。ISSジャパンのマーク・ゴールドスタイン代表は、時価総額を純資産で割った株価純資産倍率が1倍を切る企業が1割程度あるという。
兆候はすでに出始めている。コンタクトレンズ小売の日本オプティカルは9月末、新株の無償割当てを利用した買収防衛策を導入した。同社は急遽、臨時株主総会を開催し、株主に導入の賛否を求めた。日本株運用で海外投資家から評価の高い独立系運用会社のスパークス・アセット・マネジメントが同社株の約13%を握っていたことも導入の背景にありそうだ。
ISSは、日本オプティカルの議案について、顧客の機関投資家に反対を助言したことを明らかにした。反対の理由はこうだ。同社は取締役に社外取締役が1人もいないことや情報開示が不十分であることに加え、取締役全員で議決権の53%以上を保有していた。ゴールドスタイン氏は「今後、投資家に株式を売り出すのならまだ分かるが……」と困惑していた。
内外投資ファンド、日本株に触手
内外投資ファンドの日本株の持株比率が高まっている。しょうゆ最大手のキッコーマンは10月26日、即日発効の新株の無償割当てを利用する買収防衛策を導入した。
背景には、明星食品に公開買付けを実施した米系投資ファンド「スティールパートナーズジャパンストラテジックファンド(オフショア)エルピー」などの大量保有が関係している。
創業者保有企業に投資ファンドや外国人
従来、創業者一族で持合いを続けていた企業にも買収防衛策の導入が広がりつつある。消費者金融大手の武富士は10月25日、即日発効の新株の無償割当てを実施する買収防衛策を導入した。創業者の武井保雄氏一族の持株比率は約25%で年々分散が進む一方、外国人持株比率は約57%に達する(9月末時点)。
ネット広告代理事業大手のサイバーエージェントでは、12月20日に開催予定の株主総会で、株主の賛同を得たうえで買収防衛策を導入する見通しだ。藤田晋社長以外の大株主にモルガンスタンレーなど外資系運用会社が複数含まれている。
株主に直接賛否を問うカゴメ
現時点で買付者のない企業でも導入が広がっている。カゴメは10月20日、買収防衛策を導入した。敵対的に買収しようとする者が現れたとき、買付者の提案を受け入れるのか、カゴメの対抗措置の発動を支持するのかを株主に問うのが特徴だ。株主に買付者と会社の代替案を併せて提示し、株主の投票などを通じて買付者の提案を拒否するとの株主意思が示された場合、買付者への対抗措置として新株の無償割当てを実施する。
カゴメの株主数は13万人超、個人株主の比率は全体の72%に達する(3月末現在)ため、株主の判断が買収防衛の発動を左右する。
三角合併解禁控え、株式持合いも浮上
成熟した業界で生き残りをかけた企業買収防衛の側面が強い企業再編の動きも加速しそうだ。ビール大手のキリンビールとワイン大手のメルシャンは11月16日、業務提携で、キリンビールがメルシャン株の過半数を取得することで合意したと発表した。
メルシャンの岡部有治社長は同日の記者会見で「業務提携は相乗効果」と強調していたが、事実上の買収防衛策との面が強い。来年5月に予定される三角合併の解禁を控え、日本企業の間で安定株主を求めた持合いが浮上してきたともいえるだろう。
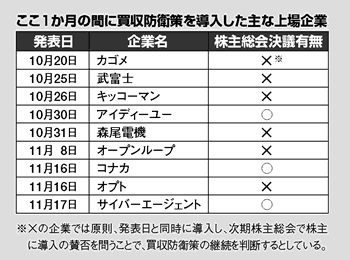
ISS「株主への導入提案は必要」
ISSは、買収防衛策の導入に際して賛否を株主総会で問うのは最低限必要で、取締役会決議で導入を決める、即日発効する買収防衛策には反対の立場だ。
しかし、多くの日本企業が株主総会で導入の賛否を問わず、取締役会決議で導入を決定していることから、顧客の機関投資家に反対を助言することすらできない。このため、来年の株主総会で買収防衛策の更新などに反対するほか、導入企業の取締役の選任議案に反対する可能性があるという。
ISSでは、従来から日本企業の提案する買収防衛策に反対を助言する場合が多かった。最大の理由は、多くの日本企業で取締役会の独立性や情報開示が不十分だからだ。日本企業の買収防衛策の導入が今後も増加するかは不透明だが、日本企業の株式を大量保有する機関投資家に影響を及ぼすISSは警戒感を強めている。
ISS、買収防衛策の導入急増を警戒
投資ファンドや外国人じわり、「持合い」浮上の兆しも
text 編集部
日本企業の間で秋以降、敵対的買収防衛策の導入が再び活発化している。王子製紙が今夏、北越製紙に買収提案したことが契機となっているようだ。武富士やキッコーマンなど有力企業が10月下旬買収防衛策を相次ぎ導入した。内外の買付者から企業経営を守る買収防衛策を導入する機運が高まっているとともに、投資ファンドや外国人投資家の持株比率がじわりと高まりつつあるのが背景にある。また、キリンビールとメルシャンのように、株式持合いを前提とした業務提携など買収防衛の側面の強い業界再編も加速しそうだ。議決権行使会社最大手のインスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)は安易な買収防衛策の導入が増加することを警戒しており、来年の株主総会で日本企業の議決権行使に影響を与えそうだ。
取締役が持株過半を保有も導入
ISSは、今夏の王子製紙の北越製紙への買収提案以降、日本企業の間で買収防衛策の導入が広がるとみている。日本企業には北越製紙以外にも時価総額に比べて純資産が多く、買収対象となりうる企業があるためだ。ISSジャパンのマーク・ゴールドスタイン代表は、時価総額を純資産で割った株価純資産倍率が1倍を切る企業が1割程度あるという。
兆候はすでに出始めている。コンタクトレンズ小売の日本オプティカルは9月末、新株の無償割当てを利用した買収防衛策を導入した。同社は急遽、臨時株主総会を開催し、株主に導入の賛否を求めた。日本株運用で海外投資家から評価の高い独立系運用会社のスパークス・アセット・マネジメントが同社株の約13%を握っていたことも導入の背景にありそうだ。
ISSは、日本オプティカルの議案について、顧客の機関投資家に反対を助言したことを明らかにした。反対の理由はこうだ。同社は取締役に社外取締役が1人もいないことや情報開示が不十分であることに加え、取締役全員で議決権の53%以上を保有していた。ゴールドスタイン氏は「今後、投資家に株式を売り出すのならまだ分かるが……」と困惑していた。
内外投資ファンド、日本株に触手
内外投資ファンドの日本株の持株比率が高まっている。しょうゆ最大手のキッコーマンは10月26日、即日発効の新株の無償割当てを利用する買収防衛策を導入した。
背景には、明星食品に公開買付けを実施した米系投資ファンド「スティールパートナーズジャパンストラテジックファンド(オフショア)エルピー」などの大量保有が関係している。
創業者保有企業に投資ファンドや外国人
従来、創業者一族で持合いを続けていた企業にも買収防衛策の導入が広がりつつある。消費者金融大手の武富士は10月25日、即日発効の新株の無償割当てを実施する買収防衛策を導入した。創業者の武井保雄氏一族の持株比率は約25%で年々分散が進む一方、外国人持株比率は約57%に達する(9月末時点)。
ネット広告代理事業大手のサイバーエージェントでは、12月20日に開催予定の株主総会で、株主の賛同を得たうえで買収防衛策を導入する見通しだ。藤田晋社長以外の大株主にモルガンスタンレーなど外資系運用会社が複数含まれている。
株主に直接賛否を問うカゴメ
現時点で買付者のない企業でも導入が広がっている。カゴメは10月20日、買収防衛策を導入した。敵対的に買収しようとする者が現れたとき、買付者の提案を受け入れるのか、カゴメの対抗措置の発動を支持するのかを株主に問うのが特徴だ。株主に買付者と会社の代替案を併せて提示し、株主の投票などを通じて買付者の提案を拒否するとの株主意思が示された場合、買付者への対抗措置として新株の無償割当てを実施する。
カゴメの株主数は13万人超、個人株主の比率は全体の72%に達する(3月末現在)ため、株主の判断が買収防衛の発動を左右する。
三角合併解禁控え、株式持合いも浮上
成熟した業界で生き残りをかけた企業買収防衛の側面が強い企業再編の動きも加速しそうだ。ビール大手のキリンビールとワイン大手のメルシャンは11月16日、業務提携で、キリンビールがメルシャン株の過半数を取得することで合意したと発表した。
メルシャンの岡部有治社長は同日の記者会見で「業務提携は相乗効果」と強調していたが、事実上の買収防衛策との面が強い。来年5月に予定される三角合併の解禁を控え、日本企業の間で安定株主を求めた持合いが浮上してきたともいえるだろう。
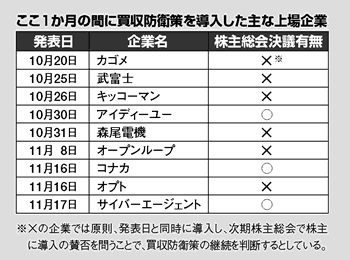
ISS「株主への導入提案は必要」
ISSは、買収防衛策の導入に際して賛否を株主総会で問うのは最低限必要で、取締役会決議で導入を決める、即日発効する買収防衛策には反対の立場だ。
しかし、多くの日本企業が株主総会で導入の賛否を問わず、取締役会決議で導入を決定していることから、顧客の機関投資家に反対を助言することすらできない。このため、来年の株主総会で買収防衛策の更新などに反対するほか、導入企業の取締役の選任議案に反対する可能性があるという。
ISSでは、従来から日本企業の提案する買収防衛策に反対を助言する場合が多かった。最大の理由は、多くの日本企業で取締役会の独立性や情報開示が不十分だからだ。日本企業の買収防衛策の導入が今後も増加するかは不透明だが、日本企業の株式を大量保有する機関投資家に影響を及ぼすISSは警戒感を強めている。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.





















