解説記事2007年01月29日 【ニュース特集】 19年度税制改正で変わる減価償却制度Q&A(2007年1月29日号・№196)
ニュース特集
償却可能限度額の均等償却で1年間の“空白期間”も
19年度税制改正で変わる減価償却制度Q&A
19年度税制改正事項の中でも実務に大きなインパクトを持つのが減価償却制度の見直しだ。昨年末に公表された19年度税制改正大綱では、残存価額、償却可能限度額の廃止や250%定率法の導入などが明らかにされたが、詳細な適用関係などいまだ不明点は多い。
今回は本誌編集部に読者から寄せられた質問のなかから、実務家の関心が高いと思われるものをピックアップ、本誌独自取材による回答を試みた。
1.償却可能限度額関係
Q 既に95%の償却可能限度額に達している減価償却資産の取扱い
当社は12月決算法人です。
19年度税制改正における減価償却制度の見直しでは、95%の償却可能限度額が廃止されましたが、19年度税制改正大綱によると、平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする一方、「平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産」については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できることとされています。
当社は、昨年18年12月決算において95%の償却可能限度額まで償却した減価償却資産を有していますが、当該減価償却資産は19年12月期より5年間で均等償却を行ってよいでしょうか?
A 19年12月期からの均等償却は認められません。20年12月期から5年間で均等償却を行うことになります。
本誌の取材によると、「平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産」に対する95%の償却可能限度額の廃止は、「19年4月1日以降に開始する事業年度から」適用されることが判明しています。
したがって、例えば3月期決算法人が有している減価償却資産が、この19年3月期をもって95%の償却可能限度額に到達した場合には、図1の通り、翌20年3月期以降5年間に渡って均等償却を行うことになります。
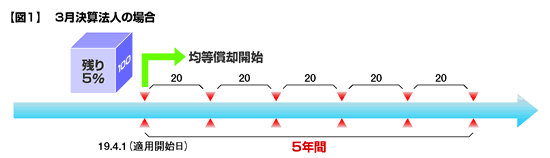 問題は12月決算法人等です。12月決算法人を例にとると、18年12月決算において95%の償却可能限度額に到達している減価償却資産については、残り5%分の償却は、「20年12月決算期」以降において行うことになります。これは、改正法の適用が「19年4月1日以後に開始する事業年度から」とされているところ、19年12月決算期は既に開始してしまっており、適用外となるためです。すなわち、18年12月決算において95%の償却可能限度額に到達している減価償却資産については、1年間まったく減価償却が行われない“空白期間”が発生することになるので注意が必要です(図2参照)。
問題は12月決算法人等です。12月決算法人を例にとると、18年12月決算において95%の償却可能限度額に到達している減価償却資産については、残り5%分の償却は、「20年12月決算期」以降において行うことになります。これは、改正法の適用が「19年4月1日以後に開始する事業年度から」とされているところ、19年12月決算期は既に開始してしまっており、適用外となるためです。すなわち、18年12月決算において95%の償却可能限度額に到達している減価償却資産については、1年間まったく減価償却が行われない“空白期間”が発生することになるので注意が必要です(図2参照)。
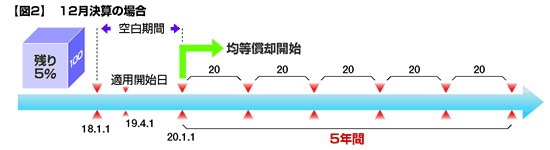
また、流通業が集中する2月決算法人においても、適用開始は21年2月期決算からと大幅に遅れることになります(図3参照)。
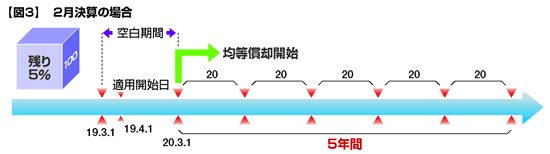
2.250%定率法関係
Q 減価償却資産を期中取得・事業供用した場合の償却方法
19年度税制改正で新たな減価償却方法として「250%定率法」が導入されますが、減価償却資産を期中に取得し、事業供用した場合の取扱いについて教えてください。
やはり米国の200%定率法のようにいわゆる「1/2簡便償却(期中のいつ取得しても、定額法による償却額の1/2を償却する方法)」が適用されるのでしょうか?
A 1/2簡便償却は適用されず、単純に月数按分により減価償却額を計算することになります。
我が国では、1/2簡便償却は平成10年度税制改正で廃止された経緯もあることから、1/2簡便償却は適用されません。減価償却資産を期中取得した場合には、下記の算式の通り、単純に月数按分することにより減価償却額を計算することになります。
<期中取得した場合の減価償却額>
取得価額×定額法の償却率(=1/耐用年数)×250%×経過月数/12
Q 償却率が1を超えてしまう場合の取扱い
「250%定率法」では、耐用年数が2年の場合、1年目の償却率が1を超えてしまうことになります。この場合、償却率は1で頭打ちになるのでしょうか? また、減価償却資産を期中取得・事業供用した場合、250%定率法で用いられる償却率には「1.25(=1/2年×250%)」あるいは「1」のどちらを使うのでしょうか?
A 償却率は1で頭打ちとなり、減価償却資産を期中取得した場合も、償却率は1を用います。
250%定率法が適用される場合、文字通り償却率は定額法の2.5倍となります。このため、耐用年数が2年の減価償却資産の場合、1年目の償却率が1.25(=1/2年×2.5倍)と1を超えてしまうことになりますが、本誌の取材で、この場合、償却率は「1」で頭打ちになることが確認されています。
問題は、減価償却資産の期中取得・事業共用を行った場合、償却率に「1.25(=1/2年×2.5倍)」「1」のいずれを使うかです。取材によると、償却率が「1」で頭打ちになる以上、下記の算式の通り、1.25ではなく「1」を使って減価償却額を計算することになります。
<耐用年数2年の資産を期中取得した場合>
取得価額×「1」×経過月数/12
Q 耐用年数の短縮特例が認められた償却資産についても、250%定率法の適用は認められますか?
A 法定耐用年数の短縮特例が認められた場合であっても、250%定率法の適用が認められます。
なお、国税庁では、法定耐用年数の短縮特例に関連し、「汎用性を有し、他の納税者も承認申請することが予想される資産」について、承認事例の公表を行うことを予定しています。
現在、東京国税局、大阪国税局など各国税局のおいて、機械装置などの承認事例の公表に向けた作業が続けられています。なお、公表様式については、国税庁で検討されている模様です。
3.全 般
Q 取得日と事業供用日が適用開始日をまたぐ場合の取扱い
当社は製造業を営む3月決算法人です。当社では大きなプラントを有しておりますが、このような大きなプラントは、その性質上、取得と事業供用日にタイムラグが生じるのが通例です。
例えば250%定率法のような新減価償却制度の適用を受けるためには、「取得」に加え「事業供用」も求められるのでしょうか?
また、取得が19年3月20日、事業供用が19年4月1日と、取得日と事業供用日が適用開始日をまたぐことになる場合、新減価償却制度の適用は認められますか?
A 新減価償却制度の適用には、取得のみならず「事業供用」が求められることになります。
したがって、単に減価償却資産を取得したのみで事業供用が行われていない場合には、250%定率法など新減価償却制度の適用は受けられないことになります(図4参照)。
また、250%定率法等は、19年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されることになるため、御社のように「取得が19年3月20日」「事業供用が19年4月1日」となる場合には、250%定率法等の適用は認められないのが原則的な取扱いです。ただし、「取得」と「事業供用」のタイムラグが“多少”である場合には、新制度の適用が認められる方向で検討が行われているようです(図5参照)。したがって、御社のようなケースでは、250%定率法等の適用が認められる可能性があります。
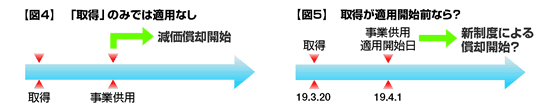
償却可能限度額の均等償却で1年間の“空白期間”も
19年度税制改正で変わる減価償却制度Q&A
19年度税制改正事項の中でも実務に大きなインパクトを持つのが減価償却制度の見直しだ。昨年末に公表された19年度税制改正大綱では、残存価額、償却可能限度額の廃止や250%定率法の導入などが明らかにされたが、詳細な適用関係などいまだ不明点は多い。
今回は本誌編集部に読者から寄せられた質問のなかから、実務家の関心が高いと思われるものをピックアップ、本誌独自取材による回答を試みた。
1.償却可能限度額関係
Q 既に95%の償却可能限度額に達している減価償却資産の取扱い
当社は12月決算法人です。
19年度税制改正における減価償却制度の見直しでは、95%の償却可能限度額が廃止されましたが、19年度税制改正大綱によると、平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できることとする一方、「平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産」については、償却可能限度額(取得価額の95%)まで償却した事業年度等の翌事業年度以後5年間で均等償却できることとされています。
当社は、昨年18年12月決算において95%の償却可能限度額まで償却した減価償却資産を有していますが、当該減価償却資産は19年12月期より5年間で均等償却を行ってよいでしょうか?
A 19年12月期からの均等償却は認められません。20年12月期から5年間で均等償却を行うことになります。
本誌の取材によると、「平成19年3月31日以前に取得をした減価償却資産」に対する95%の償却可能限度額の廃止は、「19年4月1日以降に開始する事業年度から」適用されることが判明しています。
したがって、例えば3月期決算法人が有している減価償却資産が、この19年3月期をもって95%の償却可能限度額に到達した場合には、図1の通り、翌20年3月期以降5年間に渡って均等償却を行うことになります。
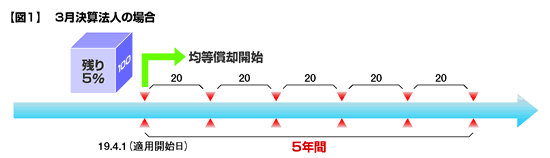 問題は12月決算法人等です。12月決算法人を例にとると、18年12月決算において95%の償却可能限度額に到達している減価償却資産については、残り5%分の償却は、「20年12月決算期」以降において行うことになります。これは、改正法の適用が「19年4月1日以後に開始する事業年度から」とされているところ、19年12月決算期は既に開始してしまっており、適用外となるためです。すなわち、18年12月決算において95%の償却可能限度額に到達している減価償却資産については、1年間まったく減価償却が行われない“空白期間”が発生することになるので注意が必要です(図2参照)。
問題は12月決算法人等です。12月決算法人を例にとると、18年12月決算において95%の償却可能限度額に到達している減価償却資産については、残り5%分の償却は、「20年12月決算期」以降において行うことになります。これは、改正法の適用が「19年4月1日以後に開始する事業年度から」とされているところ、19年12月決算期は既に開始してしまっており、適用外となるためです。すなわち、18年12月決算において95%の償却可能限度額に到達している減価償却資産については、1年間まったく減価償却が行われない“空白期間”が発生することになるので注意が必要です(図2参照)。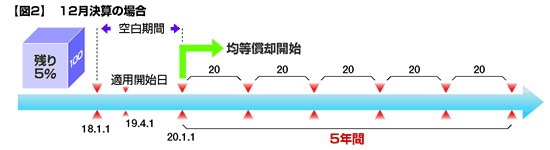
また、流通業が集中する2月決算法人においても、適用開始は21年2月期決算からと大幅に遅れることになります(図3参照)。
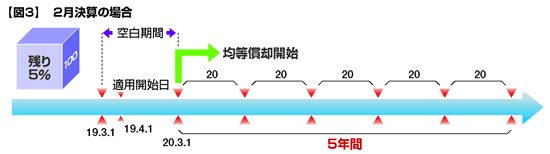
2.250%定率法関係
Q 減価償却資産を期中取得・事業供用した場合の償却方法
19年度税制改正で新たな減価償却方法として「250%定率法」が導入されますが、減価償却資産を期中に取得し、事業供用した場合の取扱いについて教えてください。
やはり米国の200%定率法のようにいわゆる「1/2簡便償却(期中のいつ取得しても、定額法による償却額の1/2を償却する方法)」が適用されるのでしょうか?
A 1/2簡便償却は適用されず、単純に月数按分により減価償却額を計算することになります。
我が国では、1/2簡便償却は平成10年度税制改正で廃止された経緯もあることから、1/2簡便償却は適用されません。減価償却資産を期中取得した場合には、下記の算式の通り、単純に月数按分することにより減価償却額を計算することになります。
<期中取得した場合の減価償却額>
取得価額×定額法の償却率(=1/耐用年数)×250%×経過月数/12
Q 償却率が1を超えてしまう場合の取扱い
「250%定率法」では、耐用年数が2年の場合、1年目の償却率が1を超えてしまうことになります。この場合、償却率は1で頭打ちになるのでしょうか? また、減価償却資産を期中取得・事業供用した場合、250%定率法で用いられる償却率には「1.25(=1/2年×250%)」あるいは「1」のどちらを使うのでしょうか?
A 償却率は1で頭打ちとなり、減価償却資産を期中取得した場合も、償却率は1を用います。
250%定率法が適用される場合、文字通り償却率は定額法の2.5倍となります。このため、耐用年数が2年の減価償却資産の場合、1年目の償却率が1.25(=1/2年×2.5倍)と1を超えてしまうことになりますが、本誌の取材で、この場合、償却率は「1」で頭打ちになることが確認されています。
問題は、減価償却資産の期中取得・事業共用を行った場合、償却率に「1.25(=1/2年×2.5倍)」「1」のいずれを使うかです。取材によると、償却率が「1」で頭打ちになる以上、下記の算式の通り、1.25ではなく「1」を使って減価償却額を計算することになります。
<耐用年数2年の資産を期中取得した場合>
取得価額×「1」×経過月数/12
Q 耐用年数の短縮特例が認められた償却資産についても、250%定率法の適用は認められますか?
A 法定耐用年数の短縮特例が認められた場合であっても、250%定率法の適用が認められます。
なお、国税庁では、法定耐用年数の短縮特例に関連し、「汎用性を有し、他の納税者も承認申請することが予想される資産」について、承認事例の公表を行うことを予定しています。
現在、東京国税局、大阪国税局など各国税局のおいて、機械装置などの承認事例の公表に向けた作業が続けられています。なお、公表様式については、国税庁で検討されている模様です。
3.全 般
Q 取得日と事業供用日が適用開始日をまたぐ場合の取扱い
当社は製造業を営む3月決算法人です。当社では大きなプラントを有しておりますが、このような大きなプラントは、その性質上、取得と事業供用日にタイムラグが生じるのが通例です。
例えば250%定率法のような新減価償却制度の適用を受けるためには、「取得」に加え「事業供用」も求められるのでしょうか?
また、取得が19年3月20日、事業供用が19年4月1日と、取得日と事業供用日が適用開始日をまたぐことになる場合、新減価償却制度の適用は認められますか?
A 新減価償却制度の適用には、取得のみならず「事業供用」が求められることになります。
したがって、単に減価償却資産を取得したのみで事業供用が行われていない場合には、250%定率法など新減価償却制度の適用は受けられないことになります(図4参照)。
また、250%定率法等は、19年4月1日以後に取得する減価償却資産から適用されることになるため、御社のように「取得が19年3月20日」「事業供用が19年4月1日」となる場合には、250%定率法等の適用は認められないのが原則的な取扱いです。ただし、「取得」と「事業供用」のタイムラグが“多少”である場合には、新制度の適用が認められる方向で検討が行われているようです(図5参照)。したがって、御社のようなケースでは、250%定率法等の適用が認められる可能性があります。
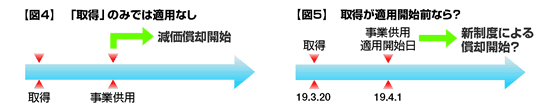
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-

-

団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -

Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.




















